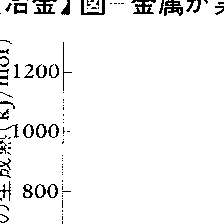翻訳|metallurgy
精選版 日本国語大辞典 「冶金」の意味・読み・例文・類語
や‐きん【冶金】
- 〘 名詞 〙 鉱石から金属を取り出すこと。また取り出した金属を精製したり、合金を作ったり、あるいは特殊な処理を施したりして、種々の目的に適する金属材料を作ること。溶鉱炉による方法、還元剤による方法、化学的に溶剤を用いる湿式法、水銀に溶かしてアマルガムとして採取する混汞(こんこう)法などがある。〔稿本化学語彙(1900)〕
改訂新版 世界大百科事典 「冶金」の意味・わかりやすい解説
冶金 (やきん)
metallurgy
英語のmetallurgyの訳語として冶金術とか冶金学とかが明治初年から用いられた。鉱石その他の原料から金属を採取し,種々の用途に適した合金とし,さらに加工を加えて所要の形とし,熱処理や表面処理によって特定の性質を付与する技術およびその基礎をなす科学のすべてを含んだ意味をもつ。金属に関する技術と科学とを総括する言葉,すなわち冶金術と冶金学とを統合した言葉としては現在は金属工学という言葉が使われる。
日本の大学における冶金学講座は1877年に東京大学理学部地質学および採鉱学科の中に開設された。この学科は80年になって地質学科と採鉱冶金学科に分かれている。冶金学の講義を行ったのは御雇外国人教師のネットーCurt Netto(1847-?)であった。彼は採鉱冶金に関して当時最も学問的水準の高かったドイツのフライブルク大学の出身であった。84年にはネットーの講義のノートを当時の学生たちが整理し,文部省の委託によって《涅氏(ねつし)冶金学》が刊行された。涅氏とはネットーのことで,この著書は日本の冶金学の創設に係る重要なテキストとなった。この中には〈冶金学ノ論スル所ハ礦鉱ヲ金類ニ還元スルノ方ヨリ此レヲ将テ合金ヲ混成シ以テ百物ヲ製スルノ法ニ至ルマテ尽ク包羅シ而シテ其旨ハ邦家経済ノ要ヲ達スルニ在リ〉とあり,さらに〈冶金料理ノ任ニ居ント欲スル人ニ在リテハ先ツ充分ニ数学,物理学,化学,金石学,採鉱学,建築学,樹木培養学,図学,会計学,経済学ノ諸科ヲ了得スヘキノミナラス……〉とある。
このような形の冶金学の始まりは1556年にスイスのバーゼルで出版された《デ・レ・メタリカ》にさかのぼる。著者のG.アグリコラはドイツのザクセンで生まれ,宗教改革の雰囲気の中で育ち,1524年に自然科学と医学の研究を志して,当時の学術の中心であったイタリアに遊学した。自然科学,医学,哲学を学び,産業技術について見聞を広めたのちドイツへ戻った。医者を開業するかたわら,鉱物性の薬物を求めて鉱物学へ関心をもつようになり,さらに岩石学,鉱山学,冶金学へと関心を深めていった。当時のドイツには金属,鉱物,冶金操作に関する知識がすでに成立していた。彼はこれらの技術知識とみずからの科学的教養を結びつけて新しい技術書を著した。〈私が見,読み,聞き,そして試験したことのないものはなに一つ本書の中には書かれていない〉と述べているように,技術の世界に近代的な科学的精神を導入した画期的な技術書である。彼は冶金を行うものは〈実際の術と学問とに精通していなくてはならぬ〉といい,それに必要な学問として哲学,医学,天文学,測量学,計算学,図学,法律学をあげている。その範囲は産業としての鉱山業全般にわたる技術,すなわち鉱石の出る場所の判別,採掘権をめぐる法律上の諸交渉,労働者の健康安全,採掘および運搬の技術,排水の機械化,選鉱および製錬の技術などが述べられている。アグリコラは金属が硫黄と水銀とからなるとする錬金術の根本教義にははっきり反対しており,生産現場における技術と計量に関する学問(測量,計算,図学,試金法)とを結びつけることで近世以降の科学的な冶金学の開宗となったのである。同時にこの書で鉱物学,地質学にとっても初めての科学的記述が行われた。人類の物質文明の歴史の中で金属は大きな位置を占めており,銅は6000年,鉄は4000年の冶金技術の歴史をもっているが,科学的裏付けをもった冶金学の歴史は16世紀以後の400年そこそこでしかない。このようにまず技術が生まれ,その技術を体系化する形で科学が生まれるというパターンは,冶金に限らずすべての技術にみられることである。
金,銀,鉄,水銀,スズ,銅,鉛の7種を超歴史的金属または古代の七金属元素(元素)と呼ぶことがあり,いずれも利用の歴史は古代にさかのぼる。人類の金属利用の歴史は自然金,自然銀,自然銅,隕鉄などの自然金属の加工から始まった(金属工芸)。やがて地上の鉱石から金属を吹き分ける術を発見するに至って量的にも多量の金属を利用することができるようになり,文明史上の青銅器,鉄器の時代に入る。金属の溶解と鉱石の還元のためには炉と送風の技術が必要であり,炉という限定された空間内に風を送ることによって燃焼の密度を上げ,高温を得て溶けた金属とスラグとを分離することを字義どおり〈吹分け〉と呼んだ。冶金技術者は古い時代にすでに粗鉛から銀を,アマルガムから金を分離する術を発明した。このことは冶金技術の改良で卑金属を貴金属に転化することが可能であるという考えを生み出した。このような思想のもとに物質の化学変化の研究が行われた時期を〈錬金術の時代〉と呼んでいる。〈すべての金属が硫黄と水銀とからできている〉とする誤った前提と,哲学者の思索から生まれた観念論的な理論体系と,〈賢者の石〉にたよる魔法からなる錬金術は,近代科学勃興以後は,物質的基盤を離れた神秘学としての観念の体系と現実の経験知識を中心とした技術の体系に分離した。後者が後に近代的な物質の科学の土台となる冶金学を用意したのである。人類のもつ物質文明の柱となる材料である金属を対象とする冶金術は,古代の青銅器の時代から現代の素材革命の時代に至るまで終始一貫してその時代の最先端の科学の母体であると同時に,科学の成果を技術に生かしてきたという歴史をもっている。このような観点からの冶金の種々の側面を金属工学への案内という形で以下に紹介する。
化学冶金chemical metallurgy
金属の化学的性質に関するすべての問題を取り扱うのが化学冶金であるが,歴史的には鉱石から金属を製造する製錬を意味していた。《涅氏冶金学》には〈噴気直立窯ニヨル冶銅術〉といった記述がある。現代風には〈溶鉱炉による銅製錬〉である。古代の製錬技術については〈鉄〉〈銅〉の項目の歴史を参照されたい。現在でも鉄冶金という言葉が製鉄・製鋼の意味で,非鉄冶金が非鉄金属の製錬の意味で使われる。化学に基礎をおく冶金技術としては製錬のほかに金属表面処理,腐食,防食など,材料の使用技術が広く含まれる。ただし近年では化学的手法に基づく化学冶金と物理的手法に基づく物理冶金との間の境目は明りょうではなくなってきており,冶金技術の目的達成のためには使える手法は区別せずに複合して使うということになってきている。金属の原料は自然界からは酸化物,硫化物,塩化物などの化合物の形で産出する。これらの原料となる化合物の生成熱を縦軸にとり,金属が実用されだした年代を横軸にとって示すと図のようになるが,生成熱が大きいほど還元は難しくなり,鉱石から金属を製造する技術は困難になると考えてよい。18世紀に入るまでは実用された金属は古代の七金属に限られていた。これらはいずれも炉を使う乾式冶金(乾式製錬技術)によって製造された。乾式冶金の技術レベルは送風技術と炉の耐火物技術で測ることができる。炉構造をくふうして自然通風を行う方式からふいごを利用した人為的送風へと発展し,さらに送風の動力が人力から水力(水車)に発展して,はじめて溶けた鉄を製造することのできる溶鉱炉が出現したのである。16世紀になるとすでにライン川流域では製粉業者の組合と製鉄業者の組合とが水利権をめぐる争いを行ったことが記録されている。産業革命期に入る18世紀後半から実用に供される金属の種類は飛躍的に増加した。19世紀に入るとマグネシウム,アルミニウム,チタンなどの軽金属が登場する。1807年にH.デービーによる溶融塩電解実験で金属カリウムが得られたことに始まる電気冶金(電解製錬技術)の誕生が,この難還元化合物からの金属製錬を可能にしたのである。金属製錬への電気エネルギーの利用は電気化学という新しい学問の発展を促した。1886年にはホール=エルー法が発明され,アルミニウムの量産が始まった。アルミニウムは現在鉄に次いで第2位の金属生産量を示している。電気冶金は水溶液を用いた金属の電解採取,電解精製にも広く応用されるようになり,原鉱石中の金属成分の溶解,副産金属の分離回収,高純度金属の製造などに利用されている湿式冶金の発展を促した。希土類元素のランタンLaからルテチウムLuまでの15元素をそれぞれ分離して各元素の純金属を製造することなども可能になっている。
20世紀後半になると新しい金属の商業生産が新しい製錬法の開発とともに展開した。ハロゲン化物を製錬中間産物として利用するハロゲン冶金がチタンの製錬におけるクロール法の成功で確立し,原子力燃料の金属ウランや電子材料のケイ素の製造などに利用されている。工業規模での真空技術の進歩は蒸留分離,熱分解,脱ガスなどの技術を含む真空冶金を生み出した。鉄鋼製錬における炉外精錬法などがこの分野の一つの目ざましい応用例である。
1980年代に入り,高度先端技術開発の時代が始まるとともに,新素材分野の一端を担って化学冶金にも新しい要求がつぎつぎにもたらされている。従来の伝統的な製品である塊状の純金属に代わって,たとえば化学蒸着の原料に用いる超高純度化合物,粒度や形状をそろえた粉末冶金や複合材料に用いる素材,金属間化合物の単結晶といったような新しい素材の供給を行わねばならない。一方,金属材料の使用環境が多彩になるのに対応して金属表面処理への要求も多様化する。一方で,古代から知られている量産金属材料もつぎつぎに新しい用途が生まれてくるので生産量を確保しなければならない。原料となる資源の質はむしろ劣化していく方向にありながら,製品の純度はより高いものが望まれ,製品への要求はいっそう精密になる。これらを技術的に解決して同時にプロセスの省エネルギー化,省力化を厳しい環境基準を守りながら遂行せねばならない。古代から現代まで,人類の文明の歴史とともに歩んできた化学冶金の重要性はそのまま将来へつながるものである。
加工冶金mechanical metallurgy
英語の直訳では機械冶金であるが,日本では加工冶金の名称が好まれている。金属の古い定義の一つに〈金属とは光沢のある固体物質で加工できるもの〉とするのがある。金属材料が構造材としてとりわけ重要であるのは〈強度が大であることと,いろいろな形に成形できること〉の両方の性質を備えているからである。この独特の機械的性質をもつ金属の塊から実用に供する成形品を製造する技術,すなわち金属加工に伴うすべての問題を取り扱う分野が加工冶金である。冶金技術が自然金属の加工から始まっていることからみても,加工冶金技術者の先祖である鍛冶師(かじし)は化学冶金技術者の先祖である山師(やまし)や金吹師(かねふきし)よりも古い歴史をもっているといえよう。金属加工は古くは鋳金(金属を溶かして型に鋳込む成形法),鍛金(金属の塊を打ち延ばす成形法),彫金(金属成形品に彫刻加飾する技法)の技法があり,現代でも金属工芸に受け継がれている。産業革命期を境に金属工芸から分離して工業生産技術として独立した現代の金属加工技術もこれらの流れを受け継いで,鋳造,鍛造,塑性加工などの分野を包含するとともに,溶接,粉末冶金,金属表面処理などを含んでいる。また実用材料の機械的性質の試験やその結果を生かして機械設計の中でいかに材料を使用するかということなども加工冶金の中に入る。このような加工冶金技術の現場に蓄えられた知識は,合金学,弾塑性学,金属材料力学,材料破壊力学,材料試験法,合金設計法などの多くの科学分野の母体となるとともに,またその成果をとり込んでみずからの成長の糧としている。
中世における加工冶金技術の到達点は,たとえば刀剣鍛冶師の製品の中にみることができる。とくにヨーロッパの十字軍騎士たちに希求されたダマスクス刀は7世紀のころからその存在が知られていた。ダマスクス刀は,もし絹のネッカチーフが落ちてくればそれを二つに切るほど鋭利に研ぎすますことができ,鉄の鎧(よろい)を切っても刃こぼれを起こさず,柳の枝のようにしなやかで曲げても折れないといわれ,刀身にはダマスクス模様Damasceneと呼ばれる独特の波紋状の紋様(日本刀の沸(にえ)に相当する)がある。この刀の材料となった鋼は炭素を1.6%も含む高炭素鋼であり,当時ずばぬけた水準にあったインドの製鋼技術がもたらしたものである。神秘のインド鋼はペルシアを経てダマスクスの鍛冶師に鍛えられたといわれる。秘伝の中にはダマスクス鋼の焼入れは〈赤毛の少年の尿の中で行うのがよい〉といった奇妙なものまであったという。もっとも塩の水溶液のほうが純水よりも焼入れ効果が大きいといったことは起こりうることである。実用の武器としてのダマスクス刀は鉄砲の出現で意義を失うが,18世紀後半の産業革命の展開に伴って,安価で強靱(きようじん)な鋼を大量に必要とするようになったヨーロッパでは伝説のダマスクス刀の原材料であるインドのウーツ鋼の秘密を探る研究が盛んになった。この研究の手がかりとなったのがダマスクス模様であり,この模様の再現を求めて研究が行われた。この〈process of damascening〉への情熱が,金属の性質をその内部構造に立ち入って解明する物理冶金学を準備したのである。
物理冶金学physical metallurgy
18世紀から19世紀にかけて冶金技術は大幅に進歩し,画期的な性質を示す合金材料,合金鋼がつぎつぎと登場した。このような近代的な技術の展開は19世紀後半から登場した物理冶金を準備し,その物理冶金の発展が現代の金属工学を支えているのである。物理冶金は金属組織および組織を構成する相内部の原子構造,電子構造に関与するすべての問題を取り扱うものであり,産業革命以後の技術上の必要と背景となる基礎科学の進歩によって支えられている。化学組成が同じ合金鋼で作った大砲が,一方はすぐに壊れ他方は長もちするといったように,実用環境での性能に大きな差を生ずるという経験に対してなぜかを答えるには,まずなによりも材料の顕微鏡組織を調べることが必要である。この方面の研究はイギリスのH.C.ソルビー,ロシアのD.K.チェルノフなどに始まった。金属材料の表面を研磨してエッチングすることで,金属材料というものが実は小さな結晶粒が入り組んで集まっている結晶粒組織をもっていることがわかる。このような実験技術の進歩でようやく結晶粒が微細で寸法のそろっているものは強靱であるが,粗粒のものや内部に粗大な介在物をもっているような材料は弱いというようなことがわかってきたのである。この反射光学顕微鏡による組織観察は現在の金属材料学においても依然として重要な基本技術である。一方で二つの異なる物質がまぜ合わされたときに生ずる異なる相の間の平衡関係に関する熱力学理論が成立し,相の存在範囲を示す線図,すなわち状態図が作られるようになる。鉄-炭素系状態図はローゼボームH.W.B.Roozeboomによって作られ,炭素鋼の凝固過程が明らかにされた。このような状態図と顕微鏡組織の組合せによって合金研究は科学的基礎を獲得したといってよい。ここではじめて,それまでの加工冶金技術において秘伝とされてきた合金調合,鋳造,鍛造,熱処理などのプロセスの意味するところを解き明かす第1歩が築かれたのである。
次いでその第2歩ともいうべき大きな進歩は,結晶内の原子配列を調べるX線回折法の登場によって用意された。結晶構造を調べる実験手段はさらに電子線回折,中性子線回折,電子顕微鏡などに発展し,金属の種々の物性測定と組み合わせてその内部構造への理解は格段と進歩した。もちろんその背後には量子力学に基礎をおく原子論,電子論の理論の発展が力となっている。あえて第3歩というべき進歩は,格子欠陥に関する理論的および実験的研究にみられる。線欠陥としての転位の存在は,完全結晶に期待される金属の理想強度と現実に観測される実用材料の強度との間に存在する大きなギャップを埋め,材料の強度の向上や塑性加工の技術の進歩に大きな貢献をした。一方,点欠陥に関する研究は,金属材料にみられる相変態,再結晶,析出硬化などの速度過程を解き明かすのに貢献した。これらの物理冶金における基礎科学の充実は加工冶金技術,化学冶金技術の分野にも大きな影響を与えており,現代ではこのように3者を分類することが無意味であるくらいに互いの境界はぼやけてきている。
これからの冶金
現代の冶金は長い歴史に支えられた豊富な知識と経験を基盤として,製錬,鋳造,加工から表面処理,腐食に至る一貫した技術の成熟と,金属材料の原子レベル,電子レベルにまで立ち入った基礎科学の充実を両輪として成り立っている。これからもこれらの経験と技術と科学の融合の上に,文明を支える柱としての冶金が展開していくであろう。金属材料はこれからは力学的強度を主体とする構造材料と特殊な物性を主体とする機能材料の二つの方向でそれぞれその特色を発揮することになるが,前者では腐食,応力腐食割れのように与えられた環境下での動的強度の劣化現象が重要であり,構造物の期待寿命に合わせた材料技術と材料科学が要求される。後者の機能材料では,新しい素材の発見を契機として新しい技術の可能性が生まれるという期待が大きく,新しい材料製造プロセス,たとえば,分子線エピタキシー,PVD(真空蒸着),CVD(化学蒸着),固相焼結,超急冷などと,材料の微量成分,内部構造,表面状態などを分析し,目的の機能を制御する方法(最近キャラクタリゼーションという呼名が使われる)との格段の進歩に支えられている。冶金は将来にわたってもネットーのいうごとく〈邦家経済ノ要ヲ達スル〉役割を果たすことになろう。
執筆者:増子 昇
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「冶金」の意味・わかりやすい解説
冶金
やきん
metallurgy
金属材料を生産する技術(冶金技術、金属工業技術)とそれに関する科学(冶金学、金属工学)の総称である。
[原善四郎]
冶金の歴史
古代の冶金
中近東やバルカン半島の新石器時代人は紀元前約5000年から自然銅を溶融・鋳造することを知り、前約4000年から銅化合物を木炭とともに加熱すると金属銅が得られることを知った。前3000年ころメソポタミアで、錫(すず)石を木炭で被覆した溶融銅に加えると、石よりも硬くて粘り強い青銅ができることがみいだされ、中近東は青銅器時代に入った。鉄は前2000年までに近東各地で隕鉄(いんてつ)とともに製錬鉄が貴重品に使用され、前1200年以後東地中海地方から鉄器が青銅器にかわる武器、農・工具となっていった。
中国では前2500年ころから銅器が現れ、前1600年ころから青銅器時代に入った。前600年ころから製鉄が始まり、鋳鉄製農具が普及した。前50年ころから武器も鉄鋼製となり、完全に鉄器時代に入った。後漢(ごかん)(8~265)の時代には、鋳鉄、錬鉄、鋼が各種の方法で量産され、水車送風、石炭が製鉄に利用された。
ローマ帝国(前27~476)には、錬鉄に浸炭して鋼とし、焼入れ硬化する技術があり、亜鉛鉱石を木炭被覆の溶融銅に加えて製造した黄銅が貨幣に用いられた。鉛板が水道管用として量産された。
[原善四郎]
中世の冶金
中世には水車の利用が冶金技術に変革をもたらした。
中国では、唐~宋(そう)(618~1279)の時代に水車送風が金属製錬に用いられており、11世紀中期の金属年産量は銅8000トン、銀100トン、鉄4万トンに達したとみられる。
ヨーロッパでは、民族大移動期(5~8世紀)中も各地で木炭炉による錬鉄生産は存続したが、9、10世紀から各地の非鉄金属(銅、銀、鉛、錫、黄銅)の生産が盛んになり、教会用品や農・工具が製作された。11、12世紀から、水車動力の冶金機械が使用されるようになった。
15世紀にライン川下流地方の製鉄炉は、水車駆動のふいごで送風し、溶融鋳鉄を生産するようになった。高炉の始まりである。高炉は主として鋳鉄砲・砲弾の製造に用いられたが、余分の鋳鉄は木炭火床で脱炭して錬鉄がつくられた。ハルツ、ザクセン地方では硫化銅鉱を焙焼(ばいしょう)し、溶鉱炉で数段階の還元溶錬工程により精銅を生産する銅製錬法(ドイツ法)が発達した。錫・鉛合金が広く用いられ、アンチモン、ビスマスの添加も行われるようになった。活字合金はこの系統の合金である。
16世紀には、これらヨーロッパの製錬、試金、鋳造技術の詳細を記述した技術書の刊行が盛んになった。ビリングチオの『火工術(ピロテクニア)』(1540)、アグリコラの『デ・レ・メタリカ』(1556)などである。中国、宋応星(そうおうせい)の『天工開物』(1637)も冶金技術の記述が詳しい。17世紀末には、金属の燃焼・還元現象を合理的に説明するためフロギストン説が生まれ、18世紀初めレオミュールはこの説に基づいて、浸炭鋼、可鍛鋳鉄の本性と製造法を研究した。
[原善四郎]
産業革命期の冶金
18世紀初頭にイギリスで、高炉を石炭コークスで操業することに成功した(ダービー・1709)。18世紀末にはイギリスで、石炭焚(た)き反射炉で錬鉄を生産するパドリング法が発明された(コート・1783)。コークス高炉の送風機にも、パドリング法の圧延機にも蒸気機関が用いられた。石炭製鉄の時代が到来したのである。高炉自体にも熱風の採用(ニールソン・1828)、高炉ガスの回収(フォール・1832)などの改良が加えられた。鋳鉄と錬鉄は産業革命を推進する工業材料となり、イギリスの鉄年産量は1750年の5万5000トンから、1853年の320万トンへと増大した。
イギリスでは錫製錬も銅製錬も18世紀中に石炭焚き反射炉で行われるようになった。後者は数段階の酸化溶錬工程からなり、ウェールズ法とよばれた。蒸気機関は圧延機の能力を高め、18世紀中には広幅鉛板や銅板(船底保護用)が圧延されるようになり、19世紀に入ってブリキ板薄鉄板も圧延機で量産されるようになった。
産業革命期に発達した気体化学に基づき、ラボアジエがフロギストン説を打破(1783)して樹立した新化学は、金属化合物、金属製錬の本質的理解を可能にした。分析化学が発達して、多くの新金属が発見され、亜鉛、コバルト、白金、ニッケル、マンガン、タングステンなどの製錬法が開発された。鋳鉄や錬鉄を構造材に用いるための強度試験が盛んに行われ、材料力学が弾性論を中心に発達した。18世紀末から、フランス、ドイツ、やや遅れてイギリスと理工系大学の設立が始まり、その教授たちによって優れた冶金学専門書が編纂(へんさん)され始めた(カルステン・1816、パーシー・1846)。
[原善四郎]
工業化時代の冶金
19世紀なかばに新原理に基づく二つの新製鋼法が登場し、鋼の量産が可能となった。〔1〕溶融銑鉄に空気を吹き込み、銑鉄中の炭素を燃焼・脱炭して溶融鋼を得るベッセマー法(1856)、〔2〕蓄熱室を備えた平炉により、溶融銑鉄と鉄鉱石を反応させて溶融鋼を得るシーメンス‐マルタン法(1860)である。これらの新製鋼法で量産される鋼材は、鉄道、船舶、橋梁(きょうりょう)、高層建築に使用され、ヨーロッパ、アメリカに重工業化時代を到来させた。1900年の世界鋼生産量は2500万トンとなった。
製鋼原料銑の需要増加にこたえて、ドイツ、アメリカで高炉技術が発達し(前床廃止・1867、炉床拡大・1880)、1897年のデュケーヌ高炉(アメリカ)は日産700トンに達した。鋼材の需要増大は鋼材加工技術の進歩を促し、圧延機では三段式圧延機(1856)、可逆式圧延機(1886)が現れ、薄鋼板製造用の連続圧延機がアメリカで稼動した(1869)。都市ガス管用として鍛接鉄管製造法(1824)や、自転車産業からの需要にこたえて継目無し鋼管を製造するマンネスマン製管機(1885)が発明された。るつぼ鋳鋼法で各種金属を配合することにより優良鋼を得る試みはファラデーに始まり(1819)、引き続いて自硬性工具鋼(マシェット・1828)をはじめ、耐摩耗性高マンガン鋼(ハットフィールド・1882)が発明された。銅製錬法もベッセマー製鋼法と同様に、溶融硫化銅・鉄(かわ)に空気を吹き込んで金属銅を得る転炉法が採用された(1880)。19世紀に入って急速に発展した電気学は冶金技術にも変革をもたらした。発電機が実用段階に入ると、ただちに、銅の電解精製(1869)、ニッケルの電解採取(1893)が工業化され、フッ化アルミニウムの溶融塩浴に酸化アルミニウムを溶解し、電解することによってアルミニウムを量産する方法が発明された(エルー、ホール・1886)。19世紀末には冶金炉への電力利用も実用化し始めた(エルー炉・1899)。
この時期に反射型顕微鏡による金属組織の観察が始まり(ソルベー・1863)、高温度測定法(ル・シャトリエの熱電対・1891)および熱力学の進歩(ギブスの相律・1873)と相まって、金属組織学の基礎がつくられ、鋼をはじめ各種合金の状態図作成や鋼の焼入れ硬化の本質の検討が進められた。
[原善四郎]
冶金の諸分野と各種の冶金
以上の冶金の歴史からみて、冶金には大別して金属製錬、金属加工、金属材料の三分野があることがわかる。金属材料とは、所要の性質をもった金属材料の組成・熱処理法を開発する分野である。冶金を、関係する科学分野によって物理冶金、化学冶金に分類することもある。製錬・加工分野をあわせて製造冶金とよぶこともある。冶金技術で生産する金属材料の種類に応じて、鉄冶金、非鉄冶金に分類する。高温化学反応による金属製錬を乾式冶金とよび、鉱石から溶剤で金属を浸出する製錬を湿式冶金という。電気を利用する冶金分野を電気冶金という。20世紀には、粉末冶金、真空冶金、原子力冶金などの新分野も開けた。
[原善四郎]
20世紀の冶金
20世紀の冶金技術の特徴は、他の生産技術とも共通して、生産工程の機械化、自動化、科学的管理が進んだことである。
鉄鋼製錬技術は、高炉技術において20世紀前半にアメリカで高炉作業の機械化、鉄鉱石の焼結・整粒、20世紀中期に旧ソ連で高圧送風、気化冷却、1960年代から日本で熱風温度上昇、重油吹込み、装入物分配制御、などの技術改良が加えられ、1970年代の高炉は日産1万トンに達した。製鋼法は、20世紀前半に重油燃料の採用などで平炉が能率を高めたが、1949年にドイツ・オーストリア共同で発明された酸素上吹き転炉法が日本で改良を加えられ、20世紀後半には平炉にとってかわった。電気製鋼炉は超高電力操業法(1964)で生産性が高まり、高級鋼、特殊鋼の生産に使用されている。溶鋼を真空脱ガス、真空脱炭する諸装置が、1960年代から低水素高級鋼、ステンレス鋼の生産に実用されている(真空冶金)。
鉄鋼加工の分野では、20世紀中期から、連続鋳造法が発展している。鋼板圧延機は、1920年代からアメリカで広幅熱間および冷間連続圧延機(ストリップ・ミル)が自動車用などの薄鋼板を量産し始めた。20世紀中期からの進歩は著しく、1970年代には圧延速度が秒速25メートルにも達した。製管技術は、1920年代から石油採掘・輸送用鋼管の需要増大にこたえて、新型の継目無し鋼管圧延機が発達し、20世紀後半には電気溶接法を利用した各種の溶接鋼管製造法が発達した。
鉄鋼材料の分野では、20世紀初頭、高速度工具鋼(テイラー、ホワイト・1906)が発明された。自動車部品用の低合金焼入れ鋼は1930年代に規格化が進んだ。1940年代に頻発した溶接船・橋梁の低温脆性(ぜいせい)による破壊事故は、破壊力学と溶接性のよい高張力鋼を発達させた。金属の高温クリープ現象の研究を基礎に、高温タービン用耐熱鋼の開発も進み、1960年代から航空・宇宙材料用として超強力鋼が研究されている。ステンレス鋼は1912年以来、クロム鋼、ニッケル・クロム鋼が開発され、第二次世界大戦後に生産が急増した。磁石鋼は日本でよく研究が進んだ(本多光太郎、KS鋼・1917)。鉄心用のケイ素鋼は20世紀初頭に実用化したが、1950年代から結晶粒の方向制御により性能を高めた。以上のような鉄冶金技術の発展で、1970年代の世界粗鋼年間生産量は7億5000万トンとなった。
非鉄金属製錬の分野では、1915年以後実用化した浮遊選鉱法は複雑鉱からの各種金属の相互分離も可能にした。この方法の産物である微粉の硫化鉱精鉱は1940年代から流動床法で焙焼されるようになった。流動焙焼炉は高能率であり、排ガス(亜硫酸ガス)からの硫酸製造を容易にした。銅の乾式冶金では、1950年代から微粉硫化鉱精鉱を酸素ないし予熱空気で急速燃焼して溶錬する自溶炉、さらに70年代から溶錬炉、からみ・かわ分離炉、製銅炉の三者を樋(とい)で連結した連続製銅炉、などが発達した。非鉄湿式冶金では、1920年代から金製錬法は、金鉱石を微粉砕し、青化ナトリウム水溶液で金を浸出する方法となった。1940年代から原子炉材料金属の湿式冶金に有機溶媒抽出法が利用されたが、この方法は60年代から銅、コバルトなどの一般金属の採取にも応用された。
金属加工分野のなかで、鋳造技術は、1920年代からの自動車量産方式が、金属鋳造作業の機械化、強じん鋳鉄やダイカスト法の発展を促進した。ダイカスト法は金属溶湯を金型に圧入して鋳造する方法で、専用のアルミニウム合金、亜鉛合金も開発された。1940年代には超耐熱合金のタービン・ブレードを鋳造するため、古来の脱ろう法が精密鋳造法として復活した。
19世紀末に発明されたアーク溶接法、電気抵抗溶接法、ガス溶接法などの金属溶接法は、1920年に最初の全溶接船が建造され実用に入った。1930年代にサブマージ・アーク溶接法、不活性ガスアーク溶接法が考案され、前者は鋼船、後者は軽合金航空機の量産に利用された。電気抵抗溶接法は今日の車体自動組立てラインに欠かせない金属加工法である。
金属粉を圧縮成形・焼結する粉末冶金法によって、タングステン線(1909)、炭化物系超硬合金(1926)がつくられ、1950年代からは小形鉄製部品の量産にも進出している。
非鉄金属材料の分野では、時効硬化性アルミニウム合金(ウイルム・1909)が金属航空機の発達を、またニッケル基析出硬化型超耐熱合金が1940年代からのジェット機の発達を可能とした。軽量・強力な金属チタンは、四塩化チタン蒸気を溶融マグネシウムで還元・分解する方法(クロール・1940)で生産され、航空・宇宙材料となっている。この用途には、1970年代から無機強力繊維を金属で結合した複合材料の開発が進んでいる。
電子材料の面では、真空管にはタングステン、モリブデンなどの金属が重要であったが、1950年以降のトランジスタ、集積回路技術の発展の背景には、帯溶融法による高純度ゲルマニウム、浮遊帯溶融法による高純度シリコンの製造技術があった。原子力発電用の核燃料、同被覆管、制御棒、原子炉圧力容器、同冷却管などの金属材料の生産には、新しい観点からの冶金技術や冶金学(原子力冶金)が必要である。
19世紀末の陰極線・X線の発見以来の物理学の飛躍的な発展は冶金学にも変革をもたらした。X線の結晶回折現象(ラウエ・1912)はただちに金属・合金の結晶構造解析に利用され、金属組織学の新研究手段となった。ボーアの原子構造論(1913)は金属の本性を明らかにし、続いて量子力学は、金属・合金の諸性質を原子・電子構造に基づいて解明する固体物理学に道を開いた。金属の塑性を説明するために仮定された転位(テーラー、オロワン、山口珪次・1934)は、電子顕微鏡による金属薄片の透過観察(ボルマン、ハーシュ・1956)によって実在が証明され、金属の強度や破壊現象の解明を前進させた。金属の極低温における超電導現象(カマーリン・オネス・1911)の理論的解明も進み(バーディーン・1956)、1960年代には合金系超電導材料が実用に供された。こうして最近の物理冶金は、量子統計力学理論の発展と、電子顕微鏡、核磁気共鳴装置、メスバウアー法、中性子回折などの実験手段の発達と相まって、金属・合金・半導体の塑性・磁性・電導性・誘電性などの物性研究が著しく進展し、アモルファス金属、形状記憶合金などの新材料を生み出している。
化学冶金の面では、化学反応を熱力学によって解明する化学熱力学が20世紀初頭に発展し(ルイス・1923)、1930年代から諸物質の熱力学的データも蓄積され、40年代以降は、金属製錬反応を熱力学によって解析・予見することが可能となった。また1920年代から発達した化学工学、30年代からの反応工学も、冶金装置、工程の開発に大きな武器となった。
こうして20世紀の冶金学は、物理学、化学、機械工学、電気工学、化学工学などの諸科学と深く関係しつつ、金属材料そのものと金属材料生産技術を研究対象として発展している。さらに最近では広く材料全般を含めた材料科学という総合的な分野が育っている。
[原善四郎]
『R.F.TylecoteA History of Metallurgy (1979, The Metals Society)』▽『A・H・コットレル著、木村宏訳『コットレルの金属学』(1969・アグネ)』▽『日本鉄鋼協会編『鉄鋼製造法』(1972・丸善)』▽『西川精一著『金属工学入門』(1985・アグネ技術センター)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「冶金」の意味・わかりやすい解説
冶金
やきん
metallurgy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「冶金」の読み・字形・画数・意味
【冶金】やきん
 して、我且(まさ)に必ず
して、我且(まさ)に必ず
 (ばくや)(名刀)爲(た)らんとすと曰はば、大冶必ず以て不
(ばくや)(名刀)爲(た)らんとすと曰はば、大冶必ず以て不 の金と爲さん。
の金と爲さん。字通「冶」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「冶金」の意味・わかりやすい解説
冶金【やきん】
→関連項目金属物理学|真空冶金
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...