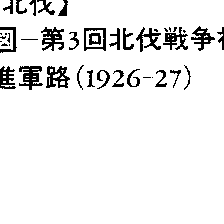精選版 日本国語大辞典 「北伐」の意味・読み・例文・類語
ほく‐ばつ【北伐】
- [ 1 ] 北方を討伐すること。
- [初出の実例]「北伐したれば南方の荊蛮が来たぞ」(出典:漢書列伝竺桃抄(1458‐60)韋賢第四三)
- [その他の文献]〔春秋左伝‐僖公九年〕
- [ 2 ] 一九二六~二八年、中国国民革命軍が北京政府を打倒した戦争。国民革命軍は、二六年蒋介石を総司令として、広州を出発。翌年、上海を占領したが、蒋の反共クーデターや武漢、南京両政府の対立により前進を中断。二八年再開、同年六月北京に入城して中国を統一した。
百科事典マイペディア 「北伐」の意味・わかりやすい解説
北伐【ほくばつ】
→関連項目賀竜|五・三〇運動|国共合作|呉佩孚|済南事件|山東出兵|周恩来|鈴江言一|翦伯賛|中華人民共和国|中華民国|中国国民党|張作霖|陳誠|南漢宸|白崇禧|馮玉祥|武漢政府|北洋軍閥|葉挺|李済深|李宗仁
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北伐」の意味・わかりやすい解説
北伐
ほくばつ
Bei-fa
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「北伐」の意味・わかりやすい解説
北伐 (ほくばつ)
Běi fá
中国,近代における孫文ら国民党系の広東を根拠地とする全国統一戦争をいう。中華民国の正統な継承者として広東政府を組織した孫文らは,北京の 奪者から政権を奪回すべく3回にわたって北伐戦争を発動した。第1回(1922年2月~6月)は桂林(のち韶関)に大本営をおき,湖南・江西に兵をすすめたが,吉安をおとしたところで陳炯明(ちんけいめい)のクーデタが起こり失敗に終わった。第2回(1924年9月~11月)は韶関に大本営をおき,4万~5万の兵(建国軍)を率いて江西に出たが,馮玉祥(ふうぎよくしよう)の北京政変で直隷派が政権をおわれたため中断された。孫文はこの局面を〈国民革命の新時代〉ととらえ,北方に対して国民会議による統一をよびかけるにいたる。第3回(1926年7月~28年12月)は蔣介石を総司令とする国民革命軍10万が湖南・江西に打って出た。北方でも馮玉祥の国民軍等が呼応した。農民運動,労働運動にささえられた国民革命軍は,兵器の劣勢を戦闘精神で補って破竹の進撃をし,7月長沙,10月武昌と呉佩孚(ごはいふ)集団を,10月南昌,翌年3月南京と孫伝芳集団を破った。ここで主導権争いから国共分裂となり,北伐は一時中断されたが,やがて南京政府に拠る蔣介石がイギリス,アメリカなどの支援もうけて支配権を確立し,28年4月北伐を再開した。25万の国民革命軍は途中で日本の山東出兵(済南事変)による妨害をうけたが,6月には安国軍をひきいる張作霖を走らせて北京を占領した(占領と同時に北京は北平に,直隷省は河北省に改名された)。日本は無用となった張作霖を爆殺して東北の支配をはかったが,子の張学良が同年末〈易幟(えきし)〉(旧来の国旗五色旗を青天白日旗にかけかえて国民政府の支配に服するとの意思を表示すること)を断行して北伐は完了をみた。
奪者から政権を奪回すべく3回にわたって北伐戦争を発動した。第1回(1922年2月~6月)は桂林(のち韶関)に大本営をおき,湖南・江西に兵をすすめたが,吉安をおとしたところで陳炯明(ちんけいめい)のクーデタが起こり失敗に終わった。第2回(1924年9月~11月)は韶関に大本営をおき,4万~5万の兵(建国軍)を率いて江西に出たが,馮玉祥(ふうぎよくしよう)の北京政変で直隷派が政権をおわれたため中断された。孫文はこの局面を〈国民革命の新時代〉ととらえ,北方に対して国民会議による統一をよびかけるにいたる。第3回(1926年7月~28年12月)は蔣介石を総司令とする国民革命軍10万が湖南・江西に打って出た。北方でも馮玉祥の国民軍等が呼応した。農民運動,労働運動にささえられた国民革命軍は,兵器の劣勢を戦闘精神で補って破竹の進撃をし,7月長沙,10月武昌と呉佩孚(ごはいふ)集団を,10月南昌,翌年3月南京と孫伝芳集団を破った。ここで主導権争いから国共分裂となり,北伐は一時中断されたが,やがて南京政府に拠る蔣介石がイギリス,アメリカなどの支援もうけて支配権を確立し,28年4月北伐を再開した。25万の国民革命軍は途中で日本の山東出兵(済南事変)による妨害をうけたが,6月には安国軍をひきいる張作霖を走らせて北京を占領した(占領と同時に北京は北平に,直隷省は河北省に改名された)。日本は無用となった張作霖を爆殺して東北の支配をはかったが,子の張学良が同年末〈易幟(えきし)〉(旧来の国旗五色旗を青天白日旗にかけかえて国民政府の支配に服するとの意思を表示すること)を断行して北伐は完了をみた。
→国民革命
執筆者:狭間 直樹
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「北伐」の意味・わかりやすい解説
北伐
ほくばつ
中国では一般的に南方から北方へ軍隊を動かして、北方勢力と戦うことを北伐という。近代中国では、太平天国や辛亥(しんがい)革命にみられるように、革新的な闘争が南から北へ向かって進められることが多かったが、普通にはとくに1920年代の国民革命期の北伐をさす。この北伐は1926年7月に始まるが、それが行われた歴史的要因は、辛亥革命後の政治情勢にさかのぼる。
辛亥革命で、革命派は北方勢力との妥協によって清(しん)朝打倒(民国樹立)に成功したが、軍閥政権の独裁を阻むことができず、第三革命で袁世凱(えんせいがい)の帝政を阻止したのちも、軍閥が各地に割拠して内戦や抗争を繰り返した。1919年9月、孫文らは広州で軍政府を組織し、軍閥打倒の闘争を開始したが、自ら軍事力をもたないために南方軍閥に依存せざるをえず、軍閥間の勢力争いに利用され、目的を果たせなかった。五・四運動を目撃して、覚醒(かくせい)した民衆の大きな力を認識した孫文は、中華革命党を国民党に改め、さらに1924年初め、コミンテルンの影響を受けながら、国民党を民衆に基盤を置く政党に改組し、「連ソ、容共、労農援助」の三大政策を掲げるとともに、革命党にふさわしい軍隊の創設を図り、この年の9月に軍閥打倒のための北伐を宣言した。しかし、孫文はその志を遂げずに世を去り、国民革命の課題は後継者に受け継がれた。
1926年7月、蒋介石(しょうかいせき)は国民革命軍総司令となって北伐を開始。革命軍は、武装した労働者、農民に支援されながら北上し、武漢、南京(ナンキン)を占領して上海(シャンハイ)に迫った。以前から動揺していた蒋介石(しょうかいせき)は列強の要求に屈し、27年4月12日、上海で反共クーデターを強行、多数の労働者、農民などを虐殺した。こうして国民革命は挫折(ざせつ)したが、蒋介石は28年北伐を再開、すでに国民党に入党した閻錫山(えんしゃくざん)、馮玉祥(ふうぎょくしょう)ら軍閥とともに、奉天軍閥張作霖(ちょうさくりん)を北京(ペキン)から追放して、同年6月北伐を完了した。蒋は共産党を除く反対勢力を一掃し、いちおう軍閥勢力を支配下に置くことに成功したが、この北伐は軍閥との妥協によって行われ、蒋自身が独裁的な新軍閥と化して民衆の支持を欠き、孫文が提唱した北伐とは異質のものとなった。
[伊東昭雄]
旺文社世界史事典 三訂版 「北伐」の解説
北伐
ほくばつ
1926年7月,蔣介石を総司令とした国民革命軍は広東から進撃し,同年内に武漢を,翌年には南京を占領した。このとき労働者らを指導して上海を自力解放した共産党の力に驚いた列強と浙江財閥は,蔣介石に働きかけて1927年4月12日上海クーデタを起こさせた。南京に国民政府を樹立した蔣介石は,国民党左派と共産党の拠る武漢政府と対立して共産党を追放,第一次国共合作は崩壊した。以後,武漢政府を吸収した蔣介石は1928年4月に北伐を再開し,張作霖 (ちようさくりん) を北京から追い出した。その後日本軍により爆殺された張作霖の子張学良が“易幟”を行って国民政府の配下にはいることを表明し,北伐は完成した。この間日本は2度にわたる山東出兵を行い,済南事件を起こして反日感情を増大させた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「北伐」の解説
北伐
ほくばつ
1921~28年,広東の南方革命政権が実施した北方軍閥政権打倒をめざした軍事行動。とくに26年7月~28年8月の蒋介石(しょうかいせき)を総司令官とした国民革命軍の出兵をさす。共産党も先遣隊を組織して積極的に参加。26年10月までに長沙と武漢を陥れ,翌年1月国民政府は武漢に移転したが,蒋介石が反共クーデタをおこし,南京に政府を樹立して武漢政府と対立。7月共産党員は武漢政府から排除され,9月国民政府は再統一された。中断した北伐も28年4月に再開,6月北京を占領,年末,張学良(ちょうがくりょう)の易幟(えきし)で中国はいちおうの統一を達成した。この間,幣原(しではら)喜重郎外相は対中国内政不干渉の外交方針を堅持したが,田中義一内閣になると,居留民保護を理由に3度にわたる山東出兵を行った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「北伐」の解説
北伐(ほくばつ)
中国の国民革命軍の北方軍閥に対する出兵をいう。1926年7月に開始され,四・一二クーデタおよびこれに続く政変で中断されたが,28年4月再開,6月北京を占領して,ここに北伐を完了した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「北伐」の解説
北伐
ほくばつ
特に1926〜28年の蔣介石中心の国民革命軍によるものが有名。蔣は共産勢力に弾圧を加えて南京政府を樹立。革命軍の分裂により中断したが,'28年再開し,張作霖を追って北京を占領。北伐を完成し,万里の長城以南の中国本土を統一した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の北伐の言及
【国民革命】より
…大会後,革命の軍隊をつくるべく黄埔軍官学校(校長蔣介石,政治部主任周恩来)が創立され,指導者養成のために農民運動講習所なども設立された。 孫文逝世後,広東政府は汪兆銘を中心とする国民政府に改組され,26年7月,蔣介石を国民革命軍総司令として北伐を開始した。国民革命軍はソ連赤軍に学んで党代表制を取り入れ,政治教育を行ったため,軍閥軍に比べて戦闘精神にひいで,とりわけ葉挺の独立団をはじめ,共産党員が重要な役割を果たした。…
【中華民国】より
…護法とは,袁世凱のあとを襲った段祺瑞がやはり臨時約法を蹂躙(じゆうりん)するのに対し,それを擁護することを根本の主義とするもので,革命によって成立した中華民国の正統な後継者との立場を表明するスローガンであった(護法運動)。ここに南北対立の局面が出現し,以後この分裂の構図は北伐の完成まで約10年間あまりつづくことになる。 この状況に直面して段祺瑞は北洋派をあげての武力統一を図ったが,その結果,同派の内部矛盾が急激に顕在化し,段祺瑞の安徽派,馮国璋(ふうこくしよう)の直隷派,張作霖の奉天派等々が入り乱れて中央政権の争奪戦を演じ合うことになる。…
※「北伐」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...