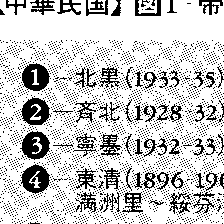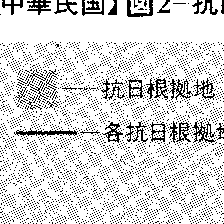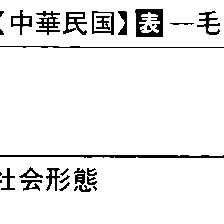共同通信ニュース用語解説 「中華民国」の解説
中華民国
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「中華民国」の意味・読み・例文・類語
ちゅうか‐みんこくチュウクヮ‥【中華民国】
改訂新版 世界大百科事典 「中華民国」の意味・わかりやすい解説
中華民国 (ちゅうかみんこく)
Zhōng huá mín guó
1912年から49年にかけての中国の国名。簡称して単に〈民国〉ともいう。清朝をたおした辛亥革命によって創立されたアジア最初の共和国で,新民主主義革命によって成立した中華人民共和国に先行するものである。版図は,外モンゴルが独立したことにより清朝滅亡時より縮小している。32年に東北地方が日本の傀儡(かいらい)国家=満州国として分離させられるなどのこともあったが,日本の敗戦とともに,東北のみならず下関条約で割譲された台湾等への支配をも回復した。49年以降,大陸を追われた中国国民党の政権が台湾に拠って今に至っている。中華民国の約40年間の歴史は,27年をピークとする国民革命を境に前後2段に分けられ,前段は北洋軍閥が支配した時期,後段は国民党が支配した時期である。首都は前段が北京,後段が南京(抗日戦中は重慶)である。行政区画では,東北に熱河省が建てられるなど若干の差異がないわけではないが,おおよそのところ現在の省制に近いものである。この時代の中国社会の性質は,基本的に,帝国主義列強が間接的に支配する半植民地であり,近代工業の発展にもみるべきものはあったが,やはり農村を中心に封建勢力が支配する半封建社会であった。この世界の人口の4分の1をしめる中国市場は各国の垂涎(すいぜん)の的で各国が権益を渉猟したが,とくに日本は露骨な侵略戦争にまで踏み出した。その困難をのりこえて,中国共産党にみちびかれた新民主主義革命が勝利し解放にいたるのである。
政治,軍事
軍閥の抗争
1911年10月,武昌の新軍蜂起に始まった辛亥革命により満州族王朝としての清朝は打倒され,12年元旦,アジア最初の共和国である中華民国臨時政府の誕生をみた。首都は南京。初代臨時大総統にはもっとも威信ある革命家孫文が就任した。新共和国は五色旗を国旗とし,暦制には12年を中華民国元年とする中華民国暦(陽暦)を採用した。南京の革命派は,主権在民,立法府の行政府に対する優位などをもりこんだ臨時約法(憲法にあたる)を制定し,民主的な議会制にもとづくブルジョア共和国のデザインをえがきあげた。しかし彼らの力はそこまでであった。孫文は臨時大総統位を袁世凱(えんせいがい)に譲らざるをえず,軍閥の親玉である袁世凱は首都を北京に移して,独裁支配への道を歩みはじめる。中国に多くの権益をもつ列強は,革命家孫文を支持することはなく,軍閥袁世凱を後押しし,国内の有産階級もやはり袁世凱に政権をまかすことをえらんだ。しだいに体制を確立した袁世凱は,列強から2500万ポンドの善後借款を得るや,革命派を挑発した(対華借款)。13年7月から9月にかけて,革命派が起こした反袁蜂起(第二革命)は簡単に敗北した。2年前には既存の体制に対して鬱積していた各階各層の不満が革命に対する支持へと収斂していったのに,今回はまったく孤立した形での軍事冒険にとどまったからである。革命派をやっかいばらいしたのち,袁世凱は国会をとりつぶし,臨時約法を廃止した。国会は13年4月に開設されたばかりのもので,臨時約法とともに辛亥革命のもっとも重要な成果だったのである。
袁世凱は力に依拠して反対派をおさえこみ,列強の支持を背景に全中国を支配しえたかのごとくであった。その勢いに乗って,彼は帝制の復活をたくらんだ。軍事力に後光をそえる精神的威信をもとめたのである。第1次世界大戦の勃発を機に,中国政治に対する実質的干渉をなしうる立場を維持しつづけられたのは日本だけになっていたが,袁世凱は二十一ヵ条要求の許諾とひきかえに日本の帝制承認もとりつけていたといわれる(帝政問題)。しかしこのあからさまな反動が,国内にくすぶる不満を一挙に爆発させた。帝制反対は反袁闘争にたちあがろうとしていた諸勢力に対してかっこうの結集軸となったのである。状況の展開を察した列強は日本をもふくめて帝制延期勧告にまわり,さらに雲南の護国軍蜂起(第三革命)となった。しかし袁世凱は帝制を強行し,16年元旦を期して洪憲と改元,国号を中華帝国と改めた。帝制反対の勢いはますます強く,わずかに83日間で袁世凱は帝制取消しに追いこまれ,失意のうちに急死する。また翌年7月に張勲と康有為が廃帝溥儀(ふぎ)の復辟(ふくへき)を敢行したが,この茶番劇も12日間の短命に終わった。民国を帝国にあともどりさせることは前皇帝にも軍閥の親玉にももはや不可能だった。袁世凱の死後,北京の中央政権を掌握したのはその右腕,段祺瑞であった。段祺瑞は日本を後ろだてに袁世凱の衣鉢を継ごうとしたが,護国戦争を経る間に各地の軍閥の地盤強化がすすみ,もはや袁世凱時代ほどの統一も図れなかった。とりわけ両広雲貴(広東・広西・雲南・貴州省)の西南地方に拠る非北洋系の軍閥は中央に対して対抗的にふるまった。西南軍閥も軍閥という点では北洋軍閥となんら異なるところはなかったのだが,〈護法〉の旗をかかげる孫文とむすぶことにより,大義名分をかかげて北京政府に対抗したのである。護法とは,袁世凱のあとを襲った段祺瑞がやはり臨時約法を蹂躙(じゆうりん)するのに対し,それを擁護することを根本の主義とするもので,革命によって成立した中華民国の正統な後継者との立場を表明するスローガンであった(護法運動)。ここに南北対立の局面が出現し,以後この分裂の構図は北伐の完成まで約10年間あまりつづくことになる。
この状況に直面して段祺瑞は北洋派をあげての武力統一を図ったが,その結果,同派の内部矛盾が急激に顕在化し,段祺瑞の安徽派,馮国璋(ふうこくしよう)の直隷派,張作霖の奉天派等々が入り乱れて中央政権の争奪戦を演じ合うことになる。段祺瑞のひきいる安徽派は20年7月の安直戦争に敗れて政権を失い,直隷派とその同盟軍奉天派が政権の座についた。ついで22年4月,直・奉両派が争って直隷派が勝利したが(第1次奉直戦争),やがて24年9月,奉天派がふたたび戦争をしかけて直隷派の支配をくつがえした(第2次奉直戦争)。奉天派の勝利は日本の後援,安徽派および南方勢力との同盟あってのことであったが,とりわけ勝利の決定的要素となったのは直隷派の驍将(ぎようしよう)馮玉祥(ふうぎよくしよう)の寝返りであった。反旗をひるがえした馮玉祥は北京を制圧して大総統曹錕(そうこん)を幽閉するとともに,清朝の皇族を紫禁城から追放した。いわゆる首都革命である。袁世凱以後,大総統位には黎元洪(1916-17),馮国璋(1917-18),徐世昌(1918-22),黎元洪(1922-23),曹錕(1923-24)が登ったが,このあと大総統位についたものはなく,段祺瑞が臨時執政(1924-26)となり,そのあと一年有余の混乱期間を経て最後に奉天派の総帥張作霖が軍政府大元帥(1927-28)となった。中央の政権争奪戦と同時並行的に地方レベルの地盤争奪戦もたえず展開された。北洋軍閥の支配時期は1000回をこえる大小の内戦が行われた時代であった。かくして,北洋支配を打倒するための北伐,国民革命の開始されるころの形勢は,東北を地盤に北京を扼(やく)する張作霖を中心に,両湖(湖南・湖北省)の呉佩孚(ごはいふ),江南の孫伝芳,山東の張宗昌,山西の閻錫山(えんしやくざん),陝西の馮玉祥といったところが華中・華北に割拠するという状況だったのである。
→軍閥
この間,中国は第1次世界大戦の協商国側に参戦して戦勝国の一員となった。中国近代史上,最初の国際戦争における勝利である。ところがパリの講和会議(ベルサイユ条約)はドイツの山東権益を日本に与えてしまったので,19年5月,ここに空前の大衆運動である五・四運動が勃発した(山東問題)。運動は勝利をおさめ,中国政府は対ドイツ講和条約への調印を拒否した。この経験と成果の影響するところはすこぶる大きかった。政治面への影響は,まずなによりも反体制運動に対する根本的な評価転換という面に現れた。いわゆる旧民主主義革命から新民主主義革命への発展である(新民主主義)。西南軍閥を足場に北京政府の打倒を図ってきた孫文は,大衆運動の重要性に注目して,19年10月に非公然結社の中華革命党を公然革命政党たる中国国民党に変えた。くわえて21年7月には,ロシア革命の道を歩もうとする中国共産党が誕生した。このときコミンテルンは東方に革命をもとめ,また孫文の方でも中国の革命に対する国際的援助をもとめていたので,双方の利害は一致し,ここに国共合作が日程にのぼることとなった。プロレタリアートの前衛党である共産党とブルジョア政党との合作協力は,半植民地・半封建社会における抑圧者=帝国主義と封建主義,とりわけそれらの政治的代理人である軍閥に対する統一戦線として可能となったものである。合作は中共党員が個人の資格で国民党に入党するという党内合作の形式が採用された。24年1月,国民党の1全大会が広州で開催され,第1次国共合作は正式に開始された。新しい国民党は,やはり孫文を総理に戴き,三民主義をその党是としてはいたが,連ソ・容共・農工援助の三大政策(三大政策という名称は3年ちかくのちに提起されたものである)の採用によってまったくその様相を一新した。それは,行動力にあふれる共産主義者を迎えいれて党を若がえらせ,ソ連赤軍に学んで党の軍隊をつくり(黄埔軍官学校),労働者農民と結びついたこれまでとはまったく違う革命闘争を展開できるようになった。
国共合作の成立後1年あまりのちに孫文は没したが,その間に党勢は大いに発展し,国民党指導下の広東大元帥府大本営(軍政府の一種。1925年7月改組して広州国民政府,いわゆる広東政府となる)も強化された。五・三〇運動に端を発した省港ストライキが16ヵ月にわたって戦えたのも広東政府が存在すればこそであった。もちろん政府の方も人民大衆に依拠することによって強化されたのであって,広東政府は陳炯明(ちんけいめい)に代表される広東省内の反対勢力を討伐するとともに,西南とくに李宗仁の新広西軍閥を味方につけ,いよいよ北伐に乗り出すことになる。26年7月,国民党中央執行委員会常務委員会主席,黄埔軍官学校校長の蔣介石が国民革命軍総司令となって北伐は開始された(党主席は北伐期間中は張人傑が代理を務めた)。単純に軍事力を比較すれば,兵力,武器ともに北伐軍の劣勢は明らかだったが,この軍隊には規律と革命精神があり,さらに呼応して起つ労農大衆という味方があった。毛沢東の文章で有名な湖南農民運動はその最たるもので,これに支えられた湖南方面の北伐軍はまたたくまに同省を制圧し,10月には華中の要衝,武漢を占領した。農民のみならず,都市民衆も決起し,27年1月には漢口,九江のイギリス租界が実力で回収されるという破天荒な事態も出来(しゆつたい)した。
蔣介石は江西方面に進み,総司令部は南昌におかれた。すでに北伐開始以前に蔣介石を頭とする新右派は共産系抑圧を図り,両者の対立が顕在化しつつあったが,共産党が譲歩して北伐をすすめたのである。すでに軍権を掌握した蔣介石はさらに政権をも手中にしようとして南昌遷都を図ったが,反蔣の左派と共産派は27年1月武漢に遷都を強行,さらに第2期3中全会で総司令職を廃して蔣介石を一軍事委員に格下げし,党・政の大権を汪兆銘に託して蔣介石に対抗しようとした。一方,帝国主義と中国の資本家,地主は,国民革命軍の破竹の進撃をみて,北伐の隊伍のなかに彼らの代理人をもとめるにいたった。彼らの眼鏡にかなったのは蔣介石で,蔣介石の方でもその道をえらんだ。4月,蔣介石は上海の赤色労働者を大量虐殺して(四・一二クーデタ)その立場を内外に明らかにした。〈清党〉の名のもとに蔣介石の支配下では白色テロが荒れくるった。武漢に対抗して蔣介石が南京に国民政府を樹立したため,一時は北京,武漢,南京の3政府鼎立の状況が生み出された。
武漢の左派勢力は蔣介石の裏切りを声高に叫んだが,その裏では国民党と共産党の対立がしだいに明確になっていった。地主の土地没収をめぐっての意見の分岐が軍事的対決にまで進み,やがて7月,武漢の国民党も〈分共〉という名の共産党粛清にふみきった(七・一五事件)。この間,スターリンの指導するコミンテルンは,国民党左派から離れることなく,しかも独自の労農武装を組織せよ,との実行不可能な指令(五月指示)を出して混乱を深めた。武漢分共により国共合作は完全に崩壊し,共産党は独自に革命の道を歩むことになるのだが,八・一南昌蜂起から井岡山への道がその新たな出発の開始であった。武漢と南京の国民党は若干の曲折を経たのち,南京政府のもとに統合され(寧漢合作,寧は南京の別称),翌28年4月に馮玉祥,閻錫山の協力を得て北伐を再開し,6月には北京を占領した。ここに関内は国民政府の支配のもとにおかれることになった。北京を逃げ出した張作霖は奉天を目前にして日本軍に爆殺された。日本で当時,満州某重大事件(張作霖爆殺事件)とよばれた大謀略事件である。跡目を継いだ張学良は,28年末,北洋時代の五色旗に替えて国民政府の国旗である青天白日旗を東北全域にかかげさせ(易幟(えきし)),ここに中国全土の統一が完成した。のち29年6月,国民党は,北京に客死して以来西山碧雲寺におかれていた孫文の遺体を,完成したばかりの南京紫金山麓の中山陵にうつし,世界各国代表参列のもとに盛大な典礼を挙行した。
→中国共産党 →中国国民党
蔣介石の国民政府
北洋軍閥の支配は打倒され,国民党による統一が達成されたとはいえ,一皮めくるとその内部は新軍閥の寄合所帯であった。そのうち強大なものは馮玉祥の国民軍(陝西,河南などの黄河流域数省をおさえ,兵力約40万),山西モンロー主義をとなえる閻錫山にひきいられた山西軍閥(河北,内モンゴルを有し,約30万),両広・両湖を支配して西南に覇をとなえる李宗仁の西南軍閥(約30万),張学良の東北軍閥(約20万),それに雑系軍閥の各地に散在するものが約50万を数えた。当時の全国総兵数は約220万と推定されていたから,蔣介石の配下は単純にみて約50万,富庶の地,江南を地盤とするなどの優点を有するとはいえ,けっして圧倒的な支配をほどこせる立場にはなかった。支配の基盤をかためるべく蔣介石がまず着手したのは党と政府の掌握であった。28年10月に公布施行された〈訓政綱領〉では,当面,国民大会(国会)の機能を国民党が代行し,しかも大権を中央執行委員会政治会議に集中することによって権力を独占する体制が構想された。〈党をもって国を治める〉一党独裁制は,のち31年5月の国民大会で制定された〈訓政時期約法〉に規定される。〈訓政綱領〉の制定とあわせて政府も同時に組織されたが,それは孫文の五権分立主義にもとづき,行政・立法・司法・考試・監察の五院制をとるものであった(五権憲法)。国民政府(国府と略称される)主席には蔣介石自身が就任し,陸海空軍総司令をも兼任した。
中央権力を手にした蔣介石にとって次に必要だったのは,他派の軍閥兵力の削減であった。29年1月,蔣介石は国民革命編遣委員会(編遣は改編,解散の意)をつくり,そこで220万を3分の1の80万に削減しようとした。大義名分からすれば反対できないが,どの軍閥も自派の勢力凋落はのぞまなかったから,このような大規模な改革の実現されるはずはなく,結局,また内戦の再開となった。まず反旗をひるがえしたのは広西軍閥であったが,馮玉祥,閻錫山ら他派もつぎつぎと起ち,30年5月には汪兆銘をかついだ大規模な反蔣戦争が爆発した。戦争は半年にわたったが,張学良の加担を受けた蔣介石の勝利に帰した。しかし蔣介石の権力はなおも安定するにはいたらず,反対派は31年5月,またもや汪兆銘を擁して広州に別の国民政府を組織した。この広州政府は日本の満州侵略に際して解消されたが,この間にまったく新しい政治勢力が発展しはじめていた。27年の合作崩壊によってほとんど壊滅的な打撃をうけていた共産党の新たな登場がそれである。毛沢東,朱徳にひきいられた紅軍は,軍閥支配力の脆弱(ぜいじやく)な江西省の辺境,井岡山にのぼって遊撃戦を展開,農村の革命根拠地でもって反革命の都市を包囲する道を歩みはじめた。土地革命によって貧農の支持を得たこの革命路線は成功し,蔣介石の包囲討伐を何度もはねかえして31年11月には瑞金(ずいきん)を首都とする中華ソビエト共和国を樹立するまでになった(土地革命戦争)。
このころ,日本の侵略は新たな段階に入り,亡国の危機が迫っていたにもかかわらず,蔣介石は日本に譲歩しつつ共産党の絶滅をはかった。いわゆる〈安内攘外〉策である。33年10月に始まる第5次包囲殲滅(せんめつ)により,蔣介石はようやく瑞金攻略に成功した。さらに34年10月に西遷(長征)を開始した紅軍を追って蔣介石はその絶滅を図ったが,これには成功しなかった。遵義会議で毛沢東の指導権が確立された共産党は,やがて陝西省北部に到達し,延安を中心として抗日戦争,解放戦争を戦いぬくことになる。したがって瑞金攻略の成功は,蔣介石の期待に反して事柄の始まりにすぎなかったのだが,しかし彼は共産党に対する包囲殲滅,追撃戦を通じて別の成果を手中にした。すなわち,各地に割拠する地方軍閥の地盤を南京政府の支配下におくことに成功したのである。
討伐用の軍事道路が主であったが,北洋時代にはほとんど無きに等しかった自動車用道路(公路)が37年には11万kmあまりに達した。鉄道建設は道路ほど目覚ましくはなかったが,それでも30年代前半に関内だけで約4000kmにおよんだ。電信,郵便面の発達もかなりのものであった。交通・通信網の発展が中央集権,国内市場の確立に果たす役割ははかりしれぬものがあるが,ことに粤漢(えつかん)鉄道(広州~武漢)の開通(1936年6月)は西南軍閥の割拠の基盤を根本的に掘りくずしたのであった。商工業も発展し,30年代前半において中国国民経済の多くの分野の指数は解放前の最高水準に達した。国民政府による統制策は一面では大衆収奪による官僚資本の形成発展をもたらしたが,同時に半植民地的な統一を促進しもした。その面でとりわけ評価されるのが35年秋の幣制改革である。〈法幣〉とよばれる紙幣本位制(初めはポンドに,のちドルともリンクされた)の採用により貨幣金融の中央統制化に成功し,ここに近代的統一的幣制の確立をみたのである。またこの間における国際関係の改善にもみるべきものがあった。28年7月以来ベルギーなど数ヵ国と平等互恵をうたった新たな通商条約を締結し,また同年7月にアメリカに対し関税自主権を回復,ついで12月にイギリス,フランスと,さらに翌年2月には日本とも新関税条約を結んだ。もっとも執拗に特権の維持を図ったのは日本だったが,大勢には抗しきれなかったのである(関税問題)。領事裁判権の取消しには成功しなかったが,中国が取消しを提起したのに対し,29年11月にメキシコが自発的に放棄するといった効果も生んだのであった。
日本の侵略と国共合作
国民革命に対しもっとも露骨に反対したのは日本であった。1927-28年にかけて3回も山東出兵を行い北伐を阻止しようとしたほどである。それでも北洋軍閥の支配が崩壊したので,日本はさらに直接的な支配に乗り出した。31年9月のいわゆる満州事変はその号砲であった。翌年3月〈満州国〉をつくり,33年3月に国際連盟を脱退すると早速に長城線を越えて関内に出兵し,35年12月には冀東防共自治政府,冀察政務委員会をつくって華北一帯に浸透を図るなど,その侵略はとどまるところを知らなかった。
この重大な民族的危機に直面しながら,蔣介石はなおも共産党討伐に血道をあげ,日本を〈友邦〉と規定し,内戦の停止等を訴える沈鈞儒,鄒韜奮らが逮捕された七君子事件(中華全国各界救国聯合会)に象徴されるように反日愛国運動を逆に弾圧した。しかしあらゆるファッショ的弾圧をほどこしても民族主義の高揚をおさえこむことはできず,その波はついに国民党の軍隊にまでおよび,36年12月,世界を震撼したかの西安事件の発生をみるのである。全国にまきおこる〈一致抗日〉の要求を蔣介石が実行にうつしたのは,37年7月の蘆溝橋事件(七・七事件)に始まる日中全面戦争(日華事変)の開始後のことで,9月,第2次国共合作が成立した。国共両党は内戦を停止し,民族統一戦線を結成して抗日戦争を戦うことになった。ソビエト政府は中華民国特区政府,紅軍は形式上,国民革命軍と改称された。特区とはふつうには辺区と呼ばれているもので,国民革命軍に改編された紅軍中のもっとも有名なものが第八路軍である。38年3月の国民党臨時全国代表大会では〈抗戦建国綱領〉が制定され,戦時最高民意機関(諮問機関)としての国民参政会の創立も決定された。この会議で蔣介石は党の総裁に選ばれて確固たる権力を手中にし,また汪兆銘は38年7月に開催された国民参政会の議長となった。全国をあげての抗戦体制が確立されたかのごとくであった。
戦争は最初,日本軍の優勢のもとに展開された。60万の大軍を投入した日本軍は,7月末には北京,天津,12月には首都南京,38年5月には徐州,10月には武漢,広州を占領し,1年あまりで重要都市のほとんどを陥落させた。だがそこまでだった。国民政府は重慶に移り,抗戦を堅持した。日本軍の占領地域では,1937年12月に北京で中華民国臨時政府が組織されて華北5省の支配に当たり,38年3月に南京で中華民国維新政府が組織され,江南・長江(揚子江)流域の支配に当たった。これらはやがて40年3月に汪兆銘を頭につくられる〈統一〉傀儡(かいらい)政権=中華民国国民政府(汪兆銘政権,南京)に統合されるのだが,抗日戦争中の中国は,大きくいって日本・傀儡政権支配下の〈淪陥区〉と重慶政府に属する〈大後方〉の二つの部分に分かれていたのである。さらにいえば,共産党の辺区政府は独立自主の原則をかかげた別組織であったばかりでなく,淪陥区のなかに多くの抗日根拠地(解放区)をつくりあげ,日本軍・傀儡軍をして点と線の維持に汲々たらしめていた。
国民参政会の成立に象徴されるように,最初は国共合作もかなり順調だったが,日本軍の侵攻がゆるんで対峙段階に入ると蔣介石は早速に共産党勢力に対する攻撃を開始した。なかでも41年1月の新四軍事件はもっとも有名である。これ以後,国共合作は実質的には崩壊し,共産党は国民参政会への参加を拒否した。12月8日に太平洋戦争が始まると,その翌日には中国は日本に宣戦した。しかし蔣介石の消極的抗戦の姿勢は変わらなかった。〈粟プラス小銃〉だけといった劣悪な物質条件下にありながら抗日の先頭に立つ共産党の威信は増すばかりで,愛国的青年は万難を排して抗日の中心=延安に向かい,戦列に身を投じた。じつに共産党側が敗戦時には110万(関東軍100万は別)を数えた日本軍の60%,傀儡軍の96%を相手に戦ったといわれる。腹背に国民党軍と侵略軍の攻撃を受けながら,共産党側は戦闘を通じてその支配地域を拡大していった。45年8月,8年におよぶ抗日戦争を勝利のうちに終えたときには,全国に19の抗日根拠地をうちたてるにいたっており,その人口は9300万に,軍隊は正規軍120万,民兵220万にまで発展していた。国民党側とて戦わなかったわけではなく,また抗日の立場を一貫して堅持しはしたが,共産党対策が先行して十分な抗戦を行わなかったのである。しかも,彼らはその反共主義から民主的愛国運動を藍衣社などの特務組織を使ってファッショ的に弾圧したばかりでなく,蔣・宋・孔・陳の四大家族を頂点とする収奪の体系をつくりあげたため,人民の支持を失っていったのである。
→抗日戦争
国共内戦
45年8月,日本は連合国に降伏し,中国は抗日戦に勝利した。降伏調印式の翌日の9月3日,全国各地で連合国共通の戦勝祝賀式典がとりおこなわれた。抗戦の勝利は喜ぶべきことだったけれども,中国の内情は複雑だった。共通の敵である日本が敗れ去ったあと,抗日の二つの中心,重慶と延安の二大勢力の決戦の時が近づいていたのである。全国土がほとんど焼土と化した未曾有の大戦禍をこうむったあとだったから,人々の和平,統一への願望は強烈で,いかなる勢力もそれを無視することはできなかった。くわえて国民党側の主力軍は奥地に配置されているという軍事的制約もあって,戦勝後ただちに国共両党間で和平交渉(重慶交渉)がおこなわれ,平和団結を確認する協定が結ばれた(双十協定)。46年1月には,国共両党に民主同盟などの諸党派を加えた政治協商会議が重慶で開催され,国民大会開催の方針も打ち出された。しかしその一方で,アメリカの莫大な援助を得て戦闘準備を終えた蔣介石は,46年6月末に共産党支配区への攻撃を開始した。兵力比は国民党側430万に対し,共産党側120万,武器等の物質条件にも圧倒的な開きがあった。したがって当初の戦闘は国民党側が優位にあるかのようであった。11月,国民党は憲法制定のための国民大会を召集(共産党と一部の民主党派は不参加),憲法草案を制定した(1947年元旦公布,同12月施行)。47年3月には,共産党側が主動的に撤退したあとへではあったけれども,延安をも占領した。だがそこまでだった。共産党の側は効果的な反撃の機会をうかがっていたのである。
抗日戦争でもっとも困難な役割をみずから担った共産党軍には豊かな経験,高い士気,それになによりも人民の支持があった。土地改革に代表される農民との結合はそのシンボルであった。また国民党官僚資本のあくなき収奪によるインフレの急進,官僚軍人の腐敗堕落から都市民衆の支持も共産党へと傾いていった。47年7月,人民解放軍(47年3月に命名)は戦略的反攻に転じた。反攻の1年後には解放軍は280万に発展し,解放区の人口は1億6800万を擁するまでになった。48年9月以降,遼瀋,淮海(わいかい),平津の三大戦役が戦われ,東北,華北が解放された。49年4月,〈全国への進軍命令〉が下ると最後の怒濤の進撃が開始され,4~5月の間に南京,武漢,上海が,ついで秋には広州,重慶も解放された。4年間の内戦中に解放軍が殲滅した国民党軍は800余万にのぼったというが,歴史上に比類のない内戦だった。
没落に瀕しながら,国民党は支配再建への最後の努力を行った。1948年3月には南京で第1回国民大会を開催し,5月,国民党総裁蔣介石が中華民国総統に就任した(副総統は李宗仁)。これは訓政時期をおえて〈三序〉の最高段階=憲政を開始することにより内外の支持をとりもどそうとする演出であったが,あくまでポーズにとどまった。内戦の最中なのだから当然のこととはいえ,同じ国民大会で,総統に独裁権を与える特別決議(〈動員戡乱(かんらん)時期臨時条款〉)がなされ,憲政の最大の眼目である民主主義が空洞化されていたからである。みせかけの憲政移行は実は国民党支配の崩壊の合図であった。戦局の日に非なるを見て,蔣介石は49年1月,総統を辞任して台湾にとんだ。2月以来,広州,重慶,成都を転々とした国民政府も12月に台北へ移った。これよりさき,共産党は新しい国家をつくりあげることに踏み切った。すなわち,49年9月,新政治協商会議を開催して,労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の共和国の樹立をうたう〈共同綱領〉を制定し,それにもとづいて10月1日,中華人民共和国の成立を世界に向けて宣言したのである。
社会,文化
都市の繁栄と農村の疲弊
清代に続き,中華民国の時代も中国は半植民地・半封建社会であり,その半植民地化は時とともに進んだ。清朝末期に始まった近代産業の発展は民国時代に入ってさらに加速され,辛亥革命時に約60万を数えた労働者階級の隊伍は五・四運動当時には約200万となり,マルクス主義,ボリシェビズム受容にとっての社会的基礎となった。もちろんこの数値は全人口に対してわずかなものでしかなく,また鉱工業生産額もピーク時の1930年代で総生産額に対して約1割を占めるにすぎない。しかし広大な農村が世界市場に結びつけられたため,半植民地的に編成された中国の国内市場はみかけ以上に大きなものだった。その象徴的存在が当時の東洋一の大都市,上海である。半植民地化の進行は,一方の極に上海を頂点とする都市の〈繁栄〉を生み出したが,他方の極に農村の疲弊をもたらした。
農村では旧来の地主制が温存されたまま商品経済化が進展した。その結果,地主・商人・高利貸の三位一体的収奪はさらにきびしいものとなり,農民は土地を失って没落していった。その一部が労働者,クーリー(苦力),遊民となって伝統的体制からはみでていったのに対し,大多数は貧農,雇農としてよりいっそう劣悪な条件のもとでの生産,生活を強いられた。彼らはそのような困難のもとで生産を担い,彼ら自身の貧困化とひきかえに全体としての富を増やしていった。そのなによりの証拠は,富の外流すなわち帝国主義列強による収奪の年を追っての増加と,19世紀末から半世紀あまりの間における,5割を超えると推定されるほどの人口の大幅な増加である。この背理は,基本的に,より小さな土地により多くの労働を投入し,しかもより多くの搾取を甘受させられることによって成り立っていた。このような社会にあっては,外国人観察者がしばしば驚きをもって書いているように,ガソリンより人力の方が安価だというだけで,重量物の運搬さえ多数の苦力の肩に依存するという状況が普通だった。しかも,この時代にあっては政治的収奪は軍閥割拠を反映して乱脈そのものだった。有名な例だが,もっとも混戦がはげしかった四川省では,数年あるいは十数年先までの税金の事前徴収はほとんど普通のことだったし,また幣制改革をはじめとする国民党政権の中央集権化のための諸施策はすべて,蔣介石ら四大家族,官僚資本の致富の手段ともなった。このように貧困をしいられた農民は,近代文明からかけはなれた(いわゆる〈一窮二白〉すなわち一に貧窮,二に文化的に白紙)存在であって,迷信にすがり,不衛生にとりまかれた生活を余儀なくされた。しかし,彼らこそ社会のもっとも基本的な富の生産者であったから,農民問題が中国近代におけるもっとも重要な社会問題となるのであって,毛沢東にひきいられた中国共産党がそれに一つの解答を与えたのである。
新文化運動の展開
清末に始まった西洋近代文明の受容は,中華民国の成立後にはいっそう拍車がかかった。文化の基盤をつくる教育制度についてみれば,1912年の壬子(じんし)学制で学校制度が体系化され,22年の壬戌(じんじゆつ)学制では小学4年の義務教育も決められた。就学率は29年に17%,36年には31%にのぼったとされるが,陶行知の小先生運動(子供が読み書きのできない大人に自分のならった文字を教える識字運動)にみられるように,民国時代を通じて文盲退治が初等教育の最重要課題であった。文字をもたぬ農民と一部の知識人のあいだに横たわる溝はほとんど越えがたいもので,封建制にあらざる身分制社会をなしていたといえる。このような社会にあって上海に代表される都市に新しい文化の花が開いていくのである。
民国初年,辛亥革命から袁世凱の反動への政治的軌跡を文化界も同じくたどった。革命時に簇生した新聞雑誌への弾圧,とりわけ革命派的なものに対するきびしい弾圧により,民主,進歩にかけた人びとの希望はうちくだかれた。帝制の思想的支柱としては儒教がもちあげられ,孔子をまつる祭典も復活された(孔教)。そのころ文壇は鴛鴦蝴蝶(えんおうこちよう)派の軟文学一色にぬりつぶされたかの観を呈していた。しかし,そのなかにも新しい要素は確実にふくまれていた。小説にしろ映画にしろ(1913年に中国で製作された物語映画が初登場),封建的桎梏(しつこく)のもとでの悲劇を素材とするものが江湖の大歓迎をうけた。このような状況のもとで《新青年》が登場した。旧社会の儒教倫理に反対し,個性の確立をうったえる新文化運動の開始である。その旗印〈デモクラシーとサイエンス〉は西洋近代文化に学べということにほかならなかったが,現状に不満をいだきながら出口を見いだしかねていた青年たちに一つの針路を指し示した。少年中国学会をはじめとする多くの青年団体の創立はほとんどその直接的な結果であった。新文化運動は倫理革命のみならず文学革命をもその内容とし,口語文学(白話文)の提唱から実践へとすすんだ。清末以来白話はたえず提唱されてきたが,それがむしろ啓蒙のための白話提唱だったのに対し,このときには文学の本質にかかわるものとして提唱されたのであって,その点でまさに革命だったのである。その後数年間に白話の新聞雑誌の創刊されるものは400種を数えたといわれる。魯迅の《狂人日記》にはじまる小説の白話化の成果はいうまでもないとして,1930年には教科書の白話化も法律で決められるにいたった。
ついで西洋に学ぶ新文化運動のなかから,革命ロシアに学ぼうとする潮流が分化した。西洋近代の行きづまりを救うものとしての広義の社会主義思想は当時の中国でも広範な関心の対象で,改良派も革命派もなべてギルド社会主義,サンディカリスム等々といったしかじかの社会主義をかたっていた。そのなかからマルクス主義,ボリシェビズムの潮流が分化,形成され,1921年の中国共産党の創立となるのである。20年代初頭に,社会主義者の内部でもアナ・ボル論争などがたたかわされ,またロシアに学べ派と西洋に学べ派との間でも,〈問題と主義の論争〉などが行われた。論争はかなり激烈であったがけっして敵対性のものではなく,〈科学と人生観の論争〉にみられるように彼らは中国文化ないし東洋文化の優位をかかげて西洋近代思想に反対する動きに対しては一致して対処したのである。保守派は《学衡》(1922,南京)などによって新思想に対抗したが,文化界の新旧対立の構図はほぼ合作した国共両党と北洋軍閥の対抗の構図を投影したものであった。新興のエネルギーは20年代前半に文芸界における創造社,文学研究会の活躍や,歴史学界における《古史弁》の刊行開始といった形をとって噴出した。
北伐の成功から一転して国共分裂へといたる政治的激変が文化界に与えた影響は大きかった。国民党は一党独裁を教育文化界でも確立しようとして,学校教育の基本に〈党化教育〉をすえる(戊辰(ぼしん)学制)などの措置をとった。その中心の主義は孫文の三民主義だが,それは三大政策をその内容とする革命的三民主義ではなく,戴季陶の解釈にもとづいたものであり,蔣介石の独裁に奉仕させるためのものだった。国民党の反動化は,祀孔令の制定,中国本位文化の提唱から新生活運動の推進にまでおよんだが,いずれも政権党の上からする運動の範囲を出ることはなかった。共産党の非合法化とともに国民党はその主義まで包囲殲滅しようと図った。しかし当時,マルクス主義の権威は世界的にも高かったし,また中国ではなによりも国民革命の失敗が共産党への同情を生み出していた。
革命の進退ともっともよく波長の合う文学の分野では,一部の御用文人が国民党を支持しただけで,国民革命後には革命文学,プロレタリア文学が主流になったといわれる。30年に魯迅を中心に結成された中国左翼作家聯盟はその象徴である。また30年代前半に学術界では中国社会の性質規定をめぐる社会史論戦,中国農村社会性質論戦などが展開されたが,これらは中国革命をいかに進めるべきかという問題意識に発した論戦で,マルクス主義を中心に展開された。このころの文化界は国民党の弾圧包囲下におかれてはいたが,民国時代でもっとも活況を呈した時期で,小説では茅盾(ぼうじゆん)の《子夜》など,アカデミズムでは馮友蘭(ふうゆうらん)の《中国哲学史》など,多くのみるべき成果を残した。やがて日本の侵略にどう対処するかが文化界でも中心的な課題とされ,文芸界では国防文学論争の展開となった。
抗日文化戦線
日中全面戦争が始まると,社会条件はすべて一変した。北京大学がまず長沙に,ついで昆明へと移って清華大学,南開大学とともに西南聯合大学となったことに象徴されるように,文化界をあげて撤退,抗戦の態勢がとられた。文芸関係者は戦地服務団,宣伝隊,演劇隊等を組織して志気の鼓舞に当たり,兵士,民衆のなかへと入っていった。とりわけ演劇の分野の活躍はめざましく,郭沫若の《屈原》などが生み出された。やがて政治面の変化と照応して,新四軍事件を境として文化面での国民党のファッショ統制が格段にきびしくなり,作品発表も自由にならないという状況になった。しかし,締めつけによって国民党が得たものは知識人の離反だけだった。人びとは抗日の最前線にたつ共産党にひかれ,延安へと向かった。これらの文芸家たちに共産党の方針を指し示したのが毛沢東の《文芸講話》である。《文芸講話》のいう労働者,農民,兵士のための作家として,趙樹理らが延安で生まれた。延安ではほかに学術面で范文瀾の新しい歴史学も生み出されたが,むしろヤンコ(秧歌)など民衆レベルの伝統の発展的継承の面で注目すべき成果をおさめた。その頂点に位置するのが歌劇《白毛女》である。抗日戦には勝利したが,それは〈惨勝〉という言葉そのままの惨憺(さんたん)たる勝利であった。そこへ東北から海南島にいたるまでの,全中国をくまなくおおう大規模な内戦が続いた。内戦と並行して進められた社会関係の大変革=土地改革に素材をもとめた丁玲の《太陽は桑乾河に輝く》などの文学も生み出されはしたものの,やはりこの時期の文化界は,ほとんど成果らしい成果を生みだすことができなかった。それは次の幕開けを準備するかのような空白の時代であった。
執筆者:狭間 直樹
経済
列強による収奪
アヘン戦争以後の中国近現代史の中で,中華民国時代はどのように位置づけられるのであろうか。毛沢東は新民主主義革命期と規定した。それを表に筆者の解釈で表した。1949年以後は筆者がつけ加えたものだが,中国内部では依然として意見が分かれている。毛沢東の独創的見解は新民主主義革命期を設定したことにある。一種の資本主義社会である新民主主義社会を生み出す担い手を無産者階級に求めたことにある。中国の歴史状況ではブルジョア階級は帝国主義が中国を覆ったため,すでに革命性を喪失し,列強や封建勢力と結託して中国の富を吸い上げる階級に転化したという判断である。
この図式を富の移動に着目してみるならば,人口の90%が居住する農村で70~80%が被搾取者となり,農村の土豪劣紳により,富が吸い上げられる。それを,都市を支配する買辧官僚資本がさらに吸い上げ,列強と分け合う構図ができあがる。中国革命とはこの2本のパイプを切断することであった。
列強は南京条約以後,各種の方法で富を収奪した。日清戦争の結果,日本が取得した賠償金は当時の日本の国民所得の3分の1に及んだ。この金をもって日本は金本位制を確立した。1900年の義和団の乱では,清朝をしてその賠償金の4倍を11ヵ国が収奪する協定に調印せしめた。1937年から敗戦までの日中戦争時に,中国が受けた経済的損害は,殺害された1200万人の代償を除いても,46年の米ドル価で実に556億ドルに及んだと推計されている。今日のドル価ではおそらく数千億ドルに達しよう。日本の国民所得の半分以上になる。第2次世界大戦後,ソ連が東北地方から持ち去った工場諸設備は当時のドル価で20億ドルと推計されている。
列強が軍事的,経済的に中国を支配した最強の手段は鉄道であった(図1)。これが中国から資源と富を収奪し,各地域を植民地宗主国の補完地となし,中国の国内統一市場形成をさまたげ,分裂国家に陥れた元凶である。C.F.リーマーの推計によると,29-38年の10年間に賠償や政府借款の返済のため,中国政府が支払った金(きん)は,毎年平均8800万元であったという。列強の民間投資の利潤から流出した送金は年平均2億3600万元と推計されている。ちなみに,34年の公債収入を除いた中央政府の歳入は7億4500万元であった。
民族資本の成長
では,国民政府は列強の単なる水先案内人だったかといえばそうではない。この点がそれまで群雄割拠していた軍閥と異なる。民族資本の成長を背景に,それなりの統一市場の形成を行った。28年の南京政府の成立はその第一歩であった。関税自主権の回復,鉄道建設,紡績工業を中心とした軽工業の振興はみるべきものがあった。35年の幣制改革は米英経済にリンクさせたとはいえ,過去のギルド的な銭荘資金に対する民族資本の勝利を示すものであった。にもかかわらず,列強の軍事的・経済的侵略を防ぐだけの力を養うことはできなかった。最強の紡績資本ですら,中国全体の紡績スピンドル数の50%あまりを占めるにすぎなかった。この民族資本が肥大化し,国家権力を自家薬籠中のものにするのは,45年の日本敗戦後である。アメリカの援助に支えられ,日本支配下の諸生産力を接収し,工業,交通,貿易,金融などのほぼ3分の2以上を掌握するにおよんだ。これが中華民国そのものを崩壊させる要因となった。
人口の90%に達する農民に対する収奪は列強と買辧官僚資本の癒着が強化されるにしたがって強まった。地主がとる小作料は収穫の40~60%,このため3分の2の農民は慢性的な借金によって生命を維持した。その借金は高利で,33,34年ころ平均月利は7%余であった。さらに,地主への賦役,軍隊への献納金,一般租税と収奪の限りが尽くされた。この結果,60%の農民が飢餓線上に追い込まれていた。このうえに,自然災害は恒常的に襲いかかった。28~30年の3年間に,西北5省を襲った大干ばつで約1000万人が餓死したという。31,35年にはおのおの370万,300万の餓死者が出たと推計されている。平均寿命は30歳以下であった。この結果が辺境,都市,海外への流亡である。都市への流出は極貧の吹き溜りのスラムを形成した。
解放区における新民主主義経済
中国共産党は列強・買辧官僚資本・地主の三位一体を崩すため土地改革の手段をとった。抗日戦争期は小作料や高利の引下げにとどめ,解放区を拡大していった。図2は1937-40年ころの解放区の分布で,ここでは組合営業,個人業,私企業を混在させた経済がつくられた。辺境地が多いので私企業に巨大資本はない。これを新民主主義経済と呼んだ。45年10月10日,戦勝後の国の運営について,国民党と共産党との間で双十協定が結ばれた。しかし,国民党内の右派が台頭し,翌年には破棄するに及んだ。共産党が三位一体を土地改革により下から崩す挙に出たのが47年からである。以後5年をかけて全国の地主を一掃した。49年10月1日の新中国成立宣言はこの運動のひとこまである。この結果,当時の穀物生産量の3割に近い小作料3000万tが農民の手に帰するようになった。
新権力は即座に将来の社会主義統一市場の形成の準備に着手した。まず,ドイツの第1次世界大戦後のインフレをはるかに凌駕(りようが)した天文学的な悪性インフレーションの克服につとめ,穀物と衣料の実物を通貨代りに使って,51年には鎮静化に成功した。分散し,地方ごとに割拠する経済を統合するために,中央財政への強力な統一措置がとられた。通貨は解放区のものだけでも12種もあった。中華民国や外国のものを含めると,多岐にわたったが,51年11月に人民幣に統一された。そして,55年にデノミを行って今日の通貨制度が確立した。経済計画の立案のために,農村を除き,各都市の商工業,交通,建築,人口などに対する総合的な調査が行われた。このようにして,53年から第1次五ヵ年計画に入っていったのである。
執筆者:小島 麗逸
台湾政権
国民党による一党独裁
人民解放戦争に敗れた国民党右派の残存勢力は台湾に逃れ,1949年12月7日,中華民国政府を台北に移すことを決定,行政院の活動を台北で開始せしめた。以後今日にいたるまで,この台湾に拠る地方政権は,〈中華民国〉を称し,中国の正統政府であると主張し続けている。内戦敗北が決定的となった49年1月に総統職を辞した国民党総裁蔣介石は,50年3月,台北で台湾政権の総統に復帰,陳誠を行政院長に指名して,蔣介石直系の人びとでこの政権を固めた。アメリカ帝国主義の対アジア戦略の中で反共の最前線のとりでとなってアメリカから強力な軍事的・経済的援助を受けた蔣介石は,〈反共・抗ソ〉〈大陸光復〉を標榜(ひょうぼう)しつつ台湾省内では台湾省民の反蔣の動きを戒厳体制で押さえ込み,国民党独裁体制をつくりあげた。台湾政権は,46年に国民党が一方的に開いた制憲国民大会で制定した〈中華民国憲法〉を憲法とし,国民大会を政権行使の最高機関としている。47年11月に,これも国民党が一方的に行った第1回選挙で選出された国民大会の国民代表は,その後1回も改選されず,若干の欠員を補充選出したのみで今日にいたっている。
政権機構の頂点には,国民大会が選出した総統,副総統と総統府がある。総統は陸海空三軍の統帥権を有し,行政院長の任命権も有している。総統は,50年から75年まで蔣介石,蔣介石の死後は75年から78年まで副総統だった厳家淦(げんかかん)がなり,78年,第5回国民大会で蔣経国が選ばれて今日にいたっている。立法機関としては立法院があるが,国民大会と同様に1回も改選が行われておらず,立法委員(議員)の大半が事実上終身議員である。行政院は責任内閣制をとっているが,任命権は総統にある。行政院の下に各部(省),委員会がある。ほかに司法院,考試院,監察院があり,28年の国民政府以来の5院制をまもっている。台湾政権下の政党は国民党が最大で,蔣介石が75年の死まで総裁,その後は総裁を空席にしたまま蔣経国が中央委主席を担当して党の最高指導者となった。78年,第5回国民大会で蔣経国が総統に選ばれたが88年1月に死去し,副総統であった李登輝が総統に就任した。96年5月の直接選挙で選ばれた最初の総統は,台湾出身の現職総統李登輝であった。台湾政権の政治体制とその変化を見てくると,蔣経国総統時代の終りの87年の戒厳令解除,その自由化の方向を引きついだ李登輝総統の,とりわけ第8代総統に選出された90年代に入ってからの憲政改革が,国民党政権台湾移動以後の蔣介石総統時代の国民党独裁体制を徐々にではあれ確実に変革してきたといえる。2000年には野党・民進党の陳水扁が総統に選出されるに至った(04年再選)。しかし08年に馬英九が総統に選出され,再び国民党が政権に復帰した。
国際的地位
台湾政権の国際的地位には大きな変化があった。1950年代から60年代を通じてのアメリカ帝国主義のアジア戦略・対中国敵視政策の中で,台湾政権はアメリカ,日本ほか多くの西側諸国によって中国の正統政府とみなされ,国連においても長いあいだ代表権を保持,安保理常任理事国でありつづけた。この間,アメリカの軍事援助を受け,日本,韓国との関係を緊密化して,東アジアの米日韓台の事実上の軍事同盟関係の一翼を担ってきたが,第三世界の力量の増大と,ベトナム戦争の失敗によるアメリカのアジア戦略の転換によって,71年10月,第26回国連総会はついに中華人民共和国の国連代表権を回復,台湾政権は国連での地位を失った。72年2月のニクソン・アメリカ大統領の訪中,72年9月の日本と中華人民共和国との国交回復とそれに伴う日本との断交,78年12月のアメリカとの断交と,70年代に入って台湾政権は国際世界での地位を急速に失い,83年末には台湾政権を中国を代表する政府として承認している国は25ヵ国,アジアでは韓国のみという状況になった。しかし,実務関係を維持している国は多く,日本との民間レベルでの経済・文化関係,人的交流は依然として活発であり,日本企業の台湾進出と貿易不均衡は日台関係と台湾経済の構造的な問題となっている。また断交後も続けられているアメリカの台湾政権への武器輸出は,中米関係の摩擦をつねにつくり出している。
81年9月,中華人民共和国政府は,中国の統一=〈第3次国共合作〉をめざして9項目提案を行い,その後も統一のための具体的構想の一端を公にしてきたが,国民党および台湾政権は〈三民主義による中国統一〉の方針をとり,共産主義の放棄を統一の条件として公式には中国政府のよびかけを拒否している。しかしながら,中国の政治・社会・経済の動向と発展の度合によっては交渉の余地ありとする柔軟な姿勢も現れてきており,統一への模索は現実のものとなりつつある。いかなる形の合作・合体になるとしても,その実現の暁には台湾政権担当者は〈中華民国〉の名称を放棄することになる。しかし,統一への動きの鍵を握っているのは,台湾政権担当者ではなく,台湾省に住む中国人住民の動向であろう。
執筆者:石田 米子
経済体制
台湾へ逃避した国民党は大陸から台湾へ移動する過程で,莫大な金銀財宝を持ち込んだといわれている。台北市にある故宮博物院はその一つである。党と同時に,上海を中心とした民間資本,主に紡績資本が大量に流れ込んだ。日本の敗戦時に残した諸設備,建物などは国民党が管理下においていた。したがって,台湾における強大な物的基礎と資金を国民党が支配下においたことになる。
国民党のその後の姿を運命づけたのは50年6月に勃発した朝鮮戦争である。それまで国民党と共産党との内戦は中国の国内問題だという政策をとっていたアメリカが一転して台湾を反共防波堤にしたてあげる政策を採用し始めた。軍事的支援を強化するとともに,莫大な経済援助に乗り出し,台湾をアメリカ資本主義の一環として取り込み始めた。台湾がアメリカより取得した援助は,劉進慶の推計によれば,51年の国民所得の11%,60年で8%,65年でも4.4%に達したという。
第2次世界大戦後の世界資本主義は戦前のそれとは性格を変えていた。古い封建的諸要素を払拭し,産業資本の成長を重視するようになった。アメリカ資本主義のこの性格が,大陸時代の国民党の性格を変えるとともに,大陸時代には封建軍閥的要素と金融資本的性格をもっていた官僚資本は産業資本主義へと衣替えしていった。重要な契機として次のものがあげられよう。
(1)土地改革の成功。50年代初め,土地改革を断行し,自作農制の創設に成功した。国民党が大陸で共産党に敗れた最大の原因は,孫文の〈耕者有其田〉の政策を実施できなかったことにある。高率小作料のうえであぐらをかく浪費的地主層を排除することによって,農村の需要が解放され,その後の工業化の市場を準備した。ラジデンスキーを中心としたアメリカの進歩派が果たした役割は大きかった。(2)アメリカの経済援助は化学肥料,電力,紡績資本にてこ入れされ,国家資本の蓄積の産婆役を果たした。これに上海から流入した国際競争力をもっていた民間の紡績資本が結びついた。アメリカの経済援助が大陸時代の国民党官僚資本の性格を変えさせ,政権自体を日本の明治期政府のような企業家にしたてあげた。(3)60年代から外国資本の導入に踏み切り,おもにアメリカと日本の資本が加工区を中心に導入されていった。これらの民間資本は繊維のみならず,50年代に技術的に完成し,成長が最も著しい電機製品が多かった。これは日米の経済圏の中で,海外需要を中心に急速な成長をとげた。
以上のいくつかの要素が複合されて,1962-63年ころから,日本より数年遅れで高度成長に入った。50年代に国民党中華民国政府は封建的な色彩をもつ官僚金融資本主義から産業資本主義的性格の官僚資本主義に転化した。台湾の高度成長は1980年代初期の鈍化はあったものの,日本の1957-58年ころから73年に及ぶ高度成長の記録を破り,1990年前後まで30年近く続いた。90年代に入ると1976年以後続いた恒常的な貿易黒字で1人当りの外貨保有量は世界最大の経済となり,大きな資本輸出国へ転化し,東南アジア・大陸中国に経済的な影響力をもって今日に至っている。
執筆者:小島 麗逸
社会と文化
国民党政府の台湾転出後,台湾は,強力な軍事統制下にありながら,独自の資本主義的民族文化を発展させてきた。その一つの到達点は教育の普及で(以下,統計数字は1982年度のもの),小学校6年,初級中学3年の国民教育(義務教育)はほとんど100%の進学率に達し,高級中学・職業高校への進学率は73.3%,そのうちの8割が大学・専門学校に進んでいる。また,新聞は,朝刊,夕刊,英字紙あわせて30種類あり,1.7世帯に1部の普及状況である。カラーテレビは1.2世帯に1台の割合で普及し,テレビ局は3局あるが,芸能およびドラマ番組には,行政院新聞局によって〈事前審査〉が行われている。ラジオは,国公営局が10局,民営局が19局ある。書籍・雑誌の出版もさかんだが,外国書籍の海賊版がことに多い。
学術・文化に対する奨励は,〈中山学術基金会〉や〈呉三連文芸奨基金会〉などによって行われてきたが,文芸の面でいえば,強力な統制下にあって,〈郷土文学〉と呼ばれる民衆の生活に根ざした独特のリアリズム文学が呉濁流などの手でつくり出された。台湾を代表する文化財としては,大陸からもちだした故宮博物院所蔵の約62万点の重要文化財があり,そのうち8000点は常時展示されている。
→台湾
執筆者:吉田 富夫
日中文化交流
留学と文化事業
中華民国期における日中文化交流は,両国の政治的な関係にとりわけ強く左右された。この時期,日中間の人的な往来はきわめて盛んであった。その中には,中国革命のために国境を越えた交遊と信頼関係を結んだ孫文と宮崎虎蔵(滔天),半生を中国で送った中江丑吉,医学生として日本へ留学中に革命と文学に目覚めた魯迅と,その留学生魯迅を誠実に援助した藤野厳九郎などの人々がいた。しかし,こうした個人の交流も,日本の中国侵略とそれに対抗する中国の抗日ナショナリズムという両国間の関係に押し潰されてしまった。1924年,孫文が彼最後の訪日に際して神戸で行った〈大アジア主義〉と題する講演は,日本に対する批判と絶望に満ちたものであった。
中国人の日本留学は清朝末期に隆盛を極めたが,民国期には全般的に振るわず,37年日中戦争が本格化すると留学生はほとんど帰国,戦前の中国人日本留学史は幕を閉じた。雑誌《新青年》の同人,陳独秀や李大釗(りたいしよう),新文学を主導した魯迅や郭沫若(かくまつじやく)など,日本留学帰国者の多くが抗日ナショナリズムの思想的指導者となった。周恩来のように,在日中に河上肇などの著作・講義を通じてマルクス主義に触れた者も多い。
この間に中国人の留学先の中心は日本からアメリカへ移った。日本留学不振の原因は,従来日本留学者が多かった普通教育の分野で,清末からの改革の結果,中国の学校制度がある程度整備されたこと,二十一ヵ条要求や五・四運動を契機とした反日感情の高まりのほかに,アメリカによる対中国教育文化交流政策の急速な発展があった。すでに20世紀初頭から,中国各地にアメリカン・ミッション系の中・高等学校が次々に創設されていたが,1908年,アメリカ政府は義和団賠償金の一部を中国人のアメリカ留学の基金とすることとした。中国の教育文化面におけるアメリカの影響力の増大に,文化的な巻返しの必要を感じた日本の外務省は,まず東亜同文会の中国における中国人教育施設に助成を与え,23年には,義和団賠償金と山東半島利権の補償金をもとに〈対支文化事業特別会計〉を定めた。これによって外務省に設置された〈対支文化事務局〉は日本最初の政府文化交流機関であり,現在の外務省文化事業部の前身となった。露骨な利権獲得的姿勢を改め,教育文化面からの接近によって感情融和を図るのが得策として始められた,この文化事業には,日中両国の学者らによる協議機関も設けられることになっていたが,日本側の独善的な運営が目だち,中国側の反発を招いた。この事業によって北京人文科学研究所,上海自然科学研究所が設立され,四庫全書が整備され,同仁会の医療活動も続けられた。日本国内でも東方文化学院(京都大学人文科学研究所,東京大学東洋文化研究所の前身)が設立され(1929),また戦前・戦後の日本の中国研究を指導した学者が多数中国に留学した。しかし,日本人関係者の個々には善意の活動があっても,中国側の積極的な協力は得られなかった。日中間の関係が泥沼化した状態では,日本側の文化政策のすべてが中国側によって文化侵略,文化帝国主義と受け取られるのは必然的であり,日本からの文化交流事業によって中国の反日運動が緩和されることはなかったといわなければならない。日中両国が全面衝突の状態に入った37年の翌年には,〈対支文化事業〉は外務省から対華工作機関の興亜院に移管され,外務省文化事業部も42年には〈戦時下不急の事業〉として廃止された。
台湾,満州における文化政策
日清戦争によって日本に割譲された台湾では,日本の植民地支配に対する島民の抵抗が強く,児玉源太郎が総督,後藤新平が民政長官になった1898年に,ようやく軍政から民政に移行した。公学校における島民子弟の日本化教育などを通じて進められる同化政策に対抗する島民の反日運動の一つが,台湾文化協会(1921)という形態をとったことは示唆的である。台湾にとっては大陸中国の文化に同一性を求めることもしだいに難しくなっていったのである。台湾の人びとは,日本が昭和期に進めた皇民化政策に対して根強い抵抗を示しつつも,徐々に日本文化の浸透を許し,また,独自の文学を生み出すにいたったともいわれる。
一方,現在の東北地方である〈満州〉では,日本が日露戦争の結果として得た地位,権益を初代満鉄総裁後藤新平が唱えた〈文装的武備〉という満州経営戦略によって永続させようとする企てがなされた。その一環として,関東州,満鉄付属地内で日本経営の中国人学校教育が進められたが,1923-24年には,中国ナショナリズムの立場を鮮明にする教育権回収運動が起こった。中国ナショナリズムに敵対して,日本が満州事変を起こし,〈満州国〉を建国してからは,〈日満一体〉の体現として〈対満文化事業〉(1932成立)によりさまざまな文化交流事業が実施された。昭和10年代には,満鉄調査部,東亜研究所などの調査機関や大学の研究者による現地調査もさかんに実施されて,日本の当代を対象とする中国研究は世界一ともいえる水準に達したが,日本人が伝統的に抱いていた中国文化崇敬の念はその間にほとんど消失した。
戦前の日中関係では,中国人留学生の来日や文化人の交流のほか,日中貿易,紡績業をはじめとする日本企業の中国進出,台湾植民地経営,満鉄・関東庁による満州経営,満州移民,そして日本軍兵士など,日本人と中国人が直接に接触する機会は,他の時期に見られないほど増大した。しかし,そのすべてが,日中戦争に至る日本側の侵略的な姿勢のために,不幸な交流の場としかなりえなかった。
台湾政権との交流
1945年,日本の敗戦により台湾は,進駐してきた国民政府軍に接収された。そして,49年末には,国共内戦に敗れて大陸を追われた蔣介石が100万の軍隊とともに逃れてきて,台湾は,アメリカの経済・軍事援助を受けて大陸反攻・反共を叫ぶ国民党政権の支配するところとなった。日本政府は51年の吉田=ダレス書簡,52年の日華平和条約調印によって台湾の中華民国政府を中国の正統政府と認める立場を選択した。そのため,戦後の日中文化交流も,72年の日中国交正常化まではかたよった交流にならざるをえなかった。すなわち,台湾との間には政府間交流が行われ,中国大陸との交流は民間交流に委ねられ,不幸な分裂としこりが生まれた。この間にも,台湾から私費留学生や学者,研究者が多数日本を訪れた。台湾と日本との文化交流は彼らの真摯な努力によってのみ担われてきたといっても過言ではない。日中国交正常化によって日台間の外交関係が消滅し,領事業務が〈交流協会〉によって担当されるようになった今日でも,その事情は変わっていない。
→中国
執筆者:平野 健一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「中華民国」の意味・わかりやすい解説
中華民国【ちゅうかみんこく】
→関連項目蒋介石|清|青天白日旗|中国国民党
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「中華民国」の解説
中華民国(ちゅうかみんこく)
1912年に建国されたアジア初の共和国。12年から28年にかけては北京政府がこれを代表したが,軍閥同士の戦争があいつぎ,国内は分裂状態にあった。28年以降は北伐を完成させ,国家統一を実現した中華民国国民政府が中華民国を代表した。しかし南京政府指導者である蒋介石(しょうかいせき)の独裁に批判が高まり,反蒋戦争が続発した。蒋は中国国民党による一党独裁体制のもとで国家建設を推進したため,国民党内部と中国共産党などからの強い反発を受け続けた。37年の日中戦争勃発後は重慶に撤退し,連合国の一員として日本に抗戦した。日中戦争中は日本との和平を求めた汪兆銘(おうちょうめい)が,南京で一時中華民国国民政府を名乗る傀儡(かいらい)政権を打ち立てた。重慶国民政府が日中戦争に勝利したのち,中国共産党との対立が深まり,内戦が勃発した。国共内戦に敗北した中華民国政府は,49年12月に台湾に撤退した。中国大陸では,49年10月中華人民共和国が成立し,中華民国の存在は否定されたが,冷戦体制のもと,アメリカなど主要国との外交承認は継続した。71年の国際連合脱退後は承認国が激減し,国際政治上孤立した。88年に成立した李登輝(りとうき)政権以降は,中華民国の名義で台湾の国連復帰運動を展開するなど,自己主張を強めている。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「中華民国」の解説
中華民国
ちゅうかみんこく
1912年1月,孫文を臨時大総統,南京を首都に樹立された。しかし,清朝を打倒する力がなく,2月袁世凱が清朝を滅亡させると,密約にしたがって袁世凱が臨時大総統に就任。袁世凱は北京に遷都したのち列国と結び,独裁体制を強化して革命派を弾圧,1915年末帝政復活を宣言するが,内外の反対で断念した。翌年,袁世凱が没すると,以後1928年まで軍閥による割拠時代となった。孫文は,1919年五・四運動の影響を受けて中国国民党を結成し,24年に同党を改組して第1次国共合作を行い,広東軍政府を樹立。1925年の孫文死後,指導権を握った蔣介石によって,26年から北伐が開始された。しかし北伐途上の1927年4月,蔣介石の上海クーデタで国共分裂となった。蔣介石は,列国や浙江財閥の支持のもとに南京国民政府を樹立。翌1928年北伐を再開して張作霖を北京から追放,張が日本軍によって爆殺されたのち後を継いだ張学良の支持をとりつけ,中国統一を完成。1931年日本が満州事変をひき起こして中国侵略を本格化したが,国民政府は共産党に対する内戦を激化。同年,共産党は瑞金に毛沢東を主席とする中華ソヴィエト共和国を樹立したが,国民政府の圧迫を受け,1934年から長征を開始。1935年国民政府は幣制改革を行い,政府系3銀行の銀行券(紙幣)だけを法幣とし,経済面でも独裁を強化した。蔣介石は,共産党側からの抗日統一戦線結成の呼びかけを拒否していたが,1936年の西安事件によってそれを受け入れた。1937年7月の盧溝橋事件によって日中戦争が全面化すると,第2次国共合作が成立して抗日民族統一戦線が結成された。戦争拡大に伴い,国民政府は首都を南京から武漢・重慶に移して抗日戦を継続し,第二次世界大戦中の1943年,米・英との不平等条約撤廃に成功。大戦終了後,1945年10月に国民党は共産党と双十協定を結んだが,11月から国共内戦を再開。1948年蔣介石が中華民国初代総統に就任したが,内戦に敗れて,49年5月中華民国政府は台湾に逃れた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中華民国」の意味・わかりやすい解説
中華民国
ちゅうかみんこく
Zhong-hua min-guo; Chung-hua min-kuo
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「中華民国」の意味・わかりやすい解説
中華民国
ちゅうかみんこく
1912年1月から1949年9月末まで続いた中国の国号。また、共産党との内戦に敗れ台湾に逃避した国民政府は、継続してこの国号を用いている。
[編集部]
山川 日本史小辞典 改訂新版 「中華民国」の解説
中華民国
ちゅうかみんこく
辛亥(しんがい)革命後の1912年から49年まで中国大陸に存在した国名。民国の歴史は,北洋軍閥支配時代と国民党時代に区分できる。北伐軍は国共合作などにより,28年末までにほぼ全国を統一。主席・陸海空軍総司令に就任した蒋介石(しょうかいせき)は31年5月に国民党による一党独裁制を定めた。数度の危機にみまわれたが,蒋の国民政府は道路建設,ドイツ人軍事顧問による軍の近代化,幣制改革・関税改革・紡績業育成に成功した。しかしこの蓄積は日中戦争によって壊滅的な打撃をうけた。第2次大戦後,中国共産党は蒋政権との内戦に勝利,49年中華人民共和国を樹立。蒋らは台湾に拠り,ひき続き中華民国を称した。日本とは1972年の中華人民共和国との国交正常化により,国交は断絶したが,民間レベルでは交流がある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「中華民国」の解説
中華民国
ちゅうかみんこく
初め軍閥の対立抗争が続いたが,1928年いちおう蔣介石が北伐に成功して国民政府による統一を達成。第二次世界大戦後,蔣政権は中国共産党との内戦に敗れ,大陸には中華人民共和国が成立したため,以後台湾に拠り,ひき続き中華民国を称している。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...