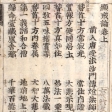精選版 日本国語大辞典 「最澄」の意味・読み・例文・類語
さいちょう【最澄】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「最澄」の意味・わかりやすい解説
最澄
さいちょう
(766/767―822)
日本天台宗の開祖。伝教大師(でんぎょうだいし)と諡号(しごう)され、澄上人(ちょうしょうにん)、叡山(えいざん)大師、根本(こんぽん)大師、山家(さんげ)大師とも称される。
中国後漢(ごかん)の王族で応神(おうじん)帝ころの帰化人の子孫と伝える三津首百枝(みつのおびとももえ)(一説に巨枝=浄足(きょし))の子として比叡山麓(ひえいさんろく)古市(ふるいち)郷(大津市坂本本町)に生まれ、幼名を広野という。780年(宝亀11)近江(おうみ)(滋賀県)国分寺の行表(ぎょうひょう)を師として出家、「心を一乗に帰すべし」との教えを受ける。785年(延暦4)東大寺戒壇(かいだん)で具足戒(ぐそくかい)を受け前途有望の国家公認の僧となったが、ほどなく南都の仏教を避けて比叡山に登り修行、多くの経論を読んで天台教学の優れたことを知り、天台典籍を求めて学んだ。入山後の最澄は、世の無常を見つめ自己の未熟を恥じ、仏道修行を実現するための五つの誓願をたて(『願文(がんもん)』)、それが成就するまで下山しないと誓った。これはのちに僧の修行の規則「十二年籠山(ろうざん)」として制度化され現在に至っている。この間、比叡山に一乗止観院(いちじょうしかんいん)(根本中堂の前身)を創建し、等身の薬師如来(やくしにょらい)像を刻み、「阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼじ)の仏(ほとけ)たち、我(わ)が立つ杣(そま)に冥加(めか)あらせ給(たま)え」と詠じたと伝える。またこの堂に献じた法燈(ほうとう)を「明らけくのちの仏のみ世までも、光りつたえよ法(のり)のともしび」とし、現在まで不滅の法燈をともす。797年内供奉(ないぐぶ)十禅師に加えられ、翌798年11月には天台智者大師の忌日法華(ほっけ)十講(現在の霜月会(しもつきえ))を始修した。802年和気清麻呂(わけのきよまろ)の子広世(ひろよ)・真綱(まつな)(783―846)に招かれて初めて山を下り、京都高雄山寺(たかおさんじ)(神護寺)において『摩訶止観(まかしかん)』『法華玄義(ほっけげんぎ)』『法華文句(もんぐ)』の法華三大部の講義を行い、南都の諸大徳も列席しその講を称賛したという。
[塩入良道 2017年7月19日]
入唐と天台宗の開宗
802年9月、先に上奏した入唐求法(にっとうぐほう)の請願に対し、入唐請益(じょうやく)天台法華(ほっけ)宗還学生(げんがくしょう)の勅許が下り、804年7月に訳語僧義真(ぎしん)を伴い肥前(長崎県)田浦(たのうら)から出帆した。ちなみに、この遣唐使節団には空海も同行していたが、福州に着くと互いに交渉のないまま別れ、最澄一行は9月1日明州に着いた。9月26日台州に至った最澄は、天台山修禅寺(しゅぜんじ)で行満(ぎょうまん)座主(?―824)から、台州竜興寺で道邃(どうずい)和尚(生没年不詳)から天台教義を学び、また道邃から大乗菩薩戒(ぼさつかい)を授かった。さらに禅林寺翛然(しゅくねん)禅師(生没年不詳)から牛頭(ごず)の禅法、越州竜興寺順暁阿闍梨(じゅんぎょうあじゃり)(生没年不詳)からは密教を授かり、わずか8か月余の間に天台山での120部345巻(『台州録』)、越州での密教典籍102部115巻(『越州録』)を請来(しょうらい)して、805年6月対馬(つしま)に帰着した。帰朝後、同年9月に高雄山寺で日本で初めての灌頂(かんじょう)を実施した。また南都六宗に加えて天台法華宗にも正式の僧の割り当て(年分度者(ねんぶんどしゃ))2人を請願し、806年1月26日勅許が下った。いわば国家的な公認を受けたこととなり、この日を日本天台宗の開宗とする。
[塩入良道 2017年7月19日]
徳一との論争
814年(弘仁5)、入唐出発にあたり渡海祈願した筑紫(つくし)(福岡県)、豊前(ぶぜん)(大分県)の神々に謝恩の旅をし、翌815年は上野(こうずけ)(群馬県)、下野(しもつけ)(栃木県)に巡化して鎮護国家のため『法華経』1000部を納める宝塔を建立した。この日本国安鎮の願は、全国に六所の宝塔をつくることを発願した『六所宝塔願文(ろくしょほうとうがんもん)』(818)となった。また美濃(みの)(岐阜県)から信濃(しなの)(長野県)への難所神坂(かみさか)峠の登り口にそれぞれ広済(こうさい)・広拯(こうじょう)2院を建て旅人の便を図った。このころ会津(あいづ)(福島県)にいた法相宗(ほっそうしゅう)の徳一(とくいつ)が天台教義を批判して『仏性鈔(ぶっしょうしょう)』を著したのに対し、817年『照権実鏡(しょうごんじっきょう)』をもって反論し、続いて徳一の反駁(はんばく)書『中辺義鏡(ちゅうへんぎきょう)』『恵日羽足(えにちうそく)』『遮異見章(しゃいけんしょう)』などに対し、『法華去惑(こわく)』『通六九証破比量文(つうろくきゅうしょうはひりょうもん)』『守護国界章(しゅごこっかいしょう)』などを著して再反駁した。これは法相宗の三乗思想と天台宗の一乗思想の論争で、世に「三一権実論争」といわれる。最澄が亡くなるまで論義が交わされたが、『法華秀句(しゅうく)』は入滅前年の権実論争の決着であった。
[塩入良道 2017年7月19日]
大乗戒壇の独立
徳一との論争や『依憑(えひょう)天台義集』(813)などにより南都仏教とくに法相宗との対立が生じ、先に認可された年分度者も、807年(大同2)から10年間は24人中4人は法相宗に争奪され、住山僧10人という状況となった。また当時の年分度者南都10人、天台宗2人は、いずれも官から任命された僧綱(そうごう)の管下で、奈良東大寺、下野(しもつけ)(栃木県)薬師寺(やくしじ)、筑紫(つくし)(福岡県)観世音寺(かんぜおんじ)の戒壇で、インド以来の二百五十戒を受ける定めであった。最澄はこれを小乗戒とし、教法が大乗仏教であるから戒も大乗戒でなければならぬと主張した。818年に菩薩出家を請う表と、天台宗の年分度者の止観業(しかんごう)(天台仏教)と遮那業(しゃなごう)(密教)の教育制度を内容とする『天台法華宗年分学生式(がくしょうしき)』(六条式)、『勧奨(かんしょう)天台宗年分学生式』(八条式)を上奏し、翌819年は大乗戒の独立を願う『天台法華宗年分度者回小向大式(えしょうこうだいしき)』(四条式)を上表した。この三式を総称して『山家(さんげ)学生式』とよぶ。最澄はこの書において年分度者を菩薩僧として育成することを目的とした。
しかし、護命僧都(ごみょうそうず)ら南都仏教の強い反対にあい、この反論として四条式の根拠と大乗戒の正統性を論じた『顕戒論(けんかいろん)』『顕戒論縁起』や、天台宗の円戒禅密(えんかいぜんみつ)の伝承『内証仏法相承血脈譜(ないしょうぶっぽうそうしょうけちみゃくふ)』を奉ったが、生存中にはついに実現せず、弘仁(こうにん)13年6月4日、「わがために仏をつくることなかれ、わがために経を写すことなかれ、わが志を述べよ」と遺言して比叡山の中道院で入滅。その7日後に藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)、良岑安世(よしみねのやすよ)の斡旋(あっせん)で大乗戒壇建立の勅許が下り、翌823年義真によって日本で初めて正式の大乗戒の受戒が行われ、延暦寺(えんりゃくじ)の寺号を賜った。さらに866年(貞観8)清和(せいわ)天皇から伝教大師の諡号が贈られたが、これが日本の諡号の最初である。
[塩入良道 2017年7月19日]
『天台宗宗典刊行会編『伝教大師全集』5巻(再刊・1968・中山書房)』▽『安藤俊雄・薗田香融校注『日本思想大系4 最澄』(1974・岩波書店)』▽『塩入亮忠著『伝教大師』(1929・日本評論社)』▽『勝野隆信著『比叡山と高野山』(1959・至文堂)』▽『壬生台舜著『叡山の新風』(1967・筑摩書房)』▽『木内央著『伝教大師の生涯と思想』(第三文明社・レグルス文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「最澄」の意味・わかりやすい解説
最澄 (さいちょう)
生没年:767-822(神護景雲1-弘仁13)
平安初期の僧。日本天台宗の開祖。俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。近江国(滋賀県)滋賀郡古市郷の生れ。12歳のとき近江国分寺に入り,国師の行表(ぎようひよう)の弟子となり,14歳のとき国分寺僧の補欠として得度し名を最澄と改めた。785年(延暦4)19歳のとき東大寺の戒壇で具足戒(小乗戒)を受けたが,この年7月,世間の無常を感じ,突如として比叡山に登って草庵をかまえ,山林修行の生活に入った。このとき作った〈願文〉には,峻厳な自己内省と,衆生救済への志向とがうかがわれる。比叡山での修行中,多くの経典類を読破したが,なかでも天台の典籍を披閲したことが契機となり,最澄の運命を決定づけた。天台宗は隋の智顗(ちぎ)が大成した教学で,唐の初めに一時衰えたものを湛然(たんねん)が挽回し,江南地方を中心に復興の気運をむかえ,おなじく江南で布教していた鑑真(がんじん)によって天台の典籍が日本にもたらされたのである。すべての人の成仏を理論的に説き明かす天台の教学に魅せられた最澄は,ながく山にこもってきびしい禅行とたゆまない学行をつづけ,その名がようやく都の人士に知られるようになった。
797年内供奉(ないぐぶ)十禅師に任ぜられ,802年和気広世の主催する高雄山寺(神護寺)法華会(ほつけえ)の講師に招かれた。斬新な講義の評判が天皇の耳にも達し,それが機縁で入唐求法(につとうぐほう)の還学生(げんがくしよう)(短期留学)に選ばれた。最澄は門弟の義真を通訳に連れ,804年7月,空海とおなじく遣唐使の船に乗って九州を出発し,9月明州に到着した。まず天台山に登り,ついで湛然の高弟である道邃(どうすい)/(どうずい)と行満(ぎようまん)について正統な天台教学の奥義をさずかった。また道邃からは大乗の菩薩戒を受け,翛然(しゆくねん)から禅を,順暁(じゆんぎよう)から密教をそれぞれ相承している。翌805年5月,遣唐使とともに帰国の途につき,7月上京した。在唐わずか8ヵ月にすぎないが,滞在中に書写し持ちかえった経典類は230部460巻をかぞえ,収穫は大きかった。最澄が帰国した当時,桓武天皇は病床にあって,すぐさま宮中に召され,天皇の病気平癒を祈っている。
806年(大同1)1月,最澄の上表にもとづき,南都六宗に準じて,天台業を学ぶもの2人(止観(しかん)業1人,遮那(しやな)業1人)の得度が年分度者のなかに加えられた。ここに日本の天台宗が開立されたのである。この勅許は,和気広世の斡旋にあずかるところが大きいと思われるが,しかし最澄が天皇の病床に侍した功に対する恩賞の色あいが濃く,真の教団の成立は大乗戒壇の設立にまたねばならない。この年3月に桓武天皇が崩御すると,最大の外護(げご)者を失った最澄とその新生の教団はやや沈滞期に入った。空海との親密な交わりが結ばれたのはこのころである。空海は,最澄よりも長く滞留して真言密教の研修につとめ,806年帰朝した。最澄は,7歳年下の空海に辞を低くして,空海が持ちかえった多量の経典のうち,真言,悉曇(しつたん)(梵字),華厳(けごん)に関するものを借りうけ,あるいは書写して研究した。812年(弘仁3)の冬,弟子の泰範,円澄,光定(こうじよう)らを率いて高雄山寺におもむき,空海より灌頂(かんぢよう)を受けている。ところが,813年最澄が弟子を空海のもとに遣わし,真言に関する書籍を借りようとしたところ,空海は,最澄と自分との間に教学的な立場上こえることのできない溝のあることを述べ,最澄の懇請をきっぱりと拒絶し,二人の交情は急速に悪化し始めた。ことに最澄が最も嘱望していた愛弟子の泰範が空海のもとへ走るに及び,空海を尊敬しながらも決別しなければならなかった。
815年最澄は和気氏の要請で大安寺において講説し,南都の学僧と激しく論争したが,それより東国へ旅立った。途中の美濃・信濃の国境に布施屋(ふせや)を置いて旅人に宿泊の便宜を与えている。関東では最澄にゆかりの深い鑑真の高弟道忠(どうちゆう)の遺弟(ゆいてい)らがいる上野の緑野(みとの)寺(浄土院)や下野の小野寺(大慈院)を拠点に伝道を展開した。会津にいた法相(ほつそう)宗の学僧徳一(とくいち)との間に,三一権実(さんいちごんじつ)の論争が始まったのは,この関東滞在中のことである。徳一が《仏性抄(ぶつしようしよう)》を著して最澄を論難したのに対し,最澄は《照権実鏡(しようごんじつきよう)》を書いて反駁した。論争は最澄が比叡山へもどった後も続き,《法華去惑(こわく)》《守護国界章》《決権実論》《法華秀句》などを著述し,徳一の主張をことごとく論破している。最澄は自己の教学の優越性に自信を深め,そして究極の目的とする大乗戒壇の設立に邁進した。かつて19歳のとき東大寺で受けた小乗戒は,まったく形式主義に堕し,国家鎮護・衆生済度の大任を果たしえないとして,818年みずから破棄を宣言し,ついで《山家学生(さんげがくしよう)式》を定め,天台宗の年分度者は比叡山において大乗戒を受けて菩薩僧となり,12年間山中で修行することを義務づけた。これに対して南都の僧綱は猛然と反論した。最澄の主張は,僧侶を養成する権限を国家やその隷属下にある南都(東大寺)の戒壇より独立して,天台宗教団の自主管理に置こうとするところに主眼点があった。最澄は南都側の反論にこたえ,《顕戒論》を執筆し,《内証仏法血脈譜(けちみやくふ)》を書いて,自己の見解の正統性を説いている。だが最澄の念願はその生存中には実現せず,822年6月4日,比叡山の中道院で没した。宿願の大乗戒壇設立は,弟子の光定の奔走と,藤原冬嗣(ふゆつぐ),良岑(よしみね)安世の斡旋で,没後7日目に勅許された。ここに天台宗が名実ともに成立したのである。なお866年(貞観8)に伝教大師(でんぎようだいし)と諡号(しごう)された。
→天台宗
執筆者:中井 真孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「最澄」の意味・わかりやすい解説
最澄【さいちょう】
→関連項目安然|一乗|延暦寺|笠森寺|弘仁・貞観時代|三昧堂|台密|天台座主記|東塔|風信帖|仏教|法印|法界寺|梵網経|曼殊院
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「最澄」の解説
最澄
さいちょう
767~822.6.4
伝教大師・叡山大師とも。平安前期の天台宗開祖。近江国滋賀郡古市郷の三津首百枝(みつのおびとももえ)の子。近江国分寺行表(ぎょうひょう)のもとで出家,東大寺で受戒,比叡山で修行。この間に天台教学に傾倒し,802年(延暦21)南都学匠に同教学を講じて入唐還学生(げんがくしょう)に選ばれ,804年入唐。天台山で道䆳(どうすい)・行満(ぎょうまん)に天台法門と菩薩戒を,㑣然(ゆうぜん)に禅を,越州で順暁(じゅんぎょう)に金剛界密教をうけて翌年帰朝。桓武天皇の命で高雄山寺で灌頂(かんじょう)を行う。806年(大同元)南都諸宗に準じて天台宗の年分度者(ねんぶんどしゃ)創設を請い,勅許を得た。ついで空海から密教を受学したが,宗教観の相違などで816年(弘仁7)決別。この頃から天台宗年分度者離散の事態をうけて教団の基盤確立に奔走した。南都教学と対決姿勢を強めるとともに,筑紫・関東で教化を行った。会津の法相宗徳一(とくいつ)と三一権実諍論(さんいちごんじつのそうろん)を展開した。818年,旧来の小乗戒棄捨を宣言。さらに「山家学生式(さんげがくしょうしき)」を奏進して天台宗独自の大乗戒壇や行業の勅許を求めたが,南都の反対をうけ,比叡山中道院に没した7日後に勅許された。著述は叡山学院編「伝教大師全集」。「日本思想大系」に「顕戒論」「山家学生式」などを所収。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「最澄」の意味・わかりやすい解説
最澄
さいちょう
[没]弘仁13(822).6.4. 比叡山
日本天台宗の開祖。三津首百枝 (みつのおびとももえ) の子。幼名は広野。 12歳で出家,14歳で得度,法名を最澄とした。 19歳のとき比叡山に登り,草庵を構え思索の生活に入る。延暦 21 (802) 年,桓武天皇から入唐の勅命を受け,同 23年入唐,天台山で行満から天台の教えを受け,また禅法,大乗菩薩の戒法,密教を学び同 24年帰国。密教を伝えるために高雄山寺に灌頂壇を設け,翌年天台宗としての年分度者を許された。弘仁 10 (819) 年比叡山に大乗戒壇建立を奏上したが,南都六宗の反対で許されず,同 13年寂。死後7日目に建立の勅許を得た。貞観8 (866) 年伝教大師の諡号を贈られた。日本最初の大師号である。主著『守護国界章』 (818) ,『山家学生式』 (818~819) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「最澄」の解説
最澄 さいちょう
神護景雲(じんごけいうん)元年8月18日生まれ。近江(おうみ)(滋賀県)の国分寺で行表(ぎょうひょう)に師事。19歳のときから12年間比叡(ひえい)山で修行。桓武(かんむ)天皇の信任を得,延暦(えんりゃく)23年空海(くうかい)らと唐(とう)(中国)にわたり,天台・密教・禅・戒をまなぶ。25年日本天台宗をひらく。晩年徳一との教理論争をおこなう一方,大乗戒壇の設立につくした。弘仁(こうにん)13年6月4日死去。56歳。近江出身。俗名は三津広野(みつの-ひろの)。通称は叡山大師,根本大師。諡号(しごう)は伝教大師。著作に「山家学生式(さんげがくしょうしき)」「顕戒論」「守護国界章」など。
【格言など】一隅を照らすもの此れ即ち国宝なり(「山家学生式」)
旺文社日本史事典 三訂版 「最澄」の解説
最澄
さいちょう
平安初期の高僧。天台宗の開祖
諡号 (しごう) は伝教大師。近江(滋賀県)の人。12歳で出家し,785年比叡山にこもり修行。桓武天皇の信任を得,入唐して天台宗を学んだ。帰国後806年に天台宗を開宗。比叡山に延暦寺をつくり,弟子の養成にあたった。晩年,一乗思想を唱えて法相宗の徳一法師と論争し,比叡山に大乗戒壇をつくろうとして僧綱 (そうごう) と対立。死後7日目に大乗戒壇設立が許可された。著書に『顕戒論』『山家学生式』など。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「最澄」の解説
最澄 (さいちょう)
奈良時代;平安時代前期の僧
822年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の最澄の言及
【延暦寺】より
…平安京の北東方,鬼門に当たることから,王城の鎮護とされた。延暦寺は788年(延暦7),最澄によって開創された。東大寺で受戒した最澄は785年世の無常を感じて比叡山に登り草庵生活に入った。…
【灌頂】より
…これによって人の師たるに堪(た)える位(阿闍梨(あじやり)位)を得るために,阿闍梨(位)灌頂ともいう。 灌頂は日本では最澄が805年(延暦24)に高雄山寺で行ったのが最初とされる。その後,正統な密教を伝え,最澄に遅れて帰国した空海は,812年(弘仁3)に同じ高雄山寺で灌頂を行ったが(11月に金剛界,次いで12月には胎蔵界),それには最澄も含め166名が参加し,受法したと伝えられる。…
【顕戒論】より
…天台宗の開祖最澄の著書,3巻。最澄は819年(弘仁10)かねてより念願の〈菩薩僧〉の養成をめざし〈天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)〉を制定,比叡山に大乗戒壇設立を朝廷に申請した。…
【書】より
…橘逸勢は真跡として確実なものは伝わらない。空海と同時に入唐した最澄はやはり王羲之調ではあるが,爽快な運筆の名筆で空海と対照的である。 空海より約半世紀後の円珍の書状を見ると,細い墨線の筆触に柔らか味を増して,和様化が急激に進んだ書風である。…
【請来目録】より
…唐から日本へ請来した典籍,物品の目録であるが,特に平安時代初期に入唐した僧侶8人の目録をさして〈入唐八家請来目録〉という。最澄(804‐805年在唐)には入唐中に作成した〈台州録〉と〈越州録〉がある。あわせて230部460巻の経典と道具が記載され,このうち〈越州録〉は原本が伝えられ,巻尾には明州刺史鄭審則の証明がある。…
【拓本】より
…これに対して全拓本を整拓という。 日本の入唐僧も拓本を持ち帰ったのであって,最澄のごときは《法門道具等目録》の中にとくに書法目録の項を設け,大唐石摺13点をあげているが,今日ではまったく残っていない。中国においても確実な唐拓はいくらも存在していないのである。…
【天台宗】より
…すでに5世紀の初め,クマーラジーバ(鳩摩羅什)が漢訳した《法華経》に基づき,智顗が著した注釈書の《法華玄義》と《法華文句》および《摩訶止観》の3部を根本聖典とする。9世紀の初めに,伝教大師最澄が入唐し,智顗より7代目の道邃と行満について宗旨をうけ,比叡山に延暦寺を創して日本天台をひらくが,最澄は,天台法華宗のみならず,達麿系の禅,円頓戒,密教という,同時代の中国仏教をあわせて,奈良仏教に対抗する新仏教運動の根拠としたため,日本天台は中国のそれとかなりちがったものとなる。とくに密教を重視する後継者によって,智証大師円珍を祖とする園城寺が独立し,天台密教の特色を発揮する一方,鎌倉時代になると浄土宗,禅宗,日蓮宗など,新仏教の独立をみるのは,いずれも日本天台の特色である。…
【法華経】より
…奈良時代には,国分尼寺が各国に建立され法華滅罪の寺と称し,《法華経》は国家的信仰としての位置を獲得した。最澄は《法華経》を所依の経典として天台宗を開創したが,やがて密教,浄土教を受容して多彩な信仰を生むようになった。貴族社会に天台宗の信仰が浸透すると,《法華経》の写経をはじめ法華曼荼羅,釈迦説相図などが描かれ,法華経美術が開花した。…
【密教】より
… 日本には,密教はすでに7世紀後半に断片的な形で伝えられていた。けれども初めて体系的なインド中期密教をもたらし,それを日本的に再構成したのは,天台宗の開祖伝教大師最澄と真言宗の開祖弘法大師空海であった。最澄と空海は,804年(延暦23)共に入唐し,最澄は,天台,戒,禅を主として学び,あわせて順暁から密教の付法を,大素らから雑密法を受け,一方空海は,恵果から両部の密教を皆伝された。…
【密教美術】より
…したがって日本は,アジアにおいて空白となっている初・中期密教美術の宝庫であり,アジア的視野に立って密教美術を考える場合,日本に残る密教美術の重要性はきわめて高いといえる。
【日本】
[雑密の時代]
最澄,空海によって,平安初期に密教(純密)が請来されたが,それ以前の白鳳・奈良時代に,すでに雑密が浸透していた。大化改新後に安宅法や仁王会が行われたことが文献に現れ,奈良時代には《金光明経》《仁王経》をはじめ《金光明最勝王経》《華厳経》《梵網経》が尊重され,鎮護国家,現世利益に重点をおく雑密的傾向が強まる中で,金銀泥の装飾経も作られるようになる。…
【留学】より
…学問僧のなかには,733年(天平5)に入唐した栄叡(ようえい),普照(ふしよう)らのように鑑真の来日に尽力したものもあった。 平安時代になると,804年(延暦23)の遣唐使に最澄と空海が随行し,彼らの学んできた天台や密教は,日本的な仏教が生まれてくる母体となった。このころから留学期間も一般に短くなり,最澄,空海も遣唐使とともに帰国している。…
※「最澄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...