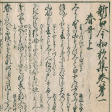精選版 日本国語大辞典 「新古今和歌集」の意味・読み・例文・類語
しんこきんわかしゅうシンコキンワカシフ【新古今和歌集】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「新古今和歌集」の意味・わかりやすい解説
新古今和歌集
しんこきんわかしゅう
第8番目の勅撰(ちょくせん)和歌集。20巻。鎌倉初期の成立。後鳥羽院(ごとばいん)の下命によって撰進された。撰者は源通具(みちとも)、藤原有家(ありいえ)、藤原定家(ていか)、藤原家隆(いえたか)、藤原雅経(まさつね)、寂蓮(じゃくれん)。在来の勅撰集と異なり、院自ら撰集作業に参加され、序、詞書(ことばがき)も院の立場において記され、「親撰体」の集の最初の集となる。
[後藤重郎]
成立
勅撰二十一代集中もっとも複雑長期の成立過程を有し、通常4期に分かち考えられる。
(1)第1期選歌時代 1201年(建仁1)7月『後撰集』の例に倣って和歌所(わかどころ)が置かれて寄人(よりゅうど)が任命され、同年11月3日寄人中6名が撰者に任命され撰集下命があり、以後選歌に従事、1203年4月20日ごろ撰者らが選歌を上進するまで。寂蓮は中途にて寂し上進せず。
(2)第2期御点時代 撰者たちの上進歌に対し、院が三度まで御点を付し精選せられた時期。
(3)第3期部類時代 1204年(元久1)7月、部類(各部への配当・各部における配列作業)下命、作業が始められ、翌1205年3月26日竟宴(きょうえん)(撰集作業が終わった「竟」のあと開かれる宴)が行われるまで。
(4)第4期切継(きりつぎ)時代 都と隠岐(おき)とに分けて考えられる。都のそれは、竟宴後、切継(切出(きりだし)、切入、継直(つぎなおし))が行われ、承久(じょうきゅう)の乱(1221)の計画の進展に伴い、切継に終止符が打たれ、1216年(建保4)12月26日、和歌所開闔(かいこう)源家長(いえなが)が書写を行った時期まで。隠岐のそれは、在島19年に及ぶ晩年、院の心がふたたび『新古今集』に向かい、約400首の歌を切り出された時期(このおりは切出のみにて都のそれとは性格が異なる)。
このように実に三十数年にわたる長期の撰集の歴史を有するのである。
それに伴い伝本も4類に分かれ成立をみている。
(1)第1類竟宴本 竟宴のおりの本。現存本文とはその後の切継により相当異なった内容であった。
(2)第2類切継時代諸本 現存諸本はほとんどが切継時代の本文を書写した系統に属し、1209年(承元3)ごろだいたい現存本文の形に定まったと考えられているが、切継の諸段階で書写された関係で、切継歌をめぐり相違がみられる。
(3)第3類家長本 都における切継に終止符を打たれた最終段階の本文として、1216年12月26日、源家長により書写された本。切出歌を1首も含まず、家長による真名(まな)、仮名の識語を有する。
(4)第4類隠岐本 隠岐にて約400首切り出された本で、新たに隠岐抄序が付される。
なお『新古今集』は、二十一代集中、複数の撰者による撰集中、どの撰者がどの歌を選んだかを示すいわゆる撰者名注記を有する本があり、撰者名の符号の種類、位置、撰者の名を全部有するか否かなどにつき相違がみられるが、注記のない歌は選歌上進後、院(または藤原良経(よしつね))による切入歌と考えられている。
[後藤重郎]
内容
歌数約2000首。仮名序藤原良経作、真名序藤原親経(ちかつね)作(ただしいずれも後鳥羽院の立場で執筆)。春、夏、秋、冬、賀、哀傷、離別、羇旅(きりょ)、恋1~5、雑(ぞう)上中下、神祇(じんぎ)、釈教の部立(ぶだて)よりなる。八代集中、秋歌が春歌に対して著しく多いのも特色であり、また『千載集(せんざいしゅう)』以後『新続(しんしょく)古今集』を除き、神祇、釈教両部は先後の別こそあれ連続して配されているが、最後の巻20が釈教部となるのは『新古今集』のみであり、後の承久(じょうきゅう)の悲運もこの配列のゆえとまでいわれた。作者は、拾遺群歌人と千載群歌人とに大別され(風巻(かざまき)景次郎による)、歌群の交替と歌人群の交替との巧みな組合せ、各歌群内における配列美により、一首一首の美とともに配列の美による歌境が展開される。作者としては、数のうえからは、撰集時代もしくはやや前の時代の歌人が重んぜられており、西行(さいぎょう)94、慈円92、良経79、俊成(しゅんぜい)72、式子(しょくし)内親王49、定家46、家隆43、寂蓮35、後鳥羽院33、俊成卿女(しゅんぜいきょうのむすめ)29、雅経22、有家19、通具17等がみられ、古い時代の歌人では、貫之(つらゆき)32、和泉式部(いずみしきぶ)25、人麻呂(ひとまろ)23等がみられる。
[後藤重郎]
歌風
万葉・古今・新古今の三大歌風と称せられ、「風通ふ寝覚の袖(そで)の花の香にかをる枕(まくら)の春の夜の夢」(俊成女)、「春の夜の夢の浮橋とだえして峯(みね)に別るる横雲の空」(定家)などにみられる、余情妖艶(ようえん)の歌風が顕著であり、修辞の面では、体言止(第五句が体言で終わり、述部がそれより前にある「倒置法」と、述部が省略されており、補って考える「省略法」とがある)、奇数句切(初句切、三句切、初句切・三句切を通常いうが、連歌との関係で三句切がとくに注目される)、本歌取(古歌の心・言葉を用いて新しい歌を詠むこと)、懸詞(かけことば)、縁語等の技法を縦横に駆使し、新古今歌風による美的世界を現出している。『古今集』が漢文学全盛の時代の後を受け、勅撰六国史(りっこくし)が宇多(うだ)天皇の前の光孝(こうこう)天皇をもって終わり、遣唐使派遣が菅原道真(すがわらのみちざね)の建言をもって廃され、辛酉(しんゆう)革命の年のゆえをもって延喜(えんぎ)と改元されるなど、宇多・醍醐(だいご)朝の新しい時代への転換期を背景に、初めての勅撰集として華々しく登場したのに対し、『新古今集』は院政という律令制(りつりょうせい)外の政治形態の下、新興勢力の武士の台頭の前にはもはや昔日の栄華は望みえず、さりとて承久の悲運はいまだ経験せず、その名の示すごとく、『古今集』とその時代の復活を夢みての撰集であった。したがって、同じく時代の転換期にありながら、懐古、復古の基盤のうえに、実よりも花にすぎたる美としての新古今歌風となったものであった。しかし一面、後鳥羽院と連歌(れんが)との関係から、中世歌人のみならず連歌師からも共感賛美の念を寄せられ、和歌の面において『古今集』への回帰が志されるときは、つねにいったんは『新古今集』を媒介として『古今集』への復帰が志向され、連歌の面においては、連歌師による注釈書の出現となり、それぞれに大きな意味をもった。近世では万葉主義、古今主義、新古今主義と三大和歌思潮の一つを形成し、近代においてもその及ぼした影響は萩原朔太郎(はぎわらさくたろう)・塚本邦雄(くにお)らと、事新しく述べるまでもなく、後世への影響も非常に大きなものがある。
[後藤重郎]
『西下経一・実方清編『増補国語国文学研究史大成7 古今集新古今集』(1976・三省堂)』▽『久保田淳著『新古今和歌集全評釈』全9巻(1976~1977・講談社)』▽『上条彰次・片山享・佐藤恒雄著『新古今和歌集入門』(有斐閣新書)』▽『藤平春男著『新古今とその前後』(1983・笠間書院)』▽『『新古今時代の歌合と歌壇』(『谷山茂著作集4』所収・1983・角川書店)』▽『『新古今集とその歌人』(『谷山茂著作集5』所収・1983・角川書店)』
改訂新版 世界大百科事典 「新古今和歌集」の意味・わかりやすい解説
新古今和歌集 (しんこきんわかしゅう)
鎌倉初期,後鳥羽院が編纂させた勅撰和歌集。20巻。略して《新古今集》ともいう。巻頭に仮名序,巻尾に真名序を付し,春,夏,秋,冬,賀,哀傷,離別,羇旅,恋,雑,神祇,釈教に分類され,すべて短歌形式の歌で長歌,旋頭歌などの雑体は含まない。流布本で1979首を収める。八代集の最後に位置し,《万葉集》《古今和歌集》と並ぶ古典和歌様式の一典型を表現した歌集と評価されている。撰者は源通具,藤原有家,藤原家隆,藤原定家,藤原雅経。
撰集経過,成立
鎌倉幕府に対抗し,朝廷の威信の回復を念願した後鳥羽院は宮廷和歌の興隆に熱情をそそいだ。歌壇新旧両派の統一をうながすとともに,みずからも作歌活動の中心に立ち,〈正治初度百首〉〈正治第二度百種〉〈老若五十首歌合〉〈千五百番歌合(院第三度百首)〉などを主催,同時に新しい勅撰和歌集の実現をめざして,1201年(建仁1)7月和歌所を設置して藤原良経らを寄人に,源家長を開闔(かいこう)に任じた。同年11月には寄人のうちから撰者6名(うち寂蓮が中途で死去)を指名,和歌撰進の院宣を下した。各撰者は1年半後に撰歌稿を提出,さらに院自身の再撰歌作業が1年半も続いた(御点時代)。続いて分類・配列作業に入り,ことに作品の配列は,その時代的特色や,主題・副主題の密接な連続と調和に細心の配慮を加えたが,その間も新たな当代の秀歌を求めて歌合などを繰り返し,作品の加除がしきりに行われた。こうして分類整理が一応終わった段階で,1205年(元久2)3月26日竟宴が催され,公式にはこれが《新古今集》成立の日とされた。しかし実際は,翌々日から院の意志による歌の増補(切入(きりいれ)),削除(切出(きりだし))が行われ,約60首の新作歌も切入された。この改訂作業(切継(きりつぎ))の期間は5年間にもわたる(切継時代)。ようやく1216年(建保4)12月26日,最終的な定本が開闔の源家長の手で清書され,第2次完成をみるにいたった。その後,承久の乱で隠岐に流された後鳥羽院は,さらに精撰本を作製,380首ほどを除棄した。院の親撰という点を尊重して,この隠岐撰抄本を最終形態とみれば,集の成立を1235年(嘉禎1),36年とする見方も成り立つ。しかし実際に流布したのは切継時代に定家,家隆が書写した本文,または家長浄書本系統であり,その意味では,形式的には第1次,実質的には第2次の成立を重視すべきである。伝本は,撰集段階を反映して,第1類元久2年原撰本系統,第2類定家家隆書写本系統,第3類建保4年家長浄書本系統,第4類隠岐撰抄本系統の4種が想定されるが,第2類のほか純粋本文が伝存せず,現存伝本も種々の混態を示す。通常,第3類本文の復元を目標に校定される。
作者,歌風
《万葉集》は別として,《古今集》から《千載集》に至る先行の七つの勅撰集に入集している作は撰歌対象とせず,当代新風和歌を中核に据えた。西行,慈円,良経,俊成,式子内親王,定家,家隆,寂蓮,後鳥羽院,俊成女の,入集歌の多い上位10名の当代歌人のうち,西行以外は御子左(みこひだり)派新風歌人である(御子左家)。古典和歌の史的変遷を映しだすとともに,その必然の帰結として当時の新風を誇示する気迫が示されている。〈幽玄〉体と称された新風は,俊成・定家父子の創造,ことに定家の独創に影響され,技法としては本歌取りの極限的な活用が志向された。古典和歌の1首または2首を本歌として取り,その再構成をはかる。本歌の特徴的な表現を部分的に導入することで,表現の細部に本歌の映像と詩趣をただよわせ,密度の濃い多重的心象を構成して奥深い心の陰影をとらえる。それは,古典和歌,物語,漢詩の情調に没入する幻想的・耽美的情念を基調とする作歌法であったから,六条家の平板な古典主義と違って,余情・妖艶の美を造型する夢幻的芸術至上主義の詩として,和歌を再生させることを意図している。構成的な技巧としては初句切れ,三句切れ,体言止めが多用される。こうして,絵画的,物語的,幻想的,象徴的などといわれる華麗な新古今様式がうみだされた。古典を媒介とする幻想的美意識の放射,物語的情調の圧縮的な投影,鋭敏で透明度の高い季節感情の把握などが,それぞれ多彩に連関しあってイメージの小宇宙を形成している。
定家の〈春の夜の夢の浮橋とだえして峯に別るる横雲の空〉〈年も経ぬ祈る契りは初瀬山尾の上の鐘のよその夕暮〉,家隆の〈霞立つ末の松山ほのぼのと波に離るる横雲の空〉,式子内親王の〈玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする〉,寂蓮の〈さびしさはその色としもなかりけり槙立つ山の秋の夕暮〉,良経の〈うち湿りあやめぞ薫る郭公鳴くや五月の雨の夕暮〉〈きりぎりす鳴くや霜夜のさ莚に衣かたしきひとりかも寝む〉,後鳥羽院の〈桜咲く遠山鳥のしだり尾のながながし日も飽かぬ色かな〉,俊成女の〈風通ふ寝覚めの袖の花の香に薫る枕の春の夜の夢〉などの代表作に彼らの美意識が顕現されているのがみられる。しかしこの時代でも,深い真情の表現が尊重されたことに変わりはない。華麗な技巧を超えた,優美で高貴な余情をたたえる人間的真実の表現は,最高の秀歌といわれた。同時に,人の世の根源的な悲哀,静澄な無常感や孤独感の抒情もこの集には多い。むしろ変転する現世に生きる虚無感や反現実の志向が,一方では華麗妖艶の幻想美に反転したともいえる。
影響
《新古今集》は撰集規模,形態,方法などで後続勅撰集の規範となるほか,表現様式面では,ことに京極派の撰集《玉葉和歌集》《風雅和歌集》に継承された。また美的理念を通して,連歌,能,茶道など,中世の芸道の象徴理論に影響を及ぼした。また東常縁(とうのつねより)の注釈を細川幽斎が増補した《新古今和歌集聞書》があり,宗祇,肖柏,宗長ら連歌師によって注釈的研究もさかんに行われた。近世には新古今を称揚した本居宣長による《美濃の家づと》,また石原正明の《尾張迺家苞(おわりのいえづと)》などの研究書が知られる。近代では,新詩社の浪漫主義運動により再評価され,さらに北原白秋,太田水穂ら象徴主義歌人,ひいてはマチネ・ポエティクの詩人たちに,日本象徴詩の源泉としての評価を受け,塚本邦雄ら前衛歌人の文学運動を生んだ。
執筆者:近藤 潤一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「新古今和歌集」の意味・わかりやすい解説
新古今和歌集【しんこきんわかしゅう】
→関連項目秋夜長物語|鎌倉時代|鴨長明|賀茂保憲女|金槐和歌集|後鳥羽天皇|千載和歌集|源家長日記|六百番歌合
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新古今和歌集」の意味・わかりやすい解説
新古今和歌集
しんこきんわかしゅう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「新古今和歌集」の解説
新古今和歌集
しんこきんわかしゅう
第8番目の勅撰和歌集。20巻。歌数約1980首。後鳥羽上皇は,1201年(建仁元)7月和歌所を設置し,11月源通具(みちとも)・藤原有家・同定家・同家隆・飛鳥井雅経・寂蓮に撰進を下命。寂蓮は翌年没したため撰者は5人。05年(元久2)3月竟宴(きょうえん)が催されたが,すぐに切継ぎ(改訂)が行われ,16年(建保4)12月和歌所開闔(かいこう)の源家長が書写して終了。その後承久の乱に敗れて隠岐に配流された上皇は,さらに約400首を削除して正本とした。これを隠岐本とよぶ。真名(まな)序・仮名序があり,春上下・夏・秋上下・冬・賀・哀傷・離別・羈旅・恋1~5・雑上中下・神祇・釈教の各巻。入集上位は,西行94首,慈円92首,九条良経79首,藤原俊成72首,式子内親王49首,定家46首,家隆43首,寂蓮35首,後鳥羽上皇33首など。総じて古典主義的枠組みのなかで,本歌取・本説取の技法を用いつつ優艶華麗な歌風を示す。本集を中心に新古今時代という和歌史の一頂点が形成された。「新日本古典文学大系」所収。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「新古今和歌集」の解説
新古今和歌集
しんこきんわかしゅう
略称『新古今集』。1205年完成。20巻。歌数約1980首。後鳥羽上皇の命で藤原定家・藤原家隆・寂蓮 (じやくれん) らが撰 (えら) び,上皇の親撰。幽玄・妖艶・象徴的ないわゆる新古今調をつくり,万葉・古今とともに三大歌風をなす。本歌取り,体言止め,三句切れなどが特色。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の新古今和歌集の言及
【短歌】より
…中世短歌の特質は,象徴性と哲学性とを基調としつつ内面化の方向を強めた点に認められるが,俊成の歌論の核心をなす幽玄,《山家集》に見られる西行の短歌作品は,はっきりとそうした特質を示しているからである。 《千載集》の次の勅撰集《新古今和歌集》(1205成立)は,上に記したような中世短歌の特質を典型的に体現したもので,選者の一人藤原定家の歌論の中心をなす有心(うしん)は,この方向の極北へ言及したものと見なしてよい。〈見わたせば花ももみぢもなかりけり浦のとまやの秋の夕暮〉(藤原定家)。…
【藤原良経】より
…平安末~鎌倉初期の廷臣,歌人。摂籙(せつろく)家九条兼実の子として生まれ,左大臣を経て従一位摂政太政大臣に昇る。和歌を藤原俊成に学び,建久期前半(1190‐97)には,歌壇を主宰して定家ら新風歌人の庇護者となり,《花月百首》や《六百番歌合》を開催。建久7年(1196)の政変により一時籠居したが,のち政界に復帰し,後鳥羽院歌壇においても中心人物として《新古今集》編纂に貢献した。仮名序を執筆し,巻頭歌作者となっている。…
【本歌取り】より
…しかし,このころはまだ修辞的な技巧としては意識されていない。意識的な技巧として推進したのは藤原俊成で,《新古今和歌集》は本歌取りの全盛時代に成立している。それまでは〈盗古歌〉と考えて,本歌取りを避ける主張もあった(藤原清輔《奥儀抄》)。…
※「新古今和歌集」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...