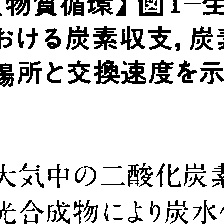日本大百科全書(ニッポニカ) 「物質循環」の意味・わかりやすい解説
物質循環
ぶっしつじゅんかん
cycle of matter
地球上の生物群が有限の物質を無限に利用する仕組みを体系的にとらえたとき、これを物質循環とよぶ。生物群は地表・地中・水中に分布して地球を覆う層(生物圏)をつくっている。この生物圏を機能的な物質系として表現するとき、「地球生態系」の語が使われる。地球生態系では、太陽エネルギーを化学エネルギーに転換して有機物が生産・蓄積され、さらにこの有機物は消費・還元されて「地球生物化学的物質循環」に組み込まれる。また、生物圏を支えている地球自体には「地球化学的物質循環」が行われている。
[寺川博典]
地球化学的物質循環
岩石の溶融体(マグマ)は結晶化して火成岩となるが、これらの火成岩は風化作用を受けて砂や粘土を形成し、堆積(たいせき)物をつくる。堆積物は堆積岩になり、さらに変成岩となって最後にマグマに戻る。これが地球化学的物質循環である。何千万年から何億年もかかるこの循環過程において、生物圏には土壌の材料が供給される。つまり、各種岩石や堆積物は生物の作用を受けて土壌を形成し、土壌は侵食・崩壊して堆積物となって地球化学的物質循環に組み込まれる。
[寺川博典]
地球生物化学的物質循環
無機的環境と生産者(植物類)・消費者(動物類)・還元者(菌類)からなる生物界との間の物質循環が、地球生物化学的物質循環である。無機物を生物界に取り入れて有機物をつくる生産者としての植物類は、この循環過程において重要な位置を占める。また、有機物の消費者である動物類は菌類の働きを助けている。さらに菌類は、有機物を無機物にして無機的環境に返す還元者として重要な位置を占めている。
(1)炭素の循環 炭素は有機物の骨組みをつくっている元素である。植物類は、光合成によって炭素を二酸化炭素の形で大量に無機的環境から取り入れて有機物を生産する。また、遺体の有機物中の炭素は、おもに菌類によって二酸化炭素に還元されて、無機的環境へ返される。植物類の純生産量に必要な二酸化炭素量の90%以上は、菌類の働きによって生じたものと見積もられている。このほか動物の呼吸や火山活動・山火事などによっても二酸化炭素は生ずるが、菌類の働きに比べると、その量はわずかである。菌類の還元力の大きいことは、還元に必要な酸素の消費量によって示される。土壌菌類での酸素の消費量は、ヒトの数百倍から数万倍である(アゾトバクターでは6万倍)。また、1エーカー(約40アール)の肥沃(ひよく)な土壌の場合でみると、深さ15センチメートルの範囲内には約2トンの土壌菌類が生活し、その働きはヒト数万人に相当するといわれる。
大気中の二酸化炭素は、容量にして約0.03%であり、その炭素の総重量は6000億トンである。なお、海中には、この約100倍が溶けており、平衡状態を保っている。植物類が1年間に有機物に転換する炭素の量は2000億トンといわれる。したがって、もし、炭素が循環しないと仮定すると、約300年(評価によっては250年から数百年の幅がある)でなくなることとなる。こうしてみると、物質循環は地球上の有限の物質を無限に利用する体系であることが理解できる(光合成に伴って生ずる酸素は年産120兆トンで、これは、もし循環しなければ数千年でなくなることとなる)。
こうした自然界の炭素の循環は、何億年にもわたって一定の速度で続いてきたものであるが、ここ数十年間は、膨大な量の化石燃料(石炭・石油など)の燃焼による二酸化炭素の放出によって攪乱(かくらん)され続けている。今後も、これらの燃料が尽きるまでは、大気中の二酸化炭素は増加し続けるわけであり、そのためにおこると予測される環境変化が憂慮されている。また、熱帯林で年々繰り返される広大な地域での森林の伐採、世界的に広がり続ける砂漠化現象なども、大気中の二酸化炭素の増加に深くかかわるものである。
(2)窒素の循環 窒素はタンパク質や核酸には不可欠な物質であり、窒素源には、遊離窒素、無機窒素化合物、有機窒素化合物がある。このうち遊離窒素と無機窒素化合物は植物と菌類が利用し、有機窒素化合物は動物と菌類が利用している。遊離窒素は大気の75%を占めているが、これは菌類と藍藻(らんそう)によってアンモニアに変えられるほか、放電によって酸化窒素を経て硝酸となる。アンモニアは植物と土壌菌類によって吸収され、その残りは硝化菌によって亜硝酸から硝酸に酸化される。この硝酸は菌類、とくに植物にとっては重要なタンパク質合成素材である。動物類が排出する尿素・尿酸は菌類によってアンモニアに変えられる。植物類によって合成されたタンパク質は、動物・菌類によって利用される。また、すべての遺体が含んでいるタンパク質は、分解され、アンモニアとなって大気に入るが、その多くはふたたび植物によって利用される。硝酸・亜硝酸は、コウボキンやシュウドモナスなどの菌類によって脱窒素作用を受け、遊離窒素として大気へ返される。このような菌類による無機窒素化合物の植物類へのバトンタッチと、大気からの固定による生物界への窒素導入は、植物類の二酸化炭素固定と並ぶ生物界の重要反応である。
(3)硫黄の循環(いおうのじゅんかん) 硫黄はいくつかの重要アミノ酸や補酵素にとって不可欠な物質である。硫黄は地殻中に豊富に存在し、還元的環境では硫化水素、大気中では亜硫酸ガスとして含まれている。生物が利用するのは主として硫酸(イオン)である。植物類と多くの菌類は、硫酸・亜硫酸を利用して有機硫黄化合物をつくる。これを動物と菌類が利用している。
有機硫黄化合物は、最後には菌類によって分解され、硫化水素に還元される。また、硫酸は硫酸還元菌によって硫化水素に還元されたあと、硫黄細菌や紅色細菌類によって酸化されて硫黄となるか、またはさらに硫酸となる。硫黄は地殻に沈積し、硫化水素は硫化鉱沈殿をおこし、何億年もかけて現在の多くの鉱床を形成したと考えられている。一方、前述の化石燃料の燃焼は、大量の硫化物や窒素化合物を放出して大気を汚染している。とくに、硫酸雨などによる地表の環境破壊は、大きな問題を残している。
(4)リンの循環 地殻元素の多くは、生物体に取り込まれて循環するが、この循環において、とくに硫黄よりも多くを必要とされるのがリンである。リンは核酸・脂質・タンパク質・補酵素・高エネルギー物質・脊椎(せきつい)動物の骨格などに含まれるが、吸収はリン酸塩の形で行われる。生物が死ぬと、リン酸化細菌が働くほか、排出物も加水分解され、溶解性の無機リン酸塩の形で遊離する。この無機リン酸塩の一部は再利用されるが、残りは流失して深海堆積物に加わり、地球生物化学的循環から外れていく。この損失を補うリンの貯蔵庫は地質時代につくられた岩石や、ほかの堆積物であるが、これらには限りがある。
炭素・酸素・窒素・硫黄では、その酸化状態の変化、つまり原子価に関する循環的変化があり、栄養素として利用されるためには酸化状態が重要な因子となる。しかし、リンの循環中においては、リン原子に原子価の変化はみられず、リン酸基部分としてそのまま存在している。なお、水素と鉄も酸化状態の循環的変化を行うが、その規模は小さい。
[寺川博典]
物質循環とエネルギーの流れ
地球上に初めて誕生した生物群は、原始有機物の化学エネルギーを利用するものであった。次に一時的に繁栄したのは、無機物の化学エネルギーを利用する生物群であった。やがて、太陽光線のエネルギーが利用されるようになり、それ以後はこれによって生物界が支えられるようになった。まず、植物類の光合成によって、光のエネルギーは有機物の化学エネルギーに転換される。ついで、この転換された化学エネルギーは、生物が栄養として利用する物質にのって流れていくわけである。この化学エネルギーは、生物界のほとんど全体を通じて生物学的仕事に使われ、生活の維持に役だてられている。化学エネルギーを運ぶ物質を構成する元素は、地球生物化学的循環を行うのに対し、宇宙からきた光エネルギーは、生物群に利用されて熱(エネルギーの一形態)となり、大気、海洋、そして宇宙へと帰っていく。このようなエネルギー変換を全体としてみると、エネルギーには新生も消滅もない(エネルギーは一定に保たれる)。これを「エネルギー保存の法則」(熱力学第一法則)とよぶが、この考えは、生物で着想され、生物体を通して確立されてきたものである。
自然生態系においては、何億年間もこうしたエネルギーの流れが維持されてきた。しかし最近では、人為的に膨大な石油エネルギーが投入され、さらに原子力エネルギーも開発された。しかも、この新しいエネルギーの登場はごく短期間に行われたものである。地球生態系からみた場合、これらの新しいエネルギーは、環境汚染・自然破壊につながる危険性をはらんでいるといえる。
[寺川博典]
『鷲田豊明著『エコロジーの経済理論――物質循環論の基礎』(1994・日本評論社)』▽『室田武著『物質循環のエコロジー』(2001・晃洋書房)』
改訂新版 世界大百科事典 「物質循環」の意味・わかりやすい解説
物質循環 (ぶっしつじゅんかん)
cycle of matter
生態系において,生物体を構成するさまざまな物質が環境から生物にとり込まれ,食物連鎖や腐食連鎖を通じて生物間を移動し,再び環境にもどされることをいう。エネルギーの流れとともに,生態系の最も重要な機能の一つであるが,化学物質は環境と生物の間をなん回でも循環することが可能であり,この点で一方的な流れであるエネルギーの流れとは対照的である。しかし,この両者は表裏をなすもので,化学物質の移動,変換には必ずエネルギーの変化が伴う。
物質の循環は,微小な範囲のものから地球規模のものまであり,生物地球化学的循環とも呼ばれるが,いずれにしても近年では人間の影響が無視できないものとなっている。安定した生態系においては,循環の経路や経過の時間なども安定しているが,特定の場所に物質が停滞したり,逆に不足したりすると,生物群集にも変動が起こり,物質循環系は乱れる。環境汚染,湖沼や海洋の富栄養化現象も,こうした物質環境系の乱れとみなすことができる。また,公害問題として注目される重金属や有毒物質で見られる生物濃縮の過程も同様な循環系の乱れであろう。
循環する物質の性状と生物の関与の仕方の差で多様な循環が形成される。生命に不可欠な水分,重要な生体成分である酸素,炭素,窒素,微量ではあるが重要な働きをもつリン(燐)や硫黄,その他の微量元素類などの循環経路が明らかにされているが,まだ不明の点も少なくない。
水の循環
地球が,他の天体と著しく違う点として液体状の水の存在が第1に挙げられる。生物圏の定義が〈液体状の水の存在と外部からの十分なエネルギー供給〉とされるように,水と生命は不可分であり,水の循環は生命の存在を支配している。地球上の水の総量は,約14億km3と推定されている。このうち海水が97%以上で,淡水は3%にも満たない。淡水の4分の3は氷雪であり,湖沼,河川,地下水など陸上の生物にとって重要な液体状淡水は全体の0.5%程度にしかならない。水は大気から降水として陸地,海洋に降る。陸地に降った水の一部は海へ流出するが,一部はさまざまな場所に蓄えられる。しかし,いずれは再び蒸発散により大気にもどる。海洋の水も同様に蒸発し,再循環する。水の蒸発潜熱は液体中最大であり,蒸発散の過程で熱収支や生物的過程にも影響をおよぼす。また水は物質を溶解しやすく,溶解物質の移動にも重要な働きをする。さらに,河川や海流のエネルギーは浸食,運搬,堆積などの地質的なしごとともなる。
地球上の降水の分布はひじょうにかたよっており,生物の分布に強い影響をもっている。したがって水は重要な資源の一つともなっている。灌漑はこうした水資源の有効利用を考えた人間の水循環系への関与の例である。森林伐採,耕地の拡大なども水循環に影響を及ぼしている。
→水
炭素の循環
生物体構成元素としては,水を除くと炭素が最も多い。生物圏での炭素循環は,一次生産者(主として緑色植物)による大気中の二酸化炭素の固定,すなわち炭水化物の合成(炭素固定ともいう。これのもっとも代表的なものが光合成である)から始まる。これをもとに植物体が合成され,これを動物が食う。その動物がさらに他の動物に食われるという食物連鎖を通じ炭素は移動する。生物はやがて死に,その遺体は分解者により分解される。これらすべての過程で呼吸による炭素の酸化が進み,二酸化炭素として大気中にもどされる(図1)。
炭素の地球規模の循環にも人間の影響が及んでいる。1958年以来,大気中の二酸化炭素濃度がハワイのマウナ・ロア山頂で測定されているが,近年は確実に増加している(図2)。この現象は化石燃料(石油,石炭)の燃焼の結果である。大気中の二酸化炭素の増加は,温室効果をもたらし,地球上の温度を上昇させると予測されている。
→炭酸固定
窒素の循環
大気の79%は分子状窒素であるが,ほとんどの生物はこれを利用できない。大気中の放電現象などによる固定,生物的固定(放線菌やアゾトバクターやある種のラン藻などが行う空中窒素固定),肥料生産の工業的固定などを通じて硝酸態またはアンモニア態窒素が生成する(図3)。生物体ではタンパク質の主要成分として存在する窒素の循環は,脱窒素作用(硝酸態窒素の還元による分子状窒素の生成)によって完結する。工業的窒素固定は,全窒素固定の3分の1にもなり,人間の関与の大きさを示している(図4)。
→空中窒素固定
リンの循環
リンは炭素,窒素に比べると量は少ないが,ATPなどの構成分として生物には不可欠である。リン酸塩を含む岩石から供給されるが,自然では慢性的な欠乏状態にある。降水の流出とともに水圏へ運ばれ,その結果,海洋はリンの貯留場となっている。人間が海鳥の糞(ふん)(グアノ)やリン鉱石から作った肥料を用いるまでは一方向の循環であった。湖沼の富栄養化はリンの添加の結果であることが多い。水溶性で非揮発性の元素の循環は基本的にはリンの場合と同じである。
→生態系
執筆者:林 秀剛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物質循環」の意味・わかりやすい解説
物質循環
ぶっしつじゅんかん
material cycle
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
最新 地学事典 「物質循環」の解説
ぶっしつじゅんかん
物質循環
material cycling
地球表層(大気圏,水圏,生物圏,地圏),地球内部,宇宙空間,あるいはそれらの相互間における物質(元素・化合物)の移動,生成,分解過程。海洋における炭素の循環を例にすると,大気-海洋間の交換で海洋に取り込まれた二酸化炭素が,生物による固定や深層への海水の移動に伴って表層から除去されたり,死んだ生物の分解を経て溶存有機炭素として表層へ戻ってきたり,あるいは,海底に到達して短時日のうちには海洋内の循環経路に入ってこなくなったりする。このような過程の全体あるいはそのしくみ(機構)の総称として用いる。
執筆者:中尾 征三・浜田 盛久
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
化学辞典 第2版 「物質循環」の解説
物質循環
ブッシツジュンカン
material circulation
炭素,窒素,硫黄,水などの物質が,生態系や環境系において移動・循環すること.生産者,動物消費者,分解者とよばれる生物間での生態系での循環,および大気圏・水圏・岩石圏などの地球環境系での循環に大別される.近年問題となっている二酸化炭素などの温暖化ガスの増加による地球温暖化現象,フロンなどによる極地でのオゾン層の破壊機構,さらに環境ホルモンなどの化学物質による地球規模での汚染原因などに深くかかわっている.循環の形態は個々の元素の化学的特性,生物による要求性,自然環境などによって異なるが,その主要部分は生化学反応によって担われている.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
百科事典マイペディア 「物質循環」の意味・わかりやすい解説
物質循環【ぶっしつじゅんかん】
→関連項目生態系
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の物質循環の言及
【エネルギーの流れ】より
…生態系においては,その構成各要素間にさまざまな物質の受渡しがあり,それに伴ってエネルギーの変換,移動がある。前者を物質循環と呼ぶのに対し,後者をエネルギーの流れと呼ぶ。すべての生命活動にはエネルギーの供給が不可欠であるが,このエネルギーの究極的な供給源は太陽の核融合反応であり,光エネルギーとして地表に送られてくる。…
【生物生産】より
…生物生産は,一定地域内で,一定時間に生物により合成される有機物量,または合成された有機物として固定されたエネルギー量であり,生産力または生産速度で表される。生物生産は生物の生活にとって最も基本的な機能の一つであり,生態系における物質循環の駆動力となっている。独立栄養生物の行う一次生産と従属栄養生物の行う二次生産とに区別される。…
※「物質循環」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...