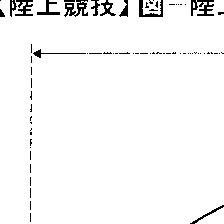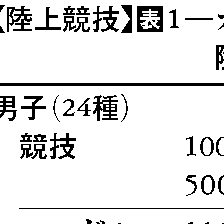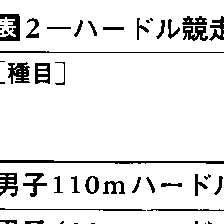翻訳|athletics
精選版 日本国語大辞典 「陸上競技」の意味・読み・例文・類語
りくじょう‐きょうぎリクジャウキャウギ【陸上競技】
- 〘 名詞 〙 競走・跳躍・投擲(とうてき)を基本として、地上で行なわれる運動競技の総称。主としてトラックおよびフィールドで行なわれる各種の競技。陸上。
- [初出の実例]「第七回国際オリムピック競技会には、陸上競技、水泳、及び庭球に十五名の代表選手を参加せしめ」(出典:陸上競技法(1923)〈野口源三郎〉一)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「陸上競技」の意味・わかりやすい解説
陸上競技
りくじょうきょうぎ
athletics
走、跳、投の人間の基本三動作から発展したスポーツ各種目(100メートル競走、走高跳び、やり投げなど)を包括した競技。
[加藤博夫 2020年4月17日]
歴史
獲物を追って走り、川や岩を跳ぶ、そして獲物に向かってやりや石を投げるなどの動作は、すでに原始時代から存在していたが、それを生活から切り離し、一定のルールのもとにスポーツ化していったのが陸上競技の原形であろう。したがってその起源を明確に知るのはむずかしいが、はっきり記録に残されているものでも、紀元前776年、ギリシアのオリンピアで開かれた古代オリンピックの第1回大会にさかのぼる。ここでは直走路で短距離競走のスタディオン走が行われ、その優勝者の名前が大会に冠された。スタディオンは長さの単位で、1スタディオンは約185メートルとされるが、スタジアムの語源となったように競技場の大きさによってレースの距離は変わり、177メートルから192メートルぐらいで行われた。しかし古代オリンピックは、明確な記録が残っている前776年を第1回大会としただけで、実際にはもっと古くから存在していたとみられ、前1370年説をはじめ諸説がある。また壁画などから、アジア、アフリカでもそれより古い時代に素朴な形での陸上競技が行われていたと想像できる証拠があり、明確に起源を知るのはむずかしい。
古代オリンピックで行われた競技は、スポーツというよりは、父なる神ゼウスのための祭典競技であり、神の儀式の一部としての役割を果たしていた。当初、大会は1日だけで、短距離競走1種目だけであった。その後第14回大会(前724)になると往復競走(2スタディオン)が加わり、以後、長距離競走、五種競技(短距離走、幅跳び、円盤投げ、やり投げ、レスリング)、ボクシング、戦車競走などが追加された。幅跳びは亜鈴など重いものを両手に持ってはずみをつける跳び方、円盤は石や銅でつくられた重いもの、やりは重心近くに皮紐(かわひも)をつけてそれに指を通して投げるなど、多少形は違うにしても、紛れもなく現在の陸上競技種目の範疇(はんちゅう)に入るもので、古代オリンピック即陸上競技といっても過言ではない。同大会は、393年に廃止されるまで4年に一度のペースで実に1000年以上も続いた。
陸上競技がスポーツの一つとして近代的な形をとり始めたのはルネサンス以降であり、その先頭を切ったのがイギリスであった。古代オリンピックは短距離から始まったが、近代の競技の始まりは長距離からだった。1740年ロンドンでの1時間競走が記録に残された最初の競技であり、ロードレースやクロスカントリーなど長距離走の形で発展し、やがては走高跳びや砲丸投げなどのフィールド競技も行われるようになった。そして1864年には、世界最古の対抗戦といわれるオックスフォード、ケンブリッジ両大学の対抗戦が始まり、2年後には全英選手権、1880年にはイギリス陸上競技協会も創設された。そしてこれが留学生などを媒体としてアメリカ、カナダ、フランスなどに広がっていくのである。
陸上競技が本当の意味での国際競技になったのは、1896年の近代オリンピックの第1回大会からである。古代オリンピックの復活を目ざしてアテネで始まったこの大会の中心競技は、陸上競技であった。開会式後の最初の種目が100メートル走予選というのも象徴的である。以後、陸上競技はつねにオリンピックのメインイベントとして位置づけられ、今日に至っている。
また国際的な組織づくりも非常に早く、1912年には国際陸上競技連盟(以下「国際陸連」と略称)を設立、本部をストックホルム(のちにロンドン。現在はモナコ)に置いた。そして1914年には世界共通の競技規則をつくり、世界記録公認制度も決められた。発足当時17か国だった国際陸連加盟国(国あるいは地域)も2019年の時点で214となり、国際サッカー連盟などと並ぶ大組織の一つになっている。さらに国際陸連は、2019年11月からはワールドアスレティックス(世界陸連)に名称変更した。
[加藤博夫・中西利夫 2020年4月17日]
記録の進歩
世界記録は年々更新され、とどまるところを知らないが、その要因には、(1)技術の進歩、(2)用具・施設の改良の二つがある。技術の進歩の好例は走高跳びである。正面跳びから始まり、バーの上で体を横に倒すウェスタンロール、さらにバーの上で腹ばいになるベリーロールとフォームが変わってきたが、1960年代後半に背面跳びという革命的な跳法が考案された。踏み切ったあと後ろ向きになり背中でバーを越す奇想天外なフォームだが、これによって世界記録は一挙に跳ね上がった。砲丸投げも同様で、1950年代にパリー・オブライエンParry O'Brien(アメリカ。1932―2007)が後ずさりでステップする常識破りのフォームを生み出して世界記録を大幅に伸ばした。ハンマー投げでもターンの技術の研究により1回転から2回転、2回転から3回転と進むにつれて記録は伸び、現在は4回転を行っている競技者が多い。
一方、用具・施設改良の好例は棒高跳びのポールである。ポールは当初は木、やがて日本製の竹、アルミニウム、スチールと変化していった。1960年代に出現したグラスファイバー・ポールは従来とは比較にならないほどの弾力性をもつため記録はうなぎ登りに伸び、スチール時代の世界記録4メートル80センチ(1960年)が、6メートル18センチ(2020年)となり大幅に更新されている。またオリンピックでは1968年のメキシコ大会から採用されたタータン・トラック(合成ゴムの全天候型走路)や助走路もその弾力性から「魔法の絨毯(じゅうたん)」として短距離や跳躍種目の記録向上に大きな役目を果たし、全天候トラックは時代とともに新素材が次々と開発され、進歩を遂げている。
近年はトレーニングへの医科学の導入によっても記録の向上が続いているが、一方では薬物を悪用したドーピングスキャンダルも後を絶たない。オリンピックでは、1988年ソウル大会の男子100メートルを世界新記録で優勝したベン・ジョンソンBen Johnson(カナダ。1961― )が薬物違反で金メダルを剥奪(はくだつ)され、2000年シドニー大会で3個の金メダルを獲得したマリオン・ジョーンズMarion Jones(アメリカ。1975― )ものちにドーピング違反を認めて失格となった。最近では2014年に組織的な疑惑が発覚したロシアが国ぐるみのドーピング問題で波紋を広げている。
[加藤博夫・中西利夫 2020年4月17日]
女子種目の増加
オリンピックに女子の陸上競技が登場したのは男子より32年遅れた1928年のアムステルダム大会からであった。このとき男子の22種目に対し女子は5種目。しかもこのうち女子の800メートル走は日本の人見絹枝(ひとみきぬえ)ら参加選手全員がゴールイン後にばたばたと倒れたため、女子には過酷であるとして国際陸連は以後30年以上、女子に200メートルを超える距離を走らせなかった。しかし、第二次世界大戦後の女性の体格および社会的地位の向上は目覚ましく、1960年のローマ大会から800メートル走が復活、1964年の東京大会では400メートル走と五種競技が増えた。その後も1972年のミュンヘン大会では1500メートル走が加わり、1984年のロサンゼルス大会ではついにマラソンまでがオリンピック種目となった。そのほか2000年のシドニー大会では、棒高跳びとハンマー投げも追加され、いまや男子と女子のオリンピック種目比率は、24種目対23種目となった。男子にあって女子にない種目は50キロメートル競歩だけになっている。
[加藤博夫 2020年4月17日]
日本の陸上競技
近代的な形での陸上競技が日本へ移入されたのは、1874年(明治7)東京・築地(つきじ)の海軍兵学寮で開かれた「競闘遊戯(きそひあそび)」が最初で、内容は150ヤード競走、走幅跳び、砲丸投げなど現在の陸上競技種目とほぼ同様だった。1878年にはアメリカ人ウィリアム・スミス・クラークの指導による札幌農学校の第1回遊戯会が行われた。またイギリス人フレデリック・ウィリアム・ストレーンジの主唱により東京大学でも運動会が開かれた。この東京大学の運動会はとくに人気があり、1883年(明治16)に第1回大会を開いて以来、約30年にわたって日本の陸上競技の中心となった。とくに東大の学生藤井実(1880―1963)は1902年(明治35)の東大運動会で100メートル走に10秒24、1906年には棒高跳びで3メートル90センチの二つの「世界記録」をつくった。当時はまだ国際陸連による世界記録公認制度はなく、日本はオリンピックにも参加していなかったため、情報交換による比較にすぎなかったが、それにしても非常にレベルが高く、1907年のアメリカの運動年鑑にもこの記録は残されている。
大学の運動会に閉じ込められていた陸上競技が独立のスタートを切ったのは、1911年(明治44)のことである。1912年のオリンピック・ストックホルム大会に初参加を決めた日本は、その前年の1911年にまず大日本体育協会(現在の日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会)を設立、東京・羽田でオリンピック予選会を開いた。種目は陸上競技のみで、運動会とは違った日本初の陸上競技会であった。翌年のオリンピックには短距離の三島弥彦(やひこ)、マラソンの金栗四三(かなくりしそう)の2人が参加したが惨敗した。
しかしこれを契機に日本の陸上界はしだいに力をつけ、1924年(大正13)のパリ大会では織田幹雄が三段跳びで6位に入り陸上競技で初入賞、1925年には全日本陸上競技連盟(日本陸上競技連盟の前身)として大日本体育協会から独立した。そして1928年(昭和3)のアムステルダム大会では織田が三段跳びで日本初の金メダルを獲得、以後、三段跳びでは1932年ロサンゼルス大会で南部忠平、1936年ベルリン大会で田島直人(なおと)が勝ち、日本はオリンピック3連勝の偉業を成し遂げた。
第二次世界大戦後、日本陸上で最初にオリンピックで金メダルを獲得したのは2000年シドニー大会女子マラソンでの高橋尚子(なおこ)である(高橋はこの功績により、女子スポーツ界で初の国民栄誉賞を受賞)。続く2004年のアテネ大会でも野口みずき(1978― )が金メダルを獲得し、日本女子が2連勝を遂げた。また2004年のアテネ大会男子ハンマー投げでは室伏広治(むろふしこうじ)(1974― )が優勝し、男子陸上で戦後初の金メダルを獲得している。
そのほかオリンピック2位入賞者は、アムステルダム大会女子800メートル走の人見絹枝、ロサンゼルスおよびベルリン大会棒高跳びの西田修平、ベルリン大会三段跳びの原田正夫(1912―2000)、メキシコ大会マラソンの君原健二(1941― )、バルセロナ大会男子マラソンの森下広一(1967― )、バルセロナ大会女子マラソンの有森裕子(ありもりゆうこ)(1966― )、北京(ペキン)大会男子400メートルリレー走の塚原直貴(なおき)(1985― )、末續慎吾(すえつぐしんご)(1980― )、高平慎士(たかひらしんじ)(1984― )、朝原宣治(のぶはる)(1972― )、リオ・デ・ジャネイロ大会男子400メートルリレー走の山縣亮太(やまがたりょうた)(1992― )、飯塚翔太(しょうた)(1991― )、桐生祥秀(きりゅうよしひで)(1995― )、ケンブリッジ飛鳥(あすか)(1993― )である。3位入賞者はロサンゼルス大会走幅跳びの南部忠平、ロサンゼルス大会三段跳びの大島鎌吉(けんきち)(1908―1985)、ベルリン大会走幅跳びの田島直人、ベルリン大会棒高跳びの大江季雄(すえお)、東京大会マラソンの円谷幸吉(つぶらやこうきち)(1940―1968)、アトランタ大会女子マラソンの有森裕子、ロンドン大会男子ハンマー投げの室伏広治、リオ・デ・ジャネイロ大会男子50キロメートル競歩の荒井広宙(ひろおき)(1988― )と続いている。
これをみると、第二次世界大戦前の日本の得意種目は三段跳びなどの跳躍種目、戦後は男女のマラソン、ハンマー投げなどということができる。とくにマラソンは第二次世界大戦後急激に伸び、男女ともほとんどのオリンピックで入賞者を出したほか、世界選手権でも1991年に男子の谷口浩美(ひろみ)(1960― )、1993年に女子の浅利純子(1969― )、1997年に鈴木博美(ひろみ)(1968― )が優勝している。世界選手権ではこのほか、2011年に男子ハンマー投げで室伏広治、2019年に男子20キロメートル競歩で山西利和(としかず)(1996― )、男子50キロメートル競歩で鈴木雄介(1988― )が優勝した。
[加藤博夫・中西利夫 2020年4月17日]
競技種目
陸上競技は大別すると、(1)トラック競技、(2)フィールド競技、(3)混成競技、(4)ロードレースの四つに分かれる。
トラック競技は、競技場内の走路で行う競走種目で、短距離走(オリンピック種目でいえば100メートル、200メートル、400メートル)、中距離走(同800メートル、1500メートル)、長距離走(同5000メートル、1万メートル)のほか、ハードル走、障害物競走、リレーが含まれる。これらの種目はいずれもピストルの発射音によってスタートするが、これまでのルールでは、どの選手も1回の不正出発(フライング)は許容されていた。しかし2010年1月からは「混成競技を除き、フライングは1回で失格」とルールが変更された。400メートルまでの競走は、スターティング・ブロックを用いるが、スターターのピストルが鳴るよりも早く競技者の足がブロックを蹴ると、フライングとわかるよう電気的にセットされ、反応速度が0.100秒未満だとフライングとなる。また200メートルまでのすべてのレースでは、真後ろからの追い風が毎秒2メートルを超えた場合、順位には影響ないが記録は公認されない。
フィールド競技は、走路に囲まれた競技場のフィールド内で行われる競技で、跳躍種目と投擲(とうてき)種目に分かれる。跳躍種目のうち走幅跳び、三段跳びは横への距離を競う種目で、踏切線から着地点までを測るが、踏切線をはみ出した場合は無効試技(ファウル)となる。この両種目は真後ろからの追い風が2メートルを超えると記録は公認されない。走高跳び、棒高跳びは高さを競う競技で、3回続けて失敗すると次の高さへの挑戦権は与えられない。
投擲種目のうち砲丸投げ、ハンマー投げは直径2.135メートル、円盤投げは直径2.50メートルのサークルからステップあるいはターンを使って投げ、やり投げだけが助走路を使って投げる。(1)定められた角度(やり投げ28.96度、他は34.92度)の範囲からはみ出して落下した場合、(2)投擲物が地上に落下する前に競技者がサークルまたは助走路(やり投げの場合)から出た場合、あるいは落下後でもサークルの半円の前半部から出た場合は無効試技となる。距離は投擲物が地面に残した痕跡(こんせき)のもっとも近い点から、サークルあるいは円弧の内側までを、それぞれの中心を結ぶ線で測る。円盤投げとハンマー投げは危険防止のためサークルの三方を金網などで囲むことが義務づけられている。
混成競技は、トラック競技とフィールド競技を組み合わせた複数種目を1人で行い、その成績を点数に換算して合計点を競う競技である。オリンピックでは男子は十種競技、女子は七種競技がともに2日間で行われる。
ロードレースは、競技場を離れて道路で行う競技で、マラソン、駅伝、競歩などがこれに入る。マラソンは従来はコースによって記録が大幅に変わるため記録は公認せず「世界最高記録」「日本最高記録」などの扱いであったが、国際陸連は2004年以降、コースの高低差などに一定の条件を決め、それをクリアしたコースの記録だけを公認することに変更し、以後は「世界記録」「日本記録」と呼称することになった。競歩はオリンピックでは道路を使っての男子20キロメートル競歩、50キロメートル競歩、女子20キロメートル競歩が行われている。
[加藤博夫・中西利夫 2020年4月17日]
パラ陸上(障害者陸上競技)
腕や脚などの身体や、視覚や知的発達などに障害のある人が走、跳、投の陸上競技種目で順位や記録を競う競技。走種目であれば100メートル走からマラソンまであるが、障害の及ぼす影響を小さくして平等に競えるように、障害の種類・程度によって細かくクラス分けして実施される点が一般の陸上競技とは異なる。ワールドアスレティックス(世界陸連)と世界パラ陸上競技連盟(WPA)の競技規則に基づいて行われ、世界記録、アジア記録、日本記録などもある。国際パラリンピック委員会(IPC)公認大会ではIPC陸上競技規則が適用される。一般の陸上競技との違いは義手、義足を着用するほか、「レーサー」とよばれる競技用車いすや投擲台などの用具を使用すること、「ガイドランナー」とよばれる伴走者や「コーラー」「エスコート」というアシスタントがサポートする点でも違いがある。
クラス分けは、障害の確認と公平に競技を行うためのもので、国際・国内競技団体公認の「クラシファイヤー」が行う。2019年(令和1)11月時点の日本パラ陸上競技連盟によるクラス分けは、4文字(アルファベットと数字の組合せ)で表記され、たとえば「T53C」のように左から順番に、(1)競技の種類、(2)障害の種類、(3)障害の程度、(4)クラス・ステータスとなっている。(1)競技の種類は走種目(100メートル~マラソン)と跳躍種目(走高跳び、走幅跳び、三段跳び)が「T」、投擲種目(砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ、こん棒投げ)は「F」となる。(2)障害の種類は10番台から60番台まであり、10番台は視覚障害のある立位競技者、20番台は知的障害のある立位競技者、30番台は麻痺(まひ)や筋強直、運動障害などのある脳原性麻痺のある立位競技者および車いすや投擲台使用競技者、40番台は低身長、脚長差、切断(義足不使用)、筋力低下などの障害のある立位競技者、50番台は脚長差、切断、関節可動域制限などの障害があり、車いすや投擲台を使用する競技者、60番台は切断などの理由で義足を装着する競技者、となっている。(3)障害の程度は0~9まであり、番号が小さいほうが障害の程度は重い。(4)クラス・ステータスは3段階に分かれるが、個人情報のためプログラムなどでは公表されていない。これまでクラス分けを受けたことのない「N」(New)、再度クラス分けを受ける必要がある「R」(Review)、クラスが確定した「C」(Confirmed)の分類がある。
視覚障害のT/F11の全盲クラスでは、選手は視力の程度を統一するため、アイパッチ、アイマスクや完全に光を遮断する眼鏡などの着用が義務づけられる。トラック種目やマラソンでは、選手とガイドランナーが両端に握り用の輪がついたガイドロープ(テザー)を握っていっしょに走る。ガイドロープの長さはトラック種目が30センチメートル以下、ロード種目が50センチメートル以下で、進行方向やコースの状況、タイムを口頭で伝えながら走る。その際、選手を引っ張ったり、選手より先にフィニッシュラインを通過したりすると失格となる。ガイドランナーも選手と同じルールのもとに競技を行い、400メートル走まではスターティング・ブロックを使用し、フライング規定などが適用される。5000メートル以上の種目では2人までのガイドランナーが認められ、交代は1回のみ許される。フィールド競技ではエスコートとコーラーの最大2人がアシスタントにつくことができ、跳躍種目ではエスコートが助走の開始地点まで誘導し、助走方向などを指示、コーラーが声や手拍子で踏み切り位置を教える。1人が2役を兼ねてもよい。T/F12の重度弱視クラスはアシスタントとの競技が可能だが、T/F13の軽度弱視クラスではアシスタントなしの単独で競技を行う。
知的障害クラスは、障害の程度による細かいクラス分けはなく、「20」の1クラスだけとなる。
脳原性麻痺クラスのトラック競技では、選手はヘルメットをかならず着用し「レーサー」とよばれる競技用車いすを使用する。大きな車輪が二つと小さな車輪が一つついており、ハンドルやブレーキ、前輪をカーブなどで固定するトラックレバーなども装備されている。大きな車輪の最大直径は70センチメートル、小さな車輪は同50センチメートル、付属品を含めた高さは50センチメートル以内と決められている。競技用車いすは近年、カーボン繊維製やチタン製など軽量化が図られ、スピードを出しやすい構造のものが開発されているが、空気力学的に有利になるフードカバーなどの付属品やギアの使用は認められておらず、大きな車輪についているハンドリムを使って前進しなければならない。
車いすのスタートでは前輪がスタートラインに触れてはならず、スタートの合図はランナーと同じで、400メートル走までが「On your marks(位置について)」、「Set(用意)」から、800メートル走以上は「On your marks」の後、それぞれ選手の腕が確実に静止しているのが確認されて号砲となる。800メートル走以上のレースでは最初の50メートルまでに選手の大部分が転倒した場合は、スターターが選手を呼び戻して再スタートを行うことができる。レース中の追い越しでは、追い抜いた選手は安全を確保してインに戻る責任があり、追い抜かれている選手は外に膨らむことなくレーンを維持しなければいけない。前輪の中心の車軸がフィニッシュラインに到達したときがフィニッシュとなる。
投擲種目で座位競技者は、サークル内に設けられた投擲台を使って競技を行う。投擲台は各辺30センチメートル以上の四角形で水平または前方が高くなるように取り付けられ、高さは75センチメートル以内である。投げるときに体が浮かないようにベルトなどで固定し、上半身だけで投げる。投擲台には握り棒を取り付けてもよい。こん棒投げは、握力がなく、やりが握れない選手を対象にした種目で、重度の脳原性麻痺競技者と頸椎(けいつい)損傷競技者のF31、F32、F51が対象となる。こん棒は長さが35~39センチメートル、重さ397グラム以上のトックリ型で、木製の胴体部分に厚さ約1.3センチメートルの金属製の底部がついている。片手で握って投げるが、投げ方に制限はなく、やり投げのように投げても後ろ向きの姿勢から頭上越しに投げてもかまわない。
切断・機能障害クラスの走種目では競技用に改良された義足を装着して競技する。義足はおもにカーボン繊維製で板を曲げたような形をしており、地面からの反発力を推進力に変えて、スピードが出るようになっている。スターティング・ブロックの使用は任意で、片足だけで走ることは認められていない。選手は両足の長さが同じになるように義足を装着する。事前に最大身長を登録しなければならず、意図的に義足を長くすることは禁止されている。跳躍種目のT42~44クラス、T61~64クラスでは義足を着用する必要はなく、片足跳び(ホッピング)が認められている。走幅跳びでは跳躍中に義足が脱落した場合は、踏切板から義足が落下した痕跡(こんせき)の最短距離が記録となる。ただし、砂場の手前や外に落下した場合は無効試技となり、助走中の脱落は、制限時間内であれば、装着し直して再度助走を始めることができる。
参加者が少ない種目では複数のクラスを統合し、コンバインド種目として実施することもある。この場合はできるだけ公平に競技が行われるように、クラスごとに設定されたハンディキャップのような係数を使ってスコアやタイムが算出され、順位が決まる。
パラリンピックの陸上競技は、1960年の第1回ローマ大会から実施され、日本は1964年第2回東京大会から参加した。日本のメダル獲得の最多は1988年ソウル大会で金メダル12個、銀メダル6個、銅メダル14個である。しかし、2012年ロンドン大会、2016年リオ・デ・ジャネイロ大会は金メダルの獲得がなく、ロンドン大会は銀3個、銅1個で、リオ・デ・ジャネイロ大会は銀4個、銅3個であった。1994年からは障害者スポーツの単一競技大会としては最大規模となる世界パラ陸上選手権も開催されており、2021年の第10回大会(9月・神戸市)は約100か国から約200種目に1300選手の参加が見込まれている。
パラ陸上選手でも世界陸連が認め、参加標準記録などの出場資格を満たせばオリンピックへの参加が可能となる。2012年のオリンピック・ロンドン大会には両脚義足のオスカー・ピストリウスOscar Pistorius(南アフリカ。1986― )が男子400メートル走と1600メートルリレーに出場し大きな注目を集めた。また男子走幅跳びで8メートル48の世界記録をもつ片足義足のマルクス・レームMarkus Rehm(ドイツ。1988― )は2016年のオリンピック・リオ・デ・ジャネイロ大会への出場を希望したが、義足による公平性の証明が不十分として参加が認められず、論議をよんだ。
[中西利夫 2020年4月17日]
『日本パラ陸上競技連盟競技運営委員会編『世界パラ陸上競技連盟(WPA)競技規則及び規定 2018―2019 原文/日本語訳 対照版』(2018・日本パラ陸上競技連盟)』▽『日本パラ陸上競技連盟・日本盲人マラソン協会・日本知的障がい者陸上競技連盟監修『パラ陸上競技公式ガイド――よくわかるパラ陸上競技の世界 2018』(2018・日本パラ陸上競技連盟)』▽『日本陸上競技連盟編著『陸上競技ルールブック 2019年度版』(2019・ベースボール・マガジン社)』
改訂新版 世界大百科事典 「陸上競技」の意味・わかりやすい解説
陸上競技 (りくじょうきょうぎ)
人類の基本的な動作である走る,跳ぶ,投げるの要素をスポーツ化したもので,独立した多数種目を包含する競技。格闘技のように単に勝敗を争うのではなく,時間や距離などの記録への挑戦も含むところに特徴がある。近代陸上競技発祥の地イギリスやイギリス連邦諸国ではathleticsと称しているが,これがスポーツ,体育一般をさすこともあるため,アメリカ流のtrack and fieldを使うことが多い。ドイツ語のLeichtathletikに相当する。
歴史
起源
陸上競技が,完成された純粋なスポーツとして発達したのは18世紀以降であるが,その起源は遠く古代にさかのぼる。原始時代,人類が獲物を追って走り,跳び,槍や石を投げた動作が原形といえるが,競技としての陸上競技は,前776年にギリシアのオリュンピアで開かれた古代オリンピック第1回大会が記録に残っている。このときは直線の短距離競走(1スタディオン=オリュンピアでは約192m)だけが行われ,エリス出身のコロイボスが優勝した。古代オリンピックは,以後4年に1度のペースで実に1000年以上も続き,現在の陸上競技種目に相当するものが加わっていった。たとえば第14回大会(前724)には往復競走(2スタディオン)が加わり,さらに長距離競走(7~24スタディオン),五種競技(短距離,幅跳び,円盤投げ,槍投げ,レスリング)などが登場している。古代ギリシアのつぼ絵などから推察すると,幅跳びは石または鉛でつくったおもりを両手に握ってはずみをつける跳び方,円盤は石や青銅でつくったもの,槍は重心近くにつけた革ひもに指を通して投げるなど,現在と形は多少異なるものの,基本的には同じである。しかし陸上競技種目中心の古代オリンピックも,393年キリスト教を信じるテオドシウス1世によって廃止された。
近代陸上競技の発展
オリュンピアの会場も,その後2度の地震と洪水のため土に埋もれ去った。ローマ滅亡以後のヨーロッパは混乱状態のうえに,肉体を罪悪視するキリスト教の時代が続く。1154年にロンドンの広場で石投げや競走があったという記録も残っているが,これは戦闘の予備訓練であり,真のスポーツではなかった。
陸上競技がルール化され,近代的な形をとり始めるのはルネサンス以後である。イギリスでは上流階級の人たちが各自の馬丁に長距離を競走させ,賞金を賭けるという形で始まった。1720年には4マイル(約6400m)を走って1000ポンドの賞金をもらった馬丁の記録が残っている。こうしたレースは,当初こそ下層階級のスポーツとみられていたが,やがて上流階級の青少年にもランニングへの関心をあおるようになり,パブリック・スクールやカレッジの生徒たちに浸透していった。本格的な陸上競技会の始まりは,1864年の第1回オックスフォード対ケンブリッジの大学対校競技会だといわれる。そして66年にはイギリス陸上選手権大会を開催,この大会で厳格なアマチュア規則を制定したため,賞金目当ての職業ランナーなどが姿を消した。さらに80年には世界初の国内陸上競技の統轄団体としてイギリス陸上競技協会Amateur Athletic Association(AAA)が誕生した。イギリスで生まれた近代陸上競技は,軍人や留学生などを媒介としてアメリカ,カナダ,フランス,ドイツなどへと広がった。
オリンピックと陸上競技
古代オリンピックの復活をめざして1896年アテネで始まった近代オリンピックの第1回大会には,水泳,テニス,体操など9競技が行われたが,中心となったのは古代オリンピックでも主要部分をなしていた陸上競技だった。開会式後の最初の種目が陸上競技の100mだったことも象徴的である。以後陸上競技はオリンピックが隆盛を重ねるごとに参加国,選手数を増やし,メイン・イベントとしての地位をますます固いものにしていった。オリンピックにからんで陸上競技の国際組織づくりも着々と進み,1912年国際陸上競技連盟International Association of Athletics Federations(IAAF)が結成され,第1次世界大戦後の21年には国際競技規則を制定,世界記録の公認制度も決定した。第2次世界大戦後も陸上競技はオリンピックのメイン・イベントとして発展を続け,83年には世界選手権を新設,第1回大会をフィンランドのヘルシンキで開催した。以後4年ごとに開催していたが,91年の第3回東京大会以降は2年ごとに変わった。発足当時17ヵ国だった国際陸連加盟国は現在209ヵ国・地域(1997)で,国際スポーツ界最大の組織の一つとなった。
技術と用具の進歩
陸上競技の記録も年々やむことのない進歩を遂げた。その大きな要因としては,科学技術の進歩に伴う競技施設や用具の改良,トレーニング技術の向上などが挙げられる。
競技場の走路についていえば,当初は校庭などの地面が使われていたが,やがてコークスを敷きつめたシンダートラックcinder track,そして雨の日でも水はけの良い煉瓦の粉状の人工土を敷いたアンツーカEn-Tout-Cas(商標)と変化していった。1968年のメキシコ・オリンピック大会から登場したタータンTartan(商標)は革命的な変化をもたらした。合成ゴムを流し込んで固めたこのトラックは,どんな雨の日でも競技を可能にする全天候型で,さらにその弾力性ゆえに競走種目や跳躍種目の記録が大幅に向上するという副産物をもたらした。用具の進歩では棒高跳びのポールが挙げられる。木から始まって日本製の竹,そして戦後はスチールと変化していったポールは,1960年代に出現したグラスファイバー・ポールによってイメージを一変した。従来は軽くて折れにくいポールをいかに探すかが主眼だったが,ガラスの繊維でつくったこのポールは,その弾力性を利用しての記録づくりをはじめからめざしたものだった。しかし施設や用具の力を借りて記録を伸ばすのは邪道だとする批判もある。
一方,トレーニング技術,競技技術の進歩によっても,記録は着実に伸びていった。たとえば第2次世界大戦後出現したスピード養成主眼のインターバル・トレーニングは,長距離に革命的な進歩をもたらし,E.ザトペック(チェコ),V.P.クーツ(ソ連)などの大選手を生んだ。走高跳びも当初は重心を最も高く上げる正面跳びだったが,バーの上で体を倒すウェスタンロール,さらにバーの上で腹ばいになるベリーロールと変化した。さらに68年のメキシコ・オリンピック優勝者フォスベリーRichard Fosbury(アメリカ)は,背中でバーを越し,頭からピットに落ちる背面跳びを考案,結果的にはこれが最も合理的であることがわかり,世界記録は大きく向上した。しかし,これも棒高跳びの場合と同様,かつて硬い砂場だった落下場所がソフトラバーを敷き詰めた柔らかいピットに変わったという着地面の改良がなければ実現しなかったことであろう。1950年代に砲丸投げで後ずさりにステップする投法を考え出したオブライエンW.P.O'Brien(アメリカ)や,ハンマー投げでの4回転ターンの技術開発などの成果は記録向上に多大の貢献をした。
タイムの計測,距離の測定も驚異的な進歩を遂げた。かつてタイムの計測といえば,ゴールに居ならぶ計時員がスターターのピストルから上がる煙を見てストップウォッチを押し,ゴールのテープを切った瞬間止めるという手作業(手動計時)で行い,計時も10分の1秒単位であった。ところが1964年の東京オリンピック大会から全自動電気計時による写真判定が採用された。スターターのピストルが撃たれると同時に電気で連動して時計が動き始め,決勝線では,100分の1秒単位の目盛が記された写真の画面に競技者の走姿が写るしくみとなっている。自動タイム測定装置でタイムと順位は即座に出るが,接戦で判定が微妙なときは,審判はこの写真を見て順位とタイムを決める。最近では,オリンピックなど公式の大会のすべてにこの電気計時が採用されている。投てき種目の距離測定も,従来は巻尺で投げた地点から落下地点までを計っていたが,東京オリンピック大会では全距離を計測せず,途中のポイントから落下地点までを短い巻尺で計測するカンタブリアンシステムが採用された。また72年のミュンヘン大会では落下地点にプリズム反射鏡を置き,スタンドから望遠鏡つきの計測器で三角測量形式にコンピューターで距離を測るなどの新技術が開発された。走幅跳び,三段跳びでも砂場の横に平行に測定器を置き,ただのぞくだけで距離が測定できる。このような技術や用具の進歩とともに,欧米を中心に冬季にも室内競技会が可能となり,競技者は年間を通じて競技を行うようになっている。
女子種目の進展
古代オリンピックでは女子の参加は禁止されていたが,近代オリンピックでの女子の参加は1928年のアムステルダム大会からだった。当時は男子の22種目に対し女子はわずか5種目。しかも800mはレース後選手が次々と倒れたため,60年のローマ大会に800mが復活するまで女子の種目は200mの距離が最高とされた。しかし第2次世界大戦後の女子の体力向上は目覚ましく,1960年代から80年代にかけて長距離種目が相次いで増え,84年のロサンゼルス・オリンピック大会ではマラソンまでが新種目として登場した。最近では男子は24種目でほとんど増えていないのに対し,女子は88年ソウル大会で1万m,92年バルセロナ大会で10km競歩(2000年シドニー大会から20km競歩),96年アトランタ大会で三段跳びと5000m,2000年シドニー大会で棒高跳びとハンマー投げ,08年北京大会で3000m障害が追加され,計23種目となった(表1)。
日本の陸上競技
日本に陸上が伝わったのは明治時代で,競技会としては1874年東京の海軍兵学寮で開かれたものが最初である。イギリスから指導者を招いての運動会だったが,短距離走,走幅跳び,砲丸投げなどの種目があった。その後78年には札幌農学校で,83年にはイギリス人のF.W.ストレンジによって東京大学でそれぞれ第1回の運動会が開かれた。以後東大の運動会は年々盛んとなり,一高,学習院,早大,慶大など他校の選手を招く競技会も行うなど,東大が陸上競技の中心となった。この東大運動会で好記録を出した藤井実(東大)が大きな話題となった。1911年には大日本体育協会(現在の日本体育協会)が組織され,オリンピック予選会が開かれた。これが大学を離れて開かれた最初の陸上競技会だった。12年のストックホルム・オリンピック大会には短距離の三島弥彦,マラソンの金栗四三の陸上選手2人が参加したが,結果は惨敗だった。しかしこれ以後,陸上競技は日本でもオリンピックの中心を占めることになった。13年には第1回の日本陸上競技選手権大会が開かれた。
1924年のパリ・オリンピック大会では織田幹雄が三段跳びで6位に初入賞。25年には日本陸上競技連盟が創設され,28年のアムステルダム・オリンピック大会では織田が三段跳びで待望の金メダルを獲得,陸上競技は黄金時代に入っていった。ことに三段跳びでは織田に続き,南部忠平(1932年ロサンゼルス大会),田島直人(1936年ベルリン大会)が金メダルをとり,オリンピック3連勝,女子ではアムステルダム大会の800mで人見絹枝が2位に入ったほか,棒高跳びの西田修平,大江季雄,三段跳びの原田正夫,大島鎌吉など多くのメダリストが輩出した。第2次世界大戦後はしばらく低迷が続いたが,やがてマラソンを中心に活躍が見られるようになった。オリンピックのマラソンでは男子は64年の東京大会で円谷幸吉(3位),68年メキシコ大会の君原健二(2位),92年バルセロナ大会の森下広一(2位)の3人がメダルを獲得した。女子では有森裕子が92年バルセロナ大会(2位)と96年アトランタ大会(3位)で連続メダリストとなり,2000年シドニー大会で高橋尚子,04年アテネ大会で野口みずきがいずれも優勝し,オリンピック2連勝を果たした。また世界選手権でも男子は谷口浩美が91年の第3回大会,女子は93年の第4回大会で浅利純子,97年の第6回大会で鈴木博美が優勝した。また,これまで外国選手の前に問題にならなかったトラック種目でも97年の世界選手権1万mで千葉真子が3位,96年のアトランタ・オリンピックでは5000mで志水見千子が4位に入賞するなど最近は女子長距離選手の躍進が特に目だっている。
陸上競技の種目
大別すると,(1)競技場内の走路(トラック)を使ってタイムを競うトラック競技,(2)走路以外のフィールド上で距離や高さを競うフィールド競技,(3)それ以外の競歩,クロスカントリー・レース,道路競走となる。トラック競技とフィールド競技の複数種目で得点を争うものを混成競技という。
トラック競技
ピストルの発射音でスタート,競技者の胴体(頭,首,腕,手,脚,足は含まれない)がフィニッシュラインの垂直面に到達したところまでのタイムを測定,順位を決める。400mまでの競走はスターティング・ブロックを用いるが,スターターのピストルが鳴る以前に競技者の足がブロックを蹴ると,フライング(不正出発)とわかるようにセットされている。現在は2回目にフライングを犯した選手が失格となる。種目としては,競走競技,ハードル競走,障害物競走,リレー競走がある。トラックは通常1周400mで,レーンの幅は日本では1.25mと統一されており,400mまでのレースはすべて各人の決められたレーン内を走らなければならない(セパレート)。200m,400m,800m,400mハードル,4×100mリレー,4×400mリレーは階段式スタートで,800mは最初の120mまでセパレート,あとはオープンとし,4×400mリレーでは第1走者がセパレート,第2走者もバックストレートに入るまでセパレートであとはオープンとなる。また200mまでのすべてのレースでは追風が平均秒速2mを超えた場合,記録は公認されない。タイムの測定は(1)手動計時,(2)電気計時の二つがある。手動計時では1人の競技者のタイムをとるために3人の計時員を置く。3人の時計のうち2人が一致したときはそのタイム,3人とも違った場合はその中間のタイムが正式計時となる。時間はすべて10分の1秒単位で計時される。国際競技会や国内選手権クラスの大会ではほとんどの場合電気計時を採用している。この場合,1万m以下のすべてのレースでは,100分の1秒表示の全自動電気計時装置により計時され,100分の1秒単位で表示される。競技場外で行われるレース(たとえばマラソン)はすべて100分の1秒単位で計時し,秒単位に繰り上げられる。
競走競技running
短距離sprintingとして100m,200m,400mなど,中距離middle distanceとして800m,1500m,3000mなど,長距離long distanceとして5000m以上の競走がある。100mは直走路を走り,スタート技術の巧拙が大きく影響する。
ハードル競走hurdles
男子110m,400m,女子100m,400mなどがある。ハードルは金属製の支柱に木製の横木を渡したものが多く,10個を跳び越す。高さは競技によって異なる。故意でなければハードルを倒しても失格ではないが,足が外側にはみ出て横木より低いところを通過すると失格となる。
障害物競走steeplechase
男女とも3000mなど。3000mの場合,トラック1周上に,男子が高さ91.4cm,女子が76.2cmの障害物4個と水濠(深さ70cm)1個を設け,7周する間に障害物を28回と水濠を7回跳び越える。1周の4番目に水濠を越えるようにするが,水濠はトラックの内,外どちらに設置してもよい。水濠の手前にも障害物が置かれ,競技者は水濠を越えるか中に入って進まなければならない。
リレー競走relay
男女とも4×100m(400m),4×400m(1600m)など。いずれも4人の走者がバトンをパスしながら継走する。バトンは必ず手で持ち運び,落としたときは落とした走者が拾わなければならない。他のレーンに落とした場合でも他の走者を妨害せず,拾い上げて自分のレーンに戻った場合は失格とならない。バトンの受渡しは発走線の前後10m,計20mのテークオーバーゾーン内で完了しなければならない。
フィールド競技
男女とも跳躍競技(走高跳び,走幅跳び,三段跳び,棒高跳び)と投てき競技(砲丸投げ,円盤投げ,ハンマー投げ,槍投げ)に分かれる。
跳躍競技jumping
走幅跳びlong jumpと三段跳びtriple jumpは水平方向の距離を競う種目。距離は踏切板の砂場側の線(踏切線)と着地点までの距離を計測する。競技者には3回の試技が許され,8位(ベストエイト)まではさらに3回の試技を許される。助走の長さに制限はないが,踏切板をはみ出した場合は無効試技(ファウル)となる。両種目とも2mを超える追風がある場合,記録は公認されない。三段跳びは踏切板で第1歩(ホップ)を踏み,同じ足で第2歩を着地,さらにその足で跳躍(ステップ)に移り,反対側の足で第3歩を着地して最後の跳躍(ジャンプ)に入るため,かつてはhop, step, and jumpといわれた。跳躍中踏み切った足でない方が地面に触れると無効試技となる。走高跳びhigh jumpと棒高跳びpole vaultは,垂直方向,つまり高さを争う種目で,一つの高さに対し競技者は3回の試技が与えられる。3回とも失敗すれば次の高さへの権利を失い,成功すれば次の高さへの挑戦権を得る。同記録の場合は,その高さの試技数が最も少なかった者,それでも決まらないときは同記録に至るまでの全体の無効試技数が最も少ない者が上位になる。助走の長さに制限はない。バーを落とすほか,走高跳びではバーの下をくぐりぬけると無効試技となり,棒高跳びではポールを箱に突っこんだあと両足が地面を離れたら,体がバーまで届かなくても無効試技に数えられる。棒高跳びのポールの材質や長さ,太さに制限はない。試技中にポールが折れたときは無効試技とはならず,やり直しができる。
投てき競技throwing
投げられた物体の到達距離を競う。砲丸投げshot putは肩から片手だけで投げる。構えたときは,砲丸をあごにつけるか,まさにつけようとする状態を保持しなければならない。砲丸の重量は男子7.260kg,女子4kg以上,直径男子110~130mm,女子95~110mmである。円盤投げdiscus throwは木製の胴に金属製の輪をつけたものを片手で投げる。円盤の重量は男子2kg,女子1kg以上,直径男子219~221mm,女子180~182mmである。ハンマー投げhammer throwは金属球に鋼鉄線をつなぎ,その端のハンドルを両手に持って振りまわし,遠心力を利用して投げる。ハンマーの全長は男子117.5~121.5cm,女子116.0~119.5cm,総重量は男子7.260kg,女子4kg以上。砲丸投げ,円盤投げ,ハンマー投げともコンクリート,アスファルトなどでつくられたサークルから投げ,前方左右34.92度の範囲に落ちたものを有効とする。サークルは砲丸投げとハンマー投げが直径2.135m,円盤投げは直径2.5m。円盤投げ,ハンマー投げは危険防止のため,U字形のかこい(金網)を設ける。槍投げjavelin throwは,金属製の柄の先端に金属製の穂先が固定された槍を片手で投げる。その場合,必ず握りの部分を持って助走し,肩または投げる方の腕の上で投げる。振り回したり,回転したりして投げてはならない。前方29度が有効角度で,その範囲内で穂先から落下しないと記録は認められない。槍は全長が男子260~270cm,女子220~230cm,重量が男子800g以上,女子600g以上。投てき競技は,走幅跳び,三段跳びと同様3回の試技が許され,上位8位までがさらに3回の試技を許される。記録の測定にあたっては,いずれも1cm未満を切り捨てる。
競歩race walking
競歩の定義は,いずれかの足が,常に地面から離れないようにして前進することをいう。したがって,競技者の前足は後足が地面から離れる前に必ず地面に接していなければならない。また,支持脚は地面に垂直になったときに,少なくとも一瞬の間はまっすぐになっていなければならない。つまり,その瞬間,支持脚のひざは曲がっていてはいけない。一般に3000m~50kmの距離で行われ,トラックまたは道路を用いる。なお,オリンピックの20km競歩,50km競歩は道路競技であるため,世界公認記録とはならず,〈世界最高〉などと表現する。
クロスカントリー・レースcross-country
丘や野山をかけめぐる競走。トラックシーズンが終わった冬季に長距離選手がトレーニングの一つとして行うことが多い。
道路競走road running
一般の道路を走る競技。マラソンや日本の駅伝競走がこれにあたる。道路競走は下り坂の多い一本道コース,追風の多いコースあるいはその逆など,道路の状況,コースの選び方など条件が一定していないため記録の公平な比較ができず,世界記録としては公認しない。〈世界最高〉などの表現で競技場内でのレースの公認記録とは別扱いにしている。
混成競技
トラック競技とフィールド競技を組み合わせた複数種目を一人で行い,その成績を点数に換算して合計点を争う競技。走る,跳ぶ,投げるのオールラウンドの能力が要求されるため〈キング・オブ・スポーツ〉ともいわれている。現在のオリンピックでは男子は十種競技decathlon(第1日=100m,走幅跳び,砲丸投げ,走高跳び,400m。第2日=110mハードル,円盤投げ,棒高跳び,槍投げ,1500m),女子は七種競技heptathlon(第1日=100mハードル,走高跳び,砲丸投げ,200m。第2日=走幅跳び,槍投げ,800m)を記載の順番に行う。
混成競技の起源は古く,古代オリンピックでは男子のみだったが五種競技pentathlonが,短距離,幅跳び,円盤投げ,槍投げ,レスリングの5種目で行われていた。近代オリンピックでも1912年のストックホルム大会からすでに十種競技として行われている。64年の東京オリンピックからは女子の五種競技pentathlon(80mハードル(1972年から100mハードル),砲丸投げ,走高跳び,走幅跳び,200m)が登場。その後女子は体力の向上に伴い,84年ロサンゼルス大会からは2種目を増やし七種競技に変更された。
いずれも,記録に応じて点数を列記した混成競技採点表に従い,各種目の合計点で順位を決める。走幅跳びと投てき種目は3回だけの試技が許され,そのうちのベスト記録が採用される。棒高跳び,走高跳びは一つの高さに3回ずつの試技が許される。フライングは2回目に失格となる。200mまでの種目のうち,どれかで追風が平均秒速4mを超えた場合,全体の記録も公認されない。
執筆者:加藤 博夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陸上競技」の意味・わかりやすい解説
陸上競技
りくじょうきょうぎ
track and field athletics
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「陸上競技」の意味・わかりやすい解説
陸上競技【りくじょうきょうぎ】
→関連項目三段跳び|人見絹枝|陸上競技場|リレーレース
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...