関連語
精選版 日本国語大辞典 「雀」の意味・読み・例文・類語
すずめ【雀】
- 〘 名詞 〙
- ① ハタオリドリ科の鳥。全長約一四センチメートル。頭は茶褐色、背面は褐色で黒色の縦斑(じゅうはん)があり、顔と腹面は灰白色。頬と喉に黒斑がある。人家付近にすみ、屋根がわらの下や石垣に枯れ草やわらで巣をつくる。群をなすことが多く、秋にイネなどの穀物に害を与えるが、繁殖期には害虫を捕食する。ヨーロッパ・アジアに広く分布し、日本各地で最もふつうにみられる鳥で、昔から多くの物語に登場し親しまれる。二〇世紀になって北アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどに輸入されて各地で増えている。スズメの近縁種は一四種が旧大陸に分布しており、ヨーロッパで人家付近にふつうにいるのはイエスズメである。
- [初出の実例]「河鴈を岐佐理持〈岐より下の三字は音を以ゐよ〉と為(し)、〈略〉雀(すずめ)を碓女(うすめ)と為、雉を哭女(なきめ)と為、如此(かく)行ひ定めて」(出典:古事記(712)上)
- 「はるさめのあがるや軒になく雀〈羽紅〉」(出典:俳諧・猿蓑(1691)四)
- ② ( 雀のさえずりの騒がしいのにたとえて ) 多弁な人をいう語。おしゃべり。
- [初出の実例]「見とむない・ととさしをいてすずめどの」(出典:雑俳・軽口頓作(1709))
- ③ 事情に精通していて、それをさかんにしゃべる人。
- [初出の実例]「江戸見物には雀が一羽付き」(出典:雑俳・柳多留‐二三(1789))
- ④ 紋所の名。①を図案化したもの。雀の丸、二羽雀、竹輪に三羽雀、ふくら雀など。
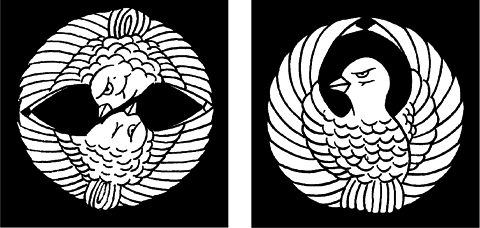 二羽雀@雀の丸
二羽雀@雀の丸
- ⑤ 辻君など、下等な遊女をたとえていう語か。
- [初出の実例]「西の京行けば、すずめ歯黒め布穀鳥(つつどり)や、さこそ聞け、色好みの多かる世なれば、人は響(とよ)むとも、麿だに響まずは」(出典:梁塵秘抄(1179頃)二)
- ⑥ 元祿時代(一六八八‐一七〇四)京坂地方の芸妓が結った髪型。〔戯場訓蒙図彙(1803)〕
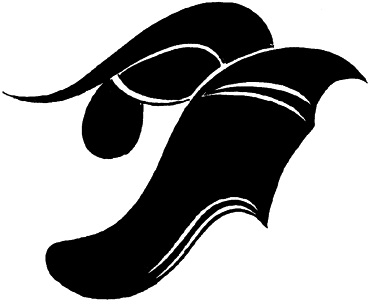 雀⑥〈戯場訓蒙図彙〉
雀⑥〈戯場訓蒙図彙〉
- ⑦ 「すずめがた(雀形)」の略。
- [初出の実例]「仲人は雀(すずメ)を出すがいとま乞」(出典:雑俳・川柳評万句合‐明和六(1769)義一)
- ⑧ 燗徳利(かんどくり)の一種。素焼で雀や鳩に似せた形のもの。
- [初出の実例]「『さ、あけないま』といっておじさんが『すずめ』を持ちあげる」(出典:梨の花(1957‐58)〈中野重治〉一)
雀の語誌
( 1 )「本草和名」には「和名 須々美」とあり、そのほか「観智院本名義抄」「色葉字類抄」にも「ススメ」「ススミ」の両訓があるから、古くはスズミの形も存在したと思われる。
( 2 )その鳴き方や動作・営巣などによる吉凶占いや天候占いは古くから各地に伝わっている。食用としても珍重された。
( 3 )魚・虫・植物などの名に「すずめ…」あるいは「すずめの…」(「すずめ鯛」「すずめ蛾」「すずめ瓜」「すずめの帷子」など)とつくものがあるが、これは「小さい」という意味を表わす場合と、雀の姿や特徴との類似からきている場合がある。
すずみ【雀】
- 〘 名詞 〙 「すずめ(雀)」の変化した語。
- [初出の実例]「北海の浜に、魚死にて積めり。厚さ三尺許り。其の大きさ
 (えひ)の如くにして雀(ススミ)の啄(くち)針の鱗あり」(出典:日本書紀(720)斉明四年是歳(北野本訓))
(えひ)の如くにして雀(ススミ)の啄(くち)針の鱗あり」(出典:日本書紀(720)斉明四年是歳(北野本訓))
- [初出の実例]「北海の浜に、魚死にて積めり。厚さ三尺許り。其の大きさ
しじめ【雀】
- 〘 名詞 〙 「すずめ(雀)」の変化した語。
- [初出の実例]「畑ふに黍はむしじめししめきてかしましきまで世をぞ恨むる」(出典:散木奇歌集(1128頃)雑上)
普及版 字通 「雀」の読み・字形・画数・意味
雀
人名用漢字 11画
[字訓] すずめ
[説文解字]

[甲骨文]


[金文]

[字形] 形声
声符は小(しよう)。〔説文〕四上に「人に依る小鳥なり。小隹(すい)に從ふ。讀むこと
 と同じ」とあり、
と同じ」とあり、 (爵)字条五下に
(爵)字条五下に が雀の象形であるという。
が雀の象形であるという。 は酒爵の象形であるから、その字を雀の意に用いるのは同声の仮借。卜文の字形は隹の上に小点を加えており、小の声を示したものか、字の立意がなお明らかでない。
は酒爵の象形であるから、その字を雀の意に用いるのは同声の仮借。卜文の字形は隹の上に小点を加えており、小の声を示したものか、字の立意がなお明らかでない。[訓義]
1. すずめ。
2. 雀いろ、雀頭のいろ。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕雀 楊氏
 語抄に云ふ、雀、須々米(すずめ)(箋注)本
語抄に云ふ、雀、須々米(すずめ)(箋注)本 和名に云ふ、雀卵、和名、須々美(すずみ)〔名義抄〕雀 スズメ・スズミ 〔字鏡集〕雀 スズメ・ヒバリ・コトリ
和名に云ふ、雀卵、和名、須々美(すずみ)〔名義抄〕雀 スズメ・スズミ 〔字鏡集〕雀 スズメ・ヒバリ・コトリ[語系]
雀・
 tzi
tzi kは同声。雀はおそらくその鳴き声を写した語。国語の「すずめ」と同様である。
kは同声。雀はおそらくその鳴き声を写した語。国語の「すずめ」と同様である。[熟語]
雀眼▶・雀穴▶・雀釵▶・雀耳▶・雀児▶・雀舌▶・雀鼠▶・雀台▶・雀斑▶・雀瘢▶・雀弁▶・雀盲▶・雀躍▶・雀踊▶・雀羅▶・雀立▶
[下接語]
 雀・雲雀・燕雀・簷雀・寒雀・
雀・雲雀・燕雀・簷雀・寒雀・ 雀・金雀・孔雀・群雀・黄雀・朱雀・竹雀・鳥雀・銅雀・暮雀・麻雀・野雀・幽雀・鸞雀
雀・金雀・孔雀・群雀・黄雀・朱雀・竹雀・鳥雀・銅雀・暮雀・麻雀・野雀・幽雀・鸞雀出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
動植物名よみかた辞典 普及版 「雀」の解説
雀 (スズメ)
動物。ハタオリドリ科の鳥
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
関連語をあわせて調べる
日本の年中行事。年末に天井や壁にたまった煤を取除き大掃除をすること。近年は正月休みに入る 12月 29日とか 30日が多いが,伝統的には 12月 13日に行なった。この日は正月を迎えるための準備を開始...





