日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本建築」の意味・わかりやすい解説
日本建築
にほんけんちく
日本建築は伝統的には中国建築の一支流として位置づけられ、木造建築が主流を占める。したがって柱や梁(はり)など直線的な材料で組み立てた構造となるが、中国建築の多くが木材の露出部を彩色するのに対し、日本建築では白木のままを基本とするなど、中国とは異なる特質を有している。
一方、西欧諸国など外国の建築はれんが造や石造のものが多く、それらは壁を主体とする面的な構成をとるのに対し、日本建築では線的な構成となる。入口や窓などの開口部を例にとれば、日本建築ではその上部に楣とよぶ水平材を置くが、外国のそれでは湾曲するアーチでせり上げるのが通例である。いわば日本建築は組立て式であり、西欧諸国の建築は積み上げ式である。日本は古くから建築用木材に恵まれていたが、巨材を挽(ひ)く鋸(のこぎり)がなく、製材上の工具に難があったため、もっぱら木目(もくめ)に楔(くさび)を打ち込んで裂き割る方法がとられた。そのため、平滑に裂けやすく耐用年数も長いヒノキが多用された。室町時代中期に大鋸(おおが)が用いられるようになり、各種木材の製材が容易になったが、それまではほとんどの用材がヒノキで占められていた。マツは中世以降、各所で多用されるようになったが、スギは軟らかいため主要材とはならず、近世以降に住宅の用材として利用されている。
[工藤圭章]
日本建築の変遷
先史時代
日本の建築もまず住居から始まるが、先土器時代は岩陰や洞穴が住居に利用されており、木材を一部組み立てたような住居は縄文早期の竪穴(たてあな)住居に初例がある。これは各地でつくられたが、地面に穴を掘り、その上に屋根をかぶせた単純なものであった。
竪穴住居に次ぐ建築としては、弥生(やよい)前期に出現する高床(たかゆか)倉庫がある。竪穴と違って高床の建築は地上に高くつくられるので、建物内は乾燥し、倉庫のみならず、弥生後期には住居としても建てられるようになり、古墳時代へと至る。弥生時代の高床倉庫は、伝香川県出土「袈裟襷文銅鐸(けさだすきもんどうたく)」(国宝)の棟持柱(むなもちばしら)のある印刻や、奈良県田原本町唐古(からこ)遺跡出土土器の篦書(へらがき)などによりその形が知られる。
一方、古墳時代の高床建築は奈良県河合(かわい)町佐味田(さみだ)宝塚古墳出土の家屋文鏡に図示されている。この鏡は4世紀後半のもので、高床の一つは屋根が切妻造(きりづまづくり)の倉庫、いま一つは入母屋造(いりもやづくり)の住居を示している。このほか入母屋造の竪穴住居や平地住居も表現されており、後者はおそらく掘立て柱の住居と考えられる。
古墳時代の建築では、奈良県天理市東大寺山古墳出土の環頭大刀(かんとうのたち)の柄頭(つかがしら)が竪穴住居を表しており、また、各種の建物の形式は家形埴輪(はにわ)によって知られる。これらは大別すると住居と倉庫に分かれるが、住居でも格式の高いものは棟に鰹木(かつおぎ)をのせている。また、破風(はふ)を棟上まで延長したような千木(ちぎ)や、垂木(たるき)を棟で交差したような千木が表現されたものもある。
竪穴住居を復原した例は静岡市の登呂(とろ)遺跡など各地にみられるが、これらの構造については、江戸時代の冶金(やきん)書『鉄山秘書』に記述されている中国地方の砂鉄精錬の高殿(たたら)とよばれる小屋の構造が参考にされている。
高床倉庫については登呂遺跡や静岡県伊豆の国市山木遺跡から構造部材が出土し、また、愛媛県松山市古照(こでら)遺跡、福岡市湯納(ゆのう)遺跡、三重県津市納所(のうそ)遺跡などでも新例が知見されている。竪穴住居や高床倉庫の柱は地面に穴を掘り、柱根元を埋め込んで立てた掘立て柱で、根元が土で固められるため、独立した柱でも固定される。日本の建築では、古くは掘立て柱が主流で、屋根も草葺(くさぶ)きの簡単なものであった。『古事記』には、志幾(しき)の大県主(おおあがたぬし)の住宅が鰹木を棟にあげているのを雄略(ゆうりゃく)天皇がみつけて、天皇の御舎(みあらか)に似ていると怒り、焼き払うように命じたことが記されているが、群馬県伊勢崎(いせさき)市茶臼山(ちゃうすやま)古墳から出土した8棟分の家形埴輪は、主屋(おもや)が切妻造の屋根に鰹木を飾り、ほかに切妻造の付属屋2棟と小屋1棟、切妻造の高床倉庫3棟、寄棟造(よせむねづくり)の高床倉庫1棟からなる。鰹木のある住居はまさに宮殿であり、これらの埴輪群を通して前方後円墳に葬られた当時の豪族の家屋構成がうかがわれて興味深い。
日本の神社建築は、このような伝統を継いだものと思われる。古代の人々は、神が降臨する場所を特異な地形地物に求めて、そこを神の依代(よりしろ)として崇(あが)め、世襲された宝物を祖神の霊代(たましろ)として祀(まつ)り、それを格納する倉庫が神殿に変化したのである。そのため高床建築の形をとり、切妻造として、棟上には宮殿に倣って鰹木が飾られた。御舎は御在所(みありか)、宮は御屋(みや)、祠(ほこら)は穂倉(ほくら)の転訛(てんか)したものという。こうしてみると、神の御在所となる神殿は、まさに御屋と穂倉の合成されたものといえよう。
[工藤圭章]
飛鳥・奈良時代
6世紀中ごろの仏教伝来後、本格的な寺院建築として飛鳥寺(あすかでら)が592年(崇峻天皇5)に起工された。この工事にあたっては百済(くだら)から寺工が来日しており、在来の掘立て柱の建物とはまったく違った、基壇を築き礎石を据えた上に柱を立てる礎石建ちの工法がとられた。柱の上には複雑な組物がのって桁(けた)を受け、さらに屋根には瓦(かわら)が葺かれ、加えて天空高くそびえる仏塔も建立された。それは従来の直線的な造形の素朴な建築に比べると、非常な技術的格差であり、飛鳥の人々はこの想像もできなかった建物の出現をみて、仏教建築のすばらしさに驚嘆したに違いない。日本の正統的な仏教建築は、この飛鳥寺の堂塔をもって嚆矢(こうし)とし、従来の日本の建築様式に大陸の建築様式が加えられることになった。今日では飛鳥寺の外観なども明らかでないが、現存する法隆寺西院伽藍(さいいんがらん)の前駆的なものが飛鳥寺であったと推定されている。
法隆寺西院伽藍の建築の特徴は、俗に徳利(とくり)柱とよばれる胴膨らみのある柱、雲斗栱(くもときょう)の組物、そして隅(すみ)組物は一方向だけ突出し、軒は一軒(ひとのき)で、高欄の中備(なかぞなえ)には人字形(にんじがた)の割束(わりづか)が用いられるなどで、後世のものとはまったく異質の様式をもつ。これは魏晋(ぎしん)南北朝など中国の古いいろいろの建築様式が朝鮮半島を経由する間に混合して伝わり、飛鳥時代の日本で、それに新しい様式が付加したものと解釈されている。ここでいう新様式とは、飛鳥寺の建築に始まった飛鳥様式が、6世紀末から7世紀にかけて技術的に発展し、丸垂木(まるたるき)から角(かく)垂木へと変化し、隅扇(すみおうぎ)垂木が指垂木へと移行したような構造的進歩をさす。このころ、すでに飛鳥様式と異なる大陸の隋唐(ずいとう)の建築様式が日本に入っていたが、法隆寺は聖徳太子ゆかりの寺として、基本的には旧様式の飛鳥様式を踏襲したと考えられる。
新しい大陸様式である隋唐の建築様式は、川原寺(かわらでら)の建築あたりから導入されたと考えられる。川原寺は積極的に中国文化を取り入れた天智(てんじ)天皇(在位661~671)が官の大寺(だいじ)として建立した寺院で、当時これと並行して罹災(りさい)した百済大寺(くだらだいじ)の再建も行われており、新しい様式が導入される素地があった。両寺とも現存しないので不明の点が多いが、現存する薬師寺東塔(730)によって当時の建築を類推できる。すなわち、薬師寺は初め藤原京につくられ、710年(和銅3)の平城京遷都とともに他の大寺とともに新都に移されたが、その際旧藤原京の伽藍をそっくり再現したのであった。
8世紀になると、都は藤原京から平城京へと移って造宮造寺が盛んになり、官の組織として造宮省や造寺司(ぞうじし)が設置され、建築工事が発展する。藤原宮以前の宮殿建築は在来の掘立て柱建築であったが、藤原宮では宮城を画する門や、国政の中心である朝堂院の一郭は大陸の建築様式を取り入れて礎石建ち、瓦葺きの建築となった。仏教建築とともに渡来した大陸の建築様式は、宮殿建築にも適用されるようになったが、平城宮のように宮城内に多数の建物を配するには、すべて礎石建ちとするのは不可能で、天皇の居所の内裏(だいり)は伝統を重んじて掘立て柱の建物とし、官衙(かんが)の建物もほとんど掘立て柱の在来工法が踏襲されている。寺院でも伽藍中枢部は礎石建ちであったが、付属建物は掘立て柱で、いわばモニュメンタルな建物が礎石建ち、瓦葺きとして建造された。
奈良時代には、また新しい建築様式が導入されている。たとえば奈良盛期の遺構である唐招提寺(とうしょうだいじ)金堂の場合、軒を受ける組物の三手先(みてさき)斗栱の二手目が横に連結され、また軒下は横の連結材(支輪桁(しりんけた))を利用して小天井と支輪が張られるなど、それまでの建築とは明らかに異なった形式をみせている。奈良時代の造寺は前記のとおり官の組織によって行われたため、この新しい建築様式への一元化が進んだ。『続日本紀(しょくにほんぎ)』には大安寺の建設に携わった僧道慈が建築の技術に優れていたことが記されており、道慈は入唐(にっとう)修業中に建築技術を修得したものと思われる。奈良時代から一元化された建築様式は、こうした入唐僧によってもたらされ、それが国分寺の建設を通して各地に伝わったものとみられる。
ところで、奈良時代には、一方において和風化が促進されるようになった。すなわち、仏教建築は本来礎石建ちで屋根は瓦葺き、床(ゆか)は土間であったが、東大寺法華堂(ほっけどう)にみられるように、床を板張りとした建物が出現し、屋根も杮葺(こけらぶ)き、檜皮葺(ひわだぶ)きの仏堂が多くなった。とくに山地に営まれる仏堂には、このような和風化されたものが多かったようである。また法隆寺東院伽藍のように、中心の堂である夢殿と、講堂に相当する伝法堂が礎石建ちの瓦葺きで、他の回廊や七丈屋(しちじょうや)は掘立て柱で檜皮葺きの建物として建てられるなど、和風と大陸様式の折衷構成をとるものもあった。
仏教の儀式も大陸伝来のものに従っていたが、やがて日本式の礼法によるようになり、礼拝(らいはい)空間に板敷きが求められた。また本来、仏堂は仏だけの場、いわば仏を祀る大形の厨子(ずし)的な扱いがなされていたが、仏を礼拝するための礼堂が仏堂に付設されることになり、仏堂の前面の庇(ひさし)が礼堂に利用されたり、さらに前面に別棟の礼堂が建てられるなど、双堂(ならびどう)の形態をとるようになった。このように奈良時代は、日本の風土に適応した仏堂が建てられ始めた時代でもある。
[工藤圭章]
平安時代
794年(延暦13)都は平安京に移るが、平城京の諸大寺はそのまま奈良にとどめ、新都では東寺、西寺の2寺だけを設けた。この2寺の造営は従来の様式の踏襲であったが、入唐して密教を学んだ最澄(さいちょう)・空海が新たに天台・真言(しんごん)の宗派をおこしたことにより、密教に基づく建築がつくられるようになった。それまで仏塔は九重・七重・五重・三重のものが建てられていたが、密教の影響を受けて建てられたのが多宝塔である。
一方、延暦寺(えんりゃくじ)の常行堂(じょうぎょうどう)もこの時代に建設されたが、この建物は方五間堂で屋根の頂部に如意宝珠をのせた宝形造(ほうぎょうづくり)で、これも多宝塔と同じく平安時代になって初めて出現したものである。前面の庇を礼堂のように扱った奈良時代の建物には、唐招提寺金堂があるが、平安時代になると、東寺の金堂や食堂(じきどう)のように、前面庇のさらに前面に孫庇(まごびさし)を設けて、そこを礼堂としたため、仏堂の奥行が4間から5間へと、1間深められるようになった。孫庇の多用も平安建築の特徴にあげられよう。
このような平面の変化とともに、構造にも変化が生じた。中国では782年(建中3)につくられた南禅寺大殿で、肘木(ひじき)形を通(とおし)肘木上に現し、部材を一木化することが試みられていたが、日本では952年(天暦6)に完成した醍醐寺(だいごじ)五重塔で、丸桁(がぎょう)の下に実(さね)肘木を一部造出した一木化が試みられ始めた。その後この傾向は高まり、現存するものでは1171年(承安1)の兵庫県一乗寺三重塔に、南禅寺大殿のような部材の一木化が認められる。一方、日本のような雨量の多い多湿性の風土では、建物の保存上、雨に対する対策が考慮されねばならなかった。まず、雨はけの面では、屋根の勾配(こうばい)が強められた。古代の建築は、たとえば母屋(おもや)では、新薬師寺本堂のように屋根裏の垂木がみえるものや、あるいは唐招提寺金堂のように天井が張られるものがあったが、庇は一般に天井が張られず、屋根裏の垂木をそのままみせる、いわゆる化粧屋根裏天井となっていた。したがって、屋根の勾配を強める方法として、屋上に屋根を重ねるような形がとられた。このような屋根を野(の)屋根とよぶが、法隆寺大講堂(990再建)の屋根がその初期のものとして知られる。
野屋根ができるようになると、庇の化粧屋根の勾配は、雨の流れに関係がなくなるので、勾配を緩くすることが可能となり、側柱(がわばしら)を高くすることが考えられた。これは採光の点では有利で、建物内を明るくする効果を生み出した。また、化粧屋根と野屋根との間の空間を利用して軒先を支持するために桔木(はねぎ)が入れられるようになり、桔木の存在により軒の出が深まるようになった。屋根の勾配を強めること、軒の出が深まること、両者とも雨仕舞(あまじまい)にはきわめて有効であり、加えて床張りの建物では床下の通気が図られるようになって、建物の保存に好影響を与えることになった。
これはまた、建物の外観をも変えることであった。屋根が高まり、側柱も高くなって、全体として建物は立ちが高くなった。床張りの建物では周囲に縁が回されるので、それが土間床の建物の基壇のように建物の足元を引き締める意匠的効果をもたらした。また、従来は建物を地上の湿気から防ぐことを考慮して基壇が高められていたが、床下の通気が容易となって、高い基壇は省略されるようになった。奈良時代から平安時代になって、仏堂は風土に適した日本的な建物に変わっていったのである。
一方、平安時代は、894年(寛平6)に遣唐使の廃止が行われてから大陸との公的な交流がなくなり、奈良時代以来の建築様式が日本的な発展をみたともいえる。前述の、構造面では部材の一木化が認められる一乗寺三重塔においては、側回りではかつて醍醐寺五重塔のように2段に組み上げられていた三手先組物が、上段には通肘木を入れて構造強化が図られているし、また組物間の中備(なかぞなえ)に入れられていた間斗束(けんとづか)が撤去されて、意匠を考慮して本蟇股(ほんかえるまた)が入れられている。中備に本蟇股が用いられるのは平安時代からで、これも新しい発展といえよう。このように、奈良時代に唐から伝来された建築様式が平安時代を通じて日本的に発展したものを、和様の建築様式とよんでいる。
多宝塔や常行堂から出発した宝形造の阿弥陀堂(あみだどう)は、平安時代の特色ある建物の一つであるが、それとともに庇や孫庇を利用した礼拝空間を設けた仏堂が、内陣・外陣を構成する奥行のより深い本堂形式の建物に発展する。その発生的なものとして現存するのが永暦(えいりゃく)2年(1161)の棟木銘をもつ當麻寺(たいまでら)本堂である。この堂はこれより早い平安初期に、孫庇の礼堂をもつ仏堂として建設されたが、礼拝空間の整備が図られ、内陣・外陣を構成する本堂に改められたもので、あたかも内陣・外陣が双堂の造合いの軒部分を省略して並べたような形を示している。大屋根の小屋組みはこの双堂部分の棟に大梁を渡して組み立てられており、野屋根がさらに発展した形をとる。1150年(久安6)に建設された高野山金剛峯寺(こうやさんこんごうぶじ)金堂は、内陣・中陣・外陣を構成し、仏堂の前に礼堂を並べた形式であるが、仏堂の側柱を礼堂の柱とつなぐ大梁を入れることによって省略し、そこを中陣としていたことが古図から知られる。これにより大梁を連続して架けることによって柱を省略する手法が、中世以前にすでに試みられていたことがわかる。
ほかに平安時代の建物としては、現存しないが寝殿造の住宅がある。奈良時代の庶民の住宅は平城京の宅地の発掘調査によって、掘立て柱建物であったことが知られており、宮殿建築でも居住用のものはやはり掘立て柱建物が主流を占めていた。また、現在は仏堂風に改められ礎石建ちになっているが、解体修理時の調査によって、奈良時代の高級貴族住宅の唯一の遺構とみられる法隆寺東院伝法堂は、当初は掘立て柱であったかもしれない。そして、奈良時代の住宅は、他の住宅跡の発掘調査例からみても、宅地にそれぞれ独立して建物が建てられるのが一般的であった。これに対して寝殿造の住宅は各建物が廊で連なり、互いに連絡が図られていた。これは、内裏の殿舎配置を祖形にしてそれを簡略化したものと推測されるが、中央に正殿としての寝殿を建て、その左右に対称的に対屋(たいのや)を配するのが基本であった。しかし、現実には対の一方が対代(たいだい)として小規模につくられたり、あるいは一方が省略されて対称性が崩れるものが多かった。初期の寝殿造の貴族住宅の形態については判然としないが、12世紀の寝殿造住宅のようすは絵巻物に写実的に描かれているので大概は知られている。そして高級貴族の寝殿造をさらに簡略化したものが、下級貴族や釈家(しゃっけ)・武家の住宅へと及んでいったと思われる。これらの住宅では、仏堂に用いられた扉のほかに、蔀(しとみ)や遣戸(やりど)が多用されており、建具の種類が豊富になってきたことが知られる。
[工藤圭章]
鎌倉時代
日本建築の中世は、源平争乱で1180年(治承4)に焼失した南都東大寺および興福寺の復興から始まるが、これに際し新しく中国の大仏様、禅宗様の建築様式が導入され、日本建築は著しく発展した。大仏様は、東大寺の鎌倉復興に尽力した俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)が、宋(そう)の建築様式を彼なりに解釈した様式であった。彼は東大寺の早急な復興のため、大量生産が可能なように部材を標準化し、建物の強度を図るために各柱は貫(ぬき)で連結した。また、屋根は野屋根をつくらず、勾配の強い屋根とし、軒も一軒とし、軒の隅は扇垂木として放射状に収めたのである。この様式は和様に一部取り入れられ、新和様として主として奈良地方に広く普及した。
続いて禅宗が布教されるに伴い、宋直輸入の建築様式が日本にもたらされた。この様式は軸部に比べ組物を小さくして柱上の台輪(だいわ)に並べ、組物に組まれた尾垂木は内部は持送りとして母屋を支えるなど、まったく新しい構造原理を取り入れたもので、入側柱(いりがわばしら)と側柱をつなぐ繋梁(つなぎばり)も海老虹梁(えびこうりょう)として高さを違えて連結するなど、新機軸を生み出した。これが禅宗様であり、やがて大仏様や禅宗様の長所を和様に応用して、これらが混然と一体化された折衷様が確立される。折衷様は、どの部分を和様、どの部分を禅宗様とするかは、構造・意匠とも造営にあたった技術者が独自に決定したので、かつて和様で一元的な構造であった日本建築も多元的になり、建物ごとに個性のあるものが出現した。そしてまた、鎌倉時代は幕府の行政が安定したため、技術者の交流も京・鎌倉と五山の大寺の造営に伴って頻繁に行われ、建築技術が全国的に安定して伝播(でんぱ)するようになった。栃木県鑁阿寺(ばんなじ)本堂、山梨県大善寺本堂、福井県妙通寺本堂、和歌山県長保寺本堂、広島県明王院本堂、香川県本山寺(もとやまでら)本堂、愛媛県太山寺(たいさんじ)本堂など、近畿地方以外でも各地に特徴ある名建築が建立された。
[工藤圭章]
室町・桃山時代
室町時代になると、鎌倉時代に発達した折衷様が主流となり、また、禅宗建築では禅宗様を主体にした建築が建てられ、多様となる。ただし、大仏様は新和様に吸収され、折衷様のなかに生かされて、純粋な和様と同様に、大仏様として存続することがなくなったのである。
室町後期はいわゆる戦国の世で、中央集権が崩れて各地に戦国大名が領国を制するようになると、技術者の全国的交流は閉ざされて、建物にも地方性が現れるようになる。なかでも和泉(いずみ)(大阪府)、紀伊(和歌山県)の各地では装飾性を強調し、細部に彫刻・彩色を施すものが現れ、次代の桃山時代の華麗な建築の源流的なものが、地方色として狭い範囲で普及する。一方、戦国の世の習いとして室町末期から城郭建築が発展し、物見のために多重の櫓(やぐら)が建設されて天守閣の発生をみる。城郭は防備を主とした軍事的な建築であるが、一方では領主の権威の誇示のため壮麗なものが建てられるようになり、とくに織田信長が琵琶湖(びわこ)南岸に建設した安土(あづち)城は、壮大な天守閣の先駆けとなった。
城郭の建設には社寺建築の技術者を直接必要としなかったが、規模が壮大になると彼らの技術を必要とした。また、臣下との面接のほか使節の接待の場でもあった城郭内の居館は格式高く優美な室内意匠を凝らし、欄間(らんま)や金碧画(きんぺきが)などで飾りたてたので、建築技術者以外に、画師(えし)、彫刻家の参加も得て、建築が総合芸術の所産として評価されるようになった。そして、居館の主室には床(とこ)・棚・書院や帳台構(ちょうだいがまえ)など座敷飾りが整えられ、書院造として確立した。豊臣秀吉(とよとみひでよし)が1587年(天正15)に建設した聚楽第(じゅらくだい)は書院造建築の粋を尽くしたもので、門なども彫刻で飾られ華麗な彩色が施されていた。このころの建築美をとどめるものでは、豊臣秀吉の霊廟(れいびょう)豊国廟の遺構と伝えられる滋賀県竹生(ちくぶ)島の都久夫須麻(つくぶすま)神社本殿や、宝厳寺(ほうごんじ)唐門(からもん)が著名である。このような建築の先駆的なものが、前に触れたように和泉・紀伊の神社建築にもみられるが、それらがこの時期に桃山建築として開花した。1607年(慶長12)完成の京都北野天満宮本殿・拝殿や宮城県大崎八幡宮(はちまんぐう)本殿・拝殿はその代表的なものである。後者には紀伊の大工刑部国次が参画しており、続いて完成をみた宮城県瑞巌寺(ずいがんじ)本堂では、大崎八幡宮の棟梁(とうりょう)であった山城(やましろ)(京都府)の中村吉次がこれにあたり、紀伊熊野(くまの)から用材が運ばれるなど、技術者や用材の交流が図られ、東北地方でも近畿と同等のものが建立されたのである。
[工藤圭章]
江戸時代
江戸時代になっても、建築には華麗さが珍重された。1617年(元和3)に建立された静岡県久能山(くのうざん)東照宮本殿では組物に丸彫りの彫刻が用いられ、同じころ建立された江戸増上寺の徳川家康の尊像を祀った安国殿(第二次世界大戦で焼失)では、尾垂木先が獣頭の彫り物になるなど、建築の構造材を彫刻化することが始められている。部材の彫刻化など多彩になると、湾曲する尾垂木や拳鼻(こぶしばな)がついた変化の多い禅宗様が好まれるのが当然で、和様とも禅宗様ともつかない折衷様が主流を占めるのである。一方、純粋の禅宗様も京都の大徳寺、南禅寺、妙心寺など禅宗伽藍の造営にあたって採用されるなど、近世になってまた違った発展をみている。しかし、禅宗寺院にあっても伽藍周辺に営まれた塔頭(たっちゅう)寺院では、本堂に方丈が利用され、和様を主体とした住宅風の建築が建てられている。
近世初期に発達した書院造は、一面装飾性の強い豪華なものであったが、江戸時代に入ると繊細さを旨とする書院造が出現する。それは茶室に始まる数寄屋(すきや)建築の影響を受けて面皮(めんかわ)柱が使われ、壁も聚楽壁や錆壁(さびかべ)が塗られる。これらの座敷では、床・棚・書院などに銘木・珍木が珍重された。1615年ころ(元和年間)から造営された桂離宮(かつらりきゅう)の書院群や1656~1657年(明暦2~3)建立の曼殊院(まんしゅいん)書院や西本願寺黒(くろ)書院は、数寄屋風書院の好例である。
近世になると、また黄檗(おうばく)宗の伝来に伴って、黄檗様の建築が造営された。長崎では1644年(正保1)から崇福寺(そうふくじ)の伽藍が黄檗様で建設されている。この寺は、同じ長崎の興福寺、福済寺(ふくさいじ)とともに、長崎在住の福州人の寺院として開かれた寺で、両寺に開創当初の建築が残らないこともあって、崇福寺の建築群は明(みん)末清(しん)初の中国建築のおもかげを残すものとして注目される。1662年(寛文2)には京都万福寺の造営が行われ、以下黄檗様は黄檗宗の布教により全国的に広まり、静岡県宝林寺本堂のように地方にもこのころの優品が残っている。
江戸時代を通じて社寺建築は折衷様が主流を占め、細部装飾が発達した。とくに彫り物が多用されて壁面を飾るようになり、建築そのものより彫刻の美が建築の価値を高める変則的な結果をもたらした。彫刻や漆・彩色で飾られる建築は日光の東照宮社殿や大猷院(だいゆういん)霊廟など関東で盛行し、関西では比較的少ない。ほかに関東では埼玉県歓喜院(かんぎいん)聖天堂、群馬県妙義神社、千葉県新勝寺三重塔・釈迦堂(しゃかどう)が著名であり、幕末期のものには静岡浅間(せんげん)神社の社殿が知られている。
1858年(安政5)アメリカほか4か国と修好通商条約を結んでから、開港場に居留地が設けられ、洋風住宅が建てられ始めた。長崎の旧グラバー邸や旧オルト邸が明治以前に建てられたものとして現存する。居留地の住宅は外国人の指導のもとに日本人の大工がつくったもので、日本建築としてはまったく新しいタイプのものであった。それまでは都市というと城下町が主で、そこには武家住宅と商家が区画された。武家住宅は書院造の簡略化されたものであり、商家は塗屋造(ぬりやづくり)のものが多く、とくに耐火を考慮して土蔵造のものまであった。一方、農村では農家はそれぞれの地方の特色をもち、きわめて保守的な平面と構造を伝えていた。したがって、当時すでに建築の種類は多種多様であった。
明治になると日本人独自の手になる擬洋風建築が始められ、現存するものでは1876年(明治9)に建設された長野県の開智(かいち)学校が有名。当時公共建築は洋風建築に倣ってつくられたが、窓回りはアーチ状に木枠を組み、建物の隅はコーナーストーン風に木組をみせたり、漆喰(しっくい)を塗り上げて、写実的に処理した。明治になって実際に海外で建築学を学んで帰朝する者が出現するまで、在来の大工が見よう見まねで洋風建築を建てており、1868年(慶応4)の築地(つきじ)ホテル館や1872年の国立第一銀行などは、錦絵(にしきえ)を見ると、当時の擬洋風建築を如実に現していて興味深い。
[工藤圭章]
日本の近代・現代建築
西洋建築移植時代
明治の指導者たちは、欧米の圧倒的に優越した文化に直面して、産業技術や軍備などを早急に摂取する必要を痛感した。彼らにとって西欧化と近代化は同義語であり、明治維新後の近代社会に対応する新しい建築課題にまず対応したのは、いわゆるお雇い外国人の技師や建築家であった。これらの明治初期の建築はおおむねヨーロッパ19世紀の折衷主義とよばれる様式で、この古めかしい様式を否定するところからヨーロッパの近代建築は始まったのであるが、日本の場合はむしろその折衷主義が近代化への母体となった。それには、幕末諸藩によって開かれた諸工業、製鉄所や造船所、紡績所などの諸施設が洋風建築の先駆となっており、長崎製鉄所(1861)や大浦天主堂(1865)などはその例である。維新政府は諸藩の諸施設を受け継ぐと同時に、新規に産業設備を設ける必要から多くの外国人技師を雇い入れ、林忠恕(はやしただよし)(1835―1893)、立川知方(たてかわともかた)(1825―1894)、朝倉清一(1840―1903)らが補佐した。1873年(明治6)にはイギリス人ダイエルらが工学寮の教師として来日し、本格的な工学教育が開始された。
こうした外国人技師の残した初期の作品としてはイギリスのウォートルスの泉布観(せんぷかん)、イタリアのカペレッティGiovanni Vincenzo Cappelletti(1843―1887)の遊就館があるが、もっとも日本に影響を与えたのはイギリス人のコンドルで、鹿鳴館(ろくめいかん)(1883)、岩崎久弥(ひさや)邸(1896、現存)、三井倶楽部(くらぶ)(1913)などがある。
一方、民間の棟梁・職人あるいは官公庁の下級技術者たちは、依然として日本的伝統の小屋組みを応用し、内外の意匠はコロニアル・スタイルといったいわゆる擬洋風(開化式)建築を生み出した。これは1872年の学制頒布を機に小学校や役場の建物として全国的に波及した。中込(なかごみ)学校(佐久市)、睦沢学校(甲府市)、開智学校(松本市)、済生館病院(山形市)などが現存するが、このスタイルは明治20年代以降は影を潜める。
工部大学校造家学科の設置は1879年であるが、そこでコンドルの教育を受けた辰野金吾(たつのきんご)、片山東熊(かたやまとうくま)、曽禰達蔵(そねたつぞう)、佐立七次郎(さたてしちじろう)(1856―1922)、同時代アメリカで教育を受けた妻木頼黄(つまきよりなか)、フランスで学んだ山口半六ら本格的日本人建築家が明治20年代から活躍を始めた。辰野の日本銀行本店(1896)、妻木の横浜正金銀行(1904)、片山によるネオ・バロック風の赤坂離宮(1906)は明治を代表する記念碑的建築である。
[近江 栄 2018年9月19日]
欧米追随からの脱皮
これより先1891年の濃尾(のうび)地震はれんが造の建造物に大きい被害を与え、外国建築をそのまま導入することの危険を教えた。この教訓と1906年(明治39)のサンフランシスコ大地震から学んで、佐野利器(さのとしかた)を中心に耐震耐火構造の鉄筋コンクリートや鉄骨造が積極的に取り入れられるようになる。新時代を象徴する鉄材の応用は、いち早く鉄道橋や造船の分野に試みられたが、建築への利用の先例としては秀英舎工場(1894)があり、これは造船技師若山鉉吉(わかやまげんきち)(1856―1899)の設計によるパイプ構造である。オフィスビルとしては銀座黒沢ビル(1910、黒沢貞次郎(1875―1953)設計)、三井物産横浜支店(1911、遠藤於菟(えんどうおと)(1865―1943)設計)があり、また鉄骨とれんがの混構造で帳壁(カーテン・ウォール)の祖形となった佐野の丸善書店(1909)がある。
議院建築(帝国議会議事堂)の建設は明治政府の重要課題であったが、1910年にその建築準備委員会が開かれ、討論会で、次代を担う建築家から国民的様式の確立について提案がなされた。討論の結果は不毛ではあったが、こうした議論がもたれたこと、そして設計案を公募するなど、模倣と習得の時代が終わり、次の新しい飛躍の時代に入ったことを示している。
[近江 栄 2018年9月19日]
分離派と日本のCIAM
1910年代には海外のアール・ヌーボーやゼツェッションの活動が新鮮な響きをもって伝えられるようになる。1920年(大正9)東京帝国大学建築科を卒業する学生グループ、石本喜久治(1894―1963)、堀口捨己(ほりぐちすてみ)、滝沢真弓(たきざわまゆみ)(1896―1983)、矢田茂(1896―1958)、山田守、森田慶一(1895―1983)ら6名は「分離派建築会」を結成し、激しい宣言文で当時の様式的な建築制作の風潮を批判し、創作を標榜(ひょうぼう)した。分離派が実際的な活動に乗り出すのは2年後で、山田は東京中央電信局を、石本は東京朝日新聞社を、堀口は大正博覧会会場を設計した。当時のヨーロッパの表現主義の流れをくむ分離派は若い層に多くの同調者を得、分離派に続く「創宇社」(1923)や類似のグループが生まれた。これらはいずれもその活動の主体は展覧会や講演会であったが、建築家がこれまで手がけてきた大建築のほかに庶民住宅にも目を向け、合理主義的な方法と階級意識とを結び付けた点が注目される。1930年(昭和5)ごろから動線という建築平面の人間の動態分析や、人体、家具の寸法、規格、住宅のマスプロといった問題も取り上げられるようになる。
1927年7月に京都の建築家を中心に「インターナショナル建築会」が結成された。この会は機能主義を目ざし、その綱領にあわせて「真正なるローカリティに根底を置く」ことを提唱し、その独自性と成果が期待されたが、実態は機能と合理性を追求するCIAM(シアム)(近代建築国際会議)を超えるものではなかった。
ヨーロッパのCIAMは個々の建築の造形よりも社会的な問題として建築を国際的にとらえようとする姿勢を示し、その第2回の会合では「生活最小限住宅」がテーマに選ばれた。ここにはル・コルビュジエに師事する前川国男、日本から山田守が参加して、日本の建築家もようやく国際舞台に登場し、インターナショナル・スタイルが本格的に日本に導入されるきっかけとなった。
こうした前衛的な思潮とは別に、銀行、会社などの民間商業建築は、古典主義やネオ・バロックなどさまざまな様式を消化しつつ、日本各地に広まっていった。
[近江 栄 2018年9月19日]
国粋主義の風潮
和洋折衷と近代化の相克は避けて通れない問題であった。やがて民族国粋主義が台頭してくると、吉田鉄郎の東京中央郵便局(1931)を典型とする合理主義建築に対して、東京帝室博物館(1937、渡辺仁設計)、九段軍人会館(1934、川元良一設計)のように時代に迎合する風潮が建築界にも生まれる。こうした国粋主義の高揚期に来日したのがB・タウトで、彼は伊勢(いせ)神宮や桂離宮などを賞賛することによって、伝統的な日本美への回帰を促進する役割を果たした。
日本の近代建築がこれから伸展しようとするやさき、1937年パリ万国博に出品した坂倉準三の日本館を例外として、戦時体制がその正常な発展を阻止した。個々の建築にかわって農漁村の住宅改善や都市計画が建築家の命題となったが、それは戦時中には実現されず、むしろ戦後の建築活動の源泉となった。そして、日本の近代建築運動は、第二次世界大戦の戦災によって戦前の20%に近い建物を失うという悲惨な結末をもって終わる。
[近江 栄]
現代
戦時下に繰り返し行われた日本的デザインを模索するコンペに重ねて当選した丹下健三(たんげけんぞう)は、そのデザイン手法を戦後にも継承し、木造建築の構成と木割の美学から引き出した伝統美と近代合理主義が交錯する独自のデザインを生み出した。広島平和記念館(1952)や香川県庁舎(1958)がその代表で、1950年代に展開された伝統論争に一つの頂点を築き、丹下のデザインは全国的な流行をみた。しかし彼はその後の日本の経済成長のなかで、これまでの「わび」「さび」的なイメージからくる「うつろいやすい伝統」はもはや克服すべきであると説いて、機敏に自らの変身を予感させていた。この変身は、当時国際的に造形主義的デザインが台頭し、ル・コルビュジエのロンシャン教会堂を先駆けとして、サーリネンのTWAターミナル、J・ウッツォンのシドニー・オペラ・ハウス・コンペ当選案などが相次いで紹介された時期と符合している。
丹下はこのような海外の多彩な造形活動に呼応して、1964年(昭和39)オリンピック施設の東京都屋内体育館で吊(つり)屋根のダイナミックな造形表現を示した。これは高度成長を達成した日本の象徴的な作品として国際的な注目を集めた。こうして1960年代は現代技術の可能性を追求した丹下健三、坪井善勝(つぼいよしかつ)、前川国男、横山不学らの作品が注目される一方で、村野藤吾(むらのとうご)や白井晟一(しらいせいいち)はこうした先鋭なモダニズムの時流とは一定の距離を保ちながら、独自の折衷的装飾性を巧みに昇華させ、村野は日本生命ビル(1964)、白井は親和銀行本店(1968)など、次々と新鮮な話題作を生み出していった。
1970年代の日本の高度経済成長は全世界の注目の的となり、いまや欧米に追い付くのではなく、先進国の教科書なしに、世界に冠たる工業生産力と対比される生活環境の貧しさを抱えながら、自ら新たな展望を模索しなければならなかった。やがて1970年の「進歩と調和」を掲げた大阪万国博覧会に突入していくのだが、すでに世界的な規模で脱工業化が進展し、人間疎外の克服、余暇への認識などが注目され始め、もはやこれまでのように工業化そのものを造形の理念とすることは成り立たなくなっていた。
すでに1960年代から建築のデザインは多様化し、1人の建築家の作品も次々と変貌(へんぼう)し、街にはつかのまの流行現象が目だってくる。こうした混迷現象を背景として、丹下門下の磯崎新(いそざきあらた)は、これまで近代建築が背負ってきた「建築を社会改革の手段」とする重荷から建築を解放し、他領域の芸術との連繋(れんけい)を援用することによって近代建築の再生を図り、著書『建築の解体』によって若者たちに影響を与えた。一方、建築評論家長谷川堯(はせがわたかし)は、村野藤吾を育てた様式の建築のもつ豊饒(ほうじょう)さへの回帰と、近代建築理念によって失われたものの大きさを訴え、『神殿か獄舎か』(1972)の著作によって戦前の洋風建築を再評価し、その全国調査を提唱した。
1970年代なかばからの建築デザインの多様化と混迷はいまだに確たる展望をみいだしえないでいる。1960年代においては丹下の系譜が普遍的で、村野の系譜は特異とされてきたが、大阪万国博以降は逆転し、工業生産を主軸とする高度経済成長型の発想に反省が求められるようになった。やがて磯崎はポスト・モダニズムの大作として、つくばセンタービルを発表する。これはルネサンスからマニエリスム、さらに現代建築の引用、もじり、反転といった手法で集大成された、きわめてユニークな表現として話題となった。
1980年代初頭を飾る作品には反近代主義ともいえる新高輪(しんたかなわ)プリンスホテル(村野)、レイト・モダニズムの赤坂プリンスホテル(丹下)がある。このほか、日本現代建築のもう一つの動向として、近代建築と伝統が混在併存する大江宏(おおえひろし)の国立能楽堂など一連の作品の展開も見逃せない。さらに共生の思想を主唱した黒川紀章(くろかわきしょう)の内外での活躍も注目された。
[近江 栄]
『山口廣・村松貞次郎他著『日本の近代建築』(1981・環境文化研究所)』▽『日本建築学会編『近代建築史図集』(1976・彰国社)』▽『稲垣栄三著『日本の近代建築――その成立過程』全2冊(1979・鹿島出版会)』▽『太田博太郎・福山敏男他著『新訂建築学大系4Ⅰ 日本建築史』(1968・彰国社)』▽『福山敏男著『日本建築史の研究』(1980・綜芸舎)』▽『太田博太郎著『日本建築史論集1 日本建築の特質』(1983・岩波書店)』▽『鈴木嘉吉編『国宝事典5 建造物』(1985・講談社)』
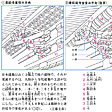
薬師寺東塔と唐招提寺金堂の三手先

新薬師寺本堂、法隆寺大講堂、當麻寺本堂…
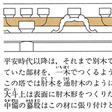
一乗寺三重塔組物

五重塔の各部名称(醍醐寺)

寝殿造(東三条殿復原平面図)

明王院

都久夫須麻神社

宝厳寺唐門

大崎八幡宮

瑞巌寺

久能山東照宮本殿

崇福寺〈長崎市〉

旧グラバー住宅(グラバー邸)

旧開智学校校舎

大浦天主堂

泉布観

旧中込学校

日本銀行本店

遊就館(明治時代)

鹿鳴館
改訂新版 世界大百科事典 「日本建築」の意味・わかりやすい解説
日本建築 (にほんけんちく)
日本の伝統的建築は,これを世界的にみれば,中国建築系の一支流にすぎない。中国建築の影響は仏教建築以前にもあったが,飛鳥時代における仏教建築の伝来,鎌倉時代における宋様式の輸入は,とくにその著しいものであった。しかし,中国の建築と日本の建築とを比較してみると,そこにかなり大きな相違がみられる。外来様式の輸入に熱心であった奈良・鎌倉時代の建築を中国のそれと比較すると,新薬師寺本堂や栄山寺八角円堂の簡素な美しさは中国の建築には全く求められないし,禅宗建築の細部にまでゆきとどいた精妙な技法は,細部の粗雑な中国建築とはかなりかけ離れたものである。このような点から,日本の建築は中国の様式を丹念に移しながらも,かなりはっきりした選択が行われたものとみなければなるまい。仏教建築の渡来するまで,数世紀にわたって鉄器の使用になれていた日本人は,すでにかなり高い建築技術をもち,様式的にも洗練されたものに達していたのであろう。そこに民族のもつ好みが,はっきりと形成されていたものと考えられる。これは,仏教建築が渡来後まもなく,瓦葺きを捨てて檜皮(ひわだ)葺きとなり,また土間をやめて板敷とするような,構造的な面でも現れており,そこに日本建築の伝統がすでに形成されていたことを物語っている。
特質
日本建築の伝統はすこぶる根強いものがあった。中国の建築が早くから椅子式になっていたにもかかわらず,日本ではついに明治維新後,西洋建築が輸入されるまで,椅子式は一般的な起居様式にならなかった。また木部には必ず彩色を施すのが中国建築の装飾法であったが,日本では住宅建築は白木(しらき)のままで終始したし,仏教建築においても,平安時代以後は白木のままのものが数多く造られた。このような伝統の根強さは,また新しい様式が起こっても,つねに旧様式が保存されるという点にもつながっている。神社建築はその最も著しい例であり,4~5世紀ころの様式である伊勢神宮の正殿が,60回の造替にもかかわらず今日まで古い形式をそのまま伝えているようなことは,他に例のない点であろう(式年造替)。この伝統維持と関連して,建築様式に地方色が少なく,きわめて画一的であるのも,見逃しえない特色である。日本人の建築に対する考え方は,ヨーロッパのそれとはまったく違っていた。ヨーロッパでは建築は人間の造ったもの,自然に対抗するものとして理解されているのに対して,日本の場合は,極端にいえば自然のうちの一部でしかありえない。自然と調和し,自然のうちに溶け込む建築が,美しい建築としてもてはやされてきた。このような建築に対する考え方は,材料の選択にも,また意匠の面でも,他の国の建築と違った特徴を生んでいる。
材料と構造
明治維新になって西洋の建築技術が入るまで,日本の建築は木造に終始した。すでに4~5世紀ころの古墳には,大きな石をしかも加工して用いているから,石の加工技術を知らなかったわけではない。だが木材が手近に得やすかったためと,建築それ自体に永遠性を求めることが少なかったために,隣国の中国で石や煉瓦(塼(せん))をかなり使っているのに,日本ではついに用いなかったのであろう。木材はヒノキが使われてきた。古代からヒノキは最上の材として尊重され,平安時代ころまでの遺構はほとんどヒノキで造られているし,神社建築では現在もヒノキを主としている。中世になって木材の不足からマツその他の材が用いられるようになり,また近世からはスギが住宅に,ケヤキが寺院建築に使用されるようになった。木材を主とするから平面は正方形か長方形で,まれに八角や六角のものがあるにすぎず,円形や曲線平面のものは造られない。その構造方式は柱の上に梁(はり)をのせて軸組みを造る楣式(びしき)/(まぐさしき)構造で,煉瓦や石のアーチ,ドームによるものとは根本的に異なる。したがって柱間の広さは梁によって制限され,そう広い柱間をとることができず,傾斜屋根をかけるため奥行きの深い建物を造ることができない。その結果として,自然,建物の大きさはある程度に制限され,大規模なものはごくまれである。柱と梁とが主要な構造材であるから,壁は仕切りにすぎず,構造的な意味はない。したがって,柱と柱との間はすべて開放とすることができる。
西洋の建築は,今日では鉄筋コンクリート造や鉄骨造のために変わってきているが,元来は石や煉瓦造のため壁を主体とした建築である。室内は壁によって自然のなかに切り取られた,人間の造った空間である。日本の場合は,柱だけが残って他は全部開放してあるから,外の自然の空間と室内の空間とは一体となって,別のものとは考えられていない。このような柱と屋根だけで壁のない開放的な構造は,西洋の建築からいえば建築という名に価しない構造物のようにもみられよう。壁が少なく,あっても柱を外に出した真壁(しんかべ)であるから,大きな壁面は構成されない。このため建物の外観は軽快となり,量感に乏しくなる。これは構造から生じた必然的な結果でもあるが,自然にそうなったというより,大きな壁面を構成できる大壁造の城郭においても,多くの軒や破風などによって壁を区切り,量感よりも軽快さを求めているから,意匠の好みといってよかろう。構造材である柱や梁などがすべて露出される結果,構造材はそのまま化粧材となる。したがって材料の選択は,たんなる強度・耐久力の問題ではなく,化粧材としての見地から選ばれる。材料の美しさが,そのまま建築の美しさを左右するからである。日本建築では装飾のない美しさが好まれるから,木材は表面に塗装を施さない場合が多い。こうなると,木目や節が建築の一つの意匠として重んじられる。すでに平安時代から鎌倉時代にかけて,柾目(まさめ),板目といった言葉が現れていることからも,古くから木材にひじょうな関心をもっていたことがうかがわれる。
傾斜のある軒の出た屋根は中国系建築の特色であるが,中国の建築にくらべると日本の建築は軒の反上り(そりあがり)が少なく,さらにその軒の出が深い。日本でも唐の様式をそのまま受け入れた奈良時代の建築に対して,平安・鎌倉時代になると軒の出はしだいに深くなる。これは雨から壁や縁をまもるためでもあり,また暑い季節,雨の降っているときでも,戸をあけておくために必要であった。建物の内部には床(ゆか)が張られる。床はすでに古代初期には一般的に行われており,奈良時代の後半からしだいに仏教建築にも入っていった。床が張られれば,建物の周囲に縁がめぐらされる。縁は建物の比例の上からは基壇と同じように扱われているが,土で築かれた基壇と,下が開放になっている縁とでは,意匠的な効果はひじょうに違う。建物の立面の中央ほどに軒の線があり,下方には縁の線がある。この二つが濃い陰をもっているから,建物の基本的な感じは垂直的なものでなく,水平的なものとなっている。
意匠
日本の建築の自然に対抗しようとしない,控え目な表現は水平的な表現を主とし,垂直線を強調しないことによって表される。塔のような高い建築においても,各重の軒が垂直的な線の延びをさえぎり,水平線によって全体の形を分断している。その軒の出は深く,濃い陰影を建物の壁に落とすから,軒の水平線は立体的にはひじょうに強い印象を見る人に与える。建物全体の軸部は横長の長方形になることが多く,柱と貫(ぬき)などで構成される軸部も正方形を基本とし,縦長の長方形とはしない。このような点は中国様式の影響の強い法隆寺や初期の禅宗建築と,奈良・平安時代以来の和様(わよう)と呼ばれる建築とを比較すると,明瞭に知ることができよう。たとえば禅宗建築では,建物の正面の幅の1.4倍くらいが棟(むね)の高さであるから,全体の形は縦長の長方形となるが,和様の建物では棟高は建物の正面の幅と同じか,それ以下となっている。柱と頭貫(かしらぬき)とで構成される各軸部の割合は,禅宗様(唐様(からよう))では中央の間で正方形あるいは縦長の長方形となるが,和様では正方形とする。禅宗様では左右の間は中央の間の7割ほどの広さしかないから,隅にいくにしたがって,軸部の縦横の差は大きくなるが,和様では左右の間があまり狭くならないから,ほぼ正方形に近く,また長押(なげし)が外に打たれるので,柱の垂直線よりも長押の水平線の方が強調される。
このような意匠の根本的な性格は,室内でも同様である。中国建築の室内は周囲の斜めに設けられた化粧屋根裏で,中央に向かって高まり,中央の水平の天井で,その高まってゆく空間を納めている。その空間構成は立体的なものであるが,日本ではこれと同様な手法をとり入れながらも,しだいに室内一面に水平な天井を張る方向に向かっている。こうなると,内部空間は水平の天井と床で仕切られた単純な立方体となってしまう。しかも椅子式でないから,天井高は低く,いっそう立体的な感じがなくなっている。建物の配置は中国の建築が縦深的配置をとるのに対し,日本のものは並列的,平面的である。最古の伽藍配置を有する四天王寺が中門,塔,金堂,講堂が一直線上に並ぶ大陸に由来するものであるのに対して,すでに法隆寺の配置は中門の左右後方に塔と金堂とがあり,その間を通して講堂を見ることができる。全部の建物が一望のもとに見られるというパノラマ的配置は,後の寝殿造,書院造においても,また浄土宗,真宗寺院などにも見られ,日本建築の配置の特殊性を示している。
非相称性もまた,日本建築意匠の著しい特色である。宗教建築や宮殿建築においては,荘厳性を高めるため左右対称(シンメトリー)とするのが世界中どこでもふつうに行われているが,日本では出雲大社や法隆寺に見られるように,古くから非相称形が行われ,住宅でも最初左右対称であった寝殿造は,平安時代末期からは対称形でなくなり,書院造などは最も格式的である上段の間においてさえも,最初から床(とこ),棚,付書院(つけしよいん)という非相称形に出発している。
装飾の少ないことも,日本建築の大きな特徴の一つである。その最も代表的なものは鳥居であろう。これをインドのトラーナ,中国の牌楼(ぱいろう)などとくらべてみると,その違いがよくわかる。これらはいずれも簡単な門であるが,鳥居は2本の柱と上にのる水平材(笠木と貫)とで造られている。トラーナも材の使用の少ないことは同様であるが,その表面には多くの彫刻がつけられている。牌楼は小さな屋根をつけたり,組物を用いたりして装飾化されている。ここに現れている差は,建築の構造そのままの美しさ,素材の美しさを主とするものと,装飾によって建築を美しくしようとする考え方の違いであり,そのことはまた,建築の彩色にまで及んでくる。日本の場合には,材料の自然のままの肌と色合いとが重んじられるが,中国の建築では必ず彩色を施すか,あるいは彫刻を加えるかして,自然のままの肌を残すものはない。
→社寺建築構造
歴史
日本建築の誕生
縄文文化期の建築は住居だけで,それは竪穴(たてあな)であった。竪穴は円形や隅丸(すみまる)の長方形などの平面で,深さ1m以内に土を掘り,壁から少し内方に4本の柱を立てたものが多く,上に草で屋根を葺いたものであった。その屋根の形は寄棟造であったと考えられる。弥生文化の時代になると農耕が始まり,イネの栽培が伝えられたので,住居のほかに倉が設けられるようになった。このころ高床の建築が伝えられ,倉や住居に用いられたが,竪穴住居はこの時代も,またつぎの古墳時代まで,さらに関東や東北では平安から鎌倉時代までも引き続き行われた。農耕が進むにつれて階級が分化して豪族が発生し,国家が誕生するが,それに伴って住居はしだいにりっぱになった。高床が豪族の住宅に用いられ,また神社建築の発生に当たっては,豪族の住宅の形式が神殿として採用された。伊勢神宮正殿(神明造)や出雲大社本殿(大社造)は,後世の様式の入ったところもあるが,基本的には古墳時代以来の形式を伝えるものと考えられる。当時の建築は白木造,掘立柱,草葺きで,屋根は直線的となっており,柱上に組物などを用いることはなかった。
古代
飛鳥時代に伝来した仏教は中国建築の様式を伝え,柱は礎石上に立ち,軒を受けるのに組物を用い(建築組物),屋根は瓦で葺いて反りがあり,木部には彩色を施し,金具で装飾した。仏教建築は,塔・金堂を中心として回廊がこれをめぐり,前に中門を開き,後ろに講堂,経蔵,鐘楼,僧房などを建てた。ここに建築群の形成する新しい建築美が生まれ,古墳時代までの素朴なものにくらべて,建築ははるかに装飾的になった。飛鳥時代の仏教建築,たとえば法興寺,四天王寺などはすべて滅びて伝わらないが,飛鳥時代末期あるいは奈良時代初期再建の法隆寺の堂塔が現存する。その様式は朝鮮を経て伝来した漢,六朝の建築様式で,柱に著しいふくらみがあり,組物に雲斗(くもます),雲肘木(くもひじき)を用い,強く鋭い表現をもったものであった。法隆寺金堂,塔,中門,回廊,法起寺三重塔などはこれに属する。
奈良時代には唐との直接交通で唐の文化が直接日本に入ってくるようになり,建築の様式も唐様式に変わった。難波京,大津京,藤原京,平城京と唐風の都城が営まれ,そのうちには唐風の壮大な宮殿建築が造営され,また多くの寺が建てられた。中央集権制の成立により政府の経済的基礎が確立し,この基盤の上に経営された平城京は日本建築史上の黄金時代をそこに現出した。平城京は南北約4.7km,東西約4.2kmで縦横に道路が設けられ,北の中央に宮城をおき,唐にも劣らぬ大伽藍である東大寺をはじめ,興福寺,薬師寺,元興寺,大安寺,西大寺などの寺が建てられた。これらの寺は唐の様式を用いたため,柱のふくらみは初期にごくわずかあるだけで,組物は雲斗,雲肘木を用いず,三手先(みてさき)が完成される。塔は2基となり,回廊は金堂に接続し,建築の表現は,飛鳥時代の鋭い気分が消えて,穏やかなものへと変わってゆく。各国に国分寺が建てられ,奈良時代寺院の遺跡は各地に見られるが,遺構は薬師寺東塔,法隆寺夢殿,同伝法堂,東大寺三月堂,正倉院,唐招提寺金堂,同講堂,当麻寺東塔,同西塔,栄山寺八角堂など,奈良地方に限られる。これらのうち,もと平城宮朝集殿だった唐招提寺講堂や,橘夫人家の一屋だった法隆寺伝法堂など,宮殿・住宅の遺構が存在することは注目すべきことである。このような大陸の建築様式の発展は,神社建築の様式にも影響を与え,屋根に反りがあり,木部に彩色を施した春日造(春日神社),流れ造(賀茂神社),八幡造(宇佐八幡宮)などが,奈良時代から平安初期にかけて発生した。
奈良時代の寺院は平地に建てられるのがふつうであったが,平安時代には密教が伝わって,比叡山延暦寺や高野山金剛峯寺のように山地に建てられるものが多くなる。新しい塔婆(とうば)形式として多宝塔が伝えられ,堂の前面に礼堂(らいどう)を設けるものが多くなった。礼堂は初めは本堂と別棟として建てられたが,しだいに一つの屋根でおおわれるようになり,堂の奥行きが深くなって,密教仏堂特有の暗い内陣を生んだ。これは仏をまつる本堂に対して,人々の参拝するための建築が発生したことを意味する。したがって,これは神社建築においては拝殿となり,八幡造から権現造へと発展する。平安時代の後半には浄土教が盛んになり,阿弥陀堂が数多く建てられた。これらは当時の人々が頭に描いていた極楽浄土の造形的表現で,平等院鳳凰堂などに見られるように,絵画・工芸の粋を集めて装飾された。大陸との交通が絶えたため建築様式の日本化が進み,仏堂も多く板敷とされ,屋根は檜皮葺きのものが多くなり,また白木造のものも造られるようになった。貴族住宅は寝殿を中心とし,東西中門廊を備えた左右対称の寝殿造が完成した。平安時代の遺構としては,室生寺金堂,醍醐寺五重塔,平等院鳳凰堂,中尊寺金色堂,富貴寺本堂,宇治上神社本殿など,京都を中心とするが,広く全国的に残っている。
中世
鎌倉時代の初め,東大寺の再建に当たって僧重源により南宋の建築様式である大仏様(天竺様)が伝えられた。大仏様は東大寺や重源が建てた寺院に用いられ,構造的な美しさに重点をおいた力強い様式で,挿肘木(さしひじき),木鼻(きばな),貫を新たに用いた。その様式は豪放で,平安時代末の繊細な様式に大きな刺激を与え,その細部は和様のうちに採用されたが,純粋なものは重源の死とともに滅び,その余影を奈良および瀬戸内海沿岸地方に残すにすぎない。大仏様につづいて,禅宗とともに禅宗様(唐様)が伝来した。禅宗様は北宋の建築様式で,建長寺が建築されるに至って確立し,禅宗の流布に伴って鎌倉時代末には広く全国に伝わった。禅宗様は細かい木割りで,組物には詰組みを用い,木鼻その他に多く曲線を用い,巧みな様式であったので,禅宗寺院以外の建築にも用いられるようになった。これらに対して,平安時代以来の様式を和様と呼ぶ。和様建築は天台・真言の寺院に引き続き用いられた最も一般的な様式であったが,大仏様・禅宗様の細部をとり入れ,鎌倉時代末には折衷様といわれる新しい様式を生んだ。鎌倉時代の遺構としては,東大寺南大門,浄土寺浄土堂(大仏様。兵庫県小野市),功山寺仏殿(禅宗様),石山寺多宝塔,興福寺北円堂,三十三間堂(和様),浄土寺本堂(折衷様。広島県尾道市)などがある。
室町時代には幕府が京都に開かれたので,京都が建築界の中心であったが,室町幕府の衰退に伴い,京都の建築界は活気を失い,これに対して,守護大名の発展に伴い,地方の建築界がしだいに盛んになった。様式的には鎌倉時代の継続で大きな変化はないが,和様の禅宗様化は進み,地方によっては独自の変化あるものが生まれてきて,これまでにみない多様性を示すに至った。とくに神社社殿形式や,細部の彫刻などに変化あるものが多く,禅宗様化して木割りが細かくなり,装飾を多くとり入れた和様は,つぎの桃山時代の豪華な様式を生みだす基盤となった。住宅の面でも,寝殿造はしだいに間仕切りがふえ,複雑な平面をもつようになってきていたが,宋・元の絵画,工芸品など唐物(からもの)の伝来により,これを飾りたてる唐様飾が発達した。これらは室町時代からしだいに設けられるようになった独立の接客空間(会所)に飾られ,座敷飾としての床,棚,付書院が発生した。しかしなおこれらは,つぎの桃山時代の書院造ほど定型化していない。また住宅中に金閣や銀閣のような楼閣建築が起こったことも注目すべき点である。この時代の遺構としては,興福寺東金堂,同五重塔(和様),円覚寺舎利殿,永保寺開山堂,安楽寺八角塔(禅宗様),観心寺本堂,鶴林寺本堂(折衷様),吉備津神社社殿,土佐神社社殿,慈照寺銀閣,同東求堂などがある。
近世
織田信長,豊臣秀吉の出現により,政治的統一が生まれた結果,京都が再び建築界の中心となった。戦乱の永続と拡大の結果,城郭建築は画期的な発展を示し,山上の山城から平野の平城が生まれ,その周囲には城下町が営まれた。城郭は大名の勢威の造形的表現として豪壮雄偉な外観をもつ。城郭内には領主の居館が建てられたが,これは彫刻,絵画,工芸のすべてを駆使して,領主の威厳を示すように装飾された。このため,これまでに見ない豪華な桃山様式が誕生した。桃山時代の住宅は,客を迎えるために最上の部屋(一の間)を用意し,二の間,三の間と続き,一の間は上段とし,これに床,棚,付書院,帳台構えが設けられ,書院造の形式が完成した。この豪華な書院造の反面,農家の質素な表現を基とした草庵風の茶室が完成し,その飾りの少ない室内意匠,自然的素材のみごとな使用は書院造にも影響を与え,書院造のうちに,数寄屋造と呼ばれる新しい様式を生んだ。室町時代末には衰退した社寺建築も封建制の再編成に伴って復興し,書院造と同じく豪華な様式によって造られた。代表的な遺構としては,姫路城,彦根城,園城寺光浄院客殿,妙喜庵待庵,大崎八幡社社殿,東寺金堂などがある。
江戸時代になると,一国一城令の発布により城郭建築は急激に衰え,大名の豪華な書院造も初期には多く建てられたが,明暦の大火(1657)以後は幕府の倹約令にもとづき,前代のはなやかさはみられなくなった。これに反して数寄屋造や茶室は盛んとなり,一般に普及して,今日の和風住宅の基礎を築いた。社寺の建設は引き続き盛んであったが,特筆すべきことは浄土宗,真宗,日蓮宗の発展で,室町時代まではまだそう大きな規模をもちえなかったのが,近世に入ってから真言,天台,禅3宗にまさるとも劣らない大建築を建てるようになった。また霊廟建築(廟)は前代の豊国廟に始まるが,東照宮の建設以来,いっそう盛んで,これらは多く権現造で建てられたため,幕府関係の神社はこれによるものが多く,この社殿形式は全国的に広まった。江戸時代の後半は庶民勢力の台頭が著しく,このため寺院建築も庶民的な色彩を加え,外陣には下駄ばきのまま自由に参拝できるようになったことも,特筆すべき変化であろう。これらの社寺建築は桃山時代以来の装飾の多い,木割りの細かいものであったが,装飾過多のため意匠的にはむしろ退歩を示し,すぐれた建築は少ない。新しい建築様式として,黄檗(おうばく)宗とともに明・清の様式(黄檗様)が入ってきたが,一般には用いられなかった。またこの時代から学校建築,劇場建築,儒教建築など新しい種類のものが生まれ,旅館も発達したことは前代にみなかったところである。この時代の遺構としては,二条城二の丸書院,西本願寺書院,桂離宮,如庵,日光東照宮,東大寺大仏殿,善光寺本堂,閑谷学校などがある。
近代以後
開国で西洋諸国との交通が開けたことは,日本建築界に仏教建築伝来以上の大変化をもたらした。新しい材料の石・煉瓦造が伝えられ,公共建築が建築界の主流となった。初めは木造に漆喰(しつくい)塗,なまこ壁を施すなど,江戸時代以来の構造により,見かけだけを洋風としたものが行われた(松本・開智学校など)。明治政府が外国人技師を招いて官庁建築の建設を始めてから,本格的な西洋建築が伝えられた。外人建築家はJ.コンドル(ニコライ堂,鹿鳴館),ウォートルス(大阪造幣寮)らで,その設計した建築は当時のヨーロッパ建築界の情勢を反映し,ルネサンス様式を主体とする折衷主義的なものである。コンドルは工部大学校の講師として多くの日本人建築家を養成し,1890年ころからは日本人建築家による大建築ができるようになった。日本銀行(辰野金吾),赤坂離宮(片山東熊),東京駅(辰野)などはその代表的なものである。濃尾の大地震(1891)に刺激されて耐震構造が重視され,鉄骨造,鉄筋コンクリート造が20世紀の初めから建てられるようになり,関東大地震後,大建築はまったく鉄筋コンクリート造によることとなった。一方,様式の面では,1897年のウィーン・ゼツェッシオンが分離派として1920年に日本にも伝わり,ヨーロッパの近代建築様式が日本でもはじめられ,朝日新聞旧東京本社(石本喜久治),中央電信局(山田守)などが建てられた。それらは芸術至上主義的な傾向が強く,また第1次世界大戦後の表現主義の影響もみられるが,しだいに合理主義,機能主義の面が強くなり,第2次世界大戦前には東京中央郵便局(吉田鉄郎),逓信病院(山田),若狭邸(堀口捨己)などを生んだ。しかし一般には折衷主義的傾向のものが多く,戦争中には国家主義的傾向が強まり,日本建築の形式的模倣が行われた。第2次大戦以後は,いちばん長くルネサンス風の伝統を守っていた銀行建築さえも,オーダーをつけなくなったように,近代建築様式は一般に広まった。住宅は書院造の伝統を伝え,それに洋風応接間の付加という形で洋風をとり入れていたが,第2次大戦後は個人の私室として,部屋の独立性が尊重され,またオープンスペースが見直されるなど,その平面は大きく転換し,多様化している。
→近代建築 →寺院建築 →住居 →城 →神社建築
執筆者:太田 博太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本建築」の意味・わかりやすい解説
日本建築
にほんけんちく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

