精選版 日本国語大辞典 「流体力学」の意味・読み・例文・類語
りゅうたい‐りきがくリウタイ‥【流体力学】
- 〘 名詞 〙 流体の流れの状態やその中に働く圧力などを研究する力学の一分野。航空工学や船舶工学などの基礎となっている。〔工学字彙(1886)〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「流体力学」の意味・わかりやすい解説
流体力学
りゅうたいりきがく
fluid mechanics
hydrodynamics
液体と気体を総称して流体といい、その運動を論ずる学問を流体力学という。とくに流体の静止状態を対象とする場合、流体静力学hydrostaticsという。浮力に関するアルキメデスの原理、水圧機の基礎を与えるパスカルの原理などがその範囲に入る。これに対して運動中の流体を対象とする場合が流体動力学hydrodynamicsである。
[今井 功]
流体力学の確立
水路、水道、噴水など実際方面の応用から、流体力学についての素朴な知識は古くから蓄積されていたが、流体力学として学問体系が成立したのは18世紀で、スイスのD・ベルヌーイやオイラー、フランスのラグランジュによって完全流体の運動方程式が樹立されたのに始まる。19世紀なかばにはフランスのナビエとイギリスのストークスによって、粘性流体の運動方程式が提唱され、流体力学の基礎は確立した。1880年にはイギリスのレイノルズによって乱流の概念が導入され、さらに20世紀に入ってドイツのプラントルの境界層理論の提出により、流体力学の現代化が始まる。これはアメリカのライト兄弟による飛行機の誕生と相まって、航空力学という新分野を生み、流体力学の飛躍的な進歩が始まる。1930年代からは、飛行機の高速化に対応して高速流体力学が展開され、第二次世界大戦の前後を通じて亜音速、遷音速、超音速の流体力学が確立する。さらに、宇宙ロケットの登場は極超音速流および希薄気体の力学を促した。一方、内燃機関、タービンに関しての熱現象や化学反応を含む流体力学の研究が行われ、さらに核融合炉に関連して電磁流体力学が登場した。船舶への応用から、波浪現象の流体力学的研究がなされ、これはまた海洋工学にも関連する。台風の発生・進行など大気現象の流体力学も重要である。これら多彩な新分野が開発される一方、乱流現象の研究は、流体力学の基礎として現在着実に進められている。
[今井 功]
流れの場
流体の微小部分を流体粒子という。流体を連続物体とみなす流体力学の立場では、これらの流体粒子によって流体が構成されていると考える。各流体粒子は並進速度vで動き、角速度Ωで自転している。この並進速度vが流体の各点における速度である。いま、点Pにある流体粒子から出発して速度vの方向に隣接している流体粒子を次々とつないでいくと、一つの曲線が得られる。これをP点を通る流線という。流線は、その上の各点の流速の方向を示す曲線である。一つの閉曲線Cをとり、その上の各点を通る流線を引くと、それらの流線を壁とする管ができる。これを流管という。流体はあたかも流管の中を流れているようにみえる。時間的に変化しない流れを定常流という。定常流では流体粒子は流線に沿って運動するから、流体中に色素を流せば、それによって流線が観察される。非定常流では、粒子の軌跡は流線とは一致しない。
隣接した流体粒子の速度が異なる場合、粒子は自転する。その角速度Ωは
で与えられる。ωは渦度(うずど)とよばれる。点Pにある流体粒子から出発して、自転軸の方向、すなわち渦度ベクトルの方向に次々とつないで得られる曲線をPを通る渦線(うずせん)という。また、一つの小さい閉曲線上の各点を通る渦線を壁とする管を渦管(うずくだ)という。微小断面積の渦管の内部にある流体部分を渦糸(うずいと)という。流速vと渦度ωとの間には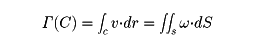
の関係式が成り立つ。ここでCは任意の閉曲線、SはCを縁とする曲面である。Γ(C)はCに沿う循環とよばれ、Cを通り抜ける渦線の総数を表す。ω=0のとき流れは「渦なし」、ω≠0のとき流れは「渦あり」という。渦なしの流れでは流速はv=gradΦのように表される。Φを速度ポテンシャルという。流体粒子は一般に時間的に体積や形を変化する。その膨張速度はΘ=divvで、変形速度はテンソルeik=∂vi/∂xk+∂vk/∂xiで与えられる。ある瞬間に球形の流体粒子は角速度ω/2で自転しながら並進速度vで動き、かつ膨張速度Θで膨張あるいは収縮しながら楕円(だえん)体に変形している。
[今井 功]
流体力学の基礎方程式
流れの状態を完全に記述するためには、流体中の各点の流速vのほか、圧力p、密度ρ、温度Tなどの物理量がわかればよい。自然現象の一つとして、流体の運動は質量・運動量・エネルギーの保存法則に支配される。これを数式で表現したものが流体力学の基礎方程式である。まず、質量保存の法則は、
という微分方程式で表される。これを連続の方程式という。次に運動量保存の法則は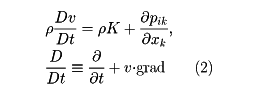
で表される。ここでD/Dtはラグランジュ微分とよばれ、流体粒子の運動に伴う時間的変化を意味する。したがってDv/Dtは加速度である。またKは流体の単位質量当りに働く外力、pikは応力テンソルである。(2)は流体とは限らず任意の連続物体に対する運動方程式であるが、実在の流体では、応力テンソルpikが変形速度テンソルeikの一次式として
pik=-pδik+λΘδik+μeik (3)
の形に表される場合が多い。比例係数μ、λをそれぞれ粘性率、第二粘性率という。また、μ'=λ+(2/3)μを体積粘性率という。普通、μ'=0と仮定される。これをストークスの仮定という。(3)の関係が成り立つ流体はニュートン流体、成り立たない流体は非ニュートン流体とよばれる。後者の例としては高分子やコロイドの溶液がある。(3)を(2)に代入して得られる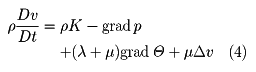
が粘性流体の運動方程式であって、ナビエ‐ストークスの方程式とよばれる。
連続の方程式(1)はDρ/Dt+ρdiv v=0の形に表すこともできる。液体のような「縮まない流体」ではDρ/Dt=0であるから、(1)はdiv v=0と簡単化される。この場合、流速vと圧力pは連続の方程式とナビエ‐ストークスの方程式だけで完全に決定される。気体のような「縮む流体」では、密度ρも変数となるので、さらに他の条件を考慮する必要がある。そのためには、エネルギー保存の法則から導かれる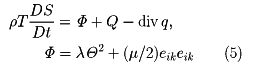
を使う。すなわちエネルギー方程式である。ここでTは温度、Sはエントロピー(単位質量当り)、Qは熱源(単位体積当り)、qは熱流である。Φは粘性によって流体の運動エネルギーが消滅して熱が発生する(単位体積当り)ことを意味し、散逸関数とよばれる。
[今井 功]
完全流体の運動
粘性のない流体すなわち完全流体では、運動方程式(2)は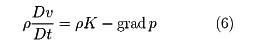
となる。これをオイラーの運動方程式という。また、エネルギー方程式(5)のかわりに、密度ρと圧力pの間にその流体の運動状態に特有の関数関係ρ=f(p)が成り立つものと仮定して議論することが多い。このような仮想的な流体をバロトロピー流体という。バロトロピー流体では、外力が保存力(K=-gradΩ)の場合、運動方程式(5)は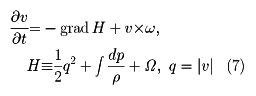
と書き表される。これから、ベルヌーイの定理(定常流では流線および渦線上でHは一定である)、圧力方程式(渦なしの流れでは∂Φ/∂t+H=f(t))、ラグランジュの渦の不生不滅の定理、ヘルムホルツの渦定理(渦糸の強さ、すなわち渦度×断面積は渦糸の全長を通じて一定で、かつ時間的に変化しない)、ケルビンの循環定理(流体粒子で構成される閉曲線に沿っての循環は時間的に一定不変である)が得られる。
縮まない流体の渦なしの流れでは、連続の方程式(1)は、速度ポテンシャルΦに対するラプラスの方程式ΔΦ=0になる。これを解けば、流速はv=gradΦで、また圧力pは圧力方程式から求められ、流れの中に置かれた物体に働く力は、物体表面に働く圧力の合力を計算すれば得られる。こうして、「静止している完全流体中を等速運動する物体には抵抗が働かない」というダランベールのパラドックスに到達する。縮む流体では、Φに対する方程式は複雑になる。しかし、とくに平衡状態からのずれの小さい場合には、近似的に波動方程式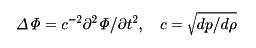
となる。音波の現象はこれに基づいて議論される。cは音速である。一般に流速Uと音速の比M=U/cをマッハ数とよび、M<1の流れを亜音速、M>1の流れを超音速という。また、亜音速と超音速の領域が共存する流れを遷音速であるという。超音速の流れでは、一般に衝撃波が現れる。これは、速度、密度、圧力、温度などが不連続的に変化する面で、強烈な音波の一種である。
[今井 功]
粘性流体の運動
縮まない流体の場合、div v=Θ=0で、流れを表す代表的な長さをl、流速をU、流体の密度をρとすると、ナビエ‐ストークスの方程式(4)は無次元の形でDv/Dt=K-gradp+R-1Δvと表される。ただし、R=ρUl/μは無次元の数で、レイノルズ数とよばれる。流れの境界の形が相似であるような二つの流れについて、流れの場全体が相似であるためには、両者のRは一致しなければならない。これをレイノルズの相似法則という。
加速度Dv/Dt=∂v/∂t+(v・grad)vは、流速vについて二次の項を含むために、(4)は非線形方程式として数学的な取扱いが困難である。Rの小さい場合は、(v・grad)vを無視したり、U∂v/∂xで代用する近似が行われる。前者をストークスの近似、後者をオセーンの近似という。Rの大きい流れでは、粘性項R-1Δvを無視すると、完全流体のオイラーの運動方程式になる。ただ物体表面では速度勾配(こうばい)の大きい薄層が現れる。これを境界層という。その方程式は、表面に沿ってx軸をとれば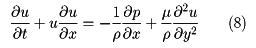
である。ただし、uはvのx成分である。これをプラントルの境界層方程式という。
高速気流では、圧縮性(密度変化)と粘性の影響が同時に現れる。この場合、粘性による摩擦熱の発生を考慮する必要がある。M>5程度以上の流れは極超音速流とよばれ、物体の先端から出る衝撃波が物体表面を覆う境界層と一体となる。
[今井 功]
『A・H・シャピロ著、今井功訳『流れの科学』(1977・河出書房新社)』▽『木村竜治著『改訂版 流れの科学』(1985・東海大学出版会)』▽『流れの可視化学会編『流れのファンタジー――写真がとらえた流体の世界』(1986・講談社)』▽『今井功著『流体力学』(1993・岩波書店)』▽『戸田盛和著『流体力学30講』(1994・朝倉書店)』▽『神部勉編著、金田行雄・石井克哉・後藤俊幸著『流体力学』(1995・裳華房)』▽『日本流体力学会編『流体力学ハンドブック』第2版(1998・丸善)』▽『古川明徳・瀬戸口俊明・林秀千人著『流れの力学』(1999・朝倉書店)』▽『D・J・トリトン著、河村哲也訳『トリトン流体力学 』上下・第2版(2002・インデックス出版)』▽『澤本正樹著『流れの力学――水理学から流体力学へ』(2005・共立出版)』
改訂新版 世界大百科事典 「流体力学」の意味・わかりやすい解説
流体力学 (りゅうたいりきがく)
hydrodynamics
外力や境界の存在の下での流体のつりあいや運動を議論する学問。流体のつりあいを論ずる流体静力学はアルキメデスの原理を発見したアルキメデスに,一方,流体の運動を論ずる流体動力学はレオナルド・ダ・ビンチ,ガリレイ,E.トリチェリにその先駆をみることができる。これらの人々による実験的な事実をふまえて,運動物体に働く抵抗を慣性抵抗(速度の2乗に比例)と粘性抵抗(速度こう配に比例)に大別するなどの貢献をしたのがニュートンである。しかし連続体の力学として問題をとらえ,圧力という流体特有の概念に立って,理想化ではあるが粘性のない流体,すなわち完全流体の運動の基礎方程式を導出したのはL.オイラーであり,これを継承したのがJ.L.ラグランジュであった。これに先立ち,圧力,運動エネルギーおよび位置エネルギーの総和が流線に沿って一定であるというベルヌーイの定理の原型を確立し,また今日の流体力学の名づけ親となったのはD.ベルヌーイである。
一方,運動方程式とともに重要な連続の方程式を質量の保存則に基づいて導入したJ.ダランベールは,完全流体の理想化の下では,流体中を一定速度で進行する物体に働く力が0となり,実在の流体と矛盾するという,〈ダランベールのパラドックス〉を見いだした。完全流体の理論はこのような欠陥があるにもかかわらず,その美しさから多くの数学者をひきつけ,複素関数論,調和関数(ポテンシャル)論の発展と表裏をなすとともに,ラグランジュ,H.L.F.vonヘルムホルツ,ケルビンらによる渦理論によって実際問題の解明に力があった。
ニュートンの粘性法則に従う粘性流体の基礎方程式が導出され,実在の流体が粘性をもつことによる実験的事実を解明する基礎がきずかれるには,フランスのナビエLouis Marie Henri Navier(1785-1836),G.G.ストークスを待たなければならなかった。ナビエ=ストークスの方程式がこれであって,オイラーの方程式を粘性0の特別な場合として含む,単純な流体に対する流体力学の基礎方程式がここに完成した。ただし方程式の非線形性のために,ストークスの近似の成り立つ,慣性項と粘性項の比(レーノルズ数といい,Reで表す)が小さい場合を除いては数値的な解法が必要であり,またReが大きくなると,O.レーノルズが円管内の流れの実験でみいだしたように整然とした層流から時空的に不規則で乱れた乱流に移行するという乱流解が含まれている。この意味でレーリーの提唱した密度一定の流れがレーノルズ数によって整理できるという相似則,またオイラーによる空気の圧縮性が流速を音速で割ったマッハ数によって支配されるという相似則の意義は大きい。
一方,20世紀初頭来の航空機の発達は,レーノルズ数の大きい流れの中の翼のような物体の抵抗が,完全流体の理論とそれをもとにした翼面の境界層の理論によって定まるというプラントルの境界層理論(1904),翼の揚力が翼のまわりの循環によって定まるというクッタ=ジューコフスキーの定理(1902,06)によるところが大きい。航空機の高速化は第2次大戦の前後から今日にかけて音速に近い流れ,超音速,さらに極超音速の流れの研究を促進した。
現在の流体力学は,乱流や微粒子の混合体のように統計的処理を必要とする統計流体力学,分子運動論の助けを借りる必要のある希薄気体力学,さらに電離気体や反応性気体のように,電磁現象,化学現象など力学の範囲を離れた取扱いが必要なものも対象としており,単純な流体でなく広義のあらゆる流れの現象を包括する体系をめざしている。
→電磁流体力学 →流れ →粘性 →乱流
執筆者:橋本 英典
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「流体力学」の意味・わかりやすい解説
流体力学【りゅうたいりきがく】
→関連項目機械工学|境界層|ジュコーフスキー|水力学|乱流
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「流体力学」の意味・わかりやすい解説
流体力学
りゅうたいりきがく
fluid mechanics; hydrodynamics
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の流体力学の言及
【ベルヌーイ家】より
…【清水 昭信】 ダニエルは1721年バーゼル大学で医学博士号を取得,その後25年から8年間ペテルブルグに滞在し,L.オイラーとともに数学,物理学の研究を精力的に行った。帰国後バーゼル大学の教授に就任するとともに,ペテルブルグ時代の研究を《流体力学》(1738)にまとめた。彼の研究は多岐に渡るが,歴史上有名なのは流体力学における二つの業績,すなわち分子運動論の立場に立った気体の諸性質の研究と,定常流に関するベルヌーイの定理の提出である。…
【水力学】より
…流体や気体のように自由に変形する物質を固体と対比して流体というが,流体が流れるときの圧力変化や周囲の物体に及ぼす力を調べる学問は,水力学,流体力学,空気力学,レオロジーなど,さまざまな名まえで呼ばれる。このうち,空気力学aerodynamicsは高速の気体の流れを,レオロジーはコロイドや高分子のように複雑な構造をもつ液体の流れを主として取り扱い,独立した分野を形づくっている。…
※「流体力学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

