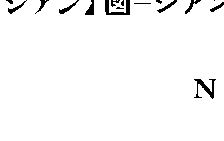精選版 日本国語大辞典 「シアン」の意味・読み・例文・類語
シアン
シアン
- 〘 名詞 〙 ( [英語] cyan ) 色の名。印刷インキの原色の青。
改訂新版 世界大百科事典 「シアン」の意味・わかりやすい解説
シアン
Cyan[ドイツ]
ジシアンdicyan,シアノーゲンcyanogenともいう。化学式(CN)2。無色の有毒の気体で,その毒性はシアン化水素に匹敵する。シアン化水素を触媒の存在下で空気,塩素,二酸化窒素等で直接酸化させると生成する。実験室では,シアン化ナトリウムNaCNと硫酸銅CuSO4から次の反応によって得られる。
4NaCN+2CuSO4
─→(CN)2+2Na2SO4+2CuCN
(反応温度50~55℃)
合成は性能のよいドラフト中で行わなければならない。生成したシアンは-80℃に冷却したステンレス製シリンダーに集め,ねじ付固定バルブで閉めて栓をして常温にもどす。また,シアン化水銀Hg(CN)2と塩化水銀(Ⅱ)を加熱しても得られる。特有な臭気がある。沸点-20.7℃,凝固点-27.9℃,沸点での比重0.9537。水1容にシアンの気体4容が溶ける。エチルアルコール,エーテルにも可溶。分子は対称中心があり,直線構造をもつ(図参照)。シアンの化学的な性質は塩素に似ていて,きわめて多くの物質と反応し,付加化合物をつくる。不純な気体を300~500℃に熱すると重合体パラシアノーゲン(CN)nを生ずる。O2と(CN)2との化学量論的割合の混合物を燃焼させると,化学反応においてこれまでに知られている最高温度の炎(約5050K)を生ずる。濃塩酸で加水分解させるとオキサミド(CONH2)2となる。これは,水に難溶性で吸湿性がなく,他の肥料とも混合可能な,よい緩効性肥料として用いられている。シアン化物はいずれも生物に対して毒性を示すので,工場排水に含まれるシアン化物に対しては排出基準が設けられている。
執筆者:漆山 秋雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
化学辞典 第2版 「シアン」の解説
シアン
シアン
cyanogen, cyan
【Ⅰ】シアン(cyanogen):(CN)2(52.03).ジシアン(dicyan)ともいう.塩化銅(Ⅱ)または硫酸銅(Ⅱ)の濃水溶液に,シアン化カリウムまたはシアン化ナトリウムの濃水溶液を加えると生成する.-90 ℃ では斜方晶系結晶で,N≡C-C≡Nの直線形分子.N-C約1.15 Å,C-C約1.38 Å.室温では猛毒の無色の気体.淡いアーモンド臭がある.融点-27.9 ℃,沸点-21.2 ℃.水に易溶,アルコール類,エーテルに可溶.水溶液は加水分解して,シアン化水素HCNとシアン酸HOCNになる.また,アルカリ水溶液ではシアン化アルカリになる.これらの性質はハロゲン(たとえば Cl2)に似ているので,ハロゲノイドともいわれる.水溶液を室温で長く放置すると,シュウ酸,アンモニア,尿素など種々のものを生成する.燃焼させるとピンク色の炎をあげて燃え,4600 K の高温に達するので炎光分析(フレームスペクトル)に用いられる.300 ℃ で長く加熱すると,褐色固体のポリマーのパラシアン(paracyanogen)になる.さらに加熱すると,パラシアンは約800 ℃ で再分解をはじめて (CN)2 を生じ,さらに約1000 ℃ で遊離基CNを生じはじめ,約1500 ℃ 以上になるとCとNとに分解する.パラシアンは図のような鎖状のポリマーと考えられる.

シアンは,有機合成やチオシアナト化合物合成の原料となるほか,殺虫剤として用いられる.[CAS 460-19-5]【Ⅱ】シアン(cyan):青緑色系の色.たとえば,カラー写真などでポジの赤,青,緑の三原色中,赤の補色で,ネガではポジの赤色に対応した部分をこの色で着色する.吸収の中心は約650 nm.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「シアン」の意味・わかりやすい解説
シアン
しあん
cyan
炭素と窒素の化合物。シアノーゲン、ジシアン、オキサルニトリルなどともいう。触媒の存在下で、シアン化水素を空気または塩素、二酸化窒素で直接酸化して得られる。金属シアン化物の熱分解や、硫酸銅(Ⅱ)水溶液とシアン化アルカリ水溶液との反応によっても得られる。無色の気体。苦扁桃臭がある。N≡C-C≡Nの直線分子。青色の炎をあげて燃える。酸素と混合して燃焼させると、炎の温度は約5000℃にも達する。水溶液は分解してシアン化水素、シアン酸を生成し、アルカリ性溶液でシアン化物とシアン酸塩を生じるなど、ハロゲン元素と似た性質を示す。エーテルなど有機溶媒に溶けやすい。吸熱化合物であるが、純粋なものは850℃まで安定である。不純なものは300~500℃で重合して、褐色のパラシアンの塊を生じ、800℃でシアンにふたたび分解する。シアンの誘導体も重合しやすい。シアン化水素と同じく猛毒で、蒸気の最大許容量は10ppmという。
[守永健一・中原勝儼]
シアン(データノート)
しあんでーたのーと
シアン
(CN)2
式量 52.0
融点 -27.9℃
沸点 -21.17℃
比重 1.806(空気=1)
溶解度 450mL/100g(水20℃)
2300mL/100g(エタノール20℃)
500mL/100g(エーテル20℃)
色名がわかる辞典 「シアン」の解説
シアン【cyan】
百科事典マイペディア 「シアン」の意味・わかりやすい解説
シアン
→関連項目海洋投棄規制条約
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「シアン」の意味・わかりやすい解説
シアン
(2) cyanogen 化学式 (CN)2 。ジシアン,シアノーゲンともいう。無色,特有の刺激臭の気体,猛毒。 N≡C-C≡N の構造をもつとされている。融点-27.9℃,沸点-20.7℃。水,エチルアルコール,エーテルに可溶。約 300℃で長時間熱すると,重合してパラシアン (褐色固体) になる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「シアン」の解説
シアン
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...