精選版 日本国語大辞典 「品詞」の意味・読み・例文・類語
ひん‐し【品詞】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] parts of speech の訳語 ) 文法上の意義・職能・形態などから分類した単語の区分け。欧米語の学校文法では、現在一般に八品詞(名詞・代名詞・形容詞・動詞・副詞・接続詞・前置詞・間投詞)とされる。国文法では、名詞・数詞・代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞・助詞・助動詞が挙げられるが、併合、細分する場合もあり、また、学説によって異同がある。「品詞」の語は、日本文法書としては、明治七年(一八七四)に田中義廉が「小学日本文典」で七品詞を説いたのが最も早い。
改訂新版 世界大百科事典 「品詞」の意味・わかりやすい解説
品詞 (ひんし)
文法用語の一つ。それぞれの言語における発話の規準となる単位,すなわち,文は,文法のレベルでは最終的に単語に分析しうる(逆にいえば,単語の列が文を形成する)。そのような単語には,あまり多くない数の範疇(はんちゆう)(カテゴリー)が存在して,すべての単語はそのいずれかに属している。一つの範疇に属する単語はある種の機能(用いられ方,すなわち,文中のどのような位置に現れるか)を共有している。こうした範疇を従来より品詞parts of speechと呼んできた。名詞とか動詞とかと呼ばれているものがそれである。
品詞の本質
単語というものは,その圧倒的多数が現実世界に存在する何か(事物,運動・動作,性質,関係等)を表している。したがって,すべての単語はその表しているものの性格に規定されて,他の単語とはどこかしら異なる機能を有している。品詞というものが機能を共通にする単語の集合であるということと,すべての単語がそれ独自の機能を有する(有さざるをえない)ということとの関係を明確にしなければ,品詞の本質には迫れない。そこで,かつて誰も同一品詞に属することを否定したことのない日本語の二つの単語,〈イヌ〉と〈散歩〉と,かつて誰もそれらと同一品詞に属するとしたことのない一つの単語,〈歩ク〉を例にとって,その関係を見てみよう。
まず,〈散歩〉と〈歩ク〉を見ると,これらの単語の表すものは決して同じではないが,比較的互いに近いものであるとはいえよう。したがって,表すものの性格がその単語の機能を規定するという点だけからそれらの機能を予想するならば,これら二つの単語の機能はかなり似かよっているはずである。しかし,実際にはこれらの機能には非常に大きな差異が認められる。たとえば,〈歩クコト〉〈歩クヒト〉とはいえるが〈散歩コト〉〈散歩ヒト〉とはいえない。あるいは,〈散歩ハ体ニヨイ〉といえるが,〈歩クハ体ニヨイ〉は破格である。こうした機能上の差異は,それらの表すものが比較的近いということから考えて,表すものの性格上の差異から必然的に生じた機能上の差異ではない。それでは,この差異はどうして生じたのであろうか。それは,日本語という言語がこれら二つの単語に異なる位置を与えたからだ,としか考えようがないであろう。
次に,〈イヌ〉と〈散歩〉を比較してみよう。今度は,これらの単語の表すものは非常に大きく違っている。前者は,ある種の事物を表し,そうした事物に含まれるある個体をとってみても,それはある一定の期間(〈イヌ〉と呼ばれるようになってから呼ばれなくなるまでの間,つまり,その犬の一生の間)を通じて,犬としての性格を呈しつづけるのである。一方,〈散歩〉の表すものは,そのような事物とはいえず,(主として)人間が比較的短い時間に行うある種の行為を表すだけである。したがって,表すものの性格からいえば,これら二つの単語にはきわめて大きな機能上の差異があることが予想される。にもかかわらず,これらの単語には顕著な機能上の共通性がある。たとえば,〈犬ガ好キダ〉〈散歩ガ好キダ〉といえるし,〈犬ダ〉〈散歩ダ〉ともいえる。もちろん,〈イヌコト〉〈散歩コト〉などとはいえない。こうした機能上の共通性の存在も,上に見た二つの単語の機能上の差異と同様に,日本語がこれら二つの単語に(この場合は)同じ位置を与えたからだ,としか考えようがない。
すなわち,日本語はそれ自身の独自性において(つまり,現実世界の状態に完全に規定されてではなく)ある単語同士を同列に扱い,ある単語同士は違った扱いをする,という状態を呈しているわけである。このことは,何も日本語に限ったことでなく,言語一般についていえることである。すなわち,言語は,それ自身のやり方で,それが保有する単語のあるもの同士には同じ位置づけを,別のものには違った位置づけを与えており,そのように同じ位置づけを与えられた単語の集合が一つの品詞に該当する,というわけである。
それでは,なぜ言語がこのようなことをしているのであろうか。それを考えるには,各言語の保有する単語が相当多数であること,そしてそうした単語の原則としてすべてを,その言語社会の成員のすべてが使いこなせなければならないということを前提とする必要がある。なぜ,単語が多数であるかといえば,そうでなければ人間を取り巻くあらゆることがらを表し分けることができず,言語として役に立たないからである。しかし,それぞれの単語は,前述のごとく,その表すものの性格の違いに規定されて,それぞれ独自の機能を本来的に有することになる。したがって,このままでは人間にとってとても扱いきれない対象ということになる。そこで,言語として,すべての単語を限られた数の範疇のどれかに属させ,一つの範疇に属する単語には機能上の顕著な共通性があり,ある単語がどの範疇に属するかはその単語のある機能を知れば容易にわかり,ある範疇に属することがわかればその単語のその他の機能が容易にわかる,という合理的な状態を保有していなければならないわけである。そうした範疇が,品詞なのである。もっとも,同一品詞に属する単語の機能上の共通性といっても,ゼロからつくり出すことはできないから,それらの単語の表すものの性格上の共通性にある程度依拠しなければならない。従来,たとえば,名詞を〈物の名を表すもの〉とするような定義がなされ,それが名詞の定義の一部としてある程度有効であったのは,このような事情によるわけである。
さて,単語によって表し分けられる,人間を取り巻く現実世界のさまざまな事象のほうは,限られた数の範疇のどれかに属しているという必要はまったくないから,単語を限られた数の品詞に分類するということは必然的に,それぞれの単語に関してその表す対象の性格から予想される機能と実際にその言語の中で有する機能の間にある種のずれ(ある面の誇張,ある面の無視)が存在することになる。すなわち,同一品詞に属する単語間の機能上の共通性とはそれらの単語の表すものの性格上の共通性によっては完全には説明しきれないものであり,異なる品詞に属する単語間の機能上の差異はそれらが表すものの性格上の差異によっては完全には説明しきれないものだということになる。その実例は,先に〈イヌ〉〈散歩〉〈歩ク〉を例にとって見た通りである。このような観点からすると,たとえば,二つの単語の機能上の差異がそれらの表すものの性格上の差異によって完全に説明しきれるものであるならば,そうした機能上の差異を理由に,それらが別々の品詞に属するとすることはできない,ということになる。非常にわかりやすい例で見ると,たとえば,〈イヌガ吠エテイル〉といえて〈ニワトリガ吠エテイル〉といえないという点での〈イヌ〉と〈ニワトリ〉の機能上の差異を理由に,これらが別の品詞に属するとすることはできないのである。なぜならば,〈イヌ〉によって表されうる事物の中には〈吠エル〉によって表されうる運動・動作を行いうるものがある(実際は,圧倒的多数の犬が吠えることができる)が,〈ニワトリ〉によって表されうる事物の中にはそのような運動・動作を行いうるものが,少なくともわれわれの常識の世界では,存在しないということによって,完全に説明しうる機能上の差異しかそこには存在しないからである。
従来の文法書のうち多少ともまともなものは,品詞分類を行うのに単語の機能を問題にしてきたといえるが,ある品詞を他から区別する作業における機能上の差異の選び方が研究者の主観にまかされていたり,あるいはせいぜい〈機能が大きく異なるものは異なる品詞に,あまり異ならないものは同じ品詞に〉といった原則に従っているだけであった。しかし,後者の原則にしたところで,〈大きく〉とはどの程度のことをさすのかと問いつめられれば,結局主観的な判断の域を出ないことになり,品詞というものが文法家の勝手な分類の所産ではなく,言語そのものの中に,言語そのものの必要性に基づいて存在するものなのだという仮定に反することになる。しかし,この仮定は正当なものであり,その正当性は,さまざまな品詞分類が提案されてはいるが,大枠はあまり変わらないということで証明されている。言語の中にそういう状態がなければ,多くの文法家の見解が大枠で類似するということはありえないからである。したがって,従来ある程度定説とされてきた日本語の品詞分類なども,違った品詞に属するとされている単語の間にそれらの表すものの性格上の差異によっては完全には説明しきれない機能上の差異があるかどうか,同一品詞に属するとされている単語の間にそれらの表すものの性格上の共通性によっては完全には説明しきれない機能上の共通性があるかどうかという観点から検討し直す必要があろう。
品詞の諸性質
(1)多くの言語においては,ある単語がその現れる個所によって,意味の,ある種の変異を伴いつつ,あるいは,伴わずにその語形(の一部)を交替させることがある。いわゆる屈折(活用,曲用)であるが,二つの屈折を示す単語において,その屈折の性格(屈折によって変異する部分の音形のことではなく,屈折全体の性格)が一致するならば同一品詞に属する(あるいは,少なくとも,近い関係にある二つの品詞に属する)といえるし,その屈折の性格の異なる二つの単語あるいは屈折を示す単語と示さない単語は別の品詞(あるいは,少なくとも異なる下位範疇(後述))に属するといえる。なぜならば,これこれこういうものを表すからといってこういう性格の屈折を有しなければならない理由などなく,したがって,屈折の性格(有無を含む)の共通性や差異は,表すものの性格上の共通性や差異によっては説明しきれるわけのものではないから,その言語の品詞分類と密接な関係を有するといえるのである。
(2)各言語はすべての単語をいずれかの品詞に所属させているわけであるが,それぞれの品詞がすべて等質的なものかというと,そうではなく,またそうでなければならない理由も見当たらない。すなわち,同一品詞に属すると考えられる単語同士なのに,その機能上の差異がその表すものの性格上の差異では完全には説明しきれない場合がある。そのような場合,それらの単語は同一品詞の中の異なる下位範疇に属することになる。たとえば,動詞と呼べる品詞が存在する言語における,いわゆる自動詞と他動詞の区別の問題であるが,その両者の機能上の差異が,表すものの性格上の差異によっては完全には説明しきれない場合,この区別がその言語内に存在することになり,それらは動詞という品詞の中の下位範疇をなすことになる。名詞と呼べる品詞が存在する言語において,いわゆる性あるいは数の区別が同様の理由で存在が確認されるならば,それらも名詞の内部の下位範疇を形成することになる。アフリカのバントゥー系の諸言語その他では名詞が〈クラス〉と呼ばれる数多くの下位範疇に分かれている(〈スワヒリ語〉の項参照)。また,いわゆる代名詞が一般の名詞と同様の理由で区別されていることが確認され,代名詞と一般の名詞との機能の面での共通性からそれらが品詞としては同一のものに属することが一方において確認されるなら,それらは一つの品詞の中で別々の下位範疇を形成することになる。ただし,下位範疇の中にもヒエラルキーがありうる(たとえば,品詞Aかつ下位範疇BとCから成り,Bは下位範疇DとEから成るとすると,D,EはAの下位範疇であるだけでなく,Bのそれでもある)と考えられ,この面での一般言語学的な,また個別言語に即しての研究はまだまだ不十分である。
(3)ある品詞の単語が屈折を示し,そのある形がその単語の他の形とは非常に異なる機能を有することがある。たとえば,英語の動詞語幹に-ingがついた動名詞,あるいは,同形で〈~しながら〉という意味を表す分詞(現在分詞)は,動詞のその他の形とは非常に異なる機能をもっている。たとえば動名詞は,動詞の他の形とは異なり,名詞に似た用いられ方を有する。これらは,原則としてすべての動詞に対応して存在するので,(2)に見た下位範疇とは本質的に異なる。こういうものを仮に派生的範疇と呼ぶことにする。フランス語の不定形などもこういった性格のものである。
以上見たように,品詞の内部に下位範疇の存在が可能であり,また,派生的範疇のようなものも存在しうるということは,人間の言語が,それが保有するすべての単語を限られた数の品詞に所属させてさえいれば,単語の問題に関してある程度の複雑さをも許容できるものであることを暗示している。
(4)各言語にどういう品詞が存在するかを見るためには,当然のことながら,何を単語とするかという問題が解決されている必要がある。それだけで発話できるものは,少なくとも一つの単語を含むといえるから,問題はそれだけでは発話できないがなおかつある程度以上の独立度を保有しているもの(たとえば,日本語のさまざまな助詞など)の扱いである。その詳しい議論は省略するとして,もしそれだけで発話されることはまずないがある程度以上独立的であるものを単語とすると,そのような単語は当然なんらかの品詞に所属していることになるが,一般に,それぞれの品詞に所属するそうした単語の数は,それぞれにつき少数で,かつ,下位範疇にさらに分かれている傾向が強い。
(5)言語によっては,ある品詞に属する単語がある種の音形上の特徴を有することがある(たとえば,日本語の形容詞(終止形)は〈イ〉で終わる)。ただし,これはあらゆる場合にそうであるというわけでない。また,ある品詞に属する単語がある種のアクセント上の特徴を共有するといったことが認められる。また,品詞の違いによって,それに属する単語の構造が異なるといったこともよく認められる事実である。
諸言語と品詞
ある言語のすべての単語の品詞分類が完成すると,そのおのおのの品詞に名称を与えることになるが,その名称は,言語学的にいえばどんなものであってもよいし,番号であってもよいのであるが,通常は,その品詞に属する単語(の大多数)が表すものの性格や,それらの機能を反映した名称を与えることが多い。前者の例としては,名詞や動詞があり,後者の例としては前置詞などがある。
以下に,そのようにして従来与えられてきた名称を取り上げつつ,人間の言語にどのような品詞が存在する傾向があるかを見てみる。ただし,注意しなくてはならないことは,ある言語のある品詞は,その言語の文法構造の枠内でのみ意味を有するということである。したがって,ある言語の文法において名詞と呼ばれるものと別の言語の文法において名詞と呼ばれるものが,仮にその名称の与え方が適当であったとしても,言語学的にいって同じものであるわけでなく,そもそも同じかどうかという問いかけ自体が無意味なのである。問題にできるのは,せいぜい,それらがそれぞれの文法構造の中において占める位置が〈似ているか似ていないか〉〈どの程度似ているか〉といったことである。
名詞
ある品詞に属する単語の大多数が事物といえるものを表す場合,〈名詞〉という名称が与えられることが多い。事物を表すものが一つの品詞を形成する(傾向にある)理由は,事物はその個体をとっても,時間的あるいは空間的に異なる無数の局面の中にその座を占めることができ,かなり長期にそれ自身としての性格を保持しつづけるという点(特殊性)が,人間の認識を通じて言語のあり方を規定することにあるといえよう。こうした品詞が存在するならば,そこに属する単語の数が非常に多いことは合理的に推察できることである。また,言語によっては,こうした品詞に属する単語に屈折が存在しうるが,そのおもな根拠は,後で見る動詞を中心とする文の述語部分の表す運動・動作と,その名詞の表す事物との間の関係を,なんらかの形で表さなければならないということにある。すなわち,名詞がある屈折形をとることでそうした関係(たとえば,主体であるとか対象であるとか)を表すということが,合理的にそのような関係を表しわける方法の一つであるからである。ロシア語,フィンランド語などの〈格〉の存在がこれの例である。
代名詞
次に,話し手本人とか話し相手とか第三者を表すのに用いられる単語,あるいはそれらに加えて,その事物の本質を捨象して,話し手や話し相手との位置関係等にのみ依拠して事物を表すのに用いられる単語が一つの範疇を形成していることが確認されるならば,それらは〈代名詞〉と呼ばれることが多い。英語などにおいては,そういう内容を表す単語は,普通の名詞にはつくことのできる冠詞が決してつかないとかいった,表すものの特殊性では完全には説明しきれない機能上の特殊性があるので,少なくとも普通の名詞とは文法的に区別されている(ただし,名詞との機能上の共通性も顕著であるので,おそらく,別の品詞というより,同一の品詞の異なる下位範疇を形成している,とすべきであろう)が,日本語の場合,俗に代名詞と呼ばれるものは,表すものは他の名詞に比して特殊に思われても,その機能には特殊性は認められそうになく,仮にあってもそれは表すものの性格によると考えられるので,名詞に所属するだけで,その中の下位範疇を(すら)形成していないと思われる。
動詞
ある品詞に属する単語の多数が運動・動作といったものを表す場合,その品詞は一般に〈動詞〉と呼ばれる。運動・動作は一般にある時ある場所で発生し比較的早期に消滅する現象であり,そういうものであることが認識を通じて言語のあり方に反映したものであるといえよう。おそらく圧倒的多数の言語では,名詞と呼べる品詞と動詞と呼べる品詞が別の品詞として存在していようし,少なくともなんらかの範疇面での区別が事物を表す単語と運動・動作を表す単語の間に存在する(たとえば,品詞としての区別でなくても,一方が他方の派生的範疇を形成するといった形である)はずである。なお,動詞と呼べる範疇に属する単語は屈折を有することが多いだけでなく,派生的範疇が存在しやすいと考えられる。
形容詞,(形容動詞)
ある品詞に属する単語(の多数)が事物のある性質(その事物がそれであることの全性質ではなく,その事物にとっては部分的な,あるいは,一時的な性質)を表すものである場合,〈形容詞〉という名称がその品詞に与えられることが多い。もっとも,運動・動作を表す単語と性質を表す単語が別々の品詞を形成しない言語も十分に存在可能であり,アイヌ語などはこれに属すると考えられる。ここにいう性質も,運動・動作も,一般的にはある事物にとっては部分的であるか一時的なものであるという点での共通性が,それらを表す単語を同一の品詞に属させることも可能であることの根底にあるようだ。なお,形容詞と呼びうる品詞が存在する場合でも,それに属する単語が非常に少ないといったことがありうるし,その機能の違いによって事物の性質を表す単語が複数個の品詞(または同じ品詞の下位範疇)に分属することもあり,また,派生的範疇も存在しやすい。また,名詞に下位範疇が存在したり,屈折が存在する場合には,形容詞にも対応する下位範疇や屈折が存在することがよくある。
日本語には,形容詞と呼んでよい品詞が確かに存在する(〈赤イ〉とか〈悲シイ〉とかが属する)が,〈形容動詞〉と通常呼ばれているものが現代日本語に認められるとする根拠は薄弱である。〈静カダ〉〈困難ダ〉などをさすわけであるが,〈静カ〉〈困難〉だけでも用いられること(例〈ココハスゴク静カ〉),ここにあらわれる〈ダ〉が,〈イヌダ〉の〈ダ〉と異なるものであるとは思えないこと,などから〈静カダ〉等をそれぞれ単一の単語と考えることに無理があるのである。ただし,〈静カ〉〈困難〉などは〈ナ〉と結びつきうることから,それらを名詞に属すると考えるとしても,一つの下位範疇を形成することは確からしい(たとえば,普通の名詞は,たとえば〈褐色〉のような,かなり性質的なものを表すものでさえ,〈褐色ナ〉とはいえないことに注意せよ)。
数詞
ある範疇に属するものが,事物の数を表すものである場合,〈数詞〉と呼ばれるのが普通である。ただし,ただ数を表すからといって数詞と呼ぶのは,言語学的にいって正確でないことは,これまでに見たことからわかるであろう。また,数を表すものがある範疇を形成していても,多くの言語では形容詞の下位範疇として存在するのが普通であろう。また順番を表す単語が一つの範疇を形成する場合,〈序数詞〉(これに対して,普通の数を表すものは,〈基数詞〉)と呼ばれることが多いが,そういうものが範疇を形成していたとしても,おそらく形容詞の下位範疇であろう。日本語においては,数や順番を表すものは,普通の名詞であるといってよいであろう。
助動詞
ある運動・動作の本質そのものでなく,その運動・動作の起こった(起こる)時と現在とのおおまかな時間的関係とか,その運動・動作に対する話し手の意図等とかを,動詞に近接して用いられる単語で表し,それらの単語が一つの範疇を形成する時,〈助動詞〉という名称が与えられることが多い。この種の事象の表し方は,言語によってきわめて多様な状態を呈するものであり,助動詞と呼びうる品詞(あるいは下位範疇)の存在しない言語もある。日本語でよくいわれる助動詞(〈タ〉とか〈レル,ラレル〉)は,確かにある範疇を形成しているようであるが,その内部にいくつかの下位範疇が(しかも,数少ない単語を分け合う形で)存在していると思われる。
副詞
動詞を中心とした述語のあらわす運動・動作などの様態や,起こった(起こる)時刻,場所などをはっきり表す単語が一つの範疇を形成する場合,〈副詞〉という名称が与えられることが多い。ただし,そうした事象の表し方は言語によってかなり変異しうる。たとえば,日本語の〈ユックリ〉〈ヤサシク〉〈今朝〉〈ココデ〉は,最初のものだけが副詞に属し,次のものから順に,形容詞の(一つの)派生的範疇,名詞,名詞+(格)助詞という性格のものである。
前置詞,後置詞(助詞)
文の述語によって表される運動・動作などに対する事物の関係などを表す単語があって,それらが一つの範疇を形成している場合,通常それらはその事物を表す名詞(句)に近接して現れるから,そうした名詞(句)の前に立つか後に立つかに従って,〈前置詞〉とか〈後置詞〉と呼ばれることが多い。日本語の文法では,後置詞にあたるものを〈助詞〉と呼んできたが,名詞(句)につづくもの(格助詞等)を,動詞などに続く接続助詞と呼ばれるものや,述語の末尾などに立ついわゆる終助詞と,助詞という一つの品詞にまとめて考えるのは,それらが共通に何かの後に立ち,かつ,屈折(活用)を有しないといっても,それは違った品詞に属することを積極的に示さないという意味しかなく,根拠十分とはいえない。前に立つものが異なるし,できあがるものも(終助詞がつく場合は特に)他と異なるからである。
接続詞
文と似た構造のものの表す内容と別のそうした構造を有するものの表す内容との関係を表す単語が一つの範疇を形成している場合,〈接続詞〉という名称が与えられることが多い。ただし,そういう品詞が存在する場合でも,所属する単語はかなり少数であるし,そうした内容を単語でないもので表すことも多い。
さまざまの品詞
このほか,その言語の文法構造によって,さまざまな性格の品詞が存在することになる。たとえば,名詞に付着してなんらかの意味(たとえば,既知のものであるか否か,等々)をあらわす少数にして短い単語が存在することがあり,それらが形成する品詞は〈冠詞〉と呼ばれることが多い。また,ある名詞を文によく似た構造のもので修飾する際に,なんらかの特別の単語を結びつけ役として使用する言語があり,それらは〈関係詞〉と呼ばれる品詞を形成することが多いが,そうしたものも数が少なく,かつ,その内部に下位範疇が存在しがちである。
なお,言語学的にいえば,品詞の存在にとって,それに属する単語が必ず二つ以上あるということは必要条件ではない。したがって,英語のto不定詞をつくるtoなどは,その機能上きわめて特殊であり,従来の英文法ではそうは扱われていないようだが,それだけで一つの品詞を形成しているとして,なんの差支えもない。
→文法
執筆者:湯川 恭敏
日本語の品詞研究の歴史
日本人が日本語の単語について,〈てにをは〉の一類を立てたのは恐らく鎌倉時代以前からのことで,漢文訓読法から注意されたと思われる。それ以外を〈名〉(物の名)と〈ことば〉(語,詞)とに分けたのは鎌倉時代末にみえる。この3分類は,十分に文法機能のうえから考察した結果ではなかろうが,17世紀初めのJ.ロドリゲスの《日本小文典》は,日本人が全品詞を〈名,ことば,てには〉の3語に包括していると述べている。〈てには〉は助辞,〈ことば〉は動詞(現在の用言。形容詞,形容動詞を含む),〈名〉はその他のいっさいである。一方,〈体〉と〈用〉との別も室町時代に連歌(れんが)の用語から起こっており,ほぼ後の体言,用言にあたっている。これらは主として意味上の区別であるが,〈ことば〉や〈用の言〉について,語形変化の性質が意識されていなかったとはいえない。江戸時代に初めて秩序だった分類を示したのは富士谷成章(ふじたになりあきら)で,〈名,挿頭(かざし),装(よそい),脚結(あゆい)〉の4種とし,すべての語をその中に収めようとした。〈脚結〉(《《あゆひ抄》》の項も参照)は助辞,〈装〉は用言,〈挿頭〉は修飾格に立つ諸種の語や接続詞,感動詞,事物代名詞などを含み,〈挿頭〉が最も雑多であるが,主用語である体言,用言のほかに,それらに対する副用語の一類を立てた点は重要である。成章以後,鈴木朖(あきら)は〈体の詞〉〈てにをは〉〈形状の詞〉〈作用の詞〉の4種とし,そのほか東条義門(ぎもん),富樫広蔭(とがしひろかげ)らに説があるが,大別としては成章の4区分にまさるものはない。
江戸末期以来,ヨーロッパの諸語の文典の影響をうけ,あるいはオランダ文典にあてはめて九分し,あるいは英文典に基づいて七分するなど,いろいろの説が現れたが,1897年に大槻文彦(おおつきふみひこ)の《広日本文典》の折衷的な〈8品詞説〉が出るに及んで,これが一般に学校文典の標準として行われることになった。すなわち名詞,動詞,形容詞,助動詞,副詞,接続詞,天爾遠波(てにをは。助詞),感動詞で,意味上の別とともに用法も考慮されている。その後,山田孝雄(よしお),岡沢鉦治(しようじ),松下大三郎,安田喜代門,時枝誠記(ときえだもとき)その他によってそれぞれ独自の分類が試みられたが,大槻文法に代わって現に学校文典の主流をなすのは,橋本進吉の説に基づく文部省編《中等文法》(1943)の〈10品詞〉の系統である。橋本のは,種類としては大槻の8種に松下の副体詞を加えた9品詞(後にさらに形容動詞を加えた)であって,目新しいものではないが,その分類の手順を,語義によらずに外形を手がかりとし,もっぱら機能によって明らかにしたところに特色がある。単語は,文節を構成するにあたって,単独でするもの,すなわち〈詞(し)〉と,他の語に付属するもの,すなわち〈辞〉とに二大別され,それぞれ活用の有無によって二分される。〈辞〉については助詞と助動詞とである。〈活用のある詞〉は用言で,命令形の有無を目印として動詞,形容詞を分ける(終止形の語尾を目印として動詞,形容詞,形容動詞を分ける)。〈活用のない詞〉は主語となるか否かで体言(名詞,代名詞,数詞を含む)とその他とする。主語とならないうちに修飾接続するか否かで副用言と感動詞を分け,副用言を〈用言を修飾する副詞〉〈体言を修飾する副体詞(連体詞)〉〈接続する接続詞〉の三つとする(この分類については,活用の有無より先に,一定の位格に立つか否かを問うほうが,機能による分類として適当かと思われる)。
なお,助詞,助動詞については,松下はともに〈原辞〉として他の品詞と同次元では扱わない。山田は助動詞をすべて用言の中に含めて〈複語尾〉と呼ぶ。時枝は詞辞の別を表現過程において概念過程を含むか否かに求めるので,いわゆる助動詞から,あるものを詞である接尾語として除外し,通例と範囲を異にする。形容動詞は,独立した一品詞として扱うのになお時枝その他の異論がある。そのほか総括のしかたも学説によって違っている。
以上のような品詞分類は単語総体を見渡しての学的操作であり,語性を明らかにし,単語が文構成にあずかって実際に活用されるための基礎知識ではあるが,しばしば文法学習が単語の認定とその所属品詞判定に時を費やし,学説の相違に神経を労するのは当をえない。一方,品詞と文の成分(文中における文節の位格--主語,述語など)との別,また,単語構成の要素である接辞が品詞分類の外にあることなども注意する必要がある。
執筆者:林 大
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「品詞」の意味・わかりやすい解説
品詞
ひんし
文法上の記述、体系化を目的として、あらゆる語を文法上の性質に基づいて分類した種別。語義、語形、職能(文構成上の役割)などの観点が基準となる。個々の語はいずれかの品詞に所属することとなる。
品詞の名称はparts of speech(英語)、parties du discours(フランス語)などの西洋文典の術語の訳として成立したもの。江戸時代には、オランダ文法の訳語として、「詞品」「蘭語九品」「九品の詞」のようなものがあった。語の分類意識としては、日本にも古くからあり、「詞」「辞」「てにをは」「助け字」「休め字」「名(な)」などの名称のもとに語分類が行われていたが、「品詞」という場合は、一般に、西洋文典の輸入によって新しく考えられた語の類別をさす。品詞の種類、名称には、学説によって多少の異同もあるが、現在普通に行われているものは、名詞・数詞・代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞・助詞・助動詞などである。これらのうちの数種の上位分類である「体言」「用言」などの名称、および下位分類である「格助詞」「係助詞」なども品詞として扱われることもある。なお、「接頭語」「接尾語」なども品詞の名のもとに用いられることもある。
それぞれの品詞に所属する具体的な語も、学説によって異同がある。たとえば、受身・可能・自発・尊敬・使役を表す「る・らる・す・さす・しむ(れる・られる・せる・させる)」は、山田孝雄(よしお)の学説では「複語尾」、橋本進吉の学説では「助動詞」、時枝誠記(もとき)の学説では「接尾語」とされる。現在の国語辞書では、見出し語の下に品詞名を記すことが普通である。ただし、圧倒的に数の多い「名詞」については、これを省略しているものが多い。
[鈴木一彦]
西洋文典の品詞
ギリシア語・ラテン語を源とする西洋文典においては、語を8種に分けるいわゆる8品詞が伝統的型であった。18世紀以降、英語の標準的な品詞は、冠詞・名詞・形容詞・代名詞・動詞・副詞・前置詞・接続詞・間投詞の九つとされている。このうち、冠詞と前置詞にあたるものは日本語にない。この西洋文典の品詞が江戸時代末期から日本文典に影響を与えた。たとえば鶴峯戊申(つるみねしげのぶ)『語学新書』(1831成稿)はオランダ文典に倣って、語を実体言(ゐことば)(名詞)・虚体言(つきことば)(形容詞)・代名言(かへことば)(代名詞)・連体言(つづきことば)(動詞などの連体形)・活用言(はたらきことば)(動詞)・形容言(さまことば)(副詞)・接続言(つづけことば)(接続詞)・指示言(さしことば)(「上を」「ほかに」の類)・感動言(なげきことば)(感動詞)の9種に分ける。田中義廉(よしかど)『小学日本文典』(1874)では、名詞・形容詞・代名詞・動詞・副詞・接続詞・感詞の7種に分け、助動詞・助詞は独立した品詞と認めていない。大槻(おおつき)文彦『広日本文典』(1897)に至って、和洋折衷の品詞分類としてもっとも穏当なものが示されている。助動詞・助詞(「弖尓乎波(てにをは)」と称している)を独立した品詞とし、名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・感動詞と並べて八品詞とした。これが明治以後の教科文典の標準的品詞と目されている。
[鈴木一彦]
日本の伝統的品詞分類
江戸時代末期までの、日本人の日本語に対する語分類の意識およびその実際について、おもなものをあげる。
(1)『万葉集』における「辞」。4175、4176番の「霍公鳥(ほととぎす)を詠む二首」の左注に、それぞれ「毛能波三箇辞欠之(これをかく)」「毛能波氐 乎六箇辞欠之」とある。ここには、少なくとも「も・の・は・て・に・を」などの助詞を「辞」と名づけて他と区別していた意識がみられる。
乎六箇辞欠之」とある。ここには、少なくとも「も・の・は・て・に・を」などの助詞を「辞」と名づけて他と区別していた意識がみられる。
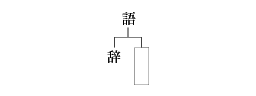
(2)宣命(せんみょう)書きにおける大字・小字の区別。宣命・祝詞(のりと)においては、「今宣(のりたまは)(久(く))奈良麻呂(我(が))兵(いくさ)起(おこす)(尓(に))被雇(やとはえ)(多利志(たりし))秦等(はたども)(乎婆(をば))遠(久(く))流(之(し))賜(たまひ)(都(つ))」(宣命)のように表記され、助詞・助動詞・活用語尾などが、体言・語幹などと区別されて小文字(本来は右寄せまたは2行割りだが、ここではすべて( )の中に表示した)で記してある。これも語分類の意識の一つである。
(3)漢文訓読の表記。漢文訓読におけるヲコト点および送り仮名としての片仮名も前述の場合と同じと考えられる。
(4)注釈書・歌論書における助辞。平安時代末期から室町時代へかけてのこれらの書では、助詞・助動詞の類を「休め字」「助け字」とよんで、他の語と区別している。
(5)『天爾波(てには)大概抄』(鎌倉時代末成立か)の分類。ここでは語を正面から二分して、「詞」と「手爾波」とし、両者の本質的な相違を説いている。この考え方は江戸時代を通じて基本的なものとなる。

(6)富士谷成章(なりあきら)『挿頭(かざし)抄』(1767)、『脚結(あゆひ)抄』(1773)。語を二分法によらず、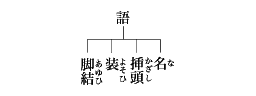
のように4種に分類する。これは、明治以後山田孝雄の文法学説に影響を与えた。
(7)鈴木朖(あきら)『言語四種(げんぎょししゅ)論』(1824刊)。3種の詞と「テニヲハ」に二分して、その本質的相違を説く。
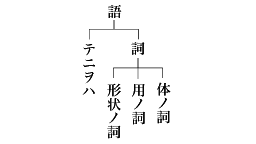
この考え方は、昭和の時枝誠記の学説に大きな示唆を与えた。
[鈴木一彦]
問題点
parts of speechというとき、partは、印欧語ではほとんど語に一致する。ところが日本語では、「私は山に登った」の場合、文を構成する直接の部分は、「私は」「山に」「登った」という句(あるいは文節)となる。つまり品詞分類と語分類との間にあるギャップが生じてくる。助詞・助動詞および連体詞・副詞・接続詞・感動詞などの位置づけが問題となるゆえんがここにある。
[鈴木一彦]
百科事典マイペディア 「品詞」の意味・わかりやすい解説
品詞【ひんし】
→関連項目形容詞|形容動詞|助動詞|接続詞|前置詞|代名詞|単語|動詞|副詞|名詞
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「品詞」の意味・わかりやすい解説
品詞
ひんし
parts of speech
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

