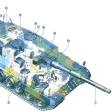翻訳|tank
精選版 日本国語大辞典 「戦車」の意味・読み・例文・類語
せん‐しゃ【戦車】
- 〘 名詞 〙
- ① 戦争に用いる車。兵車。〔日葡辞書(1603‐04)〕 〔史記‐韓世家〕
- ② 戦車砲、機関銃などの武装を有し、防護用の装甲をした車体にキャタピラを備えた車両。第一次世界大戦に初めて出現した。潜水、渡河の可能な水陸両用型など多数の種類がある。重量により、重戦車、中戦車、軽戦車に分けられ、用途により、主力(主戦闘)戦車、偵察(軽戦闘)戦車、支援戦車に分けられる。タンク。
- [初出の実例]「横行若は斜行する戦車に対しては」(出典:歩兵操典(1928)第五五一)
改訂新版 世界大百科事典 「戦車」の意味・わかりやすい解説
戦車 (せんしゃ)
tank
威力の大きな火砲を搭載し,強力な装甲板によって防護され,道路のないところでも自由に走りまわることができる戦闘車両で,陸上戦闘の中核となる兵器である。戦車のことを〈タンク〉というのは,イギリスで初めて作られた戦車の形が水槽(タンク)に似ていたことと,新兵器の秘密がもれるのを防ぐため,この名称をイギリスで使ったのが始まりといわれている。なお戦車と外形的に似ているものに自走砲がある。戦車は近接戦闘用兵器として,火力,機動力,防護力ともに高い性能が要求されるのに対し,自走砲は搭載している火砲によって相手に打撃を与えるもので,戦車ほどの機動力や防護力は要求されないのが通常である。
沿革
(1)第1次大戦時 近代的戦車が初めて戦場に姿を現したのは第1次大戦中の,1916年9月15日のことである。この日,イギリス軍のマークⅠ型戦車がソンムの戦に使用され,戦況を左右するほどの成果は得られなかったが,ドイツ軍将兵に与えた心理的効果は絶大であったといわれている。翌17年11月のカンブレの戦では,同じくイギリス軍がマークⅣ型戦車を主とする数百両の戦車を集中的に使用して,ドイツ軍陣地を深さ約10kmにわたって突破するのに成功し,戦車は陣地線突破用の新兵器として注目されるようになった。第1次大戦中にはイギリスのほかフランス,ドイツも戦車を製造し使用したが,当時の戦車の大半は旋回砲塔をもたず,エンジンは乗員室と同じ場所にむきだしで置かれていた。しかし大戦末期の18年に出現したフランスのルノーFT戦車は,全周旋回できる砲塔を車体中央部に取り付け,前部に操縦室,後部にエンジン室を配置するなど,すでに現代戦車の基本的形態を備えていた。第1次大戦当時の対戦車火器については,在来の野戦砲を対戦車火器として使用したり,小銃や機関銃用の徹甲弾を開発装備する程度でまだ本格的なものはなく,数百両の戦車が集中的に使用される状況では,戦車の進攻を阻止するのは困難であった。
(2)大戦間 第1次大戦後,将来戦の様相に関する研究が各国で盛んに行われ,それぞれの国情および用兵思想に応じて戦車についての考え方が固められていった。各国とも将来戦において戦車が有用であることは認識していたが,用法については大別して二つの考え方に分かれていた。一つは戦車を中核とした諸兵連合部隊を編成して,これを機動的に運用するというもので,他の一つは戦車を歩兵および騎兵に対する支援兵器として運用するというものである。前者を最初に唱えたのはイギリスのJ.F.C.フラーやリデル・ハートらであり,これを実行したのがドイツであった。また後者の考え方をとった代表的な国はフランスであった。
日本では1925年に戦車隊が創設され,当初はイギリスおよびフランスから購入した戦車を装備していた。27年に初めての国産戦車が試作され,その後29年から37年にかけて89式戦車や97式戦車などが出現した。当時の日本の戦車は世界にさきがけてディーゼルエンジンを採用するなど,機動力に関する技術ではすぐれたところもあったが,火力,特に戦車砲の威力や装甲防護力については,第2次大戦直前の欧米先進国の水準には達していなかった。
(3)第2次大戦時 1939年9月,ドイツ軍のポーランドに対する電撃戦によって第2次大戦は開始された。電撃戦は,航空機(急降下爆撃機)により敵部隊に銃爆撃を加えて混乱させ,続いて戦車を中核とし歩兵および砲兵等を含む機甲部隊が突進するものであった。40年5月,ドイツ軍はフランスに対しても電撃戦を遂行して成功を収めた。こうした電撃戦のあいつぐ成功により,戦車は陸上戦闘における主役の地位を確保するに至った。41年6月に開始されたドイツ軍のソ連への侵攻では,当初は電撃戦が成功するかと思われたが,しだいにソ連軍の抵抗も強まり,ドイツ軍の急進撃は不可能となった。この時期,ソ連軍が装備していたT34戦車は,ドイツ軍のⅢ号,Ⅳ号戦車より火力,装甲ともにすぐれており,ドイツ軍にとって大きな脅威となった。ドイツ軍はこれに対抗すべく,火力,装甲を強化したⅤ号パンテルPanther戦車,Ⅵ号ティーゲルTiger戦車の開発を急いだが,ソ連軍もT34戦車の搭載砲を76mmから85mmに変更するとともに,JS Ⅱ,JS Ⅲなどの重戦車を装備して対抗した。このように戦車の火力と装甲を強化する激しい競争が展開され,大量の戦車や自走砲を投入した激烈な戦車戦が各地の戦場で戦われた。なかでも東部戦線で戦われた大規模な戦車戦であるクルスク戦車戦が有名である。この戦闘でソ連軍は大規模な地雷原および対戦車壕など各種対戦車障害と,ドイツ軍を上まわる戦車,自走砲,対戦車火器を組み合わせた深さ約80kmにわたる対戦車防御組織をつくり,ドイツ軍戦車部隊の進撃を阻止した。また北アフリカ戦線ではドイツ軍,イタリア軍とイギリス軍の間で戦車戦が戦われたが(エル・アラメインの戦),途中から参戦したアメリカはM3,M4などの大量の戦車をイギリスに供給し,物量に劣る枢軸国を苦戦に追い込んだ。このように,ヨーロッパ,アフリカ戦線の陸上戦闘は戦車を中心として戦われ,物量が勝敗を決する長期消耗戦となった。一方,太平洋戦場では開戦当初,日本の戦車隊がイギリス軍を急襲して陣地線の突破に成功する例もみられたが,当時の日本の戦車は97式戦車が主力であり,連合軍が装備しているM4戦車に比べて質・量ともに劣っており,本格的な戦車戦は行われなかった。
第2次大戦中には対戦車兵器および対戦車戦法も著しく発達した。対戦車兵器としては,対戦車砲の威力向上と自走化が進むとともに,新たに開発された成型炸薬弾が個人携行の対戦車兵器用弾薬としても大量に使用された。また航空機の対戦車攻撃兵器としての価値が高まり,機関銃で装甲の弱い戦車上面を攻撃する対戦車専用の航空機も開発された。対戦車戦法に関しては,クルスク戦車戦の例にみられるように,戦車をはじめ各種の対戦車兵器と対戦車障害を巧みに組み合わせて縦深に配置した対戦車防御組織により,戦車の進撃をくいとめる戦法が編み出された。
(4)第2次大戦後 1950年に発生した朝鮮戦争,1950年代に核戦争を想定して実施された各種実験演習等を通じて,戦車の必要性,有効性があらためて認識されるに至った。特に核爆発によって発生する熱線,爆風,放射線に対して戦車はかなりの防護性があり,また核戦場では部隊の迅速な集中と分散が要求されることから,各国は新たな構想に基づいて戦車や装甲車の開発に着手し,機甲部隊や機械化部隊の整備充実に努めた。
1973年に発生した第4次中東戦争では,初期段階で対戦車ミサイルをはじめ各種対戦車火器を縦深に配置したエジプト軍陣地に対して,イスラエル軍は戦車部隊単独で攻撃をかけ,またたく間に多数の戦車が撃破された。この結果は,ミサイルをはじめとした各種対戦車火器の巧みな運用が戦車に対してきわめて有効であることを示すとともに,戦車を効果的に運用するためには,航空機や歩兵,砲兵,工兵等の密接な協力が必要なことをあらためて認識させた。現在,各国はめざましく発展している科学技術の成果をとり入れて,引き続き新しい戦車の開発を進めるとともに,すでに装備化した戦車についても火力,機動力,防護力すべてにわたって性能改善に努めている。日本でも第2次大戦後に自主開発して装備化した61式戦車,74式戦車に続いて,現在,新戦車を開発中である。一方,対戦車火器の発達も著しく,特に対戦車ミサイルをはじめとする精密誘導兵器,対戦車ヘリコプターの出現は,戦車にとって大きな脅威となっている。
用法
戦車の用法を大別すると,戦車を歩兵部隊に配属して歩兵主体の戦闘に直接協力させる方法と,戦車を主体にして歩兵,砲兵,工兵等を協力させ,機動的に運用して敵を奇襲・急襲する方法がある。第1次大戦では主として前者が用いられ,第2次大戦では主として後者が用いられた。後者の典型的な例は,ドイツ軍が第2次大戦初期に実施した電撃戦である。現代においても戦車の基本的用法は同じで,状況により戦車を歩兵部隊に配属して使用することもあり,戦車に歩兵,砲兵,工兵等を協力させる形で運用することもある。いずれの場合においても,戦車の能力を十分に発揮させるためには,航空機および対空火器による支援と歩兵,砲兵,工兵等の密接な協力が欠かせない条件である。なお,近代的な陸上戦闘部隊は戦車や装甲車化歩兵を主体にして編成されるが,戦車を主体に編成された部隊を機甲部隊,装甲車化歩兵を主体に編成された部隊を機械化部隊という。
分類
戦車は用途により,主力(主戦闘)戦車,偵察(軽戦闘)戦車,支援戦車に区分できる。また伝統的な区分として重量や搭載火砲の大きさにより,軽戦車,中戦車,重戦車に分ける方法もある。おおまかにいえば主力戦車が中戦車に,偵察戦車が軽戦車に,支援戦車が重戦車にそれぞれ対応するとみてよい。しかし,かつて支援戦車として生産された重戦車は現在ほとんど姿を消し,最近では主力戦車が第2次大戦当時の重戦車に匹敵する重量になってきている。現在の主力戦車は搭載火砲が105~125mm,重量が40~60t程度であり,軽戦車は搭載火砲が75~90mm,重量が15~25t程度である。軽戦車については特に空輸性が重視されている。
構造
標準的な戦車は全周旋回できる砲塔と車体で構成される。砲塔中央前方には砲耳軸を介して主火砲が取り付けられ,上面には目標の捜索や砲の照準に使用する照準具類がある。砲塔内には車長,砲手,装塡手の座席があり,また砲および砲塔を操作するハンドル,ハンドルの動きを砲や砲塔に伝える電気または油圧モーター,歯車装置のほか,射撃統制装置(射撃管制装置),通信機などがある。車体は中央部に砲塔が旋回軸受を介して取り付けられ,前方に操縦手座席と操縦装置,後方にエンジンと変速操向機がある。エンジンで発生した動力は変速操向機を経て,歯車機構により駆動輪に伝わり,駆動輪が履帯を回すことによって車体を動かす力に変換される。履帯は両端を駆動輪と誘導輪で,中間を上部転輪で支えられる(上部転輪がない型式もある)。車体はトーションバーや油気圧式の懸架装置を介して下部転輪により支持される。車体および砲塔は防弾鋼板製で,部分的に複合装甲等の特殊装甲が組み込まれている。
性能
戦車の性能は通常,火力,機動力,防護力の3要素によって表される。
(1)火力 火力に対する要求は,威力のある弾丸を正確迅速に射撃できることである。弾丸の威力を増大させるため,これまで火砲および弾薬の改良が進められてきた。たとえば戦車砲の口径は,第2次大戦初期まで37~75mm,大戦末期には85~88mmとなり,大戦後は90~100mmの時代を経て105~115mm,さらに120~125mmへとしだいに大きくなってきたが,同時に砲身材料の高品質化,加工法の改良,火砲設計技術の向上等があって,高初速,高威力の弾丸を発射できるようになった。弾薬についても当初は徹甲弾だけであったが,その後,成型炸薬弾や粘着榴弾が開発され,徹甲弾も比重の高い弾心材の使用,細長弾化等の改良によって,装甲板に対する貫徹威力が大幅に向上している(弾薬)。また,正確迅速な射撃を行うために必要な射撃統制装置は,第2次大戦後,特に電子技術および制御技術の発達に伴って急速に進歩した。たとえば,目標までの距離を測る測遠機は光学式のものからレーザー光線利用式に,また射撃諸元を計算するための弾道計算機は機械式から電子式に変わり,射撃を実行するための一連の動作がほとんど自動的に行われ,迅速に高精度の射撃ができるようになった。さらに,車体が傾いても砲や照準線をつねに一定方向に保つことができるスタビライザーの採用により,走りながら正確な射撃をすることも可能となっている。このほか,暗視装置の発達により夜間や悪天候時の監視・射撃能力も最近では大幅に向上している。
(2)機動力 機動力については,道路上はもちろんのこと道路以外でも,できるだけ軽快機敏に動きまわれることが要求される。機動力を左右する要素として,戦車の形状,寸法,重量のほか,エンジン,変速操向装置,懸架装置等がある。戦車用エンジンは第2次大戦まで主としてガソリンエンジンが使用されていた。大戦後は燃料の経済性やエンジン火災が発生しにくい等の利点があるため,各国ともディーゼルエンジンを使用するようになった。また,最近ではアメリカのM1戦車のように,ガスタービンを主エンジンとして採用する例もみられる。
エンジン出力は第1次大戦当時100馬力程度であったのが,第2次大戦末期には500~650馬力となり,現在では800~1500馬力に達している。戦車総重量に対するエンジン出力の比,すなわち重量t当り馬力も最近では20~30馬力となり,これに伴って走行速度および敏捷性が大幅に改善されている。
たとえば初期の戦車の走行速度は時速6~10km程度であったのに比べ,最近では時速60~70kmで走行できるようになっている。このほか,変速や方向変換のための操作が容易な変速操向装置や,日本の74式戦車に採用している油気圧式のように,走行中の振動や衝撃を吸収する能力にすぐれた懸架装置などを用いることによって,最近の戦車は重量がかなり重いにもかかわらず,凹凸の多い地形を軽快に走りまわることができる。
(3)防護力 防護力については,敵の弾丸によって撃ち抜かれないための装甲防護力がまず要求される。装甲防護力を左右する要素としては,戦車の全体形状のほか,装甲板の材質,構造,厚さ,傾斜角度等がある。装甲板の厚さは初期の戦車では10~30mm程度であったが,対戦車火器の威力が大きくなるにしたがってしだいに厚くなり,第2次大戦末期には砲塔や車体前部など主要部の装甲の厚さは100mmをこえるにいたった。装甲板として使用される防弾鋼板の性能も,材料技術や加工技術の進歩により著しく改善された。しかし対戦車火器の威力の増大が防弾鋼板の性能向上を上まわり,戦車の重量限界を考えると単一の防弾鋼板だけで所要の防護力をもたせることは実用上不可能となった。そこで,装甲板を二重,三重にし,間に空間を設けるなどして,装甲防護力を向上させる努力が続けられた。1970年代に入って,防弾鋼板と他の材料,たとえばセラミックス,チタン合金,アルミ合金,高分子材料などを組み合わせた複合装甲技術が飛躍的に進歩した。この種の複合装甲は特に成型炸薬弾(現在の対戦車ミサイルはすべて成型炸薬弾である)に対する防護力がすぐれており,徹甲弾に対しても同重量の単一防弾鋼板よりはすぐれた防護力をもっている。戦車の防護力として,1960年代以降の戦車では,核兵器,生物兵器,化学兵器に対する防護も重視され,戦車内の気圧を外気より少し高くして,汚れた空気が直接車内へ入り込まないようにする与圧装置や,汚れた空気を浄化する空気浄化装置などが組み込まれている。さらに,対戦車ミサイルのような対戦車誘導兵器に対処するため,誘導を妨害する装置や警報装置等も備えている。
将来の趨勢
戦車に対抗する手段として,対戦車ミサイルや誘導砲弾などの精密誘導兵器,対戦車ヘリコプターなどが著しく発達したため,すでに戦車だけでこれらに対応するのは不可能となっている。したがって装甲歩兵戦闘車,自走砲,その他の各種兵器と組み合わせて適切に運用する必要性はますます高まってくるが,火力,機動力,防護力を兼ね備え,攻撃にも防御にも融通性をもって使える戦車は,依然として陸戦の主要兵器としての地位を保つであろう。技術的には最近特に進歩が著しい電子技術,材料技術,ロボット技術などの成果を取り入れて,火砲や弾薬の高威力化,エンジンの小型高出力化,複合装甲の軽量小容積化,弾薬装塡や照準,操縦等各種操作の自動化と省力化,夜間を含む全天候戦闘能力の向上等が図られるであろう。また今後ますます重視される生き残り性を高めるために,戦車全体の形状も見直され,今までのイメージとは違った戦車が出現するかもしれない。
執筆者:中冨 逸郎
戦車 (せんしゃ)
ロバや馬に引かせて使用された,古代の戦闘用の車。近代兵器としての〈戦車〉については次項を参照されたい。
古代オリエント
シュメール初期王朝時代,ロバに引かせた4輪の戦車が存在していたことは,ウル王墓(前2700ころ)出土スタンダードのモザイク画から明らかにされる。ほかに2輪戦車もあった。車輪は2枚(しばしば数枚)の板を接合して造られ,まだ輻(や)を有していなかった。重くて敏活な行動に適していなかったシュメールの戦車は,アッカド時代以降,利用されなくなったように思われる。前2千年紀に入ると,6本の輻の車輪を付け,馬に引かせた軽快な2輪戦車が出現して,戦争に革命的変化をもたらした。当時の馬術用語にインド・ヨーロッパ語がみられることは事実であるが,戦車の導入についてはっきりしたことはわかっていない。いずれにせよ,新しい戦車の活躍が目だってくるのは前1600年以後のことである。戦車の利用はヒッタイト,ミタンニ,カッシートをはじめとして,シリア・パレスティナに広がり,エジプトにはヒクソスによって伝えられた。馬と戦車を維持するためには相当の資力を必要としていたので,戦車隊は貴族階級によって編成されていた。戦車搭乗者は,新王国時代のエジプトでは御者と戦士の2人であり,ヒッタイトでは盾持ちを加えた3人であった。戦士の武器は弓と矢,それに槍であった。
戦車はアッシリアの征服戦争に重要な役割を果たした。2頭立てのほかに,高位者のために3頭あるいは4頭立てがととのえられ,搭乗者は2人から3人,ときには4人(盾持ち2人を含む)の場合もみられた。サルゴン2世以来,車輪は大型化し,8本の輻をもち,ときとして人間の高さに達した。アッシリア帝国の軍隊は歩兵隊,騎兵隊,戦車隊から成り,その数的比率はおよそ100:10:1であった。それにもかかわらず,戦場において決定的な働きを示したのは戦車隊であった。なお,アッシリアが工兵隊を動員して戦車隊の行軍を助けていたことも無視できない。しかし,前1千年紀前半にイラン系諸族によってもたらされた騎馬戦術は,急速に戦車隊の意義を失わせることになった。
執筆者:佐藤 進
古代ギリシア・ローマ
ギリシアでは青銅器時代末期に戦車は軍事上の本質的要素となり,ふつう1人の御者と1人の貴族戦士を乗せた2輪の戦車が疾駆突撃する戦闘が行われていた。〈クノッソス文書〉によれば約400台の戦車と700頭の馬が宮殿の近くで維持されている。この戦車戦術は前2千年紀末の王宮経済の崩壊後ほとんど使用されなくなったため,ホメロスはかつての戦車戦術を誤って理解し,ほとんどタクシーなみに英雄を戦場まで運ぶ乗物として戦車を描いている。戦場に着いた英雄貴族たちは先陣として戦車に乗って前に進み出て,敵が近づくと地上に下り,徒歩のまま槍を投げ合った。それで勝負がつかないとさらに近寄って槍や剣で戦った。そして形勢が悪くなれば待機させていた戦車に飛び乗って逃げ,勝った場合にもそれに乗って追撃した。これはホメロスの時代(前9~前8世紀)における戦車の使用方法を反映したものである。
ホメロス以後,戦車への言及はまれであり,それも周辺地域に限られている。しばらくの間エウボイア,ボイオティア,リュディア,キプロスそしてエトルリアで,ガリアでは前3世紀まで,キレナイカとブルターニュでは紀元初めまで,そしてアケメネス朝ペルシア帝国では鎌を付けた形で戦車が使われた。ローマでは戦車は,一時,王の特権的乗物として使われたが,すぐに凱旋式と戦車競技にしか使われなくなっている。クセノフォンによればキュロス王により初めて考案されたとされる鎌を付けた戦車は,前189年にはアンティオコス3世の軍隊で,前86年にはミトリダテス6世の軍隊で,前47年にはその子ファルナケス2世の軍隊で使われた。後4世紀には《軍事について》と題する作者不明の著作に,ローマ帝国の軍事力回復をねらった提言の中で戦車が言及されている。しかしながら戦車が自由に動けるためにはまず平らな広野が必要であったばかりでなく,戦車の動きを妨げることも容易であったこと,戦車を引く馬が攻撃されやすかったことなどから,戦車を復活させようとする試みはすべて失敗に終わった。
執筆者:市川 雅俊
中国
中国の戦車は,一般的には兵車と呼ばれ,〈経書〉に散見するが,殷代からすでに存在していたことは,安陽小屯(河南省安陽市郊外)から出土した車馬遺跡(車馬坑)から明らかである。その形は,二つの車輪に1本の轅(ながえ),その両側に1対の馬をつなぐもので,この形は殷から戦国時代にかけても変化がない。当時の軍隊は5両の戦車が1隊を形成し,1両につき戦車兵が3名,歩兵5名が配置され,それが軍隊の中核であった。つづく秦代の戦車としては,近年,秦兵馬俑坑から130両にも及ぶ木製・銅製の戦車が出土し,秦代の戦車の形および戦闘方法がより詳細にわかった。それによると,秦の戦車もやはり単轅で,轅の長さ4m弱,1.4m×1.2mの長方形の輿をもち,4頭立てとなっている。またその種類は,指揮車,副車,駟集車(先導車)および一般戦車の4種からなる。とくに一般戦車は,乗員が3名,手には矛,戈などを持ち弓矢は補助的に置かれている。遠くの敵には矢を射て,接近戦になれば矛,戈を使用したのであろう。漢代になると,一般的な車の形がかわり,2本の轅の間に1頭の馬をつけるものが現れ,戦車もそれに応じて2本轅になる。ただ戦争形態としては,戦車戦は春秋末から戦国初期で終りを告げ,それ以後は騎馬戦へと戦いの形態が変化してくる。それに伴い,戦車も実戦用のものから,車馬行列の一車として社会的身分のシンボルとでもいうべき役割を担ってくるようになる。
→騎兵 →歩兵
執筆者:冨谷 至
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦車」の意味・わかりやすい解説
戦車
せんしゃ
tank
打撃力、防御力、機動力をあわせ備えた攻撃的兵器。一般的には装甲車、自走砲なども含め、広く装軌式戦闘車両をさす場合も多いが、狭義には全周旋回可能な砲塔内に直接射撃を主とした強力な火砲を装備し、全体を強固な装甲板で防護した全装軌式(キャタピラー式)車両をいう。
[竹内 昭]
分類
第二次世界大戦以前は重量により、軽戦車、中戦車、重戦車などに区分するのが慣例であったが、時代あるいは国によりその基準には大きな差があった。現在ではその用途により、偵察戦車、主力戦車(主戦闘戦車)、支援戦車というような分類法がとられている。
戦車に近似したものに自走砲がある。これは本来、火砲をトラクター上に搭載して移動の便を図っただけの、戦車とはまったく別のものであるが、装甲防御力の付与、機動力の向上に伴い、その用法は別にして、機構的にはあまり差がなくなってきている。
[竹内 昭]
沿革
戦車の歴史をさかのぼれば、紀元前2000年ごろの「チャリオット」(chariot=古代戦車)に至るが、一般的には第一次世界大戦中にイギリスで試作されたリトル・ウィリーをもって始祖としている。第一次世界大戦後期はまったくの塹壕(ざんごう)戦で、全面的に膠着(こうちゃく)状態となったため、この均衡を破ることを目的に、敵の機関銃弾によく耐え、壕を自由に突破できる奇襲兵器として考えられたのが戦車であった。リトル・ウィリーは武装なしの試作車だったが、続いて57ミリメートル砲各1門を車体両側面のスポンソン(はり出し砲門)に装備した実戦型戦車の原型であるビッグ・ウィリーが完成し、1916年1月16日に最初の走行試験が行われた。
これらの開発は、当時海軍大臣の職にあったウィンストン・チャーチルの支持のもとに設立された陸上軍艦委員会Landships Committeeのメンバーによって行われたが、機密保持上、ロシアから発注された前線部隊に水を運ぶ「水槽」(タンク、tank)として取り扱われた。これが戦車(タンク)の語源であり、現在もなお使用されている。
ビッグ・ウィリーを基礎とした量産型のⅠ号型戦車Tank Mk. 1は、1916年9月15日のソンムの戦いに初めて投入されたが、数量がわずか49両であったのに加え、故障車が続出したため、ドイツ軍にある程度のショックを与えたものの用兵的には失敗に終わった。このため、一部に戦車に対する批判の声が大きくなったが、翌1917年11月20日のカンブレー戦においては474両を狭正面に集中投入し陣地突破に大成功を収め、その地位を確保した。
イギリスのこの計画とはまったく別に、フランスにおいても戦車の開発がJ・E・エティエンヌ将軍Jean-Baptiste Eugène Estienne(1860―1936)を中心に行われ、1916年2月には400両がシュナイダー社(現、シュナイダーエレクトリック社)に発注されたが、1917年4月まで実戦に投入されなかったため、戦車の発明国はイギリスであるというのが世界の定説になっている。他方ソ連では、革命前の帝政ロシアが1914年8月に設計を開始し、1915年5月に試験を完了した1履帯(キャタピラー)式の「不整地通過車」を世界最初の戦車として位置づけていた。
第一次世界大戦にはイギリスのⅠ号型からⅧ号型重戦車、A型からD型までの中戦車、フランスのシュナイダー戦車、サン・シャモン戦車、ルノーFT軽戦車、イタリアのフィアット2000型、ドイツのA7Vなどが製作されたが、これらのうち戦後の戦車発達の母体となったのは、フランスのルノーFTであった。ほかの戦車のほとんどが限定射界の火砲しかもたぬ自走砲に近い構造であったのに対し、ルノーFTは車体中心線上に全周射界の砲塔を有し、走行装置に緩衝機構を採用するなど、近代戦車の始祖としての資質を十分に備えていたのである。
第一次世界大戦終結後、第二次世界大戦までの約20年間は、関連産業のレベルアップとともに戦車の技術的成長期にあたり各国で各種の試みが行われたが、画期的な進歩発達をみたのは第二次世界大戦においてである。第二次世界大戦初頭にドイツ軍が演じた電撃戦は、戦車を軍の衝撃力として用いるもので、それまでの歩兵の支援を主体とする戦車用兵思想に革命をもたらすものであった。また戦争の進展に伴い戦車への対抗手段には戦車が第一であるという考えも強まり、その結果、開戦時には九七式中戦車(日本)、Ⅲ号戦車(ドイツ)、M2軽戦車(アメリカ)などのように重量10~20トン、37~57ミリメートル砲装備が標準であった主力戦車が、大戦末期には、パンター(ドイツ)、M4中戦車(アメリカ)、T34中戦車(ソ連)のように30~45トン、75~90ミリメートル砲装備が標準となり、なかにはドイツのティーガーⅡ型(69トン、71口径88ミリメートル砲装備)、ソ連のИС(イエス)Ⅱ(46トン、43口径122ミリメートル砲装備)などの強力な重戦車も登場した。第二次世界大戦の終結により戦車の開発も一時的にスローダウンした。とくに核兵器の登場に伴い戦車無用論も強くおこったが、各種実験の結果はまったく逆に装甲車両の対核兵器有効性を示すことになり、各国とも戦後型新鋭車両を次々と開発するようになった。
現代の戦車をこれまでの戦車と比較した場合、攻撃力、防御力、機動力のすべてにわたり画期的な向上が図られている。攻撃力については搭載火砲、使用弾薬の発達もさることながら、命中精度を高めるための射撃統制装置が飛躍的に進歩し、最新のエレクトロニクス技術の採用により初弾必中を期している。防御力については、従来の防弾鋼板やアルミ合金に加え、セラミックス、チタン合金などを組み合わせた特殊な複合装甲が開発され、とくに対戦車ミサイル、ロケット弾などに用いられる成形炸薬(さくやく)弾頭に対し有効なものになっている。また核汚染地域などで行動する必要が生じた関係上、特殊フィルターとブロワーを組み合わせ、内圧を高めて有害外気の車内侵入を防ぐ、対CBR防護装置の設置も不可欠の条件となった。一方、機動性については軽量大出力のディーゼルエンジンまたはガスタービンが採用され、高効率の操向変速装置と相まって、瞬発性と高速力を得ている。
代表的な例としてはアメリカのM1系列、ロシアのT-80系列、ドイツのレオパルト2系列、イギリスのチャレンジャー系列、フランスのルクレール、日本の90式戦車などがあり、いずれも120~125ミリメートル級の主砲をもち、重量は50~60トン前後となっている。
主砲は高初速を得るために、これまでのライフル砲身にかわり、翼安定弾を発射する滑腔砲が主流になった。
[竹内 昭]
構造
標準的な戦車は車体部と砲塔部からなり、操縦室、戦闘室、機関室の3部分に分かれる。操縦室は車体前部にあり、操縦手1名が座る。第二次世界大戦以前の戦車ではこれに並び車体前方機関銃を操作する銃手席を設けたものが多かった。砲塔を中心とする戦闘室には、戦車長、砲手、装填(そうてん)手の3名が座乗し、戦車長は車両の指揮、砲手は主砲・砲塔銃の射撃、装填手は弾丸の装填を行う。自動装填装置の採用により装填手をなくしたものもある。
主砲は砲塔内に駐退復座機とともに砲耳(砲身を取り付けるための突起部)を介して取り付けられ、任意の俯仰(ふぎょう)角度が得られるようになっている。駐退復座機は射撃の際の砲の反動を吸収するとともに後座した砲を定位置に戻す装置であるが、戦車砲は砲塔内容積の関係から通常の火砲に比較して後座量が小さい。砲の方向変換は歯車装置により砲塔全体を旋回させて行うが、その作動は電気または油圧を主体とし、手動機構を併用するのが普通である。
後部の機関室には、エンジン、変速操向機があり、終減速機(変速操向機からの動力を減速し起動輪に伝える歯車装置)を通して動力を起動輪に伝達し履帯(キャタピラー)を駆動する。装軌車の方向変換は装輪車と違い、左右の履帯の速度を変えることによって行うが、その操向機の方式には多くの種類がある。
[竹内 昭]
『加登川幸太郎著『戦車』(1977・圭文社)』▽『原乙未生・栄森伝治・竹内昭著『日本の戦車』(1978・出版協同社)』▽『R・M・オゴルキーヴィッツ著、林磐男訳『近代の戦闘車両』(1983・現代工学社)』▽『林磐男著『タンクテクノロジー』(1992・技術教育研究会)』▽『土門周平著『戦車と将軍――陸軍兵器テクノロジーの中枢』(1996・光人社)』▽『ピーター・チェンバレン、クリス・エリス著『世界の戦車』(1997・大日本絵画)』▽『上田信著『戦車メカニズム図鑑』(1997・グランプリ出版)』▽『ヴァルター・J・シュピールベルガー著、津久部茂明訳『ティーガー戦車』(1998・大日本絵画)』▽『ヴァルター・J・シュピールベルガー著、高橋慶史訳『パンター戦車』(1999・大日本絵画)』▽『斎木伸生著『ドイツ戦車発達史』(1999・光人社)』▽『日本兵器研究会編『世界の主力戦車カタログ』(2000・アリアドネ企画)』▽『日本兵器研究会編、清谷信一企画・監修『現代戦車のテクノロジー』(2001・アリアドネ企画)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戦車」の意味・わかりやすい解説
戦車[現代]
せんしゃ[げんだい]
tank
戦車[古代]
せんしゃ[こだい]
chariot
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「戦車」の意味・わかりやすい解説
戦車【せんしゃ】
→関連項目キャタピラ|装甲|対戦車ミサイル|兵器
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「戦車」の読み・字形・画数・意味
【戦車】せんしや
 乘、奮
乘、奮 百
百 、沃野千里、
、沃野千里、 積(ちくし)饒多(ぜうた)にして、地勢形
積(ちくし)饒多(ぜうた)にして、地勢形 なり。
なり。字通「戦」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「戦車」の解説
戦車(せんしゃ)
①2~4頭の馬にひかせる主として戦闘用の車(多くは2輪車)。すでに前3千年紀のシュメールに出現しているが,実体車輪を用い,牛やオナガー(ロバの一種)にひかせているので,戦闘能力は疑問。前2千年紀に入り,スポーク付きの軽量車輪と馬が導入されて,初めて実戦向きとなり,オリエント各地に広まり,ギリシア,ローマにも伝えられた。ガリアやインドでも存在が知られており,中国では殷(いん)代後期には戦闘に用いられていた。しかしいずれの地においても,やがて機動力に勝る騎兵にとって代わられるようになり,儀礼的行列や競技にしか用いられなくなった。
②タンクのこと。第一次世界大戦中,1916年9月ソンムの戦いでイギリス軍が初めて使用した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の戦車の言及
【殷】より
…西方トルキスタンから玉(ぎよく)が輸入され,美しい玉器が大量に作られる。後期に見られる馬で牽引する戦車も非常に発達した形式のもので,軍隊の中心は戦車によって構成されたほど多数使用されたが,現在のところ中期の遺跡からは車の遺物がまったく発見されないので,完成した戦車の技術が西方から伝えられたのではないかとも言われるが,当時の西域との関係はまったく史料に欠け,不明である。 また後期になり,初めて文字が発見される。…
【ウマ(馬)】より
…馬の家畜化がシベリア南部から黒海北部草原に至るステップ地帯で進められただろうことは,ほぼまちがいない。
[戦車と馬]
古代オリエント世界では,馬は戦車を引くものとして前2千年紀前半に登場する。戦車はそれ以前からあったが,それはオナジャーによって引かれる型であった。…
【車】より
…円形の輪縁は幾本かの木片をつなぎ合わせてつくられたが,1本の細長い木を加熱して曲げてつくることもあった。初期のスポーク車輪は,一般に戦車に使用され,馬が引くためにスピードは出たが,がんじょうでなかったので,それほどの成果は上がらなかった。
【車両の歴史】
[ヨーロッパ]
古代で車が目覚ましく活躍したのは,戦車である。…
【攻撃機】より
…地上目標(艦船,戦車,飛行場など)に対する攻撃を主目的とする軍用機で,航空母艦用の艦上攻撃機と近接地上支援用の陸上機型攻撃機の2種類に大別される。アメリカ軍ではこれらを総称してアタッカーattackerと呼んでいる。…
【自走砲】より
…各種の火砲を戦車や装甲車などの車体に取りつけ,自力で走行できるようにしたものの総称。搭載している火砲の種類により,自走カノン砲,自走榴弾(りゆうだん)砲,自走迫撃砲,対戦車自走砲,対空自走砲などと呼ばれる。…
※「戦車」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...