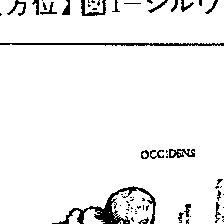精選版 日本国語大辞典 「方位」の意味・読み・例文・類語
ほう‐いハウヰ【方位】
- 〘 名詞 〙
- ① ある方向が一定の基準方向に対してどのような関係にあるかを示すことば。東西南北を基準として、一六または三二方向に区分する。十二支によれば北から東まわりに子(ね)・丑(うし)・寅(とら)と一二等分し、また易(えき)では北から東まわりに、坎(かん)・艮(ごん)・震(しん)・巽(そん)・離(り)・坤(こん)・兌(だ)・乾(けん)と八等分する。方角。
- [初出の実例]「已に伏羲八卦の方位が定て」(出典:史記抄(1477)一八)
- [その他の文献]〔張衡‐東京賦〕
- ② 各方向に陰陽、五行、干支、易の八卦などを配し、その方向に向かっての吉凶を判断する術。吉方(えほう)、金神(こんじん)、鬼門(きもん)の類。
- [初出の実例]「そも八将神の方位にそむかず建とは」(出典:人情本・春色梅児誉美(1832‐33)初)
- ③ 向いたり、進んだりする方。方向。
- [初出の実例]「此力亦其方位に従ひ以て其名を異にす」(出典:改正増補物理階梯(1876)〈片山淳吉〉一)
改訂新版 世界大百科事典 「方位」の意味・わかりやすい解説
方位 (ほうい)
ある基準に基づいて,一定の方向またはその方向から測った他の方向を示す語を方位という。
現在,日常用いられる地図のほとんどは,北が上となっており,そうでない場合には,北を表示する磁石の針を表した記号で地図の方位が示されている。これは羅針盤が発明されて航海に用いられるようになり,地図の方位も磁針の指す方向と一致して北が上に置かれるようになって以来一般化したと考えられている。それ以前には地図の方位基準は一定でなく,その時代の世界観を表し,たとえば東方の地上楽園を地図のいちばん上に置いた中世ヨーロッパの地図や,南が上になっているイスラム世界の地図などがみられる。方位記号も頰をふくらませて息を吹きつけている風神の顔や文字がそれぞれの位置に配されている例がみられる。方位観念には,地域,時代によりさまざまな基準によるものがある。
地図学における方位
地球上の1点で,その点を通る子午線の北の方向を基準として測った他の点の方向を方位azimuthという。一般に北の方向から右回り(時計回り)の角度で示し,この角度を方位角azimuth angleと呼ぶ。
また回転楕円体である地球上の原点(測量や測地座標系の基準となる点)で定めた方位を原方位と言い,これは三角測量その他の測地方位の観測や計算の基準となる。日本の原方位は,測量法により,日本経緯度原点(東京都港区麻布台2丁目18番地1号内,旧東京天文台の子午環の中心点)から千葉県鹿野(かのう)山の1等三角点を望む方位で,その方位角は156度25分28.442秒と定められている。
方位を表現する方法には,このように,基準とする方位と,示そうとする方位とのなす角度で表す方法(角度法)がある。これに対し,三十二方位法という表現法がある。これは基点を中心とする円を32等分して得られる方位(主方位)に名称を付し,示したい方位については,それにいちばん近い主方位で近似的に言い表す方法である。その名称は主方位を決定する順序と関連し,次のようである。第1は,東西南北のいわゆる〈四正方位〉で,第2にこれらの中間方位が定められる。この場合の名称は第1順位を先に置き,北東,南東,南西,北西とする。第3は,以上の八方位の中間方位(十六方位),第4はさらに十六方位の中間方位を定めたものである。十六方位においても,第1,第2順位の方位名を先に付して,北北東,東北東などと表現する。三十二方位では第1~第2順位の方位の中の最も近い方位を選び,それよりもどちらに偏しているかによって,その名称の後に微北,微東などを付し,南西微南,南微西のように言い表す。この方法は示そうとする方位を簡単に表現でき,十六方位の名称は日常用いられている。
執筆者:高崎 正義
相対的方位
方位は,われわれがよく知っている東西南北の体系が唯一のものではない。世界中を広く見渡してみると,むしろ別の原理で体系づけられた方位のほうが多い。東西南北と言い表しているような方位を絶対方位absolute orientationと呼ぶのに対し後者は相対方位relative orientationと呼ばれる。すなわち,まわりの状況によって方位のとり方が変化する体系を相対方位という。たとえば台湾,フィリピン,インドネシア,太平洋地域などで話されているアウストロネシア語では,〈海〉-〈陸〉が方位の語として用いられている。そして,島のどの位置にいるかによって,方位としての〈海〉は北であったり南であったりする。
より詳しい例をインドネシアのスラウェシ(セレベス)島の南部にあるスラヤール島についてみよう。スラヤール島は南北に細長い島で,島の中央に南北に走る山脈がある。島民のほとんどは西海岸に住む。西海岸では,方位としての〈山〉は東の方角,同じく〈海〉は西を,〈下〉は北を,〈上〉は南を指す。しかし,北の端にいくと,方位としての〈海〉は北を,〈下〉は西を指す。さらに東海岸に出ると〈海〉は東を指す。ところがおもしろいことに,〈下〉は西海岸と同じように北の方角をいう。このことから,スラヤール島の方位は二つの異なった方位のとり方が組み合わされて構成されていることがわかる。すなわち,〈海〉-〈陸〉は相対方位であるが,〈上〉-〈下〉は絶対方位である。それは島の南北の端を除いて,〈上〉はつねに南を指しているからである。〈上〉-〈下〉方位は,実はこのあたりで南北に吹く季節風の方向と一致しているのである。
ところで,〈海〉-〈陸〉の方位がとれない場合,たとえば,島影の見えないような海の中にいたとき,島民はどのように方位をとるのであろうか。風の方向から決めるのであろうか。そうではなくて,太陽の方向,夜ならば星の方向によって方位を決める。すなわち,太陽の沈む方向が〈海〉の方位とみなされ,その方向に向かって右方向が〈下〉の方位とみなされる。それは島民の大部分が住む西海岸での方位のとり方そのままである。このことは,相対方位といえども,太陽の沈む方向といった絶対方位の認識を欠いているのではないことを示している。そして,相対方位が直接的には使えないようなときに絶対方位がたちあらわれてくる。相対方位の基本的な様相はこのようなものだが,2対の方位がある場合,つねに一方が絶対方位というわけではない。モルッカ諸島のテルナテ島では〈海〉-〈陸〉,〈上〉-〈下〉の2対の方位をもつが,ともに相対方位である。川が地形的に重要な地方では,〈上流〉-〈下流〉,〈川に向かう方向〉-〈川から離れる方向〉の4方位がみられる場合が多い。また,地形的に斜面である所を生活の場としているニューギニアやヒマラヤでは,〈上方〉-〈下方〉が重要な方位として出現する。フィヨルド地帯では,〈外〉-〈内〉,〈上方〉-〈下方〉が4方位としてみられる。さらに,モンゴルやアイルランドでは〈前方〉-〈後方〉,〈左〉-〈右〉という語が4方位として用いられていた。
このようなさまざまの相対方位をみていると,そこには人間にとっての方位のとり方の基本というものが浮かびあがってくる。おそらく,人間にとって,〈上方〉-〈下方〉という方向感覚がもっとも原初的なものであろう。上下感覚は頭部に眼があることによって起こる感覚であるだけでなく,上下方向に動いた場合の全身的な体感とも関係している。ついで,〈前方〉-〈後方〉という方向感覚が重要である。人間の眼が顔の前面に集中しているために生じた感覚である。〈左〉-〈右〉という方向感覚は前2者に比べるとずっと後に起こったものである。なぜなら,ある基準が設けられないかぎり,左右は成立しないからである。
この三つの方向感覚が相対方位を形成する基礎である。これらを,身体感覚に直接関係しているところから身体的方位bodily orientationと呼ぶ。〈海〉-〈陸〉,〈川に向かう方向〉-〈川から離れる方向〉,〈内〉-〈外〉という方位は〈前方〉-〈後方〉という方向感覚から派生したものである。斜面における〈上方〉-〈下方〉,〈上流〉-〈下流〉,さらに地形的な上下と関与しない,より抽象的な〈上〉-〈下〉は上下感覚から派生したものである。そして,抽象化した〈上〉-〈下〉の方位を除くと,いずれも地形と密接に関係しており,これらの方位は地表的方位terrestrial orientationと呼ばれるものである。
この地表的方位に対して季節風のような風を基準とした方位は,特定の季節においては絶対方位として機能するが,時間の幅を広くとると,吹く方向が変化するから相対方位となる中間的な方位で,これを大気圏方位aerial orientationと呼ぶ。太陽や星を基準とした絶対方位をこれらに対応させて天文的方位celestial orientationと呼ぶこともある。世界各地でみられる方位は,これら身体的方位およびそこから発達した地表的方位,さらに大気圏的方位,天文的方位のさまざまな組合せによって形成されたものである。
→空間 →右と左
執筆者:吉田 集而
日本
日本では,中国の易学や陰陽五行説などの影響が強いが,朝鮮の風水思想のような体系は成立しなかった。五行による四方と中央,八卦(はつか)による八方,十二支による十二方,八卦と十干の一部による二十四方が方位の基準である。八卦は,六朝時代の八将神では循環する方位となり,日本の陰陽道では牛頭(ごず)天王の八王子とされ,太歳(たいさい)神,大将軍,大陰(だいおん)神,歳刑(さいけい)神,歳破(さいは)神,歳殺(さいさつ)神,黄幡(おうばん)神,豹尾(ひようび)神をいい,この方位を神殺の凶方といって恐れた。金神(こんじん)も凶方で遊行するとされ,その方位への旅行や普請などを忌む。九星術(九星)や気学に由来する本命,的殺,五黄殺,暗剣殺,歳破,月破は方殺といい,日の吉凶の判断などに使用された。方位には禁忌が伴うので,吉方に位置を変えて行事をする方違(かたたがえ)も行われている。これらの考え方は,修験者,陰陽師(おんみようじ),祈禱者によって民間に流布したものである。
外来の方位で最も恐れられたのは,陰から陽に転ずる鬼門(丑寅(うしとら))の北東,陽から陰に転ずる裏鬼門(未申(ひつじさる))の南西である。鬼門は悪霊の来る方位とされ,屋敷神を置いたり,京都に対する比叡山のように寺を置いて鎮護したりした。戌亥(いぬい)(西北)も重要で,鬼門以前は,この方位が恐れられたらしい。西北風をアナジとかタマカゼと称し,悪霊とともに善神も来る両義的な方位とし,屋敷では稲荷をまつる。以上の3方位に辰巳(たつみ)(東南)を加えて四角(しかく),四隅(しぐう),あるいは四維(しい)と呼び,それぞれ艮(うしとら),坤(ひつじさる),乾(いぬい),巽(たつみ)の字をあてる。
また,神聖な方位には,恵方(えほう)(明きの方)があり,新しい年神,歳徳神を迎える方位で,年神棚,門松,若水汲み,鍬始めはその方位を意識している。恵方はふつうは暦により決定されるが,東北地方では年末の最後の雷の鳴り収まった境の山を恵方とし,年神はそこから来るという所もある。方位は建築に際して意識され,井戸,門,玄関などの方位を家相説(家相)に基づいて決定し,図面を描く家相師が,江戸時代後期には活躍した。
方位の伝承や禁忌は,一概に迷信とは言いきれない。それは,地域の人々の日常経験から生み出された文化的背景をもつ空間定位のあり方を含んでいるからで,東-西,海-陸,上-下という方位それ自体に聖俗,優劣,浄穢,吉凶といった意味づけが伴っている場合,これを人間の文化の所産として〈方位観〉と呼んで,社会構造や霊的存在と関連づける世界観の研究が,沖縄やインドネシアのバリ島,アメリカ・インディアン,南アメリカのインディオなどを対象として進められてきている。
執筆者:鈴木 正崇
西洋の方位観の諸源泉
磁針を使い方位を知ることは,フェニキア人など一部の海洋民族を除き一般には知られていなかった。そこで方位の決定は日の出入りなど天体現象を利用するか,季節風のような一定の気象現象に基づいて行われた。古代地中海世界では生活に密着した各季節の風が,方位を知る目安に用いられ,今日でも方位を意味する英語はbearing(bearは〈生じる〉の意)といい,〈風の生まれるところ〉を原義とする。古代ギリシアでは東西南北を表す象徴に風神の姿を用い,各風神の性格をそれに対応する方位の特徴とも関連づけた。すなわち北風の神ボレアスBoreasは厳しく荒々しい性質を持ち,西風の神ゼフュロスZephyrosは春と生命をもたらす優しい青年,南風の神ノトスNotosは力強く,また東風の神エウロスEurosは豊饒を恵む神とされる。ローマ時代を通じてこの4風神はさらに12方位の風神に拡張され,プトレマイオスの世界図をはじめ古地図の方位を示す装飾図像となった。
こうして方位の表現法と意味とが定着すると,これに身体感覚との対応も付け加えようとする動きが起こる。すなわち人間の顔面や両手といった相対的方位(方向)directionに東西南北を対応させることで,方位は感覚の面からも定まった。そして地中海世界では,〈絹の国〉中国に至る東方に向かって後方(西側)を地中海,左手(北側)をドン川,右手(南側)をナイル川とする方位観が一般化した。これを世界図として図形化したのがTOマップで,Oの中にTをはめこんだ形をしているところから,そう呼ばれた。丸い輪郭をもつ世界がドン川とナイル川によって横に二分され,さらに下側の半円は地中海によって縦に二分される。したがってTOマップ上の方位は,感覚的にはアジアへ向かう東側を上方とした。この方位感覚は日の出を見る東方(オリエント)に優位を与え,やがてキリスト教を通じてパラダイスが存在する神聖な方向を上方に向ける中世の世界図へと継承されていった。
地図による方位の平面化はこうして必然的に上-下という別種の方位観をも含むようになった。世界図が早くから発達したギリシアでは,北を上とする表現法が用いられていた。またギリシア人は世界が球体であることを知っていたので,幾何学的類推を働かせた。その結果,人間が住む世界oikoumenēに対し,対向世界antoikoi,対蹠(たいせき)世界antipodes,反世界antikthonēsが球面上に存在してつりあいを取っていると考えた。前2世紀の人マロスのクラテスKratēs Mallōtēsは対蹠世界には足が逆向きについた住民がいると述べている。この方位観は今日もなお,ロンドンの対蹠にあたるオーストラリアを〈下の世界Down Under〉とする英語の言い方などになごりをとどめている。いずれにしても北を上方とする方位観は,ルネサンス以降TOマップに代わってプトレマイオスの地図などが広く流布するにつれ,人々の間に定着していった。なお,ある地点から見て各方位はどの方角にあたるかを示す記号に,風配図wind roseと呼ばれるものがある。直訳すれば〈風の薔薇(ばら)〉の意で,幾層かの同心円と中心から放射される方位線とから成る。形が薔薇の花びらに似ているためにそう呼ばれ,ギリシア時代からすでに使用されていた。各花びらにはその方位に関連する象徴的意味が付与され図が描きこまれた。
また四大との関係では,南に空気,東に火,西に水,北に地が結びつけられる。西洋オカルティズムではこの四大元素を媒介にして,中国の五行に似た色と精霊と方位の対応表も作られており,方位の吉凶占いが行われる。また実際面でも,ローマのウィトルウィウスのような建築家は方位と健康のかかわりを重視した。一日中安定した陽光が得られる北側に明り取りを設けよといった忠告がその一例である。これら家相学的な発想も加わり,方位に対する西洋的イメージの基礎は固まったが,ほかにエジプトやパレスティナでの方位と風向の関係が聖書を通じて影響を与えている。また,北ないし西ヨーロッパの地理的条件も中世以降の方位観念形成の大きな要因となっている。
執筆者:荒俣 宏
中国
古代の初等教育では,6歳にして東・西・南・北の方位名を数とともに教えられたという(《礼記》内則)。漢代の字書《説文解字》によれば,東は太陽が東方の木中からのぼる形,西は太陽が西方にあって鳥が巣上にある形,南は南方の草木がしなやかに伸びている形,北は2人の相そむく形とする。しかし今日の甲骨学の成果によれば,方位の名はそれを示す具体的な方法がないので,いずれも仮借(かしや)であったり,なにかに託したりしたものであるという。甲骨の卜辞には,すでに風雨の記録が残されており,東・西・南・北の方角が示されている。また卜辞によれば,東方を析,風を (きよう),南方を夾,風を
(きよう),南方を夾,風を (び),西方を夷,風を彝(い),北方を
(び),西方を夷,風を彝(い),北方を (えん),風を
(えん),風を (しゆ)とあらわして方神とその使者とされる風神の名称がみえるが,後の《山海経(せんがいきよう)》にみえる名称と異なっている。卜辞の世界においては,方神・風神がその年の収穫の豊凶を支配すると観念され,方神・風神信仰が示され,やがて四神につながっていく。
(しゆ)とあらわして方神とその使者とされる風神の名称がみえるが,後の《山海経(せんがいきよう)》にみえる名称と異なっている。卜辞の世界においては,方神・風神がその年の収穫の豊凶を支配すると観念され,方神・風神信仰が示され,やがて四神につながっていく。
ところで磁石を知るまでの中国古代において,方位は土圭をもって定められた。土圭とは木柱であるが,これを地面に垂直にたてる。そして太陽の光が地面に投ずる土圭の影を測定して,南北の子午線と東西の緯線を知り方位としたという(《周礼》大司徒)。そして戦国時代には指南針があらわれた。《論衡》によれば,天然磁石である司南の杓(さじ)を地盤の上に投ずれば,南を指して落ちつくという仕掛けであった。地盤は,漢代の占い師が用いた方形の盤で,地盤の四周には甲,乙,丙,丁,庚,辛,壬,癸,の八干と子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥の十二支,それに乾,坤,巽,艮の四維,あわせて24方向が示されていた。
人事の吉凶禍福が方位によって決定されるという信仰は,中国においてかなり古い時代から存在した。《墨子》貴義篇には,墨子が旅行の方位を説く占い師をやりこめた話が載せられているが,ここにも見られるように戦国期には陰陽五行家が出て,陰陽五行説に《易》の哲学を合わせ,各方角に五行,八卦あるいは十干十二支を配して一つの宇宙人生観を作ったものと考えられる(干支)。
方位においてはとくに住居が問題になるが,これについてさまざまな点から論及した書物は《黄帝宅経》が最初である。これは黄帝の名を冠してはいるが唐代の作と考えられている。そこでは図2のように,方位を24方向に分け,乾,震,坎(かん),艮(こん)および辰を陽位(刑禍(わざわい))とし,坤,巽,離,兌および戌を陰位(福徳(さいわい))とし,たとえば家を建てる場合は,刑禍の方向つまり陽を先に,福徳の方向つまり陰を後に建てれば吉,さらに陽位では亥から巳の方向に仕事を進め,陰位では巳から亥の方向に進めるのを吉とするなど,陰陽のバランスを考え細かく説かれている。
執筆者:西脇 常記
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「方位」の意味・わかりやすい解説
方位
ほうい
方角と同義であるが、とくに人事の吉凶との関係において考えられるもの。東西南北の四方位が四正(しせい)、その中間の東北、東南、西南、西北が四隅(しぐう)で、あわせて八方位となる。方位はさらに12に分けられ、古代中国ではこれに十二支を配当した。また、八方位は3分して二十四方位ともする。これら各方位にはそれぞれ特別の意義が付与されていて、人間の運命に影響を及ぼすものとするが、古代中国のこの考えは日本にも早く伝えられ、陰陽師(おんみょうじ)などによって広められて、旅行、移転、新築その他いろいろの場合に方位の吉凶をみることが行われて現代に至っている。方位の吉凶は、(1)「丑寅(うしとら)(東北)の鬼門(きもん)」のように固定しているものと、(2)年、月、日、時刻などによって変わるものとの二通りがある。
(1)の丑寅の鬼門は今日でも重視されるが、その理由については諸説がある。あるいは東北が死霊、すなわち鬼の出入りする門という説に由来するものとし、あるいは、空間としての丑寅を時間の丑寅に置き換え、旧12月の丑月(うしのつき)と旧正月の寅月(とらのつき)をともに年の境、丑刻・寅刻を昨日から今日の1日の境とし、この丑寅を変化宮とみての畏怖(いふ)による、とするが、このほかにも異説がある。
(2)は、一定の法則によって循環する凶神・吉神の在泊方位につれて、その吉凶が変わるもので、その凶災には金神(こんじん)、八将神(はっしょうじん)などによる「神殺(しんさつ)」と、方位による「方殺(ほうさつ)」とがある。金神の作用は強く、その在泊方位に向かって土木作業、出行、移転などを忌む。八将神は陰陽道における午頭天王(ごずてんのう)の八王子で、四季と四つの土用の行疫神。一定周期により循環するこの八神の在泊方位は禁方となる。これらの神殺に対し、方殺では、五黄殺(ごおうさつ)、暗劔殺(あんけんさつ)、本命殺(ほんめいさつ)、本命的殺(ほんめいてきさつ)、歳破(さいは)が五大方殺とされ、これらの方位はすべて凶である。
吉神は歳徳(としとく)、太歳(たいさい)、天徳(てんとく)、月徳(げっとく)、天徳合(てんとくごう)、月徳合(げっとくごう)などで、その在泊方位を用いる人々に対し幸慶を与えるとし、「恵方詣(えほうまい)り」で知られる恵方とは、その年の歳徳神の在泊方位をさすものである。
[吉野裕子]
百科事典マイペディア 「方位」の意味・わかりやすい解説
方位【ほうい】
→関連項目家相
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「方位」の意味・わかりやすい解説
方位
ほうい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「方位」の読み・字形・画数・意味
【方位】ほうい
字通「方」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の方位の言及
【空間】より
…ただし,動物での個体空間を抽出することはむずかしく,人間の場合は言語をもちいてはじめて明らかになったにすぎない。【吉田 集而】
[方位における空間認識]
人は自分の住んでいる自然にもとづいて空間意識をもつ。地球が丸いということがわかり,地球が自転しつつ太陽の周囲を公転するという認識がもてた現在でも,太陽は東からのぼり,西に沈むという意識を人々はまだ用いている。…
【数】より
…前者は対概念を二つ組み合わせて4要素とし,この四つの要素によって世界が成立しているとみる世界観である。典型的なものは4方位に関係づけられた世界観である。一方,八分観はきわめてまれなものであるが,原理的には四分観の4要素がさらに二分された8要素からなると考える世界観である。…
※「方位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...