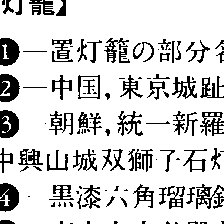精選版 日本国語大辞典 「灯籠」の意味・読み・例文・類語
とう‐ろ【灯籠】
- 〘 名詞 〙 =とうろう(灯籠)①
- [初出の実例]「夜にいりぬれば、とうろかけつつ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)国譲中)
- 「Tôrono(トウロノ)ヒカリガ ホノカニ ミエタニ」(出典:天草本平家(1592)四)
改訂新版 世界大百科事典 「灯籠」の意味・わかりやすい解説
灯籠 (とうろう)
戸外用の灯火器。風から守るため,火炎部を囲う構造(火袋)をもつ。灯楼などとも書く。主として室内で用いる燭台,灯台,雪洞(ぼんぼり),行灯(あんどん),ランプ,また携帯用の龕灯(がんどう),提灯(ちようちん)などとは区別する。原形は,中国大陸から朝鮮半島を経て,仏教とともに伝来した。材質の違いから木灯籠,陶灯籠,金灯籠,石灯籠があり,形状の違いから台灯籠(置灯籠,立灯籠),釣灯籠がある。置灯籠を構成する基本的な部材は,下から基礎,竿,中台,火袋,笠,宝珠の6部材。釣灯籠はこのうち下の基礎,竿がなく,かわりに宝珠部分に釣手を,中台に脚を付ける。1基の灯籠中で,材質を違えた部材を組み合わせる例はほとんどない。石灯籠に火袋を木でこしらえたものを見るが,ほとんどが石の火袋が破損したのを後補したものである。中国には,黒竜江省寧安県の東京(とうけい)城趾に,渤海時代の石灯籠が現存する。日本の石灯籠とは火袋,笠,宝珠の部分で意匠が異なる(瓦葺き八角仏堂を模し,宝珠ではなく相輪(そうりん)を乗せる)が,基礎,竿,中台などの基本的な構成は変わらない。また朝鮮半島には,慶州を中心として数多くの統一新羅時代の石灯籠が残っている。部材の構成は日本と同じであるが,意匠の点で先行する。
(1)木灯籠 春日大社蔵の黒漆六角瑠璃釣灯籠(鎌倉時代)が最古のもの。木灯籠は風食,炎上など破損を受けやすく,遺品の例は少ない。
(2)陶灯籠 近世になり陶器製の灯籠が現れる。釉薬で彩色できる点が他と異なる。遺品は木よりも少なく,東京国立博物館蔵(江戸時代)のものが知られる。
(3)金灯籠 鉄製と金銅製がある。鋳金,鍛金,彫金など金属工芸技術が駆使され,細部にわたって装飾を施す。台灯籠では鉄製,金銅製相半ばするが,釣灯籠では鉄製が多い。なかでも春日大社回廊の釣灯籠は,多くが鉄製で1000基以上に及ぶ。石灯籠に比して金灯籠に台灯籠の遺品が少ないのは,金属が高価であること,鋳つぶして他に再利用できること,腐食に弱いことなどが理由であろう。金銅製台灯籠の最古の遺品は東大寺大仏殿前金銅八角灯籠(奈良時代)で,火袋に鋳出された音声菩薩が有名。鉄製としては,台灯籠では大阪府河内長野市の観心寺鉄灯籠(平安時代),釣灯籠では京都国立博物館蔵の鉄鍛造釣灯籠(鎌倉時代)などが秀品として知られる。
(4)石灯籠 灯籠といえばこの石灯籠を指すことが多く,台灯籠の大半が石灯籠である。元来は仏寺の堂前に献灯したものであり,平安時代以降,神社にも取り入れられた。台灯籠が本来の灯籠の形状であるが,時代が降るにつれ庭園の点景として用いられるようになり,さまざまに形を変えつつ今日に及んでいる。古くは堂前中央に1基を建てたものが,室町時代以降,1対,2対と数を増すようになり,ついには春日大社のようにおびただしい数(2000基以上)を献ずるようになる。平面形も,本来の八角形が時代が降るにつれ六角形,四角形,三角形,円形,自然石形などの異形が現れる。ほかの材質に比べ,風食・破損しにくいこと,石という材質が茶人に好まれたことが遺品の多い理由であろう。発掘調査により,飛鳥寺跡,山田寺跡の,いずれも金堂跡南面で石灯籠基礎が発見されており,仏教伝来とともに灯火を献ずる慣習も伝来したことが知られる。興福寺五重塔前には自然石に八弁の蓮華紋を刻した基礎(奈良時代)が残っている。上部を備えたものでは,当麻寺金堂前石灯籠(奈良時代),春日大社柚木型石灯籠(平安時代),平等院鳳凰堂前石灯籠(平安時代),東大寺法華堂前石灯籠(鎌倉時代)などが知られる。石灯籠は,後世に派出したさまざまな形式を分類して当麻寺形,般若寺形,春日形,三月堂形,西円堂形など社寺名,堂名などの所在地名で分類したもの,庭園鑑賞用にデザインされたものを利久形,織部形,遠州形,珠光形などのように茶人の名で分類したもの,あるいは雪見形,琴柱(ことじ)形,草屋形など形状で分類したものがあるが,いずれも観賞的な好み上の分類であり一定しない。桂離宮,修学院離宮には,さまざまにデザインされた石灯籠が庭園の要所に配置してあり,江戸時代庭園用石灯籠の典型といわれる。
執筆者:伊東 太作
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「灯籠」の意味・わかりやすい解説
灯籠
とうろう
照明具の一つ。灯楼とも書く。大別すると台灯籠と釣(つり)灯籠に分かれ、それぞれ、木製、石製、銅製、鉄製などの種類がある。台灯籠には立(たち)灯籠と置(おき)灯籠、釣灯籠には下げ灯籠と懸(かけ)灯籠がある。灯籠は神仏に灯明を献ずるためや、交通の照明としてのほか、庭園内では鑑賞のための庭灯籠が置かれた。
現存する石灯籠として古いものでは、奈良・當麻(たいま)寺金堂前にある奈良時代の凝灰岩のものや、奈良・春日(かすが)大社の平安時代の花崗(かこう)岩のものが有名である。石灯籠の台座だけは奈良・飛鳥(あすか)寺で飛鳥時代創建時の大理石の台座が出土している。銅製のものでは奈良・東大寺大仏殿前の奈良時代の銅灯籠、奈良・興福寺南円堂前の平安時代の銅灯籠が著名である。また、古い釣灯籠には、奈良・東大寺の鎌倉時代の鉄灯籠や広島・厳島(いつくしま)神社の南北朝の銅灯籠がある。
台灯籠は宝珠、笠(かさ)、火袋(ひぶくろ)、中台(ちゅうだい)、竿(さお)、台座からなる。置灯籠では竿以下が省略されるものもある。立灯籠では宝珠下に受花(うけばな)をつくるもの、笠の隅が蕨手(わらびて)となるもの、火袋が四角形や八角形のもの、中台下に受花、台座上に反花(かえりばな)を刻むものをはじめ、竿も角形・円形があり、覆輪(ふくりん)や紐(ひも)を巡らす節(ふし)をつけるものなど、多様である。その代表的なものの所在する場所名を付して、般若寺(はんにゃじ)形、元興寺(がんごうじ)形、三月堂形、太秦(うずまさ)形、柚(ゆ)の木(き)形、西の屋形、奥の院形、蓮華寺(れんげじ)形、善導寺形などがある。庭灯籠にはそれを愛用した人名をとり、珠光(じゅこう)形、利休(りきゅう)形、遠州(えんしゅう)形、織部(おりべ)形などがあり、形態によって蛍(ほたる)灯籠、雪見(ゆきみ)灯籠などの種類がある。釣灯籠は宝珠、吊輪(つりわ)、笠、火袋、受台、脚からなり、火袋には透(すかし)彫りが施され華麗なものが多い。
交通の便を図ってつくられた灯籠としては、香川・金刀比羅宮(ことひらぐう)北神苑の高灯籠、滋賀・大津琵琶(おおつびわ)湖畔の常夜灯が巨大なものとして知られている。
[工藤圭章]
『中村昌生・西澤文隆監修『日本庭園集成 燈籠』(1985・小学館)』▽『川勝政太郎著『日本石造美術辞典』(1978・東京堂出版)』
百科事典マイペディア 「灯籠」の意味・わかりやすい解説
灯籠【とうろう】
→関連項目回り灯籠
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「灯籠」の意味・わかりやすい解説
灯籠
とうろう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
家とインテリアの用語がわかる辞典 「灯籠」の解説
とうろう【灯籠】
普及版 字通 「灯籠」の読み・字形・画数・意味
【灯籠】とうろう
字通「灯」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
動植物名よみかた辞典 普及版 「灯籠」の解説
灯籠 (トウロン)
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...