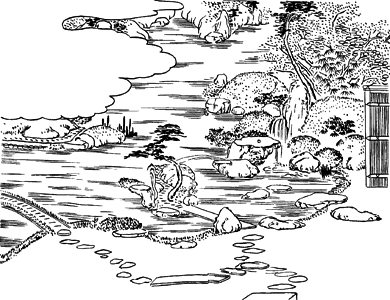精選版 日本国語大辞典 「築山」の意味・読み・例文・類語
つき‐やま【築山】
改訂新版 世界大百科事典 「築山」の意味・わかりやすい解説
築山 (つきやま)
庭園などで,人工で土砂を小高く盛り上げ,あるいは石を積んで築いた山。中国では仮山という。古墳も築山の一種といえるが,庭園では612年(推古20)に渡来人路子工(みちこのたくみ)が皇居の南庭に設けたという須弥山(しゆみせん)が,記録(《日本書紀》)にあらわれる最古の例である(ただし,これを須弥山石像とする説がある)。平安時代以降,毛越寺(もうつじ)庭園はじめ実例は多いが,特に江戸時代の大名庭園では庭景の一要素として重視され,高い築山上からの眺望を目的としたり(東京駒込六義園,高松栗林園),富士山(熊本水前寺成趣園)や中国の廬山(東京小石川後楽園)など内外の名勝を写したりして,趣向をこらしたものがつくられた。
執筆者:村岡 正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「築山」の意味・わかりやすい解説
築山
つきやま
日本庭園における人工的な山の呼称。庭園の意匠のなかでは、池や流れの水に対して主要なものであるが、鎌倉時代までは「築山」の呼称はなく、室町時代の『作庭記』にも「又山をつき野すぢを置事(おくこと)は地形により池の姿にしたがふべき也(なり)」とあるように、「山をつく」→「山を築く」からこのことばが生まれたと考えられる。
築山には、地形に変化を与えその起伏によって庭に深みをもたせようとする場合と、築山の高所からの眺望を目的とする場合が考えられ、一般に多くの石組(いわぐみ)を施すのが普通である。築山の意匠で特異なものに江戸初期の寛永(かんえい)(1624~44)ごろのものがあり、ここでは石組も植栽もせず、芝や刈り込みだけで山容の美を主張している。
[重森完途]
百科事典マイペディア 「築山」の意味・わかりやすい解説
築山【つきやま】
→関連項目石組み
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「築山」の解説
築山
つきやま
庭園内に人工的に構築した山。築山の語は江戸時代の作庭書「築山庭造伝」(北村援琴著,1735成立)にみえるのが早い例。「作庭記」には「山をつき野すじををくことは」とあり,築山のうち緩勾配の低いものを野筋(のすじ)といった。平安時代以降実例は多いが,とくに江戸時代の大名庭(だいみょうにわ)では庭景の要素として重要視され,眺望の場所としたり,名山を写す(熊本水前寺成趣園は富士山を,江戸小石川後楽園は廬山を写す)など趣向をこらしたものが造られた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「築山」の意味・わかりやすい解説
築山
つきやま
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
家とインテリアの用語がわかる辞典 「築山」の解説
つきやま【築山】
普及版 字通 「築山」の読み・字形・画数・意味
【築山】ちくざん
字通「築」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の築山の言及
【庭園】より
…大きな露地は途中に垣根を一つ二つつくって変化をつくり,また見る要素を強くするようになった。平庭に近かった露地に築山をもうけ,流れや池までもつくり,また石灯籠が重要な見どころとなったのもこのころである。ここに寝殿造風な庭園の伝統や書院庭の石組みの流れと触れあう面があった。…
※「築山」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...