精選版 日本国語大辞典 「調和」の意味・読み・例文・類語
ちょう‐わテウ‥【調和】
ちょう‐かテウクヮ【調和】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「調和」の意味・わかりやすい解説
調和
ちょうわ
本来独立した諸要素が統一的全体をなすこと。漢語としては古くから具体的に、音楽・料理の味についていわれる一方、陰陽、上下の調和といったぐあいに、抽象的な意味で(形而上(けいじじょう)学的宇宙論、あるいはそれと密接に連関する倫理学の文脈などで)使われることもあった。現在わが国の慣用では、ギリシア語「ハルモニア」を語源とする西洋諸語(harmonyなど)の訳語として使われることも多い。なお、音楽理論で和音の進行に関する規則を扱う部門には、同じ西洋語に対して「和声論」「和声法」などの訳があてられるのが普通である。ここでは、この語を主として「ハルモニア」の訳語と考え、各時代、各著述家におけるその意味の変遷を、西洋語の圏内でたどる。
[津上英輔]
古代
「結合」を表すar-を語根とするharmoníaの語は、ホメロスの両叙事詩(『イリアス』『オデュッセイア』)で、舟や筏(いかだ)を構築する結び合わせの手段および精神的領域での一致を意味している。このうち前者の具体的な意味は多様な対象に適用され、ギリシア語としては後世まで存続するが、この語がラテン語を通じて西欧世界に受け継がれ、今日いう「調和」の意味を担うに至ったのは、この語の有する哲学的な性格のゆえである。ヘラクレイトスは対立しあうもの、自己自身に相反するものから調和が生じると考え、それを弓やリラ(竪琴(たてごと))の弦に譬(たと)えた。弦は両側から引かれながら、なお全体として一つの張力を保っているからである。ピタゴラスは、音の高さと弦の張力ないしその長さとの間に数の比例関係を発見したと伝えられ、音の秩序が数比に支配されていることを初めて洞察した人物とされる。
他方ハルモニアは多様な音の統一体として、音階構造ないし広義の旋法をも意味していた。そこで彼またはその学派において、ハルモニア概念は音の場面で数と結び付き、数の秩序に従う他の諸現象にも適用されて、存在論的な意味合いを帯びるに至ったと考えられる。ディオゲネス・ラエルティオスによれば、「万物は調和によって成り立っている」というのがピタゴラス学派の教説であった。そうした思弁のなかでももっとも顕著で遠く近代にまで受け継がれたのが「天体の調和」の観念である。アリストテレスの伝えるところ(『天体論』第二巻)、ピタゴラス学派は諸天体がその運行に伴って音を発し、その音が互いに響き合って調和をなすと考えていた。プラトンはこの観念を神話として紹介する一方(『国家』第10巻)、『ティマイオス』では宇宙創造神話に音階構成理論を取り入れることによって、ハルモニア概念に宇宙論的意義を担わせた。
音楽理論の立場から天体の調和を扱ったのは、ゲラサのニコマコス(後1~2世紀)、クラウディオス・プトレマイオスKlaudios Ptolemaios(後2世紀)、アリステイデス・クィンティリアヌスAristeides (Aristides) Quintilianus(後2、4世紀のいずれか)である。アリストテレスが紹介するように(『霊魂論』第1巻)、「霊魂は一種の調和である」という命題もおそらくピタゴラス学派に由来するものであり、宇宙論との関連からも注目に値する。またプラトンの『ゴルギアス』において語られているように芸術や技術の分野でも調和の概念は秩序や適合の概念とともにきわめて重要であり、たとえばウィトルウィウスVitruvius(前1世紀ころ)は『建築十書』第一巻で、ほぼ「調和」に相当するsymmetriaを建築の六契機の一に数えている。
[津上英輔]
中世
ボエティウスは古代の音楽観を宇宙・人間・楽器の音楽と整理して西欧中世に伝え(De institutione musica, I)、イシドルスは世界が音の一種の調和によって成り立っていると考えた(Etymologiae, Ⅲ)。天体の調和の観念は、中世になって宇宙論的意味を失い、天使の音楽として神学的に解釈し直されるようになり、トマス・アクィナスにおいては、音楽用語から転じて正しい比率一般を意味するようになった調和概念は、完全性・輝きとともに美の一契機とされた(『神学大全』第一巻)。
[津上英輔]
近世以降
中世後期から音楽理論における思弁的傾向が薄れるに伴って、調和の概念も特殊音楽的意味と哲学的ないし美学的意味とに分解する。音楽用語としてのハルモニアは、ルネサンス以降の音楽実践の変質と相携えて、音どうしの縦の関係(和音)を表すようになり、そのまま現代の和声概念へと引き継がれてくる。一方、ピタゴラス的な天体の調和の観念も姿を消したわけではない。たとえば、天文学者J・ケプラーは惑星の軌道を音楽的調和の反映とみ、その確信に基づいて有名な彼の第三法則を導き出したし(Harmonice mundi, V,1619)、現代のカイザーH. KayserやハーゼR. Haaseはこの方向の代表者である。
しかし思想史的にいっそう重要なのは、ライプニッツのモナド論における予定調和の概念である。彼の考えでは、世界を構成するおのおの独立の実体が互いに関係づけられ、そこに生ずる諸現象が照応しあうのは、神があらかじめ定めた調和によってにほかならない。「この世界の内なる調和を信ずることなくしては、いかなる科学もありえない」とアインシュタインもいうとおり、近代科学も自然現象の普遍的法則性をあらかじめ措定する限り、その根本的立脚点において調和概念に深くかかわっているといわなければならない。また美学の分野では、調和が秩序や均衡や適合とともに美の概念の一契機をなしてきたし、現在もなお重要な役割を果たしている。
[津上英輔]
『W. TatarkiewiczHistory of Aesthetics, I (1970, Mouton-PWN, Warszawa)』
改訂新版 世界大百科事典 「調和」の意味・わかりやすい解説
調和 (ちょうわ)
harmony
事物や事象の全体的な均衡の美を表す観念で,古代ギリシアに淵源する。ギリシア語ハルモニアharmoniaは元来,大工仕事で建材の各部をたがいに嚙み合わせて,ぴったり接合することを意味した。その後比喩的に転用されて,一致,協力,和合などの意味を持つようになった。この言葉に哲学的な意義が付与されるようになったのは,音楽の生み出す魔術的な効能にひきつけられ,音楽的調和の観点から宇宙論を展開したピタゴラス学派によるところが大きい。彼らによれば,恒星天や諸惑星はそれぞれ固有の周期で世界の中心のまわりを回転するが,その際これらの星はおのおの回転速度に対応する音を奏で,これらの音は全体として霊妙な楽音をかもし出すとされた。彼らはこれを世界の調和と名づけた。調和の観念のこのような宇宙論的含意はプラトンによってさらに継承・発展させられ,ヒッポクラテス学派やストア学派の思想にもその反響をはっきりと読みとることができる。だがアリストテレスはこの観念を厳しく論難した。そのため,アリストテレスの哲学が支配したヨーロッパ中世ではほとんど顧慮されることがなかった。しかしルネサンスの時代になって,プラトンやピタゴラス学派の思想が原典を通して詳しく理解されるようになるにつれて,調和の観念は再び脚光を浴びるようになった。とりわけケプラーは,その主著のひとつが《世界の調和Harmonice mundi》(1619)と題されていることからもうかがえるように,世界の調和の観念を基軸に据えて,コペルニクスの太陽中心説を独特の仕方で展開した。
→和声
執筆者:横山 雅彦
調和 (ちょうわ)
生没年:1638-1715(寛永15-正徳5)
江戸前期の俳人。姓は岸本,名は友正。通称は猪右衛門。陸奥岩代の人という。30歳前後から江戸住。初め安静門,のち未得に従う。1668年(寛文8)以前すでに宗匠として立っており,76年(延宝4)ころ《石亀集》を編んだが未刊,79年に《富士石》を上梓,以後貞享初めまでに《金剛砂》《題林一句》《ひとつ星》などを刊行,大名,旗本らの多数を擁して,その勢力を誇示した。その後は活動の分野を〈前句付〉へひろげ,《洗朱(あらいしゆ)》《風月の童(わらわ)》《相槌》《十の指》など高点句集を刊行,不角らとともに有力な点者となった。1707年(宝永4)一派の子英を中心に,其角,沾徳(せんとく)らの洒落風俳諧の流行に対して正風体を主張した《つげのまくら》を刊行したが,俳壇の主流とはなりえなかった。他に俳諧撰集として《夕紅(ゆうくれない)》《面々硯(めんめんすずり)》などがある。晩年の動静は《梅の露》《把菅(たばねすが)》《是迄草(これまでぐさ)》などに知られる。正徳5年10月15日没。句集に《俳林不改楽》,追善集に《続俳林不改楽》などがある。〈題喜 春雨や三日といふ夜星一つ〉(《俳林不改楽》)。
執筆者:石川 八朗
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「調和」の読み・字形・画数・意味
【調和】ちよう(てう)わ
 和し、鼎俎(ていそ)(鍋とまな板)を
和し、鼎俎(ていそ)(鍋とまな板)を ひて行く。五たび
ひて行く。五たび (王)に就き、五たび湯(王)に就く。
(王)に就き、五たび湯(王)に就く。字通「調」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「調和」の解説
調和 ちょうわ
世界大百科事典(旧版)内の調和の言及
【調和関数】より
…n(≧2)次元ユークリッド空間の領域Dにおいて定義された関数u(P)=u(x1,……,xn)が,連続な2階偏導関数をもち,ラプラスの偏微分方程式,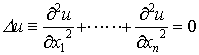 を満たすならば,uはDにおいて調和であるという。 uがDで調和のとき,任意のP∈Dと,Pを中心とする任意の閉球B⊂D,その表面Sについて,
を満たすならば,uはDにおいて調和であるという。 uがDで調和のとき,任意のP∈Dと,Pを中心とする任意の閉球B⊂D,その表面Sについて,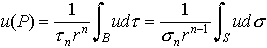 が成り立つ。…
が成り立つ。…
【和声】より
…和声(ハーモニー)の語源は,古代ギリシアのハルモニア(調和)に由来するが,今日,和声といった場合,音楽において和音が水平的・時間的に連結されたとき,その音響現象を意味する。したがって広義には複数の楽音が垂直的に同時に響く音楽すべてに和声現象が生じるが,狭義には,和音の連結法が作曲技法の基礎となった18~19世紀ヨーロッパの機能和声法を指す。広義には,ヨーロッパ音楽では中世のオルガヌム以降,ルネサンスのポリフォニー音楽などに,まだ十分に規則化されない和声現象が豊かにみられ,また民族音楽においても,ガムラン,雅楽などをはじめとして多くみられる。…
※「調和」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

