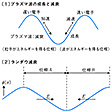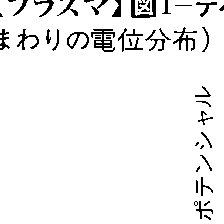プラズマ(読み)ぷらずま(その他表記)plasma
精選版 日本国語大辞典 「プラズマ」の意味・読み・例文・類語
プラズマ
- 〘 名詞 〙 ( [英語・フランス語] plasma )
- ① 高度に電離した物質の電子と陽イオンとが混在している状態。超高温の太陽コロナ・電離層・星間物質や放電中の発光部で見られるほか、人工的にも作られ原子核融合の実験などに利用。〔世界を変える現代物理(1963)〕
- ② ⇒プラスマ
日本大百科全書(ニッポニカ) 「プラズマ」の意味・わかりやすい解説
プラズマ
ぷらずま
plasma 英語
plasma フランス語
Plasma ドイツ語
プラズマということばはギリシア語で「型に流し込んでつくられる状態」の意味で、生理学では「血漿(けっしょう)」、細胞学では「原形質」を意味するが、物理学においては「相互作用をする荷電粒子の集団」と理解される。1929年にアメリカのラングミュアが、放電管内に生ずる陽光柱の状態を表すのにこのことばを用いたのが、物理学におけるプラズマの概念の始まりである。現在では、超高温の電離気体ionized gasの状態を表すのに用いられることが多いが、これは、物質が固体、液体、気体と、温度を高くするにしたがって状態を変え、超高温の状態ではさらに特徴的な性質を示すことに対応している。この意味で「物質の第四の状態」と把握されている。
[宮原 昭]
プラズマの定義
プラズマは微視的にみると、正負の電荷をもつ粒子と中性粒子との混合物であり、全体的にはほぼ中性であることが必要であるが、それだけでは十分でない。考えている系が、集合体としての集団作用を示すことが必要で、そうでなければわざわざプラズマの概念を取り上げる必要はない。集団作用が現れるためには、荷電粒子間の平均距離にも比すべき「デバイの長さ」Debye lengthという量に比べて、プラズマの寸法が十分大きければよい。デバイの長さλDは
程度である。ここでT(温度)は後述の電子温度(eV)、ne(電子密度)はm-3単位である。
現在、プラズマとよぶときは、電離気体を考えることが多いので、正負の荷電粒子が両方とも動きうることを予想しているが、元来の定義によれば、金属中の格子イオンと電子の系や電解質溶液中の正負イオンの存在もプラズマと考えられる。実際、プラズマの定義に必要なデバイの長さの概念は、強電解質の理論から派生してきた。しかしプラズマの応用の大部分が核融合とプラズマプロセスであるため、ここではプラズマとして、気体プラズマをおもに取り扱う。この場合プラズマの系を考えるときに必要な量は、系を形成するイオン種、電子、中性粒子の密度および各粒子の温度であり、さらに系全体としての体積、粒子やエネルギーの拡散の時定数などである。
密度は単位体積当りの粒子の個数で表すが、温度は絶対温度で表すよりも、エネルギー単位である電子ボルトeVを用いることが多い。これは、プラズマ諸量の関係を表すときに、温度そのものよりもボルツマン定数kB=1.38×10-23J/Kを乗じたkBTの形で表すことが多いので、エネルギーの次元のもつ量kBTをそのまま温度とみなして、単位エネルギーもエネルギーの単位でよぶのが便利なためである。1eVは1.602×10-19Jであるから、1eV=kBTから、1eVに相当する絶対温度Tは1.16×104Kである。目安としては1eVは約1万℃と考えてよい。
[宮原 昭]
プラズマの研究史
プラズマの研究は、ラングミュアらの放電管内の陽光柱の研究に端を発しているが、その後の研究によって、この概念の適用できる物質の存在は、宇宙全体の規模で考えると99.9%以上であると見積もられている。プラズマを特徴づける量であるデバイの長さは、放電管では10マイクロメートル、惑星空間では10メートル程度と、考えられている系の寸法に比べて十分短い。スウェーデンのアルベーンの1970年ノーベル物理学賞受賞は、宇宙空間のプラズマ物理研究の功績による。
地上のプラズマの研究は、電気工学の発展に伴う放電現象やその応用に関連して広範囲に行われてきた。しかしなんといっても画期的にプラズマの研究を促進したのは、核融合研究との関連においてである。核融合研究は、不幸なことに水素爆弾によって実用化された核融合反応エネルギーの利用を、制御された形で行う目的で開始された。この研究が国際協力のもとに公開で行われたのは、1955年の第1回原子力平和利用国際会議以降のことである。当面の目標を、重水素・三重水素の混合プラズマで、1億℃以上の超高温プラズマを、密度と閉じ込め時間の積が1020sec/m3といういわゆるローソン条件を満たす形で実現することに置いたが、この目標はJET(Joint European Torus、欧州トーラス共同研究施設)によって達成された。次段階の目標として核融合実験炉ITER(イーター)(International Thermonuclear Experimental Reactor、国際熱核融合実験炉)計画が発足したが、この計画の目的は核燃焼プラズマの研究を行い、500メガワットの核融合出力を長時間持続し、発電炉の鍵(かぎ)となる技術を実証することである。2001年に完了した工学設計活動(EDA)の成果をさらに発展させ、核融合実験炉ITERの建設開始に向けた技術的な準備が着実に進められている。これと平行して、EU(ヨーロッパ連合)、日本、ロシア、中国、アメリカ、韓国の政府代表による公式協議が進められてきた。2003年末までに、協定書案、ITER国際研究機構の構成・運営・物品調達方式・分担、リスク管理、知的財産権などの検討はほぼ完了した。政府高官による建設地および費用分担の交渉が2003年12月より本格的に開始された。ITERの建設地に関しては、EUはカダラッシュ(フランス南部)、日本は六ヶ所村(青森県)への誘致を強く主張し、お互いに譲らず、膠着(こうちゃく)状況がしばらく続いていたが、2005年6月、カダラッシュに建設されることが決定した。
プラズマ研究のもう一つの動機として、電離層と通信との関係がある。地上約50キロメートルを超えるとだんだんと荷電粒子の密度が増してプラズマ状態となり、350キロメートルくらいで最大になる。そこでの短波長電波の反射や混変調効果(ルクセンブルク現象)の研究は、無線通信の発達とともに盛んに行われた。そのほかにも、宇宙電磁現象の理解や宇宙船との関連で行われているプラズマ推進の研究もある。
1980年ころから、核融合研究とは対照的に低温プラズマの研究が、情報機器の大量生産の要求と相まって盛んになった。現在プラズマ工学といわれている分野にはIC(集積回路)製造に関するプラズマ加工、PVD(Physical Vapour Deposition、物理蒸着法)、CVD(Chemical Vapour Deposition、化学蒸着法)などのプラズマコーティング、プラズマを用いる光技術、TVなどのプラズマディスプレー、人工ダイヤモンド生成から環境浄化まで広範囲な応用分野が展開されている。
[宮原 昭]
プラズマ物理学
プラズマは、荷電粒子間のクーロン相互作用のために通常の気体にはみられない特異な性質を現す。これらを研究する物理学の分野をプラズマ物理学という。
[宮原 昭]
プラズマの生成・閉じ込め・加熱
プラズマを生成するには、気体を電離させる必要があるので、気体分子や原子の軌道電子に電離エネルギー以上のエネルギーを与える。水素プラズマの場合、水素原子の電離エネルギーは13.6eVであるので、それ以上のエネルギーを与える必要がある。気体を高温にしていく場合には、粒子はボルツマン分布をしておりエネルギーの高い粒子も含まれるので、温度は13.6eVに相当する15万℃にしなくても電離することができる。通常、プラズマを生成するには、あらかじめ紫外線照射などによって弱く電離した気体に電流を流して、ジュール熱によって加熱したり(オーム加熱)、プラズマに磁場(磁界)が印加されている場合には、磁力線の周りを荷電粒子であるプラズマ粒子はサイクロトロンのように周回するが、その周波数(ジャイロ周波数、サイクロトロン周波数とよばれる)に共鳴する高周波を外部から加えて加熱する方法(サイクロトロン共鳴加熱)は効率のよい加熱法である。ガラス容器に封入されている気体から生成されるプラズマの応用であるネオン管や蛍光灯では、中性粒子が多く混在しているので、プラズマをそのまま放置しておくと、熱伝導や再結合によってエネルギーを失って通常の気体となってしまうので、外部から絶えず電力を供給してプラズマ状態を維持している。核融合炉心プラズマは、1億℃以上の超高温の重水素・三重水素プラズマの生成が必要となる。このような高温に加熱するためには、エネルギーや粒子の逸出の時定数を、十分長くして有効な加熱が行えるようにする必要がある。
核融合研究の重要な課題に高温プラズマの閉じ込めがある。プラズマが容器に触れるとその表面が蒸発し、放射損失によってプラズマが冷えてしまうので、普通の容器による閉じ込めは不可能である。高温プラズマの閉じ込めは、プラズマが荷電粒子の集合体であることを利用して磁場を用いる方法(磁場閉じ込め)と、粒子が質量をもっていることを利用する慣性閉じ込めの方法がある。前者はプラズマの寸法を大きくすることにより、1億℃のプラズマでも数秒程度の閉じ込め時間を得ることができるが、後者は粒子の速度に密接に関係して、通常はナノ秒(10-9秒)以下である。核融合炉の方式に、密度1020/m3、閉じ込め時間数秒を考える磁場閉じ込め方式と、密度1029~1030/m3、閉じ込め時間ナノ秒以下の慣性閉じ込め方式のものがあるのは、高温プラズマの閉じ込めの方法に対応している。
プラズマを1億℃以上まで加熱しようとすると、プラズマの電気抵抗は高温では小さくなるのでオーム加熱は有効でなくなる。この場合には、高エネルギー中性粒子を注入してプラズマ粒子とのエネルギー緩和によって加熱する方法(中性粒子入射加熱)や、イオンのサイクロトロン周波数に共鳴する高周波を印加して加熱する方法(イオンサイクロトロン共鳴加熱)が有効である。高温プラズマの損失機構としては、閉じ込めの不完全さによる粒子損失、熱伝導損失とともに、放射損失や荷電交換損失が問題となり、全体としてのエネルギーや粒子のバランスが核融合研究の課題である。
[宮原 昭]
プラズマのモデル
プラズマの性質やふるまいを理解し記述するためには、いろいろの側面からみる必要がある。このモデルには大きく分けて、(1)波動を伝える空間を形成する連続媒質とする見方と、(2)荷電粒子の集合体との見方、の二つがある。この二つの見方は相補的であって、この両面からみて初めてプラズマを本当に理解できるといえる。
[宮原 昭]
単粒子モデル
外部磁場が一様・定常で、外力がローレンツ力のみのときは、荷電粒子の旋回中心は1本の磁力線に沿って運動するが、磁場が不均一であったり外力が加わったりすると、旋回中心は磁力線に沿って垂直な方向にも動き始める。磁場に垂直な方向への運動をドリフト運動という。両端が強い直線状のいわゆるミラー磁場による閉じ込めや、ドーナツの輪切り面が、みなソレノイドコイル(導線を多数回円筒状に巻いたコイル)になっているような単純トーラス磁場におけるプラズマ粒子のドリフト運動は、この考え方で第一段階の記述を行うことができる。このようなプラズマのモデルを単粒子モデルとよぶ。
[宮原 昭]
MHDモデル
プラズマは多数の荷電粒子の集合体であるから、当然ボルツマン方程式で記述できる。さらに高温プラズマでは、第一近似としてボルツマン方程式の右辺の粒子間の衝突を無視することができるので、粒子間の相互作用として集団的運動に起因する電磁場によるもののみを取り入れた方程式(これをウラソフ方程式とよぶ)によって記述することができる。プラズマはイオンと電子との混合物と考えられるが、イオンと電子では質量が3桁(けた)以上も異なるので、質量の寄与すなわちプラズマの運動は、だいたいにおいてイオンの運動のことであり、電子は非常に動きやすくかつ速度の平均値もイオンの速度の平均値よりもはるかに大きいので、電流はほとんど電子の寄与による。このようにプラズマが全体としての運動と、電流のふるまいを支配する二つの方程式を独立に考えた系をMHDモデルとよんでいて、プラズマの巨視的な運動を議論するのに適している(MHDは磁気流体力学の略)。
[宮原 昭]
プラズマ振動
プラズマ中の波動でもっとも特徴的なのは、巨視的に電気的に中性のプラズマがわずかに平衡位置からずれたとき、そのずれを取り戻す力が作用した結果生じるプラズマ振動plasma oscillationである。その振動数はプラズマ密度によるが、通常、主として電子が動き、イオンは止まっていると考えられるので、プラズマ周波数ωpeは、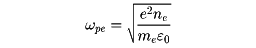
で与えられ、電子プラズマ周波数とよばれている(ここでeは電子の電荷、meは電子の質量、neは電子の密度、ε0は真空中の誘電率)。この値は電子密度(通常はプラズマ密度に等しい)1020/m3のとき90ギガヘルツ程度である。
プラズマ振動のように荷電粒子に基づく振動はプラズマを特徴づけるもので、同じ縦波でも音波のようにプラズマ中でも普通の物質中でも現れるものと本質的に異なっている。この波動の減衰機構としては有名なランダウ減衰があるが、これは波の位相速度に近い電子の運動とのエネルギーのやりとりで説明できる。
プラズマ振動はプラズマ中に励起される代表的な振動であるが、プラズマ(という媒質)中に励起される振動はそのほかにも多くある。この場合、一様・定常なプラズマ中では媒質はテンソル量の誘電率によって特徴づけられる。この量をマクスウェルの方程式で外部電荷、電流をゼロと置いて固有な振動を解析すると、プラズマ中に励起される波動を求めることができる。その代表的なものは、縦波としてはイオン音波、横波としては電磁波、イオンサイクロトロン波、アルベーン波、ホイスラー波などである。ホイスラー波は、地球磁場の磁力線に沿って、南半球で発生した雷の信号を北半球まで伝える波として有名である。
[宮原 昭]
ドリフト波
空間的に密度の非一様性をもつ場合には、プラズマ中の波動はいろいろな影響を受ける。もっとも著しいのは、一様なプラズマ中では存在しない種類の波が現れることで、この波は発生の機構が磁場中の荷電粒子のドリフトと密接に結び付いているので、ドリフト波とよばれている。
プラズマは荷電粒子の集まりとみなされ、プラズマ中の荷電粒子の運動では粒子間の直接の衝突の影響は比較的小さい。荷電粒子は第一近似では外界から加えられた電磁場中を自由に運動し、第二近似の段階で、他の荷電粒子が集団的に運動するために生ずる電磁場の作用を受ける。個々の粒子との直接の衝突が問題となり統計的な処理が必要となるのは、さらに詳しい議論の段階である。実際、プラズマらしい性質のおもなものは、第二段階までの近似で得られる。
[宮原 昭]
プラズマの電気伝導度と温度依存性
プラズマ中の電気伝導や熱伝導などの輸送現象は、電子がおもな担い手となっている。たとえば、プラズマの電気伝導度の温度依存性はTの3/2乗に比例していて、温度の高いほど抵抗は小さくなる。磁場閉じ込めプラズマの磁場に平行な比抵抗は100eV(約100万℃)ではステンレスと同程度であるが、1キロeV(約1000万℃)では銅の程度、10キロeV(約1億℃)の核融合炉の炉心プラズマでは銅の30分の1という比抵抗値となる。1000万℃以上のプラズマを加熱するときにオーム加熱が有効でなく、高周波加熱や中性粒子入射加熱が必要となるのはこのためである。
[宮原 昭]
プラズマと放射
プラズマ中ではイオンの周りには激しく電子が運動しているから、電子の受ける加速度に伴う放射が存在する。これは通常、X線のなかでは比較的波長の長い軟X線領域に波長のピーク値をもつ制動放射と、磁場が存在する場合に電子のジャイロ運動に基づくシンクロトロン放射がある。プラズマ内部で発生するこれらの放射がどの程度プラズマ外に放射されてくるかは、放射とプラズマの平衡などに関係するが、通常、これは光学的厚さによって表される。
実験室プラズマや炉心プラズマでは、制動放射に対してプラズマは透明であるが、シンクロトロン放射に対しては不透明であり、黒体放射と同じように考えられている。
そのほか、プラズマ中の多価イオンの電子レベル間の遷移による線放射がプラズマの内部エネルギーの損失機構としてとくに高温プラズマの生成の際に重要となるが、これらは、その波長域によってプラズマに吸収されたり外界に逸出したりする。この線放射を観測することによって、プラズマパラメーターについての多くの知見を得ることができる。
[宮原 昭]
地球周辺のプラズマ現象
太陽も自身の質量に起因する重力によって閉じ込められたプラズマであるが、太陽系内でもほぼ全域にわたってプラズマが充満していると考えられる。とくに太陽の周辺ではプラズマ密度nが1011~1015/m3、プラズマ温度Tが100eV程度のプラズマがあり、日食の際はコロナとして観測される。地球近傍では地球半径の10倍くらいの距離にわたって地球磁気圏が形成されているので、プラズマがとらえられている。地上70~500キロメートルにわたっては電波伝播(でんぱ)でよく知られた電離圏(電離層)がある。密度がいちばん大きいF‐2層(高さ200~500キロメートル)では、プラズマの密度、温度はそれぞれ1012/m3、0.1eV程度であるが、この領域には中性粒子も多く混在していることがロケットによる観測などで知られている。バン・アレン帯はさらにそれより上層の1万2000キロメートル程度のところにあるプラズマ層で、地球磁場によってとらえられた高速のイオンや電子が盛んに放射を行っている領域である。
オーロラもプラズマであるが、高緯度地方の高さ数百キロメートルの天空にみられる発光現象で、おもに10キロeV程度のエネルギーをもつ電子が、地球磁場の磁力線に沿って極光帯の電離層まで侵入してきて、大気中の原子・分子を発光させるものである。
[宮原 昭]
プラズマの応用
プラズマのもっとも重要な応用は核融合炉心プラズマである。これは「核融合」の項で詳述している。
ネオンサインは、プラズマ密度5×1018/m3、電子温度2.5eV、イオン温度0.15eVのネオンのプラズマである。蛍光灯は少量の水銀と100パスカルのアルゴンまたはキセノン、クリプトンなどを封入して放電をおこさせ、その結果生じる水銀の253.7ナノメートル(nm)の共鳴線が、管壁に塗った蛍光物質を励起して白色に近い発光を得るものであり、全入力の20%以上が光として放出されるので広く利用されている。
プラズマディスプレーは1990年代になって急速な進歩を遂げ実用化された。薄型、軽量、完全平面、大画面などの特徴をもち、液晶ディスプレーとともにブラウン管の表示にとってかわりつつある。原理的には放電安定化抵抗を通して、パルス電圧を電極間に印加し放電を行わせることによる。情報の表示は、放電に伴って発生する光を用いるが、表示の色は、赤色のときはネオンの585.6ナノメートルを用いるが、カラー表示のときはキセノン放電に伴う紫外線を用いて、真空紫外用蛍光体を励起発光させている。
プラズマを熱源として金属などの溶接・溶断に用いることは、アーク溶接などから始まったが、近年ではさらに高温のプラズマを利用したプラズマジェットが考案され、材料の高速・精密溶断などに用いられている。
プラズマ中における活性・化学種のプラズマ励起反応を応用するいわゆるプラズマプロセシングは、プラズマCVD、プラズマエッチング、反応性イオンエッチング、プラズマ重合、プラズマ酸化・窒化、炭素被膜生成など広い範囲にわたって材料処理技術の最先端の位置にあり、IC加工も含め今後ますます発達するであろう。プラズマによる負イオン生成や高温による廃棄物処理など環境問題の解決にも、2000年以降応用が始まった。
[宮原 昭]
『西島和彦監修、一丸節夫著『プラズマの物理』(1981・産業図書)』▽『水野幸雄著『共立物理学講座23 プラズマ物理学』(1984・共立出版)』▽『宮本健郎著『プラズマ物理入門』(1991・岩波書店)』▽『川田重夫著『プラズマ入門』(1991・近代科学社)』▽『Francis F. Chen著、内田岱二郎訳『プラズマ物理入門』(1996・丸善)』▽『電気学会・マイクロ波プラズマ調査専門委員会編『マイクロ波プラズマの技術』(2003・オーム社)』▽『プラズマ・核融合学会編『プラズマの生成と診断――応用への道』(2004・コロナ社)』▽『高部英明著『岩波講座 物理の世界 さまざまな物質系4 さまざまなプラズマ』(2004・岩波書店)』▽『宮本健郎著『プラズマ物理・核融合』(2004・東京大学出版会)』▽『電気学会・プラズマイオン高度利用プロセス調査専門委員会編『プラズマイオンプロセスとその応用』(2005・オーム社)』▽『プラズマ・核融合学会編『プラズマエネルギーのすべて――カラー図解』(2007・日本実業出版社)』▽『八坂保能著『放電プラズマ工学』(2007・森北出版)』▽『篠田傳監修『プラズマディスプレイ材料技術の最前線』(2007・シーエムシー出版)』▽『後藤憲一著『プラズマの世界』(講談社・ブルーバックス)』
改訂新版 世界大百科事典 「プラズマ」の意味・わかりやすい解説
プラズマ
plasma
プラズマなることばは,三つの学問分野において別々の意味をもって用いられている。すなわち,血液学分野においては血漿(けつしよう)を意味することばとして,細胞学分野においては原形質を意味することばとして,そして物理学・電気工学分野においては自由運動する荷電粒子の集団を意味することばとしてそれぞれ用いられている。しかしここでとり上げるのは3番目の意味でのプラズマである。
プラズマの定義
プラズマという語を〈電解気体ionized gas〉という意味に用いた最初は,1920年代アメリカのI.ラングミュアである。彼は,例えばグロー放電やアーク放電中の陽光柱と呼ばれる部分には,負の電荷をもつ電子と正の電荷をもったイオン(正イオン)とがほぼ同じ割合で混在して巨視的には中性状態になっていることを確かめ,このような媒質を物質の一つの状態と考えてプラズマと名付けた。
現在の物理学でこのプラズマは〈異なった符号(正と負)の電荷をもつ2種以上の荷電粒子群を含み,そのうち少なくとも一方の荷電粒子群は不規則な熱運動を行っており,寸法としてはデバイ長よりも大きな部分〉と広く定義されている。ここでデバイ長とは,巨視的に見てこの媒体が電気的中性を保つとみなしうる最小の長さであり,言い換えれば,個々の電荷(荷電粒子)のクーロンポテンシャルが周囲に集まった逆符号の電荷によって遮へいされる距離といえる(図1)。家庭用の蛍光灯に見られる放電プラズマではこのデバイ長は0.01mmくらいであり,これより大きな体積部分は巨視的に見て電気的中性をほぼ保つと見てよいので,その放電管内にある気体の状態はプラズマと呼んでよい。
さて上の定義によると,プラズマは通常の放電気体にかぎらず,半導体,その他の固体中にも存在し,事実固体中にも,電子とドナー,正孔(ホール)とアクセプター,あるいは電子と正孔からなる種々のプラズマが存在しうると考えられており,これらは固体プラズマと呼ばれている。しかし現在,狭い意味では,荷電粒子(電子と正,負のイオン)の密度および電離度(荷電粒子の密度と中性分子の密度の比)が大きく,しかもその中での導電現象などの物性が磁場によって大きな影響を受けるような状態にある気体をプラズマと呼んでいる。
ところで,たいていの気体では荷電粒子群の温度(熱エネルギーの目安)が数万~10万K以上になるとほぼ100%電離してしまって中性分子はほとんどなくなり,いわゆる完全電離プラズマができる。この状態は通常の中性気体,あるいはわずかに電離した(弱電離)プラズマとは非常に異なった新しい物性を示すようになるので,〈物質の第4態〉(固体,液体,ふつうの気体に次ぐ第4番目の状態という意味)といわれている。このような理想的な100%電離気体をとくにプラズマと呼ぶことも多く,その物性,とくに電磁界との相互作用を研究する物理学の新しい分野としてプラズマ物理学が生まれ,最近とくに急速に発展しつつある。プラズマ物理学の中でも,とくにそれを電気的なふるまいを示す流体としての特徴を重視して研究する分野を電磁流体力学(MHDとも略称される)と呼んでいる。
プラズマ研究の歴史
プラズマ研究の歴史を顧みると,前述のラングミュア以来主として放電物理という立場から弱電離プラズマの基本的性質が調べられた。一方,これらと並行してほぼ同時代の1930年前後から始まり天体物理学,地球物理学との関連において発展してきた別の流れがある。これは地磁気,磁気嵐,オーロラ,さらに後には宇宙線の起源の究明に端を発したものである。そしてこの研究を通じて太陽を含む多くの恒星の内部およびその周辺(太陽コロナなど),あるいは宇宙空間内における電離気体の重要性がしだいに認識されるようになった。現在のプラズマ物理学および電磁流体力学の理論的発展はこの方面の多くの研究者の業績に負うところがきわめて大きく,さらに最近の宇宙科学の進展ともあいまってますます盛んになりつつある。例えば宇宙通信という実用的見地からも,一種のプラズマとみられる電離層とかバン・アレン帯内での電波の伝搬,それからの反射,散乱というような問題と関連して研究が行われている。
さらに,プラズマ研究の大きな流れが,宇宙および地上での熱核融合研究と関連して発展した。すなわち1929年ホウターマンスF.G.Houtermansらは,太陽をはじめとする恒星における膨大なエネルギー源のおもなものは高温のプラズマ状態にある軽い原子核間の熱核融合反応であることを理論的に示唆し,その後40年代になって,太陽における核融合反応がベーテH.A.Betheらによって解明された。さらに第2次世界大戦後水素爆弾という形で熱核融合プラズマの地上における応用が現実のものとなった。現在,原子力平和利用として世界各国で大規模に行われている核融合炉建設のための研究は,50年ころから主としてアメリカ,イギリス,ソ連などで開始されたものであるが,これは将来における高温プラズマのもっとも大きな工学的応用とみなされ,この研究開発に刺激されてプラズマの学術的研究がおおいに進歩しつつある。
プラズマの応用
プラズマの応用としては,往々にして上述した核融合研究に目を奪われがちである。しかし,見方によっては,プラズマの応用ともみられるものはむしろ核融合以外の分野において実用的な成果を上げている。現在すでに放電管,または放電装置と呼ばれる各種の応用機器があり,周知のように光源(水銀灯とかナトリウムランプ),熱源,整流装置,スイッチおよび遮断機,電気集塵器,各種の気体レーザー,プラズマ化学および半導体のプラズマプロセス,同位体の分離などに利用されているか,あるいは利用が検討されている。また高電圧工学の分野でもプラズマの性質が調べられその知識が利用されてきた。しかし従来のこれらの応用ではおもに弱~中電離で,かつ数万K程度の比較的温度の低いプラズマの性質が利用されるのが大部分であった。したがって,それは電離度の高い(数十%程度以上の)プラズマで,しかもそれ自身の物性,とくにプラズマと電磁場との相互作用をより直接的,積極的に利用しようとする今日の核融合研究中心の高温プラズマ研究とは,その性格がかなり異なっている。以下,簡単にプラズマの工学的応用について述べる。
(1)核融合反応の研究 重水素プラズマ,または重水素と三重水素の混合プラズマを一定の空間内に閉じ込めることによって核融合反応を起こさせ,そのエネルギーを電力の形で取り出して利用することを目的として世界各国で大規模な研究が行われている(核融合,核融合炉)。
(2)直接発電への応用 MHD発電および熱電子発電などの直接発電にプラズマが利用されている(直接発電,MHD発電)。
(3)宇宙科学への応用 ロケットの電気推進の一種にプラズマを用いた推進方式がある。この方式においてはロケットを推進するための力(推力)そのものはふつうの化学燃焼方式のものより小さい。しかし燃料そのものが気体であるため,推力とその推力を出すために必要な1秒間当りの燃料量との比(特性インパルス)が大きくなる。そこで,大気圏外の長距離宇宙旅行に好適として注目を浴びている。
(4)プラズマ電気工学 プラズマはその基本的な性質として,その電子の密度,温度,外部より加えられた磁場などの条件によって多種多様のモード(姿態)の電磁波を伝える。そこでこのような電磁波の特異な伝搬特性を利用して電子工学方面への応用が種々考えられている。現在のところ,マイクロ波帯における種々の回路素子(減衰器,移相器,導波管スイッチ,周波数逓倍器,検波器など)としての応用が検討されている。さらにマイクロ波用の増幅器,発振器としての応用もいろいろ研究されている。また本項の初めに半導体その他の固体中にもプラズマが存在することを述べたが,現在この固体プラズマを応用した電子の回路素子の研究も行われている。情報機器の分野においては,プラズマ・ディスプレーと呼ばれるカラー画像の表示装置の開発が行われている。そのほかとくに最近の傾向として,半導体デバイスの製造過程に各種のプラズマ応用が取り入れられつつある。なかでも放電プラズマを用いた酸化皮膜の生成とか,アモルファス・シリコン太陽電池の製造は,工業ベースに乗っている。
(5)プラズマ・ジェット 大気中のアーク放電プラズマは強力な熱源として金属工業その他の方面でアーク炉,アーク溶接などに広く実用されている。このエネルギー集中度を大きくして高温を得るためにくふうされたのがプラズマ・ジェットである。ふつうのプラズマ・ジェット発生装置は,金属円筒状容器の一端を一方の電極とし,それと同心的に設けたタングステンなどの棒状金属を他方の電極として,その間にアークを起こし,その円筒内に外部から適当な高圧ガスを送り込む形式のものである。このようにすると高温プラズマが外部に向かって安定にピンチされて噴出する。このような方法で得られるプラズマ・ジェットは温度が1万~2万Kで,厚い金属板または棒の高速度切断(溶断),高融点材料(セラミックスその他)の物体表面への塗布(塗布しようとする高融点材料を粉末状にして加圧ガス流とともにジェット装置内に注入する),金属材料表面の各種熱処理,溶接などにすでに実用されている。
(6)その他 以上のほかに,粒子加速器(イオン加速器,プラズマ・ベータートロン,プラズマ加速器などと呼ばれるもの)の応用として,高エネルギーばかりでなく,高密度の荷電粒子流をつくるという原子核物理学方面および半導体処理工程への貢献がある。また気体レーザーはプラズマ中における各種粒子の量子力学的な効果の応用とみなすことができ,その性能の向上にはプラズマの研究が不可欠である(メーザー,レーザー)。
プラズマの物理
プラズマの物理的性質を議論するとき,それを構成する個々の荷電粒子の運動に着目して議論する場合と,プラズマ全体を一つの流体とみなして議論する場合(MHD理論)の二つが代表的な方法といえる。以下ではそれらの議論に際して基本と考えられるいくつかの現象について,簡単な説明を加えておく。
ドリフト運動
速度を有する荷電粒子が静磁界B中に置かれると,その運動の軌道は磁力線にまつわりつくような円軌道となり,この運動を旋回運動あるいはサイクロトロン運動と呼ぶ。旋回の方向は磁界の方向に対して電子(負電荷)は右回り,正イオン(正電荷)は左回りである。このとき静磁界ばかりでなく,さらに静電界Eが磁力線と直角方向に加わると図2のように荷電粒子は旋回運動の途中で加減速を交互に受け,結果として,正負の符号によらずに,磁界と電界の両者に直交する方向に旋回中心が移動していく。一般に磁力線を横切る荷電粒子の運動はドリフト運動(移動)と呼ばれるが,上の例ではそれが磁界と直交する電界によって起こるため,とくに〈E×Bドリフト〉と呼ばれている。
ドリフト運動の他の例として〈磁界こう配ドリフト〉がある。いま,磁界が空間的に不均一であり,図3のように右側にいくほど磁界が大きくなるとすると,荷電粒子の旋回軌道の曲率は左右で異なり,左側のほうが大きく,結果として正負電荷は互いに逆方向にドリフト運動を起こす。そのためこのドリフト運動によって荷電分離が生ずる。
トロイダル・ドリフト
いま,直線電流で作られる同心円状の磁力線配位内に磁力線群で囲まれた円環状(トーラス)プラズマがあるとする。この中の個々の荷電粒子は上で説明した磁界こう配ドリフトを起こし,したがって正負電荷が上下方向に分離する。その結果プラズマ内には上下方向の電界が発生し,今度はその電界と,もともとの電界とによって,正負両電荷は径方向の外側へE×Bドリフトを起こす。結局,円環状のプラズマは全体として外側へと広がっていってしまうため,それを元の位置にとどめておくことができない。この現象はトロイダル・ドリフトと呼ばれており,核融合研究におけるプラズマ閉込めに際して,まず解決しなければならない問題である。
ミラー効果
旋回運動を行いながら磁力線に沿って進行する荷電粒子は,図4のように磁界が強まって磁力線が絞られていくと,それに従ってその旋回のピッチが小さくなり,ある点でピッチがゼロ,すなわち進行が止んだ後に反射され逆方向に動き始めて,もときた道を戻る。これがミラー(磁気鏡)効果と呼ばれるもので,もし図4のように磁力線に沿った2ヵ所で,対面してこのような場所があると,荷電粒子はその間の領域に閉じ込められる。この効果を応用した核融合プラズマ閉込め装置がミラー装置である。
プラズマ振動とプラズマ周波数
プラズマ内の正・負両電荷の集団が平衡位置より互いにわずかの距離だけ分離したとする。このときその表面には,正,負の分極電荷が生ずるため,内部には電界が生じ,両電荷の集団は元の平衡位置に戻ろうとする。しかしその復元過程において電荷は質量を有するから,その慣性効果で行き過ぎてしまい,今度は逆方向に分極を起こす。こうなると再度復元力が働くが,やはり慣性効果によって平衡位置で静止せず,結局,振動現象が生ずる。この振動のことをプラズマ振動,その固有周波数のことをプラズマ周波数と呼んでいる。いま有限幅をもったプラズマがあり,プラズマに入射する電磁波を考える。この波の周波数が,プラズマ周波数より低い場合,電磁波の振動電界はプラズマ粒子の運動を引き起こし,電界は短絡(ショート)されてしまうから,その電磁波は内部へは入れない。つまりその場合,電磁波はプラズマ表面で反射されてしまう。他方二つの周波数の大小関係が逆だと,電磁波はプラズマ中を通り抜けることができる。
ところで,地球をとりまいている電離層は地磁気に閉じ込められたプラズマの一種であって,そのプラズマ周波数は数十MHzである。したがって,それ以下の周波数をもつ短波とか長波は電離層で反射されるが,それ以上の周波数をもつVHF~UHF帯の電磁波(例えばFM放送とかテレビの電波)はそこを通過してしまう。
磁束の凍結と再結合
プラズマでは温度が高くなるとその電気抵抗は減少する。そのためプラズマ内を通り抜けている磁力線はプラズマといっしょに運動する。この原因は,プラズマが磁力線を横切って動こうとするとき電磁誘導の法則によって磁束の変化を阻止しようとする渦電流が内部に生じ,磁力線はプラズマとともに動くように変形させられることにある。これは何もプラズマのみに見られる現象ではなく,導電性の高い物質共通のものといえる。ところで流体であるプラズマにおいて,固体の場合とは異なって磁束の凍結は必ずしも理想的には起こらない。とくにプラズマの変位が大きく磁力線の変形が大きくなると,プラズマ中に電磁的な乱れが生じて局所的に電気抵抗が増え,そこで凍結は破れてしまって磁力線の配置換えが起こる。このような現象は〈磁力線の再結合〉と呼ばれている。
例えば,電離層などの地磁気に捕らえられたプラズマを考えてみよう。そこには常時太陽からのプラズマ流(太陽風)が吹きつけているので,プラズマは太陽とは逆側に地磁気の磁力線とともに吹き流されている。しかしときどきプラズマ内に不安定現象が起こるため磁力線の再結合が起こり,そのとき電界が生じてプラズマ粒子は加速される。南極や北極においてしばしば見られるオーロラは,このようにして加速された粒子が原因となった発光であろうといわれている。このような複雑な現象の研究においてはコンピューターを用いたシミュレーションが有効であり,逆の見方をすれば,今日の高性能コンピューターの存在がプラズマ研究を推進させている一要因になっている。
執筆者:関口 忠+桂井 誠
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プラズマ」の意味・わかりやすい解説
プラズマ
plasma
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「プラズマ」の意味・わかりやすい解説
プラズマ(物理)【プラズマ】
→関連項目アルベーン|オーロラ|核融合科学研究所|自由電子|トカマク|ピンチ効果
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
化学辞典 第2版 「プラズマ」の解説
プラズマ
プラズマ
plasma
電離した陽イオンと電子からなる荷電粒子を含む気体.プラズマには,大部分が中性粒子でその一部が電離している弱電離プラズマと,全部が電離している完全電離プラズマがある.半導体の分野などをはじめとして,工業的に利用されるのは弱電離プラズマである.プラズマは直流(交流)アーク放電や高周波誘導などによって発生させる.工業的に広く用いられる熱(平衡)プラズマは,電子および中性粒子の温度がほぼ等しく,5×103~2×104 K の温度範囲にある.熱プラズマは熱容量が大きく,これを用いると物体を急速に加熱できる.応用は広範囲にわたり,プラズマCVD,プラズマ重合,プラズマエッチング,溶射,浸炭など,各種の表面改質などに利用される.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「プラズマ」の解説
プラズマ
世界大百科事典(旧版)内のプラズマの言及
【核融合炉】より
…容器内で壁から隔離して閉じ込められたプラズマを数億度という超高温に加熱し,そのとき起こる熱核融合反応によってエネルギーを取り出そうとする装置。
【熱核融合プラズマの条件】
熱核融合を起こすには,プラズマを閉じ込め,外部から十分高温になるまで加熱する必要がある。…
【放電】より
…グロー放電とアーク放電は外観から名付けられたものであるが,陰極からの電子放出機構がグロー放電では正イオンの衝突などによるγ作用,アーク放電では熱電子放出あるいは電界放出であるという差がある。放電によって生じた電離した状態の媒質をプラズマという。 気体放電の開始理論にはイギリスのタウンゼントJ.S.Townsendが提唱したタウンゼントの理論と,のちに同じイギリスのミークJ.M.Meekの提唱したストリーマー理論がある。…
※「プラズマ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...