デジタル大辞泉 「層」の意味・読み・例文・類語
そう【層】[漢字項目]
[学習漢字]6年
1 重なる。重なったもの。「層雲/下層・重層・断層・地層・表層・成層圏・電離層」
2 階を重ねた建物。階。「階層・高層」
3 ある基準で区分した、人々の集団。「知識層・中間層・読者層」
4 程度が大きいことを表す語。「一層・大層」


 (そう)(こしき)の初文。
(そう)(こしき)の初文。 は〔説文〕八上に「重屋(ちやうをく)なり」とあり、重層の家をいう。すべて累層をなすものを、層楼・層雲のようにいう。
は〔説文〕八上に「重屋(ちやうをく)なり」とあり、重層の家をいう。すべて累層をなすものを、層楼・層雲のようにいう。 字鏡〕
字鏡〕 志奈(しな)、
志奈(しな)、 、
、 乃己志(たふのこし)〔和名抄〕
乃己志(たふのこし)〔和名抄〕
 乃古之(たふのこし)〔名義抄〕
乃古之(たふのこし)〔名義抄〕 シナ・カサヌ・シキル・タフノコシ・コシ・タカシ/
シナ・カサヌ・シキル・タフノコシ・コシ・タカシ/
 カサネカマヘタリ
カサネカマヘタリ ・曾dz
・曾dz ng、
ng、 (増)tz
(増)tz ngは声義近く、
ngは声義近く、 が上下重なる器であるように、すべて上下に累増するものをいう。
が上下重なる器であるように、すべて上下に累増するものをいう。 ▶・層出▶・層霄▶・層城▶・層畳▶・層層▶・層台▶・層塔▶・層濤▶・層冰▶・層壁▶・層峯▶・層巒▶・層累▶・層楼▶・層浪▶
▶・層出▶・層霄▶・層城▶・層畳▶・層層▶・層台▶・層塔▶・層濤▶・層冰▶・層壁▶・層峯▶・層巒▶・層累▶・層楼▶・層浪▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
層は現代数学,とくに幾何学,関数論,さらには微分方程式論などで広範囲にわたって利用されている重要な概念である。層は非常に一般的な考えであり,数学における種々の概念を統一的に扱ったり,問題を定式化するのに有効な道具である。もともとは,1940年代後半に岡潔が多変数関数論の研究の中で,現在の前層にあたるものを利用した。岡はそれを不定域イデアルと呼んだが,他方同じころ,これとは独立にルレーJ.Leray(1906-98)が同様なものを考えた。その直後,H.カルタンらが層の一般論を展開,多変数関数論に有効に利用した。セールJ.P.Serre(1926- )は層の概念が代数幾何学において非常に有効であることを示した(1955)が,それはその後の代数幾何学の発展の基礎となった。
位相空間Xの各開集合Uにアーベル群(環,R加群など)F(U)が対応していて,V⊆Uのとき,準同型ρv,u:F(U)→F(V)が与えられているとする。もし,ρu,uが恒等写像で,W⊆V⊆Uならば,
ρu=ρw,v・ρv,u
となっているとき,この{F(U),ρv,u}をX上のアーベル群(環,R加群)の前層という。Xのかってな開集合Uの任意の開被覆U=∪Uiを取ると,
(1)すべてのiについて,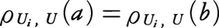 となるa,b∈F(U)は一致する,
となるa,b∈F(U)は一致する,
(2)各iについて,ai∈F(Ui)が与えられていて,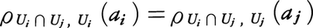 がすべての組(i,j)で成り立つならば,F(U)の元aで,
がすべての組(i,j)で成り立つならば,F(U)の元aで,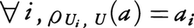 となるものが存在するという2条件を満たすとき,この前層は層であるという。
となるものが存在するという2条件を満たすとき,この前層は層であるという。
Xが一次元ユークリッド空間のときの,F(U)={有理関数f(x)/g(x)で,g(a)≠0,≏a∈U},あるいはXが複素n次元(n≧1)空間のときの,F(U)={U上解析的な関数}として,ρv,uはいずれの場合にも関数の定義域をUからVに制限する写像とすれば,両方とも層になっている。しかし,Xがn次元ユークリッド空間で,Uが空でない開集合ならば,G(U)=Z(整数全体がなすアーベル群),空集合φについてはG(φ)={0}とおく。U≧V≠φのときはρv,uはZの恒等写像,ρφ,u=0と決めれば,{G(U),ρv,u}は前層であるが,層ではない。実際,開集合Uが二つの空でない開集合U1,U2の和集合U=U1∪U2で,U1∩U2=φとする。a,b∈Zが相異なるとして,a∈G(U1),b∈G(U2)と考えると, であるから,Gが層であるならば,c∈Z=G(U)で,
であるから,Gが層であるならば,c∈Z=G(U)で,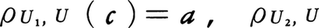
 となるものがなければならない。しかし,
となるものがなければならない。しかし,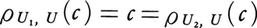 だから,このようなcは存在しない。この前層Gは位相幾何学で重要なものである。
だから,このようなcは存在しない。この前層Gは位相幾何学で重要なものである。
執筆者:丸山 正樹
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
地層を岩相単位で区分する場合に用いられる基本的な単位で、部層より一段階上、層群より一段階下のもの。累層ともいう。通例、岩質の点で同一の特徴をもった一連の地層で、岩質の急変するところで層を区分する。層にはさまざまな厚さのものがあるが、普通、地質図に表記できる程度のものが用いられる。命名するときは、模式地名をつけて、たとえば成田層というように用いられる。層はかならずしも部層に区分されるとは限らない。
[村田明広]
formation
岩相層序区分の単位の一つ,層群と部層の中間で,2つ以上の部層の集り。2000年4月1日の地層命名の指針の改訂により,累層に相当する地層単元(層序区分の単位)は層とすることに改められた。層は岩相的に他とはっきりと区別されていることが必要である。層という単位の層厚に基準はなく,1m程度から数千mまでの幅がある。ふつう,単に○○層(地名+層)と命名・呼称されているものの大部分は,層または部層である。層状の地層や岩体を表わすことから,堆積岩以外に噴出岩や変成岩類にも用いられることがある。
執筆者:山田 一雄・公文 富士夫・柴 正博
参照項目:日本地質学会地層命名規約
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...