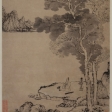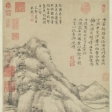精選版 日本国語大辞典 「南宗画」の意味・読み・例文・類語
なんしゅう‐が‥グヮ【南宗画】
改訂新版 世界大百科事典 「南宗画」の意味・わかりやすい解説
南宗画 (なんしゅうが)
Nán zōng huà
中国の画風の一つ。南画ともいう。南宗画という用語は16世紀後半から17世紀初頭にかけて活躍した松江華亭(現,上海市)の画家,董其昌(とうきしよう),莫是竜(ばくしりゆう),陳継儒において見られる。彼らはみずからを文人画の本流に棹さすものと自負し,その立場から当時の万暦画壇を批判し,独自の絵画史観を展開した。南宗画の基本的な立場は,刻画(細かく輪郭づけて描く)よりも渲染(せんせん)(水墨でぼかす),行家(こうか)(くろうとで匠気をもつ)よりも利家(りか)(しろうとで士気をもつ)というもので,様式的には細密巧緻で濃厚豊麗なものより,簡略粗放で軽淡清雅をよしとし,精神的には技巧に基づく客観主義より文人的教養を伴った人格表現を重視した。
南宗画という命名の由来は,当時流行の禅宗趣味(董其昌はかなり禅学に没頭している)から,五祖弘忍(ぐにん)の後が,神秀(じんしゆう)の北宗禅の漸修と,慧能(えのう)の南宗禅の頓悟とに分かれ,慧能が六祖を継いでから簡略を旨とする南宗禅が栄えたことになぞらえて,画にも北宗,南宗の別があるとし,その起源も禅宗と同じく唐にまでさかのぼり,北宗は細密な輪郭線によって着色山水を描く李思訓に始まり,南宗は渲淡によって李思訓らの鉤斫(こうしやく)(輪郭でくくる)の法を一変した王維に始まり,画でも禅の頓悟に比せられる南宗画が栄えたという。莫是竜によれば,北宗は李思訓,李昭道,趙幹,趙伯駒,趙伯驌,馬遠,夏珪とつながり,南宗は王維,張璪,荆浩,関仝,郭忠恕,董源,巨然,米芾(べいふつ),米友仁,元末四大家(黄公望,呉鎮,倪瓚(げいさん),王蒙)と続くとするが,董其昌,陳継儒のいう系譜とはやや異なる。この南北の系譜については,伝統的な線描を骨格とする職業画家李思訓と,破墨山水を描いて初期水墨画家の一人に数えられ詩人を本職とする王維とをそれぞれ北宗,南宗の祖とするのは理解できるが,二人につづく南北画人の系譜は歴史的事実と整合させがたく,董其昌らの無理な作為が目だつ。
では南宗画を唱えた意図は何であろうか。南北の系譜についていえば元以降,明・清にあってはどうかという点について董其昌,莫是竜は明言していないが,彼らの同調者あるいは後継者によれば,南宗は元の四大家ののち沈周(しんしゆう),文徴明,董其昌,清初の四王(王時敏,王鑑,王翬(おうき),王原祁(おうげんき))と続き,北宗は南宋画院の馬遠,夏珪,李唐,劉松年をうけて明の画院の戴文進にいたり,その後継者たちは浙江出身の戴文進にちなんで浙派と呼ばれ,沈周,文徴明ら蘇州(呉)出身者に代表される呉派文人画に対置される。そして浙派は呉派の側から狂態をたくましうする邪学であると非難されている。このような事実からみると,南宗・北宗の論は,董其昌らが明の宮廷画院およびその流れをくむ画家たちを攻撃し,社会的・商業的に優位に立とうとする意図からなされたものと思われる。
そもそも董其昌らのいう文人画(すなわち南宗画)は元以降,産業・商業の発達に伴って成熟した市民階級の画であり,市民が自己の生活環境(町やその周辺の名勝や個人の別荘や庭園など)を明るく肯定的にとらえるもので,そこには知性的・倫理的・享楽的雰囲気が巧みにあらわされている。これに対して宮廷画家や職業画家たちは南宋画院の技術的洗練を受けつぎつつ,それを過度に誇示し,山水では好んで高峰幽壑(ゆうがく)・奇樹怪石を描き,花鳥・人物では技術的に呉派文人画を圧倒した。浙派を邪学とする非難には,技巧面でのコンプレクスも含まれていよう。呉派の側にも問題があって,沈周,文徴明以後,しだいに浙派を圧倒して画壇の主流を占めるようになると,文人画の職業化がおこり形式化が著しくなり,董其昌のころには蘇州の画壇は沈滞ぎみであった。また明末に市民文化の爛熟期を迎えると,蘇州をはじめ杭州,松江,南京,揚州,新安など,江蘇・浙江の長江(揚子江)デルタ地方から安徽・江西にかけての諸都市を中心に多くの画家たちが輩出し,その身分も市井の画工から文人の余技まで,その作風も地方色の顕著なものから特異な個性を発揮するものまで多様を極めた。こういった文人画をも含めた狂噪混乱に,ある秩序を与えようとする意図も南宗・北宗論には見られる。
南宗画の意味するところは,したがって元の四大家以降の明・清文人画の理想的なあり方である。また南宗画の実質ということも考えうる。南宗画とは江南の風景を描くという意味を必然的に含み,江南山水画の制作に当たって開発された技法や構図がその実質をなす。水墨技法も江南において多く発達し,五代の宮廷画家董源は,華北の構成主義的山水とは異なる〈一片の江南〉と呼ばれる肩のこらない風景を平淡天真と称される素直な描写でとらえ,披麻皴(ひましゆん)と呼ばれる柔かい皴法(しゆんぽう)をあみ出した。北宋の米芾は董源を称揚し,極度に発達した水墨技法で変幻する雲山を描き,米点と呼ばれる技法を示した。これらは南宋の画院にも大きな影響を与えたが,元の四大家以後の南宗画の技術的伝統の根幹をなした。董其昌は山水画のエッセンスを追究するという理論的な画家で,以後の南宗文人画発展に大きな役割を果たしたが,典型に基づく制作を主張することによって,かえって形式化,無気力化が目だつようにもなったが,董其昌をつぐ清初の四王が出ると南宗文人画がアカデミズムを形成するようになり,清朝の宮廷画風をも風靡した。花鳥画についても五代・宋初から着色と水墨,写生と写意の2流が併存していたが,文徴明や董其昌にほぼ平行して陳淳や徐謂(じよい)が出て,水墨あるいは着色のつけたて,または粗放な水墨で写意的な花卉(かき)を描き,清初の惲恪(うんかく)も没骨(もつこつ)花卉を描いて,ともに南宗花鳥画の伝統を形成した。
→北宗画
執筆者:山岡 泰造
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「南宗画」の意味・わかりやすい解説
南宗画【なんしゅうが】
→関連項目王【き】|王原祁|巨然|金弘道|呉派|山水画|浙派|相阿弥|董其昌|董源|長崎派|馬和之
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「南宗画」の意味・わかりやすい解説
南宗画
なんしゅうが
中国、明(みん)代後期に莫是龍(ばくしりょう)、董其昌(とうきしょう)らが唱道した、それまでの中国絵画を大きく二つに分類したうちの一つ。彼らは中国絵画を南宗画と北宗画とに分け、南宗画の祖を唐代の王維(おうい)とみなし、五代南唐の董源(とうげん)、巨然(きょねん)、北宋(ほくそう)の米芾(べいふつ)・米友仁(ゆうじん)父子、元末の四大家、王蒙(おうもう)・倪瓚(げいさん)・呉鎮(ごちん)・黄公望(こうこうぼう)を経て、明の呉派(ごは)の沈周(しんしゅう)、文徴明(ぶんちょうめい)に及ぶものとする。南宗画を絵画の正統とする莫是龍、董其昌らは、技巧的な職業画家の絵画(北宗画)を嫌い、絵画に書巻(しょかん)の気を求め、自然な感興を穏やかに表現することを望んだ。技術的には披麻皴(ひましゅん)(麻をほぐしたような柔らかい描線)を多く用い、色彩も軽やかなものが多い。
そもそも南宗画・北宗画という分類は、絵画の分類を南頓北漸(なんとんほくぜん)と禅に見立てたり、南宗画の始祖に仏教に深く帰依(きえ)していた王維を持ち出してきたり、多分に恣意(しい)的な立論であるが、董其昌がその画論書を『画禅室随筆(がぜんしつずいひつ)』と名づけたように、董其昌自身禅に強い関心を寄せていたことにも一因がある。とにかく南宗画・北宗画の論が明代後期に出現して以来、その影響力は今日にまで及び、南宗画をよしとし北宗画を悪くみる、いわゆる「尚南貶北(しょうなんへんぼく)論」が一部の人々には根強く残っている。だが現在、この論が改めて検討される時期に達し、絵画史の認識も新しくなりつつある。なお、「南画(なんが)」と称するのは日本のみで、中国本土の南宗画を母体としつつも、その意味と形態の差でおのずから違ったものとなっている。
[近藤秀実]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「南宗画」の意味・わかりやすい解説
南宗画
なんしゅうが
nan-zong-hua
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「南宗画」の解説
南宗画
なんしゅうが
唐の王維を始祖とみなすが,五代・宋初期の董源 (とうげん) によって完成され,元・明・清代には支配的画風となった。明代の董其昌 (とうきしよう) によって大成された。自然山水を主観的な心境で表現し,水墨淡彩,細くやわらかい描線を特徴とする。元末期の黄公望 (こうこうぼう) ・倪瓚 (げいさん) ・呉鎮 (ごちん) ・王蒙 (おうもう) の四大家,明の沈石田 (しんせきでん) ・王元章,清初期の四王呉惲 (しおうごうん) らが著名。江戸中期以降の日本画に影響を与えた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「南宗画」の解説
南宗画
なんしゅうが
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「南宗画」の解説
南宗画(なんしゅうが)
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の南宗画の言及
【山水画】より
…前者はその代表とされる戴進が杭州出身であったため,明代に入って浙派と称され,後者は沈周(しんしゆう)を始めとして主に蘇州出身の画家によって形成されたため,呉派と呼ばれ,あわせて明代絵画史を画する二大潮流をなした。明末に至って董其昌は禅の宗派にたとえて,浙派を唐の宗室画家の李思訓・李昭道父子に始まる北宗(ほくしゆう),呉派を盛唐の詩人でもあり文人画家でもある王維に始まる南宗(なんしゆう)とする南北二宗論を展開し,董源,巨然から米芾,米友仁,元の四大家を経て呉派文人画に至る,南宗画の正統を継承すると自負する自己の史的位置を,山水画の始源にまでさかのぼって確立しようとした。しかしながら,明末の時点ではすでに浙派に対する呉派文人画の勝利は決定的であり,華北と江南という地方性,文人画家か宮廷画家かといった階層性,そこから生じる表現上の相違などが複雑に交錯した,中国山水画における南北の対立と総合の図式は,華北と江南という枠組みが江南の中の浙派と呉派の対立というように集約され,さらに一方が他方に対して勝利を告げた明末のその時点で実質的に解消していたといってよい。…
【董源】より
…南唐の中主李璟に仕えて後苑(北苑)副使となり,宮廷画家として活躍した。山水画は水墨と着色をかき,北宋末期の米芾(べいふつ)が並びなき神品と絶賛して以来,名を高め,後世,南宗画(なんしゆうが)の事実上の開祖とされた。その画風は,江南の水気豊かな自然を,披麻皴(ひましゆん)(皴法)などにより柔らかく平淡にとらえ,伝称作品の《瀟湘図巻》(北京故宮博物院)にその一端がうかがえる。…
【南画】より
…日本において,南宗画(なんしゆうが),文人画とほぼ同義に用いられてきた語で,明らかに〈南宗画〉をいう言葉の略称であったと思われる。その起源は定かではなく,江戸時代にも用いられた例がなくはないが,特に大正以降,盛んに使われるようになった。…
【文人画】より
…董其昌の南北宗論は実は南宗正統画論であり,中国の絵画を南宗(なんしゆう)と北宗(ほくしゆう)の2様式に分け,李思訓・南宋院体・浙派と続く系譜を北宗,王維・董源・米芾・元末四大家・呉派の系譜を南宗とし,南宗の北宗に対する正統的優位を主張した。そして系譜をみてもわかる通り,南宗正統画は文人画でもあったのである(南宗画,北宗画)。 こうして次の清朝はほとんど文人画一色と化し,四王呉惲(しおうごうん)の南宗正統画派,八大山人,石濤などの遺民画家,金陵派や新安派などの江南都市絵画,あるいは金農,鄭燮(ていしよう)などの揚州八怪が登場した。…
※「南宗画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...