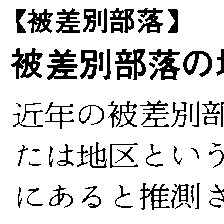精選版 日本国語大辞典 「被差別部落」の意味・読み・例文・類語
ひさべつ‐ぶらく【被差別部落】
改訂新版 世界大百科事典 「被差別部落」の意味・わかりやすい解説
被差別部落 (ひさべつぶらく)
都市部,農山漁村部のいかんを問わず,特別な差別意識により,交際,婚姻,就職等々の面での厳しい差別をこうむりつづけてきている集落を指す。別に〈未解放部落〉ともいい,行政上は〈同和地区〉と称する。しかし,これらの呼称はまだ必ずしも全国的に普及しきっているとはいいがたく,ことに,被差別部落に対する差別の撤廃のための啓発活動が行政,教育などの面で積極的に推進されていない地方では,伝統的に受け継がれてきた独特の差別呼称が,こんにちもなお日常生活の陰陽両面で用いられているのが実情である。また,集落,村落,在所などと同義の語として〈部落〉の語を適用している地方が多いので,場合によっては誤解をまねきやすいが,被差別部落を略して〈部落〉とも称し,被差別部落に対する差別を〈部落差別〉,被差別部落にかかわる社会問題を〈部落問題〉,部落差別からの完全な解放をめざす社会運動を〈部落解放運動〉という。
被差別部落の成立
被差別部落の沿革が,個々の被差別部落にそくして明らかになることは,部落差別の根源を客観的に照らしだし,差別の不当性をいっそう明確にしていくためにも望ましいが,なにぶんにも,ほとんどの被差別部落については伝来の文献史料が過少で,とくにその成立事情については口碑のほかに頼るべきものがない場合が圧倒的に多い。しかし,一般的には,被差別部落は封建的身分制度により,16世紀末~17世紀に成立し,その後も時期を異にしつつ,北は東北の諸藩から南は九州の諸藩にいたるまでの全国各地において,漸次出現したものとみられる。したがって,いわゆる部落差別が本格化したのは,江戸時代の幕藩体制のもとでのことであった。部落差別は,確かに明治維新以降の近代化による政治・経済・社会のひずみとも密接な関係にあるとはいえ,江戸時代における武士・百姓・町人・賤民の身分格差のなかで最底辺におかれていた賤民身分の人々に対する格別の差別意識に深い根を下ろしており,その意識が,社会的偏見に凝縮されて,交際,婚姻等々の面での苛酷な差別を,現代にいたるまで存続させてきていると考えられるからである。
江戸時代における被差別部落の中核部分をなしたのは〈えた〉であったが,その名で呼ばれる人々の存在は,いちはやく中世,鎌倉時代末期の文献で〈穢多〉という漢字表記とともに確認される。江戸幕府としては,全国的支配体制の維持のためには統一的な身分制度が不可欠であり,兵農分離・太閤検地・戸口調査・〈かわた〉身分(後述)の確定等々をはじめとする豊臣政権の実績を基礎におきながら,いっそう徹底した形での身分制度の実現をめざした。そこで〈えた〉=〈かわた〉が被差別民の中核部分として確定される端緒が開かれたのであるが,それが制度的に明確になるまでには相当な歳月を要し,各地方の実情・独自性ともかかわりながら,漸次,年を追って強化されていった。
近世以前の被差別民
部落差別は,いうまでもなく被差別部落の編成・固定に発するが,〈えた〉や〈非人〉をはじめとする各種の賤民層に対する差別は,明らかに近世以前に存在しており,豊臣政権と江戸幕府は,既往の差別慣習を踏まえて旧来の被差別民の身分的な整理・再編・固定をはかり,被差別部落の基本的な枠組みを確立させたと考えられる。したがって,被差別部落,ならびに部落差別の根源について適切な理解を得るには,被差別部落の成立を導きだした歴史的前提として,先行する各時代の身分制を概観しておかねばならない。
古代律令制下の賤身分
日本で賤の身分が制度的に明確にされたのは,7世紀の半ばにおける律令制の発足による。その際,中国の隋・唐や朝鮮の高句麗・新羅・百済などでの実際例が参考にされたとみられているが,670年(天智9)に作られた日本最初の戸籍である《庚午年籍(こうごねんじやく)》に〈良〉と〈賤〉の区別が初めて明記された(ついでながら当時はまだ〈賤民〉の語はなく,これは比較的新しい時代に用いられだした語である)。律令制下の賤身分に位置づけられていたのは,〈五賤(ごせん)〉または〈五色(ごしき)の賤〉と総称された5種類の身分であった。それを上位から順に追うと,天皇(大王=オオキミ)・皇族の墓の守衛に専従した〈陵戸(りようこ)〉,なんらかの理由によって〈良〉身分を奪われ,官奴司(やつこのつかさ)/(かんぬし)に所属して雑用に従事した〈官戸(かんこ)〉,貴族に隷属した〈家人(けにん)〉,官奴司に隷属して雑用に従事した〈公奴碑(くぬひ)〉,個人の所有下におかれて雑用に従事した〈私奴婢〉であった。また〈良〉の下層部には,手工業をはじめとする特殊な技能をもつ各種の〈品部(しなべ)〉〈雑戸(ざつこ)〉がおかれ,その職能は世襲とされ,他の〈良〉に比して卑賤視されたが,そのうちあるものはむしろ〈賤〉に近い扱いを受けていた。〈良〉と〈賤〉との身分的差別は厳格であったが,双方の間に生じた婚姻関係については公認しており,〈良〉〈賤〉の間にできた子はすべて〈賤〉にした。しかし,この方式は8世紀の初頭にいたって改められ,双方の婚姻はいっさい禁じられた。その後,8世紀末の789年(延暦8)にいたり,〈良〉〈賤〉の間にできた子はすべて〈良〉にすることとした。法の定めとは別に,現実には双方の婚姻があとを絶たず,やむなく所生の子を〈賤〉にしつづけるのは,租税等の賦課をとおして国家財政の基盤としていた〈良〉人口の減少につながる恐れがあったからとみられている。ただし,奴と婢の間の子はすべて〈賤〉であった。奴婢人口の安定的確保のためであるが,その奴婢身分も,律令制から荘園制へという時代・社会構造の大きい転換のなかで,10世紀初めの延喜年間(901-923)にいたり全面的に廃止され,日本の賤民史上に特筆される画期をなした。これ以後,律令制にもとづく身分制・賤民制の仕組みは急速にくずれていった。
中世荘園制下の被差別民
律令制の解体,荘園制の時代の到来は,律令制下の官司に隷属していた各種の〈賤〉身分の人々や〈品部〉〈雑戸〉らを国家的組織から解放した。そのことは,多くの場合公家や寺社などの荘園領主の支配下に新たに組み込まれることでもあったが,一方では,官司のもとで着実に身につけていた優秀な専門的技能・知識をいかして自主的に対処できる領分も,前代に比して,はるかに拡大することとなったのである。
この時代には,かつてのような身分制度はなかったが,民衆の中には耕地などの土地を有さず,主人に隷属し,人身譲渡の対象ともされた〈下人(げにん)〉〈所従(しよじゆう)〉がおり,また,とくに公家社会や寺社組織の上層部から卑賤視された人々がさまざまに生みだされた。後者のうちで最も多数を占めたのは,おそらくは〈非人〉と称された人々であったと推察される。その内実は種々雑多であって,大寺社に人身的に隷属して〈キヨメ〉(清めの意で,寺社域・道路の汚穢(おわい)を清めたり,葬送行事にかかわる下役を勤めたりする)の雑役に駆使されたり,雑芸で口を糊したりしたものから,物乞いでかろうじて生きた〈乞食〉の集団をなしたものまでをも指しており,これには〈癩者〉(ハンセン病患者)をはじめとする貧窮孤独の病人や身体障害者も含まれ,仏教思想による〈慈善救済〉,具体的には,いわゆる〈施行(せぎよう)〉(施し)の対象となっていたものである。彼ら〈非人〉の多くは,京都(京)の清水坂(きよみずざか)や奈良(南京・南都)の奈良坂など都市の周縁部に位置する交通の要衝や,荘園内に設定された〈散所(さんじよ)〉という地域を根拠地として,〈非人長吏(ちようり)〉や〈散所長者〉による統率・管理のもとで集落生活を営んでいた。さらに鎌倉時代中期には,すでにこの〈キヨメ〉たち(職能の呼称が,それに携わる人の呼称にもなった)は〈えた〉と同一視されており,〈えた〉はまた〈河原のえた〉ともいわれたように〈河原者(かわらもの)〉と一体であったことが知られている。〈河原者〉は河原の刑場での処刑に関する雑役,河原を作業場とする鳥獣の屠割や皮革の生産を主たる生業としたが,南北朝時代以降,彼らのなかから作庭に従事する〈山水(せんずい)河原者〉が輩出したことは文化史上に名高い。
以上にみたように,この時代の被差別民は多種多様であり,そのあり方も,相互に入りまじったり,呼称表現は違っていても実体に変りがなかったりして,明らかに律令制下で賤民分がおかれていた状態や,江戸時代の幕藩体制のもとで〈えた〉〈非人〉らがおかれていた状態とは異なっていた。統一的な政権による,統一的な身分制度が定立しなかったからである。ことに中世後期(南北朝時代以降)に入ると,民衆勢力の向上のなかで社会全体に下剋上の風潮がみなぎりはじめ,身分の流動性はいっそう激しくなり,上層の支配者たちに卑賤視されていた人々のなかからも,経済的実力を蓄えたり,〈一芸の上手〉とたたえられるほどに独自の技芸に磨きをかけたりして,みずからの社会的地位を高めるものが現れたのであった。しかしながら,その一方では,特定の人々に対する集中的な偏見もまた,この中世後期を通じてしだいに強まり,近世初期における被差別部落の成立へと向かう路線が着実に用意されることとなった。その人々とは,中世後期の社会で身分的に卑賤視されていたもののうち,とくに,屠殺や斃(たおれ)牛馬の処理の作業を基礎におく皮革生産(皮)の熟練者と,刑吏的職能に長じていたものとにしぼられたといっても,あながち過言ではあるまい。そして,このことは,荘園制を根底から揺さぶりつつ歴史の舞台に登場してきた戦国大名たちの領国支配体制のもとで明確になってくる。
戦国大名下の被差別民
各地に続出した戦国大名は,領国支配のために家臣団と商工業者を城下に集住させて城下町を建設し,独自の〈分国法〉を制定し,兵農分離策を推進するとともに,軍備の確保のために不可欠であった皮革を安定的に保持すべく,皮革生産者たちに対して特別の保護と統制を加えた。保護とは,領国内での皮革生産・商売の権利を他者の侵害から擁護し,屋敷地(住所)を保障し,領民一般が賦課される諸役を免除されることであった。その代償に,他の職業に転ずること,指定の住所を移ることは,固く禁じられた。このようにして皮革生産者は,支配領域は領国に限られるとはいえ強力な軍事力をもつ大名権力に直接的に把握され,従属することとなった。そして,〈河原のえた〉もやはりそうであったように,時と場合によっては,刑吏的任務をも課せられたとみられる。さらには,これも重要な点であるが,その住所として特定されたのは,概して城下町の周縁部,交通上の要衝,河原の地であったらしい。このような事情は,駿河の今川氏,伊豆の後北条氏,甲斐の武田氏などの例で推察されているが,いずれの場合でも該当者は〈かわた〉の呼称で呼ばれていた。
〈かわた〉の語は,室町時代初期の史料にすでに現れていたが,しきりに用例が見いだされるようになるのは,この戦国時代から江戸時代にかけてであり,漢字があてられる際には〈皮太〉〈革多〉〈皮田〉などと表記された。皮革業にかかわる者であることが自他ともに強く意識されてのことであろうが,本来は皮革生産・商売に携わる者の呼称では,皮作,革作,皮剝ぎ,皮屋などが一般的ではなかったかと考えられ,〈かわた〉の語の原義については,なお検討の余地を残しているとみてよい。また,〈かわた〉の呼称がたんに職能を指すか,それとも一定の身分を示すかについても,今後の研究の深化にまつべき点が多いが,すでにこの時期には〈不浄・ケガレ(穢)〉を忌避する伝統的な宗教思想・信仰心から,斃牛馬の皮剝ぎや解体処理などを〈けがらわしい〉こととする見方が寺社を通じて民間にも広まっていたので,そのような認識と〈かわた〉の人々とが結び合わされて,彼らに対する卑賤観をしだいに強めたことは容易に推察される。キリシタン宣教師ルイス・フロイスの言によると,〈かわた〉と同じくこの時期に,〈死んだ獣類の皮を剝いでその皮を売〉って生活していた〈えた〉は,〈最も卑しい,仲間外れにされた賤民〉であり,〈まるでほかの人たちと交際するに価しない不浄な人たちのように,いつでも村落から離れて住んでい〉たといわれており(《日本史》),〈えた〉と〈かわた〉との共通性は明白であろう。しかし同時に,こうした観察記録からの印象や,〈被差別〉ということから受ける印象を一面的にたもつことによって,一概に彼らが〈悲惨な貧窮民〉であったかのように考えてしまうのは,けっして適切ではなく,少なくとも近世初頭の近畿地方の実例では,〈かわた百姓〉たちの農地保有高は他の百姓の場合に比して遜色(そんしよく)がないどころか,むしろそれを越えるものも少なくはなかった。〈かわた〉のすべてが皮革生産の専業者というわけでなく,皮革生産とあわせて農耕に従事し,〈百姓〉としての性格を強めていた〈かわた百姓〉も多数いたのである。
近世の被差別部落
織田信長のあとをうけた豊臣秀吉による全国統一事業は,各戦国大名の実績を吸収しながら検地・刀狩りを中心として急速にすすめられ,のちの徳川家康による江戸幕府の成立を容易にした。この豊臣政権の全国統一から江戸初期にかけて,各種各様の被差別民は各地で統合・再編の対象として浮かび上がり,被差別部落と部落差別とが幕藩体制のもとで確立していくうえでの基本的な路線が設定されはじめた。その出発点が,太閤検地であった。
太閤検地が被差別民にもたらした最大の意義は,すでに彼らが実現していた土地保有の現状が公認され,貢租徴収のための土地台帳である検地帳に〈かわた〉という肩書とともに記名されたことであった。いいかえれば,〈かわた〉という呼称を政権が公的に採用したわけである。この〈かわた〉の呼称が,雑多な賤民的身分・職能の者を集約的にあらわすのに格好の呼称の一つとして豊臣政権に認識されていたことは,検地の際に,それまでは中世以来の被差別民である〈キヨメ(清目)〉〈散所〉として記帳されていた者たちが新たに〈かわた〉という肩書に改められて,その名を検地帳に記載された実例のあることからも推察される。豊臣政権による〈かわた〉身分の創出ということが説かれるゆえんである。そして,この〈かわた〉という身分呼称は江戸時代に受け継がれ,呼称は異にしていても〈えた〉と等しい扱いをされた(以下の説明では,〈えた〉の語で統一する)。
〈えた〉と〈非人〉
江戸時代における賤民身分の構成は,まず〈えた〉が中核部分として上位におかれ,その下位に〈非人〉が位置づけられて,この両者が賤民身分の根幹をなし,さらにその周辺部に種々雑多な生業の被差別民多数が配されるという形であった。〈えた〉身分と〈非人〉身分とについてみると,法的に根本的な取扱いの格差があった。〈えた〉だと,一代に限らず末代にいたるまで〈えた〉とされたし,〈非人〉だと,〈えた〉より下位であるにもかかわらず〈足洗い〉といって,きわめて厳重な条件付きではあったが一般民の身分に転ずる道が用意されていた。その条件とは,〈非人〉身分で3代を経た者,もしくは10年以上〈非人小屋〉で暮らした者は除外するということであった。このような法的措置は,江戸時代においてはむろんのこと,ごく近代にいたるまで被差別部落相互の間の連帯を阻害しがちの要素として機能しつづけたし,こんにちも,克服さるべき課題として,かすかながらではあろうが一部の被差別部落住民の意識の底に潜在しているとみられる。そういう意味でも,この二つの身分の法的措置は,まことに心にくいまでの絶妙な賤民統治策であったといわねばならない。また,賤民身分の構成上,その周辺部をなした種々雑多な被差別民たちは,〈乞胸(ごうむね)〉〈夙(しゆく)〉〈茶筅(ちやせん)〉〈鉢屋(はちや)〉〈ささら〉〈説経(せつきよう)〉〈猿飼(さるかい)〉〈青屋(あおや)〉等々数十種類に及んだが,一般的に卑賤視されたことはまちがいなくても,法的な処遇については必ずしも一定せず,錯綜(さくそう)しており,現実には複雑な様相を呈している場合が多かった。たとえば,〈乞胸〉だと江戸に限って存在し,〈町人〉身分でありながら,物もらい,大道芸などを生業とすることで乞胸頭を通じて非人頭の支配下に編入されたが,その業界を離脱すると〈町人〉にもどるのであった。なお,ついでながら〈えた〉身分については,地方によっては独自の呼称が適用されていたし,それらは現代においても被差別部落,ならびに被差別部落出身者に対する蔑称として用いられている。
17世紀の後半以降,しだいに被差別部落に対する政治的・社会的処遇の苛酷さがきわだってきた。たとえば,幕府による寛文・延宝年間(1661-81)の〈総検地〉実施の際に〈かわた百姓〉の検地帳への登録のしかたが変更され,〈かわた百姓〉の分だけをまとめて一般百姓の分の帳面とは別仕立てにする〈別帳扱い〉が行われるようになった。また地方によっては,被差別部落をまるごと別の土地へ移転させることも強行されるようになった。一般民との分離策である。ちなみに,自然災害,日照,水利等々に関して立地条件の劣悪な被差別部落が少なくない現状には,江戸時代における強制移住策が大きく働いているともいわれるほどである。一般民との分離ということでは,神社の氏子組織からの排除,祭礼・行事における明確な差別,入会権の剝奪も当然のごとく各地で行われだしたし,風俗面での規制も強化されて,たとえば〈非人〉は斬髪(元結を結わないで髪を散らす髪風)に限るなどとされた。こうした賤民層に対するさまざまな措置は,むろんのこと長い年月の間に,徐々に,かつ執拗に積み重ねられたものであるが,そうしたことが集中的に表面化していた時期は,幕府・藩による政治の矛盾や社会情勢の変動が目だっていた時期と,しばしば重なりあっていた点が重要である。
この時代における被差別部落の人口は,限られた範囲でしか判明していない(幕末の段階では〈えた〉は28万余,〈非人〉は2万3000余で,その他が8万余という)。しかし,被差別部落の人口の問題で注目されているのは,史料に恵まれた摂津,和泉の被差別部落に関する18~19世紀にわたる百数十年間の実例からみると,一般民の場合はだいたいにおいて元禄・享保(1688-1736)ころに頂点に達したあとは伸びなかったのに,被差別部落の場合には増加の一途をたどった事実である。この要因については,社会増の考え方が排されて,出産による自然増によることが明らかにされており,それは,被差別部落では信仰心の深さにより〈間引き〉が極力避けられたためであろうと推測されている。被差別部落に対する差別が,近世初頭とは比較にならぬほどに深刻化していったこの段階での人口増加は,集落地の拡張が周囲の人々からの忌避によって至難であったためにおのずと住居の密集化をもたらしがちであったろうし,また,当然に生活苦を導いたことであろうが,多くの被差別部落の住民は幾種類もの零細な雑業を兼ね合わせて生計の維持に努めるとともに,住民どうしの扶助関係を強めていたものと考えられている。相互扶助精神の強いことは,被差別部落の人々にきわだつ特質の一つなのである。
信仰と伝承
被差別部落の信仰という点では,真宗(浄土真宗)ならびに白山信仰との密接な関係があげられる。中世の末期から近世の初頭にかけての一向一揆においては,各地で少なからぬ被差別民がこれに深く関与していた。事例はあまり多くはなく,また地域も限られてはいるが,近畿で一向一揆の拠点になった集落であることが明確なところが,現代の被差別部落に重なっている事実も,近年の研究で明らかになっている。一向一揆は真宗本願寺教団と世俗権力との長期にわたる武力闘争であったが,真宗と被差別民との深い関係はすでに長い歴史をもっており,その要因としては,宗祖親鸞以来の真宗の教義が〈屠沽(とこ)の下類〉(《歎異抄》)としての被差別民の立場や願望に合致していたことがあげられる。また真宗の教義にふれて,すすんで転宗した他宗寺院も中世末~近世初頭には少なからずあり,さらには江戸時代半ばからの,諸宗寺院に対する幕府の宗教政策によって,真宗以外の宗旨の被差別部落の寺院が強制的に真宗に改宗させられるようになったこともあって,被差別部落の宗旨としては真宗がもっとも多く,その伝流は現代にも脈々と保たれているのである。
一方,白山信仰は,加賀白山の信仰にかかわるものであるが,被差別部落と白山信仰との関係は,とくに東日本各地において深く,少なからぬ数の被差別部落が氏神として〈白山神〉をまつりつづけてきている。その理由については未解明の点が多く,今後の研究にまつところが多大であるが,近年の民俗学的研究では,関東,中部地方の被差別部落に伝わる《三国長吏由来》(いわゆる〈河原巻物〉の一種)に見える〈長吏〉(葬儀に従事した被差別民)とその役割・機能・宇宙観に注目して,〈白山神〉が,概して加賀白山とのつながりを強調されている場合は〈ハクサン〉といい,色彩の白に関する伝承がまつわっている際には〈シラヤマ〉と呼び慣らわされている事情のもつ意味や,この神が悪疫を打ち払う力のある〈祟り神〉であるとともに〈血穢〉〈死穢〉をも厭(いと)わず来臨して〈生・死・再生〉にかかわる神ではないかということなどが総合的に考え合わされつつあるのは,内容のいっそう豊かな被差別部落史研究を築き上げるためにも重要なことと思われる。
幕末の動き
ところで19世紀に入ると,被差別部落に対する差別はさらに深まり,今日では信じがたいような差別が現出する。1798年(寛政10),伊予の大洲藩では,〈えた〉身分の7歳以上の男女は胸に方形の毛皮をつけること,また〈えた〉の家の門口には毛皮をかけること等々が布達された。1856年(安政3)備前岡山藩で起こった〈渋染(しぶぞめ)一揆〉は,藩による極端な〈えた〉身分の衣装制限に抗する五十数部落(被差別部落)の抵抗運動であり,数ヵ月にわたる苦闘の末に被差別部落側は,ようやくにして本望を遂げた。この闘いは,〈公権力〉との闘いたるにとどまらず,一般民衆の差別意識との闘いでもあった。また,19世紀に集中する被差別部落と一般民との訴訟沙汰の顚末(てんまつ)は,あらためていうまでもなく被差別部落の側の不利に終わっている。法廷である〈お白洲〉に引きすえられるときも,一般民が筵(むしろ)に座らされれば,被差別部落民は砂上に座を占めねばならなかったのである。1859年,江戸浅草の〈えた〉一人が山谷の神社の祭礼の日に殺された事件では,〈穢多頭(えたがしら)〉弾左衛門の強硬なる抗議にもかかわらず江戸北町奉行は,〈えた〉の生命は〈平人〉の7分の1でしかないとして,これを却下し,弾左衛門ですら〈ほこ〉を収めねばならなかった。〈えた〉7人に対して〈平人〉1人分という北町奉行の認識が,なにに発していたかは明瞭ではないが,この一件は,幕末期における一般民の被差別部落認識にいっそう重大な影響を及ぼしたとみられる。そのような〈差別の枠組み〉が〈公権力〉と一般民衆とを結ぶ形で確立した体制のなかで,あえて異議の申立てをなし,実力をもって抗争することは,一死を覚悟してかかることであった。しかし,圧倒的に不利な条件のなかで,それを試みた被差別部落民たちが,まちがいなくいたのである。1843年(天保14)の〈武州(武蔵国)鼻緒騒動〉の発起人の一人であった被差別部落民は,〈一度死ねば二度とは死なず,一命捨つる時は本望なり〉と称して重追放の処分に服した。
こうした一連の事態には,政治・社会に対する被差別部落民の対応のしかたに積極的な姿勢が現れてきていたことがうかがえるが,それについては,いちはやく1837年(天保8)の大塩平八郎の乱に際して被差別部落民が参加していたことや,66年(慶応2),維新前夜の第2次長州征伐における被差別部落民の活躍が重視されている。そして明治維新を迎え,71年(明治4)8月28日,ついに維新政府によって,〈穢多非人等ノ称被廃候条,自今身分職業共平民同様タルヘキ事〉という太政官布告(いわゆる〈身分解放令〉)が出されたのである。
近・現代の被差別部落
〈身分解放令〉は,江戸幕藩制下での苛酷な差別にあえいできたすべての被差別部落住民,とりわけて〈えた〉〈非人〉と呼ばれた人々にとって,なににも代えがたい朗報であり,これ以後における部落差別反対論に,重大な法的根拠を付与することとなった。
しかしながら,政府の施策としては,この解放令にともなうべき具体策,すなわち被差別部落住民の生活権の保障にかかわる諸施策がまったくなかったために,急速な近代化の傾向のなかで被差別部落の貧困化を助長し,そのことがまた部落差別をいっそう深刻なものとしていった。〈一般民〉は,〈えた〉〈非人〉が〈平民同様〉の身分に引き上げられたことを喜ばず,逆に,〈一般民〉が〈えた〉〈非人〉と同じ地位へと格下げされたのと同然であると解し,露骨ないやがらせはいうまでもなく,とくに西日本各地では〈えた〉〈非人〉の解放に反対する激しい実力行動(解放令反対一揆)を起こして被差別部落を襲撃し,集団的危害を加えた。伝統的な身分意識によることではあったが,当時の国内状況においては,近代化のための諸政策が民衆の生活にもたらしていた矛盾への不満のはけぐちに被差別部落が選ばれ,迫害の対象にされたのである。また,幕藩制下の部落産業のなかで中心的な位置を占めつづけてきていた皮革の生産・販売に関する特権も維新によって失われ,〈一般〉に開放されたため,弾左衛門らの懸命の尽力にもかかわらず,需要の急増に対応しうるだけの資本力を有した資本家の手にゆだねられていき,そのもとで被差別部落住民は生活の不安定な低賃金労働者としての道を歩むこととなった。資本主義社会の成立が,被差別部落の生活基盤をいっそう低劣なものとし,経済的条件にもとづく生活実態の酷さが,部落差別意識の温存を促しつづけた。部落解放運動は,このような江戸時代以来の差別的処遇の伝流のうえに資本主義化がもたらす諸矛盾が重なって深刻化していく部落差別に目覚め,その撤廃を自覚的に,自主的に推進していこうとする被差別部落住民自身によって,明治20年代の後半から30年代にかけて,しだいに表面化した。
初期の部落解放運動
初期の部落解放運動は,いわゆる〈部落改善運動〉として現れた。この運動の基本は,〈一般民〉からの差別の要因として被差別部落の生活実態の酷さ,風俗・教養面での立遅れを重視し,それらを自主的に〈改善〉すべく努力を積み重ねることで自立の基礎を固め,しかるのちに〈一般〉と被差別部落との〈融和〉を広く社会に訴えていこうとする点にあったといえる。その組織体は全国各地で編まれたが,和歌山県における〈進徳会〉(1893),大阪府における〈勤倹貯蓄会〉(1895),岡山県における〈備作平民会〉(1902)などの結成,活動がよく知られている。ことに,〈備作平民会〉は岡山県内の被差別部落を統合したもので,1県単位での運動組織の先駆をなしたものであるが,これについで1903年(明治36)に大阪で結成された〈大日本同胞融和会〉は,東京,愛知,三重,京都,大阪,奈良,和歌山,兵庫,岡山をはじめとして九州,四国地方からも参加者を得,ほぼ全国的規模での〈部落改善運動〉組織として誕生し,解放運動史上に一時期を画した。
このような〈部落改善運動〉の展開のなかでは,前述のごとく,問題解決の出発点を被差別部落住民自身の〈自粛〉と〈努力〉とにおき,そのうえで〈一般〉からの〈同情〉〈融和〉を獲得しようとする考え方が定着したのであるが,その一方では,被差別部落住民に対する差別的処遇について個別・具体的に抗議し,相手に是正を要求する気運もしだいに高まり,〈人間としての当然の権利〉の主張が積極的に試みられるようになった。このような傾向は,部落差別そのものを広く社会的視野のなかで客観的・科学的にとらえなおし,民主主義思想・社会主義思想の影響を受けながら真の解放への道を探り求めるという,新たな運動のあり方を切り開く端緒をなした。
〈部落改善〉の政策
政府は,1907年(明治40)における内務省の全国的な部落調査以来,被差別部落に対する行政的措置の必要性を認め,具体策を講ずるべく,12年(大正1)に内務省が〈細民部落改善協議会〉を開催,その翌年には内務大臣が地方官会議の席上で初めて被差別部落の問題について訓示を行い,さらに17年には内務省による〈全国細民部落調査〉が実施された。この間,第1次世界大戦による国際情勢の激変,世界各地における民族独立運動の勃興,ロシア革命による初の社会主義国の出現とその影響等々のなかで,〈部落改善運動〉の内部に社会運動としての性格が芽生えており,政府は,被差別部落の生活実態を放置しておくことが新たな〈社会不安〉の因となり,ひいては天皇制の国家体制そのものの存立基盤を根底から脅かしかねないことを深く憂慮された。その点がはっきりとしたのは,18年のシベリア出兵時に激発した〈米騒動〉と被差別部落との密接な関係による。〈米騒動〉の結果,起訴された民衆は8000余人にも及んだが,実にその1割強が被差別部落住民によって占められたことは,被差別部落の生活の窮状を明白に告げており,あらためて〈被差別部落対策〉の不可欠なことを政府・地方官庁関係者に強く認識させることとなった。そして,この〈米騒動〉後,行政機構の改正や,〈救済事業〉の推進を提唱する団体の出現が目だってきた。しかし,最もたいせつなのは,国としての具体的施策の実現であり,その要諦(ようてい)は,いわゆる〈部落改善〉のための予算編成である。政府は,ようやくにして20年の予算に〈地方改善費〉の名目で5万円を計上した。初めての被差別部落に対するこの国家的措置が実現したのが,明治新政府の〈身分解放令〉布告の年から数えて実に半世紀も後のことであったのは,記憶するに値しよう。
水平社の創立
第1次世界大戦前後のこのような情勢下,民間では〈融和運動〉が各地で推進されていた。それの趣旨は,政府・地方官庁等が被差別部落の〈自粛〉を促す〈慈恵〉的措置を基本とするのに不満を表明し,〈人道主義〉の立場を強調して,〈官民一致〉の体制による差別の解消を広く国民に訴えていくというものであった。この運動の組織団体としては,〈大和同志会〉(1912),〈帝国公道会〉(1914),〈同愛会〉(1921)等々があり,それぞれに国民の意識啓発の面で一定の役割を担ったが,その主たる担い手が被差別部落の有力者層,ならびに議員・財界人たちであったこともあって,部落差別の根を政治・社会の構造的矛盾のなかに見いだし,〈社会改革〉の展望において解放の道を求めるというような立場とは無縁であった。この点への批判は,官庁・警察・学校教師・僧侶・有力者らが主導する型の〈部落改善事業〉のあり方や本質への反発も含めて,被差別部落内の青年層のあいだでしだいに高まり,同情的な差別撤廃論を排して自発的な集団運動を積極的にすすめようとする勢いが強まり,ついに1922年3月3日,京都市の岡崎公会堂における〈全国水平社創立大会〉の開催をみるにいたったのである。女性,少年らも多数含む参加者数は約2000人と伝えられている。当日採択された宣言,〈水平社創立宣言〉は,〈全国に散在する我が特殊部落民よ団結せよ〉の文言で始まり,〈水平社は,かくして生れた。人の世に熱あれ,人間に光あれ〉で結ばれて,こんにちではその観念的な面が反省されながらも,部落差別に対して毅然たる態度で闘う意思を明確に表明した熱気あふれる記念碑的文章として,部落解放運動の精神的支柱をなしている。
全国水平社の発足は,その後における部落解放運動の全般にわたって深甚な影響を及ぼした。ことに,創立大会で採択された運動方針は,部落差別そのものの基本的理解について,差別する側にも,差別をこうむる側にも,ともにその人間としての尊厳を失わせるものであるとの認識に立ち,差別する側に対しては公開の場で〈糾弾(きゆうだん)〉を行って謝罪・反省を求め,それを通じて双方が人間としての尊厳を確認・回復しうるのだとした。また,〈部落改善事業〉の本質が,被差別部落の〈懐柔〉を目的とするところにあり,被差別部落内の有力者を中心とした支配体制を擁護する立場に立つ〈慈善救済〉的な事業は,かえって被差別部落の大衆の自立・自尊心をむしばみ,自主的な部落解放運動の育成を阻むものであるとして,これを痛烈に批判した。そして,この大会の報は全国各地の被差別部落に伝達され,差別者に対する〈直接糾弾〉を主眼として活動する水平社の地方組織が続々と編成されたのであった。
差別糾弾運動の展開
水平社による差別糾弾運動の展開は,日本近代社会における部落差別の実態を巨細両面にわたって明るみに引き出すとともに,封建社会以来の因習の根深さ,過酷さを,あらためて人々に認識させた。また同時に,水平社に参加した被差別部落の大衆の,〈人権〉回復をめざす組織的で果敢なる言動は,部落差別を当然のこととしてきた人々はむろんのこと,水平社の撤底した糾弾闘争方針を究極的には受け入れず,あくまでも談合・示談による個人的解決が穏当であるとした人々の激しい反発をまねき,随所において不幸なる対立・抗争を呼んだ。たとえば,1923年,奈良県で発生した〈水国(すいこく)事件〉(奈良県水平社と,右翼の国粋主義団体であった大日本国粋会との抗争事件)は,全面衝突はかろうじて避けられたものの,双方が刀剣,猟銃,竹槍などで集団武装して対峙した。この事件は,被差別部落の婚礼行列に対して〈一般民〉の老人が被差別部落を暗示する差別的な指のしぐさを示したのに発し,水平社側がこれを糾弾し,個人的な示談による解決をいっさい排して,あくまでも公的に謝罪することを要求した。しかし,これに反発した青年団,在郷軍人会,国粋会は結束し,他府県の被差別部落からも応援を求めた水平社側と対抗したものである。また,25年,群馬県で発生した〈世良田(せらだ)事件〉は同村民の差別発言の糾弾に端を発し,しかも,村民から被差別部落側に対して確約されたはずの〈差別謝罪演説会〉が一方的に取り消されたことから対立が激化して乱闘事件へと発展し,あげくには千数百人が計画的に被差別部落(戸数はわずか23戸)を襲撃,夜を徹して家屋の破壊,家財の焼却,傷害などの行為にでた。
また,大日本帝国軍隊内部における被差別部落出身兵士への差別待遇も,被差別部落出身兵士たち自身の,身命を賭した告発行動によって広く天下にさらけ出された。そこでの差別は,軍隊内業務・労働面における任務の課され方,個人に対する非公式の呼称,いやがらせ等々,枚挙にいとまがない状況であったが,外部とは隔絶した組織機構内でのこととて,容易には洩れず,被差別部落出身兵士たちはひたすら忍耐するほかはなかったのである。しかし,1926年(昭和1)の〈福岡連隊事件〉(九州水平社幹部で入隊した井元麟之(いもとりんし)らによる軍隊責任者の追及と,これに発する水平社への弾圧),翌27年の名古屋での陸軍特別大演習観兵式における〈天皇直訴(じきそ)事件〉(岐阜歩兵第68連隊兵士であった北原泰作(きたはらたいさく)が天皇に直接,差別の撤廃を訴願し,懲役1年の実刑)などは,〈天皇の軍隊〉がもつ差別的体質について国民の認識を促そうとした被差別部落出身兵士たちの果敢な行動として,部落解放運動史上,末永く記憶されるに違いない。
さて,糾弾闘争の展開と,それにともなう差別の顕然化のなかで,水平社運動は,さらなる重圧と試練に耐えねばならなかった。政府は,水平社運動の広まりや激化に注目せざるをえず,〈改善費〉予算の増額を水平社に申し入れたり,あるいは水平社と融和団体との合併案を提示したりしたが,水平社は創立以来の基本姿勢に立って,それを拒否したうえ,昭和初年から労働運動,農民運動との連携を深めていったので,政府はしだいに水平社運動弾圧の方向へと進み,あわせて〈中央融和事業協会〉を設立して,融和団体の育成・統合と,融和事業の拡充をはかった。これに対して水平社は,差別の根本を政治・社会・経済の諸制度の中に見いだす観点をいっそう深め,その変革が部落差別の撤廃にとっては最も基本的なことであるという主張を掲げるにいたった。
このような政府,水平社双方の動きの背景に,零細な生業,低賃金労働,不安定な生活にあえぐ被差別部落の大衆の苦悩があった。貧窮をきわめる被差別部落の生活実態をいかにして向上せしめるか。水平社は〈慈恵〉的処遇を拒否するとはいえ,現実の生活基盤の改善は被差別部落の大衆の等しく切望するところであった。ここに,融和団体が説く〈経済更生〉〈部落改善事業〉推進の道をとるか,それとも水平社が主眼とする政治的・社会的変革--革命の道を選ぶかが,現実の課題として迫っていたのである。水平社は,被差別部落大衆の生活向上への切実な願いを直視し,従来は一貫して排してきた〈改善費〉の位置づけ方を見直し,1933年の第11回大会で提唱した〈部落委員会の方針〉において,〈改善費〉を被差別部落への〈恩恵〉としてでなく基本的権利に属するものとみるべきだとして,〈改善費〉闘争の展開を説くとともに,それの拡充と,運用面での民主化を強く打ち出し,さらには,融和団体,青年団,農業組合などの既成の団体にも被差別部落大衆が加入して,その内部から民主化のための積極的行動を起こすようにと呼びかけるにいたったのである。
〈高松地方裁判所差別裁判事件〉
1933年(昭和8)6月の〈高松地方裁判所差別裁判事件〉に対する反対闘争は,この時期の部落解放運動にとっては,きわめて重要な意義を担った。事件の発端は,娘の愛人が被差別部落出身者であることを知った親が,相手方に対して離別を迫ったがいれられず,被差別部落の出身であることを黙して娘との同棲生活に入ったのは〈詐欺・誘拐〉にあたるとして告訴したのに発する。高松地方裁判所は,この訴えを認め,被告に実刑判決を下した。この判決は,〈身分解放令〉以来の国の基本理念を根本からくつがえす誤審判決であり,被差別部落出身者に対する差別を公権力が是としたものとして,当然のことながら全国各地の被差別部落大衆の憤激をかった。全国水平社,各融和団体は組織をあげて広範な反対闘争をくりひろげ,部落解放運動史上,戦前における最大の差別糾弾闘争とまで評価されるほど盛上りを示したのである。これに対しては,司法当局は関係裁判官,検事らの降格・更迭等を行い,判決の不当性を暗に認めた。
〈融和事業完成十ヵ年計画〉
1934年には,被差別部落に対する国民的関心が深まるなかで〈融和事業〉についての長期的展望が強く望まれるにいたり,中央融和事業協会は全国融和事業協議会に〈融和事業の綜合的進展に関する件〉を提出した。そこでの論議をふまえて,35年には36府県・38団体からなる全国融和事業協議会で〈綜合的進展に関する要綱〉〈融和事業完成十ヵ年計画〉が可決され,政府に対応を求めたのである。被差別部落の生活実態の改善に関する,初の長期計画であり,計画案が表面化した当初は全国水平社は批判的であったが,これに寄せられた被差別部落大衆の期待が切実かつ多大であったため,方針を再検討して,第13回大会においては〈部落改善費増額要求運動〉が提唱された。長期計画の内容は,経済更生施設の増加,日雇労働組合・協同組合の編成,部落産業の奨励,共同販売組織の編成,隣保館・託児所・診療所・共同浴場の増設,住宅・道路・上下水設備の改善,地区指導者の育成など経済・日常生活面でのさしせまった問題の解決策から,〈融和事業に関する教育的方策要綱〉に示された学校教育・社会教育での〈融和教育〉の実施までもが視野に収められており,画期的ともいうべきこの計画の実現のためには,総予算5000万円,初年度予算600万円が必要とされたのであったが,おりからの軍国主義化・戦争拡大・軍事費の膨張という事態のもとでは実現はむずかしくなり,国の予算編成に際しては大幅に削減され,初年度額はわずか150万円(従来どおりか,もしくはそれ以下)にきりつめられたため,目だった効果はみられなかった。
戦時体制下の被差別部落
1936年2月,全国水平社の松本治一郎(福岡市出身)が衆議院議員選挙で当選し,第69帝国議会において,被差別部落出身の代議士として堂々の論陣を張り,〈人民融和に関する質問〉〈華族制度改正に関する質問書〉を提起,明治以来の身分制度を厳しく批判するとともに,その後も一貫して被差別部落に対する差別にかかわる〈国家〉の責任の重大性を指摘しつづけた。しかし,37年7月,〈日中戦争〉の勃発と拡大は国内のファッショ化をいちだんと強化し,いわゆる〈挙国一致〉の戦時体制のもと,あらゆる革新政党・運動団体がそうであったように,水平社もまた苦渋を忍んで方針を転換せざるをえず,侵略戦争の遂行を基本とする〈国策〉をあえて容認し,戦争協力を声明しつつ,被差別部落大衆の生活維持に意を注がねばならなかった。また,中央融和事業協会を中心に統一されて活動してきた他の融和団体は,41年6月,政府によって新たに〈同和奉公会〉に組織替えされ,すでに1940年8月の第16回大会を最後の大会として,それ以降は目だった活動もみられなかった各地の水平社組織の活動家たちも,少なからずこれに参加していった。この改組は,〈融和運動〉を国の行政と一体化した形で拡大・浸透させ,前年の10月に結成されていた官製の国民統制組織たる〈大政翼賛会〉と並存させるのを目的としたもので,全国各地の支部の運営には市町村長・町内会長・学校長・各種団体長・僧侶・神官などが充てられ,行政主導型の組織活動が行われたのであるが,戦時下における関係予算の実質的減少という事態のなかでは,被差別部落大衆の物質的・精神的な支えとして,軽視できない意義を担ったのみならず,その経験の数々は戦後の部落解放運動・同和行政にも多大の教訓を残したとみてよいであろう。
このような時代の趨勢のなかで,1941年12月8日,日本は〈太平洋戦争〉に突入,その直後には,〈言論・出版・集会・結社等臨時取締法〉が施行され,水平社関係団体も取締りの対象とされたが,水平社は,政府からの求めをいれず解散声明を発しないまま,42年1月,自然消滅の形をとって創立以来20年の戦いの歴史に,いったん幕を下ろした。かくして,部落差別の撤廃をめざす運動の沈滞は覆いがたいものとなり,被差別部落大衆は,転業・休業・失業,移転,〈応召〉,さらには〈その(部落差別観念のある)社会を離れれば,その差別観念は個人の心から遠く離れてゆく〉のであり,〈満州(現,中国東北部)開拓地では現実に差別観念を発生せしむる特定の社会的根拠がない〉し,〈差別は解消する〉のだという,移民を促す〈国策〉の喧伝(けんでん)のもと,歴世の深刻な〈部落差別〉ゆえに,先祖代々住みなれた故郷を後にして,〈満州〉へと移住していった被差別部落民も多かったのである。その中には,45年8月15日,太平洋戦争終結の日の夜から中国人の襲撃を受け,2日後の17日夕刻には,男子が兵役に徴発されていたために大部分が老人,女性,子どもであった総員272人のうち271人が戦死または自決したという熊本県の被差別部落の移民団集落もあった。
部落解放運動の再建
敗戦による占領下,民主的諸改革が推進されるなかで部落解放運動の再建の気運も急速に高まり,戦前の全国水平社の〈部落委員会〉の伝統を受け継いで,〈全国水平社主催〉をうたう参加の呼びかけのもと,1946年2月19日,京都市の新聞会館に23府県から240人が参集して〈部落解放全国委員会〉(解放委員会)が結成され,翌日には〈部落解放人民大会〉が開催された。そのとき採択された〈宣言〉は,〈全国に散在する六千部落三百万の兄弟諸君! 日本帝国主義の敗戦により,凶悪野蛮なる軍国主義的・封建的専制支配は終焉(しゆうえん)を告げ,人民解放の輝かしい時代は来た。今日こそ部落民衆が完全に解放される絶好の機会である〉と呼びかけ,〈日本の歴史のあらゆる時代を通じて,常に最下層の地位に抑圧されて来たわれわれこそ,すべての抑圧された民衆を解放する先駆者でなければならない〉と鼓舞するとともに,〈蹶起(けつき)せよ,親愛なる兄弟諸君! われわれの叫ぶ合言葉は,軍国主義的・封建的反動勢力の徹底的打倒! 一切の民主主義勢力の結集による民主戦線の即時結成! 民主政権の樹立による部落民衆の完全なる解放! である。右,宣言す〉と結んでいた。当日は,京都市長が祝辞を述べ,日本共産党,自由党,進歩党,日本社会党の代表が挨拶をした。そして,大会では,〈財閥資本〉から〈部落産業〉をとりもどして〈全面的振興を期す〉ること,〈華族制度・貴族院・枢密院(すうみついん)その他一切の封建的特権制度を廃止して身分的差別の撤廃を期す〉ること,〈民主主義日本の建設を期す〉ることが決議された。この日,部落解放運動は,みごとによみがえったのである。
しかしながら,被差別部落に対する差別の撤廃は,全国的な民主化の風潮にもかかわらず,容易ではなかった。1947年,初の参議院議員選挙において全国区4位で当選し,参議院副議長に選出された松本治一郎は,慣例になっていた天皇に対する〈横向き歩行〉(カニの横ばい)形式の挨拶に際して,〈人間が人間を拝むようなことはできない〉との理由で断り,この形式による天皇への挨拶の消滅を導いた。その翌年,松本は〈戦争協力者〉の汚名をこうむり,公職を追放されたが,被差別部落大衆の激しい反対運動により,51年に公職追放は取り消された。おりしも,〈単独講和〉による日本独立の年であった。
〈行政闘争〉と〈同和対策事業特別措置法〉
同じく1951年に起こった京都市の〈オール・ロマンス事件〉は,戦後の部落解放運動の方向を基本的に規定するほどの重みをもつ事件であった。これは,京都市職員が《オール・ロマンス》という雑誌の同年10月号に載せた〈暴露小説・特殊部落〉が被差別部落に対する差別意識を露骨に示すものとして,部落解放委員会京都府連合会の活動家たちの注目を浴びたのに端を発した。そして,これに対する〈糾弾〉が,被差別部落の劣悪な生活実態を放置・温存させてきた〈京都市行政〉のあり方へと向けて,積極的に,かつ具体的に展開されることとなり,京都市当局は,衛生・民生・教育・土木等々の13部局の各管轄面で,部落解放委員会京都府連合会の指摘する行政上の欠点・難点のすべてを,覆いがたい現実として全面的に認めざるをえなかった。それほどまでに,被差別部落の生活実態はひどい状態におかれたままであったのである。この闘争の結果,京都市は,全国的な〈同和行政〉の推進に,いちはやく先鞭をつけることとなり,また部落解放運動は,被差別部落の生活環境の改善,仕事・就職の保障,教育条件の整備などを中心的課題としながら,〈日本国憲法〉が保障する〈基本的人権〉に深くかかわることとして,行政側の責任を根底から問いただす〈行政闘争〉を幅広く展開していくこととなった。なお,戦後初の〈地方改善事業〉予算が,わずかながら厚生省で計上されたのは,1953年のことであった。
1955年8月,部落解放全国委員会は,大阪市での第10回全国大会の決定により,〈部落解放同盟〉と改称,58年以降は部落差別の完全撤廃を国民的課題として提唱し,そのための〈国策の樹立〉を,たゆまずに国に要求していく方向へと向かった。60年の〈同和対策審議会〉の設置,65年の〈同和対策審議会答申〉,66年の〈同和対策協議会〉の設置等々の一連の事態をへて69年7月に公布・施行された〈同和対策事業特別措置法〉は,その発足前後において,かえって被差別部落大衆の〈自力更生〉の精神をむしばみはしないかとの危惧の念に立つ意見も部落解放同盟の内部に強くあったし,また結果的には時限立法(10ヵ年)であること,環境改善事業の実施を中心としていること,ならびに,国の責任の所在が明瞭でなく,国よりも地方自治体の財政上の負担がはるかに過重になったこと,同和対策の目標のいかんをめぐる深刻な意見対立などで,重大な課題を後に残しはしたものの,この法にもとづいて,被差別部落大衆の積年の切実な願望であった生活条件,教育条件等々の抜本的改善が漸次積み重ねられてきたことは明白であり,〈戦後〉部落解放運動の大きい成果であった。
生活環境の改善
たとえば,近畿地方のある県の被差別部落99地区に例をとってみると,39地区が湿地,20地区が傾斜地,14地区が河川周辺,4地区が谷間,3地区が海岸沿い,2地区が崖地,17地区が平地という立地条件は変わらないが,1969年段階の調査では〈生活環境〉を〈悪い〉とするのが42%,〈普通〉とするのが23%であったのに,8年後の77年の調査では,〈非常によい〉が25%,〈普通〉が21%で,〈悪い〉とするのは27%にまで減退していた。また,中国地方のある県でも,79年の被差別部落住民の意識調査で〈非常によくなった〉と〈かなりよくなった〉とが合わせて78%という結果が出ていた。
ついでながら,〈生活環境〉にかかわって〈住宅条件〉をみておくと,1960年の〈住宅地区改良法〉の制定後,75年までに,173地区,2万2227戸の〈改良住宅〉の建設をみていたが,これは大部分を占める小規模な被差別部落が基準の枠外におかれていたため,1970年〈小集落地区改良事業〉が実施され,75年までに260地区,6460戸の改良住宅が建設されたし,1961年以来,75年までに〈(同和対策)公営住宅建設事業〉によって〈同和向け公営住宅〉約3万4600戸が建設され,また1966年からは〈住宅改修資金〉,73年からは〈宅地取得資金〉,74年からは〈住宅新築資金〉など住宅・宅地に関する資金の低金利融資制度の実施をみたために,被差別部落によっては,その面目は文字どおり一新されたのである。
しかしながら,住宅条件をも含めた〈生活環境〉の改善については,被差別部落の所在地域の特性(都市部と農村部,大都市と中小都市)や,部落解放運動と同和行政の相互の伸展の度合などに大きく左右されることであるから,とうてい全国一律の状況とはいかず,事実,〈同和対策事業〉の対象からそれた被差別部落の場合にはとくに遅れてきた。また,1977年当時に〈生活環境は改善された〉と認識されていた各県の被差別部落においても,なお,道路・下水道・排水溝の整備,河川の修復,診療所・病院などの保健・衛生施設の新設・整備等々の要望が強く現れていたことは,それらが被差別部落の周辺の〈一般〉の場合においては基本的に解決ずみであったことを思いあわせると,被差別部落がいかに劣悪な〈生活環境〉におかれつづけてきていたかが容易にしのばれよう。
被差別部落の実生活の細部については不分明な点が少なくないが,一つの目安としては〈生活保護〉の受給率がある。1971年の政府調査結果によると,関係府県の平均受給率が1.20%なのに対して,〈同和関係〉の平均受給率は7.57%で,実に6.3倍にもなっており,4年後の75年の政府調査によっても,関係府県の平均受給率が1.15%なのに対して〈同和関係〉の平均受給率は7.60%で,6.6倍にのぼる。ちなみに,北陸地方のある市の一被差別部落の場合,同和地区指定をまだ受けていないが,その〈生活保護〉の受給率は,市全体の平均受給率の30倍を超える高率を示している。〈生活保護〉制度は,いうまでもなく日本国憲法の保障する国民の生活権にかかわるものであり,条件を満たしておれば当然これを受ける権利があるにもかかわらず,〈生活保護〉を受けることを〈世間体〉から恥じる気風が〈一般〉〈被差別部落〉のいかんを問わずまだ残存していて,現実には〈生活保護〉を必要としているにもかかわらず,それを受給していない世帯が少なくないものと推察される。
保健衛生条件の向上
被差別部落において,保健・衛生施設の新設・整備が強く要望されていたことはさきにもふれたが,このことは,被差別部落の多くが日照・通風・給水・排水などの要件に恵まれない立地条件にあること,限られた敷地内に多数の住居が密集せざるをえなかったこと,農村部落の場合はともかくとしても,都市部落の場合にはとくに各住居内の家族1人当りの起居空間があまりにも狭隘(きようあい)であったこと,家族の健康管理が行き届くだけの生活の〈ゆとり〉が容易に得られなかったこと等々,被差別部落がおかれていた社会的・地理的位置による。そのような事情が〈日常生活〉の積み重ねのなかで,〈人間〉の肉体と精神とにどれほど深刻な刻印を刻みこむかは,被差別部落よりも恵まれた生活条件のもとで生活しえたものには,これまた容易には理解しがたい面があるのである。
病気に例をとってみれば,伝染性結膜疾患の一種であるトラコーマ(トラホーム)は,かつては,非衛生的な地域環境に住居が密集し,しかも狭隘な起居空間に多数の家族員が同居を強いられていた大都市の被差別部落に患者を発生させやすく,そのうえ〈医療〉との疎遠な関係のもとでは慢性化する場合が多かったため,近畿地方のある大都市の一部では,その病状が被差別部落住民であることを暗示する〈身分のシンボル〉にさえなり,さらには,その病状を表現する特別の俗語までもがひそやかに流布されて,被差別部落に対する蔑称の一つにもなっていた。〈生活環境〉〈医療〉の立遅れが,被差別部落への差別を温存させたのみならず,それを増幅させた過酷な実例である。〈生活環境〉の改善,〈医療〉施設の充実により,そのような〈身分のシンボル〉としての病気は急速に減退したが,近畿地方における1977年の身体障害者調査の一例によれば,身体障害者のうち最高率(44.6%)を示す〈肢体不自由〉以外の障害では〈視覚障害〉がきわだった高率(34.4%)を示しているのも,やはりトラコーマの後遺症と判定されているのは,部落差別の歴史と現状とに深くかかわる問題として注目に値する。
次に注目しておくべきなのは,平均寿命の問題である。1965年の近畿地方の大都市の調査によると,当該都市の平均値に比して被差別部落の場合は平均寿命が約4年短いという結果がみられ,新生児・乳児の死亡率が高く,また,死産率を見ても〈自然死産率〉〈人口死産率〉ともに〈一般〉よりも高かったのが,その後における市当局の〈母子保健対策〉の推進により,約10年間に大幅に改善されたことが75年の調査で確認されている。それでもなお,当該都市の平均に比べると,やや高い数値を示している。ちなみに,1925-49年のデータによると,同市内のある被差別部落では,出生1000人当り190人もの乳児が死亡していたのであって,言語を絶する数字といわざるをえない。
教育条件の改善
次に〈教育〉に目を移してみると,被差別部落においては明治の学校教育制度の発足以来,一貫して長期欠席(長欠)・不就学の児童・生徒の問題を抱えてきていた。近畿地方のある県での1951年の調査によると,1ヵ月以上の長欠は,被差別部落の小学生の場合,県全体の児童総数に対する長欠者の比率が0.8%であるのに比して被差別部落の長欠者は7.7%で,実に9.6倍にもなり,また中学生の場合は6.3倍に達していた。その主たる理由は,家庭の貧困と,それにもとづく家計補助労働・家事従事,学校教育に対する軽視または不信などがあげられ,地域によっては〈少年非行〉が家庭と教育現場の双方に深刻な課題を提起しつづけたのである。部落解放運動は,当然のことながらこの問題にいちはやく注目していたが,とくに〈全国同和教育研究協議会(全同教)〉(1953結成)の全国的活動を基盤にすえながら,被差別部落の教育条件の改善を主要目標の一つに数え,58年の〈勤務評定反対闘争〉以来,長欠・不就学の児童・生徒に関する対策の樹立,学校給食費の免除,教科書・学用品の無料支給,教員定員の増加等々を強く要望して,〈義務教育無償化〉の運動に先鞭をつけた。こんにちの義務教育課程での教科書の無償配布も,被差別部落の児童・生徒たちを含む近畿・四国地方の各地の学校から実現されはじめたのが全体に及んだものであることは,記憶されてよい。さらには,教育・学力保障に関する被差別部落の親たちの権利意識が部落解放運動のなかでしだいに高揚し,〈同和対策事業〉の推進による生活水準の漸次上昇に基礎づけられて,長欠・不就学の問題は大幅に解消され,奨学金制度の普及にも支えられて高校進学率も高まり,各種学校・短期大学・4年制大学進学者数も,すでに昔日の比ではなくなった。そして,被差別部落出身青年の活躍分野は,公務員,教員をも含めて拡張されてきている。
また,これもたいせつな問題として,被差別部落の識字率のことがある。とくに中・高年者層の場合,幼少時における不就学の結果として〈文盲〉もしくはそれに近い状態のままで困難な生活に耐えてきた人々が少なからずあり,〈読み書きができるようになりたい〉という彼らの痛切な願いは,ごく普通の学校教育課程を踏んで育った〈一般〉側には,容易には信じがたいほどである。部落解放運動は,このことを〈部落差別によって,文字が被差別部落から奪われつづけたため〉と認識し,〈部落差別によって奪われた文字を奪いかえす運動〉として〈識字運動〉を各地で継続して,多数の学校教員の協力を得ながら〈識字学級〉を開設し,実績をあげてきている。目に一丁字とてないままに古稀をすぎた老婦人が,〈しきじがっきゅうでべんきょうして,かなはだいたい,おぼえました〉と自筆の文字で喜びを他者に伝え,〈夕やけを見てもあまりうつくしいと思は(わ)なかったけれど,じをおぼえて,ほんとうにうつくしいと思うようになりました。……これからもがんばって,もっともっとべんきょうをしたいです。十年ながいきをしたいと思います〉と告げた手紙文を見れば,誰しも,部落差別が被差別部落から奪いつづけてきたものの大きさに,あらためて眼を開かれるであろう。そして,役所・病院の窓口で,買物さきで,旅さきで,運転免許取得のための試験場でと,〈読み書きができるようになった〉喜びと自信が,彼らの生きがいを押しひろげてきているのであり,これもまた,わずかずつではあったが〈生活保障〉の実現に基礎づけられてのことである。
さらに,〈同和対策事業特別措置法〉の実施以前に発していたことではあるが,社会教育の面での〈同和問題の啓発〉に関する講座・講演会などの諸事業も,地方自治体に担われつつ,積極的に展開されるようになった。この動きは,行政管轄内に未組織の小規模被差別部落を相当数含んでいながら,公的にはその存在を否認しつづけてきた地方自治体においても,地元の被差別部落住民や,部落差別の実態に深い関心を寄せてきた〈一般〉の市民の熱意と要望にもとづき,〈人権意識の啓発〉という形で現れてきている。
さて,以上に大略みてきたところからも察せられるように,〈同和対策事業特別措置法〉の実施以後,被差別部落はいろいろな点で大きく〈変化〉していた。しかしながら,全国各地の,個々の被差別部落の実態にそくして,つぶさに点検を重ねれば,被差別部落全般の生活の安定化のためには10ヵ年の時限立法たる同法ではなお不十分であるとの判断に立って,その〈強化延長〉を要望する意見が時限(1979年3月31日)を前にして運動団体・政党・学識経験者・宗教団体など各方面から積極的に出されるにいたり,1978年11月,3ヵ年の延長(1982年3月31日まで)が決定された。かくて,通算13ヵ年にわたった〈同和対策事業特別措置法〉のもと,国,地方自治体あわせて約5兆3000億円の実質事業費(推定)が充てられ,同和地区指定を受け入れた被差別部落の環境・生活改善に大きく資するとともに,さまざまな角度から〈同和問題〉への国民の関心をひくのにあずかって力があった。
現状と諸問題
〈同和対策事業特別措置法〉の延長期限切れを前にして,部落解放同盟(略称,解同),全国部落解放運動連合会(略称,全解連。部落解放同盟を離れた日本共産党系の同盟員が中心となって1970年に部落解放同盟正常化全国連絡会議〈略称,正常化連〉を結成,76年に改称),全日本同和会(略称,同和会。融和主義にもとづいて部落差別の解決を目ざす保守系の解放運動組織)などの各団体からはむろんのこと自由民主党,日本社会党,日本共産党などの諸政党からも盛んな論議や提案がうまれた。これに加えて各地方自治体でも,国庫補助の法的措置が打ち切られることで,さらに財政上の負担が増大するとして政府に法律の強化・改正もしくは同法の再延長を強く要望した。78年の調べ(部落解放同盟,地方自治体)では,未指定地区を含めて約5兆7000億円もの〈残事業〉があるとみられていた。こうして,〈同和対策事業特別措置法〉にかわる新たな法の制定をめざす気運が醸成されて,期限切れ直前の82年3月31日,自民党案をもとにして内閣総理府がまとめた〈地域改善対策特別措置法〉が国会で成立した。この新法は,旧法の精神を受け継ぎながら,通算13ヵ年の期限内には果たしえなかった諸課題の解決を目ざすべく制定されたものである。ただし,これも5年後の87年3月31日を期限とする時限立法であり,残務処理的な性格のつよさがいちはやく指摘されていた。
すでに述べておいたように,部落解放運動の推進と,それを受けての同和対策事業の展開は,一般的には被差別部落の生活条件・生活実態を大きく変化させてきており,さまざまな角度からの新たな現状分析が必要とされる段階にきていることは,すでに各方面から指摘されているし,諸団体においてもその試みがなされつつある。しかし,新法のもと,部落解放運動・同和行政の当面する状況はきわめて複雑な様相を呈しており,それぞれに抱え込んだ諸課題は,深刻,かつ重大である。たとえば,部落解放運動においては,被差別部落における〈生活・意識の変化〉や被差別部落に対する〈部落差別の現在〉を,どのようなものとして把握するか,〈部落差別の完全撤廃〉のための部落解放運動の理論を,いかなる〈思想〉にもとづいて編成するかという基本問題をめぐって,大きく意見が分かれ,ことごとに対立してきている。また,同和行政を的確に実施する義務を地域住民全体に対して負う地方自治体においても,根本的には,国に比して過重な責任を担いつづけねばならない事情があったうえに,部落解放運動における深い亀裂を前にして,行政側として独自に保つべき基本姿勢を確立せぬままに,動揺を重ねる場合が少なくなかった。要は〈部落差別の完全撤廃〉にあることは火をみるより明らかであるが,それだけになおさらのこと,困難な課題がさしせまった形で山積し,錯綜した現代日本の政治・経済・社会・文化の構造のなかで,〈部落差別の完全撤廃〉という,国をあげての大目標にいたる道が模索されているのが現状である。したがって,これまでにもまして国民ひとりひとりが,立場のいかんをこえて,真剣かつ柔軟に〈部落問題〉に思いをいたし,率直に〈対話〉を重ねるべき時がきているといえよう。そのためにも,前項〈近・現代の被差別部落〉を受け継ぎながら,近年におこった重要な事項について,年次を追って概観しておくこととしよう。
狭山事件
まず,〈狭山事件〉のことがある。これは1963年5月,埼玉県狭山市で発生した女子高校生の誘拐殺人事件の容疑者として被差別部落の一青年(石川一雄)が逮捕され,取調べの結果,犯行を自白し,64年3月,浦和地方裁判所での第一審判決で死刑の宣告を受けたが,同年9月の第二審(控訴審,東京高等裁判所)法廷で犯行を否認したことに端を発する。その後,事件と部落差別との関係に重大な関心を寄せた部落解放同盟は,積極的に真相究明に取り組んだ結果,石川被告の無実が確信されるにいたり,69年3月,法務大臣に対して裁判の公正と被告の即時釈放とを申し入れるとともに,広く国民に,被告の完全無実,ならびに,警察当局の初動捜査のあり方に被差別部落に対する予断・偏見が強く働いていたことを訴え,〈同和対策事業特別措置法〉実現の要求とあわせて,〈狭山差別裁判反対闘争〉を運動の基軸にすえた。しかし,74年10月,第二審の判決公判では,すでに物的証拠も含めて反証が提示されていたにもかかわらず,有罪・無期懲役の判決が下された。部落解放同盟は,これを日本国憲法の保障する国民の基本的人権に深くかかわる重大問題として,ねばりづよい抗議運動を広範に展開,76年1月には最高裁判所に〈上告趣意書〉を提出,文字どおり全組織をあげて世論を喚起し,各方面の反響も甚大であったが,77年8月,最高裁判所は上告を棄却,刑が確定した。部落解放同盟は,ただちに再審を請求したが,これも80年2月に棄却された。その翌年,弁護団は新証人による証言にもとづいて〈再審請求意見書〉を提出した。
矢田事件
次には〈教育〉の場での問題があり,ここでは二つの著名な事件にしぼってみておこう。その一つは,1969年(〈同和対策事業特別措置法〉公布・施行の年)に大阪市で起こった,いわゆる〈矢田事件〉である。この事件の背景には,被差別部落を校区にもつ学校を避けて他校に入学する〈越境入学〉問題があった。すなわち,その前年5月の〈部落解放研究第2回全国集会〉で,奈良県内の中学校(公立)に進学するはずの12名の生徒が,〈部落のある学校に行くと勉強ができない……,乱暴される〉との理由で大阪市立の2校に入学している事実が明らかにされ,これを契機として部落解放同盟大阪府連合会が〈不正・部落差別の越境入学〉を許した責任を問うて大阪市教育委員会を糾弾,教育長はその非を認めた。大阪市教育委員会の調査結果によると,〈越境入学〉者は3万人を超えていたという。
このような状況を前に〈越境反対闘争〉が展開され,闘争を積極的に推進する部落解放同盟と,教師の当面する緊急課題ではないとする日本共産党との間に対立を生じ,この対立を背景にしながら〈矢田事件〉は発生したのである。直接の発端は,大阪市教職員組合の一支部の役員選挙に際して,関係者の一人が挨拶文の中で〈越境〉〈補習〉〈“同和”のこと〉等々に言及し,それらのために勤務時間外の仕事が教師に押しつけられ,下校が遅くなり,どうしてもやりたい仕事ができないのではないかと呼びかけていたのが,部落解放同盟矢田支部により部落差別を助長する文書として抗議され,糾弾が開始されたことにあった。この事件の舞台となった被差別部落の中学校の場合は,30%以上が他校区に〈越境入学〉していたという。部落解放同盟による糾弾の結果,当該文書の撤回,関係者全員の自己批判が確約されたが,約束は守られず,糾弾に関して〈暴力行為〉〈監禁〉等があったとの理由で,地区の部落解放同盟矢田支部長ら2名が告訴されるという事態へと急転し,法廷で争われることとなった。その結果,1975年6月,大阪地方裁判所の第一審判決では無罪となったが,原告側は大阪高等裁判所に控訴,この控訴審では有罪(懲役3ヵ月・執行猶予1年)の判決が出され,刑が確定した。被告・弁護団は上告したが,最高裁判所は82年3月にこれを棄却した。なお,この事件は,部落解放同盟と対立する〈正常化連〉(前述)が結成されるにいたった主要因の一つに数えられている。
八鹿高校事件
次は,1974年11月に兵庫県養父郡八鹿(ようか)町(現,養父市)で起こった〈八鹿高校事件〉であり,部落解放同盟側と日本共産党側との対立がいっそう顕然化するなかで発生した事件である。事件発生当初より,日本共産党は機関紙《赤旗》その他を通じて〈法治国に許せぬ大暴力事件〉〈大集団リンチ事件〉として報道を開始し,以後もその観点を一貫して大規模な組織的宣伝活動をくりひろげ,これには部落解放同盟も,事件にいたるまでの相手側の〈挑発〉的言動への批判を中心にしつつ当然反論を加えつづけた。この事件は,当時の兵庫県下における教育事情を背景にしており,当時の八鹿高校(県立)における普通科と職業科とに対する教育的配慮の問題性の深さ,同県南但地方での部落解放運動の複雑かつ緊迫した情勢とも密接にからみあいつつ,ついに11月22日,同校教師集団と〈八鹿高校糾弾共闘会議〉の関係者たちとが現地で実力で衝突し,教師側に重傷を含む多数の負傷者を出すにいたったものである。事件後,〈共闘会議〉議長ら14名が告訴され(うち1名は公判中に死去),83年12月14日,神戸地方裁判所(第一審)で全員有罪(最高は懲役3年,執行猶予4年)の判決が下された。部落差別への〈糾弾〉は是としつつも,行き過ぎた集団の〈暴力〉の行使は非とする,ただし,事件にいたる一連の経過には,被告の側にも酌量すべき情状の余地があるとしたものである。つづいて,被告側の控訴により大阪高等裁判所にもちこまれた。発生当時より,政界をも含めて,部落問題の現状や部落解放運動のあり方に深く心を寄せてきた人々の耳目を集めるとともに,基本的な事実関係についてはほとんど知らされることのなかった〈一般〉国民に〈被差別部落の人間は恐ろしい〉〈同和問題はやっかいだから,さわらぬほうが無難〉という意識をいやましにさせた事件でもあっただけに,真の部落差別撤廃への道を探り当てていくためにも,今後のなりゆきが注目されるところである。
身元調査と宗教における差別問題
さて,被差別部落に対する差別の持続に大きく働くのが〈本籍地〉〈居住地〉の問題である。一方では,部落差別が年ごとに〈解消〉へとおもむきつつあることが力説され,国民の〈人権意識〉の向上と,それにともなう部落問題への正当な認識は,確かに昔年の比ではなくなったともいえようが,反面においては,被差別部落出身者をとりまく現実にはなお厳しいものがある。そして,部落差別撤廃のための不断の努力を怠るならば,たとえ表面的には部落差別が解消しつつあるかにみえても,すぐさまそれは〈不死鳥〉のようによみがえるのであり,ときに表層に噴出する部落差別の根底には,目に見えない部落差別意識があたかも〈地下水脈〉のように着実に世代間に伝習され,いかに差別の不当性が叫ばれようとも,かえって秘めやかに再生産されつづけることを軽視してはならない。そのことを痛切に知らせたのは,公共機関における〈壬申戸籍(じんしんこせき)〉の取扱いの問題と,被差別部落の所在地を列挙した《特殊部落地名総鑑》の販売・購入問題であった。
〈壬申戸籍〉は,〈解放令〉の翌年,1872年(明治5,壬申の年)に初めて編まれた近代的な戸籍であり,日本近代史研究史料として貴重なものではあるが,現在の戸籍簿・除籍簿などから遡及(そきゆう)して〈壬申戸籍〉にいたれば,その当時の被差別部落出身者の系統を引く者であるか否かが容易に判明するために,とくに〈縁談〉を中心とした身元調べの格好の資料として,興信所などの民間企業や個人が所定の手数料を納入して閲覧・利用する例が多大であった。部落解放同盟の抗議を受けた法務省は,1968年1月,これの閲覧禁止を通達した。以後,戸籍の閲覧について慎重な手続上の配慮がなされるようになったし,就職にかかわる履歴・調査書の〈本籍地〉の記載を都道府県名のみとしたり,家族に関することは氏名・性別・年齢のみとするなどの簡潔な記載方式を採用した〈統一社用紙〉が,〈人権擁護〉の観点から普及したりしたのである。なお,75年4月には,最高裁判所が興信所による身元調査は違憲であるとの判例を示した。
被差別部落の所在地に関して5600ヵ所もの地名を記載した《部落地名総鑑》がひそかに販売され,大手企業・銀行その他がこれを購入している事実が露顕したのは,1975年春以来のことである。類似の図書は数種販売されており,部落解放同盟大阪府連合会は,76年2月,法務省に対して,購入企業数・購入企業名の公表を要請した。購入企業数は200社を超えているが,なかには応募者のうちの被差別部落出身者をチェックする目的で購入したことを明言した企業もあり,そうは明言せずとも,この種の図書が就職差別のために利用された可能性はあるとみなくてはならない。この件が社会的に広く反響を呼ぶなかで,企業の責任者に反省が求められるにいたり,各地に〈同和問題企業連絡会議〉が発足するとともに,企業内での研修も漸次進められるようになった。
もうひとつ重視すべきことに〈差別戒名〉(〈戒名〉の項参照)のことがある。仏教界と部落差別の問題はすでに長い歴史をもち,仏教者自身がこの問題に真剣にたちむかうことが強く要望されつづけてきたにもかかわらず,被差別部落を檀信徒として包摂することの多い浄土真宗以外の宗派では,いたって関心が薄かった。1979年8月,アメリカでの〈第3回世界宗教者平和会議〉の席上,曹洞宗宗務総長(当時)が被差別部落の存在を否定する発言をしたことが,部落解放同盟の糾弾を通じて宗教界に反省をもたらすきっかけとなり,81年には〈同和問題にとりくむ宗教教団連帯会議〉が結成された。この一連の動きのなかで,仏教界の部落差別をあらためて照らしだす鏡として〈差別戒名〉のことが大きくクローズ・アップされるにいたり,長野県をはじめとして各地で続々と発見された墓石の刻銘や過去帳の記載例は数十種に及び,そのいずれもが被差別部落民であることをはっきりと示すものであって,知る人を驚かしたが,その戒名一つ一つは,江戸時代を通じて連綿と,〈あの世〉へ旅立っていった被差別部落の人々に僧侶が授けつづけてきたものであり,仏教者の良心をいたく刺したのである。現在までの発見例は,曹洞宗,真言宗,浄土真宗に及んでおり,従来,檀信徒に関する身元調査に寺院の住職がかかわる場合が少なくはなかったこともあわせて深刻な反省をもたらすと同時に,部落差別をとおして,仏教の立脚点,現代的意義があらためて問い直されつつあるのは喜ばしい。
以上に,被差別部落の歴史と現状を概観してきた。大きくみれば,ゆっくりとしたあしどりではあっても国民の認識はしだいに開かれてきているといえようが,解決へといたる道程はまだ長く,かつ険しいであろう。そして被差別部落の存在そのものが,被差別部落と〈一般〉の双方に対して,人間としての証(あかし)を求めつづけるのであって,その点においてこそ,被差別部落が歴史と現在をとりむすびつつ,ひたすらに担いつづけてきたあまりもの重荷が,初めて燦然(さんぜん)たる光を放つ。〈人の世に熱あれ,人間に光あれ〉。
執筆者:横井 清
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「被差別部落」の意味・わかりやすい解説
被差別部落【ひさべつぶらく】
→関連項目河原巻物|狭山事件|識字運動|同和教育|部落解放同盟
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「被差別部落」の意味・わかりやすい解説
被差別部落
ひさべつぶらく
おもに近世における賤民(せんみん)的身分に起因して差別を受けている人々が居住する地域をさす。近代以後の政策による移転や流入等によって必ずしも近世の賤民居住地域と一致するわけでない。
1871年(明治4)、明治政府は「解放令」を「一君万民」と開化政策の一貫として発布したため、被差別部落の人々にとって「開化」は差別からの解放を意味し、彼らは「一君万民」思想にも取り込まれながら、教育や生活改善を通じて「開化」実現をめざすが、部落外の人々は「旧習」に則り、差別・排除を行おうとする。1880年代になると部落の経済的窮乏が進行し、コレラの流行などとも相まって、被差別部落に対して不潔・病気・異種といった徴表が付与されていく。さらに明治民法制定にともなう「家」意識の浸透は、「異種」と見なされる被差別部落の人々を自らの「血筋」や「家」から排除する方向に作用した。
日露戦後に全国的に展開された部落改善政策は、被差別部落を個人の恣意(しい)では変わりえない人種を異にした存在であるとする認識を民衆レベルに浸透させ、内務省や府県当局が使用した「特殊(種)部落」という呼称が、それまでの「新平民」に替わって定着する。しかし被差別部落側からの不満も噴出し、内務省や民間融和団体帝国公道会は融和政策に転じていく。
1918年(大正7)の米騒動と1922年の全国水平社結成は社会に部落問題の重要性を再認識させ、水平社による差別問題の告発を受けて1925年中央融和事業協会が設立されて本格的な政策が展開される。またデモクラシーの潮流のなかで普遍的平等思想が社会的に認知されたことも大きな意味をもった。しかしそれは部落差別解消には直結せず、1930年代以後戦時体制が進行するなかで、社会の側の差別意識を内包したまま、部落問題は「国民一体」というたてまえのなかに解消されていった。
戦後は、基本的人権の尊重を謳った日本国憲法のもとで部落解放運動が再開され、1965年(昭和40)の同和対策審議会答申は、部落問題を「国の責務」として認めるに至る。それを受けて同和対策事業が実施され、部落内外の住環境や経済面の格差はかなり解消したが、ねたみ差別意識や「エセ同和」など新たな問題も生じた。また、2002年には特別措置法も廃止されたが、今なお存在する差別を等身大にとらえつつ、いかにそれに向き合うかという模索が続けられている。
[黒川みどり]
『黒川みどり・藤野豊編著『近現代部落史』(2009・有志舎)』▽『黒川みどり著『近代部落史――明治から現代まで』(2001・平凡社)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被差別部落」の意味・わかりやすい解説
被差別部落
ひさべつぶらく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の被差別部落の言及
【えた】より
…1871年(明治4)8月28日,明治新政府は〈太政官布告〉を発して,〈非人(ひにん)〉の呼称とともにこの呼称も廃止した。しかし,被差別部落への根強い偏見,きびしい差別は残存しつづけたために,現代にいたるもなお被差別部落の出身者に対する蔑称として脈々たる生命を保ち,差別の温存・助長に重要な役割をになっている。漢字では〈穢多〉と表記されるが,これは江戸幕府・諸藩が公式に適用したために普及したものである。…
※「被差別部落」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...