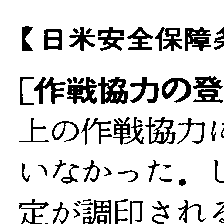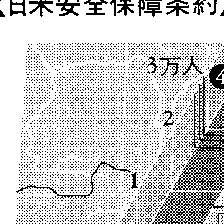目次 旧条約の締結と内容 条約改定へ 新条約の特徴と問題点 安保反対運動 日米軍事協力の進展 安保体制の歴史的意義 アメリカと日本の軍事的関係を規定した条約。1951年9月8日サンフランシスコのアメリカ陸軍第6軍司令部で調印され,52年4月28日発効した。60年1月19日,改定条約が調印され,6月23日批准書が交換され,同日発効した。英文名は前者がSecurity Treaty between Japan and the United States of America,後者がTreaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of Americaである。前者にはアメリカ軍配備の条件を定める〈日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定〉(日米行政協定 ,1952年4月28日発効)および吉田=アチソン交換公文が付属し,後者には〈日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定〉(日米地位協定 ,1960年6月23日発効),および二つの交換公文,すなわち(1)条約第6条の実施に関する交換公文,(2)吉田=アチソン交換公文等に関する交換公文(岸信介首相とC.A. ハーター国務長官との間で作成・交換された)が付属している。
旧条約の締結と内容 1950年4月にアメリカ国務長官の政策顧問となったJ.F.ダレスは就任当初から日本の安全保障政策として占領軍の段階的撤退と日本再軍備の意図をもち,51年初の来日時に日本政府に再軍備を勧説した。これに対し占領軍司令官マッカーサーに支持された吉田茂首相らは大規模な再軍備を不適当と主張し,アメリカ軍の駐留を求めた。朝鮮戦争 (1950-53)の経験からアメリカ側は日本側の要望をいれることが得策であるとし,2月6日の事務レベル会談における提案で,平和条約に日本が個別的・集団的自衛権をもち,集団的安全保障取極(とりきめ)を締結できることを規定し,これをもとに,日米間にアメリカ軍の駐兵によって日本の安全保障に協力する主旨の簡潔な取極(協定,条約など)を結び,在日アメリカ軍 の地位,特権などは行政協定に譲るという方式を示した。7月30日に提示されたアメリカ案でいわゆる〈極東条項〉が追加され,日本に駐留するアメリカ軍を〈極東における国際の平和と安全の維持〉および〈外部からの武力攻撃に対する日本の安全に寄与するために〉使用することができるとされ,事務的折衝を経て8月18日に日米間の意見が妥結,20日に案文(英文)が作成された。日本文は8月24日に作成され,8月25日〈日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約〉として最終案文が確定された。調印式は9月8日,サンフランシスコ講和条約が調印された当日の午後5時,吉田茂,D.アチソン,ダレス,A.ワイリー,S.ブリッジス によって調印された(発効は1952年4月28日)。この条約は,署名前の演説でアチソン・アメリカ国務長官が〈太平洋地域の平和と安全の防衛体制の一部を成す〉と述べたように,米・比,米・台,米・韓の相互防衛条約 ・協力関係やアメリカ,オーストラリア,ニュージーランド間の太平洋安全保障条約(ANZUS(アンザス)条約 )と密接に結びついたアメリカ太平洋戦略の一環に位置づけられた。
条約は前文と5ヵ条からなり,前文ではこの条約が講和条約の認める集団安全保障取極を締結する権利に基礎をおいたものであることを記し,日本側が,武装を解除された状態での暫定措置として,日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内およびその付近にアメリカが軍隊を維持することを希望し,アメリカ側は自国軍を維持する意思があることを示し,かつ日本が〈自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待〉するとされている。1条は,日本が日本国内とその付近にアメリカ軍を配備する権利をアメリカに与えること,その軍隊を〈極東における国際の平和と安全に寄与し〉,外国の〈教唆又は干渉によってひき起された大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて,外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる〉としている。これは,日本がアメリカ軍に基地貸与を認めたこと,かつそのアメリカ軍が日本以外の極東地域における戦争・武力紛争に出動しうること,および日本国内の内乱や騒じょうに介入しうることを認めたことを意味する。2条ではアメリカの事前の同意なしに,第三国に基地,駐兵,演習,軍隊の通過の権利を許与しないことを規定し,アメリカ軍配備の具体的条件はすべて行政協定にゆだねることにした(3条)。しかしこの条約ではアメリカは日本防衛の義務を明記せず,また日本も条文上は軍備増強等の義務は負わなかった。
安保条約の締結に対しては多くの反対論,反対勢力があらわれた。憲法擁護・全面講和・非武装中立の運動を進めていた社会党,共産党,総評,進歩的知識人などは,この条約がアメリカ占領軍を平和条約発効後も引き続き駐留させる役割を果たし,そのアメリカ軍に基地を提供してアジアでの戦争を助け,日本がアメリカに従って冷戦に荷担する意味をもつ等の理由で反対し,日教組は〈教え子を再び戦場に送るな〉とのスローガン を掲げた。同条約が占領の継続という印象を与えたことは保守勢力の間にも反対論を生み,日本の政治的自主性が回復されないことへの不満とともに他方で日本が本格的に再軍備すべきであるという主張もあらわれ,この結果,1951年10月26日の衆議院における批准投票では賛成289票に対し反対71,欠席106を数えた。
条約改定へ 1953年以来ダレスは国務長官に就任し,同条約の運用を指揮した。アメリカ側は日本の軍備増強を進めるためMSA援助を日本に提供することを明らかにし,その具体化のため53年10月,池田=ロバートソン会談が開かれ,翌54年3月日米相互防衛援助協定(MSA協定 )が結ばれた。これに助けられて同年7月自衛隊法が施行され,保安隊は陸・海・空の3軍で構成される自衛隊へと変容し,14万6000人の兵員を擁するにいたった。しかしダレスらは30万~36万人への増強を求め,55年8月重光葵(まもる)外相が訪米時に安保条約の改定を提案した際も,現状では西太平洋の防衛に共同責任をもつことは不可能であるとして拒否した。この時期,アメリカ政府内にアジアにおける民族解放戦争 の発展や社会主義勢力の伸張をおさえるため経済成長政策の推進を求める勢力が強まり,日本の経済的役割が重視されるようになって,軍備の急増を伴わなくても安保条約の改定に応ずるべきであるとする動きが強まった。57年,岸信介内閣 が安保条約検討のため委員会設置についてアメリカと合意し,58年夏から事務的折衝に入り60年1月19日,新条約の調印が行われた。佐々木 隆爾
新条約の特徴と問題点 新条約の発効により旧条約は失効した(9条)。新条約は前文と10ヵ条からなるが,旧条約と異なり,経済協力の促進(2条)を規定するため,名称に〈相互協力〉を冠する。旧条約は本質的には基地貸与条約であって,日本は日本とその付近へのアメリカ軍の配備を認め,この軍隊は,(1)極東における国際の平和と安全の維持のため,および,(2)外部からの武力攻撃に対し日本の安全に寄与するために(日本政府の明示の要請がある場合は,外部の干渉による大規模な内乱・騒じょうの鎮圧を含む),〈使用することができる〉と規定したが,アメリカの日本防衛義務を明記しなかった。これは,アメリカが相互防衛条約を締結する際の基本原則である,上院のバンデンバーグ決議 Vandenberg Resolution(1948)の〈自助と相互援助〉の条件を,当時の日本が備えていないと判断されたからであった。したがって旧条約は,日本の防衛力漸増へのアメリカの〈期待〉を記す前文とともに,終期を定めることなく〈暫定措置〉とすること(4条,前文)によって,将来日本がそのような条件を満たししだい,本格的な相互防衛条約によってとってかわられるべきことを予定していた。
1960年の新条約締結は,一方では50年代における日本の軍事力増強と経済発展,および政府による憲法9条解釈の転換(〈戦争の放棄 〉の項参照)とによって,日本が〈自助と相互援助〉の条件を基本的には満たすようになったと判断されたこと,他方ではアメリカの世界戦略が同盟国の軍事力をより重視する方向で再編されたことによって実現したと考えられる。なお,基地闘争に見られるような,旧条約の不平等性への国民の批判や,1959年から60年にかけて高揚した安保闘争が,新条約に与えた複雑な影響も忘れてはならない。こうして60年の日米安全保障条約は,不完全ながら〈自助と相互援助〉に基づく相互防衛条約=軍事同盟条約となった。この観点から同条約の特徴を示す。
第1に,この条約は,〈憲法上の規定に従うことを条件として〉ではあるが,自助と相互援助によって軍事力を増強することを,日米両国の条約上の義務とする(3条)とともに,この義務の履行を随時協議の対象とした(4条)。4条の協議は,日本の安全または極東における国際の平和と安全への脅威が生じたときにも行われるが,これを通じて,削除された旧条約の内乱条項が事実上再現する可能性も指摘されている。
第2に,最も重要な点として,日米両国は5条により,〈日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃〉への,共同防衛を約束した。これは,個別的自衛権および集団的自衛権について定めた国連憲章51条に基づくものであり,共同防衛の対象たる武力攻撃が領域的限定を受けたのは,憲法9条を考慮してであると説明された。すなわち政府によれば,日本は憲法上集団的自衛権をもたないが,在日アメリカ軍への攻撃は同時に日本の領域への攻撃であるから,共同防衛は日本にとっては個別的自衛権の発動として合憲であるとされる(〈自衛隊 〉の項を参照)。しかし,在日アメリカ軍への攻撃は,たとえば,日本の領海上の第7艦隊への攻撃のように,日本にとっては領海・領空侵犯のみで武力攻撃とならず,個別的自衛権発動の要件を満たさない場合もあり,この場合の共同防衛は集団的自衛権によらねば説明できないとの批判もある。
第3に,この条約は,アメリカが極東の平和と安全の維持のために在日基地を使用できるとする〈極東条項〉を,旧条約から引き継いだ(6条)。この〈極東〉は,その防衛のためにアメリカが在日基地を使用しうる区域であって,〈大体においてフィリピン以北〉および日本とその周辺であるが,アメリカ軍の出動範囲はこれに局限されない,と説明された。この〈極東条項〉が日本を無関係な戦争に巻き込みかねないことへの国民の危惧を鎮めるためにおかれたのが,6条の実施に関する交換公文の〈事前協議prior consultation〉である。ここにおいて,(1)アメリカ軍の日本への配置の重要な変更,(2)その装備の重要な変更(たとえば核の持込み),および,(3)戦闘作戦行動(5条の場合を除く)のための在日基地の使用は,日米の事前協議の対象とされた。しかし,〈協議〉は〈同意〉ではないこと,日本には発議権がないことなどのほか,(2)については疑わしい場合の立入検査権が日本になく,核の〈持込みintroduction〉と違って〈通過transit〉は除外されている疑いが濃いこと,(3)については補給や移動は含まないことといった事情のために,その実効性に疑問がもたれており,事実,条約発効以来この規定は一度も発動されたことがない。
この条約は,10年間効力を存続したのちは一方の締約国による終了通告があればその後1年で終了する(10条)とされているが,このような通告はなく改定も行われていない。しかし,その後の国際情勢と日米両政府による条約の位置づけの変化などによって,その具体的意義は変わってきた。1969年の日米共同声明と72年の沖縄返還とによって,極東の平和と日本の安全の不可分性が承認され,日本の局地防衛は自衛隊の責任とされるとともに在日アメリカ軍はアジアにおける抑止力と位置づけられるようになった。また,81年の日米共同声明以来,西側諸国の一員としての日本の地位と日米の同盟関係が強調され,安保条約はNATO(ナトー)とともに西側防衛の二本の柱の一つとされて,日米共同作戦計画が急速に具体化された。松井 芳郎
安保反対運動 安保条約に対しては,旧条約の下でもその実施に際しさまざまな反対運動が起こった。代表的なのは基地反対闘争 で,1953年に本格化する内灘試射場 事件をはじめ,浅間山基地化を阻止した運動(1953)や妙義山接収計画を撤回させた運動(1955年を頂点とする),北富士演習場使用問題(1955年以降),砂川基地問題(1955年以降)などが注目された(〈軍事基地 〉の項参照)。とくに59年3月,東京地裁は,砂川事件 (1957)に対し,アメリカ駐留軍は憲法9条違反であり,したがってアメリカ軍をとくに厚く保護する刑事特別法 は違憲・無効とし,被告に無罪の判決を下し,高まりつつあった安保条約改定反対運動に影響を与えた。さらに1954年3月のビキニ環礁での水爆実験でマグロ漁船第五福竜丸が被爆した事件を契機に,原水爆禁止運動 が飛躍的な発展をとげ,55年,原水爆禁止日本協議会が結成され,毎年日本で原水爆禁止世界大会を開くようになり,在日アメリカ軍の配置・装備の変化,とりわけ核兵器配備と核戦争の可能性についての論議が強められた。
当時,ダレス国務長官が〈大量報復戦略〉を推進し,自衛隊の発足と強化がそれと関連していたことから,安保条約が日本を核戦争に巻き込む可能性が強いとか,自衛隊の海外派兵や内乱鎮圧の可能性が増す等の議論が,国民の戦争体験と結びついて広く受け入れられ,有力な世論となった。また岸内閣が57年〈国防の基本方針〉を国防会議で決定し,それに基づき〈第1次防衛力整備計画〉を翌58年から実施に移し,同58年10月,突如〈警察官職務執行法 改正案〉を国会に上程したことは,これらが軍備増強と基本的人権の抑圧に象徴される戦前の政治体制への復帰を意味するという印象を国民に与え,軍国主義の復活あるいは民主主義の危機ととらえられた。さらに日中・日ソ貿易に厳しい制限を要求するアメリカの対日経済政策への反発も財界を含め広くみられたのであった。
これらの諸要因は,岸内閣の安保条約改定交渉の開始を契機にいわゆる安保闘争が発展する基礎をなした。1959年3月,総評,社会党をはじめ諸社会団体によって日米安保条約 改定阻止国民会議が結成され,4月15日の第1次統一行動を皮切りに60年10月の第23次統一行動まで持続的に国民運動を組織・指導する役割を果たし,全国で2000余にのぼる地域共闘組織に支えられてデモや国会請願運動を展開した。60年5月19日,安保条約案の批准が自民党の単独採決で強行されると,安保条約賛成者までが議会制民主主義擁護のために国会請願に加わり,運動は空前の規模に達し,労働者の政治ストも行われた。この安保闘争は,新安保条約の批准阻止には成功しなかったが(6月19日に自然承認),事前協議条項を挿入させ,またその運用を慎重にさせる役割を果たし,かつアイゼンハワー大統領の訪日を中止させ,岸内閣を辞職に追い込んだ。
日米軍事協力の進展 新条約の運用は,日本首相とアメリカ大統領間の日米首脳会談 をはじめ両国政府要人間の会談,日米安全保障協議委員会(1960年以降。日本側は外務大臣,防衛庁長官 ら,アメリカ側は駐日大使,太平洋軍司令官ら),日米安全保障事務レベル協議(1967年以降。両国の防衛・外交当局の次官レベルで構成),日米安保運用協議会(1973年以降。日本側は外務省北米局長,防衛庁防衛局長,統幕議長ら,アメリカ側は駐日大使,在日アメリカ軍司令官ら)等を通じてなされ,また2条の運用をはかるために日米経済貿易合同委員会,日米文化教育委員会,日米科学合同委員会が設けられた(1961)。この間駐日アメリカ軍の兵力数は旧安保条約が発効した1952年の26万人から新安保条約発効時には4万5000人,71年には2万7000人にまで減少したが,72年の沖縄返還で沖縄駐留兵力が加わり6万5000人に増加,79年には空軍2万1600人を中心とする4万5000人となった。在日アメリカ軍施設・区域の件数は1952年4月の2824件,59年年度末の243件,67年年度末には145件となったが,72年年度末には172件,85年初には125件となった。その面積は1952年1353km2 ,59年に336km2 ,72年に549km2 ,85年に837km2 となった。とくにそのうち地位協定第2条4項bによる施設(自衛隊の施設をアメリカ軍が一時使用するもの。現在使用していないものが多い)の件数,面積が,1982年ごろから急増し,85年初で22件,511km2 となった。
ベトナム戦争後,アメリカは世界戦略の中に日米安保体制をより重く位置づけるようになり,湾岸戦争(1991)で在日米軍の行動の敏速性と攻撃精度が最大であったという歴史的経験を経て,95年,アジア全域を対象とする地域紛争戦略へと転換してこの中軸に日米安保体制をすえる方針を公表した。ここで東アジアの前進配備米軍の兵力を当分約10万とし,このうち在日米軍を軍艦乗組員を含めて約6万とすることとなった。在日米軍基地 は1997年1月現在で米軍管理地が314km2 となっている。
新条約発効後の日本側の軍事力増強は,第2次防衛力整備計画(二次防)が1962-66年に,三次防が67-71年に,四次防が72-76年と進められ,以後〈防衛計画の大綱〉に従って実施されることになった。
1968年1月,佐藤栄作首相は核兵器を〈持たず,作らず,持ち込ませず〉の非核三原則 を確認するとともに,核の脅威に対しては安保条約に基づきアメリカの核抑止力に依存する態度を表明した。しかし日本政府は,アメリカ軍が核兵器を持ち込んでいないことを確認する独自の手段をとらず,国会内外でしばしば核持込みの疑惑が出され,さらに元駐日大使ライシャワーらはのちに持込みの事実を証言している。69年11月,佐藤首相は日米共同声明で沖縄の戦略的重要性を認め,かつ〈韓国の安全は日本自身の安全にとって緊要〉であり,台湾の安全も重要とし,安保条約をこれら諸地域と緊密に関連させて運用する意図を明らかにした。これをもとに佐藤内閣は沖縄返還交渉を開始し,71年返還協定に調印,72年5月発効し,沖縄県の施政権は日本に返還され,安保条約はここにも適用されるようになった。在日米軍基地はベトナム戦争(インドシナ戦争 )に際して大々的に利用され,とくに沖縄基地はB52戦略爆撃機の発進基地となり,また海兵隊の訓練基地として重要視され,本土基地は兵站(へいたん)・補給,訓練,休養・慰安など多様な役割を果たしたが,このことは安保条約運用の実態を国民に印象づけ,ベトナム反戦運動 の高まりとともに,安保条約反対の気運・運動が強まった。
1975年の南北ベトナム統一後,日米軍事協力は急速に具体化され,78年11月,日米安全保障協議委員会で〈日米防衛協力のための指針〉(いわゆるガイドライン )が了承され,国防会議,閣議でも了承された。同指針は日米共同作戦計画についての研究,作戦,情報および後方支援の実施要領の策定などを規定した。これとならんで防衛庁・自衛隊幹部による共同作戦計画,有事立法の研究・策定が推進されるようになった。アメリカ軍と自衛隊の共同訓練は55年以来海上自衛隊 とアメリカ海軍との間に対潜・掃海訓練を中心とし実施されてきたが,同時にアメリカ第3艦隊の実施するリムパック RIMPAC(Rim of the Pacificの略)にも80年以来海上自衛隊が参加するにいたった。航空自衛隊とアメリカ軍の共同訓練は1978年以来,陸上自衛隊の共同訓練も81年以来実施されてきた。
安保体制の歴史的意義 このように安保条約は,サンフランシスコ講和条約以後の日米関係の規定要因となり,その結果,国際社会における日本の位置や進路はアメリカの戦略的要請に沿うことを余儀なくされ続けた。近代日本の対外政策は,1902年の日英同盟のように当該時期の超大国との同盟または協力を主流としたが,安保条約を軸とする戦後政治はこの伝統を踏襲したものとなり,それは日英同盟の存続期間20年をはるかに超えて40余年に及び,超大国への依存の体質を決定的にした。
この体質は,ソ連の崩壊により米ソ冷戦が終わった1990年代にむしろ強化された。日本は在日米軍の経費負担を軽減するために巨額の〈おもいやり予算〉を支出し,米軍が地域紛争への即応をめざし訓練を強化することを認め,在日米軍が中近東にまでおよぶ広範囲にわたって作戦に出動するのを支援してきた。67年に宣言された〈非核三原則〉も,日本政府は入港する米艦船に適用する努力を行ってこなかった。南太平洋非核地帯条約 ・東南アジア非核地帯条約 などの締結によってアジア・太平洋諸国は明らかに核軍備の忌避と廃棄に向かっているが,今や日米安保体制はこの潮流に逆行する要因として機能している。
日本に対する諸外国の評価もこの点と関連している。朝鮮戦争,ベトナム戦争においては日本は出撃,訓練,兵站・補給,休養・慰安などの基地としての役割を果たし,交戦の相手国から協力・荷担を非難されたし,第1次防衛力整備計画以後の軍事力増強政策は〈軍国主義の復活〉と非難された。1950年代末以来の高度経済成長政策が進展すると,アジアの諸親米政権との間に交貿・開発援助が増加し,これら政権との関係は緊密化したが,その反面これら諸国民衆の中には〈経済的侵略〉〈軍事独裁政権の補強〉等と非難するものが少なくない。中国は72年日中国交回復が,米・中の関係改善の一環として実現すると,ソ連との対抗上安保条約や日本の軍備増強に対する非難をやめ,支持の態度に転換した。この事実は,安保条約に対する評価がその国とアメリカとの関係の変化によって容易に変わるものであることを示している(コラム参照)。佐々木 隆爾