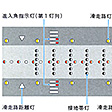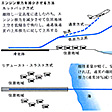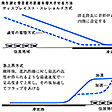翻訳|airport
精選版 日本国語大辞典 「空港」の意味・読み・例文・類語
くう‐こう‥カウ【空港】
- 〘 名詞 〙 航空輸送のため公共の用に供する場所。エアポート。〔現代語大辞典(1932)〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「空港」の意味・わかりやすい解説
空港
くうこう
airport
民間の航空輸送のために公共に開放されている飛行場。日本では空港整備法第2条で「空港とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場」と定義している。航空機の離着陸という飛行場としての機能のほかに、旅客の乗降や乗り継ぎとその手続、手荷物・郵便物の取扱い、航空機の整備・燃料補給、発着の誘導のための交通管制などの施設や、旅客・空港勤務者のための交通機関・サービス施設などが必要である。現代の空港は、旅客輸送および貨物流通面で、国内のみならず国際的な規模の輸送の拠点となっており、海上輸送における港と並んで、その国の経済・政治・文化の門戸といえる。
[落合一夫]
空港の分類と設置条件
分類
日本では空港整備法により、以下の3種類に分けられている。
〔1〕第1種空港 国際航空路線に必要な飛行場。東京、大阪の両国際空港、千葉県の成田国際空港、大阪湾泉州沖の関西国際空港および伊勢湾常滑(とこなめ)沖の中部国際空港の五つがある。原則として国(すなわち国土交通大臣)が設置して管理を行うが、特例として成田国際空港は成田国際空港株式会社(2004年3月までは新東京国際空港公団)が、関西国際空港は関西国際空港株式会社が、また中部国際空港は中部国際空港株式会社が、それぞれ設置と管理にあたっている。
〔2〕第2種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場。原則として設置や管理は国土交通大臣が行うが、適切と認めた地方公共団体に設置と管理をゆだねることができる。仙台、名古屋、福岡など24(2006年3月現在)の空港がある。
〔3〕第3種空港 地方的な航空輸送を確保するために必要な飛行場。政令で定める関係地方公共団体の協議によって決められた地方公共団体が設置と管理にあたる。富山、鳥取、奄美(あまみ)など53(2006年3月現在)の空港がこれに該当する。
空港の規模、つまり広さや滑走路の長さなどは、前記の分類には直接関係はないが、第1種空港には当然大型機が多数発着するので、事実上、第1種、第2種、第3種の順に小さくなっていく。別に、国際民間航空機関(ICAO(イカオ))が、滑走路についてAからIまでの基準を定めており、空港の規模は滑走路の数とこの基準で判断することができる。空港の設置・管理の方式は国によって多少異なるが、日本はおおむねアメリカの方式に倣っている。
[落合一夫]
設置条件
航空輸送の必要が新たに生じたり、輸送量の増大に現用空港が応じられなくなったり、設備が旧式化して新しい技術や機種に適合しなくなると、新空港の設置が必要になる。候補地の選定にあたっては、次の諸条件を満たすことが望ましい。(1)周囲、ことに滑走路の延長上に、障害となる地形や建造物がないこと。(2)霧・雨・雪・突風および台風などの気候上の障害が少なく、風向も年間を通じてほぼ一定していること。(3)気温および標高が低く、航空機の浮力が得やすいこと。(4)近接する主要都市との交通が便利であること。(5)既存の空港・飛行場や航空路に対し、離陸・上昇・待機・進入・着陸の各段階での飛行経路や空域に十分な余裕があること。(6)人口密集地帯に対して、騒音・大気汚染などの影響を最小限度にとどめられること。(7)広大な用地の入手が容易であること。
しかし、この条件には互いに相反するものもあり、すべてを満足させることは困難である。たとえば利用者にとって大都市と空港の距離が近いこと、つまり交通の利便性は不可欠である。しかし、このことは必然的に大都市周辺の住民にとっては、公害や事故等の問題発生の可能性をも高くしている。
日本を代表する成田および大阪の両国際空港は、騒音問題により午後10時または11時以降の発着が行えない。関西国際空港は、用地取得のむずかしさから大阪湾泉州沖を埋立てて造成され、数々の難工事のすえ完成したが、その結果24時間の運用が可能となった。同じく海上空港の中部国際空港も24時間の発着が可能。また、東京国際空港(羽田)も沖合い展開工事の進行に伴い、1997年(平成9)より24時間運用を可能としている。このように、いずれの空港も、輸送量の増大、旅客サービスの質の向上、公害規制の強化などの現実のなかで、航空機性能や航法機器の進歩などを駆使して理想の空港を目ざして努力を続けている。
1960年代に入り航空旅客輸送量は増大し、毎年2桁(けた)の伸びを続けたが、1973年(昭和48)に発生した石油ショックによって一時鈍化した。しかし、1980年代経済活動の回復に伴って輸送量は増加し始め、空港の新設・拡張はふたたび活発となった。日本の周辺では、シンガポール、香港(ホンコン)、上海浦東(シャンハイプートン)、ソウル仁川(インチョン)、広州新白雲(パイユン)など発着制限がなく施設の完備された新空港が、1990年代から2000年代に相次いで開港した。設置時期が早かった東京の優位性は次第に低下しつつある。
[落合一夫]
空港の設備
旅客および貨物を、安全・正確・快適、そして能率的に輸送するのが空港の機能である。そのなかでもっとも優先するのが安全、つまり飛行場としての機能である。飛行場として必要な設備は、運航関係と整備関係に分けられる。
[落合一夫]
運航関係
着陸帯(滑走路、誘導路)、駐機場(エプロン、スポット)、交通管制、離着陸誘導、標識(照明)、気象通報、通信、給油、救難などの施設がこれである。
[落合一夫]
着陸帯
航空機が離着陸や滑走を行うための区域である。航空機が直接離着陸を行うのは滑走路であるが、横風や降雨など天候の悪いとき、夜間や霧など視界が十分でないとき、計器飛行による着陸などの場合に、航空機が滑走路の中心から流されたり滑ったりして事故につながるのを防ぐため、滑走路の両側と前後端に十分な余裕をもたせてある。このうち、着陸方向の滑走路の延長方向部分をオーバーラン・エリアoverrun areaという。すなわち着陸帯とは滑走路とこうした安全余裕を含めたものの総称である。着陸帯はICAOの等級に従って航空法および同施行規則に規定されている。計器着陸帯(ICAO等級のAからG)は滑走路に対し300メートル以上、また有視界飛行着陸帯(H、I)は150メートル以上の幅が必要である。実際の着陸帯には滑走路、安全余裕のほかに誘導路が付属していることが多い。
〔1〕滑走路runway 長さ・幅・勾配(こうばい)などで、ランク分けされている。国際空港、国内の主要空港では、大型機が発着するので、ICAOのA級、できればそれ以上の余裕があることが望ましい。しかし、ジェット旅客機の設計基準にある離着陸性能の決定基準から、いまのところ1万5000フィート(約4500メートル)以上の長さはまず必要でない。滑走路は長さのほか航空機の最大重量と着陸時の衝撃に耐えうる強度が要求される。
航空機が大型・高速化すると長大な滑走路が必要となり、巨額の建設費と広大な用地を要するため、以前のような何本もの横風用滑走路を設置することはなくなり、もっとも頻度の高い横風に限定して設ける傾向になっている。そして、飛行場の効率をあげるため、離着陸を並行して行えるよう一つの方向に2本以上の滑走路を並列に配置するようにしている。たとえば、世界最大の1万3700ヘクタールの広さをもつアメリカのデンバー国際空港は、2000年現在は3600メートルの滑走路を5本もつが、2010年の完成時には、主滑走路8本と横風用4本をそれぞれ平行に配置し、悪天候でも3機を同時に離着陸させることができる。同空港の滑走路は3500~4500メートルの長さをもち、2005年に出現が予想される700~800人乗りの超大型旅客機の運航に備えている。
滑走路の表面は、離陸に対しては加速性をよくするため車輪の転がり抵抗が小さい、滑らかな面がよく、また着陸時や離陸断念時の減速・停止には逆に大きな摩擦係数が必要という相反するむずかしい条件が課せられている。また雨などで路面に水がたまっているときは摩擦係数の低下が著しいので、滑走路の全体または末端部分には、溝切り(Grooving)を施し、水はけをよくして摩擦係数の低下を防いでいる。
〔2〕誘導路taxiway 滑走路と駐機場を連絡する航空機の通路で、離着陸する航空機が円滑に流れ、滑走路が効率よく使用できるように計画される。そのため着陸後の航空機を迅速に退避させたり、誘導路から加速しながら離陸・滑走に移れるよう、滑走路との接続部の角度や広さには十分な配慮が必要とされる。かつては、700~800人乗りの超大型ジャンボ機やSST(超音速旅客)機、あるいはSTOL(エストール)(短距離離着陸)機などの運航も考慮して空港の機能を計算していたが、航空会社間の競争が激しく、経費の節減が進められていることから、経済性の低いSST機やSTOL機の運航は2000年現在考えられておらず、逆にそこそこの性能の向上によって経済性の高い双発機が多用されるようになった。その結果、空港の規模は滑走路の長さよりも数の増設に振り向けられており、同時に多数の飛行機の離着陸ができるような傾向にある。しかし近い将来(2006年以降)、700~800人乗りの超大型ジャンボ機やエアバスA-380機の就航に備え、4500メートル級の滑走路と旅客扱い機能の向上は必要となる。
[落合一夫]
駐機場(エプロンapron)
空港ターミナルに接して設けられるのが理想的である。航空機に対する燃料・潤滑油の補給、水・食料そのほか旅客サービス用品の積み込み、旅客の乗降、貨物・手荷物・郵便物の積み下ろし、簡単な整備・点検・修理や清掃が行われる。エプロンの中の、指定された1機ずつの駐機場所をスポットspotという。
エプロンには十分な広さが必要である。すなわち、航空機の大型化で1機当りの所要スペースは広くなり、便数の増加に対応して多くの航空機を収容しなければならない。さらに地上走行中の航空機は小回りがきかず自力で後退することもむずかしいので、十分な余裕を設けないと、エプロン上や誘導路への出入の際に航空機同士の接触・衝突事故を起こす危険もある。また、エプロン上は各種のサービス車両が走行するので、これらによる事故も考えられる。万一事故が発生すれば、大きな被害につながるおそれがあるため、エプロンは、1機当りの広さ、スポットの間隔、空港ターミナルや他の航空機に与えるジェット後流の影響、進入・駐機の方式、旅客の搭乗方法などを慎重に考慮して設定されなければならない。
航空機はスポットにいる間、燃料や貨物・郵便物・各種の旅客サービス用品を搭載し、手荷物をもって旅客が搭乗するので、もっとも重い状態になる。したがって、スポットにはそれに耐え得る静的な強度が必要である。また、エンジンの排気や燃料その他の油類で表面が侵されたり汚れたりするのであること、補修・清掃が容易であること、水はけについても考慮されなければらない。
[落合一夫]
航行援助装置・着陸誘導施設
夜間、霧・雨などで視界が悪い場合や多少の悪天候下でも、航空機を安全に運航、離着陸させるためには、最新の電子工学を駆使した機器やさまざまの施設が必要である。空港にはその中枢として管制塔がある。管制圏内の航空機の管制、離着陸の許可など、すべての指示は管制塔から行われる。
着陸誘導施設としては、GCA(地上誘導着陸装置)、ILS(計器着陸装置)、PAPI(パピ)(精密進入経路指示灯。PAPIに移行する以前はVASIS(バシス)=進入角度指示灯が使用されていた)などがある。現代の空港はGCAにかわってILSが主流となっている。さらにマイクロ波を使って従来のVHF(超短波)より精度の高い誘導が行えるMLS(マイクロ波着陸装置)への移行を目ざしているが、主流となるには至っていない。また、空港内の地上の航空機や車両の動きを監視するASDE(Airport Surface Detecting System空港面探知装置)を備え、悪天候下の事故防止を図るところも増えてきた。
航行援助装置では、DME(距離測定装置)、VOR(超短波全方向式無線標識施設)、NDB(無指向性無線標識施設)などの設備がある。なお、今日では人工衛星や慣性誘導装置を利用して、地上の施設に頼らなくても自機の位置の確認が容易に行えるようになったため、新しい航行援助施設はつくられていない。
そのほか、空港の所在を示したり、離着陸・地上走行を援助する灯火(航空灯火)が、世界共通の規定に基づいて設置されている。
[落合一夫]
給油施設
ジェット機では機体の大きさに対して大量の燃料を搭載する。その燃料を補給するために、普通の空港では、大型のタンク車によって航空機に搭載するが、規模が大きくなると、燃料タンクは空港敷地内の空港主要部から離れた安全なところに設置し、エプロンやスポットの地下に埋設した補給用配管を通じて、高い圧力をかけ大量の燃料を短期間で搭載できるようにしている。大型機の発着する主要空港では、燃料の必要量が多いので、燃料タンクを石油コンビナートとパイプラインで直接結んでいるところも少なくない。また高圧空気や電力など動力源の取出し口をスポットに設けた空港も増えており、これらの使用により従来使用していた専用車両が不要になり、エプロンの混雑が緩和されるほか、地上装置の着脱に要する時間が節約でき、航空機に装備してあるAPU(機上補助動力装置)を運転しないですむことから、運航費を節減できる利点がある。
[落合一夫]
消火・救難施設
航空機は引火しやすい燃料を大量に搭載している。そして、スポットと燃料タンクはパイプで直結されている。したがって、たとえ小さな事故でも、たちまち大火災に広がるおそれがある。また離着陸時の事故は、貴重な人命や高価な機体の損失にとどまらず、空港周辺に大きな被害を及ぼす。そのため事故に対処する万全の消火・救難施設が必要である。化学消防車、クレーン車、レッカー車、救急車、排煙車、照明車などのほか、空港が海に接していれば、高速の救命艇、消防艇も必要となる。さらに救難・消火活動において回転翼の強い吹き下ろし気流で煙や火炎を吹き払い、活動を援助する専用のヘリコプターを配備するところもある。
[落合一夫]
整備関係
航空機の点検・修理・整備・洗浄などのための施設である。エンジンや各種装備品については、空港内に工場・倉庫が設けられていて、修理や部品交換を行う。
[落合一夫]
整備の種類
運航の合間に空港のスポット・整備場で行う点検・整備には、毎飛行ごとの外観点検、燃料補給、出発態勢の確認などを含む出発前点検、エンジン・オイル、作動油、酸素の補充、痛みやすい動翼(舵、フラップなど)、タイヤ、ブレーキ、エンジンをチェックするA整備、A整備に加えてとくにエンジン関係を詳細に点検するB整備がある。これらの点検・整備に必要な人員・車両・工具も空港に常備されている。運航を中止して行うC整備以上の整備には格納庫が使われる。
[落合一夫]
格納庫(ハンガーhanger)
航空機が木製布張り構造の時代には、天候の変化から機体を保護するために、地上での駐機には格納庫に収める必要があった。しかし、航空機が全金属製構造となってからは格納庫の必要がなくなり、さらに現在では機体が大型化して停留機数も増えたため、機材のすべてを収容する格納庫を設けることが不可能になった。したがって通常は悪天候や夜間などの短時間の停留、または作業量の多い長時間の整備・修理のための施設となっている。大型機の手入れには高所作業が多いので、高い足場や階段、電力や高圧空気の取出し口を多数設けたり、大型のジャッキなどが必要である。空港にはこのような設備(Dockドック)を備えた格納庫が、その規模に応じて設置されている。格納庫は、(1)大きさ、(2)エプロンや滑走路との相対位置と交通路、(3)エンジン・計器・各装備品の整備工場との関係、(4)建物によって気流が乱されたり、標識や他の航空機を確認する障害にならないこと、(5)着陸誘導施設や他の通信の電波を妨害しないこと、などを考慮に入れて、設置場所や高さ・広さ・形状が決められる。
[落合一夫]
旅客取扱い関係
旅客が空港に到着してから航空機に搭乗するまで、または航空機から降りて空港を離れるまでに必要な施設で、通過・乗り換え・乗り継ぎの旅客の待ち合わせ・休憩も考慮しなければならない。
〔1〕航空会社カウンター 航空券の予約・発売、搭乗手続、手荷物の受付など。
〔2〕旅客搭乗施設 待合室、ロビー、運航状況の表示・アナウンス装置、接続地上交通機関への誘導設備など。
〔3〕旅客乗降施設 ボーディング・ブリッジ(搭乗用被覆通路)、タラップ(搭乗階段)、ウォーキング・ベルト、エスカレーターなど。スポットが建物から離れている場合には連絡バスおよび発着場も準備される。
また、国際空港にはCIQ(出入国管理、税関、検疫)の施設が必要である。
空港には旅客以外にも多数の人々が集散する。送迎客・見学者などの外来者はもちろん、空港・航空会社・官公署・地上運輸関係の従業員などである。空港には、旅客やこれらの人々の需要に応ずる設備が必要である。
〔4〕サービス施設 レストラン、ホテル、売店、銀行、郵便局、公衆電話、医療機関、理髪店など。
〔5〕交通施設 鉄道、バス、タクシー、小型飛行機やヘリコプターなどの発着場、駐車・駐機場など。
[落合一夫]
空港ターミナル
これらの諸施設を総合的に収容する建物が空港ターミナルである。空港ターミナルは、管制塔と並ぶ空港の象徴であり、世界の主要空港においてはもちろん、ローカル空港に至るまで、それぞれの地域の特色を盛り込んだ最新の設備をもつビルディングが建設されている。ことに主要空港では、各国それぞれ独自の理論に基づいて理想の空港システムを目ざして建設されてはいるが、航空旅客や貨物の輸送量の増大と、航空機の大型・高速化、便数の増加と集中化のために、施設の拡張や改良が追い付けない状態である。空港の建設には長期間を要するため、空港やターミナルの計画には、完成後の技術水準や経済の発展を考慮した先見と周到な準備が必要で、よほど将来を見通した展望をもたないと、完成早々に旧式となるおそれすらある。
[落合一夫]
貨物・郵便物関係
貨物の受け入れから搭載まで、荷下ろしから空港を出るまでに必要な施設である。貨物カウンター、積み下ろし設備、フォークリフト、コンベヤー、集積・整理場、コンテナ関係施設、倉庫、保税上屋など。大規模な空港では、貨物の取扱量が膨大なため、旅客と貨物の両方をひとつの空港ターミナル内で処理せずに、別に貨物専用ターミナルを設けるのが普通である。
[落合一夫]
世界の空港
日本の空港
日本には、第1種5、第2種24、第3種53の空港と、アメリカ軍と共同で使用している三沢(みさわ)、自衛隊と共同使用の千歳(ちとせ)・徳島など5空港、そのほかに弟子屈(てしかが)、調布その他の八つの公共用飛行場などがある。
2006年(平成18)現在、日本の空港整備に関するプロジェクトとしては千葉県の成田国際空港および関西国際空港の第2期工事、東京国際空港(羽田空港)の沖合い展開の完成、中部国際空港の拡張計画などがある。
[落合一夫]
成田国際空港
1962年(昭和37)新東京国際空港として計画を開始し、1973年に第1期工事を完了、1978年に開港した。2004年(平成16)現名称に改称。当初の予定では第2期工事が完了すれば、敷地総面積1065ヘクタール、滑走路は4000メートル、2500メートルに、横風用の3200メートルの3本になるはずであった。いずれも幅60メートルで、2本の主滑走路は計器着陸のために十分な間隔を置いて平行に設置され、同時に離着陸を行うことができる。滑走路には2本ずつの一方通行式誘導路が設けられる。スポットは旅客用96、貨物用18、停留用118、試運転用6となり、エプロンの総面積は250ヘクタールとなる。
開港時から供用されている第1旅客ターミナルビルは12万平方メートル、貨物ターミナルビルは17万平方メートル。1992年(平成4)第2旅客ターミナルビル28万平方メートルが開設された。ILS、NDB、VOR、DMEを備え、ICAOの基準のカテゴリーⅢAを満たす。しかし、第1期工事が完了した状態(約550ヘクタール)で供用が続けられていた2000年の時点では、滑走路は4000メートル1本だけで、年間旅客数2571万人、貨物取扱い量は158万トンにとどまっていた。第2期工事の着工と、完成の見通しは不明であるが徐々に好転しつつある。2002年に日本と韓国で共同開催されたサッカーのワールドカップもあって、中・小型輸送機発着のため、供用中の4000メートル滑走路(A滑走路)と平行して一部完成したB滑走路を利用して2180メートルの暫定滑走路が2001年に完成、2002年から供用された。
[落合一夫]
関西国際空港
騒音問題と能力の限界に達した現大阪国際空港(伊丹(いたみ)空港)にかわって、大阪湾泉州沖約5キロメートルに設置された空港である。官民共同出資の関西国際空港株式会社が設置にあたり、最終的には4000メートル級主滑走路2本、3400メートル横風用滑走路1本、総面積1200ヘクタール、総工費1兆2000億円となる。1985年2月に発表された第一次構想では、東西1250メートル、南北4400メートル、面積500ヘクタールの変形五角形の人工島に、3300メートルの滑走路1本と空港施設を設け、総工費8200億円、年間離着陸10万回を予定していた。1983年、空港設置が地元で承認され、翌1984年、関西国際空港株式会社が設立されて本格的作業に入ったが、供用開始は計画より2年遅れの1994年(平成6)9月となった。本空港は世界で初の本格的海上空港で、24時間の運用が可能である。本空港の完成に伴い制約のきわめて多い大阪国際空港は撤去が原則とされていた。しかし、当初の取決めの拡大解釈によって存続が決定した。
[落合一夫]
東京国際空港の沖合い展開
騒音問題と限界に達した能力を拡大するため、東西の再旅客ターミナルの整備、2500メートルの新B滑走路、3000メートルの新A滑走路、同じく3000メートルの新C滑走路を設け、総面積を約1100ヘクタールとするものである。これにより年間離着陸回数を16万回から25.5万回に、取扱い乗客数を2700万人から8500万人に拡大する。1983年計画承認、1984年2月着工、第1期工事完了・新A滑走路供用開始が1988年7月、西旅客ターミナル(通称ビッグバード)の共用開始が1993年9月、新C滑走路供用開始が1997年9月、新B滑走路の供用開始が2000年3月で、2004年12月には東旅客ターミナル(第2旅客ターミナル)供用開始とともに西旅客ターミナル(第1ターミナル)のリニューアル工事が開始された。
[落合一夫]
中部国際空港
中部圏の国際ハブ空港hub airport(拠点となる空港)として、愛知県常滑(とこなめ)市沖約3キロメートルに人工島を造成し、2005年に開港した。国、地方自治体、民間の出資で、1998年に中部国際空港株式会社が設立、空港の建設と運営にあたっている。開港時は敷地470ヘクタール、3500メートル滑走路1本であるが、完成時には空港島を900ヘクタールに拡張し、4000メートル滑走路2本となる予定。名古屋空港の旧定期路線を引き継ぐ。なお、中部国際空港の開港に伴い、名古屋空港は県営名古屋空港として整備され、定期国内線、チャーター便、国際ビジネス便などが就航する。
[落合一夫]
アメリカの空港
公共用と私有を合計して1万に近い空港があり、大空港はほとんど地方公共団体か公団によって運営されている。
ニューヨーク地区には、ジョン・エフ・ケネディ(国際・国内線)、ラ・ガーディア(国内線)、ニューアーク(おもに国内線)の3空港があり、ニューヨーク港湾局が総合的に運営している。ジョン・エフ・ケネディ国際空港は敷地面積2052ヘクタール、4442メートル、3460メートル、3048メートル、2560メートルの4本の滑走路と、別にコミュータ機用の780メートルの滑走路をもつ。
西海岸最大のロサンゼルス国際空港は、敷地面積1386ヘクタール、3686メートル、3382メートル、3135メートル、2721メートルの4本の滑走路がある。年間離着陸回数は約74万回で、年間約6161万人の旅客と約196万トンの貨物を取り扱っている(2001年現在)。この空港で初めて採用されたサテライト式ターミナルは現代の空港計画の基準とされている。
[落合一夫]
ヨーロッパの空港
ドイツには10か所の定期航空用空港があり、連邦政府と地方公共団体の共同か地方公共団体単独の出資による会社形態で運営されている。代表的な空港はフランクフルト・アム・マイン国際空港で、敷地面積約1700ヘクタール、各4000メートルの平行な滑走路2本と4000メートルの横風用滑走路1本の計3本の滑走路を有する。
イギリスの空港には国有と市有、イギリス空港公団管理の3種があり、国有は15か所、公団管理が4か所である。ロンドン地区のヒースロー(おもに国際線)とガトウィック(おもに国内線)は公団の運営である。ヒースロー空港は敷地面積約1200ヘクタール、3902メートル、3658メートル、2357メートルの3本の滑走路がある。
オランダのスキポール空港は敷地面積1750ヘクタール、2018メートルから3490メートルまでの計5本の滑走路を有する。この空港は標高がマイナス、つまり海面より低いところにあることと空港ターミナルの設計がきわめて優れていることが特色である。
フランスではパリのシャルル・ドゴール空港が代表的である。4215メートル、4200メートル、2700メートル2本の合計4本の滑走路があるが、敷地は3104ヘクタールと広大で、必要に応じて施設を増やす余地を残している。1974年に開港しただけに、旅客や航空機の流れに十分の考慮をはらっており、機能的な空港となっている。
ここにあげたフランクフルト、スキポール、ドゴール以外のヨーロッパの空港は、アメリカに比べて規模も小さく設備も旧式のものが少なくなかったが、国際的な視野に基づいて改良が加えられ、近代化が進んでいる。
[落合一夫]
展望と問題点
貨物輸送量の増大と大型化
超大型貨物機の就航によって、大量輸送と大型貨物の輸送が可能になり、貨物輸送量は年を追って増大している。かつての航空貨物は小口・軽量が主体であったが、近年は技術集約度・付加価値の高い電子機器などの工業製品や、鮮度が重要な食品類などが中心となっており、これらは航空輸送を前提とした流通システムをとっている。現代の航空貨物はほとんどがコンテナに搭載されているので、コンテナの組付け、取卸し、仕分けなどのために、機械化、コンピュータ化されたコンテナ・ヤードは不可欠である。航空機による貨物輸送の需要の増加が予想されており、貨物専用空港は今後さらに必要な存在となる。
[落合一夫]
空港内の動線の効率化
旅客を航空会社のカウンターから待合室、搭乗機へどう流すか、その逆の動きはどうかについては、以前からいろいろな方式が試されてきた。たとえば、フィンガー(またはピア)方式、サテライト方式、ピア・サテライト方式、オープン駐機方式などである。しかし、立地条件や規模、予算あるいは経費とのバランスとの問題があり、いまだ最良といえるシステムは確立していない。さらに、航空機の地上走行や停留、サービス用車両の交通などについても、検討の余地が多く、空港内の移動・交通対策は、大きな課題として残されている。
[落合一夫]
空港と環境
離着陸誘導施設や航行援助装置、滑走路の長さなどが万全であっても、それだけでは理想的な空港とはいえない。気象条件をはじめとして、都心との距離や交通機関、他の空港・航空路との関係、空港周辺の障害物などは、空港の機能に大きな影響を与える。ことに、国内では周辺住民の環境保全の要求は、空港にとって無視できない要因となっている。これらの理由から、離着陸における出発・進入コースの制限、エンジンの出力や上昇角度の規制が行われ、その結果機材の性能が抑えられることになり、有償搭載量が削減されたり、操縦士に多大な負担を強いることもある。離着陸の便数や運用時刻が限定される例は少なくないが、機材の進歩(たとえば、ボーイング-767、同-777、A-320その他の双発ジェット旅客機の導入)もあり、かなり改善されてきた。日本では国土の広さに対して航空旅客の需要が多く、超大型機(ジャンボ機)の就航によって対処しているが、空港周辺では、大気汚染や騒音という従来の航空公害に加えて、近年発生・増大している新たな問題として、人為的なミスによる離着陸時の事故の危険性、超大型機の低空通過による威圧感などがある。
[落合一夫]
航空機の進歩
技術の進歩により、従来より静かで、安全で、経済的な新機材が次々に開発されている。新型機は、既存の空港の規模に適応するように計画されているので、5000メートルもの長大な滑走路を必要とすることはないが、滑走路の増設をはじめとする空港の施設の拡充は安全性や利用者の便からいって急務である。電子技術の発達に伴い、情報・通信分野は国際的な規模で経済、社会、文化あらゆる面の交流・流通を促している。物資の流通はもちろん、直接人と人とが接触して意思の疎通を図ることの必要も増える。速度を最大の特長とする航空輸送の意義はさらに高まっていくことは明らかである。空港もその動向に応じて将来の発展を見越して計画を進めてゆかなければならない。
[落合一夫]
『井戸剛著『空港の科学』(1970・日本放送出版協会)』▽『青木公著『エアポート・シティ』(1974・朝日ソノラマ)』▽『津崎武司著『日本の空港』(1980・りくえつ)』▽『野間聖明著『マン・マシン時代を考える』(1980・日本航空協会)』▽『杉浦一機・別冊宝島編集部編著『巨大利権「空港建設」』(宝島社新書)』▽『杉浦一機著『空港ウォーズ』(1999・中央書院)』▽『鎌田慧著『大空港25時』(1996・草思社)』▽『佐藤章著『関西国際空港』(中公新書)』▽『上之郷利昭著『羽田空港物語』(1997・講談社)』▽『原口和久著『成田空港365日』(2000・崙書房出版)』▽『関西空港調査会編『エアポートハンドブック2000』(2000・月刊同友社)』▽『港湾空港タイムス編『大都市拠点空港』(1999・都市計画通信社)』▽『村山元英著『民営ハブ空港論』(1997・文真堂)』▽『『全国空港ウォッチングガイド』新改訂版(1997・イカロス出版)』▽『アントラム栢木利美著『国際空港「乗客」物語』(1996・学陽書房)』▽『東北産業活性化センター編『国際ハブ空港の建設』(1995・日本地域社会研究所)』
改訂新版 世界大百科事典 「空港」の意味・わかりやすい解説
空港 (くうこう)
airport
航空機を発着させるための施設のうち,主として航空運送の用に供される公共用の民間飛行場で,ある程度以上の規模と設備をもつものを指していう。
空港の歴史
19世紀末から20世紀初めの航空草創時代,航空機の離着陸は草原,河原,広場,演習場などを利用して行われていたが,航空機の発達につれて,1920年代初・中期になってヨーロッパで航空輸送が勃興すると,それに伴って簡易な滑走帯と旅客用の施設などをもつ飛行場が現れ,以後30年代末までに現代の空港の祖型となるような施設が欧米各国で次々に完成した。日本では1929年に開港した大阪飛行場(木津川河口。水上および陸上機用)と福岡飛行場(福岡県名島。水上機専用)が最初であるが,本格的な空港としては31年8月に開港した東京飛行場(現,東京国際(羽田)空港)が最初である。
当時の空港は都市の機能とはほとんど関連がなく,航空機を発着させるための最小限の施設の提供といった程度の認識しかもたれていなかったし,利用者にとっても旅行のプロセスの中での通過点の一つにすぎなかった。しかし,航空輸送が発展し貨客量が増大するにつれ,空港の比重も加速度的に高まって,現在では都市の構造の不可欠な一部と考えられるようになり,とくに主要都市の大型空港はそれ自体一つの衛星都市のような機能を果たしている。したがって各国とも空港の問題を重視し,優先的な考慮をはらうようになってきた。
空港の種類
空港の規格や施設については,ICAO(イカオ)によって詳細な基準が定められており,これに基づいて日本では航空法,同施行規則および空港整備法にその設置,管理,安全規制,工事費負担などについての諸規定が設けられている。それによると,空港は用途別に陸上および水上飛行場と,陸上および水上ヘリポートの4種に,規模では滑走路の長さによってAからIまでの9等級に分類されている。また,性格と機能から,航空交通網の基幹となる空港で,設置,管理とも国が行う第1種空港(ただし新東京国際(成田)空港は新東京国際空港公団(2004年民営化され,成田国際空港株式会社となる)が,また関西国際空港は関西国際空港株式会社が管理),主として国内幹線用の空港で,国が設置し,管理は国または地方自治体が行う第2種空港および主としてローカル航空輸送用の空港で,設置,管理とも地方自治体が行う第3種空港の三つに分けられている。ただし,第2種,第3種空港とも保安施設関係のみはすべて国が担当する。なお,国際空港という名称は便宜的なものであって法律上の規定はない。
空港の機能
空港の機能の基本は安全かつ効率的に航空機の発着と貨客の流れを処理することにあるが,このほか付随機能として航空機の駐機,整備,気象業務,保安・警備,都心および他空港との交通手段の提供なども行われ,また,大型空港では食事,宿泊,通信,事務,情報提供など利用者が生活の一部を支障なくすごせるような設備をも有する。1970年代以降,ジャンボジェットやエアバスなど大型輸送機の増加に伴い,空港の機能を設定する場合にもこれらの大型機の受入れを基準にして考えられるようになった。
貨客施設
空港の施設のうち,貨客関係のおもなものは旅客および貨物ターミナルビルを中心に,付属するホテル,駐車場,倉庫,鉄道・バス駅,アクセス道路などからなっている。大型空港の旅客ターミナルビルには単一棟型(大阪国際空港),複数棟型(ケネディ空港),フィンガー展張型(ヒースロー空港),サテライトビル型(新東京国際空港)などの型式があるが,駐機スペースの多寡,移動距離の大小,建増しの難易,ビル間の連絡などの点でそれぞれ一長一短がある。大型の施設では多数の乗降ゲートとそれに付属する待合室があり,また,出発客と到着客を階によって分離するなど,旅客の動線がなるべく交わらないように配慮されているところも多い。航空機への乗降には歩行,バス輸送およびターミナルビルに取り付けられた乗降用ブリッジの三つの方式があるが,ブリッジの利点がしだいに認められ,大型空港はもちろん中程度の規模のところでもこれを採用する空港が増えつつある。大型空港のターミナルビルには旅客用の設備として搭乗手続カウンター,待合室,案内所,ハイジャック検査装置,手荷物移送および引渡し設備,医療・救急施設,商店街など(国際空港では税関,検疫所,出入国管理所も)があり,ほかに官庁事務所,通信室,気象台,航空会社および関連会社の事務所,VIP専用室,郵便局,銀行,警察などが置かれていることが多い。貨物の処理は,中・小空港では旅客ターミナルビルの一部を利用して行われるが,大型空港では専用ターミナルと倉庫があり,ケネディ空港のように各航空会社がそれぞれ独自の貨物ビルを所有している例もある。新しい貨物ビルには受入れ,仕分け,保管,発送が完全にオートメーション化された無人ビルも少なくない。また,大型空港では各大手航空会社がそれぞれ自営の機内食工場をもっているところが多い。
運航施設
空港における航空機の運航のための施設としては滑走路,誘導路,駐機場,管制所がある。
滑走路runwayは,小空港では土地を展圧しただけで舗装のないものもあるが,ふつうはコンクリートの基礎部分に表面をアスファルトで覆った構造のものが多く,大型機用のものは数百tの衝撃荷重に耐える強度をもつ。規模は長さ1000~1500m,幅30~45m程度のものから,長さ3000~4000m,幅60~90mに及ぶものまである。滑走路は1本だけでも年間13万回前後の発着を処理することができるが,交通量の多い空港や風向の不安定な空港では複数の滑走路が必要となり,海外の大型空港では4本以上設置されているところも珍しくなく,デンバー空港では12本もある。複数滑走路の場合は個々の空港の条件に応じてX形,L形,=形,♯形,放射形などさまざまな組合せで配置される。このうち=形や♯形の併行配置は比較的わずかなスペースで高い処理能力が期待できる形式であるが,併行する両滑走路で同時に発着を行うためには,安全上1500m以上の間隔をとって設置する必要があり,間隔が狭い場合には効率が低下する。滑走路の両端には航空機のオーバーランに備えてそれぞれ50~150m程度の過走帯(オーバーランエリアoverrun area)と呼ばれる延長部分が設けられている。最近では滑走路の排水をよくして制動効果を高めるため,表面に横方向の細い溝を切るグルービング加工を施すことが多くなった。なお,滑走路とその周辺を含む矩形の部分を着陸帯landing areaといい,これを中心とする一定範囲内では法令によって建築物などの高さが制限されている。
誘導路taxiwayは滑走路と駐機場を結ぶ連絡路で,滑走路に準ずる幅と強度をもつ。従来の誘導路には滑走路との結合部が直角で,かつ直線的に駐機場と結ばれる形のものが多かったが,大型空港では出発・到着機の流れをスムーズにするため滑走路と併行に同じ長さをもつ誘導路を敷設し,さらに航空機が高速で進入できるようその併行誘導路と滑走路を円弧状の連絡路で結ぶ形式のものが増えてきた。空港によっては出発機と到着機を同時に走行させるため2本の併行誘導路をもつところもある。
駐機場はエプロンapronまたはランプrampとも呼ばれ,ターミナルビルの前や整備地区に接して設けられた広場で,貨客の積卸し,給油,点検・整備,駐機などを行うための場所である。駐機場には航空機を停留させるため一定の駐機点(スポット)が設けてあり,大型空港ではこれを100ヵ所以上もつところも少なくない。駐機点はなるべくターミナルビルの直前に設けるのが理想であるが,スペースに限りがあるため,出入機数の多い空港ではターミナルビルからフィンガーをのばしたり,あるいはビルから離れた場所に駐機させて旅客をバスで輸送したりして処理している。また,中・小空港では給油をタンクローリー車に依存しているが,大型空港ではハイドラントと呼ばれる地下埋込式の燃料タンクが駐機場に設置され,直接地表から給油する方式をとっている(航空燃料)。
空港の航空交通管制所は空港内およびその周辺の航空機の衝突を防ぎ,かつ航空機の流れを効率よく処理するための機関であって,原則として計器飛行方式で運航される航空機のみを取り扱う。現在では民間輸送機は晴天のときでも計器飛行方式で飛ぶことが多いので,輸送機の発着する空港にはほとんど管制所が設けられている。管制所では管制官が直接航空機を見ながら作業をする管制塔airport control tower(control tower)と,レーダーによって監視・誘導を行うレーダー管制室とが協力して管制にあたる。管制塔は空港内全域と周辺の空域を360度見渡せる位置,高さ,構造が要求され,なかには長崎空港やシンガポールのチャンギー空港のように,隣接する二つの飛行場を同時に見渡せるよう60~80mの高さをもつものもある。また,近接して複数の空港がある場合,混乱を防ぐため1ヵ所のレーダー管制室で一元的に管制を行っているところもある。
空港のコラム・用語解説
【世界の主要空港】
- ケネディ空港 John F.Kennedy International Airport
- 1948年7月に開港したニューヨーク市の第3空港。国際線の交通量と貨物の取扱高では全米第1で,アメリカの空の玄関口といわれる。都心から南東21kmの地点にあり,面積1995ha,4本の滑走路と8棟の旅客ターミナルビルおよび22の貨物施設をもつ。管理はニューヨーク・ニュージャージー港湾局。なお,ニューヨークにはほかにラ・ガーディアLa Guardia Airport,ニューアークNewark Airportの2空港がある。
- オヘア空港 O'Hare International Airport
- 1955年10月に開港し,近年まで出入旅客数では世界第1位にランクされ続けたシカゴ市営の空港。市の北西30kmにあり,2833haの敷地に6本の滑走路と4棟の旅客ターミナルビルをもつ。シカゴにはもう一つミッドウェーMidway Airportという古い空港もあり,併用されている。
- ダレス空港 Dulles International Airport
- アメリカ連邦航空局が管理する国営空港で,1962年11月開港。ワシントン市の西方43kmにあり,面積4047ha,3本の滑走路を有し,ターミナルビルは巨大な単一棟型。交通量は少ないが広さでは全米第2位で,市内にあるワシントン・ナショナル空港Washington National Airportと併用されている。
- サンフランシスコ空港 San Francisco International Airport
- 1927年開港という歴史の古いサンフランシスコ市営空港で,湾の埋立てによって拡張を続け,現在では面積2107ha,♯形に配置された4本の滑走路をもち,出入旅客数で全米第5位。サンフランシスコ都心から南へ15kmのところにあり,湾を隔てた対岸にオークランド空港Metropolitan Oakland International Airportがある。
- ロサンゼルス空港 Los Angeles International Airport
- 1930年開港のロサンゼルス市営空港。現在では1416haの敷地に4本の滑走路と9棟の旅客ターミナルをもち,取扱量では旅客,貨物ともに全米第3位。市の南西16kmの太平洋岸にあり,アメリカ西海岸最大の空の玄関となっている。
- ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ空港 Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
- ハーツフィールド空港などとも呼ばれる。1926年開港のアトランタ市営の空港。規模はさほど大きくないが,旅客取扱量が多い。市の南方13kmにあって,面積1518ha,滑走路5本をもち,アメリカ南部航空交通の中心となっている。
- ダラス・フォート・ワース航空 Dallas-Fort Worth International Airport
- 7082haという世界第3位の敷地をもつ超大型空港。ダラス,フォート・ワース両市の共有施設として1974年に開港。滑走路7本,旅客ターミナルビル5棟。両市からともに27kmの中間点にあり,出入旅客数では全米第6位。
- モントリオール・ミラベル空港 Montreal Mirabel International Airport
- オリンピック競技の開催にあわせて1975年に開港したカナダ国営の大型空港。空港自体の面積は7000haで,アメリカのダラス・フォート・ワース空港にわずかながら及ばないが,周辺に2万9000haもの巨大な騒音緩衝地帯をもつのが特徴である。モントリオール市の北西55kmのところにある。2004年10月,拡張計画が中断され,国際線は,同市にあるピエール・エリオット・トルドー空港に移行した。
- ヒースロー空港 Heathrow Airport
- 発着機数,出入旅客数ともにヨーロッパで最大の空港。イギリス空港会社の経営で,1930年に開港された。現在は1141haの敷地に2本の滑走路と5棟の旅客ターミナルビルをもつ。ロンドンの都心から西へ22kmの地点にあり,地下鉄でも連絡されている。ロンドンにはこのほかガトウィックGatwick Airport,ルートンLuton Airportの2空港がある。
- フランクフルト空港 Frankfurt Airport
- 西ドイツ最大の空港で,正式名称はライン・マイン空港Rhein-Main Flughafen。交通量ではヨーロッパ第2位の空港。1936年に飛行船の基地として建設されたものを拡大,近代化した施設で,現在は面積1203haの敷地に2本の並行滑走路が設けられ,フランクフルト・アム・マイン空港公社が経営にあたっている。フランクフルト・アム・マイン市の南西12kmの地点にあり,都心とは鉄道でも結ばれている。
- パリ・ド・ゴール空港 Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
- 1974年3月に開港したヨーロッパ第2の空港。長距離海外線用の基地で,交通量はさほど多くはないが,3104haの広大な敷地をもち,最終的には5本の滑走路が建設される。パリの北東25kmにあり,経営はパリ空港公団。パリにはもう一つ南郊に国内線および近距離国際線用のパリ・オルリー空港Aéroport de Paris-Orly(1536ha,滑走路3本)があり,交通量はこちらのほうが多い。
- ローマ・フミチノ空港 Roma Fiumicino Airport
- 1961年に開港された空港で,正式名称をレオナルド・ダ・ビンチ空港Aeroport Leonardo Da Vinci di Fiumicinoという。ローマの西方35kmの海岸にあり,面積1430ha,滑走路3本で,経営はローマ空港公団。このほかローマにはチアンピーノCiampino Airportという古い空港もあり,一部国内線の運航に使われている。
- スキポール空港 Schiphol Airport
- 1920年供用開始という世界最古の空港の一つで,海面より4m低いのが特徴。アムステルダムの都心から7kmの近さにあり,1750haの敷地に滑走路5本。発着機数ではヨーロッパ第3位,旅客数では第4位である。経営にはスキポール空港公団があたっている。
- カストラップ空港 Kastrup Airport
- 北欧最大の空港で,1925年開港。コペンハーゲンの南方8kmにあり,オーレソン海峡に面している。面積1100ha,滑走路3本で,交通量は北欧第1位。コペンハーゲン空港公団の経営。
- シェレメチエボ空港 Sheremet'evo Aeroport
- モスクワに4つある空港のうち海外線専用に使われている施設で,1961年開港。市の北西28kmにあり,面積は不明。滑走路は2本ある。1980年のオリンピック競技開催に際して新しい旅客ターミナルビルが建設され,超大型輸送機の受入れが可能となった。
- 東京国際空港
- 羽田空港ともいう。1931年に東京飛行場の名で開業された空港で,戦後しばらく,国際線を含め日本の航空交通網の基幹空港であったが,1978年の成田空港の開業に伴って,国際線は成田に移った。この時点では427haの狭隘な敷地に滑走路2本のみの貧弱な施設ながら,世界第7~8位の旅客数を処理し,大阪国際空港(伊丹空港-当時)とともに,国内航空交通網の中心となっていた。その後,拡張計画が進められ,2008年現在,面積1271ha,滑走路3本,旅客ターミナルビル2棟の規模となっている。国土交通省が管理にあたっている。
- 成田国際空港
- 成田空港ともいう。1978年5月に開港した首都圏の新しい国際線用空港で,都心から東方66kmの千葉県成田市三里塚地区にある。最終的には面積1125haとなる予定で,現在滑走路2本,旅客ターミナルビル2棟。開業当時は新東京国際空港と呼ばれたが,2004年4月,管理する新東京国際空港公団の民営化で,同公団が成田国際空港会社となったとき,成田国際空港と改称された。
- 台北・中正国際機場
- 1979年2月に開港された国際線用の新空港で,都心から西へ31kmの海岸にあり,面積1200ha,滑走路は最終的に3本建設される。誘導路でも大型機の離着陸ができることなど,すべてにわたって有事即応の配慮がはらわれている。市内にある国内線用の松山空港と併用。管理は政府交通部。
- 香港・啓徳(カイタク)空港 Kai Tak Airport
- 1927年にイギリス空軍の基地として完成したのが起源で,面積わずか222ha,滑走路1本のみの小施設ながら,東南アジアでもっともにぎわう空港であったが,交通量が限界に達していたこと,環境や安全性に問題があったことから,1998年に閉鎖。新設の香港国際空港Hong Kong International Airportが開港した。
- シンガポール・チャンギ空港 Singapore Changi Airport
- 東南アジア最新最大の空港で,シンガポール島の東端の一隅にあった空軍基地を埋め立てて拡張し建設したもの。1981年7月に開港。面積は1663ha,滑走路は2本。管理は政府民間航空局。
→航空交通管制
航行援助施設
現代の航空機の運航は,空港,航空路に設置されている無線機器,レーダー,照明機器などの航行援助施設に全面的に依存して行われている。したがって空港にとってこれらの施設は不可欠のものであり,その装備の良否が空港の機能を左右するといってもよい。
空港に設置されている援助施設のうち,無線機器としては無指向性無線標識(NDB。non-directional radio beaconの略),超短波全方位無線標識(VOR。VHF omni-directional radio range beaconの略),距離測定装置(DME。distance measurment equipmentの略),VHF/UHFまたはマイクロ波を利用した計器着陸装置(ILS。instrument landing systemの略),レーダーには空港監視レーダー(ASR。airport surveillance radarの略),精測進入レーダー(PAR。precision approach radarの略),空港面探知装置(ASDE。airport surface detecting equipmentの略),照明機器としては空港灯台,滑走路灯,滑走路中心線灯,接地帯灯,滑走路末端灯,進入灯,進入角指示灯,空港境界灯,誘導路灯,駐機場灯,障害物灯などがある。さらに近年はATIS(automatic terminalinformation systemの略。空港の情報を自動的に提供する装置)やウィンドシア(wind shear。風の断層)を観測する装置を備える空港も増えてきた。主要大型空港ではこれらの全部,または大部分を備えているが,辺地の小空港ではNDBだけといったところもかなり残っている。空港はこれらの機器の装備状況と進入コースの状態によって視界不良時の進入許容限界がカテゴリーⅠ,Ⅱ,Ⅲa,Ⅲb,Ⅲcの5等級に分類され,Ⅲcの基準を満たす空港では雲高・視界ゼロの状態でも着陸することが認められる(ただし,実際にそれを行うためには,航空機側にもそれに対応する設備と有資格の乗員の乗務が必要となる)。
→航空保安無線施設
整備施設
どの空港においても大なり小なりなんらかの整備設備が設けられているが,とくに航空会社が運航・整備の中心基地と定めている空港では,それぞれオーバーホールを含む大規模な整備・修理を行えるだけの工場,検査施設,部品倉庫,格納庫,エンジンテスト施設などが設置されている。このほか大型空港では,燃料貯蔵施設,配電・給排水設備,消防・救難施設なども完備している。
空港の管理・運営
ロシア以外の先進国では国が管理・運営する空港はきわめて少なく,大部分は自治体ないし公社・公団がそれに当たっている。日本ではかつてはすべて運輸省・自治体の管理であったが,成田空港で公団方式が,また関西新空港では株式会社方式がそれぞれはじめて採用された。
空港計画
現代では空港は交通・物流体系のみならず,一国の政治,外交,産業,経済から学術,文化,スポーツに至るまで広い範囲にわたって濃密な関連をもつ。したがって多くの国においては空港問題は国家の長期計画ないし地域の開発計画の一つの柱として組織的に建設・運用されるようになってきた。また,発展途上国,とくに観光収入に依存している国々においても,観光客誘致の窓口として空港に優先的考慮がはらわれている。
空港の建設にあたって要求される条件としては,なるべく都市に近いこと,将来の拡張の余地を含めて広大なスペースがとれること,付近に人家が少ないことおよび大きな障害物がないこと,他空港や航空路との干渉が起こらぬよう十分な空域が確保できること,気象条件が安定し,鳥害の少ないことなどがあげられるが,先進各国ではもはや大都市近郊にこれらの条件を満たす土地が乏しいため,新しく建設される空港はしだいに都市から遠くへ押しやられる傾向が強く,都心との連絡に1~1.5時間程度を要するところが増えつつある。この傾向は地理的条件に恵まれない日本の場合とくに著しく,ローカル諸都市でさえすでに近郊の平地に空港用地を求めることができず,新空港はほとんど丘陵地帯の頂部を整地するか,ないしは海上に建設せざるを得なくなってきており,それも地形,気象,鳥害などの点でかなりの不利をしのびつつ建設・運用されている例が多い。これらの問題を解決する方策としては,気象・海象条件が許せば海上空港が理想に近く,1975年5月に完成した長崎空港が世界最初の海上空港の例となった。その後,関西新空港がこれに続き,さらに中部圏でも海上空港が開港した。中部国際空港は愛知県常滑市の沖合を埋め立てて新設された海上空港で,2005年2月開港。愛称はセントレア。空港島の面積580ha,滑走路は3500m×1。管理運営は中部国際空港株式会社。ただ,長崎のように既存の島を利用することができれば建設は比較的容易であるが,関西や中部圏のように基礎になる島がない場合には埋立てによるか,または巨大な構造体を構築しなければならず,コストの面でかなり不利となる。韓国の仁川国際空港は韓国・仁川沖合の島を利用してつくられた空港で,2001年3月開港。ソウル郊外の金浦空港に代わって国際線を受けもつこととなった。滑走路は3750m×2。
このほか,世界的な航空貨物量の増加に伴って,先進各国では貨物専用空港を建設する構想も増えてきた。貨物空港の場合は必ずしも都市近郊に設置する必要がないなど,一般空港に比べて要求される条件がかなり異なるうえ,さらに後背地に工業地帯などを建設することによって新しい機能をもつ空港となる可能性もある。
日本の空港計画の端緒となったのは1956年4月に公布された空港整備法であったが,これに基づいて行われた当初の施策が,当時急速に発展し始めた航空輸送の需要を処理するべく最低限の施設を応急的に整備するといった方針であったため,1950年代後半および60年代前半を通じてあまり見るべき成果がなかった。しかし66年に発生した5件の連続大航空事故を契機として,ようやく空港施設改善の気運が高まり,以後,空港整備5ヵ年計画が運輸省によって連続的に実施されてきた。その結果,ジェット輸送機の発着しうる大型空港がしだいに増え,また,保安施設や航行援助機器の整備も比較的短期間に格段の進歩をみた。
空港の抱える問題点
現代の空港は公益のみならず周辺地域社会の利害とも濃密な関連をもち,かつ,その建設・運用にはつねに膨大な利権を伴う。したがって,どこの国においても政治勢力の介入を招きやすく,空港の機能や利用者の安全・利便よりも政治・経済的配慮が優先して問題が処理されることが多い。さらに最近はしばしばこれに空港反対運動の動きがからむため,問題はいっそう複雑な形となってひずみが拡大されがちで,とくに日本ではその傾向が強い。一方,構造・運用が膨大かつ精緻(せいち)になるにつれ,反面,その体質にきわめて惰弱な部分が生ずるという点では空港も他の巨大システムと同じで,とくに空港の場合は安全問題の関与する局面が多いだけに,末端の小トラブルでもただちに体系全体の機能麻痺につながりやすいし,外部からの軽微なインパクトによってさえ容易に運用は阻害される。しかも,技術の進歩にもかかわらず,空港に要求される機能が複雑化し,関連する分野が拡大するにつれて,この基本的な脆弱(ぜいじやく)性も同時に拡大していくものと考えられる。したがって空港の機能を維持するためには,精密・厳正な管理と高い水準の技術および十分な投資が必要となる。これを実現するのは先進各国においてさえ容易なことではないが,一部には空港を国威のシンボルないし国家のアクセサリーとしてとらえる国々もあり,先進国に依頼して大型空港を完成しながら維持・管理能力が伴わず,とくに安全面で信頼性の低さが指摘されているところも少なくない。
先進国の各空港もそれぞれ問題を抱えているが,なかでももっとも深刻なものは騒音被害である。1960年代後半以降,ジェット輸送機の増加につれ空港がにわかに周辺住民からうとまれる存在となったため,至上命題として周辺地域社会との関係改善に最大限の努力が払われてきた。その結果,航空機・エンジンの改良,家屋の防音工事,立退きなどとともに,飛行コースや飛行方法にも規制が加えられ,かなりの効果をあげている。反面,この規制によって航空機は安全上必ずしも望ましくない飛行法をとらざるを得ないことが多いが,この問題はほとんど顧慮されないという矛盾も起きている。また,70年代の2回にわたる石油危機以後,世界の航空機・エンジン製造業者が技術開発の主力を騒音処理から燃料消費低減へとほぼ全面的に転換したため,騒音低減の研究には以前ほどの努力がはらわれなくなっているように見える。
航空交通管制上の問題として,航行援助機器の進歩や管制の自動化の進展にもかかわらず,交通量の急激な増加によって,空港内および周辺での航空機衝突の可能性は依然減少しておらず,とくに高速の中・大型輸送機と膨大な数にのぼる低速小型機との混合交通を許しているアメリカの各大都市空港では,輸送機の衝突やニアミスが絶えない。空中衝突に限らず,空港周辺での航空事故について見逃されがちなことの一つは,それが地上に惨害を生ずる可能性である。とくに周囲を人家や工場,学校などに取り囲まれ,滑走路の間際まで家並みの迫っているところの多い日本の都市空港では,いったんこの種の事故が起これば大被害をもたらすおそれがきわめて強いが,それにもかかわらず一般の関心はほとんど騒音のみに集中して安全の問題はあまりかえりみられず,対策も進んでいない。
→空港公害 →航空機騒音 →航空事故
執筆者:関川 栄一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「空港」の意味・わかりやすい解説
空港【くうこう】
→関連項目航空
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「空港」の意味・わかりやすい解説
空港
くうこう
airport
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「空港」の解説
空港
世界大百科事典(旧版)内の空港の言及
【飛行場】より
…軍用と民間とを問わず,また,設備の整った大規模な施設から草原や空地を利用した程度の小規模なものまですべてを含むが,艦船の甲板上に設けられた離発着帯などは除く。飛行場のうち主として民間航空輸送の用に供されるものを空港といい,また,ヘリコプター専用の施設をヘリポートという。日本の航空法は民間飛行場を陸上飛行場,水上飛行場,陸上ヘリポートおよび水上ヘリポートの4種に分類し,さらにそのそれぞれを滑走路または着陸帯の長さによって2~9等級に分け,その設置,管理,構造,保安設備,周辺障害物の制限などについて規定している。…
※「空港」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...