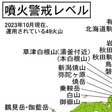デジタル大辞泉
「硫黄島」の意味・読み・例文・類語
いおう‐とう〔いわうタウ〕【硫黄島】
 東京都、小笠原諸島の南西、硫黄列島の中央の火山島。第二次大戦の激戦地。現在は自衛隊の基地が置かれている。中硫黄島。いおうじま。
東京都、小笠原諸島の南西、硫黄列島の中央の火山島。第二次大戦の激戦地。現在は自衛隊の基地が置かれている。中硫黄島。いおうじま。
 菊村到の短編小説。昭和32年(1957)発表。同年、第37回芥川賞受賞。昭和34年(1959)映画化。
菊村到の短編小説。昭和32年(1957)発表。同年、第37回芥川賞受賞。昭和34年(1959)映画化。
[補説]明治時代以降「いおうとう」と呼称されていたが、第二次大戦で占領した米軍が「いおうじま」と呼んだ。昭和43年(1968)の返還後は旧呼称に復したが、昭和57年(1982)の地図改訂で「いおうじま」と誤記されて以降この呼称が定着。平成19年(2007)に元島民らの要求が受け入れられ、国土地理院と海上保安庁によって「いおうとう」の呼称が正式とされた。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
硫黄島
小笠原諸島の火山島。太平洋戦争末期の1945年2月に米軍が上陸。国内初となる陸上戦闘が始まり、日米両軍合わせて約2万8千人が死亡したとされる。68年に米施政下から日本に返還されたが、自衛隊の基地が置かれ、今も一般人の立ち入りは制限されている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
Sponserd by 
いおう‐じまいわう‥【硫黄島】
- [ 一 ] 小笠原諸島の南西部、硫黄列島の中央にある火山島。中硫黄島ともいう。面積二二・三六平方キロメートル。太平洋戦争の激戦地。戦後、アメリカに施政権があったが、昭和四三年(一九六八)日本に復帰し、東京都に編入。いおうとう。
- [ 二 ] 鹿児島県大隅諸島の北西方にある火山島。面積一一・七八平方キロメートル。硫黄岳(七〇四メートル)がある。平安時代に俊寛が流された場所といわれる。硫黄が島。鬼界ケ島。喜界ケ島。薩南硫黄島。吐噶喇(とから)硫黄島。
いおう‐が‐しまいわう‥【硫黄島】
- =いおうじま(硫黄島)[ 二 ]
- [初出の実例]「鬼界が嶋へぞ流されける。〈略〉硫黄と云ふ物みちみてり。かるがゆへに硫黄が嶋とも名付たり」(出典:平家物語(13C前)二)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
硫黄島
いおうじま
[現在地名]三島村硫黄島
鹿児島港から一〇八キロの洋上にある。主峰硫黄岳(七〇三・七メートル)が噴煙を吐く周囲一四・五キロの火山島。古くは鬼界島とよばれたとされ、俊寛説話で知られる。海岸は鬼界カルデラの壁で、ほとんどが断崖。東は新硫黄島(昭和硫黄島)を挟んで竹島、西は黒島。北方約五〇キロに薩摩半島南端の枕崎市、南方約四〇キロに屋久島がある。面積一一・七八平方キロ。元禄国絵図には島回二里五町とあり、権現・へいけの城などの記載がある。また「三国名勝図会」では鹿児島から三一里、山川湊(現山川町)から一八里。また硫黄岳について「海上より聳へ立ち、形状奇高なり、土俗の説に、登り三里、下り一里といへども、大抵半里許もあるべし、山面都て焼石にて艸木生ぜず、山の半腹より上は処々硫黄燃上り、山頂最も多く燃出づ」などとみえる。
〔古代・中世〕
古代以来、記録・物語類にみえる貴海島・鬼界島などは硫黄島にあたるとする説がある。中世は薩摩国河辺郡十二島のうち口五島に属し、地頭職・郡司職が設定されていた。また中世には流刑地、硫黄産出地として知られていた。「平家物語」巻二は治承元年(一一七七)俊寛・平康頼・藤原成経の配流地を「薩摩潟鬼界が島」とし、延慶本「平家物語」は配流地の鬼界島を島のなかに火山島があり、硫黄を産するので油黄島と名付けられたとしている。「吾妻鏡」文治三年(一一八七)九月二二日条に「貴海島」とみえ、阿多忠景が勅勘を被って逐電したという。忠景は硫黄島で没したという説がある(「谷山氏系図」川辺郷土史)。正嘉二年(一二五八)に平内俊職が流されたといい(「吾妻鏡」同年九月二日条)、弘安元年(一二七八)には殺害人松夜叉丸が流されている(同二年四月一一日「六波羅御教書」旧記雑録)。嘉元四年(一三〇六)四月一四日の千竈時家譲状(千竈文書)にみえる河辺郡十二島に含まれた。文保三年(一三一九)東福寺(現鹿児島市)で禁を犯した家臣は当島に流される定となった(同年二月五日「島津忠宗禁制」旧記雑録)。元弘の乱では関東調伏を祈祷した科で文観が流された(「太平記」巻二)。興国四年(一三四三)河辺郡「黒島硫黄郡司職」が、かめまつ丸に与えられた(同年一〇月二二日「某書下」旧記雑録)。応永年間(一三九四―一四二八)当島は黒島・竹島とともに「三島」とよばれ、守護島津久豊から種子島氏に与えられた(種子島家譜)。
「海東諸国紀」の九州之図や、明代の一五五七年刊の「日本一鑑」の絶海新篇図などに島名が記載され、「万暦三代征考」の日本総図には硫黄山とみえる。
硫黄島
いおうじま
火山列島(硫黄列島)の中心島で、父島の南南西約二七五キロに位置する。「いおうとう」ともよぶ。火山島で、島内のいたるところに噴気孔がある。面積は二二・三六平方キロ。島の南西端に最高峰の摺鉢山(一六一メートル)がある。明治二〇年(一八八七)東京府知事高崎五六が島を巡視、同二二年田中栄二郎が硫黄採掘と漁業基地建設の目的で渡島している。同二四年正式に日本領土となり、東京府の所管となった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
Sponserd by 
硫黄島(いおうとう)
いおうとう
東京都小笠原諸島(おがさわらしょとう)の南西、火山列島(硫黄列島)の中央にある粗面安山岩の活火山島。中硫黄島ともいう。直径10キロメートルの海底カルデラのカルデラ縁上に形成された火山。小笠原支庁小笠原村に属す。東京の南約1250キロメートルに位置し、周囲約22キロメートル、面積23.16平方キロメートル。北東から南西に伸長した段丘が発達し、中央部は平坦(へいたん)であるが、中北部に元山(約115メートル)、南西端に摺鉢山(すりばちやま)(169メートル)がある。
1889年(明治22)以降小規模な水蒸気爆発が繰り返されている。1968年(昭和43)以来、防災科学技術研究所、気象庁、国土地理院などによって火山観測が続けられている。島内各地に硫気、地熱地域が分布。また、ほぼ全島にわたり、200年以上にわたって地盤が隆起し続けており、1981~1984年や2001~2002年(平成13~14)さらには2011年1月末~2012年5月には最大1メートルを超える隆起が観測され、隆起がみられていた時期や後に小規模の水蒸気爆発が発生した。気候は亜熱帯気候帯に属するが、活火山島のため植物相は貧弱である。
16~17世紀以来、欧米人によって存在が認められていたが、絶海の小島ということから、長く無住・無主の地として放置されていた。1887年(明治20)ごろから、日本人で漁労や硫黄採取に従事する者があって、1891年9月の勅令第190号をもって硫黄列島とし、小笠原の所轄に編入した。明治末期ごろからサトウキビの栽培に成功し、以来それが最大の産業となった。その後、糖価の下落で死活問題にまで追い込まれたが、昭和初期コカノキの栽培に成功して、その特異な存在が知られるようになった。そのほかデリス球根、バナナその他の熱帯性果実、野菜なども栽培していたが、市場遠隔のため振るわなかった。住民はすべて内地からの移住者で、1944年(昭和19)には1164人を数えたが、第二次世界大戦のため、同年全員内地に引き揚げた。1945年アメリカ軍が上陸、激戦場となり(硫黄島の戦い)、その陥落後は日本本土攻撃の基地となった。
第二次世界大戦後、アメリカの施政権下にあったが、1968年(昭和43)小笠原諸島の日本復帰とともに、東京都小笠原支庁に所属した。なお、硫黄島はアメリカ軍により「いおうじま」とよばれ、戦後はこの呼び方が定着、1982年以降は国土地理院もこの呼称を使用していた。しかし、旧島民は戦前より「いおうとう」とよんでいたことから、小笠原村は国土地理院に変更を要望。2007年(平成19)6月、国土地理院と海上保安庁海洋情報部で構成する「地名等の統一に関する連絡協議会」の決定により、旧称に復した。現在、硫黄島には、海上自衛隊硫黄島航空基地隊が置かれている。電波灯台のロラン局の維持にあたっていたアメリカの沿岸警備隊は1993年(平成5)撤退し、かわって、同年からアメリカの空母艦載機による夜間発着訓練(NLP:Night Landing Practice)が行われるようになった。小笠原国立公園の中にあるが、除外されている。人口402(2010)。
[菊池万雄・諏訪 彰・中田節也]
『東京都島嶼町村一部事務組合編・刊『伊豆諸島・小笠原諸島民俗誌』(1993)』▽『森田敏隆写真『日本の大自然28 小笠原国立公園』(1995・毎日新聞社)』▽『清水善和著『自然史の窓 小笠原自然年代記』(1998・岩波書店)』▽『青山潤写真・文『小笠原 緑の島の進化論』(1998・白水社)』
硫黄島(いおうじま、鹿児島県)
いおうじま
鹿児島県佐多(さた)岬の南西約40キロメートルにあるおもに安山岩からなる活火山島。鹿児島県鹿児島郡三島村(みしまむら)(村役場は鹿児島市内にある)に属する。面積11.65平方キロメートル。最高点704メートル。火山列島(東京都)の同漢字名の島と区別し、吐噶喇(とから)硫黄島、薩摩硫黄島(さつまいおうじま)とよぶ。別名鬼界ヶ島(きかいがしま)。
東方の竹島とともに、7300年前の噴火で生じた鬼界カルデラ(径20キロメートル前後)の縁をなす。西日本火山帯に属し、おもに流紋岩の溶岩と火砕流堆積(たいせき)物からなる。主峰の硫黄岳は円錐(えんすい)形の成層火山で、現に硫気活動が盛んで、1998年(平成10)から小噴火が継続的におこっている。1934~1935年(昭和9~10)の海底噴火で誕生した新島(昭和硫黄島。最高点24メートル)が東方に残存する。平安末期に僧俊寛(しゅんかん)が流された地といわれ、墓がある。1964年硫黄採掘が中止され、耕地も少なく過疎化が進んでいる。鹿児島港から村営定期船が寄港する。人口108(2009)。
[諏訪 彰・中田節也]
硫黄島(いおうじま、東京都小笠原村)
いおうじま
東京都小笠原諸島(おがさわらしょとう)の南西、火山列島(硫黄列島)の中央にある粗面安山岩の活火山島。正しくは「いおうとう」。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
硫黄島 (いおうじま)
薩摩硫黄島,鬼界ヶ島ともいう。鹿児島県薩摩半島南岸の南方約50kmの東シナ海にある火山島。東方約10kmの竹島,西方約30kmの黒島とともに鹿児島郡三島村に属し,口之三島の一つ。東西約6km,南北約3km。竹島とともに鬼界カルデラ(カルデラの直径東西約22km,南北約13km,形成時期不明)の北外縁に位置する。北端部から南西部にかけては先カルデラの火山体で,標高約300m以下の山地または台地からなる。東部から南東部は後カルデラ火山で,東部に主峰硫黄岳(704m)が,南西部に小型スコリア丘稲村岳(約240m)がある。硫黄岳は急峻な円錐形の成層火山で,山頂に直径約500mと200mの2火口がある。山頂火口および山腹各所で激しい硫気活動があり,そのあるものはきわめて高温(850℃)で,火山ガスの研究上重要である。硫気孔では藩政時代から1960年代前半まで硫黄を採掘していた。南西部に唯一の集落長浜と港があり,零細な農漁業が営まれている。人口114(2010)。東方約2kmにある新硫黄島(標高25m)は1934年の海底噴火で水深300mの海底から溶岩が噴出し,形成されたもの。
執筆者:鎌田 政明+横山 勝三
歴史と伝承
産出する硫黄で海面まで黄色くなるのでかつては黄海ヶ島,鬼界島,貴海島と呼ばれた。1177年(治承1)平氏の六波羅政権を倒す計画に失敗した俊寛,藤原成経,平康頼らが配流された島で(《愚管抄》),《平家物語》では鬼界島と書かれている。成経,康頼が大赦で帰島後,俊寛は悲嘆のなかで没した。これは俊寛説話として著名であり,本島に俊寛を祭った御祈神社や俊寛堂がある。同じころ勅勘をこうむった南薩摩の豪族阿多平四郎が本島へ逃亡し,六波羅から追討使が派遣されたが渡海に失敗した。1186年(文治2)河辺平太道綱が本島へ逃亡し,翌年には義経同意のやからが隠れているという疑いがあったため,源頼朝は宇都宮信房と鎮西九国奉行天野遠景をつかわして本島で合戦し,これを帰順させた(《吾妻鏡》)。島内の記録によれば,壇ノ浦で敗れた平資盛と安徳天皇一行は本島に逃れ,1243年(寛元1)安徳天皇はここで没したと伝え,安徳帝陵,黒木御所,硫黄大権現宮など関係史跡がある。この平家落人伝説は1773年(安永2)薩摩藩へ提出された《平家没落由来記》以後知られることとなった。1331年(元弘1)北条氏調伏の罪で文観が本島へ配流され,4年後赦免された(《太平記》)。
執筆者:三木 靖
硫黄島 (いおうじま)
小笠原諸島のうち硫黄列島の三つの火山島の真ん中にある島。別名,中硫黄島。第2次世界大戦後,アメリカ軍の施政下にあったが,1968年復帰し,現在は東京都小笠原支庁小笠原村に属する。面積20.2km2。第2次大戦末期に日本兵が全員玉砕した島である(硫黄島作戦)。火山島といっても付近の南・北硫黄島とは構造が異なり,南端の小円錐形で大きな火口のある活火山(摺鉢山,161m)と標高100m余の平たんな凝灰岩層の台地(元山火山)とが結合して一つの島を形づくっている。摺鉢山は硫黄を噴気するだけで爆発性の活動はしていない。元山火山体は元来海底火山の噴出物(おもに火山砂礫)がまず海底に堆積した後,ドーム状隆起運動を行って海面上に現れたもので,この運動は現在も続いている。1950年以降の測定により島の北東部で最大10mをこえる隆起量が確かめられ,間欠的な地盤上昇の結果,10段の階段状地形が島の周囲の海岸付近に残っている。地熱が高く最高温度は元山付近で観測され,100℃をこえるところもある。飲用に耐える地下水が得られず,天水以外の水源はない。1944年の強制引揚げ以前には1100人余の人口があり,硫黄の採掘やサトウキビの栽培をしていたが,現在は戦前および日米激戦地としての戦中の面影はほとんどない。
→小笠原諸島
執筆者:浅海 重夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
硫黄島
いおうとう
東京都,小笠原諸島の南部,硫黄列島中最大の火山島。活火山で,常時観測火山。別称中硫黄島。小笠原村に属する。海上自衛隊航空基地がある。台地状をなし北東部に元山(115m),南西端には円錐火山の摺鉢山(169m)がある。硫気を噴出し地熱も高い。過去たびたび噴火を起こしており,近年では 2012,2013年に小規模な水蒸気爆発があった。島の隆起を示す海岸段丘や断層崖が発達し,今日でも活発な隆起活動が続いている。無人島であったが,安永8(1779)年ジェームズ・クックの探検隊が発見,1891年日本領有後移民が居住。漁業,硫黄採集や熱帯農業に従事した。太平洋戦争の激化に伴い,住民は全員本土に引き揚げ,その後戦史に残る激戦場になった(→硫黄島の戦い)。第2次世界大戦後アメリカ合衆国の軍政権下にあったが,1968年日本に返還された。面積 23.16km2。
硫黄島
いおうじま
鹿児島県南部,薩摩半島南方約 40kmの洋上にある火山島。活火山で,常時観測火山。口之三島の一つで三島村に属する。最高点は硫黄岳(704m)。硫黄岳は流紋岩からなる成層火山で,噴気活動が活発。1934~35年東方 2kmの海底で溶岩の流出を伴う大規模な噴火が起こり,新島(昭和硫黄島)が形成された。地名の由来となった硫黄採掘は 1964年まで行なわれた。諸説ある鬼界ヶ島の所在地の一つといわれ,鬼界ヶ島の別名をもつ。1994年全国で初の村営飛行場として薩摩硫黄島飛行場が開港した。定期船で鹿児島港と結ばれている。面積 11.65km2。人口 150(2000)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
いおうとう
硫黄島
Ioto ,Iwo To ,Io To ,Iwo Jima
かつては「いおうじま」とも。伊豆─小笠原弧とマリアナ弧の会合部に位置する底径40km以上で,比高2,000m以上の海底火山頂部の火山島。長径8.6kmの島の北東部は台地状の元山,南西部は円錐形の火砕丘の摺鉢山からなり,千鳥ヶ原(砂州)により接続している。直径約10kmのカルデラがあり,釜岩や東岩などの岩礁群は外輪山にあたる。元山は2700年前頃の大規模水底噴火の噴出物が隆起した海成段丘で,カルデラ中央の再生ドームと考えられる。活発な地殻変動・地熱活動・地震活動が続く常時観測対象の活火山であり,19世紀末の入植以来,島内外で多数の小規模噴火の記録がある。噴火の多くは水蒸気噴火とされたが,2022年には南海岸沖でパン皮状火山弾を噴出する水蒸気マグマ噴火が発生。元山付近の隆起速度は世界的にも高速で長期的平均で15~20cm/年,火山活動が活発な時期で1m/年に達する。活断層も多数あり,元山を囲む環状と摺鉢山を横切る北東―南西方向の正断層帯で変位量が大きい。噴出物はかんらん石・単斜輝石斑晶を含む粗面岩ないし粗面安山岩。参考文献:長井雅史ほか(2015)地質雑, Vol. 124:65
執筆者:長井 雅史
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
Sponserd by 
硫黄島(鹿児島)【いおうじま】
九州,薩摩半島南方45kmにある面積11.65km2の火山島(活火山)。竹島,黒島とともに鹿児島県鹿児島郡三島村(31.36km2,500人,2000)を構成,俊寛らの流刑地といわれ,鬼界ヶ島ともいう。噴煙を上げる中央火口丘の硫黄岳(704m)では硫黄を採取。自給的な農・漁業が営まれる。鹿児島港から定期航路が通じる。
→関連項目大隅諸島|川辺十島|文観
硫黄島(東京)【いおうとう】
硫黄列島中の一島で,中硫黄島ともいう。面積23.73km2。凝灰岩の元山を主体とし,南西端に摺鉢(すりばち)山がある。日本領時代サトウキビ栽培,硫黄採取が行われ,1944年人口1164人を数えたが,同年全員が本土へ引き揚げた。第2次大戦末期激戦地となり,米軍は占領後,日本本土爆撃の基地に利用した。1968年日本へ返還された。地熱を帯びた島で噴気孔も多く,活火山として気象庁が常時観測している。
→関連項目硫黄島作戦
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の硫黄島の言及
【境】より
…堺とも書く。あらゆる事物や空間を区切るさまざまな仕切り(境界)。歴史上,境は原始社会から現代に至るまで,小は家と家の境,耕地と耕地の境などから,大は国郡などの行政区分上の境や国境まで普遍的に存在する。 日本の古代では,山や川などの天然・自然の境界物が基本的な境とされていた。《出雲国風土記》に登場する国堺・郡堺の記載50例(重複を含む)をみると,山が15例,水源1例,川が10例であり,さらに埼3例,浜1例,江1例を加えれば,国郡の堺の7割が自然の境界だった。…
【三島[村]】より
…人口513(1995)。薩摩半島南方40~50kmの海上にある[口之三島](くちのみしま)(竹島,硫黄島,黒島)からなる。いずれも火山島で,なかでも硫黄島は常時噴煙を上げている。…
※「硫黄島」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 
 東京都、小笠原諸島の南西、硫黄列島の中央の火山島。第二次大戦の激戦地。現在は自衛隊の基地が置かれている。中硫黄島。いおうじま。
東京都、小笠原諸島の南西、硫黄列島の中央の火山島。第二次大戦の激戦地。現在は自衛隊の基地が置かれている。中硫黄島。いおうじま。 菊村到の短編小説。昭和32年(1957)発表。同年、第37回芥川賞受賞。昭和34年(1959)映画化。
菊村到の短編小説。昭和32年(1957)発表。同年、第37回芥川賞受賞。昭和34年(1959)映画化。