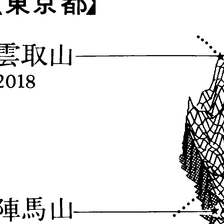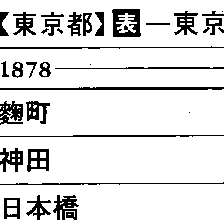精選版 日本国語大辞典 「東京都」の意味・読み・例文・類語
とうきょう‐とトウキャウ‥【東京都】
- 関東地方南西部の都。武蔵・伊豆両国の一部分にあたる。明治元年(一八六八)江戸府は東京府と改称され、同四年の廃藩置県により荏原・豊島・多摩・足立・葛飾の諸郡を合併。同一一年伊豆七島が静岡県から移管され、同一三年には小笠原諸島が内務省から移管された。さらに同二六年多摩三郡が神奈川県から編入されて現在の地域となる。昭和一八年(一九四三)東京市と合体して東京都が成立。都庁所在地、新宿区西新宿。東京。
日本歴史地名大系 「東京都」の解説
東京都
自然環境
〔西に高く、東に低い地形〕
東京都は日本列島のほぼ中央、東北日本と西南日本の接点にある。関東地方の南部に位置し、北を埼玉県、南を東京湾と神奈川県、東を千葉県、西を山梨県に囲繞されている。関東山地から東京湾へ、東西に細長い主要部分と、太平洋上に点在する島嶼部から構成され、面積は二一八七・〇五平方キロ、香川県・大阪府に次いで狭い。標準経緯度は、旧東京天文台(港区飯倉)で、北緯三五度三九分一八秒、東経一三九度四四分四一秒の数理位置にある。主要部の地形は西部関東山地から、多摩丘陵・狭山丘陵・武蔵野台地を経て、荒川・中川・江戸川の沖積低地へと標高を順次低下させ、東京湾で終わる。地形は多摩川水系の造形とみることができ、関東山地の渓口集落である
標高は多摩川の上流、
〔多様な気候風土〕
気候環境は多様な気候風土の総合体の感が強い。中心市街地では大都市が抱える特殊な都市気候の卓越が、西郊の武蔵野台地では関東平野を代表する平野気候の特徴が、西の関東山地では地形の影響が強い山地気候が、伊豆諸島から小笠原諸島にかけては海洋の影響が強い海洋気候が、それぞれ独自な気候環境を描き出している。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「東京都」の意味・わかりやすい解説
東京[都] (とうきょう)
基本情報
面積=2187.50km2(全国45位)
人口(2010)=1315万9388人(全国1位)
人口密度(2010)=6015.7人/km2(全国1位)
市町村(2011.10)=23特別区26市5町8村
都庁所在地=新宿区(人口=32万6309人)
都花=ソメイヨシノ
都木=イチョウ
都鳥=ユリカモメ
東京都は関東地方南西部を占め,主部をなす東西に長い陸地部と,太平洋上の伊豆諸島,小笠原諸島の島嶼(とうしよ)部からなりたっている。陸地部は東京湾の湾奥部に位置し,東は千葉県,北は埼玉県,西は山梨県,南は神奈川県に接する。面積は大阪府,香川県に次いで全国第3位の狭さであるが,人口は世界で最も多い都市の一つで,全国の約1割を占めている。東京は,江戸時代300年の幕政の中心であった江戸を基盤として発達した。現在も日本の首都であると同時に政治,経済,文化,交通の中心であり,周辺の各県域におよぶ首都圏を形成している。有楽町にあった東京都庁は1991年新宿に超高層の新庁舎が完成し,移転した。
→江戸 →武蔵国
地形と気候
東京都の陸地部の地形は,関東平野の南西部を占め,西は標高1500~2000mの関東山地,東は20~180mの武蔵野台地が大部分を占め,西から東へ向かって階段状に低くなる比較的単純な構造である。台地東側の荒川(隅田川),中川(古利根川)沿いと南側の多摩川沿いに若干の沖積低地があり,多摩川の南岸には多摩丘陵がある。また,南の太平洋上には伊豆諸島,小笠原諸島の火山島群が南北に細長く点在する。気候は表日本気候区に属し,都心部の年平均気温は15℃。夏季は小笠原気団におおわれて高温多湿であるが,冬季は北西季節風が卓越して乾燥し,気温もかなり低くなる。太平洋上の島嶼部は南半が亜熱帯気候区に属し,北半も黒潮に洗われるためいずれも冬季に温暖で,年平均気温は八丈島で18.1℃,小笠原諸島では22.6℃と高い。年平均降水量は都心部で約1500mm,島嶼部で約3000mmである。
執筆者:井内 昇
歴史
市域の発展と行政区画の変遷
都域はかつての武蔵国の荏原(えばら)郡,豊島(としま)郡,多摩郡の全域と足立,新座(にいざ),葛飾(かつしか)各郡の一部,および伊豆国の伊豆七島(伊豆諸島)にあたる。明治以前は江戸市内ともいうべき〈府内〉と,周辺地域の〈府外〉との境界は,江戸図において朱引線によって示されていた。府外には多くの天領,旗本領が配されたほか,大名領,寺社領などが散在し,伊豆七島は天領であった。1868年(明治1)江戸を支配下に置いた維新政府は5月江戸府を置き,次いで鎮台を置いて寺社,町,勘定三奉行を廃して社寺,市政,民政三裁判所を設けた。さらに7月江戸が東京と改称されたのに伴い,鎮台および関八州鎮将を廃して鎮将府を置き,駿河以東13国を管轄させ,また江戸府を改めて東京府とした。しかし当初の東京府の管轄域は府内の旧町奉行支配地(町地)にすぎず,しだいに広げられていったものの,武家地が正式に管轄下に置かれたのは69年11月であった。なおこの年,東京城が皇城と改められ事実上の遷都が行われている。一方,府外に関しては前年の68年武蔵知県事3名が任命されて旧天領を管轄,翌年各知県事の支配地を小菅(こすげ)県,品川県,大宮県としたが,現都域にはそのほか韮山(にらやま)県,入間(いるま)県,彦根県などの管轄地も混在していた。71年7月の廃藩置県を経た同年末に府県統合が行われて従来の府県はいったん廃止となり,新たに東京府が置かれた。管轄域は荏原,豊島両郡と多摩,足立,葛飾3郡の一部であり,多摩郡の大部分は神奈川県に属した。72年東京府所管の多摩地方も神奈川県に移管したが,まもなく東京府に再編入,その後75-76年に埼玉県下の足立,葛飾両郡の一部が東京府に編入された(南足立郡,南葛飾郡)。次いで78年伊豆七島が静岡県から,80年小笠原諸島が内務省から移管され,さらに93年神奈川県下の多摩地方(当時は西多摩郡,北多摩郡,南多摩郡)も移されて,旧多摩郡全域が管轄下に置かれ,その後小地域の編入は何度かあったものの,ほぼ現在の都域が確定した。
一方,1878年の郡区町村編成法によって東京府は15区6郡(荏原,南豊島,北豊島,南葛飾,東多摩,南足立の6郡。96年南豊島,東多摩両郡が合併して豊多摩郡となり5郡)に編成され,その15区が89年市制特例によって東京市となり,1932年市域拡張でさらに20区が新設された。43年都制が施行され,東京府,東京市を廃して,その全域を管轄域とする東京都が誕生。47年3月区の配置分合により22区となり,同年5月22区は特別区とされた。同年8月23区となり,23区は特別区として現在に至っている。なお小笠原諸島は太平洋戦争の敗戦によって1946年行政権が停止されてアメリカ軍政下に置かれたが,68年に返還されている。
執筆者:狐塚 裕子
東京市の発展
明治初期,〈東京〉と記して,〈とうけい〉と称したこともあった。東京は,過去1世紀余りの歴史においては,戊辰戦争,関東大震災,そして太平洋戦争下の空襲による被災によって三つの時期に区切ることができる。ここで対象とする東京市の歴史は,1868年の遷都から都制が施行される1943年までの75年間である。
幕藩体制を否定して成立した明治新政府は,将軍徳川慶喜追討の大号令を契機とする戊辰戦争の展開の過程で首都の決定をすすめた。討幕派の指導者大久保利通の大坂遷都論,前島密の江戸遷都論,ついで構想された京都・江戸の二京併置論などが提起されるなかで,最終的に政府の方針は江戸遷都に確定した。政府(討幕)軍にとって,それは幕府権力とそれを支持する佐幕派の支配する東日本を抑えるための軍事占領であり,事実,当時の江戸には軍政が施行された。遷都に臨み,政府は京都の民衆やその他の反対の動きを回避するため,江戸を東京と改称したが,その布告には東京への遷都を明記しなかった。さらに政府は諸外国に対して東京の開市を宣言し,東京が商業(貿易)都市ではなく,首都つまり政治都市として発足する方針をとった。明治初期の東京では,欧米諸国の要請により,1867年(慶応3)に幕府が指定した築地居留地が整備され,72年2月銀座・築地地区の大火後,この地区に煉瓦造の洋風市街地が建設され,大通りの道幅も広げられた。同年9月,新橋~横浜間に開通した鉄道(現,東海道本線の一部)は,首都の表玄関と日本最大の開港場とを連結した。欧米の文化は横浜港などを媒介として東京に流入し,82年には日本橋~新橋間に鉄道馬車が開業するなどして文明開化が始まった。
廃藩置県後,政府や東京府は旧諸藩邸を接収して官・軍用地にあて,また富国強兵・殖産興業の方針のもとで官営工場を設立するとともに,陸・海軍省所管の軍事工場や軍事施設も設置していった。他方,近代都市をめざして鉄道網も整備され,83年には現東北本線の一部が開業して上野が東北方面への玄関となり,85年には東海道本線との連絡を目的として現山手線の一部が開業,1925年に環状運転されるようになった。市街地改造論や築港問題も政府や東京府関係者の間で検討され,そうした動きは,1888年以降の東京市区改正事業として,道路(鉄道馬車の普及に伴う道路の舗装と拡張),水道(木管水道から鉄管水道への改良)の整備に結びついた。また星亨らの努力の末,1度は衆議院で可決された東京築港案は築地付近案ではなく,芝浦中心案であった。しかしこの計画は星亨暗殺事件で廃案となった。資本主義の発展は,隅田川以東の江東地区一帯を中心に,印刷,製本や機械,金属加工,雑貨品生産などの民間工業を生み出すと同時に,産業革命のなかで大規模な機械制紡績工場も登場し,とくに日清戦争以降,資本の集中が進んだ。日本資本主義が独占段階へ移行する20世紀初めに東京では,財閥の系列下に産業資本と金融資本が結合し,日本の政治,経済,社会の中心として,人口の集積と経済集中が進行した。その反面,過密,貧困などの社会的矛盾が深まり,いわゆる〈近代〉都市問題も発生した。都市問題は,社会問題(とくに都市スラム)と環境問題(伝染病の流行や公害問題など)に区分できるが,機械制工場を中心とした労働市場の形成が不十分な段階での人口の流入・集中は,都市失業者を増加させ,貧困問題を深刻化させていった。
このころから東京市内の交通機関の中心は鉄道馬車から電車へと移行し,1903年8月品川~新橋間に電車が走った。東京電車鉄道,東京市街鉄道,東京電気鉄道のいわゆる三電会社が相次いで設立され,市内を縦横に路線が伸びていった。しかし3社おのおのの電車賃は市民に評判が悪く,06年9月には3社が合併して東京鉄道株式会社となった。ちなみに3社合併の契機となったのは,東京市電値上反対事件(1906年3月)である。日露戦争直後の日比谷焼打事件(1905),東京市電争議(1911)に始まり,護憲運動(1912-13),廃税運動(1912)などの都市民衆運動の展開を背景に,大正デモクラシーの動きは,第1次大戦期の東京の米騒動(1918)に至って,その頂点に達した。
1923年の関東大震災は,死者約10万人,損害55億円(内務省調査)の被害を出し,下町を中心に全市に壊滅的打撃を与えた。〈明治の東京〉は崩壊し,〈帝都復興〉とともに,以後,東京は新たな段階を迎える。内相で帝都復興院総裁を兼任した後藤新平の帝都復興都市計画は,激しい反対のなかで縮小され(当初30億円計上された復興費は12億円に削減),後の東京の発展に禍痕を残した。ちなみにこの計画の基本方針としては,遷都はしないこと,ニューヨーク市政調査会理事ビアードCharles Austin Beard(1874-1948)に委嘱して欧米式の最新の都市計画を採用すること,地主に対して断固たる態度をとることがあった。大震災を契機に近郊の隣接町村への人口移動が始まり,東武,西武,東急,小田急各線の開業や電化が進んで,東京の市街地は西ないし南西部へと急激に膨張し始めた。このようにして東京の郊外では,サラリーマンなどの新中間層の住宅需要に応じて田園都市の造成や周辺農村の乱開発が進んだ。それに応じて,地価上昇や通勤距離の遠隔化,交通の混雑などの都市問題もいっそう深刻になった。32年にはそうした都市化の進展を前提に,周辺5郡を合併して〈大東京〉(合計35区)が成立した。さきに1893年,神奈川県会の反対を退けてそれまで神奈川県の管下にあった三多摩地方を合併し,また98年には特別市制を撤廃して,〈自治〉を獲得するとともに市役所を開設した東京市は,ここに〈大東京〉を実現したことにより,その発展の基礎を固めた。
1929年の経済恐慌は,東京にも多数の失業者を生み出し,不景気のなかで五・一五事件や二・二六事件など,しだいに軍国主義化が進んだ。日中戦争を経て,43年の東京都制の実現は,府・市二重行政の解消という役割も果たしたが,その背後では,市民の自治権拡張運動を圧殺し,東京をアジアの中の〈皇都〉として位置づけようとするファシズム体制下での都市政策の結果であった。
執筆者:石塚 裕道
第2次大戦による壊滅的打撃と戦後の発展
43年に東京は都制を施行したが,翌44年以降アメリカ軍の空襲が頻繁に行われるようになって壊滅的な状況におちいり,空襲を避けるため疎開も進められた。45年8月には東京都の人口は349万人(区部人口は278万人)と戦前最高時の半分以下に減少した。戦後,人々は再び東京に戻りはじめ,復興が軌道にのると地方から東京への流入人口も増加し,53年に東京都の人口は戦前の最高をこえて747万人となった。その後増加率はやや鈍ったが62年には1000万人をこえ,95年現在,1178万人(区部797万人)に達している。一方,区部の西に広がる三多摩地域でも戦後市街地化がめざましく,とくに1940年代から70年代にかけて武蔵野台地上を走るJR中央線や京王,西武など私鉄各線沿いの市町村は衛星都市化して人口が急増し,郡部各町村は次々に市制を施行した。このため70年に北多摩郡,71年に南多摩郡が消滅し,95年現在,西多摩郡が残るにすぎず,旧三多摩地域は現在の26市1郡にあたる。これら三多摩地域と島嶼部を合わせた市部,郡部の人口は,95年現在で381万人である。
東京都の人口急増に伴って区部で各種の過密による弊害が表面化しはじめ,政府は1951年に首都建設法,56年には関東の1都6県に山梨県を加えた範囲を首都圏として建設・整備する首都圏整備法を制定して人口集中の抑制をはかった。しかし,その後も東京都への人口集中が続いただけでなく,東京の市街地は県境をこえて隣接の神奈川・埼玉・千葉3県に拡大した。通勤圏で示される東京大都市圏の範囲は都心から半径約50kmに及び,その範囲の人口は1990年10月現在2920万人(全国の2割以上)に達している。
産業
日本の首都である東京都には立法・行政・司法の中枢機能や,外国の大公使館が集中している。またテレビ,新聞,広告,コンピューター関連などのマスコミや,100以上の大学,80近い短大,そして図書館,美術館,博物館など文化施設の集中も著しい。1人当り都民所得,高額所得者数,1人当り個人預貯金残高,公共下水道普及率,自動車保有台数なども全国1位である。昼間人口が全域で1449万人(1990)に達する東京都は,総生産額が全国の2割に及ぶ日本一の産業中心地でもある。産業別就業人口比(1990)では第2次産業人口28.3%は全国平均に近いが,第3次産業が71.2%と全国一高く,第1次産業は0.5%で最低と,全国で最も巨大な都市的性格をもつ行政区画であることを示している。
(1)商業・サービス業 商店数,従業者数,年間販売額でみる限り東京の商業は全国一であるが,その内容には1975年以降次のような傾向があらわれている。第1に,従業者数,年間販売額などの全国比は隣接の埼玉・千葉両県では上昇しているが東京では低下ぎみである。第2に,小売業販売額の伸びを業種別にみると,レジャーや趣味に関するものなどは伸びているが,生活に密着した食料品などは逆に減少し,業種間に成長格差が生じている。第3に,大型店の伸びは区部より市部,郡部で大きい。サービス業は従来,理容業,洗濯業,公衆浴場などが代表的であったが,最近では広告業,物品リース業,情報サービス業が代表的なものとして全国的に高い比率を占めている。
(2)工業 東京の工業の特色は,事業所数,従業者数では全国一だが,1工場当りの従業者数では全国平均を下回ることである。1994年現在,従業者4人以上の工場数は3万4512(全国比9.0%),従業者数66万6254人(全国比6.4%)で,1工場当り従業者数19.3人は全国平均27.2人に及ばない。製造品出荷額は19兆3770億円で,愛知県,神奈川県,大阪府に次ぎ第4位である。業種別に出荷額をみると,特化係数が高いのは出版・印刷,皮革・同製品,精密機械,電気機械で,低いのは鉄鋼,繊維,化学,木材・木製品などである。1960年代以降東京の工業にあらわれた最も顕著な変化は,工場数はほぼ横ばいなのに従業者数が激減したことである。とくに従業者300人以上の大規模工場は1963年からの17年間にほぼ半減し,94年現在192にすぎない。これは区部の工場新設禁止,地下水くみ上げ禁止などで大工場の立地条件が極度に悪化して区外へ移転し,さらに公的住宅機関がその跡地を集合住宅用地として積極的に買収したため,移転に拍車をかけたことなどによる。このように大工場の区外移転が進む一方,20人以下の小規模,零細工場は多品種少量生産という都市型工業の利点を生かして逆に増加している。
江戸時代に零細な手工業として始まった東京の伝統工業はおもに下町に分布し,明治から現在に至るまで業種,製品などに変化はあるものの城東地区を中心に家内工業として存続している。明治以後新しく興った近代工業は,原材料の搬入に船を利用できる東京湾岸沿いの下町や隅田川沿い低地に立地した。1880年代に繊維,セメントなどの官営工場が設けられ,90年代に入ると相次いで民間資本の工場も建てられるようになった。鐘淵紡績を代表とする繊維工業がその中心で,ほかに食品,製紙,機械,窯業,土石などの業種がおもなものであったが,少数の大規模工場以外はいずれも中以下の規模であった。明治時代のこれらの工場はほとんどが城東・城北両地区に集中していたが,大正時代に入ると神奈川県の横浜・川崎の工業地帯に続く城南地区に機械工業を中心とする臨海工業地帯が発展しはじめ,とくに第1次大戦後大工場が立地するようになり,東京湾岸には1941年東京港,横浜港,川崎港を合わせた国際貿易港京浜港が開港し,横浜・川崎地区の工業地帯と一体となって京浜工業地帯を形成した。内陸部でも昭和初期に武蔵野,三鷹,田無(たなし)を中心に航空機などを中心とする新しい軍需関連の工業が興り,戦時中に府中,立川,昭島,日野にまで拡大した。戦後の60年以降,首都圏整備計画の一環として八王子・日野地区,青梅・羽村・福生(ふつさ)地区に電気,機械,自動車などの近代工業が導入され,新しい工業地帯が形成されている。八王子市の絹織物や青梅市の夜具地生産の伝統工業があり,戦後一時好況期を迎えたが,その後停滞・縮小の状態にある。
(3)農業 江戸時代から大都市近郊の有利性を生かした農業経営が行われてきたが,現在は市街地化の進展で耕地の壊廃が進み,農家数の減少も激しく,耕地面積,農家戸数,農業粗生産額はいずれも全国最下位である。しかし,現在も都内で生産される野菜は都民総消費量の約1割を占めている。おもな品目はダイコン,ゴボウ,ウドなどで,生産量は少ないが練馬のキャベツ,江戸川のコマツナなどや鉢物などの近郊園芸農業も注目される。しかし,東京の耕地面積の98%(1993)は市街化区域内にあり,今後の営農継続の見通しは明るくない。島嶼部では温暖な気候を利用してさやエンドウ,切花,観葉植物などが栽培・出荷されている。
(4)林業 かつて奥多摩の林業は青梅林業の名で知られたが近年は停滞が続き,現在は良質な杉,ヒノキが少量生産されるにすぎない。
(5)水産業 江戸時代から有名な東京湾のアサクサノリは沿岸埋立てで全滅し,アサリ,ハマグリなどの貝類も生産額は少ない。現在,東京都の水産業は伊豆諸島周辺での漁業が中心で,魚種はアジ,サバ,トビウオ,その他の底魚類など多彩で資源量も豊富だが,天然の良港に恵まれず,漁船の動力化・大型化が遅れ,豊かな漁業資源を十分に活用できないでいる。
交通
江戸時代初めから五街道の起点であった日本橋が,現在も国道1号,4号,6号線などの起点をなしている。1964年の東京オリンピック大会を契機に高速道路の建設が盛んとなり,首都高速道路のほか,都内を起点とする高速道路に東名高速道路や中央・関越両自動車道がある。JRは東京駅を起点とするものに東海道・東北・上越の各新幹線と従来線の東海道本線,中央本線,総武本線,京葉線などがあり,JRの山手線,京浜東北線も通過している。私鉄は山手線の駅を起点にして外側へのびており,主要なものに新宿駅を起点とする京王電鉄京王線,小田急小田原線,西武新宿線,渋谷駅を起点とする東急東横線,京王電鉄井の頭線,品川駅を起点とする京浜急行本線,上野駅を起点とする京成本線,池袋駅を起点とする西武池袋線,東武東上線などがある。都電網に代わった地下鉄網は,日本最初(1927)の帝都高速度交通営団銀座線をはじめ,縦横にはりめぐらされている。東京国際空港(羽田空港)は,千葉県成田市に新東京国際空港が開港(1978)して以来,おもに国内線の起点となった。また東京港は伊豆諸島,小笠原諸島への定期航路や北海道,近畿,四国,九州への長距離フェリーの発着場となっている。
東京都の五つの地域
東京都は(1)中心区部(旧市域),(2)周辺区部(新市域),(3)三多摩都市化地域,(4)三多摩農山村地域,(5)島嶼部の五つに大別できる。
(1)中心区部 1889年東京市になった15区は,その地形的特色からさらに下町と山手(やまのて)に二分される。現在の下町低地のかなりの部分は江戸初期まで東京湾奥部の入江であったが,幕府はこれを積極的に埋め立てて武家屋敷や町家を配し江戸城の守りを固めた。付近は必ずしも居住には適さないところであったが,水運の便に恵まれ商工業が発達した。明治以降,日本橋や銀座一帯は商業地区となり,1914年東京駅が開業して以来発展した丸の内一帯はビジネス地区,また霞が関一帯は中央官庁が集中する行政地区となり,日本の政治・経済の中心をなしている。ビジネス街,官庁街の集中する千代田区の昼間人口は約85万人(2005)で,夜間人口の20.4倍に膨脹する。東京湾岸沿いの城東・城南地区および隅田川沿いの城北地区は,戦前の東京の工業の中心であったが,一方,千代田,中央,文京,新宿などの都心区では都心業務活動などと結びついた都市型の出版・印刷業が発達している。また60年に決まった〈新宿副都心建設計画〉により,新宿西口の淀橋浄水場跡地付近には東京都庁舎をはじめ,ホテル,オフィスビルなど30階以上の超高層ビルが建ち並び,新都心を形成している。下町地区では明治以後も継続的に海岸部の埋立てが行われ,とくに61年以降,東京港域内で大規模埋立事業が進められ,さらに86年に着工された東京臨海副都心計画によって90年代にレインボーブリッジが完成し,東京臨海交通〈ゆりかもめ〉,東京臨海高速鉄道が開通した。13号埋立地・お台場海浜公園一帯は,国際展示場,ホテル,放送局,住宅団地,複合商業施設の建設が進んで,東京の新名所となった。京浜工業地帯を背後にひかえた東京港は年間貨物取扱量約8700万t(1995。2005は約9200万t)で,首都圏の生活物資の約3割を扱う商業港として重要な役割を果たしている。一方,武蔵野台地東端部にあたる山手台地は開析谷が発達し,坂が多く起伏の多い変化に富んだ市街地がつくり出されている。江戸時代にはおもに武家屋敷と社寺で占められていたが,明治以降は良好な住宅地となった。第2次大戦後,東京の経済機能の充実とともに都心への近接性を求めて業務施設の進出がめざましい。とくにJRや私鉄の各線が集中する池袋,新宿,渋谷の副都心や,JR,地下鉄の各駅周辺に業務地区が広がり,かつての落ち着いた住宅地もマンションなど集合住宅に変わりつつある。
(2)周辺区部 1932年に旧東京市を取り巻く新しい20区が創設された。当時これらの新市域にはまだ農村的性格が残っていたが,戦後著しく都市化が進み,おもに私鉄沿線から始まった市街地化は現在ほとんど全域に及んでいる。練馬,世田谷などの各区ではなお農地が残存するが,周囲を宅地が取り囲み,農家の後継ぎが得にくいこともあって近い将来消失の可能性が大きい。これら新市域は下町と荒川,多摩川の各低地を除けば武蔵野台地上にあり,一般に住宅地として適しているが,都市計画の実施が遅れたため,旧市域に比べると道路,街路その他の都市基盤整備が遅れている。
23区の人口は1965年に最高の889万人に達したあと漸減を示し,1955年代から千代田・中央両区で人口減少が始まり,90~95年には練馬,江戸川両区を除く21区で人口が減少した。この区部人口の減少は,一般に大都市のドーナツ化現象として知られる。東京都区部の人口減少のおもな原因は,旧市域では業務地域の拡大,都市公害などによる生活環境の悪化や地価の高騰などであるが,新市域では地価高騰に起因する住居費の上昇がおもな原因と考えられる。
(3)三多摩都市化地域 三多摩は,旧北多摩郡,旧南多摩郡,西多摩郡(現在3町1村)の3地域からなる。23区の西に続く北多摩地域は標高50~150mの武蔵野台地上に,また多摩川を隔てた対岸の南多摩地域は開析が進んだ多摩丘陵上を占めている。遺跡の分布などからすれば,先史時代には多摩丘陵が居住適地であったと推定できるが,戦後の市街地発展は北多摩でめざましかった。中央本線をはじめ西武,京王など私鉄各線も相次いで輸送力増強を図り地下鉄も乗り入れるなど,都心への時間距離が著しく短縮されたため,北多摩はすでに近郊住宅地化がほぼ全域に及び,さらにその西に続く西多摩地域の青梅線,五日市線に沿う福生,羽村,青梅,あきる野の各市まで通勤圏に組み入れられている。一方,南多摩は交通条件に恵まれず,戦後20年間は開発が進まなかったが,1965年以降,多摩ニュータウンの建設が契機となり,京王線,小田急線も延長されて宅地化が進み,とくに中央本線,横浜線,八高線や京王線の集まる八王子市周辺で顕著である。八王子市は江戸時代以降商工業で栄えた三多摩の中心地であるが,1960年代に首都圏整備計画による工業開発の結果,電気機器,一般機器などの近代工業が発展,さらに70年代以降区部から20をこえる大学が移転し,学園都市の側面ももつようになり,人口も50万人をこえた。戦前に軍都であった立川市は古来交通の要地に発達した商業中心地で,戦後は中央本線のほか青梅線,五日市線,南武線が集中し,東京のベッドタウン化がめざましく,東京都の長期構想では八王子市とともに多摩地方の中核都市として位置づけられ,開発が進んでいる。
(4)三多摩農山村地域 都市化が進んだ三多摩でも,交通の便に恵まれない周辺部はなお農村の状態をとどめている。しかし台地,丘陵上では農地をところどころ残しながら宅地化が進んでおり,近い将来,関東山地の山村以外は大部分が都市化すると見こまれる。関東山地の山間部の檜原(ひのはら)村,奥多摩町はなお山村の面影をとどめるが,主産業の農林業が極度に不振で,近年観光産業の導入が図られている。
(5)島嶼部 伊豆諸島は交通不便な離島の集りである。東京に最も近い大島は三原山を中心とする観光資源に恵まれ,戦前から観光地として開けていたが,八丈島,三宅島,神津島などの6島は戦後まで林業,漁業に頼り,内地から隔離された独自の離島社会を形成していた。戦後,離島振興の一環として港湾や島内道路が整備され,三宅・八丈両島には航空路も開かれ,観光地化が急激に進んでいる。しかし,従来島民の生活を支えてきた林業,漁業,養蚕業や,戦前導入された酪農業などはいずれも不振で,代わって観葉植物や切花などの栽培・出荷が盛んになってきた。小笠原諸島は戦時中に住民が強制的に本土に移住させられ,戦後はアメリカ軍の管理下に入ったが,1968年日本に復帰した。観光業の振興に必要な飛行場が島内にないため週1便の定期航路のみであるが,観光客は増加している。1985年にミカンコミバエの根絶が確認されて農作物が島外に持ち出せるようになり,観光と結びついた果物栽培などが盛んになってきている。
執筆者:井内 昇
東京都の遺跡
東京では古くからの開発と都市化で数多くの遺跡が消滅している。多摩ニュータウン遺跡群(多摩市,稲城市,町田市,八王子市)なども今日の東京の遺跡を象徴しているといえよう。この多摩丘陵から多摩川をはさんだ北側,武蔵野台地の関東ローム層中では近年数多くの先縄文時代の遺跡が調査されている。多聞寺前(たもんじまえ)遺跡(東久留米市),鈴木遺跡(小平市),多摩蘭坂(たまらんざか)遺跡(国分寺市),はけうえ遺跡(小金井市),東京天文台構内遺跡(三鷹市),野川遺跡(調布市)などである。こうした先縄文文化が南関東で最初に確認されたのが茂呂(もろ)遺跡(板橋区)である。
縄文時代では,早期撚糸(よりいと)文系土器群で最古とされる井草式の標準遺跡の井草遺跡(杉並区),同じく早期稲荷台式の標準遺跡の稲荷台遺跡(板橋区)などが学史的にも貴重。早・前期のゾウ遺跡(御蔵島村)や中期の野増(のます)滝ノ口遺跡(大島町)は離島における縄文文化の姿を知るのに重要である。草花遺跡(あきる野市),楢原(ならはら)遺跡(八王子市)などは古くから知られた中期の遺跡である。後・晩期では,E.S.モースの発掘で知られる大森貝塚(品川区,大田区),西ヶ原貝塚(北区),下沼部貝塚(大田区)など学史上著名なものが多い。
弥生時代では,〈弥生〉の名の発祥の地であり,後期中葉弥生町式の標準遺跡でもある弥生町遺跡(文京区),同じく後期前葉久ヶ原式の標準遺跡の久ヶ原遺跡(大田区),それに後期末の集落址で,弥生土器から土師器(はじき)への移行期の土器型式である前野町式の標準遺跡の前野町遺跡(板橋区)などがある。宇津木(うつぎ)遺跡(八王子市)は方形周溝墓という呼称の生まれた遺跡である。
古墳時代では,中期和泉式の標準遺跡である和泉遺跡(狛江市)をはじめ,中田遺跡(八王子市),船田遺跡(八王子市)など大集落址がある。高塚墳としては5世紀中葉の亀塚古墳(狛江市),6世紀代の芝丸山古墳群(港区),5~8世紀にわたる荏原(えばら)古墳群(大田区)などがある。
桐ヶ丘遺跡(北区)はおもに奈良・平安時代の集落址で,多くの墨書土器が出土した。武蔵国分寺址(国分寺市)は古くからの調査により伽藍配置も明らかにされ,瓦窯址の調査も進んでいる。とりわけ文字瓦の出土は全国随一といわれる。
→伊豆諸島 →小笠原諸島
東京都のコラム・用語解説
【東京都】
[官庁街]
[市街地]
[土蔵造]
[オフィス街]
[繁華街]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
事典 日本の地域ブランド・名産品 「東京都」の解説
東京都
[東京都のブランド・名産品]
あかいか | いさき | 稲城の梨 | 江戸甘味噌 | 江戸衣裳着人形 | 江戸押絵羽子板 | 江戸甲冑 | 江戸からかみ | 江戸硝子 | 江戸木目込人形 | 江戸切子 | 江戸指物 | 江戸更紗 | 江戸刺繍 | 江戸漆器 | 江戸簾 | 江戸象牙 | 江戸つまみ簪 | 江戸手描提灯 | 江戸刷毛 | 江戸表具 | 江戸筆 | 江戸鼈甲 | 江戸前あなご | 江戸木彫刻 | 江戸木版画 | 江戸和竿 | 大蔵大根 | 奥多摩わさび | 金町小かぶ | 雷おこし | 亀戸大根 | きんめだい | くさや | 小松菜 | シクラメン | 千住ねぎ | たかべ | 多摩織 | 佃煮 | 東京うこっけい | 東京打刃物 | 東京うど | TOKYO X | 東京額縁 | 東京桐箪笥 | 東京銀器 | 東京くみひも | 東京琴 | 東京七宝 | 東京三味線 | 東京しゃも | 東京染小紋 | 東京彫金 | 東京手植ブラシ | 東京手描友禅 | 東京籐工芸 | 東京仏壇 | 東京紅 | 東京本染ゆかた | 東京無地染 | 人形焼 | 練馬大根 | のらぼう菜 | 八丈たるかつお | 八丈春とび | べったら漬 | 本場黄八丈 | 村山大島紬
出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東京都」の意味・わかりやすい解説
東京〔都〕
とうきょう
人口 1404万7594(2020)。
年降水量 1528.8mm。
年平均気温 16.3℃。
都木 イチョウ。
都花 ソメイヨシノ。
都鳥 ユリカモメ。
日本の首都。本州のほぼ中央,関東地方の南西部に位置する。東西に細長い都域を占め,埼玉県,千葉県,神奈川県,山梨県に囲まれ,南東部は東京湾に面する。 23特別区,26市,1郡 (西多摩) ,4支庁 (大島,三宅,八丈,小笠原) から成り,郡,支庁内に5町8村がある。千代田区丸の内にあった都庁は,1991年新宿区西新宿に移転。長禄1 (1457) 年太田道灌が江戸城を築城,天正 18 (1590) 年徳川家康が入府してから急速に発展,江戸時代を通じて日本における武家政治の中心地となった。明治1 (1868) 年新政府が成立し,2年の明治天皇の再度の東京入り以後首都としての実をそなえはじめた。現在は世界最大級の人口をもち,ニューヨーク,ロンドン,パリ,シャンハイ (上海) などと並ぶ国際的大都市に成長している。中央の諸官庁をはじめとする行政機関や金融機関,大企業の本社などが集中。新聞,放送,出版などの文化面,大学,研究機関などの教育・学術面でも日本の中枢をなしている。交通面でも全国の鉄道網,道路網,航空路の一大中心となっている。西部は関東山地に属し,西端に都内の最高峰,雲取山 (2017m) がそびえ,山岳地一帯は秩父多摩甲斐国立公園に属する。中央部は多摩,狭山の丘陵,武蔵野台地で都心部の衛星都市が多く,大規模な多摩ニュータウンをはじめ,多くの団地が建設,大学も移転進出している。明治の森高尾国定公園および6つの都立自然公園 (滝山,高尾陣場,多摩丘陵,狭山,羽村草花丘陵,秋川丘陵) がある。太平洋上の伊豆,小笠原の諸島はそれぞれ富士箱根伊豆国立公園,小笠原国立公園に属している。江戸の里神楽は重要無形民俗文化財。 (→都制 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「東京都」の解説
東京都
とうきょうと
東京を区域とする地方自治体。東京の地方制度は1889年(明治22)5月の市制・町村制施行以来,市長をおかず府知事がその職務を行うとする東京・大阪・京都の市制特例もかねて議論が多く,首長の官選・公選をめぐり政府・貴族院と衆議院・東京市が対立していた。戦時体制への移行にともない,首都東京の行政一元化・効率化が要請され,1943年(昭和18)7月1日に東京府・東京市を廃止し,東京都制が施行された。都下の市町村に対しては他府県と同様の権能をもち,特別区については市としての権能をもっている。当初は太平洋戦争突入による戦時体制強化のため発足したこともあり,きわめて官治的色彩の強い都制であった。しかし戦後の46年9月,地方制度の民主化の一環として東京都制の画期的な改正が行われ,それまで任命制だった都長官と区長を公選制とし,区の課税権と起債権が認められた。47年4月に統一地方選挙が実施され,公選の都長官が誕生。翌5月3日新しい地方自治法の施行によって,官治色の強かった東京都制は戦後の民主化のなかで廃止され,東京都は他の道府県・市町村と同じように普通地方公共団体として発足し,従来の都長官は都知事と改称された。同時に区は特別地方公共団体として法人格が与えられ,原則としてそれぞれの区は市と同様の自治権をもつ特別区として発足することになった。戦前の区は35区あったが,47年自治権の基盤確立のため適正な面積を基準に特別区の編成替えが行われ23区がおかれた。また町村合併による市制も昭和30~40年代に施行された結果,2013年(平成25)現在で島嶼部を含め23区26市5町8村からなる。都内の人口は62年に1000万人をこえ,その後,一時減少したが,2015年(平成27)4月では1343万人となっており,首都として政治・経済・文化の面で過度の集中がつづき,その対応が東京都の行政にも求められている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東京都の言及
【江戸開城】より
…徳川家は,田安亀之助(徳川家達(いえさと))が相続,駿河70万石に移封され,慶喜も同地へ移った。7月17日,天皇の詔書により江戸は東京と改称され,10月,江戸城も東京城と改められた。【井上 勝生】。…
【首都】より
…イギリスのロンドンも,やはり警察が中央政府の監督の下におかれている。
[日本の場合]
ところで,日本の首都である東京もまた明治以来,中央政府の強い統制を受けてきた。1874年に東京警視庁が設けられて以来,いくたの変遷を経ながらも,中央の任命する警視総監が府知事と対等独立の職として第2次世界大戦敗戦時まで存続した(警視庁)。…
【都市】より
…大都市になると住宅地区内の一部に都心業務を代替する副都心satellite centerが形成されることがある。東京を例にとれば,丸の内の業務地区,日比谷,有楽町の娯楽地区,日本橋,京橋,新橋の中心商業地区,人形町から箱崎にかけての卸売商業地区,隅田川両岸の墨東(江東)工業地区,蒲田,六郷の南部工業地区があり,工業地区を除いたものが東京のCBDとなる。その外側に上野,浅草,池袋,新宿,渋谷,五反田などの副都心がみられる。…
【屋敷】より
…地借・店借のものたちはそれを負担せず,町政・公事にも関与しえず,家持・地主と地借・店借とは身分的に区分されていた。地租改正に先だって,1872年(明治5)いちはやく東京市街地(町地(まちじ),武家地)に地券が交付され,沽券税法の施行をみた。これは,町地(町屋敷,拝領地など種々の土地を含むが,その主要部分は町屋敷),武家地には旧幕時代,さまざまの特典が与えられていたので,それを統一税制下の課税対象に組み込むための措置であり,それを迅速に果たしえたのは,町屋敷には早くから売買・質入れが認められて所有権が成立していたからである。…
※「東京都」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...