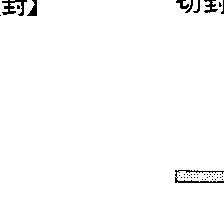精選版 日本国語大辞典 「封」の意味・読み・例文・類語
ふう【封】
ふ【封】
ふう‐じ【封】
普及版 字通 「封」の読み・字形・画数・意味
封
常用漢字 9画
[字訓] つちもる・ほうずる・さかい
[説文解字]



[金文]




[字形] 会意
 (ほう)+土+寸。金文の字形には、上の部分を田に作るものがある。土は土地神たる社主の形で、
(ほう)+土+寸。金文の字形には、上の部分を田に作るものがある。土は土地神たる社主の形で、 (社)の初文。そこに神霊の憑(よ)る木として社樹を植えた。封建のとき、その儀礼によって封ぜられる。〔説文〕十三下に「
(社)の初文。そこに神霊の憑(よ)る木として社樹を植えた。封建のとき、その儀礼によって封ぜられる。〔説文〕十三下に「 侯を
侯を するの土なり。之に從ひ、土に從ひ、寸に從ふ。(寸は)其の制度を守るなり。
するの土なり。之に從ひ、土に從ひ、寸に從ふ。(寸は)其の制度を守るなり。 侯は百里、伯は七十里、子男は五十里」という。字は社樹を封植する形である。〔周礼、地官、封人〕に「
侯は百里、伯は七十里、子男は五十里」という。字は社樹を封植する形である。〔周礼、地官、封人〕に「 そ國を封ずるには、其の
そ國を封ずるには、其の 稷(しやしよく)の
稷(しやしよく)の (ゐ)(壇、お土居の類)を設け、其の四疆を封ず」とあり、〔逸周書、作
(ゐ)(壇、お土居の類)を設け、其の四疆を封ず」とあり、〔逸周書、作 解〕にその具体的な方法についての記述がある。すなわち封建のときには、国の中央に大社を建て、
解〕にその具体的な方法についての記述がある。すなわち封建のときには、国の中央に大社を建て、 の四方に青・赤・白・驪(り)(くろ)の土をおき、中央の黄土と合わせて白茅に
の四方に青・赤・白・驪(り)(くろ)の土をおき、中央の黄土と合わせて白茅に (つつ)み、これを土封する。五行配当の思想を含むが、なお古義を存するところがあろう。周初の〔宜侯
(つつ)み、これを土封する。五行配当の思想を含むが、なお古義を存するところがあろう。周初の〔宜侯
 (ぎこうそくき)〕は、虎侯
(ぎこうそくき)〕は、虎侯 を宜地に封建する儀礼をしるし、「王、宜の宗
を宜地に封建する儀礼をしるし、「王、宜の宗 に立ちて南
に立ちて南 (
( )す。王、虎侯
)す。王、虎侯 に命じて曰く、
に命じて曰く、 (ああ)、宜に侯となれ」と冊命(さくめい)し、礼器や土地・人民を賜与することをいう。その儀礼が、その地の宗社において行われていることが注意される。
(ああ)、宜に侯となれ」と冊命(さくめい)し、礼器や土地・人民を賜与することをいう。その儀礼が、その地の宗社において行われていることが注意される。[訓義]
1. ほうずる、封建、諸侯を任命する儀礼。古くは封土の上に木を植えた。
2. 社の境に土もりする、さかい、さかいする。社のさかいの四方に五色の土をうずめた。
3. 大きい、広い、厚い、ゆたか。
4. 封じる、とじる、ぬる、とざす。
5. 書状、封書。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕封 ツカ・オホキナリ・シルス・アツシ・トヅ・ムカフ・カタム 〔字鏡集〕封 カタム・ワカツ・シルス・カク・シノク・ムカフ・アツシ・ツツム・フセク・トヅ・ツカ・オホキナリ
[声系]
〔説文〕に封声として
 など二字を収める。
など二字を収める。 は〔詩、
は〔詩、 風、桑中〕の〔
風、桑中〕の〔 箋〕に「
箋〕に「 は
は
 (まんせい)なり」とあり、かぶらをいう。封に豊大の意がある。
(まんせい)なり」とあり、かぶらをいう。封に豊大の意がある。[語系]
封piongは
 p
p ng、
ng、 pi
pi mと声の通ずるところがあり、
mと声の通ずるところがあり、 (ほう)や
(ほう)や (へん)は棺を下ろすために土を大きく深く掘ることをいう。封を
(へん)は棺を下ろすために土を大きく深く掘ることをいう。封を の意に用いることもあり、土を掘り、またもりあげることをいう。
の意に用いることもあり、土を掘り、またもりあげることをいう。 (邦)peongはこの封建によって生まれた政治的領域の意である。封にまた豊大の意があり、豐(豊)phiongと声が近い。
(邦)peongはこの封建によって生まれた政治的領域の意である。封にまた豊大の意があり、豐(豊)phiongと声が近い。[熟語]
封印▶・封緘▶・封禁▶・封検▶・封口▶・封号▶・封鎖▶・封識▶・封事▶・封璽▶・封実▶・封書▶・封章▶・封
 ▶・封泥▶・封纏▶・封套▶・封
▶・封泥▶・封纏▶・封套▶・封 ▶・封霊▶・封
▶・封霊▶・封 ▶・封姨▶・封
▶・封姨▶・封 ▶・封域▶・封界▶・封外▶・封畿▶・封圻▶・封境▶・封疆▶・封洫▶・封君▶・封建▶・封
▶・封域▶・封界▶・封外▶・封畿▶・封圻▶・封境▶・封疆▶・封洫▶・封君▶・封建▶・封 ▶・封侯▶・封
▶・封侯▶・封 ▶・封国▶・封冊▶・封豕▶・封祀▶・封爵▶・封樹▶・封獣▶・封植▶・封植▶・封畛▶・封人▶・封簽▶・封禅▶・封壇▶・封地▶・封秩▶・封冢▶・封
▶・封国▶・封冊▶・封豕▶・封祀▶・封爵▶・封樹▶・封獣▶・封植▶・封植▶・封畛▶・封人▶・封簽▶・封禅▶・封壇▶・封地▶・封秩▶・封冢▶・封 ▶・封垤▶・封典▶・封土▶・封内▶・封駁▶・封畔▶・封表▶・封墓▶・封略▶・封勒▶・封禄▶
▶・封垤▶・封典▶・封土▶・封内▶・封駁▶・封畔▶・封表▶・封墓▶・封略▶・封勒▶・封禄▶[下接語]
改封・開封・函封・緘封・畿封・蟻封・丘封・虚封・厳封・侯封・冊封・削封・始封・徙封・賜封・実封・爵封・受封・襲封・譲封・食封・世封・正封・素封・増封・追封・提封・典封・同封・分封・別封・密封・隆封
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「封」の意味・わかりやすい解説
封 (ふう)
あるものを空間的に閉じこめ,内外の空間の間の相互干渉を遮断するためのしるし。この空間は,文書の封のように物理的に設定されたものもあれば,たとえば地震鯰を封じこめるために鹿島神宮の要石によって作られたそれのように,呪術的に設定されたものもあった。文書の場合,現在の封筒のようにして作られた空間の封じ目に,〆や封などのしるしを印判や手書きで加えることによって封が完成するが,このしるし自体に空間を守る呪力がそなわっており,したがって封印で守られる空間も単なる物理的なそれではないと意識されていたところに,前近代の封の特質がある。文書の封のもっとも簡単なものは,何個もの押印によってすき間なく字面をおおうことにより,文字の改変を防いだ,律令制における公文書の例がある。中世では,訴状の裏に裁判担当者が花押(裏判(うらはん))を加える〈裏を封じる〉方式が出現したが(裏封),これも訴状のすりかえを防止するという意味で封の一種といえる。近世の目安裏判も同様の慣行である。また文書の紙継目に,文書の改変を防止するためにすえられた印や花押は,封印または封判と呼ばれていた。近世になって発達した割印,押切印,千鳥印なども,この継目裏印の延長として理解できよう。継目裏印には〈五大力菩薩〉の印文をもつものがあり,封印に呪力が期待されていたことを物語っている。〈封じ目菩薩〉と呼ばれることもあったこの名号は,戦国から江戸時代にかけて書状の封じ目に書かれることがあったが,これは封じた内容を改変から保護する力がこの菩薩にあると信じられていたからである。封を加える空間の作り方には,書状の場合,古くから切封,結封,捻封(ひねりふう),折封などの封式があった。これらは,書状本体あるいは書状の包紙(封紙)の折り目や結び目に封を加えるもので,糊を使わないのが原則であったが,17世紀中葉から糊封も出現し,さらに江戸時代の末には現在の封筒のような封式も使用されるようになった。
執筆者:高木 昭作
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「封」の意味・わかりやすい解説
封
ふう
古文書学上の用語。封とは、厳密には、文書が受取人に届くまでに開けられないように、封じ目を加えることであるが、広くは、文書の折り方、封の仕方を含めて封式という。書札様(しょさつよう)文書は、普通、本紙(ほんし)・礼紙(らいし)・封紙の三紙からなり、本文は本紙一紙に、または本紙・礼紙の二紙に書く。その後、本紙・礼紙を背中合わせにして重ね、左から折り畳み、それを封紙に包み、上書(うわがき)として宛所(あてどころ)・差出書を書き、折(おり)封・捻(ひねり)封・糊(のり)封(糊封は主として近世)などの封をして相手方に届ける。これが正式な場合であるが、ときには封紙を省略し、本紙と礼紙、あるいは本紙一紙だけで相手方に送ることもある。この本紙または本紙・礼紙に封じ目を加える方法としては、切(きり)封・捻封・結(むすび)封の三つがある。切封・捻封は広く中世にみられる。結封は一部正倉院(しょうそういん)文書にもその例をみるが、近世に多くみられる。中世の書札様文書にあっては、私的な性格の強い文書には封じ目を加えるが、公的な文書にはみられない。
[上島 有]
世界大百科事典(旧版)内の封の言及
【封建法】より
…領主・農民の関係についての荘園法や,主人とミニステリアーレとの関係についての家人法を含む意味に用いられることもないわけではないが,普通には,封建主君と封建家臣との間の人的な関係,および両者の間に授受される〈封〉をめぐる物的な関係を規律する法体系を封建法と呼ぶ。レーン法とも呼ばれる。…
【封禅】より
…中国の帝王がその政治上の成功を天地に報告するため,山東省の泰山で行った国家的祭典。〈封〉と〈禅〉は元来別個の由来をもつまつりであったと思われるが,山頂での天のまつりを封,山麓での地のまつりを禅とよび,両者をセットとして封禅の祭典が成立した。《史記》封禅書には,春秋斉の管仲のことばとして,有史以来,封禅を行った帝王は72人,そのうち管仲の記憶するところは12人であること,天命を受けたうえで封禅は行われること,封禅を行うためには祥瑞(しようずい)の出現が必要であること,が述べられているけれども,後世における仮託の説であろう。…
【手紙】より
…また材料の帛(きれ)により尺素というが,尺は紙の大きさを示すことから,短い文,手紙を意味する。手紙は公文書の,伝達様式によるいろいろの名称に対し(古文書(こもんじよ)),私的な対人間の音信文を指していい,現今では郵便はがきに対して,封書を指していうことが多い。
[文体と様式]
文字のない時代,相手に用件を伝える場合は使者に口上(こうじよう)を述べさせたが,手紙は漢字の伝来とともにもたらされ,漢文の書札様式がそのまま用いられた。…
※「封」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

 〈
〈 〈
〈