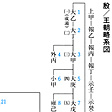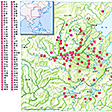精選版 日本国語大辞典 「殷」の意味・読み・例文・類語
いん【殷】
- 紀元前一〇二七年(諸説あり)まで黄河下流域に栄えた中国最古の実在の王朝。王都の名から商とも。伝説上の夏王朝、次の周王朝とともに三代と総称される。→殷墟(いんきょ)
改訂新版 世界大百科事典 「殷」の意味・わかりやすい解説
殷 (いん)
Yīn
中国古代の王朝名。この王朝の存立した時代および文化の名称としても使用する。ただし当時の王朝の人びとはみずからを商と称していたので,殷とよぶよりも,商とよぶのが正確であるが,日本では一般に殷の名を使用する。後の周の人びとが殷とよぶようになるが,その理由は明らかではない。
歴史
殷王朝は,《史記》によると成湯天乙(いわゆる湯王,甲骨文では唐,大乙とよぶ)が,夏王朝の桀(けつ)王を倒して滅ぼし,創設したといわれる。夏王朝の存在は確認されないが,甲骨文の発見によって殷の存在は確認され,王系による逆算と,考古学的年代測定とにより,大乙による王朝の創立は前17世紀末もしくは前16世紀初と推定されるに至った。《史記》や甲骨文によれば,大乙以前に,契(せつ)から振(王亥)に至る7人と,上甲以下示癸までの6人,計13人の先公があるが,これらは殷代に人為的に作られた可能性があり,正確ではない。また大乙以降にも,なお一,二その在位・継承順位が確実でない王がある。大乙は都を亳(はく)(河南省偃師(えんし)県)におき,以後黄河中流域に勢力を保った。しかし前15世紀後半の第10代中丁のときには都を囂(ごう)(河南省鄭州市)に移した。中丁以前を殷前期(代表的遺跡の偃師県二里頭遺跡の名により二里頭期ともいう)とし,以後を中期(鄭州市二里岡遺跡により二里岡期ともいう)とする。
《史記》によると,中丁以降第18代陽甲のときまで,王朝内部に王位継承をめぐる争いが激しく,王朝の力が衰えたという。甲骨文によっても,王系の混乱が最も多い時期であることが,《史記》の伝承を裏付けている。しかも第12代河亶甲は相に,第13代祖乙は耿(こう)(河南省沁陽県),さらに庇に,第17代南庚は奄(山東省曲阜県)に都を移したと言われる。このうち相,庇が現在のどこか異説が多いが,いずれも河南中東部,山東西部,安徽北西部の範囲内にふくまれ,中期の殷の政治的勢力範囲の重要部がここにあったことを示し,その範囲が前期より拡大したと言える。
この時期には,中心部である河南でも,周辺部である河北や湖北でも同じように,多数の青銅器を副葬品とし,数人の殉死者をともなう族長墓が造られ,また鄭州市には巨大な城郭が築かれ,地方にも小城郭都市が造られるようになる。これは,社会内部に身分・貧富の差が生じ,貴族階層が出現するとともに,中央のみならず,各地に地方的な政治の中心が形成されたことを示している。この貴族層の出現は,殷王の統治の障害となり,前13世紀初めの第19代盤庚は,貴族層を排除するため,それまでの政治的中心から,北の河南省安陽市北郊に都を移した(この地が当時殷とよばれたとする説があるが,確認されない)。これ以後,第30代帝辛(紂(ちゆう)王)が周によって滅ぼされる前11世紀後半までを後期(安陽市北郊の小屯村遺跡により,小屯期ともよぶ)とする。第22代武丁は,河南北部,河北南部,山西中・北部の異部族を攻め,これを西方に移動させ,王朝の勢力を西,北に拡大した。前11世紀前半には陝西中部まで直接影響を与えるに至った。この時期殷王の勢力は極盛に達し,政治的・経済的権力を掌握するのみならず,当時行動の規模となる卜占を主宰し,神意を人びとに伝える力をもつと考えられ,死後は神として祭祀され,数十人の殉死者や数百に及ぶ随葬品とともに巨大な王墓に埋葬された。しかし前11世紀後半になると,進攻の方向を一転して,中期に殷勢力の基盤となっていた安徽北部の再征服に力を集中した。このことは殷王朝の内部に動揺を生じさせるとともに,負担の過重から離反するものがあらわれ,その機会をつかんだ陝西中部の周に背後をつかれ,牧野(河南省淇県)で敗れ,帝辛は自殺し,滅亡した。前1050年ごろのことである。
文化
最も特筆すべきことは,金属器すなわち青銅器の鋳造と文字の使用が開始されたことである。青銅の技術が中国で発見されたものか,外来のものであるか,現在では前説をとる学者が多い。前期の時代に,簡単な爵(酒器)や鈴,ナイフなど小型の器の鋳造が始まる。銅,錫の鉱石からの分離,合金としての融合がまだ十分ではないが,石器時代と異なった新しい技術の出現である。中期になると,酒器,食器や兵器など多種類のものが作られ,その表面に饕餮文(とうてつもん)などの文様を表出するようになり,器形も大型化し,高さ1m,重さ82.4kgに達する巨大な方鼎(立方形の調理用器)なども作られた。この時期に青銅器をともなう殷の文化は,陝西北部,山西,山東,湖南,江西まで広がる。しかも土器をはじめ青銅器なども比較的均質であることは,一つの文化が急速に広がったことを示している。一方,この時期にはじまる原始的な磁器や灰釉陶は,長江(揚子江)流域で発達して,北の黄河流域に伝えられたとみられる。後期には,殷の文化圏は,北は遼寧南部,南は湖南南部,西は陝西西部,東は東シナ海沿岸まで達する。この範囲は前221年秦始皇帝が統一したときの範囲とだいたい一致するので,統一の文化的基盤が殷後期に成立したと言える。
青銅器鋳造の技術は最高に達し,巨大な器に細密な饕餮文や夔鳳文(きほうもん),雷文などを表出し,象やフクロウなどの写実的な立体形の器を作る。しかも黄河流域の安陽などを中心とするものが豪壮な気風をもつのに対し,長江流域のものは流麗な風をもつという地方的差も見られる。この時期の青銅器の美術的価値は世界最高である。また江南で開発された漆が,この期には黄河流域でも広く使用されるようになる。西方トルキスタンから玉(ぎよく)が輸入され,美しい玉器が大量に作られる。後期に見られる馬で牽引する戦車も非常に発達した形式のもので,軍隊の中心は戦車によって構成されたほど多数使用されたが,現在のところ中期の遺跡からは車の遺物がまったく発見されないので,完成した戦車の技術が西方から伝えられたのではないかとも言われるが,当時の西域との関係はまったく史料に欠け,不明である。
また後期になり,初めて文字が発見される。これが甲骨文字で,漢字の現存の最古のものであり,それを使って書いた記録の大半が卜いの記録であるので,卜辞ともいう。この文字は,現在,河南省鄭州市の後期の遺跡で数点発見される以外は,すべて安陽市北郊小屯村一帯でしか発見されず,しかも原始的な絵画文字からは進化した文字であり,その祖形は未発見であるため,この文字の起源もやはり大きな問題である。
このほか後期の末近くなると,青銅器の内面に20字から30字位の銘文を鋳出するようになる。内容は,族長たちが,王などから恩賞を与えられた記録であり,初めて個人の功績が意識された。当時の宗教は,最高神としての天(帝とよぶ),雨や実りを左右する自然神と祖先神という3種の神格が見られるが,しだいに祖先神が祭祀の中心におかれるようになり,上甲以下の十干の一つを名とする先王をその即位の順にしたがって,名と同じ十干の日に祭る5種類の祭祀が系統的に行われた。具体的な儀礼などは明らかでないが,この5種の祭祀が一巡するのに360日前後を要し,一巡するのを1祀として数え,王の即位年数を13祀などと表現し,また祭祀表カレンダーによって時を示した。このカレンダーの基礎は太陰太陽暦で,閏月を設けて太陽の運行と調節した(殷暦)。また星などの観察も行われていた。
経済
この時代の経済は農業が中心で,華北では主としてキビ,アワが,江南ではイネ(水稲)が栽培された(コムギは未確認)。これらの穀物を用いた酒の醸造も盛んで,殷が滅亡したのは,人びとが酒におぼれたからだという伝承があり,また青銅器中酒器が非常に多く,形も多様で,セットの基本が酒器であったことが,このことを裏付けている。農具は木製の耒(らい)や石製の鋤・鎌(石刀)などで,新石器時代とほとんど変化はない。青銅製の斧やのみなどは貴族層の兵器あるいは工具として使用されたにすぎない。また施肥や灌漑なども可能性は認められるが,遺跡や遺物での確証はない。したがって王や貴族・神官あるいは青銅器・玉器の技術者の発生・存続を可能にした農業上の余剰生産がどのような方法によって達成されたか重要な問題となっているし,穀物などがどのような方法で租税として徴収されたかも不明である。また当時の繊維製品は,麻が主材料であったが,養蚕による絹織物も生産されていた。王などから家臣に与えられたり,墓から発見される子安貝を貨幣として使用したとする説もあるが疑問である。
制度
甲骨文によると,政治組織として,武官系統と文官系統に大別され,前者には多馬,射,多犬,亜などの集団があり,軍隊には旅,師などの単位があり,いずれも左・右・中の3編成であった。しかしその規模や構成方法などは明らかではない。文官系統には,尹,史,作冊,吏,卿事などの官があり,祭祀や記録を扱ったとされる。また多工,百工,左(右)工とよばれるものもあり,手工業技術に関与した官であると考えられる。このほか卜官があり,これらは世襲のものもあり,王ごとに改めて服属する部族から徴集されたものもある。このほか,小臣,多臣などと称される貴族階層や,殷王室の同族中から選抜編成されたとされる多子,多子族,王族などの集団があり,王命を受けて随時祭祀や軍事上の任務に従事しているが,その構成などは不明である。さらに女官には,婦,多婦とよばれるものがあり,殷王あるいは王子たちの夫人であると言われたり,巫女のようなものであったと言われたりする。ときに軍事上の指揮官をも命ぜられた。このように政治制度などが不明なのは,当時の唯一の史料が卜占の記録で,政治・経済の内容にふれないからである。殷は最古の確認された王朝であり,古代文明であるが,その文化的要素には,なお起源の明確でないものが多い。しかし日常生活の基礎的用具や農業などは新石器時代の文化の延長線上にあり,その発展の経過は遺物によって確認されているので,青銅器技術などを外来的要素とするには注意が必要である。
→殷墟 →殷周美術
執筆者:伊藤 道治
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「殷」の読み・字形・画数・意味
殷
10画
[字訓] さかん・ただしい・あか
[説文解字]

[金文]




[字形] 会意
 (いん)+殳(しゆ)。〔説文〕八上に「樂を作(な)すことの
(いん)+殳(しゆ)。〔説文〕八上に「樂を作(な)すことの んなるを殷と
んなるを殷と ふ」と、楽声の殷々たることをいうとするが、字形からいえば「朱殷(しゆあん)」のように、血の色をいうのが原義であろう。
ふ」と、楽声の殷々たることをいうとするが、字形からいえば「朱殷(しゆあん)」のように、血の色をいうのが原義であろう。 は身の反文。身は妊娠の象。これを殳で殴(う)つのは、何らかの意味をもつ呪的方法と思われる。金文に
は身の反文。身は妊娠の象。これを殳で殴(う)つのは、何らかの意味をもつ呪的方法と思われる。金文に に作り、その呪儀を
に作り、その呪儀を 中で行う。孕んでいる子の、生命力を鼓舞する意の呪儀であろう。
中で行う。孕んでいる子の、生命力を鼓舞する意の呪儀であろう。[訓義]
1. さかん、大きい、ゆたか、多い、深い。
2. 正しい、あたる、ただす。
3. 慇に通じ、ねんごろ、うれえる。
4. 血などの赤黒の色、あか、あかい。
5. 古代の王朝の名、地の名、姓の名。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕殷 サカユ・サカリナリ・サカリニ・オホキナリ・タダシ・ミダル・アヤシ・アカクロナリ 〔字鏡集〕殷 サカリ・サカユ・オホシ・オホキナリ・ミダル・ネムコロ・フルシ・アカシ・アカイロ・モロモロ・ナホ
[声系]
殷・慇i
 nは同声。慇は慇痛。殷はもと身(妊娠の象)を殴つ形で朱殷の意。その義を承ける。
nは同声。慇は慇痛。殷はもと身(妊娠の象)を殴つ形で朱殷の意。その義を承ける。[語系]
殷・慇・隱(隠)i
 nは同声。隱に隠痛の意がある。
nは同声。隱に隠痛の意がある。[熟語]
殷紅▶・殷殷▶・殷盈▶・殷鑒▶・殷墟▶・殷彊▶・殷勤▶・殷見▶・殷
 ▶・殷戸▶・殷厚▶・殷懇▶・殷祭▶・殷雑▶・殷実▶・殷衆▶・殷昌▶・殷商▶・殷賑▶・殷盛▶・殷切▶・殷薦▶・殷然▶・殷湊▶・殷足▶・殷
▶・殷戸▶・殷厚▶・殷懇▶・殷祭▶・殷雑▶・殷実▶・殷衆▶・殷昌▶・殷商▶・殷賑▶・殷盛▶・殷切▶・殷薦▶・殷然▶・殷湊▶・殷足▶・殷 ▶・殷
▶・殷 ▶・殷同▶・殷繁▶・殷富▶・殷阜▶・殷聘▶・殷憂▶・殷雷▶・殷
▶・殷同▶・殷繁▶・殷富▶・殷阜▶・殷聘▶・殷憂▶・殷雷▶・殷 ▶・殷輅▶
▶・殷輅▶[下接語]
戸殷・紅殷・朱殷・衆殷・庶殷・寧殷・豊殷・有殷・隆殷
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「殷」の意味・わかりやすい解説
殷
いん
中国古代の王朝の名称。ただし、自名としては「商」と称し、これを滅ぼした周が前代の王朝を「殷」と称した。現在の中国では「商」とよぶ場合が多い。年代については諸説あるが、ほぼ紀元前17、16世紀の境より、前11世紀なかばごろまでと考えられる。
[松丸道雄]
伝承と甲骨文の発見
『史記』殷本紀その他の古文献によれば、始祖契(せつ)の母簡狄(かんてき)は、有 (ゆうじゅう)氏の娘で帝嚳(ていこう)の次妃であったが、玄鳥(ツバメ)の卵を呑(の)んで契を生み、契は禹(う)の治水を助け、舜(しゅん)によって商に封ぜられて、子姓を賜った、とされる。次代の昭明より第12代主癸(しゅき)(甲骨文では示癸)まで父子相続が行われ、その後、天乙(てんいつ)(成湯(せいとう)、甲骨文では大乙)が継いだ。これ以前、都を8回移したが、成湯のとき、亳(はく)(河南(かなん/ホーナン)省曹県近くか)に移ったのち、夏(か)の桀王(けつおう)を滅ぼし、武王と号し、天子の位についた。ここに殷王朝が始まる。それ以後もしばしば遷都が行われ、成湯から数えて第18代の盤庚(ばんこう)のときまでに5回移った、とされる。第30代帝辛(ていしん)(紂(ちゅう))のとき、国は大いに乱れ、西方に興った周によって滅ぼされたという。
(ゆうじゅう)氏の娘で帝嚳(ていこう)の次妃であったが、玄鳥(ツバメ)の卵を呑(の)んで契を生み、契は禹(う)の治水を助け、舜(しゅん)によって商に封ぜられて、子姓を賜った、とされる。次代の昭明より第12代主癸(しゅき)(甲骨文では示癸)まで父子相続が行われ、その後、天乙(てんいつ)(成湯(せいとう)、甲骨文では大乙)が継いだ。これ以前、都を8回移したが、成湯のとき、亳(はく)(河南(かなん/ホーナン)省曹県近くか)に移ったのち、夏(か)の桀王(けつおう)を滅ぼし、武王と号し、天子の位についた。ここに殷王朝が始まる。それ以後もしばしば遷都が行われ、成湯から数えて第18代の盤庚(ばんこう)のときまでに5回移った、とされる。第30代帝辛(ていしん)(紂(ちゅう))のとき、国は大いに乱れ、西方に興った周によって滅ぼされたという。
このような史書中の伝承が、はたして史実であったか否かについては、長らく不明であったが、1899年、河南省安陽(あんよう/アンヤン)県近くの小屯(しょうとん)という村のわきを流れる洹河(えんが)が氾濫(はんらん)して堤防が崩れ、そこから、文字を刻した亀甲(きっこう)や獣骨の断片が多数発見された。偶然のきっかけから、これらを入手した劉鉄雲(りゅうてつうん)が、この文字を解読した結果、これらのうちに、前記の文献中の殷の王名が多数、読みとられた。これによって、これらが殷代の遺物であること、また逆に、史書中の記述が架空のものではなく、殷王朝が実在したことが確実になった。その後、甲骨片は同地域で多数発見され、1928~37年の間に中央研究院歴史語言研究所の手によって大規模な発掘が行われ、大量の甲骨片とともに、巨大な王墓や宮殿跡、その他無数の遺物、遺跡が発見されて、ここが『史記』にいういわゆる殷墟(いんきょ)であり、この地が、盤庚から末王帝辛までの都址(とし)であろうと考えられるに至った。20世紀、中国考古学、古代史研究における最大の発見といわれる。史書では、これに先行する夏王朝が存在したとされるが、その実在を証明する遺物、遺跡が未発見であるため、現在、殷王朝が中国史上、確認される最古の王朝である。
[松丸道雄]
政治・社会・文化
前述の経緯から、殷代社会、文化の解明のための資料は、甲骨文の解読結果と考古学的知見とにほぼ限られる。甲骨文は、殷王室の卜官(ぼくかん)によって、殷王朝の祭祀(さいし)、農耕、天候、外敵の侵攻と征伐、王の行旅、狩猟、疾病等々、万般にわたって、殷人が人間世界に支配力を有すると考えた天帝に、その神意を問いただすために行われた占いの結果を書き刻んだものである。とりわけ祭祀に関する占卜(せんぼく)が多く、これは、殷王室の先王先妣(せんぴ)のいわば祖先神を対象とした場合と、河、岳など自然神を対象とした場合に分けられる。これらを祀(まつ)ることが政治における秩序形成の中核をなしていたという意味で、祭政一致の政治形態をもったといえよう。王都は、甲骨文中で「大邑(たいゆう)」とよばれているが、これを取り巻く氏族邑が多数存在して支配貴族の住地となり、さらにこれら氏族邑には多数の小邑が隷属していたと考えられる。これらの邑相互の累層的支配隷属関係が国家構造の基本であって、これを邑制国家ないし都市国家とよぶ。王都には、すでにある程度の支配官僚層の形成が認められる。
経済的には農業が中心であったと考えられ、キビ、アワ、大麦などが栽培されたほか、家畜(ウシ、ウマ、ヒツジ、ブタ、イヌ、ニワトリなど)を飼い、また養蚕も行われた。これらのために生産奴隷が使用されたかどうかには、まだ定説がないが、甲骨文中に羌(きょう)とよばれる異族が多数、祭祀の犠牲として用いられており、また発掘される王墓周辺から実際におびただしい殉葬人骨が出土するところからすれば、異族奴隷の広範な存在は否定できない。
文化的にもっとも特徴的なのは、この時期が中国青銅器文化の最盛期にあたっている点である。考古学的には、殷代全期を、前期・二里頭(にりとう)期、中期・鄭州(ていしゅう)期、後期・安陽期に区分するのが通例である。中国史上の青銅器の萌芽(ほうが)は二里頭期に認められるが、中期には早くも大型の精巧な青銅祭器類が多数制作されるようになり、後期に至ると質量ともに驚嘆すべき青銅祭器、武器などがつくられた。外范(がいはん)分割法によって鋳造された青銅器として、技術的に最高の完成度をみせている。かつ、複雑な文様を付して、世界的にみて古代青銅器文化の粋とされる。
こういった殷文明の来源については未解明の部分が多い。いわゆる世界六大文明のうち、メソポタミア・エジプト・インダス諸文明、およびメソアメリカ・アンデス両文明が、それぞれ相互に関係していることは認められている。しかし殷文明のみは、これらとの間にどのような関係があったかについては、今後の解明にゆだねなければならない。
[松丸道雄]
『貝塚茂樹編『古代殷帝国』(1957・みすず書房)』▽『伊藤道治著『古代殷王朝のなぞ』(1967・角川書店)』▽『松丸道雄著「殷周国家の構造」(『岩波講座 世界歴史4 古代4』所収・1970・岩波書店)』
百科事典マイペディア 「殷」の意味・わかりやすい解説
殷【いん】
→関連項目衛|夏|灰陶|輝県古墓群|箕子朝鮮|金石文|周|周公|殉葬|商|青銅器|青銅器時代|禅譲放伐|妲己|鼎|鄭州遺跡|鉄器|銅鏃|銅矛|二里頭遺跡|版築|文王|木槨墓|木棺
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「殷」の意味・わかりやすい解説
殷
いん
Yin
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「殷」の解説
殷(いん)
Yin
商ともいう。前16世紀頃~前11世紀の中国古代の王朝。伝説では大乙(たいいつ)(湯王(とうおう))のとき夏を倒して王朝を創め,第30代帝辛(ていしん)紂王(ちゅうおう)のとき周に滅ぼされた。前半の史実は不明で,第19代盤庚(ばんこう)以後の都とされる殷墟(いんきょ)が発掘によって明らかとなった。殷人は国都の商(大邑商(だいゆうしょう))の周辺黄河中流域の諸族を支配する部族連合国家を形成していた。王位は初め兄弟相続,のちに父子相続に変わった。殷王は祭祀諸政を占卜(せんぼく)によって決する神政政治を行い,王のもとには氏族制による王族・貴族集団があった。これら支配階級は高度の青銅器文化を持ち,軍事を担当し,氏族奴隷を農耕や家事に使っていた。殷墟時代の主業は石器,木器などを使った農業とされる。その交易圏はモンゴル,華南,東南アジアに及んでいる。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「殷」の解説
殷
いん
実在した中国最古の王朝。みずからは商と称す
『史記』の伝説によると,殷の湯王が夏を討って王朝を開き,悪政で名高い紂 (ちゆう) 王が周の武王に滅ぼされるまで30代続いた。初め都は数度変遷したらしいが,後半,安陽県の殷墟 (いんきよ) (大邑商)に落ちついた。殷墟の発掘による遺跡・遺物および甲骨 (こうこつ) 文字の解読によって,王位相続の方法,宗教的色彩の強い社会,占いによる国事の決定(祭政一致),氏族制,木器・石器・土器とともに青銅器を使用した農業,牧畜・養蚕の生活などがわかった。また王の系統,王権の強大さと奴隷の存在などもほぼ確認されたが,文化の系統などには未解明の点が多い。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の殷の言及
【殷周美術】より
…中国の殷・周王朝の時代から秦による統一までを扱う。はじめ夏(か)に天下を治める徳があったとき,遠方の国々は物の図を献じ,鼎(てい)を鋳てその図を彫り込んだ(《左氏伝》)という。…
【帝王陵】より
…
[王墓と帝王陵]
帝王陵の名に値する墓として,あるいは大規模な葬送儀礼が行われたことを示す墓として,かつて問題にされた墓を列挙してみよう。応神,仁徳に代表される古代天皇陵,殷の大墓,秦漢帝国以降の帝陵,朝鮮三国時代から新羅統一時代にいたる陵墓,西アジアのウルの王墓とウル第3王朝の陵,ペルシア帝国の王陵,ハリカルナッソスのマウソレウム,エジプトのマスタバやピラミッドなどが著名である。これらの墓は2種類に大別することができる。…
※「殷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...