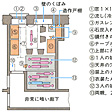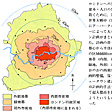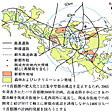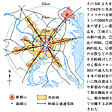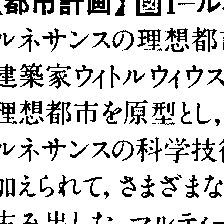精選版 日本国語大辞典 「都市計画」の意味・読み・例文・類語
とし‐けいかく‥ケイクヮク【都市計画】
- 〘 名詞 〙 都市生活を改善し、健康で文化的、機能的な住みよい都市をつくるための計画。都市計画法で定められ、地域・地区・街区の指定、道路の拡幅・新設、市街地の開発、建築の制限などが実施される。
- [初出の実例]「槇町を中心にした都市計画が出来上ると、東京駅付近に繁華を奪はれる」(出典:銀座細見(1931)〈安藤更生〉二)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「都市計画」の意味・わかりやすい解説
都市計画
としけいかく
city planning
都市計画とは、本来的には、都市の持続的な維持・発展を図るために、都市の営みを空間的かつ計画的に制御・コントロールするための総合的な公的・社会的システムである。より具体的にいえば、都市計画は、(1)人間居住の主要な場である都市空間において(対象)、(2)調和ある都市の持続的な維持・発展を目ざして(目標)、(3)都市問題の解決、すなわち生産、交通、居住、福祉、医療、教育、文化、余暇活動などにおける住民生活上の現在および将来の問題の発展的解決を図るために(目的)、(4)公権力としての都市自治体が住民組織、ボランティア団体、NPO(民間非営利組織)など住民セクターおよび企業や経済団体など民間セクターと連携して(主体)、(5)法制、財政、金融など各種行財政制度を総合的に組み合わせながら(方法)、(6)自然・歴史環境の保全と活用、土地利用の規制と誘導、住宅・都市インフラ(インフラストラクチャー、社会的生産基盤)施設の建設と更新、市街地の整備と再生などを計画的に推進する(機能)、(7)都市空間の保全、整備、開発、再生に関する建設・社会技術であり、公的・社会的システムである。
しかし都市が社会的・歴史的存在である以上、都市計画もまた社会的・歴史的存在であるといえる。都市計画の実態的な性格や内容は時代とともに変遷してきたし、今後もまた変化発展していくであろう。したがってここでは、都市計画を、産業革命を契機とする資本主義社会の成立を歴史的画期として、それ以前の都市計画を「前近代都市計画」、それ以降を「近代都市計画」としてまず区別し、さらに現在そこから新しい「現代都市計画」が胎動しつつあるという一つの社会的・歴史的過程としてとらえてみることにする。
[広原盛明 2024年2月16日]
前近代都市計画
前近代都市計画は、(1)王、貴族、領主、教会、修道院、ギルドなど各時代の都市および国家の支配階級による、(2)主として宗教、交易、軍事治安、政治、集会上の、(3)大規模施設の配置と建設に関する空間計画であり、土木建築技術である。それは、支配階級の拠点としての都市の発生と拡大を背景として生まれ、帝国支配の前衛基地である軍事的植民都市の建設を契機として発展した。たとえば古代ギリシアやローマでは、アテネやローマなどの自然成長的都市と、イオニアや小アジアの諸都市などの計画都市の2種類の都市が共存していた。
古代アテネは紀元前5~前4世紀の最盛期には都市域220ヘクタール、人口10万~15万人、人口密度450~680人/ヘクタールという過密都市に成長するが、都市全体は無秩序に支配され、計画的意図はわずかパルテノン神殿を中心とする「アクロポリス」と市場や集会が開かれる自由市民広場「アゴラ」一帯の建築に限定されていた。一方、奴隷はもとより自由市民でさえもその住居は貧しくて密集し、給水設備も便所もなく、狭くて折れ曲がった道路はところかまわずごみや汚物の捨て場と化していた。世界帝国の首都古代ローマは、その帝国支配の必要性から、属国からの莫大(ばくだい)な富と奴隷労働によって軍事道路、橋梁(きょうりょう)、上下水道、公共浴場、公共便所などの軍事土木施設や衛生施設の建設を進め、そのことが3世紀までに都市域2000ヘクタール、人口70万~100万人、人口密度350~500人/ヘクタールという想像を絶する超大都市の形成を可能ならしめた。しかし神殿、凱旋(がいせん)門、闘技場など巨大建築群による都心改造工事が歴代皇帝によって繰り返されたにもかかわらず、都市全体を計画的に制御することはまったく関心の外であり放置されたままだった。貴族など富める者は郊外や田園の快適な別荘に移り住む一方、市民や奴隷は土地建物投機の犠牲となって6~8階にも達する市内の高層集合住宅スラムの中に押し込められていた。集合住宅に対する高度制限(18~21メートル)や狭い道路での昼間車両通行禁止などの規制も行われたが、実効ある措置とはならなかった。
一方、この時代の代表的な計画都市は地中海沿岸に点在するミレトス、プリエネ、オリントスなど古代ギリシアの軍事植民都市、およびイタリアを中心にヨーロッパ一円に建設され、フィレンツェ、ウィーン、トリノ、パリ、ロンドンなど、後の中世都市や近代都市の礎石となった古代ローマの軍事要塞(ようさい)都市である。古代ギリシアの都市国家は、人口が直接民主主義の及ぶ範囲が一定規模超えるときは、兵士を中心に約1万人の植民を派遣して新しい植民都市を建設し、領土拡大を図ることを原則としていた。また古代ローマ帝国は、その広大な領土支配を維持・防衛するためにローマ軍団の兵営地を中核に約35ヘクタール、人口5万人の軍事要塞都市を防衛線に沿って多数計画的に配置した。
周囲を堅固な城壁で囲われたこれらの軍事計画都市は、周辺領土や農地の分割の必要性から発達した測量技術を基礎に、主要街路に従った規則正しい格子状街路網と街区構成をもち、神殿、市場、公共建築物などは主として主要街路が交差する中央部に、住宅は周辺部の街区の中に配置されるという整然とした幾何学的土地利用計画と建物配置計画を有していた。ミレトス出身の政治家であり都市計画家であるヒッポダモスHippodamos(前500ころ―前440ころ)の名にちなんで「ヒッポダモス式都市計画」といわれるのがこれである。このように前近代都市計画は支配階級の拠点施設計画であったため、多数の隷属民を抱えた母都市では部分計画の域にとどまり、周辺領土や農地の支配拠点であった軍事植民都市にして初めて全体計画の段階にまで発展しえたのである。それゆえに支配階級の拠点としての前近代都市は住民多数の生活空間となりえず、支配階級の権力の崩壊は都市の直接的な縮小や崩壊へとつながりやすく、多くの都市がその後廃墟(はいきょ)への道を歩んでいった。
[広原盛明 2024年2月16日]
近代都市計画
近代都市計画は、(1)資本家、地主、官僚など国家および都市支配階級による、(2)無秩序な資本活動の結果発生する疫病、公害、災害、交通難、住宅難など各種都市問題の事後的・部分的改良および都市空間の再編成、資本投資のための、(3)物的環境をコントロールする空間計画であり、土木建築技術および社会経営技術である。近代都市計画はイギリスの近代工業都市にその典型をみるように、18世紀後半以降の産業革命に伴う資本とプロレタリア人口の未曽有(みぞう)の都市集中と都市問題の深刻化を背景に、19世紀後半からの国家・地方自治体による労働者住宅スラムに対する各種衛生法規や建築住宅規制として生まれた。20世紀初頭には都市の急膨張に伴うスプロール開発(無秩序な市街地拡大)に対する土地利用規制、中心市街地の過密・混雑を緩和するゾーニング(用途、機能ごとの区画設定)計画として発展し、第二次世界大戦以降は都市圏全体の開発をコントロールする都市基本計画、マスタープランとしてほぼその形式を整えるに至った。
[広原盛明 2024年2月16日]
事後的・局部的改良の都市計画
前近代社会は基本的に農業社会であり、農村の余剰生産力に支えられ都市人口が総人口の10~20%の範囲を超えることはなかった。しかし機械制大工場制度に基づく資本主義経済の成立は、都市の工業生産力を飛躍的に増大させて大規模かつ急激な都市化を引き起こし、たとえばすでに1801年に96万人の大人口を擁していたロンドンは、1901年には454万人へと、100年間に実に5倍近くに増加して世界最大の都市に成長した。この間イギリスの都市人口は、1750年総人口の20%・100万人から1851年50%・900万人、1901年77%・2850万人へとわずか150年の間に30倍近くに激増し、都市は史上初めて人間の支配的な生活空間へと変貌を遂げたのである。
しかし自由放任経済の下での未曽有の都市化は、工場での過酷な労働条件に加えて、工場、住宅が混在し密集する労働者住宅街を中心に、想像を絶する劣悪で非衛生的な居住環境をつくりだした。そこでは工場からの煤煙(ばいえん)、ガス、悪臭が絶えず住宅街を襲い、工場排水と家庭汚水と屎尿(しにょう)がいっしょになって側溝や河川にあふれ、労働者家族のほとんどは日照、通風の得られない三方が壁の背割り長屋や地下室住宅の一室に閉じ込められていた。衛生状態についてはコレラ、チフスなどの疫病が繰り返し発生し、1000人当りの乳児死亡率が19世紀を通して130~160人台と極端に高く、1875年当時の労働者階級の平均寿命はマンチェスター市17歳、リバプール市15歳という状況であった。こうした労働力の急速な消耗と磨滅、伝染病への恐怖、そして労働者救貧費用の増大が、19世紀なかばから資本家階級をして「公衆衛生法」「職人・労働者階級住宅法」「ロンドン建築法」など一連の都市計画的立法に踏み切らせ、公害、疫病、不良住宅等の都市問題の事後的・局部的改良への第一歩がようやくにして踏み出されたのである。
[広原盛明 2024年2月16日]
「田園都市」構想
近代都市計画の第二歩は、都市の急激な膨張を背景とする20世紀前半から始まった郊外土地利用に関する公共コントロールの導入である。産業革命は交通革命を伴った。蒸気機関車による鉄道網は19世紀なかばまでにイギリス全土にわたってすでに8000キロメートルに達して、人口の都市集中と無秩序な郊外のスプロール開発を押し進め、第一次世界大戦以降は乗合バスの発達と自動車の普及がさらに拍車をかけた。1898年、近代工業都市のアンチテーゼとしてイギリスの都市計画家、E・ハワードによって提案された「田園都市」構想は、スプロール開発への懸念と快適な田園生活環境を望む中産階級に熱狂的に迎えられ、二つの田園都市レッチワースとウェリン(ウェルウィン)・ガーデン・シティがロンドン北方に建設された。この構想の計画・経営理念は、都市と農村の結婚(結合)である。すなわち、(1)都市が工業、商業、農業の各生産手段を所有して職住一体の都市として自立する、(2)土地の共有化によって都市の拡大と土地利用の混乱を防ぐ、(3)田園的環境の中での快適な衛星都市を個人の投資に基づく株式会社組織によって建設し経営する、というものであり、周辺2000ヘクタールの農地に囲まれた都市の規模と密度は中心市街地405ヘクタール、人口3万2000人、人口密度80人/ヘクタールという小規模で低密度のものであった。田園都市は近代都市計画の目ざすべき理念と方向をモデル的に提示した点できわめて大きな意義をもったが、母都市である大工業都市そのものの都市問題解決を対象としえなかった点で歴史的限界をもち、その後ロンドンのハムステッド田園郊外住宅地の開発や、アメリカの近隣住区理論に基づくニュー・ジャージー州ラドバーン計画などにみるように、主として新興中産階級の高級郊外住宅地の経営・計画技術として世界各国に普及していった。
こうした事情から、イギリス最初の都市計画法「1909年住宅・都市計画等法」は郊外開発予定地のみを計画区域に限定しており、「1932年都市・農村計画法」は計画区域を既成市街地の一部にも拡大したが、基本的性格は郊外の住居区域の設定などの土地利用規制とそれに伴う住宅・建築規制すなわち郊外ゾーニング(区分け)計画であり、とりわけ中産階級のための質の高い環境アメニティ(快適さ)の確保に計画の重点が置かれていた。したがってこの段階でのゾーニング計画は、都市の土地利用を全体的にコントロールしていく公共的手段としてよりも、その後のアメリカ都市に典型的にみられるように、中産階級が田園環境アメニティを享受し土地資産価値を維持するための私的な住宅地経営・計画手段、すなわち工場や移民・労働者階級の居住地を排除する「排他的ゾーニング計画」として機能していたのである。
[広原盛明 2024年2月16日]
基本計画としての都市計画
近代都市計画の第三歩は、1929年世界大恐慌を契機とする先進資本主義諸国の経済政策の計画化や、第二次世界大戦下の戦時・戦後経済の計画化などを時代背景として成立した都市のマスタープラン、都市基本計画制度である。資本主義経済が独占段階に発展し、政治・経済中枢である大都市・大都市圏の重要性が飛躍的に増大するにつれて全国的な地域開発計画とともに、大都市圏全体の高度な空間整備が要求され、ここに初めて都市の業務・商業・工業・居住・レクリエーションなど土地利用の全体的・総合的調整、交通運輸・給排水・エネルギー・情報など都市機能を支える都市基幹施設の整備、そして都心部・拠点地区などの再開発事業などを長期的・系統的に進める総合的空間整備計画が成立する。これが都市のマスタープランあるいは都市基本計画といわれるものである。
イギリスでは第二次世界大戦後成立した労働党政府の下で、近代都市計画の集大成ともいうべき「1947年都市・農村計画法」が制定された。この法律は、全国の主要地方自治体に計画権限を与え、統一した様式の開発計画と開発プログラムの策定を義務づけ、開発計画を基にすべての開発を公共的にコントロールするという徹底した計画主義にたっていた。そのうえ開発に伴う地価上昇などの開発利益はキャピタル・ゲイン課税として100%社会に還元するという開発利益の国有化を打ち出し、世界の近代都市計画の戦後法制化の進展に多大な影響を与えたのである。
[広原盛明 2024年2月16日]
日本の近代都市計画
第二次世界大戦前
日本の近代都市計画は1888年(明治21)公布の「東京市区改正条例」に始まる。明治政府によって上からの急速な近代化・資本主義化が図られた日本では、先進諸国に追いつくため、近代統一国家の首都であり、外交交渉の舞台となった東京を、内外に国家的威信を示す東洋第一の通商経済・政治中心都市として近代化する必要に迫られていた。「市区改正」はもともと農村の耕地整理である「田区改正」に対応する都市の市街地改造を意味するが、日本の近代都市計画が「国家による、国家威信発揚のための、帝都改造事業」から始まったことは、その後の日本の都市計画を著しく中央集権的・官治的な性格に傾斜させることとなった。
東京市区改正条例の第一の特徴は、市制施行が目前に迫っているにもかかわらず市区改正を都市自治体の固有事業(自治事務)とせず、国家機関である「東京市区改正委員会」が議定して内務大臣が承認し、東京府知事が執行と経費負担の責任を負うという国家事業としたことである。第二は、市区改正事業の主内容が、新鉄道の拠点東京駅を中核とする霞が関(かすみがせき)中央官庁街と丸の内ビル街を生み出すための用途地域指定と官有地払下げ、および新都心周辺の幹線道路建設(総事業費の70%)とコレラの大流行を背景にした上水道の建設(同28%)など公共土木事業に集中したことである。第三は、この条例が十分な独自財源をもたず、財源難の理由から大阪、京都、名古屋といった六大都市にさえ条例適用が許されなかったことである。
その後、日清(にっしん)・日露戦争、第一次世界大戦を経て日本資本主義が急速に発展し、人口1万人以上の都市人口が1887年490万人(総人口の12%)から1917年(大正6)1854万人(同32%)へと30年間でほぼ4倍増するなど急激な都市化が進むなかで、都市化をコントロールするため東京市区改正条例をほぼ踏襲した「都市計画法」および「市街地建築物法」が1919年に制定された。両法においては、(1)土地用途を住居・商業・工業などに区分し、その上に建築される建築物の種類・高度・床面積などを制限する「地域地区制度」を創設したこと、(2)主として土地所有者の負担で市街地整備を行う「土地区画整理制度」を採用したこと、(3)道路のない未開発地や狭い道路しかない市街地で最小9尺(2.7メートル)幅の道路用地を確保するため、当時は「公費を投ぜずして行う郊外の都市計画」といわれた「建築線指定制度」を導入し、この指定を受けなければ建築不許可としたこと、そして(4)適用自治体を当初の六大都市から全市・指定町村に拡大したことなど、近代都市計画としてのいちおうの体裁が整えられた。
しかし1930年(昭和5)当時、用途地域が決定されていたのは都市計画法適用都市97のうち27都市にすぎず、かつ「工業地域」といえども危険度の高い工場と住宅の混在をそのまま認めるなど土地利用規制はないも同然であった。土地区画整理に関していえば、1930年までに都市計画事業として認可された51件、2172ヘクタールよりも、公共用地の提供が少なくて済み、減歩率(公共用地に提供する土地の割合)が低い耕地整理のほうが544地区、3万3137ヘクタールと格段に多かった。その結果耕地整理、区画整理、建築線指定などによって造成された郊外住宅地は、道路幅員が狭くて公園など公共公益施設がほとんどないという低水準のものが多かった。そして(1)都市計画の策定および都市計画事業の執行を国の事務としたこと、(2)都市計画の議決機関として地方議会を認めず国家機関としての都市計画委員会を中央、地方に設けたこと、(3)国庫補助金や土地増価税(地価の上昇に対する課税)などの都市計画財源を大蔵省や大地主層を中心とする貴族院の反対にあって確保できず地方自治体の負担としたこと、(4)都市計画決定できる都市施設は広範にわたっていたが、中央省庁間のセクト争いによって実際に都市計画事業として整備されるものは道路、河川、運河などごく一部の公共土木事業に限定されていたことなど、その基本的性格はまったく変わらなかった。
日本の都市計画が当初きわめて限定的な役割しか果たしえなかったなかで、不幸にもその活躍の場を与えたのが関東大震災と第二次世界大戦の戦災であった。1923年9月関東一円を襲った巨大地震は1府6県に10万5000人の死者と46万5000戸の住宅滅失をもたらし、東京市だけでも市街地面積の44%にあたる3390ヘクタールを焼失させるなど壊滅的被害を与えた。同年末に成立した特別都市計画法に基づく震災復興都市計画事業は、土地の1割無償減歩を基礎とする公共団体施行の強制的土地区画整理事業を導入して7年間に区画整理3600ヘクタール、道路延長76キロメートル、公園45ヘクタールという大事業を完成させ、東京、横浜の中心市街地改造の一大契機となった。しかし罹災(りさい)者住宅対策のために設立された財団法人同潤会による住宅供給は、仮設住宅を含めても滅失住宅の1.2%、5600戸余りにすぎなかった。また、第二次世界大戦による戦災は全国215都市を罹災させ、全国住宅の5分の1にあたる265万戸と、国富の4分の1にあたる653億円(当時価格)を失わせて都市住民に壊滅的打撃を与えた。なかでも被害の大きかった115都市は、罹災区域6万3153ヘクタール、罹災人口970万人、罹災戸数232万戸、死者33万1000人という惨状であった。
[広原盛明 2024年2月16日]
第二次世界大戦後
1946年(昭和21)制定の「特別都市計画法」に基づく戦災復興事業は、関東大震災時を上回る15%無償減歩の土地区画整理事業を導入して、焼失面積を超過する6万6157ヘクタールの大区画整理事業を計画し、その後の財源不足のなかで縮小されはしたが、102都市で1959年までに当初計画の44%にあたる2万9100ヘクタールの市街地を整備していちおう終了した。こうして全国ほぼすべての戦災都市が住民の戦争犠牲と無償土地提供のうえに区画整理を行い、中心市街地の多くが整備された。「土地区画整理は都市計画の母」といわれるようになったのは、皮肉にもこのためである。
第二次世界大戦前の都市計画法が新都市計画法に移行したのは、すでに戦後20有余年を経過し高度経済成長政策が未曽有の都市化を引き起こしつつあった1968年であった。これら新都市計画法および建築基準法は、都市計画を「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義し、その内容を土地利用規制、都市施設整備、市街地開発事業に3区分した。
土地利用規制は、(1)都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に二分して市街化規制する「線引き制度」、(2)市街化区域内で建築物の用途・形態・容積などを規制する住居系3種類、商業系2種類、工業系3種類の8用途地域と高度・防火・景観地区など特別目的23地区から構成される「地域地区制度」、および(3)大都市地域で市街地整備や住宅地供給促進の特定区域を指定する「促進区域制度」から構成される。
都市施設整備は、道路、公園緑地、上下水道、河川、学校、病院、市場、住宅団地、官公庁施設、流通業務団地など公的性格が強くかつ市街地の骨格を形成する都市施設を「都市計画施設」として決定することにより、施設予定区域内での建築行為を規制し、土地取得の際には土地収用法の適用を可能とするものである。
市街地開発事業は、市街地を面的かつ総合的に開発するための都市計画事業のことをいい、土地区画整理、工業団地造成、市街地再開発など6種類の「市街地開発制度」、これら事業予定区域の制限をあらかじめ行う「市街地開発事業予定区域制度」、および身近な生活環境整備を図るために各種地区施設や建築物の用途・形態、敷地の最小規模などを規制できる「地区計画制度」からなっている。
新都市計画法は、(1)都市計画の決定権限を建設大臣(現、国土交通大臣)から都道府県知事および市町村へ委譲したこと、(2)都市計画の策定に関し公聴会、縦覧、意見書提出などの住民参加規定を設けたこと、(3)都市計画区域を「線引き」することによって「市街化させない区域」の制度化を初めて実現したこと、(4)開発水準を向上させるため「開発許可制度」を創設したこと、(5)用途地域をよりきめ細かくして「地域地区制度」を充実させたことなど、従来の土木施設計画を総合土地利用計画へ発展させた点で、画期的な制度改革と評価された。しかし都市計画が依然として、国土交通大臣が国家の下部機関としての知事に対して都市計画決定の指示権・代行権をもつ、地方議会の議決を要しない国家機関委任事務であること、住民参加規定はあるが住民意見が都市計画決定に反映される保障規定がないことなど、基本的に東京市区改正条例以来の中央統制的性格は変わっていない。
明治以来の懸案であった都市計画財源確保についても、国庫補助金に関する規定はあるがこれを具体化する政令がなく、従来どおり個別事業ごとに各省庁から縦割り補助金が出る割拠体制が続いている。したがって、補助金獲得に有利でない限り基幹都市施設といえども都市計画施設として計画決定されない例も多く、都市としての都市計画事業の総合性、すなわち事業相互間の予算配分や優先性などが担保されているとはいいがたい。また、市街地開発事業もおのおのの根拠法に基づいて計画策定や国庫補助金の決定・執行などが行われており、都市計画法の下に統合されているわけではない。つまり各省庁のエージェンシー(代執行機関)としての自治体各部局によって個別都市計画事業が行われているのであって、地方自治の一環としての都市計画事業が行われているわけではないのである。
土地利用規制については線引き制度や開発許可制度の創設によってスプロール開発規制が意図されたが、(1)市街化区域の線引きが「あるべき都市パターン」を目ざすよりも不動産業者や地主の意向に沿って現状のスプロール開発を追認する形で設定される場合が多いこと、(2)市街化区域で1000平方メートル未満のミニ開発は開発許可を必要としないこと(都道府県の規則で300平方メートル以上の開発まで開発許可制度を適用することは可)、(3)開発が原則として禁止されている市街化調整区域でも20ヘクタール以上の計画的宅地造成であれば「穴抜き開発」が可能であることなど、数多くの問題点を有していた。つまり日本の都市計画は「建築不自由の原則」および「計画なければ開発なしの原則」に基づいて運用されてきたのではなく、「建築自由の原則」を基本的に堅持しながら「開発行為濫用の部分的規制」に関する社会的技術として運用されてきたのである。
[広原盛明 2024年2月16日]
30年ぶりの大改正
その後、都市計画制度は、都心部の土地利用転換を図る「再開発地区制度」(1988)、市街地の居住機能確保と土地利用高度化を進める「住宅高度地区利用計画制度」(1990)、「市町村マスタープラン」(1992)、「高層住居誘導地区」(1997)の創設など幾多の改正を重ねてきたが、2000年(平成12)5月に1968年都市計画法制定以来の「30年振りの大改正」を標榜(ひょうぼう)して都市計画法と建築基準法の一部改正が行われ、2001年5月から施行された。主要な改正点および問題点は以下のとおりである。
第一は、都市計画区域外に「準都市計画区域」が新しく指定され、都市計画区域に準じた規制が行われることになったことである。この都市計画法改正においては、その大前提として第二次世界大戦後の高度経済成長期以来の激しい都市化と都市拡張の時代が終息し、日本は「都市化社会」から「安定・成熟した都市型社会」へ移行したとの認識が繰り返し強調されている。したがって、その論理的帰結としては広大な市街化調整区域(未都市化地域)を縮小・再編するのが筋であるが、改正法では逆に大型商業・レジャー施設が幹線道路沿いやインターチェンジの農村集落周辺で無秩序に立地しつつあるスプロール開発を肯定し、これを「都市の卵=準都市計画区域」とみなして農村地域へ都市地域を広げようとしている。しかも準都市計画区域内での3000平方メートル未満の開発行為は開発許可を要しないし、都市計画区域および準都市計画区域の区域外でも1万平方メートル以上の開発行為には開発許可制度が適用される(開発してもよい)ことになっている。
第二は、区域区分制度の選択化すなわち「線引き選択制」への転換である。もともと都市計画区域内を市街化優先区域と市街化抑制区域に区分する線引き制度は無秩序な市街化(スプロール開発)を抑制するために導入された1968年都市計画法の最大の眼目であったはずだが、都市化が終息した段階では都市化圧力の強い地域を除いてその要否を都道府県の選択に委ね、「すべての都市計画制度の前提」から「都市計画の一つのメニュー」に変えることになった。その結果、都市計画区域内2039市町村(平成大合併前)は、(1)線引きが義務づけられる三大都市圏の特例市および政令指定都市を含む368市町村(都市計画区域内市町村の18.1%)、(2)線引きが選択制へ移行する474市町村(同23.2%)、(3)線引きが未実施で選択制へ移行する1197市町村(同58.7%)となり、都市計画区域内市町村の8割強が線引き選択制へ移行することになった。同時に線引きが存続する市町村の市街化調整区域においては地方条例により開発許可立地基準を緩和し、あらかじめ開発予定地域を定めて開発を認めていくという緩和措置も導入された。また、開発許可に際して開発行為が適合すべき基準(いわゆる技術基準)も条例で緩和することが可能となり、「良好な市街地の形成を図るためのナショナル・ミニマム」を担保する国の責任はどこかに消えた。逆に地方自治体が、これまで乱開発を規制するために独自で運用してきた宅地開発指導要綱に対しては開発業者に過度の負担を強いるものとみなし、地方自治体が法律にない基準を追加したり(横出し規制)、法律の基準自体の上乗せ規制をすることがいずれも禁止された。
第三は、既成市街地の高度利用を図るために「開発権移転」を伴う「特例容積率適用区域制度」が創設されたことである。かねてより既成市街地において指定容積率を限度いっぱいに利用できない状況に対してデベロッパー(開発業者)側から強い不満が出されていたが、この制度は、法定容積率を利用しきれていない敷地(「送り地」)の「未利用容積率」を商業地域など特定容積率適用区域内の他の敷地(「受け地」)の容積率に上乗せして利用することを可能にするというものである。もともと既成市街地の容積率は都市集中の継続を前提とした過大な容積率が指定され、土地利用の混在を容認する現行用途地域制度の下では商業ビルや高層マンションの建設に伴う近隣紛争が多発していた。したがって安定・成熟した都市型社会の下では「ダウンゾーニング」(容積率の引下げ)こそが求められる本来の改正方向であったが、逆に未利用容積率の移転・売買を通してさらに既成市街地の高度利用を推進しようとする方向が強化された。
第四は、市町村のマスタープラン=「市町村の都市計画に関する基本的な方針」をコントロールする「都道府県都市計画マスタープラン」が法定化されたことである。当初、都道府県マスタープランは農山村地域すべてを都市計画制度の枠組みに組み入れ、都市的土地利用と開発可能性を全国土に拡大していくために都道府県全域を覆うものとして構想されていた。しかし、農水省をはじめ都道府県の一部からも強い反対意見が出されたため「都市計画区域マスタープラン」に後退して「(方針)都市計画」となったが、市町村の基本方針や都市計画がそれに即して定められるべき「上位都市計画」であることには変わりない。したがって、これまで比較的自由に制定されてきた市町村マスタープランは、今後は都道府県マスタープランの制約の下に置かれることになり、市町村が定める都市計画は知事との「同意付き協議」が義務づけられることになった。
第五は、都市計画決定手続に関する改正、とりわけ住民参加権限の強化に関してはほとんどみるべき内容がないことである。国土交通省は都市計画法改正の解説において「都市計画は究極的には住民自治に基づくものであるとの考えの下、住民にもっとも近い市町村を都市計画決定の基本主体とするとともに、旧法の時代以来、国を都市計画決定の主体としていたシステム、つまり旧法においては国が直接決定するシステム、昭和43年法においては都道府県知事が国機関委任事務すなわち国の代行者として決定するシステムであったものを、都市計画決定を市町村または都道府県の自治事務すなわち地方公共団体の本来の事務であり、それぞれの地方公共団体が基本的には自己の判断および責任に基づき決定するというシステムに変換するという、大きな思想転換を行いました」と述べている。しかし公聴会における住民の意見具申や異議申立てを都市計画決定に反映させる法的措置や権限が規定されていないこと、都市計画が地方自治体の自治事務であるとしながら地方議会が都市計画決定から排除され、「付属機関」にすぎない都市計画審議会が決定機関とされていること、都道府県の都市計画決定に対して市町村が異議ある場合の相互同意規定や法的処理方法がないこと、自治事務としての都市計画行政を推進するための独自財源についてはまったく言及されていないことなど、国が基本的な都市計画決定権限を掌握して都道府県を後見し、都道府県が市町村をコントロールする体制は明治以来、基本的に変化していない。
ただし、2009年地方分権改革推進計画においては、都市計画区域、区域区分、用途地域、都市施設、市街地開発事業を決定する権限が、都道府県から市町村にほぼ移譲されることになった。これにより「まちづくり条例」という名の法律が市町村によってつくられることが可能になり、独自の都市計画策定を目ざす自治体も現れるようになった。しかし、この場合においても、国が「都市計画運用指針」(2000年初版発行、2023年時点第12版、362ページ)と題する参考資料を発行して、市町村を実質的にコントロールする仕組みは継続されている。
[広原盛明 2024年2月16日]
近代都市計画から現代都市計画へ
都市人口が農村人口を凌駕(りょうが)して都市が人間の支配的な生活空間であり永続的存在へと転化したときから、都市計画は前近代都市計画のように一部支配階級のための土木建築技術であることが許されなくなった。近代都市において都市住民の多数者である労働者階級の居住地が初めて都市計画の対象となったのはこのためである。しかし近代都市計画が資本活動に基づく開発行為をコントロールして都市問題を解決しえたかというと、そうとはいえない。むしろ1980年代後半からは、都市計画を自由な資本活動への制約とみなして、「計画の自由化」や「規制緩和」を主張する「反都市計画主義」ともいうべき新自由主義的傾向が猛威を振るっている。都市計画制度の2000年改正はまさにその象徴ともいうべきできごとであった。
だが、日本型近代都市計画を生み出した20世紀の成長システムは、いまや完全に勢いを失っている。経済成長はバブル経済の崩壊後低迷の一途をたどり、地球環境の制約は国連環境計画の数々の提言にもみられるように、より一段と厳しいものになった。明治以来増加を続けてきた人口は21世紀初頭にピークに達し、日本は半世紀後に総人口が3割減少するという史上初めての構造的な人口減少時代にすでに突入している。地方圏はもとより東京圏以外の大都市圏でも人口減少傾向がしだいに顕在化しており、しかも2020年(令和2)新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)の世界的大流行(パンデミック)以来、ますます加速している。つまり、経済成長と人口集中を背景にした右肩上がりの都市成長は歴史的終焉(しゅうえん)の時期を迎え、地価上昇に基づく開発利益メカニズムは一部の大都市を除いて破綻(はたん)したのであって、ふたたび元の姿に戻ることは考えにくい。
また、1995年(平成7)の阪神・淡路大震災に引き続き、2011年(平成23)3月11日に発生した東日本大震災は、近代都市計画に根本的な変革を迫る歴史的契機となった。
その背景となった事象の第一は、国土を都市部と農村部(農山漁村)に形式的に二分し、都市部の計画は国土交通省(旧、建設省)が所管し、農村部の計画は農林水産省が所管するといった従来の縦割り的計画制度が事実上破綻したことである。東日本大震災においては、被災地域が超広域にわたるため都市部と農村部が連携・協働しなければ地域の復旧復興を実現できず、復興支援活動も復興計画策定も効果的に実施できないことが判明した。また、地域の持続的発展すなわちサステイナブル・デベロップメントを図るためには、都市部と農村部の資源を総合的に活用することなくして地域の環境・経済・社会が維持できないことも明らかになった。すでに2000年代の小泉純一郎内閣による構造改革に伴う平成大合併によって地方自治体とりわけ小規模町村のほとんどが吸収合併され、都市自治体と農村自治体の区別は実質的に消滅している。また、これまで大都市部に限定されていた政令指定都市要件が緩和され、広大な中山間地域を含む超広域政令指定都市も出現している。一つの自治体の中に都市部と農村部が混在するのが普通になり、地域の持続的発展を図るためには、都市部と農村部を包含する都市・農村計画すなわち現代都市計画が求められるようになったのである。
第二は、物的施設整備を中心とする近代都市計画、すなわち「ハードな都市計画=フィジカル・プランニング」の歴史的限界が明らかになったことである。近代都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、主としてテクノクラート(計画専門家、技術官僚)によるハードな土木建築技術体系として制度化されてきた。しかし東日本大震災における巨大地震や巨大津波の襲来は、物的施設計画(ハコモノ計画)に依存する都市や市街地が災害に対して脆弱(ぜいじゃく)であり、大規模災害には十分に対応できないことを示した。都市の持続的発展のためには、物的施設の整備のみならずそれを使いこなせるだけのノウハウとライフスタイル(生活文化)をもった住民の存在が不可欠であり、それを育てる住民主体の「ソフトなまちづくり」の必要性が明らかになった。住みよい安全な都市を維持するための現代都市計画にとって、その主体としての地域住民がどれほど地域に対して誇りと愛着をもち、どれだけ住むためのノウハウを身に付けているかという「まちづくり文化」の存在が鍵になったのである。
第三は、拡大成長型の近代都市計画が名実ともに終焉し、持続発展型の現代都市計画に出番が回ってきたことである。人口減少・少子高齢化が進み、被災地の復旧復興の担い手となる若者層が手薄な東日本被災地では、地域の復旧復興は都市の量的拡大を通してではなくコンパクトで良質な「都市の質」の確保によって実現することが求められている。持続発展型の現代都市計画とは、都市の規模拡大を目的とするのではなく、都市の調和ある成長やそこに実現すべき「都市の質」を重視する都市計画である。それは地域住民による高度経済成長以来の自然・歴史文化財保護運動や居住地改善・まちづくり運動の経験を通して地域社会に蓄積され、基本的人権としての「環境権」「居住権」「まちづくり権」などの理論構築を伴いながら、市民参加・住民参加を基礎とした現代都市計画制度として、しだいに成熟してきている。このように現代都市計画は近代都市計画のなかから生まれ、その成果と遺産を受け継ぎつつ同時にその歴史的制約をも越えていこうとする地域住民の社会運動であり、地域・自治体運動といえるであろう。21世紀は、本来的な都市計画が「現代都市計画」として初めて登場する歴史的画期なのである。
[広原盛明 2024年2月16日]
『大塩洋一郎編著『日本の都市計画法』(1981・ぎょうせい)』▽『ラトクリフ著、大久保昌一監訳『都市農村計画』(1981・清文社)』▽『渡辺俊一著『比較都市計画序説』(1985・三省堂)』▽『石田頼房著『日本近代都市計画の百年』(1986・自治体研究社)』▽『原田純孝編著『現代の都市法』(1993・東京大学出版会)』▽『日本都市計画学会地方分権研究小委員会編『都市計画の地方分権』(1999・学芸出版社)』▽『日笠端著『都市基本計画と地区の都市計画』(2000・共立出版)』▽『簑原敬編著、小川富由他著『都市計画の挑戦――新しい公共性を求めて』(2000・学芸出版社)』▽『原田純孝編著『日本の都市法Ⅰ・Ⅱ』(2001・東京大学出版会)』▽『都市計画法制研究会編著『改正都市計画法の論点』(2001・大成出版社)』▽『福川裕一他著『持続可能な都市』(2005・岩波書店)』▽『高見沢実編著『都市計画の理論――系譜と課題』(2006・学芸出版社)』▽『広原盛明著『日本型コミュニティ政策――東京・横浜・武蔵野の経験』(2011・晃洋書房)』▽『日本都市計画学会編『都市計画293号――日本都市計画学会60周年記念号』(2011・日本都市計画学会)』▽『蓑原敬他著『これからの日本に都市計画は必要ですか』(2014・学芸出版社)』▽『小林敬一著『都市計画変革論――ポスト都市化時代の始まり』(2017・鹿島出版会)』▽『岩見良太郎他著『住民主権の都市計画――逆流に抗して』(2019・自治体研究社)』▽『響庭伸著『平成都市計画史』(2021・花伝社)』
改訂新版 世界大百科事典 「都市計画」の意味・わかりやすい解説
都市計画 (としけいかく)
都市計画は都市というスケールの地域(都市圏)を対象とする物的計画physical planningである。都市の将来の目標を設定し,生産,居住,休息,交通など人々の経済的・社会的活動を安全に快適に効率よく遂行せしめるために,各構成機能が要求する空間を平面的・立体的に調整して,住宅地,商業地,工業地,農地山林など土地の利用と,道路,鉄道,公園,上下水道,建築物など施設の配置と規模を決定し,総合的な考え方にたって構成する計画をいう。また,これを実現する手段・方法を含めて都市計画ということもある。都市の総合計画は経済計画,社会計画,物的計画,行財政計画などからなり,都市計画はその一端を担うものである。経済計画と社会計画は都市における人間活動の計画で,非物的計画と呼ばれるが,物的計画はこれに対応して,活動の行われる場を確保し,施設を整備する計画である。行財政計画はこれらの計画を実現するに当たって行政体の行動を裏づける条件を設定する計画である。したがって,非物的計画と物的計画は表裏一体でなければならない。日本の市町村では地方自治法に基づいて,総合的かつ計画的な行政の運営を図るため,議会の議決を経てその地域における基本構想を定めなければならない(地方自治法2条5項)。また,市町村が定める都市計画は,上記の基本構想に即したものでなければならない(都市計画法15条3項)。しかし,中央集権的行政機構や行政の縦割りの支配的な現状では,総合的かつ計画的な行政運営は十分であるとはいえない。
一定の地域に対する物的計画を地域計画という。地域計画はその対象地域の大きさと計画内容によって,国土計画,地方計画,都市計画,地区計画などの各段階が考えられる。一般により広域を対象とする計画を上位計画,より狭域を対象とする計画を下位計画という。上位計画から下位計画へブレークダウンする振分け方式と,下位計画から上位計画へ要求を求める積上げ方式の二つの考え方があるが,いずれにしてもスケールの異なる地域計画間のフィードバックによって,計画の調整を図る必要がある。
最近,経済の発展と技術革新の進行に伴って都市活動が広域化し,都市計画の区域も周辺の農村地域を含むようになり,広域都市圏計画,都市農村計画などの概念が重視されるようになった。また,一方において都市の部分に対する地区計画の重要性もいっそうたかまりつつある。
史的概観
都市を計画し実現するということは古くから行われている。L.マンフォードは都市は人間の文明・文化の象徴であると述べているが,だれが,だれのために,なんの目的で都市を計画したかという点で,それぞれの時代の都市計画は,異なった様相を呈している。
古代においては王侯,貴族,僧侶が都市を支配し,宮殿,神殿,市場を中心に都市が構築された。古代エジプトのカフンは紀元前約3000年にピラミッド建設の工事に動員された奴隷と職工のために建設された都市で,格子状の街区割りをもち,明らかに計画的に建設されたものである。アゴラと称する広場を中心とした古代ギリシアの諸都市,おなじくフォルムを中心とする古代ローマの諸都市,東洋では中国,インドの首都,日本の平城京,平安京などが,古代の計画都市の例としてあげられよう。ヨーロッパ中世の都市の多くは,堡塁としての要素を強く持ち,城壁によって囲まれ,不規則な狭い街路網をもっていた。そして居城,市場,教会を中心に高密度な市街地が形成されていた。ルネサンス期になると商業の発達が著しく,パリ,フィレンツェ,ベネチアなどの都市の人口が増加し,中世の都市の改造が行われはじめた。16~17世紀にかけて,デューラー,スカモッツィなどの理想都市の提案があった。これらは支配階級の権威と防衛とを重視し,都市の形は多角形または星形をとり,市街地は幾何学的な街路パターンをもち,主要な場所には広場が配置されている。17~18世紀になると中央集権的な機構を備えた近代国家が成立し,都市を堡塁とする考えは薄れ,城壁は取りこわされ,モニュメンタルな広場を結ぶ広幅員の直線道路と威風堂々たる街並みの形成,いわゆるバロック風の都市計画が主流となった。1666年大火後に行われたC.レンによるロンドン改造計画,ランファンPierre Charles L'Enfant(1754-1825)のワシントン建設計画,また19世紀になって行われたG.E.オスマンのパリ改造計画などは,いずれもバロック風都市計画の例である。
都市計画思潮
いつの時代にあっても,現実の矛盾や苦難からのがれ,よりよい未来の都市をつくりたいという願望がある。プラトンの《国家》やT.モアの《ユートピア》に代表されるように,哲学あるいは文学的表現をとって理想社会を描き出すものもあるが,レオナルド・ダ・ビンチやデューラーのように,図によって具体的な都市形態を表現したものも少なくない。産業革命以後もこのような理想都市の提案は数多くみられ,そのうちのいくつかの理念は行政にとり入れられたり,民間の開発に組み込まれて今日の都市計画に影響を及ぼしている。
19世紀の初頭からR.オーエンをはじめとする社会改良家たちは,貧困,不衛生など資本主義社会の矛盾の解消を理想社会の実現に求め,支配階級を説得することによってこれを実現しようとした。これらの提案の多くはあまりにも空想的であり,経営に難点があったりして実現しなかった。しかし,労働者の生活へ向けた関心,協同組合方式による運営,都市と農村の結合といった計画志向は当時の世人の注意を喚起し,工場経営者の中には自分の工場を都市の郊外に移して,労働者に対しよい住宅と環境を与えることが望ましいと考え,モデル・タウンを実際に建設するものが現れた。エッセンの製鉄工場が開発したいくつかのクルップ・コロニー(1865- ),キャドバリーGeorge Cadbury(1839-1922)のボーンビルBournville(1895),リーバWilliam Hesketh Lever(1851-1925)のポート・サンライトPort Sunlight(1887)などは有名である。E.ハワードは1898年《明日の田園都市》を出版して田園都市garden cityの理想を説いた。この提案は,都市と農村の結合,土地の公有,人口規模の制限,開発利益の社会還元,自給自足,住民の自由と協力など,多くの特色をもつものであった。ハワードの提案は多くの人々の支持を受け,ロンドンの北方にレッチワースおよびウェルウィンの二つの田園都市が実現した。ハワードの田園都市は世界各国に大きな影響を与え,田園都市に類するもの,あるいは田園郊外garden suburbsが各地に建設された。またこの発想の展開によって衛星都市satellite citiesの概念が登場し,第2次世界大戦後,イギリス政府によるニュータウン政策に引き継がれた。
ハワードの田園都市とならんで,後世に大きな影響を与えたものとして,ル・コルビュジエの理想都市があげられる。彼は1922年〈人口300万人の現代都市〉を発表して以来,次々に新しい発想を展開した。彼の目ざす理想都市は,広大なオープン・スペース,自動車交通のための立体道路,高層建築を機能的に組み合わせ,近代的な都市美を演出しようとするものであった。彼は都市への人口集中と急速に進展する工業化社会の論理に忠実であった。その簡潔な都市論と未来都市の美しい表現は多くの建築家や都市計画家の心をとらえ,大きなセンセーションを巻き起こした。彼の都市計画案がそのまま実現した例は,シャンディガールなどわずかで,ほとんどないといってよいが,今日の都市計画とくに既成市街地の再開発に与えた影響は見のがすことができない。このほかソリア・イ・マータArturo Soria y Mata(1844-1920)やミリューチンNikolai Aleksandrovich Milyutin(1889-1942)によって提案された帯状都市,T.ガルニエ提案の工業都市,ゲッデスPatrick Geddes(1854-1931)の計画理論,F.L.ライトのブロード・エーカー,C.ジッテ,チーム・テン,リンチKevin Lynch(1918-84)の都市設計論など数多くの独創的な理想都市の提案がある。
近代都市計画の発達
現代の都市計画は産業革命以後,資本主義の発達に伴う急激な都市化に対応し,深刻化する都市問題に解決を見いだそうとする社会・経済の流れの中で成長した。このプロセスはイギリスに最も典型的にみられる。18世紀末から19世紀初頭にかけて,農村人口の都市への流入が激しくなり,大都市や工業都市には中小の工場と粗悪な住宅が密集し,悪疫が流行した。このような状態に対して,1839年以降,都市の保健・衛生に関する一連の法律が制定され,これがやがて1851年住居法に発展し,1909年住居および都市計画等法を経て,25年都市計画法の制定に至るという経過をたどっている。
一方,新興工業国ドイツでは1875年にプロイセン建築線法を制定し,1902年にはフランクフルトで土地区画整理の手法が考案され,地区の基盤整備と建築物の規制の制度が確立した。アメリカでは測量技師による道路計画,造園家による公園・緑地計画が先行し,19世紀末,シカゴの世界博を契機に全米に都市美運動が起こり,多くの都市の都心部が整備された。これらの活動を踏まえて,行政が都市計画と本格的に取り組むようになったのは1900年の末ごろからである。アメリカの都市計画で特筆すべきことは,工業化の進展,ビルの高層化,自動車の普及に対応して,高速道路網の整備,地域制zoning(法律または条例によって都市を地域または地区に区分し,敷地規模,および構造物の位置,容積,高さ,形態,用途,建蔽率などを規制する制度)の採用,民間による郊外住宅地の開発規制が進められたことであろう。また,アーサー・ペリーによる1919年の近隣住区論の提唱は有名である。スラム・クリアランスはイギリスでは居住制限法の制定とともに開始されるが,アメリカでは1933年ローズベルト大統領のNIRA政策以後,国民住居法に基づいて本格的に採り上げられることになる。
しかし各国における都市計画の急速な発展は,なんといっても第2次世界大戦以後である。まず各国で都市計画の基本法が体系的に整備された。これは各種都市機能の高度化と交通手段の変革とくに自家用車の普及に対応して,人々が求めるより働きやすく,住みよい都市環境を造成するためには,従来の個別的な計画手法では対応できなくなったためである。これは一方においては広域的な対応と他方,地区ごとのよりきめの細かい対応との両面において進展がみられた。
イギリスでは1946年新都市法,47年都市農村計画法が制定され,有名なニュータウン開発をはじめ,都市再開発事業も盛んに行われるようになった。西ドイツでは60年連邦建設法の制定によって,これまで各州で行っていた都市計画が全国統一されたシステムによって施行されるようになった。アメリカでは全国に都市間・都市内の高速道路網が完成し,65年には従来の住宅政策機関を統合し,住宅・都市開発省(HUD)を発足させ,ニュータウン開発,都市更新,大量輸送機関などに関する施策を一元的に行うようになった。このほか,フランス,オランダ,スウェーデン,カナダなども,新開発,再開発に大きな業績を残した。
日本の都市計画
日本における近代都市計画は明治維新後に始まる。明治政府は文明開化,富国強兵,殖産興業を旗印として,近代国家の建設を急ぐ中で,外に対しては威信の高揚,内に対しては国家権力の象徴としての意味をもつ都市の大規模施設の建設から着手しなければならなかった。したがって外国の都市計画技術の導入は,住民の生活環境整備は二の次にして,外国人居留地のある横浜,神戸,長崎などと帝都である東京の都心部に集中的に行われた。1872年(明治5)の大火で焼失した銀座れんが街の復興は,都市改造事業の最初のものであった。(〈東京[都]〉の項目の別欄〈東京・明治期の街づくり〉を参照)。次いで88年には東京市区改正条例が公布され,皇居周辺と下町の一部を対象として,道路の新設・拡張,河川・橋梁・公園の整備が行われたが,この間に日本の産業革命が進行し,東京,大阪をはじめとする大都市や港湾都市の都市化が急速に進み,1919年に都市計画法と市街地建築物法が公布された。東京をはじめ六大都市はこれらの法律に基づいて,都市計画区域,用途地域・防火地区の指定,幹線道路網等の計画を決定し,やがてその他の中小都市もこれにならった。
1923年の関東大震災は,1府6県下に10万4000の死者と46万5000の住宅の滅失という大被害をもたらした。この復興事業を行うために復興院(総裁後藤新平)の官制が公布された。計画区域は東京の都心および下町を含む区域で,その内容は地域制を実施し,土地区画整理事業を施行し,幹線街路,河川,運河,公園,上下水道などを整備することにあった。このうち最大の経費を要したのは土地区画整理と道路整備で,区画整理は3600haにも及び,その規模は世界に例をみないものであった。この経験により,土地区画整理は日本の都市計画事業の手法として定着していった。なお,24年住宅の復興のため設立された財団法人同潤会は復興住宅のほか,日本ではじめて近代的な鉄筋コンクリート造アパート団地を開発し(同潤会アパート),不良住宅地区改良を行うなど,画期的な業績を残した。
大正末期から昭和初期にかけて,大都市の郊外電鉄の沿線において民間の分譲地の開発が盛んになり,住宅地計画の技術が進んだ。また31年の満州事変以降,旧満州・内蒙古に対する関心が高まり,日本から都市計画技術者の派遣も盛んになった。第2次世界大戦中は軍関係都市の整備事業として山口県光市,姫路市広畑,神奈川県相模原市などで大規模な区画整理事業が行われた。
1945年終戦を迎えたが,全国の戦災都市は120市,全焼全壊家屋は230万戸に及んだ。ただちに戦災復興院が設けられ,再び区画整理方式による復興事業が進められた。事業の成果は都市により著しく異なるが,これにより多くの地方都市の中心部は道路率20~30%,公園率3%を確保してようやく近代都市としての形態を整えるようになった。住宅の応急復興は地方公共団体による公営住宅によって行われたが,ほとんどが木造住宅であった。55年日本住宅公団が設立されてからは,鉄筋コンクリート造による住宅団地の開発が全国的に盛んになり,大都市の周辺地域には公共公益施設を完備した大規模なニュータウンの開発も行われるようになった。一方,既成市街地における駅前地区や工場移転跡地などの再開発事業も盛んになった。
都市計画の理念と施策の大綱
日本の都市が今日おかれている状況からみて,将来の都市計画の目標とすべき点を掲げれば次のとおりである。
(1)市民生活の優先 都市環境の利便性,効率性を高めるだけでなく,安全性,保健性が確保され,さらには自然や文化財の保護,美しい都市景観の創出など人間性の豊かな都市環境を創出することを基本とする。(2)市町村の計画権限の拡充 都市の環境整備には住民の意見を十分に取り入れることが必要であり,市町村がその計画の主体でなければならない。このため,地方自治の本旨をふまえ,計画に関するすべての権限と財源を市町村に与えなければならない。(3)地方の個性の発揮 歴史的条件,地方的伝統をふまえ,住民と自治体の協力によって,独自の新しい文化を生みだす個性のある都市計画を確立する必要がある。(4)科学的裏づけと社会的公平 正確な情報に基づいて計画を策定し,住民の参加のもとに計画を決定し,その実現に当たっては社会的公平の原則を貫くことが重要である。何人も都市計画によって不当な利益を得てはならないし,また不当な損失をこうむってはならない。(5)財産権に対する社会的拘束の強化 計画なきところに開発なしの原則を確立し,すべての開発に対して,地区施設と建築物に対する具体的な計画を義務づけ,これまでのような無計画な市街化を抑制する必要がある。
以上の基本的な考え方に従って,具体的には次のような施策を展開する必要がある。(1)大都市の過大化の抑制と健全な地方都市の育成。(2)広域都市圏計画の推進と多核都市の形成。(3)大都市機能の再編成と抜本的な防災対策。(4)自動車と大量輸送機関のそれぞれの利点を最大限に生かした都市の総合交通体系の確立。(5)緑や水の保全,文化財の保護,美しい都市景観の創出。(6)健全な住宅と生活環境を定常的に供給しうる態勢を確立するため,土地利用計画と地区計画による都市計画制限の強化。
都市基本計画
都市というスケールの地域を対象とする総合的な都市構成計画で,ゼネラル・プランあるいはマスター・プランと呼ばれる。後述する法定都市計画と異なり,計画目標年次が長期(15~20年)で,計画の内容は包括的・弾力的であって,法的拘束力はないが,法定都市計画に方向を示し,ガイドラインとしての機能を果たす。計画立案方式は,(1)区域設定,(2)都市の目標設定,(3)都市計画調査および解析,(4)計画立案,(5)実現のプログラム策定,の諸段階を経て計画が確定される。都市の目標設定では,計画人口,都市の性格,環境の目標水準等を定めることが必要である。また基本計画の内容としては,土地利用計画,交通系統計画,供給処理施設計画,公園・レクリエーション施設計画,公共建造物の計画などが挙げられる。一方,今日においては上記のような施設別の計画だけでなく,安全性,保健性,利便性,快適性の確保といった環境の目標を達成するため,都市計画の内容として,新たに防災計画,交通事故防止計画,公害防止計画,自然保護計画,さらに文化財保全計画,都市景観計画などが組み込まれるようになってきている。また,計画の立案のプロセスにおいて住民の意向を反映させるため,審議会への住民代表,地元専門家,議員などの参加,住民集会,住民に対するヒアリング,アンケートなど,さまざまな形での住民参加のしくみが考えられるようになってきている。
土地利用計画
土地利用は放置すれば各種利用主体間に競合を生じ,経済的要因と社会的要因のみによって定まる。その結果,都市の土地利用に混乱を生じ,都市機能の麻痺を招くことになる。例えば,落ち着いた一戸建住宅地区に風俗営業が侵入したり,高層建築が建てられ,騒音,風紀,日照障害,風害などが発生する。そこで将来の予測に基づいて,公共の利益の視点から各種機能別の立地特性を考慮した合理的な土地利用の将来像を示し,建設活動を誘導することが必要になる。土地利用計画を立案するには,将来人口と将来の都市機能の集積を想定し,これらに必要な土地の量(スペース要求)と都市機能ごとの立地要求を考慮して,土地の用途の配置と土地利用強度(密度)を定める。土地の用途は農地山林など非都市的用途と住宅系,商業系,工業系など都市的用途に分かれる。住宅系はさらに,中高層住宅を主とする地区と低層戸建住宅を主とする地区などに分かれる。商業系はオフィスなどの立地する業務地区と大規模な商業活動を行う商業地区と近隣商業地区などに分かれる。工業系は大規模専用工業地区と中小工場などが立地する地区などに分かれる。また,土地利用強度としては人口密度,建築密度(建蔽率,容積率)が一般に用いられる。
交通系統計画
交通は住宅と職場や消費地,あるいは業務施設の間の人や物の移動のために欠くことのできない機能である。交通系統計画は都市内外に発生する交通需要を予測し,旅客と物資の輸送を円滑に行うための計画である。交通需要は通過交通,都市間交通,都市内交通の三つに分けられ,それぞれ需要特性がある。交通手段は徒歩をはじめとして各種のものがあり,徒歩以外はなんらかの交通機関を利用する。輸送対象は旅客と物資に分けられるが,これらは道路,鉄道,航路,空路などの経路によって輸送される。市街地においては大小の道路が組み合わさって道路網を形成している。道路を利用するものとして,徒歩,自転車,乗用車,トラック,バス,路面電車などがあり,専用軌道を利用するものとして鉄道,軌道,モノレールなどがあり,今後はその他各種の新交通機関の発達が予想される。交通系統計画を立案するには,現在の交通需要の実態を調査によって把握し,これを解析して将来の交通需要の総量を求め,地域別の分布交通を予測し,交通機関別分担を定め,最終的には各交通路線への配分を行う。近年アメリカを頂点として自家用自動車が普及し,これに応じて高速道路,都市内の道路や駐車場の整備が急速に進められてきたが,大都市では自家用車の利用には限界があり,車の利用を制限して大量輸送機関との分担をはかることが交通計画上の大きな課題となっている。また,都市における人間性尊重の主張から自動車と人の交通の平面的あるいは立体的な分離方式,歩行者専用モール,歩車共存方式(ボンエルフ)など道路と周辺の環境をめぐって新しい手法が用いられるようになってきた。
公園緑地計画
都市内にオープン・スペースを確保し,市民の保健・休養の場所をつくり出す計画部門で,樹木や水と都市施設との関係において,自然的要素を主とした都市景観をつくり出す意味においても重要である。オープン・スペースには,(1)市街地の拡大防止,(2)保安,(3)生産,(4)レクリエーション,(5)修景の諸機能があるとされている。緑地の配置については,環状,放射状,複合などいくつかの型があり,これを公園緑地系統park systemと呼んでいる。公園には自然公園,運動公園,普通公園,近隣公園,児童公園など機能によって分けられ,それぞれ利用者の誘致距離に合わせて系統的に配置される。
その他の計画
以上のほか,都市の運営上重要な施設として,上下水道,電気・ガスなど供給・処理施設,学校などの教育文化施設,病院・保育所など保健・福祉施設,市町村庁舎など都市運営施設等の計画があり,さらに都市防災,事故防止,公害防止,自然保護,文化財保全,都市景観など都市環境計画があり,都市の基本計画はこれらを総合した都市構成計画として策定される。
大都市圏計画
ロンドン,ニューヨーク,東京などの大都市は人口,機能の集中が大きく,通勤,通学,物資の流動など都市の経済・社会活動が通常の都市の範囲を超えて広域にわたって展開されている。そこで通常の都市基本計画よりさらに広域の,いわゆる大都市圏計画を設定している。
1944年にアバークロンビーLeslie Patrick Abercrombie(1879-1957)の提案した大ロンドン計画は,中心部から外に向かって,内部市街地,郊外,緑地帯,外周田園地帯の4地帯を区分し,内部市街地から約100万の人口を工業とともに外周のニュータウンおよび既存都市等に分散することを提案した。この提案に沿ってイギリス政府は八つのニュータウンと数多くの拡張都市の開発を行ったが,これだけではロンドンの集中緩和には効果がうすいという考えから,60年以降は東南部イングランドを対象として100km圏の広域計画が提案され,ニュータウン政策に修正を加えた。ニューヨークについては,マンハッタンからほぼ半径100km圏を対象として,1929年に民間団体の地方計画協会Regional Plan Associationが〈ニューヨークとその周辺地域の地方調査〉をまとめて報告し,68年には第2次地方計画書を発表している。これによると目標の2000年における地域内人口は2780万人と推定されている。また,パリ圏整備本部は1965年にパリ市を中心とする3県にわたる基本計画を発表したが,目標年次2000年の人口を1400万人と想定している。この計画の特徴は,(1)既成市街地をはさみル・アーブルに至る2本の並行する都市開発軸を設定,(2)この軸に沿って交通体系を整備し,七つのニュータウンを開発,(3)既成市街地の再開発により,ラ・デファンスをはじめ6ヵ所の副都心を整備,(4)開発軸以外のセクターの開発の抑制,などである。東京については,1956年に首都圏整備委員会が発足し,58年に首都圏整備法に基づいて第1次基本計画を定めた。この計画では東京を中心に半径約100km,1都7県にまたがる区域を対象とし,既成市街地,近郊地帯,および市街地開発区域の区分を設けることとした。近郊地帯は緑地帯として構想されたもので,ロンドンのグリーン・ベルトを範としたといわれる。この計画は改訂されて68年第2次基本計画が策定され,既成市街地の外周およそ50km圏を近郊整備地帯として開発と規制を調整することとなった。続いて1976年には広域多核都市複合体構想を盛りこんだ第3次基本計画が策定された。
地区計画
都市の部分である地区を対象として,その物的環境を整えるための基本計画である。地区計画は都市計画の重要な部分であり,かつ個々の建築や施設の開発を都市計画に結合せしめる重要な役割を担っている。したがって,地区計画は都市基本計画の方針に整合しなければならないと同時に,その枠内において地区内の社会的・経済的要求を十分に折り込んで計画されなければならない。このために計画策定に当たって地区内の利害関係者の参加を欠くことはできない。また,地区計画は地区の基盤施設(道路,公園,駐車場等),学校・病院・集会所などコミュニティ施設,住宅,工場,商店など地区の機能の主体となる建築物が一体的に構成され,単に機能のみでなく,地区景観のデザインを含む総合計画であることが望ましい。地区計画はその立地条件と目的によって,新市街地の開発,既成市街地の再開発,地区の環境保全などに分かれる。また,土地利用計画からみれば,業務地,商業地,住宅地,工業地,あるいは海や河川の沿岸,鉄道や道路の沿線・沿道,あるいは計画区域に含まれる農山漁村や非都市的土地利用の地区にも適用される。
地区計画の立案プロセスは,(1)地区の区域決定,(2)計画目標の設定,(3)調査・解析,(4)計画諸元の決定,(5)地区設計・計画の決定,(6)実現のプログラム作成という一連のプロセスがあり,この間に住民および権利者の参加によって合意を得ることが必要である。地区計画は用地を一括買収するなどして,地区の総合的な開発事業によって実現を図る場合と地区施設の整備と計画規制による誘導によって実現を図る場合とがある。前者については,住宅団地,工業団地,商業地再開発など多くの事例があり,計画技術の蓄積もあるが,後者については地区施設の整備に重点を置くもの,建築物に対する規制を主とするもの,地区環境の保全を目的とするものなどがあり,今後の研究と実績にまつところが大きい。
都市計画の実現
都市基本計画を実現するためには,法律に基づく都市計画(法定都市計画)の決定と,都市計画制限および都市計画事業の実施が必要である。このため,各国でも都市計画法(名称はさまざま)を制定している。多くの先進諸国では都市計画の決定主体は市町村であるが,日本では都道府県知事の決定する都市計画と市町村が決定する都市計画とに分かれる。法定都市計画の内容は国によってかなり相違がある。都市計画事業は道路,公園,上下水道などの都市施設を整備し,あるいは1団地の開発などを行うもので,公共が積極的に用地を取得し,事業費を投入して実現を図る手法であって,これについては国によってあまり差がない。一方,都市計画制限は,開発の主体が原則として民間であって,公共はこれに対して一定の枠組みと条件を付して制限を加えると同時に,条件を満たすものに対して各種の恩典を与えて,民間の開発をできるだけ都市計画に整合せしめようとする手段であって,この手法は国によってかなり相違がある。イギリスでは都市農村計画法に基づいて都市全域を対象とするストラクチャー・プランとその部分である地区を対象とするローカル・プランの2段階の計画があり,裁量の幅の大きい計画許可planning permissionの制度によって開発がコントロールされる点に特色がある。西ドイツでは連邦建設法に基づき全市域を対象とするFプランFlächennutzungsplanと地区ごとの詳細計画Bebauungsplanの運用によって,これらの計画に合致するものにだけ開発の許可が与えられる。アメリカでは国内を統一する都市計画法がなく,州の授権法によって各都市が条例に基づいて都市計画を施行する。またハワイ州を除いては総合的な土地利用規制の制度はない。民間開発を規制する手段としては地域制zoning,敷地割規制subdivision controlが一般に行われている。また,近年,ニュータウンなど大規模開発に対しては計画単位開発規制P.U.D.regulationsの制度を設け対応するようになった。
日本の土地利用計画は,都市計画法,建築基準法およびその関連法に基づいて行われる。都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分け,それぞれの区域に対して整備・開発・保全の方針を定め,一定の規模以上の開発に対しては,開発許可制度によって敷地の区画形質の変更について規制を加え,また市街化区域には原則として地域・地区の指定を行って,敷地ごとに用途,建蔽率,容積率をはじめ各種項目にわたり建築の規制を行っている。日本の都市計画制度の体系には,地区施設と建築物を一体的に整備する地区計画の策定を義務づける制度がない。したがって市街化区域内の小規模な開発は,建築基準法による敷地単位の規制のみで容認される。このため都市の周辺部におけるスプロール現象といわれる散落状市街地が広範に形成され,日常生活に必要な公共施設の整備とは必ずしも整合せず,また既成市街地における宅地の細分化,用途の混合,無秩序な高層・過密化を防止することが困難である。
→国土総合開発 →都市 →都市計画法 →都市交通 →都市再開発 →都市問題 →土地区画整理 →土地利用
執筆者:日笠 端
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「都市計画」の意味・わかりやすい解説
都市計画【としけいかく】
→関連項目内田祥三|環境アセスメント|建築基準法|帯状都市|地域地区制|都市
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画」の意味・わかりやすい解説
都市計画
としけいかく
City planning
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
不動産用語辞典 「都市計画」の解説
都市計画
出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の都市計画の言及
【地域計画】より
…地域の開発,利用,保全などのための計画。対象とする地域の広狭により,国土計画,地方計画,広域都市計画,都市計画などの名称でよばれるが,これらのうち地方計画(地方ブロックないし県ぐらいの大きさの地域の計画)と同義に地域計画という言葉を用いることも多い。 地域計画は,地域社会の生産,環境などの基盤をなす公共・公益施設を整備し,合理的な土地利用を誘導し,またそのために必要な規制を図るなど,人間活動の物的面の環境条件の創出,改善をその中心的な課題とする。…
【町割】より
…また町割の結果できあがった形態をも〈町割〉と呼ぶ。実際には武家地内の屋敷の割りつけ,また宿場町,港町,在郷町などの形態についても〈町割〉を用いることがあり,近世城下町に限定せず,都市内に街路を通して街区および区画を定め,区画内の敷地割を行うこと,いわば〈都市計画〉の意味で広く用いることが多い。その都市計画の結果として成立した街路,街区,町区画などの都市の形態も〈町割〉と呼んでいる。…
【ローマ美術】より
…コンクリートはネロの時代から宮殿などにも使われるようになったが,技術的に完成の域に達するのはハドリアヌスの時代のころと考えられる。
[都市計画]
パラティヌス丘の皇帝宮殿やカラカラ浴場のような大建築では,多くの建物が複合している。全体を構成するさまざまな部分が互いに建築的効果を補い合いながら,全体としての建築のおもしろさをもりあげるためには,周到な組織的計画が必要である。…
※「都市計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...