目次 東洋 中国漢代以降の冠 日本の冠 ヨーロッパ の王冠 元来〈かんむり〉は〈かうぶり〉の音便形であるから,頭にかぶるものはみな冠といえようが,帽や笠あるいは冑と区別してとくに威儀を正したり権威の象徴として用いるものを冠という。冠の起源については不明なところが多い。はじめは布製の帯や月桂樹枝を環状に丸めたものなどとして存在したらしく,王朝時代のエジプトでは布製帯状の,アルカイク時代のギリシア では月桂樹冠の図像が認められる。ただし,単なる髪飾なのか冠としての意味を備えていたものなのかは判断できない。古く前3千年紀前半のウル の王墓から金で花葉をかたどりカーネリアンで飾ったかぶりものが,またトロイア Ⅱ市のメガロン神殿からやはり黄金製のものが出土しているが,これも同様である。帯状のものは,ギリシアにおいて金製の帯に発達してディアデマdiadēmaと呼ばれた。ヘレニズム時代になると貴石を象嵌(ぞうがん)したものが現れ,ビザンティンにおいてこれに立飾がつき,宝石を散りばめるようになって冠として完成した。黒海北岸のスキタイ 王墓からティアラtiaraと呼ばれる冠状金製品が出土している。スキタイと同系のアケメネス朝ペルシア の諸王も冠を愛用したらしく,ビストゥンの石彫に表現されたダレイオス1世は帯に凸字形の立飾をめぐらせた冠をかぶる。この形はササン朝ペルシア でも変わらず,金貨や銀器に表された王の図像においては,さらにゾロアスター教 のシンボルである日月を飾ってある。中央アジアのサカ族の王墓と思われるイシク・クルガンIssyk kurgan(アルマトゥイ東方)から矢の形などの金製の立飾が発見された。これは鎧を装着した状態で埋葬されていたので,立飾はあるいは冑を飾ったものかもしれぬが,とすれば冑も防御具としてだけではなく,一種の権威の象徴として用いられたことになろう。山本 忠尚
東洋 中国では冠帽といい,男子の頭髪を覆い束ねるものをさし,成人に達したらつける。古代は殷周の玉人などによって確かめられ,春秋戦国時代には身分社会の象徴として定着する。秦漢以後の冠帽は,俑や壁画あるいは実物によって確かめられる。概して布もしくは漆塗の織物で頭頂を覆う形式をとり,天子の冠などには玉を垂下する。
漢文化の浸透する以前の匈奴,鮮卑などは頭部を覆ったり周囲を飾る金製の冠を用い,王権の象徴とした。4世紀以降の鮮卑,高句麗,百済,加羅,新羅では,以前の匈奴や鮮卑の制をうけつぎ,歩揺と呼ばれる金片をちりばめた金製の冠を用い,そのほかに羽根をつけたり樺を付した冠があった。とくに古新羅の墳墓からは,多くの金製の優品が発見されている。
古墳時代の日本では,5世紀の遺例として中国遼寧省の鮮卑墓と同じつくりのものが奈良の新沢126号墳から出土している。6世紀以降の遺物は少なくないが,いずれも金銅製冠である。一方,埴輪によって各種の形態をうかがうことが可能であり,朝鮮半島の加羅地方の冠と共通するところが多い。仏像の冠を天冠 とか宝冠と呼ぶが,古墳時代の金銅製冠をとくに天冠と呼ぶ場合もある。7世紀後半になって,隋・唐の冠位制が導入され,それ以降は朝鮮式の冠はすたれていく。町田 章
中国漢代以降の冠 中国の歴代王朝は基本的には漢代の冠制を踏襲したが,南北朝ごろから巾,幘が公式のかぶりものとして採用され,冠は祭服および朝服の一部に残るだけとなった。とくに,隋・唐以後,朝服の冠はほとんど幞頭 (ぼくとう)によって代用され,その制度は7~8世紀の日本や朝鮮の冠服制にも伝えられた。《衣服令》にも〈礼服(らいふく)の冠〉が記されている。五代から宋代にかけての中国では,硬質の幞頭が現れた。これは針金の芯に漆紗を貼り,幞頭の垂紐も漆で固め,これを水平に張りまたは上方に巻き上げ,その形状も直線形のほか円形,楕円形,紡錘形など種々の形が出現した。日本ではこれを〈唐かむり〉または漆紗冠(しつしやかん)などと呼んだ。元代に入ると女子も冠をつけた。皇后や高級女官は顧姑冠というモンゴル女性特有の冠をかぶった。男子も祭服には中国式の冠を用いたが,朝服には固有の帽や笠(りゆう)をつけた。敦煌壁画のなかにも吐蕃王国の貴婦人が宝冠をかぶった姿が描かれているが,チベット やモンゴル,ウイグルなどの遊牧民族 の女性にとって,冠帽の習俗は本来固有のものであった。明朝は中国伝統の冠制とともに,皇后や宮廷女官の祭服・朝服に鳳冠の制をとり入れた。北京近郊の明の十三陵の定陵から発見された金鳳冠がある。清朝は満州族の建てた国であったから,大祭用の冕冠(べんかん )以外はすべて固有の満州式冠帽を採用した。清朝時代の冠服には朝服と吉服があり,男女それぞれ,朝服冠,吉服冠を着用した。さらに,そのいずれにも冬冠と夏冠があった。
朝鮮の統一新羅時代には,金冠のほかに錦冠,紫冠,鳥羽冠や白樺冠があったが,高麗,李朝を通じて,その冠服は宗主国である中国王朝の制度に従った。杉本 正年
日本の冠 日本の上代は男女ともに結髪をし,一般にはかぶりものはなかったが,603年(推古天皇11)冠位十二階 がしかれ,役人は冠をつける風習が生じ,以来,明治時代に至るまで官服には冠を用いた。もっとも冠制ができる以前にも,一部の豪族の間には冠帽を用いる風があり,古墳から発掘されるものの中には金銅製の精巧なものや,埴輪の男子像にも種々のかぶりものをつけたものがある。
冠制で制定された冠は,《日本書紀》によると頂上をとりまとめて袋のようにし,縁をつけたものとあるから,髻(もとどり)の上からかぶり,そこを上からしぼり結んだものであったろう。この冠は位階によって区別があり,徳冠は紫,仁冠は青,礼冠は赤,信冠は黄,義冠は白,智冠は黒の色を用いた。その後647年(大化3)には従来の絁(あしぎぬ)製であったものを錦と絹との2種類とし,織冠,繡(しゆう)冠,紫冠,錦冠の4種は錦製,青冠,黒冠,建武冠の3種は絹製で,縁には冠と違った別裂(きれ)をつけ,背には漆塗の羅(ら)を張った蟬(かざりぐし)のようなものをつけた。これらの冠は大会,饗客(きようきやく),斎時などに用い,別に黒の絹でつくられた鐙冠(つぼこうぶり)という,当時の壺状鐙の形をなしたものがあった。その後,冠の裂地には二,三の変改があったが,天武天皇のときに新たに漆紗冠(しつしやかん)と圭冠(けいかん )とが制定され,前者は唐制にのっとったもので,冠の前後に四つの纓(えい)がついており,前纓は平時は上にあげて髻の前で結び,後纓は垂らすか,あるいは髻の上を結んだひもにはさんだ。これが後世の冠の祖となったもので,当時の形態を知るものに法隆寺伝来聖徳太子 の像がある。また圭冠は上円下方の圭玉の形をしたもので,後世の烏帽子 の祖となった。
奈良時代には礼服・朝服の制が確立して礼冠と頭巾(ずきん)(漆紗冠の系統)とがそれぞれ用いられた。その礼冠の制はつまびらかでないが,平安前期のものは,文官は漆地金製で櫛形や押鬘(おしかつら)があり,茎を立て玉を飾り,額上には四神獣や麒麟(きりん)の像を立て位階を区別した。また武礼冠(ぶらいかん)は箱形の羅を飾り,これに緌(おいかけ)をつけた。このほか天皇の冕冠,女帝の宝冠,童帝の日形冠,皇太子の九章冕冠などがある。
朝服に用いられた冠は,平安朝になるとその形がしだいに整備され,額(ひたい),巾子(こじ),纓というように独立した形をとり,平安時代末の鳥羽天皇ころからはその地質も固くなり,ついにこんにち見られるような冠が成立した。すなわち額,縁(へり),巾子,簪(かんざし ),上緒(あげお),纓,緌,懸緒(かけお)などからなっている。
(1)額 冠の頂にあたる部分。甲ともいう。平安時代末から鎌倉にかけて,その縁の高低によって厚額,薄額などの種類ができ,後者は多く年少者や賤官(せんかん )の者が用いた。また甲に半月形の透しを入れたものを透額(すきびたい),三日月形 をなしたものを半透額といい,壮者の上気の洩れるためであるといわれた。平安時代中期に額充(ひたいあて)というものができ,多くこれを着けたが,後に額がかたく塗り固められるにいたって,従来の羅頭巾のなごりをとどめたものであったろう。
(2)縁 磯ともいう。このような直立した縁ができたものも平安中期以後からのことである。
(3)巾子 髻を入れる具で,これを髻の上から挿して冠をかむる。冠が固くなるとともに,この巾子は冠の内部に固定した。しかし後世でも元服のときには抜巾子(ぬきこじ)の冠といって,巾子の抜けるものが用いられたのはその旧形を残したものである。そして巾子の形も時代によって一様ではなく,平安前期から中期にかけては幅も広く大きな形となり,その巾子のとくに高いものは高巾子冠といって踏歌(とうか)などに用いた。
(4)簪 巾子の前あたりに左右から出ている串状のもので,角(つの)ともいう。この起源には数説があり,一つは冠の落ちないように挿した釘の形式化したものだといい,一つは前纓の巾子の前で結んだ形の硬化したものという。
(5)上緒 巾子の前に細いひも状をなしたものをいう。冠の初期に巾子を上からひもで結び固めたものの形式化したものだと考えられている。
(6)纓 漆紗冠の後纓にあたるもので,平安時代の中ごろまでは,まだやわらかく肩にかかったが,後しだいにかたくなり,両側にクジラの髭(ひげ)を入れて羅を張り,後方に湾曲して垂れるようになった。なお江戸時代の中ごろから天皇の纓は巾子の後に直立し,いわゆる立纓冠(りゆうえいのかん)ができた。纓にはその端が方形をなすものと,円形をなすものとがあったが,後世は一般に方形のものが用いられ,これをなお燕尾(えんび)と称した。皇太子元服 のときにこの燕尾の纓が用いられるのは,その旧形を伝えたものであるといえよう。また武官は本来短い纓を用いたのであるが,平安時代以来,文官で武官を兼任するものが多くなり,武官の冠も文官と区別がなくなり,武官の冠には纓を巻いて夾木(きようぼく )で止めることが行われた。これを巻纓冠(けんえい のかん)という。また文官でも,危急の場合には纓をたたんで夾木で止めることが行われ,これを柏夾(かしわばさみ)と称した。また天皇は烏帽子をかぶることがなかったから,内々では纓を巾子の上に引き起こし,檀紙(だんし)に穴をあけたものでこれを上から挿して止めておいた。この檀紙に金箔をほどこしたものを用いたので,これを金巾子の御冠と称した。これらはみな纓のさまたげになることを避けた方法であった。なおこのほか,纓には細纓というものがあり,これは六位以下の武官や六位の蔵人が,ただ2本のクジラの髭をたわめて挿した。また諒闇(りようあん)や重服(じゆうぶく)のときには縄纓といって1筋は藁,1筋は黒布の縄でつくったものを用いた。
(7)緌 大宝令の武官の服制に見えているもので,五位以上の礼冠,六位以下の頭巾に用いた。中国では纓の端の飾りを緌といい,これに翠羽(すいう)をもってしたことが《晋書》輿服志に見えているが,当時の日本の緌の形態は明らかでない。けだし頭巾の脱落を防いだ実用目的をかねた装飾物であったろう。後世,武礼冠の緌は飾物となり,頭巾の緌は馬の尾で半月形につくったもので,これは纓の端の総(ふさ)などの形式化したものとも考えられている。この緌は六位の武官が常用し,六位以下は儀式のときに着けた。その着装法は巾子の後から簪の上を越して額上に交差し,あご下で結ぶ。
(8)懸緒 纓冠は上述のように,はじめ髻の部分を上からしめ,纓によって保たれたのであるが,それらがしだいに形式化して用をなさなくなったため,ついに別に懸緒をもって冠をとめることとなったのである。平安末期に蹴鞠(けまり)などのときに紫の緒を用いたが,平時に用いるものは白の紙捻(こびねり)で,1回かぎりで切り捨てることとなっているのは,これが略儀のものであることを示している。
なお冠地は奈良朝以来,五位以上は羅,以下は縵(きぬ)製であったが,羅は後に紋織の綾の有文の冠となり,これに対して無文の冠は重服のときや,六位以下の者の冠となった。礼服 (らいふく)日野西 資孝
ヨーロッパの王冠 国王,聖職者,軍人などが冠をかむる風習は古くからみられ,とくに王冠は古代エジプトで精巧なものが用いられていた。近代の王位を示す王冠の起源はギリシア,ローマの花や葉で編んだ冠でなく,東洋から伝わった絹または亜麻布に豊富な刺繡をしたバンドで,ヨーロッパではアレクサンドロス大王 がペルシア王の用いていたのを採用したのがはじめであった。ローマの皇帝たちは布バンドと月桂樹の冠の両者を用いたが,後者は王位の表象とは認められていなかった。ローマ人は皇帝がそのような表象を用いることを好まなかったからであった。この布バンドがユスティニアヌス1世 (東ローマ皇帝,在位527-565)のとき,精巧な装飾を施した黄金のバンドにかわり,こんにちの豪華な王冠の形に発達した。
現在イギリスの王家で用いられている王冠は2個あり,チャールズ2世(1661年戴冠式)以来の〈聖エドワード王冠 〉は純金で目方が重い(約30kg)ので,現在は戴冠式のとき儀式的に国王の頭にのせられるだけで,戴冠式の帰路ならびにその後はビクトリア女王 の戴冠式のときにつくられた〈帝国王冠Imperial State Crown〉が用いられている。後者は白金の台に二千数百個のダイヤモンド,約300個の真珠,10個以上のサファイア ,エメラルド ,数個のルビーが飾られ,ダイヤの中には309カラットの〈アフリカの星〉(これは王冠を使用しないときだけに挿入されている)があり,ルビーの中には〈黒太子〉という小さい鶏卵くらい(5cm以上)のものが飾られている。過去の諸国の王家に伝えられた歴史的な王冠の中では,オーストリア王家のものは1570年にマクシミリアン2世がつくったものであり,モンツァ(ミラノから約15km)のサン・ジョバンニ聖堂にあるロンバルディア の王冠にはキリストを処刑した十字架の釘が打ちのばして冠の内側にリボン状にとりつけてあるので〈鉄の王冠〉と呼ばれている。これはグレゴリウス1世(ローマ教皇,590年登位)の時代につくられたといわれている。そのほかドイツ帝国の王冠,1858年にスペインのトレド付近で発掘された7世紀の8個の王冠や,ロシアのロマノフ朝の王冠(1762年に,エカチェリナ2世のためにつくられたもの)などがよく知られている。なお,イギリスでは皇族や貴族が儀式のときにかむる宝冠(コロネットcoronet )が定められ,位階にしたがって装飾が異なっている。
瓶のあたまにつけるいわゆる〈王冠〉は,アメリカのペインターWilliam Painterが1892年に発明して特許をとった。正式な名前は王冠とその裏のコルクを合わせた〈王冠コルクcrown cork〉で,そのころのガラス瓶には口にみぞがなくて利用者が少なかったが,瓶の製造業者がみぞのある瓶をつくるようになったので世界的に普及した。春山 行夫
 [名]かんむり。
[名]かんむり。 [ト・タル][文][形動タリ]最もすぐれているさま。首位に立つさま。「世界に
[ト・タル][文][形動タリ]最もすぐれているさま。首位に立つさま。「世界に [接尾]助数詞。スポーツや将棋などの競技・大会で、勝ち得た称号の数や優勝回数を数えるのに用いる。「タイトル三
[接尾]助数詞。スポーツや将棋などの競技・大会で、勝ち得た称号の数や優勝回数を数えるのに用いる。「タイトル三
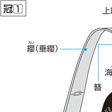



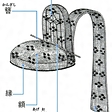

 中で儀礼を行う意であろう。結髪加冠のことならば元服。〔説文〕七下に「
中で儀礼を行う意であろう。結髪加冠のことならば元服。〔説文〕七下に「 なり」と畳韻を以て訓し、「髮を
なり」と畳韻を以て訓し、「髮を 以なり。弁冕の
以なり。弁冕の 名なり。冂(けい)に從ひ、元に從ふ。元は亦聲なり。冠に法制
名なり。冂(けい)に從ひ、元に從ふ。元は亦聲なり。冠に法制 り。寸に從ふ」と、寸を法制の意に解するが、加冠の形である。また字を冂に従うとするが、完・寇の字形との関連からみても、
り。寸に從ふ」と、寸を法制の意に解するが、加冠の形である。また字を冂に従うとするが、完・寇の字形との関連からみても、 に云ふ、
に云ふ、 頭、賀宇布利(かうぶり) 〔名義抄〕冠 カウブリ・カウブラシム・イタダク・オソヒ・トサカ・サカ・シメス
頭、賀宇布利(かうぶり) 〔名義抄〕冠 カウブリ・カウブラシム・イタダク・オソヒ・トサカ・サカ・シメス



 冠・素冠・弾冠・豸冠・長冠・鳥冠・貂冠・典冠・投冠・童冠・道冠・南冠・冕冠・宝冠・鳳冠・免冠・礼冠・練冠
冠・素冠・弾冠・豸冠・長冠・鳥冠・貂冠・典冠・投冠・童冠・道冠・南冠・冕冠・宝冠・鳳冠・免冠・礼冠・練冠