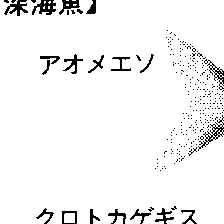精選版 日本国語大辞典 「深海魚」の意味・読み・例文・類語
しんかい‐ぎょ【深海魚】
- 〘 名詞 〙 一般に水深約二〇〇メートル以上の深海にすむ魚の総称。光が少ないか全くない、低水温、高水圧、生物現存量の少なさなどに適応するため、体の構造や生活様式を特異に発達させた一次性深海魚と、浅海域の魚類とあまり変わらない体や生活様式をもつ二次性深海魚がいる。現在最も深い記録はアシロの仲間の八三七〇メートルである。深海魚には、他にチョウチンアンコウ類、ハダカイワシ類、ソコダラ類、ホテイエソ類などがいる。
改訂新版 世界大百科事典 「深海魚」の意味・わかりやすい解説
深海魚 (しんかいぎょ)
deep-sea fish
一般に海洋の水深200m以深に生息する魚類の総称で,夜間表層に浮上する種も多い。海洋の150~200m以深の層は,光合成に必要な光量が十分でなく植物プランクトンや海藻は生育できない。したがって深海魚はすべて動物食性である。深海環境を特徴づけるものとして,光が少ないかまたはほとんどないこと,低水温,高水圧,餌料生物のきわめて少ないことなどがあげられるが,これらの条件に適応するためにいろいろに変わった形態や生態を示す魚が多い。
中・深層遊泳性魚類
深海魚は中・深層遊泳性魚類と深海底生性魚類に大別することができる。中・深層遊泳性魚類は,一般に海底から離れて浮遊遊泳生活を行うもので,そのおもなものにハダカイワシ類,ハダカエソ類,ヨコエソ類,テオノエソ類,ホテイエソ類,ホウライエソ類,トカゲハダカ類がある。そのほかにシギウナギ,ソコイワシ,デメエソの仲間,フリソデウオ類,クジラウオ類,ボウエンギョ類,チョウチンアンコウ類,カブトウオ類,フクロウナギ類などの少数群を合わせて合計約1000種が含まれる。なかでも生物量の多いのは,ハダカイワシ類,ヨコエソ類,テオノエソ類で,これらは体長10cm未満のものが多くマイクロネクトンmicronektonと総称され,サケ・マス類,イカ類,カツオ・マグロ類,イルカ,クジラ,オットセイ類などのような外洋性有用動物の重要な餌となっている。
中・深層は餌料生物に乏しいので,そこに生息する魚類の食性には二つの異なった方向への適応が見られる。つまりハダカイワシ類やテオノエソ類の一部のように,夜間は餌の豊富な100mより浅い層に浮上し摂餌活動を行い昼間は200m以深に戻る,いわゆる日周鉛直索餌回遊を行うものがある。これに対し,ホテイエソ類,ホウライエソ類,トカゲハダカ類,チョウチンアンコウ類,フクロウナギ類のように餌を待ち伏せたり,下あごのひげや伸長した第1背びれの先端の発光器で餌を誘引して丸のみにする仲間がいる。これらの仲間では,数少ない餌に遭遇する機会を有効に利用するために,鋭いきば状の歯のある大きな口をもつ。このため大きな餌まで捕食できる種が多い。これらの種の食道や胃は伸縮自在で,自分と同程度またはそれ以上の大きさの餌でさえも丸のみにすることができる。
中・深層遊泳性魚類の生息空間は,一般に太陽の光,とくに青系の光の影響を多少なりとも受ける200~1000m層の上部漸深海帯,1000~3000mの下部漸深海帯,水温の鉛直勾配のほとんど見られぬ3000mから大洋底(5000~6000m)までの深海帯,大洋底からさらに深くきれ込んだ海溝部分の超深海帯に区分される。
上部漸深海帯の魚類には,ハダカイワシ,ヨコエソ,テオノエソ類,ワニトカゲギス・ホテイエソ類を代表とする発光魚が生息する。発光器の機能はいろいろに分化している(発光のメカニズムについては〈生物発光〉の項目を参照)。ハダカイワシ類においては,体側の発光器は種によって異なる配列をしており,同種の仲間の認識に役だっているらしい。また腹面に沿って列状にならぶ発光器は,昼間薄明層に生息する際に下方から攻撃を加える敵魚に対し,自分のシルエットを隠すために発光させることが実験的に確かめられている。さらに尾柄部に発光器のあるハダカイワシ類(ススキハダカ類,ブタハダカ類など)では,雄では尾柄の背面に発光器があるのに対し,雌では腹面にあり,雌雄の識別に役だっているものと考えられる。眼前発光器をもつ種では,二次性徴として雄の発光器が大きく発達する。発光器と眼の発達は,互いに並行的で,発光がさまざまな生態的な情報伝達の手段として使われていることを裏づけている。これらの魚類の網膜には光の明暗を感覚する杆状体(かんじようたい)が高密度に分布し,その感覚能力は陸上のフクロウの仲間と同じく,脊椎動物中もっとも優れたものと推定されている。したがって人間には暗黒と感じられる上部漸深海帯においても,上層からの太陽の光量の変化や生物発光を十分感覚していると思われる。200m以浅の浅海系へ日周鉛直索餌回遊をする魚類はすべて上部漸深海帯に生息する。鉛直移動はうきぶくろの浮力調節により行われているので,鉛直移動に要するエネルギーはそれほど大きくないと思われる。実際にこれらの魚のうきぶくろには,血液とうきぶくろとの間でガスを吸収,放出することにより浮力を調節する機能をもつ,卵状体ovalと赤腺red glandがよく発達している。上昇,下降の速度は,毎分数m程度とゆっくりしており,その開始時刻や上昇の上限は水中照度の変化に支配されており,また種によっても異なっている。例えば満月の夜は,明るいので上昇深度がふだんより深くなる。夜間に表層へ索餌浮上する魚類の体側,とくに腹面は銀色のうろこで覆われ,背側は濃紺色をしており,ちょうど表層性の外洋魚のカツオ・マグロ類のような配色となっている。これは太陽光がかなり到達する上部漸深海帯で,体色の真っ黒なワニトカゲギス・ホテイエソ類のような待状せ型の魚食性深海魚から身を守るための一つの適応と考えられる。
下部漸深海帯の中層遊泳性魚類で代表的なのは,チョウチンアンコウ類,カブトウオ類,フクロウナギ類,フウセンウナギ類などである。いずれも眼が退化的で,発光器も餌を誘うためのものと考えられるもの以外はもたない。このほかに上部漸深海帯で繁栄しているハダカイワシ類,セヨコエソ類の中から分化して深層に適応した種がわずかに生息するが,いずれも発光器は退化的で,なかには失っているものもいる。また眼の退化傾向を補うように,水中を伝わる振動を感ずる側線器官が体側や頭部に発達しているものが多くなる。上部漸深海帯では,同種間や異種間の情報伝達に発光や太陽光を利用した視覚が使われていたのに対し,下部漸深海帯,さらに深い深海帯では水中を伝わる振動の知覚が,嗅覚(きゆうかく)とともに重要な働きをしていると考えられる。例えばチョウチンアンコウ類では雄の嗅覚器が非常に発達している種が多い。また体色は黒色で,うろこが極端に軟らかいか,ない種が多い。骨も骨化が進んでおらず,体が柔軟で脆弱(ぜいじやく)である。
3000m以深より5000~6000mの大洋底にいたる深海帯に生息する深層遊泳性魚類には,チョウチンアンコウ類に属するごく一部の深海性種,ソコダラ類のうち海底から離れて生活するようになったごく一部の仲間,単顎ウナギ類Monognathidaeがいるが,この層の魚類相はきわめて貧弱である。この層になると眼の退化傾向はいっそう進み,体色素を欠く種も出現し始める。
深海底生性魚類
海底から離れて遊泳生活を行う種につき述べてきたが,これに対し陸棚斜面から大洋底,さらにもっとも深い海溝部の海底付近に生息する深海底生性魚類がいる。これらの代表種として,ソコダラ類,セキトリイワシ類,深海性ウナギ類,ソコギス類,トカゲギス類,アオメエソ類が主として水深200mから3000mにかけての漸深海帯に,シンカイエソ類,チョウチンハダカ類,ホラアナゴ類,ソコギス類が3000m以深の深海帯の海底に生息する。このほかに深海底生性魚類には,ゲンゲ類,クサウオ類,イタチウオ類が含まれ,これらの仲間は沿岸の表層域から大洋底まで近縁種が広く分布しており陸棚性深海魚と総称される。深海底生性魚類には,ソコダラ類が腹面に発光バクテリアの共生した発光器をもつ以外,発光器がない。3000m以深の深海帯になると体色素を欠き,眼やうろこの退化した種が増え始める。また眼の退化を補うように水中振動を感ずる側線器官などが発達している。
6000m以深の海溝部(超深海帯)からいままでに4種の魚類が採集されており,いずれもクサウオ科とイタチウオ科に属し,深海底生性と考えられる。従来の魚の採集記録で深いものをあげると,ソ連の調査船ビーチャジ号(2世)が日本海溝の7579mの深さから採集したクサウオ科コンニャクウオ属の1種Careproctus amblystomopsis,アメリカの研究船ピルスベリー号がプエルト・リコ海溝の8370mから採集したイタチウオ科の1種Abyssobrotula galatheaeなどがある。クサウオ類やイタチウオ類は,陸棚上の沿岸域から海溝部の超深海帯の海底にまで近縁種が生息し,圧力,照度,水温など大きな環境要因の差にもかかわらず,魚の体構造,体形に基本的な差が見られない。そこでこれらの魚は比較的新しい時代に陸棚から陸棚斜面の海底沿いに深海に適応したと考えられている。このような深海魚を陸棚性深海魚と総称するのに対し,前半で述べた中・深層遊泳性魚類や深海底生性魚類のうちソコダラ類,深海性ウナギ類(ホラアナゴの1種),ソコギス類,トカゲギス類,アオメエソ類,シンカイエソ類,チョウチンハダカ類は,その仲間全体が通常200m以深,つまり陸棚より沖合の外洋に生息するという意味で外洋性深海魚と総称される。
発生
深海魚には稚仔魚(ちしぎょ)の時期を200m以浅の表層で過ごすものが多い。ハダカイワシ類やヨコエソ類を中心とする中・深層遊泳性魚類の大部分の稚仔魚は,その餌料として重要な微小プランクトンの豊富な海面から水深100m付近の層に分布する。深海底生性魚類で4000~5000mの大洋底にすむシンカイエソ類,イプノプス類やイトヒキイワシ類も稚仔魚期を浅海系で過ごすことが知られている。これらの魚類では成魚は深海,仔魚は浅海に適応しているために仔魚と幼魚で形態的に著しい差のある種が多く,初期の発育段階において変態と呼ばれるほどの外部形態の変化を示すのがふつうである。一方,底生性のセキトリイワシ類,ソコダラ類は卵黄物質に富む大きな卵を産み,それから孵化(ふか)する仔魚も大型で上部漸深海帯の500~1000m層付近に分布する種が多い。つまり大型の仔魚は,大型のプランクトン類を捕食できるために微小プランクトンの豊富な浅海層へ上昇しなくともよく,そのうえ深海のほうが外敵に会う機会も少ないわけである。
利用
深海性魚類で漁業の対象となっているものは,中・深海層遊泳性魚類ではハダカイワシ類の1種Lampanyctodes hectorisだけで,南西アフリカ沖で年間数百tから数万t漁獲され,魚粉や魚油の原料とされている。しかし,その漁獲量変動が著しく大きく,漁業として安定するためには本種の生態に関する基礎的研究結果に基づく漁業管理が必要と思われる。一方,深海底生性魚類を対象にした漁業には水深200~1000m付近の大陸棚斜面における底引きトロール漁業があり,アオメエソ,キンメダイ,ムツ,メヌケ類,マダラ,スケトウダラ類をおもな対象としている。したがって現在漁獲対象となっている深海魚はすべて上部漸深海帯に生息する魚類である。1000m以深の下部漸深海帯および深海帯に生息する魚種を対象とした漁業については,対象魚の生息密度が一般に低いこと,生態的知識の集積が不足していること,技術および採算の面から困難の多いことなどを考慮すると当分望みは薄いといわざるをえない。
執筆者:川口 弘一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「深海魚」の意味・わかりやすい解説
深海魚
しんかいぎょ
deep-sea fish
水深200メートルぐらいからさらに深い海中や海底にすむ魚類の総称。ヌタウナギ類、カグラザメ類、ツノザメ類、ガンギエイ目、ギンザメ類、ウナギ目、ワニトカゲギス目、ハダカイワシ目、タラ目、アンコウ目、キンメダイ目、スズキ目など多くのグループが含まれ、その種類数は2000種以上ある。とくにソコギス目とクジラウオ目、チョウチンアンコウ亜目の魚類は深海だけに生息している。
深海は太陽光線がほとんど届かないため暗黒であり、高水圧、低水温で、しかも餌(えさ)が少ない。深海魚はそこに適応して摂餌(せつじ)、繁殖などを行うため、きわめて特徴的なものが多い。わずかな光でも視力を得るために、オオメマトウダイ、ソコマトウダイ、ギンサケイワシなどは目が大きくなっている。逆に、ホソミクジラウオ、イレズミコンニャクアジなどでは極端に小さい目になり、1500メートル以深に生息するチョウチンハダカでは完全に目がなくなっている。それ以外にデメニギス科の魚、ボウエンギョなどのように目が望遠鏡のようになった魚、上向眼をもったテンガンムネエソ、前方から上方に向きを変えることができるデメニギスもいる。
発光器は深海魚にとくによく発達している。ハダカイワシ類やワニトカゲギス類では真珠のような発光器が体表に配列し、仲間どうし、または雌雄間の認知に、また体の輪郭を消すために利用されている。これらの発光やフジクジラやカラスザメなどのサメ類の腹面の発光は自力発光器、チョウチンアンコウ類のエスカ(ルアー)、ソコダラ類などの発光は共生する細菌によって光る他力発光器によるものである。また、チョウチンアンコウ類の口の背方にある誘引突起(竿(さお))の先端にあるエスカや、ワニトカゲギス類のひげの先端の発光器は、獲物を誘引して確実に捕食する働きをしている。
大きな口は、少ない獲物を確実にとらえるために発達している。フクロウナギは頭蓋骨(とうがいこつ)の7~10倍の大きな口で、獲物をとらえる。ホウキボシエソ科の魚は大口であるが、下あごは骨だけで、皮膚はないので、口を閉じるとき水の抵抗を少なくする。下あごの先端に強くて長い歯をもっているので、口をとらばさみのようにして獲物をとらえることができる。
海では深さが10メートル増すごとに1気圧が加わるので、深海魚はつねに大きな水圧を受ける。これに耐えるため、深海魚では皮膚や骨格の構造が疎となり、周囲の海水が容易に体内に入り込んで、内外の圧力がつり合うようになっている。クサウオ科やウラナイカジカ科の魚は体がぶよぶよし、骨格は退化的である。
暗黒の深海での繁殖生態は特異である。チョウチンアンコウの仲間は雌が著しく大きいが、雄はきわめて小さい。繁殖期には雄は雌に付着して繁殖の成功率を高めている。ミツクリエナガチョウチンアンコウは雄が雌と完全に癒着し、雌から栄養の供給を受ける。ヨコエソ科の仲間は雄から雌に性転換する。餌が少ないので最初はエネルギーが少なくてすむ雄として成熟し、後に大きな体の雌になる。また性比のバランスを保つのにも使われる。
深海魚のうち700~1000メートルの間にすむものは、食用となるものが相当にある。キンメダイ、チカメキントキ、ハマダイ、ムツ、キチジ、アコウダイ、バラメヌケ、ババガレイ、ヒレグロなどは商品としても価値が高い。ハダカイワシ類、ニギス、アオメエソ類はいずれも小形ではあるが、肉質がよくて煮物、干物、練り製品にされ、タラ類、とくにスケトウダラ、マダラ、メルルーサは世界各地で広く食用にされる。日本ではスケトウダラはかまぼこをはじめ各種の練り製品の原料として非常に重要である。また、ツノザメ、アイザメ、ビロウドザメなどの深海ザメの肝臓油は、スクアレンを多量に含むが、このスクアレンは化粧品や健康食品に、また、極低温で凍らないため精密機器、航空用などの潤滑油として珍重されている。なお、全般的に魚類資源が減少しているため、深海漁場の開発や深海魚の研究が盛んになってきている。
[落合 明・尼岡邦夫 2015年1月20日]
『長沼毅著『深海生物学への招待』(1996・日本放送出版協会)』▽『北村雄一著『深海生物図鑑』(1998・同文書院)』▽『尼岡邦夫著『深海魚 暗黒街のモンスターたち』(2009・ブックマン社)』▽『尼岡邦夫著『深海魚ってどんな魚――驚きの形態から生態、利用』(2013・ブックマン社)』
最新 地学事典 「深海魚」の解説
しんかいぎょ
深海魚
deep-sea fish
一般的に,生活の大部分を水深200m以深で生息する魚類を指す。ただし,ハダカイワシなどのように日周鉛直移動をするものや,一生のうちに深海と表層を往復するものもある。また,浅海魚と深海魚の生息域が重複することもあるため,明確な定義を定めるのは難しい。現在知られている深海魚では,中深海に生息する種は約750種,漸深海では約200種,深海底では約1,000種が存在すると考えられている。
執筆者:宮田 真也
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「深海魚」の意味・わかりやすい解説
深海魚
しんかいぎょ
deep-sea fish
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「深海魚」の意味・わかりやすい解説
深海魚【しんかいぎょ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
栄養・生化学辞典 「深海魚」の解説
深海魚
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...