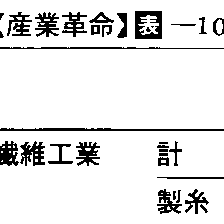共同通信ニュース用語解説 「産業革命」の解説
産業革命
18世紀に蒸気機関を活用し機械化したことを第1次、20世紀初めに電力を使って大量生産を実現したことを第2次と考える説が有力。第3次は20世紀後半に進んだコンピューターによる生産自動化とされる。現在の第4次では、インターネットやITによってメーカーや物流業者、小売企業がつながり、製品の品質や価格、サービスの競争力を強化することを目指している。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「産業革命」の意味・読み・例文・類語
さんぎょう‐かくめいサンゲフ‥【産業革命】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] Industrial Revolution の訳語 ) 封建制度から資本主義制度への転換の基礎となった技術的進歩と産業上の諸変革による、経済・社会組織の飛躍的な変革をいう。一七六〇年から一八三〇年にかけてイギリスのアークライト、カートライトなどによる紡績機械の改良に端を発し、その他の欧米諸国がこれに続いた。なお一九世紀後半の電気・石油の使用に伴う重化学工業の発達を第二次産業革命、現代の原子力利用への移行を第三次産業革命と呼ぶことがある。
- [初出の実例]「其上今や産業革命時代に進まんとする我国の社会状態は」(出典:新小説‐大正五年(1916)二月号・街頭の群集〈大山郁夫〉)
改訂新版 世界大百科事典 「産業革命」の意味・わかりやすい解説
産業革命 (さんぎょうかくめい)
industrial revolution
産業革命論の変遷
〈産業革命〉という言葉そのものは,K.マルクスやフランスのA.deトックビルらによっても用いられたが,厳密な学術用語としては,1880年代になってイギリスの社会改良家A.トインビーによって確立させられた。トインビーは,ケンブリッジで教鞭をとるかたわら,ロンドンのイースト・エンドなどのスラム改良に活躍した人物で,今もトインビー・ホールにその名をとどめている。彼にとって〈産業革命〉とは,18世紀後半,つまりジョージ3世登位以降,19世紀前半までのイギリスが,生産活動の機械化・動力化,工場制の普及,その結果としての工業都市の成立,産業資本家層と工場労働者の階層の勃興など,農村社会から資本主義的工業社会へ〈急激に〉大転換を遂げたことを意味した。それは,いかにも劇的な変化であったから,〈革命〉の名が与えられたのである。
ところで,トインビーやハモンド夫妻のように,19世紀末から20世紀初頭にかけて〈産業革命〉論を展開した人々は,ほとんどが近代都市における貧困や失業,犯罪,疾病,労働や生活の環境の悪さなど,現実の社会問題と取り組んだ社会改良家であった。こうした近代都市の社会問題は,かつての農村共同体の中ではあまり目だたなかったことばかりで,産業革命とそれに伴う都市化の産物というほかない。産業〈革命〉という経済・社会のカタストロフィーがあって,牧歌的だった〈古き良きイギリス〉が,〈暗くて惨めな〉工場労働を主体とする貧困と犯罪の都市的・工業的社会に変えられてしまった,と彼らが考えたのも無理はない。革命的な激変があったことと,それが社会問題をもたらしたという二つの発想が,こうしてまず第1期の産業革命論の柱となったのである。産業革命による労働者の生活水準の低下を主張しているという意味で〈悲観説〉派とも呼ばれるこれらの人々は,婦人や児童の工場や鉱山での労働が低賃金のうえ,労働環境が極度に悪かったとして,とくにこれを問題にもした。
しかし,資本主義世界が相対的に安定した1920年代になると,産業革命がもたらした現代社会への肯定的姿勢が強くなり,近代経済学的な発想法の影響もあって,〈楽観説〉が成立する。実質賃金統計などを作成してみると,労働者の生活水準は,産業革命期にもむしろ上昇しているとするこの立場は,J.H.クラッパムによって整えられ,T.S.アシュトンらに受け継がれて,欧米では通説の位置を占めた。産業革命前の社会も,悲観説が想定したほどのパラダイスではなかったし,〈産業革命〉と呼ばれている現象自体,数世紀にわたる連続的な変化の集合であって,短期の〈革命〉的激変などではない,というのが楽観説派の立場である。しかし,楽観説の立場にも,実質賃金統計の不完全さや,計量不能な要因,たとえば心理的な不満などをどう考えるかといった問題が残されており,今なお悲観説を強く支持するホブズボームEric J.Hobsbawmのような史家も少なくはない。
いずれにせよ,以上二つの立場では,産業革命は現代イギリス社会の起源をなしたできごとととらえられている。つまり,産業革命は,イギリス史上の歴史的固有名詞と考えられており,英語ではThe Industrial Revolutionと表記された。ただ,悲観説はそれが生んだ現代イギリスが多くの社会問題を含み,改良を要する社会だとし,楽観説はそれを肯定的にとらえただけの違いなのである。しかし,その後まもなく,産業革命の概念は二つの方向に拡大適用されるようになる。ひとつは,他の国々における同種の歴史的動向にその名がかぶせられ,〈フランス産業革命〉や〈ドイツ産業革命〉といった用語法が成立したことである。もうひとつは,〈13世紀の産業革命〉やJ.U.ネフの提唱した16世紀の〈初期(早期)産業革命〉,19世紀末以来の,化学と電力を主体とする〈第2次産業革命〉といった,イギリスないし世界史上のいろいろな時期に,この言葉があてられるようになったことである。歴史的固有名詞であったThe Industrial Revolutionは,一般名詞のindustrial revolutionsに拡散してしまう傾向を示しているのである。本来の〈産業革命〉を指すために,〈最初の〉とか,〈古典的〉とかいった形容詞をつけなければならなくなっているのは,このためである。
しかし,さらに20世紀後半,南北問題が深刻になると,産業革命の問題は〈工業化〉の問題として,世界史的な視野の中におかれはじめる。工業化,つまり農業社会から工業社会への移行という概念は,ロストーWalt Whitman Rostow以来,〈近代的経済成長〉つまり〈1人当り国民所得の持続的成長〉の開始の問題と結びつけられることが多くなっている。しかし,1人当り国民所得の成長を指標として,各国が同一の発展段階を次々とたどる--とくに各国の産業革命期にあたる,決定的な〈離陸take-off〉の段階を過ぎた国は,〈持続的成長〉をもつ国,つまり開発された北の国になる--というロストー的発想では,工業化や〈持続的成長の開始〉は要するに〈各国産業革命〉の概念の言換えにすぎないともいえる。これに対して,工業化を18世紀のイギリスに始まり,いまだに完了しない世界史上の一過程ととらえる立場もある。成長経済学の立場でのガーシェンクロンAlexander Gerschenkron(1904-78)やマルクス経済学的な〈新従属派〉理論の見方は,その例である。
したがって,1950年代までは,産業革命の一国内(とくにイギリス)での社会的帰結に関心が集中していたのに対し,成長経済学的な工業化論では,産業革命つまり〈離陸〉や工業化は当然〈望ましい〉ものであったとして,むしろその原因論に興味を示した。さらに近年になると,世界史は単一の歴史であり,一部の地域の工業化こそが,他の地域を低開発化し,現在の南北問題を生んだと考える立場が強くなっている。また,社会史への関心の高まりもあって,ふたたび庶民生活への産業革命の衝撃が問題にされるなど,社会的帰結への関心の逆戻り現象も認められる。
→経済発展
イギリス産業革命
前提
産業革命の概念そのものが多様なだけに,その始期と終期についても見解は必ずしも一定していない。かつては,綿業における重要な発明の時期などを手がかりに,漠然と1760年代から19世紀前半くらいに措定されていたが,始期については,人口増加や1人当り所得の成長の起点との関係で,1740年代説や80年代説が出されたし,その終期についても,新たな技術体系の一応の完成を意味する機械工業の確立--機械そのものの機械による生産--や産業資本主義の確立を意味する資本制恐慌の始期(1848)などが提唱されている。
いずれにせよ,18世紀のイギリスで最初の産業革命が起こったのだとすれば,その前提条件は何だったのか。それが産業資本主義の確立を伴ったという意味では,資本と労働の供給,原料供給や製品市場が問題となる。これらの条件を歴史的に準備したのは,エンクロージャーをはじめとする農業の変革(いわゆる〈農業革命〉)と,重商主義帝国の形成を背景とした貿易の成長(いわゆる〈商業革命〉)であったといえよう。エンクロージャーやノーフォーク農法(輪栽式農業)の採用によって,一方では農民は土地に対する権利を失って賃金プロレタリアート化したが,他方では,農業の生産性が高まって,人口増加が可能になった。商業革命も,商業資本の蓄積を進めながら,当面ほとんど無限ともいえる原材料--たとえば綿花--をもたらし,また広大な製品市場をも与えた。
さらに,毛織物工業を軸として,各種の製造工業がひろく展開していたことも,毛織物工業が産業革命の主導部門になったわけではまったくないが,資本・賃労働関係の展開を促進したことはまちがいない。
以上のほかに,たとえば人口増加の問題がある。人口増加と経済発展との因果関係は複雑で,前者を産業革命の前提条件とみるか,むしろその結果とみるか,議論の分かれるところである。しかし,1740年代から急激に人口が増えはじめたことが,労働力の供給を容易にしたことは事実である。
綿業--軽工業
技術革新と生産規模の劇的な拡大に象徴される産業革命の過程そのものは,まず綿織物工業を主導部門として始まった。主導部門とは,とくに成長率が高く,波及効果の大きい部門のことである。イギリスの綿業は,J.ハーグリーブズやR.アークライトの発明を契機として,1760年代後半から急成長を遂げ,たちまち国民経済の中核をになうようになる。1802年には,輸出でも毛織物を凌駕してしまうのである。17世紀には綿織物は,イギリスでは生産されず,東インド会社の主要輸入品であったことを思えば,その成長は驚異的である。1700年と20年に制定されたキャラコ禁止法が,インド産綿布の輸入を禁止したこともその成長の一因であったが,毛織物とは違って原料の綿花がすべて輸入品であっただけにその供給に制約がなく,その市場も熱帯を含む全世界に広がりえたことなどが,有利に作用したのである。綿業は,紡績部門と織布部門とに大別されるが,両部門の技術革新が跛行的に進行し,互いに刺激を与え合ったことも,その急成長の一因であった。1785年にJ.ワットの蒸気機関が紡績に利用されるようになると,それまでの水力紡績機とは違って,工場の立地や生産の集中に対する制約がなくなり,ランカシャーを中心に,大工場の林立する綿工業都市が多数成立した。
軽工業である綿業の創業資金は比較的少額であったうえ,株式会社こそ法によって禁止されていたものの,〈パートナーシップ〉制などによって負担を分散することができたから,その創業者は社会のほとんどあらゆる階層から出現した。ただし,著名な発明家で経営者として成功した者は,アークライトを除いてまずないし,社会的地位の高かった地主=ジェントルマンも,綿業に手を染めることはまれであった。
製鉄業と石炭鉱業--重工業と交通革命
綿業は本質的に軽工業であっただけに,その波及効果には限界があった。したがって,産業革命が社会・経済の根底からの転換を引き起こすようになったのは,製鉄業のような重工業が拡大しはじめてからである。16世紀のイギリスでは,木炭を燃料としてかなり大規模な製鉄業が展開していたが,建築,造船などとともに,この産業が木材を乱用した結果,〈森林の枯渇deforestation〉が起こり,17世紀には停滞してしまう。しかし,1708年,コールブルックデールのA.ダービーによってコークス製鉄法が開発され,75年にはワットの蒸気機関がコークスを燃やす際の送風用に導入されて,この隘路が一挙に切り開かれた。またこのことによって,製鉄業と石炭鉱業が不可分に結びつけられ,産業革命の中核をなしていくことになる。84年には,H.コートによるかくはん式精錬法(パドル法)が発明され,銑鉄のみならず良質の錬鉄をもコークスによってつくれるようになった。主要な製鉄業地帯は,バーミンガムを中心とするミッドランド,南ウェールズ,スコットランド南部などであったが,銑鉄 1tの生産に石炭10tを要しただけに,製鉄所の多くは炭田に近接して設立されたのである。
他方,石炭鉱業のほうも,すでに16世紀の〈早期産業革命〉においてもかなり重要な位置を占めていたが,なお石炭の主要な用途はロンドンを中心とする家庭用で,1700年ころでも年産200万t余にすぎなかった。しかし,ダービーの発明以来,その需要は急増し,1800年の生産量は1100万tを超えた。T.ニューコメンの大気圧機関を改良したワットの蒸気機関も,本来は炭坑の排水用に使われたものだが,1769年に認められたワットの特許を商品化するのに力を貸したスコットランドのJ.ローバック,バーミンガムのM.ボールトンがいずれも製鉄業者であったことは,鉄と石炭と蒸気機関の密接な関係を象徴している。
1781年にこれもワットがクランクの装置を発明し,往復運動を回転運動に転換することが可能となり,紡績機や機関車などに蒸気機関が利用される道が開かれた。製鉄業と石炭鉱業にとっては,運輸コストが決定的に重要でもあったから,鉄と石炭と蒸気機関は一体となって交通・運輸革命をもたらした。内陸交通の手段が馬車しかなかった時代には,穀物や石炭,木材のような重い物資は,海岸沿いの地方や航行可能な河川の流域以外には供給しにくかった。馬車交通そのものも,ローマ時代から進歩のない舗装技術に頼っていたために,道路の状況が悪く,十分には機能しなかった。したがって,河川改修とともにターンパイク,つまり有料道路の建設が交通革命の端緒を開く。最初の有料道路は1663年に議会で承認されているが,法律上その建設が認可された総延長距離は1730年までに898マイル(約1440km),50年までには1382マイル(約2210km)に達し,50,60年代にはさらに激増した。18世紀末になると,舗装技術そのものも,J.L.マッカダムやT.テルフォードによって改良された。
しかし,馬車交通では輸送能力が限られる。1760年代から運河の開削熱が高まり,ミッドランドやランカシャーを中心に,全国に運河網が広がった。〈運河マニア(運河狂時代)〉の典型とされるブリッジウォーター公が,ワースリーの自領からマンチェスターまで開通させた運河は,マンチェスターでの石炭価格を半減させたともいう。さらに1825年,G.スティーブンソンによって蒸気機関車が実用化されると,1830年代から50年代にかけての〈鉄道マニア〉時代を経て,鉄道が国内交通の核となる。国内の鉄道が延べ6000マイル(約9650km)を超え,ほぼ全土が鉄道網でおおわれた1850年には,新規の鉄道建設に投じられる資金と既設のそれからあがる利潤がほぼ均衡した。
有料道路や運河の建設には,議会の承認を要したうえ,必要な資金も膨大だったから,地主が計画に参画しているケースが多く,財団trustの形式をとるのがふつうであった。鉄道建設となるとますます巨大な資金と大量の労働力が動員されたし,営業が始まると,人間や物資の流通を一挙に高め,生産の集中や大都市の成立を可能にするなど,各方面へのその波及効果は計り知れないものがあった。イギリスでは,鉄道網の完成がほぼ産業革命の完了期にあたるとされるのは,このためである。
イギリス産業革命をリードしたのは,以上にみたような目だった技術革新を経験した部門だけではない。たとえば,スタッフォードシャーを中心とする陶器業は,技術的には大きな変化を経験しなかったが,製品の規格化や労務管理,マーケティングの方法などの改善を通じて大発展を遂げた。初代の商工会議所会頭となったJ.ウェッジウッドは,こうした〈非典型的産業革命〉のチャンピオンであった。
社会的帰結
産業革命は,経済革命である以上に社会革命であった。第1にそれは,産業ブルジョアジーと賃金労働者という二つの階層を勃興させ,伝統的な支配階級である地主=ジェントルマンを含めて,社会を三つの階級に分裂させていった。もっとも,上流=地主貴族と中産階級であるブルジョアジーとは,ともに有産階級として,その利害をしだいに一致させてもいく。産業革命はまた,17世紀末でも総人口の4分の3を占めた農村人口の比率を低下させ,都市住民との比率を逆転させた。
とすれば,近代的な二つの階級の成立と都市化という現象が,庶民生活をどのように変えたといえるか。悲観説・楽観説両派による〈生活水準論争〉は泥沼化して決着がつかないが,論争の過程で,たとえば次のような変化の実態はしだいに明らかになってきている。工場労働における低賃金と労働時間の長さが同時代にもしきりに問題にされたことは,12時間労働を規定した1833年の工場法などをみれば明らかである。また初期の工場法が婦人労働と児童労働をとくに保護の対象としたことも事実である。しかし,産業革命期に生じた最大の問題は,長時間労働や低賃金そのものにあったのではない。雇用の不安定さを別にすれば,問題の焦点はむしろ,定められた時刻から時刻まで集中的に労働を続けなければならないこと(〈タイム・ディシプリン〉の問題)や,労働が家族集団とはまったく別の編成で行われる結果,生産単位としての家族の紐帯が切られたこと,などにあった。かつての農業労働が祭りやレジャーと混然一体となっていたのに比べると,いまや資本家に売り渡された時間--出来高賃金から時間制賃金への移行が背景にある--と残りの時間との区分が明確化したのである。こうなると,労働者としては,〈労働時間の短縮〉は当然の要求となった。実質賃金についていえば,産業革命期にそれが顕著な低下を示したとするには無理がある。婦人や児童の工場労働がとくに過酷で,低賃金であるという主張もよくきかれたが,以前の農業社会で婦人や児童が労働をまぬがれていたわけでもない。そこでは家族単位の労働--農業であれ,家内工業であれ,大半の商業であれ--がふつうであったから,労働の報酬は戸主が一括して受け取っており,むしろ妻子の労働はいっさい金銭では報われないのがふつうであった。したがって,婦人や児童の労働についても,本当の問題は家族が離れ離れに労働を行わなければならず,母たる者が,もはや子どもの衣服を縫ってやることもできないという,旧来の家族構造の崩壊という事実にあった。生産単位としての家族の崩壊は,それがもっていた職業などについての教育機能をも失わせた。産業革命の初期に識字率が著しく低下したかどうかは論争があってよくわからない。しかし,家庭や共同体やギルドがもっていた教育機能が失われた以上,公的な初等教育の制度が整う1870年までの間は,民衆の教育水準があまり上昇しなかっただろうという推定はできる。
産業革命が庶民生活にもたらした変化の多くは,都市化の結果でもある。この点で象徴的なのは,当時の労働者が一般に故郷の農村からあまり遠くへは行きたがらなかった事実である。全体としてのイギリスにおける人口の重心は,ランカシャーやミッドランドに産業都市が多数成立した結果,北西方へ移動したが,個々の労働者は故郷からあまり遠くない都市--せいぜい隣の州--くらいまでしか移動しなかったことは,A.レッドフォードらによって証明されている。もとの共同体との関係をできるだけ残したいという心情が,そこに働いているといえよう。逆に,新興都市には,それだけ共同体的紐帯がなかったわけである。住宅をはじめ,上・下水道や街灯,公園,消防,警察,救貧などの諸施設・制度の整備以上に,共同体的紐帯の確立が産業革命期の都市の最大の課題となったのは,このためである。友愛組合のような組織は,そうした努力の表れである。しかし,都市労働者の紐帯をもっともはぐくんだのは,結局パブであった。パブを核とする労働者の生活文化は,中産階級からの厳しい批判--禁酒運動や動物虐待禁止運動はそのもっとも目だった動きである--にさらされつつ,根強く生き残った。
産業革命による社会構造の転換は,政治の面にも投影され,1832年には一般にブルジョアジーの政治参加を認めたといってよい第1次選挙法改正が行われた。しかし,労働者に選挙権を認めた第2次選挙法改正は,激しいチャーチスト運動があったにもかかわらず,1867年まで成立しなかった。1846年に穀物法が,49年に航海法がそれぞれ廃止されたことも,地主や商業資本家に対する産業ブルジョアジーの政治権力の強化を示唆している。1835年には,都市自治体法が成立して,都市行政の近代化の礎石も築かれた。
その他の欧米諸国の産業革命
世界にさきがけて産業革命に成功したイギリスは,その圧倒的な経済力を生かして,自由貿易主義の原則を打ち出した。自由競争こそは,イギリスの優位を保障するものだったからである。しかし,このことは同時に,フランスやドイツ,アメリカ合衆国などの後発国にとっては,イギリス商品による国内市場の席巻を意味した。これらの国々が,一方ではイギリス商品の流入を防ぎながら,他方では先進的なイギリスの技術や制度を吸収して自国の工業化(産業革命)を熱心に追求したのは当然といえる。こうして一般に,イギリス以外の国の産業革命は,多少とも意図的・政策的に促進されたものである。この傾向は,ドイツ,日本,ロシアのように,より後発的な国になるといっそう強くなり,〈上からの産業革命〉とでもいうべき状況が生じる。また,イギリスが世界市場をおさえた結果,後発諸国の工業化は自国の国内市場開発を主体に進めなければならなかったケースが多い--とくに,フランスやドイツ,アメリカ合衆国--が,その際,決定的な役割を果たしたのが,イギリスから導入された鉄道である。イギリスで産業革命の完了を意味した鉄道網の完成が,他の国々ではその開始を示す指標とさえ考えられるゆえんである。
フランス
フランスでは,イギリスで発明されたほとんどの紡績,製鉄などの先進技術が1780年代末までに導入されたが,散発的に特権的な企業家がこれを利用したにすぎず,それが急速に普及するのは,フランス革命を経て,各種の産業規制が廃止されてからである。綿糸の紡績工程にミュール精紡機が普及した1810年前後が,フランス産業革命の一応の始期といえる。しかし,イギリスと違って世界市場を握りえなかっただけに,フランスでは綿業が圧倒的な比重をもつことはなく,麻類や絹織物が重要な位置を占めた。絹織物業は産業革命初期の段階では綿業より高い成長率をもち,大衆消費財よりは奢侈的な高級品生産を志向してきたこの国の経済構造をよく示している。製鉄業も,1820年ころからパドル法が導入されて急激な成長を遂げた。42年から48年までの鉄道ブームによって,鉄道網も42年の665kmから48年の932kmにのびた。続いて50年代後半から60年代にかけては,工業生産に占める鉄道投資の比率がピークに達し,70年には延べ1万8000km程度にまで達した。大まかにいって,1850年代以降は,鉄道と製鉄業がフランス産業革命の主導部門となった。また,52年,クレディ・モビリエと呼ばれる大投資銀行が成立したことも,ナポレオン3世治下の高度成長を支えた。60年のイギリス・フランス通商条約は,フランスが対イギリス自由貿易政策に転換したことを意味するが,このような転換は,フランス自体の産業革命の完成を意味しているといえよう。
ドイツ
ドイツの産業革命は,およそ1830年代から70年代にかけて進行した。ここでも綿業などにおけるイギリスの先進技術は,ほとんど18世紀のうちに導入されたが,ドイツ関税同盟が成立するまでは国内市場も未統一だったために,普及しなかった。19世紀初頭にも全輸出の4分の1を占め,軽工業の中心をなしていた亜麻工業が,機械化になじみにくかったこともある。したがって,1835年にニュルンベルク~フュルト間に最初の本格的な鉄道が敷かれて以来,鉄道網が急速に広がり,それを軸として石炭業と製鉄業が急速に展開し,この国の産業革命は,初めから重工業に高い比重がかかっていく。製鉄業に関していえば,すでに30年代初めにコークス炉やパドル法が導入され,普及した。ドイツ産業革命の特徴の一つは,政府の役割が非常に大きかったことで,たとえば57年のプロイセンの鉄道の半分近くが国営であった。また,産業革命が本格的に進行した時期に,なお国家の政治的統一が完成していなかったこと,東部のプロイセンのシュレジエン地方とルール地方などを中心とするエルベ川以西の経済発展がよほど跛行的だったことなども,この国の産業革命を複雑なものにしている。
アメリカ
アメリカ合衆国は,本格的な封建制度をもたなかったこと,植民地という特異な状況から出発したことなどの点で,経済発展のコースもイギリスやフランスとはかなり違っていた。たとえば南部の綿花生産地帯は当初,もっぱら旧本国イギリスの綿業に結びつけられていたが,1812-14年の第2次英米戦争などを契機に政府が保護貿易主義を打ち出したため,国民経済自立(いわゆる〈アメリカ体制〉の確立)を求める気運が高まった。こうして,1830年代には,元来南部からイギリスへの綿花の輸出を握って利益をあげてきたニューイングランドに,綿織物工業が〈ウォルサム型〉工場の形態をとって急速に展開する。〈ウォルサム型〉工場とは,ニューイングランド北部に始まった紡・織一貫の大工場のことで,同じニューイングランドの南部に発達した紡績中心の〈ロード・アイランド型〉工場と区別される。しかし,広大な国土に比較的少ない人口が分散している当時のアメリカでは,運河や鉄道を中心とする交通革命が先行しなければ,国内市場の形成,本格的工業化の進展はありえない。この意味で,40,50年代にイギリスからの輸入によって行われた鉄道網の完成(1857年に4万kmとなり,当時のイギリスの2.5倍程度)がもった意味は大きい。鉄鋼業もすでに50年代に,ペンシルベニア,マサチューセッツなどを中心に発展しはじめていたが,南北戦争が北軍の勝利となって終わると,原料・食糧供給地としての南部や西部が,イギリスではなく北東部に従属するようになり,国内の再生産軌道が--つまり〈アメリカ体制〉が--確立する。したがって,アメリカ史上,〈産業革命〉をどの時期に措定するかについては,必ずしも一定した学説はないが,第2次英米戦争から南北戦争の前後にかけての時期をあげるのがもっとも一般的となっている。いずれにせよ,この後も相対的労働力不足の状態におかれたアメリカでは,19世紀を通じて労働集約的な技術革新が進行する。
このほか,ロシア,日本などにも相ついで産業革命が起こる。ロシアのそれは,1830年代から70年代末,80年代初頭に措定されており,日本の場合は日清・日露両戦争期を中心に考えられている。
執筆者:川北 稔
日本の産業革命
日本の産業革命は,松方財政による紙幣整理と広範な農民の没落を前提にして,1886-89年の企業勃興をもって始まり,日清・日露戦争の間に急速に進展し,日露戦後の1910年ころに終了し,日本資本主義の確立をみるにいたる。1886-1909年の工場数・労働者数の増加に示されるように,その過程で工場制工業の発達を主導したのは,紡績業と製糸業を先頭とする綿・絹2部門の繊維工業であった。そのほかでは,官営工場の比重の高さと,運輸通信業・鉱山業における労働者数の増加が注目される。以下,主要な工業部門について産業革命の過程をみよう。
紡績業
紡績業は繊維工業の中でも機械制大工業としてもっとも顕著な発達を遂げた。政府の助成をうけて発足した各地の2000錘紡績がいずれも不振を極めていたときに,渋沢栄一の指導下に1882年に設立された大阪紡績会社は,1万錘規模の機械を昼夜二交替制で稼働させて高利益をあげたが,それに刺激されて,1886-89年に鐘淵紡績,三重紡績,尼崎紡績,摂津紡績など,東京,大阪周辺でつぎつぎと大紡績工場が設立された。大紡績は,当時輸入綿糸の中心であったインド綿糸および在来手紡糸,ガラ紡糸との国内市場での競争に打ち勝って急速に発展した。一方で原料を国産綿花から輸入綿花へ転換することにより,1896年綿花輸入税免除を画期として国内綿作の凋落を決定づけ,他方で国内市場を制覇するや否やいち早く輸出を志向し,94年の綿糸輸出税撤廃と日清戦争の勝利を契機として朝鮮および中国市場への本格的進出を開始した。このような急速な発展を支えた条件として,(1)株式会社組織による主として都市商人層の資金の集中,(2)イギリスからの紡績機械(ミュールからリングへ転換)の輸入,(3)若年女子の低賃金労働の昼夜二交替制での利用,(4)原料としての安価な輸入綿花への依存があげられる。1900年以後,一時輸出が停滞するが,10年以降中国市場を中心に綿糸輸出が再び急増し,13年には中国市場で日本綿糸輸入量がインド綿糸輸入量を超えるにいたる。
製糸業
工業のなかで最多数の工場労働者を吸引した製糸業は,欧米の生糸需要に誘引されて1870年代後半から工場生産を開始し,90年代以降は対アメリカ輸出依存度を高めつつ急速に発達し,1905-09年にはアメリカ市場においてヨーロッパ糸および中国糸を凌駕して,日本の貿易収支を支える最大の輸出産業としての地位を確立した。この間,初期の官営模範工場の富岡製糸場や小野組の器械製糸会社が不振に陥ったのに代わって,洋式器械を模造した繰糸器と蒸気力または水力を用いた工場制の器械製糸と,在来の座繰器を改良し,揚返しまたは荷造り工程だけを工場化した問屋制または組合組織の座繰製糸という,二つの形態が各地に発展したが,1890年代以降の生糸輸出の発展を主導したのは器械製糸,とくに長野県諏訪地方を中心とする緯糸用普通糸を作る器械製糸であった。1900年代後半には,片倉製糸など諏訪糸大製糸による普通糸の優良化と,それまで普通糸生産の周辺にあった郡是製糸などの優等糸生産とが相まって経糸市場へも進出し,アメリカ市場を制覇していった。群馬県,福島県などの座繰製糸は,1894年に器械製糸に追い越され,1910年以後は衰退に向かい,国内向けとして存続していった。労働生産性がフランス,イタリアの約2分の1であった日本の製糸業が,ヨーロッパ糸および中国糸を圧倒していった最大の根拠は,養蚕農民が供給する安い原料繭と農村からの出稼ぎ女工の低賃金・長時間労働とによる生産費の低減であり,それに1900年代後半以後は生糸品質の優良・斉一化と一定の生産性向上が加味された。そして,低賃金のもとで女工の労働意欲をかきたて品質を高めていったものは,賞罰採点式等級賃金制と呼ばれる独特の賃金制度であった。
織物業
織物業では日露戦後の1900年代後半まで問屋制家内工業(出機(でばた)・賃機制度)が支配的であった。とくに久留米,川越などの内地向け綿織,西陣,桐生などの内地向け絹織においては,問屋制家内工業が大正期まで強固に存続した。しかし綿織物業では,輸入綿糸の使用とバッタン機の導入によって輸入綿布に対抗し,1880年代末までに国内市場を支配し,90年代には紡績会社兼営の機械製綿布と在来綿布とが並んで朝鮮および中国へ輸出される。1900年代には兼営織布の輸出が順調に進むとともに,その後半に泉南,知多など先進綿布産地を中心に国産力織機(りきしよつき)と電動機を用いた力織機工場が成立してくる。先進綿布産地における力織機工場化は1910年前後に急速に進展し,家内賃織が解体して農家婦女子が織布女工へ転化していった。この転換は国内市場での競争のなかで生じたものであるが,力織機工場生産はやがて輸出向けとして発展していく。兼営織布を中心とする綿布輸出は,日露戦争の勝利による朝鮮の植民地化と中国東北部への軍事的・政治的進出を背景に急速に進み,1910年ごろにはイギリス,アメリカ製綿布および土産綿布を駆逐して朝鮮市場を独占し,中国東北部市場をも支配するにいたった。絹織物業でも1890年代から1900年代にかけて石川,福井および福島の諸県を中心に輸出羽二重(はぶたえ)生産が急速に発展するが,その生産形態は手工制工場,賃織,独立家内工業が並存していた。しかしここでも日露戦後に急激に力織機工場が展開し,賃織が解体し,家内工業が衰退していった。
重工業
日本の産業革命においては,機械・金属工業などの重工業は,生産技術の世界的水準との極端な格差のために発展がきわめて困難で,重工業製品の多くを先進国からの輸入に頼らなければならなかった。そうしたなかで,官営の〈軍事工場〉八幡製鉄所および財閥傘下の大規模造船所だけが,軍事的・政治的必要から国家資金を集中的に投下されて突出的に発展した。殖産興業期に創設された陸・海軍工厰を中心とする官営軍事工場は,軍艦・兵器生産の自立を課題に日清・日露戦争を通じて拡充され,小銃などの自給を達成するとともに,その生産技術も著しい躍進を遂げて,日露戦争前後に世界的水準に到達する。軍工厰は鉄鋼や工作機械まで自製して自足生産を目ざすが,しかし日露戦争には軍艦,鋼砲,鋼材などを輸入に依存せざるをえない限界が露呈され,その後急速に八幡製鉄所の拡充,民間造船所・製鋼所との結合を進めて軍器生産の国産化を達成していった。
軍用・官用鉄鋼の自給を課題として日清戦後に創設された八幡製鉄所は,技術と機械設備を先進国に依存し,鉄鉱石・コークス炭を中国・朝鮮に求めて生産を軌道にのせ,日露戦後には一応銑鋼一貫体制を成立させた。それは,同じころ銑鋼一貫作業を開始した釜石製鉄所,日露戦争前後に設立され多くは軍官需と結びついた住友鋳鋼場,神戸製鋼所,川崎鋳鋼場,日本鋼管などの財閥系資本による鋼材生産と相まって,鉄鋼の自給率を高めていった。しかしなお第1次大戦前には鋼材自給率は34%にとどまった。
官業払下げに起点をもつ三菱,川崎などの大規模造船所は,造船奨励法,航海奨励法(ともに1896)による政府の助成をうけ,海運業の発達と対応しつつ,機械工業のなかで突出的に発展した。1900年ごろには造船技術が国際水準に接近し,日露戦後には海軍工厰との結びつきを強めて軍艦製造へも進出し,造船業の自立化が達成された。造船以外では,鉄道の発達にともなう客貨車生産を中心に車両業が自給化を進めたこと,三井の支配下の芝浦製作所による発電機,汽缶など大型機械製作の成功,ほとんど唯一の工作機械専門メーカーである池貝鉄工所による旋盤の完全製作などが注目されるだけで,機械工業の工場生産は低位にとどまった。
日本産業革命の特徴
日本の産業革命が展開した19世紀末~20世紀初頭には,欧米先進諸国ではすでに重化学工業の発展を基礎に独占資本主義体制が成立し,これら欧米列強による世界の帝国主義的分割が進行しつつあった。日本の産業革命は,欧米列強に資本・技術・市場面で従属しつつ,その従属からの自立を課題とする国家の政策に支えられ,とくに朝鮮,中国への軍事的・政治的進出を契機に展開した。官営軍事工業を中心とする重工業の発展が,軍事的・政治的必要にもとづく国家の政策的支援と,朝鮮,中国からの軍事力を背景とする原材料の確保によって可能とされただけでなく,紡績業,製糸業などの繊維工業の発展も日本銀行を頂点とし特殊銀行,都市銀行を通ずる政策金融に支えられ,朝鮮,中国への綿製品の輸出の増大も軍事力・政治力に支えられていた。こうして産業革命による日本資本主義の発展は同時に日本の帝国主義への転化をもたらし,日本帝国主義の形成は先進諸国による東アジアの帝国主義的分割の重要な契機となった。
また日本の産業革命においては,多くの産業が相互に関連して工業化を進める関係が乏しく,若干の戦略的産業が国家の政策と外国貿易に依存して突出的に発展したため,産業部門間に極端な発展の不均等が生じた。頂点に労働者1000人以上を雇用する軍工厰,造船所,紡績工場が聳立する一方で,労働者30人未満の手工制工場が繊維・食品工業だけでなく機械・化学工業にも多数存在し,さらに底辺には家内工業が織物,和紙,畳莚などの生産分野に大量に存続していった。そして,中小工場,家内工業はもちろんのこと,機械制大工業の発展も農村から不断に供給される低賃金労働に依存していた。とくに産業革命を主導した紡績・製糸・織物業では,若年女工の遠隔地募集が拡大するにつれ,彼女らを劣悪な条件で拘束する寄宿舎制度が成立し,それが長時間労働と相まって彼女らの肉体をむしばみ,数々の〈女工哀史〉を生んだ。出稼ぎ女工を供給したのは地主制下の零細農家であるが,日本の産業革命は半封建的地主制を解体させることなく,むしろ米と繭の生産を軸とする小農生産を拡充することによって寄生地主制の全国的拡大をもたらした。
産業革命は日本でも都市化を進めたが,日本の場合とくに東京,大阪などの大都市に人口を集中させ,そこに日雇,土工,人夫などの都市雑業層を中心とする劣悪な生活条件の都市下層民を形成させた。重工業や鉱山・運輸業で形成された近代的労働者階級の生活状態も,第1次世界大戦前までは,都市下層社会の水準から抜け出ることができず,その労使関係にも前近代的関係が温存された。
執筆者:大石 嘉一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「産業革命」の意味・わかりやすい解説
産業革命
さんぎょうかくめい
industrial revolution
定義
過去において、人類の文明史を画期した大きな事件は二つあった。一つは、人類が紀元前8000年ごろにメソポタミア地方で農業を始めた「農業革命」、もう一つは18世紀イギリスで開始された「産業革命」である。現在、産業革命がつくりだした物質文明は、過去における二つの大変革に匹敵するような大きな変革に直面している。アルビン・トフラーはこれを人類史における「第三の波」とよんでいるが、人によっては「第二の産業革命」とよぶこともある。
18世紀イギリスに起こった産業革命は、農業文明社会から工業文明社会への移行を意味するから、普通これを「工業化」とよんでいる。工業化はその後ヨーロッパ諸国、アメリカ、日本、ロシアなどに拡大し、さらに20世紀後半には、中国、韓国、東南アジア、中近東、ラテンアメリカ、アフリカ諸国に広がりつつある。工業化を簡単に定義することは困難であるが、物質的財貨の生産に無生物的資源を広範に利用する組織的経済過程であるといってよい。すなわち農業社会では、そのエネルギーを人間や動物の筋力か、風力、水力といった自然の力に頼っていた。また生活に必要な炊事や暖房、生産のための熱エネルギーは、主として薪炭に依存していた。これに対して工業化は、こうしたエネルギーの生物的資源への依存から、石炭やガス、石油といった一度消費してしまえば再生不可能な化石燃料への依存に移ることで、その際、新しいエネルギー体系への移行とその経済過程への適用を支えたものは、科学技術の進歩であった。
こうしてイギリス産業革命は、かつて経済学者のアーノルド・トインビーが主張したような激変的でドラスティックな現象としてではなく、少なくとも16世紀中ごろから工業化が始まったとする見解が今日では支配的である。
各国の工業化初期段階において、生産的投資が短期間に急速に上昇する現象がみられる。この現象に注目したのがアメリカの経済史家ロストウで、彼はこれをテイク・オフ(離陸)と名づけ、「生産的投資率が国民所得の5%ないしそれ以下から10%以上に上昇すること」という数量的規定を与え、低開発国の工業化に一つの歴史的規準を提供した。彼によれば、テイク・オフ期は各国ともだいたい20年間である。イギリスは1783~1802年、ドイツは1850~1873年、日本は1878~1900年(明治11~33)と押さえたが、この期間については異論がないわけではない。
ところで産業革命は、生産における技術革新と急速な経済成長をもたらしたのみならず、従来の農業社会の構造を根底から崩壊に導いた。生産と消費が一体であった農業社会にかわって、いまや生産職場と家庭は分離し、人々の生活は、労働を売って得られる賃金収入に依存せざるをえなくなった。現代の都市サラリーマン型生活が生まれたのもこのときである。農村共同体の崩壊に伴って、教育、福利厚生、娯楽などの社会的諸機能が共同体から分離、独立するなど、社会組織の大変革が起こった。
こうした産業革命を最初に経験したのはイギリスであるから、次に主としてイギリス産業革命について述べる。なお、日本の産業革命については「日本産業革命」の項を参照されたい。
[角山 榮]
起源
イギリスでは早くから封建制度が解体し、農村には独立にして自由な農民層が多く現れていた。また農民を母体とした農村毛織物工業が発達し、農民層分解の進展とともに前貸問屋制やマニュファクチュア(工場制手工業)の形態をとった初期資本主義的生産関係が、他のヨーロッパ諸国よりも順調に現れてきたこと、しかも17世紀中ごろの絶対権力を一掃した市民革命、海外市場・植民地の獲得、海外商業競争に対する有効な重商主義的諸政策と相まって、マルクスのいう本源的蓄積が著しく進んでいた。
[角山 榮]
エネルギー危機
人類最初の産業革命の引き金となったのは、16世紀中ごろ以降ヨーロッパを襲った森林資源の枯渇・欠乏、薪炭不足に伴う深刻なエネルギー危機であった。ヨーロッパのなかでも、エネルギー危機がもっとも深刻な状態で現れてきたのはイギリスである。これに対してイギリスがとった危機克服の対策は、代替エネルギーとして石炭を家庭用、工業用燃料として組織的に利用することであった。その結果、行き詰まっていたイギリス工業生産は石炭燃料の利用によって活気を取り戻し、1540~1640年の間「初期産業革命」とよばれるような急激な経済成長がみられた。こうしてイギリスの石炭生産量は1540年ごろの年20万トンから、1650年ごろ約150万トン、1700年ごろ約300万トンへと飛躍的な増加をみた。ちなみに17世紀後半のイギリス一国の石炭生産量は、全世界のほぼ85%を占めていたのである。
石炭に対する需要と生産が増大するにつれ、技術的に解決を迫られた課題がさしあたり三つあった。炭坑の排水問題、石炭の生産地から消費地への輸送問題、鉄鉱石溶解における石炭利用の技術開発がそれである。これらの課題が社会的、技術的に解決されていくなかで産業革命への条件が整備されていく。すなわち炭坑の排水処理の技術的課題は、セーベリーが考案した「坑夫の友」(1698)とよばれるポンプ、ついでニューコメンの「気圧機関」(1712)など初期の蒸気機関の発明を促し、ついにワットの複動式蒸気機関=動力機の発明(1781)に導いた。
他方、石炭輸送に絡んで登場してきたのが動力エネルギー危機であった。16世紀以降ヨーロッパは増大する動力エネルギー需要を、主として畜力とくに馬力の供給に依存したが、家畜の増加は飼料の増産の必要を高めた。とくに石炭輸送など陸上輸送が急速な成長を遂げたイギリスでは、穀物と飼料の増産を可能にした新しい土地利用形態、たとえば根菜類、クローバーなど飼料作物を導入したノーフォーク式四種輪作法のような技術革新が現れた。それにもかかわらず、家畜と人間が食糧と土地をめぐって競合するという事態が生まれた。家畜の増加が人間の生存を脅かし始めたのである。18世紀イギリスは、まさにそうした畜力増加の社会的限界が危機的状況となって現れた時代であった。人間の食糧と生存のために、いかに畜力を節約するかという問題と同時に、畜力にかわるいっそう効率的な動力をいかにつくりだすかという問題が、18世紀イギリスの最大の社会問題となった。
畜力の節約のために、車輪の改良、道路の改修、運河の建設といった社会的間接資本への投資が促進されはしたが、動力エネルギー危機は最終的には畜力にかわる新しい動力の出現を不可避のものとした。それを解決したのがワットの動力機である。それは水力、風力、畜力、人力など農業社会の基本的動力を凌駕(りょうが)して動力革命をもたらし、産業革命がまさに「第二の波」の名に値する画期的な技術的基礎を確立したのである。
[角山 榮]
生活革命
産業革命は綿工業から起こってくる。どうして産業革命がヨーロッパの伝統的産業である毛織物工業からではなく、ヨーロッパにまったくなじみのなかった綿工業から起こってくるのか。その歴史的背景として、17世紀後半におけるイギリスのアジアとの接触、それがもたらした生活革命に注目する必要がある。
当時のアジアは豊かで、優れた文化が栄えていた。茶、陶磁器、絹、綿布などはヨーロッパ人のあこがれの的となったが、なかでもイギリス東インド会社がもたらした美しく染色したインド・キャラコは、イギリスをはじめヨーロッパ人の間に新奇なファッションとして人気を集め、一種の衣料革命を引き起こした。綿布はドレスのほか、ベッドのシーツ、カーテンにも利用できるため、綿製品に対する需要が庶民の間に急速に広がった。その需要にこたえて、インド綿布に太刀打ちできる綿製品の製造が、18世紀初めのイギリスの国民的課題となった。原料の綿花は西インド諸島においてアフリカ奴隷を労働力とするプランテーションで栽培されたが、綿工業それ自身は、イギリス本国と西アフリカと西インド諸島を結ぶ三角貿易で栄えていたリバプールへ原綿が輸入された事情もあって、リバプールの後背地マンチェスター周辺で始まった。綿工業を推進したのは、旧来の支配階級であった地主や伝統的織物業者ではなく、主として商人およびヨーマンとよばれる農民であり、その多くは宗教的には非国教徒で、国家の援助もなく、自助の精神で企業家になった人たちであった。
[角山 榮]
経過
綿工業が主導
こうして産業革命は綿工業から始まった。綿工業における機械の発明は、ジョン・ケイの飛杼(とびひ)の発明(1733)から始まり、紡績部門ではハーグリーブスのジェニー紡績機(1764~1767)、アークライトの水力紡績機(1769)、クロンプトンのミュール(1779)、ロバーツの自動ミュール、織布部門ではカートライトの力織機(1785~1787)の発明によって、蒸気力を動力とする機械制工場生産が確立した。その中心はマンチェスターおよびグラスゴー周辺であった。綿工業の発展は、鉄工業、石炭業、機械工業といった関連諸産業の発展を促し、石炭と鉄の時代を現出した。
鉄工業における技術革新で注目すべきは、銑鉄生産過程におけるアブラハム・ダービー1世によるコークス炉製鉄法(1709ころ)と、鍛鉄生産過程におけるヘンリー・コートのパドル法(1783)である。とくにパドル法の発明によって鉄生産は飛躍的に増大した。その中心は南ウェールズ、バーミンガム周辺の中部地方およびスコットランドである。また機械工業においては、従来の時計工業、水車・馬車製造業における伝統的技術を受け継ぎながら、ヘンリー・モーズリーおよびその3人の弟子リチャード・ロバーツ、ジェームズ・ナスミス、ヨゼフ・ホイットワースらによって、精度が高く自動化された旋盤や工作機械がつくられるようになり、1830年以降には機械による機械の大量生産体制が確立した。
[角山 榮]
鉄道の出現
産業革命の技術的、生産力的成果の総仕上げは鉄道の出現である。鉄道の初期の歴史は石炭輸送をもって始まったが、スティーブンソンの発明した蒸気機関車は、その速度と能率において画期的な成功を収め、鉄道時代を迎えるに至った。まず1825年には石炭を炭坑から水路まで運ぶストックトン―ダーリントン鉄道が開通し、ついで1830年にはマンチェスター―リバプール鉄道が開通して商業的成功を収めた。その成功に刺激されて鉄道網は急速にイギリス全土に拡大し、産業資本循環の大動脈を形づくるとともに、国内市場が一挙に広がった。
イギリスに始まった鉄道建設は、すぐそれに続いて西ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国において急速に進められるとともに、19世紀中ごろ以降になるとインド、ラテンアメリカ諸国など後進地域へも鉄道が広がり、鉄道はまさに産業文明のシンボルとなった。こうして世界の鉄道総延長は、1847年には2万5100キロメートルであったのが、1857年には8万2800キロメートル、1867年には15万5700キロメートルへと飛躍的な発展を遂げた。
鉄道建設のためには、莫大(ばくだい)な資金、建設資材、技師、労働者を必要とするが、これらすべてを自給できたのはイギリスだけで、大陸諸国、アメリカ合衆国、未開発諸国においては、初期の鉄道建設にあたって、資金、レール、機関車、建設技師など、なんらかの形でイギリスに依存したのである。しかし先進資本主義国においては、鉄道建設ブームは、ロストウのいうテイク・オフのための主導部門を形成し、鉄道主導型の産業革命を引き起こすことで自立的国民経済の形成に著しい役割を果たした。一方、後進的農業諸国における鉄道の導入は、かならずしもテイク・オフへの契機にならなかったばかりか、かえってイギリス資本への従属を強める結果をもたらした。
[角山 榮]
政治の変化と世界経済の支配
自由主義経済体制へ
産業革命は単に経済構造の革命的変化をもたらしただけではなく、同時に政治的社会構造をも大きく変えた。政治的変化として注目すべきは、産業ブルジョアジーの勃興(ぼっこう)の結果、従来の貴族・地主支配の政治体制に動揺が始まったことである。すなわち、新興産業ブルジョアジーは1832年の選挙法改正をかちとることによって被選挙権を与えられ、一方労働者階級も一般男子普通選挙権を要求してチャーティスト運動(1838~1848)に結集した。こうした政治闘争は、資本主義体制が内部にはらんだ資本家と賃労働者との矛盾対立と絡み合って、イギリス社会を大きく揺さぶった。
また自由主義を標榜(ひょうぼう)する産業ブルジョアジーは、旧来の重商主義的諸規制や統制が彼らの自由な経済活動を妨げるとの立場から、それらの撤廃のための強力なキャンペーンを展開した。その推進力となったイデオロギーは、アダム・スミスからマルサス、リカードへと発展した古典派経済学の自由放任主義である。こうして19世紀前半、地主的、重商主義的諸規制は逐次廃止されていった。そのおもなものは、エリザベス「徒弟法」の廃止(1813~1814)、東インド会社の貿易特権の廃止(1833)、救貧法の改正(1834)、穀物法の廃止(1846)、航海条例の廃止(1849)などである。他方、自由貿易の実現は輸入関税引下げの形をとって進められた。それは1824~1825年のハスキソンWilliam Huskisson(1770―1830)の改革によって徐々に進められ、1840年代のピールの改革では、原料に対する最高関税限度を5%、半加工製品は12%、加工製品は20%を限度としたが、1845年に原綿の輸入関税は廃止された。ついで1850年代のグラッドストーンの関税引下げを経て、1860年には保護関税ないし差別関税はほぼ全面的に撤廃された。こうしてイギリスは自由貿易国となったが、イギリスの自由化に対応して1860年代には、英仏通商条約(1860)をはじめヨーロッパ諸国も自由化政策を採用し、自由主義経済体制が国際的にも完成をみるに至った。
[角山 榮]
世界資本主義の形成
19世紀を通じて工業化はイギリスからフランス、ドイツ、アメリカ、さらにロシア、日本へと拡大したが、工業化を民間の自生的な努力で達成したのはイギリスだけで、後発諸国の工業化は、イギリスの機械制製品の洪水的流入を防ぎ、国内資本の保護育成を図るため保護関税政策の採用など、国家の積極的な工業化政策に負うところが大きい。一方、工業化に成功しなかった農業諸国は、自由主義経済のもと、先進工業諸国に食糧や原料を供給し、工業国からは工業製品を輸入するという、世界的な分業構造のなかに強制的に包摂された。こうして世界経済は、イギリスを軸とする先進工業諸国と、これに従属的な植民地的、半植民地的農業諸国とに分かれ、これらが支配=被収奪の有機的な関係で結ばれた世界資本主義として再編成された。ここに現代における「第三世界」「南北問題」の原型が形成されたのである。
[角山 榮]
都市の生活環境
人口増加と工業都市の成立
普通、産業革命が始まったとされる1760年ごろのイングランドとウェールズの推定人口は660万、その後1800年には916万、1851年には1800万へと著しい人口増加をみた。従来停滞的であった人口がどうして急激な上昇に転化したのか。18世紀の人口増加の理由として、徒弟制が弛緩(しかん)して青年の自立が早まり早婚になった結果、出生数が増えたとする意見もあれば、ペストの減少や生活環境の改善で死亡率が低下したとする意見もあってはっきりしない。
しかし増加した人口の大部分は都市へ流れ、工業都市の群生をもたらした。1750年ごろには、ロンドンの70万を例外として、人口10万を超える都市は一つもなかったが、1830年にはマンチェスター、リバプール、バーミンガムなど、人口10万を超える都市が七つも出現、いずれも工業都市であった。近代工業都市の特徴は、中世都市が宗教と芸術の香りに満ちた美しい都市であったのに対し、石炭の煙で汚れ、不衛生で、悪臭たちこめる、労働者がひしめき合う不潔な都市であった。
[角山 榮]
劣悪な生活環境
生活の場が農村にあった時代は、生産したものは自らそれを消費することができた。しかし産業革命は、従来農村共同体のなかで一体であった生産と消費の分離をもたらした。労働者は家庭を離れて工場へ働きに出かけねばならない。ところがいまや生産の場となった工場内では、労働者は騒音と不衛生な環境のなかで、時計の示す時刻と監督者の厳格な規律と服従のもと、1日14、15時間に及ぶ長時間労働を強いられた。一方、労働者にとって消費や憩いの場である住宅といえば、たいていは工場の周りに建てられたにわかづくりの粗末なバラック長屋であった。それは普通広さ6畳ほどの部屋が二つ、しかも一つのベッドに3、4人が交代で寝起きし、便所は十数世帯の共同で、浴場の設備はなかった。
飲料水は、生活の場が農村にあったときは自由に得られたが、工業都市ではいまや水道会社から代金を払って買わねばならない商品であった。したがって貧しい労働者には、水もたやすく手に入らなかった。たとえばマンチェスターでは、1809年に給水会社が創設され給水を始めたが、ブルジョアの住む地域には1年6シリングで豊富に給水したのに対し、町の大部分は雨水をためた貯水槽から給水されていたにすぎない。またロンドンのクラーケンウェルのスラム街では、1863年になっても1日にわずか20分しか給水されない1本の水道栓に、十数世帯が頼っていた状態であった。このように「水はビールのように貴重なもの」であったから、労働者の家庭では飲料や料理に使うのが精いっぱいで、それを洗濯や入浴に使う余裕はほとんどなかった。こうした生活環境はきわめて不衛生なもので、しばしば伝染病の温床となった。とくに不潔な衣類がチフスの原因とされ、公衆衛生の立場から公衆洗濯場や公衆浴場を設けることが地方自治体に課せられるようになるのは、1848年の「公衆衛生法」以後のことである。
[角山 榮]
食事、伝染病、高い死亡率
この時代の労働者はいったいどんな食事をとっていたか。多くの労働者にとって、パンとジャガイモが食事のほとんどすべてであり、それにバター、チーズ、ベーコン、紅茶がすこしつく程度で、新鮮な肉はまだぜいたく品であった。パンは初めは自家製であったが、主婦が働きに出るようになると、パン屋のパンに依存するようになった。パンが褐色のパンからしだいに白いパンに移ったのはこのころである。白いパンをつくるのに漂白剤としてみょうばんを使うことが多く、ときには白亜、石粉、石膏(せっこう)、驚くべきことには人骨をさえ混合した。こうしたいんちき食品はこの時代の紅茶やコーヒーにもみられた。にせものの紅茶には出がらしの茶葉を再製、着色したものや、ときにはサンザシの葉を紅茶に仕立てあげたものさえあった。
また19世紀前半、都市労働者の手に入った魚といえば、塩漬けのニシンしかなかったが、1860、1870年代になると、冷凍装備のトロール船によって捕獲された新鮮な魚が、安い値段で庶民の台所に届くようになった。こうして新鮮な魚とくにタラがイギリスに入ってくるようになって登場したのがフィッシュ・アンド・チップスで、それが労働者の食べ物として定着したのは1864~1874年のころである。
ところで労働者は、職場における長時間労働と劣悪な生活条件のなかで、肉体の磨滅と生命の短縮を強いられた。1830年代末、マンチェスター、リバプールなど工業都市における労働者階級の平均寿命は、15~19歳という信じられないほどの低さであった。他方、農村に住む地主階級の平均寿命は50~52歳で、都市労働者階級とは大きな開きがあった。労働者階級の高い死亡率の原因は、主として赤痢、チフス、結核、コレラ、しょうこう熱など非衛生的環境に由来する伝染病のほか、とくに乳幼児の高い死亡率が平均寿命を引き下げたからである。
[角山 榮]
社会改良の動き
工場内における劣悪な労働条件および貧困な生活環境から、多くの社会問題が発生した。社会問題に対する対応には二つの動きがあった。一つは、資本に対する労働側の抵抗としての労働運動の展開であり、いま一つは、博愛主義者による社会改良の動きである。
労働運動はまず1811~1812年、1816年に起こったラッダイト運動、すなわち機械打ち壊し運動から始まった。1824年に「団結禁止法」が撤廃されてからは、ストライキが各地で頻発し、労働組合結成が全国的に広がった。こうして労働者は組織の力によって高い賃金を獲得しようと努めたほか、労働組合や相互扶助方式を利用して、現存社会を改良し新しい社会を打ち立てようとした。そのなかで注目すべき動きとしては、ロバート・オーエンの指導で結成された「全国労働組合大連合」(1834)、協同組合(1844)、チャーティスト運動などがある。
一方、工場内の非人道的労働条件の改善は、博愛主義者の動きとも絡んで、「工場法」の制定を促した。1802年の最初の工場法で、教区徒弟に対して12時間以上の労働および深夜業を禁止したのに続き、1819年、1833年、1844年の工場法でしだいに青少年の労働時間が短縮された。1847年には、原則として1日の労働時間を10時間とする十時間労働法が議会を通過した。また、博愛主義者チャドウィックEdwin Chadwick(1800―1890)らの努力によって、1840年代から非衛生的な都市の生活環境の改善が進んだ。なお、この時代の労働者の生活水準の低下を主張する「悲観派」に対して、むしろ生活水準は上昇したとする「楽観派」の主張が古くから対立し、俗に「生活水準論争」とよばれる論争がいまなお続いているが、1850年代末以降は実質賃金が上昇に転じたことは明らかであり、産業革命の生産力的成果と世界経済支配のうえにイギリスはビクトリア朝の黄金時代を迎えるのである。
[角山 榮]
『T・S・アシュトン著、中川敬一郎訳『産業革命』(岩波文庫)』▽『P・マントウ著、徳増栄太郎他訳『産業革命』(1964・東洋経済新報社)』▽『小松芳喬著『英国産業革命史』再訂新版(1971・一条書店)』▽『P・マサイアス著、小松芳喬監訳『最初の工業国家』(1972・日本評論社)』▽『角山榮著『産業革命の群像』(1971・清水書院)』▽『角山榮著『生活の世界歴史10 産業革命と民衆』(1975・河出書房新社)』▽『角山榮編『講座西洋経済史Ⅱ 産業革命の時代』(1979・同文舘出版)』▽『荒井政治・内田星美・鳥羽欽一郎編『産業革命の世界』全3巻(1981・有斐閣)』▽『角山榮・川北稔編『路地裏の大英帝国』(1982・平凡社)』▽『アルビン・トフラー著、徳山二郎監修、鈴木健次・桜井元雄他訳『第三の波』(1980・日本放送出版協会)』
百科事典マイペディア 「産業革命」の意味・わかりやすい解説
産業革命【さんぎょうかくめい】
→関連項目アシュトン|イギリス|クラッパム|工業|工場|産業考古学|社会主義|人口爆発|水力紡績機|世界の工場|繊維工業|紡績|ホブズボーム|綿織物|ヨーロッパ|ロストー
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「産業革命」の意味・わかりやすい解説
産業革命
さんぎょうかくめい
Industrial Revolution
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「産業革命」の解説
産業革命
さんぎょうかくめい
Industrial Revolution
18世紀後半,まずイギリスで始まり,その後約1世紀の間に今日の主要工業国に波及した。イギリスで産業革命が進展した背景としては,(1)世界貿易で独占的地位を築き,(2)2度の市民革命で社会の近代化が行われ,(3)資本の蓄積が進み,(4)農業革命によって労働力が生み出され,(5)豊かな鉄鉱・石炭資源に恵まれていたこと,などがあげられる。
イギリスでは,まず木綿工業部門に始まった。1733年ジョン=ケイの飛び杼の発明を先駆けとして,ハーグリーヴズのジェニー紡績機(1764),アークライトの水力紡績機(1768),クロンプトンのミュール紡績機(1779)が発明され,織布部門でも,カートライトの力織機(1785)は蒸気機関と結合して普及した。ニューコメンの蒸気機関は,ワットによって改良され,やがて大規模な工場の動力として実用化され,従来の水力を利用していた時代の工場の立地条件の制約は解消された。技術革新は繊維産業から他の諸部門にも波及し,冶金工業・工作機械工業なども発展した。
こうした諸産業分野の急激な発展に伴い,原料や製品の輸送のために道路や運河の整備が進み,蒸気機関を利用した鉄道・汽船も実用化された。鉄道は,1830年にリヴァプール〜マンチェスター間に開通したが,その後20〜30年で国内の鉄道網が整備され,全国規模の経済統一を促した。こうした交通・運輸技術の革新を交通革命と呼ぶ。
産業革命により,工場制機械工業が成立したことで工業が経済の中心となり,近代資本主義が確立した。産業資本家は地主や商業資本家に代わって経済力を強め,政治的発言力を強めていった。しかし,人口が都市に集中すると治安や衛生状態が悪化し,工場では労働者が劣悪な条件で働かされるなど,新しい社会問題も生じた。
こうしていち早く産業革命を経験したイギリスは,19世紀後半「世界の工場」として世界経済に君臨した。そして,ベルギー・フランス・アメリカ・ドイツでもそれぞれに特徴ある産業革命が始まり,おくれてロシア・日本にも波及した。19世紀末からは産業の重心が重工業に移り,ドイツ・アメリカを中心に電気エネルギーの工業化,化学工業の発展,独占資本の形成がみられ,これを第二次産業革命,現代の原子力エネルギーの開発を第三次産業革命と呼ぶことがある。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「産業革命」の解説
産業革命(さんぎょうかくめい)
the Industrial Revolution
18世紀後半のイギリスで,木綿工業に始まる広範な産業部門で技術革新が進行し,蒸気機関が動力として採用され,それに伴って社会構造も変化して資本主義社会が確立した現象。ただ,この用語が18世紀後半から19世紀前半のイギリスを超えて広く他の諸国にも適用されるようになるにつれて,そこに多くの疑問が生まれてきている。まずイギリスの場合は,それが外からの力を借りずに自然発生的に生じたものであり,紡績・織布部門における多くの発明が,製鉄・機械工業を刺激し,さらに運輸部門における交通革命を引き起こし,その過程で農村から切り離された労働者が工場に雇用されて都市化が進行したことは,事実であったにしても,その過程が過去との「断絶」による激変であったのか,それとも過去の遺産の上に立つ「連続」的な進化の成果であったのかについては議論が分かれている。またその結果,それまでの農村社会にみられた伝統的な雇用関係を喪失して資本主義的な労働関係に組み入れられた労働者が,資本家の搾取による「窮乏」を強いられて,その「生活水準」が低下することになったかについても論争がある。イギリス以外の後発諸国においては,イギリスの圧力のもとで,それぞれの社会経済的発展をイギリスを目標にして遂行しなければならなかったので,その変革は多かれ少なかれ国家主導型にならざるをえず,これを「産業革命」という概念でとらえられるか否かも問題となる。その傾向が最も強くみられたのは,ドイツ,日本,ロシアの場合であった。「工業化」という言葉は,産業革命の技術的側面に重点を置き,より一般化した使われ方をする。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「産業革命」の解説
産業革命
さんぎょうかくめい
機械の発明と応用を起点に,大衆消費財生産部門の機械制工場生産化が中軸となって,資本・賃労働関係が全経済の基軸をなすに至る過程。まずイギリスで綿紡績業を中軸に1760~1830年代に産業革命が進展し,欧米諸国もこれに対抗して産業革命を推し進めた。日本では,幕藩体制下での小商品生産の一定の成熟,開港後の貿易にともなう商品経済の再編,政府による原始的蓄積政策の推進を前提に,1886年(明治19)以降の企業勃興により開始された。輸入紡績機による1万錘規模の綿紡績会社が続出し,輸入綿花を用い,低賃金の若年女子を昼夜2交替制でフルに利用することで,手紡糸やインド綿糸を駆逐し,97年には中国を中心とする綿糸輸出が輸入を上回った。1900年の日清戦後第2次恐慌は,綿紡績業の拡大がひきおこし,大部分の産業部門に波及した最初の本格的資本主義恐慌であった。ただし先進資本主義国の外圧のなかで進展したために,各産業部門間の関連は分断的であり,諸部門の生産形態は重層的であった。なお,生産手段・消費資料の両生産部門の「2部門定置」という観点から,産業革命の終期を日露戦後の07年頃におく説も有力である。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「産業革命」の解説
産業革命
さんぎょうかくめい
1760〜70年代にイギリスに始まり,19世紀を通じて欧米の主要な資本主義諸国や日本で行われた。日本の産業革命は欧米より遅れて日清戦争(1894〜95)のころ,紡績・製糸・綿織物を中心とする軽工業部門に第1次産業革命が,続いて日露戦争(1904〜05)前後に重工業部門の第2次産業革命が進行した。この時期を通じて日本の資本主義が急速な発展をみせたのは,安くて豊富な労働力による。この安い労働力は,一方で国内市場を狭くするので,資本は海外市場を求め,軍事的・侵略主義的な性格をもった。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の産業革命の言及
【イギリス】より
…中世の三圃制農業の伝統を受け継ぐ混合農業が主体であるが,酪農や市場園芸などへと多様化しつつある。また西ミッドランド大都市圏は産業革命によって発展した古い工業地域であり,バーミンガムやスタッフォード炭田を含む黒郷(ブラック・カントリー)の鉄鋼業が衰退し,代わってコベントリー,ウルバーハンプトンなどの機械工業が台頭している。(4)東部 丘陵のイースト・アングリアと低平なフェンランドから構成されるが,年降水量が平均625mmと少雨であるため,小麦,大麦,ジャガイモ,テンサイ等の畑作が大規模に行われ,イギリスの穀倉をなしている。…
【学校】より
…これらの構想は,革命政府の下では実現されなかったが,教育を権利としてとらえ,学校教育の世俗性や無償をめざすことは,その後,近代教育の原則として認められるようになった。
[産業革命と学校]
一方,中世末期以来,手工業の発展とともに,同業組合学校や徒弟学校,さらに実科学校などが設置されるようになっていたが,学校が特定の上層階級の人のものでなく,広く一般民衆にとっても必要不可欠の存在とみられるようになるのは,産業革命に続く19世紀中葉のナショナリズムの高揚をまたなければならなかった。フレーベルは,人間は少年時代になると〈学校の人Schüler〉になるといった(日本では中国渡来の〈学童〉の語を,明治以来小学生にあてた)。…
【休日】より
…休日は働く者の労働のリズムを整え,労働力の再生産に活力を与えるために欠くことのできないものである。
【産業革命以前の休日】
工場法が施行されるずっと以前から,働く人びとは厳しい労働のあいまに,それぞれの生活に即した休日をもった。古い時代,休日はおおむね祭礼を伴った。…
【クラッパム】より
…ケンブリッジ大学における初代の経済史学講座教授(1928‐38)。1926年出版の《近代イギリス経済史》(全3巻,1926‐38)第1巻において,A.トインビー以来定着していた〈悲観説〉的な産業革命論に対して産業革命の明るい面を描き出し,それがむしろ労働者の生活水準を引き上げたとする〈楽観説〉派の起点となった。その研究方法が記述史料よりも,統計的なデータを重視していたことも大きな特徴である。…
【工業化】より
…人類史的にいえば,18世紀末のイギリスを起点として,現在も進行中の過程ともいえる。もっともふつうには,各国経済における工業部門の比重が決定的に高まることをさしており,歴史的にはそれぞれの国で産業革命とよびならわされている現象とほぼ一致する。この意味での工業化とは,産業資本,ことに固定資本の強度の蓄積,人口の激増,労働力の第2次産業への集中,第2次産業における技術革新の進行,そして何よりも1人当り国民所得の持続的成長の開始などによって特徴づけられる。…
【交通】より
…この時代の航海はヨーロッパ各国の国策として推進され,海外貿易によって金銀貨幣の増大を図ろうとする重商主義政策を生んだ。
[近世・近代]
イギリスの産業革命の原動力の一つとなった蒸気機関の発明は,19世紀に入ると,それをレールの上の車を走らせることに応用したトレビシックやG.スティーブンソンによって,鉄道という新しい交通機関の誕生となった。鉄道は建設と輸送の両面から,産業革命をいっそう進展させる役割を果たした。…
【産業】より
…工業は完全に農業から独立し,さらに商業に対しては支配的とさえなっていった。このように,いわゆる産業革命によって社会のしくみもすっかり変化してしまった。 以上のような歴史的発展のなかで,諸生産が社会的分業の一環として自立し,漁業,農業,林業,牧畜業,鉱業,工業等を形成してきた。…
【産業衛生】より
…ほぼ同時代の日本には,佐渡の金山で,坑内の換気のために通気坑を3年がかりで掘ったという記録(1663)や,珪肺(よろけ)の記録(1756)があるが,産業の規模は小さく,産業衛生活動はヨーロッパとは比べられないほど遅れていた。 イギリスに始まった産業革命によって生み出された労働者の健康上の諸問題は,こうした蓄積の上にたつ産業衛生の近代的な展開を促すことになった。新しく誕生した労働者階級の生活と労働の状態の改善の要求も高まり,産業衛生の課題は,過長な労働時間の短縮をはじめとした労働条件の改善,母性保護と年少者の保護,職業病の補償と予防などがとり上げられていった。…
【産業資本】より
…このような資本,労働という基本的生産要素が社会的に形成され,生産設備,原材料を含む生産要素を購入したり,生産物を販売したりする〈市場〉がある程度発達していることが産業資本成立の要件である。これに生産技術上の基礎を与え,近代的産業資本成立の現実的契機となったのが18世紀後半に始まるイギリスの産業革命であった。 商品経済発展のなかから生まれた産業資本は,いかなる生産活動にも適応しうる人間労働をはじめ,あらゆる生産要素を市場で手に入れることによって,人々が必要とするほとんどすべての生産物を市場に供給することができる。…
【資本主義】より
…その初期段階はマニュファクチュア(工場制手工業)のかたちをとり,技術的には手工業の段階にありながら,労働者を工場に集め分業によって生産力をたかめた。 しかし,資本主義による生産が飛躍的に拡大するのは産業革命によってのことである。イギリスでは18世紀の後半に綿工業を中心に多くの機械が発明され,工業技術が革新されて近代的工場制度が成立した。…
【植民地】より
…【中村 研一】
【近代植民地と世界資本主義システム】
[周辺部としての植民地]
経済学的観点からみた近代植民地とは,15世紀末以降に,形成過程に入った世界資本主義システムcapitalism world‐systemに従属的に包摂された〈周辺部periphery〉であり,その従属的性格は政治的独立後も周辺部の社会経済の構造的特徴として残存している。 いわゆる〈地理上の発見〉から産業革命に至る時期の世界資本主義システムとは,その〈中心部center〉としてのヨーロッパにおいては萌芽的に資本制生産様式の出現をみつつも,世界的に膨張しつつある商業網の周辺部においては,不自由労働のもとでの商品生産形態がみられるという,過渡的かつ不均等的・複合的なシステムであった。この時期のヨーロッパ経済においては,工業活動は比較的未発達で,おおむね商業資本に従属していたので,この端緒期の資本主義は商業資本主義とも呼ばれる。…
【トインビー】より
…オックスフォード大学卒業後,母校で教鞭をとるかたわら,ロンドンのイースト・エンドやブラッドフォードなどの工業都市で社会事業を展開。病弱のため早逝したが,のちに編集・出版されたオックスフォードにおけるその経済史の講義は,〈産業革命〉の概念を最初に確立したものとして,史学史上の記念碑的価値をもつことになった。彼の〈産業革命〉論は,その社会事業家としての問題意識と一体となって,劇的な変化,つまり革命があったこと,その結果民衆の生活水準が著しく低下したことの2点を柱としており,以後,この2点をめぐってさまざまな論争が展開される。…
※「産業革命」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...