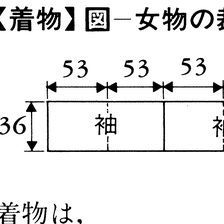精選版 日本国語大辞典 「着物」の意味・読み・例文・類語
き‐もの【着物・著物】
- 〘 名詞 〙
- ① 身に着る物の総称。ころも。衣服。
- ② 日本古来の衣服。和服。洋服に対していう。〔和英語林集成(初版)(1867)〕
- [初出の実例]「銘仙の衣服(キモノ)に同じ羽織」(出典:付焼刃(1905)〈幸田露伴〉一)
着物の語誌
→「きるもの(着物)」の語誌
きり‐もの【着物】
改訂新版 世界大百科事典 「着物」の意味・わかりやすい解説
着物 (きもの)
〈着るもの〉という意味から,衣服と同義語として用いられることもあるが,洋服に対して在来の日本の着物,すなわち和服を総称することもある。しかし現在一般に着物という場合は,和服のなかでも羽織,襦袢(じゆばん),コートなどをのぞく,いわゆる長着(ながぎ)をさすことが多い。これは布地,紋様,染色に関係なく,前でかき合わせて1本の帯で留める一部式(ワンピース)のスタイルのもので,表着(うわぎ)として用いる。以下〈着物〉の語はおもに長着をさして使う。
着物の発生と変遷
現在の着物をさかのぼると,小袖(こそで),衵(あこめ),襖(あお)などとなり,古代の衣服に近づいていく。着物型の衣服が成立したのは,だいたい奈良朝(8世紀)のころといわれる。着物は形の上では小袖と同じで,両者を区別することはむずかしい。小袖は平安末期(12世紀後半)までは男女の下着として着用されていたものであるが,鎌倉時代になると,しだいに上に着ていた衣服が省略されるようになり,表着として着用されるようになった。室町時代に入ると,それまで男女ともに着用されていたズボン式の袴(はかま)が省略されるようになり,着流しが一般の風俗となった。したがって,この袴をとり去った着流しの小袖から実質的には着物と呼ぶことができる。しかし男子は外出時など,場合に応じては袴をつけて,二部式(ツーピース)の衣服を併用したが,女子の衣服は一部式の着物だけになった。このことは男女の社会的地位の開きの裏づけによるもので,形の上では同じであるにもかかわらず,着物は性別を強調しながら,それぞれに発展していった。
男の着物の変遷
室町時代の着物は身丈(みたけ)が長いだけで袖は短く,丸みをおび,帯も細かったが,くつろぐ服として発生した以上,装飾的になるのは当然であった。しかし,男の着物は肉体の活動をさまたげる不自然な方向をとらず,原則として自主的な美感をみたすものにとどまった。袖は寛文・延宝(1661-81)のころ7~8寸(21~24cm),貞享(1684-88)に1尺(約30cm)となり,元禄(1688-1704)以後さらにのびたが,1尺3寸が限界であった。寛永(1624-44)ころ一部の伊達(だて)者が袖口を長くし,紅絹(もみ)の肌着をまとったが,これも風俗化せず,一時の流行でおわった。
男の着物の装飾は,形よりも材料,染色,模様に重点がおかれたが,それらは封建社会の身分制と結びついて,装飾そのものを支配した。ことに江戸時代初期のころは,はっきり区別され,支配者である武士社会の内部でも将軍,大名から下士,若党にいたるまで数多くの段階にわかれ,町人社会も大店(おおだな)の主人と番頭と手代,職人は棟梁(とうりよう)と弟子,農民は地主と自作と小作など,それぞれ服装に相違があった。たとえば白無垢(しろむく)の肌着は四位以上,それも大名は嫡男とかぎられ,熨斗目(のしめ)(腰に横縞または縦横縞のあるもの)は身分ある武士の式服であり,綸子(りんず)は一般武士には許されないなどである。地質(じしつ)の順位は綸子,羽二重(はぶたえ),竜文絹,二子(ふたこ)絹,紬(つむぎ)の順で,以下,麻および木綿となる。農民は特殊なものでないかぎり紬以上を禁じられた。武家の下僕は豆腐をこす袋や暖簾(のれん)に使う細布(さいみ)(糸の太い粗布)を紺に染めて着,民間の下僕は生平(きびら)(さらさない麻布)を着た。一般の民衆は麻または木綿を常用した。季節により服を替えるのはのちのことで,初期のころは4月に綿入れの綿を抜いて袷(あわせ)にし,貧しいものは夏にその袷をはいで2枚の単(ひとえ)にして使った。なお特殊なものに紙布(しふ)(紙をさいて糸状により,織ったもの)があった。しかし町人の経済力が増すにつれて,服装による身分の秩序はしだいにくずれるようになった。
江戸初期には将軍徳川家康でさえ小倉織木綿を用いたが,それが元禄ころには一般町人のものとなり,また羽二重紋付は士分以上のものであったのが,まず町人の着用が黙認され,文化・文政(1804-30)のころには公然となった。慶長年間(1596-1615)には大名のものであった熨斗目も,民衆の礼服として用いられるようになった。宝永年間(1704-11)豪商淀屋辰五郎が財産を没収された罪科の第1条は白無垢の肌着を用いたことであったが,のちには町人も葬式には白無垢を着るようになった。また武士は光沢のあるもの,町人は光沢のないものを着るなど,江戸初期にはそれによって材料の優劣を示したものであったが,江戸中期以後町人の着た木綿の唐桟(とうざん)は,武士の着た絹の上田縞などの5倍以上も高価なものであった。こうした着物の身分差の崩壊は,武士と町人の力関係の変化を示し,身分制の崩壊と正比例している。江戸末期にはさらに多くの服制が有名無実となり,御用金調達,経済的功労,貸借関係を通じて,町人は地位,名字,帯刀などとともに裃(かみしも),紋付羽織その他,以前には僭上沙汰(せんじようざた)と思われたぜいたくを公認または黙認されるようになった。服制が法律上で廃止されたのは1872年(明治5年1月18日)であるが,すでにそれ以前に効力は失われつつあった。しかし一般民衆が服装の自由を獲得してまもなく,男の洋服が普及しはじめ,着物にとって代わるようになった。現在では,男の着物は特殊な職業の人にしか着用されず,一般にはほとんど家庭内でのくつろぎ着となっている。
女の着物の変遷
室町時代の女の着物は本質的にあまり男と変りなく,袖も短く,帯も1寸~1寸5分幅で,腰に低く巻き,前,横,後と好むところで結んだ。江戸時代に入っても,初期のころはそれほど装飾的ではなかったが,やがて急速に女の着物だけが著しく装飾化をとげるようになった。1683年(天和3)幕府は女の錦紗(きんしや),縫い,惣鹿子(そうかのこ)(総絞)を禁じたが,1689年(元禄2)に銀250目,1721年(享保6)に銀300目までの縫いの注文仕立てを認めたことで明らかなように禁令は風俗の美化をおさえきれなくなった。
振袖はもと長さに関係なく,〈わきあけ(八つ口)〉の袖をいい,汗の発散と動きやすさのため童児用であったが,江戸時代に装飾化して若い娘のものとなり,長さを増しはじめた。寛文年間(1661-73)には1尺5寸を大振袖といったが,やがて2尺(貞享),2尺5寸(享保),3尺近く(寛延)と地にたれるばかりになった。通常の詰袖も安政・文久(1854-64)には1尺5寸に達した。なお帯もしだいに幅を増すとともに繻子(しゆす)や緞子(どんす)の厚地呉服物を用いたため,結び目は巨大となり,後結びが定型となった。裾をひくのはもと御殿女中の習慣であったが,のちには一般家庭に普及し,江戸全期をへて明治中期までつづいた。色彩も男女の別がようやく行われ,かつては両性に用いられた赤が女と子どもの専用となり,江戸後期には子どもも女子にかぎられた。着付も重ね着が標準となり,少なくとも2枚,一般に3枚,多いものは4枚を重ねた。そのため目につく袖口,八つ口,衿(襟),裾だけを二重にした〈比翼(ひよく)仕立て〉という裁縫を生んだ。
元禄以後〈華美〉と〈流行〉が著しくなり,《女重宝記》に〈時々のはやりそめも五年か八年の間にすたり〉とあるように,あらゆる意匠の変化を次々と求めるようになった。その流行の源泉は遊女風俗と歌舞伎である。着物の刺繡(ししゆう)は三都の遊女に始まり,曙(あけぼの)染の友禅模様も大型裾模様も遊女から始まった。裾に綿を多く入れて (ふき)を多く出すことも,遊女風俗の普及である。また歌舞伎の多くは遊女生活を扱ったから,遊女になる女方の姿も注目の的となり,着物の模様や帯や髪形の模倣を生んだ。
(ふき)を多く出すことも,遊女風俗の普及である。また歌舞伎の多くは遊女生活を扱ったから,遊女になる女方の姿も注目の的となり,着物の模様や帯や髪形の模倣を生んだ。
男の装飾が身分の差に結びつくのに反し,女の装飾が年齢の区別を強調したことは,女の着物の特徴であるということができる。振袖は娘のもので,結婚すれば詰袖となった。島田髷(まげ)に赤衿襦袢は娘,丸髷に色襦袢は人妻であった。江戸後期になるとこの区別はさらに細分され,増加し,裾模様の高さは娘7寸,若妻5寸,中年3寸,関西では娘の袖に丸みをつけないなど,いろいろとあげられる。明治の服制廃止後も,女の着物がほとんど影響を受けなかったのは,これらの区分が地位身分よりも年齢にもとづいているためである。引裾は明治中期まで行われ,3枚重ねの盛装は大正期までつづき,幅広い帯と振袖はその後も結婚衣装に代表されている。昭和期に入って機能的な洋服がようやく普及するにつれ,とくに第2次大戦後は着物はしだいに少なくなっている。
→小袖 →服装
材料および染色
着物の形態は袖の長短,衿の広狭など部分的な変遷はあるが,基本的な型については小袖から現在の着物までほとんど変化はない。そのため,着物の変遷や種類は,材料および染色,模様によるところが大きい。着物の材料は,室町期に中国から輸入された織物として綸子,紗綾(さや),繻子,緞子,錦,金襴(きんらん)などがあり,さらにビロード,紗(しや),羅紗(らしや),更紗(さらさ)などに及び,羅紗をのぞいては江戸時代にすべて国産されるほどであったが,綸子,紗以外のこれらの呉服物は主として羽織と帯に利用され,着物地におもに用いられたものは絹,麻,木綿の3種である。
絹はもと宮廷貴族の独占物であったが,平安末期から鎌倉期にかけて武士の勢力が高まるにつれ,しだいに使われるようになり,室町時代に武士が政権を奪取してからは完全に独占がくずれさり,それ以後しだいに民間に普及するにいたった。それは商業の発展によるもので,封建制度の身分差はさまざまの面で服装を支配したにもかかわらず,絹は江戸中期以後は富裕な町人階級にも広くゆきわたった。羽二重や縮緬(ちりめん)は,江戸中期以後に,主として前者は男子用,後者は女子用の代表的な絹織物となった。絽(ろ)は夏向きに利用され,紬は絹のなかではいちばん庶民的な織物であった。しかしこれらの大半は,江戸初期には特権的な身分を,後期には経済力の優越を示したぜいたく品で,一般民衆のものではなかった。これに反して麻は先史時代から広く栽培され,明治時代にいたるまで一貫して民衆の服装の中心であったといえる。生産技術が原始的なこと,質実堅固なこと,純白にさらさなくても(半ざらし),生地のままでも着られることなどのためである。江戸期には麻織の着物を〈かたびら〉と称し,各藩の武士の間で,5~7月の間は必ずこれを用いるおきてとなった。しかし,着物時代に登場し,最も広く行われたのは木綿で,従来,着物地といえば木綿と考えられてきたくらいである。綿種の渡来には各説あるが,少なくとも15世紀末には日本の一部に栽培され,16世紀初めにかけて近畿から関東に急速に広まったものと思われる。木綿の普及した理由は,絹はもとより麻と比べても,はるかに生産工程が単純なこと,暖かいこと,染色しやすいこと,肌ざわりよく,体によくなじむことなどで,絹を利用できない一般民衆にとっては着物地を代表するものであった。
次に染色は,すでに織り上げた白生地に好みの模様を染めぬくのと,糸で染めて柄地反物を織り出す方法と二つある。着物以前の染色はすべて前者であって,染めにくい麻を常用していた民衆は無地または紺1色であった。着物に木綿が用いられるようになってから,糸で染めることが行われたが,麻の藍染の伝統をひきついで,木綿は紺色を主とし,浅葱(あさぎ),ねずみ,薄茶色をわずかに用いた。柄は縞または絣(かすり)で,白地の多いものを白絣,紺地の多いものを紺絣といった。白生地染に比べれば変化にとぼしく質素であるが,地方の家内工業の中から各種の創意が生まれた。
白生地染は京都を中心にして発達し,藍を主とする地方染に対して京染といった。これは平安朝以後のあらゆる染色技術のほかに,のりを用いた技術を加えて,友禅染,小袖染などの精巧な美術品を生むようになった。これら引染の方法は,すでに戦国時代に始まって,くくり染の余白に手がきが行われたが,江戸期にはそれぞれの手法が独立して,くくり染は絞に発展し,友禅染はのりで白ぬきしてプリントするようになった。京染による模様と意匠の変化はほとんど無限で,優雅美麗をきわめ,世界的に有名な着物の美しさはこの複雑な染色技術に負うところが多い。総模様,絵羽(えば)模様などは一部式の着物であるために可能な模様のつけ方であり,また女の帯幅が広がりはじめると,帯そのものの装飾化と,それが着物を横に切るただ一つの強いアクセントとなることによって,模様に決定的な影響を及ぼすようになった。
→織物 →染色
農村の着物
着物の特徴を着流しの一部式のものとすると,農村では着物の生活を営んでいない。農民は労働の性質から,着物の発生後も二部式のズボン形式のものが衣服の中心で,着物は休日や祭日の晴着としてのみ着用された。その意味では,着物は都会の服装だということができる。農民の男女がはく袴は,大別すると裁付(たつつけ),もんぺ,軽衫(かるさん)の3系統に分けられ,各地によって呼名や形態が異なり,600種以上にも達する。袴の上着には,だいたい着物と同型のものが着用されるが,身丈は腰までくらいで,着物が足首および裾をひく長さのいわゆる〈長着〉であるのに対し,〈短着〉と呼ばれるものである。材料は麻のほかに,東北地方のマダまたはシナ,九州地方のヘラ,四国地方のタクまたはタフ,越後地方のイラなど,その土地の山野に自生する植物の繊維が用いられた。木綿は都会のように普及せず,晴着として用いられた。
着物の改良
男子の服装は明治初期から,軍人,官公吏,学生と順を追ってしだいに洋服化されたが,女の服装は江戸時代以来の着物生活であったため,新しい社会生活に適応しない面が注目されるにいたった。1899年医学者ベルツの,日本の女子の体格が悪いのは帯によるという意見にもとづき,女学生が袴を採用するようになったのはその一例である。一般の着物については,1902年実践女学園校長下田歌子らが改良の必要を説き,試案を出したのが始まりである。東京女子体操音楽学校校長藤村トヨは女の着物の欠点を科学的に研究し,1915年に一種の改良服をつくったが,それは朝鮮服に近いもので,広く用いられずにおわった。しかし1923年の関東大震災で着物の欠点が暴露されてから,社会的関心が高まり,そのころから改良運動はようやく盛んとなった。みやこ腰巻やズロースの着用が叫ばれ,腹合せ帯や名古屋帯が生まれたのはこのころである。しかし,封建社会の〈女らしさ〉の要求から生まれた拘束的な女帯や不自由な袖や歩行をしばる裾がバランスを保って総合的な女の着物を成立させているかぎり,これらの部分的な改良の試みは本質的な機能性を取り戻すことができず,昭和初めころからしだいに洋服にとって代わられるようになった。
第2次大戦が始まると,女の着物は強制的に改良が加えられた。袖は1尺くらいの元禄袖にきめられ,また,それまで2丈8尺から3丈3尺あった着尺地丈を,2丈5尺にして長い袖をつくれなくした。また上着と下着からなる二部式の婦人標準服を制定したが,この強制的な改良は戦争中だけのものであった。戦後は,従来の女の着物の欠点を改め,機能,衛生,経済の面から改良を加えるとともに,近代感覚をとりいれ国際性をもたせる試みがさまざまになされてきたが,先に述べた改良運動の歴史が示すように,帯,袖,裾を否定しえない〈着物〉の特性は機能性と調和しえないため,現在ではおもに社交用,儀式用,趣味的な衣服にとどまっている。
執筆者:村上 信彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「着物」の意味・わかりやすい解説
着物【きもの】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「着物」の意味・わかりやすい解説
着物
きもの
人が着るものとして、衣服と同じ意味で使われることもあるが、和服を総称していうことが多い。
[編集部]
世界大百科事典(旧版)内の着物の言及
【長着】より
…コートや羽織などの丈の短い和服に対し,いわゆる着物をさす。和服の基本である着物は室町時代末期の小袖の形式を受けつぎ今日に至るが,男物長着の方がその原形を残している。…
【服装】より
…古墳時代には豪族の間で朝鮮半島経由の北方系衣服が採用され,ついで飛鳥,奈良時代の貴族は新しく隋・唐風の様式を導入し,北方系ないし内陸地方の服装が行われることとなった。この影響で,従来の日本の南方系衣服に北方系の衣服形式が加わって融合し,日本独特の着物の萌芽が見られた。すなわち,布の織幅が狭く,二幅仕立てとした貫頭衣の前部をほどき,前落しの部分を襟としたものや,それに袖をつけたり,さらに衽(おくみ)をつけた着物の発生である。…
※「着物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...