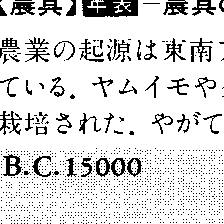精選版 日本国語大辞典 「農具」の意味・読み・例文・類語
のう‐ぐ【農具】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「農具」の意味・わかりやすい解説
農具 (のうぐ)
農業技術の体系は,整地を通じて作物栽培にとり好適な条件を耕地内に実現し,作物の生育過程に応じて作物体,耕地を適切に管理することによって収穫を得,さらに収穫物を食用に供するための調製加工を行う一連の行為としてとらえることができる。時間的連鎖をもって展開するこの一連の行為が農作業であり,農具とは農作業に使用される畜力や人力用の用具である。しかし農具とそれ以外の用具とは明確に区別されるわけではない。とくに農作業が耕地外での諸作業との関連を強めるにつれて,その区別はより困難となる。たとえば,伐採用の山刀,精米・製粉用の各種の臼,また唐箕(とうみ)や綿繰器などの人力用用具は耕作過程には直接使用されないので,非農具といいうる側面をもつが,広義には農具に含めることができよう。近代になって人力,畜力の機械動力による代替が進んだが,これらは農業機械として一括され農具には含めない。また犂(すき)は,トラクター用のものは農業機械として扱われるが,畜力用のものは農具として扱われる。しかし同じ畜力を利用するものでも,もみすりや揚水などを行う畜力機は,回転動力を得る一種の原動機であるから,農具という範疇(はんちゆう)には入れない場合もある。
農耕類型と農具
世界には無数の農具が存在するが,その存在形態は環境的基盤(気候,土壌など),それにより規定される主要栽培作物(とくに主食用作物)の作物特性などと関連するところが大きい。とくに農具のなかで最も重要な耕起・整地作業に使用される耕具のあり方は,これらとの関連が著しい。〈環境-作物-農具〉の相互関係に注目して,世界の四つの基本的農耕類型における主要農具について述べる。
根栽農耕
一年を通じて高温多湿な湿潤熱帯に広く分布する農耕で,ヤムイモ,タロイモなどの各種のいも類,バナナなどの樹木作物を主作物とする。根栽農耕の主要農具は掘棒であり,新旧両大陸の同農耕地帯全域に広く分布している。掘棒は採集狩猟民が用いるやりや棍棒状の武器から発展したものと考えられる。各地で使用される掘棒の形態は多様であるが,一応,(1)やりと同様に一方の先端を鋭くしただけのもの,(2)ボートのオールのように,太いほうの先端を平らにしかつ鋭くしたもの,(3)骨,石,金属などの硬い扁平な刃をとりつけたもの,の三つに分類可能である。(1)は突くという機能しかもたないが,それだけで農耕を行いうるのは,主作物の根栽類,樹木作物が栄養繁殖作物に属するからである。これらの作物は挿芽や株分けなどで繁殖するので,土に穴をあけてそこに若茎を挿植するだけでよいから,(1)のタイプの掘棒だけでも農耕を行うことができる。もちろん,耕土を多少とも耕起し土を膨軟にしたほうが作物体の生長にはよいので,(1)から(3)に向かうにつれて耕すという機能が増していき,踏鋤(ふみすき)に近づいていく。根栽農耕ではこのような掘棒によって,整地,挿植穴づくり,除草,いも類の塊根のさぐり掘り,根の掘りとりなどのすべての農作業を行う。
掘棒と並んで根栽農耕地帯に広く分布する耕具はくわである。くわは柄に対して鋭角状に耕刃がとりつけられた農具である。両者のとりつけ法の相違により,くわにもいくつかの種類があるが,基本的には,(1)耕刃の上端部に刃孔があってそこに柄を差し込むもの,(2)それ以外のもので,柄に穴があってそこに耕刃の突起部を差し込むものや,また木の一方にツタなどを巻きつけて耕刃を固定したものなど,の二つに分かれる。湿潤熱帯の根栽農耕地帯に分布するくわは(2)が多い。(1)は(2)よりも発達したタイプで,犂を主要耕具とする犂農業地帯で生まれたとされる。くわ,とりわけ(1)タイプのくわは根栽農耕地帯外の他の農耕地帯にも広く分布している。
ミレット農耕
ミレット(ほぼ雑穀にあたる)は,長い乾季をもつ熱帯サバンナや温帯モンスーンの非灌漑農業における主要作物で,夏季の雨をもとに栽培される。ミレット農耕は種子で繁殖する種子農業に属し,湿潤熱帯の根栽農耕とは根本的に異なる。ミレットの種子(穀粒)は麦や稲に比べて小粒で,そのため発芽と初期生育を確実にするためには,まず耕地の周到な整地が要求される。また夏を作季とするため雑草の繁茂が著しく,周到な中耕除草が必要である。世界の三大ミレット農耕地帯は西アフリカ,インドのデカン高原,中国北部(華北)にあり,それぞれ独自の農具を発展させてきた。西アフリカでは,整地,中耕除草ともに鉄の耕刃をもったくわを用いた人力耕(耨耕(どうこう))が行われる。ここは,くわや掘棒を主要耕具とする地帯のなかにあって,犂農耕地帯から鉄加工技術とともに刃孔差し込み式のくわをうけ入れてきた地域に相当する。播種(はしゆ)はくわでつくった条溝(すじみぞ)に手で条(すじ)まきする方法で行われ,特別な用具は存在しない。刈取りの農具は半月鎌で,脱穀から粒食の場合には精白,また粉食の場合は製粉までも木製の長い竪杵とくびれ臼を用いて一挙に行う場合が多い。また製粉には円棒状の上石を鞍(くら)状の下石にすりつけて粉にするサドル・カーンsaddle quernも広く用いられている。このように西アフリカのミレット農耕はすべての作業が人力によってなされるのを特色とするが,北方の地域では近年犂の導入もみられるようになった。
デカン高原のミレット農耕では,整地は無床ないし短床のインド犂による犂耕(りこう)と,角材の横木の下に長い木あるいは鉄の歯をとりつけた耙(まぐわ)(熊手耙)による耙耕(はこう)とを組み合わせて行われる。犂,耙ともに2頭の雄牛でひく軛(くびき)にまっすぐな轅(ながえ)で接続されて牽引(けんいん)される。播種は犂に単筒ドリルをとりつけて1条だけを条まきする場合もあるが,独自の畜力用条まき具の発達が著しい。それは上端に種子投入分配杯があり,そこから数本から十数本の竹あるいは鉄製パイプがのび,各パイプは耙と同じように,一定間隔をあけて横木にとりつけられたパイプ状の歯に接続されている。分配杯に投入された種子はパイプを通って転がり落ちて,歯が耕地面につけていく条溝に着床し,歯の数だけ一度に播種される。デカン高原では畜力用中耕除草具(やや幅広の鉄製歯をもつ耙状のものや4本の歯の左右2本ずつの先端に鉄刃をとりつけて作条の間を除草するものなど),また人力除草具(半月鎌を小型化した形をしているが刃は外側についていて土中に突いて根を切ることができるものなど)の発達が顕著である。このようにデカン高原のミレット農耕は整地,播種,中耕除草が畜力用農具で行われる点に大きな特色がある。刈取りは半月鎌で行われ,脱穀は数頭の雄牛に踏ませる牛蹄脱穀が多いが,2頭の雄牛に石製のローラーを引かせて行うこともある。風選は箕で上から落とす方法であり,粒食の場合の精白は木製の竪杵と石の臼で,また製粉は円盤状の二枚石を組み合わせたロータリー・カーンrotary quern(粉ひき臼)でなされる。
華北のミレット農耕では,耕起は長床の枠型犂(中国犂)を牛馬にひかせて行うが,1頭用の揺動犂なので役畜には2本の綱で結ぶ。砕土はデカン高原と同様の熊手耙,あるいは方形の枠型の下にやや長い鉄製の歯をとりつけた枠型耙を,牛馬1頭にひかせて行う。播種用の農具は耬(ろう)とよばれる畜力播種具である。耬は箱の中の種子をふり分けつつ落下させ,箱の下方にとりつけられた耕刃が切っていく溝に着床させていく条まき具である。しかし華北では整地・播種作業に限られ,中耕除草はくわないしは鋤でなされ,人力に依存していた。刈取りは半月鎌による。脱穀は石製ローラーを牛馬1頭にひかせてすることが多いが,からさおでたたく方法もある。風選,精白,製粉はデカン高原とほぼ同じである。
水田稲作農耕
東アジアおよび東南アジアの水田稲作農耕の主要農具は,華北やデカン高原のミレット農耕と深い関係をもつ。まず耕起用農具は,東アジアでは華北と同じ長床の枠型揺動犂で,それは東南アジアでも大陸部の北部やフィリピンにまで及んでいて,そこでは水牛1頭を牽引動物としている。またマレー半島やインドネシアではインド犂から派出した短床のマレー犂が使用され,2頭用の軛に接続される。耕起を終え湛水(たんすい)させた水田の代搔(しろか)きは畜力用熊手耙で行われる。中耕除草は手による草取りで,簡単な手道具を除いて特別の農具の発達をみない。それは湛水により雑草の生育が抑制されるからである。収穫は半月鎌の根刈り方式が一般であるが,東南アジアの島嶼(とうしよ)部では小型手鎌で穂刈りもみられる。脱穀は東南アジアや華南(中国南部)では稲束を手で板や土にたたきつける打ちつけ脱穀や牛蹄脱穀が行われ,東アジアではからさおが使用される。風選もデカン高原や華北と同じく箕を持ち上げて穀粒を落下させて夾雑(きようざつ)物を取り除く方法がとられる。精白は基本的に竪杵と臼によるが,足踏臼の発達がみられる。
麦農耕
西アジアから地中海沿岸へと続く冬雨型乾燥地帯の麦作は冬を作季とし,1年の休閑を介在させる2年1作で栽培されることが多い。犂は湾轅犂(わんえんり)が一般で,イラン,トルコなどでは方形犂が使用される。いずれも木製の犂轅で2頭用軛に接続して使用される浅耕用の長床犂である。耙は厚板,丸太状,はしご状の木製耙が多く,下面に歯がとりつけられることもあるが小突起にすぎない。耙の上に人が乗って体重を加重させて牽引させ,耙耕は砕土のほか,鎮圧,磨耕という土壌水分保全のための機能を強くもつ。播種は手によるばらまきが普通で,播種用農具をみない。古代メソポタミアの印章などには双柄単刃犂に単筒ドリルをとりつけて播種する情景が描かれているが,これはインドのミレット農耕に接する麦農耕地帯からの借用であろう。播種が終わると耙耕と同じ方法で覆土するが,それは種子の覆土だけでなく上記の土壌水分保全を目ざすものでもある。播種法におけるばらまきの普遍化は中耕除草の欠如と対応するものであり,独自の中耕除草用農具はない。刈取りは半月鎌で根刈りする。脱穀は数頭の牛に踏ませる牛蹄脱穀が多いが,イランなどでは丸太に木,石,鉄の小突起を打ちつけた丸太状の車輪を前後に二つとりつけた脱穀車が使用される。これはこの地方独特の農具である。脱穀が終わると,まず木製の熊手でわらと穀粒を分け,ついで木製スコップで夾雑物の混じった穀粒を上にほうりあげて風選する。ミレット農耕や稲作農耕で箕に入れて頭上から地面に向けて落とすのとは対照的な方法がとられる。精白も不要のため杵と臼も存在しない。製粉は水平翼車のついた水車式の大型ロータリー・カーンないしは手回しの粉びき臼で行われる。
麦農耕は西アジアや地中海よりも湿潤な北西ヨーロッパに入ると独自の農具を発達させる。それは,車輪,犂刀,大型犂鐴(りへき),撥土(はつど)板がついた深耕と反転が可能な重量犂の発達であり,その牽引法も牛2頭から馬数頭~十数頭の連畜方式へと変化した。ここに成立した車輪犂のうえにトラクターへと続く耕具の近代化が展開していったのである。また北西ヨーロッパでは農耕と家畜飼養とが有機的な統合をとげた混合農業が発達し,牧草栽培が重要となった。採草作業は両手で使用する大鎌を発達させた。耙も砕土のみを目的とする長い歯のついた枠型耙を主とするようになった。しかし19世紀の農業革命により条まき機が登場(華北のミレット農耕の耬の影響によるとの説もある)するまでは,播種はばらまきで中耕除草も行われなかったし,脱穀は牛蹄脱穀法が普通であった。農業革命以前の北西ヨーロッパの麦農耕は整地行程における独自的展開を除くと,農具のうえからも農法的にも西アジアの麦農耕と同じ基盤の上に立っている。農業革命以後の農業方法は農具から農業機械の体系へと変化し,それが新大陸の農業を発展させる原動力となった。
→農業 →機械
執筆者:応地 利明
農具の歴史的展開
ヨーロッパ
世界の農業は大きく二つのカテゴリーに分けられるが,それぞれにおいて農具の果たしてきた役割もまた異なる。日本の農業が属しているカテゴリーは,西洋の農業が属しているそれとは違うので,この二つのカテゴリーの違いを知っておくことは,西洋の農具そして機械化への歩みを理解する助けになる。
世界の農業は,雨量と気温に関係づけて,休閑農業と中耕農業に分けられる。休閑農業はヨーロッパや西南アジアのような夏に乾燥する地域に発達した農業であり,休閑することによって地力を回復させる。一方,中耕農業は東アジアや東南アジア,インドのような夏に湿潤な地域に発達した農業であり,休閑すれば分解した土壌中の有機質が雨によって流失して地力が減退するばかりでなく,翌年からの雑草の繁茂が著しい。また,休閑農業には本来中耕の必要がなく,中耕するような農耕は園芸horticultureと呼ばれ,農業agricultureとは区別される。中耕農業ではすべての作物に中耕を必要とする。このような相対立する性格を有するがために,両者における農具の発達,そして機械化への歩みも異なる。農具の発達は農作業の労働能率を高めることになるが,それによって浮いた労働が,集約化してもあまり土地生産性の高まらない休閑農業では,経営を拡大する方向に用いられ,そのことが畜力その他の原動力を利用する機械の発達を促した。一方,中耕農業においては,もともと労働を集約化しなければ農業そのものが成立せず,また労働を集約化すれば土地生産力が格段に高まるから,経営を拡大するよりも,むしろ労働を集約化して人力を利用する道具の発達を促した。
犂は,耕起具のうちで最も重要なものであるが,湿潤地で用いられたものと乾燥地でのそれとでは基本的な違いがある。前者では,深く耕した土塊を反転し,地表に繁茂した雑草を埋め殺す。したがって,大型で重く,土を反転するための撥土板をもっている。後者は,播種のための耕起とともに,土中の水分を保つ,すなわち土の表層近くだけを浅く耕して土中の毛管現象を断ち,地表面からの水分の蒸発を防ぐためのものである。したがって浅く耕す,小型で軽い撥土板のない犂である。西南アジアと南ヨーロッパは冬雨で乾燥地のため後者が,これに対し北ヨーロッパは夏雨で湿潤地のため前者が用いられた。なお,南北ヨーロッパの境界は,ほぼアルプスを横ぎる東西の線である。
最も古い犂の記録は,前3千年紀ごろイラク南部において見いだされる。もちろん乾燥地用の犂で,2本の柄がついている。この型の犂は,古代メソポタミアや古代エジプトにおいて広く使われた。それが二圃式農法(冬作→休閑)とともに,南ヨーロッパに伝わった時期は前1千年紀と考えられているが,形は変わっている。すなわち,犂床の先に犂先がついていたのが認められ,犂を牽引するときの力のバランスをとるための,犂床から前方に腕をのばし,綱を結わえつける犂轅が一般に湾曲していた。もちろん撥土板はなく,耕地を縦横に浅耕する。したがって耕地は正方形のものが多かった。
ローマ時代には,犂は北ヨーロッパにも伝えられたが,そこは夏雨の湿潤地であるため三圃制(冬作→夏作→休閑)が可能で,この農法に適した形に犂は変えられていった。前述のように撥土板をもち土を深く耕せるもので,牛2頭で牽引されたこの種の犂が,1世紀のころのローマ人による記録に見いだされる。大きな牽引力に耐えうるように犂の構造も変わり,犂轅と犂床が犂柱を介して方形に結合されるようになった。また犂体の安定をとるため犂轅には車輪が取り付けられた。三圃制は南ドイツで成立して以来13世紀にかけて北ヨーロッパ全体に広まっていくが,それとともにこの型の犂も広まっていった。そして,北ヨーロッパのかなりの部分を占めるゲルマニア地方(今のドイツ,チェコスロバキア,ポーランド,オーストリアなど)の名をとって,ローマ犂に対してゲルマン犂と呼ばれた。11世紀から13世紀にかけての時期に,この犂は,複数の犂を並べて取り付け,6~12頭の馬で牽引されるような大型のものになり,耕起能力も飛躍的に向上し,開墾が促進された。フランスの代表的な中世史家M.ブロックは,11~13世紀を〈大開墾時代〉と呼んでいる。なお,犂の大型化とともに,畑の端での方向転換に要するむだな時間を少なくするため,畑の形は細長くなった。その後,犂の形に基本的な変化はなかったが,畑の種類や作業の内容に応じて撥土板や犂先の形が変えられていった。また,イギリスの産業革命期に,深耕犂に機動性をもたせた無輪の,スウィング・プラウswing ploughと呼ばれる単犂があらわれた。
播種器(機)
播種器は古代からインドやバビロニアにおいて用いられていたが,そこは乾燥地でしかも古くからの麦作地帯であった。乾燥地での種まきで最も肝要なことは,適当な土壌水分のときに手早くしかも一定の深さに種子を入れていくことで,そうしないと発芽が著しく妨げられるからである。麦はイネと違って1粒の種子から収穫できる穀粒が格段に少ないため多くの播種量が必要で,種子をむだにすることができない。播種器は中国へは漢代に伝えられたといわれているが,中国の北部(華北)も西南アジアも同じ乾燥地農業の地帯である。一方,西方へはイベリア半島の南部をながく占領していたイスラム教徒によって伝えられ,南ヨーロッパ全般に広まった。湿潤地である北ヨーロッパで播種に機器が使われだすのは,時代をくだり18世紀に入ってからで,しかも根菜類の作付用であった。なお,古代の播種器は筒に種子をほうり込んで土中に落とすというものであったのに対し,18世紀の北ヨーロッパでつくられたものは種子を繰り出すための機械的な装置をもっていて,車輪から得る回転動力で動かされるため〈器〉ではなく〈機〉という文字を使うことにする。
18世紀後半のイギリスでは産業革命とともに都市人口が急増し,農産物の需要も急増した。厩肥(きゆうひ)を増産するには家畜の頭数を増やさなければならず,そのために飼料の根菜作物を大量に栽培する必要から播種の機械化が考えられた。この播種機を発明したのはイギリス人のタルJ.Tull(1674-1740)であった。彼は,植物は根から土粒を食って生長するという,当時流行していた説を信奉していた。たまたま南フランスを旅行中に,作物の条間を馬で中耕しているのを見た彼は,作物が生育中も土粒を食べやすくするため,土を細かく砕くための作業に便利な条まきを,機械化することを考えるようになった。もともと休閑農業ではばらまきが普通で,中耕の必要がなかったため,彼の発明は一時忘れられていたが,死後になって日の目をみた。
鎌と脱穀法
刈取り用具である鎌には片手で使うシックル(半月鎌)と両手で振り回し,草や穀物を根もとからなぎ倒すようにして刈るサイズ(大鎌)がある。シックルの原形はすでに古代エジプトでみられる麦の刈取りに用いられ,サイズはもっぱら牧草の刈取りに用いられた。シックルはサイズに比べ能率が悪いが,刈り残した茎と落穂は共同体における貧民の取り分とされ,その権利を保つためにサイズは長い間麦の刈取りに用いられなかった。18~19世紀になり,イギリスやフランス,ドイツでエンクロージャーにより共同体が破壊されると,貧民の強固な抵抗を受けながらもサイズが麦の刈取りにも使われるようになっていった。
刈り取った麦の脱穀は,堅く踏み固められた打穀場に麦を広げ,棒切れ(のちには中国から伝わってきたからさお)で打ったり,家畜の足で踏ませたり,ローラーやそりを引っぱり穂を押しつけて行った。旧約聖書に〈穀物をこなしている牛に,くつわをかけてはならない〉とあるのはこのことである。脱穀の方法は19世紀になってスレッシャーが発明されるまでまったく変わらなかった。ただ1~3世紀の属州ガリア(ほぼいまのフランス)のラティフンディウム(大土地所有)で,牛で押す箱型の2輪車の前方に櫛(くし)状の歯をつけて麦畑を進んでいき,穂首をちぎって収穫する機械が使われていた(まさに千歯扱(せんばこ)きであるが,歴史的なつながりはないようである)。このように,休閑農業ではその性格上,規模拡大のための農具(機械)が古くから考えられていた。
動力化
さて,近代農業への流れのなかで,農具も動力機械に移っていく。まず耕起の動力化は,実用化した蒸気エンジンにより試みられたものの,機動性がないためあまり進展をみなかった。そのうちに,石油エンジンを搭載したトラクターが19世紀後半にアメリカで開発され,その普及とともに動力化が本格化した。アメリカは産業革命や工業技術力では当時後進国であったにもかかわらず,世界の先頭をきって機械化を進めたのは,土地が広く人口が少なかったからにほかならない。当初,エンジンの動力は,それまでの馬を機械に置き換え,トラクターによる牽引への利用に限られていた。やがてエンジンの回転動力により,播種機や刈取機(車輪から回転動力をとる畜力用は,すでに南北戦争のころ完成していた)を動かすようになった。脱穀には,これもすでに発明されていたスレッシャーが刈取機とともにトラクターと一体化され,その名もコンバインド(結合された)・ハーベスター(略してコンバイン)として19世紀から20世紀にかけてのアメリカ農業の動力機械化をさらに推し進め,その影響は半世紀遅れてヨーロッパに,そして世界中に及んだ。
執筆者:飯沼 二郎+堀尾 尚志
中国
中国における古代の農業の中心は華北乾地農法で,その作業は大略,耕起→整地(耙,労(耮(ろう)))→播種→整地(耙労,除草,中耕など)→収穫→調整という手順である。以下農具についてだいたいこの順序で述べていく。
耕起具
新石器時代に石鏟(せきさん)とよぶ扁平な石器がくわないし鋤として用いられた。これとともに用いられたのが耒耜(らいし)で,《易》繫辞伝に〈神農木を斲(き)って耜となし木を揉(たわ)めて耒となす〉とあり,耒は自然木の二またになった部分などをとり土を掘るのにつごうよく加工したもの,耜は棒の先に平板を組み合わせた作溝用の農具と見られていた。もっとも耒は鋤の木柄の部分,耜は刃(さき)の部分という説もあり,楊寛は〈世界的に見て農具には掘起し用と作溝用のものがあるが,華北の耕地である黄土が比較的柔軟なため早くから作溝用の農具が手労農具の主流を占めた〉というが,事実,殷のときから耜系統が中心と思われ,さらに鉄が使用され始めて,耜の優位が著しくなり,耒耜で1個の農具をさすようになったのであろう。
耜(一般の農具にも通ずるが)の発達変化を特徴的に示すのは,柄と庇(すきさき)の接着角度,柄の湾曲度で,庇のつけ方には句庇(こうし)と直庇があり,柄には直柄,上弦柄,下弦柄があるため基本的には6種の形ができる。深く掘るには直柄・直庇がよく,作溝には下弦柄・句庇が便利であるが,一長一短,使用者の体力,対象となる作物,耕地の土質によりどれが適当とも,より発達した形ともいえない。おのおのの条件に応じて,現在のように器具に応じた柄の曲げ方,庇のつけ方がくふうされたのであろうが,《周礼》考工記の耜は,当時の平均的な形と各部分の比率を示しているといえよう。
牛犂は,前6世紀ころから斉(山東省),秦(陝西省)地方から始まりしだいに一般化した。最初は,播種溝をつくるための作条犂である。深く広いU字形の溝を作る耕犂に必要な犂鐴(へら)が確認できるのは三国時代であったが,最近の考古学的な発掘によって,鐴をつけていたと考えうる漢代の犂鏵(りか)(さき)も出現した。したがって,2牛3人で使用し深さ・広さ1尺の溝を作った前漢武帝のときの趙過の犂は不完全ながら反転犂の範疇に入りうるものと思われる。江南の水田用の犂は,北方の犂をもとにして漸次改良発達していったものであろうが,その過程の具体的なことはわからない。しかし《耒耜経》(唐の陸亀蒙撰)の犂は現在江南の長床犂と大差ないレベルまで発達している。
整地具
穀物の栽培過程で砕土(耙)し,さらに土壌を鎮圧(労)して毛細管現象を強化し,土中の水分を上昇させることが華北乾地農法の基本である。この作業は最初,槌(つい)(耰(ゆう)),板(木斫(もくしやく))の類を使用していたが,牛耕の普及につれて畜力利用の撻(たつ)(柴木を束ねて重石を置いたもの)などの使用をへて,耮(労=木を編んだもの),ややおくれて人字耙(じんじは),方耙などの耙,労おのおのの専門目的を持った農具が出現した。《斉民要術》で新鋭農具のごとく扱われている〈鉄歯 榛〉は方耙,人字耙と思われるので,北魏末に耙,労の農具は一応完成の域に達したといえる。その後水田では唐以後,礰
榛〉は方耙,人字耙と思われるので,北魏末に耙,労の農具は一応完成の域に達したといえる。その後水田では唐以後,礰 (かくたく),磟碡(ろうとく),耖(しよう)などが用いられるようになった。
(かくたく),磟碡(ろうとく),耖(しよう)などが用いられるようになった。
除草,中耕は最初は耜を使用していたが,深耕,易耨が叫ばれるようになって,除草,中耕用の鋤,鉏(じよ),鏟(さん)などが作られるようになり,さらに集約化,密植化が進むにつれ先の鋭い鋒(ほう)が作られた。それにおのおのが除草,中耕のしかたの違う蔬菜(そさい)の種類の増加が加わって,刃先の大きさ,鋭さ,柄の長短,湾曲,庇の角度,方向に変化があたえられ,現在のように多種多様の除草・中耕の道具を作ったものであろう。ただ,その進歩を各時代でおさえていくことははなはだ困難である。元の《王禎農書》の〈農器図譜〉には現在使用されている器具がほとんど示されているので,元代までにはこれらの器具は完成されたといってよいであろう。水田では手耘(しゆうん),足耔(そくし)(手,足にはめる除草用のつめ)を用いて手で除草し,足でかき回して除草したが,元代になって耘盪(うんとう)が作られた。
播種具
最初はもちろん手まきであるが,華北では耕起するとすぐに播種する必要上,牛耕の発達とともに畜力,人力でひく播種器(耬)が発明され,さらに進歩した犂に種箱を付して作条溝作りと播種を同時に行う耬犂(耬車)が漢代ころには出現した。耬犂は華北農業の特色的な農具で,後漢には一度に3溝に播種する三脚耬も見られる。
収穫具
最初は日本の石庖丁と同様な石刀が使用されたが,鉄器の普及とともに粟鋻(ぞくけん)や 鎌(こうれん)や鍥(けつ)などにかわり,漢代のころには柄の長い芟(さん),鏺(はつ)が見られるので,おそらく畑作では戦国時代ころ穂刈りから根刈りになったものであろうか(稲作ではかなりおくれ,江南では漢代は穂刈りであった)。現在の鎌状の農具も根刈りの普及とともに普及したものと思われる。脱穀には先秦時代から連耞(れんか)が使用され,また北魏ごろには磟碡も脱穀に使用された。水稲の場合は長い間竹蓆(むしろ)の上で石に打ちつけて脱穀していたが,明代ころから稲桶,稲床が使用されている。脱穀後の選別は空中にほうりあげて軽い物を除く原始的な方法から,唐・宋のころになって扇車が使用されるようになった。
鎌(こうれん)や鍥(けつ)などにかわり,漢代のころには柄の長い芟(さん),鏺(はつ)が見られるので,おそらく畑作では戦国時代ころ穂刈りから根刈りになったものであろうか(稲作ではかなりおくれ,江南では漢代は穂刈りであった)。現在の鎌状の農具も根刈りの普及とともに普及したものと思われる。脱穀には先秦時代から連耞(れんか)が使用され,また北魏ごろには磟碡も脱穀に使用された。水稲の場合は長い間竹蓆(むしろ)の上で石に打ちつけて脱穀していたが,明代ころから稲桶,稲床が使用されている。脱穀後の選別は空中にほうりあげて軽い物を除く原始的な方法から,唐・宋のころになって扇車が使用されるようになった。
精白具(製粉具)
古くから竪杵と臼が使用され,搗杵(つきぎね)も先秦時代に見られる。漢代になると碓(たい)や畜力使用の碾(てん)が出現し,後漢になると精白に水力が利用されはじめた(水車)。唐代のころから小麦が麦類の中心となった。穀物類の中で小麦の製粉はとくに微粒子の麵(めん)(パウダー)にする必要があるので,小麦の普及につれて磑(がい)(磨ともいう。すりうす)も普及してきた。磑の普及は唐代からとの説もあるが,中国の西北境から発見された居延漢簡から軍事施設の末端の (すい)の設備品に磑が見られるし,東端の楽浪から現在とあまり変わらぬ溝の刻まれた石臼(磨)が発見されているから,国内でもかなり一般化していたに違いない。おそらく小麦は西方で発達した加工具とともに伝えられたものであろう。ただ唐代では水力利用の磑を使用した製粉業は利潤の高い企業となり多くの荘園に設置され,田畑灌漑と摩擦を生ずるに至ったのは注目すべきことである(碾磑)。灌漑用農具は先秦では桔槹(きつこう)(はねつるべ),漢代では戽斗(ことう)(ふりつるべ),翻車が使用されたが,灌漑田の比率は低いものであった。唐以後水田耕作が中心になって踏車,筒車,牛力の水車が多く使用された。
(すい)の設備品に磑が見られるし,東端の楽浪から現在とあまり変わらぬ溝の刻まれた石臼(磨)が発見されているから,国内でもかなり一般化していたに違いない。おそらく小麦は西方で発達した加工具とともに伝えられたものであろう。ただ唐代では水力利用の磑を使用した製粉業は利潤の高い企業となり多くの荘園に設置され,田畑灌漑と摩擦を生ずるに至ったのは注目すべきことである(碾磑)。灌漑用農具は先秦では桔槹(きつこう)(はねつるべ),漢代では戽斗(ことう)(ふりつるべ),翻車が使用されたが,灌漑田の比率は低いものであった。唐以後水田耕作が中心になって踏車,筒車,牛力の水車が多く使用された。
以上は中国在来の農具について述べたものであるが,明末になると西洋の器具が伝えられたけれども,中華民国の時代になるまであまり普及しなかったようである。また民国以後,とくに中華人民共和国になって,食糧の自給,農業の発達に力をそそぎ,電力・石油を動力とする農業機械の普及に努めていることは周知のとおりである。なお農具はその種類も多く(《王禎農書》の〈農器図譜〉には250種以上の図が描かれている),単に器具の名称を列挙しただけでは各器具の区別,用途の相違を理解することは困難なので,ぜひ図譜類を参照すべきである。前記《王禎農書》以来,大部の農書には農器の図の付せられているものもある。
執筆者:米田 賢次郎
日本
日本の稲作は弥生時代に始まるが,稲作とともにすでに分化,発達した農具が日本に伝えられた。縄文時代に原始的な農耕が行われたとすれば,土掘具としての打製石器が中心であった。稲作の開始以降の農具史は大きく5段階に分けることができるが,それはまた,社会経済の時代区分のいくつかとも対応し,農具や栽培技術で支えられる農業生産力の変化とともに社会経済も変化してきた。
第1の段階は,弥生時代から古墳時代前半にあたる。農具は刃先まで木製であって,卓越した支配権力を支えるだけの生産力もあげえなかったのである。第2の段階は,5世紀中ごろに朝鮮半島からU字形鉄刃先の農具が伝えられて以来,10世紀までの古墳時代後期から平安時代前期までに対応する。新しい形態の鉄製農具は,ともに伝えられた稲の新しい栽培技術,すなわち稲の登熟期に水田の水を落とす方法とともに,それまでの年中湛水の水田しか耕せない農具による稲作に比べ,はるかに高い生産性をもたらし,古代国家の基盤を強固なものとした。なおこのころの主要な耕具はくわであった。第3の段階は,華北から伝えられた長床犂(唐犂)が普及していく11世紀から16世紀ころまでである。このころ土地制度も荘園制へと変わっていき,しだいに進んでいく大土地所有制の下で犂は主要な耕具となった。
第4の段階は,16世紀末から19世紀末まで,すなわち近世と明治時代の前半に対応する。中世を通じて,名主のもとで使われていた,名子とか被官とか呼ばれる下層農民は,わずかながら土地を与えられ,くわによる農耕を家族労働で営んでいた。肥料の使用は鎌倉時代の後期から始まり,時代がくだるにつれ施肥量も増えてくるが,それにつれて耕し方も深くしなければならない。当時の犂ではその要求に応じられず,むしろくわのほうがまだ深く耕すことができ,そのくわを用いていた下層農民のほうが高い生産性をあげるようになっていった。そうした下層農民を基本的な農民として位置づけたのが検地であり,彼らを直接支配して高い生産性を確保していった勢力が天下統一へと進んでいった。こうして再びくわが主要な耕具となったのである。
犂の時代からいったんくわの時代になり,時代が進むにつれ集約的農業が確立していき,次の第5の段階である犂の時代に再び進んだという点が,日本の農具史ひいては農業史の大きな特色といえよう。その第5の段階は,新しい犂が普及しだす明治時代後半から,動力耕耘(こううん)機が急速に普及しだす昭和30年代に至るまでである。かつては,より深く耕すために当時の犂に取って代わったくわも,さらに高まった肥料増投のための深耕化の要求にもはや応じられなくなった。また,落水する水田の面積が拡大するにともなって畜力耕の必要がさらに強まり,犂を根本的に見直す気運のなかで新しい犂が開発され普及した。これは,それまでの犂に比べ犂床が短いため短床犂と呼ばれたが,この犂の誕生は明治農法の確立を促し,その生産力が近代の地主制そして資本主義の発展を支えていったのである。
ここでは日本の農具史を5段階に分けたが,この分け方が定説として定まっているものではない。いま述べた第1と第2の段階をあわせて,くわ→犂→くわ→犂と性格づけをした4段階とみる考えや,農具の所有形態に着目し,共有(前記の第1段階)→権力者の集中占有(第3段階の初期)→一般農民の私有(それ以降)と性格づけした3段階とみる考えもある。また第4の段階をさらに二つに分け,その画期を元禄・享保(1688-1736)におくという考えもある。
第1~第2段階(弥生時代~10世紀)
第1段階の稲作は年中湛水の低湿地の水田で行われ,木製農具を用いた。この時代の遺跡から出土する農具はすでに発達,分化した形をとっており,くわは平ぐわに加えまたぐわがみられ,平ぐわに柄を取り付ける角度が,打ちぐわとして使う90度近いものと,引きぐわとして使う約60度のものの2種類がある。そのほか田を均平にするえぶり(朳)や田に草を埋め込むための田下駄,あるいは収穫した稲を乗せる田舟がみられる。これらは,すでに中国の江南地方で発達し,稲作とともに稲作システムの構成要素として伝えられたものである。穂はみのったものから石庖丁でもって穂首から切り取り,そのまま蓄えられ必要に応じて竪臼でつき,もみを穂から離す脱穀と,もみを玄米にするもみすりを同時に行った。鉄製刃先はすでに弥生時代中期末から増加するが,5世紀中ごろに新たな技術が伝わり,乾いた田畑の土を耕せるように,くわや踏鋤の先にU字形の鉄刃先をかぶせるようになった。鉄製の農具が普及するようになった第2段階の始まりである。
第3段階(11世紀~16世紀)
第3の段階に入ると,長床犂が普及していき,まぐわ(馬鍬)による代搔きも始まる。そして,稲の収穫もそれまでの石庖丁による穂首刈りから鎌による根刈りに変っていく。それとともに,脱穀ともみすりの方法も,それまでの竪臼と杵で二つの工程を同時に行っていた作業が分離されてくる。それぞれの具体的な方法は明らかでなく,古典の記述から推測するしかないが,おそらく,手あるいは棒や竹で穂をしごいて脱穀し,木の臼でもみすりしていたのであろう。このように,第3の段階の農具については,史料が少ないためにはっきりしないことが多い。たとえば,第1の段階でみられた,木製ながらも相当に分化していた農具が鉄器化の過程を経てどうなっていったのかもよくわかっていない。ただ,耕起からもみすりに至る農作業の基本的なパターンは,次の第4の段階に入るまでは変わらなかったということはできる。
第4段階(16世紀末~19世紀末)
第4の段階に入ると,くわを主要耕具とする家族労働による農耕を営む小農民(近世本百姓)の自立が,先進地に限られてはいたが進み,それとともに,個々の農具も徐々にではあるが分化していく。くわは耕起のためだけに用いられていたが,しだいに刃が薄くなってくると除草に用いるというように使い分けが進み,やがて除草専用のものが現れるようになる。やがて,元禄~享保のころになると,米の反当り収量が増加し,一方,都市商業の発達や海運の発達とともに菜種や綿などの商品作物の栽培が盛んになり,小農民の自立が先進地以外でも進行する。二毛作の拡大により,農作業の能率化が要求されてくるが,農村からの人口流出にともない労賃の高騰も手伝って,新しい農具がこの時期を境にして数多く登場してくる。この時期を画期として,第4の段階をさらに2期に分けることができると述べたのは,こういう理由からである。
そうした新しい農具のうち特筆すべきものの多くは,収穫以後の脱穀・調整作業を省力化・能率化するものであった。脱穀・調整は多くの雇用労働を要し,また年貢収納の時期と拡大していく裏作の作付作業が重なるため,省力化・能率化がぜひとも必要であった。脱穀には千歯扱きが発明され,50年の間にほぼ全国に普及した。もみすりには,中国から伝えられた土臼が,それまでの木臼に取って代わった。もっともこれは,千歯扱きほどには広く普及しなかったが,土臼の普及した地域では,玄米からぬかをとる搗精(とうせい)に踏臼(唐臼)が用いられた。木臼ではもみすりと同時にある程度の搗精を行うことができたが,土臼ではもみすりの能率はあがるが搗精はあまりできなかったため,あらたに搗精の工程が必要となったのである。踏臼の使用によって,ぬかの少ない白米が食べられるようになったが,白米を食べるようになった都市では,脚気が増えるという結果をもたらした。このほか,もみ殻やわらくずを能率よく除く唐箕(とうみ)も中国から伝わり普及した。玄米ともみを選別するふるいとして,千石通しや万石が現れた。
一方,水田の開発が進むにつれ,水をあげるための踏車が現れ,自然流下では水を入れられないところにも水田が開かれた。また水田の除草にはがんづめが使われるようになった。畿内とその近辺以外へはあまり普及しなかったが,二挺掛(にちようがけ)と呼ばれる特色のある農具もこの時期に発明されている。これは,麦の播種溝をつくるものであるが,麦の播種期は綿の収穫期と重なるため,綿が完熟するまで畑から引き抜かないで,しかも綿の条間に麦の播種溝を能率よくつくるものである。溝を2条一度につくれるよう2本の細い犂床をもっているため,この名がつけられた。この二挺掛と同じように綿作の関係で現れてきたものに畑用のまぐわや水かけおけがあるし,都市近郊の野菜栽培の盛況を伝えるものに豆まき車やいも植車がある。このように多彩な農具がこの時期に現れている。また,この時期から使われだした耕具に備中ぐわがある。刃がまた状になっており,粘土質の土を起こすのに,土への打込みをたやすくするとともに,土との粘着抵抗を減らすことができた。二挺掛や千歯扱き,そして踏車は日本で独自に発明された数少ない農具の代表的なものである。また,今日,農業博物館やあるいは民俗資料館などで目にする農具の多くは,この時期から使用され始めたものである。
第5段階(明治時代後半~昭和30年代)
近代に入ると畜力耕の必要が唱えられ,十分な耕深が得られる短床犂が開発された。中国犂(長床犂)は日本に伝えられて以来,その形を変えることなく,くわが主役の時代にも,水田の漏水を防ぐための床締めに一部で使われていた。一方,朝鮮から伝えられたと思われる無床犂も一部ではあるが使われていた。その両者の中間形態として生まれたのがこの短床犂で,これが時代の要求に合うものとして熊本で改良されたが,それと同じ時期にまったく独立して長野でも開発する努力が重ねられていた。そして,この短床犂が半世紀以上の間,日本の近代農業の発展を支えてきたのである。
短床犂は,その後も幾多の改良がなされ,最終的な完成をみたのは,1923年であったが,そのころは機械化への胎動が始まっていた。すなわち,すでに農用エンジンの国産化が始まっていたし,ほぼ実用的なロータリー耕耘機が使用され始めていた。いわゆる耕耘機ブームといわれる昭和30年代を迎え本格的な機械化に入るが,この30年代前半はロータリー耕耘機ではなく,歩行型トラクターに短床犂をひかせたものが主流で,短床犂の年産台数からいえば,この時期が短床犂の最盛期であった。短床犂と並んで日本の農具を代表する千歯扱きは,大正から昭和の初期にかけて,足踏みによる回転型の脱穀機に変わっていった。それはやがて動力式に変わったが,動力式への転換を決定づけたのは,歩行型トラクターや耕耘機が普及し,そのエンジンを脱穀機の動力源として利用したことであった。また,もみすりや精米は,それぞれの機械の開発とモーターやエンジンの普及とともに,大正から第2次大戦後にかけて機械化されていった。なお,短床犂が開発されたころにともに発明された水田除草機の田打車は,それまでのしゃがんでがんづめを使うという重労働から農民を解放したが,機械化の段階をとおらず,除草剤の普及により姿を消した。
→農業 →農耕文化
執筆者:堀尾 尚志
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「農具」の意味・わかりやすい解説
農具
のうぐ
農作業に用いる構造の簡単な道具のことをいう。作物の栽培や農産物の加工、養畜、養蚕など広範に使われる。農具は、農業の始まりとともに手先にかわるものとして、1本の棒の使用から、やがて曲がり木を利用するようになるなど自然発生的に始まったものと考えられており、鋤(すき)、鍬(くわ)、犂(すき)(プラウ)の刃先は木製から石製へ、石製から鉄製へと進化したとされている。しかし、その発達の仕方は、それぞれの農業の置かれた環境、自然条件や、農業の形態、民族の風習などによって異なる。農具はまた人力用と畜力用とに大別でき、西洋では畑作中心の農業で、しかも有畜大規模経営の道を歩んだため、早くから畜力用具が発達したが、日本では水稲作中心で零細集約経営に進んだため、農具は人力用を中心に発達した。ヨーロッパ諸国やアメリカ、日本などにおいては、農具から農業機械への発展の道をたどり、農業の主要な作業の手段としては農業機械が使われており、アジアやアフリカの新興国においても、経済発展に伴って動力を用いた農業機械の普及が一部で始まっているが、まだ多くの国々では人力用、畜力用の農具に依存している。
[井上喬二郎・谷脇 憲]
種類
耕うん、整地のための代表的な農具として、人力用では鋤、鍬があり、畜力用として犂がある。土を耕すことは作物栽培のもっとも基本的な作業であり、ヨーロッパ諸国や日本では、トラクターを動力として耕うん、整地が行われている。アジアの新興国では、21世紀になって経済発展が進み、その度合いに応じて、四輪トラクターをはじめとする動力を利用した農具の利用が進んでいる。中国やタイ、マレーシア、インドの稲作の中心地では、乗用トラクターが使われるようになってきている。これらの国々の一部やインドネシア、フィリピン、ミャンマー(ビルマ)、バングラデシュなどでは歩行用トラクターが使われ、経済発展の及んでいない周辺部では、まだ畜力犂による耕うんが残っている。犂は犂床(接地部)の長さにより無床犂(むしょうり)、長床犂、短床犂に分類される。日本では古来、無床犂、長床犂が使われていたが、昭和に入って短床犂が使われるようになった。現在、中国や東南アジアで使われている犂は長床犂であり、インドでも大部分が長床犂の系統である。スーダン、タンザニアなどアフリカの諸国や東南アジアの一部では畜力耕も行われておらず、鍬を使っての人力耕うんが行われている。これらの地方では、鍬のように土を打って耕す道具と、鋤やシャベルのように土をおこす道具との2種類のみで、耕うん、整地、作溝など土を処理するすべての作業を行っており、形状も単純である。
田植は、日本では田植機が用いられているが、日本以外は手植えが主流であり、しかも大部分が乱雑植えであって、田植用の農具はほとんどない。一般に東南アジアでは、日本に比べ草丈の長い苗を移植するが、苗を深く植えるための道具(マレーシアでのククカンビンなど)を使う地方もある。
収穫用農具としては、刈り取りのための鎌(かま)、掘り取りのための鍬が基本である。日本の稲用の鎌は、緩い円弧の鋸刃(のこば)が柄に約60度の角度でついているものが用いられているが、日本以外の大部分の国では、強い円弧の鋸刃が柄の延長上に取り付けられた西洋小鎌(シックル)に類似したものが用いられている。アフリカやインドネシアの一部では穂刈りが行われており、指につけた穂刈り用ナイフ(インドネシアのアニアニなど)で摘み取られる。
脱穀作業は、ごく一部で動力脱穀機や足踏み脱穀機が用いられているが、大部分は、穂のついた束を脱穀台にたたきつけたり、牛のひづめに踏ませたりして脱穀する。藁(わら)や穂くずと穀実の選別は自然の風を用いる。その後、竹や草で編んだ莚(むしろ)や地面に広げて天日で乾かす。現在、日本では、刈り取り、脱穀、乾燥の作業は、バインダー、コンバインや乾燥機を用いている。
欧米や日本では農業機械が発達して、農具は重要性を減じ、脱穀用具としての千歯扱(せんばこき)や籾摺(もみす)り用具としての唐臼(からうす)などのように、現在みることのできなくなった農具も少なくないが、鍬や鎌などの小道具は今日でもなお欠くことのできない農具として使われている。東南アジアやインド、アフリカの諸国では、現在でも農具類は作物生産に欠くことのできない重要な道具である。それぞれの国によって種類や形状、発達の違いはあっても、たとえばタイの水牛に引かせる稲束運搬そりや、バングラデシュのてこを利用した人力揚水機(ダン)などのように、それぞれの置かれた条件に対応したくふうがみられ、変化を重ねながら発達の道をたどっている。
[井上喬二郎・谷脇 憲]
日本の農具の歴史
日本の農具の発達段階を概観すると、(1)石製農具と木製農具の段階、(2)古墳時代の鉄製農具の出現と普及、(3)江戸時代以降の農具改良と発明、(4)昭和初期からの動力機具の出現と第二次世界大戦後の農機具の発展・普及に大別できる。これは耕うん、収穫、脱穀調整用具を基準とした発達段階であるが、いずれも各段階は当時の生産・生活様式、社会・経済構造と密接な関連をもって展開している。
日本における農耕の開始についてはさまざまな議論があり、縄文時代の農耕の確定には問題もあるが、最近は各地の縄文遺跡からエゴマ、ヒョウタン、リョクトウ、ソバ、イネなどが検出され、また福岡県板付(いたづけ)遺跡からは縄文時代終末期の水田遺構と関連施設、農具、籾(もみ)が出土し、日本の水稲作の開始は従来の土器編年に従えば縄文時代晩期の終末期で、さらにこれ以前には焼畑農耕や庭畑(住居周辺の常畑(じょうばた))での作物栽培が行われていたと考えられる。農具についていえば縄文時代終末期以降、弥生(やよい)時代には水稲作が定着・普及するなかで多くの木製・石製農具が検出されているが、これ以前は打製石斧(せきふ)などが耕うん用具として比定できるのである。弥生時代の水稲作に伴う農具では、耕うん用具としてカシ類の木を材料にした平鍬(ひらぐわ)、丸鍬、股鍬(またぐわ)、鋤(すき)(長柄鋤、着柄鋤、スコップ)、収穫用具として穂首刈りを行った石包丁(いしぼうちょう)・石鎌(いしがま)があり、この収穫具は水稲だけでなく、畑作穀類の収穫にも使われたようである。弥生時代の中期には鍬・鋤の一部の型のものは、その先端に鉄刃がはめられるようになり、北九州では弥生中・後期には鉄鎌が出土し、一部を除いてはこの時期から石包丁がほとんどみられなくなる。さらに弥生後期には木製のエブリ、田下駄、大足(おおあし)、田舟が使われ、脱穀調整具としての竪臼(たてうす)、竪杵(たてきね)、横杵もみられる。これらのことから、弥生前期には刃先まで木製であっても耕うん用具には分化がみられ、後期にはエブリ、大足による代掻(しろか)きや緑肥の踏み込み、さらに水路からの灌漑(かんがい)と排水、高倉による穀物の保存など、水稲作技術やその経営にある程度の完成をうかがうことができる。
鉄製農具の使用は一部弥生時代中期からみられるが、これが大きな意味をもってくるのは古墳時代になってからである。古墳時代に入ると鉄製の股鍬(馬鍬)が現れ、ついで5世紀中ごろには鉄製のU字形の鋤先・鍬先が木製の鋤・鍬に着装されるようになる。これによって稲作は乾田耕作、深耕が可能となり、生産量が増大し、さらに収穫には刃先が湾曲した曲刃(きょくば)の鉄鎌が使われ出し、水稲の根刈りが確実となってくる。この時代には水稲のほかにアワ、ヒエ、オオムギ、コムギ、ダイズ、アズキ、ウリ、ナス、モモ、アサなどが遺跡から検出され、畑作の進展もうかがえる。鉄製の耕うん用具の発達は、5世紀中ごろからの鉄の国内生産、古墳の造築からも十分予想でき、土木技術の発達から灌漑施設も充実するのだが、鉄製農具の所有は、初めは在地の首長層に限られ、これが普及するのは6世紀になってからである。一方ではこうした鉄製農具による生産力の向上が古代国家成立の基礎となっていったのである。
古墳時代の鍬・鋤の発達と鎌の確立に続き、次の時代には犂(からすき)が出現する。犂は従来、島根県美濃(みの)郡匹見(ひきみ)町(現、益田市)出土の犂鑱(すきさき)が古墳時代のものとされていたが、これは最近の研究から室町時代末以後のものとわかり、古代犂は正倉院の「子日手辛鋤(ねのひのてがらすき)」と、平安時代の諸文献にみえるものがもっとも古い資料である。「子日手辛鋤」は無床犂(むしょうり)で、平安期の『新撰字鏡(しんせんじきょう)』『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』の「加良須支(岐)(からすき)」は、『延喜式(えんぎしき)』の犂とともに長床犂系のものである。犂のカラスキという訓からは、これが大陸からの伝来であることがわかり、犂の普及は10世紀後半から12世紀初めにかけてである。『新猿楽記(さるがくき)』(11世紀中ごろ)や『今昔物語』(12世紀初)などには鋤、鍬、馬耙(まぐわ)(馬歯(まぐわ))、犂(辛鋤)、鎌などがみえ、この時代には西日本を中心に犂が普及し、さらに鍬、鎌などの鉄製農具が一般農民にまで広まったと考えられる。
鎌倉・室町時代には犂は上層農民のもので、下層農民は鍬を耕うん用具の主体とし、さらに太閤(たいこう)検地以後江戸時代は、耕うん用具の発達が鍬の分化という形で進んでいく。鍬は歴史的に身分階層化が進むなかで、下層の農民が自立、維持していく基礎的農具としての意味をもつわけで、江戸時代後期には各地の自然・耕地状況、使用目的に応じたさまざまな形態のものが確定するのである。大蔵永常(おおくらながつね)の『農具便利論』(1822)では24地方27種の風呂(ふろ)鍬のほか、唐鍬(とうぐわ)、備中(びっちゅう)鍬、踏鋤(ふみすき)(鋳鍬(いぐわ))、鋤(京鋤(きょうすき)、江州(ごうしゅう)鋤、関東鋤)、馬鍬なども記され、鍬や鋤による田畑の耕起、砕土、均平、畝立(うねた)て、中耕、除草などの技術は完成していたと考えられる。綿作地帯では筋切り、二挺掛(にちょうがけ)といった作条具も記され、中耕除草用具には雁爪(がんづめ)、小熊手(こぐまで)、草削りなどもできていた。
江戸時代はこれらとともに脱穀調整用具も著しく発達した。収穫用具の鎌は、江戸時代前期に砥石(といし)の名産地が生まれていることから日常的な農具となっていたことがうかがえ、脱穀用具では元禄(げんろく)期(1688~1704)に竹の千歯扱(せんばこき)がつくられ、その後鉄製に変わって急速に広まり、さらに選別用具では1684年(貞享1)の『会津農書』に「颺扇(とうみ)」(唐箕)がみられ、寛政(かんせい)年間(1789~1801)には各地で使われるようになった。脱稃(だっぷ)(籾摺(もみす)り)に用いる磨臼(すりうす)は江戸時代になると土の唐臼(からうす)が使われ、江戸時代後期には遣木(やりき)の往復運動によって臼を回転させる方式のものが普及し始めている。脱穀用具は千歯以前は、扱(こ)き箸(ばし)(扱き竹)、扱き管(くだ)を使ったが、竹歯・鉄歯の千歯が出現することによって脱穀能率は飛躍的にあがった。千歯の異名「後家倒し」は、まさに能率向上とこれによる家族労働形態の変化を示している。唐箕については文献上では前述のとおりだが、実物では明和(めいわ)4年(1767)の銘のものが残されている。
江戸時代にはこのように農具の改良・発明あるいは摂取が行われ、日本農業の労働集約的な性格ができあがった。しかしあくまで手耕の枠を超える農業ではなかった。これが明治に入ると西洋農学の影響を受け、犂への関心が高まり、牛馬による犂耕が普及され、明治中期には在来の長床犂・無床犂の利点をあわせた短床犂がつくられ、各地で使われるようになるのである。そして大正初期には千歯にかわって足踏み脱穀機が発明され、昭和初期には動力脱穀機が出現して脱穀調整用具が機械化され、第二次世界大戦後には動力耕うん機の普及によって耕うん過程も機械化された。
[小川直之]
ヨーロッパの農具の歴史
ヨーロッパの北西部は寒冷湿潤な気候で、土壌も粘土質の所が多いため、古代から乾地農法として農業が発達していた地中海域とは環境がまったく違っていた。そのため耕うん技術ひとつについてみても、軽い土壌の表層を砕いてかき混ぜ、水分を有効に保持させる乾地農法は、湿潤な粘土質土壌を畝(うね)立て、深耕、反転などにより排水の効果をあげようとくふうする農法には適用できず、使用される農具も適さなかった。ヨーロッパでは農法と農具が独自の形態をとって発達した。
[小林 正]
犂
新石器時代には木製掘り棒、鍬(くわ)などが使用され、その後、地中海域で使用されている犂(すき)がヨーロッパ各地に広まったとされているが、この犂は粘土質土壌に適さないため、軽い土壌のほんの一部地域での使用に限られていたようである。
ローマ時代以降粘土質の生産性の高い土地の開墾が盛んとなり、耕地が広大となった10世紀から13世紀になって、農具は目だった発達をみるようになる。
紀元前1世紀には鉄製刃板がついたものが普及し、また鉄製犂刀(りとう)も取り付けられていた。この刃板と犂刀は地中海域のものとは異なった形で堅牢(けんろう)につくられ、重いものであった。
7世紀には車輪が取り付けられることによって耕深を調節したり、使いやすくする技術が開発され、11世紀には壢土(れきど)(すくい上げた土)を直接反転させる撥土板(はつどばん)がつくられた。近代のプラウの原型はこの時代にできたものと考えられる。撥土板は複雑な曲面のため当時の技術では製作が困難であったが、19世紀に入り初めて各種の撥土板が完成した。
[小林 正]
砕土器
11世紀には犂で耕うんしたところに種が播(ま)かれ、馬鍬(まぐわ)により砕土、覆土が行われたようである。馬鍬は木枠に鉄製の歯杆(しかん)を取り付けたもの、オーク材の円柱に歯杆を取り付けた回転式のものなどがつくられ、現在の歯杆固定形、回転形ハローのもととなっている。
[小林 正]
播種器具
古代の耕うんは種子の覆土作用も同時にさせていたようであり、犂に木製の管を取り付けた播種(はしゅ)機が古くからあったとされているが、使用された形跡は少ない。中世においてはシードリップとよばれる枝編み細工の箱形容器に種子を入れ肩から下げて手で播いていた。また簡単なものは前掛けを上方に折り曲げて、その中へ種子を入れて播いていた。
[小林 正]
鎌
新石器時代には穀類の刈り取りには火打石でつくられた刃を鋸歯(きょし)状に取り付けた木製の鎌(かま)が使用された。刃部の曲線は現在の小鎌のような中凹状であった。ヨーロッパでは天候が変わりやすい気象条件であったため収穫作業は高能率が要求され、鎌の柄(え)についても手首が疲れないようくふうがなされた。前4世紀のころより片手で使用する小鎌は柄の端で刃が後方に曲がった形となり、手首の酷使を軽減させている。
中世に入り牧草などの刈り取り作業を能率化するために、両手で使用する柄の短い大鎌がつくられ、11世紀のころこの大鎌には長い柄に短い取っ手がつけられるようになった。
14世紀の終わりごろには穀類を刈り取ったあと束ねやすくするために、稈(かん)(茎)を集める働きをさせる半円形の細枝を柄に取り付けた把装大鎌が普及し、16世紀以降穀類の刈り取りは小鎌からこの大鎌にとってかわられた。今日のシックルsickleは当時の小鎌、サイスscytheは大鎌、クレードルcradleは、把装大鎌がそれぞれもととなって発達したものである。一方、畜力用収穫機は茎の先端近くから刈り取る収穫櫛(ぐし)なるものが古代ローマにあったとされているが、以後の利用はみられない。畜力用モーア、リーパーreaper(刈取機)、バインダー、コンバインは19世紀に入ってから考案された。
[小林 正]
脱穀器具
19世紀中ごろまでは、連枷(れんか)を使用して人力で打ち落とすか、禾穀(かこく)を地面に敷き役畜に踏ませたり、石のローラーを引かせたりして脱穀した。スレッシャーthresher(脱穀機)は19世紀前半に考案されている。
[小林 正]
中国の農具
鍬
鎬(こう)は日本の唐鍬またはばち鍬に類似し、歯鎬(しこう)は備中鍬に類似していて、歯杆の数は2~4本である。板鍬は日本の金鍬によく似ている。日本に伝播した本家であるが、種類は少ない。
[小林 正]
犂
中国の犂は前4世紀ごろ地中海域で使用されていたものが伝えられたとされている。現在の犂の形状は11世紀ごろのものが原型となっているようで、日本の長床犂(ちょうしょうり)と似た形をしている。
[小林 正]
鎌
中国の鎌刀(れんとう)はヨーロッパの鎌と形状は異なる。昔の鎌刀は鉄製の刃に木の柄をつけたものと、刃も柄部もすべて鉄製のものとがあった。その形は現在のものと大差ないが、柄の取り付け方法が違っている。削穀刀(さっこくとう)は主としてアワ穂の刈り取り、爪鎌(つめがま)はコウリャン、アワなどの穂だけを収穫するときに使用されていた。
[小林 正]
脱穀器具
畜力でけん引する石ローラー、連枷、稲床などがおもなものである。選別には扇車(せんしゃ)(唐箕(とうみ))が使用されている。石ローラー、扇車は中国で考えられた農具である。
[小林 正]
『農政調査委員会編・刊『体系農業百科事典 第1巻』(1966)』▽『飯沼二郎・堀尾尚志著『農具』(1976・法政大学出版局)』▽『大日本農会編『日本の鎌・鍬・犂』(1979・農政調査委員会)』▽『大塚初重・戸沢充則・佐原真編『日本考古学を学ぶ2』(1979・有斐閣)』▽『日本常民文化研究所編・刊『紀年銘(年号のある)民具・農具調査――東日本』(1980)』▽『日本常民文化研究所編・刊『紀年銘(年号のある)民具・農具調査――西日本』(1981)』▽『森浩一他編『日本民俗文化大系3 稲と鉄』(1983・小学館)』▽『農業機械学会編『生物生産機械ハンドブック』(1996・コロナ社)』
百科事典マイペディア 「農具」の意味・わかりやすい解説
農具【のうぐ】
→関連項目杵
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農具」の意味・わかりやすい解説
農具
のうぐ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「農具」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の農具の言及
【農業】より
…これを出発点として野菜,綿,菜種,藍,紅花,大麻,養蚕などを通じて,大きな地域差・年代差をもちながら農民の手から商品として売られる生産物が増加し,地域によっては米も商品となっていくところの,変化の過程だったと要約できる。この間に自給肥料は魚類,油粕類の購入肥料を利用するようになり,同時に農具,作物品種も改良され,面積当り生産量も増加していく。この変化の全過程を通じて,田畑ともに毎年作付けを行い,さらに二毛作も一般化していると考えられる。…
【農書】より
…特に王禎《農書》は山東生れの彼が安徽,江西の地方官をした経歴を生かして南北農業を対比,総括して記している。さらに《農器図譜》16巻は初めての総合的な農具の図解で,在来農具のほとんどに及び,農史研究のうえに役立つことが多い。明代農書の代表的なものは徐光啓の《農政全書》60巻である。…
【百姓】より
…これらの小農は親方,御家,公事屋,役家などと呼ばれる村落上層農民(初期本百姓)に隷属し,生産・生活の全般にわたって主家の支配と庇護を受けていた。彼らは主家から零細耕地を分与され,主家の許しを受けて刈敷場(かりしきば)から肥料を採取し,自分持ちの小農具(鍬(くわ),鎌(かま))で分与地を耕作し,そこで自己の再生産をまかない,一定日数の賦役労働を主家の農業経営に提供した。主家への労働提供に際しては,大農具(家畜,犂(すき))は主家のものを使用し,小農具は自分持ちの農具を持参して使用し,食事の給付などを受けた。…
【弥生文化】より
…また,陸田も当然存在したであろう。 農具には各種の鋤,鍬(くわ)があり,刃の先までカシなどの硬い木材で作ってある。IV期(中期末)以降,九州では青銅および鉄の刃先を使い始めたが,弥生時代末期に至るまでこれはなかなか普及しなかった。…
※「農具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新