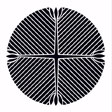精選版 日本国語大辞典 「若松」の意味・読み・例文・類語
わか‐まつ【若松】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- ① 樹齢の若い松。また、生えて間もない松。⇔老松(おいまつ)。
- [初出の実例]「巖(いはほ)ろのそひの和可麻都(ワカマツ)限りとや君が来まさぬ心(うら)もとなくも」(出典:万葉集(8C後)一四・三四九五)
- ② 新年の飾りの小松。また、門松。《 季語・新年 》
- [初出の実例]「たみもとくわか松もろともに、千世かけて、千世かけて、さかふる御代こそめでたけれ」(出典:虎明本狂言・松楪(室町末‐近世初))
- ③ 松の若葉。松の新芽。《 季語・春 》
- ④ 白紙を刻んで作った松葉状の花。葬礼の時に用いるもの。
- [初出の実例]「若枩を紙でこさへる気のどくさ」(出典:雑俳・柳多留‐二一(1786))
- ⑤ 襲(かさね)の色目の名。表は萌葱(もえぎ)で裏は紫のもの。若緑。→松襲(まつがさね)。
- ① 樹齢の若い松。また、生えて間もない松。⇔老松(おいまつ)。
- [ 2 ]
わかまつ【若松】
- 姓氏の一つ。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「若松」の意味・わかりやすい解説
若松(福岡県)
わかまつ
福岡県北九州市北西部に位置する港湾地区。1914年(大正3)市制、1963年(昭和38)門司(もじ)、小倉(こくら)、若松、八幡(やはた)、戸畑(とばた)の5市合併による北九州市設置により区制施行し、同市若松区となる。響灘(ひびきなだ)に臨み洞海湾(どうかいわん)を抱く若松半島の大部分を占める。若松港は江戸時代福岡藩の藩米の積出し港で、遠賀(おんが)川分流の堀川(ほりかわ)の開削に伴い、1830年(天保1)焚石会所(たきいしかいしょ)が芦屋(あしや)に次いで置かれて石炭積出し港となったが、明治初年のころはまだ寒村にすぎなかった。1890年(明治23)築港会社の設立と、1891年の筑豊(ちくほう)興業鉄道(現、JR筑豊本線)開通により、全国一の石炭積出し港に発展した。その後石炭産業とともに栄えてきたが、昭和30年代のエネルギー革命による石炭産業の衰退と、洞海湾で他の旧4市と隔てられている半島性のために地位低下が著しい。近年では北湊(きたみなと)や二島(ふたじま)の埋立地に立地する金属、機械、輸送機器などの工業のほかに、半島北東端に造成された大規模な響灘工業用地にブリヂストン、三井鉱山(現、日本コークス工業)などの大手企業が進出したが、西部は住宅地に計画が変更された。1962年開通した若戸大橋(わかとおおはし)(国の重要文化財)は若松の半島性を解消するとともに、北九州市の新名所ともなった。南西部には北九州市立大学、早稲田大学大学院(北九州キャンパス)、九州工業大学大学院などが集合する北九州学術研究都市が整備中である(2018年第2期事業完了)。西部の島郷(しまごう)では野菜生産を中心とする農業が、響灘沿岸では一本釣りなどの沿岸漁業が行われている。高塔山(たかとうやま)公園から石峰(いしみね)山(302.5メートル)、頓田(とんだ)貯水池、響灘緑地(グリーンパーク)を経て脇田(わきた)海岸に至る玄海(げんかい)遊歩道や、玄海国定公園に含まれ、遠見ノ鼻(とおみのはな)や千畳敷(せんじょうじき)などの景勝地がある海岸一帯は行楽客でにぎわう。若松港(北九州港)は洞海湾内の若松、戸畑、八幡地区の各埠頭(ふとう)からなり、洞海港ともいう。
[石黒正紀]
『『若松市史』(1959・若松市)』
若松(長崎県)
わかまつ
長崎県南松浦(みなみまつうら)郡にあった旧町名(若松町(ちょう))。現在は新上五島町(しんかみごとうちょう)の南部を占める。旧若松町は五島列島の中央部に位置する若松島(古名狩俣(かりまた)島)を主体に、1956年(昭和31)日ノ島(ひのしま)村を合併、町制施行。2004年(平成16)上五島、新魚目(しんうおのめ)、有川(ありかわ)、奈良尾(ならお)の4町と合併、新上五島町となる。旧若松町域は、31の島(有人島6)からなり、中心となる若松島と中通島(なかどおりじま)南西部は若松大橋で結ばれ、中通島の区域には国道384号が通じる。名称は霊木を祀(まつ)る若松宮に由来する。中心集落にある若松港は、海域公園に指定された若松瀬戸に臨み、西海国立公園(さいかいこくりつこうえん)の観光基地で、港からは五島各地への航路があり、海上タクシーも用意されている。町の産業は漁業が主軸で、一本釣りのほかハマチ、タイなどの養殖が盛んで、若松、神部(かんべ)、土井(どい)ノ浦には水産加工場がある。町内には交通不便な地区が多く、キリシタンの伝統をくむカトリック集落が散在し、桐(きり)(中通(なかどおり)島)、土井ノ浦、小田(おだ)(有福(ありふく)島)には天主堂がある。また、国の重要文化財として、極楽寺(ごくらくじ)の銅造如来(にょらい)立像がある。漁生浦(りょうぜがうら)島(2009年の人口35)、有福島(同150)、日ノ島(同58)は、小瀬戸、ヒギレ、宮瀬戸を隔てて若松島(同1889)の属島をなすが、近年これらの瀬戸に交通路や水路を兼ねた防波堤が建設され、本島と結ばれている。また、中通島の西岸の集落から若松港への通学船が就航している。
[石井泰義]
改訂新版 世界大百科事典 「若松」の意味・わかりやすい解説
若松 (わかまつ)
陸奥国会津郡の城下町。現在の福島県会津若松市の中心部。1189年(文治5)源頼朝の奥州攻めの勝利によって会津に所領を与えられた三浦一党の佐原氏は,のち蘆名氏を名のり,14世紀,直盛のとき小高木(現在の若松城跡)に館を造り,東黒川館と称し住したという。黒川を拠点に中世会津を支配した蘆名氏は,1589年(天正17)伊達政宗に滅ぼされ,政宗もまた1年余で米沢へ去った。
90年,豊臣秀吉から会津の地を与えられ黒川へ入った蒲生氏郷(がもううじさと)は,郷里近江国蒲生郡の若松の森にちなんで,黒川を若松と改めた。氏郷は,これまで郭内にあった大町,馬場町などの町屋を郭外に移し,近江国日野町から従ってきた商工業者には日野町(のちの甲賀町)を割り出した。商人,手工業者の住む町屋は郭外に,侍屋敷は郭内に画然と区別し,雑居を改めた。特別の由緒をもつ寺社以外は郭外に移した。若松町の基本的なあり方は氏郷によって作られたといえる。大町,馬場町,本郷町,三日町,桂林寺町,六日町には六斎市が開かれた。1593年(文禄2)には天守閣も完成,毎日どこかの町で市が開かれ,若松は〈奥州の都〉とうたわれるほどのにぎわいをみせたという。大町,一之町と七日町とを分ける札辻からは,東へ白河・二本松街道,南へ下野街道,西へ越後街道,北へ米沢街道が走り,若松は交通の要地であった。98年(慶長3)上杉景勝120万石,1601年蒲生秀行60万石,27年(寛永4)加藤嘉明40万石と領主は交替,そして43年に入部した23万石保科(のち松平)氏が幕末まで会津を支配した。その間,若松は城下町として会津地方の政治,経済の中心地であった。2ヵ所に町奉行所が置かれ,町々では検断,名主が町政に当たった。延宝(1673-81)ごろからは市に代わって常設店舗が町々に増えていき,古手(ふるて)・茶・肴・小間物などを扱う問屋・小売の商人,酒造・塗・鍛冶などに従事する手工業者を,筆頭検断簗田氏が商人司としてたばねていた。
会津戦争は,若松の武家屋敷の大半と町屋の3分の1を灰にした。町は大きな打撃をうけた。しかし1868年(明治1)民政局設置,翌年には巡察使が来て町の復興に当たった。72年株仲間は廃止され,商工業は自由に行われるようになった。漆器業,酒造業などが盛んとなり,米,繭,木材などが若松を経由して他地方へ売り出された。産業の発展は,金融機関の設置を促し,第三十一国立銀行,安田銀行会津支店,会津銀行が次々に開設された。貨物を輸送する内国通運会社が生まれ,郵便取扱所,県裁判所の若松出張所も設置された。若松県を経て76年福島県に所属すると,第11区会所が若松に置かれ,若松は依然会津地方の中心であった。89年市町村制施行により若松町となる。人口2万1100人余。99年,郡山~若松間に岩越鉄道が開通すると,さらに町は発展を約束された。同年市制施行,若松市となる。55年市名を会津若松市と改めた。
→会津藩
執筆者:丸井 佳寿子
若松 (わかまつ)
福岡県北部,北九州市の区名。1914年市制施行の若松市が,63年小倉など4市と合体して北九州市となった際に区制を施行。人口8万5167(2010)。若松半島のほぼ全域を占め,東半の中生層の山地と西半の低い丘陵地からなる。市街地は東端の洞海旧湾口に発達している。近世には福岡藩の米蔵,焚石会所などが設けられ,遠賀川~堀川運河~洞海湾のルートで結ばれて,米や石炭が積み出されていたが,明治前期までは小集落にすぎなかった。1890年築港会社が創業し,翌年筑豊鉄道(現,JR筑豊本線)が開通してから筑豊炭田を後背地とする全国一の石炭積出港に発展した。並行して鉄鋼や炭鉱関連,港湾立地型の諸工業も発達し,北九州工業地帯の一角を形成してきた。1950年代末からの石炭産業の急激な衰退で深刻な打撃を受けた。62年戸畑区との間に若戸大橋が通じ,69年からは響灘(ひびきなだ)海岸に大型工業団地が造成され,鉄鋼,コークスなどの工場が立地した。
西部の丘陵地帯では野菜栽培も盛んであるが,宅地開発も進行している。沖合8kmの白島には洋上石油備蓄基地(560万kl)が建設された。東端の市街地背後には高塔山公園があり,火野葦平の文学碑が建つ。北岸は玄海国定公園の東端をなす脇田(わいだ)海岸など美しい海岸が続く。
執筆者:土井 仙吉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「若松」の意味・わかりやすい解説
若松【わかまつ】
若松[町]【わかまつ】
若松[区]【わかまつ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本歴史地名大系 「若松」の解説
若松
わかまつ
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「若松」の意味・わかりやすい解説
若松
わかまつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
[日本酒・本格焼酎・泡盛]銘柄コレクション 「若松」の解説
わかまつ【若松】
世界大百科事典(旧版)内の若松の言及
【会津藩】より
…陸奥国若松に藩庁をおいた藩。1589年(天正17)中世会津を支配した蘆名氏を破り,この地を領した伊達氏はまもなく去り,90年蒲生氏郷が90万石の領主として黒川の地に入った。…
【会津若松[市]】より
…福島県会津地方北東部にある市。1899年北会津郡若松町が県内最初の市制を施行,若松市となり,1955年会津若松市と改称,同時に北会津郡の大部分を占める湊ほか6村を編入した。人口11万9640(1995)。…
【遠賀川】より
…18世紀に入ると流域農村で石炭やハゼ蠟の生産が進んだので,それらの輸送が盛んとなった。1762年(宝暦12)の堀川の完成によって,冬の季節風をまともに受ける芦屋をさけ,直接に洞海湾内の若松への艜の航行が可能になったので,以後,商品の多くは若松に送られるようになった。幕末には年間,延べ2万艘の艜が上下し,約8万tの米,石炭を積み下ろしたと推定される。…
【洞海湾】より
…福岡県北東部,北九州市の若松,戸畑,八幡東,八幡西4区に囲まれた湾。石峰・皿倉両山塊間の地溝が入海となったもので,東西に細長く,湾奥まで約8kmある。…
※「若松」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...