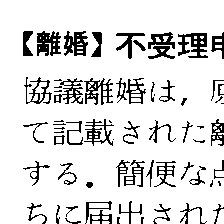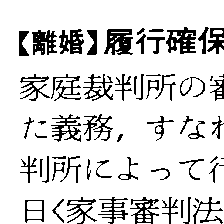離婚(読み)リコン(その他表記)divorce
精選版 日本国語大辞典 「離婚」の意味・読み・例文・類語
り‐こん【離婚】
- 〘 名詞 〙 夫婦が生存中に婚姻を解消すること。日本の法律では協議離婚のほか、裁判上の離婚、調停による離婚が認められている。夫婦わかれ。
- [初出の実例]「夫婦は其協議を以て離婚を為すことを得」(出典:民法(明治三一年)(1898)八〇八条)
- [その他の文献]〔晉書‐王羲之伝〕
改訂新版 世界大百科事典 「離婚」の意味・わかりやすい解説
離婚 (りこん)
divorce
Ehescheidung[ドイツ]
その社会で承認されている結婚関係(日本民法では婚姻という)を,生存中に解消すること。単なる同棲や内縁とみなされる男女関係の解消は,これに含まれない。離婚禁止を重要な教義としてきたキリスト教系の諸国では,ほぼ18世紀まで離婚は認められなかった。18世紀末のフランス革命を契機として限定的な離婚方式が作られ,19世紀から20世紀にかけて,それらの国々でも一般的な離婚制度がおかれるようになった。ただし,ブラジル,チリ,アルゼンチン,フィリピンなど,依然として離婚法をおかない国も存在する。日本では,他のアジア諸国と同じように,宗教や公権力によって離婚が規制されることはなかったので,かなり古くから,離婚は自由にされていた。ただし,夫側からの離婚のみであって妻側には離婚の自由がなく,妻の離婚請求権を初めて認めた1873年5月15日太政官布告も,父兄弟の付添いを条件とし,夫妻双方の離婚請求権を認めた明治31年民法も不平等な離婚原因を残していた。夫婦平等の離婚制度が出現したのは,ようやく1948年施行の現行民法に至ってである。
離婚の種類
現在ほとんどすべての国において,国が離婚の成立に関与し,破綻の実情を確かめるとともに,裁判による離婚のみを認めている。しかし日本においては,〈裁判離婚〉のほかに,明治民法以来現在まで,当事者間の自由な合意とその届出だけでよい〈協議離婚〉の制度が存在し,大多数の離婚はこの形式で処理されてきた。ちなみにタイ,ミャンマー(旧ビルマ),ベトナムやスウェーデンなどにも協議離婚の制度はあるが,裁判所等の公機関によって離婚意思の確認が行われることにおいては,日本とは相違している。
日本では第2次大戦後,家庭裁判所が創設され,協議が調わない離婚についての紛争は,まず,必ず家庭裁判所の調停にかけられ(調停前置主義),そこで〈調停離婚〉が成立しないか,審判で離婚を宣せられたもの(〈審判離婚〉)が確定しなかったかの場合のみ,訴訟として〈裁判離婚〉の審理に持ち込むという新しいシステムがとられた。審判離婚は,2週間以内に異議の申立てがあれば失効する点を除けば,簡易な形をとった一種の裁判離婚であるが,調停離婚は,両当事者の離婚合意を斡旋したものであるから,その本質は協議離婚の一種といえる。ただしかし,単に意見を一致させたというのではなく,家庭裁判所が法の趣旨をくみ,社会正義に照らして妥当と思われるレベルにまで高めた合意を得るように尽力するのであるから,その実質はかなり裁判離婚に近いものとなる。
法定離婚原因
裁判離婚には,民法に定められた特定の離婚原因を必要とする。明治民法では10種あげられていたが,現行民法では次の5種である(770条1項1~5号)。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき 不貞とは,学説では夫婦間の貞操義務に反する一切の行為と解しているが,判例では,姦通(性関係の実行)にほぼ限っている。その他の異性との不正常の行為等の場合には,他の事情と総合して第5号に当たるとしている。(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき 遺棄とは,相手方を置去りにして飛び出す行為だけでなく,相手方を追い出したり,相手方をして出ざるをえないようにしむけて復帰を拒むことなど,すべてを含んでいる。職業上の必要など合理的な理由のために別居していても,生活費の供与を怠るときは遺棄となる裁判例は多数ある。遺棄の期間は問わない。(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 連続して3年以上,生死がわからないときであって,生存が推定されるようなたんなる行方不明(所在不明)は含まれない。(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき 最高裁判所は,当初,たとえこれに該当しても,病者の離婚後の療養・生活などについて,保障の見込みがついたうえでなければ,離婚請求は許さないとの態度をとっていたが,1970年判決以降は,その態度をやわらげている。(5)そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき もはや婚姻の本質に応じた共同生活の回復が不可能とみられるほど深く破壊した事由をさす,と解されていて,具体的には次のような場合が該当する。(a)懲役を受けるような犯罪を犯し,家族生活に重大な支障を与えたとき。(b)耐えがたいほどの暴行虐待を与えて,婚姻継続には忍従のほかないようなとき。(c)相手方の身内から虐待・侮辱を受けるにもかかわらず,相手方が婚姻維持に努力を払おうとしないとき。(d)いわゆる性格の相違がひどくて調和がはかれず,愛情の喪失がはなはだしいとき。(e)双方に離婚意思はあるが,感情や財産上の問題から協議が調わないとき。(f)破綻についての責任はどちらにもなく,相手方に離婚意思もない場合でも,重大な事由と認定されるような特別な事情,たとえば,一方が強度の性格異常者であったり,親族同士の対立が激烈であったり,などするとき。
なお最高裁判所は,1952年の判決以来,婚姻破綻がもっぱら夫に起因し,妻がなお夫婦関係の継続を望む場合には,夫からの離婚請求を繰り返し退けることによって,〈有責配偶者からの離婚請求は許されない〉との法理を堅持してきた。しかし,その最高裁も1987年の判決で態度を変更した。夫婦間の別居が双方の年齢,同居していた期間と比べ相当長期に及び,未成熟の子供がいない場合については,特別の事情のない限り,有責者からの請求も認める,と判断した。結局,各国の動向にならって破綻主義にふみきったのである。
そこで,法務省の法制審議会も,96年の〈民法の一部を改正する法律案要綱〉において,第4号を〈夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき〉,第5号を〈3,4のほか,婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき〉と改めるよう提案している。
離婚の効果
離婚のもっとも基本的な効果は,婚姻から生ずるいっさいの権利義務が消滅し,姻族関係も消滅することである。
(1)氏の変更 婚姻の際に氏を改めた妻または夫は,離婚によって婚姻前の氏に復し(復氏),戸籍は別のものになる。ただし,氏が変わることによって不便や不利益を感ずる者は,離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法の定めに従って届け出れば,婚姻中に称していた氏を称することができるように,1976年6月から法改正された。
(2)子の監護と親権 離婚する夫婦の間に未成年の子があれば,子の保護のために,その子の親権者と監護者を決定する必要がある。子の監護者と親権者は一致することが望ましいが,必ずしも同一人であることを要しない。親権者は父母のいずれかしかなれないが,監護者は現実に保護監督する者でよい。親権者ならびに監護者は,協議離婚の場合は当事者が協議して決めるが,協議が調わないときは家庭裁判所が定める。調停の場合には,合意が斡旋され,審判離婚,裁判離婚の場合には,裁判所が決定する。のちに事情の変更があれば,家庭裁判所は前の決定を変更できる。子と同居できなくなった親も,親子関係が消滅したわけではないから,事情が許す限り,日時を定めた面接交渉の権利(面接交渉権)が認められる。しかしそれは,あくまでも子ども本人の福祉にかなうか否かを中心に判断されなければならない。
(3)離婚給付 離婚に際しては,財産分与,慰謝料,養育費など金品の給付を伴うのがふつうである。婚姻中夫婦が築いた共有財産の清算が財産分与であり,一方当事者の責に帰す原因で離婚を余儀なくされた他方当事者が,その精神的苦痛の慰謝を金銭で求めるのが慰謝料である。養育費は未成熟の子がいる場合のみ発生する。子の扶養責任は,親権・監護権の帰属と関係なく父母双方にあり,それぞれの経済的能力に応じて負担すべきものである。実際には,母が子を引き取ることが多いので,父が養育費用の一部分を金銭で負担する形をとることが多い。その方法や金額は父母の協議によるが,協議ができない場合には,家庭裁判所の調停ないし審判によって定められる。ふつうは,子が18~20歳になるまで毎月一定額を送付するという形になる。家庭裁判所で決められたものは,家事債務の一種となり,履行が遅滞した場合には,履行確保(別欄参照)を求めることができる。
現実の大勢
戦後日本における離婚件数は,1960年代前半まで横ばいないし低下を続けたが,65年以降上昇に転じた。ただし,84年から5年間は婚姻数の減少をうけて若干下降したが,89年から再び上昇し,96年には件数(20.7万),率(1.66%)ともに戦後最高を記録した。
しかし,94年前後の普通離婚率による比較では,アメリカ・ロシアの約3分の1,イギリス・チェコの2分の1,カナダ・デンマークの6割程度で,イタリアを除く先進工業諸国の中ではもっとも低率である。
離婚の種類としては協議離婚がもっとも多用され,ずっと約90%を占めている。残りの大部分は調停離婚で,裁判離婚は約1%,審判離婚は0.1%もなく,ほとんど利用されていない。裁判離婚においては,法定離婚原因が厳格に適用されるが,大多数を占める協議離婚と調停離婚では,法定離婚原因には関係なく,実情に応じて離婚がなされている。大胆にいえば,1%の有責主義と99%の破綻主義が同居しているような二元性がある(1987年9月,最高裁は有責配偶者の離婚請求を条件つきで認める判決を下した)。
最近の離婚調停申立て理由では,性格相違についで,異性関係,暴力,虐待が多く,協議離婚では,性格相違についで,異性関係,経済,性などを理由とするものが多い。全体としては,親族関係や土地にあわないといった集団的原因は薄れて,当事者本人の判断による個人的原因へ,〈家〉のためとか,家風にあわないとかいった制度的原因から,夫婦本人の精神的・情緒的価値を中心とする心理的原因へ比重が移り,以前とは質を変えた離婚観が主流になってきたといえる。
少子時代に入ってはいるが,離婚する夫婦には,最近でも6割まで未成年の子どもがいる。子が少ないことが,子の引取りをめぐっての争いをかえって深めている感が強い。明治民法時代には,離婚後の親権は,父がいない場合を除いて父に専属していたから,少なくとも形式上は争いようもなかったし,戦後になり現行民法の時代になっても,1960年ころまでは,妻が子を連れての離婚は,生活上困難だったがために,争いが目だたなかった。ところが,65年ころからは女性の子連れ離婚を平気とする情勢の変化が起こってきた。女性の就職機会の増加,保育園の増設,児童扶養手当や生活保護費の増額等が,それを支える経済的条件であったろう。
この結果,65年以降は親権者となる割合が夫優位から妻優位へ逆転している。
しかし,子の養育費を現実に受け取れるのは,妻が子を引き取った場合でも約6分の1にとどまり,その絶対額は低く,財産分与,慰謝料の低額ぶりとあわせて,離婚後の生活は,総じてなお妻側にきびしいものとなっている。
各国の動向
1960年代以降,先進工業諸国に属する各国で,離婚が急に多発するようになった。イギリスでは1962年ころから,アメリカ,カナダ,旧ソ連では64年ころから,デンマーク,スウェーデンでは66年ころから離婚率が上向きに転じ,68年前後からは急上昇で増加を続けている。
では,各国では近年どうしてこんなに離婚が増えたのだろうか。もちろん個々のケースは個性的な事情をそれぞれもっているうえに,各国の社会的・文化的条件が異なるので,簡単にはいえない。旧ソ連におけるアルコール依存症,社会主義国家の共働き(妻の労働過重と妻の自立の容易さ),イギリスやアメリカに多くみられる早すぎる結婚,極端な個人主義等々,特色だといわれるものはないでもないが,それらは他国でも程度の差こそあれみられることである。しいて全体の底を共通して流れる水をすくうとすれば,〈伝統的婚姻観の動揺ないし消滅〉ということに尽きる。中世以来,キリスト教が君臨した欧米諸地域で高揚された大原則,一夫一婦制の厳守,婚姻外性関係の禁止,罪悪である離婚の絶対禁止が,各国で音を立てて崩れてきたのである。
このような情勢の変化から離婚率は徐々に上昇してきたにもかかわらず,第2次大戦終了後もしばらく各国の離婚法は不変であった。スペイン,チリ,アルゼンチン,ブラジルなどのラテン系カトリック国は依然として離婚の規定すらおかなかったし,イギリス,アメリカ,フランス,ドイツなどのキリスト教国は,限定された条件がある場合のみ離婚を認める〈有責主義〉をかたくななまでに守り続けてきたからである。〈有責主義〉とは,婚姻継続を困難にする不貞,遺棄,虐待など一方の配偶者に明らかに責任を負うべき悪い行為があって,しかも,無責な他方配偶者がそれを原因として請求したときのみ離婚を認めるという立法論で,法定された原因に該当しなければ,夫婦関係がどんなにこわれていても認められないのである。
しかし,法がどんなに制限しても,結婚に絶望し,離婚によって新しい人生の救済を求める男女は増える一方で,この有責主義的制限離婚法と現代婚姻観との矛盾葛藤は各国で激しくなり,1950年代に入るや〈破綻主義〉(夫婦関係が実質的に破綻していれば有責性を問わずに離婚を認めようとする考え)へ改革する方向が,各国でまさぐられるようになってきたのだった。破綻主義的立法は1907年のスイス民法に始まり,スカンジナビア諸国でも第2次大戦前から一部見られてはいたが,大きな潮流となったのは1960年代からである。オーストラリア(1961),チェコスロバキア(1963),ポーランド(1964),ソ連(1965),東ドイツ,アメリカ・ニューヨーク州(1966),カナダ,ブルガリア(1968),イギリス,スウェーデン,アメリカ・カリフォルニア州(1969),イタリア(1970),ベルギー(1974),フランス(1975),西ドイツ(1976),オーストリア(1978)など,ほとんどの先進諸国が1960年代から70年代にかけて離婚法の改正に踏みきった。
カトリックが多数を占める国もプロテスタントの国もあり,社会主義国家も資本主義国家もそれぞれ多数含まれる。宗派や体制の相違を超えてこれらの諸国に共通する改正点は,かなり徹底した破綻主義の採用である。多くの国では,裁判官の審理によって破綻の有無を決める中途半端なものではなく,一定期間の別居事実があればそれだけでよいとし,道徳や制裁的判断を入れることをやめる徹底した破綻主義を採っている。別居期間は1年から7年ぐらいまでさまざまで,夫婦双方合意のうえでの別居をさすのが普通だが,最終的には不合意な別居でも一定期間経過すれば一方の意思のみの〈単意離婚〉ができる国(イギリスやアメリカ・ニューヨーク州など)すら出現した。
こういった離婚原因の拡大は,各国においてさらに離婚の増加をもたらした。しかし,法の改正だけで離婚が増えるわけではない。離婚の自由化を求めてやまない世論の盛り上がりと,それを国会で通過承認せざるをえない政治情勢のほか,婚姻観に対する市民意識の変化こそもっとも大きな原動力だったのである。
執筆者:湯沢 雍彦
渉外離婚の諸問題
国籍の違う夫婦(いわゆる国際結婚をした夫婦)や,同国人夫婦でも,一方または双方が外国に居住している夫婦が離婚をする場合には,純粋に国内的な離婚とは異なり,どの国の法に従って離婚したらよいかという離婚の準拠法の問題,裁判により離婚をする場合にはどの国の裁判所がその離婚につき裁判をする権限を有するのかという離婚の国際的裁判管轄権の問題,さらに,外国で離婚をした場合には,その離婚が内国で承認されるかという承認の問題が生じる。
離婚の準拠法
(1)離婚の準拠法の決定 渉外離婚に適用される法(離婚の準拠法)が何かは,離婚をする場所(法廷地)の国際私法によって決められる。離婚準拠法の決定について,諸国の国際私法の立場はさまざまである。たとえば,イギリス,アメリカでは,離婚の裁判管轄権が認められれば,法廷地となった場所の離婚法を適用するという法廷地法主義がとられているが,ヨーロッパ大陸の多くの国の近時の立法例では,かつての夫の本国法主義を改めて,両性平等の見地から,夫婦に共通する国籍,常居所などの要素を,順次,基準にして,準拠法を段階的に決めていくという立場がとられている。
日本の法例も,1989年の改正前は,婚姻の効力や離婚につき夫の本国法主義を採用していたが,同年の改正により,夫婦を平等に扱う段階的連結による準拠法決定の方法を採用するにいたった。この方法は,まず,婚姻の効力に関する法例14条で定められ,この14条を準用するというかたちで,夫婦財産制に関する同15条と離婚に関する同16条で採用されている(法例14条における段階的連結については〈婚姻〉の項の[婚姻の効力]を参照)。したがって,離婚の準拠法は,まず,夫婦に同一の本国法があれば,その法律により,それがないときは,夫婦の同一の常居所地法により,それもないときは,夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律(密接関連法)によることになる。法例14条のそのままの適用ではなくて,準用であるのは,最後の連結である当事者に密接に関係する地が,離婚の見地から定められるからである。
以上のようにして決定される準拠法が原則として離婚の準拠法とされるが,法例16条但書には,いわゆる日本人条項が設けられているので,夫婦の一方が日本に常居所をもっている日本人であるときには,常に日本法が適用される。しかし,この但書に対しては,この場合は,準拠法の決定について,外国人である当事者の側の国籍や常居所が考慮されないこととなるから,当事者間の公平に欠けるとの批判がある。
(2)離婚準拠法の適用範囲 そもそも離婚をすることが認められるかという離婚の許容性の問題,および,離婚が認められる場合にどのような原因があれば離婚が認められるかという離婚原因の問題は離婚の準拠法によって判断される。したがって,離婚準拠法となった外国法によれば離婚原因が認められないときは離婚は認められない。しかし,もし,当該事件をめぐるさまざまな事情からみて,離婚を認めないことが,法例33条の定める国際私法上の公序に反すると判断される場合には,その外国法は排除されて離婚が認められることになる。1989年の法例改正前の判例には,夫の本国法が離婚を禁止している場合に,公序により,その適用を排除したものが相当数ある。逆に,離婚準拠法に従って離婚を認めることが上記の公序に反するときには,離婚は認められないことになる。なお,89年の改正前の法例16条但書には,日本法によっても離婚の原因がある場合でなくては,日本の裁判所は離婚を宣告できないという規定があったので,この場合に公序によって外国法の適用を排除する必要はなかった。
どのような方法で離婚できるかという問題も離婚準拠法によって判断されるから,離婚準拠法が裁判離婚しか認めない場合には,日本で協議離婚をすることはできない。問題となるのは,離婚準拠法が裁判離婚しか認めない場合に,日本の家庭裁判所で調停離婚や審判離婚をすることができるかである。この問題をめぐっては,学説上の多数説と判例の間に対立がある。学説の多数は,調停・審判離婚は当事者の意思に基づいて行われる協議離婚の性質を有するものであるから,離婚原因があれば強制的に離婚を成立させる裁判離婚とは質的に異なるとしてこれを否定する。これに対して,家庭裁判所では,調停・審判が判決と同一の効力をもつことから,調停・審判離婚は裁判所の判断の加わった簡易な裁判離婚であるとして,このような場合にも,調停・審判により離婚を成立させており,この立場を支持する学説も存在する。
離婚の際には,慰謝料,財産分与,未成年の子の親権者・監護者の指定,離婚後の扶養や離婚後の氏等に関する諸問題が生じる。このうち,離婚後の扶養に関しては,扶養義務の準拠法に関する法律4条1項により離婚に適用された法律によって決定されることが明らかであるが,これ以外の問題については,法律の規定がなく,どれが離婚準拠法の適用範囲に入るかについて,学説・判例は必ずしも一致しているわけではない。
離婚に際して請求される慰謝料のうち,離婚することそのものにより受ける精神的損害に対する慰謝料の請求が離婚の準拠法の適用を受けることには,学説上ほぼ異論はなく,かつてはこれを法例11条の不法行為の問題としていた判例も,現在では,離婚準拠法説をとるとみてよい。しかし,一方の他方への暴力行為など,離婚の原因となった行為に対する慰謝料請求については,これを法例11条の不法行為の問題とみるものと,これも離婚の問題とみるものとに見解は分かれている。離婚の際の財産分与の問題は夫婦財産制と密接に結びついているので,夫婦財産制の準拠法によるべきであるという見解もあるが,判例・学説上の多数説によれば,夫婦の財産の清算までは夫婦財産制の準拠法によるが,その後の財産の分与の問題は離婚の準拠法によって決定されることになる。離婚する夫婦に未成年の子がいる場合,離婚後だれがその未成年の子の親権者または監護者になるかの問題については,1989年の改正前までは,これを離婚の問題とする見解と親子関係の問題とする見解に,学説・判例ともほぼ二分されていた。しかし,改正後の法例21条が,改正前の父の本国法主義を改めて,子を中心に親子関係の準拠法を定める立場をとったことから,改正後は,この問題を親子関係の問題とする見解が学説・判例の双方で有力になっている。離婚後の氏の問題は,離婚の効果の問題と考えるのが従来の多数説の立場であったが,89年の法例改正後は,人格権の問題として,本人の属人法によるとする立場も有力に主張されている。
離婚の国際的裁判管轄権
裁判所が渉外的離婚に関与するときには,問題となっている離婚につき,そもそも,どこの国の裁判所が,その離婚を扱う権限があるのかという国際的裁判管轄権の問題が生じる。この問題についても,世界的に統一された規則はないので,現在のところ,それぞれの国がそれぞれの立場から,どのような場合に自分の国の裁判所に離婚の国際的な裁判管轄権があるかを定めているにすぎない。日本には,この点についての成文規定が存在しないので,学説・判例において,さまざまな見解が示されてきた。ただし,最高裁判所が,1964年3月25日の大法廷判決で,外国人間の離婚につき,被告の住所が日本にあれば,日本の裁判所に裁判管轄権が認められるのが原則であるが,原告が被告により遺棄された場合,被告が行方不明の場合,その他これに準ずる場合には,被告の住所が日本になくても,原告の住所が日本にあれば,日本の裁判所は裁判管轄権を有するという判断を示して以来,この立場に従う下級審の判例が多くなっている。しかし,この最高裁判所の判決は,事件外国人夫婦の離婚に関するものであったので,当事者の国籍が離婚の裁判管轄権の決定につき,基準となるかどうかについては何も示してはいない。
外国で行われた離婚の効力
外国で,裁判以外の方法で行われた離婚は,法例16条の定める離婚準拠法に従ってなされたものであれば,法例33条の公序に反しない限り,日本でも認められる。
外国の裁判所の判決により得られた離婚は,その判決が日本で承認される要件を備えていれば,日本でも有効な離婚として認められる。外国判決の承認については,民事訴訟法200条(1999年1月1日施行の改正民事訴訟法では118条がこれにあたる)に規定があるが,同条が外国の離婚判決にも適用されるかどうかをめぐって,学説・判例ともさまざまに分かれている。ただし,最近の判例の多くは,同条の全面適用,つまり同条の定める1号から4号の要件をすべて外国離婚判決承認の要件とするという立場に立っている。しかし,学説上は,全面的適用説と,同条に定められた要件のうち,4号の相互の保証の要件は外国離婚判決の承認には適用されないという見解とが,なお,大きな対立をみせている。
執筆者:鳥居 淳子
歴史
日本
古代
養老令では妻に〈子無き〉をはじめ七つ(大宝令では六つ)の欠点があるとき夫の一方的離婚を認め,それに対し妻側からの離婚は夫が外蕃に没落(外国で捕らわれたり,遭難すること)ないし逃亡して一定年限後も帰らない場合に限られていた。しかしこのような規定は女に離婚権のない中国法を直接継受した結果で,当時の離婚の実態はそれと大きく異なっており,婚姻決定権を婚姻の当事者が保持していたことの当然の帰結として,離婚は男女双方から自由に行いえた。当時の離婚の特徴はその容易さとあいまいさだが,その表示法としては,男の〈夜離(よがれ)〉〈床離〉,女の男への〈閉め出し〉(通いの場合),男の同居時の自己の調度類,とくに枕の取り戻し,女によるその送り返し,(妻方居住の場合)などがあったが,夫提供の独立居住婚の場合には妻が夫家を出た。なお自己の結婚の決定権を失う10世紀以降の貴族の女性に,女性側からの積極的離婚を示す例がほとんど消失する事実が注目される。
執筆者:関口 裕子
中世
鎌倉末期の《沙石集》に,次の説話が載っている。奥州の百姓が慳貪(けんどん)で妻子に対してもきわめて無情であったので,妻はたびたび逃げようとしたが,そのたびに捕らえられていた。そこであるとき,その妻は,所の地頭に訴えを起こし,その下知によって救われたいと申し出た。このとき,地頭はこれに対して〈夫コソ妻(め)ヲサル事アレ,妻トシテ夫ヲサル事,イカナル子細ゾ〉と質問したので,妻はくわしく事情を話した。そののち夫に対する取調べも行われたが,〈妻ガ申状違(たがわ)ズ〉ということになり,夫はついに〈不当ノ者也ケリトテ,境ヲ追越(おいこし)ヌ〉ということになった,といわれる。これをみると,社会一般の法理としても,離婚を申し立てる権利があるのは,あくまでも夫の側で,妻が離婚を請求するのは,少なくとも一般の慣習にはずれた行為とみなされていたことが知られるであろう。だが,注意しておきたいことは,その場合にも,妻側に相当の理由がある場合には,その離婚訴訟がむげに却下されることはなく,地頭など所の領主の裁量によって,その要求が認められる場合が少なくはなかったということである。このことは,江戸時代などと比較して,夫に対する妻の立場がある程度認められていたことのあらわれである。
こうした妻の立場を示したものに,同じく《沙石集》にみる次の話がある。遠江国のある人の妻が,離婚されてその家を出ようとしたとき,夫の側から,〈人ノ妻ノサラルヽ時ハ,家中ノ物,心ニ任セテ取ル習ナレバ,何物モ取給ヘ〉との申出があったが,妻は笑って,〈殿ホドノ大事ノ人ヲ打捨テユク程ノ身ノ,何物カホシカルベキ〉と,その場を静かに立ち去ろうとしたという。つまり,ここには,中世の在地世界に,離別された妻は,夫の家中の物品を,好きなだけ持ち去ることができるという慣習法が存在していたことが示されている。これは結局,結婚ののち,妻が夫の家中で占めていたいわゆる家内支配権(主婦としての権限)が,かなり強固なものであったことのあらわれであろう。したがって,《御成敗式目》21条にも,離婚請求権がいかに夫側にあったとしても,簡単には妻を離別しがたい,ある程度の歯止めがかけられていた。すなわち,それによると,妻になんらかの重科があって,棄捐(きえん)(離婚)された場合には,たとえ往日の契状があったとしても,その妻は夫の所領を知行しつづけることはできないが,妻にさしたる過ちがないにもかかわらず,夫が〈新しきを賞し,旧(ふる)きを棄(す)てる〉という軽い気持で,旧妻を離婚しようとしたならば,妻は,夫からかつて譲られた所領をいっさい返すに及ばない,というのであった。とすれば,ここには,一夫一婦制家族を原則的に守ろうとする幕府の期待がこめられていることがしられるであろう。もっとも,それでも,離婚するときには,夫が妻に去状(さりじよう)(離縁状)を与えることが必要だった。これがないと,その妻はあらたに改嫁=再婚することができないからである。
執筆者:鈴木 国弘
近世
江戸時代には離婚のことを離縁,ときには離別と称した。離縁は武士の場合,夫の家と妻の実家から主君にあてて,双方熟談のうえ離縁する旨の届を出し,これが受理されることにより成立した。百姓,町人にあっては,夫から妻(もしくは妻の父兄)にあてて離縁状を交付することが離婚の成立要件であった。離縁状を授受することなく再婚したものは,幕府法上処罰される規定であった。しかし地方によっては,離縁状の交付が行われない慣習のところもあった。離縁状を交付する権限は妻にはなく,夫にだけ認められていたので,夫の専権離婚であったといわれ,また離縁状の文言に〈我ら勝手に付き〉といったことばがしばしば書かれ,離婚の原因・理由を示すことなく離縁できたので,無因離婚であったといわれてきた。しかしこれについては近年,批判もある。妻の側から離婚を求める方法も,縁切寺への駆込(かけこみ)のほか,親類,五人組等の斡旋,武士や有力者の家へ駆け入り,縁切奉公すること等々,種々の方法が存在したし,他方,夫の一方的恣意的離婚意思から妻を保護する方法も,決して少なくはなかったのであり,少なくとも,離縁状1本で一方的に簡単に離縁できるというわけではなかったようである。とはいえ,当時の離婚率はかなり高かったと推定され,その中には追出し離婚によるものも相当数あったと考えられる。また,離婚後の子の帰属については,身分,時期,地方により取扱いが異なっており,当事者の協議にゆだねる場合,男子は父方,女子は母方に付ける場合,男女子ともに父方に付する場合などがあった。
なお,離縁ということばは,当時,養子縁組の解消にも用いられた。養子の離縁(養子差戻しともいう)は,武士の場合は,養方実方両家が双方熟談のうえ,理由(病気,心底にかなわないなど)を記して,養子差戻願,養子取戻願を差し出し,主君の許可を受けることで成立した。養子が養家を家督相続した後は,養親もこれを離縁することができなかった。百姓,町人の場合は,養父は,養子が家督相続する前であれ,後であれ,心底にかなわない養子を離縁できたし,養子の側からの離縁請求も可能であった。また養父の死後養母が養子を離縁することも,庶民の場合は認められていた。
執筆者:林 由紀子
中国
都知事の張敞(ちようしよう)は,毎朝,妻のために眉をかいてあげ,都じゅうの評判になったという(《漢書》)。そんな愛妻家もあったが,移り気で身がってな男が少なくなかった。〈妻は斉(さい)なり〉すなわち妻は夫と斉(ひと)しい,という訓詁があるものの,実際の妻の地位は必ずしも強くなく,夫の一方的意思で離別されることがあった。それに規制を加えるために,礼を定めた聖人は,妻を離婚しうる七つの条件〈七出〉を決めている。〈七出〉は,父母に従順でない,子がない,姦淫,嫉妬,悪い病気,饒舌,窃盗(《大戴礼》)。〈父母に従順でない〉とは,たとえばしゅうとめと折合いのよくない場合である。〈子が無い〉は,これを〈七出〉の第1にあげる説もあるほどで,婚姻は〈上は以て宗廟につかえ,下は以て後世に継ぐ〉ものなので,〈子が無い〉のは十分な離婚理由となる。庶民ならともかく,天子や諸侯は〈子が無い〉ではすまない。子を作るのが唯一最大のしごとであり,万一,皇后に子が無いときのことを考えて,三夫人,九嬪,二十七世婦,八十一御妻を備えておく(《礼記》)。120人もおればだれか天子の子を身ごもるだろう,との期待である。離婚状には夫の手形・足形が押されており,再婚許可書の意味もあったという。しかし貧窮な庶民は〈七出〉がどうであろうと,妻に離婚状なぞ与えてしまえば,その日から家事に困り,金がないので後妻も迎えられないので,うかつに離婚はできなかった。
いにしえの聖人は,妻を離婚しえない3条件〈三不去〉をも決めることを忘れなかった。〈三不去〉とは,めとったものの帰すべき里のない者,父母の3年の喪を終えているとき,初め貧賤で後に富貴になった場合。帰る里のない妻を離婚してはならないは,大人の配慮と称すべきだろう。二つめはいかにも中国的で,父母(舅姑)が死ぬと3年の喪に服するが,夫とともにこの喪を終えた妻は,よく父母につかえたのだから,離婚はまかりならぬという。その三は〈糟糠(そうこう)の妻〉。苦労をともにした妻は,〈堂より下さず〉つまりおろそかにしてはならなかったのである(三不去七出)。
執筆者:日原 利国
イスラム社会
イスラム社会における離婚は,それによって生ずる男性側の責任と物質的な代償の大きさからみて,普通考えられているほど簡単なものではない。また相互の共通利益や互恵の関係や愛情の絆が消滅してしまったときでも離婚できないというカトリック的厳格主義でもない。両極端の中間のところで解決を図ろうとしているようである。ハディースにみる〈離婚は合法的なもののうちでも最も嫌悪さるべきものなり〉とはこのことを伝えている。明確な理由があれば,男女ともに離婚権を有するが,婚姻と違っている点は,一方の解消意思だけで成立する点である。多くの場合,男性が一方的に離婚宣言をするが,この場合1回だけの宣言では正式な離婚とはならない。2回目の宣言をした後でもまだ仮離婚にすぎない。この間に双方に復縁の意思が生ずれば,いつでもまた元に戻ることができる。しかし,どちらの場合もイッダ`idda期間(3回の月経をみる期間で,妻はこの間に結婚できない3ヵ月の再婚待機期間。コーラン65章1,4節による。死別の場合は4ヵ月と10日)中に復縁する必要がある。もしこの期間が過ぎた後で離婚宣言を取り消す場合は,新たな結婚契約のもとに必要なマフルmahr(婚資金)を改めて支払わないかぎり復縁できない。3回目の離婚宣言をすると正式に離婚が成立するが,それでも妻と復縁したいときは,妻はいったん他の男と再婚してから,正式にその男と離婚した後に再度結婚契約を結び,マフルを支払った後でなければ復縁できない。男性側は離婚することによって次のような負担を負わねばならない。すなわちマフルの未払い分の清算(通例は2分の1),イッダ期間中の妻の生活費,将来も含めて子どもの養育費(再婚しても養子は認められていない),それにすでに前払いしたマフルで費やした分と,新居のために費やした費用の損失等を覚悟せねばならない。離婚理由にはさまざまあるが,妻の不妊や男児が生まれない場合,また夫の扶養義務の不履行や理由のない失踪なども立派な理由になる点が変わっている。不和が高ずるとつい異教時代の永久離婚形式の文言〈お前の背中はわしの母さんの背中だ〉を口走ってしまうが,これはイスラムでは禁句とされ,したがって離婚宣言は無効となる。コーランによると,この宣言を取り消すためには,宗教的な償いとして2ヵ月間の断食をするか,貧者60人に対して食事をふるまわなければならない。
執筆者:飯森 嘉助
ヨーロッパ
古代ヘブライ社会,古代ローマ社会はいずれも強力な家父長権を中心にした家父長制家族であるが,前者は一夫多妻制であり,後者は一夫一婦制をとるという差異がある。ヘブライ社会は夫による専権的な追出し離婚からしだいに夫の離婚権を制限する方向に変わっていった。古代ローマも,当初は夫が強力な権威をもったために,夫の一方的意思で離婚することが認められたが,このほかに相互の協議による離婚も認められていた。
西欧において,カトリック教会の離婚を禁止する婚姻非解消主義が確立したのは,12世紀中葉以後である。10世紀ころから王権が衰微し,教会の勢力が拡大するに伴い,教会婚姻法が形成された。教会婚姻法では,婚姻をもってキリストと教会との結合の表徴,すなわちサクラメント(秘跡)とみなし,婚姻は神によって創造された非解消の結合とされた。カトリック教会が婚姻をサクラメントとみ,婚姻非解消主義を標榜するとともに,10世紀半ばごろ,教会は婚姻事件に関する裁判権を掌握するようになった。このようにして,教会は婚姻の存否や効力だけでなく,婚約,別居,嫁資など婚姻に付随する事項まで裁判管轄権を広げ,婚姻立法権を一手に占めることになり,13世紀教会婚姻法の体系がほぼ完成されたといわれる。
1563年,トリエント公会議では,婚姻非解消主義を維持することを再確認した。もっとも,教会は非解消主義のゆえにいっさいの離婚を認めず,婚姻についての裁判権を独占したが,現実には,地方の慣行では離婚を認めるところもあったし,また,婚姻生活継続が事実上不可能という事態が生ずるのはやむをえないことであって,教会はこれらの現実と妥協するために,非解消主義を緩和する方法を案出していた。婚姻について身体的交渉のない未完成婚と交渉がある完成婚とに分け,前者については婚姻の解消を認めたり,広く婚姻の無効宣言をしたり,あるいは別居制度を適用するなどがそれである。
やがて,これらの教会婚姻法や婚姻非解消主義を批判する動きが台頭してくる。教会財政の紊乱(びんらん),聖職者の退廃を原因として教会の勢力が衰退しだし,これに代わって絶対王政が確立されはじめる。ルターやカルバンなどの宗教改革の指導者が,婚姻=サクラメント理論に対して批判を加え,離婚を認めるべきことを説き,婚姻事件につき教会裁判所には管轄権限がないことを主張した。
このように,教会婚姻法に対する批判が勢力を拡大するに伴い,婚姻事件についての教会裁判所の独占的管轄権に対しても世俗裁判所によって異論が唱えられ,教会裁判所と世俗裁判所との管轄権争いの事件が増加した。まず,民事婚思想が拡大し,婚姻の本質は合意であってサクラメントは合意を再現する形式にすぎないと,婚姻につき合意とサクラメントとが分離され,合意については世俗裁判所,サクラメントについては教会裁判所がそれぞれ管轄権をもつとされ,実際には,従来の教会裁判所の管轄領域が世俗裁判所によって奪われる事態が生じた。フランスでは,14世紀以来,婚姻事件のうち夫婦財産制,夫婦財産の分離,子の嫡出,姦通などについては,世俗裁判所が教会裁判所と競合して管轄権をもつようになり,16世紀には,教会裁判所の管轄に属していた婚姻の効力について世俗裁判所が関与するようになった。未成年の子の婚姻については,1556年の王令により,男子は30歳まで,女子は25歳まで婚姻するに際しては親の同意を要すると定められて以後,同意なき婚姻について親から出された婚姻の効力の争いは,世俗裁判所で処理されるようになった。
このようにして,婚姻事件に関する教会裁判所の権限はしだいに縮小され,16世紀には高等法院Parlemantにより婚姻に関する教会裁判所の判決が権限踰越(ゆえつ)に対する控訴appel comme d'abusで破棄されるものが増加し,教会裁判所の管轄権が形骸化していった。また,別居事件は教会裁判所の管轄であったが,夫婦財産の分離は世俗裁判所の管轄であるため,事実上,世俗裁判所が別居事件についても裁判権をもつようになった。
このようにして,18世紀には教会に残された婚姻に関する権限は,婚姻挙式の司宰と婚姻登録簿の保管だけになってしまった。18世紀には,モンテスキューをはじめ,ボルテール,ディドロなどの啓蒙思想家,百科全書派の思想家により婚姻非解消主義は不合理,反情と批判され,民事婚思想が拡大し,離婚を容認する気運が高まっていった。
フランスでは,1791年9月3日の革命憲法7条で〈法律は婚姻を民事契約とのみ認める〉と定め,宗教婚主義を排斥し,これに代わって民事婚主義が登場し,ついで,1792年9月20日法は離婚を容認するに至った。1804年のナポレオン法典は個人主義の原理,政教分離の原理にのっとり離婚制度を定めた。フランス以外の西欧諸国の近代民法典もほぼ同じような離婚規定をおき,離婚を容認してきた。そして,第2次大戦以後は離婚原因を拡大し,有責主義から破綻主義へと離婚法は変わりつつある。
1970年代に,西欧の人々の離婚観が変わったとされている。カトリック教国フランスでも,72年の離婚者に対する調査では,離婚を肯定する者が多い。離婚は辛い体験だが,自分の将来の人生を台なしにするものではないとする者が男子49%,女子39%,離婚は自分を解放し,人生に新しい機会を与えると考えている者は男子40%,女子43%である。離婚は人生の終局的な破綻とみている者は,男子7%,女子12%にすぎない。このような世論に従い,75年,フランスでは,離婚法の改正が実現し,離婚はいっそう容易になった。
執筆者:有地 亨
諸文化にみる比較
法律婚主義をとる文明社会では,事実上の別居と法的離婚とは必ずしも一致しないが,未開社会においても両者を区別している例がある。アフリカのヌエル族では,妻が出生親族のもとへ帰っても,花嫁代償が返還されるまでは婚姻関係は解消されない。離婚がどの程度悪いものとみなされるかも,社会によって,時代によって異なる。たとえば,キリスト教圏や旧中国では婚姻を神あるいは天の合わせ給えるものと考え,その結果離婚を忌避していた。もっとも旧中国の法令では,上述のように七出を定め,夫の側からの離婚権を認めていたが,実際には経済的制約も加わって離婚は少なかった。これに対して離婚を異端視しない社会もある。日本でも地方によっては男女とも初婚にこだわらず,相手を変え高い離婚率を示していた例もある。またマレーでは,祖父母と孫の関係,義父母と義子の関係などの結合が夫婦関係の破綻を補完し,西欧社会などでみられるような不適応現象を必ずしも伴わず,むしろ離婚が恒常的に家族制度と結びついているかに見える場合さえ存在する。
このように離婚に対して寛容な社会でも,その頻度は条件によっては高いとは限らない。婚姻の安定性が,父系の強さ,花嫁代償の額に比例しているという仮説も出されたが,ソマリア,アラブ,タレンシなどの父系社会では,花嫁代償が低額とはいえないのに,離婚はまれではないという。母系社会では,女性の子を産む能力への権利は,その親族が保持しつづけるので,離婚が多いとされている。もっとも,母系のアッサムのカシ族では,相続者である妻,つまり家付き娘と結婚した場合は,しばしば出入りする妻の兄弟と夫の衝突で離婚が多いのに対し,非相続者の女性との婚姻は,同じ妻方居住婚であっても,世帯内で夫の権利を妨げる者がいないので,比較的安定しているという。したがって婚姻の安定性は,出自など単一の要因だけでなく,それをとりまく諸制度や条件を考慮に入れる必要がある。
→婚姻
執筆者:末成 道男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「離婚」の意味・わかりやすい解説
離婚
りこん
社会的に有効な婚姻関係を、生存中に解消すること。
民法上の離婚
民法上の離婚とは、婚姻届を出して結婚している夫婦が、その結婚を解消すること。結婚式をあげたが婚姻届を出していないうちにその結婚を解消することは、内縁離婚とよばれることがあるが、ここでいう離婚ではない。離婚は夫婦が話し合いで決定すべきことを原則とし(協議離婚)、夫婦の話し合いで離婚するかどうか決まらないときは、裁判所が関与して離婚するかどうかを決定することができる(裁判離婚または判決離婚という)ことになっている(民法763~771条)。
[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日]
離婚の方法と種類
日本の民法や家事事件手続法によると、離婚の方法として協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚の4種類が認められている。
(1)協議離婚 夫婦が話し合いで離婚することを決め、離婚届を市区町村役場へ届け出ることによって離婚が成立する(民法763~765条)。このような手軽な方法で離婚ができるとする立法は、世界にもあまり類例のないもので、離婚要件を緩和しようとする世界的傾向からすれば、進歩的立法と称することができるが、他面この制度は、三行り半(みくだりはん)を書けばいつでも妻を追い出すことができるとされた江戸時代の離婚から尾を引いた追出し離婚を容認するものとして、明治時代以後も利用されてきた。家風にあわないという一事で、発言力のない妻の意思を無視して舅(しゅうと)・姑(しゅうとめ)が一方的に離婚を決めるというのがそれである。現在ではそのようなことは許されないし、夫婦双方が話し合って決めた離婚でなければ法律上有効な離婚とはいえない。もっとも、離婚届を出すという合意に基づき届出が行われれば、法律上離婚は成立する。また、離婚することにいったんは合意し、離婚届に印を押したが、その後気が変わったという場合に、まだ離婚届が市区町村役場に提出されていなければ、離婚届が提出されてきても受理しないでほしい旨を書面であらかじめ申し出ておくことができる。この書面を離婚届不受理申出書(俗に翻意届)という。不受理申出書が出ているときは、離婚届は受理されないから、離婚は成立しないことになる。
(2)調停離婚 夫婦間で離婚の話し合いがつかない場合や、財産上の問題、子供の問題が解決できない場合には、夫婦の一方から家庭裁判所へ調停を申し立てることができる(家事事件手続法244・257条)。調停は、裁判官1人と、原則として男女2人以上の調停委員とで構成される調停委員会で手続が進められ(同法247・248条)、夫婦双方の言い分を聞いたうえで、仲直りの余地があると判断されたときは、離婚しないで円満解決するような案が示されるが、どうしても離婚するよりほかないと判断される場合は、離婚案が示される。いずれの場合も、夫婦のどちらか一方が反対すれば調停は成立しない。夫婦の双方が調停委員会の示した案を受諾すれば、その内容は調停調書に記入され、調停は成立する。その調停調書は、裁判によって判決が確定した場合と同じ効力を有する(同法268条)。調停離婚が成立すれば、そのときに離婚は成立したことになるが、戸籍にその旨を記載するために、調停の成立した日から10日以内に報告的意味の離婚届を出さなければならない(戸籍法77条)。
(3)審判離婚 調停が成立しなかった場合、家庭裁判所は、必要と認めれば、双方のため衡平に考慮して、職権で申立ての趣旨に反しない限度で、離婚の審判をすることができる。この審判に対して、2週間以内に当事者から異議の申立てがないとき、または異議の申立てを却下する審判が確定したときは、離婚が成立する(家事事件手続法286・287条)。この場合にも、調停離婚同様、報告的意味の離婚届を出さなければならない。
(4)判決離婚 夫婦の一方が離婚に応じない場合は、離婚は前記(1)~(3)の方法では成立しないが、法律で定められた一定の事由(離婚原因)があれば、地方裁判所に訴えて離婚の判決をもらって離婚することができる(民法770・771条)。裁判離婚ともいう。
民法第770条の定める離婚原因は次のとおりである。
(1)配偶者に姦通(かんつう)などの不貞行為があったとき。
(2)配偶者が正当の理由なく同居せず、生活費を渡さないなど悪意で遺棄したとき。
(3)配偶者が行方不明で3年以上生死が明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。ただし、その場合でも、病者の離婚後の療養・看護などについてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度、前途にその方途の見込みがついたうえでなければ離婚を認めないというのが最高裁判所の判例である。
(5)その他婚姻を続けることができない重大な事由があるとき、すなわち、同居に耐えない虐待・侮辱をするなど、離婚請求の相手方に責任のある場合に限らず、結婚生活が破綻(はたん)して元に戻る見込みがないと判断されるときをいう。この最後の(5)は、いわゆる破綻主義を採用したことを宣言するものであって、夫婦双方の性格の不一致や愛情喪失などの無責的な理由によって結婚が破綻した場合にも離婚を認めるのである。ただし、夫婦の一方が不貞行為をするなど、自ら結婚の破綻を招いておきながら、結婚が破綻したことを理由に離婚を請求する、いわゆる有責配偶者からの離婚請求の場合には、夫婦の年齢および同居期間に対比して別居が相当の長期間にわたること、未成熟子(一本立ちしていない子供)が存在しないこと、離婚によって夫婦の一方が精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれないこと、の三つの条件を満たすときに、離婚請求は認められるというのが、最高裁判所のとる立場である(最高裁判所大法廷判決昭62・9・2、民集41巻6号1423頁)。
[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日]
離婚に伴う法律問題
(1)財産上の問題 夫婦が結婚前からもっていた財産(嫁入り道具など)は、当然、その人のものである(民法762条1項)。夫婦が結婚中に協力して取得した住宅その他の不動産、預金、株券などは、その名義のいかんを問わず、夫婦の共同所有とみるべきものであるから、離婚に際して清算することが認められる。これが、夫婦の一方が他方に対して有する財産分与請求権である(通常は無資産・無収入の妻から夫に対して請求されることが多い)。もっとも、財産分与には前記のような清算のほか、離婚後の生活に困窮する場合には、そのような者の生活扶助をさせるという意味をもたせる場合もある。財産分与は現物給付でも金銭給付でも、また一時払いでも分割払いでもかまわない。財産分与について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ申し立てれば、調停・審判で、その額と方法を定めてくれる。なお、財産分与は離婚後2年経過すると請求できない(民法768条)。
(2)慰謝料の問題 不貞行為や虐待など相手方の有責行為によって離婚せざるをえなくなり、そのことによって精神的苦痛を受けた配偶者は、相手方に対して慰謝料を請求することができる。もっとも、財産分与請求も同時に行っているときは、財産分与のなかに含めて処理されることも認められる。なお、慰謝料は通常、離婚後3年を経過すると請求できない(同法724条)。家庭裁判所の調停では慰謝料という名目をつけること自体が争点になることがあり、そのような場合には解決金という名目が用いられることがある。
(3)子供の問題 夫婦間に未成年の子がある場合には、父母のどちらを親権者とするかを決めなければならない(民法819条)。それと同時に、子を手元に置いて監護する者や監護についての必要な事項(養育費など)についてもはっきりさせておく必要がある。親権者が監護者である場合が多いが、親権者を父とし監護者を母とするようなこともできる。また祖父母などに監護を委託することを決めてもよい。前記につき、話し合いで決定できなければ、家庭裁判所へ申し立てて決めてもらうことができる(同法766条)。
子の籍は、親権者・監護者がだれになるかに関係なく、結婚中の戸籍にそのままとどまるから、離婚によって結婚前の氏に復した者の籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て、子の氏の変更の届出をしなければならない(同法791条)。
(4)氏と戸籍の問題 結婚によって氏を改めた者は、結婚前の氏に戻り、結婚前の戸籍に復するか、新しい戸籍をつくることができる。結婚中の氏をそのまま称していたいときは、いわゆる婚氏続称の届出(正式には戸籍法77条の2の届出)を離婚届と同時にまたは離婚後3か月以内に出すことができる(民法767条)。
[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日]
離婚が無効の場合、または取り消すことができる場合
夫婦の一方や、嫁を気に入らない姑などの第三者が無断で離婚届を出したような場合には、離婚は無効である。もっとも、戸籍に記載された離婚を消除するためには、家庭裁判所へ離婚の無効を申し立てることを要する。また、だまされて、あるいは強迫されて離婚届に印を押したというような場合には、だまされたと気がついたとき、または強迫を逃れたときから3か月以内に離婚の取消しを家庭裁判所へ請求することができる(民法764条による同法747条の準用)。
[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日]
離婚届
協議離婚を成立させるための、また調停、審判、裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届出をいう(戸籍法76・77条)。協議離婚届の場合には、未成年の子の親権者を父母のどちらとするかを定めなければ、届出は受理されない(民法765条・819条)。調停、審判、裁判による離婚があった場合には、同時に未成年の子の親権者についても決定されるから、決定したとおりのことを届け出ればよい。届出は書面で届出人の本籍地または居住地の市区町村役場にする。
[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日]
国際結婚の破綻による離婚問題
国際結婚が破綻した場合の離婚については、日本の法律が適用されるとは限らず(準拠法の問題)、また、離婚訴訟も日本の裁判所に提起できるとは限らず(国際裁判管轄の問題)、外国法上の離婚の裁判を日本の手続に従って行うにあたっても問題が生ずることがある(手続法上の問題)。さらに、外国裁判所による離婚判決でも一定の要件を具備すれば日本でその効力が認められる(外国判決の承認の問題)。国際結婚した夫婦が離婚する場合には、これら国際私法上の諸問題が発生する。
[道垣内正人 2022年4月19日]
準拠法
離婚に関する諸外国の法は、それぞれの宗教、文化その他の事情によりさまざまに異なっている。かつてはカトリックの影響の強い国ではいっさいの離婚が禁止されていた。現在でも、フィリピンや中南米のいくつかの国は離婚禁止国である。ヨーロッパではカトリック教国でも離婚が認められるようになっているが、たとえばイタリアでは、原則として、法律上の別居を認める旨の判決を得てから1年間(離婚の合意があれば6か月)経過しなければ離婚は認められない。そこまで厳しくなくても、アメリカ諸州も含めて、裁判離婚しか認められないのが普通である。これらの離婚に厳しい国々に比べ、日本は、夫婦間の調整がつかなければ裁判離婚をするほかないが、調整がつけば協議離婚をすることもできる点で、韓国などとともに、世界でも特異な国である。なお、イスラム教国では、一般に、夫からの一方的な離婚が認められる点で他の地域の法律とは大きく異なっている(タラーク離婚)。
離婚の準拠法は国際私法によって定められる。日本の国際私法典である「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)では、第27条に規定されている。それによれば、夫婦の本国や常居所などに基づいて準拠法が定められる(段階的連結)。第1段階では、夫婦の本国法が同一であるか否かがチェックされ、同一であればその法(同一本国法)が準拠法とされる。この場合、重国籍の者については、国籍を有する国のうち常居所を有する国があればその国の法がその者の本国法とされ、そのような国がなければ、当事者にもっとも密接に関係する国を具体的状況のもとで判断し、その国の法がその者の本国法とされる(同法38条1項)。他方、無国籍者の場合にはこの第1段階は成立しないものとして扱われる(同法38条2項但書)。次に、第2段階として、夫婦の本国法が同一でない場合には、常居所地法が同一であるか否かがチェックされ、同一であればその法(同一常居所地法)が準拠法とされる。最後に、第3段階として、同一本国法も同一常居所地法もない夫婦については、過去の婚姻生活地などを考慮して具体的状況のもとで夫婦にもっとも密接な関係のある地の法(最密接関係地法)による(以上、同法27条本文)。以上の段階的連結の例外として、当事者の一方が日本に常居所を有する日本人であれば日本法が準拠法とされる(同条但書)。これは、国際離婚について戸籍窓口での協議離婚届の処理を可能とすることを目的とするものである。すなわち、日本法によれば協議離婚が認められるため、日本法が離婚の準拠法であることを形式的な基準で判断できるように、戸籍と住民票の記載に基づいて事務処理をすることができるようにしたものである。なお、法務省民事局長通達により、日本人については住民票があればよく、また住民票が消除されていても、出国後1年以内であれば日本に常居所があるものとして扱われる。
以上の段階的連結は、やや複雑ではあるが、最密接関係地法を準拠法とするという国際私法の理念にかなり忠実なものである。もっとも、連結点(特定の地の法を導き出すことのできる場所的要素。連結素ともいう)を時間的に固定していないので、夫婦の一方が本国や常居所を変更すると、離婚訴訟の途中であっても準拠法が変わってしまうという問題が指摘されている。
このようにして決まる離婚の準拠法は、離婚の許容性や離婚原因はもちろん、離婚の際の親権者指定にも適用される。離婚に伴う財産分与については、一括して離婚の準拠法によるとの見解もあるが、性質に応じて、夫婦財産の精算については夫婦財産制の準拠法によるとし(「法の適用に関する通則法」26条)、また、慰謝料は原則として離婚の準拠法によるものの、たとえば身体障害に至るような暴力によるものについては不法行為の問題として、加害行為の結果が発生した地の法による(同法17条)という見解もある。なお、離婚後の扶養については、離婚の準拠法による旨の明文の規定がある(扶養義務の準拠法に関する法律4条)。日本には、婚姻中の配偶者の同居義務をはずす法定別居という制度はないが、日本で法定別居が求められた場合には、離婚に関する規定(「法の適用に関する通則法」27条)によって準拠法を定めることになる。
[道垣内正人 2022年4月19日]
国際裁判管轄
裁判による離婚の場合、国際裁判管轄がある裁判所に提訴しなければならない。人事訴訟法3条の2によれば、離婚については、被告の住所が日本国内にある場合(同条1号)、原被告とも日本の国籍を有している場合(同条5号)、夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあった場合であって、原告の現在の住所がなお日本国内にあるとき(同条6号)、原告が日本国内に住所を有する場合であって、被告が行方不明であるとき、被告の住所がある国でされた原被告間の離婚判決が日本で効力を有しないとき、その他の日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき(同条7号)には、日本の裁判所に管轄が認められる。この第7号は緊急管轄を認めるものであるとされ、日本に国際裁判管轄に関する明文の規定がない時代の最高裁判例を取り込んでいる(最高裁判所昭和39年3月25日判決、民集18巻3号486頁、最高裁判所平成8年6月24日判決、民集50巻7号1451頁)。離婚について国際裁判管轄が認められれば、離婚に伴う財産分与請求や親権者指定の請求についても管轄が認められる(同法3条の3、3条の4)。なお、裁判所は、上記のルールによれば日本の裁判所が国際裁判管轄を有することとなる場合であっても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を害し、または適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部または一部を却下することができるとされている(同法3条の5)。
[道垣内正人 2022年4月19日]
家庭裁判所の手続
日本の家庭裁判所の調停離婚手続は、日本法上の協議離婚制度を前提としているので、離婚の準拠法が外国法であって、裁判離婚しか認められない場合に、日本で調停離婚をすることができるかどうかが問題となる。実務上はこれを行っているが、学説上はそれを疑問視する見解も少なくない。また、外国法上、離婚の申立てがあると一定の資格のあるカウンセリング機関による調停を行い、そこでの和解不成立によって初めて裁判離婚の手続を行うこととされていることがある。このような場合に日本における離婚手続をその規定にあわせて行うことは困難である。これは、実体法が外国法である場合に、日本の実体法を前提としてつくられている日本の手続法との間に齟齬(そご)が生ずる一例であるが、手続法は本来、実体法の定めるところを実現するために存在するのであって、可能な限り日本の手続法の運用を柔軟にしていく必要がある。
[道垣内正人 2022年4月19日]
外国判決の承認
外国裁判所の離婚判決の承認についても、民事訴訟法第118条が適用され、そこに定める要件を具備すれば日本での効力が認められる。詳細は「外国判決」の項参照。
[道垣内正人 2022年4月19日]
民俗学上の離婚
生存中の夫婦間における婚姻の解消。離婚の形態は時代により身分により多様であったが、法制的にも慣習的にも一定の手続を必要とした。古代の律令(りつりょう)制社会では、夫が一方的に妻を離婚してもよいとする棄妻(きさい)の規定が戸令(こりょう)に設けられていた。すなわち、「七出之状(しちしゅつのじょう)」といい、妻に無子、婬泆(いんいつ)、不事舅姑(きゅうこにつかえず)、口舌(こうぜつ)、盗竊(とうせつ)、妬忌(とき)、悪疾のうち一つでも該当するものがあれば、手続に従って離婚してもよいとした。しかしこれはまったく唐制の模倣であり、どの程度日本の実情に即した規定なのか疑問とされる。当時は公家(くげ)社会でも婿入り婚が支配的であり、婚姻も離婚も原則として当人同士の愛情に基づいていたと思われるからである。婚姻は男が女のもとを訪れる妻問(つまど)いによって開始されるのに対し、離婚は夫がその妻問いをやめてしまうか、夫が妻の家から離れてしまうか、いわゆる夜離(よが)れの状態が続くことをさした。したがって、婚姻も離婚も男女は対等であり、いずれにも男性の一方的優位はおこりうるはずもなかったようである。
このような状況に大きな変化をもたらしたのは、室町時代、武家社会における嫁入り婚の発達であった。武家社会では、「家」制度のもとで家父長権が強大となり、夫側の立場が補強された反面、婚礼とともに夫の家に入る嫁の座はとかく安定を欠き、その地位はきわめて劣弱となった。夫側からは理由も明示せず独断的に離婚を申し渡すことができたのに、妻側はそれに対してなんの対抗もできないありさまであった。嫁と姑(しゅうとめ)の間にしばしば緊張が生じ、姑が、家風にあわないとの理由で嫁を追い出すことさえ珍しくなかった。したがって嫁の座は、子供、なかんずく男子を生んで初めて落ち着くというわけで、離婚は結婚後数年間以内に頻発した。嫁入り婚は江戸時代には庶民社会にも浸透し、しだいに全国的に普及し、やがてこれが婚姻方式の主流をなすに至るとともに、離婚にも武家風の男性専横が現れてきた。江戸時代には離婚は一般に離縁、縁切りとよばれ、その際夫は妻に証拠として離縁状を手渡すしきたりであった。これを俗に三行り半といったのは、本文を三行半に書いたからである。離縁されれば、妻は夫の家を追われて実家に戻らなければならなかった。いわゆる出戻りである。こうして嫁入り婚では、いったん離婚すれば女性は自らの立場を著しく損じることとなり、婿入り婚において離婚後も女性が元どおり生家で生活を続けられるのとは大きな相違であった。当時、このような状況のもとでは、妻側から夫側の横暴に対して異議を唱え離縁を求めることは許されなかった。ただ非常手段として、神職や山伏の家、あるいは尼(あま)寺などに逃げ込み、それらの人々の尽力によって離縁を迫ることはできた。この種の寺では相模(さがみ)(神奈川県)鎌倉の東慶寺や上野(こうずけ)(群馬県)新田(にった)郡の満徳寺が、俗に縁切寺、駆込寺(かけこみでら)として有名であった。また縁切りを神仏に祈る習俗も広く、祈れば効き目があると信じられた縁切地蔵、縁切稲荷(いなり)、縁切薬師(やくし)などが各地に伝えられていた。東京都板橋区下板橋にあった縁切榎(えのき)(実はケヤキ)も、江戸時代からよく知られ、川柳(せんりゅう)に「板橋へ三くだり半の礼参り」などと詠まれてもてはやされた。
このような一般的な状況に対して、明治以降も一部の地域ではいささか様相を異にしてきた。まず婿入り婚が第二次世界大戦前後まで各地に保持され、そこでは古来の男女対等に基づく婚姻・離婚の風潮がみられた。とくに海女(あま)や行商など女性の働きが重要なところでは、離婚によって女性の立場を損じることは少なく、数回も離婚と再婚を繰り返す者もみられた。嫁入り婚の場合でも、農漁村では女性も一人前の働き手であり、その存在は都会のサラリーマンの妻よりははるかに重んじられた。離婚に際しても妻側がかならずしも受動的とはいえず、また再婚にあたってもあまり処女性にこだわらないというのが農漁村の伝統であった。
[竹田 旦]
人類学上の離婚
人類社会全般について離婚を論じるうえには大きな困難がある。カリブ人の諸社会においては、結婚の合法性に対するこだわりはみられないし、一時的な性のパートナー以外は認めず、夫婦と子供からなる婚姻家族の単位すらもたなかったインドのナヤールのような社会もあったからである。婚姻が明確に定義されていないところでは、そもそも離婚は問題にできない。また婚姻が永続すべきものだとは考えていないような社会も多く、そこでは離婚はとりたてて問題にするべきできごとではない。
しかし、おおよその傾向として、イギリスの人類学者グラックマンによると、父権の明確な体系では離婚はまれでまた困難であるという。またレーブE. M. Loebは、父系出自、高価な婚資、低い離婚率の間に相関関係があるとも主張している。確かに父系社会においては、出自集団の存続は外部から婚入してくる女性に依存しており、いかにこれら女性の生む子供に対する権利を確保するかが婚姻制度の中心的関心事となっている。結婚は、この権利の譲渡を示す明確な儀礼的手続によって始まり、同様にその終止も正式な手続によってマークされる。南スーダンのヌエル社会では、この意味での正式な離婚、つまり女性に対して支払われた婚資のウシが返却されない限り、彼女の生む子供は、たとえ彼女が夫と別居し別の男と世帯をもち、そこで生まれた子供であっても、婚資を支払った法律上の夫の子供として扱われる。かりに、法律上の夫がすでに死亡していても同様である。レビレート婚や亡霊婚にもみられるごとく、この意味での結婚は死によっても解消されない。こうした社会での離婚は、妻の不妊などの特殊な場合やごく限られたケースでしかおこらない。これに対して母系社会の場合、夫への正式な権利の譲渡は必要とされない。相手の男がだれであっても女性は自動的に自らの集団の成員を供給する。こうした社会の多くで離婚が許容され、また結婚が永続すべきものとは考えられていないのも、うなずける。ザンビアにある母系のベンバ社会では、男は何回にもわたる離婚歴のなかで、同じ女性と二度結婚することもけっして珍しいことではない。
[濱本 満]
『大村敦志・河上正二・窪田充見・水野紀子編著『比較家族法研究――離婚・親子・親権を中心に』(2012・商事法務)』▽『二宮周平・榊原富士子著『離婚判例ガイド』第3版(2015・有斐閣)』
百科事典マイペディア 「離婚」の意味・わかりやすい解説
離婚【りこん】
→関連項目苛酷条項|再婚|貞操|別居制度|面接交渉権|離縁
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「離婚」の意味・わかりやすい解説
離婚
りこん
divorce
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の離婚の言及
【慰謝料】より
…傷害の程度により慰謝料額は千差万別であるけれども,傷害事故の慰謝料が死亡事故の慰謝料を上回らないのが原則である。(3)離婚 民法上離婚による慰謝料について特別に定めた条文は設けられていない。このため,判例はこれを不法行為による慰謝料と解している。…
【縁切】より
…江戸時代には女性が縁切寺,駆込寺に逃げることがあり,東慶寺(神奈川県鎌倉市)は有名である。婚姻当事者よりも,家と家,とくに夫の家を基調とする武士社会では嫁入婚が一般化し,夫は法的にも道徳的にも一方的に妻を離婚できたのに対し,これが許されなかった妻は縁切寺に駆け込むことで離婚できたのである。しかし地方によっては,婚姻は当事者の自主性にまかされ,離婚も夫と妻双方の話合いで行われた。…
【縁切寺】より
…江戸時代において妻が駆け込んで一定期間在寺すれば離婚の効果を生じた尼寺で,〈駆込寺〉とも〈駆入寺〉ともいう。当時庶民の間では,離婚は仲人・親類・五人組等の介入・調整による内済(示談)離縁が通例であったと思われるが,形式上妻は夫から離縁状を受理することが必要であった。…
【婚姻】より
…それらが同時なのか交互なのか判然とする史料はない。離婚の記述が非常に多い点から後者の可能性は強い。 コーランの四人妻についての啓示は,625年のウフドの戦の直後に下されている。…
【ベドウィン】より
…小麦,米,コーヒーなどは購入されるが,乳製品や食肉は自給している。 社会生活上の特色の一つとしてあげられるのは,女性の離婚が,かなり容易に行われるということである。一夫多妻制は今日でも続いているが,女性は配偶者を選択する自由があり,夫に不当な扱いをされた場合には,離婚を求めることができる。…
【離縁状】より
…江戸時代において庶民が離婚するとき,嫁入り・婿入りを問わず,必ず夫から妻へ交付するを要した文書で,これの授受によって夫婦とも再婚することができた。幕府法上離縁状の授受なしに再婚した場合,男は所払(ところばらい)の刑に処せられ,女は髪をそり親元へ帰された。…
※「離婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...