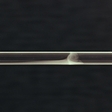水の中にインキを一滴そっと入れると,いろいろ模様を描きながら沈んでいくが,その際,色のついた部分がゆっくり周囲に広がって薄くなっていくのが見られる。濃い部分が作る模様はインキと水のわずかな比重の差による流れが作り出すものであるが,ゆっくり周囲に広がる現象は拡散である。煙突やたき火の煙が風のない日でも,もくもく上がったりたなびいたりするのは,対流などによるためで,もしまったく静止した空気の中に同じ温度の煙をそっと置くことができたら,煙は非常にゆっくり周囲に散っていく。これが拡散現象で,例えば,風のない晩秋の夕べに煙が町一帯にもやのように立ちこめてしまうことがあるが,やがて時が経つにつれ,いつしか消え去ってしまう。酸素ボンベの栓を開くと,たとえボンベの圧力が外の空気の圧力と同じであっても,やがて中の酸素が外の空気と混ざり合って,ボンベの中も外も窒素対酸素の濃度比がいたるところ一様になってしまう。これも拡散であるが,このように異なる物質(この場合は酸素と窒素)どうしが互いになるべく同じ濃度比になるように混ざり合っていく現象を相互拡散という。一方,圧力の異なる二つの酸素ボンベ(一方は真空でもよい)を結びつけると,両者の密度が同じになるように,圧力の高いほうから低いほうへ酸素ガスが流れ込んでくる。これも拡散現象であり,このように同種類の物質における拡散を自己拡散と呼ぶ。茶わんに熱い茶をいれると,しだいに外側まで熱くなってくるが,これは固体内での熱エネルギーの拡散現象で,熱拡散と呼ばれている。ただしストーブで部屋が暖まるのは対流によるもので,空気中における熱拡散はきわめて緩慢である。
拡散方程式
一口に拡散というと非常に意味が広がってしまうが,物理学などでいう拡散は,多くの場合,そのマクロな動きが拡散方程式によって記述されるような現象を指している。この拡散方程式は,フィックの方程式とも呼ばれ,次の二つの法則を組み合わせたものである。一つはフィックの第1法則と呼ばれるもので,密度ρの拡散を例にとると,この密度を構成している粒子の流れJ(流れの方向に垂直な単位面積を単位時間当りに通過する粒子数)がρのこう配に比例し,またこのこう配とは逆向きになっているというもので,J=-D gradρで表される。この比例係数Dを拡散係数という。これは近似的な法則で,ρのこう配があまりきつくなると成立しなくなる。もう一つは粒子数の保存則で,それは任意の位置において,ρの時間変化の割合と,Jのこう配とを結びつける連続の式と呼ばれる方程式,∂ρ/∂t=-div Jで表される(tは時間)。これは厳密に成り立つ。以上二つの法則はρに対する一つの線形偏微分方程式にまとめられ,∂ρ/∂t=D(∂2/∂x2+∂2/∂y2+∂2/∂z2)ρ≡D∇2ρと表せる。これがフィックの方程式である。ρ,Jをそれぞれエネルギー密度とエネルギーの流れに置き換えれば,フィックの方程式は熱エネルギーの拡散方程式になる。エネルギー密度の時間的および空間的変化率は,それぞれ温度Tの時間的および空間的変化率に比熱を乗じたものに等しいので,フィックの方程式はTに対する線形偏微分方程式 ∂T/∂t=De∇2Tになる。一般に熱伝導の方程式と呼ばれているものはこれである。熱伝導率はエネルギーの流れとTのこう配の間の比例係数であるから,熱エネルギーの拡散係数Deに比熱を乗じたものになる。
→熱伝導
拡散の非可逆性
フィックの第1法則は非可逆的である。すなわち,ある拡散の過程があったとき,その時間の向きを逆にしたような過程は存在しえないことを主張する。実際,きれいな湖の中にひとりでにインキの固まりが現れたり,海や空気の中に自然発生的にエネルギーが凝集し,北洋の海水の一部が沸騰し始めたり,都会の中にひとりでに窒素ばかりの酸欠空気が現れたりといった拡散の逆現象はありえない。拡散は自然界が与えられた条件のもとでは,可能な限り大きなエントロピーを獲得しようとしている姿の現れであり,必ずエントロピー生成を伴うものである。このような非平衡系でも,空間の各点の近傍では,熱平衡が成立しているという前提のうえにフィックの法則は成り立っている。この前提を局所平衡という。場所によって異なる温度というとき,この仮定が暗黙のうちに使われている。
以上の視点で,拡散を非可逆過程の熱力学の枠組みに組み込むことができる。密度のこう配は非可逆的な流れを引き起こそうとする熱力学的力であり,フィックの第1法則は流れがこの力に比例するというのであるから線形法則である。したがって拡散方程式は線形非可逆過程の方程式の一つである。線形非可逆過程の枠組みの中にいる以上,化学ポテンシャルの異なる二つの粒子の間にはさまれた系の拡散流とか,温度の異なる二つの熱源の間にはさまれた系の熱流では,どんな初期条件から出発しても行き着くところは定常状態である。
拡散方程式が多くの人々の注目を集めるようになったのは,熱伝導の方程式の非定常解をJ.B.J.フーリエが論じてからであるといえよう。これはまたフーリエ級数の初登場でもあった。しかしそこではまだ非可逆過程の熱力学という奥行きは感じられていなかった。
拡散の分子論
拡散方程式の分子論的基礎は,二つのまったく異なるアプローチから与えられた。一つは熱平衡状態にある液体の中に浮遊しているコロイド粒子(微粒子)の拡散である。このときコロイド粒子には常時たくさんの分子があらゆる方向からぶつかっている。その結果,コロイド粒子の受ける力は,どの瞬間においても,平均化されてしまってほぼゼロではあるが,粒子が小さいため完全にゼロとはみなしえない。この消え残った力は絶えずゆらいでいる。これによりコロイド粒子のブラウン運動が見られるのであるが,この運動は決定論によっては決められず,確率法則に支配されている。ここで,ある位置から出発したコロイド粒子が,時間が経つにつれ,空間の中でどんな確率分布をとっていくかを記述するのがスモルコフスキー方程式である。この方程式から出発して,確率分布の変化が時間的にも空間的にもゆっくりで,はなはだしい飛躍はないとすると,確率分布が拡散方程式に従うことが示される。したがって平衡状態にある液体の中を浮遊している多数のコロイド粒子の密度も,拡散方程式に従うことになる。コロイド粒子に電荷があって,これに外から電場をかけて外力Fを与えると,粒子は平均の速度vをもつようになるが,他方,粒子が液体分子から受ける力は,ゆらぎの部分を平均してならしてしまっても,ゼロでなくなって,それはvと逆向きの抵抗の力になる。この抵抗のため,vは外力Fに比例した一定値に落ち着く(v=bF)。この比例係数bを移動度という。アインシュタインはこの移動度bと拡散係数Dの間にはD=kTbという関係が存在することを見いだした。ここにkはボルツマン定数で,Tは絶対温度である。これはアインシュタインの関係式と呼ばれ,相対論や光電効果の発見と並び重要な発見である。なぜなら,これは,すべての動きが止まっているかに見える熱平衡状態において,激しい分子運動があるというボルツマンの主張を,間接的にではあるが,Dやbという実測可能な量によって実証するものとなったからである。
拡散の分子論のもう一つのアプローチは,気体や液体の分子運動論から,分子の密度やエネルギー密度の拡散方程式を導くというものである。分子は大部分の時間を等速直線運動をし,互いにぶつかり合うときにだけ撃力を及ぼし合っているとして,衝突は確率の法則に従っていると仮定する。これを分子の位置と運動量の確率分布が従う方程式に表したものがボルツマン方程式である。ここで確率分布の時間的空間的変化が緩やかであるとし,局所平衡に近い分布をしていると仮定すると,粒子密度やエネルギー密度が拡散方程式に従うことが証明され,拡散係数を粒子の質量,密度,衝突の強さなどの関数として求めることができる。このアプローチによる拡散のミクロ理論は,ブラウン運動のアインシュタイン理論(1905)よりかなり遅れて,粘性などの輸送係数のミクロ理論とともに発達したのである。
粒子がまっすぐ衝突なしに突き進んでしまったら,拡散方程式に従う現象など期待できない。衝突のため粒子は平均自由行路といわれる距離ぐらいしか直進できない。その結果,ある位置から出発した粒子は時間の経過とともに出発点からどれくらい離れるかというと,時間tに比例しては離れられず,せいぜい\(\sqrt{t}\)に比例した距離程度である。この事情はブラウン運動のときと同じで,これが拡散現象の根源なのである。
固体の熱伝導は,フォノンに対するボルツマン方程式から上と同様にして導かれるが,種々の難問がある。このほか,磁性体の無秩序相におけるスピンの拡散や,伝導電子のスピンの拡散も,マクロにはフィックの拡散方程式で記述される。固体の中を原子やイオンや格子欠陥が移動していくようすは,一歩一歩が確率過程であり,ブラウン運動に似ているので,これらは拡散現象を呈する。金属中に蓄えられた水素や,氷における水素の遍歴運動もこうした拡散現象の一例であるが,一歩ごとの遍歴運動が量子論のトンネル効果によるので量子拡散の現象といわれることがある。なお,絶対0度ではフィック型の拡散現象はきれいな系では存在しえない。それは,平均自由行路が無限に長くなったり,遍歴運動が凍りついてしまうからである。
→ブラウン運動
執筆者:伊豆山 健夫