精選版 日本国語大辞典 「東山道」の意味・読み・例文・類語
とうさん‐どう‥ダウ【東山道】
- [ 一 ] 令制の広域行政区画。畿内(五畿)の外を七道に分けたものの一つ。近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽の八か国。はじめ定制がなく大宝元年(七〇一)に至って近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵・下野とされ、のち陸奥・出羽を加え、宝亀二年(七七一)武蔵を東海道に移して八か国が固定した。とうせんどう。
- [初出の実例]「武蔵野国〈略〉改二東山道一、属二東海道一」(出典:続日本紀‐宝亀二年(771)一〇月己卯)
- [ 二 ] 古代以来、畿内より東国へ達する幹線道路。東海道が海の道であるのに対し山の道と称される。近江草津で東海道と分かれ、木曾谷をさかのぼって塩尻に至り、浅間山麓を越えて碓氷(うすい)峠を下って武蔵国に至る。中世以来、中仙道とよばれ、近世五街道の一つとなる。
日本歴史地名大系 「東山道」の解説
東山道
とうさんどう
- 宮城県:総論
- 東山道
下野国から 借
借
 借
借 借郷があることから、「大日本地名辞書」によって白石市越河付近に擬定するのが妥当と思われる。なお大槻如電の「駅路通」では、越河より白石の町に近い同市
借郷があることから、「大日本地名辞書」によって白石市越河付近に擬定するのが妥当と思われる。なお大槻如電の「駅路通」では、越河より白石の町に近い同市 借駅を出た官道は、北上して白石川流域に出て、その左岸を進んで大河原に出る。さらに同川左岸を東に進むと船迫に至る。「吾妻鏡」によると、阿津賀志山の戦で勝利した頼朝は舟迫宿に逗留したとあることから(同書文治五年八月一一日条)、船迫擬定説が生れる。両説いずれが正しいとは定めがたいが、船迫付近には円墳・横穴古墳が多くあり、天安二年(八五八)創建と伝える
借駅を出た官道は、北上して白石川流域に出て、その左岸を進んで大河原に出る。さらに同川左岸を東に進むと船迫に至る。「吾妻鏡」によると、阿津賀志山の戦で勝利した頼朝は舟迫宿に逗留したとあることから(同書文治五年八月一一日条)、船迫擬定説が生れる。両説いずれが正しいとは定めがたいが、船迫付近には円墳・横穴古墳が多くあり、天安二年(八五八)創建と伝える
東山道
とうさんどう
- 群馬県:総論
- 東山道
上野国南部を横断した古代の官道。信濃から上野に至り、下野を経て陸奥に至る最も長い官道であった。古代律令国家は官道を維持・管理するためにほぼ四里(約一六・六キロ)ごとに駅を設け、駅馬を置いておもに公用に供した。「延喜式」兵部省に「上野国駅馬 坂本十五疋、野後・群馬・佐位・新田各十疋、伝馬 碓氷・群馬・佐位・新田各五疋」と記され、
上野国内の五つの駅の所在推定地は次のとおりである。坂本は現
道筋は碓氷峠、国府付近、新田郡の三地域では説が分れる。碓氷峠については、現在の碓氷峠が明治一三年(一八八〇)に開通される以前は、南の
東山道
とうさんどう
- 山形県:総論
- 東山道
陸奥国府の置かれた
〔奥羽連絡路の開設〕
養老五年(七二一)出羽国は陸奥按察使の管轄下となった。以後出羽国は陸奥国とよりいっそう連係を深めながら、北方の開拓にあたることになる。天平五年(七三三)には出羽柵は庄内地方から秋田村 賀美郡
賀美郡 至
至 出羽国最上郡玉野
出羽国最上郡玉野 八十里」などとみえることから、山道駅路
八十里」などとみえることから、山道駅路
東山道
とうさんどう
- 長野県:総論
- 東山道
古代の令制による官道の一で、「日本書紀」景行天皇五五年二月五日条に「以 彦狭島王
彦狭島王 拝
拝 東山道十五国都督
東山道十五国都督 」とあり、その読みについては「釈日本紀」に「ヤマノミチ」、「西宮記」には「ひうかしのやまのみち」、「北山抄」には「山の道」などとしているが、種々の考察に基づき、「あづまやまのみち」と読むべきであろう。
」とあり、その読みについては「釈日本紀」に「ヤマノミチ」、「西宮記」には「ひうかしのやまのみち」、「北山抄」には「山の道」などとしているが、種々の考察に基づき、「あづまやまのみち」と読むべきであろう。
「延喜式」によれば近江国
東山道
とうさんどう
- 滋賀県:総論
- 東山道
古代の地方行政領域の一つ東山道諸国を貫いて古代
東山道
とうさんどう
- 岐阜県:総論
- 東山道
律令体制下の大行政区分である七道の一つ、東山道諸国を貫いて設けられた官道。京から近江国・美濃国・信濃国などを経て陸奥国に至る。途中その沿線からはずれた国には支路を設けている。「令義解」厩牧令の諸道置駅馬条によれば、東海道とともに中路とされ、東山道が律令政府によって重要な位置づけがされていたことがわかる。そのおもな理由は、東国へのルートであることによる。これは東山道の初源的な姿を、大和朝廷の東国進出ルートに求める見解にも一致する。
東山道の開発・整備がいつ頃行われたかについては確証はないが、美濃国についていえば、「続日本紀」大宝二年(七〇二)一二月一〇日条の「始開美濃国岐蘇山道」との記述や、同書和銅六年(七一三)七月七日条に「美濃信濃二国之堺、径道険隘、往還艱難、仍通吉蘇路」とみえる記事がある。ここにみえる
東山道
とうさんどう
- 東京都:総論
- 東山道
律令制下において京を中心に諸国を編成した五畿七道の一。「ヤマノミチ」「ヒムカシノミチ」などとも読まれる。「日本書紀」景行天皇五五年条に彦狭島王を東山道一五国の都督としたとあるが、東山道が制度として整備されるようになるのは天智期以降である。近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵・下野・陸奥・出羽の諸国が所属する。これらの諸国へは京より直線形態を旨とする官道が開削され、この官道をも東山道と称した。
武蔵国府へ至る官道は、「続日本紀」宝亀二年(七七一)一〇月二七日条に「武蔵国雖 属
属 山道
山道 兼承
兼承 海道
海道 、公使繁多、祗供難
、公使繁多、祗供難 堪、其東山駅路、従
堪、其東山駅路、従 上野国新田駅
上野国新田駅 達
達 下野国足利駅
下野国足利駅 、此便道也、而枉従
、此便道也、而枉従 上野国邑楽郡
上野国邑楽郡 経
経 五ケ駅
五ケ駅 、到
、到 武蔵国
武蔵国 、事畢去日、又取
、事畢去日、又取 同道
同道 向
向 下野国
下野国 」とあることから、上野国南部を通過する東山道本道から
」とあることから、上野国南部を通過する東山道本道から
東山道
とうさんどう
- 福島県:総論
- 東山道
律令体制下の東海道・北陸道などとともに、畿内から東方あるいは北東方に延びる街道名であると同時に地域名でもある。地域としての東山道は近江・美濃・飛騨・信濃・武蔵・上野・下野・陸奥および出羽の九ヵ国を含む。のちに武蔵は東海道に編入されて八ヵ国となる。街道としての東山道は、京都から
東山道
とうさんどう
- 岩手県:総論
- 東山道
東山道
とうさんどう
- 栃木県:総論
- 東山道
律令国家のもとで東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の幹線七道が設定された。これら七道はその重要度に応じて大路・中路・小路に区分され、三〇里(約一六キロ)ごとに駅が設置され、前述の三区分にしたがって、各々二〇疋(大路)から五疋(小路)の駅馬が配され、おもに公的な文書伝達・物資輸送の用に供された。下野国内を南西部から北東部へと縦貫する幹線が東山道で、「令義解」によれば中路とされる。「延喜式」兵部省諸国駅伝馬条によれば、東山道の駅は総計八六で、各駅に配された駅馬数は一般に中路相当の一〇疋前後であった。下野国内には足利・
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
百科事典マイペディア 「東山道」の意味・わかりやすい解説
東山道【とうさんどう】
→関連項目青墓宿|足柄関|板鼻|駅・駅家|近江国|柏原宿|株河駅|黒田宿|群馬[県]|上野国|信濃国|下野国|白河関|墨俣川の戦|世良田|出羽国|鳥居本|番場宿|飛騨国|厩橋|美濃国|武蔵国|陸奥国
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「東山道」の意味・わかりやすい解説
東山道 (とうさんどう)
古代の地方行政区画の七道(五畿七道)の一つ。本州の中央から東北にわたる地域。《西宮記》では〈ヤマノミチ〉〈東ノミチ〉などと読んでいる。《日本書紀》崇峻紀にみえる東山道は後の追記。ただ672年(天武1)の壬申の乱の記事に東山軍の名がみえ,685年に東山使者として石川虫名派遣がみえるので,東山道の成立を天武朝末年とみることができよう。《延喜式》では近江,美濃,飛驒,信濃,上野,下野,陸奥,出羽の8国が所属するが,所属国はたびたび変遷を示した。出羽は712年(和銅5)に北陸道の越後から分立しこの道所属となった。721年(養老5)信濃から諏方が分立したが,731年(天平3)また併合された。また718年(養老2)陸奥と常陸の数郡を割いて石城(いわき),石背(いわしろ)の2国が設けられたが,721年ころ廃止された。さらに武蔵は771年(宝亀2)東海道に所属変更となった。北辺の防衛で重要な地域であった。なお駅制の官道としての東山道は〈なかつみち〉ともよばれ各駅に馬10匹をおく中路とされた。
→中山道
執筆者:亀田 隆之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「東山道」の意味・わかりやすい解説
東山道(とうさんどう)
とうさんどう
古代より東海・北陸両道の間に位置し、畿内(きない)から東方、山間の諸国を経て奥羽地方に及ぶ行政区域と、その道筋をいう。正しくは「とうせんどう」と訓(よ)む。『北山抄(ほくざんしょう)』(11世紀初め成立)は、東山道を山乃道(やまのみち)・東乃道と称している。『日本書紀』は、景行(けいこう)天皇の55年、彦狭島(ひこさしま)王を東山道15か国の都督(ととく)に任じたと記しているが、当時いまだ分道の制はなかった。700年(文武天皇4)巡察使が東山道に派遣されたころ、七道が分置されたようで、東山道は近江(おうみ)、美濃(みの)、飛騨(ひだ)、信濃(しなの)、武蔵(むさし)、上野(こうずけ)、下野(しもつけ)、陸奥(むつ)の八か国をさしたが、その後出羽(でわ)を加え、武蔵を除いた。1868年(明治1)陸奥・出羽をそれぞれ分けて七か国としたため、東山道は15か国となる。なお、東山道の道筋は中路で、各駅には馬10疋(ぴき)を定置した。
[丸山雍成]
『『古事類苑2 地部一』(1970・吉川弘文館)』
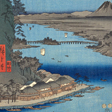
歌川広重『六十余州名所図会 近江 琵琶…
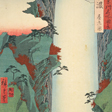
歌川広重『六十余州名所図会 美濃 養老…

歌川広重『六十余州名所図会 飛弾 籠わ…

歌川広重『六十余州名所図会 信濃 更科…

歌川広重『六十余州名所図会 上野 榛名…
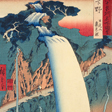
歌川広重『六十余州名所図会 下野 日光…

歌川広重『六十余州名所図会 陸奥 松島…

歌川広重『六十余州名所図会 出羽 最上…
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東山道」の意味・わかりやすい解説
東山道
とうさんどう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「東山道」の解説
東山道
とうさんどう
(1)古代の七道の一つ。現在の近畿地方から中部・関東地方の山地沿いをへて東北地方に連なる地域で,近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵(771年東海道へ編入)・下野・陸奥・出羽の各国が所属する行政区分。(2)これらの諸国を結ぶ交通路も東山道と称し,「山の道」ともよばれ,畿内から各国府を順に結ぶ陸路が官道として整備された。駅路としては中路で各駅に10頭の駅馬がおかれる原則であり,「延喜式」では総計86駅に841頭の駅馬をおく規定であった。地方官として732~734年(天平4~6)に東海東山二道節度使,746年に東山道鎮撫使を設置した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「東山道」の解説
東山道
とうさんどう
現在の中部・関東・東北の山地一帯の地方で,近江・美濃 (みの) ・飛驒・信濃・上野 (こうずけ) ・下野 (しもつけ) ・陸奥 (むつ) (明治初期に磐城 (いわき) ・岩代・陸前・陸中・陸奥に分かれた)・出羽(明治初期に羽前・羽後に分かれた)の8カ国(明治以後13カ国)。武蔵は初め東山道に属したが,771年以降東海道に属した。のちこの地を通る街道をさすようになった。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東山道の言及
【駅伝制】より
…中央から辺境にのびる道路にそい,適当な間隔で人・馬・車などを常備した施設すなわち駅を置き,駅を伝わって往来する交通・通信の制度。世界史上,前近代に広大な地域を支配する中央集権国家が成立すると,外敵の侵入や国内の反乱に直ちに対処するばあいを含め,支配維持のために中央と地方とを常時連絡する手段が必要となり,さまざまな形態の駅伝が制度として定められるのが一般であった。このように駅伝制はもともと前近代における支配手段の一種であったから,国家の管理下に置かれて民間の自由な利用は許さないのが原則であり,また国家権力の解体とともに衰退していった。…
【奥州街道】より
…中世の陸奥の主要幹線道路。古代の陸奥国の幹線的官道は,下野国から白河関をこえて陸奥国に入り,陸奥国を縦に貫く道である(東山道)。そのコースは,中世にも〈奥大道〉などと呼ばれて,基本的に変わることなく受けつがれた。…
【信濃国】より
…現在の長野県。
【古代】
東山道に属する上国(《延喜式》)。はじめ科野国と記されたが,713年(和銅6)の好字制により信濃国とされた。…
※「東山道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


