精選版 日本国語大辞典 「東海道」の意味・読み・例文・類語
とうかい‐どう‥ダウ【東海道】
- [ 一 ] 古代の五畿七道の一つ。伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江・駿河・甲斐・伊豆・相模・安房・上総・下総・常陸の一四か国に東山道から移された武蔵を加えた一五か国をいう。海つ道。
- [ 二 ] [ 一 ]の諸国を結ぶ道。鎌倉時代に京都と鎌倉を結ぶ街道として、急速に発達。江戸時代は五街道の一つとして京都と江戸を結び五三の駅(東海道五十三次)を置いた。現在は、ほぼこれに沿って国道一号が通じる。
日本歴史地名大系 「東海道」の解説
東海道
とうかいどう
- 静岡県:総論
- 東海道
畿内から発し東海地方を経由して東国へと続く幹線道。またこの道路に沿って分布する畿外諸国をまとめた行政上の単位をさす。和訓はヒガシノウミノミチ。静岡県内の遠江・駿河・伊豆三国はいずれも行政上「東海道」に属し、中央放府との間での使者の往来・情報伝達は東海道を利用して行われた。古代には坂東・奥羽諸国と中央との連絡路として、東山道とともに重要な役割を果した。江戸時代は道中奉行管轄下の五街道の一つ。
〔古代〕
行政単位としての東海道は、天武一二年(六八三)頃成立したとする見解が有力である。交通路としての東海道という名称もこの時期に確定したと考えられるが、畿内から静岡県内を経由して坂東へと続く道路そのものは、むろん古くから存在していたであろう。静岡県内には急流河川を中心とする小平野と海岸部に張出す山地・台地とが断続的に並ぶが、交通路としての東海道はこれらを東西に横断する。そのため浜名湖や天竜・大井・
具体的なルートについては、「静岡県史」編纂や「静岡県歴史の道調査」事業、さらには矢田勝氏らによる条里地割を基にした古代道復原研究などで追究が進められている。
東海道
とうかいどう
- 神奈川県:総論
- 東海道
〔古代〕
「古事記」や「日本書紀」によれば倭建命(日本武尊)が
宝亀二年(七七一)一〇月それまで東山道に属していた武蔵国を改めて東海道に属させることとなったが、その理由として当時の東海道はすでに相模国から陸路を通り下総国に至っており、武蔵国は東海道に属するほうが便利であるとされている(「続日本紀」同月二七日条)。すでに神護景雲二年(七六八)三月に下総国
東海道
とうかいどう
- 東京都:総論
- 東海道
古代に畿内から発し、東海地方を経由して東国へと至った幹線道。またこの道沿いに分布した畿外諸国をまとめた行政上の単位でもあった。律令制下では大・中・小路に分けたうちの中路にあたる。東山道とともに古代には畿内と坂東・奥羽諸国をつなぐ重要な道であった。江戸時代には、江戸を基点として整備された五街道の一つで、道中奉行が管轄した。江戸(日本橋)―京都(三条大橋)間に、初宿の品川宿から
〔古代・中世〕
律令制下においては中国の州県制にならい国郡制をしき、諸国を五畿七道に編成した。東海道は七道の一で、「ウミツミチ」「ヒムカシノウミノミチ」などとも読む。「日本書紀」崇神天皇一〇年条に四道将軍の派遣先の一としてみえるが、制度として整えられるようになるのは天智朝以降である。伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江・駿河・甲斐・伊豆・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸の諸国からなる。もっとも武蔵国が東海道所属になるのは宝亀二年(七七一)一〇月以降で、それ以前は東山道に所属していた。これらの諸国へは京より直線形態をとる官道が敷設され、この官道をも東海道と称した。東海道諸国を束ねる常置の官司は設置されていないが、臨時の官である巡察使や間民苦使は道単位で置かれており、大同元年(八〇六)五月に置かれることになった観察使も道を分掌し、初代の東海道観察使は藤原葛野麻呂であった(公卿補任)。ただし観察使は弘仁元年(八一〇)六月に廃止され参議制に戻っている(「日本紀略」同月二八日条)。朝廷から地方諸国へ布告される太政官符や宣旨等は道ごとに専使が遣わされたり逓送の方式により伝達された。官道設置の目的の一は朝廷からの下達を迅速に行うことにあり、他は地方諸国から朝廷へ必要事項を上申する際の交通路として使用された。そのため三〇里(約一六キロ)ごとに馬の乗継ぎや休養・宿泊施設である駅家が設置された。
初期の官道としての東海道は相模国府を出ると三浦半島に向かい、その先端部より東京湾口を横切り上総国に上陸し、一は南下して安房国府へ向かい、他は北上して千葉県市原市に所在した上総国府へ至り、そこより
東海道
とうかいどう
- 滋賀県:総論
- 東海道
歴史時代、ほぼ一貫して畿内と東国を結んだ主要幹道。古代には都を発し東国の太平洋岸地域を通り、常陸国からさらに北上、陸奥国
〔古代〕
初めて近江国内を通るのは天智天皇六年(六六七)からの近江大津京の時代で、大津京南を出た道筋は 萩野
萩野 (逢坂関)を越えて近江に入った。「日本紀略」延暦一四年七月二六日条に「遣左兵衛佐橘入居検近江若狭両国駅路」とあるのは、文脈からいえば北陸道にかかわる記事と読むこともできるが、平安京成立の翌年であることからすれば、近江一国の駅路を若狭一国の駅路とともに調査したと読むこともできる。
(逢坂関)を越えて近江に入った。「日本紀略」延暦一四年七月二六日条に「遣左兵衛佐橘入居検近江若狭両国駅路」とあるのは、文脈からいえば北陸道にかかわる記事と読むこともできるが、平安京成立の翌年であることからすれば、近江一国の駅路を若狭一国の駅路とともに調査したと読むこともできる。
東海道
とうかいどう
- 三重県:総論
- 東海道
〔古代〕
東海道の名称は、周知のように「日本書紀」崇神天皇一〇年九月条の、いわゆる四道将軍派遣のことを記すなかに「武渟川別をもて東海に遣す」と出る。都より東国へ通ずる海沿いの道路に連なる地域という意味であろう。大宝令施行以前の伊勢国内の道筋については、壬申の乱における大海人皇子のとった経路がそれとされる。すなわち書紀によれば、吉野を出た皇子は、大和国 萩野
萩野
都が京都に移されると、東海道は再び手直しが行われる。近江国から鈴鹿峠を越える新道がそれで、「三代実録」仁和二年(八八六)五月一五日条に、新道開削について実地調査が行われたことを記し、同年六月二一日条に、伊勢斎王内親王がこの新道を通って大神宮へ入ることを伊勢国へ通知したとも記している。
東海道
とうかいどう
- 愛知県:総論
- 東海道
〔古代〕
東海道は五畿七道の一として行政上の地域を称した。「日本書紀」には崇神天皇一〇年の四道将軍を派した伝承に「武渟川別をもて
東海道はまた京からこの地域を通って常陸国府(現茨城県石岡市)への道をさした。各所に駅家を設けて人馬を常備したが、「延喜式」(兵部省)によれば現愛知県内の駅は
〔中世〕
鎌倉幕府の成立で、東海道は鎌倉街道とよばれ、鎌倉と京を結ぶ重要な道となる。「吾妻鏡」文治三年(一一八七)三月三日条には、美濃国守護に新宿を加うべきことの記事があり、また幕府から朝廷への使者も美濃を通っているので、これが公式の道となったといえよう。
東海道
とうかいどう
- 千葉県:総論
- 東海道
古代の官道。畿内と東国を結び、房総から常陸に出て陸奥
東海道
とうかいどう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
百科事典マイペディア 「東海道」の意味・わかりやすい解説
東海道【とうかいどう】
→関連項目愛知[県]|赤坂|新居[町]|新居関|安房国|伊賀街道|伊賀国|石部[町]|伊豆国|伊勢路|伊勢国|今切渡|磐田[市]|駅・駅家|江尻|大磯[町]|大木戸|大久保長安|大山街道|岡部[町]|小田原[市]|音羽[町]|尾張国|甲斐国|掛川[市]|柏原宿|金谷[町]|川越|川崎[市]|観音寺城|蒲原[町]|北[区]|京街道|草津[市]|相模国|薩【た】峠|佐夜ノ中山|静岡[県]|静岡[市]|七里渡|品川宿|島田[市]|志摩国|清水[市]|下総国|宿・宿駅|宿村大概帳|白河関|白須賀|鈴鹿[市]|墨俣川の戦|駿河国|関[町]|茶壺道中|土山[町]|手越宿|遠江国|鳥居本|中山道|中原道|日坂|沼津[市]|箱根峠|箱根関|原|番場宿|引間|常陸国|平塚[市]|袋井[市]|藤枝[市]|藤川|藤沢[市]|伏見奉行|二川|保土ヶ谷[区]|舞阪[町]|三河国|三島[市]|水口[町]|武蔵国|山崎通|山中郷|由比[町]|吉田|六郷渡
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「東海道」の意味・わかりやすい解説
東海道
とうかいどう
京師より太平洋に沿って東方に至る地域または街道名。
[児玉幸多]
古代
崇神(すじん)天皇のとき、四道将軍の1人、武渟川別命(たけぬかわわけのみこと)が巡視した東路(うみつみち)、日本武尊(やまとたけるのみこと)や景行(けいこう)天皇が東国に赴いたときの道と伝承する、三浦半島から房総半島へ渡るのが古代の道であったのであろう。律令(りつりょう)制では行政区画の五畿(ごき)七道の一つである。すなわち初めには伊賀、伊勢(いせ)、志摩、三河、尾張(おわり)、遠江(とおとうみ)、駿河(するが)、伊豆、甲斐(かい)、相模(さがみ)、上総(かずさ)、下総(しもうさ)、常陸(ひたち)の13か国であった。718年(養老2)上総の4郡を割いて安房(あわ)国を置いたが、741年(天平13)旧に復し、757年(天平宝字1)にふたたび安房国を置いた。また771年(宝亀2)に武蔵(むさし)国を東山道(とうさんどう)より東海道に転属し、これより15か国となった。道筋も相模より武蔵を経て下総に入ることとなった。行政上では各国に国司が置かれたほか、東海道全域に対して巡察使・観察使などの派遣されることもあった。これら諸国を結ぶ街道も東海道というが、都が大和(やまと)にあったときには、伊賀国に入り、それより伊勢、志摩を経て尾張、三河に達したが、都が山城(やましろ)に移ると、近江(おうみ)から鈴鹿(すずか)峠を越えて伊勢に入るようになった。令制によれば、街道には駅が設けられて、公使の利用に供せられたのであるが、『延喜式(えんぎしき)』の諸国駅伝馬の条には伊賀と伊豆両国には記載がない。主要路から外れたことになる。これら駅の所在については明確でない所も多く、したがって古代の東海道の道筋のすべてを明らかにすることはできない。平安時代の初め802年(延暦21)に富士山が噴火したため、足柄(あしがら)道を廃して「筥荷途(はこねじ)」を開いたが、翌年には足柄道が復旧して、官道はもとに戻った。
[児玉幸多]
中世
鎌倉時代になると、鎌倉と京都の間が最重要路となり、幕府では宿ごとに早馬を常設するなどのことをしている。また公私の旅行者の増加によって宿駅に遊女が集まるようにもなり、天竜川畔の池田宿、浜名湖畔の橋本宿などがとくに著名であった。なお鎌倉時代からは、鎌倉と京都の往来に、熱田(あつた)から美濃(みの)路を経て東山道の近江から入洛(にゅうらく)、また逆に下洛する道筋も用いられた。戦国時代には、東海道諸国は群雄が競い興り、尾張の織田(おだ)、三河の松平(徳川)、駿河の今川、甲斐の武田、相模の北条などの諸氏が勢力を振るい、それぞれの領内には伝馬制度が発達した。
[児玉幸多]
近世
関ヶ原の戦いによって徳川家康が覇権を確立すると、1601年(慶長6)には東海道諸宿に伝馬制を設け、宿ごとに36匹の馬を常備させて、公用旅行者またはそれに準ずる者の使役に供した。宿の設置は一時に完了したものではなく、戸塚(とつか)宿は1604年、石薬師(いしやくし)宿は1616年(元和2)、川崎宿は1623年など逐次追加されて1624年(寛永1)の庄野(しょうの)宿の設立によって、江戸(日本橋)―京都(三条大橋)間に品川―大津宿の53宿が整い、通常「五十三次」という。次ぐは継ぐと同意で、宿ごとに人馬の継立(つぎたて)をしたからである。なお大津より分かれて、伏見(ふしみ)、淀(よど)など四宿を経て大坂に至る街道も東海道とした。そのほか東海道の脇(わき)街道としては、熱田から伊勢湾の北岸の万場(まんば)、佐屋(さや)などの四宿を経て桑名(くわな)に至る佐屋路と、浜松から分かれて、浜名湖の北岸の気賀(きが)、三ヶ日(みっかび)などの三宿を通って御油(ごゆ)または吉田へ出る本坂(ほんさか)通があった。また本街道の箱根(はこね)と新居(あらい)(今切(いまぎれ))と、本坂通の気賀には関所があって、往来人や携帯品を改めた。
宿の任務は人馬の継立や旅行者の休泊に応ずることにあり、人馬は初め馬36匹の提供を義務づけられていたが、寛永(かんえい)期(1624~44)には本街道では100人、100匹とされた。この人馬は幕府公用の旅行者や大名、公家(くげ)、武士などが指定された数までを使役でき、その事務は各宿の問屋場で行った。そのほかの庶民は馬士(まご)や駕籠(かご)かき人足と相対(あいたい)で利用した。東海道には天竜川、大井川などの大河川があるほか、今切、伊勢湾などの渡海場もあり、船または人足によって渡る所が多く、風波や大水のために交通が途絶することもまれではなかったので、それを避けるために中山道(なかせんどう)を通行する者もあった。しかし参勤交代の大名をはじめ、東海道の利用者はもっとも多く、それに応じて本陣、脇本陣、旅籠(はたご)屋、あるいは茶屋などの設備も整い、小田原の外郎(ういろう)、箱根細工、丸子(まりこ)のとろろ汁、宇津(うつ)ノ谷(や)峠の十団子(とおだんご)、掛川の葛布(くずふ)、新居のうなぎ、鳴海絞(なるみしぼ)り、桑名の蛤(はまぐり)、草津の姥(うば)ヶ餅(もち)、大津絵など各地の名産・名物も多く、旅人を通じて諸方に広められた。
幕府はこの重要街道を確保するために、小田原、沼津、田中、掛川、浜松、吉田(現豊橋(とよはし))、岡崎、桑名などにはすべて譜代(ふだい)大名を配置した。それに駿府(すんぷ)を直轄とし、名古屋に親藩を置いた。将軍の上洛などにはそれらの城内が宿所にあてられた。一般旅行者には十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の滑稽本(こっけいぼん)『東海道中膝栗毛(ひざくりげ)』や歌川広重(ひろしげ)の浮世絵『東海道五十三次』などで親しまれ、18世紀末からは伊勢参宮や奈良、大坂、京都などの参詣(さんけい)や見物のために利用された。それらの紀行文も数多く残されている。このころには行政区画としての東海道の意味はなくなり、幕府の巡見使も東海地域というような範囲を単位とするようになった。
[児玉幸多]
『大熊喜邦著『東海道宿駅とその本陣の研究』(1942・丸善)』▽『大島延次郎著『日本交通史概論』(1964・吉川弘文館)』▽『児玉幸多・豊田武編『体系日本史叢書24 交通史』(1970・山川出版社)』▽『児玉幸多校訂『近世交通史料集 四 東海道宿村大概帳』(1970・吉川弘文館)』
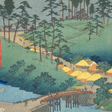
歌川広重『六十余州名所図会 伊賀 上野…

歌川広重『六十余州名所図会 伊勢 朝熊…

歌川広重『六十余州名所図会 志摩 日和…

歌川広重『六十余州名所図会 三河 鳳来…

歌川広重『六十余州名所図会 尾張 津島…

歌川広重『六十余州名所図会 遠江 浜名…

歌川広重『六十余州名所図会 駿河 三保…

歌川広重『六十余州名所図会 伊豆 修禅…

歌川広重『六十余州名所図会 甲斐 さる…

歌川広重『六十余州名所図会 相模 江之…
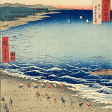
歌川広重『六十余州名所図会 上総 矢さ…
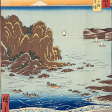
歌川広重『六十余州名所図会 下総 銚子…

歌川広重『六十余州名所図会 常陸 鹿島…

歌川広重『六十余州名所図会 安房 小湊…

歌川広重『六十余州名所図会 武蔵 隅田…
改訂新版 世界大百科事典 「東海道」の意味・わかりやすい解説
東海道 (とうかいどう)
地方行政区画の七道(五畿七道)の一つ。《西宮記》では〈ウヘツミチ〉〈ヒウカシノウミノミチ〉と読んでいる。北は東山道,南西は畿内および南海道の紀伊に接し,南東は太平洋に面している。《日本書紀》崇峻紀にみえる東海道は後の追記とみられるが,672年(天武1)壬申の乱の記事に東海軍とあり,また685年に東海使者として都努牛養派遣の記事がみえるので,その成立を天武朝末年に求めることができよう。《延喜式》によれば伊賀,伊勢,志摩,尾張,三河,遠江,駿河,甲斐,伊豆,相模,武蔵,安房,上総,下総,常陸の15国が所属するが,このうち武蔵は771年(宝亀2)に東山道から編入され,また安房は718年(養老2)に上総より分立したものである。大化前代から東山道の諸国とともに,大和朝廷の軍事力供給地としてとくに重きをなしたが,律令制下でも防人(さきもり)や征夷の兵士の供給地として,重要性に変りはなかった。なお駅制の官道としての東海道は令制では中路で,各駅に駅馬10疋をおくのが原則であった。《延喜式》では伊勢の鈴鹿駅より常陸の雄薩(おさか)駅まで55駅がおかれ,最多で22疋,最少で2疋の駅馬をおいている。
執筆者:亀田 隆之
中世
行政管区としては古代と同じく15ヵ国であった。しかし1185年(文治1),源頼朝が駅制を定めて京都・鎌倉間の交通路の整備をはかったので,交通路としての東海道は近江,美濃,尾張,三河,遠江,駿河,伊豆,相模を通過するこの幹線道路をさすようになった。この道を平安時代,すなわち《延喜式》に記載された東海道と比較すると,まず鈴鹿峠を越える伊勢路が,関ヶ原を越える美濃路に変更されていること,また足柄峠を越えたのち相模国府(海老名(えびな)市)より武蔵国府(府中市)にむかって内陸部を進んでいた道が,海岸沿いに鎌倉へ直行するようになったこと,さらにより鎌倉への近道となる芦ノ湖南岸の箱根路,湯坂道が,従来の北の足柄道と同等に利用,整備されるようになったこと等がおもなちがいである。室町時代の京都・鎌倉間は《大乗院日記目録》(応仁2年(1468)12月15日条)によれば,その間120余里,63宿ある。その宿場は近江では大津,勢田(せた),野路(のじ),守山,鏡,武佐,蒲生野(がもうの),愛智川(えちがわ),四十九院,小野,馬場(番場(ばんば)),佐目加井(醒井(さめがい)),柏原,居増,美濃では山中,垂井(たるい),赤坂,墨股(すのまた),尾張では黒田,折戸(下津(おりづ)),萱津(かやづ),熱田(あつた),鳴海(なるみ),沓懸(くつかけ),三河では八橋(やつはし),矢波木(矢作(やはぎ)),作岡,山中,赤坂,渡津,今橋,遠江では橋本,匹馬(引馬(ひくま)),池田,国府,袋井,懸川(掛川(かけがわ)),西坂(日坂),菊河,鎌塚,駿河では島田,前島,藤枝,岡部,満利子(丸子(まりこ)),手越,国府,瀬無川,高橋,興津(おきつ),湯井(由比(ゆひ)),蒲原(かんばら),車返,伊豆では三島,相模では葦河,湯本,小田原,酒匂(さかわ),郡水,志保見,平塚,懐島(ふところじま),鎌倉であった。これらの宿には守護の館がおかれたり,また市が開かれ,遊女や傀儡(くぐつ)もいて繁栄していたことが,多くの紀行文や記録によって知られる。
執筆者:服部 英雄
近世
戦国時代には松平,今川,後北条など東海道諸国で力を振るった大名が伝馬制度を設けたが,東海道全体に通ずる施設は行われなかった。関ヶ原の戦の終結した直後の1601年(慶長6)正月,徳川家康は東海道諸宿に伝馬の制を布き,1日に36疋までの伝馬の提供を命じ,代償に居屋敷を与えた。宿はすでに既存の集落を利用したが,18年(元和4)に箱根宿,23年に川崎宿を設置するなど遅れたものもある。江戸(日本橋)・京都(三条大橋)間に品川,川崎,神奈川,保土ヶ谷,戸塚,藤沢,平塚,大磯,小田原,箱根,三島,沼津,原,吉原,蒲原,由比,興津,江尻,府中,丸子,岡部,藤枝,島田,金谷,日坂,掛川,袋井,見附,浜松,舞坂,新居,白須賀,二川,吉田,御油,赤坂,藤川,岡崎,池鯉鮒(ちりゆう),鳴海,宮,桑名,四日市,石薬師,庄野,亀山,関,坂下,土山,水口,石部,草津,大津の53宿があるので,五十三次という。また大津から伏見,淀,枚方(ひらかた),守口の4宿を経て大坂に至る京街道も東海道の延長とみなされる。江戸・京都間が126里6町余,江戸・大坂間が137里4町余であった。脇道として,浜松から浜名湖の北岸を通って吉田または御油に出る本坂(ほんさか)道(姫街道)には気賀,三ヶ日,山嵩の3宿があり,宮から伊勢湾の北を巡って桑名または四日市に出る佐屋路には岩塚,万場,神守,佐屋の4宿があった。宮からは名古屋,墨俣,大垣を経て中山道の垂井に合する美濃路があるが,これが鎌倉時代の東海道の一つの道にほぼ重なる。箱根関,新居関があるほか,大井川,天竜川や宮・桑名間の海路(七里渡)などの難所があった。しかし近世では宿駅,継立人馬等の施設が最もすぐれ,参勤交代の大名をはじめ通行者が多く,つねににぎわいをみせた。多くの紀行文のほか,案内書も多く,歌川広重の《東海道五十三次》や十返舎一九の《東海道中膝栗毛》なども広く流布した。明治維新後の鉄道東海道本線は鎌倉時代の東海道の一つにおおむね沿っている。
執筆者:児玉 幸多
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「東海道」の解説
東海道
とうかいどう
(1)古代の七道の一つ。伊勢湾沿岸から現在の中部・関東両地方の太平洋岸にそった地域で,伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江・駿河・伊豆・甲斐・相模・武蔵(771年に東山道から移管)・安房・上総・下総・常陸の各国が所属する行政区分であった。地方官として732~734年(天平4~6)に東海東山二道節度使,746年に東海道鎮撫使,761~764年(天平宝字5~8)に東海道節度使を設置した。(2)これらの諸国を結ぶ交通路も東海道と称し,「海の道」ともよばれた。畿内から各国府を順に結ぶ陸路を基本に官道が整備され,当初は相模国から上総国へは海路で渡った。駅路としては中路で各駅に10頭の駅馬がおかれる原則であり,「延喜式」では総計55駅に465頭の駅馬をおく規定であった。源頼朝による東国政権がうまれると,1194年(建久5)には大宿8人,小宿2人の人夫がおかれ,最も重要な街道となった。1601年(慶長6)徳川家康は改めて宿を設定して伝馬の常備を命じた。五街道の一つ。宿駅は品川から大津まで,江戸―京都間の126里余に53宿あり,東海道五十三次(継)といわれた。また大津からわかれて伏見・淀・枚方(ひらかた)・守口の4宿をへて大坂に至る京街道も含めた137里余という見方もある。道中の箱根・新居には関所が設置され,大井・天竜両川や桑名七里渡など難所も多いが,参勤交代の大名や参府の公家の通行など交通量は非常に多く,文化の伝播にも重要な役割をはたした。脇道は浜松から御油(ごゆ)を結ぶ姫街道,熱田(宮)から桑名を結ぶ佐屋路(さやじ),中山道垂井(たるい)に至る美濃路などがある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東海道」の意味・わかりやすい解説
東海道
とうかいどう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「東海道」の解説
東海道
とうかいどう
②江戸時代の五街道の一つ
現在の中部・関東地方の太平洋岸一帯の地域で,伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江 (とおとうみ) ・駿河・甲斐・伊豆・相模・武蔵・安房 (あわ) ・上総・下総・常陸 (ひたち) の15カ国。
鎌倉時代以来発展し,江戸時代に最も重要な交通路となった。宿場は江戸〜京都間53次。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
事典・日本の観光資源 「東海道」の解説
東海道(蒲原宿、由比宿)
「美しい日本の歩きたくなるみち500選」指定の観光名所。
出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東海道の言及
【浜通り】より
…福島県を地勢をもとに東から浜通り,中通り,会津地方の3地域に分けた場合の地域名の一つで,古くから関東から東北地方への通路である浜街道が通っており,その街道の通過する周辺地域としてこの名称が用いられる。浜海道,東(ひがし)海道,海道とも称した。現在,交通路としては国道6号線とJR常磐線が通じている。…
【駅伝制】より
…駅制が律令国家の強力な中央集権的支配のもとで急速に展開したのにくらべて,伝馬制の維持管理は国造の子孫である郡司たちの古来の実力によるところが大きかったから,国家権力を背後にした国司が郡司を圧迫し弱体化させる傾向の強かった律令時代には,比較的早くから維持管理が困難となったようで,10世紀初頭の延喜式で伝馬が置かれているのは全国で590あまりの郡のうちの4分の1にも満たなくなっていたが,駅制も律令国家と同時に衰退しはじめ,10世紀後半には飛駅の派遣もまれとなり,11世紀にはほとんど機能しなくなった。しかしそのころから発達してきた民間の商品流通は,交通の要地にあった駅の跡に宿(しゆく)を発達させ,商人や一般の旅行者が利用できるようになり,鎌倉幕府は東海道の宿に周囲の荘園から人馬を提供させて京と鎌倉の間の公用の連絡に用い,さらに江戸幕府は江戸を中心に東海道・中山道・日光道中・奥州道中・甲州道中の五街道を整備して,宿場の中継による公私の交通や飛脚(ひきやく)による公私の通信の便宜をはかった。宿駅【青木 和夫】
[中国]
中央集権国家体制の下にあった前中国においても,駅伝は古くより発達して,その網は全国にはりめぐらされていた。…
【京街道】より
…豊臣秀吉が大坂・淀・伏見に築城の後,1594年(文禄3)に淀川左岸に文禄堤を築造し,堤防上を道路として伏見・大坂間の近道としたのが起源である。江戸幕府は道路をさらに整備し,京街道に伏見・淀・枚方・守口の4宿駅を設定し,品川から大津までのいわゆる東海道五十三次のほかにその延長上の宿とみなし,道中奉行の管轄下に置いた。【乾 宏巳】。…
【五街道】より
…江戸幕府が直轄した主要な五つの陸上交通路。江戸を起点として四方に達する道で,東海道,中山道,甲州道中,日光道中,奥州道中をいう。名称は1716年(享保1)に幕府が公称を一定したが,民間では中山道を中仙道,木曾街(海)道といい,甲州道中を甲州街道ということも慣用された。…
【遠江国】より
…現在の静岡県西部,大井川以西。
【古代】
東海道に属する上国(《延喜式》)。国名は〈琵琶湖=近ッ淡海〉(近江)に対する〈浜名湖=遠ッ淡海〉(遠江)に由来するとされている。…
※「東海道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...




