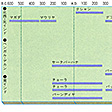日本大百科全書(ニッポニカ) 「インド史」の意味・わかりやすい解説
インド史
いんどし
インドの範囲とインド史の特徴
インドということばは、ヒンドゥーと同じ語源から出てきたことばで、西方の人々、とくにアレクサンドロス大王の軍勢がインダス川岸に到達したとき、そこに住んでいた人々をヒ(シ)ンドゥー、その土地をヒンド(インド)とよんだことに始まるとされている。したがって、インドという呼び方は外国人によるものであり、当時のインド人自身は、自分の住んでいる土地をバーラトと称した。バーラトとは『マハーバーラタ』という物語名にも残っているように、もともとは北インド、とくにガンジス川中流域をさすことばであった。
このように、インドにしろバーラトにしろ、もともとは狭い範囲の土地をさしていたが、19~20世紀になると、ともに現在のインド、パキスタン、バングラデシュ3国を含む、インド亜大陸全域をさすことばとして使われるようになった。それはイギリス植民地支配下に、インド亜大陸全体をイギリス人がインドとよぶようになり、同時に、イギリス支配に抵抗するインド人の民族運動の側からも、自らの国をバーラトと称するようになったからである。現在のインド国内ではバーラトという国名を用いている。
インドは、エジプト、メソポタミア、中国と並んで最古の文明発生地とされている。したがって、インドの歴史は長く、その文化は独自の展開を示している。しかし、19世紀以来、ヨーロッパの社会科学、人文科学においては、インドは「歴史なき」アジア社会の一典型とみなされ、太古以来、凝固したように発展しない社会であると考えられてきた。このようなインドのイメージは、19世紀、歴史の激動のなかにあったヨーロッパ人の目には、インドが相対的に変化が緩慢なようにみえたこと、さらに、インド社会の変化、発展の仕方がヨーロッパの歴史発展のあり方とは非常に様相を異にするものであったことなどによるものと考えられる。たとえば、前近代のヨーロッパ社会は、土地所有関係を基軸として理解することができるが、インド社会の発展は土地所有関係の変化イコール発展として理解することは困難である。このような西欧社会とインド社会との質的相違が、いままでインド社会(インド史)の内在的理解を困難にしてきた原因であると考えられる。
インド独立後、とくに1960年代以降、インド人によるインド史研究が多数の優れた業績を生み出すようになった。これらによってインド史発展の特徴、インド社会の固有のあり方といったことが今後ますます明らかになると期待される。
[小谷汪之]
考古時代
インド史においてもっとも古い文化は、インダス文明とよばれているものである。インダス文明は、インダス川の流域から東はデリーのすぐ西まで、南はグジャラート州のナルマダ川の河口周辺まで、東西約1600キロメートル、南北約1400キロメートルという広大な範囲に広がるもので、地域によっていくらか差があるが、だいたい紀元前2500年ごろから前1700年ごろまで栄えた。インダス文明の特徴は都市遺跡で、整然と計画された都市の内部には穀物倉庫、浴場などの公共施設があった。しかし、神殿や王宮の跡は発見されておらず、インダス文明が同時期のメソポタミアなどの文明とは異質な要素をもっていたことを示している。インダス文明の文字(インダス文字)はまだ解読されていないが、遠距離交易に用いたと考えられる封泥(ふうでい)が多く発見されている。インダス文明の中心的な遺跡はモヘンジョ・ダーロ、ハラッパー、カーリーバンガン、ロータルなどである。インダス文明は前1700年ごろ急速に衰えるが、その原因としては、アーリア人などの外来民族による破壊を重視する見解や、気候条件、地形的条件の変化を重視する見解などがあって、結論が出ていない。インダス文明を担った人々は、現在南インドに居住しているドラビダ諸族と同一系統の人々であったという見解が有力になっている。ただ、インダス文明がその後のインド史の発展とどうつながるのかという点については、よくわかっていないのが現状である。
[小谷汪之]
古代
インドにおける歴史時代の始まりは、前1000年ごろ、アーリアン(アーリア人)と称される人々が、インド北西部からパンジャーブを通り、ヒマラヤ南麓(なんろく)に沿って東に進み、ガンジス川上流域に定着したことに始まる。彼らはガンジス川の河谷の湿潤な灌木(かんぼく)地帯を切り開きながら農耕村落を形成していった。それには鉄器が大きな力となったと考えられ、また、この地域で発見される灰色彩文土器も彼らがつくったものとされている。こうして、ガンジス上流域からさらに中流域(現在のビハール州)へと農耕が拡大していくなかで、インド史上最初の国家が形成されていった。
[小谷汪之]
部族国家の誕生から統一国家へ
前6世紀ごろ、この地域には多数(仏典によれば16国)の国々が存在したが、その多くは基本的には、部族国家あるいは氏族国家の段階にあったと考えられる。しかし、これらの国々のうちでも、とくに農耕が発達し、村落形態での定住が安定的に行われるようになった経済的先進地帯の国は、部族的あるいは氏族的国家の段階を抜け出し、専制的古代国家の形成へと進んでいた。そのなかでも強大だったのは、現在のウッタル・プラデシュ州に位置したコーサラ国、ビハール州に位置したマガダ国の両国であった。これらの諸国による対立、抗争が繰り返され、数多くの国々が滅ぼされていったが、最後にマガダ国がコーサラ国を破って、ガンジス流域を統一した。このマガダ国の後を継いだナンダ朝を滅ぼして、インド全域に及ぶ最初の古代帝国をつくったのがマウリヤ朝である。
[小谷汪之]
マウリヤ朝
マウリヤ朝は前317年、チャンドラグプタによって創始されたとされるが、前300年ごろにはガンジス流域のみならず、北西インドから、マケドニアのアレクサンドロス大王の残存勢力を一掃して北インド全域に支配力を及ぼした。マウリヤ朝の第3代王がアショカ王(在位前268ころ~前232ころ)である。アショカ王の時代に至って、マウリヤ朝の勢力は南インドや東海岸部(オディシャ)にも及び、インド半島南端部を除くインド全域を支配するに至ったとされている。
しかし、この時代になっても、インド全域が定着的な農耕社会になっていたわけではなく、依然として部族的あるいは氏族的な体制をもった半独立の国々がたくさん存在し、とくに丘陵、山間部には数多くの独立的な部族が広範に存在していたことは疑いない。それゆえ、マウリヤ朝がインド全域に及ぶ大統一帝国であったといっても、それはガンジス流域、北西インド(パンジャーブからアフガニスタンにかけての地方)、ウジャイン(マルワ)を中心とする中部インドの一部、デカン地方の一部など、経済的先進地帯に対する支配と、それらの地域を結び付ける交通路の管理、支配に限られていたと考えたほうがよいであろう。マウリヤ朝では、この広大な領域を支配するために、中央直轄地域のほかは全国をいくつかの属州に分けて統治した。中央直轄地域の支配のためには、王の下に、それを補佐する会議(パリシャド)、大官(マハーマートラ)と称される上級官僚群、軍事長官(セーナーパティ)の指揮下に置かれた軍人などが存在した。各属州は太守によって治められたが、北西インドのタクシャシラー、中部インドのウジャインなど重要な属州の太守には王子が任命された。
マウリヤ時代の農村社会生活についてはよくわからないことが多いが、農民村落以外に大工(だいく)村、鍛冶屋(かじや)村といった各種の手工業者村落が存在したことがわかっている。このような村落のあり方は、のちにみられるような、一つの村落のなかに大工、鍛冶屋など1ダースばかりの職人たちがそろっているという村落形態とはかなり異質なものであったと考えられる。おそらく諸種の村落の間に分業関係が成り立っていたのであろう。農民村落における土地所有関係にもわからないことが多いが、国家と農民との間に中間的な領主的階層が存在しなかったこと、農民は自己の耕作する土地に対してある種の権利をもっていたこと、などがだいたいわかっている。
[小谷汪之]
カースト制
インド社会を特徴づけるカースト制も、古代国家の形成過程とともにだんだん形を整えてきたものと考えられる。バラモン(祭司層)、クシャトリア(政治・軍事的支配層)、バイシャ(商工農民層)、シュードラ(奴隷層)という四つの種姓に人々を区分する考え方はバルナ(色)の制度といわれるもので、いわゆるカースト制(ジャーティ制)とは本質的に別のものである。バルナ制は実際に厳格に実施された身分制度であるというよりは、むしろ特権身分としてのバラモン階層が、自己の優越性を顕示するためにつくりだしたイデオロギーとしての性格が強い。それに対してカースト制は、本質的には社会的分業体制によって位置づけられた、人々の具体的な集団帰属を示すもので、生活そのものにかかわる現実的な社会関係である。したがってカースト的な身分編成は、国家権力によって編成、維持された政治的な身分制というよりは、むしろ、分業関係に基礎を置く「社会的身分」というべきものである。カースト制的社会関係は、分業の発展、分業体制の変質、それを通して発展する階級的諸関係などの要因によってつねに変動する、きわめて流動的な体制である。各カースト集団の集団結合を支えていたのは、内婚制と共食関係であったが、各カースト内部には最小単位としての外婚集団が存在し、それらがいくつか集まって一つの内婚集団を形成していたと考えられる。このように、分業の発展、新たな階級関係の発展などを通して、新しい人間集団が形成されてきたとき、それらの人間集団が内婚集団としてのカーストを形成したこと、そして、それらのカーストが四つの種姓のいずれかと理念的に結び付けられたことが、カースト制をインド社会の特徴とみなさせる原因となったのである。しかしこのような傾向は、前近代社会においてはいずれにしろ一般的に認められることであって、インド史の特殊性を示すものということはできない。
[小谷汪之]
中世
ヒンドゥー時代
マウリヤ朝時代に先進的な文化がインド各地に伝わり、その影響下に各地方の発展が始まった。マウリヤ朝自身はアショカ王の死後急速に衰え、前2世紀中ごろには滅ぼされた。その後はマウリヤ朝のような統一国家は形成されず、インド各地にそれぞれの地方を代表するような王朝が次々と成立し、興亡を繰り返した。まず勢力を広げたのは北西インドを中心とするクシャン朝で、後2世紀前半カニシカ王の時代に全盛となった。当時デカン地方にはサータバーハナ朝(アンドラ朝)があり、南インドではチョーラ、チェーラ、パーンディヤの三つの王国が鼎立(ていりつ)していた。その後、4世紀初頭には北インドにグプタ朝が成立し、強大な勢力となった。そのころ、デカン地方にはチャールキヤ朝、南インドにはパッラバ朝があった。グプタ朝が衰えたのちの北インドは、一時ハルシャ朝が成立して統一を回復したが、すぐに崩れ、それ以後はラージプート諸王朝といわれる一連の王朝が乱立した。そのころベンガル地方にはパーラ朝が興り、ベンガル文化の基礎を築いた。
このグプタ朝以後、12世紀ごろまでのインド社会のあり方を知るうえで基本的な史料となるものは、いわゆる銅板文書(タームラ・パトラ)である。銅板文書は、主として王や在地の有力者によって寺院その他に土地が賜与されたことを証明するためにつくられたものである。通常、縦15センチメートル、横20センチメートル、厚さ1センチメートルほどの銅板に文字が彫りつけてあり、多くの場合、それを数枚束ねてある。南インドでは銅板文書はあまりみられず、それにかわって、石造寺院の壁面に土地の寄進を示す石刻文が多数刻み込まれている。これらの同時代史料から、当時、国王のもとに領主層とよぶべき人々が広範に形成されてきていたこと、バラモンが村落を賜与されて住み着き、農村社会の教化や、治安の維持に力を発揮していたことなど、多くの興味深い事実がわかる。ただ、この時代の基本的性格をどう規定すべきなのか、たとえば封建制という一般的な時代区分でくぎることができるのか、という点になると諸説に分かれて、かならずしも一致した結論を出すことができない。
[小谷汪之]
ムスリム時代
北インドがラージプート系諸王朝の分立・抗争に明け暮れていた12世紀、アフガニスタン方面から北西インドを通ってイスラム教徒(ムスリム)の諸勢力が次々とインドに侵略を始めた。アフガニスタンのゴール朝のムハンマドの武将であったクトゥブッディーン・アイバクはデリーを落とし、1206年インド最初のムスリム王朝である奴隷王朝(1206~1290)を創始した。奴隷王朝の後を継いだハルジー朝(1290~1320)のアラーウッディーン・ハルジーは、西インド(グジャラート)やデカン地方にも侵略を開始し、南インドのカーカティーヤ朝、パーンディヤ朝、ホイサラ朝などをも破った。ハルジー朝にかわったトゥグルク朝(1320~1413)のムハンマド・ビン・トゥグルクは、一時デカン北部に都を移すなど南下政策を重視し、デカンからさらに南インドに数度にわたる遠征軍を送った。これら2人の王の活動を通して、イスラムの影響が北インドから遠く南インドにまで及んでいった。トゥグルク朝のデカン遠征軍の武将たちはグルバルガ(カルナータカ州)を都としてバフマン朝(1347~1520ころ)を樹立したが、これはデカン地方最初のムスリム政権である。15世紀末バフマン朝が衰えると、デカン・ムスリム五王国とよばれる諸国が分立することになった。それに対して、デカン以南のヒンドゥー諸勢力はビジャヤナガル王国を建てて対抗したが、結局ムスリム諸王国の連合軍に敗れて衰退した。
この12世紀から16世紀初頭にかけての、いわゆる初期ムスリム時代のインド社会については、あまりよくわからないのが現状である。その原因は、この時代に関する基本的文献であるペルシア語史書には、宮廷内の勢力争いや、イスラム聖者の奇跡の話などが多く、社会のあり方、とくに農業や他の諸産業の状態などについてはほとんど言及がないことによっている。この時代には、それぞれの地方語で書かれた文献史料は宗教文献を除いてはなく、いわゆる地方の文書はほとんど存在しないため、在地の社会状態を知ることはきわめて困難である。
[小谷汪之]
ムガル帝国
北インドではデリー諸王朝ののち、1526年バーブルによってムガル朝が樹立された。その第3代皇帝アクバル以後、ジャハーンギール、シャー・ジャハーン、アウランゼーブと続く約150年間がムガル帝国の全盛時代であった。この間にムガルは北インド一帯からパンジャーブ、アフガニスタン地方のみならず、グジャラート、シンド、ベンガルなどを征服し、さらにアウランゼーブ(在位1658~1707)の時代にはデカンのムスリム諸王朝を次々と滅ぼし、遠く南インドにまで兵を送って、その版図を、半島南端部を除くほぼインド全域に拡大した。しかし、この拡大しすぎた版図の基礎は意外にもろく、すでにアウランゼーブの在位中に揺らぎだしていた。デリー北方、むしろムガル帝国の中心部の一つともいうべきパンジャーブにかけての地方では、シク教徒の活動がすでに活発になっていた。ムガル帝国はシク教主(グル)を捕らえて処刑するなどの弾圧を加えたが、その勢力を根絶することは不可能であった。また、デカン地方では、西ガーツ山脈の山中に根拠地を置くマラータの活動にも悩まされた。マラータ勢力はシバージーの指揮下に17世紀中ごろから独立運動を開始していたが、1674年シバージーは、ヒンドゥーの古式にのっとった即位の儀式を行って正式にマラータ王国の王位についた。アウランゼーブ帝は自らデカンの軍営に数十年間滞在して、マラータ勢力を追い、1680年にはシバージーの息子で第2代王サンブージーを捕らえて虐殺した。そのためマラータ勢力は一時後退し、第3代ラージャラームは南インドに逃れて抵抗を続けた。しかし、17世紀末になると勢力を盛り返し、デカンからムガル勢力を押し返し始めた。1707年マラータとの絶望的な戦いのなかに老帝アウランゼーブが死ぬと、ムガル帝国は急速に分解の様相を示し始めた。各州の太守がそれぞれになかば独立国をつくり始め、ムガル帝国はデリー周辺のわずかな地域を実効支配しうるだけになっていった。ムガル皇帝も有力な州太守などによって擁立される傀儡(かいらい)的存在と化していき、18世紀末になるとムガル宮廷の実権はマラータのシンデー家によって掌握されるようになった。このようにムガル帝国は、1720年代ぐらいからはむしろ有名無実といったほうがよいような存在だったのである。
[小谷汪之]
在地領主層の成長
アウランゼーブ帝の死を契機として、ムガル帝国はなぜこのようにもろく分解していってしまったのであろうか。それには、アウランゼーブの厳格なイスラム正統主義への反発などがあったともされるが、しかし基本的には、ムガル型の統一帝国の存続をもはや許さないような条件が在地で成熟してきていたことが最大の原因であったと考えられる。それは簡単にいえば、在地の領主的諸階層の成長であり、彼らに支えられた多数の在地権力の形成が、結局はムガル帝国の存在を許容しなくなったのである。マラータ王国の成立をもたらした原動力も、在地の領主層である郷主(デーシュムク)であり、シク王国の形成もまたシク在地領主層の活動が集約されたものである。したがって、18世紀初頭ムガル帝国が事実上分解したのちは、インド各地に地方的政権が分立・割拠するという状態が続くことになり、大統一国家の生まれる契機は存在しなかった。18世紀中ごろ以降インド最大の勢力となったマラータも、けっして中央集権的な権力機構をもつものではなく、実体はマラータ大領主たちの連合体というべきものであった。
[小谷汪之]
ムガル~マラータ時代の社会
このムガル~マラータ時代(16~18世紀)のインド社会については、かなり明らかになってきている。とくにマラータについては、彼らの言語であるマラーティー語で書かれた地方の文書がきわめて多数残されており、それらを編集、出版する努力が19世紀からインド人自身によって続けられてきたため、多くの興味深い事実を知ることができる。地方文書の代表的なものは、さまざまな問題についての裁判集会(ゴート)の記録(ゴート・マフザル)である。これらから、当時もっとも紛争の種となったのは、村長や村書記の職とそれに伴う諸権利であったことがわかる。これらの職および職得分は自由に分割して売買することができる物件となっており、その売買などに際してしばしば紛争が発生したのである。先に述べたように、マラータ勢力を支えたのは在地の郷主とよばれた豪族層であったが、この郷主の職と職得分もまた売買、相続、譲渡、分割などを行うことのできる物件となっていた。このように共同体と国家とにかかわるすべての職と職得分とが物件化し、自由に売買されるような状態にあったのである。マラータの豪族階層はこれらの諸職を購入、横領などを通して集積することによって、自己の領域的支配権を形成していった。
同様なことはムガル帝国についても明らかになってきた。ムガルにおいては、在地の豪族的階層は一般にザミーンダールと総称されていた。ザミーンダール層はザミーンダーリーとよばれた職を集積することによって形成されてきたが、ザミーンダーリーとは、ある一定の範囲の土地からの税をムガル帝国に支払う義務に伴う職、職得分のことであった。
このようにムガル~マラータ時代については、在地の領主的階層の形成過程がかなりの程度まで明らかにされてきている。これらから、ムガル~マラータ時代のインド社会は、世界史的には一般に封建制とよばれる段階にあったということができる。ただしそのことは、16~18世紀のインド社会が、いわゆる中世ヨーロッパ社会や近世日本社会とまったく同じ形態の社会であったということを意味するのではない。封建制という概念はきわめて抽象度の高い概念と考えるべきであり、各国それぞれの封建社会には固有の特色があったと考えねばならない。
[小谷汪之]
イギリスの植民地支配
インドが分裂と政治的混乱のただなかにあった18世紀、インドにとっての脅威は外からやってきた。それは、インドを植民地化しようとするイギリスの進出であった。イギリスがまず進出の足掛りとしたのはベンガル地方であった。1700年イギリスは、現在のコルカタ(カルカッタ)市のもととなった小さな漁村を獲得し、ここに城を築いて拠点とした。18世紀前半は通商を主としていたが、なかば以降はベンガル太守位をめぐる紛争にしばしば介入し、政治にまで進出していった。1757年、いわゆるプラッシーの戦いでフランスを破って、フランスをインドから追い出すことに成功したイギリスは、1764年、バクサルの戦いにベンガル太守・アウド太守・ムガル皇帝の連合軍を破り、ベンガル州の徴税行政権(ディーワーニー)をムガル帝国から奪い取った。この結果、ベンガル地方は実質的にはイギリスの植民地と化した。1799年には南インド、マイソール王国のティプー・スルタンを殺して、この地を征服し、1767年以来4回に及ぶマイソール戦争が終結した。1804~1805年には北インド各地でマラータ諸勢力と戦い、これを破って、北インド一帯に広大な領土を獲得した。1818年、数度にわたる戦争のすえ、マラータの宰相(ペーシュワー)政府が最終的にイギリスに敗れ、滅亡した。この結果、イギリスはデカン高原西部を中心とするマラータ領を獲得した。こうして1820年までにはパンジャーブのシク王国を除くインドの全域がイギリス支配下に入るか、あるいはイギリスとの間に条約を結んで従属したインド勢力(藩王国)のもとにあった。1849年、シク王国も滅ぼされ、ついにイギリスはインド植民地化を完了した。そののち、1850年代には、直系の子孫のない場合には養子相続を認めないという、いわゆる「失権の原理」により、多数のインド藩王国がとりつぶされた。なかでも1856年のアウド王国のとりつぶしは大きな影響を与え、それがいわゆる「インドの大反乱(セポイの反乱)」(1857~1859)の一つのきっかけになったとされている。
[小谷汪之]
インド社会の変質
イギリスのインド支配はインド社会に大きな混乱をもたらした。それは、イギリスが自己の理念にあわせてインド社会を支配しようとして、インド社会に内在する論理を無視する傾向が強かったからである。イギリスは地税徴収に際して、土地を排他的に所有する者を確定し、彼らから地税を徴収するという原則をたてた。それは、旧来のインド社会における土地制度、すなわち、さまざまな職得分として重層的に形成されていた土地権益の体制に一挙に大きな変更を加えるものであった。このような社会に対して、排他的、近代法的な土地所有権の観念を押し付けることは、在地の社会関係を大きく混乱させることとなった。また、旧来のインド社会では、さまざまな紛争は一般にパンチャーヤトとよばれる集会によって裁決された。それは慣習法的世界であり、下級審→上級審の序列関係もなければ、一事不再理の原則もなかった。裁決の結果を強制する力も基本的には社会慣習の拘束力であった。このような法慣行をもつ社会に対して、イギリスは、自己の誇る「近代的」法、裁判制度を導入しようとし、インド法典の編纂(へんさん)に全力をあげて取り組んだ。そのこともまた、インド社会の慣習法的関係に大きな変動を引き起こすものであった。経済の面では、イギリス支配下にインドは国際的な商業関係により強く組み入れられるようになり、旧来の村落や地域社会を単位とした経済構造に大きな変動が引き起こされた。これらの諸変動による混乱を経て、インド社会はイギリスにとって好都合なように改造されたのである。それは、一つの固有の文化の体系をもった社会が解体させられたことを意味している。
[小谷汪之]
帝国主義時代
インドの大反乱後、インドは政治的にも経済的にも一大変動期を迎えた。しかも、帝国主義時代が開幕する1870年代から、イギリス帝国の要石(かなめいし)としてのインドは、帝国主義支配を直接受ける場に転化したのであり、インドの民衆も果敢な反帝国主義運動を展開した。全インドを代表する形での政党、インド国民会議派が発足したのもこのころである。
1858年、インドの大反乱のさなか、イギリス東インド会社は解散され、インドは、インド政庁のもとでイギリス支配をじかに受けることになった。大反乱の後始末と帝国主義支配の導入とが重なっているところに、19世紀後半のインド史の特徴が集約されている。大反乱後、イギリス側はビクトリア女王の宣言(1877)にみられるように、まず藩王国の併合方針を捨て、それを温存する方針を打ち出した。その結果、植民地インドは、イギリス領インドの諸州と諸藩王国からなるモザイク状の変則的な統治形態をとることになった。この形態はインドが独立するまで継続された。一方、経済的な面では、イギリスのインド支配は、従来の商品、原料市場に加えて、資本投下市場としての性格を新たにもつための準備がなされた。資本輸出の対象は鉄道建設であり、その端緒はすでに1853年にみられたが、1870年代には建設が本格化し、世紀末には主要鉄道網が完成された。資本投下は、このほか、ジュート(黄麻(こうま))、石炭、綿工業などにも及び、イギリスによる帝国主義支配は確実に進行した。
インドの民族産業の中心である綿工業は、1854年のパールシー(インドに移住したゾロアスター教徒)による綿紡績工場の設立を口火にして、以後急速に発展した。とくにボンベイ(現、ムンバイ)に工場が集中し、これは同地方の経済的な先進性を保証する基盤になった。20世紀初めの転換期に、おりからの民族運動の高揚に乗じて、パールシー系のタタ資本は綿工業に加えて製鉄業に社運をかけ、それに成功したことはよく知られた事実である。また19世紀後半から20世紀初頭にかけて、インド資本は植民地的な条件に規制されながら、しだいに経済的な基盤を強化していったことは特筆に値する。もっとも、インド社会における資本の形成は、インド社会にブルジョア革命が遂行されたことを意味しない。インド社会は、植民地支配とそれが依拠する半封建的な諸関係を土台とする「近代」社会としての性格をもっていた。インドの民衆により実現されるべき近代社会とは、イギリス支配と半封建的な諸関係の廃絶のうえに構築されるものであった。
インドの大反乱後、ベンガル地方の中間層を代表とするグループによって、インドの世論高揚を目的とする全国的な政治組織の必要性が叫ばれ始めた。また、イギリス人の元官僚の間にも、こうした組織の結成を期待する声が出始めた。1885年12月、商工都市ボンベイでインド国民会議派(以下、会議派と略す)の創立大会が開かれた。これにはベンガル人政治家のスレーンドラナート・バネルジーや、ボンベイ州出身のパールシー出の政治家ダーダーバーイー・ナオロジーも参加し、新党の目的にはイギリス・インド間の友好関係の促進が盛り込まれていた。同時に大会決議は、行政制度の民主的な改革とか、軍事費の削減と輸入綿花関税の再実施を求めていた点が注目される。もちろん、この新党は正面切って帝国主義批判を掲げたわけではなく、いわば穏健な路線を出すにとどまっていたが、大会決議には、インドの有識者による帝国主義批判の初期形態を確かめることができる。ともかく、南インドを含めた広大なインドの諸州から諸代表が一堂に会すること自体、インド政治に新しい章を開くものであった。
1905年から1908年にかけて、会議派の指導のもとにベンガル分割反対運動が展開された。1905年、時のインド総督カーゾンは、ベンガル州を東西に分割すると発表した。その理由は、ベンガル州の面積が行政的にみて大きすぎるためとされ、ムスリム多数地域としての東ベンガル州と、ヒンドゥー多数地域のベンガル州に分割されることになった。もともと、行政論は口実であって、インドの先進地帯の一つであるベンガル地方のベンガル民族主義運動にヒンドゥーとムスリムの対立を持ち込み、それを弱体化するところに真のねらいがあった。イギリス側は、すでに1871年に帝国主義分割の第一弾として、バローチ民族をアフガニスタンとイランとイギリス領インドに3分割するゴールドスミット・ラインを設定し、1893年にはアフガニスタンとイギリス領インドとの間にデュアランド・ラインを導入し、アフガン(パシュトゥンまたはパターン)民族を分断している。この分割当時は、インド内部に反対世論はいっさいなかったが、さすがにベンガル分割の強行は、鋭いインド側世論の反発と抵抗を招いた。インド内外の状況は一変していた。1905年末に開かれた会議派大会はイギリス製品のボイコットを決定し、翌1906年12月の会議派のカルカッタ大会ではナオロジー議長のもとで、英貨ボイコット、スワデーシー(国産品愛用)、スワラージ(独立)と民族教育の達成が決定された。英貨ボイコットとスワデーシーは同じメダルの両面をなし、それを支える民族教育が提起され、いずれもスワラージという目的を実現するための手段とされた。この反対運動の主要な指導者は、パンジャーブ出身のラーラー・ラージパト・ラーイ、ベンガル出身のビピン・チャンドラ・パールBipin Chandra Pal(1858―1932)、ボンベイ州のバール・ガンガーダル・ティラクの3人であった。彼らは革命的民主主義者と評価されている。
この運動は、しかし、指導理念を異にする穏健派の妨害と、イギリス側の弾圧により短命に終わった。ティラクはビルマ(現、ミャンマー)に追放され、ラージパト・ラーイはアメリカに逃れた。イギリス側は、1909年にモーリー‐ミントー改革を採択し、ムスリム中間層に取り入る「改革」を試みた。1906年にインド・ムスリム連盟がイギリス側の肝入りで発足していたのである。1911年ベンガル分割令は撤回され、両ベンガル州は1州に戻された。同時に首府はカルカッタ(現、コルカタ)からデリーに移された。
[中村平治]
両大戦間期
第一次世界大戦と第二次世界大戦を含むほぼ30年間の時期を、インドでは「ガンディー段階のインド民族運動期」とよんでいる。その当否はともかく、この段階は、インドの民衆が自国の独立を果たすために多岐にわたる政治闘争を提起した時期であった。他面、インド・ブルジョアジーもその活動範囲を拡大し、第二次世界大戦期にはボンベイ・プランの提起にみられるように、独立インドの経済開発構想を打ち出すまでに発展していた。また、この過程はイギリス支配の総体としての後退期に対応し、第二次世界大戦期には、インドは従来の債務国から債権国へと転化する重大な局面を迎えた。
第一次世界大戦とそれに続く1920年代は、インドの反英民族独立運動が高揚した時代である。世界大戦に植民地インドが動員されるという形は第一次世界大戦と第二次世界大戦の二度にわたって強行されるが、イギリス本国のために大量の人員や資源が利用された結果、インドは多大の犠牲を払うことを余儀なくされた。その払った犠牲の代償は文字どおり少ないものであり、インドの政治的、経済的な危機は急速に深まっていった。
すでに第一次世界大戦期には、イギリス側は戦後に自治の実現を約束する前提で、からくもインドの戦争支持を取り付けたが、モンタギュー‐チェルムズフォード改革(1919)はインド民衆の期待を満たすものではけっしてなかった。インド側は、アメリカ大統領ウィルソンの自決原則も空手形でしかない現実を鋭く見抜いていた。会議派とマハトマ・ガンディーにより指導された反帝民族運動としての第一次非暴力的抵抗(サティヤーグラハ)運動は、1919年に開始された。イギリス支配に対するインド側の多様な抵抗形態も、突き詰めれば、会議派指導者の思惑を超えて、反帝・反封建の2方向を示し、都市小ブルジョアジー、労働者と農民を幅広く巻き込んでいった。この民族闘争は、イギリス対インドという次元では被抑圧民族の階級闘争という性格をもっていた。1922年には運動は停止されるが、ガンディーを指導者とする会議派は、労働者、農民の組織化と政治化には否定的な態度をとっていた。実は民族運動の進行するなかで、1920年には全インド労働組合会議が結成され、個別的ではあるが北インドの各地に農民組合が誕生していた。同じ年の1920年に当時のソ連・タシケントでインド共産党の創立大会が開かれ、労農党という方式でインド各地で活動を広げていった。
1930年の初め、会議派指導の反帝民族運動はふたたび高揚し、1934年まで続行された。世界恐慌の波は植民地インドを直撃し、都市生活者や農民を不況と生活苦の渦中に投げ入れた。会議派はラホールで開かれた1929年大会でジャワーハルラール・ネルー議長のもとに完全独立を決議し、1930年1月26日を独立要求日に設定し、広範な運動を提起した。不幸なことに、この時期のインドの労働運動はイギリス当局の弾圧により勢力をそがれ、コミンテルンの方針を意識してか、全インド労農党(1928創立)もこの反帝民族運動に協力しなかった。インド農民を結集する全インド農民組合の創立も、1936年にやっと実現された。イギリス側は反撃の機会をうかがっており、サイモン委員会の派遣と数次の円卓会議の開催を通じて、インド統治法(1935)の実現に成功し、会議派に依拠するインドの中間層を統治機構内部に組み入れることができた。会議派の二面性、つまりイギリスに対する抵抗と妥協が、はしなくもこの段階で浮上する結果となった。また、この統治法の導入は、M・A・ジンナーに率いられるインド・ムスリム連盟を政治的に認知する機会をもたらした。連盟はパンジャーブとベンガルの両州で第一党となった。新統治法による限定的州自治の導入は、そのまま第二次世界大戦後のインド・パキスタン分離独立の予行演習の場所づくりにもなったといえよう。
第二次世界大戦の開始とともにインドは参戦国になった。戦争への対応は会議派の場合、徹底した非協力方針を貫いていた。独ソ戦の開始(1941)とともに戦争は帝国主義戦争から反ファシスト人民戦争に変化した。こうした国際的な状況変動のなかで、会議派はインドの即時独立こそ世界の進歩的な陣営を強めるとの態度をとっていた。一方、ムスリム連盟はイギリスに協力する方針を採択し、1942年8月、会議派がインド退去要求闘争を提起して弾圧され、非合法化されるや、パキスタン独立要求(1940)を大々的に宣伝する絶好の機会を得た。一方、反ファシスト人民戦争の支持と対英協力方針を出したインド共産党は、1942年7月に合法化された。共産党は、会議派のインド退去要求闘争を敵前自殺ときめつけ、会議派の民族主義「偏向」を批判していた。これに対して会議派は、共産党をイギリス帝国主義の代理人であると反論した。
戦争期におけるインド政治は、見方によれば、会議派、ムスリム連盟、共産党の3党が互いに衝突しあうなかで、当面の置かれた状況に共同して対処する場を破壊したところに、その特徴がある。しかも、インドの将来構想についても、ムスリム連盟はムスリム国家パキスタンを掲げ、共産党は多民族統一を基礎とする連邦国家構想を1942年段階で提起していたが、会議派はヒンドゥー、ムスリム統一を基礎とする連邦制を掲げていて、連盟構想のもつ具体性と、共産党の提起した多民族問題の歴史性に対処しきれない限界を示していた。事態は独立後の国家構想をめぐる争いにまで進んでいた。
[中村平治]
独立後の国家建設
1945年8月の第二次世界大戦の終結から1947年のインド・パキスタンの分離独立までの期間は、一般に権力の移譲段階とよばれている。独立に向けての背景としては、第二次世界大戦の間の宗主国イギリスへの人的および物的な動員により、植民地インドが従来の債務国から債権国の地位に上昇したことや、戦後のインド国民軍将校裁判への抗議、ボンベイ(現、ムンバイ)のインド海軍の反乱、労働者・農民運動の展開など、下からの民衆運動があげられる。
実をいうとイギリスは当初、統一インドの実現には無関心を装い、本音ではインド国民会議派とインド・ムスリム連盟の両党だけを権力移譲の対象に設定していた。当然、イギリスはムスリム連盟指導者M・A・ジンナーの主張するパキスタン構想に対して「黙殺」という名の承認を与えていた。1947年6月、最終的にイギリス側の提案、つまり印パ分離構想と諸藩王国の自由選択案が示され、会議派と連盟はこれを受諾する。パキスタンはインドを挟む飛び地国家としてインドより1日早く独立した。また全体でインド亜大陸面積の5分の2を占め、560を数える藩王国群はほとんどが新生インドに併合された。その後、半世紀を超えるインドの歴史過程は以下の3段階に区分して理解することができる。
[中村平治]
第1段階
1947年8月15日、独立インドの首都デリーにあるムガル朝遺跡レッド・フォートでは、独立インドの象徴たる三色旗――ヒンドゥー教と他の宗教集団との団結を示す――が掲げられた。前日深夜、その初代首相となるJ・ネルーは「運命との出会い」と題する演説を試み、インドが新しい時代を迎える意義を強調した。
確かに独立は、統一インドが完全には実現していないこと、印パ間の難民の移動、カシミール問題、ハイデラバードやトラバンコール両藩王国の分立への動き、さらにはマハトマ・ガンディー暗殺といった負の側面ももっていた。しかし独立によりイギリス植民地支配に終止符が打たれ、司法制度の継承、警察・軍隊や官僚の継続、運輸・港湾・通信の掌握、インド文官職(ICS:Indian Civil Service)のインド行政職(IAS:Indian Administrative Service)への転換など、インドによる国家建設の基本条件が用意された。そして1950年1月にインド憲法が施行され、インドは独立時の自治領から共和国へ発展し、主権在民の理念のもとで、独立国家として連邦議会と諸州議会からなる連邦制国家が誕生した。
インドでは第1回総選挙(1951~1952)が小選挙区制ながら成人選挙という形で21歳(1989年以降は18歳)以上の男女が参加して行われた。こうしてインド国民は連邦議会議員と各州議会議員を選出する権利を行使して、主権者たる事実を内外に披瀝(ひれき)した。選挙を通じて国民は連邦、各州ともにネルーの率いる国民会議派を支持し、与党としての国民会議派の統治体制がここに確立された。さらに1956年11月には多言語国家インドの現実を反映する言語別州再編成がいくつかの例外を伴いながらも実行され、ケララ州(ドラビダ系のマラヤーラム語)など新言語州が多く誕生した。この背景には一方で下からの連綿とした民衆の要求運動があり、他方で会議派指導層内部でも五か年計画を効果的に進めるうえで州再編成の緊急性が痛感されたという事情があった。
経済計画の分野ではインドは「社会主義型社会」の建設を定式化して、工業化と土地改革を提起した。前者は連邦政府の課題であり、後者は州政府の課題とするところであった。1951年以後、五か年計画が導入され、政情で棚上げされる時期もあったが、今日まで継続されてきた。少なくとも第1段階では重化学工業の建設と拡大が重点課題とされ、すでに植民地期に起源をもつインド系の紡績業(19世紀なかば)やインド系の製鉄業(20世紀初め)の存在が、新政府による原子力発電や重化学工業の強化を推進する前提をなしていた。さらに独立時の会議派が全体として民主主義勢力により指導されていた事情から、藩王国や伝統的な地主制が封建勢力を代弁する批判対象として設定されていた。それに対しイギリス側は核物質を産出するケララ地方にある一藩王国の独立の動きに食指を動かし、統一インド構想に泥を塗るような姿勢を残していた。またネルーを含む会議派指導者は、地主階級(一般に高カースト)の存在が、インド農村社会の発展を阻んでいるとかねて認識していた。
インドは外交面でも著しい活動をみせた。その基本方針は大国と安易な軍事同盟を結ばず、アジア・アフリカの新興国家どうしで相互に主権の尊重や事態の平和的解決を目ざす非同盟主義政策を進める点にあった。そのため独立前後にはこうした方向と重なる一連の国際会議がインドで開かれ、中華人民共和国の承認も同国成立直後に実行され、平和五原則(1954)が中印間で承認されている。またアジア・アフリカ会議のインドネシアでの開催(1955)や非同盟諸国会議のベオグラードでの開催(1960)など、ネルーの果たした役割は決定的であった。それは冷戦時代のなかで歴史的な選択肢であった。
この政治体制はネルー型民主主義体制(ネルービアン・デモクラシー)とよばれているが、一般的にはインド型民主主義体制と呼称すべきである。何よりもネルーと会議派政権が、分離独立を不可避的な前提としながら、藩王国問題にみられるように国家建設での離反要因や対抗勢力を徹底的に批判し、排除した点に特徴があった。つまり民主主義とそれを奉ずる国家への国民の帰属意識が強く要請され、国民もそれに対応した段階であった。
確かにインドでは多くの面で改革や発展がみられたが、その内外でいくつかの問題が押し寄せた。とりわけ友好的なインドと中国間で国境戦争が発生した結果、両国の関係は大きく後退した。双方の国際政治観の相違も一つの対立要因であった。さらに一連の土地改革が実施されたが、多くの州、とくに北部インドで地主制度は存続した。1964年、ネルーは文字どおり波乱に満ちた生涯の幕を閉じた。
[中村平治]
第2段階
インド型民主主義の第2段階は1960年代後半、ネルーの娘インディラ・ガンディーの首相就任実現と与党国民会議派内部の権力闘争により、その幕が切って落とされた。この段階の特徴は民主主義の制度や理念がインディラ主導の強権主義や大衆迎合主義との間で激しい切り結びを進行させるところにあった。
首相インディラの信任投票ともいわれた第4回総選挙(1967)で、彼女に率いられる会議派は過半数を制し、からくも連邦政府の座に着いた。このときの州議会選挙では非会議派や反会議派の諸政党による州政権の樹立という新事態が生まれた。州政治の場合、南インドのタミル・ナド州では反バラモン主義を掲げるドラビダ進歩連盟が会議派を破り、西ベンガル州ではインド共産党(マルクス主義)がこれまた会議派による20年にわたる長期統治を打破して、ジョティ・バスJyoti Basu(1914―2010)州首相政権が誕生した。第1段階での会議派による連邦と各州の一元的な統治体制は崩壊し、これが第2段階のインド政治の特徴となった。
1969年、会議派はインディラ派と反インディラ派に分裂し、以後首相インディラの独断専行が進んだ。1970年代には食料自給を目的にして「緑の革命」と称する農業改革が推進され、とりわけパンジャーブ州がその実験場となり、経済政策では部分的にせよ自由化が導入された。しかし、汚職、インフレ、生活不安が慢性化し、その強権政治をもって危機突破を図るインディラによって、1975年から1977年まで非常事態宣言が実施された。そこでは人権の苛酷(かこく)な弾圧のみならず言論や集会が制限され、連邦政府は各州議会に強制断種を強要し、1000万人以上の犠牲者が農村一帯に生まれた。それは人口べらしが貧困の絶滅につながるという短慮に基づいていた。その強権主義政治は1971年の隣国パキスタンの東部地方たるバングラデシュの独立戦争への関与と支援の面でも発揮された。その結果インドの南アジアにおける地位は不動のものとなった。また1974年5月、インディラは国威をかけてインド西部のラージャスターン州で初の核実験を試み、全世界の国々から批判を浴びた。この実験はインドに非同盟運動の旗手から単なる担い手への役割後退を促した。
第6回総選挙(1977)ではインディラの率いる会議派は敗北し、1969年にインディラと袂(たもと)を分かった反インディラ派の会議派政治家M・デサイを首相とする連立内閣が発足した。しかし寄せ集め内閣の弱点が露呈され、同政府は思いきった施策方針を打ち出せず、第7回総選挙(1980)を通じて、インディラの奇跡的な政界復帰を許すことになった。復帰後のインディラは強い指導性を買われて再登場したと自認していた。それは幾分かの真実を含んでいたが、非常事態期に壊滅した草の根の会議派党組織はもはや再建されなかった。中央集権化した会議派は南インドに若干の拠点をもつにすぎず、伝統的な活動の場である北インド諸州ではその威信と威力は大きく後退していた。
1970年代末からパンジャーブ州では地域勢力としてアカーリー・ダル(シク不滅党)が急成長して、パンジャーブ州の自治強化を訴え、1980年代になると一部は無差別テロを組織して、アムリッツァルのシクの総本山を拠点とした。そのスローガンはシク国家のカーリスターン(清浄な国)の樹立にあった。こうした事態の背景には独立以来同州が、農業州として固定されてきた事情があった。1984年、インディラ政権はシク総本山への武力行使を断行し、双方に多大の犠牲者を出した。事態は沈静したかにみえたが、同年、インディラは首相官邸でシク警護兵により射殺された。
インディラの死後、その長男ラジブ・ガンディーが第8回総選挙で当選し、新首相になった。素人政治家の登場という点に人々の期待が集まった。しかしラジブ政治はその母親の方式、つまり取り巻き集団の形成や上意下達方式の重視というスタイルを踏襲した。しかもラジブ首相がインド人民党(BJP)にすり寄る姿勢をみせるに及んで、会議派の威信は後退した。1989年、第9回総選挙が迫るや、同首相は人民党の宿願であるアヨーディヤーでのラーマ寺院建立の定礎式を承認した。これは目前の総選挙でのヒンドゥー票の獲得を狙(ねら)いとしていた。また武器購入をめぐる「汚職疑惑」がラジブ首相自身の足元を揺さぶることになる。ラジブ首相期で特筆すべきことは、1985年に南アジア7か国からなる協力機構として南アジア地域協力連合(SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation、本部はカトマンズ)が発足し、インドもその構成国となったことである。
[中村平治]
第3段階
第3段階は1980年代末・1990年代初めから今日に至る時期である。それは民主主義勢力がヒンドゥー原理主義や大衆迎合主義の勢力としのぎを削る、切迫した段階である。第9回総選挙の結果、会議派は下野して、V・P・シンVishwanath Pratap Singh(1931―2008)を首相とする反会議派連立内閣が成立した。新政権は低カースト集団の社会的な向上など革新的な政策を打ち出したが、一部世論の反発も招いた。同政権は人民党による反憲法的な示威行動を取締りの対象とした。その結果、人民党の閣外協力は撤回され、同党は辞任した。1991年、第10回総選挙が行われた。そこではタミル過激派のテロによってもたらされたラジブの不慮の死という事件を挟み、会議派のナラシマ・ラオP. V. Narasimha Rao(1921―2004)政権が辛勝した。同内閣は1991年に自由化政策を公表する一方で、人民党の傍若無人の行動には寛容な態度で臨んだ。1992年末、同政権は人民党によるアヨーディヤーのバーブリー・マスジッド(イスラム寺院)破壊行為を他人事のように傍観していた。
インド人民党はインド大衆連盟(1950年創立)を1980年に改称したもので、その前身は1925年に発足した民族奉仕団である。民族奉仕団は植民地期では社会運動組織であり、その組織は今日なお政党としての人民党と密接な関係をもつ。同党の目的はインドにおけるヒンドゥー教国家の建設にあり、共産主義とイスラムを敵視し、インド憲法の一つの理念である政教分離主義を公然と否定している。その思想上の系譜はヨーロッパのファシズムを代表するヒトラーに求められ、同党の日常活動にはファシズムへ傾斜するマイノリティへの暴力を含む反社会的な行動が目だっている。
連邦下院の5年任期を経過したラオ内閣は第11回総選挙(1996)で無残にも敗北した。そこでは第一党に躍進した人民党が組閣を強行したがそれも過半数に足らず辞任し、民主派のデーベ・ゴウダDeve Gowda(1933― )が首相として指導する統一戦線内閣が成立した。同政府はおおむねラオ内閣の方針を継承したが、政局の不安定性は否定しようもなく、会議派からの揺さぶりが続けられ、I・K・グジラールInder Kumar Gujral(1919―2012)への首相バトンタッチがなされる。やがて会議派幹部の策動が功を奏し、グジラール内閣も辞任した。
第12回総選挙(1998)の結果、人民党は第一党の地位を占めたが、例によって過半数(定員545)に達しなかったため、地域政党をかき集め、A・B・バジパイ(バージペーイ)内閣が発足した。この党と連携するおもな地域政党はパンジャーブ州のアカーリー・ダル、マハラシュトラ州のシブ・セーナー(シバージー軍)やタミル・ナド州の全インド・アンナ・ドラビダ進歩連盟である。
新政権は経済の自由化に関する限り、既定の政府の路線を継承しながら、対米関係でも友好方針をとったが、こと中華人民共和国に対しては冷たい関係の提起にとどまった。同時に同党はヒンドゥー原理主義に基づく大国主義を誇示する機会をねらっていたが、それは1998年5月に実践された。人民党は1974年以来の核実験をかのラージャスターン州で実行した。これはただちに隣国パキスタンでの初の核実験を強行する口火ともなり、核廃絶にむかう世界から非難を浴びた。
1999年4月、全インド・アンナ・ドラビダ進歩連盟が人民党に離反した結果、連立内閣は連邦議会下院で1票差で不信任の対象とされ、同内閣は辞職し、1999年9月には6億5000万人の有権者による第13回総選挙が行われた。しかし、これによって定数545議席のうちインド人民党は182議席を獲得し、バジパイ率いる与党連合が過半数の296議席を占めることができたため、人民党主導のバジパイ連立政権は続投することとなった。
2004年5月の第14回総選挙では、バジパイ率いるインド人民党は敗北、国民会議派が与党第一党となった。国民会議派は、同派の総裁であるソニア・ガンディーSonia Gandhi(1946― 、暗殺されたラジブ・ガンディー元首相の妻、イタリア出身)を議員団長に選出し首相就任が確実視されたが、辞退。マンモハン・シンが首相に就任した。インド初のシク教徒の首相であり、過去にラオ内閣時代の財務相など経済分野の要職を多く務めた。経済改革、貧困対策、パキスタンとの対話路線の継続を表明して二期を務めたが、2014年5月の総選挙後に退任。選挙に勝利したインド人民党のナレンドラ・モディNarendra Modi(1950― )が首相に就任した。
独立半世紀以上を経過したインドは、いま大きな転機にたたされている。現段階の最大の特徴は、先行する第2段階で確認された州レベルの政権党が、イデオロギー的に左右のいずれであるかを問わず、国政レベルで不可欠の役割を果たすに至った点にある。大まかにいって、インドの民衆(農村人口が総人口の80%を占めている)の前には二つに一つの道が示されている。東部インドの西ベンガル州では、1977年以来、インド共産党指導の左翼戦線州政府が一貫して政権を維持し、土地改革による貧農や農業労働者主導の一大変革が農村地帯で進んでいる。同州での食料生産高は1970年代末からの20年間で倍増した。地主の私兵集団と低カースト・先住民を主体とする農業労働者との間で「血で血を洗う殺害事件」が日常化している北インドの諸州とは対照的に、西ベンガル州における政治変動は明日のインドの選択肢を先取りするものである。
[中村平治]
『山本達郎編『インド史』(1960・山川出版社)』▽『D・コーサンビー著、山崎利男訳『インド古代史』(1966・岩波書店)』▽『ターパル、スピィア著、辛島昇他訳『インド史』全3冊(1970~1975・みすず書房)』▽『中村平治著『南アジア現代史Ⅰ インド』(1977・山川出版社)』▽『中村平治著『現代インド政治史研究』(1981・東京大学出版会)』▽『中村平治著『インド史への招待』(1997・吉川弘文館)』▽『近藤治編『インド世界』(1984・世界社)』