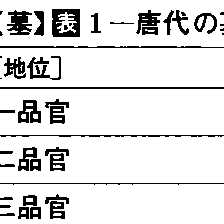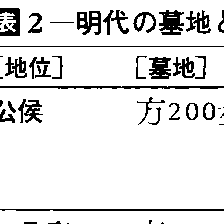精選版 日本国語大辞典 「墓」の意味・読み・例文・類語
はか【墓】
- 〘 名詞 〙 遺体や遺骨を葬ってある所。つか。おくつき。墳墓。また、その上に立てた墓碑(ぼひ)の類もいう。墓標。墓石。
- [初出の実例]「田道が墓(ハカ)を掘る」(出典:日本書紀(720)仁徳五五年(前田本訓))
ぼ【墓】
- 〘 名詞 〙
- ① 人を葬る所。はか。〔十巻本和名抄(934頃)〕 〔書経‐武成〕
- ② 皇室典範によって定められた、天皇・皇后・太皇太后・皇太后以外の皇族を葬る所の呼称。陵(りょう)に対していう。〔皇室典範(1947)〕
改訂新版 世界大百科事典 「墓」の意味・わかりやすい解説
墓 (はか)
遺骸を埋葬する場所,またその施設を墓という。形態的には土を高く盛った墳墓(冢(ちよう),塚(つか))に対して墓は地下に埋葬し墳丘をもたないものを指すが,一般に墓という場合,墳墓はもちろん,死体を遺棄した場所や,崖などに穴をうがって埋葬したもの,また墓石などの石碑類も意味することが多い。旧石器時代以来,人類はさまざまな方法で死者を葬ってきたが,先史時代における墓の形態や葬法と,東アジアを中心とする巨大な墳丘をもった墓については,〈墳墓〉の項目を参照されたい。
日本
中国や朝鮮の文化の影響を受けた持統天皇の陵戸(りようこ)(陵戸・守戸)の設置,藤原仲麻呂の儒学の重視,荷前(のさき)制度のはじまりなどから,墳墓祭祀が浸透しはじめると,墳側に廬(いおり)を何年間も設けて死者に仕える者が現れてきた。これに応じて墳墓の地の樹木を伐採してはならぬなどの埋葬地の整備がはじまった。もっとも,すでに721年(養老5)には墳墓の上に刻字の碑を立てよとの詔が出されている。そして,《続日本後紀》の承和7年(840)条には,淳和天皇の〈骨を砕き粉となし,山中に散ずべし〉という詔に対して,中納言藤原吉野が山陵は宗廟のようなものだから墓をつくるべきであるといって反対する言葉が出てくる。しかし,まだ個々の墳墓にまで関心は広く及んでいない。一般庶民の埋葬地は前代より河川敷や海浜などに設けられ,遺体は遺棄されていた。《続日本後紀》の承和9年(842)条には京都の鴨河原にある髑髏(どくろ)5500余頭を焼いたとあることや,《三代実録》の貞観13年(871)に出羽国飽海郡の山上(鳥海山)が爆発したのは冢墓(ちようぼ)が山から流れ出る山水を汚したからであるという報告のあることが,このことを物語っている。また律令政府は平安京内にある墳墓を京域の外へ出した。《類聚国史》には延暦11年(792)山城国紀伊郡深草山の西面が京域に近いという理由で葬埋することが禁止されたとあり,続いて延暦16年(797)には山城国愛宕郡・葛野郡の人は家側に葬ってはならぬとされた。そして,代わって《三代実録》の貞観13年(871)条に葛野郡の五条荒木西里,六条久受原里,紀伊郡十条下石原外里,十一条下佐比里,十二条上佐比里などの河原が百姓の葬送放牧の地と定められた。《梧庵漫記》には阿弥陀が峰,鳥戸野,船岡山,西院,竹田の5ヵ所が京都の庶民の葬送地となったとされている。平安京に移り住んだ貴族たちのなかには,京域のすぐ近くに墳墓を設けた者もあった。《兵範記》には久寿2年(1155)に村上天皇の系譜をひく源氏の墓が北白河の寂楽寺の北山に21ヵ所もあると記されている。
貴族の墳墓の上には卒塔(都)婆(そとば)が立てられた。その早い例は《文徳実録》の嘉祥3年(850)4月18日条にみえる仁明天皇の深草陵である。この卒都婆は作善を意味するものであって,死者の魂をまつるために立てられたものではなかった。しかし,平安中期になると,まつることを目的に石卒都婆を建立するものが出た。比叡山の中興の祖,良源である。天禄3年(972)のことである。これ以後,盛んとなってきた浄土教と舎利信仰によって,人骨に人格を認める動きが出た。〈空也誄(るい)〉によると,空也は鳥辺野に葬送された遺骸を集めては油を注いで荼毘(だび)にふし,〈南無阿弥陀仏〉と供養し阿弥陀如来に結縁させたとある。同じ浄土教信者である慶滋保胤(よししげのやすたね)は《今昔物語集》に〈卒堵婆ノ前ニ至テ,卒堵婆ニ向テ手ヲ合セテ,額ヲ土ニ付テ,度々礼拝シテ〉という行為をしたと紹介されている。このように遺体を尊重する風は,貴族の墳墓に対する考え方に影響を与えた。藤原道長は北家の墳墓の地である宇治の木幡の側近くに死者の冥福を祈って墓寺である浄妙寺を建立した。しかしまだ,貴族たちは埋葬地に卒都婆を立ててももうでることはなく,葬送の地には鬼がいる,などといって近寄らなかった。平安時代の末期になると,ようやく木幡に墓守が置かれ死者のそれぞれの墳墓の地が明らかとなってきた。11世紀末から12世紀になると,火葬骨の一時的な安置所である殯殿(もがりどの)にもうでる風習が発生した。そして堀河天皇の墓所の上に阿弥陀如来の立つのが夢に見られるまでになった。ここに埋葬した上に阿弥陀堂を建立する風習が生まれてくる。現存する代表的な事例が平泉の中尊寺金色堂である。寿永1年(1182)の皇嘉門院の場合は,阿弥陀如来の代りに石卒都婆が安置された。もちろん,依然として高く土盛をしただけの塚もあった。大阪府羽曳野市の通法寺にある源頼義・義家の墳墓にそれを見ることができる。また,古代の殯宮が玉殿(たまどの),玉屋(霊屋(たまや))に継承され,しかも墳墓の地にそのまま放置されるような事例もある。
平安末期ころから埋葬地に石製や木製の卒都婆を立てることが一般的となった。五輪塔や宝篋印塔(ほうきよういんとう)がよく使われた。さらに火葬骨や爪髪などを木製の五輪塔や竹の簡にこめて兜率天(とそつてん)の浄土であると信じられた高野山の奥の院へ納める風習も発生した。これは金色堂や奈良の元興寺極楽坊,伯耆大山の阿弥陀堂などの地方の霊山にも見られるようになった。古い髪爪塔として有名なのは京都高山寺の明恵上人の宝篋印塔である。室町時代になると,後花園天皇の陵にこの宝篋印塔が立てられた。こうした死者のために卒都婆を立てることは,鎌倉時代の武士にも継承された。さらに関東では阿弥陀三尊の種子(しゆじ)を刻む板碑が埋葬地の上などに立てられた。建碑は造塔(作善)の一種であり,これによって,埋葬地にもうでるという風習が一般化したわけではなく,一周忌が過ぎれば捨ててかえりみないのが普通であった。室町時代になって,盂蘭盆(うらぼん)会が習俗として定着するにともない,墳墓にもうでることが起こった。《満済准后日記》の応永20年(1413)7月14日の記事がその早い例である。それでも応永22年7月15日の条には〈新古雑乱ス。子細ヲ相尋処ニ面々所意各別也〉とあるので,墓地の整理は見られないようである。明応8年(1499)になってようやく,《大乗院寺社雑事記》に〈極楽坊庭聖〉の存在が伝えられており,整理と管理がはじまったらしい。この遺体・遺骨を大事にする風習は高野聖によってさらに発展させられた。人々はすすめられるまま,一石五輪塔の地輪の部分に供養すべき人の戒名(かいみよう)などを刻み,高野山の奥の院へ奉納した。これが江戸時代になると,大名たちによる奥の院への石塔建立となった。やがて,身近な霊場や身近な寺院,村の寺へも五輪塔,木製卒都婆などが寄進されるようになった。両墓制のはじまりである。しかし,石碑にかかる費用や石工の問題もあって,まだまだ限られた人,限られた地域の人たちのものであった。一般庶民の遺棄墓制はそのまま継承されていった。今でも,岐阜県,滋賀県の真宗地帯で広く見られる風習である。骨は早く自然に返すこと,仏壇をまつればよいというのである。ただ,浄土宗や日蓮宗,曹洞宗の集落や家でも埋葬地やそれ以外のところへ石碑を立てない例があり,石碑を立てない風習は真宗に限ることはない。
江戸時代になると,大和(奈良県),河内(大阪府),和泉(大阪府)などの埋葬地へ浄土宗系の僧侶が住み,墓地を管理する墓寺をつくっていった。しかし,東北地方では,近畿地方一般と同じく,埋葬した上に石碑類を立てる風習はなかったらしい。古川古松軒が《東遊雑記》で,現在の秋田県三種町の旧山本町豊岡のこととして〈人死して墓というものなく,野に葬りて土をかきよせて置くのみといへり〉と報告しているからである。結局,石碑が全国的に見られるようになるのは明治になってからということになる。これも江戸時代には夫婦単位の建碑が多かったものが,明治以降は個人墓が出現し,現在では〈先祖代々の墓〉とするのが多くなった。さらに,それまで同族ごとに設けられていた墓地,とくに集落や飲料水の近くに設けられていた墓地は非衛生ということで,村から遠く離れたところに共同墓地が設けられるようになった。現在では火葬骨を石碑の下に納骨する風習の広がりもあって,埋墓にも石碑を建立するようになってきた。当然,今までもうでることのなかった両墓制の埋墓へももうでる風が生まれてきた。埋葬地に石碑を建立する風習は個人意識の目覚めと石工の活躍などによって,全国に広まりつつある。さらに石碑と墓地を要求する動きは寺院の墓地造成を招き,ついには墓のアパートまで生まれるまでにいたった。それでもなお,三十三回忌などが過ぎるとトイアゲ(弔い上げ)といってウレツキトウバを立ててせっかくの石碑を倒したり捨てたりするところもあるのである。
→葬制 →墓碑・墓標
執筆者:田中 久夫
中国
中国の墓の構造は,棺と槨と,それらを納める墓室から成っている。先秦時代までは,地下に墓壙を掘り,その中に木槨をこしらえて棺を入れるという竪穴墓が主流を占めていたが,やがて地下に掘った横穴を墓穴とする洞窟墓が生まれ,墓道がつくられるようになった(木槨墓)。この変化は,墓を単なる死体の保存場所と考えることから,住居と墓を並称して陽宅陰宅と呼ぶことに明らかなように,生前と同様の生活を営む場へと墓の意義を転じる死生観の変化を意味した。そこで,副葬品も生前用いたと同じ武器,道具,楽器,食料品,明器(めいき)など,数量が多くなり,当然墓室も広くなり,壁画で飾られた墓も出てきた。洞窟墓の系統に,四川省では崖面を利用し,崖に横穴式の墓を掘る崖墓というものもある。内部は洞窟墓と同じように墓道がつくられ,大規模なものは多くの墓室を備えている。墓壙の中には,後漢以後になると,死者の世系,名字,爵里,行治,卒葬日月などを金石に刻んだ墓誌,あるいは銘をともなった墓誌銘が置かれるようになり,また,近年発掘された馬王堆漢墓のおびただしい竹簡からも知られるように,書物を埋める場合もあった。それは単に宝物というばかりでなく,死者の固い信条を示すものでもあり,みずから副葬の書を遺言していく人物もあった。南斉の張融が左手に《孝経》と《老子》,右手に《法華経》を持たせるよう遺令したのはその典型である。
さて,地上の墳(つちもり)が出現したのは,戦国末期ころであり,秦の始皇陵をはじめ,漢の諸陵において巨大を極めた(帝王陵)。また,墓上に木を植えることも,墳と同じように後世の産物である。これは,盗掘者の手から守るためにまわりの森林と同化し墓をカムフラージュするためと,木への信仰に起因するものと考えられる。木は梓(しん),松(しよう),柏(はく)がとくに好まれたが,これらは古代から棺材としても選ばれた木々である。それらが霊のすみかである墓に植えられたのは,死骸の腐敗を防ぎ,その復活を促し,魂をつねにその霊のもとにつなぎとめる働きをもっていると信じられたからである。昔の比翼も及ばないといわれた若夫婦があいついで亡くなり,これを哀れんだ家族が同じ墓に埋葬したところ,墓中から梓の木が生い立ち,一つの根と2本の幹をもち,1本の木のように抱き合っていたという。このような話がたびたび人の口に上るのも,木と霊魂との結びつきの信仰の強さを表明しているといえる。
秦・漢以後には,参道の両側や墓前に石柱,石人,石獣などが並べられるようになった(石人石獣)。これは墓側に寝殿や廟が出現した時代と一致する。後漢になると,墓前には墓碑,墓碣(ぼけつ)あるいは時代によって神道碑,神道碣と呼ばれる,墓誌と同様死者の事跡を記した石碑が立てられるようになった。石碑には,上部に丸い穴があいているが,これに縄をつけて棺を下ろした古代のなごりといわれている。碑と碣の違いは身分の上下による(碑碣)。
墓地は,《周礼(しゆらい)》の説によれば,貴族から庶民に至るまで宗族ごとに公共の墓地が用意され,そこに埋葬することになっている。しかし戦国末からは,社会の変化とともに家族単位の墓地に分散するようになった。漢代以後,原野などを開拓して墓地をつくる場合,その地が土地神との売買契約によって正統な手続を踏んで収得されたものであることを証明するために,鉛,木,玉石などに姓氏,年月,墓域の境界を明記した買地券が,明器として埋められた。国家に対して特別な働きのあった者は,天子から墓地を与えられて陪冢がつくられることもあったが,唐末の一時期,任地で卒するとそこで葬った場合を除いて,一般には本籍地の墓地に葬られた。墓地の位置は,城郭の外,古代では居住地の東または北に置いたようである。個々の墓地の選定に関しては,《孝経》喪親章に〈其の宅兆を卜(ぼく)して之を安措(あんそ)する〉と言明されているように,慎重に占われた。そして,後漢の袁安の有名な話に代表されるように,やがて墓地の位置と子孫の繁栄を結びつける風水説が生まれ,墓地に対する人々の関心をいっそう強くした。風水の言葉からもわかるように蔵風得水する場所が好まれ,墓地としては前に水が流れ後ろに山を控えた地形が理想とされた。
《礼記》に〈物の大きさは,しばしば地位と身分のしるしである。棺と槨の厚さ,そして墓丘,墓墳の大きさは地位と身分のしるしである〉というように,墓地の大きさ,墳の高さをはじめとし,墓地の内外に設けられたあらゆる設備は,死者の地位と富によって規模と数量が異なり,経書をはじめ歴代の礼制に詳しく規定されている。唐代のある時期を例にとると表1のようになる。三品以上は,石人石獣6個,五品以上は4個,五品以上はそのほかに亀形の碑台で竜紋のある石碑高さ9尺,七品以上は飾りのない石碑高さ4尺とされた。明代では,やはり石碑台座の装飾,高さなども詳しく規定されている(表2)。
→葬制
執筆者:西脇 常記
朝鮮
ここでは主に李朝以降の墓について述べる。山所,墓所,陰宅と呼び,山につくるのが普通である。墓の位置や方角は風水説(三国時代に中国から伝わるが,李朝時代には一般民衆にまで浸透)に従って青竜(向かって右の丘陵),白虎(向かって左の丘陵),内明堂(前面の平地)をはじめ,主山(後方の山型の地形),案山(墓の前方の小高い地形)などをみて地官(風水師)が決める。土葬をするので1人につき1基が通例であるが,夫婦を一つの墓に納めることもある。墓は山神に簡単な祭祀をしてから掘る。この作業を山役という。壙中を掘って底部を松の葉で掃き清め,この中に棺を納める。地方によっては屍だけを出して納めることもある。棺を銘旌(めいせい)(死者の姓名や官位を記した弔旗で,葬列の先頭に立てる)でおおい,その上に板または割り竹を横に並べておく。喪主がひとすくい土を入れた後に壙を埋め,土をつきかためて封墳を築いて芝をはる。墓の前には石の祭床や碑石が立てられ,大きなものになると望柱石や石像などで飾る。墓は土まんじゅうなので定期的な手入れが必要である。修理の時期は春の寒食(3月)のころで,これを改沙草という。もう1回は秋夕(陰暦8月15日)の準備としての伐草である。墓の風水上の位置が子孫の盛衰に大きく影響を与えると考えられているため,墓地の選定には細心の注意が払われるとともに,その位置をめぐって争いの起こることもしばしばである。子孫に不幸の続くときにはより良い場所を求めて移葬することもある。同じ山に一族の墓がある場合には,子孫の墓を先代の墓よりも上につくることはできないから,山腹の上から下に向かってあたかも族譜上の系譜関係が具現されるような観を呈する。
毎年一定の日(陰暦10月または3月)には墓所で時祭(時享祭)と呼ばれる墓祭が,5世代以上前の祖先に対して行われる。この祭祀は各個の家をはなれて,当該祖先の子孫全員の責任において,普通は門中の行事として行われ,門中の人々が墓地に集まって始祖から順に一つ一つの墓をまわって祭祀をする。盛大な時祭はその門中の威勢を示すものとされ,時祭のシーズンには山が白衣姿でおおわれる。これらの祭祀は儒式で行われるが,これと並行して朝鮮南部の全羅道や慶尚道の島嶼(とうしよ)部では,草墳をつくり,屍が骨になるのを待って埋葬する複葬の習俗もある。
執筆者:嶋 陸奥彦
ヨーロッパ
ヨーロッパの人々が墓を死者がその中で生き続ける住居と考えていたことは初期の葬制からも明らかにうかがえる。古代ギリシアのミュケナイの四角い石の墓室や通路つきの丸天井の墓室は住居を模したものである。棺を用いる場合はその形までが屋根状のふたをもった家をかたどっている。北欧のバイキング独特の舟葬も,船を家としたバイキングらしい発想に由来する。これらの墓の中で死者がなんらかの形で生き続けるという信仰から,死者が墓の中や死者の国あるいはそこへの旅路で必要なものを添えるのが副葬品の意味である。飲食物はもとより日用品,ときには所有物として配偶者,召使,動物までもいっしょに埋葬された。死者が骸骨や幽霊となって墓から立ち現れたり,死体に魂がとどまり種々の働きをする話は古代ギリシア,ローマ以来多く伝わっている。
第2に墓は礼拝の場所として祖先崇拝に結びついていた。墓に近親者を葬ることは生存者の義務であった。神聖な場所として墓に死者のための供物が供えられる。中世に墓地はアジール(庇護権)の場であり,今日のドイツの法律でもみだりに墓を破壊したり汚す者は3ヵ年間までの禁錮刑になる。神聖な場所として死者を守るために,中世北欧ではルーン文字やトールの槌やハーケンクロイツ(鉤十字)を墓に添えた。キリスト教時代に入ると聖水をふりかけ,墓の十字架を立て,中に十字架,ロザリオ,聖者像,聖書,祈禱書などを入れた。墓に供える花は死者に安らぎを与える。墓の場所にも意味がある。ゲルマン人はよく墓所を見晴しの良い道路沿いや海や湖の近くに選んだ。死後も引き続き残した家族のなりわいを見守りたいという希望を遺言する例もある。氏族の結びつきの強いところは一般に祖先崇拝も強い。逆に生前悪事を多く働き死後もいっそう恐れられた悪人は遠い山あいの僻地や岬に葬られた。
第3に墓は前兆をあらわす場所と考えられる。例えば,墓の中でする音は,はやっている悪疫が今後も長く続く前兆とされた。また,クリスマスのころ墓が雪でおおわれないと,産婦が多く死ぬといわれた。
第4に墓は魔法の力をもつとされる。危険な働きを示して畏怖の対象となる反面,ふしぎな効験を示して崇拝の対象ともなった。前者の例をあげると,墓の上をとび越える者は成長がとまる。墓の上で倒れたり,墓を越えて下ったりする者はまもなく死ぬ。とくに妊婦が墓の中をのぞいたり,まわりや上を歩いたりすると胎児が死ぬ。ある者をゆっくり殺そうとする場合にはその髪の毛やつばや血を墓の死者に与える。後者の効験の例として,ある特定の墓の水は病に効く。歯痛を治すには夜12時に黙って口にいっぱい含んだ穀物や塩を墓にあけた穴の中に吐くといい。リウマチの痛みどめには墓の上を歩く。熱のある子は日没時に墓の上をころがす。墓の露でこするといぼがとれる。新しい墓に尿を注ぐと不能が治り,シャツを入れると痙攣がおさまるなどの効能が,現代まで俗間では信じられてきた。
執筆者:谷口 幸男
イスラム
イスラムでは遺体(ジナーザ)は埋葬し,けっして火葬にされない。顔面がメッカに向くように横たえられる。通常その上に平らな墓石が置かれ,時に頭部に石碑が立てられる。ただしワッハーブ派は墓石を置かず,土を盛るだけにする。イスラム初期では墓参りは禁じられたが,歴史的に聖廟(マザール)崇拝が発展した。死後に聖者(ワリー)として崇拝されるものは,強い呪力(バラカ)をもつと信じられ,墓石に呪力が宿るので,聖墓に直接触れて呪力を獲得しようとする聖廟儀礼が発達し,呪力によって病いや災いを免れることを望む人々を集めた。また祈禱(ドゥアー)を捧げて安産・幸せを祈る婦人も多い。参詣者(ザーイル)が多くなると,墓石の上に丸天井のある建築(クッバ,グンバド)が建てられ,周辺に墓地が形成された。聖者の近くに埋葬されることで,死後,聖者の仲介が求められるからである。有名な聖廟には,遠隔地から参詣(ジヤーラjiyāra)が行われ,とくに年1度の聖廟の例祭(マウリド,インドではウルス)が催され,この期間に市が立ちにぎわう。下エジプトではタンターの聖者アフマド・アルバダウィーの聖廟が,インドではアジュメールの聖廟が有名である。聖者崇拝の対象は,スンナ派世界ではスーフィー聖者で,その他,学者,殉教者,異常な能力の持主などがある。シーア派の十二イマーム派では,各イマーム廟,イマームザーデ廟の崇拝が盛んである。イマーム廟は,イラク南部(ナジャフ,カルバラー,カージマイン),メディナにあり,イラン国内ではイマーム・レザー廟がマシュハドにある。首都テヘラン近くのコムには,イマーム・レザーの妹ファーティマの廟があり,参詣者が多い。これら聖廟への異教徒の入場は門前で厳重に禁止される。イマームザーデ廟はイマームの子孫の墓で,イラン全土にいたる所に分布している。ワッハーブ派は,これら聖廟を,非イスラム的慣行(ビドア)とみて反対する。
→葬制 →墓地
執筆者:加賀谷 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「墓」の意味・わかりやすい解説
墓
はか
遺体や遺骨を葬ってある場所。またその上に建てた石碑類だけをいうこともある。墓は遺体や遺骨を処理する場所であるとともに、死者のために死後の祭りをするための場所や設備である。ただし火葬における遺体処理場は、火葬場とか焼き場とかいって墓とは区別しており、寺院などに設けた位牌(いはい)堂や霊廟(れいびょう)、家庭で祀(まつ)る仏壇、納骨堂や供養塔の類は、死後の祭りのためのものであるが一般に墓とはよばれていない。墓はその国、その民族の生命観、死後観など文化全体のありようを反映するもので、しかも時代によって変遷し、階層や宗教によって違い、外来文化の影響によって複雑に変化することがある。
[井之口章次]
日本の墓
遺体を処理するという意味の葬(はふ)るという語は、放(はふ)る(投げ捨てる)と同根だといわれている。語源説だけでは年代が明らかでなく、歴史時代以前でも土をかけるとか、目につかない場所に移すとかの配慮はあったろうと思われるが、霊魂信仰では遺体や遺骨を重視せず、霊魂だけを不滅のものとして尊重したから、遺体処理の場所に死者に関する記念物を設けることはなかった。そこへ大陸から古墳文化が伝来し、一部上流の支配者たちが巨大な古墳を築造するようになると、死者の霊ばかりでなく遺体や記念物をも尊重する気風が強くなってきた。
火葬は仏教とともに伝来したとされているが、仏教はまた個人の尊重を教え、それが遺骨の重視につながったことが考えられる。仏教では、死者の霊が十万億土の彼岸(ひがん)に去って、ふたたび現世(げんぜ)に立ち戻ることがないとしながらも、死者の霊を供養するための供養塔を設けることとした。現在一般にみられる石碑墓は、死者を埋葬した上に目印としてのせる小石と、この供養塔との合体したものである。
埋葬した上に石碑を建てて祀る単墓制に対して、両墓制といわれるものがある。1人の死者に関して、死体を埋(うず)める埋(う)め墓と、石碑を建てて祀る詣(まい)り墓とを二重にもつ墓制で、近畿地方にもっとも濃密に分布し、本州各地に点在する。遺体はけがれたものとして葬り、その中の霊だけを先祖として祀る。庶民のために石碑を建てる習俗は、近畿の先進地帯でも中世末からのことであり、広く普及したのは近世の中ごろとみてよいから、石碑と対応する両墓制発生の時期はほぼ推定することができる。両墓制の地帯では、埋め墓を村境の外に設けたり、離れ島や山かげにつくる所があり、また両墓を隣接して設ける例もある。両墓制は土葬を基本としているので、近年火葬の普及とともに減少の傾向をたどっている。
各地の墓地をみると、いまは集団墓地が多くなったが、もとは家ごとに墓地をもち、あるいは分家が本家のそばに墓を設けて同族墓を形成しているものが多かった。各戸がかってにあちこちに墓地を設け、すべてを免租地に指定することは共同の利益に反するので、明治時代以後しばしば墓地の共同化が進められた。自家の宅地内に墓を設ける屋敷墓もあった。大都市では条例で土葬は禁止されており、もちろん衛生上も住宅に近接して土葬することは好ましくない。沖縄や奄美(あまみ)の島々には曝葬(ばくそう)(棺を地上に放置する)や洞窟(どうくつ)葬が行われ、また葬後十数年ののち洗骨(せんこつ)する風習も点在する。沖縄本島で亀甲(きっこう)墓とよばれる巨大な門中(もんちゅう)(同族)墓は洞窟葬と中国式の墓との結合したものであろう。生前に自分の墓をつくることは、聖徳太子が自ら墓所を築いたことなどが知られており、仏教では逆修(ぎゃくしゅ)とよんで一部に流行した。逆修でも夫婦(めおと)墓でも、生きている者の法名(ほうみょう)には朱を入れておく。行き倒れや、祀りをしてくれる子孫のない人の墓は無縁墓とよび、寄せ墓をして整理したり、一括して三界万霊塔を建てておく。小児の墓は、生まれ変わることを期待して一般に正式な墓を設けず、埋めた上に石地蔵をのせたりした。
近世の中ごろから庶民も石碑を建てることが流行し、石碑を刻む技術も発達した。石工(いしく)のうちの彫刻工の仕事で、しだいに堅い石材を使うようになって堅物細工とよばれている。石碑の形は供養塔から発展したので、初期には層塔、宝塔、宝篋印塔(ほうきょういんとう)、五輪塔などが多く、卵塔(らんとう)形、仏像形、卒塔婆(そとば)形からしだいに角石形に統一されてきた。世間には墓相のよしあしなどをいう者もあるが、これにはなんの根拠もない。石碑を建てる時期は、3年・7年・13年目などの年忌のおりが多いが、家々の事情によって一定しない。また、個人墓、夫婦墓、先祖代々の墓などがある。
大都市に人口が集中し土地利用が高度化すると、都市計画の一環としての墓地規制が必要になり、経営には知事の許可を必要とするなど法的にも規制が定められている。景観のうえからは公園墓地、土地の高度利用のうえからは墓地団地や納骨堂など立体化が図られ、石碑についても個性的なものが多くなった。別に愛玩(あいがん)動物の墓(納骨堂)もある。
[井之口章次]
世界の墓
墓は、それぞれの社会の葬制や他界観と深くかかわっている。しかしそれ以外にも、その社会の自然環境や生業形態から、埋葬される人間の死亡時の年齢や性別、社会的地位や身分まで、墓やその習俗に影響する要因は多様である。そのため、墓にかかわる形態や習俗には、世界各地で顕著な多様性がみられる。
墓という観念を伴った死体処理の最古のものは、ヨーロッパの旧石器時代中期にみられる。フランスのムスティエ洞窟では、伸展葬や屈葬が行われ、副葬品も添えられていた。同じくフランスのラ・フェラシー遺跡では、成人男女と小児計四体の人骨が発見され、その周囲に石器や動物骨などの副葬品も置かれており、人為的に埋葬された跡が明らかである。この時期の人類がある程度の漠然とした墓の観念や他界観をもっていたことが、そこからうかがわれる。
旧石器時代後期に入ると、埋葬法も副葬品も複雑化していく。赤土を含んだ土地に遺体を埋葬したり、遺体に赤土が塗られたり、また遺体から頭蓋骨(とうがいこつ)を切り離し別に埋葬するなど一種の頭蓋骨崇拝も存在したようである。さらに遺体の手足に石をのせたり、遺体を石で保護するなど墓に石が使用され始めた。これは、新石器時代のヨーロッパにおいて巨石文化として独自の形態をとるようになる。いわゆるドルメン、ストーン・サークルなどの巨石を用いた墓がその例である。
しかし墓の変遷をみるうえで大きな転換点となるのは、農耕社会への移行に伴う定住化の段階であろう。新石器時代のエジプトではすでに共同墓地が造営されていた。定住化によって人類は現在みられるような恒久的な墓を獲得したと思われる。さらに王朝の発達によって、支配者層の巨大墳墓が出現するようになるのもこの段階である。エジプトのピラミッド、中国の王墓、日本の天皇陵などがその例である。これら豪壮な王墓は、その巨大さ、精巧さ、華麗な副葬品や内部装飾から、強力な王権や高度な技術文明の存在をうかがわせるものである。またこれらの王墓が遺体や墓そのものの長期の保存を目的として造営されたことも新たな特徴の一つである。
今日の墓の形態やその習俗は、文明社会から伝統社会あるいは未開社会とよばれる地域に至るまで多種多様である。一般に、遺体を地中に埋めて土を盛った塚や、埋葬した場所に墓標を設ける形式は、仏教、キリスト教、イスラム教などの大宗教に特徴的である。だが伝統社会や未開社会では、墓の形態はきわめて多様である。台や木の上に死体を置く台上葬や樹葬とよばれる葬法は、北アジアや中央アジアをはじめ、インドネシア東部、メラネシア、オーストラリア、アメリカなど各地にみられるが、これも墓の一種とみなせるかもしれない。また、遺体を家屋の内部に葬る形態は、アフリカ、インドネシア、南米のアマゾン地域に点在し、さらにその発展形態ともいわれる墓の上に小屋を建てる習俗も、同地域をはじめ、オーストラリア、北アジア、アメリカ、東南アジアなどに広く分布している。洞窟葬の一種である壁龕(へきがん)墓の形態は、アフリカ、オーストラリアの各地に分布している。
しかしながら、死体処理に際してなんらかの儀礼が行われることが人類一般に普遍的ともいえるのに対して、墓はかならずしも死体処理と直結しているわけではない。チベット仏教やインドのパールシー教徒の間で行われている鳥葬や、メラネシア、ポリネシアで行われている舟葬は、厳密な意味での墓をもたない。火葬ののち遺骨を神聖な川に流すヒンドゥー教徒の場合も同様である。以上は死体放棄ともいえるものであるが、いわゆる伝統社会や未開社会においては、一般にわれわれが想起する墓地や墓標をもたない地域も多く、死者が葬られるある区域が漠然とした墓の観念につながっている場合もある。
墓がどこにつくられるかは、その社会の他界観や世界観と密接に関係してくる。一般に樹葬や台上葬は、天上や太陽といった上方他界観と関連し、死者の魂があの世に行きやすいようにという意味をもつといわれる。中国や韓国にみられる「風水」信仰は、墓地と家屋の方向によって幸・不幸が左右されるとする信仰である。よい方角に墓をつくれば、死者は感謝し、その子孫に幸運を授けるが、悪い方角だと怒って不幸をもたらすと考えられている。日本の墓相もこれに類似する信仰である。インドネシアのバリ島では一般に「山側」が神聖な方向、「海側」が不浄な方向とされている。そのため、バリの村落では、埋葬中の死者の霊を祀(まつ)る寺院は「海側」に位置しており、「山側」にある古い祖先や村の始祖を祀る寺院と対置している。また中国のように墓標の配列様式が社会組織を反映する場合もある。
[白川琢磨]
『井之口章次著『日本の葬式』(1977・筑摩書房)』▽『大林太良著『葬制の起源』(1965・角川書店)』▽『森浩一編『墓地』(1975・社会思想社)』
普及版 字通 「墓」の読み・字形・画数・意味
墓
常用漢字 13画
(旧字)
14画
[字訓] はか・おくつき
[説文解字]

[字形] 形声
声符は
 (ぼ)。〔説文〕十三下に「丘なり」とあり、丘墓の意。金文の図象に、亞(亜)字形中に
(ぼ)。〔説文〕十三下に「丘なり」とあり、丘墓の意。金文の図象に、亞(亜)字形中に ・犬を加えるものがあり、亞は玄室の形。犬は埋蠱(まいこ)を防ぐ犬牲、
・犬を加えるものがあり、亞は玄室の形。犬は埋蠱(まいこ)を防ぐ犬牲、 は暮で、幽暗の意であろう。墓は古くは地下に作り、墳丘は後起の制。中山王墓には、その墓の塋域を示す図がある。
は暮で、幽暗の意であろう。墓は古くは地下に作り、墳丘は後起の制。中山王墓には、その墓の塋域を示す図がある。[訓義]
1. はか、おくつき。
2. 墓域、塋域。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕
 ツカ・ムハフ・ハカ 〔字鏡集〕
ツカ・ムハフ・ハカ 〔字鏡集〕 ムハフ・ハカ・クサ
ムハフ・ハカ・クサ[語系]
 ・
・ ・
・ (暮)・
(暮)・ makは同声。幽暗寂
makは同声。幽暗寂 の意をもつ一系の語である。
の意をもつ一系の語である。[熟語]
墓域▶・墓塋▶・墓下▶・墓穴▶・墓碣▶・墓闕▶・墓壙▶・墓祭▶・墓誌▶・墓志▶・墓室▶・墓守▶・墓樹▶・墓処▶・墓所▶・墓隧▶・墓前▶・墓側▶・墓地▶・墓田▶・墓碑▶・墓標▶・墓表▶・墓木▶・墓銘▶・墓門▶・墓陵▶・墓
 ▶・墓廬▶
▶・墓廬▶[下接語]
塋墓・謁墓・丘墓・墟墓・古墓・修墓・省墓・旌墓・先墓・掃墓・兆墓・冢墓・展墓・破墓・拝墓・表墓・墳墓・封墓・陵墓・廬墓
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「墓」の意味・わかりやすい解説
墓【はか】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の墓の言及
【葬制】より
…これは,死体は一時的に土葬・風葬などの処理を受け,その後肉体軟部の腐敗の完成を待ってあらためて骨部を保存するやり方である。複葬は死体の処理が時間的にながくかかることによって単純葬と区別されるが,その内実は死体の破壊と保存とを一連の儀礼的処理過程のなかで組み合わせることにあると言ってよい(再葬墓)。 死体の処理から進んで,葬制全体の意味要素を分析するときに直面するのは,死と死者にかかわる儀礼としてすべての葬制が含みもつ二価背反性である。…
【宗廟】より
…これが宋代になると,西を尊位として西から東へ横1列に室を並べてゆく制度に変わったのみならず,祧廟(祧された祖先のための独立の廟)が宗廟の西に建てられている。 ところで,廟と墓とは本来別のものである。前者は死者の霊魂を迎える場所であり,後者は死者を送る場所であって,礼制の上でも宗廟の祭祀は〈吉礼〉に,葬送の儀礼は〈凶礼〉に判然と分類されている。…
【墳墓】より
…〈墳〉は土を高く盛った墓を指し,冢(ちよう)とも呼ばれる。日本ではその俗字,塚(つか)を使うことが多い。…
【墓地】より
…死人を埋葬し墓を建てる場所。墓場(はかば),墓所(ぼしよ∥はかどころ∥はかしよ),墓原(はかわら),霊園ともいう。…
【陵墓】より
…君主の墳墓をいう。
【中国】
文献では《史記》趙世家,粛侯15年(前335)の条に〈寿陵を起こす〉とあるのが初めてで,戦国中期,国君が生前にみずからの墓をつくり,それを〈陵〉と称したことを記す。…
【両墓制】より
…遺体の埋葬地と,霊魂の祭祀対象としての墓石の,二つの墓を地所を別にしてもつ墓制のこと。埋葬地を埋墓(うめばか)といい,イケバカ,ステバカ,サンマイなどともいう。…
※「墓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

 〈ボ〉死体を葬る所。はか。「
〈ボ〉死体を葬る所。はか。「 〈はか〉「
〈はか〉「