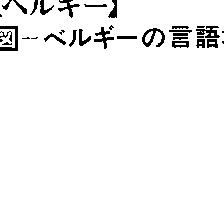改訂新版 世界大百科事典 「ベルギー」の意味・わかりやすい解説
ベルギー
Belgium
基本情報
正式名称=ベルギー王国Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Kingdom of Belgium
面積=3万0528km2
人口(2010)=1088万人
首都=ブリュッセルBruxelles(日本との時差=-8時間)
主要言語=フラマン語(オランダ語),ワロン語(フランス語)
通貨=ベルギー・フランBelgian franc(1999年1月よりユーロEuro)
ヨーロッパ北西部にある立憲君主国。北はオランダ,東はドイツ,南東はルクセンブルク,南はフランスと境を接し,西は北海に面して65.5kmの海岸線を形づくりイギリスに対する。面積は日本の九州の約7割。ヨーロッパではオランダと並ぶ高い人口密度(324人/km2。1989)を保つ。現在9州よりなる。国名は,ローマの征服以前この地方に住んでいたケルト系住民ベルガエ族Belgaeに由来し,中世・近世を通じて,この名はネーデルラント全体を表すラテン語名として用いられてきたが,18世紀末のブラバント革命以来,現在のベルギーの地域を指すようになった。国旗(黒黄赤の縦割の三色旗)は,同じくこの時初めて制定されたもの。
ベルギーは小国ながらも,経済的,文化的に最も発達した国の一つで,その歴史を通してヨーロッパの経済,政治,文化のうえで大きな役割を果たしてきた。他方,この国はゲルマン・ラテン両民族の接点にあり,また西ヨーロッパのほぼ中軸とでもいうべき位置にある。このことがベルギーの経済・文化の発達を大きく促進したのはいうまでもないが,歴史上,まさにこの要衝の位置のゆえに繰り返し列強の争奪の的となって戦禍に苦しめられたり,外国支配下に置かれてきた。そのため,この国の誕生(独立)は1830年と比較的新しく,現在の領域自身もこうした歴史的経過の中でしだいに形づくられたものにほかならない。
自然,地誌
ベルギーの地形は全体として平坦であるが,国のほぼ中央を東西に貫くサンブル=ムーズ川の流域を境に,北部のフランドルやケンペンKempenの低地と,中部の丘陵地,南部のアルデンヌ山地に分けることができる。北部は,スヘルデ川(およびその支流のレイエLeie川,デンデルDender川,ネーテNete川,リューペルRupel川)の流域で標高100m以下の低地が広がる。土質は河岸に粘土の沖積層がみられるほかは,オランダ南部から続く洪積層の砂質で,一部に砂質・粘土,砂・黄土が見られる。海岸はオランダと同様砂丘が連なって内陸の低地を保護している。海岸の内側は海面以下の干拓地で,オランダの場合ほど大規模ではないにしても肥沃な牧場をなしている。中部は,ムーズ川の北(エスベーHaysbaye)が標高100mの丘陵地,南(コンドローCondroz)が100~200mの石炭紀層で,長い間ベルギー産業の中心地であった。ここは石灰質,片岩質の肥沃な土壌に恵まれている。その南がアルデンヌ山地でドイツのアイフェル丘陵から続く標高200m以上の高原のところどころに500m台の山がそびえ(最高は,リエージュ南東のボトランジュBotrange山で694m),ほとんどが美しい森林に覆われ,その間をムーズ川の支流の急流が台地を刻んでいるので,夏の行楽地として名高い。この高原を南に下ると,ベルギー領ロレーヌの丘陵にぶつかる。
気候は,高緯度にあるにもかかわらず,メキシコ湾流の影響で沿岸部は比較的温暖で,降水量もそれほど多くはない。しかし,アルデンヌ山地は全国平均気温より4℃低く,冬には降雪も多い。冬には北風が吹くが,全体としては偏西風が優越している。
住民,言語,宗教
ベルギーは,ゲルマン系のフラマン人Flamand(フランデレン人)とラテン化したケルト系のワロン人Wallonの二つの民族からなる複合民族国家であるが,スイスやカナダのような連邦制を採用していない。もともと,現在のベルギーの地域はラテン化したケルト人の居住地であったが,ローマ帝国末期から10世紀までの間に北部や東部からゲルマン人が移住し,西フランドル州ムースクロンMouscronからリエージュ州ラネーLanayeまでほぼ東西に延びる言語境界線は,それ以来ほとんど変わることなく続いている。
北のフラマン人は,オランダ人と同じく低地フランク人で,低地ドイツ語の一種であるフラマン語(フランデレン語。公式にはオランダ語)を用いている。このフラマン語とオランダ語は語彙(ごい)や文法はほぼ同じで,正書法も統一されているが,一部の用語や訛(なまり)に違いが認められる。ワロン語wallonはフランス語の方言の一種であったが,教育を受けた階層は標準フランス語を話すようになり,今日ではほぼフランス語に同化されている。両者の人口比は,さまざまの政治的対立がからむため,1960年の調査が流産に終わり,その後正確な調査は行われていないが,フラマン語とフランス語(ワロン語)をそれぞれ公用語とする地域の人口は,全人口比57%,32%である。なお,首都ブリュッセルは,言語境界線の北側にありながらフランス語が優越し,両言語併用地域に指定されており,人口の約85%がフランス語を常用している。したがって,両言語の人口比は,ほぼ6対4と,フラマン系が数において勝り,人口増加率(1960年代)もフラマン側7.3%,ワロン側2.6%と大きな差がみられる。なお,ドイツと国境を接する東部地帯(オイペンEupen,ザンクト・フィートSt.Vithなど)は,ベルサイユ条約でドイツから割譲された地域で,約6万人(全人口比0.6%)がドイツ語を常用している。ベルギー憲法の制定(1831)以来,両言語は対等の資格を認められていたものの,大国フランスと共通し文化的にも広く用いられていたフランス語は,ワロン系のみならずフラマン人の上流階級の言語となり,国政,経済,文化の面で事実上唯一の公用語としての地位を占めてきた。その不合理な状態の改善は,19世紀末以来80年にもわたるフラマン人の運動の成果と,フランス語の国際的地位の低下の影響によるもので,1963年の言語法により,フラマン,フランス,ドイツ語の3地域で,それぞれの言語が唯一の官庁・教育言語に指定され(境界地域で少数派の権利を保護),ブリュッセルはフラマン,フランス両言語共用地域となった。その結果,フラマン地域では,フランス語の街路表示,看板などが姿を消し,企業内での伝達もフラマン語の使用が義務づけられている。そして,議会ではいずれの言語も用いることができ,閣僚は双方同数と定められている。また,軍隊はそれぞれの言語別に編成され,高級官僚や高級将校は,両言語を完全に話せることが任用条件とされている。
宗教では,16世紀,八十年戦争(オランダ独立戦争)期にカルバン派や再洗礼派,ルター派などプロテスタントが優位に立ったが,その後再びカトリック化された。現在,人口の90%以上がローマ・カトリックで,八つの司教区に分かれ,ブリュッセル大司教が全体を統括している。1830年の独立以来,信教の自由は保障されているが,カトリック教会があらゆる点でベルギーの大勢力であることには変りはなく,教育のみならず,農民,中小企業者,労働組合,政党などに大きな影響力を及ぼしている。この点,ベルギーは高度の工業社会でありながら,カトリック教会と国家との関連で,他の国にみられない独自の問題をはらんでいるといってよい。
政治
憲法,政治行政制度
独立直後の1831年に制定された立憲君主制の憲法により国民の基本的人権と主権在民が規定され,議会制民主主義と三権分立の原則が確立された。元首は国王でザクセン・コーブルク家に継承され,1990年から女子の王位継承が認められた。第2次大戦後の危機的時代からベルギーの民族的・社会的対立のなかで統合の象徴として大きな役割を果たしたボードゥアン1世(バウデウェイン1世,1953年即位)が1993年に死去した後を承け,第6代のアルベルト(アルベール)2世が即位した。ベルギーは,長年の民族対立を解決するため,1988年に始まって93年5月までかかった憲法改正で,ついに連邦国家に移行し,国制は大きく変わった。すでに1974年から,文化・教育・医療に関する事項は,それぞれ評議会と大臣を有するオランダ語,フランス語,ドイツ語の三つの言語=文化〈共同体〉の所管となったが,さらにこの憲法改正によって,フランドル,ワロン,〈首都ブリュッセル〉の3〈地域〉が創設されて,独自の議会と政府を組織し固有の財源と連邦政府からの補助金を運用して経済政策,環境,エネルギー,一部の国際関係など重要事項を決定できることになった。この3地域のうち〈首都ブリュッセル地域〉は,オランダ語とフランス語の2言語併用地域とされている。また,フランドル地域はブリュッセルのオランダ語住民代表を参加させ,オランダ語共同体と合体している。またドイツ語地域はワロン地域に含まれるが,独自の共同体を認められている。ベルギーは,このような複合的な分権化の方式で,言語とその使用地域の錯綜した問題を解決しようと試みている。その結果,中央政府および議会は,はっきり連邦政府=議会として位置付けられ,その権限も連邦財政,国防,社会保障,司法,外交などに限定され,首相を除く14名の閣僚は,オランダ,フランスの両言語使用者同数とされている。連邦議会は二院制で上下両院の議決を必要とするが,上院は一部の分野を除き,立法の提案は行わない。下院(代議院)は,18歳以上の有権者の直接普通選挙(比例代表制)によって選出された150名の議員(任期4年)から構成される。上院(元老院)議員71名のうち25名がオランダ語選挙人団,15人がフランス語選挙人団から,またオランダ語,フランス語,ドイツ語の各共同体評議会から10名,10名,1名が選出される。さらにこれら議員がフランドル人6名,フランス人4名の議員を追加指名する。政党は,伝統的に全国的な三大政党(カトリック系のキリスト教国民党,自由進歩党,社会党)を中心としてきたが,1960年代からフランドルとワロンの民族対立のあおりでそれぞれが二分され,両方の地域=民族政党や右翼政党が得票の3割を占めるため,連立内閣はつねに不安定となったが,それでも,1992年以降,キリスト教国民党(オランダ語系)のデハーネ首相のもとでの中道左派5党連立内閣は,閣僚のスキャンダルの打撃や労働組合の大規模なストによる反対を押し切って,財政緊縮や憲法改正の難事業を達成した。
地方行政
ベルギーでは,先に述べた連邦化によって地方行政も大きく変革され,フランドル地域(東西フランドル,アントウェルペン,フランドル・ブラバント,リンブルフの5州),ワロン地域(エノー,ナミュール,リエージュ,リュクサンブール,ワロン・ブラバントの5州)と首都ブリュッセルの3〈地域〉に分かれ,その下に10州と589の市町村があり,首都ブリュッセルは隣接19自治体を含む。これら州,市町村はそれぞれ議会をもち,州知事は〈地域〉政府から任命され,市町村長はそれぞれの議会より選挙される。
外交,軍事
ベルギーは,第1次大戦まで永世中立国であったが,2度の大戦で中立を侵犯された経験から,第2次大戦後は一貫して西側の一員として集団安全保障に頼り,NATO(北大西洋条約機構)の発足当時からその一員である(ドイツに2個旅団駐屯)。また戦後,隣接の同じ小国オランダやルクセンブルクとベネルクス関税同盟を結んだうえ,EEC,ヨーロッパ鉄鋼石炭共同体,EURATOM(ヨーロッパ原子力共同体)にも発足当初から加盟し,現在EUの本部もブリュッセルに置かれている。
軍事面では,1995年から徴兵制を廃し,民間人の活用により軍人を大幅に削減した結果,兵力は4万5900人まで縮小された(陸軍3万0600人,海軍2800人,空軍1万2500人,軍事費は958億ベルギー・フラン。1993)。陸軍の一部と空軍の大部分はNATO軍に編入され,また93年からフランス,ドイツとともに欧州合同軍に参加し,94年から海軍はオランダと共通の司令部の下に運用されている。
経済,産業
工業
経済の重心は,産業革命期以来,ワロン地域のサンブル=ムーズ=エーヌ川沿いの製鉄,石炭,機械,化学工業にあり,また首都ブリュッセルも,ヨーロッパ金融の大中心地であった。第2次大戦後の復興期にも,戦災の少なかったこれら地方の工業は大いに繁栄を見せたが,1960年代になると,鉄鋼業の設備は旧式化したのみならず立地も不利となり,またもともと条件のよくなかった石炭業は,石油との競争の前に苦境に立たされた。他方,北部のフラマン地域は,その代表的産業であった繊維工業の不振や機械化による農業人口の過剰により慢性的な大量の失業者を抱えていたため,政府や地方自治体は,工業団地の造成,租税の減免と利子補給や特別融資などの便宜を計って新投資,とりわけ外資の誘致に努めた。このような有利な条件と低賃金,労働組合が穏健なこと,そして諸外国への交通の便のよさがあいまって,石油精製,石油化学,薬品,自動車組立て,電子機器などの新産業を中心に,続々と新工業地帯が誕生した。その重心は,アントウェルペン,ヘント,ゼーブリュッヘZeebruggeなどの臨海工業地帯,そしてアントウェルペン=ブリュッセル枢軸にあるが,それ以外にも,内陸の小工業団地がいくつも誕生している。これら新工業投資の3割を占めたのは,ヨーロッパ市場への進出を企てるアメリカ系多国籍企業であり,そのほかにもドイツ,フランスの化学,自動車産業の進出が続いた。また日本からは,本田技研工業(オートバイ)やYKK,パイオニア,鐘ヶ淵化学などの現地生産の工場が進出している。また,内陸地帯のベルギー,ルクセンブルクなどの諸製鉄企業も,ヘントの郊外に新しい臨海製鉄企業シデマルSIDEMARを共同で設立し,その粗鋼生産高はベルギーの全体の22%に達している。こうして,石油危機直前の72年には,フラマン,ワロン両地域の賃金格差はほとんど解消していた。その後,世界的不況の中で,とりわけ80年代からワロン地域はその代表的産業である鉄鋼の深刻な不況に苦しめられ,人員整理を余儀なくされ,失業率は全国平均14.3%でワロン地域は25.9%と,フランドルの7.4%に比して格段に高い(1994)。このため,ワロン地域の構造改善と大規模な再開発投資が必要となったが,不況と財政難に加え,両民族の対立によって難航した。しかし,ハイテク・精密化学などの新産業への投資で,ようやく蘇生しつつある。
主要工業としては,まず機械工業が挙げられ,国内工業生産の20%を占め,その3分の2が輸出に向けられる。とりわけ,資本財と輸送機器の両者は他を大きく引き離している。鉄鋼業は今日も世界有数の国の一つで,粗鋼年産は1100万tと,イギリス,フランスの6割以上に達している。化学工業は第2の工業部門で,その総生産の3分の2が輸出されており,石油化学・有機化学製品がその中心である。ベルギーの代表的化学工業会社であるソルベー社は,石炭産業と結びついたソーダなどの重化学を中心としていたため,戦後の石油化学を中心とした技術革新に出遅れたが,その後精力的な研究開発投資によって遅れを取り戻し,ベルギーの化学工業は成長産業の一つに数えられている。このほかベルギーには,繊維(綿,麻,毛織物,レース編),縫製,ビール,精糖,皮革,製紙,ダイヤモンド加工,ガラス(板ガラス,クリスタルガラス),さまざまのハイテク産業など,実に多様の産業部門が展開している。
農業
農業人口は,とりわけ第2次大戦後激減し,現在,有業人口の2.9%,その生産は国民総生産の2.9%を占めるにすぎない。農家経営は2.5~50haの中・小規模経営が大多数を占める。とりわけ東・西フランドル州は中世以来零細な集約経営が密集しており,全国の農家経営の27%が1ha未満である。また,農地・森林面積の71%が借地である。こうした零細農家は工場への出稼ぎや副業労働で生計を立ててきたが,戦後のフラマン地域の工業化やEC諸国の農業・工業双方での競争によって,兼業や出稼ぎは大きく減少した。土地利用面では46%が永久牧草地で,耕地のうち穀作地は22.7%とオランダに比してかなり高い。このほかテンサイ,ホップ,亜麻などの工業用原料,花などの栽培や酪農も盛んである。同国の農業は小規模ながら生産性は高く,現在国内需要の80%を賄っている。
エネルギー
ベルギーは,1950年代までヨーロッパの最も有力な石炭産出国の一つで,それだけに石炭への依存も強かった(1960年代は60%)。しかし,その後の石油の普及とオランダ沖の天然ガスの輸入の増大により,ベルギーの炭鉱はすべて閉山に追いやられた。現在,石油が総エネルギー消費の36.8%を占め,石炭は23.4%(1993年)。このほか天然ガス25.2%,核エネルギーは14.3%を占める。発電量は698億kWhで,うち原子力が60.2%,石炭火力23.3%,石油1.9%,ガス12.9%,水力1.7%となっている。
貿易,運輸
工業の発達した小国だけに貿易依存度は高く(1994年の対GDP比では,輸出52%,輸入47%),工業生産もその41%が輸出に向けられている。貿易(ルクセンブルクと共通)の相手国はEU諸国が輸出入とも圧倒的比重を占め(輸出74.9%,輸入73.5%。1992),なかでもドイツ(20.2%,20.1%),フランス(19%,16.1%),オランダ(13.2%,17.7%)がぬきんでている。なお,日本の占める割合は輸出1.1%,輸入2.6%である。他方,植民地時代10%台を占めてきたザイール(旧ベルギー領コンゴ,現コンゴ民主共和国)との貿易は,輸出0.1%,輸入0.45%と減少している。輸出品目は,金属・機械・輸送機器37.3%,化学製品15.3%,その他工業製品32%,輸入品目はエネルギー源12.1%,原料12.5%,化学製品12.7%,金属製品・機械・輸送機器27.5%である。ベルギーは,ヨーロッパ通貨制度に加盟したが,その枠内での為替相場は割高で輸出が伸び悩んでいた。1982年2月22日の改訂により,ベルギー・フランが他の通貨に対し3%切り下げ,マルクが5.5%切り上げられたことによって,EU諸国を中心に輸出の伸びを見せた。
ベルギーの貿易港としては,アントウェルペンが,ロッテルダム,ル・アーブルに次ぐヨーロッパ第3の荷扱量を誇り,ベルギーの海上貿易の90%を占めている。同港はベルギーのみならず,ドイツ,北部フランスとも,鉄道,高速自動車道,ライン・スヘルデ運河(1976完成)によって結ばれ,その貨物の一部も吸収している。ベルギーの商船は,1996年現在52隻,95万トンである。またベルギーの代表的航空会社SABENA(1990年部分民営化)は1923年の設立で,ヨーロッパの主要都市間のみならず,中近東,北アメリカ,極東,アフリカとの間に路線を広げてきた。80年代にはベルギー・フラン高も加わって業績不振に陥ったが,リストラとブリュッセル新空港の開港で立ち直り,1993年には64億人キロの乗客と10億キロトンの貨物輸送の実績を見せている。
金融,財政
ベルギーの中央銀行は,国立銀行(1851設立。日本銀行設立に当たりその模範となった)である。さらに,金融業務は,民間銀行,全国貯蓄・年金金庫Caisse Générale d'Espargne et Retraiteおよび政府系特殊銀行がそれぞれ分担している。金融業務は,二大投資銀行,ソシエテ・ジェネラルとブリュッセル銀行がそれぞれのコンツェルンの持株会社をなしてきたが,1929年の大恐慌により苦境に陥ったのを機に,銀行業務は持株会社から分離された。現在ベルギーには,外国資本によるものも含め金融機関が127(うち外国系41)あり,預金高は2兆6400億ベルギー・フランである。二大銀行のシェアは70%で,残りのベルギーの銀行も両者の系列に属する。一方,全国貯蓄・年金金庫は1世紀の歴史があり,年金業務や住宅貸付などを営んでいる。このほか,政府系産業金融機関では,産業金融公庫(1918設立)に加えて,国立投資会社(1962設立)が,地域開発投資や構造改善事業を支援している。また中小企業・農民向けには,国民職業信用金庫,国立農業信用公社がある。
財政では,連邦化によって地域と市町村財政の比重が34%まで高まった。国家財政は,すでに1970年代の好況期から社会保障費の膨張で赤字を出していたが,不況の下で租税収入の伸び悩みに加えて,公共事業費の増大や,老齢化や失業増による社会保障費の膨張,そしてなによりも公債費の増大により,赤字は累積し財政危機に陥り,通貨統合を前に緊縮財政を強いられている。
労働,社会保障
ベルギーは早くに工業化された国でありながら,労働立法や社会保障へ歩み始めたのは19世紀末のことで,その後両大戦間期から本格的整備をみた。労働組合は,社会党系,カトリック系,中立系の分立に加え,フラマン,ワロン間でも組織の分裂が見られる。最大の労働組合連合体は社会党系のベルギー労働総同盟(ABVV,FGTB)111万,カトリック系のキリスト教労働組合総連合(ACV,CSC)90万である。ベルギーの労働組合は,1948年以来,最低賃金制を獲得し,これは物価にスライドして改訂されることになっているため,アメリカの賃金と比べて25%も賃金水準を高めて,国際競争力を弱めた。そのため,このスライド制が労使対立の一つの焦点となってきたが,80年代の不況によって上昇にブレーキがかかり,相対的単位労働コストはドイツの73%まで下がっている。社会保障は,社会保険庁が,失業保険(初年度60%,次年度40%支給),健康・労災保険,遺族・退職年金を一元的に管理しており,労使が双方で4分の3,国が4分の1を拠出している。また,自営業者にも,健康保険,遺族・退職年金が認められている。
教育,社会
教育
教育は,6~12歳の初等教育,12~18歳の中等教育,18歳以上の高等教育に分かれる。義務教育は6~14歳。学校教育における宗教教育の自由をめぐるカトリック派対自由主義・社会主義の対立は,19世紀以来教育の枠を越えてしばしば大政治問題となったが,1959年主要政党間に結ばれた〈教育協定〉により,私立学校は国庫助成によって公立学校と同一の教育待遇と設備を保障され,国民はいずれの地域でも,公立・私立を自由に選択できることになった。1989-90年度では,初等教育では56.1%,中等教育では64.9%と私立学校(カトリック系)が優勢である。いっさいの教育は1963年の言語法により,当該地域言語によって行われる。従来,ベルギーでは父兄による教育言語選択の自由が認められていたため,中等教育以上ではフランス語が圧倒的優位を保ってきたが,今日では両言語の生徒・学生数の比はほぼ人口比なみとなった。大学も両言語均等の原則にのっとり,同数ずつ置かれ,学位を出しうる正式の大学としてヘント,リエージュの,モンスの3国立大学,カトリック私立大学であるルーバン大学および新ルーバン大学(フランス語部門の分離独立),ブリュッセルの両自由大学,ブリュッセル・カトリック大学(オランダ語)があり,このほか,大学進学者の増加にこたえてアントウェルペン,モンス,ナミュール,ハッセルトに小規模単科大学が新設されている。このほか,商学,農学,工学,芸術などの専門単科大学のほか,教育養成などの教育機関および大学院レベルの高等商業学院などが設けられている。
マスコミ
ベルギーは新聞の発達した国で,日刊紙のみで38紙を数え,それぞれ政党の系列下にある。フランス語紙は23紙でフラマン語14紙に比べて多いが,発行部数は,全体の250万部を両言語紙がほぼ均分している(このほかドイツ語紙1)。ラジオとテレビも,フラマン語とフランス語の両放送(国営)に分かれ,ラジオ3チャンネル,テレビ2チャンネルをそれぞれ放送している(このほか,ドイツ語放送1)。通信社としては,ベルガ通信社がある。
文化
現在のベルギーにあたる地域では,中世以来16~17世紀にいたるまで,都市の発展に支えられて美術や音楽の分野で目ざましい活動が見られたが,その後,文化的活動は沈滞し,やっと1830年の独立後,フランス語系文学(ただし,作家の多くはフラマン系)が世界的名声を博した。その先駆はド・コステルCharles De Coster(1827-79)(《オイレンシュピーゲルの伝説と冒険》)で,1881年から《若きベルギーJeune Belgique》誌によったベルハーレン,ロデンバック,メーテルリンクなどが,象徴主義の画家たちとも交流して,その全盛時代を築いた。フラマン語では,コンシャーンスHendrik Conscience(1812-83)が,歴史小説《フランドルの獅子》(1838)でフラマン民族の覚醒を促し,ヘゼレも抒情詩で名高い。このほかベルギーの生んだ文化人としては,シムノン(文学),C.フランク(作曲),ピレンヌ(歴史学),ケトレ(統計学),メルシエ枢機卿(カトリック哲学),ミショー(文学,絵画)が著名で,自然科学の分野では,ボルデ(細菌学),ヘイマンス(生理学)の2人のノーベル賞受賞者を出した。工業技術の面では,ルノアールJ.É.Lenoir(ガス機関),グラム(発電機),ベークランド(合成樹脂)などの発明家を輩出している。
執筆者:石坂 昭雄
美術
近代国家としてのベルギーの誕生(1830)は,この地域における初期中世以来の古く豊かな美術伝統の断絶を意味するものではないが,ここでは便宜上19世紀初頭以降のみを扱う。
フランス新古典主義の領袖ダビッドが1816年から25年に没するまでをブリュッセルで送ったことは,同地を中心とした新古典主義アカデミズムの確立に決定的に作用し,ダビッドの一番弟子ナベスFrancois-Joseph Navez(1787-1869)はアングルを思わせる肖像画によって多大な名声を博した。他方,やや遅れてアントウェルペンでは,ワッペルスGustave Wappers(1803-74),レイスHenri Leys(1815-69)など,自国およびドイツの絵画伝統に根ざしながらフランスのドラクロアを範として自国の歴史的事件を描くロマン主義者が台頭する。ロマン派の中でもウィールツは想像力を幻想的・怪奇的な主題に向けた。写実的描法と現実への愛着がフランドル美術の伝統的特性であったことから容易に想像されるように,写実主義が全ヨーロッパ的隆盛をみた19世紀半ば過ぎには,光に満たされた静謐な室内の情景を描いたデ・ブラーケレールHenri de Braekeleer(1840-88),筆触を生かして詩情豊かな風景を描いたフォーヘルスGuillaume Vogels(1836-96)らの優れた画家が出た。19世紀後半,自国よりむしろパリで活動した画家としては,瀟洒(しようしや)な女性風俗を描いたステバンス,悪魔的あるいは好色的な主題を得意としたロップスや,モローに師事しかつ印象派の影響を受けたエバンプールHenri Evenepoel(1872-99)がいる。一方,〈レ・バン(二十人組)〉が1884年以降ブリュッセルで国際的規模の展覧会を開いたことにより,印象主義,新印象主義等,パリの最新の動向が伝えられた。ベルギーは世紀末の象徴主義の一中心でもあり,〈レ・バン〉の創設者の一人クノップフがこれを代表する。同じく創立会員のアンソールは,独特の幻想世界を創造,強烈な色彩と大胆な筆致により,表現主義の先駆ともなった。
世紀のかわり目に主として工芸・建築に新風を吹き込んだアール・ヌーボーの運動においても,オルタとバン・デ・ベルデという傑出した建築家を生んだベルギーの役割は大きい。さらに後者は1901-14年にドイツで活動して機能主義の美学を標榜するバウハウス運動を準備し,帰国後は装飾を排した近代建築の推進者となった。19世紀の彫刻は新古典主義に支配され,労働者や農民を写実的かつモニュメンタルに表現したムーニエと象徴派のミンネGeorge Minne(1866-1941)の作品以外は新味に乏しい。後者は後述する第1次〈ラーテム派〉の一員でもある。
20世紀の主たる美術動向は,キュビスムを別として,ベルギーでも順次その展開をたどりうる。フォービスムは彫刻家でもあったワウテルスに,たくましく構築的なベルギー版表現主義は第2次〈ラーテム派Latemse school〉と呼ばれるペルメーケConstant Permeke(1886-1952)らの画家に代表される。一方,彼らに先立って,20世紀初頭ヘント近郊の小村シント・マルテンス・ラーテムSint-Martens-Latemに住みついた画家デ・サーデレールValerius de Saedeleer(1867-1941)らの第1次〈ラーテム派〉は,自然と自国の伝統を糧として現実の中の神秘を描こうとした。アントウェルペン近郊で制作したスミッツJacob Smits(1855-1928)の芸術にもこれに通ずるものがある。伝統といえば,迫真の写実と奔放な幻想が共にフランドル美術の特質であった以上,ベルギーがマグリット,デルボーというシュルレアリスムの大家を生んだことにはなんの不思議もない。一方でセルフランクスVictor Servranckx(1897-1965)が1917年にベルギー最初の抽象画を発表して以来,ファン・リントLouis van Lint(1909- )その他の抽象主義も確固たる力として近年に至っている。
→フランドル美術
執筆者:高橋 裕子
音楽
1830年に独立した国であり,それまではベルギーの音楽と呼べるほどのものをもたないが,ここでは現在の国境内における音楽を歴史的に記述する。
音楽史上,ベルギーで最初に活発な動きをみせた町はリエージュである。10世紀ころから同地の聖歌はその周辺地域に大きな影響を与えていたし,その後のリエージュは音楽理論の中心地となり,ジャック・ド・リエージュJacques de Liège(1260ころ-1330以降)といった理論家を輩出した。12,13世紀には,その近隣地帯で典礼劇が盛んに催され,その写本は現在もいくつか残っている。世俗音楽としては,トルベールの流れをうけているが,ベルギーは地理的にドイツ語圏に近いこともあって,ミンネザングの影響も見のがせない。ポリフォニーのジャンルでは,まずは14世紀に書かれた《トゥールネのミサ曲Missa Tornacensis》(ポリフォニー様式によるミサ通常文の最初の完全なセット)が注目に値する。さらに,15世紀から16世紀にかけてすぐれた音楽家を輩出すると同時に,ブルゴーニュ楽派,フランドル楽派の作曲家に活躍の場を与え,多くの宗教曲,世俗曲をうみ出した。16世紀中ごろから,アントウェルペンで楽譜出版業を開始し音楽の普及に努めたスザトTylman Susato(1500ころ-61から64)やファレーズPierre Phalèse(1510ころ-76ころ)らの功績も大きい。17世紀に入ると,イタリアやフランス,ついでドイツの音楽が主流を占めるなかで,オルガン音楽のケルクホーフェンAbraham van den Kerkhoven(1618?-1701),オペラのザンポーニGioseffo Zamponi(?-1662),教会音楽のフィオッコPietro Antonio Fiocco(1650ころ-1714)などが活躍,ハープシコード製作でもリュッケルス一族が名器を作り出していた。また,音楽活動は宮廷や教会のほか,市民の間でも盛んとなり,諸都市に愛好家によるコレギウム・ムシクムcollegium musicum(ラテン語)が誕生した。18世紀には,ブリュッセルやリエージュなどでオペラやバレエが盛んとなり,グレトリーやゴセックらが作品を残している。1700年設立のブリュッセルのモネ劇場が活動の中心であったが,この劇場は19世紀に入っても,他国の斬新な劇作品の初演場として名高かった。1830年,ベルギー独立と同時にブリュッセル,リエージュ,ヘントに,ついで43年にはアントウェルペンに音楽院が設立され,新たに国民的な音楽を培うことに力が注がれた。なかでもブリュッセルのフェティスとヘファールトFrançois Gevaert(1828-1908)の音楽学上の業績,アントウェルペンのブノワPeter Benoît(1834-1901)の作曲活動,イザイエに代表されるリエージュのバイオリン楽派は特筆に値する。20世紀の音楽活動は,ワーグナーの流れを受けた作曲家ジルソンPaul Gilson(1865-1942)やヨンゲンJoseph Jongen(1873-1953)に始まり,活発な歩みを続けている。1921年にコラールPaul Collaer(1891-1989)によって設立されたプロ・アルテ演奏会が他国のさまざまな現代音楽を積極的に紹介,これに啓発された音楽家は多い。1958年,プースールがブリュッセルに電子音楽スタジオを開設,この方向の活動もめざましい。このほか,1960年代からの古楽復興活動は注目に値する。ベルギーは,古楽器の可能性を完全に追求した説得力のある新しい古楽解釈の旗頭でもある。
執筆者:高野 紀子
歴史
中世
中世には,現在のベルギーの領域はフランドル伯領(フランドル),ブラバント公領(ブラバント),エノー伯領,リンブルフ公領,ルクセンブルク(リュクサンブール)公領,ナミュール伯領,リエージュ司教領などに分かれ,フランドルの大部分はフランス王国に,残りは神聖ローマ帝国に属していたが,実質上は独立した邦国をなしていた。そして,このなかでもフランドルは,12世紀以来,毛織物工業の中心で,ブリュッヘ(ブリュージュ),ヘント,イーペル,コルトレイクなど多くの都市が密集し,中世の〈ブラック・カントリー〉とさえ呼ばれている。また,ブリュッヘは,イタリアやスペイン,ドイツの商人たちが集まる大商業都市で〈北欧のベニス〉とたたえられた。これらの諸邦がしだいに一つにまとめられていったのは,1384年ブルゴーニュ公(フランス王家の分家)フィリップがフランドル伯領を相続して以来のことで,その後,ブルゴーニュ家およびこれを継いだハプスブルク家は,ネーデルラントの諸邦の君主権を相続や征服によって次々に獲得し,ついにカール5世(神聖ローマ皇帝,スペイン王)は1543年に,リエージュ司教領など二,三の小邦を除く,ネーデルラント全17州(北フランスの一部も含む)の主権を得た。
ネーデルラントの分裂
この17州は,依然,独立の諸邦が共通の君主を戴いていただけで統一国家には遠かったが,歴代君主はブリュッセルに宮廷を設け,全州を扱う政庁や裁判所も設置され,各州議会の代表者を集めた議会も随時召集されていた。そして当時のネーデルラントでは,かつてのフランドルの諸都市は衰退していたものの,これに代わって農村に毛織物工業や麻織物工業も発達し,早くも資本主義的経営もみられ,農村でも荘園領主の賦役はまったく姿を消して,農民の高度に集約的農業経営が一般化していた。また,ブリュッヘに代わって,アントウェルペンがヨーロッパ最大の商業都市として繁栄するなど,当時のベルギーは,経済・文化とも,ヨーロッパの最先進地帯であった。
しかし,1555年父カール5世からこれを相続したフェリペ2世(スペイン王。在位1556-98)が,当時この地方に浸透していたプロテスタンティズムの弾圧と旧来の各地方や諸身分の特権を無視した絶対主義的な統治を企てたため,八十年戦争(オランダ独立戦争)が勃発した。この独立戦争の中心は,フランドルやブラバントをはじめベルギー地域の方にあったが,独立軍は海からオランダ地域を制圧し,一方,フェリペ2世から鎮圧のために派遣されたアルバ公は,カトリックの貴族たちを味方につけ,これを足がかりにしだいにアントウェルペンをはじめベルギー全域を制圧していった。この過程で,ベルギーのプロテスタント,とりわけ多くの文化人や手工業者・商人が,オランダやイギリス,ドイツに逃れ,その経済・文化は決定的打撃を受け,繁栄はオランダに移ってしまった。その後,独立戦争は,1609-21年の十二年休戦を除いて48年まで続いたが,しだいにオランダに押され,ブラバント北部,フランドルの一部,上マース(ムーズ)地方などがオランダの手に帰した。そして,アントウェルペンは海への出口をオランダに握られ,1648年の講和条約(ウェストファリア条約)で,海への出入りを禁ぜられた。こうして,ネーデルラント17州は,独立を達成した北部のオランダとスペイン王主権下の南部のベルギーとに分裂し,ベルギーはさらに1667-68年フランスの侵略を受け(フランドル戦争),アルトアやフランドル・エノーの一部も奪われた。こうして,ベルギーはスペインの従属国としてスペインと諸列強との戦争に絶えず巻き込まれ,他方でスペインやその植民地との貿易では外国扱いされた。その後スペイン王が嗣子なくして死ぬと,その王位をめぐってフランスとオーストリアが争い,結局1713年のユトレヒト条約でオーストリアがベルギーを得て,95年までこの地を支配し続けた。
産業革命の進展と独立革命
こうして長年,外国支配と戦乱に打ちひしがれてきたベルギーに新しい経済発展の兆しが見えてくるのは1750年以降のことで,南部のサンブル=ムーズ川流域の毛織物工業(ベルビエ),鉄工業(リエージュやシャルルロア),石炭(リエージュやモンス)が順調に伸び,またフランドルでも新しい農法(フランドル農法)の発達普及によって人口の伸びが著しかった。そして,アメリカ合衆国の独立,フランス啓蒙思想などの影響下に,しだいに独立と旧体制改革を求める動きが表面化してくる。しかし,フランス革命勃発前後に起こったベルギー最初の独立運動(ブラバント革命。1789-90)は,オーストリアに鎮圧された。次いで95年フランス軍の侵入をうけ,フランスに併合された。フランスは封建制の廃止や営業の自由など革命(1789)の成果を持ち込み,教会財産の多くを没収して競売に付し,各邦や都市の特権を廃して九つの県に整理した。こうして,フランス統治下にベルギーのフランス化が進み,とりわけフランスという大市場に完全に組み入れられ,ナポレオンの大陸制度(1806)によってイギリスの競争から守られたため,ベルギーはフランス内で最も進んだ工業地帯の一つとなり,ヘントの綿工業やベルビエの毛織物工業などを皮切りに産業革命が開始された。
しかし,ナポレオンの没落後,ベルギーは列強諸国の取引の結果,オランダに統一され,1815年オラニエ・ナッサウ家のウィレム1世を国王に戴くネーデルラント王国Koninkrijk der Nederlandenを形づくった。しかし,同王国では,人口325万のベルギーの利益より,わずか200万のオランダ側のほうが優先され,経済政策においても商業国オランダの利益となる自由貿易政策が工業国ベルギーに押しつけられたことから,しだいにベルギーのブルジョアジー,自由主義者の不満が高まった。またベルギーで大きな勢力を占めるカトリック派も,プロテスタントが主流のオランダに反発して,自由主義者と手を結び,国王に反抗するようになった。そして,1830年8月,フランスの七月革命に触発されてブリュッセルをはじめ各地に暴動が起きると,ブルジョアジーとカトリック派は全土を掌握して臨時政府を組織し,同年招集されたロンドン会議で,ベルギーはフランスとイギリスの支持の下に独立を認められ,永世中立を保障された。次いでベルギーは,当時最も民主主義的な,三権分立と議会制を定めた憲法を制定し,ドイツのザクセン・コーブルク家のレオポルド1世(在位1831-65)を国王に迎えた。なお,リュクサンブール州のうちドイツ語を使用する東部は,オランダ国王が元首を兼ねる大公国としてベルギーから分離された。
→ベルギー独立戦争
独立後の経済発展
こうして発足したベルギーでは,独立後の経済的危機に対処するため,国家の手で精力的な鉄道建設が行われ,他方ソシエテ・ジェネラルやベルギー銀行などの投資銀行が次々に新しい株式会社を設立したり産業金融を推進した結果,1840年ころにはヨーロッパ大陸で最初に産業革命が終えられて,安定した資本主義国家が築かれ,48年の二月革命の争乱にもほとんど巻き込まれなかった。そしてベルギーは,ドイツ,フランス,イタリアなど周辺諸国に鉄,石炭,機械などを供給し,また資本や技術も提供しながら,その経済発展を維持した。また80年代以降,有力な市場であったロシアが輸入禁止政策に転ずると,ベルギーの大製鉄企業は続々ロシアに子会社を設立して現地生産に乗り出し,中国でも96年,北京~漢口間の鉄道建設を請け負い借款を提供したほか,天津の市電を経営していた。他方,ベルギーは熱心に植民地獲得を試みたが,いずれも成功せず,ようやく1884-85年のベルリン会議でコンゴ(現,コンゴ民主共和国)が,コンゴ自由国(事実上,国王レオポルド2世(在位1865-1909)個人の領土)として認められた。しかし,植民地から収益を上げようとして現地住民を虐待したことが世界の非難を浴び,コンゴ自由国の統治権は1908年ベルギー国家に移管され,〈ベルギー領コンゴ〉が誕生した。
ところで,ベルギーの政治や社会を支配してきたのは,フランス語を話す一握りのブルジョアジーで,労働者階級やフランス語の教育を受けていないフラマン人の中・下層階級は無権利状態に置かれていた。1870年代から両者の覚醒が,新しい政治的対立を生み,社会主義政党(労働党。現,社会党)やフラマン運動(またはフランデレン運動。フラマン人の自治要求運動)の政党が勢いを増し,部分的には改革の実績を築いたが,問題の多くが,第1次大戦後に持ち越された。
20世紀--残された言語問題
1914年,第1次大戦が勃発すると,ドイツはベルギーの永世中立を侵してフランスへの侵入を試み,その後4年にわたりベルギーの大半がドイツ軍の占領下に置かれた。激しい攻防戦の場となった諸都市では多数の文化財が破壊され,多数の非戦闘員も巻き込まれた。この間,フランスのル・アーブルに労働党も含めた挙国一致の亡命政権が樹立されていたが,戦後公約に従って普通選挙制を実施し,またさまざまの社会立法を導入した。しかし,フラマン系住民の地位向上については,戦後の親フランス的ムード,あるいはフラマン運動の中から多くの対ドイツ協力者を出したことによって,すっかり抛擲(ほうてき)されていた。しかし,1923年からヘント大学のフラマン語化問題をめぐって対立は再燃し,ついに30年にその完全フラマン語化が,32年にフラマン語地域の行政・教育用語のフラマン語への一本化,39年に軍隊の両言語別編成が実現した。一方,順調に復興したベルギー経済は,1929年の世界恐慌の中で危機に陥り,大量失業とストライキの激発の中でレックス党Rexなどファシズム政党と共産党の勢力が伸びたが,中道諸派の連合で議会制民主主義を守り抜いた。ベルギーは,36年英仏との軍事同盟を断念して中立政策に復帰したが,40年再度ドイツに中立を破られ44年まで全土を占領された。国王レオポルド3世(在位1934-51)は,軍とともにドイツに降伏したが,政府はロンドンに亡命し,抗戦を続けた(このため,国王は戦後復位できなかった)。解放後のベルギーは,マーシャル・プランを活用し,また植民地コンゴでの銅・ウランの産出によって比較的早く復興した。また45年オランダ,ルクセンブルクとベネルクス関税同盟を結び,EECにも発足当初から加盟した。しかし,戦禍をあまり受けなかったベルギー経済も60年代に入って地盤沈下をきたし,これにコンゴ植民地放棄(1960)の打撃が加わったが,幸いにフランドル地域の外資による工業化とEECの市場統合・国際分業に支えられて,新しい再建の道を歩みだした。
一方,言語問題は,戦後も終始対立がやまず,両地域の対立が内閣を辞任させてきたが,70年の憲法改正によって連邦化の方向が規定された。しかし,その実施,とりわけブリュッセルの扱いをめぐって,77年主要政党間で〈エフモントEgmond協定〉が結ばれたものの,それすら実施に移されないままになっていた。しかし,経済危機を克服するために,ついに1988年,ブリュッセルを両言語同権とする独立地域とすることで連邦化が合意された。
執筆者:石坂 昭雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報