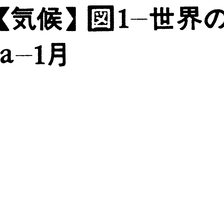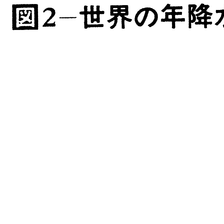翻訳|climate
共同通信ニュース用語解説 「気候」の解説
気候
それぞれの
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「気候」の意味・読み・例文・類語
き‐こう【気候】
- 〘 名詞 〙 ( 一五日を一期として「気」といい、五日を一期として「候」というところから )
- ① ある地点または地域で、一年を周期として毎年決まった順序でくり返される、最も出現確率の高い大気の状態。ある土地の、長期間を平均してみた天気の状態。緯度や、海抜の高低、その他、風、海流、地形などの因子によって決定される。気帯。
- [初出の実例]「蜀は気候異而冬も暖也」(出典:杜詩続翠抄(1439頃)八)
- 「高山は気候(キカウ)も替る故に」(出典:文明開化(1873‐74)〈加藤祐一〉初)
- [その他の文献]〔杜牧‐阿房宮賦〕
- ② 時節。時機。
- [初出の実例]「さる時は気候を不レ知てもかなうまい事ぞ」(出典:史記抄(1477)一四)
- 「製本(しこみ)は製本の時節あり。発販(うりだし)は発市(うりだし)の気候(キカウ)あり」(出典:滑稽本・浮世床(1813‐23)初)
気候の補助注記
現在は、ある地域の気象に関して、「気候」は恒常的なもの、「天候」「天気」は短期的、一時的なものを指すとして区別されている。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「気候」の意味・わかりやすい解説
気候
きこう
climate
気候とは、地球上において1年を周期として繰り返す大気の状態である。この周期的変化は、かなりの幅はあるが、ほぼ一定の範囲内にある。
[吉野正敏]
気候のスケール
気候は地球上の大気の状態であるから、地球上の地域の大小に応じて、把握する大気の状態は大小さまざまのスケールがある。世界全体、アジア、南極大陸などの地域のスケールの場合を大気候、関東地方、南ドイツなどの地域のスケールの場合を中気候、東京都区内の気候、富士山の気候などの場合を小気候、水田の気候、温室内の気候などを微気候とよぶ。
気候は気象現象の積み重ねから成り立つ。気候が長い期間における大気の状態であるのに対し、気象は厳密にいえば大気のある瞬間の状態をいう。もちろん、大気候に対応する気象現象は寿命時間が長く、小さいスケールの寿命時間は短い。
[吉野正敏]
気候要素と気候因子
気候を構成している日照、日射、気温、湿度、降水量、気圧、風などを気候要素という。大気候では、気圧が気候分布を成因的に説明するのに重要な要素であるが、小気候では、風が他の小気候要素の分布に影響を及ぼす重要な要素である。また一つの要素でも種々の表現法がある。たとえば気温だけをとっても、気温の日変化、日較差、年変化、年較差、積算温度などが、その表現方法の諸形態である。またいくつかの要素を組み合わせて表現する場合もある。たとえば月平均気温と月平均相対湿度の年変化の状態で表現するクライモグラフclimographや、月平均気温と月降水量の年変化の状態で表現するハイサーグラフhythergraphなどがある。ケッペンの気候区分も、気温と降水量の組合せで気候を表現するものである。
気候要素の分布に影響を及ぼすものを気候因子とよぶ。地球上の位置(緯度・経度)、地形、水陸分布、地理的位置(大陸の東岸・西岸など)、海抜高度などがその主たるものである。この因子は、大気候から微気候へのスケールの変化に応じて、重要なものが異なる。たとえば大気候においては、緯度が重要な因子であるが、小気候や微気候においては緯度は問題とならない。小気候、微気候では、微地形とか、地表の植被の状態などが大きな意義をもつ。
気候の表現方法は、先に述べたような気候要素の組合せによるほか、気候の成因、植生や自然現象を指標とする方法などがある。たとえば、気候を成因にまでさかのぼって考え、低気圧、高気圧、前線などの出現頻度などに注目して行う方法がある。また、天気、天候というような絶えず変動している状態も基準の一つになりうる。これらは動気候学的表現または総観気候学的表現とよばれている。
[吉野正敏]
世界の気候分布
世界の気候分布をもっともよく反映しているものは、植生分布である。世界の気象観測所の数は限られており、分布密度は地域的にかなりの差がある。この難点を救うために、植生を指標として、その分布に合致するような気候要素の組合せによる指数を考案する試みが、たくさんの人々によって研究されている。世界のおもな気候の特徴を述べると次のとおりである。
(1)熱帯多雨気候 高温多湿が特徴で、熱帯雨林を形成している。赤道前線または熱帯内収束帯(ITCZ)が位置する所に、雨がとくに強く降る。原生林が繁茂し、プランテーション農場が点在する。「夜は熱帯の冬」といわれるように夜間は気温が降下し、濃い霧や多量の露がみられる。赤道からやや離れると、太陽高度の季節変化によって、夏は熱帯気候と類似しているが、冬は中緯度高気圧からの乾いた貿易風の影響で乾いた季節となる。このような地域では森林はまばらになり、背の高い草原と耐乾性の低木林が卓越し、サバナ気候となる。この中間型として、多雨で雨量の季節変化がはっきりしている気候があり、これを熱帯モンスーン気候(熱帯季節風気候)とよぶ。
(2)乾燥気候 降水量が蒸発量(または蒸発散量)より少ない地方で、植生がほとんどない砂と礫(れき)などの景観が卓越する。ステップ気候は、緯度的にみると砂漠気候の南北両側に現れる。乾燥気候の分布は、中緯度高気圧の発源地域と関係がある。
(3)温帯気候 気温の季節変化が明らかで、冬はかなり寒く、夏は熱帯と同じくらいの高温になる。年降水量は700~1500ミリメートルで、森林はよく生育する。日本では、北海道を除いてこの気候に属し、中国東部の長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう))流域や西ヨーロッパ、北アフリカの一部、中近東の一部、北アメリカの南東部と太平洋岸などがこの気候地域に属する。南半球ではオーストラリアの南部、アフリカ内陸部の一部、南アメリカの一部などである。現在の高い文明をもつ地域がほとんどこの気候下にある。
(4)亜寒帯気候 冬は長く寒い。冷帯気候ともよぶ。その間、地面は凍結し、積雪に覆われている期間も長い。夏はかなり高温になり、針葉樹林はこのために生育が可能となり、農耕も短期間行われる。この気候地域は、シベリアを中心としたユーラシア大陸と、アラスカを中心とした北アメリカに分布する。南半球には、この緯度に相当する所に陸地がないので、この気候は出現しない。
(5)寒帯気候 両極地方に分布する。気温の日変化は小さく、年変化は大である。冷帯に近い所では、夏の間だけ地表面の雪や氷が融(と)けてコケ類をみる。極に近くなると、一年中、雪や氷に覆われている。
[吉野正敏]
古気候
地質時代や考古時代など、遠い過去の時代における気候を古気候という。地球は長い歴史をもつが、数億年にわたって現在とはかなり異なった気候が卓越していた。そして高緯度帯と低緯度帯との間の温度差は比較的小さかった。そして現在、赤道と極地方の間にあるような著しい温度差は、約7000万年の昔、すなわち新生代第三紀に始まった。第四紀になって高緯度の気温は急激に低下し、極氷が発達した。氷河は数回大きく発達し、中緯度にまで達した。続いて高緯度に退いた。約1万年前からをみても、高緯度帯と中緯度帯の気温は変化し続けている。また、気象台などにおける気象観測が始まった最近の100年間の観測によっても気候変動が続いていることが確かめられている。気候は一定不変ではなく、つねに変化しているが、その変化の波は、波長も振幅もさまざまである。
数万年前からの日本の気候変化は次のように考えられている。約4万7000年前にはマンモスが北海道へ南下したと推定され、寒冷であった。その後やや温暖になったが、2万~1万8000年前にはふたたび寒冷になった。このころは全世界的に寒冷で、ビュルム氷期の最盛期と考えられている。その後はしだいに温暖になり、いまから6000~5000年前は縄文海進とよばれ、温暖であったために、極地方の氷が融けて海面がもっとも上昇した時期にあたる。その後、しだいに緩やかに寒冷化し、3000~2000年前は、冷涼、湿潤な時代になった。すなわち弥生(やよい)時代は寒冷であったと考えられている。11~12世紀は温暖であったが、15世紀は小氷期とよばれるような寒冷な時期を迎えた。京都のサクラの開花も遅れがちであったことが知られている。その後、17世紀は温暖となったが、18~19世紀は小氷期とよばれ、寒冷であった。19世紀後半~20世紀の気候の変化は、1891~1910年の20年間が冷涼多雨、1911~1950年は酷暑少雨、1951~1970年は冷涼多雨、1971~1985年は高温と低温、多雨と小雨の極端な状態が顕著に現れた。さらに1990年代になって、温暖な冬、高温な夏が多くなった。日本を含め、世界における20世紀後半の気温の上昇傾向は明らかである。
[吉野正敏]
日本の気候
日本は面積が狭いにもかかわらず、アジア大陸の東縁に南北に連なる長い島国で、アジア大陸との間に日本海があり、暖流が流れていることや、地形が複雑であることなどの理由で、日本の気候は多種多様である。日本の気候は、日本海側、太平洋側、九州、瀬戸内、北海道と東北の太平洋岸などの主要気候区に分かれており、それぞれの気候の特徴はかなり異なる。
日本は世界的にみて多雨地域に属する。年降水量が2000ミリメートル以上の地域は、九州南部、四国南部、紀伊半島南部、東海道の一部、秋田県から福井県に至る日本海側一帯である。屋久(やく)島では1950年(昭和25)に1万0216ミリメートルの年降水量を観測し、内陸部では奈良県大台ヶ原で1920年(大正9)に8214ミリメートルを記録している。本州で平均年降水量が最大の地域は紀伊半島南部で、尾鷲(おわせ)は4000ミリメートルを超す。日降水量では、徳島県那賀(なか)郡木頭(きとう)村(現那賀町木頭)の日早で1976年9月11日に1114ミリメートルを観測したことがある。1901年から約100年間の年降水量は、日本を含めた東アジア全体をみると1950年代が多雨であった。したがって、その後は降水量減少の傾向にあった。日本では、西南日本ほどこの傾向が強く、北日本・東日本では弱い。
日本では四季の変化が比較的明瞭(めいりょう)である。春の入りは3月の中旬で、このころになると日によって寒暖の差は大きいが、しだいに暖かさを増してくる。天気は周期的に変化し、いわゆる「ひと雨ごとの暖かさ」とよばれる天気の変化がみられる。4月上旬には太平洋岸で一時、日照が少なく雨模様になる。4月下旬になると天気は安定し始め、移動性高気圧に覆われて、日中は初夏を思わせる暑ささえ感じることもあるが、夜間は冷え込み、翌朝には山間部で霜が降りることさえある。これは「八十八夜の別れ霜」とよばれている。
5月中旬は晩春で、一時、梅雨(つゆ)模様になる。これを「走り梅雨」という。平均して5月18日から初夏となり、北日本では多照であるが、南方からしだいに梅雨(ばいう)が迫ってくる6月7日は梅雨の入りで、気温はすこし下がり、雨の季節となる。6月下旬は梅雨の最盛期で雨量も多く、蒸し暑い。
7月下旬は夏となり、気温は高く、西南日本は小笠原(おがさわら)高気圧に覆われ、安定した天気が続く。8月8日は立秋で、このころ一時気温は下がるが、その後また暑くなり、残暑とよぶ。8月下旬からは初秋で、このころ台風が来襲することが多い。二百二十日(にひゃくはつか)ごろにはとくに台風の危険があり、9月中旬には秋霖(しゅうりん)となり、気温は下がり始め、雨の季節となる。10月中旬は本当の秋で、天気はよく、冬の季節風の一番手が吹き始める。11月3日ごろには好天が多い。11月下旬からは初冬で、気温は降下する。平均して12月18日は冬の入り、西高東低の冬型気圧配置の頻度が多くなる。季節風も発達し、山には雪が積もる。12月下旬にいったん季節風が弱まることがある。1月下旬は気温が著しく低い。こうして2月上旬の初春に連続する。
以上の四季の変化のなかで、もっとも強いアクセントをつけるものは、梅雨と台風と冬の季節風である。梅雨は約40日もの間、じめじめとした陰鬱(いんうつ)な天候をもたらす。これは、ヒマラヤ山脈とチベット高原によって2本に分流しているジェット気流が、日本上空で1本に合流し、大きく蛇行してオホーツク海上空でしばしば閉曲線をつくって、いわゆるブロッキング現象をおこし、このためオホーツク海には高気圧が停滞する。この高気圧からの北東の冷たい湿った気流が北日本に押し寄せ、南の小笠原高気圧からの暖かい湿った気流との間に形成されるのが梅雨前線である。東アジアの日本上空に特徴ある現象である。梅雨は水田耕作を主体としてきた日本の農業にとってはきわめて重要な現象で、雨ばかりでなく、北日本では、北東の気流が強ければ「やませ」が発達して冷害となり、南の気流が強い年には乾燥によって、とくに西日本に干害が出る。従来の日本の木造家屋は、床が高く、戸障子は開放的で、高温多湿の夏の気候に適していたのである。
台風が来襲すると降水量は300~400ミリメートル、風速は毎秒30~40メートルにも達し、多大の被害を与える。台風は1年に平均約3.8回来襲する。台風の通過に伴って、しばしば高潮がおこり、また河川の堤防が壊れて洪水がおこる。中心示度の低い台風ほど被害は大きくなる。
冬の季節風は台風ほどの被害は及ぼさないが、日本海側の地方に、強い北西の風と雪と陰鬱な天候を約半年にわたってもたらす。日本海には暖流が流れるので、シベリアからの低温で乾いた空気は日本海上で湿気をもらい、日本の山地にぶつかって多量の降水をもたらす。場合によっては、北陸沿岸に発生する局地的な不連続線に沿って豪雪を降らせる。いわゆる里雪とよばれるもので、人口密度の高い平野部に1日50センチメートル以上もの新積雪をみることもまれではない。
[吉野正敏]
気候と産業
気候は農作物の生育には決定的な影響を及ぼす。一定の範囲内では気温・降水量などの気候要素と正の関係が強い。さらに、ある限界値を超すと収量はかえって減少する。その限界値は、作物によって異なることはもちろんであるが、同じ作物でも栽培技術、品種などによって差がある。現在、水稲の北限は北海道に達しているが、最暖月の平均気温20℃の地域にほぼ一致している。日本の稲作では、夏の高温と日照時間が長いことが必要で、「日照りに不作なし」といわれているほどである。灌漑(かんがい)用水の不足は、ダムや溜池(ためいけ)などの設備によって補うことができる。これに反して夏の低温や日照不足は冷害をもたらす。梅雨前線の停滞位置の異常や、北東気流(やませ)の強い場合との関係はすでに述べたとおりである。凍霜害(霧害)は、モモ、ナシ、クワなどに、晩春に現れることが多い。放射冷却で冷えた地面に接した空気が0℃以下に冷えるためにおこる。このような冷却した空気は重いため、傾斜地を高度の低いほうに向かって流れ、いわゆる霜道(しもみち)を形成し、谷底や盆地底にたまって冷気湖を形成する。凍霜害はこのような所で大きい。谷壁斜面や盆地周縁の斜面はこのためかえって高温で、これを斜面の温暖帯という。このような所は温度条件がよいので、果樹などの栽培に適しており、ミカン、モモなどが植えられているのをよくみかける。
気候と水産業との関係も大きい。とくに沿岸漁業は風との関係が強く、冬の季節風が強い季節には、吹雪(ふぶき)や高い波のため、ほとんど休漁に近い状態となる。太平洋岸でも、寒冷前線の通過に伴う突風によって小型の漁船の遭難が多い。
工業地帯では、煙突から出る汚染物質による大気汚染が大きな問題となる。汚染物質はそのときの卓越風によって風下の地域に運ばれる。風がなく、逆転層が発達している場合には、汚染物質が地面付近に漂い、人間の健康や動植物の生育に影響が出る。とくにひどい場合には、人間の死亡率が平常のときを大きく上回り、植物は葉が枯れたりする。
[吉野正敏]
気候と動植物分布
世界の植生分布と気候との関係についてはすでに述べたが、日本における森林帯の分布は、気候の複雑さに対応して、国土の面積のわりには複雑で、暖温帯林、冷温帯林、亜寒帯林がある。暖温帯林には、九州、四国、本州の南半分に分布する常緑広葉樹林と、中部地方の内陸の山麓(さんろく)地帯から、関東、東北地方の低山や平地にかけて分布する暖帯落葉樹林がある。冷温帯林は、ブナで代表される落葉樹林と、モミ、ツガ、ヒノキ、スギなどの常緑針葉樹林とからなる。北限は北海道の黒松内(くろまつない)低地である。この北側はシナノキ、カエデ、ニレ、カツラなどを交えた大陸型の温帯落葉樹林が分布する。亜寒帯林は北海道の中央山地以東を占める。エゾマツ、トドマツがその代表的なものである。
動植物は季節の進展に伴って、それぞれの生育段階の変化をみせる。その動物季節の一例をあげると、昆虫の初見、初鳴、終見、終鳴の日、鳥類の渡り、初鳴の日、休眠の初日と終日、魚類のとれ始めと終わりの日などである。植物では、たとえばサクラの開花日、八分咲き日、満開日、クワの発芽日、開葉日、モミジの紅葉日、カラマツの黄葉日などで、植物季節とよぶ。これらは、多種の気候要素の総合されたものの指標であるばかりでなく、ある期間の総合された結果を表しているので、農作物の栽培(農作業の日程)の参考にもなり、気候の年による進みと遅れの指標として有意義である。
[吉野正敏]
都市気候
空間スケールによって気候を分類するとき、狭い地域の気候を小気候とよぶが、とくに都市に関する気候は都市気候とよび、環境汚染の著しい所として注目されている。都市気候のうち、もっとも顕著な現象は、気温が市街地では郊外に比較して高温なことである。これを都市気温(または都市温度)という。とくに、日最低気温、すなわち夜明けごろの気温が、郊外より市街地のほうがより高く、等温線の形が地形図の島の等高線の走り方に似ているところから、ヒートアイランドともよばれる。風が強い日や曇った日には明らかでない。都市気温の原因としては、以下のことが考えられる。
(1)細塵(さいじん)、二酸化炭素CO2、亜硫酸ガスSO2などの汚染物質による煙霧層の発達が光化学スモッグ現象をおこしたり、いわゆる温室効果をもたらすこと
(2)市街地における燃焼熱
(3)市街地の建造物によって増加した気流の乱れに伴う熱交換
(4)市街地と郊外の建築物の構成物質による差
市街地では湿度は低下し、弱い雨や霧日数は増加する。日射量は少なくなり、風は一般に弱くなるという現象がみられる。
[吉野正敏]
『吉野正敏著『日本の気候・世界の気候』(1979・朝倉書店)』▽『吉野正敏著『気候学』(1984・大明堂)』▽『吉野正敏他編『気候学・気象学辞典』(1985・二宮書店)』▽『吉野正敏著『小気候』新版(1986・地人書館)』▽『気象庁編『日本気候図』1990年版(1993・大蔵省印刷局)』▽『気象庁編『近年における世界の異常気象と気候変動――その実態と見通し』(1994・大蔵省印刷局)』▽『気候影響・利用研究会編『エルニーニョと地球環境』(1999・成山堂書店)』▽『気象庁編『気候変動監視レポート』1999年版(2000・大蔵省印刷局)』
改訂新版 世界大百科事典 「気候」の意味・わかりやすい解説
気候 (きこう)
climate
地球を取り巻く大気の状態を表す言葉に気象,天気,天候,気候がある。これらはよく似た言葉で,しばしば混同して使われる。気象は広い意味で使われるときは大気の状態や大気中で起こるすべての現象を指す。ある時刻または時間帯の気象の状態を天気という。その時間帯は数分間からせいぜい2~3日間程度までである。これに対して数日間以上にわたって同じような天気状態の移り変りが続くときには天候という。これに対して,もっと長い期間(通常は数十年間)の大気の総合した状態を気候という。気候の定義は〈地球上のある地点,または地域で,1年を周期として,毎年決まった順序で繰り返される,最も出現確率の大きい大気の総合状態〉である。簡単に考えるときは,気候とは〈ある土地に固有な大気の平均状態〉を指すことが多い。
気候は気象や天気と比べると,抽象的な概念であるが,〈今年の冬は寒い〉とか〈今年は雨が多い〉とか,〈今年は春が遅い〉とかいうときの判断基準になっているのが気候である。気候の概念は,人間生活に結びついて生まれてきた。狩猟や漁労から農牧業へと人間生活が変わると,あらかじめ季節の移り変りを知る必要が生じて暦が作られた。中国では二十四節気七十二候が考えられ,1年を24等分して,その名称を暦の中に記すことが行われた。立春,春分,啓蟄(けいちつ),夏至などがそれで,太陽の黄道上の位置に対応している。この気をさらに3等分したものが候である。日本には江戸時代にこれが伝わって,気候という言葉が作られたと考えられる。農学者佐藤信淵が文政年間(1818-30)に書いた《経済要録》の中にも〈赤道下を距る遠近の分度を測り,気候寒暖の番数を審かにし……〉とある。一方,ヨーロッパでは英語のclimateと類似の用語が用いられているが,いずれもギリシア語のklinein(傾く)に由来したもので,太陽光線の傾きあるいは山地斜面の傾きと関係すると思われる。英語のclimateの意味も16世紀ごろは緯度帯を意味しており,今日の気候帯に対応するものであった。これはギリシア語のklimataに由来するもので,ギリシアでは古い時代に昼の長さの差異により,赤道から極までを24のklimataに分けたといわれている。
気候は大気の総合状態であるが,形や大きさを直接測ることはできない。そこで通常は気候を気象測器で観測できる,日射,気温,湿度,降水量,気圧,風などの気候要素に分けて,それぞれの長年の平均値をとり,それらを組み合わせるのが普通の方法である。平均をする期間はあまり長くとると,その間連続して観測資料がある地点が少なくなるばかりでなく,気候変動の影響が加わるので,世界気象機関(WMO)の取決めにしたがって,現在は国内については1951年から80年までの30年間を用いている。これを気候の平年値という。平年値は,10年ごとにその直前の30年間の平均値をとるよう更新される。
大気現象では,気候で表されるような大気の正常状態から著しくかけ離れた状態が起こることがある。これが異常気象で,人間生活に重大な影響をもつ異常気象災害が起こることが多い。WMOでは世界各国の気象庁から異常気象の報告を求めるときに,25年以上に1度の確率でしか起こらぬ現象を異常気象の目安としたが,日本でも気象学上の異常気象の目安としては,平年値に対応して30年に1度の確率でしか起こらない現象を取り上げることが多い。
近年,気候変化の研究が盛んになり,気象観測が行われる以前の古気候の復元が試みられるようになった。このような場合の気候の推定値は,年代が古くなるほど,長期間の平均的な値を示すことに注意する必要がある。
気候の分類
気候はその地点や地域に固有なものであるが,気候を考える場合には,どの程度の広がりをもった地域を対象にするかによって,問題にする現象が異なる。たとえば北海道と関東地方との気候を比較するために,東京と札幌の1月の月平均気温差が約10℃であるという場合には暗黙のうちに,東京は関東地方の,また札幌は北海道地方の代表地点と考えている。したがって,関東地方の中での気候の場所による気温差,まして,東京の都心と郊外との気温差は考えていない。このようにどの程度の規模の広がりを対象にとるかという視点から,大気候,中気候,小気候,微気候に分けられる。この分類でとくに注意すべき点は気候の規模が小さくなるにつれて,現象の面積的な広がりが小さくなるだけでなく,上方の限界すなわち高さも低くなることと,気候の場所によるちがい(地域差)を生じる原因(気候因子)が異なることである。気候因子には,緯度,水陸分布,地形,地理的な位置,海流,植生などの地上被覆の状態などいろいろなものがあるが,中気候より規模の小さい気候では,小規模な地形(とくに高度)や地上被覆の状態がとくに重要で,緯度のちがいは問題にならない。
特定地点や地域の気候を知るためには,そこにある観測所の気候要素の平年値や極値を月別,あるいは年についてまとめた気候表やその値を地図上に記入して等値線を引くなどした気候図などの気候資料が必要である。しかしこのような気候資料のある地点は限られている。日本は,世界的に見ても観測所が最も密な国の一つであるが,それでも各種の気候要素の値がわかる気象台や測候所の数は全国で約150地点である。気温や降水量だけの資料であれば全国で前者は約1500地点,後者は約2000地点ある。したがって気象台や測候所の資料だけでは,中気候よりも規模の小さい気候現象を調べることはむずかしい場合が多い。とくに小気候や微気候のように局地的な現象は,既存の観測網でとらえることはむりで,そのための特別観測が必要になる。
気候を表すにはいろいろな方法がある。異なった場所の気候を比較するためには,決まった基準にしたがって気候を分類し,地図上で同じ気候に属する地域(気候区)を区分しておくと便利である。これが気候分類であり,気候区分でどのような基準で気候分類を行うかによって,気候区分も異なってくる。世界の気候区分は,多くの気候学者によって試みられているが,その方法は気候の成因に基づくものと,植生分布のように気候を端的に反映するものを指標にとって,それに合うよう経験的に分類する方法とがある。有名なW.P.ケッペンの気候区分は自然植生分布に対応した後者の立場に立つ代表的なものである。
気候は地形などとともに自然環境を構成する主要な要素の一つで,人間生活と深いかかわりをもっている。気候環境という立場でみると,気候は高温・低温と湿潤・乾燥の二つの面が重要である。気候が湿潤な東アジアを例にとると,高温な東南アジアから低温な北極に向かって北上するにつれ,植生は常緑熱帯雨林から照葉樹林,常緑広葉樹林と針葉樹の混合林,または落葉広葉樹林と針葉樹林との混合林に,さらに針葉樹林からツンドラ,氷雪原へと移り変わる。また赤道アフリカの湿潤気候地域から北アフリカのサハラ砂漠の乾燥地域にかけて,熱帯雨林から雨緑樹林,硬葉樹林,とげ林,サバンナを経て砂漠へと著しい植生の変化が見られる。このような自然植生と同様,農業も気候と密接な関係があり,栽培植物の種類や栽培限界,耕作限界などがそれぞれ決まる。
地球上の気候を支配する主要なエネルギー源は太陽からやってくる日射量である。日射の年総量は,おおまかにみると緯度圏にほぼ平行して低緯度から高緯度に向かって減少しているので,昔から熱帯,温帯,寒帯の境を南・北回帰線(23°27′)と極圏(66°33′)とする考え方が広く行われている。しかし詳細にみると赤道付近よりも,緯度20°~30°付近に日射量が多い地帯があるが,これはこの付近が亜熱帯高圧帯におおわれ雲が少ないためである。気候要素の中では,気温と降水量がとくに重要である。気温はとくに断らない限り,地上約1.5mの高さの気温を指す。地球全体の平均気温は14.3℃といわれているが,地上付近の気温分布は,日射量に支配されているので,おおまかにみると緯度圏にほぼ平行して,低緯度から高緯度に向けてしだいに低温になる。しかし気温分布図をより細かくみると,同一緯線上でも気温の地域差が大きい。とくに海岸と内陸とでは,気温の年較差(最暖月と最寒月の気温差)や日較差(日最高気温と日最低気温の差)が異なり,海洋に近いところでは変化が小さい海洋気候となり,内陸では変化の大きい大陸気候となる。この程度を表す示数が大陸度である。また同じ海洋に面した地域でも,大陸の東岸は西岸と比べて気温の年較差が大きく,夏は高温,冬は低温で,いわゆる東岸気候,西岸気候のちがいがみられる。ケッペンは,最寒月18℃の等温線によって熱帯気候と温帯気候を区分し,最寒月の平均気温18℃以下-3℃以上を温帯気候,最暖月の平均気温10℃以上で最寒月の平均気温-3℃以下を亜寒帯気候,最暖月の平均気温10℃未満を寒帯気候とした。このように気温は年平均をみるだけでなく,最暖月と最寒月の気温も重要である。なお,ケッペンの気候区分図で明らかなように,南半球には亜寒帯気候の地域がほとんどない。これは亜寒帯気候の出現する地域に陸地がないためである。
気温の年変化は,熱帯地方ではほとんどなく,気温の年較差は3℃以下の常夏の国であるが,赤道から高緯度に向かうにつれて,しだいに年較差が大きくなり,温帯地方が春夏秋冬の四季が最も明らかである。世界の気温の極値は,バスラ(イラク)の58.8℃(1921年7月8日)が最高,ボストーク基地(南極)の-89.2℃(1983年7月21日)が最低である。
降水量の分布は気温分布よりもさらに複雑である。地球全体の平均年降水量はおよそ1000mmであるが,大気中に含まれる水蒸気の総量を降水量に換算すると(可降水量という),25mmにしかならない。したがって地表面に降った雨や雪が大気中に蒸発して雲をつくり,ふたたび雨や雪となって降るという水の循環が,地球全体で1年に約40回繰り返されていることになる。大気中に含むことができる水蒸気量は,気温が高いほど多いから,低緯度は高緯度と比べて降水量が多く,雨の降り方(降水強度)も強い。しかし雨や雪は大気の運動と関係が深く,上昇気流のあるところでないと降らない。とくに緯度20°~30°の亜熱帯高圧帯におおわれるところは著しく降水量が少なく,草原や砂漠におおわれる乾燥気候になっている。また地球表面から大気に供給される水蒸気の84%は海洋から蒸発し,残りの16%が陸地から供給される。しかも海洋上の水蒸気が陸地に向かって運ばれるとき,海洋に面した斜面上で地形性の上昇気流によって雨や雪が降ることが多い。世界の年降水量の最大はハワイのカウアイ島のワイアレル山の1万1684mm,最少はチリのアリカの0.8mmである。乾燥地域は年間の降水量よりも蒸発散量が多いために生じる。蒸発散量は気温が高ければ多くなるので,乾燥気候と湿潤気候の境界(乾燥限界)は,熱帯地方では年降水量750mmぐらい,温帯地方では400mmぐらいである。
世界各地の気候を考える場合には,降水は年の総量だけでなく,その季節配分が重要である。年間の降水配分があまり変化しない地域と,雨季と乾季の区別の明らかな地域が存在する。赤道付近では年間を通して雨が多いが,その外側は高日季のあとに年2回の雨季と乾季のある地域があり,さらにその外側に晩夏に1回の雨季と残りの期間が乾季がある地域があり,しだいに雨季が短くなって乾燥地域に移り変わる。乾燥地域の高緯度側には,偏西風帯の温帯低気圧や前線による雨の地域が広がる。この地帯の大陸の西側では,赤道側にずれるほど雨季が夏から冬へずれる。また内陸部では,夏に集中的に降雨がある。
降水量は日射量や気温と異なり,年々の変動が大きい。とくに半乾燥地域や乾燥地域では変動率(年々の降水量の平年値からの偏差と平年値の比)が大きい。したがって気候表に載せられている平年値以外に変動率を考える必要がある。とくに半乾燥地域では,降水量の変動が直ちに農業や牧畜などに影響を及ぼす。
世界の積雪地域は南極大陸を除くと大部分は北半球にある。氷河や万年雪におおわれる極地方や高山を除くと,北半球の平野部で広い範囲が積雪におおわれるのは10月から5月までである。積雪期間の長短は必ずしも最深積雪とは関係せず,むしろ気温との関係が深い。寒帯地方の海洋気候地域では積雪期間が長く,北極海沿岸では8ヵ月以上に及ぶ。最深積雪からみると日本は世界屈指の雪国で新潟県上越市(高田)の377cmは,世界の平地の積雪記録といわれている。
気候と人間
気候は人間生活にさまざまの影響を及ぼしている。和辻哲郎が《風土》の中で論じたように,高温多湿なモンスーン・アジアに稲作が,乾燥気候の西アジアで遊牧が,そして温和な温帯気候のヨーロッパに農牧を中心とする農業が営まれてきたばかりでなく,そこの住民の生活様式や住居の形態,気風や思考,文化など,衣食住全般に影響を及ぼしてきた。E.ハンチントンは,《気候と文明》(1924)の中で,文明が栄えるのには好適な気候があり,西ヨーロッパや北アメリカなどはこれに属するとした。
人間が気候環境の異なる地域に移住すると,人間はそこの気候環境に適応しようとする。これが気候順応である。たとえば3歳以前に日本からフィリピンに移住した日本人の汗腺数は,日本で生まれ育った日本人よりも約50%多く,現住民とほぼ同数に増加する。
人間は昔からそこの気候に適応して生活をしてきたが,今日では農業ばかりでなく,工業,商業,交通,衛生,作業能率など多くの分野に関係している。そしてただ気候に適応するだけでなく,目的に合うよう気候調節も試みられている。室内気候の冷暖房による調節や温室などはその例である。土木建築の設計にその土地の気候条件を考慮することもふつうに行われるようになった。
しかし一方では技術の飛躍的進歩によるエネルギー消費の拡大などのために,予期しなかった気候の改変も生じるようになった。たとえば都市気候や大気汚染などは,その著しい例の一つである。かつて人間は,強風地域の防風林や多雪地域の雁木などの気候景観にみられるような,生活の知恵で気候環境に適応して生活をしてきたが,今後は二酸化炭素の増加に伴う気候温暖化などの解決のより困難な問題に対応しなければならなくなっている。
執筆者:河村 武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「気候」の意味・わかりやすい解説
気候
きこう
climate
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
最新 地学事典 「気候」の解説
きこう
気候
climate
ある場所や地域に関して,各季節に年々繰り返される天候を通じて帰納された大気の平均的な総合状態。または,それを季節的に連続させた年間の時系列。年々変動の一定の幅を含む。西洋での語源は,ギリシア語のklinein(傾く)に由来し,太陽高度を介して緯度帯(klimata)から地理的な形で気候の概念が生まれた。東洋では中国の二十四気七十二候,つまり年間の季節推移から出発した。それぞれ今日の気候の概念の両側面をなす。気候の生成には,日射の受熱をエネルギーの根源とし,地球の自転・太陽の季節移動のほか,緯度・水陸分布・地形・海流などの気候因子が作用する。これら諸条件のもとで起こる大気現象の集積が地域ごとに気候特性をつくる。大気大循環によって赤道多雨気候・亜熱帯乾燥気候等々の大規模な気候帯が形成され,それが海陸の配置によって海洋性気候・大陸性気候,また大陸の両側には西岸気候と東岸気候とが特徴づけられる。太陽高度に伴う大気運動の季節変化によって気候の分布は多彩化され,山脈の配置や海流によってさらに局地化される。これら諸気候の地域的なスケールは,大気現象や気候因子の広がりの大きさに対応し,大気候・中気候・小気候に区別される。
執筆者:設楽 寛・田中 博
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
百科事典マイペディア 「気候」の意味・わかりやすい解説
気候【きこう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「気候」の読み・字形・画数・意味
【気候】きこう
 暉を含む
暉を含む  暉能く人を
暉能く人を しましむ 游子憺(たの)しんで歸ることを
しましむ 游子憺(たの)しんで歸ることを る
る字通「気」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の気候の言及
【風土】より
…風土は中国起源の語で,元来,季節の循環に対応する土地の生命力を意味した。土地は,天地の交合によって天から与えられた光や熱,雨水などに恵まれているが,生命を培うこれらの力が地上を吹く風に宿ると考えられたのであろう。許慎(後漢)の《説文解字(せつもんかいじ)》に〈風動いて蟲生ず〉とあるように風という字の中の虫は,一年中で最も早く生じる生物であった。人間本来の性は同じでも,土地の生命力ごとにその涵養のされ方には違いができることから,風土の語は,《後漢書》では場所ごとに異なる地方差を意味するに至った。…
※「気候」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...