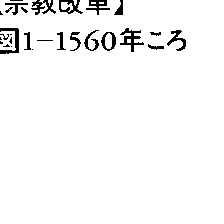精選版 日本国語大辞典 「宗教改革」の意味・読み・例文・類語
しゅうきょう‐かいかくシュウケウ‥【宗教改革】
改訂新版 世界大百科事典 「宗教改革」の意味・わかりやすい解説
宗教改革 (しゅうきょうかいかく)
Reformation
宗教改革は,16世紀前半,ヨーロッパのキリスト教,それもローマ・カトリックの教界内部でおこった神学,教義,典礼,教会体制の全般にわたる変革運動である。中世いらい,キリスト教はヨーロッパの社会,政治,文化,思想など,生活の諸分野と密接に結びつき,これを深く規定していたため,この変革と,それを通じて成立したプロテスタンティズムは,ルネサンスと並んで,近代ヨーロッパ世界の形成にとって,重要な意義をもつこととなった。
改革の先駆け
宗教改革の一般的前提をなしたものは,ローマ教皇権の動揺に象徴せられるごとき,中世カトリック教会体制の内部的な構造変化である。カトリシズムは,中世ヨーロッパの封建制度とのからみ合いの中で,一個の巨大な法的・権力的秩序をつくりあげていた。教皇権によって統轄される聖職者身分の階層秩序,支配体制こそがカトリシズムの正統な教義の枠組みである限り,すべての信仰箇条は一種の法的規定という性格をそなえており,個人の信仰は,神の定めた教会の伝統的諸権威への内面的な服従を意味していた。そしてこの権威,ないしそれが強制する正統な教義に反する信仰内容は,すべて〈異端〉として,世俗権力の協力のもとに,きびしく禁圧された。
14世紀ごろから,政治的な意味での封建制度がしだいに弱体化し,各地域に領域的・集権的な統一国家体制が築き上げられるに伴い,もともと封建的な権力分散状況のもとでのみその普遍性と絶対性を保証されていた教皇権は,不可避的に動揺せざるをえなくなる。教皇のアビニョン捕囚(1309-77)と,それに続く教会大分裂(シスマ,1378-1417)は,フランスの国民的王権の台頭による教皇権の空洞化を示す典型的な事件であった。そして,このようなローマ教会体制の動揺の中から,いくつかの宗教的な改革理念が生まれてきた。
第1は,教会大分裂の克服,教会統治の刷新をめざして開かれた,コンスタンツ公会議(1414-18),バーゼル公会議(1431-49)の両公会議に表現される,改革公会議運動である。これは,司教階層が中心となって,教会統治体制を,従来の教皇絶対主義から一種の立憲君主制に変えようとするものであり,15世紀中葉におけるガリカニスム(フランス国民教会主義)の成立が示すごとく,国王による中央集権化の努力とそれに伴う萌芽的なナショナリズムがこれと結びついていた。しかもこの体制改革運動の背後には,俗権と教権の分離を唱える神学者オッカムらの新しい教会統治理念が働いていたが,カトリシズムの中心的な教義内容に対する批判にまで進むことはなかった。
第2は,〈宗教改革の先駆者〉と呼びならわされるウィクリフやフスの改革運動である。彼らは,教権と俗権の分離や教会統治体制の変革にとどまらず,神の掟としての聖書を中心に据え,それに根拠をもたない教会の慣行・教義を批判したため,異端の烙印を押された。ウィクリフによる聖職者の身分的特権に対する攻撃と聖書の英語訳,フス派による両種聖餐,つまり俗人信徒にもパンと並んでブドウ酒を授けよ,との要求などは,信徒の共同体としての教会の理念を示している点で,宗教改革とより深くつながるものをもっていた。
第3は,信徒個々人の魂と神との直接的な交わりを求める,内面化された信仰としての神秘主義の流れである。ドイツのエックハルトやタウラー,《イミタティオ・クリスティ》で知られるフランドルのトマス・ア・ケンピスなどに代表されるこの神秘主義は,都市の発達に支えられつつ,中世末期には広く各国の俗人社会に広まり,体制の中で形骸化した信仰生活に新しいいぶきを与えた。
第4はルネサンスの人文主義と結びつく,改革的なキリスト教哲学であり,この思潮はしばしば神秘主義と混じり合っている。フランスのルフェーブル・デタープル,ネーデルラント出身のエラスムスらが掲げたこのキリスト教的ヒューマニズムの理念は,古典研究を通じての人間形成という立場から,やはり聖書を重んじ,キリスト信仰を原初の純粋な姿に立ち戻らせようとする志向において,宗教改革に大きな推進力を提供した。
ルターの福音主義
ドイツ中東部の領邦,ザクセン選帝侯国の首都ウィッテンベルクで,アウグスティヌス会の修道士であり大学の神学教授であるマルティン・ルターが,1517年10月31日,贖宥の効力に関する〈九十五ヵ条提題〉を公にしたことが,宗教改革の口火となった。深い罪意識と鋭敏な良心から,律法の遵守や善き〈行い〉(功績)による救いの道を説くカトリシズムの教義に根本的な疑いをいだいた彼は,オッカム神学の研究や上司シュタウピッツを通じての神秘主義との接触,しかし何よりも〈神の言(ことば)〉としての聖書への沈潜の中で,救いの問題の新たな神学的理解へと到達した。〈信仰義認論〉または〈福音主義〉と呼ばれるものがそれであって,〈ひとの救いは,行いによるものではなく,十字架のキリストにおける罪の贖(あがない)を信ずることのみによる〉という確信を根底としている。そのさい,ルターの個人的宗教体験に客観的な裏づけを与えたものは,とりわけ旧約聖書の《詩篇》と新約聖書のパウロ書簡(《ローマ人への手紙》《ガラテヤ人への手紙》)であった。〈九十五ヵ条〉で表明された彼の疑念と批判は,教皇が,贖宥状(免罪符)の購入のごとき外的な〈行い〉(功績)に免じて,信徒の罪そのものを赦す特別の力をそなえていると思うのは誤りであり,真の内的な悔い改めと,唯一の救い主キリストの御業(みわざ)に示される神の恩寵への,全面的な信仰によってしか魂は救われない,という根本的確信の帰結にほかならなかった。
〈九十五ヵ条〉は,このように教皇庁財政の手段と化していた贖宥状販売への批判にとどまるものではなく,教皇権の本質とキリスト信仰の中核にかかわる重大な論点を含んでいたため,ルター自身の予想をはるかに超える広い反響を呼び起こした。当初ローマ教皇庁はこの事件をたいして問題にせず,ルターの側でも論題の真意を詳しく解説した書物を公にして,教皇の理解を求めたが,贖宥状販売に直接かかわっていたドミニコ会の神学者たちとの論争を通じて,双方の対立は時を追って厳しくなり,ドミニコ会の告発で,翌18年6月には,ルターに対する異端審理がローマで開始される。そして19年6~7月,教皇側の最も有力な正統神学者エックとの間に,ライプチヒで行われた討論会(ライプチヒ討論)において,ルターがついに教皇の至上権を明確に否認し,公会議も誤りを犯す可能性があり,フスの学説にも福音的なものがあると公言するにおよんで,ローマ教会との決裂は事実上とり返しのつかぬものとなった。
ルターの改革構想
〈神の言〉たる聖書を唯一の権威とし,信仰者の良心をかけたルターの勇敢な教皇権批判は,フッテンをはじめドイツの人文主義者たちの強い支持を得,エラスムスを尊敬する神学者メランヒトンのごときは,1518年いらいウィッテンベルク大学におけるルターの同僚教授として,その改革運動の協力者となった。彼の福音主義は,さらに広く市民層から農民層にまで及ぶ国民的な世論を獲得するにいたるが,そこには当時急速に発展しつつあった印刷術の力が大きく働いており,ルター自身この手段を存分に活用して,多くの著述や論争文,説教を公にした。とりわけ歴史的に重要な意味をもつのは,20年の夏から秋にかけて次々に書かれたいわゆる三大改革論,《キリスト教界の改善について,ドイツ国民のキリスト教貴族に与う》《教会のバビロン捕囚》《キリスト者の自由》である。
《ドイツ国民のキリスト教貴族に与う》は,ルターが初めてドイツ人としての国民意識に立って,ローマ教皇勢力によるあくどい財政的収奪や,聖職売買,そのほか国民生活を圧迫し正しい信仰をそこなうさまざまな悪弊を列挙し,教会当局者が無能を暴露している現在,統治権力を神にゆだねられた貴族(実際には領邦君主たるドイツ諸侯)に,教会生活全般の改革をたすけるよう呼びかけたものである。そこにはまた,聖職者の独身制や,一般に特権的な身分としての聖職者の否定,つまり,いわゆる〈万人祭司主義allgemeines Priestertum〉の理念が,聖書にもとづいて展開されているが,プロテスタント教会のありかたを深く規定したこの根本理念は,《キリスト者の自由》においても,〈信仰義認論〉をふまえつつ,改めて強くうち出された。ルターにとって〈自由〉とは,律法の前で露呈される罪からの解放,キリストの福音への信仰のみによって神の前に義とされた,キリスト者の霊的・内的な自由のことであり,かかるキリスト者は,肉的・外的存在としては,自由な魂の喜びにあふれて,隣人への奉仕に身をささげる神の僕だと説いたのである。これら両論著がドイツ語でひろく読まれ,まさに国民的な影響を及ぼしたのに対し,《教会のバビロン捕囚》はラテン語の神学者ないし聖職者向けの著述であるが,ここで彼がカトリック教会の七つの秘跡(サクラメント)に聖書主義の立場から批判を加え,サクラメントを洗礼と聖餐の二つだけに限定したことは注目すべきである。
改革の進展
ローマでは,1520年6月に教皇レオ10世が,いまや異端の判決を下されたルターに対し,所説の撤回を破門の威嚇によって強要する教勅(《エクススルゲ・ドミネ》)を発していた。ドイツ各地に反ローマ感情が高まる中で,さまざまな妨害を受けつつ,この教勅がルターのもとに届いたのは,秋に入ってからだった。ルターは12月10日,これを公衆の面前で火中に投じ決意のほどを示したので,翌21年初め,正式に破門の教勅が出された。時のドイツ(神聖ローマ帝国)皇帝カール5世は,スペイン王でもあり,厳格なカトリック信者だったが,彼は,皇帝選挙のさい恩義をこうむったザクセン選帝侯への政治的顧慮からしても,ルターの処置について,教皇の意のままには動かなかった。21年春ウォルムスで開かれた帝国議会(ウォルムス国会)に,皇帝がルターの出頭を求め,いまいちど〈異端的〉な所説を撤回する機会を与えたのはそのためである。しかしルターはあくまで良心を曲げず,取消し要求に応じなかったので,皇帝はウォルムス勅令を発して彼の帝国公民権を奪い,その著作の禁圧を命じた。
ルターの保護者であるザクセン選帝侯フリードリヒ3世(賢侯)のはからいで,チューリンゲンのワルトブルク城に身を隠したルターは,ここで新約聖書のドイツ語訳(《ルター訳聖書》)という重要な仕事を短期間になしとげた(刊行は1522)。一方,皇帝はあたかもこのころ勃発したフランスとの戦争(イタリア戦争)のため,10年近くもドイツから遠ざかっていたので,ウォルムス勅令はほとんど空文と化し,ザクセン,ヘッセンなど,各地の領邦や帝国都市で福音主義の宣教が行われ,修道院の解散,典礼の改廃などを伴う教会生活の変革が,世俗権力の協力のもとでおし進められた。かかるルター主義の拡大に触発されて,さらに急進的・民衆的な宗教改革運動が台頭する。メランヒトンら正統のルター主義者により〈狂信派Schwärmer〉の烙印を押されたこの一派の動きは,早くもルターのワルトブルク隠棲中のウィッテンベルクで,彼の同僚カールシュタットらの指導する騒擾となって現れた。事態を憂慮したルターのウィッテンベルク帰還(1522春)によってこの騒擾自体は収まったが,同種の急進主義は,伝統的な社会体制を変革しようとする下層市民や農民の要求と結びついて各地に飛火し,教会秩序を混乱させる危険を生んだ。〈狂信派〉の最も有力な指導者として活躍したのがトマス・ミュンツァーで,彼は1525年の有名なドイツ農民戦争に大きな役割を演じ,反乱が領邦君主により武力で鎮圧される中で処刑された。この経験は,もともと社会観において保守的だったルターやその協力者たちに強い衝撃を与え,以後,宗教改革の政治的主導権は領邦君主に移っていく。
領邦教会制
中世カトリシズムは,本来教会と国家の関係については,〈教会の中に国家がある〉という立場をとってきた。中世末期における国民国家形成の動きは,教皇統治体制の動揺に対応しつつ,フランス,スペインなどで,領域内の教会を王権の統制下に置こうとする傾向を示したが,宗教改革は,俗権の宗教的任務を強調することによって,この領域教会主義を確立した。諸侯領の連合体にすぎないドイツでは,それが帝国レベルの国民教会ではなく,領邦教会制という形をとったのである。ルター派諸侯による領邦教会体制の組織は,スペイン王たる皇帝カール5世が,フランスと呼応するオスマン・トルコ勢力のオーストリア侵入の危険に直面し,1527年のシュパイヤー帝国議会で彼らに政治的譲歩を余儀なくされたことから,いっそう促された。戦局の好転とともに,29年の第2回シュパイヤー帝国議会で,皇帝側がこの譲歩を撤回したとき,ルター派諸侯は強く抗議し,これがプロテスタントという呼称のおこりとなった(シュパイヤー国会)。その後,ルター派を旧教会に引き戻そうとするすべての努力にもかかわらず,いったん根をおろした領邦教会体制を覆すことはもはやできなかった。切迫するカトリック勢力との政治的対決を何とか回避すべく,メランヒトンはつとめて温和な表現をとった福音主義の信仰箇条を作成し,30年のアウクスブルク帝国議会に提出したが(〈アウクスブルク信仰告白〉),カトリック諸侯はこれを退けたので,ルター派の諸侯と帝国都市はシュマルカルデン同盟に結集し,対決に備えた。
スイスの宗教改革
これより先,1522年以来,エラスムスとルターの影響下に,ツウィングリがスイスのチューリヒで市政府と提携しつつ宗教改革運動を展開し,この運動はバーゼル,ベルンなどにも広がっていた。ルター派のヘッセン方伯フィリップPhilipp der Grossmütige(1504-67)は,ドイツのプロテスタントとツウィングリ派とを合同させようと図り,29年,マールブルクの居城で,ルター,メランヒトンらとツウィングリらスイスの改革指導者との宗教会談(マールブルク会談)を開かせたが,聖餐の典礼の解釈をめぐって両者は意見が合わず,合同の試みは挫折した。まもなく起こったスイスのカトリック諸州との戦争で,ツウィングリが31年に陣没したのち,この地の宗教改革は壊滅に瀕した。
ツウィングリの改革運動も,信徒の共同体たる教会と市民共同体としての都市の権力を結合した点で,一種の領域主義を追求するものであったから,これに不満な人々は,純粋な聖徒共同体の理念を掲げて,幼児洗礼を否認し,当局の弾圧でスイスを追われた。これが再洗礼派というセクトのおこりである。あたかもドイツ農民戦争の時期に,再洗礼派はドイツに入り込み,農民や小市民が主たる担い手となってネーデルラントなどにも広がったが,ルター派は,この運動を〈狂信派〉の急進主義と同一視し,きびしい迫害を加えた。また同じくドイツ農民戦争のころ,ルターは人間の自由意志が魂の救いに役だつか否かの問題で,エラスムスと対立し,ついにたもとを分かつにいたった。このようにルター派は,福音主義の原理を共有する他の〈過激な〉諸勢力をも,温和な人文主義的改革路線をも,ともに退けることによって,教義的な硬直化のきざしを見せはじめた。
一方,領邦分立主義と結びつく政治的なプロテスタンティズムとカトリック陣営との敵対はますます深まり,トリエント公会議(1545-63)の招集でカトリシズムの内的刷新と教皇権の復興(反宗教改革)が緒についたその翌年,皇帝は公会議への出席を拒んだドイツ・プロテスタントの武力弾圧に乗り出した。このシュマルカルデン戦争(1546-47)は皇帝側の勝利に終わったが,それに乗じて皇帝の統治権を強化せんとするカール5世の野心は,52年に宗派をこえたドイツ諸侯の反撃にあい,むなしくついえ去った。失意の皇帝がネーデルラントに退いたのち,カールの弟フェルディナント1世が主宰するアウクスブルクの帝国議会で,ドイツの宗教問題に政治的な決着がつけられた。このいわゆるアウクスブルクの宗教和議により,ルター派は帝国内におけるカトリックとの同権を認められたが,両宗派を選択する権利が諸侯と帝国都市当局のみに与えられた事実からもわかるように,この取決めは領邦教会制の法的な是認を意味していた。プロテスタントの主権者がその領域内の教会財産・修道院領を接収し,教会統治権を掌握する,このような国教会体制は,ドイツのほか,ルター主義を受け入れた北欧の諸王国においても実現された。
カルビニズムの登場
アウクスブルクの宗教和議とほぼ同じころ,スイスのジュネーブでは,カルバンによる宗教改革が最終的に勝利していた。人文主義者として出発し,ルフェーブル・デタープルらの福音的ヒューマニズムの影響下に信仰を形成したカルバンは,1530年代に本格化したフランス王権による福音主義への弾圧を前にスイスへ亡命し,《キリスト教綱要》(1536)いらいプロテスタンティズムの第2世代を指導する地位へと押し上げられた。G.ファレルの要請でジュネーブ教会の改革運動に投じた彼は,信徒の共同体の意味における個別教会の自律を重んじ,その機関として長老の制度を導入する一方,ルター派が保持していた司教(監督)制度を廃止することにより,新しい型の改革派教会の形成をはかった。神の主権性を強調し,信徒の生活のきびしい倫理的規律を要求するカルバンの改革理念は,その不寛容のゆえにさまざまな反対勢力との闘争を余儀なくされたが,強靱な意志力をもってついにこの危機を切り抜けた。現世における〈神の栄光〉の実現をめざす行動主義は,反宗教改革の旗手たるイエズス会と戦闘的性格の点で類似しており,ジュネーブに創設された神学校は,スコットランドの宗教改革者ノックスをはじめ,多くの有能な宣教者の養成を通じて,プロテスタンティズムの拡大に大きな役割を果たした。カルビニズムは,伝統的社会秩序を重んずるルター派に比べると,資本主義的な営利活動の肯定,カトリックの君主に対する政治的抵抗を容認するなど,より自由主義的な性格をもっており,勤労者層のほか貴族の間にも支持を得て,フランスのユグノー戦争や,スペインの支配に対するネーデルラントの独立運動(八十年戦争)などで,その戦闘的なエネルギーを実証した。なお,イングランドでは,ヘンリー8世の時代に,もっぱら政治的動機から教皇権よりの独立,国教会体制の移行がはじまったが,プロテスタントの教義の受容はエドワード6世治下のことであり,主教制と独自の礼拝形式をもつアングリカニズムの確立は,メアリー女王のカトリック反動を経て,エリザベス1世の時代に持ちこされた。正統なカルビニズムの立場から,この国教会体制を批判する長老派教会は,さまざまな迫害をうけつつも勢力を伸ばし,ピューリタンと呼ばれる非国教徒の主流を形成してゆく。
執筆者:成瀬 治
イギリス宗教改革と国教会の成立
イギリス宗教改革とは,イギリスの教会に対するローマ教皇の宗教的・司法的・財政的諸関係を断ち切り,教皇の支配から教会を解放した国家の行為であった。ロラード派の運動や国民の間に広まっていた反聖職者感情,ルター主義の移入,またW.ティンダルの英訳聖書の刊行(1525)など宗教改革を可能とした原因・背景を数えることもできるが,この宗教改革を成立させるために作用した国家の役割は決定的であった。
大法官ウルジー枢機卿がヘンリー8世とキャサリンの離婚問題処理に失敗したあと,教皇庁への脅迫,そして国王による教会支配の方向が現れ,1533年の上訴禁止法(あるいは上告禁止法)によって,教皇とイギリスの関係は決定的な段階を迎えた。この法は,遺言・結婚・離婚訴訟等が国王司法管轄権内で処理されることを命じ,教皇座・外国法廷からの召喚,またそれらへの上訴を禁じ,国王離婚問題を王国内で処理することを当面の目的とした。しかもこの法には,国王による聖俗の一元的支配,国家統一が明示され,イギリスが主権国家であることを宣言して,外国主権者からの独立が主張されていた。こうした宗教改革,英国国教会(アングリカン・チャーチ)の成立は国家主権の宣言と連動したできごとであり,34年の国王至上法(あるいは首長令)によってローマ教会からの離脱の総仕上げが行われた。ついで36年と39年の2回にわたって修道院解散法が出,全修道院財産の没収が行われた。その理由としては国家財政強化説が有力であって,没収修道院領は漸次売却されて,主としてジェントリーの富を豊かにした。36年の小修道院解散法が議会を通過してまもなく,北部諸州で〈恩寵の巡礼〉と呼ばれる農民反乱がおこり,宗教改革,修道院解散の反対を唱えつつ,囲込み反対,農民保有地の保全を要求したが,鎮圧されてしまった。この時期の国教会の教義は〈十ヵ条〉(1536),《主教の書》(1537)にみられ,保守・改革両派の対立の結果,カトリック,プロテスタント両要素が混在している。他方,トマス・クロムウェルによって2回にわたって出された〈国王指令〉(1536,38)では,ルター的宗教改革とエラスムス的教会・社会改革が併用され,国教会のよりいっそうの改革をめざした。これに対し,すでに1521年教皇から〈信仰の擁護者〉という称号を得たほどの反ルター主義者ヘンリー8世は宗教改革の進展を好まず,ノーフォーク公,ガードナー主教と組んで39年〈六ヵ条法〉を通過させ,化体説・一種聖餐communion in one kindの確認,聖職者の結婚禁止など保守化を強め,翌年にはクロムウェルを処刑した。ヘンリー8世の志向する宗教改革は教皇抜きのカトリシズム,あるいは島国カトリシズムといえる。
プロテスタントとして教育されたエドワード6世が1547年王位につくと,摂政サマセット公は〈六ヵ条法〉を撤廃し,聖職者の結婚を認め,49年の礼拝統一法によって第1祈禱書が確定され,52年ノーサンバーランド公支配下ではより改革的な第2祈禱書が出,翌年T.クランマー大主教はプロテスタント的な信仰箇条〈四十二ヵ条〉を出した。
メアリー1世が即位(1553)するとカトリック復帰がおこり,議会はエドワード6世期の諸法律を廃して47年当時へ戻し,さらに54年の議会はヘンリー8世期の反教皇的諸法律を退けて,宗教改革前の状況を回復した。ただし没収修道院領回復の企ては多額の補償金を必要としたため議会の賛成するところとならず,失敗に終わった。55年から翌年にかけてクランマー,H.ラティマー,N.リドリー,J.フーパーらの改革派聖職者が異端として火刑に処せられた。
エリザベス1世期(1558-1603)には形勢はもう一度逆転し,59年の国王至上法によって女王は国教会の〈至上の統治者〉となり,礼拝統一法によってエドワード第2祈禱書を改正して新祈禱書を確定し,63年には四十二ヵ条を改訂して〈三十九ヵ条の信仰告白〉を作り,71年の議会はこれを承認可決した。
アイルランドに関しては,1536年ヘンリー8世はアイルランド議会で国王至上法を決議させ,さらに60年エリザベス1世も国王至上法と礼拝統一法を成立させて国教会を強制したが,抵抗は大きく,国教会は主としてアイルランドの中のイギリス化された部分だけにとどまった。
このようにして英国国教会はカトリシズムとプロテスタンティズムの中道を行く教会となり,イギリス人の生活と文化に大きな影響を与えることになった。しかしその中道・中庸性のゆえにこそピューリタンの攻撃を受け,イギリス革命を迎え,やがて王政復古に際して国教会として再生し,現代にいたるわけである。たしかに主権国家形成期に成立した国教会は,国家教会という形で宗教改革を実現した。したがって国家と教会の緊密性は避けがたく,しばしば体制教会として立ち現れたわけで,将来,国教会制度が廃止されるときが来れば,そのときにおいてこそイギリス宗教改革ははじめて完成するといえるであろう。
執筆者:栗山 義信
宗教改革と近代世界
宗教改革運動は,文化の領域におけるルネサンス運動とさまざまにからみ合いつつ,近代ヨーロッパの形成に大きな役割を演じた。ナショナリズムと結びつく聖書国語訳の普及や,〈万人祭司主義〉に対応する聖職者の身分的特権の否認,修道院制の廃止と教会財産の接収,俗人信徒の職業労働の宗教的評価,〈良心〉の自律性に示される個人主義などは,それぞれの意味で,生活諸分野の近代化の推進力となった。しかし,〈政教分離〉ないし〈信教の自由〉の実現という点では,ルター派,カルバン派を問わず,統治権力や領域主義と結びつき体制化した正統プロテスタント教会は,さしあたりその障害となり,宗教戦争や〈魔女狩り〉の激発に力を貸した。この面でのキリスト教の近代化や,新しい科学的世界観の成立に対しては,ルネサンス文化の潮流と並んで,正統プロテスタント教会から異端視された再洗礼派などの,より個人主義的な諸セクトのほうが,長期的にみて重要な意義をもっていたといえる。
→カトリック改革 →反宗教改革
執筆者:成瀬 治
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「宗教改革」の意味・わかりやすい解説
宗教改革
しゅうきょうかいかく
Reformation 英語
Reformation ドイツ語
Réforme フランス語
中世カトリック教会を分裂させ、プロテスタント諸教会を樹立させた16世紀の教会改革をさす。
中世カトリック教会は、14世紀の教会の大分裂(シスマ)によって普遍的権威を失い、ボヘミアではフスによる教会改革をつきつけられていた。コンスタンツ公会議(1414~1418)はシスマの解決=教会全体の統一とフスの処理に一応成功したが、教会全体の改革には失敗した。その後、神学者、神秘主義者をはじめ各方面から改革要求が提示されたが、カトリック教会は世俗的栄華・権勢を求め、教義の形骸化、聖職者の腐敗を改められなかった。
ルターに始まる16世紀の宗教改革は、新しい信仰原理に基づく改革を図ったが、結果的にキリスト教会を分裂させ、プロテスタント教会を樹立させることになった。この宗教改革運動は、カルバンの登場により新展開をみて、ヨーロッパ各地に広がってゆく。そのころヨーロッパの主要各国では、中央集権的国家が形成されつつあり、この形成過程に宗教改革運動は繰り込まれざるをえなかった。各国の政治事情によってその展開様相はさまざまな変化をみせるが、国王権力の絶対化に貢献する場合もあれば、国の独立運動の思想的主柱になったり、良心の自由を生み出し、近代化に貢献する側面もみられた。
[森田安一]
ルターの改革
カトリック教会は、救いに至る道が秘蹟(ひせき)のなかにあるとし、とくに悔悛(かいしゅん)の秘蹟が人間を贖罪(しょくざい)に導く出発点とみなしていた。その贖罪は善行によって獲得されるが、それを容易化するために、贖宥状(しょくゆうじょう)が考案されていた。1515年、教皇レオ10世はローマのサン・ピエトロ教会の建設のために贖宥を告示し、ドイツでの贖宥状販売を許した。「箱の中へ投げ入れられた金がチャリンと鳴るや否や、魂が煉獄(れんごく)から飛び上がる」(『九十五か条の論題』27条)と誇大宣伝をされて売りまくられた。ルターは、人々が贖宥状を購入することによって、あらゆる罰と罪責から解放され、確実に救済される、と信じたことに宗教的危機を感じた。金銭による贖宥状の購入という安易な行為には、「悔い改め」というキリスト者の基本的行為がまったく無視されていたからである。宗教改革運動の引き金となった『九十五か条の論題』(1517)は、ローマによるドイツの財政的搾取を問題としただけではなく、新しい信仰原理の提示であった。その第1条において、ルターはキリストが「信ずる者の全生涯が悔い改めであることを欲した」とし、第36条では、真実の痛悔が「罰と罪責よりの完全赦免」であると主張した。さらに、第28条では救済は「ただ神の御心にのみかかっている」と主張した。人はただ信仰によってのみ義とされ(義認説)、その信仰のよりどころは聖書以外にない(聖書主義)とする確信である。この確信は、さらに万人司祭主義を引き出す。『ドイツ国民のキリスト教貴族に与う』(1520)において、ルターは「すべてのキリスト者は真に教会的身分に属し、相互の間に職務上の区別以外になんの差別もない」とし、神と人との仲介者としての特別な身分特権をもった聖職者階層の存在を否定した。こういった根源的な主張は、カトリック教会体制の土台を崩すことになった。1519年にカトリック神学者エックと行ったライプツィヒ討論会において教皇の教義上の権威と公会議の無謬(むびゅう)性を否定し、1520年には教皇の破門脅迫状を公然と焼却し、1521年にはウォルムス国会(帝国議会)における皇帝カール5世の面前での審問にも信念を変えず、帝国追放処分刑を受けた(ウォルムス勅令)。このような信念に基づくルターの英雄的行為は、ドイツ国民の各身分、階層に支持され、改革運動は国民的運動に展開するかにみえた。しかし、帝国追放刑を受けたルターは、彼の国主ザクセン選帝侯フリードリヒ賢侯の保護を受け、ワルトブルク城に一時身を隠してしまった。
選帝侯の保護とは裏腹に、国民各階層はこのころよりルターの教説を独自に解釈し、ルターから離反することになった。ルターのお膝元(ひざもと)であったウィッテンベルクでは、1521年カールシュタットが教会慣習の具体的変革を目ざし、いわゆるウィッテンベルク騒擾(そうじょう)を引き起こした。1522年にはジッキンゲンに率いられた帝国騎士が「騎士の乱」を起こし、1524年には農民戦争(ドイツ農民戦争)が勃発(ぼっぱつ)した。農民たちは村落による牧師の任免権、十分の一税の廃止、農奴制の廃止、諸負担の軽減、共有地の確保などを、聖書を盾に要求して、蜂起(ほうき)した。当初、ルターは農民の要求を全面的には否定しなかった。部分的には農民の肩をもち、領主側に譲歩を求め、仲裁裁定的解決を提案していた。しかし、ミュンツァーがチューリンゲン地方の農民を率いて、社会体制の変革を目ざしていると気づくと、農民の徹底的弾圧を諸侯に呼びかけた。『反乱を起こす霊の持ち主についてザクセン諸侯へ』(1524)ではミュンツァーの暴動的性格を説き、『農民の殺人、強盗団に抗して』(1525)では領主たちを鼓舞激励して反乱農民の徹底的殺戮(さつりく)を唱えさえした。農民たちの主張、行動は、霊的事柄と世俗的事柄の混同にあり、両者の明確な区別のうえにたてられたルターの世界観に反していたからである。
ルターは、1525年には人文主義者の雄エラスムスともたもとを分かった。「人文主義なくして宗教改革なし」といわれるように、当初人文主義者はルターを支持し、共同戦線を張っていた。しかし、ルター破門が確定するころより、人文主義者たちは、ルターを支持する者とカトリックにとどまる者とに分かれていったが、エラスムスの『自由意志論』(1524)、それにこたえたルターの『奴隷意志論』(1525)の応酬によって両者は決定的に離別した。このように国民各階層がルターの改革運動から離脱すると、改革運動は領邦諸侯と緊密に結び付いていった。
ドイツ農民戦争後の混乱を収拾するために開催された1526年のシュパイエル国会において、「一般公会議あるいは国民会議の開催まで」という条件付きではあるが、諸侯は「神と皇帝に対し責任がとれるものと期待し、確信するように、自らで生活し、統治し、事態を処理すべき」という決議がなされた。この決議に基づいて、ルター派諸侯は領内の宗教的整備に積極的に取り組んだ。ザクセン選帝侯領内では『巡察者のための訓令』(1527)を発布し、ルター派神学者のなかから巡察者を任命し、領内の宗教、教育事情を視察させて、宗教的統一を図った。この巡察教会制度は、宗教的統一を通じて同時に領内の政治的安定を確保することももくろまれ、事実上の領邦教会体制の樹立につながっていった。以降、宗教改革は領邦諸侯に主として担われて展開をみる。
[森田安一]
ツウィングリの改革
ドイツの宗教改革は、ルターの個性とその思想を抜きにしては語れない。しかし、彼の思想を伝えた群小の改革者を無視しても成り立たない。なかでも南ドイツに大きな影響を与えたスイスの宗教改革者ツウィングリは注目に値する。彼は都市チューリヒにおける宗教改革を完成したが、以前にはスイス人文主義の流れにたつ人物であった。エラスムスに強く共鳴し、キリスト教的人文主義の立場から聖書中心主義を唱え、「キリスト教再生」を考えていた。ツウィングリは、「私たちの地方の人が誰(だれ)もルターの名を聞くはるか以前の1516年に、私はキリストの福音(ふくいん)を説教し始めました」と主張し、ルターとは別個に信仰による義認を再発見して改革に取り組んだことを強調している。ルターの影響を無視できないとしても、エラスムスの「キリスト教再生」の立場を絶対的に必要な宗教改革の前段階と彼がみなしていたことは明らかである。ルターとエラスムスの決定的な対立を知った現代からではなく、1520年前後の時代にたって宗教改革と人文主義の関係をみるとき、両者の濃密な関係を否定することはできないであろう。
また、ツウィングリの改革方式は、都市の市民的、政治的伝統に適合的であった。「都市は宗教改革運動の母体、本来的な社会基盤とみなさねばならない」(メラー)と説かれているが、チューリヒの宗教改革は、都市における最初の成功例であった。したがって、チューリヒの改革方式は他の諸都市の見習うところとなった。その改革方式は、公開討論会方式といえるものである。都市は領邦諸侯の場合とは異なり、縦の支配関係ではなく、横の仲間的団結に基づく政治が基本軸であった。宗教改革を実施する場合にも、たてまえのうえでは市民の総意に基づいてという仲間的関係にのって行われる必要があった。それを実現する方式が、公開討論会である。都市の政治を決定する拡大市参事会の面前で多数の聖職者、神学者、学識者を集めて改革の可否を聖書に照らして討論させ、その討論の経過、結論を受けて、拡大市参事会が都市内の秩序と平和維持を図りつつ改革を決める方式である。これは、まさに万人司祭主義の原理を実現し、カトリック教会から自立して俗人たる市民も参加して改革を推進できる方式でもあった。しかし、いったん結論が引き出されると、都市当局者は改革者と協力して上からの改革統一を図って新教会を樹立していった。この方式は、南ドイツ、スイスの諸都市に導入され、都市の宗教改革が進展した。
一方、改革者と都市当局者とが手を携えた形で改革が行われることに不満を抱き、徹底的な改革を速やかに行うべきことを主張する人々が現れた。ツウィングリを取り巻くチューリヒの若い知識人たちが徹底した聖書主義と急進的改革とを求めて始めたこの運動は、悔悛(かいしゅん)した者たちのしるしとして再洗礼(成人洗礼)を実施して、再洗礼派運動としてまたたくまに都市民衆や農民戦争敗北後の鬱屈(うっくつ)した状況にいた農民の心をとらえていった。南ドイツではフートHans Hut(1490ころ―1527)、フープマイアーBalthsar Hubmaier(1480ころ―1528)などの活躍が注目されるが、伝播(でんぱ)する過程で神秘主義、千年王国思想などの影響を受けてさまざまな傾向が生まれた。しかし、この運動はカトリック、プロテスタント両派の諸侯、都市当局に一致して弾圧された。典型的な例としてミュンスター千年王国事件(1533~1535)があげられる。
[森田安一]
宗教改革の政治化
宗教改革は、民衆的性格を弱めるにつれて、政治的闘争の色を濃くしていった。ツウィングリは「キリスト教都市同盟」を結成し、カトリック勢力に対抗した。ルター派諸侯の雄であったヘッセン方伯フィリップPhilipp von Hessen(1504―1567)は、プロテスタントの政治的大同盟結成を図り、そのために1529年にルター、ツウィングリらの神学者をマールブルクに会合させ、神学的一致を達成させようとした。この試みは失敗したが、皇帝カール5世は1530年にアウクスブルクに国会を開催して、宗教分裂の解決に乗り出してきた。ルターは帝国追放刑の身で公式の場に姿を現せなかったので、彼の片腕メランヒトンが「アウクスブルク信仰告白」をまとめ、帝国議会に提出した。カトリックとの教義上の相違をできる限り少なくした努力のかいもなく、皇帝の回答はローマ教会への復帰命令であった。このウォルムスの勅令の再実施により、1531年5月15日までにローマに服するように勧告が出された。この危機に直面してルター派諸侯は「シュマルカルデン同盟」を結んで政治的に結集し、軍事的に皇帝とカトリック諸侯に抵抗する構えを示した。カトリック側も、1538年に「ニュルンベルク同盟」を結成し、結局シュマルカルデン戦争が勃発するに至った。
1546年にルターが死亡し、プロテスタント諸侯の武力の中心者であったザクセン侯モーリッツの裏切りもあって、プロテスタント側は敗北した。皇帝は1548年に「仮信条協定」を帝国法として発布したが、部分的妥協を示していたとはいえ、信仰による義認を認めなかったので、「仮信条協定」はプロテスタント側にも評判の悪いものであった。しかし、プロテスタント側の衰微は甚だしく、皇帝は勝利に酔った。ところが、勝利の勢いにのって、息子のフィリップを帝位継承者に選ばせ、スペインとドイツを恒久的に結合させようとするに及んで、カトリック諸侯も反皇帝の姿勢をみせた。このような状況のなかで、モーリッツは再度寝返り、新教側にたって皇帝を攻撃した。皇帝軍は敗北し、1555年にアウクスブルクの和議を締結するに至った。この結果、領邦君主はカトリックかルター派かのどちらかの宗派を選び、それを臣下に強制する権利が認められた。帝国都市は、両派併存が認められ、どちらか一方に決めることは許されなかった。しかし、その場合でもツウィングリ派、カルバン派、再洗礼派を選ぶ信仰の自由はなかった。
[森田安一]
カルバンの改革
ルター、ツウィングリの改革が、結局は国家教会体制の樹立に終わったのに対して、カルバンによるジュネーブの宗教改革が新しい型の改革を展開した。彼は、都市ジュネーブにとってはよそ者であり、市民的、都市政治的伝統の外にたっていた。ツウィングリのように都市当局との癒着状態はおきず、生涯を通じて都市当局と緊張、対立関係を維持した。カルバン神学の特徴である教会(宗教)と国家(政治)の分離、区別の外的条件がここにあった。そのうえに、彼の神学思想が作用した。彼は自律的教会訓練、「不品行者を教会から除外、または治癒、矯正する方策」を教会に確保することに心血を注ぎ、教会政治の職制としての「長老制」を確立させた。それにより、市民は厳しい公共道徳を要求され、市民生活の隅々まで厳格な規律が求められた。これはカルバンの予定説教義の一側面でもあった。人間の救いは神が予定しており、人間は神の道具にしかすぎないという考えである。神に選ばれ、救いに予定されていれば、市民生活も当然に神の意にかなう規律正しいものであり、隣人愛に燃え、徹底して隣人に尽くすはずだという前提である。カルバン思想の集大成である『キリスト教綱要』(1536年、決定版は1559年)は神の聖なる教えとして市参事会によって認められ、ジュネーブの宗教改革は確立をみた。
一方、カルバンの教えはおもに新興市民層、中産的生産者層に担われて各国に広まり、スコットランドではプレズビテリアンズ(長老派)、イングランドではピューリタン(清教徒)、フランスではユグノー、オランダではゴイセンとよばれる教派を形成した。カルバン派の勢力より優勢な宗派が存在したこれらの国々では、彼らは「神の道具」意識に基づき、積極的な行動主義をとった。能動的抵抗運動を展開し、信仰の自由のために、あるいは民族運動と結合し国の独立のために戦い、ヨーロッパ近世の歴史を動かした。フランスからの独立運動と絡んだスコットランドの宗教改革は、ノックスに指導された。彼は、亡命中にカルバンを知り、故郷にカルバン的宗教改革をもたらし、自ら『スコットランド信仰告白』を起草した。オランダでは、スペインの過酷な支配から独立する運動と宗教改革運動とが結合した。1566年、カルバン派の教会会議は蜂起(ほうき)を支持し、血みどろの戦いが行われた。北部地方はユトレヒト同盟に結集して、あらゆる信仰強制に対する抵抗が誓われ、最終的にカルバン派の厳しい教会規律が打ち立てられ独立も達成した。フランスでは、宗教改革は王権と貴族の政治闘争に完全に巻き込まれた。1572年のサン・バルテルミーの虐殺(2万~5万人)にもかかわらず、ユグノー教徒は貴族と同盟し、教会の組織化も着実に進めていった。1598年のナントの王令で、改革派教会もしばらく容認されることになった。
[森田安一]
イギリスの宗教改革
イギリスの宗教改革の発端は、宗教的要素よりも政治的要素や国王の離婚問題にあり、他国とは異なった経過をたどった。チューダー朝第2代目の国王ヘンリー8世は、1521年にルター批判の書『七秘蹟(しちひせき)の確立』を著し、教皇から「信仰の擁護者」の称号を受けるほどであったが、王后キャサリンとの離婚を教皇に許可されなかったため、一転してローマ教会からの分離を宣言した。いわゆる宗教改革議会(1529~1536)を開催し、多数の反ローマ的議会立法を成立させた。1534年には「国王至上法」(首長令)を制定して、国王は「イギリス教会の地上における最高の首長」となった。教会組織面では、カトリック教会から分離してイギリス国教会(イングランド教会)が成立したが、教義や儀式面では「六か条法」(1539)に典型的に見られるようにカトリック的であった。しかし、次王エドワード6世の治世には、「アウクスブルク信仰告白」を規準とした「四十二か条信仰告白」(1553)が定められ、「一般祈祷書(きとうしょ)」(1552)により、母国語による統一的な礼拝様式も定められた。クランマーの手によって教義のプロテスタント化が行われたのである。ところが、エドワードが早世し、ヘンリー8世に離婚させられたキャサリンの娘メアリー1世が1553年に登位すると、ふたたびカトリック化が行われた。メアリーは、スペインのフェリペと結婚する(1554)と、異端取締法を復活させ、クランマーら高位聖職者を含め多数の者を処刑し、「血に飢えたメアリー」とあだ名された。
次のエリザベス1世は、中間の道を選び、イングランド教会(イギリス国教会)を確立させた。1559年に「国王至上法」と「礼拝統一法」を制定したが、前者はヘンリー8世のときと同様に教会に対する王権の優位が定められている。しかし、今度の場合、国王は「聖俗両面での最高の統治者」と規定され、国王の祭司的権威が薄められている。「礼拝統一法」はエドワード6世の「一般祈祷書」を復活させたものであるが、ここでも反カトリック的性格は弱められている。1571年には「四十二か条信仰告白」を要約した「三十九か条信仰告白」が議会で裁可された。「四十二か条信仰告白」とは異なり、もはやそれほど宗教改革的とはいえず、イギリス教会の伝統が表出している。「三十九か条」は、今日なおイギリス国教会の信仰基準となっている。エリザベス1世の中道主義は、平安の道を歩んだわけではない。国教忌避者はカトリックだけではなく、ピューリタンのなかにもいた。1560年代からまさに非難の意味を込めてピューリタンとよばれたカルバン教徒は、教会への国家の影響行使に同意せず、国教会の内部に長老会制度の樹立を企てた。さらには、単一教会の自律性を主張した会衆派が生まれ、そのなかの分離派は国教会からの分離、独立の教会組織を目ざした。そのため、「国教忌避者処罰法」(1593)の制定により、徹底して弾圧された。しかし、ピューリタンを制圧しきることはできず、ピューリタン革命によってイギリス国教会は大きく揺さぶられることになる。
[森田安一]
『R・H・ベイントン著、出村彰訳『宗教改革史』(1966・新教出版社)』▽『G・R・エルトン著、越智武臣訳『宗教改革の時代』(1973・みすず書房)』▽『R・シュトゥッペリヒ著、森田安一訳『ドイツ宗教改革史研究』(1984・ヨルダン社)』
百科事典マイペディア 「宗教改革」の意味・わかりやすい解説
宗教改革【しゅうきょうかいかく】
→関連項目アン・ブーリン|ウィッテンベルク|ウィーン大学|騎士戦争|宗教戦争|マロ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宗教改革」の意味・わかりやすい解説
宗教改革
しゅうきょうかいかく
Reformation
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「宗教改革」の解説
宗教改革
しゅうきょうかいかく
Reformation
ルターの九十五か条の論題提起(1517)に始まり,アウグスブルクの宗教和議(1555)で一応の解決がみられた。領主権力でもある教会の搾取に対する農民の不満,人文主義者らによる教会の権威や伝統に対する批判,魂の救済を求めるカトリックの内部改革の動きなどが底流にあり,ウィクリフ・フス・サヴォナローラらが改革の先駆となった。贖宥状の効力に関するルターの九十五か条の論題に端を発した改革運動は,教皇や皇帝と対立し,貴族や農民の支持をえて動乱に発展した。ドイツ農民戦争(1524〜25)は失敗に終わったが,改革派諸侯によるシュマルカルデン戦争(1546〜47)ののち,アウグスブルクの宗教和議が成立し,領邦内におけるルター派の信仰選択の自由が認められた。宗教改革の精神はさらにツヴィングリ・カルヴァンによって全ヨーロッパに広まり,特にカルヴァン主義の禁欲的な生活倫理は,フランスのユグノー,イギリスのピューリタン,オランダのゴイセンなど,当時新興の中産的産業市民層に信奉され,資本主義の発展を促す倫理的要素となった。これらの宗教改革運動に対応して,カトリック内部でも改革が行われた。イギリスでは,ヘンリ7世により絶対主義が成立し,教会もウィクリフの革新運動などにより王権の下に置かれていた。1534年,ヘンリ8世が王妃との離婚をローマ教皇に認められなかったことから,ローマ教会からの独立を決意し,首長法によりイギリス国教会を設立してその首長となり,修道院を解散してその財産を没収した。その後,メアリ1世の時代に一時カトリックにもどったが,エリザベス1世が1559年に統一法を発して,イギリス国教会が確立した。しかし,その改革は政治的なもので,教義や儀式はカトリック的な要素が多く残った。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「宗教改革」の解説
宗教改革(しゅうきょうかいかく)
Reformation[英,ドイツ],Réforme[フランス]
プロテスタント諸教会の起点をなす16世紀ヨーロッパの宗教的・政治的変革運動。神学的には1517年の九十五カ条の論題に始まるルターのカトリック批判を土台とし,「信仰と功績と」ではなく「ただ信仰のみ」を旗印とする福音主義を打ち立てた。14~15世紀におけるウィクリフやフスの教皇制攻撃はある意味でその先駆をなすが,ライプツィヒ討論以来,教皇権や教会法の否定を通じて,修道院の解消を伴う世俗権力と教会との新たな領域的結合がもたらされる。司祭の宗教的特権にもとづく客観主義的なサクラメント教会の代わりに提唱された,聖書のみを信仰の究極的規範とする主体的な平信徒の共同体としての教会理念は,さしあたり国家権力による教会支配を招き,その対極に再洗礼派を分出した。これと並んでとりわけカルヴァンの指導のもとに,説教と聖餐を中心とする自律的な教会生活が組織され,世俗内禁欲(予定説)と結びついた宗教的職業倫理は,広く西欧のブルジョワジーに担われつつ,近代資本主義社会の成立に際し重要な精神的・主体的要因となるが,その過程における神秘主義やヒューマニズムの思想的影響も無視できない。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「宗教改革」の解説
宗教改革
世界大百科事典(旧版)内の宗教改革の言及
【イクナートン】より
…在位,前1364年ころ‐前1347年ころ。宗教改革者。アクナトン,アケナーテンともいう。…
【イギリス】より
…アメリカおよびその影響を受けた日本では,政教分離が自明の理と考えられているが,ヨーロッパでは長い間,一つの国(あるいは領邦)には一つの教会しか認められなかった。したがって,〈イングランドの教会〉は,宗教改革まではローマ・カトリック,その後ピューリタン革命まではアングリカン・チャーチ,共和政時代までは長老派教会,王政復古後はまたアングリカン・チャーチと内容を変えた。このような変化はすべて議会の制定法によって行われた。…
【カルバン】より
…フランス出身の宗教改革者。姓はもとコーバンCauvin,当時の教養人の例にならってラテン語化してカルウィヌスCalvinus,さらにフランス読みにしてカルバンという。…
【キリスト教】より
…さらに,この宗教を形づくっている教会・教派についていうと,1世紀の原始キリスト教は2世紀に入ってローマ帝国内の制度的教会(古カトリック教会)となり,これがのちに東方正教会とローマ・カトリック教会とに分かれて各自展開をとげていった。ローマ・カトリック教会からは,宗教改革によってプロテスタント教会が分かれ出た。これはルター派教会と改革派教会,およびスコットランドの長老派教会をもっている。…
【敬虔主義】より
…三十年戦争の悲惨な体験がきびしい罪意識を生み出し,真に福音的・ルター的な信仰の再起をうながした。16世紀の〈宗教改革〉の結果が主知主義的正統主義となり,教会は領邦教会として形骸化していったとき,いわば新たな宗教改革が意図されたのである。宗教改革は〈信仰義認〉を唱えたが,敬虔主義の標語は〈生きた信仰・再生〉であった。…
【信教の自由】より
…これらの動きはすべて異端として断罪され,したがって宗教的真理に立った主張とは認められなかった。 16世紀に至って宗教改革は西欧の宗教を二分し,旧来の宗教に対して互角の論陣を張ったため,その主張が宗教的根拠を持たぬものであると断定することはもはやできなくなる。すなわち,宗教についての考え方が多元化しはじめた。…
【ドイツ】より
…しかし西部ドイツの領域では,領主制は,土地領主制,体僕領主制,裁判領主制などに分かれ,一円的支配領域を形成しにくい状況にあった。こうしてドイツは11~12世紀から大空位時代を経て宗教改革を迎えるときにいたってもなお,神聖ローマ帝国という擬制的帝国の名の下で実質的には割拠する諸侯の支配(ランデスヘルシャフト)の下におかれ,これらの諸侯も領域(ラント)内において中世末までは都市を完全に掌握するだけの力をもっていなかったのである。しかしながら,これらの領域支配圏のみが実質的には中世後期から近世にかけてドイツ国家の実体をなしており,このことは領域内の私闘(フェーデ)を禁止し,平和の確保を目的とするラント平和令がラントの範囲内でまず出されていたことにも示されている。…
【プロテスタンティズム】より
…16世紀の宗教改革にはじまり,そこから発展・分化したキリスト教の一群を包括する名称。ローマ・カトリック教会,東方正教会とならぶ,キリスト教の三つの大きな流れの一つ。…
【読み書きそろばん(読み書き算盤)】より
…また,15世紀中葉J.グーテンベルクによって金属活字印刷術が発明され,ヨーロッパの各地に続々と印刷工房が生まれたが,手写本と比較してはるかに安価に製作された印刷本にしても,当初は教会や学者・学生を対象にしたもので,その大半は民衆の日常生活とは無縁のラテン語書で占められていた。ラテン語教育
[16~18世紀]
民衆の読み書きそろばんの歴史において著しく貢献したのは,宗教改革以後のプロテスタント教会とカトリック教会である。プロテスタント教会は聖書の理解に基づく個人的信仰の確立をめざし,聖書の母国語への翻訳を行い,これを読ませるために民衆教育の普及に積極的に取り組んだ。…
【ヨーロッパ】より
…キリスト教国家の理念というものがそれである。しかしながら16世紀には北ヨーロッパでルターに始まる宗教改革が進行し,互酬関係を教義のなかに取り込んだカトリック教会の救済理論を打ち破った。現世で善行を積めば来世での救いが保障されるという教義はルターによって大きな変更を加えられた。…
【ルター】より
…ドイツの宗教改革者。農民の出で鉱夫であったハンス・ルターHans Lutherの子として中部ドイツのアイスレーベンに生まれる。…
【ルネサンス】より
… 第3に,ルネサンスが近代思想・科学の定礎であるとする見方に対しては,その当否が争われているが,それとは別個に,そうした系譜論的議論の方法ではなく,文化全般を同時代の社会の構造の内部において分析しようとする構造論的理解法が提起される。すなわち,とりわけ,後にみるように,15,16世紀には,ルネサンスと並行して宗教改革,大航海などの諸活動が進行しており,これらの時代的全要素のなかにルネサンスも定置すべきである,また先にみた社会的背景をも考慮にいれて,文化運動全体の論理的構造を,同時代性(サンクロニーsynchronie)のなかで完結してとらえることが先決だ,とするものである。以上の3点が,旧来のルネサンス観への修正として唱えられる。…
※「宗教改革」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...