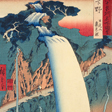精選版 日本国語大辞典 「日光」の意味・読み・例文・類語
にっ‐こう‥クヮウ【日光】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙 日の光。太陽の光線。
- [初出の実例]「早驚二春気一禅林臘先負二日光一定水氷」(出典:菅家文草(900頃)五・感雪朝)
- [その他の文献]〔北史‐孝文昭皇后伝〕
- [ 2 ]
- [ 一 ] 「にっこうぼさつ(日光菩薩)」の略。
- [初出の実例]「日光、月光、皆たち給へる御姿どもなり」(出典:栄花物語(1028‐92頃)鳥の舞)
- [ 二 ] 日光市を中心とした日光国立公園を含む一帯の地域の総称。
- [ 三 ] ( 男体山(なんたいさん)の別名二荒山(ふたらさん)を「にこうさん」と音読したものの変化という ) 栃木県西北部の地名。奈良末期に四本龍寺(のち輪王寺)、二荒山神社が開かれてから発展。江戸時代は東照宮の門前町として栄えた。男体山、中禅寺湖、東照宮、輪王寺などがあり、自然美と人工美に富み、市域の大部分が日光国立公園に含まれる。昭和二九年(一九五四)市制。
- [ 四 ] 短歌雑誌。大正一三年(一九二四)四月創刊。北原白秋、土岐善麿、古泉千樫、木下利玄、川田順、釈迢空ら約三〇人が結集、閉鎖的なアララギ派の写生歌に対し、短歌の文学性を拡大、歌壇に新風を送ったが、昭和二年(一九二七)通巻三八巻で終刊。
- [ 一 ] 「にっこうぼさつ(日光菩薩)」の略。
改訂新版 世界大百科事典 「日光」の意味・わかりやすい解説
日光[市] (にっこう)
栃木県北西部の市。2006年3月今市(いまいち)市,旧日光市と足尾(あしお)町,藤原(ふじわら)町および栗山(くりやま)村が合体して成立した。面積1450km2は市としては高山市,浜松市に次ぐ全国3位の広さ。人口9万0066(2010)。
足尾
日光市南西端の旧町。旧上都賀(かみつが)郡所属。人口3248(2005)。渡良瀬川最上流域の足尾山地を占める。わたらせ渓谷鉄道線(旧JR足尾線)が通じる。1610年(慶長15)に発見され,江戸幕府直轄の銅山として栄えた足尾鉱山を中心に発達した鉱山町で,鉱山は明治初期に古河鉱業(現,古河機械金属)の経営に移ったが,大正中期の最盛期には人口3万8000人を数え,県内では宇都宮市に次いだ。明治中期には足尾鉱毒事件が起こり,大正期にかけて労働争議が頻発した。1973年に鉱山は閉山となり,1965-75年に人口は半減した。製錬所は引き続き輸入鉱石の製錬を行っている(79年の足尾線廃止により操業停止)。78年に日足トンネルが開通し,日光との連絡が便利になり,鉱山の歴史を坑内に展示した銅山観光や,坑内から湧出した温泉,また鉱滓を原料にした足尾焼の生産など,鉱山の遺産をもとにした観光開発が進んでいる。西部の日光国立公園の庚申山には特別天然記念物の食虫植物コウシンソウが自生する。東部の古峰ヶ原高原は前日光高原県立自然公園に属する。
執筆者:千葉 立也
今市
日光市南東部の旧市。1954年市制。人口6万2047(2005)。中心集落今市は鬼怒川の支流大谷(だいや)川が作る扇状地の扇頂部に位置し,近世には日光道中(現,国道119号線)の宿駅として栄えた街村集落である。旧街道沿いには特別史跡,特別天然記念物として有名な杉並木がある。明治以降は国鉄(現JR)日光線(1890開通),東武日光線(1929開通),鬼怒川線(1920年に下野軌道として開通)の分岐点として,また日光地方,鬼怒川上流地方などに対する地方中心都市として発展してきた。また県内有数の木材集散地で,家具,線香などの林産関係の工業や食品加工業などが盛んであり,近年は,電気機械,化学などの工業も進出している。
執筆者:桜井 明久
今市宿
下野国の宿場町。日光道中,日光例幣使街道(壬生(みぶ)通り),会津西街道が合し,日光の入口にあたる。1617年(元和3)徳川家康の廟が日光山内につくられ,将軍が日光社参をするようになって,宇都宮城主本多正純により,宇都宮城下を経由して日光に至る日光道中が開かれ,それが壬生通りと合するところに作られたのが,今市宿である。20年,将軍秀忠が寄進した〈日光山領〉に今市700石とあるのが,史料上の初見である。宿の町並みの北側に文明年間(1469-87)の開基と伝えられる如来寺があるが,その門前集落などが移ったのではないかと考えられる。将軍はじめ諸大名,公家,庶民の日光参拝,遊覧などでにぎわうとともに,会津方面の山村からは炭や木材などを,駄賃稼ぎ馬(中附駑者(なかつけどちや))で送り出してくるなど,地域の商業の中心地となった。17世紀中ごろ,日光山領の中心として,御蔵(米倉)が建てられ,穀屋も多かった。1696年(元禄9)には宿の家数186軒,ほかに水呑百姓が37軒という記録がある。幕末,二宮尊徳が日光山領の農村復興にあたり,1855年(安政2)報徳役所が建てられ,翌56年,彼はそこで病没した。1889年,周辺8ヵ村をあわせて町制をしく。
執筆者:河内 八郎
栗山
日光市北部の旧村。旧塩谷郡所属。人口1933(2005)。鬼怒川および支流湯西川の最上流域を占め,福島県,群馬県と接する。平家の落人伝説が残る隔絶山村で,第2次大戦中の鉱山開発,電源開発を契機に,自動車道路が通じた。村域のほとんどは国有林を主体とする山林で,ダイコンの高冷地栽培や,シイタケなどの栽培が行われる。鬼怒川に建設された川俣ダムの川俣湖南岸に川俣温泉があるほか,湯西川沿いに湯西川温泉,鬼怒川最上流に手白沢,日光沢などの奥鬼怒温泉郷があり,道路の整備とともに観光客がふえている。手白沢温泉の奥に湯沢噴泉塔(天)がある。
執筆者:千葉 立也
日光
日光市南西部の旧市。1954年市制。人口1万6379(2005)。市域の大部分は鬼怒川支流の大谷川とその支流の流域にあり,南の一部は黒川流域に含まれる。90%以上が山地からなり,大谷川の北は日光火山群,南は足尾山地の北限にあたる。西部には,日光火山の主峰男体(なんたい)山があり,その南麓には中禅寺湖と湖から流出する大尻川(大谷川)にかかる華厳滝が,西麓には戦場ヶ原があり,景勝地に恵まれ日光国立公園の中心をなす。奈良時代末期,勝道によって開かれた修験道の聖地で,二荒山(ふたらさん)神社,輪王(りんのう)寺があり,近世初期日光東照宮の造営と日光道中の整備により,2社1寺の門前町として発達した(なお1999年に2社1寺は〈日光の社寺〉として世界文化遺産に登録された)。市街地は東部の大谷川沿いにあり,神橋を境に門前町の東町(出町)と,東照宮造営の際に形成された職人町として生まれ,明治以降は別荘地であった西町(入町)からなる。明治以降は外国人の来訪も多く,明治初期にはすでに洋式ホテルがつくられた。1890年国鉄(現JR)日光線,1929年東武日光線などの開通により,東京からの日帰りも可能となり,東武鉄道資本による観光地形成がすすんだ。第2次大戦後,アメリカ軍の休養施設としてホテル,スキー場などが接収されたことなどを契機として国際観光都市に発展。
大谷川と左沢川の合流点にある清滝町には,細尾峠越えで結ばれる足尾鉱山と大谷川水系の水力発電の動力によって立地した古河電工日光精銅所,古河アルミニウムがある(現在はともに古河電工日光事業所)。旧日光市は,産業別就業人口率で第3次産業が65%(1990)を占める観光都市であるとともに,金属工業を中心に第2次産業が32%を占める工業都市でもあるが,73年の足尾鉱山の閉鎖などにより近年はふるわない。日光彫の膳椀,日光下駄などの伝統工芸品も特産する。
執筆者:平山 光衛
歴史
日光東照宮の門前町,日光道中の宿駅として発達した。日光の地名は,古くからこの地方の山岳信仰の中心であった男体山をめぐる自然を仏説の補陀落(ふだらく)山に見立てた勝道が,8世紀の末に四本竜寺(のちの輪王寺)を建て,同時に山神の二荒神をまつったのに始まる(のちの二荒山神社)。12世紀になると二荒を日光と音よみにするようになったが,このころから日光は天台宗系の修験の道場として繁栄し,16世紀初めには門前町の存在が確認できる。1617年(元和3)東照社がここに移されて以来,町は社をはさんで東西に拡張され,将軍,公家以下の社参者の宿泊,幕府や諸大名の御手伝普請による造営によって繁栄した。1791年(寛政3)までは日光山目代山口氏の支配であったが,以降は日光奉行が管轄した。
執筆者:高木 昭作
藤原
日光市北東部の旧町。旧塩谷郡所属。人口1万0684(2005)。鬼怒川と支流の男鹿(おじか)川最上流域の山間地を占める。鬼怒川沿いに鬼怒川温泉,川治温泉があり,東武鬼怒川線により東京や日光と結ばれるため,関東でも有数の温泉観光地になっている。竜王峡など鬼怒川の渓谷や五十里(いかり)湖,日塩もみじラインなど,日光国立公園の特別地域に指定された景勝地も多い。就業人口の過半数がサービス業に従事する。明治末期から電源開発事業が進められ,五つの発電所がある。鶏頂山山麓の開拓地ではイチゴの促成栽培のほか,ダイコン,ホウレンソウなど高冷地野菜の栽培が行われている。かつて越路鉱山から銅を産出した。東武鬼怒川線終点の新藤原駅と会津鉄道線会津高原駅を結ぶ野岩鉄道線,国道121号線(会津西街道)が通じる。
執筆者:千葉 立也
日光 (にっこう)
栃木県北西部,旧日光市(2006年の合併以前の自治体)を中心とする地域の通称。日光火山群の南部,大谷(だいや)川水系の中・上流地域にあたり,現在の日光市の旧今市市の一部も含む。華厳滝より上流の奥日光,下流の表日光(口日光)に分けられる。また,日光火山群の北,鬼怒川上流の日光市の旧栗山村を裏日光(奥鬼怒),旧日光市南部から鹿沼市北西部,日光市の旧足尾町東部を含む足尾山地北部を,前日光と呼ぶこともある。表・奥・裏日光は日光国立公園に含まれ,前日光は県立自然公園に指定されている。日光は雄大な自然に恵まれた地であり,また男体(なんたい)山を中心に奈良時代末期に勝道によって開かれた山岳仏教の聖地で,近世には徳川家康をまつる日光東照宮の造営により栄え,国宝などに指定された建築物や文化財も多い。このため〈日光を見ずして結構というなかれ〉とまでいわれ,日本を代表する観光地の一つとして国際的にも知られている。
表日光は日光市街地を中心にした大谷川沿いの地域で,かつては神仏習合の〈日光山〉と総称された二荒山(ふたらさん)神社,東照宮,輪王(りんのう)寺の2社1寺とその門前町を含み,華美な彫刻のほどこされた東照宮陽明門をはじめ人工美にあふれ,かつては〈日光詣〉でにぎわい,今も日光観光の中心地にあたる。また市街の北,赤薙(あかなぎ)山南麓の霧降(きりふり)高原はニッコウキスゲの群落や紅葉で知られ,板穴川にかかる霧降滝(落差75m)は,華厳滝,裏見滝とともに日光三名瀑に数えられる。
馬返~中宮祠(ちゆうぐうし)間の坂は道路のカーブが48あったことから,いろは48文字にちなんでいろは坂と名付けられた。1872年(明治5)に男体山の女人禁制が解かれるまでは,この坂が結界であった。1954年の改修によりカーブの数は減ったが,交通量増加に伴い65年上り専用の第2いろは坂が建設され,両坂合わせて48のカーブが数えられている(上り・下りとも84年無料開放)。いろは坂より西部が奥日光にあたり,表日光とは対照的に雄大な自然景観が広がり,華厳滝,男体山,中禅寺湖などの景勝地がある。中禅寺湖の北にはシラカバ,ズミ,カラマツ,ミズナラなどの樹林に囲まれた高層湿原の戦場ヶ原が広がる。西の小田代ガ原,北の三岳山麓の蓼(たて)ノ湖,涸沼なども戦場ヶ原と同じように日光火山群による堰止湖が埋積し湿地化したものである。白根山東麓の湯ノ湖北岸には,勝道発見と伝えられ,近世までは中禅寺別当の支配・管理下にあった日光湯元温泉(硫黄泉,45~73℃)がある。近くには湯元スキー場があり,1965年金精(こんせい)峠下をトンネルで抜けて群馬県利根郡片品(かたしな)村の菅沼と結ぶ金精道路(95年無料開放)の開通により,奥日光の観光拠点として発展した。
裏日光は鬼怒川の水源地にあたる秘境で,川俣温泉,奥鬼怒温泉郷がある。奥日光からは山王峠を越える道路が川俣温泉に通じている。鬼怒沼山(2141m)の溶岩台地上にある鬼怒沼は標高2000mを超え,日本では最も高所にある湿原の一つで,周囲にはコメツガ,トウヒ,オオシラビソなどの自然林がある。前日光は薬師岳から夕日岳,横根山,粕尾峠にいたる山稜の東側の高原地帯を指し,傾動地塊とみられる足尾山地北部の緩傾斜面にあたる。中心の古峰原(こぶがはら)は勝道が修行をつんだ地で,男体山,女峰山,白根山などの日光連山や富士山,南アルプスなどが眺望できる。大芦川上流の古峰(ふるみね)神社はかつては日光修験者の道場で,天狗信仰で知られ,関東,東北などに広い信仰圏をもつ。
執筆者:平山 光衛
信仰
日光はかつては関東地方における代表的な修験道の道場であった。日光の名称は1138年(保延4)の清滝(きよたき)寺の大般若経奥書,41年の《中禅寺私記》を初見とする。それ以前は二荒山と呼ばれており,〈二荒〉を音読することによってニコウ,日光に変化したとする見解が一般的である。しかしフタアラがなぜニコウと音読されるようになったかは,その背景として太陽崇拝,日輪崇拝が説かれているものの問題として残る点であり,さらに二荒の名称起源に関しては諸説がある。空海の書とされる《沙門勝道歴山水瑩玄珠碑幷序》に男体山を指して〈補陀落山〉と記されているところから,日光山が観音の補陀落(ふだらく)浄土とみなされ,それがフタラク,フタアラに転じたとする説が最も有力である。しかし,アラを現れると解し,男体・女峰の2神が出現したことに由来するという見解も捨てがたく,《滝尾建立草創日記》には,中禅寺の鬼門に洞窟があり,年2回の大風が吹き出し,寺などを荒らすので二荒と称していたが,この地に来た空海が祈禱によって風を鎮め,二荒を日光に変えたとする伝説が記されている。また都賀郡の布多郷から〈布多の荒山〉となったという説もある。
執筆者:宮本 袈裟雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「日光」の意味・わかりやすい解説
日光(市)
にっこう
栃木県北西部に位置する国際観光都市。1954年(昭和29)日光町が小来川(おころがわ)村を編入して市制施行、2006年(平成18)今市市(いまいちし)、上都賀(かみつが)郡足尾町(あしおまち)、塩谷(しおや)郡栗山村(くりやまむら)、藤原町(ふじはらまち)を合併。地名のおこりには諸説があり、僧空海が書いた勝道上人(しょうどうしょうにん)碑文は男体山(なんたいさん)を補陀落山(ふだらさん)と記し、これに二荒(ふたら)の字をあて、「にくゎう」と読み、日光をあてたとするのが通説となっているが、『滝尾(たきのお)建立草創日記』によると、中禅寺(ちゅうぜんじ)の鬼門の洞穴から年2回大風が吹き出し、国内を荒らしたので二荒といった。空海がこれを鎮め二荒を日光と改名したとする説もある。人口7万7661(2020)。
[平山光衛]
自然
北は帝釈(たいしゃく)山地を境に福島県、西は鬼怒(きぬ)川源流域の山々や、白根山(しらねさん)(2578メートル)、皇海山(すかいさん)などを境に群馬県と接する。いずれも2000メートル級の山々である。南は1000~1500メートルの足尾山地北縁部にまたがる。面積1449.83平方キロメートルは県下一位。森林面積は市域面積の約8割を占める。市域の北部は鬼怒川の上流域で温泉地帯を成す。その南には日光火山群と大谷(だいや)川流域が広がる。日光火山は女峰山(にょほうさん)、男体(なんたい)山、大真名子(おおまなご)山、小真名子山、太郎山、白根山などからなり、その美しい山容に加えて、中禅寺湖(ちゅうぜんじこ)、湯ノ湖などの湖沼や湿原、滝など優美な自然景観に恵まれ、その大部分が日光国立公園区域に含まれる。南部の薬師岳・地蔵岳の一帯は前日光県立自然公園に含まれる。2000メートル級の山岳地帯から500メートルほどの市街地まで標高差が著しく、気温は市街地で年平均約12℃、中禅寺湖畔では年平均7℃、8月は19℃と避暑に向いている。
[平山光衛]
交通
JR日光線、東武鉄道日光線、鬼怒川線、第三セクターの野岩鉄道(やがんてつどう)、わたらせ渓谷鉄道が通じる。国道119号が宇都宮に、120号が奥日光金精(こんせい)トンネルを通って群馬県沼田に、121号が今市を通って鹿沼(かぬま)、北部の山王トンネルで福島県会津地方に、122号が足尾を通り沢入(そうり)トンネルを抜けて群馬県桐生に通じる。有料の自動車専用道の日光宇都宮道路が清滝(きよたき)と宇都宮を結び、鬼怒川上流域の温泉地帯と塩原温泉郷(那須塩原市)をつなぐ鬼怒川有料道路が整備されている。
[平山光衛]
歴史
弥生(やよい)時代すでに集落が形成され、古墳時代の遺物も出土している。勝道上人が782年(延暦1)二荒山登頂に成功し、山麓(さんろく)の中禅寺湖(南湖)畔に神宮寺を創建し、日光開山は神仏習合の山岳信仰の地としての展開をみた。鎌倉時代は関東北方の鎮めとして日光山は幕府の信仰が厚く、室町時代にも修験道(しゅげんどう)の隆盛などで繁栄し、連歌(れんが)師宗長(そうちょう)は「院々僧坊五百に余り」と記した。豊臣(とよとみ)秀吉の小田原(おだわら)攻略に際し、日光山衆徒は北条氏に加担したため、中世以来の社領の大部分を没収され、急速に衰えた。僧天海(てんかい)が日光山貫主となり、1617年(元和3)徳川家康の遺骸(いがい)が久能(くのう)山から日光に移葬されてからふたたび繁栄した。とくに寛永(かんえい)の造営によって東照宮は面目を一変して、現在みる精巧華麗を極める建造物となり、「日光を見ずに結構というな」の名言を生んだ。明治維新後、神仏分離によって二社一寺に解体され、江戸時代幕府の聖地とされた特権は失われたが、人工の美は残り、これが、もとからの自然山水の美観とともに国立公園法指定の原動力となった。南西部の足尾では1611年(慶長16)から銅の採掘が始まり、足尾銅山は幕府の御用銅山となった。明治に入って古河(ふるかわ)鉱業(現、古河機械金属)の鉱山町として発展したが、1973年(昭和48)閉山となった。
[平山光衛]
産業
産業別就業者構成比は第一次産業5.3%、第二次産業28.5%、第三次産業66.2%となっており(2010)、観光中心ではあるが、工業都市の性格もあわせもつ。古河(ふるかわ)電工日光事業所のある清滝地区の金属工業のほか、食料品製造や伝統工業の日光彫、日光下駄(げた)、湯葉などの特産がある。
[平山光衛]
観光
表日光の日光東照宮、二荒山神社、輪王寺をはじめ、霧降高原(きりふりこうげん)、奥日光の山岳、湖、滝、鬼怒川、日光湯元などの温泉資源、足尾の銅山観光などもあって、国際的観光地として著名であり、年間約1150万人(2000~2010年)の内外観光客が訪れる。表日光地区が俗に「東武県古河(ふるかわ)市二社一寺町字日光」といわれるところに観光地としての一面をみることができる。日光杉並木街道附(つけたり)並木寄進碑は特別史跡および特別天然記念物に、「華厳瀑(けごんばく)および中宮祠(ちゅうぐうし)湖(中禅寺湖)湖畔」は国名勝に指定されている。なお、二荒山神社、日光東照宮、輪王寺は、1999年(平成11)に「日光の社寺」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。
[平山光衛]
『『日光市史』全3巻(1973~1979・日光市)』▽『『日光市史 史料編』全3巻(1986・日光市)』
日光
にっこう
短歌雑誌。1924年(大正13)4月~27年(昭和2)12月。37冊を発行。創刊同人は北原白秋(はくしゅう)、前田夕暮(ゆうぐれ)、石原純(じゅん)、古泉千樫(こいずみちかし)、折口信夫(おりくちしのぶ)(釈迢空(しゃくちょうくう))、川田順、木下利玄(りげん)、土岐善麿(ときぜんまろ)、吉植庄亮(よしうえしょうりょう)ら。発行所日光社(初め鎌田敬止(かまたけいし)、のち四海民蔵(しかいたみぞう)方)。大正末期の結社分立のなかで、当時の有力歌人が結社の枠を超えて自由な親しい気分で結集し、他ジャンルとの交流、口語歌の試作、随筆、研究などにも精力的に活動した特色ある同人誌。大正から昭和への転形期の歌壇をリードしたが、一面において、島木赤彦中心の閉鎖的な『アララギ』体制への反運動としての性格をもつ。白秋系と夕暮系同人の増加と不一致のため消滅した。
[前田 透]
百科事典マイペディア 「日光」の意味・わかりやすい解説
日光[市]【にっこう】
→関連項目今市[発電所]|下野国|日光|日光道中
日光【にっこう】
→関連項目日光御成道
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「日光」の読み・字形・画数・意味
【日光】につこう(くわう)
 に堂
に堂 に在りて立つ。日光
に在りて立つ。日光 中より之れを照らし、
中より之れを照らし、
 (しやくしやく)として熱し、后東西に之れを
(しやくしやく)として熱し、后東西に之れを くるも、光
くるも、光 ほ斜照して已(や)まず。是(かく)の如きこと數夕、后自ら之れを怪しむ。
ほ斜照して已(や)まず。是(かく)の如きこと數夕、后自ら之れを怪しむ。字通「日」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「日光」の解説
日光
にっこう
古来,神仏習合・山岳信仰道場の地として知られ,奈良末期に勝道上人によって開かれた。1617年徳川家康の神廟が建てられて以来,日光奉行管轄下に門前町として繁栄。東照宮・大猷廟(家光の廟)・輪王寺・二荒山 (ふたらさん) 神社などがある。江戸時代,将軍や諸大名の参詣が絶えず,大いににぎわった。1954年市制を施行。1999年,二荒山神社など2社1寺と境内地,周辺地帯は世界遺産に登録された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「日光」の解説
日光 にっこう
近江(おうみ)(滋賀県)園城(おんじょう)寺の僧といわれる。喜多古能の「仮面譜」によれば,仮面十作(じっさく)のひとり。翁(おきな)面を得意とし,作品に「父尉(ちちのじょう)」などがある。
デジタル大辞泉プラス 「日光」の解説
日光〔道の駅〕
日光〔バラの品種〕
動植物名よみかた辞典 普及版 「日光」の解説
日光 (ニッコウ)
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の日光の言及
【折口信夫】より
…この山道を行きし人あり〉を含む歌集《海やまのあひだ》(1925)に結実する。《アララギ》と別れた迢空は24年北原白秋,古泉千樫らと《日光》同人になり,さらに鳥船社を結成して活躍を続け,太平洋戦争に養子折口春洋(はるみ)を硫黄島でうしなう悲傷を歌った《倭(やまと)をぐな》(死後出版,1955)まで,旺盛な作歌意欲を示した。句読点をほどこすなど,短歌形成とそれに内在する律動との関係をつきつめ,そればかりでなく長歌や自由律の詩作にも筆を染めて,《古代感愛(かんない)集》(1947,これによって翌年芸術院賞受賞)など3冊の詩集を編んでいる。…
【影】より
…記紀神話には案外なほど中国神話や中国古代思想からの影響因子が多く,冒頭の〈天地開闢神話〉からして《淮南子(えなんじ)》俶真訓,天文訓などを借用してつくりあげられたものであり,最小限,古代律令知識人官僚の思考方式のなかには中国の陰陽五行説がかなり十分に学習=享受されていたと判断して大過ない。しかし,そのように知識階級が懸命になって摂取した先進文明国の〈二元論〉哲学とは別に,いうならば日本列島住民固有の〈民族宗教〉レベルでの素朴な実在論思考のなかでも,日があらわれれば日光(ひかげ)となり,日がかくれれば日影(ひかげ)となる,という二分類の方式は伝承されていたと判断される。語源的にも,lightのほうのカゲは〈日気(カゲ)ノ義〉(大槻文彦《言海》)とされ,shadeやdarknessを意味するヒカゲは〈祝詞に日隠処とみゆかくるゝを略(ハブ)き約(ツ)ゞめてかけると云(イフ)なり〉(谷川士清《和訓栞(わくんのしおり)》)とされている。…
※「日光」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...