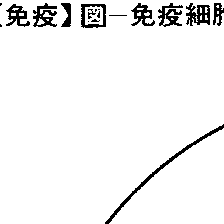翻訳|immunity
精選版 日本国語大辞典 「免疫」の意味・読み・例文・類語
めん‐えき【免疫】
- 〘 名詞 〙
- ① ( ━する ) ある特定の病原体、またはそれが出す毒素に対して、生体が特異的に抵抗性をますこと。また、その状態。伝染病にかかったあとに得られるものと、病原体あるいはその毒素から精成したワクチンの注射をうけて得られるものとがある。また、先天的に備わったものもある。
- [初出の実例]「幸ひこの種痘は善感し、局部の発疱によりて免疫(メンエキ)するに至った」(出典:江戸から東京へ(1922)〈矢田挿雲〉八)
- ② 転じて、物事がたび重なるにつれて慣れてしまうことのたとえ。
- [初出の実例]「恋せざる男女は種痘せざる人の如し。何時如何なる処にてその病素に中らんも知れず、危し。されどその免疫期間は極めて短し、或は全く無き人あり」(出典:病牀録(1908)〈国木田独歩〉三)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「免疫」の意味・わかりやすい解説
免疫
めんえき
immunity
免疫の免とは、元来は税を逃れる意の免税とか、兵役から免除される意の免役などとして使われ、なんらかの義務から自由になるという意味をもつ語であった。しかし、近世になるとこの語が医学の領域に持ち込まれ、疫病から逃れる意味の「免疫」となり、さらに細菌またはウイルスなどの感染から免れる、または予防する意味として使用されるようになった。そして今日のライフサイエンス(生命科学)の観点からは、生体防御機構の重要な因子としての位置づけがなされている。なお、免疫現象を解明するための学問を免疫学immunologyとよぶ。
[辻 公美]
免疫学の歴史
古代から経験的に、ある特定の病原体の感染を受け、これから回復した患者は、まったく同じ病原体に対して抵抗性を有することが広く知られていた。たとえば古代ギリシアでは、ペストが猛威を振るって次々に多くの死者を出したとき、すでにペストにかかって、しかも治癒した人のみが病人の看護をしたといわれている。また、15世紀の中国やアラブ諸国においては、天然痘(てんねんとう)(痘瘡(とうそう))の患者の膿(うみ)を接種したり、あるいはその痂皮(かひ)(かさぶた)を粉末にして吸入させたりして、重症にならないようにするという試みがなされていた。18世紀に入ると、イギリスの医師E・ジェンナーは、牛痘(ウシに痘疹(とうしん)のできる病気)に感染した乳搾りの女性は痘瘡にかからないことを知り、牛痘を人為的にヒトに接種することにより、天然痘を予防することに成功した。すなわち、1796年5月14日、8歳の牧童に牛痘を接種し、人為的に免疫を行い、天然痘に対する免疫を獲得させたわけである(これを獲得免疫という)。フランスの細菌学者L・パスツールは、このジェンナーの業績を記念するため、「種痘操作」に対してワクシネーションvaccinationの語を与えた。これは免疫原として使用した牛痘の元であるワクシニアウイルスvaccinea virus(vaccaはウシの意)の名をとったものである。
さらに19世紀末には、R・コッホ、パスツールにより病原微生物が分離され、純粋培養ができるようになると、伝染病の原因も明らかとなった。これに伴ってニワトリコレラ、炭疽(たんそ)、狂犬病などの予防法も開発された。そして1881年、一度伝染病にかかっても、さいわいに回復できると、二度と同じ伝染病にかからないという、いわゆる「二度なし現象」とよぶ免疫の概念がパスツールによって提唱された。現在では、分子レベルでの研究が進み、多くのことが解明されたが、当時においては、この二度なし現象がどのような機序(メカニズム)でおこるかは明らかでなく、細胞説と体液説とが対立していた。今日の細胞性免疫の考え方を初めて唱えたのはロシアの細菌学者E・メチニコフといわれ、彼は細胞の貪食(どんしょく)機能の研究結果から、この機能が免疫現象に重要な位置を占めることを主張した。
1890年、ドイツの細菌学者E・フォン・ベーリングと北里柴三郎(きたさとしばさぶろう)は、ジフテリアおよび破傷風菌に対する抗毒素がヒトの血清中にあることを発見し、免疫の本体が抗体の存在であることを明らかにした。これ以降、血清学(抗原抗体反応)は黄金時代を迎えることとなった。血清反応は、初めは細菌に対する抗体の反応と考えられていたが、やがて、病原微生物に限らず卵白や動物血清などのタンパク質に対しても血清反応がおこることが証明された。この結果、なんらかの免疫反応をおこし、抗体をつくる物質を抗原と総称するようになった。このような歴史を経て、20世紀の免疫学の基礎が築かれたわけであり、今日の驚異的な近代免疫学の進歩へと発展するのである。
[辻 公美]
免疫の成り立ちとその構成因子
一般に免疫反応をおこす生物は、自分のものでないもの、つまり、なんらかの異物(これを非自己という)に出会うとこれを抗原と認識し、その体内に複雑多岐にわたる機構が働く。異物に対しては特異的な反応が生じ、抗原抗体反応がおこるわけである。この反応は、その生体にとってプラスになる場合とマイナスになる場合とがあるが、いずれも生体の防御反応となっている。これを生体の抵抗性という面からみると、生まれながらにして保有するもの(自然免疫)と、抗原にさらされて初めて獲得するもの(獲得免疫)とがある。この抗原と抗体との対応は厳密に特異性があり、これはよく「鍵(かぎ)と鍵穴」の関係に例えられる。
免疫系(一連の免疫現象)は単純化して考えると、その免疫反応の主体性によって細胞性と体液性(液性)とに二大別され、簡単にいえば前者ではリンパ系細胞、後者では抗体分子が主役をなしている。一般にはこの両者の反応がおき、正常な生体の免疫反応が成立する。免疫系の中枢臓器は胸腺(きょうせん)、骨髄、リンパ節、脾臓(ひぞう)などであり、おおよそリンパ球は1012個(1兆個)、抗体分子は1020個という超天文学的な数で全身を回っている。また、抗原は無数に存在しうるため、これに対応して無数の種類の抗体がつくられていると考えられる。免疫学の進歩によって、いかにしてそれぞれの特異的な免疫反応が成り立つかがしだいに明らかにされつつある。この免疫系は、よく指揮者と個々の演奏者とからなるオーケストラに例えられる。つまり、指揮者(免疫反応)と個々の担当者(リンパ球と抗体分子)とがそれぞれの機能を果たしたうえ、全体性との調整によって、よりよい調和を保つというわけである。
免疫を担当、ないしは免疫に関連する細胞群は、リンパ系細胞、形質細胞、網内系細胞、骨髄系細胞からなり、リンパ系細胞はさらにT細胞、B細胞、NK細胞などに判別される。そしてさらにT細胞は、サプレッサーsuppressorT細胞、ヘルパーhelperT細胞、ディレイドタイプdelayed-type反応性T細胞、キラーkillerT細胞などに細分されている。また、これらの細胞群は、細胞表面の特異物質あるいは単クローン性抗体(モノクローナル抗体)によって種々の機能的な分類が可能となっている。抗体はリンパ系の抗体産生細胞から産生されるが、血清中のグロブリンタンパクに属している。この免疫グロブリンにはA、G、M、D、Eの五つの種類が明らかとなっており、それぞれに特異的な機能を有している。
[辻 公美]
CD分類と免疫
ヒト白血球分化抗原Human Leucocyte Differentiation Antigensに関する国際ワークショップが1982年に開催され、CD(Cluster of Differentiation)分類が用いられるようになった。当初、CD分類は字のごとく、白血球表面抗原に対する抗体の分類を目的としたものであったが、現在では細胞表面抗原または分子に対するものまで含まれる。したがってCD抗原すべてが免疫に関係していない。
たとえば、T細胞系に関するものとして、CD1、2、3、4など、B細胞系にはCD10、19、20、21など、骨髄球・単球系に対してはCD13、14、15など、血小板にはCD9、31、36、41など、NK細胞にはCD12、44、45、46など、血管内皮細胞にはCD105、106、109、140など、接着分子としてCD11、18、29、43など、サイトカイン(生理活性物質)レセプター(受容体)はCDw137などがある。
[辻 公美]
抗原認識・抗原提示
分子遺伝学、細胞工学などの急速な進歩により免疫反応の機構が解明され、生体が抗原に接したとき、どのようにして抗原抗体反応がおこるか明らかとなってきた。
外来抗原が生体内に侵入すると、抗原提示細胞Antigen Presenting Cell(APC)であるマクロファージ(大食細胞の一つ)などに食べられ、細胞内で処理され、ポリペプチド(数個~十数個のアミノ酸で構成されている)に分解される。そして宿主のMHC(主要組織適合遺伝子複合体Major Histocompatibility Complex。Major Histocompatibility Antigen。ヒトではHLA=ヒト白血球抗原Human Leucocyte Antigen)クラスⅡ分子(後述「免疫反応と遺伝制御」の章参照)と立体的に結合し、この抗原分子をヘルパーT細胞(CD4陽性T細胞)上のT細胞レセプターT Cell Receptor(TCR)と結合させ抗原認識を完了させる。一方、内在性抗原ペプチドは、小胞体に運ばれながら細胞内処理過程を経て、MHCクラスⅠ分子と結合し、細胞表面に提現され、キラーT細胞(CD8陽性T細胞)に認識される。
[辻 公美]
細胞接着分子と免疫
細胞接着分子(細胞と細胞または細胞と細胞外の基質タンパクとの接着を担う分子を総称する)は、生体内の細胞どうしの恒常性維持に必要である。免疫系においては、リンパ球、好中球などの遊走とか、前述のT細胞の抗原認識過程において細胞相互の接着現象が必要である。
[辻 公美]
免疫反応と遺伝制御
生体はある抗原に対して免疫反応をおこすが、それは遺伝的支配を受けている。このことはマウスなどの実験を通してわかっていたが、合成ポリペプチド抗原をはじめとする種々の抗原に対する免疫応答に関して、マウスの第17染色体のH‐2遺伝子領域の研究が進み、特定の遺伝子の存在も証明された。これを「免疫応答遺伝子」とよんでいる。また、抗体である免疫グロブリンも抗原性を有することが明らかとなり、同種免疫によって証明される免疫グロブリンの抗原特異性を「アロタイプ」とよんでいる。現在、このアロタイプの遺伝的多型性を指標として免疫グロブリンの遺伝学的研究が進められている。ヒトの免疫応答遺伝子はHLA遺伝子と連鎖することが証明され、ヒト主要組織適合遺伝子複合体(MHC)であるHLA抗原のHLA遺伝子群は第6染色体短腕にあり、全遺伝子のほとんどの領域の解明が終っている。概説すると、HLA遺伝子群はクラスⅠ、Ⅱ、Ⅲがあり、さらにクラスⅠはA、B、C、クラスⅡはDR、DQ、DPなどの遺伝子群を有することがわかっており、ヒトの生命現象に関して生物学的意義を有することが明らかとなっている。たとえば、
(1)臓器移植の成否は、提供者(ドナーdonor)と受容者(レシピエントrecipient)とのHLA抗原の一致度に影響されること
(2)HLA抗原と疾病との間には強い相関があるため、疾病の素因、鑑別診断、治療、予後因子、予防に役だつとともに、難病の遺伝要因の解明に利用できること
(3)HLA抗原は多型性を有し、さらに人類学的な差異があるため、人種の起源の検討などの人類学的研究に利用できること
(4)法医学的には親子鑑定などの個人識別に有力な手段として応用されていること
などである。
[辻 公美]
免疫理論の歴史と抗体産生
ある特定の抗原に対して特異的に免疫反応が生じる、すなわち特異的に抗体が生じることは前に述べたが、これがいかなる機序によるものかについては、なおすべてが解明されていない。過去には種々の仮説が提唱された。免疫理論の仮説の歴史に少し触れる。これらの仮説は、現在のところ二大別される。一つはアメリカのハローウィッツF. Haurowitzなどによる「指令説」であり、もう一つはオーストラリアのF・M・バーネットによる「クローン選択説」である。すなわち、前者は、抗原自体が抗体をつくる細胞に直接指令を出すというもので、いわゆるオーダーメイド方式といえる。後者は、抗体はあらかじめ、すでに抗体をつくる細胞に存在するが、抗原は自分に対応する抗体をつくる細胞を選び出し、細胞の分裂増殖を促すというもので、レディーメイド方式といえる。歴史的にみると、「選択説」の前駆をなすのは、1900年、ドイツの血清細菌学者エーリッヒP. Ehrlichによって提唱された「側鎖(そくさ)説」である。これは、生体の細胞には抗原に対応できる側鎖があるとする考え方である。すなわち、もし、ある抗原に対応できる側鎖が存在すると、抗原はその細胞に結合し、その結合物は細胞から離れる。このため、細胞膜には傷ができるが、細胞はその傷を修復するために同じ側鎖をつくり、これを細胞膜外に放出する。この放出された側鎖が抗体であるとするもので、ある意味では選択説の立場にたっている。1971年、免疫学者N・K・ヤーン(国籍はイギリス、デンマークの2か国)は「ネットワーク説」を出したが、この考え方は、バーネットのクローン選択説とともに広く受け入れられている。
種々の仮説は、その後多くの研究成果を経て、分子遺伝学、分子免疫学の技術により、免疫反応および抗体産生機序が明らかとなった。
免疫系が外来抗原を認識して、特異的な免疫反応あるいは応答をおこすには、一つはT細胞抗原レセプター(前述の「抗原認識・抗原提示」の章を参照)と、もう一つは抗体―免疫グロブリンとの関与が必要である。一般に抗体産生をつかさどるのはB細胞系で(T細胞は細胞性免疫をつかさどる)、骨髄の造血幹細胞から産生され分化しさらに成熟する。B細胞は、B細胞表面上のレセプターにより抗原を直接認識し、また一方でT細胞に抗原提示を行う。そして抗原を認識したB細胞は形質細胞へ分化して抗原特異的抗体を産生する。
さらに遺伝子工学技術を用いた免疫グロブリンの遺伝子操作を行うことにより、種々の目的に対応した抗体(たとえばヒト型抗体など)の作成が可能となり、副作用を最小限に抑えた臨床投与が行われ始めた。
[辻 公美]
免疫反応の種類と分類
免疫反応の種類には、(1)自然免疫・獲得免疫、(2)細胞性免疫・液性免疫、(3)高免疫反応・低または無免疫反応(免疫不全ともいわれる)などがある。
免疫反応の異常は、免疫反応の強弱により免疫過剰と免疫不全に分けられる。免疫反応に関与するすべての因子が過剰反応をおこすとき、免疫過剰となり、たとえばアレルギーがおこる。一方、免疫反応低下、またはまったく免疫反応がおきないとき、免疫不全とよばれる。免疫不全には、不全遺伝子(欠損分子)と臨床像により種々の免疫不全症あるいは免疫不全疾患が分類されている。たとえば、アデノシンデアミナーゼAdenosine Deaminase欠損症(ADA欠損症)に対して、その欠損遺伝子であるADA遺伝子を挿入する遺伝子治療が行われ成功を収めている。今後は種々の欠損遺伝子、抑制遺伝子、促進遺伝子などの人体への挿入による遺伝子治療が期待されている。
現在の免疫学において主流をなしているのは、生体防御反応の立場からの位置づけである。一個の生体がいかなる機構のもとで生命維持がなされているかを考えたとき、その生体にとって有利に働く免疫反応と、逆に不利に働く免疫反応とが区別されるが、実際にはこの両者が複雑に錯綜(さくそう)することによって生体防御反応がおこっている。以下、生体防御反応における免疫の種類について述べる。
[辻 公美]
アレルギー(免疫反応による組織障害)
生体の防御に対して不利に働く免疫反応がおこり、体の組織になんらかの障害をもたらすとき、一般にこれをアレルギー(過敏症)とよぶ。つまりアレルギーとは、抗原が一度体の中に入り、なんらかの免疫反応がおきたあと(これを感作(かんさ)されたという)、ふたたび抗原と遭遇しての二次反応が生体にとって不利に作用する場合である。分類的にみると、古くは、この二次反応が数分から30分以内のものを即時型、2日から4日の長時間を要するものを遅延型とよんでいたが、その後、Ⅰ~Ⅴ型に分類されるようになった。
[辻 公美]
自己免疫
生体は自己の体の構成成分に対して免疫反応をおこさないものと考えられていたが、実際にはこの基本原則に反して、自己の構成成分に対してその生体が免疫反応をおこす事実がみいだされた。これが「自己免疫疾患」とよばれるものである。歴史的には1907年、オランダのドナートW. F. Donathとオーストリアのランドシュタイナーによって初めて発見されたもので、両者は、発作性寒冷血色素尿症患者の血清が自己の赤血球を壊すということをつきとめた。自己免疫疾患の代表例としては、橋本病、悪性貧血、重症筋無力症、若年性糖尿病、全身性ループスエリテマトーデス、皮膚筋炎などがあり、ほとんど厚生労働省の難病指定を受けている。
[辻 公美]
腫瘍免疫・癌免疫
20世紀の中葉、癌(がん)の移植実験を行った際、ある系統のマウスにメチルコラントレンなどで腫瘍(しゅよう)をつくり、それがなんらかの手段で縮小したり、切除されたり、治癒したあとで、同じ腫瘍を移植しても移植は成功しないことが発見された。これは、生体内になんらかの免疫反応がおこったためと考えられた。そして、このような抵抗性を導入する抗原を腫瘍特異性移植抗原(TSTA)または腫瘍特異性抗原(TSA)と名づけた。その後の1970年、バーネットは免疫学的監視機構の考えを導入し、腫瘍が免疫学的監視機構から逃れて増殖することができると、癌は発生増殖することがあると説明した。しかし、この点はなお完全には解明されていない。また、アメリカの外科医エバーソンT. C. EversonとコールW. H. Coleは、1900~1960年の間に世界中で確実に癌と診断された患者が、なんの治療も行わないのに自然に癌が退縮・治癒した症例176例を集計報告し、体液中のなんらかの因子が免疫に関与することを想定した。さらに臓器移植の成功例と長期生存例が増えるにつれ、移植後に高頻度に悪性腫瘍が発生すると報告されている。癌の免疫療法には、特異的なものと非特異的なものとがあるが、外科、放射線、化学療法などとともに癌の対策に導入され、効果をあげている。今後は新しい技術の導入により、さらに腫瘍免疫の解明と実用化が期待されており、とくに遺伝子治療、オーダーメイド癌治療が行われようとしている。
[辻 公美]
移植免疫
移植を行うには、つねに提供者と受容者とが必要である。そして、移植免疫は、提供者と受容者との遺伝学的差異により、次の4種に分けられる。
〔1〕自己移植(自家移植) 自分のものを自分に植える場合で、まったく免疫反応(拒絶反応)はおきない。
〔2〕同系移植 一卵性双生児間などの移植で、提供者と受容者で個体は異なるが、遺伝学的には同一であり、拒絶反応はおきない。
〔3〕同種移植 同一種属内(たとえばヒトとヒト)における他人同士の移植であるが、遺伝学的には相異なる者同士の移植であるため、拒絶反応がおきる。いちおう細胞免疫が主体と考えられている。
〔4〕異種移植 相異なる種属間(たとえばイヌとブタ、サルとヒトなど)における移植で、液性免疫が主体をなすとされている。ヒトの提供臓器が絶対的に不足しているため、異種移植、再生医療の臨床応用の研究が盛んである。
一般に移植という場合は、〔3〕の同種移植をさし、これを成功させるには、とくに次の2点がたいせつとなる。
(1)組織適合性検査 提供者と受容者との間の遺伝学的差異をできるだけ少なくして、生体にとって不利な拒絶反応を最小限にとどめるための検査である。ヒトの場合では、HLA‐A、B、C、D、DR、DQ抗原などを一致させるほど、移植の成功率は高くなる。HLA抗原は、臓器移植においては移植抗原としての機能をもつほか、疾患感受性(具体的には疾病の素因、原因、診断、治療、予後、予防を追求するうえでたいせつな因子)、および免疫応答機構を解明するための手掛りとなる。なお、HLA遺伝子は前述したように第6染色体の短腕に位置している。
(2)移植免疫反応の抑制 移植免疫反応を抑える(免疫抑制)には、特異的と非特異的な方法があるが、ともになんらかの手段で生体を免疫学的無反応状態、またはそれに近い状態にさせることが必要となる。具体的には免疫学的トレランス(耐性)、免疫学的エンハーンスメント(促進)などが行われる。この分野も今後の遺伝子工学の導入によって、さらに開発が期待される。
[辻 公美]
免疫血液
現在の外科学の著しい進歩の裏には、さまざまな因子が寄与しているが、とりわけ完全な輸血と麻酔の進歩、および化学療法による感染防止が大である。1901年、ランドシュタイナーは、自分と5人の研究室員の血液から血球と血清を分離し、いずれの組合せにおいて凝集反応がおこるか否かを観察して、今日のABO式血液型(その当時はA、B、C型と命名した)を分類した。1940年、ランドシュタイナーとA・S・ウィーナーは、アカゲザルの血球で、ウサギ、モルモットを免疫して得た抗体によってRh因子を発見した(1937年ごろに研究着手し、1940年発表)。この研究とほぼ前後する1939年、アメリカのレビンP. LevineとステットソンR. E. Stetsonは、25歳の女性が二度目の子供を死産したあと、出血が止まらないため、ABO型の適合した夫の血液を輸血したところ、激しい反応をおこすという臨床例を得た。この反応は抗体によるもの、つまりABO型のものではなく、妊娠による免疫抗体であると判定され、Rh式血液型と同一であるとされた。現在、Rh式血液型は新生児溶血症の原因であることが判明している。
このほか、赤血球の血液型にはMN式(MNSs式)血液型、P式血液型、ケルKell式血液型、ルイスLewis式血液型、ダフィーDuffy式血液型などが発見されている。また、前述したように、白血球にもHLAという血液型があるほか、血小板や血清にもそれぞれ血液型のあることがわかっている。
[辻 公美]
生体の防御機構と免疫および感染免疫
生体の防御機構は自然抵抗性と獲得抵抗性とによって支配されるが、さらに獲得抵抗性には、細胞性免疫と液性免疫を含む特異的抵抗性と、炎症、インターフェロンなどによる非特異的抵抗性とが考えられている。また、感染防御も生体防御の一つであるため、特異的機序によるものと非特異的機序によるものとが区別される。そして感染免疫にも細胞性と液性のほか、両者による感染防御機構が成立している。
生体反応の恒常性維持については、免疫反応を広義に考える必要に迫られる。すなわちストレスと免疫、栄養と免疫、スポーツと免疫、精神と免疫、生活習慣と免疫、漢方治療と免疫、神経系と免疫、過労と免疫、ホルモンと免疫など、多くの研究課題がある。
感染に対して発症または発病を防ぐ手段として予防接種があるが、この予防接種はこれからの医学(とくに予防医学)にとってたいせつな領域であり、この点に関しては、遺伝子工学の開発により種々の新しい技術導入が行われている。予防接種には能動免疫と受身(じゅしん)免疫(受動免疫)とがある。能動免疫とは、抗原物質またはその病原体を接種して、能動的に免疫反応をおこさせて感染から予防しようとするもので、原則として効果発現までに時間を要する。また、受身免疫とは、抗血清などの投与をさしているが、この場合は即効性はあるが副作用をおこすことがある。このほか、受身免疫の一つとして、感作リンパ球による細胞レベルでの免疫法もある。この分野は細胞工学の新しい技術の導入とともに、今後はさらに発展することが期待される。
既述したように免疫は古典的血清学から近代免疫学へと進み、さらに現在では遺伝子工学、細胞工学などとの関連において研究が急速に進んでいる。具体的には、抗原抗体反応の理論、生体防御機構、分子遺伝学、免疫細胞の相互作用などの各領域において、さらに大きな進歩を遂げようとしている。
[辻 公美]
『山村雄一・多田富雄他著『免疫学入門』(1980・医薬の門社)』▽『狩野恭一著『医学免疫学』(1980・東京大学出版会)』▽『狩野恭一著『免疫学入門――ABCから中心テーマへ』(1980・東京大学出版会)』▽『菊地浩吉・森道夫他著『医科免疫学』(1981・南江堂)』▽『辻公美編著『移植学・分子レベルから臓器レベルまで』(1986・文光堂)』▽『上出利光著『接着分子――免疫反応のコーディネーター』(1995・中外医学社)』▽『笠倉新平編『サイトカイン』第2版(1997・日本医学館)』▽『日本BRM学会編『CD分類ハンドブック――細胞膜分化抗原の国際分類1996』追補版(1998・癌と化学療法社)』▽『菊地浩吉・矢田純一・奥村康編『Annual Review 免疫1999』(1998・中外医学社)』▽『萩原政夫・辻公美著『異種移植概説』(1998・日本医学館)』▽『菊地浩吉編著『周り道免疫学』(1998・メディカルレビュー社)』▽『イワン・ロアット他著、多田富雄監訳『免疫学イラストレイテッド』第5版(2000・南江堂)』▽『テレンス・A・ブラウン著、村松正實監訳『ゲノム――新しい生命情報システムへのアプローチ』(2000・メディカル・サイエンス・インターナショナル)』▽『谷口克・宮坂昌之編『標準免疫学』(2002・医学書院)』▽『小林芳郎他著『スタンダード免疫学』第2版(2003・丸善)』
改訂新版 世界大百科事典 「免疫」の意味・わかりやすい解説
免疫 (めんえき)
immunity
免疫とは,まず字義どおり〈疫を免れる〉仕組み,ことに感染症から免れるための,一連の生体防御機構をさす。その機構の基本となるのは,生体が〈自己〉でないもの,すなわち〈非自己〉を〈自己〉と識別して,〈非自己〉から〈自己〉を守る,という反応能力である。そこから免疫を,単に感染症に対する自然の,あるいは獲得性の抵抗力としてとらえるのではなくて,生体が自己を他のあらゆるものと区別して,その全一性を守る,という生物学的恒常性の一つとしてとらえることができる。このようにとらえると,後述のように,さまざまな生物学的問題に触れることになる。ここでは,〈疫を免れる〉という意味での免疫と,〈自己〉の全一性を守る生物学的恒常性の一つとしての免疫について述べ,その関連性について触れたい。
免疫の歴史と概念
免疫という日本語は,英語のimmunity,あるいはドイツ語のImmunitätの訳語として明治時代から用いられるようになったが,その大もとはラテン語のimmunitasで,ローマ時代に,租税や公役から免除されるという行政上,ことに税制上の言葉であった。これがヨーロッパにしばしば大流行を起こした天然痘やペストなどの厄病から免れるという意味に転化し,医学・医療上の概念としてとり入れられるのである。
伝染病と免疫
伝染病の記載は,前2000年ころのエジプトの記録に現れる。ギリシア時代には,すでに伝染病を耐過するとそれに再びかからないことが,前430-前429年のトゥキュディデスによるアテナイにおける疫病流行の記録に記されている。中世のヨーロッパのペストの流行に際しても,生き残った聖職者が患者を介護しても,もう再びペストにかかることがなかったことが,恩寵(おんちよう)として語られている。
しかし免疫が,ほんとうの意味での医学・医療上の問題として現れるのは1700年代に入ってからで,種痘の登場による。初めは人痘(ヒト天然痘患者の痂皮や膿汁など)が用いられたが,次いで有名なE.ジェンナーによる牛痘(ウシ天然痘のそれら)の人工的接種がなされ,これらによって天然痘に対する免疫能力をつくり出すことができることが発見された。ジェンナーは,当時中国からイギリスに伝わった少量の人痘材料を吸入させるという恐ろしい方法から,1798年に牛痘の膿汁を接種するという画期的な方法を開発し,危険度を低下させ,天然痘に対する免疫抵抗性を与えることに成功した。雌牛すなわちラテン語のvaccaからの材料を使ったということで,免疫を誘導するのに使われる予防接種材料は広くワクチンvaccineと呼ばれるようになった。この種痘の成功と普及によって,1980年には天然痘は地球上から姿を消すに至った。
1800年代には,さまざまな病原細菌が発見され,伝染病が微生物によって媒介されることが明らかにされるようになった。ジェンナーの種痘の実績は,L.パスツールによって,炭疽やニワトリコレラなどさまざまな伝染病に応用されるようになった。ワクチンも,生きた微生物を含んでいる生菌ワクチンから,加熱その他の方法で殺した菌で行う死菌ワクチン,さらに細菌のつくり出すタンパク質や多糖類などでも有効な場合があることがわかり,現代においては有効部分を人工合成した合成ワクチンも登場するようになっている。
抗毒素の発見
この間の重要な発見は,1890年のE.vonベーリングと北里柴三郎による抗毒素の発見である。彼らは,ジフテリアや破傷風などのように,毒素を産生する菌を注射した動物の血液の中には,毒素を特異的に中和する働きをもっている物質が出現することを報告し,この物質が血液中の液性成分,すなわち血清の中に含まれていることを証明した。この血清を投与することによって,ジフテリアや破傷風にかかった患者に劇的な効果を表すことがわかって,いわゆる血清療法の嚆矢(こうし)となった。この物質はやがて,タンパク質であり,試験管内でさまざまな反応を起こし,生体内では感染防御に働く分子であることが明らかになり,のちに〈抗体〉と呼ばれるようになった。これに対し,この抗体産生を誘導する微生物由来の異物,さらには広く〈自己でないもの〉を〈抗原〉と呼ぶのである。抗原と抗体の試験管内および生体内での反応を〈抗原抗体反応〉と呼ぶが,これは免疫反応の重要な要素である。また,生きた微生物だけではなく,その構成成分のタンパク質,多糖類などに対して抗体をつくるという事実の発見は,やがて,自己でないもろもろのもの,異種の動物の赤血球や血液タンパク質,卵や牛乳由来の,もともとは生物にとって有害でない物質や,自分と異なった血液型をもったヒトの赤血球,さらには人工的な化学物質の一部に対してもつくられることの発見につながり,かくして免疫は,〈感染免疫〉,すなわち〈伝染病から免れる〉という最初の疾病学的概念から離れて,生物学上のもう一つの基本概念,すなわち〈自己と非自己の識別機構〉に転化するのである。
細胞性免疫
このようにして,免疫の本体の一つは,抗体というタンパク質の合成ということになるが,もう一つの重要な見解が19世紀末葉に現れる。毒素を中和する抗体という体液性の物質が免疫の本体としてとり上げられる一方,細胞こそが免疫の本体であると考える学説である。上記の免疫の体液説に対して細胞説と呼ばれる。E.メチニコフは,感染を受けた生体から採った白血球やマクロファージ(大食細胞)は,病原微生物を貪食する能力が高まり,それが病原体に対する防御反応として働くと考えた。マクロファージの貪食作用のみを重視したメチニコフの考えは,当時の体液説の前では必ずしも説得力を発揮できなかったが,のちにいわゆる細胞性免疫として一括される,遅延型アレルギー,移植片拒絶反応,接触過敏症,リンパ球による標的細胞破壊など,抗体によらないで免疫系細胞によって起こってくるさまざまな反応が記載されるにおよんで,免疫なる現象のもう一つの大きな側面として再び浮かび上がってくる。
新しい概念の確立
こうして,免疫の重要な二つの側面,抗体による体液性免疫と細胞が直接働く細胞性免疫についての研究が進展し,それぞれについて重要な発見が相次いだ。抗体については,それが抗原と特異的に反応できるタンパク質で,しばしば血清中の他の一連の酵素系(補体)を活性化して,さまざまな生体内反応を起こすこと,試験管内では抗原と結合して沈殿を起こしたり(沈降反応),もし抗原が粒子状抗原であればそれの凝集を起こしたりする(凝集反応),いわゆる〈抗原抗体反応〉を起こすことがわかった。補体を活性化すれば,抗原の溶解や破壊,白血球による貪食を誘導する。抗体分子の構造も解明されて,基本的には抗体は,人間では五つのクラスの免疫グロブリン(IgG,IgM,IgA,IgD,IgE)に属する糖タンパク質であることや,それを決定している遺伝子の興味ある知見なども追加された。
そのうちでも重要なことは,抗体が生体内で抗原と反応すると,抗原を〈非自己〉として排除するように働くばかりでなく,さまざまの生体反応をひき起こすことである。この抗原抗体反応にもとづく生体反応のうちで,個体にとって不利となるような反応を,一般にアレルギーと呼んでいる。血清療法が盛んになって,異種動物,ことにウマの血清を注射すると,数日のうちに蕁麻疹(じんましん),糸球体腎炎,血管炎などの病的反応が起こってくるが,これは注射された血清に対して,生体が免疫反応を起こして抗体をつくり,生体内で抗原抗体反応が起こったためである。これを血清病という。もし同じ血清を2度注射すると激しいショック症状(アナフィラキシー・ショック)を起こして,しばしば死に至る。気管支喘息(ぜんそく)や花粉症なども,吸入によって侵入する抗原に対するアレルギー性反応である。
一方,細胞性免疫では,結核菌体成分で免疫された個体に,その成分,いわゆるツベルクリン液を皮内に注射すると,24~48時間で最高に達する発赤,腫張,硬結などが現れるツベルクリン反応が記載された。アナフィラキシーなどの,抗体によるアレルギーが即時に起こってくるのに対して,反応が時間的に遅延して起こることから遅延型アレルギーと呼ばれる。この種のアレルギーを起こす個体では,抗体は検出されず,また抗体でこの反応を起こすことはできない。これに属する疾患には接触性過敏症がある。また,移植片の拒絶反応も,抗体ができて起こるのではないことがわかった。これらの反応は,免疫系の重要な細胞であるリンパ球やマクロファージの直接の障害作用によって起こる反応であり,それに関与する細胞や,細胞由来の非抗体性の因子のそれぞれも解明されつつある。また,こうした反応が生体内で起こった場合に生起する病的な反応についての理解も進みつつある。
こうして免疫という現象に関与する分子や細胞の働きについての解明が進むにつれて,免疫という現象が,病原微生物のみならず,個体にとって異物であるもの,すなわち非自己に対する生体の総合的な反応であるという見解が定着するに至った。現代の免疫学は,なぜ免疫系が自己と非自己をこのように鋭敏に識別し,細胞性ならびに体液性免疫を発動させて,自己の全一性を守っているのか,さらにこのような免疫応答が,いかなる細胞のいかなる遺伝子における発現によって起こるのか,それを調節している機構は何か,という問いに向かって進みつつある。すでに明らかなように,このように〈非自己〉に対する防衛反応が,誤って〈自己〉に向けられれば,〈自己〉を際限なく破壊するように免疫反応は進むであろう。事実,自己に対して免疫反応が発動して,さまざまな難病(自己免疫疾患)が起こることが知られている。また免疫機構に欠陥が生じれば,生理的な反応を起こすことができずに,生体は無防備状態になってしまう(免疫不全)。ことに,ある種のウイルスが免疫を担当しているリンパ球に感染した場合には,重篤な免疫不全が起こり,しばしば致死的である(後天性免疫不全症候群,AIDS(エイズ)がこの例である)。免疫系の構成,さらにはそれを統御している機構を解明することは,現代の免疫学に与えられた最大の課題である。
獲得免疫と自然免疫
疫を免れるという意味では,個体はもともと自然の抵抗性を備えている。たとえばヒトはイヌのジステンパーにかからないし,ブタはヒトの赤痢菌に対する感染性を生まれつき免除されている。ヒトの癩菌を,特殊な動物以外の実験動物に感染させてハンセン病様の感染症を起こさせることは不可能である。このようにして,それぞれの動物種は,もともとある種の感染症から免れるように生まれついている。そのほかにも,自己でないような異種の細胞やウイルス感染などで変化した細胞が生体内に存在すると,個体は非特異的な液性因子,たとえばリゾチームや補体成分などでそれを破壊しようとするし,ナチュラルキラー細胞natural killer cell(NK細胞と略記)と呼ばれるリンパ球系細胞は,それに初めて出会ったにもかかわらず異物と認めて破壊してしまう。さらに拡大して考えると,O型の人は,輸血を受けたことがないにもかかわらず,もともとA型赤血球に対する少量の抗体をもっているし,自然界に存在するさまざまな抗原物質に対して,これまで接触した経験がないのに,しばしばきわめて微量の抗体をつくりつづけている場合も多い(これを自然抗体という)。これらすべての場合,免疫現象は生まれつき備わった形質によるものなので,それを〈自然免疫〉と呼ぶ。自然免疫がなぜ成立するかについては,いまだに不明の点が多い。
それに対して,免疫一般は,すでに述べたように,感染ないし接触という一つの契機を通して誘導される。たとえば,天然痘の予防接種を受けなければ天然痘に免疫にはならないし,はしかに一度かかって初めて一生はしかにかからない免疫が成立する。この事実を,パスツールは〈二度なしnonrésidive〉現象と呼んだ。実際,細菌などの抗原が初めて侵入すると,しばしの潜伏期をおいてから抗体の合成が始まるが(一次免疫反応),2度目に同じ抗原が入ってきた場合には,即座に抗体合成が始まり,かつ合成される抗体量も一次反応より著しく多い(二次免疫反応)。一次免疫反応によって,生体は二度なし現象を獲得するのだが,それはどうやら,最初の反応によってある能力が獲得的に成立するからと考えられる。このようにして獲得される免疫学的能力を〈免疫学的記憶〉と呼ぶ。免疫学的記憶はしばしば一生の間続き,このようにして成立する免疫現象を〈獲得免疫〉と呼ぶ。
免疫系の細胞
自己と非自己を識別し,非自己に対しては,抗体を合成したり細胞性免疫を起こしたりする免疫系は,複雑な多種類の細胞から成立している。抗原が生体内に入ってきて最初に遭遇するのは,メチニコフが考えたように,マクロファージ(大食細胞)と呼ばれる細胞である。この細胞は,大型で複雑な突起を出しながら遊走する性質があり,生体内のリンパ系組織のみならず結合組織や体腔などのいたるところにみられ,侵入してきた抗原を盛んに貪食する。
ところが,免疫応答はマクロファージだけでは起こらない。免疫応答に関与するリンパ球系細胞群の構成と相互作用を図に要約した。たとえば抗体をつくり出すためには,少なくとも2種類のリンパ球系細胞が関与する。いずれも骨髄の造血幹細胞と呼ばれる祖先細胞から分化したリンパ球と総称される細胞であるが,機能的にはまったく異なっている。一つはT細胞T cellと呼ばれる細胞で,胸腔内に位置する胸腺thymus(T細胞のTはthymusに由来する)に入って,胸腺上皮の影響下で分化した小型のリンパ球で,胸腺を経由したのちはリンパ節,脾臓などの末梢のリンパ臓器の特定の部位(胸腺依存域)に分布する。もう一つの細胞は骨髄bone marrowに由来するという意味からB細胞と呼ばれ,造血幹細胞に直接由来するもので(ただし鳥類では,総排出腔の近くにあるファブリキウス囊の影響下で分化する),末梢リンパ組織に集まった,同じく小型のリンパ球である。B細胞の特徴は,細胞表面に免疫グロブリン,すなわち抗体分子のレセプターをもち,これによって抗原を認識する能力があることである。
形のうえでは区別のつかないこの2種類のリンパ球が,巧妙な協同作業をすることによって抗体合成が行われる。すなわち,マクロファージに取り込まれた抗原は,部分的に消化されて,その一部がマクロファージ表面に特定の様式で提示されるらしい。この提示のしかたが遺伝的に決定されていて,ある個体では有効に,ある個体では無意味に提示されるので,免疫応答性はマクロファージの抗原提示のレベルで,遺伝的な統御を受けているとされるのである。提示された抗原はT細胞およびB細胞の抗原レセプターによって認識される。T細胞はこれによってまず分裂し,次いでさまざまな活性分子を放出する。この活性分子のなかには,マクロファージの働きを変化させるもの,T細胞の分裂を誘導するもの(T細胞増殖因子T cell growth factor。TCGFと略記し,インターロイキン2ともいう),B細胞を刺激するもの(B細胞刺激因子B cell stimulating factor。BCSFと略記),インターフェロンなど複数の分子が含まれ,T細胞のもつ複雑な働きを媒介する。B細胞は,免疫グロブリンレセプターで抗原を認識するが,それだけでは抗体の合成には至らず,T細胞からの第2のシグナルを受けて,初めて増殖,分裂する。T細胞からの複数のB細胞刺激因子が順序正しく働くと,B細胞は,分裂ののちに抗体を大量に合成する抗体産生細胞,すなわち形質細胞(プラズマ細胞ともいう)へと分化し,抗体を分泌するようになるのである。このようにして,抗体を合成するという一つのまとまった仕事を行うために,免疫系は,複数の細胞が複雑な分子群を介して,細胞間相互作用を行っているというのが今日の理解である。この抗体産生のために必要なT細胞を,反応を補助しているという意味でヘルパーT細胞と呼ぶ。
ところがそれに対して,免疫応答を抑制するように働く細胞もいることが明らかにされるようになった。この第3の細胞は,抗体をつくりすぎることがないよう,さらに自己にとって不利になるような抗体をつくることがないように監視して,ヘルパーT細胞の機能を抑えたり,直接にB細胞の分化を抑えたりして,最終的には免疫反応全体を統御している重要な細胞である。これをサプレッサーT細胞と呼ぶ。自己成分に対して反応する抗体をつくってしまうような自己免疫疾患では,しばしばサプレッサーT細胞が減少して,そのために自己抗体がつくられる場合がある。これらの細胞群が,互いに反応しあいながら,調和のとれた反応系としての免疫系を保っているのである。
このような体液性免疫のために働く細胞群のほかに,細胞性免疫に関与するT細胞群がある。たとえば遅延型アレルギーでは,マクロファージから抗原情報を受けとったT細胞は,分裂すると同時に,さまざまな炎症を起こすような微量活性物質(これをリンホカインlymphokineという)を産生する。このなかには,上記の,他の細胞に対して影響を与える分子群のほかに,それ自身毒性をもって細胞を障害するようなリンホトキシンその他の因子が含まれ,いわゆる遅延型過敏症を起こす。
また別のT細胞は,異物である細胞や,ウイルスなどが感染して異物化した細胞に出会うと,直接にそれにとりついて破壊してしまうような働きをもっている。これをキラーT細胞あるいは細胞傷害性T細胞と呼ぶ。移植片の拒絶や,ウイルス感染細胞の除去,さらには癌免疫の主役はこのキラーT細胞であろうと考えられている。しかしここでもまた,細胞性免疫を補助するヘルパーT細胞,抑制するサプレッサーT細胞も存在し,抗体産生と同じように複雑な調節が行われていることが知られている。
そのほかに,T細胞でもB細胞でもないヌル細胞null cellと呼ばれるリンパ球があって,このなかには非特異的に癌細胞に結合して破壊するナチュラルキラー細胞が含まれる。これらの多種類の細胞の総合的な働きで免疫系は維持されているので,しばしば免疫学的オーケストラなどと称される。
免疫はどうして成立するか
一つの個体にとっては無数といっていい〈非自己〉に対して,どうして一つ一つ正確な免疫が成立するのだろうか。これについて古くは,抗原が入ってくると,その抗原の立体構造に相補的に抗体分子がつくり出される(指令説,抗原鋳型説)という考えがあったが,それが誤りであることはタンパク質合成の原則からも明らかである。それに対して,生体はもともと,自己以外のいかなる抗原とも反応できるようなリンパ球を前もってひとそろい用意してあって,抗原は,自分に対応したリンパ球を選択し,それを増殖させるように働くと考える説が有力となった。一つの細胞が抗原によって選択されれば,その細胞の一連の子孫(クローン)が増える。この増えた細胞が抗体の合成や細胞性免疫を行うと考えるのが,F.M.バーネットのクローン選択説である。すなわち一度増えたクローンは,同じ抗原の刺激で急速に増殖し抗体をつくるので,二次免疫反応が起こるという考えである。
それでは,どのようにしてすべての非自己である抗原と反応できるほど多種類のクローンを用意できるのか。その点に関しては,リンパ球が造血幹細胞から分化してつくられる際に,ランダムな突然変異が起こって多様なクローンが生じると考えられている。実際,最近の分子生物学的研究によれば,抗体の多様性は,遺伝子のランダムな再構成と突然変異によってつくり出されることが証明されている。バーネットは,こうしてつくり出されたクローンのなかから,自己と反応するようなクローンは除去されるか抑えられ(禁止クローン),非自己と反応するひとそろいが残されると考えた。ことに胎生期に,抗原と接触したクローンは,その抗原を自己と思い,二度とそれに出会っても反応しない(この現象を免疫学的寛容という)。うまくできた学説ではあるが,それは確かに免疫系の現実には合っている。イエルネN.K.Jerne(1911-94)は,さらにすべての非自己に対応するクローンは,互いに反応し合いながら一種のネットワークをつくって,そのひとそろいを維持していると考える(これをネットワーク説という)。この考えによれば,個体がいかなる非自己と出会っても反応できるようなひとそろいのクローンを用意するために,ランダムな組合せの抗体遺伝子ができ,それを表現している細胞が互いに反応してネットワークをつくり,ネットワークに入らなかったクローンを除去すると同時に,ネットワークの平衡状態が維持されることになる。一つのクローンが刺激されると,そのクローンと反応する他のクローン群も刺激されて,ネットワーク内部での自己調節が行われると考えるのである。これらの理論が,生理的あるいは病理的条件下での免疫反応をどこまで説明し,さらに未来の展望を与えるかが,いま問われているところである。
→抗原 →抗体
執筆者:多田 富雄
免疫システムの起源と進化
免疫の古典的な定義は,ある病原体に感染した動物(ヒトを含めて)は,その後に同じ病原体に感染した場合に,それに対して迅速かつ高度の排除作用を発揮するということである。ここから,免疫とは,特異性認識と記憶を特徴とする非自己排除機構であるという最も狭義で厳密な定義が出てくる。もちろん,非自己を排除するには,非自己に対する特異性認識が絶対的な必須条件ではない。人間の体内で,自己体の生存を根本的に支えている食細胞やナチュラルキラー細胞などは,非自己をおしなべて自己ではないと非特異的に認識して攻撃する。広義には,これらの非特異的認識に立脚する機構も免疫と称して差支えないが,ここでは狭義の免疫について,その系統発生について述べる。
上述の狭義の免疫機構にたずさわっている細胞はリンパ球である。だから,狭義の免疫とは,リンパ球系免疫機構であるといって差支えなく,その免疫系は脊椎動物で著しく発展している。それゆえ,多くの免疫学者は,リンパ球は脊椎動物に固有のものであると錯覚しているようであるが,ほんとうはそうではない。現在,脊椎動物に固有の免疫応答は,抗体を産生することだけであり,脊椎動物に固有のリンパ球とは,リンパ球のなかでも特別に分業化されたBリンパ球系だけであることが定説となっていて,もっと基本的なリンパ球であるTリンパ球は,無脊椎動物に起源を求めることが可能である。無脊椎動物を対象とした研究は,それらを飼育管理することの困難さから,高等脊椎動物での研究ほど進んでいないが,環形動物や棘皮(きよくひ)動物では,特異性認識と記憶をそなえた非自己排除機構とリンパ球の存在が証明されている。もちろん,リンパ球といっても,脊椎動物のそれとは外観が必ずしも同じではない。しかし,たとえば同種内移植拒絶反応において,特異性認識と記憶を示す二次応答で,移植部位に向かって,単なる炎症反応の場合と異なって,とくに多数動員される細胞をリンパ球と総称することに,論理的矛盾はない。
動物体は自己体の構築について非常に保守的であり,自己の細胞だけで体をつくるようにする。最下等の多細胞動物である海綿動物や腔腸動物のような二胚葉性動物では,すべての細胞が互いに自己同一性を認識しあうことによって,それを可能にしている。ところが,動物は進化にともなって細胞間での分業化が進み,各体細胞からは自己同一性の相互認識機構が退化し,代りに非自己を探知して排除する専業細胞であるリンパ球を分化させたと思われる。
リンパ球が動物進化の途上において,どの辺りから出現したのかは今のところ明らかではなく,今後の研究にまたねばならない。しかし,環形動物や棘皮動物でリンパ球がみられることから考えると,その起源を下等三胚葉性動物(原体腔類)に求めることは理にかなっているであろう。
執筆者:村松 繁
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「免疫」の意味・わかりやすい解説
免疫【めんえき】
→関連項目アレルギー性疾患|アレルギー反応|アレルギー・マーチ|異種間臓器移植|移植片対宿主反応病|感染巣|キメラ|サイコオンコロジー|自己血輸血|自己免疫|種痘|スネル|帯状疱疹|多田富雄|腸内細菌|ツベルクリン反応|DNAワクチン|伝染病|乳児|脳内モルヒネ|無輸血手術|免疫不全症|予防接種|淋菌|リンパ球
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
妊娠・子育て用語辞典 「免疫」の解説
めんえき【免疫】
出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免疫」の意味・わかりやすい解説
免疫
めんえき
immunity
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
化学辞典 第2版 「免疫」の解説
免疫
メンエキ
immunity
一度かかった病気にかかりにくくなる仕組み.生体に不都合な異物を認識し,排除する機構.抗体の関与する液性免疫と,キラーT細胞やNK(natural killer)細胞が中心となる細胞性免疫がある.これらの高度な免疫系のほかに,無脊椎動物にまで広く備わっている自然免疫(innate immune response)がある.自然免疫の場合,レクチンが中心となっており,特異性は低い.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
栄養・生化学辞典 「免疫」の解説
免疫
世界大百科事典(旧版)内の免疫の言及
【インムニテート】より
…ヨーロッパ中世の法制史用語。ラテン語ではインムニタスimmunitas,英語ではイミューニティimmunityという。インムニタスは,古代末期のローマ帝国では,諸種の公的負担からの免除を意味する法技術的用語であったが,フランク王国では主として教会大所領の特別な国制上の地位を表すようになる。…
【アレルギー】より
…また,こうした外来の物質に対して過敏な状態にすることを感作sensitizationという。現在は〈抗原抗体反応が生体に及ぼす影響のうち病的過程を示すもの〉を総括した言葉であると考えればよく,同様に免疫はいちおう〈抗原抗体反応が生体に及ぼす影響のうち有利に作用するもの〉と考えるのが普通である。
[アレルギー研究の歴史]
アレルギー反応は古くから知られており,前1世紀にはすでにルクレティウスが〈甲の薬は乙の毒〉ということわざを残しているが,現在での食事アレルギーに対する言葉として理解できる。…
【体】より
…器官は,その働きのうえから,植物性器官と動物性器官に分類される。植物性器官は,消化器,呼吸器,循環器,内分泌器,生体防御器官,生殖器,排出器に分けられ,体の代謝,免疫,種の保存などに関与する。これらの器官は,ほとんどが頭部の前下面,および体幹の腹側に集められている。…
【血球】より
…単球のライフサイクルも顆粒球とほぼ同じである。リンパ球の寿命は短いものでは数日,長いものでは数年~十数年にも及び,寿命の長いリンパ球は免疫の記憶に関係していると考えられている。血小板の母細胞である巨核球は,核は分裂しても細胞質は分裂せず,そのため細胞は肥大し,100μm以上の巨大細胞となる。…
※「免疫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...