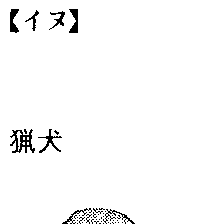日本大百科全書(ニッポニカ) 「イヌ」の意味・わかりやすい解説
イヌ
いぬ / 犬
dog
[学] Canis familiaris
哺乳(ほにゅう)綱食肉目イヌ科に属する動物。人間にもっとも早く飼いならされ、家畜にされた種である。イヌ科の動物は、分類学者のコーベットG. B. Corbetらによれば10属35種を数え、オーストラリア区を除く全世界に分布する。オーストラリアにはディンゴが生息するが、これは土着の野生種ではなく、人の移住について南アジア方面から入ったイヌが野生化したものと考えられている。
系統学的にみると、イヌ科動物の特徴は次のようなものである。体形は長距離を徘徊(はいかい)するのに適して一般に四肢は長く、リカオンを除き前肢に5指、後肢に4趾(し)(足指)を有する。指趾には鉤(かぎ)づめがあるが、ネコのように引っ込められず、指行性である。吻(ふん)はとがり、歯は犬歯の発達がよく、第4臼歯(きゅうし)と第1臼歯からなる裂歯もよく発達する。消化器は食性により差があるが、肉食性の強いオオカミでは短く、体長の3倍である。小さな盲腸を有し、また陰茎骨がある。生態面では、一般に夜行性で、つがいか家族単位の群れで生活する種類が多いが、単独生活者もいる。群れをなして中形のシカ、レイヨウ類を襲ったりするものもいるが、小動物、昆虫などを捕食するものも多く、かなりの種類が季節によっては植物質のものを食べる。感覚では嗅覚(きゅうかく)と聴覚が鋭い。これら野生イヌ類は、種類によっては1、2年で性成熟し、寿命は10~15年である。
種としてのイヌはイヌ属に属し、オオカミに似た形質を残してはいるが、家畜化の途上で人為淘汰(とうた)を受け、さまざまな品種が産み出され、形態に著しい差異がある。そのなかでイヌ科動物として共通な特徴をあげると、次のようである。
[増井光子]
形態
獣猟犬、テリア類のなかに短脚のものもいるが、一般に四肢は長く、獲物の追跡に適する。後肢にはときに1、2本のオオカミづめ(5本趾(し)の遺伝的産物として、ときに現れる不要な過剰趾)を生ずることがある。このつめは犬種によっては発現しやすく、紀州犬には多い。これは一般に生後まもなく切除するが、ピレニアンマウンテンドッグでは犬種の特徴となっている。歯牙(しが)もよく発達し、総数42本であるが、第1前臼歯(ぜんきゅうし)、門歯などに欠歯を生ずるものがある。欠歯は退化現象の一つで、どの犬種でも厳しくチェックされる。裂歯の発達もよいが、普通、オオカミには及ばない。吻(ふん)は犬種により著しい短縮を示すものもあるが、普通はほどよい長さがあり、頭骨のプロフィールでは前頭骨から鼻骨にかけてへこんでいて、明瞭(めいりょう)なストップ(へこみ)を有する。瞳孔(どうこう)は丸い。消化管は雑食傾向が強いため体長の5倍あり、オオカミの3倍に比べるとずっと長い。また足裏と指間以外は汗腺(かんせん)の発達が悪く、体温調節は、あえいで口中から水分を蒸散させて行う。しかし、皮脂腺の発達は良好で、肛門(こうもん)腺の発達もよい。肛門腺の分泌物のにおいは固有の体臭であり、道で出会ったイヌは互いに臀(しり)のあたりのにおいをかぎ合って、相手を確認する。
イヌの形質のなかにはオオカミと共通するものがみられる。オオカミと共存する地域における足跡などのフィールド・サインの相違点は、イヌの指では中央の2本がオオカミに比べると短く、オオカミの足跡がやや細長いのに比べると円形に近いことであるといわれるが、なかにはきわめてオオカミに類似した足のあるものもあり、アメリカのナチュラリストであるシートンは正確に区別するのはたいへんむずかしいとしている。毛色は品種によりさまざまで変化に富む。鼻梁(びりょう)、前胸部、四肢の先端、尾端に白斑(はくはん)が生じやすい。耳介には立ち耳と垂れ耳があり、尾は巻き尾とそうでないものがある。
[増井光子]
感覚
イヌの感覚のなかでは嗅覚(きゅうかく)がもっとも発達している。嗅覚は生後7日目ぐらいから働き始める。嗅覚の鋭さの判定は容易ではないが、塩酸や乳酸に対しては100万分の1の濃度でもかぎつけるといわれる。またスライドガラスについた人の指跡も、もしそのガラスが室内に置かれていれば、6週間後でもかぎ当てることができる。また別の報告では、バターに含有されるカプロイン酸に対しては6×10-18、香水中にあるイオノンに対しては5.1×10-17の閾値(いきち)を有するという。聴覚も鋭く、シェパードでは音量が同じなら人間の4倍も遠くから聞きつけるともいわれ、6万~12万ヘルツの高音も聞き取れる。視覚は一般にマイナス2~3D(ジオプトリー)の弱度の近視といわれている。しかしグレーハウンドは逆にプラス0.5~1.5Dの遠視といわれ、遠くにいる獲物を視覚で識別するドッグレース用のイヌのなかにはプラス3Dの遠視のものもいるという。飼い主と他人との区別は100メートルほどでできなくなるようである。しかし動くものに対してはずっと敏感で、人か他のものかの区別は八百数十メートルぐらいまで可能とされる。色覚については一般に色盲とされるが、明暗視では明色と暗色のコントラストは人間並みに区別可能である。両眼球軸角は犬種によって異なるが、一般には92.5度である。
[増井光子]
祖先と歴史
イヌの祖先
イヌ科の野生種10属35種のうち、イヌに近い形質を有するものは、イヌ属に属するオオカミ、コヨーテ、ジャッカル類で、これらにはイヌと同じく2n=78の染色体がある。このため、これら3種の野生種とイヌとは、子をつくる能力(妊性)のある雑種を産み出す。従来はイヌの祖先としてオオカミやジャッカルの多源説がとられていたが、その後イヌのさまざまな形質を調べあげていくと、ジャッカルよりオオカミにより類似している点が多いとして、オオカミ単源説が有力になってきた。しかし学者のなかには、祖先をオオカミだと断言するにはなお問題点が多いとし、オーストラリアのディンゴや南アジアに半野生状態で生息するパリア犬に近いが、すでに絶滅した種ではないかとする意見もある。しかし、イヌはいったん家畜化されて以来、人の移住に伴って世界中に拡散していき、その土地土地でオオカミなどの血を混じつつ、多くの品種を生じていったものと考えられる。最近は分類学の方面にも生化学的研究方法が取り入れられ、タンパク質の組成や赤血球膜の糖脂質類の分析から、イヌの系統や拡散状態を調べようとする研究が行われている。
[増井光子]
家畜化の歴史
イヌはあらゆる畜産種のうち、もっとも古い家畜化の歴史を有する動物である。従来は紀元前9500年ぐらいから人に飼われていたといわれていたが、最近の遺跡の発掘から、その年代はさらにさかのぼっている。1974年(昭和49)に東京大学西アジア調査団は、シリア砂漠の北方にあるドゥアラ洞穴の発掘を行ったが、このときイヌ科の動物の骨をみつけた。シリア地方にはシリアオオカミとジャッカルが生息しているが、出土した骨はいずれの野生種とも異なり、家畜化されたイヌに近いものであった。この洞穴には、5万年前から10万年前の一時期、石器時代の人々が住んでいたので、これからみるとイヌの家畜化の歴史はずっと古くなる。
ではどのような経過でイヌは人と暮らすようになったのだろうか。イヌの祖先たちは、現在の野犬にもみられるように、人の住居近くに出没し、残り物をあさっていたと考えられる。彼らは未知のものに対し警戒心が強く、排斥しようとしたり、警戒したりしてほえ立て、これが人間にも有利に働いたと思われる。現在でもある地域では、居住地の汚物の処理にハゲワシ、ハイエナ、ジャッカルなどのいわゆる掃除屋が働いて、それなりの評価を受けている。石器時代の人々もまた、周りに小動物が徘徊(はいかい)しても、とくに追い払おうとしなかったと思われる。しだいに双方は接近し、順化されたものも生じて家犬への道へ進んでいったものであろう。
[増井光子]
生態
イヌの社会
オオカミの群れの研究については多くの報告がみられる。オオカミ社会はつがいを基盤とする家族群で、普通最強の雄が群れを率いる。イヌの生態についてはどうだろうか。オーストラリアの野生犬ディンゴの研究では、単独で行動している個体がもっとも多く、73%を占める。つがいが16.2%でこれに次ぎ、3頭の群れは5.1%、4頭は2.8%であったという。単独生活者はときに集まってルーズな群れをつくったりもする。彼らは遠ぼえをしたり、ほえたりして互いに連絡し、ほえ声は繁殖周期と関連して多くなる。調査されたディンゴは、獲物としてウサギなどを狩り、腐肉なども利用していた。またアメリカのメリーランド州でのイヌの研究でも、2頭連れでの行動が割に多かったが、50.6%は単独で行動しており、5頭の群れはわずか1.9%であった。さらにイリノイ州での野犬の研究では、群れの成員は2~5頭で、約30平方キロメートルほどの行動圏(ホームレンジ)を有し、死肉、生ごみ、小動物など入手できるものはなんでも利用し、ほかの群れに対しては排他的で、行動圏から追い払うのがみられた。群れにはリーダー的行動をとるものもいたが、成員間の順位争いといったものは、あまり明瞭(めいりょう)でなかった。さらにまた、ミズーリ州セントルイスでの雄2頭、雌1頭からなる野犬の調査では、自分の行動圏内での群れは、50回の観察例のうち37回は雌にリードされていた。しかし、何かを追跡するというようなときは、29回の観察例のうち、雌が13回、雄の1頭が15回、仲間をリードしていた(1回は不明)。また、この雄は、知らない個体のマーキング(印づけ)に対し、回数多く上塗りのマーキングを行っている。
[増井光子]
コミュニケーション
では、これら仲間の間でのコミュニケーションはどんな方法によるのであろう。イヌたちは音声のほかに、耳や尾の動き、体の動きなどを用いて感情を表す。感情の表出は同じメンバー間ではよく理解され、大きな闘争に至ることは少ない。イヌの行動のうち顕著なものは、あちこちに尿をかけることである。この尿によるマーキングは、雌より雄のほうが多く行う。また、自分の行動圏内にある未知のものに対し、何度も繰り返し尿をかけることがある。変わったにおいのするものに体をこすりつけることもある。尿によるマーキングは、異性に対してはアピールの役目を果たし、同性に対してはときに排他的になることもある。また、かぎなれないにおいに対し、自己のにおいを上塗りすることで、それをなじみのあるにおいに変化させる効果もある。変わったにおいを体につけることも、体臭と混ぜ合わせていぶかしい感じを和らげようとする行為だとみる学者もいる。
[増井光子]
イヌの系統
現生するイヌは、畜産文化研究家である加茂儀一の区分けに従いその祖先をたどれば、おおむね次の7系統に分類される。
[増井光子]
パリア犬型
C. f. poutiatini もっとも古い型のイヌで、旧石器時代後期の遺跡から出土している。パリア犬は現在でも南アジアの村落に半野生状態で生活しており、ディンゴに似て野生犬の形質を多く保持している。体格は中ぐらいで変化に富み、立ち耳のものや、垂れ耳のものがいる。グレーハウンドや猟犬の祖先ともみなされている。日本の柴犬(しばいぬ)もこの系統と関連があると思われる。
[増井光子]
テリア型
C. f. palustris 紀元前2800年ごろのスイスの新石器時代層から初めて出土した。しかし北ヨーロッパでは前8000年ごろの地層から発見されているし、西アジアやエジプトでも新石器時代の遺跡から発掘されている。パリア犬の流れをくむものとみなされている。ポメラニアン、テリア類、そり犬などがこれに属する。
[増井光子]
牧羊犬型
C. f. martis-optimae 青銅器文化が東方からヨーロッパに進出したときに、伴われていったものとみられている。またこのころ興った牧羊業と密接な関連がある。その順化の発祥地としてはイランが想定されている。コリー、シェパードなど各種の牧羊犬がこれに属する。
[増井光子]
グレーハウンド型
C. f. leineri 古くは前5000年の古代エジプトの遺跡から出土している。古代メソポタミア、インダス文明時代にもこのタイプのイヌが存在した。各種のハウンド類がこれに属する。
[増井光子]
ブルドッグ型
C. f. inostranzewi チベットあたりが発祥地とみられ、前1050年、中国の周の時代に皇帝への贈り物にされている。前9000年の中石器時代にデンマークからも発見されている。パリア犬型のイヌに北方オオカミの血を混じたものとみられている。極地犬、ピレニアンマウンテンドッグ、オフチャルカ、オールドイングリッシュシープドッグなどがこれに属する。
[増井光子]
猟犬型
C. f. inter-medius オーストリアの青銅器時代層から出土。前2000年ごろパリア犬型のものからグレーハウンド型のものを生じ、さらに猟犬タイプに移行したとみられる。スパニエル類、ポインター、ブラッドハウンド、ディアハウンド、ブラッケなどがある。
[増井光子]
新大陸のイヌ
新大陸には人の移住に伴い、パリア犬型、テリア型のもの、ブルドッグ型のもの、大形のテリア型のものなど四つの系統が認められている。
[増井光子]
日本犬
以上7系統のほかに、わが国には日本犬の系統がある。日本ではイヌの骨は縄文時代の遺跡から出土している。当時わが国にはニホンオオカミやエゾオオカミが存在したが、日本のイヌはオオカミを順化したものでなく、大陸からの人の移住のときに、ともに渡来したものとみなされている。
[増井光子]
繁殖と寿命
オオカミは性成熟に達するのに2年はかかり、繁殖は早春から初夏にかけてなされる。しかしイヌの性成熟はずっと早い。早熟なものでは生後4か月で発情が認められるが、大方のものは8~10か月で性成熟に達する。繁殖は周年認められるが、春と秋にやや多い。雌が雄を許容するのは、出血が始まって10日目ごろからである。それまでは雌はあたりを徘徊(はいかい)し、普段より排尿回数が増え、何頭もの雄に追従される。交尾はかならずしも特定の雄とだけ行われるものではないが、雌によっては厳しく雄を選定し、他を許容しないものがいる。妊娠期間は約2か月、1産1~6子が多い。小形犬では1胎子数は少なく、大形犬では7~8頭を産むこともまれではない。もっとも多くの子を産んだのは、フォックスハウンドのレナ号で、23頭である(1944)。また、セントバーナードのケアレス・アン号も23頭の子を産み、うち14頭が生き残ったという記録がある(1975)。子イヌは初め閉眼しており、耳孔もふさがっているが、2週目ごろから目が開きだす。乳歯は3~4週目ごろから生え始め、1か月を過ぎるとしだいに固形食を食べ始める。オオカミでは雄親が餌(えさ)を巣に運ぶが、イヌでは認められない。しかし雌親には、子の前に半消化状の餌を吐き出して与えるものがある。
一方、イヌの寿命は普通12歳か13歳ぐらいであり、平均寿命は8~9歳ぐらいである。激しい使役に従事するものや闘犬では寿命は比較的短いが、室内でだいじにされている小形犬には比較的長生きのものが多い。正確な長寿記録では、オーストリアのイヌで、1910年から39年まで29年5か月生きた例がある。
[増井光子]
用途
その長い家畜化の歴史のなかで、イヌは広い分野にわたって人間の生活の手助けをしてきた。生来の警戒心の強さから、たいていのイヌは見知らぬものの侵入に対しほえ立てて、番犬の役目を果たすものであるが、この警備面での能力を引き出し、改良していったのが、警察犬、軍用犬、警備犬などである。また、その鋭い嗅覚(きゅうかく)を利用して、獲物を狩り出したり、犯罪の摘発にも活躍している。
警察犬は日本では1937年(昭和12)に誕生したが、ドイツシェパード犬、エアデールテリア、ボクサー、ドーベルマン、コリー、ゴールデンレトリバー、ラブラドルレトリバーの7犬種が認定され、活躍している。比率はシェパードが多い。犯人追跡とか物品鑑別といった作業のほかに、最近は麻薬探知犬として麻薬の発見にも用いられている。
軍用犬は第一次、第二次世界大戦に盛んに用いられたが、その歴史は古く、前490年ごろ古代ギリシア時代にすでにイヌが戦争に登場してくる。近代戦争に用いられた犬種はシェパード、エアデールテリア、ジャイアントシュナウザー、ドーベルマンなどが多かった。これらは伝令、偵察、歩哨(ほしょう)などで活躍した。
猟犬は銃器の発達とともに多くのものが作出された。なかには平原で視覚をもとにして獲物を発見し追跡するグレーハウンドのようなタイプもあるが、多くは嗅覚を利用して、茂みに潜む獲物を狩り出すものである。有名犬種にはセッター、ポインター、ビーグルなどがある。
交通機関の十分発達していない時代や、厳しい環境下では、イヌの労力も大いに利用された。そり犬や荷を引く駄用のイヌがそれである。極寒の地では犬ぞりは重要な交通機関の一つであり、サモエド、ハスキー、アラスカンマラミュートなどが代表犬種である。日本でも樺太(からふと)(サハリン)、北海道では大形の通称カラフト犬がそり犬として用いられていた。そり犬はゆっくりとなら自分と同重量の荷を引くことができる。かなりのスピードが要求される場合は、体重の半分の重量を引かせるのが普通とされている。イヌの牽引(けんいん)力は相当強く、『ギネスブック』には2721キログラムの鉛塊を引いたセントバーナードの例がある(1974)。またアラスカで行われた犬ぞりレースでは、1680キロメートルの距離を14日14時間43分で走った記録もある(1975)。ヨーロッパの一部ではイヌに荷車を引かせることもかつては盛んで、とくにベルギーあたりでよくみかけられた。
ヨーロッパでは牧畜は青銅器時代に始められた。飼養する家畜をオオカミやその他の肉食動物から守るために、各種の牧羊犬が作出された。牧羊犬のなかには、散らばるヒツジの群れを巧みにまとめて誘導するタイプのものや、もっと大形で、家畜群の見張りをし、外敵を防ぐタイプのものがある。コリー、ボーダーコリーなどは前者に属し、グレートピレニーズなどは後者のたぐいである。
山岳での遭難や水難に際して、大形犬が救助犬として用いられた。ニューファウンドランドは、セントバーナードに匹敵する黒色の大形犬であるが、水難救助犬として名高い。またセントバーナードが、スイスのアルプス山中にある聖バーナード寺院に飼われ、山越えして旅する人々の遭難救助にあたったイヌであることはよく知られている。
目の不自由な人々のための道案内役として盲導犬がある。性質温和で怜悧(れいり)な犬種が選ばれる。日本ではまだ歴史が新しく、普及事業に苦労も多いが、しだいに社会的に認められてきつつある。犬種はシェパード、ラブラドルレトリバーなどが多いが、ほかにエアデールテリア、ボクサー、スタンダードプードルなども用いられる。盲導犬のほかに、最近は耳の不自由な人のために、聴導犬の訓練も各国で注目を集めだしている。
イヌを飼育していると、別に仕事をしてくれなくても、いっしょにいるだけで楽しい。イヌの愛らしさを強調し、体形も小形化して室内でも飼育できるようにしたのが愛玩犬(あいがんけん)である。長毛種のシーズーや、マルチーズ、ポメラニアン、ヨークシャーテリアなどは、たいへん人気があるし、短毛種でも動作のきびきびしたミニチュアピンシャーは昭和40年代には流行犬となった。
動物を使っての競技にも人々の関心は集まる。競馬もそうであるが、欧米ではドッグレースが盛んである。レースに用いられる犬種は長脚の快速犬で、グレーハウンドかホイペットである。日本ではドッグレースは認められていないので、グレーハウンドはめったにみかけられない。イヌどうし、もしくはイヌと他の大形獣を戦わせて楽しむ闘犬の歴史もずいぶん古い。大形犬のマスチフは古代ローマ時代から闘犬として用いられ、牡牛(おうし)やクマ、ライオンとさえ戦わされた歴史がある。日本の土佐闘犬は、土着の四国犬にマスチフやブルドッグ、ポインターなどを交配し、闘犬用に作出された犬種である。闘犬は現在ではほとんどの国々で禁止されているが、日本では土佐闘犬の闘技は認められている。定められた柵(さく)内で時間を決めて(30分)闘技が行われ、10項目に及ぶ細かい判定基準があり、勝敗を競う。
このようにイヌは昔から多方面にわたり人の生活に役だってきた。一方、最近は機械化が進み、かなりの地方まで交通網が開けてきた。極地に住むエスキモーの社会にまでスノーモビルが普及し始めている。また牧畜作業にしても、平原を車で疾走して畜群を誘導することが可能であるし、各地で自然破壊が進み、かつては獲物とされた動物が保護される立場になったことにより、猟犬も用を失うことが多い。嗅覚を利用する面ではなおイヌの能力に頼ることが多いが、かつてのイヌの職域はかなり縮小されてしまった。能力があっても磨かなければやがては衰える。目的を失った犬種は、別の方面に活路をみつけなければやがて飼育頭数が減じ、消滅するものも出てこよう。しかし、これは畜用種であれば仕方ないことかもしれない。
[増井光子]
おもな犬種
世界各地にはそれぞれ土着の犬種があるが、それは世界的に認められたものではない。犬界には、欧米に紹介され国際的に認められ、相当数の愛好者を有し、ドッグショーにもしばしば出陳されない限り、世界的な犬種として通用しない風習がある。各国にはそれぞれ犬種団体があり、血統登録事務やショーの開催を行い、犬種標準を定め、犬種の純血度の維持、改良普及に尽力している。なかでも国際的に有名なのは、イギリスのケネル・クラブ(KC)と、アメリカのケネル・クラブ(AKC)である。犬種団体は国に一つの場合もあるが、複数の場合もあり、公認する犬種に差があることがある。たとえばアメリカには、アメリカン・ケネル・クラブ(AKC)と、ユナイテッド・ケネル・クラブ(UKC)の二大クラブがある。日本ではAKC(1884年創立)のほうがよく知られているが、UKCも歴史は古く、1898年に創立され、AKCが公認していない犬種であるピットブルテリア、イングリッシュシェパード、ブルーチックハウンド、プロットハウンドなどを公認している。
日本の犬界は、ドイツシェパードやボクサー、グレートデンなどではドイツ犬界の影響が大きいが、その他のものでは主としてイギリス、アメリカに影響されるところが大きい。日本の犬種団体の一つ、ジャパン・ケネル・クラブ(JKC)は現在10種の日本産犬種と170種の犬種、計180種を公認している。この日本産犬種のなかで世界公認犬となっているのはチンのみであり、秋田犬がAKCで公認されている。また、日本スピッツがイギリスのドッグショーに登場したり、柴犬(しばいぬ)がアメリカのカリフォルニア州で開かれたショーに初出場して注目を集めたりして、しだいに他犬種も認められつつある。柴犬は北ヨーロッパにも輸出され、訓練試験でも性能の高いことが証明された。
現在世界的なAKCが公認している犬種は150種以上に上っているが、これはまだ増える可能性がある。イヌの品種は各地の土着犬も含めると数百種に達すると思われる。最近、日本へも珍しい犬種として、中国原産のチャイニーズシャーペイ、フランス原産のローシェン、チベット原産のチベッタンテリア、スペイン原産のガルゴなどが輸入されている。
登録された犬種は、用途別に大きくグループに分けられる。AKCでは、猟犬、獣猟犬、使役犬、愛玩犬、テリア、非猟犬の6グループに分けていたが、1983年からは使役犬グループを分けて、牧羊牧畜犬グループを設け7グループとすることになった。次に各グループのおもな犬種について、簡単に説明する。
[増井光子]
猟犬グループ
sporting dogs 猟犬は主として鳥猟に用いられる犬種で、獲物を回収運搬する役のレトリバー種もここに含まれる。鳥猟犬としてはポインター、セッターが双璧(そうへき)で、愛好者も多い。イングリッシュポインターはイギリス原産。体高61~69センチメートル。白地に黒やレバー色の斑点(はんてん)がある。イングリッシュセッターも原産はイギリス。体高58~65センチメートル。絹のような長毛で、白地に黒やレモン色の斑、もしくは更紗(さらさ)模様が多い。アイリッシュセッターは全身栗(くり)色の美しい犬種で、アイルランドの産。体高55~65センチメートル。小柄なスパニエル種は短めの四肢をしていて、体のわりには重量感がある。家庭犬としても愛好者が多い。アメリカ原産のアメリカンコッカースパニエルはスパニエルの代表的犬種で、体高約33~40センチメートル、長毛で毛色は黒、バフ、斑など多様。断尾する。イングリッシュコッカースパニエルは原産地イギリス。体高38~42センチメートル。毛色はローン、黒、斑など。ラブラドルレトリバーの原産はイギリス。体高54~62センチメートル。毛色は黒、黄、クリームなど。日本では鳥猟犬としてよりも盲導犬として知られている。ワイマラナーは原産地ドイツ。体高57~70センチメートル。独特の灰褐色を呈し、断尾する。獣猟にも用いられる。
[増井光子]
獣猟犬グループ
hounds 獣猟犬は各種の獣猟に用いられる犬種である。アフガンハウンドは最近たいへん人気のある犬種で、原産地アフガニスタン。体高60.5~71.5センチメートル。毛色はフォーン、黒、クリームなどで長毛。ビーグルは小形で愛らしく家庭犬として人気が出てきた。医学や生理学などの実験用にも用いられている。体高30~38センチメートル。原産はイギリス。本来はウサギ狩りの猟犬。ダックスフントの原産はドイツ。長胴短脚のユーモラスな犬種。体高20~27センチメートル。アナグマ猟犬であるが、家庭犬としても愛好者が多い。ボルゾイは原産地ロシア。グレーハウンド型の美しい巻き毛がある。体高68~78センチメートル。オオカミ猟に用いられていた。毛色は斑(はん)、ビスケット色、ブリンドルなど。グレーハウンドは家イヌとしてもっとも古い起源を有し、エジプト原産。ドッグレース犬としては快足を誇っている。体高65~72センチメートル。毛色はブリンドル、フォーン、斑で短毛。
[増井光子]
使役犬グループ
working dogs 使役犬は警察犬、そり犬、盲導犬、遭難救助犬など、作業に従事する犬種で、中形から大形のものが多い。ボクサーは原産地ドイツ。体高54~64センチメートル。断耳、断尾する。警察犬に用いられるほか家庭犬としても愛好者が多い。毛色はフォーン、虎(とら)毛など。ドーベルマンも原産地ドイツ。体高61~71センチメートル。短毛でスマートな犬種。断耳、断尾する。毛色はチョコレート、ブラックエンドタン。グレートデンは最大犬種の一つである大形犬。ドイツおよびデンマーク原産。体高は雌で70センチメートル、雄で76センチメートル以上。短毛で筋肉質、断耳、断尾する。毛色はフォーン、黒、ハルクイン、ブルー、虎毛。シロクマのようなピレニアンマウンテンドッグは原産地ピレネー(フランス・スペイン国境地方)。体高65~82センチメートル。山岳地方の牧羊犬で、毛色は白。マスチフも最大犬種の一つで、体高は雄で75センチメートル以上。かつては闘犬、護身犬として飼育されていた。短毛でフォーン、虎毛など。セントバーナードは原産地スイス。短毛と長毛がある。山岳救助犬としてよく知られている。体高は雌で65センチメートル、雄で70センチメートル以上。大きいほどよいとされる。毛色は濃い赤と白、トライカラーなど。
[増井光子]
牧羊牧畜犬グループ
herding dogs コリーは牧羊犬の代表種であり、原産地イギリス。短毛と長毛がある。体高56~66センチメートル。毛色はセーブル、トライカラー、ブルーマール、白。シェパード犬は原産地ドイツ。万能作業犬で、警察犬、盲導犬としても活躍する。体高55~63センチメートル。毛色は黒、ウルフ、ブラックエンドタンなど。シェトランドシープドッグはコリーを小形にしたような犬種で、家庭犬としてたいへん人気がある。長毛で、体高33~41センチメートル。原産はイギリスのシェトランド諸島。オールドイングリッシュシープドッグは原産地イギリス。全身むく毛の大形犬。体高56センチメートル以上。毛色はグレー、グリズル、ブルーマールの単色と白斑(はん)および白とブルーマール斑。ベアデッドコリーは近年人気の出てきた犬種。原産地イギリス。体高46~59センチメートル。むく毛で、硬い上毛を有する。口ひげ、ほおひげがある。毛色はフォーン、スレート色、グレーなど。
[増井光子]
テリアグループ
terriers 小形のものが多いが、なかには中形のものもいる。多くのものが獣猟に用いられてきた。いずれも気性が強く、陽気なテリア・キャラクターといわれる独特の気質を有する。エアデールテリアはテリアのなかで最大で、体高55~61センチメートル。警察犬、盲導犬、獣猟犬に用いられる。原産地イギリス。毛色は四肢と頭部が褐色で背が黒く、断尾する。トリミングが必要。スコッチテリアは小形で立ち耳の頑丈な感じの家庭犬。体高25~28センチメートル。毛色は黒、ブリンドル。トリミングが必要。フォックステリアにはワイヤーヘアードとスムースの2種があるが、前者のほうがファンが多い。体高39センチメートル以下。毛色は白地に黒とタンの斑(はん)がある。イギリス原産で、断尾しトリミングする。ベドリントンテリアもイギリス原産。子ヒツジのような感じの犬種で、トリミングが要る。体高38~44.5センチメートル。毛色はブルー、レバー色など。ミニチュアシュナウザーの原産地はドイツ。口ひげを生やした陽気な犬種。断耳と断尾、トリミングをする。毛色はペパーエンドソルト、黒など。
[増井光子]
愛玩犬グループ
toys 愛玩犬は室内で飼育される小形の犬種。チワワは最小の犬種で、体重わずかに0.4~2.7キログラムしかない。長毛と短毛がある。毛色は赤、黒、クリーム、ブラックエンドタンなど。原産地はメキシコ。マルチーズの原産地は地中海のマルタ島。体重3.7キログラム以下で、全身長毛に覆われた美しい犬種。ポメラニアンは原産地ドイツ。体高20~25センチメートル。長毛で立ち耳。毛色は赤、オレンジ、クリーム、セーブルなど。ヨークシャーテリアは原産地イギリス。長い絹のような被毛があり、立ち耳。断尾する。毛色はスチールブルーで、子犬のうちは黒っぽい。トイプードルの原産地は中部ヨーロッパ。体高28センチメートル以下。トリミングする。毛色は白、黒、シルバーなど。シーズーは原産地中国。近年人気がある。体高26.5センチメートル以下で長毛。毛色はいろいろで、尾先と頭部に白斑(はん)があるものが好まれる。
[増井光子]
非猟犬グループ
non sporting dogs 前述のグループに属さない一般家庭犬をいう。チャウチャウは中国原産の犬種で、体高50センチメートル。毛色は赤、ブルー、黒、クリームなど。ブルドッグは原産地イギリス。体重22.5~25キログラム。短毛で毛色はブリンドル、フォーン、斑(はん)など。ダルメシアンは原産地クロアチア。体高48~60センチメートル。短毛で、白地に黒かレバー色の丸い小斑がある。
[増井光子]
日本原産犬種
日本には昔から人とともに暮らしてきた在来種として、秋田犬、北海道犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬(かいけん)、柴犬などがある。そのほかに日本で改良、作出された犬種として、チン、日本テリア、日本スピッツ、土佐闘犬がある。日本テリアは短毛のフォックステリアに似た犬種であるが、頭数は少ない。
[増井光子]
ドッグショー
前述のさまざまな犬種の作出、改良にドッグショーが果たした役割は大きい。多数の純血犬を一堂に集めて優劣を競うこの催しは、1859年にイギリスで開催されたのが最初である。品種改良のために体形の良化を目的とし、総合的な美しさに重点を置くベンチショーと、能力向上を目ざす各種作業犬のフィールドトライアルや訓練大会などがあるが、一般には前者をドッグショーとよぶ。また、全犬種が出場するもの、単犬種だけのもの、用途別に区分されたグループを対象とするグループ展などにショーのタイプが分けられるが、一般の人が見て楽しいのは全犬種展である。出場するイヌは、年齢、性別、既取得資格などによりクラス分けされ、勝ち抜き戦で席次を定めていく。最近は人気が高く終年開催されるが、普通は春、秋に多い。世界的に有名なのは、イギリスのクラフト展、アメリカのウェストミンスター展などである。
[増井光子]
飼育管理
飼い方の注意
イヌは植物質のものもよく食べるが、元来は肉食獣であるので、よい発育を期待するには、動物タンパクは欠かせない。飼料中のおもな成分の比率は、成犬では動物タンパク20~30%、脂肪10~20%程度であるが、発育期のものでは、動物タンパクは33~50%ぐらいを要する。とくに急速に成長する長脚の大形犬では、十分な動物タンパク、カルシウム、運動が必要である。最近は良質のドッグフードが各種市販されている。ドッグフードには、粒状の固形飼料から、ビスケット状のもの、肉片を生乾きにしたタイプのもの、缶詰とさまざまなものがある。味のほうも肉、鳥、チーズ、ミルクなど、イヌが好みそうなにおいと味つけがされている。また、間食用に、多分に人の視覚にあわせた骨片形のものや、チーズスティック形のものもある。ドッグフードは栄養学的に配慮されてはいるが、毎日同じ献立になるので、イヌが飽きやすい点もある。食事は、子イヌのうちは1日3、4回に分けて与え、成長につれて回数を減じ、成犬では1日2回とする。幼犬時代のほうが体のわりによく食べる。また、育児中の雌には普段より増量して与える。ドッグフードを用いない場合は、くず肉、魚のあら、もつなどを少量の野菜と煮て、ご飯、パン、うどんなどのデンプン質のものにかけて与える。以上のことは一般的な飼育法である。前出のようにグレートデンやセントバーナードなどのような大形犬は、大きいほどよいとされる犬種である。雄大な体格に育成するには、くる病など骨疾患にかかりやすいこともあり、くふうが必要である。こうした特殊な犬種の育成法については、犬種別の飼育書を参照することが望ましい。
日常管理としては毎日の運動が必要である。イヌは元来、広域を徘徊(はいかい)して探索行動を好む動物であるので、一定場所に係留され続けると欲求不満に陥りやすい。運動は小形犬なら30分程度、中形犬で30~50分、大形犬には1時間~1時間半ぐらい、朝夕行う。これは食事前に済ませることで、帰ったあとはブラシで汚れをよく落とし、清潔な水を与える。ブラッシングも欠かせない。短毛種では布で汚れをふき取り、ブラシをかける。普通の犬種や長毛種ではブラッシングのほかに櫛(くし)で毛をすくことも必要である。とくに春の換毛期には多量の枝毛をみるので、すき取ることが必要である。被毛の手入れを怠ると、不潔になり皮膚病の原因にもなる。犬種によってトリミングが要るものもある。トリミングとは指先もしくは器具を用いて、特定部位の毛を抜き取ったり刈り取ったりして整えることである。トリミングする犬種はプードルやテリア類、コッカースパニエルなどである。これらの犬種は、もしトリミングしないで放置すれば、もじゃもじゃの感じになってしまう。1回トリミングすると、ほぼ1か月ぐらいはそのスタイルを保てる。トリミングは習熟すれば一般家庭でもできるが、専門のトリマーもいる。美容的なものとしては、毛の手入れのほかに断耳と断尾がある。ともにそのイヌのもつ姿態の特性をいかすためのものである。断尾の場合は生後1週間ほどのうちに実施し、出血もごく少ない。後肢にオオカミづめがあるものや、犬種によっては前肢の第1指をやはりこの時期に切除する。断耳のほうはずっと時期が遅く、4~5か月ごろの、外耳の成長が完了した時期に行う。断耳する犬種をしないでおくと、垂れ耳となる。この断耳はイヌに苦痛を与えるものとして、イギリスでは禁止されている。このため、イギリスから輸入されるボクサー、ドーベルマン、ミニチュアシュナウザー、グレートデンは垂れ耳のままである。
イヌは環境適応性が強い動物であるが、多くの病気もある。とくに幼犬時代の伝染病であるジステンパーと成犬のイヌ糸状虫症(フィラリア)は、二大疾患といえよう。内部寄生虫症としては、回虫症、十二指腸虫症、鞭虫(べんちゅう)症、イヌ条虫症などが多い。ジステンパーにはよいワクチンがある。生後3か月ぐらいのころに接種を受けるとよい。伝染病にはジステンパーのほかに、伝染性肝炎、レプトスピラ症などがある。これらが混合されたワクチンもあり、ジステンパーの単独ワクチンよりは、こちらの接種のほうが望ましい。また近年はパルボウイルスによる新しい伝染性腸炎が発症して、愛犬家の間に恐慌を引き起こした。これは急性の出血性腸炎をおこす病気で、死亡率も高かったが、こちらにもワクチンが開発されている。内部寄生虫である回虫は幼犬に多い。多数寄生した場合は発育障害をきたすので駆虫が要るが、売薬を買ってやたらに飲ませるのはよくない。駆虫に先だって獣医師の健康診断を受けることが望ましい。心臓糸状虫症はほとんどの成犬がかかる疾病である。カによって血液中に存在する子虫が伝搬されるので、予防は、カに刺されないようにすることである。カよけの電灯、蚊取り器なども市販されており、補助手段として用いられる。子虫の感染を防ぐ薬剤もあり、カの発生期間中投薬する。心臓に寄生した成虫の駆除には、手術による摘出、投薬法などがあるが、獣医師と相談するとよい。ほかには交通事故による外科疾患も多く、老犬では皮膚や内臓に腫瘍(しゅよう)などもみられる。
[増井光子]
飼い主の義務
飼い主は、従来は春と秋の2回、1985年(昭和60)4月より年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、役所に飼い犬届を出さなければならない。イヌによる咬傷(こうしょう)事件も多いので、日常管理にも十分な注意を払うべきで、1975年に告示された「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」にも、放し飼いや汚物により迷惑をかけないように努めることを定めている。イヌのほえ声に対する苦情も多いので、むやみにほえるのをやめさせるしつけも必要である。また無配慮の結果産まれた子イヌを捨てる行為も多く、これは野犬を増やし人畜に被害をもたらすもとともなるし、動物愛護上も好ましいことではなく、1973年にできた「動物の保護及び管理に関する法律」(1999年に改正され、「動物の愛護及び管理に関する法律」となった)で規制されている。繁殖を必要としない場合は不妊手術を望みたい。
[増井光子]
イヌと人間
イヌは地球上でもっとも広い分布をもつ家畜であり、イヌを知らなかったのは、ヨーロッパ人と接触する以前のタスマニア(オーストラリア大陸南東)島民と、アンダマン(インド、ベンガル湾)島民だけであろう。イヌの家畜化は、人類がまだ狩猟採集生活を営んでいたころすでに始まっており、北イラクのパレガウラ(1万2000年前)、イギリスのスター・カー(9500年前)、アメリカのジャガー・ケーブ(1万年前)などの古い遺跡からその骨が出土している。K・ローレンツ(1903―1989)は、イヌと人間の共生的関係は5万年前から始まっていたとしている。新大陸へは、更新世(洪積世)末期(2万~1万年前)に旧大陸から移住してきた人類によってもたらされたと考えられ、太平洋の島々へも、イヌは人類とともに船で渡ったといわれる。
野生動物や敵から人間と家畜を守る番犬として、また愛玩(あいがん)動物としてなど、イヌは諸民族によりさまざまな用途に利用されてきた。猟犬として使われることも多く、南アメリカ南端のフエゴ島先住民のように、魚を網に追い込むためにイヌを使うという特異な例もある。牧畜犬としての利用は、中近東やヨーロッパの牧羊民のみならず、中央アジアのカザフ人(ウマの飼育)や、シベリアのサモエード人(トナカイ飼育)などにもみられる。このほか新旧両大陸の極北地方では、イヌはそりを引く運搬動物として重要である。その毛皮が衣服に加工されることも多い。北アメリカの平原先住民は、イヌに引き具をつけて荷運びに使っていた。また軍用犬としての利用は古く、すでに古代アッシリアやギリシア・ローマ時代にみられる。イヌを食べる民族も少なくないが、純粋に食料として扱われる場合(古代メキシコのアステカ人、アフリカのマンデ諸族など)と、宗教儀礼や呪術(じゅじゅつ)の一部として食される場合(北アメリカの先住民をはじめ世界中にみられる)に区別できる。逆にイヌの肉がタブーとされることも多く、これは犬祖(けんそ)神話などの宗教的、神話的観念と結び付くことが多い。
イヌは諸民族の世界観のなかでも重要な役割を演じている。ベトナムのヤオ人は、原初に槃 (ばんこ)というイヌがおり、中国の皇帝の宿敵を倒した褒賞に皇女をもらい受け、その子供たちが自分たちの祖になったという起源神話を伝えている。エジプトのアヌビス神や、古代メキシコ(アステカ人)のショロトル神も、イヌの属性をもつ神であり、双方とも現世と冥界(めいかい)の仲介者としての務めを果たしていた。また古代アンデスのワンカ人やシベリアのニブヒ(ギリヤーク)人などは、イヌを神々への供物とし、邪術を防いだり、雨乞(あまご)いをする際にもイヌを供犠(きょうぎ)した。
(ばんこ)というイヌがおり、中国の皇帝の宿敵を倒した褒賞に皇女をもらい受け、その子供たちが自分たちの祖になったという起源神話を伝えている。エジプトのアヌビス神や、古代メキシコ(アステカ人)のショロトル神も、イヌの属性をもつ神であり、双方とも現世と冥界(めいかい)の仲介者としての務めを果たしていた。また古代アンデスのワンカ人やシベリアのニブヒ(ギリヤーク)人などは、イヌを神々への供物とし、邪術を防いだり、雨乞(あまご)いをする際にもイヌを供犠(きょうぎ)した。
[松本亮三]
イヌの民俗
日本で犬の語が最初に文献に現れるのは『古事記』の下巻からで、上代にはすでに猟犬や番犬用のイヌを飼育するための「犬飼(養)部(いぬかいべ)」が存在していた。また、平安時代の末から鎌倉時代にかけて行われた犬追物(いぬおうもの)は、イヌを狩猟動物に見立てた武技の一種である。このほかイヌはそりや荷車を引くなどの労役にも使われたが、とくに狩猟者にとって重要で、タカ狩りに伴われるほか、ウサギ狩りや鳥撃ちにも欠かせないものであった。早くから家畜化が進んでいたが、一方でオオカミ、ヤマイヌ、野犬などとの区別が明確でなく、ヤマイヌの群れに取り囲まれたとか、頭の上を跳び越えられたとか、「送り狼(おおかみ)」の話などもある。送り狼は、夜道を歩くと後ろからついてくるというもので、途中で転べば襲われるが、転ばなければ家まで送ってくれるという。またイヌを恐れる人は、イヌに出会ったとき両手の親指を中にして握り、「戌亥子丑寅(いぬいねうしとら)」と3回まじないを唱えればイヌがほえないという。霊的な動物としても登場し、三峯(みつみね)神社(埼玉県秩父(ちちぶ)郡)や、山住(やまずみ)神社(静岡県磐田(いわた)郡)では山犬(ニホンオオカミ)を使令(つかわしめ)としている。イヌの霊が、人間にのりうつるといわれる犬神憑き(つき)の現象も、中国、四国、九州地方に伝えられている。郷土玩具の「犬張り子(いぬはりこ)」は、寝室に置いて幼児を守る魔除(まよ)けとされた。またイヌの出産が軽いことから、岩田帯(妊娠5か月目の戌の日に締める腹帯)に安産を祈って犬の字や絵を書いたり、宮参りなど誕生後初めて生児が外出するときに、額へ鍋墨(なべずみ)や紅(べに)で犬の字を書いて魔除けにすることもある。千葉、茨城から福島県にかけて、イヌがお産で死ぬと、主婦たちが犬卒塔婆(いぬそとば)と称する二股塔婆(ふたまたとうば)を路傍に立てて供養する習俗があるが、これは講仲間(信仰的動機で集まった集団)がイヌの死に関係なく立てる場合もある。
イヌは「犬塚(いぬづか)」(犬を葬った由来を説く伝説)、「白米城(はくまいじょう)」(落城伝説の一つ)、「犬飼村(いぬかいむら)」(人身御供(ひとみごくう)伝説)など多くの伝説に登場し、「桃太郎」「花咲爺(はなさかじじい)」「猿神退治」などの昔話のなかでも重要な役割を果たしている。イヌを取り上げた諺(ことわざ)も多く、イヌが人間生活のなかにいかに深く入り込み、密接な関係を長く保ってきたかがわかる。
[井之口章次]
『ローレンツ著、小原秀雄訳『人・イヌにあう』(1968・至誠堂)』▽『平岩米吉著『犬の行動と心理』(1976・池田書店)』▽『愛犬の友編集部編『愛犬の百科シリーズ』全7巻(1978・誠文堂新光社)』

アイリッシュセッター

アフガンハウンド

イングリッシュセッター

イングリッシュポインター

エアデールテリア

グレートデン

コリー

シェトランドシープドッグ

シェパード

スコッチテリア

スピッツ

セントバーナード

ダックスフント(ロングヘア)

ダルメシアン

チベッタンテリア

チャウチャウ

チワワ(スムースコート)

チワワ(ロングコート)

チン

ドーベルマン

日本テリア

ビーグル

ピレニアンマウンテンドッグ(グレートピ…

ブルドッグ

ベアデッドコリー

ベドリントンテリア

ホイペット(ウィペット)

ボクサー

ポメラニアン

ボルゾイ

マルチーズ

ミニチュアシュナウザー

ミニチュアピンシャー

ヨークシャーテリア

ラブラドルレトリバー

ワイマラナー

ワイヤーヘアードフォックステリア

アヌビス


 獣猟犬 獲物を追う方法から視覚型と嗅覚(きゆうかく)型に分ける。(a)視覚型 グレーハウンド,サルキー,アフガンハウンド,ボルゾイなど。(b)嗅覚型 フォックスハウンド,ビーグル,ブラッドハウンド,
獣猟犬 獲物を追う方法から視覚型と嗅覚(きゆうかく)型に分ける。(a)視覚型 グレーハウンド,サルキー,アフガンハウンド,ボルゾイなど。(b)嗅覚型 フォックスハウンド,ビーグル,ブラッドハウンド, 鳥猟犬 スパニエル,セッター,ポインター,
鳥猟犬 スパニエル,セッター,ポインター,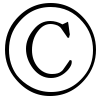 テリア類 かつてネズミなどの駆除に使われたもので,使役犬に含めることもある。フォックステリア,ミニチュア・シュナウツァー,
テリア類 かつてネズミなどの駆除に使われたもので,使役犬に含めることもある。フォックステリア,ミニチュア・シュナウツァー,