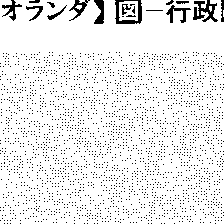目次 自然 地形 気候 土壌 植物,動物 住民 人種,言語 人口 宗教 国民性 歴史 古代,中世 ブルゴーニュ家,ハプスブルク家の支配 オランダ共和国--経済,文化の黄金時代 ネーデルラント王国の成立 憲法改正と産業革命 資本主義の進展 第1次大戦と戦間期 第2次大戦と戦後 1960年代以降 政治,軍事,外交 政治制度 地方行政,司法 軍事 外交 経済,産業 経済 財政,金融 農林漁業 鉱工業 貿易 交通,観光 労働,社会保障 社会,文化 社会 教育 文化 音楽 日本との関係 基本情報 正式名称 =ネーデルラント王国Koninkrijk der Nederlanden/Kingdom of the Netherlands 面積 =3万7354km2 人口 首都 =アムステルダムAmsterdam(日本との時差=-8時間) 主要言語 =オランダ語 通貨 =グルデンGulden(英語でギルダーGuilder),1999年1月よりユーロEuro
ヨーロッパの北西部にある立憲君主国。日本の九州にほぼ等しい面積の小国で,人口密度は世界屈指の高さである。16世紀後半の建国以来ホラント州(現在の南・北ホラント両州)がこの国の政治,経済,文化の中心であったため,〈ホラントHolland〉とも呼ばれる。東は西ドイツ,南はベルギーと国境を接し,北と西は北海に面して長い海岸線を形づくる。国名のネーデルラント は〈低い国〉の意で,現在も国土の約4分の1は標高0m以下にある。憲法上の首都はアムステルダムであるが,国会,政府諸機関,諸外国公館はハーグに置かれている。現在11州よりなり,本国のほか,カリブ海上のアンティル諸島(クラサオ島,アルバ島など)を領有する。
オランダは,ヨーロッパ諸国中最も早い時期(1600)から日本と交渉をもった国である。鎖国時代には唯一の交易相手国で,西欧の文物はもっぱら長崎,出島のオランダ商館を介して日本に輸入された。このため〈オランダ〉は外国の代名詞となり,〈オランダイチゴ〉〈オランダ海芋(かいう)〉〈オランダ鏡〉など,舶来品にその名を冠した例が多い。西欧諸科学もオランダ語を通じて紹介されたため,〈蘭学〉と呼ばれた。〈オランダ〉の呼び名は〈ホラント〉またはポルトガル語の〈オランダOlanda〉に由来し,古くは〈阿蘭陀〉〈和蘭陀〉〈和蘭〉と記された。
自然 地形 この国の地形の大部分は第四紀に形成されたが,東部の西ドイツ国境沿いに第三紀層がわずかにみられ,南東部に突出したリンブルフ州南部台地は白亜紀の岩石からなる標高90~300mの丘陵地(最高点は321mのファールセルベルフVaalserberg)を形成し,地表近くに石炭紀の地層をもつ。国土の骨格を形づくる地形は,オランダを東から西,北へ貫流するライン川,マース(ムーズ)川の新旧の堆積地形であり,その広い中央部はライン川の三角州で河成粘土からなる。ライン川はオランダに流入するとワールWaal川とネーデルライン川に分かれ,後者はアルンヘムの東方でエイセルIJssel川を分流し,さらに下流はレックLek川と呼ばれる。エイセル川は北流してアイセル(エイセル)湖に注ぐ。沿岸地域のうち,南西部のベルギー国境から北東に延びる海岸地帯にはスヘルデ川の東・西両河口とライン川,マース川の河口が北海に向かって広く開かれ,多くの島が点在する。デルタ工事はこれらの島を堤防でつないで海岸線を短縮した。ハーグ南西のフック・ファン・ホラントからわずかに湾曲して北上する沿岸部には新旧の砂丘があって北海に対し天然の堤防となり,その内側の土地は海面より低く(最低点は約-6m),主として海成または河成粘土と泥炭からなる。北ホラント州の北端デン・ヘルデルDen Helderから北東方に弧を描いてフリージア諸島が延び,その内側にはワッデン海を隔ててフリースラント,フローニンゲン両州の海岸が続く。堤防の内側の海成粘土と泥炭の地域は干拓され肥沃な農地に変えられた。フローニンゲン東部のスロホテレンSlochteren付近には,泥炭層の上に空気を通さない岩塩層が形成されたため膨大な量の天然ガスが埋蔵されている。1932年ゾイデル海の締切り堤防(29.8km)が築かれ,堤防上の自動車道路で北ホラント州とフリースラント州 は結ばれ,ゾイデル海は北東ポルダー(干拓地)をはじめとする四つの大ポルダーと淡水のアイセル湖 (面積1200km2 )に変貌した。
ライン川とアイセル湖のあいだのオランダ中央部の台地は洪積層の砂質土壌である。リス氷河期の氷河が50~100mの氷堆石丘と幅広い谷をつくるこの地域には森林とハイデ(ヒースの生えた荒地)が広がり,起伏に富む風光明媚な景観で知られ,広大な国立公園〈ホーホ・フェリュウェ〉がある。エイセル川沿いの河成粘土地帯の東側,すなわちヘルデルラント州東部とオーフェルアイセル州 は氷堆石丘が点在する広い沖積平野で,洪積層の砂質土壌の低湿な土地は干拓されて牧草地に利用されている。南部の北ブラバント州とリンブルフ州北部は標高50m以下であるが,泥炭地は干拓され牧草地となっている。リンブルフ州南部の,ベルギーから続く丘陵地帯は石灰岩をレス(黄土)がおおい,小麦,テンサイの栽培に適し,また渓谷の斜面は牧草地とされ,地層中には岩塩,石炭が含まれる。
気候 北緯50°~53°という高緯度にもかかわらず,メキシコ湾流と偏西風の影響により西岸気候地帯に属し,全国的に温和な気候で農業に適する。月平均気温は7月で約18℃,1月で約2℃。平均年降水量は約750mmで,春にやや少なく7~11月にわずかに多いが,年間ほぼ均等で,穀物類よりもジャガイモ,テンサイなどの栽培や牧畜に好適である。冬は降雪もほとんどなく,大きな海港は凍結しないが,運河や湖沼は東から張り出す高気圧の影響で短期間凍結する。かつて偏西風が動かした多数の風車は低地帯の水を海に汲み上げたばかりでなく,製粉,毛織物の縮絨,製材などの動力源として利用された。
土壌 土壌は一般に肥沃とはいえない。ことにハイデは地味がやせているので農耕は営めない。フローニンゲン,フリースラント,ゼーラント,北東ポルダー,南東ポルダー,オストフレーボラントなどの海成粘土地帯はやや肥沃で,小麦,テンサイ,ジャガイモ,マメなどが栽培される。ただし土地利用においては,土壌の質とともに地下水位の高低が重要な要因である。すなわち,地下水位が高ければ土地の湿度が高くなり,牧草地に適する。デルタ地域や北ブラバント,オーフェルアイセル,ドレンテなどの泥炭地や海面下の海成粘土または砂質の地域はこの例である。他方,地下水位が低い土地は乾燥し,粘土質,砂質いずれも耕作農業に適するが,砂質地では肥料の多用によってのみ農耕が可能である。オランダは化学肥料投下量がヨーロッパでもっとも多く,1ha当り150kgを超える。
植物,動物 低地帯の小国にもかかわらず,オランダの植物相はかつてはきわめて豊かで変化に富んでいた。しかし,数十年来の人口増大,工業化(都市化,道路網建設,環境汚染),農薬多用などによって植物の環境は急速に悪化している。植生は顕花植物とシダ類を含めて約1200種,蘚苔類約600種を数える。地味のやせている砂質地のうち,コロイドの貧弱な土壌にはオーク・カバ樹林が,コロイド性の土壌にはブナ・オーク樹林が,肥えた洪積層の土壌(砂礫ローム,第三紀ローム,古い河成ローム,レス地帯)にはオーク・シデ樹林が,また肥えた沖積地の粘土質あるいは砂質地域のうち,河谷にはエゾノウワミズザクラ ・トネリコ樹林が,河川地域の低湿な粘土地帯にはトネリコ・ニレ樹林あるいはヤナギ・ポプラの群生が見られる。石灰分の乏しい北部の海岸砂丘は蘚苔類におおわれ,ツツジ科の群落がある。内陸部の泥炭地にはアシ,スゲ,蘚苔類や塩性植物が,また乾燥地にはギョリュウモドキ類の群落が,南部の石炭質の砂丘にはクロウメモドキ類,イボタノキ属,バラなどの低木林が見られる。自然植生は広葉樹が多いが,針葉樹の植林地が森林総面積の70%,国土の7%を占める。
動物相は西ヨーロッパ型に属するが,とくに見るべきものはない。西部および東部の平たんな沖積世の地域よりも東部および南部の洪積世の砂質地域に動物の種類が多く,アカジカ,ノロジカ,イノシシ,キツネ,アナグマ,テンがすむ。リンブルフ南部には他地域に見られぬハムスター,ヤマネ,カメ,サンバガエル,ヤモリが生息し,またワッデン海と西フリージア諸島はカモメなど多数の鳥類が生息,繁殖し,カモなどの水鳥,シギなどの渉禽類の越冬地ともなっている。アイセル湖が淡水化されたため,植物相と動物相は著しい変化を被り,ニシンやアンチョビーに代わってウナギが繁殖し,またデルタ工事によってゼーラント産のカキ,イガイも消滅した。魚類は179種(うち淡水魚57)が知られている。1905年に自然保護団体が結成されて以後,官民の両側から自然の保存と保護が熱心に行われている。
住民 人種,言語 オランダは人種的には北方人種(ノルディーデ)とアルプス人種(アルピーネ)の境界線上にあり,数のうえでは前者が圧倒的に多い。北方人種はライン川,マース川以北の諸州に多いが,東部地域では毛髪はブロンドとなり,長身瘦軀,長頭の特徴もやや薄れる。ライン川,マース川以南では北方人種と並んでアルプス人種も見られ,両者の融合の度合も強い。交通の発達,工業化,都市化は両人種の融合を促進し,地域的特性は減少してきている。オランダ人の身長は平均170cmでスウェーデン人,ノルウェー人,スコットランド人と並んでヨーロッパの中で最も高く,皮膚の色は白い。
住民の大多数は,インド・ヨーロッパ語族の西ゲルマン語派に属するオランダ語を使用する。しかしひと口にオランダ語といっても,風俗,習慣などと同様,多少の地方差が見られる。オランダ語
人口 オランダの人口は18世紀~19世紀前半には停滞していたが,1870-80年ごろの工業化開始期以降ヨーロッパ第1の人口増加国になった。すなわち,1830年には約260万人であったが,1900年に約510万人と倍増し,30年には約800万人,80年には約1400万人,さらに95年には1545万人に達している。ことに1950-70年の増加率は顕著で,6~7年ごとに100万人増え続け,それに伴い1km2 当りの人口密度も1947年の297人から72年の396人に増えた。増加の原因には,(1)死亡率の低下,(2)住宅環境の改善,(3)高度経済成長と社会保障の拡充のほか,(4)カトリックおよび一部のプロテスタントが産児制限をしないこともあげられる。1950年代に1000人当りの出生率は22.7人に著増し,死亡率は7.4人と著しく低下した。しかし,出生率は69年19.2人,71年17.2人と周辺諸国の水準(ベルギー14.5人,西ドイツ17.7人,イギリス16.1人,フランス17.2人)に近づき,他方,男子71.7歳,女子76.7歳に延びた平均寿命が安定した結果,72年には死亡率も8.5人と上昇し,70年代に入り人口増加はやや鎮静化した。
国内の人口分布を見ると,人口の比較的少ない地域は北部諸州(ドレンテ州,フローニンゲン州,フリースラント州),ゼーラント州,リンブルフ州,アイセル湖周辺のポルダーなどの農業地域で,1950年代の工業化と都市化により,これらの地域からはさらに人口が流出した。西部(南ホラント州,北ホラント州南部,ユトレヒト州)は古くから人口密集地域で,南ホラント州の人口密度は1000人を超える。第2次大戦後は都市化が進み,70年には人口2万人以上の都市(136都市)の住民が全人口の60%以上を占めている。人口増加は1万~5万人規模の新興都市に著しく,ことに過密大都市周辺のニュータウンの増加率が際だっている。とりわけ西部では,人口第1位のアムステルダム,ロッテルダム,ハーグ,ユトレヒトの四大都市をはじめ,ドルトレヒト,ライデン,ハールレム,ヒルフェルスム,デルフト,フェルゼン・ベーフェルウェイクVelsen-Beverwijkの人口10万以上の10都市とそれらの都市を囲むニュータウン群が環状に連なり,一大複合都市地帯(オランダ語で〈ラント・スタット〉と呼ぶ)を形成し,国土の5%に当たるこの地域に全人口の30%以上の約500万人が居住している。次いで人口の多い地域は,オランダ綿工業の中心地のトウェンテ地方(エンスヘデ,ヘンゲロー),北ブラバント州の都市群(ブレダ,ティルブルフ,エイントホーフェン など),リンブルフ州南部の鉱業地域(マーストリヒト,ヘールレン・ケルクラーデ,シッタルト・ヘレーン)などである。
宗教 国民のうち,カトリックが40%,プロテスタントが30%(改革派23%,再改革派7%),諸派(アルミニウス派,再洗礼派,ルター派)およびユダヤ教が8%で,残りの約20%は無宗教である。オランダは歴史的にはプロテスタントの国であったが,改革派教会の特権の廃止(1796),憲法改正による信仰の自由の確立(1848),ローマ・カトリックの教権制度復活(1853)によって自立した勢力になったカトリック教会は,19世紀後半の自由党員と自由主義の支配に抗して,政治・社会・文化・教育の全領域で信徒を統合し指導した。自由主義とさらに19世紀末以後の社会主義の浸透による世俗化の進行は,カトリック教会よりも改革派教会にいっそう強い打撃を与え,加えて再改革派の分離(1892)も改革派の勢力を低下させた。第2次大戦後,若い人びとの教会離れが加速され,それが比較的少ないといわれるカトリック教会でさえ日曜礼拝参加者は1967年の63%から70年40%(アムステルダムでは25%)に減少した。
国民性 一般にオランダ人気質あるいは国民性といえば,豊かな現実感覚,素朴,寛容,きちょうめん,計画性,商業国民的な打算としたたかさなどを挙げることができる。こうした特徴は部分的には同じゲルマン系のイギリス人やドイツ人と共通するものでもあるが,にもかかわらずそれらは全体として見るときオランダの歴史や文化に独自の刻印を与えている。オランダの歴史家ホイジンガは《レンブラントの世紀》の中で,17世紀のオランダ文化の特質として簡素な生活およびこれと密接に結びついている節約と清潔好きをあげ,つぎのようにいう。簡素な生活は衣服や慣習,社会生活の色合いや精神的態度から,繁茂する森林もなく平たんな国土自体のたたずまいや都市の構造にまで及ぶ。このような特質は,世界と諸事物を現実として受容し,あらゆる事物の絶対的実在性を確信しようとする現実感覚に由来する,と。また,オランダ人はきちょうめんで,事をなすに当たっては慎重,計画的で決して功をあせらない。きちょうめんさは,たとえば東インド会社の帳簿,日誌,本店とアジア各地との往復文書などの綿密で膨大な記録とその驚くべき保存ぶりなどからもうかがえよう。第2次大戦中ドイツ空軍の爆撃で全壊したロッテルダム市中心街を先見的な都市計画によってみごとな都市空間につくりあげたことは,オランダ人の計画性の好例であり,戦後オランダの国土計画や社会計画などを指導した中央計画局の存在は国際的に有名になった。素朴さについていえば,17~18世紀以来オランダの支配者層は,フランスやイギリスの貴族とは異なり宮廷的な優雅や軍事的栄光とは無縁で,ひたすら海上貿易のもたらす利益を追求した市民たちであった。今日,女王は市民たちにまじって自転車でショッピングをし,権威の象徴であるよりも平和な家庭の主婦,母親のイメージが強い。市民はまじめだが,きまじめやむきになることを警戒し,冗談やユーモアを好む。アムステルダムのキャバレーで戦後30年以上も社会と政治を風刺しているウィム・カンは国民的人気をえ,大晦日の夜のテレビでウィムの鋭いが人間味のあるジョークを聞きながら新年を迎えるオランダ人は多い。堅苦しい秩序や画一主義はオランダ人の最も嫌悪するところで,人それぞれに違うことを認め合うことの中にこそ人間らしさがあると考えるのである。オランダ人が自由や平和を貴ぶのは,小国オランダが生きてゆく道は自由な貿易とそれを保障する国際的平和の中にしかないことを自覚しているからである。多くのオランダ人は英独仏の3ヵ国語を話し,商業に必要な冷静な打算と,柔軟で一筋縄でゆかない抜け目なさを発揮してきた。それらの特質については定評のあるユダヤ人を17世紀に多数迎え,同国人として温かく遇したのも,商業国民としての自信や自覚があったからだと思われる。また,エラスムスの祖国として知られるこの国には,寛容とヒューマニズムの伝統がいまも深く根づいている。19世紀中葉まで改革派教会が公認の宗教として国教会に近い地位を占めたが,カトリックの信徒が迫害されたことはなく,19世紀後半に誕生したプロテスタント系とカトリック系の両政党は常に友好関係を保ってきた。かつてユダヤ人のほかフランスのユグノーなど多くの亡命者の避難港であったオランダが,戦後多くのインドネシア人,スリナム人や移住労働者を受け入れたのも,寛容とヒューマニズムに由来する民族的偏見のなさゆえである。1979年,ベトナムのボート難民の報がひとたび伝わると,政府は3000人の受入れをいち早く決定し,救済資金の寄付金が30億円に達したことも特筆してよいだろう。
歴史 古代,中世 オランダは16世紀末に独立するまで,今日のベルギー,ルクセンブルク,北フランスの一部を含むネーデルラント の一部をなし,これらの地方とほぼ共通の歴史をもった。
前1世紀の中葉,ユリウス・カエサルの率いるローマ軍はベルガエ人を破り,ライン川以南の地域を征服して属州ガリア・ベルギカGallia Belgicaとし,さらにライン川を越えて全ネーデルラントを支配しようとしたが,ライン川北方に住むバタウィ人Bataven,カンニネファート人Kanninefaten,フリーシー人Friezenなどのゲルマン系諸部族にさえぎられて成功しなかった。3世紀以降のゲルマン民族大移動期において,フリーシー人は沿岸地域に居住し続け,ザクセン(サクソン)人は北東部からエイセル川の線まで進出し,またフランク人はライン川の南部地方に侵入し,徐々に勢力を拡大した。734年フランク王国カロリング家のカール・マルテルはフリーシー人を,さらに孫のカール大帝はザクセン人を征服し,ネーデルラントはフランク王国の支配下に入った。8世紀にはユトレヒトを中心にアングロ・サクソン の修道士ウィリブロードWillibrordやボニファティウスBonifatiusの布教によってキリスト教化が進んだ。この時期ドレスタットを中心に栄えたフリーシー人の遠隔地商業は9世紀に入ると北海沿岸,ライン川,マース川沿いに猛威を振るったノルマン人の略奪によって衰微した。フランク王国はカール大帝の子ルートウィヒ1世(敬虔王)の死後,ベルダン条約(843)により三分され,ネーデルラントはロタリンギア領となり,さらにメルセン条約(870)でドイツ領に入った。10世紀以降とめどなく進行する封建化のうちから地方伯や豪族はしだいに自立化し,13世紀ごろにはホラント伯領(ゼーラントも支配),ヘルレGelre(ヘルデルラント)公領,ブラバント公領,ユトレヒト司教領が形成された。
ブルゴーニュ家,ハプスブルク家の支配 15世紀前半,フランス王室の分家であるブルゴーニュ家のフィリップ(善良公)はホラント,ゼーラント,ブラバントなどを手に入れ,その子シャルル(突進公)もさらに北方に勢力を伸ばそうとしたが戦死し,ブルゴーニュ公領ネーデルラントはシャルルの女相続人マリアと結婚したオーストリアのハプスブルク大公マクシミリアン1世の領有に帰した。マクシミリアン1世の孫カール5世(1500-58)はハプスブルク家領のオーストリアとあわせてネーデルラントを継承し,母方の縁でスペイン国王を兼ね,さらにネーデルラント諸州の支配権を次々に手に入れてネーデルラント全領域を支配した。カールはブリュッセルに政庁を置いて,中央集権体制を強化した。1517年にドイツで始まった宗教改革はすぐネーデルラントに波及し,ことに南部のフランドル(フランデレン),ブラバント地方の市民のあいだにカルバン主義が普及し,旧教を守護するカールは新教を禁止した。この時期にはまたイタリア・ルネサンスの人文主義がアントワープをはじめとする諸都市の富裕な市民階級のあいだに広まった。ロッテルダムのエラスムスは生涯の多くを国外で過ごしたが,平和と寛容を基調とする彼の人文主義はのちのちまでこの地方の市民に大きな影響を与えた。
オランダ共和国--経済,文化の黄金時代 1555年カール5世はネーデルラントの統治を息子フェリペ2世(スペイン国王,在位1556-98)の手にゆだねた。59年以後スペインに住むフェリペはブリュッセルに執政を置いて,ネーデルラントを統治させた。フェリペは父カール以上に新教徒を激しく弾圧し,さらに集権的な統治を推進し,ついにネーデルラント住民の反乱を招いた。貴族の反抗,聖像破壊運動(1566),アルバ公に率いられたスペイン軍の到着(1567)とアルバ公の圧政は,ついに八十年戦争(1568-1648)を引き起こした。〈海乞食〉(乞食団 )の蜂起による反乱側のホラント,ゼーラント両州占拠(1572)を経て,ネーデルラント北部の7州は,1579年ユトレヒト同盟 を結成し,81年スペイン人に対する独立を宣言した。反乱の指導者オラニエ公ウィレム1世が84年暗殺されると,オルデンバルネフェルトが共和国の政治を指導し,オラニエ公の遺子マウリッツを指揮官にスペイン軍と戦い,1609年にはスペインと12年間の休戦条約を結んで実質的な独立を達成した。オランダ共和国(正式にはネーデルラント連邦共和国)は独立の達成とともに,ヨーロッパで最も富裕な商業国家になった。バルト海貿易を基礎にイギリス,フランス,地中海沿岸地域のあいだの中継貿易を発展させ,さらにアジア(1602年オランダ東インド会社 設立),西インド諸島に進出して巨富をえ,アムステルダムはヨーロッパ最大の貿易港,金融市場になった。アムステルダムをはじめホラント州の諸都市には,商業とともに工業も発達し,諸都市の富裕な市民層を基盤として,絵画,建築,文学,学問などが急速に発達し,17世紀中葉のオランダは大政治家ウィトの指導のもとに,経済的繁栄と文化隆盛の絶頂に達した。
しかし,17世紀の後半オランダはその経済的繁栄を嫉視するイギリスやフランスの挑戦を受け,2度にわたる英蘭戦争 (1652-54,1665-67)とフランス軍の侵入(1672)にあい,国力とともに経済と文化はしだいに後退した。フランス軍侵入によりウィトは退き,代わってオラニエ家のウィレム3世が総督に就任したが,ウィレムはイギリスの名誉革命(1688)でイギリス国王(ウィリアム3世)として迎えられ,衰運をたどる祖国を再興することができず,18世紀のオランダはしだいにヨーロッパの政治と経済の表舞台から退場した。18世紀,オランダの沈滞した政治と社会を改革しようとする〈民主派〉や〈愛国党〉の運動も見られたが成功せず,フランス革命の余波を受け,1795年フランス軍の侵入によってオランダ共和国は崩壊し,バタビア共和国 (-1806)が成立した。オランダ共和国 →八十年戦争
ネーデルラント王国の成立 1806年ナポレオンは弟ルイをオランダ国王に任命してバタビア共和国をオランダ王国Koninkrijk Hollandとし,さらに,10年にはフランスに合併した。13年ナポレオンがライプチヒで大敗するとオランダ人は駐留フランス軍を追放し,イギリス亡命中のウィレム6世を主権者として迎えた。ナポレオン戦争後,イギリス,プロイセンはフランスの膨張を阻止するためオランダの強化を策し,パリ条約でベルギー,リエージュをオラニエ=ナッサウ家 の統治下に編入することに決めた。15年ウィレムは憲法を制定し,ブリュッセルで即位してウィレム1世と称し,ここにネーデルラント王国Koninkrijk der Nederlandenが成立した。しかしオランダの旧支配者層は中継貿易復活の夢を追い,工業の保護育成に消極的で,近代的企業家は出現せず,国民の大部分は失業と貧困の中に埋没していた。加えて1579年以来2世紀半にわたってオランダと異なる運命を歩んできた南部のベルギーはウィレム1世の独善的なオランダ中心主義と専制的統治に対してしだいに不満を抱くようになっていた。
ベルギーの住民はほとんどがカトリック教徒で,南東部ワロン語(フランス語)地域の工業先進地域は保護主義を要求し,住民は公用語のオランダ語に強い反感をもっていた。ベルギー住民はフランスの七月革命勃発(1830)のニュースに触発されてついに独立運動を起こした。列国はロンドン会議(1830)を開催してベルギー独立を承認したが,ウィレムは頑強に反対し,39年にいたってこれを受け入れた。ウィレムは専制的統治とベルギー独立に対する頑迷な態度によって国民の人気を失って退位し,息子のウィレム2世が登位した。
憲法改正と産業革命 1840年代に入ると停滞と無気力の支配するオランダにも,イギリス,フランスなど先進国の影響を受けた知識人と未熟ながら東部のトウェンテ地方やアルンヘム近辺,北ブラバント州などに芽生えた産業資本家層によって自由主義運動が展開された。トルベッケ を先頭とする自由主義運動は48年の憲法改正に結実し,この改正によって教育・結社・集会・出版・信仰の自由,責任内閣制,単年度予算制,一定額以上の納税者による議員の直接選挙などが実現し,オランダは近代的な立憲君主国家へと脱皮する。憲法の自由主義的改正後,自由派(自由党)はほぼ40年間にわたってオランダの政治・経済を支配した。19世紀後半はまた近代的政党の形成期であった。自由党,カトリック党(RKSP)の成立に促されて保守的なプロテスタントもA.カイペル の指導で反革命党(ARP)を結成し,自由党が自由主義的で世俗的な公教育を推進すると,カトリック党と反革命党は結束して反対し,宗派立の私立学校に対する国庫補助を要求した。
48年憲法と自由主義的経済政策,オランダ領東インド植民地(ジャワ島など)の搾出利潤による鉄道敷設,アムステルダムの北海運河やロッテルダムの新マース運河の開設,後背地ドイツの工業化によるライン航行の発達などによって,オランダは60-70年代にいたってようやく本格的な産業革命を迎えた。さらに東インド植民地における強制栽培制度の廃止と自由農業企業の展開は対植民地貿易の繁栄を促し,植民地物産の加工業や中継貿易を発展させた。
資本主義の進展 1890年ごろまでにオランダの産業革命は完了し,その結果,資本主義の進展はオランダの国民経済を世界資本主義体制の中に組み込んだ。1870年代末から始まった長期的不況に代わって,97年から第1次世界大戦まで続く国際的な好況下に,オランダ経済も進展した。綿業,製陶,製紙,マーガリン製造,機械・金属工業に加えて植民地物産の加工業が発達した。工業の発展と後背地ドイツの経済繁栄,対植民地貿易によって貿易も拡大し,貿易額は1876年の1000万グルデンから1912年の1億グルデンへと10倍になり,また海運業と造船業が飛躍的に成長した。1870年代以降アメリカとロシアの安価な小麦の流入により長期的恐慌に陥ったオランダ農業は,協同組合化,機械化,飼料・肥料の輸入による園芸・酪農への構造転換を図り,97年以後の持続的好況の波に乗ってドイツ,イギリスへの農産物輸出を拡大させた。
資本主義の展開は労働運動を活発にし,労働者階級の解放と民主化を推進した。81年にはドメラ・ニーウェンハイスFerdinand Domela Nieuwenhuis(1846-1919)が社会民主同盟(SDB)を結成し,94年トルールストラPieter J.Troelstra(1860-1930)らにより社会民主労働党(SDAP)が結成され,1906年にはオランダ労働組合連合(NVV)が成立した。労働者階級の政治的自覚は激しい選挙権拡大運動に発展し,1887年自由党政府の憲法改正で有権者は10万から35万に増大した。19世紀後半,自由主義と資本主義を推進してきた自由党の勢力は皮肉にも資本主義の確立とともに退潮し,代わってカトリック党,反革命党の宗派政党が勢力をえ,社会民主労働党も急速に台頭し,以後オランダはこれら諸政党の連立政権の時代に入った。
第1次大戦と戦間期 1914年7月第1次世界大戦が勃発すると,列国の紛争に巻きこまれないよう政府は厳正中立を堅持し,国土防衛のために総動員令を発した。オランダはドイツ軍の侵入を免れたが,戦争は海上貿易の縮小と日常必需品の不足など国民経済を困難に陥れた。戦時下の国民的一体感の盛り上がる中で,17年ファン・デル・リンデンCort van der Linden(1846-1935)内閣は憲法を改正し,すでに戦前からの懸案であった選挙法改正(普通選挙,比例代表制)と学校問題(公・私立学校の全額国庫負担)を解決し,19年議会は婦人参政権などの社会立法(1日8時間労働,老齢年金受給開始年齢引下げなど)を可決した。戦後オランダ経済はいち早く復興したが,20年秋には過剰生産と戦後インフレの危機が始まり24年まで続いた。25年以後,経済は相対的安定期を迎え,27年以後も農業不況を除いてオランダの好況は持続した。
29年10月アメリカに始まった大恐慌は好況に終止符を打ち,31年5月にはオーストリアの金融恐慌により事態はいっそう深刻となり,失業者は10万人を超え物価は1920年代の水準まで下落した。33年コレインHendrik Colijn(1869-1944)が組織した危機突破内閣は不況克服と雇用拡大に全力をあげたが,失業者数は33年35万人,35年41万人,36年47万人と増え続け,実に全労働人口の約40%に達した。この年オランダは金本位制を廃してグルデン切下げに踏み切り,ようやく不況のどん底から脱した。しかし,慢性的農業恐慌下の農民や経済秩序の崩壊におびえる中産市民,失業労働者などは,危機に対処する強力な対策を実施しえない議会政治に失望し,30年代半ばには左右両翼の急進主義の勢力が大きく伸びた。他方で自由主義的知識人らによるファシズムと共産主義とに抵抗する組織や運動も勢いをえ,37年の総選挙では左右両勢力は敗退し,コレインの率いる反革命党が勝利をえた。第2次大戦前夜の39年8月,デ・ヘールDirk Jan de Geer(1870-1960)挙国一致内閣が成立し,社会民主労働党は党首アルバルダほか1名の議員がオランダ史上初めて政権に参加した。同月28日新政権は総動員令を布告し,ウィルヘルミナ女王(在位1890-1948)はラジオ放送で厳正中立の声明を発表した。
第2次大戦と戦後 1940年5月10日未明,ナチス・ドイツ空軍の爆撃機編隊はロッテルダム,ハーグ周辺にある空軍基地を爆撃し,時を同じくしてドイツ機甲部隊は東部国境の諸地点から進撃を開始した。さらに落下傘部隊は西部の重要拠点に降下した。予想を絶するドイツ軍の電撃作戦に,女王一家と政府はロンドンに亡命し,ドイツ空軍の集中爆撃でロッテルダム市中心部の大半が廃墟と化すると,重要都市が全滅するのを恐れたオランダ軍は同月15日降伏した。以後,解放までの5年間オランダ国民はドイツ軍の占領下にあって苦難の時を過ごした。
ドイツ軍占領下における議会活動の停止,言論の弾圧,ユダヤ人狩り,強制労働,日常必需品の欠乏とインフレの経済破局の中で,占領軍に対する抵抗運動が激しく燃え上がった。44年5月のノルマンディー上陸作戦に成功した連合軍はフランス,ベルギーを解放し,年内にオランダに迫った。しかしドイツ軍はライン川,マース川の線で頑強に抵抗し,ようやく45年5月5日連合軍カナダ部隊の攻撃のまえにワーヘニンゲンで降伏した。解放直後,女王と亡命政権は帰国し,戦後の再建は開始されたが,食糧も衣料も原料も欠乏し,経済復興は進まなかった。48年からアメリカのマーシャル・プランによるヨーロッパ復興計画が発足し,50年代初頭には戦前の生産水準に復した。占領下におけるナショナリズムの高揚,対独レジスタンスの経験は,戦後オランダの経済発展にとって労使の協調,政府による賃金,物価,家賃,地代などの厳しい統制,徹底的な計画経済などの遂行を可能にした。50年代のオランダ経済は政治における国民的コンセンサスの実現,労使の安定,低い賃金・物価水準,工業化の推進によってめざましい経済成長と輸出拡大を達成した。
46年,社会民主労働党と自由民主同盟は解党し,国民政党を目ざして労働党(PvdA)を結成し,労働党党首ドレースWillem Drees(1886-1988)は48年から10年間にわたって共産党を除く幅広い連立政権を組んで多難な政局を指導し,高度経済成長を達成した。ドレース内閣にとって植民地独立問題と53年2月にオランダ南西部デルタ地帯を襲った大洪水とは大きな試練であったが,後者はデルタ計画 としてデルタ地域締切り工事に結実した。オランダ領東インドは第2次大戦中日本軍に占領されたが,日本軍が降伏するとスカルノらはインドネシアのオランダからの独立を宣言した。49年オランダ政府はハーグ円卓会議を開催してインドネシアへの主権委譲を決め,4世紀半にわたって築いた東インド植民地におけるオランダの権益はすべて失われた。
1960年代以降 50年代末ロッテルダムのユーロポート港における臨海工業の発展とヨーロッパ経済共同体(EEC)の成立によってオランダ経済はいっそうの発展期を迎えた。しかし高度経済成長は60年代前半に激しい労働力不足,賃金・物価の高騰,外国人労働者の移住を引き起こした。第4次ドレース内閣の崩壊(1958)をもって,戦後オランダの政治を支配した,共産党を除く全政党による連立政権の時代は終りを告げ,連立政権の柱だったカトリック人民党(KVP)と労働党が対立を深め,59年の選挙では両党に続いて自由民主人民党(自民党。VVD)が第三党として浮上した。労働党は戦後初めて閣外に去り,カトリック人民党と反革命党,キリスト教歴史連合(CHU)の宗派3政党と自由民主党の連立政権が続いた。65年カトリック人民党,労働党,反革命党のカルスJoseph M.L.T.Cals(1914-71)連立内閣が成立して広範な学制改革を行ったが,この頃から数年間,豊かな福祉国家は学生・若者の反乱と新左翼の台頭に揺れ動いた。66年春のベアトリックスBeatrix(現女王)の結婚に反対する〈プロボProvo〉(反体制のアナーキスト・グループ)らの運動,68年大学の管理強化反対の学生運動,労働者の街頭デモなどの直接行動が続いた。急進主義は政党にも波及し,労働党左派の青年層は新左翼を名のり,王制廃止や反NATOを唱えて党内のヘゲモニーを握り,66年には〈民主66(66年民主主義者)〉が結成されて憲法改正,上院廃止,首相公選などを主張した。他方70年には〈民社70(70年民主社会主義者)〉が成立してニューライトを標榜した。
持続する賃金・物価の高騰は輸出不振を招いて67年以降不況に陥り,失業が増大し,オランダ経済はスタグフレーションに突入した。70年代に入っても激しい労働争議,学生運動が続発し,オランダ社会はひととき騒然とした空気に包まれた。73年中道左派のデン・アイルJohannes M.den Uyl(1919- )連立政権が成立した。秋の石油危機にはオランダはアメリカとともにアラブ産油国から石油禁輸の対象とされたが,幸い国内天然ガスの生産・消費量が飛躍的に増え,この危機を乗り越えることができた。多党化と豊かな福祉社会の中で教会や宗教がしだいに影響力を弱めてゆくことに危機感をもったカトリック人民党,反革命党,キリスト教歴史連合の宗派3政党は73年キリスト者民主同盟(CDA)として院内統一会派を結成した。77年の選挙で労働党が第一党になったが過半数には至らず,第二党CDAのファン・アフトAndreas A.M.van Agt(1931- )を首班とするCDA,自由民主人民党(VVD)連立政権が成立した。
81年の選挙ではCDAが第一党になったものの,VVDをあわせても過半数に満たず,小党分立の様相をますます濃くした。ファン・アフト首相はCDA,労働党,〈民主66〉と中道左派連立内閣を新たに組織したが,82年5月,労働党はアメリカの巡航ミサイル配備受入れ,社会保障費削減に反対して連立を解消した。同年9月の選挙でCDAは第二党に後退,議席を伸ばしたVVDと中道右派連立内閣を結成した。首相にはCDAの新党首ルッベルスRudolph Lubbers(1939- )が就任した。連立政権は86年の選挙を乗りきって第2次ルッベルス内閣を成立させ,経済回復に成果をあげたが,89年,環境保護計画の財源をめぐって連立内部で対立が生じ,内閣総辞職,選挙の繰上げ実施となった。選挙ではVVDが後退し,第一党の座を保持したCDAのルッベルス首相は政局の安定を求めて連立の相手を労働党に替え,CDAと労働党による中道左派の第3次ルッベルス内閣を発足させた。
政治,軍事,外交 政治制度 1815年に成立したオランダ(ネーデルラント王国)は,オラニエ=ナッサウ家を世襲王室とする立憲君主国である。しかし,1815年制定の憲法が48年,84年,87年,1917年,24年と数次にわたって改正された結果,20世紀初頭,オランダは実質的には議会制民主主義国家になった。憲法は,国王・内閣の権限,議会と参政権(普通選挙と比例代表制),司法,地方行政,防衛,国家財政,教育などについて規定し,信仰・言論・集会・結社・出版の自由を保障している。責任内閣制で,憲法上は国王に任命されるが,実質的には議会の多数党から任命される首相と各省大臣の構成する閣僚会議が行政権を執行する。立法権は国王と議会が行使する。議会は上下両院からなり,下院(150議席,4年任期)は直接・普通選挙で選出され,上院(75議席,6年任期,3年で半数交替)は州議会から選出される。法案は国王が枢密院に諮ってまず下院に提出する。下院は法案の採否と修正の権利および発議権をもち,上院は修正権,発議権をもたない。上下両院とも選挙年齢は25歳(1917)から23歳(1946),21歳(1962),18歳(1972)へと引き下げられた。
19世紀末以来オランダの政党はカトリック系,プロテスタント系(2派),労働党系,自由党系に分かれ,過半数の議席を占める大政党が存在しなかったので,連立政権が続いた。1917年比例代表制が導入されると小党分立の傾向はさらに固定化された。第2次大戦後,ことに60年代後半から小党分立,多党化傾向はいっそう強まったが,他面この国の憲政史に1世紀近くも大きな役割を果たしたカトリック人民党とプロテスタント系の反革命党,キリスト教歴史連合は73年合同してキリスト者民主同盟(CDA)になった。
地方行政,司法 オランダは11の州provincieと約850の地方自治体(市町村の区別はなく,大都市も小村落も同じようにヘメーンテgemeenteと呼ばれる)がある。州,ヘメーンテの権限は非常に強く,独自の財政をもつ。またその首長は国王により任命され,議会の議長を務める。立法機関としての州議会およびヘメーンテ議会は直接選挙制の議員によって構成される。行政機関として州参事会(州知事と6人の州議員)およびヘメーンテ参事会(市長,議員互選の助役)がある。なお中世以来,治水,堤防管理などのための,地域住民の自治組織があり,地域デモクラシーに重要な役割を担ってきた。
訴訟は民事,刑事とも主として専門の裁判官(勅任,終身制)によって扱われる。62の区裁判所,19の地方裁判所,5の控訴院,最高裁判所(ハーグ)がある。警察は国家警察と自治体警察とに分かれ,後者は大都市に置かれる。
軍事 オランダにとって,NATO軍との協力が国土防衛,軍備の基本政策である。兵役は義務制(徴兵制)で,兵役期間は陸・海・空軍によって異なり16~24ヵ月である。1980年,総兵力11万5000人で,陸軍7万5000人,海軍1万7000人,空軍1万9000人,軍事費は約44億グルデンである。陸軍は大部分NATO軍に編入され,一部は西ドイツに駐在し,また別に国内防衛部隊がある。海軍は巡洋艦1,駆逐艦12,フリゲート艦大型6,同小型6,潜水艦6などのほか海軍航空隊,陸戦隊を有し,NATO大西洋海軍に統合されている。空軍の航空機種はロッキードF104G(スターファイター),ノースロップNF5AV,80年以後はアメリカのF16戦闘機を採用し,対空誘導弾ナイキ,ホークが配備されている。
外交 第2次世界大戦以後オランダは西ヨーロッパの忠実な一員として今日にいたっており,(1)NATO体制の堅持とヨーロッパ統合の推進,(2)貿易・海運国家として海空航行の自由と通商の自由の堅持,(3)第三世界への積極的な経済・技術援助,を外交の三大基調としている。
1944年ベルギー,ルクセンブルクと〈ベネルクス関税同盟〉(58年に経済同盟)を結び,政治的経済的に緊密な協力体制をつくり上げた。46年国際連合の原加盟国となり,ほとんどの国連諸機関に加入している。49年NATOの一員になり,51年ECSC(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体),57年EEC(ヨーロッパ経済共同体),EURATOM(ヨーロッパ原子力共同体)に参加した。67年ECSC,EURATOM,EECは統合されてEC(ヨーロッパ共同体)となる。オランダはヨーロッパ統合に積極的で,ヨーロッパ議会をはじめとするヨーロッパ諸機関に参加しその民主化を唱導し,EMS(ヨーロッパ通貨同盟)発足,ヨーロッパ議会直接選挙の実施,ECへのイギリスの加盟,さらにギリシアの正式加盟決定を積極的に支持した。東欧諸国との関係は他の西欧諸国と変りはない。1950年イギリスに続いて中国を承認した。インドネシアとは,スハルト政権になってから外交・経済関係を復活させ,オランダは借款供与,投資を行っている。
経済,産業 経済 第2次世界大戦によってオランダは国富の30%,生産設備の40%を失い,さらにインドネシアの独立によって,経済的支柱であった植民地向けの貿易,工業,海運,膨大な投下資本と利潤を喪失した。戦後の経済的破局と人口増大に直面したオランダは,単なる経済復興でなく工業化を中心とする経済構造の再編成を決意し,工業化は,マーシャル・プラン援助をきっかけとして,50年代から60年代にかけて着々と成功を収めた。政府は賃金,家賃,小作料,生活必需品価格を厳しく統制したが,イギリスのように重要産業を国有化することはなく,経済発展を私的な利潤追求活動にゆだね,政府は金融,税制,公共投資などの間接的手段を通じて経済を計画化された方向に誘導することをたてまえとした。
戦後オランダのめざましい経済成長は国民所得,輸出,投資,労働生産性の著しい上昇に示されている。国民所得は1945年以降,年率平均10%(実質4.5%)の上昇をみせ,人口1人当り所得は1万0662ドル(1980。世界第9位)である。経済成長率は,60年代には5.8%(1964-69)とヨーロッパ諸国の中でも上位にあったが,70年代には他の諸国並みに低下した。78-80年には平均1.8%,81年にはマイナス成長となり,83年には失業率が17%に達した。しかし政府の景気浮揚策もあって80年代半ばから景気は回復し,88-91年には3%を超える成長を遂げた。以後もEU諸国の景気回復を背景に経済は比較的安定しているが,失業率は依然として減っていない。
財政,金融 財政支出は国民所得の約30%を超え,教育,社会保障,防衛,建設,農業に対する歳出が多い。財政支出の不足は公債でまかなわれるが,1970年代に入り低成長による歳入減少と失業対策費の激増の結果,公債による累積赤字は深刻な政治問題となった。地方財政はほとんど国からの補助金に頼っている。
通貨はグルデンGulden(1グルデン=100セント。現在はユーロ)。オランダは71年5月に変動為替相場制に移行した。オランダの中央銀行で唯一の発券銀行であるネーデルラント銀行 Nederlandsche Bankは1814年設立され,1948年国有化された。市中銀行としてはオランダ一般銀行Algemene Bank Nederland(通称ABN)とアムステルダム・ロッテルダム銀行Amsterdam-Rotterdam Bank(通称アムロ)の二大銀行が金融市場の60%を支配する。前者はオランダ貿易会社とトウェンテ銀行の合併,後者はアムステルダム銀行とロッテルダム銀行の合併によって,ともに1964年に誕生したが,その後さらに両者は合併してABNアムロとなった。
農林漁業 農地は約200万haで国土面積の約57%を占め,その約1/3が耕地,2/3牧草地となっており,園芸用地は14万ha(農地の約7%)である。19世紀末長期的な農業不況に陥ったオランダは,協同組合化,牧畜・園芸への構造転換を図り,隣接工業諸国市場へバター,チーズ,ベーコン,卵,野菜などの加工農産物や花卉・球根を輸出するようになった。20世紀に入るとさらに濃縮牛乳,粉乳,種ジャガイモ,種子,植物苗の輸出が加わった。他方オランダは過密人口を養うため大量の穀物を輸入する。酪農,畜産,園芸生産物の輸出と食糧,飼料,肥料の輸入など,外国貿易への高い依存度がオランダ農業の特徴である。農業経営は,フローニンゲンの小麦耕作地帯を除き,小・中規模で,労働力と肥料を大量に投下する集約的農業である。第2次大戦後農地の交換分合による再配置や国際競争に耐える適正規模の農家を育成する農業政策が行われた。
北海を舞台に昔から漁業は盛んである。シタビラメ,ニシン,タラなどの漁獲高は30万t余りで,エイマイデン,スヘーフェニンゲン,フリシンゲン,ウルクがおもな漁港である。アイセル湖ではウナギ漁が盛んである。林業はほとんど行われず,森林面積は国土のわずか8%で,木材の大部分を輸入に頼っている。
鉱工業 鉱産物は乏しく,わずかに石炭(リンブルフ南部),岩塩(ドレンテ),石油などであったが,1964年フローニンゲン市東部に推定埋蔵量1兆8000億m3 の天然ガスが発見され,一躍豊かな地下資源国となった。政府はシェル,エッソと3者出資でオランダ天然ガス会社を設立して生産を開始し,パイプ網を通じて国内はもとよりベルギー,北フランス,西ドイツへ天然ガスを配送している。73年天然ガス産出量は7000万m3 を突破し,その輸出価額は輸入石油のうちの国内消費価額を超え,エネルギー自給率は110%だが,政府は天然ガス資源確保のため輸出を漸次抑制し,エネルギー輸入を急増させる方針をたてている。
60年代における織物業の衰退と石油化学工業の大発展により,オランダの工業構造は大転換を遂げた。シェル,エッソ,カルテックス,インペリアル・ケミカル,ブリティッシュ・ペトロリアムなどの国際石油資本がロッテルダムのユーロポート地区に進出し,石油精製や半製品製造を行い,その半ばをパイプ網を通じて西ドイツなどへ輸出している。ロッテルダムにはまたマーガリン,人造肥料などを製造するユニリーバ・コンツェルンの主力工場がある。そのほかアムステルダムの薬品工業,リンブルフ州南部の石炭化学工業(国営炭坑),ヘンゲロー,デルフゼイルのソーダ工業がある。これらのうちローヤル・ダッチ・シェルとユニリーバ(ともに英蘭合弁企業),アクゾAKZO(レーヨン,ソーダ)はフィリップス(電機)と並んで超巨大多国籍企業である。
金属工業は,鉄鋼,機械,エレクトロニクス,造船が主要部門である。エイマイデンの国営ホーホオーフェンスHoogovens製鉄は1924年に始まり,現在西ヨーロッパ最大の銑鋼一貫工場で,スズ,アルミ,亜鉛の製錬も行う。エレクトロニクス産業の代表はエイントホーフェンにある多国籍企業フィリップス(フィリップス・グロエランペンファブリケン 。1891創立)で,オランダ各地に約20の関連工場がある。造船業は19世紀からロッテルダム,アムステルダム両港で発達し,さらに船舶用エンジンから始まって機械工業が発達した。造船業は激しい国際競争にさらされた結果,巨大投資を必要とするマンモス・タンカー建造を目ざして集中合併が行われ,1971年ライン・スヘルデ・フェロルメRijn-Schelde-Verolmeコンツェルンが成立した。ほかにアムステルダム,ロッテルダムの車両工業,エイントホーフェンの自動車(DAF),アムステルダムのフォッカー社(航空機)などが有名である。
食品工業としては,ザーンダムをはじめ各地で菓子製造が盛んで,ファン・ホーテン,ドロステなどのチョコレートは国際的にも知られている。バター,チーズ,ミルクなど酪農製品は各地の農業協同組合により生産される。ビール,ジンの醸造はロッテルダム,スヒーダム,アムステルダムなどが中心である。以上のほか伝統的産業としてアムステルダムのダイヤモンド加工やデルフトの陶磁器(デルフト焼)は重要な輸出品である。
貿易 人口稠密な資源小国で,国内市場が狭くしかも高度に工業化した西ヨーロッパの中枢に位置するオランダの生きる道は,加工貿易立国である。貿易の主要相手国は輸出入とも西ヨーロッパ諸国ことに西ドイツ,ベルギー,ルクセンブルクのEC域内に集中している。天然ガスの輸出で1973年以後貿易収支は黒字に転じた。
交通,観光 国土が平たんで道路網が整備され,トラック,バス輸送の比重が大きい。水路網も発達し,ことにライン川は国際的大動脈である。鉄道網も整備され,ヨーロッパ各地とも国際列車で結ばれているが,マイカーの普及でオランダ国有鉄道の経営は悪化し,政府の助成金は急増している。航空便はアムステルダム近くのスキポール空港からオランダ航空(KLM)が全世界に飛び立っている。
観光収入はオランダ経済にとって重要である。他方,60年代の所得向上とともにオランダ人の国外観光が盛んになり,観光支出は増大し,観光収支の赤字は増える一方である。
労働,社会保障 工業化とそれに伴う第3次産業の発達は,第2次大戦後激増した労働人口と農村からの流出労働人口を吸収してもなお,著しい労働力不足をもたらした。50年代の末には地中海沿岸諸国から10万人を超える労働者が移住し,繊維,製鉄,鉱山,建設などの肉体労働,非熟練労働に従事したが,労働力不足は解消せず64年の失業率は0.7%にまで下がった。過度の労働力不足は一方で労働条件改善への圧力を強め,週45時間労働(週休2日制)を実現させ,他方で賃金の急騰を引き起こし,物価も追いかけて急上昇した。賃金・物価の上昇は続き,72年以後はさらに不況と失業増大が加わり,政府は大幅の赤字財政を組んで失業克服対策に取り組んでいるが効果はあがらず,83年現在の失業者数は45万人を超えている。
労働組合は労働党系のオランダ労働組合連合(NVV),カトリック系のオランダ・カトリック労働組合総同盟(NKV),プロテスタント系のオランダ・キリスト教労働組合連合(CNV)があったが,前2者は76年合併してオランダ労働組合連盟(FNV)となり強大な勢力を誇っている。労働組合は保守的で争議件数も少なく,労働協会,社会経済理事会,経営評議会などの審議や運営に代表を送っている。失業保険,健康保険,産業災害保険,孤児手当,寡婦年金,児童手当,一般老齢保険などのほか,身体・精神障害者の保護雇用に関する特別立法もあり,オランダは社会保障制度の整備した福祉国家として知られている。
社会,文化 社会 19世紀後半の議会制確立期に,自由党が結成されるとこれに対抗してプロテスタント,カトリック教会はそれぞれ政党を組織し,自由党の推進する公教育に対抗して私立(宗派立)学校への全額国庫補助を実現した。20世紀に入り自由党が衰退し代わって労働党が勢力をえると,宗教政党も労働組合を組織してこれに対抗した。その結果オランダ人の社会生活は,宗教,政治,文化からスポーツ,社交,さらに新聞,ラジオ,テレビに至るあらゆる領域を通じて縦割りに組織された。こうしてほとんどの国民は,プロテスタント,カトリック,非宗派,労働党のうちいずれかの下位文化に所属している。しかし第2次大戦後,各政党は開かれた国民政党を目ざし,他方で,国民の中産化,都市化,画一的なマスコミの普及,若者の管理と拘束への反発や教会離れなどが生じた結果,伝統的な縦割り社会は動揺しつつある。
オランダ人の生活は,室内に閉じこもる冬と屋外の生活を楽しむ夏に分かれる。3月末あるいは4月初めの復活祭の頃から春の気配が感じられ,4月末の女王誕生日,5月5日の解放記念日を中心にチューリップやヒアシンスの満開期を迎えるが,まだ風も強く寒い。6月から8月は夜の10時近くまで明るく,最も楽しい季節であり,またバカンスのシーズンでもある。オランダ人はバカンス手当(日本のボーナスにあたる)を手にして,1ヵ月近く海や森へあるいは海外旅行に出かける。夏が終わると短い秋が到来し,新しい学期と音楽シーズンが始まり,やがて長い冬が訪れる。12月5日のシント・ニコラス祭,クリスマスの頃になると朝9時ごろまで暗く,午後3時過ぎると薄暗く,昼間も曇りがちとなる。オランダ人が好んで使う〈ヘゼリヒgezellig(楽しい)〉という言葉が〈他人とつき合う〉を意味することからもわかるように,オランダ人は,家族や友人とのつき合いを無上の楽しみとして貴ぶ。オランダ人は1年を通じて決まった曜日に決まった友人・家族同士訪問し合い,コーヒーとチョコレートとジンを飲みながら深夜まで歓談し,若い人の誕生日などには明け方までおしゃべりやダンスに興じるのが普通である。
教育 1968年オランダは高校,大学進学者の増大,急激な工業化と社会変動に対応して小学校から大学に至る広範な学制改革を行った。現在,義務教育は9年で,そのうち6年間は小学校(小学校の7割は私立校。ただし全額国庫負担)で,残りの3年間の中等教育は多種多様な形態で行われる。すなわち6年の基礎教育課程を終えた児童のうち約4割は中等職業訓練学校(4~6年)へ進み,他はヒムナシウム,アテネウムと呼ばれる大学進学コース(VWO,6年制),大学へも進学できる後期中等普通教育(HAVO,5年制),前期中等教育(MAVO,3~4年制)に分かれて進学する。MAVOと中等職業訓練学校の卒業生は高等職業訓練学校へ進むことができる。大学は国・公・私立合わせて,六つの総合大学と七つの単科大学がある。なお成人学級活動も盛んである。
文化 近世初め人文主義者エラスムスを生んだオランダには,独立後まもない17世紀前半,アムステルダムを先頭とする商業都市の富裕な市民層を基盤として文化の黄金時代が到来した。オランダ美術を代表するレンブラント,フェルメール,ハルス,哲学者スピノザ,国際法のグロティウス,自然科学のホイヘンス,レーウェンフック,スワンメルダム,数学のステフィン,さらに詩人ホーフトや詩人・劇作家フォンデルなどが活躍し,独自の国民文化を創造した。オランダ人の実際的能力と創造力はまた干拓,築堤などの水利,土木などに発揮され,オランダは近代西欧文化の生成と発展に大きく貢献した。
18世紀以降,国力と経済力が不振になると,文化もまた沈滞し,ようやく19世紀後半における議会制や近代化の本格的な開始とともに学問・文化の発展も再開された。とはいえ,イギリス,ドイツ,フランスのような文化大国に囲まれてそれらの影響下にあったことは否定できない。1860年,E.ダウエス・デッケルがムルタトゥーリの筆名で《マックス・ハーフェラール》を発表して東インド植民地における過酷な搾取の実態を批判して衝撃を与え,85年詩人クロース,フェルウェー,批評家L.ファン・デイッセルらが《新道標Nieuwe Gids》を創刊して新文学建設の旗手になった。〈80年代の運動〉と呼ばれる文芸復興以後,100年の間オランダは優れた詩人,散文作家,劇作家を多数輩出したが,残念ながらオランダ語という言語の壁に阻まれて作家も作品も国際的な知名度は高くない。この点では,《中世の秋》や《エラスムス》などで世界中に読者をえた歴史家のホイジンガや英語の著作の多いヘイルは例外といえよう。ただし自然科学の研究水準は高く,エイントホーフェン(生理学),デバイ(物理学・化学),C.エイクマン(生理学)ら10名を超えるノーベル賞受賞者を出しており,国際的に知られた研究所も少なくない。絵画においては19世紀末にゴッホ,20世紀にバン・ドンゲンVan Dongenがフランスで,モンドリアンがアメリカで活躍した。
建築では,17世紀にファン・カンペンがアムステルダム市庁舎,ハーグのマウリッツハイスを残し,19世紀後半のカイペルスはネオ・ゴシック様式のアムステルダム国立美術館,アムステルダム中央駅を建て,20世紀になってベルラーヘはアムステルダムの株式取引所の設計で合理的な近代性を追求した。戦間期の〈デ・ステイル 〉グループは画家のモンドリアン,ファン・ドゥースブルフも加え,アウト,リートフェルトらが幾何学的形態と明確な空間の創造を唱え,国際的反響を呼んだ。第2次大戦後のモニュメンタルな作品にはロッテルダムのラインバーン,ユーロマスト,スキポール空港ビルなどがある。
ヨーロッパ文化圏のまっただ中にあって,オランダのような小国が他の文化大国の文化に圧倒されないで独自性を主張することはむずかしい。しかも,かなりのオランダ人は英・仏・独語を学習しているので外国の文学,芝居,映画などを十分に理解できるからなおさらそうである。第2次大戦後豊かな社会生活には多様で活発な文化活動が必要なことを認識した政府は,音楽,演劇,オペラなどに多額の国家助成金を出している(例えば,現在19のオーケストラが国家補助を受けている)。オランダ美術 →オランダ文学 栗原 福也
音楽 15~16世紀にネーデルラント出身の音楽家が,多声音楽の担い手としてヨーロッパ中で数多く活躍したが,そのほとんどは南部出身であり,現在のオランダ出身者は,A.アグリコラ,J.オブレヒトなど数少ない。1581年に新教国としてスタートしたオランダは,富裕市民階級を中心に音楽面でも飛躍的に発展した。最も注目されるのが,オルガン,チェンバロによる鍵盤音楽の興隆である。17世紀初め,アムステルダムで活躍したスウェーリンクJ.P.Sweelink(1562-1621)はその代表的作曲家で,オルガン音楽では,北ドイツ出身のオルガニストを多く育て,北ドイツ・オルガン楽派の祖となり,チェンバロ音楽でも,イギリスのバージナル音楽の伝統を吸収し,高い技巧を加味した独自の様式を打ち出した。当時,カルバン派教会の礼拝では,会衆による詩篇歌のみ許され,オルガン演奏は禁止されていたが,市当局主催の,市民のためのオルガン演奏会は各地で盛んに行われた。それ以来オルガンは,オランダで,カリヨンと並んで国民的に愛好される楽器となった。
17~18世紀にオランダ各都市に生まれた市専属の音楽家を含む市民の演奏団体は,市民に鑑賞の場を提供し,近代の公開演奏会の先がけとなった。19世紀前半はドイツ・ロマン派の影響が強かったが,19世紀末から20世紀初めにかけて,ズウェールスB.Zweers(1854-1924),レントヘンJ.Röntgen(1898-1969),ディーペンブロックA.Diepenbrock(1862-1921),ウァフナールJ.Wagnaar(1862-1941)らの作曲家が出て,オランダ音楽を世界的水準にまで高めた。1888年に設立されたアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団は,名指揮者メンゲルベルクとのコンビで,世界有数のオーケストラに成長した。20世紀の主要作曲家として,パイパーW.Pijper(1894-1947),アンドリーセンH.Andriessen(1892-1981),バディングスH.Badings(1907- ),ファン・バーレンK.Van Baaren(1906-70)があげられる。
近年注目されるのはルネサンス・バロック音楽の再興で,リコーダーのF.ブリュッヘン,チェンバロのG.レオンハルトなどの演奏家のめざましい活躍により,オランダは古楽器の演奏と研究でヨーロッパの中心となっている。
民族音楽は,カトリック圏にとどまった南部ネーデルラント(ベルギー,ルクセンブルクなど)が,宗教的年中行事に伴う伝統音楽,土俗的な楽器・舞踏などを地方色豊かに今日まで伝えているのに比べて,禁欲的なカルバン派に転じた北部(オランダ)では,特徴的なものは少ない。古くからの民謡,独立戦争当時作られた俗謡,風刺歌が,曲集としていくつも出版され,印刷譜として伝承されている。舞曲は,南部にはルネサンス舞曲の流れを汲むものが多いが,オランダ,特に北部のフリースラントでは,スコットランドから伝わった軽快なリールが中心をなす。楽器は,ロンメル・ポットと呼ばれる唸るドラム,ホンメルと呼ばれるチターの一種,リエールと呼ばれるハーディ・ガーディ,ドゥーデルザックと呼ばれるバッグパイプ,木靴を胴体にした小型フィドルなどがあげられる。今日オランダの街角で見かける自動オルガンは19世紀に登場したものだが,大道芸人のなごりをとどめたものといえる。ネーデルラント楽派 植田 義子
日本との関係 日本とオランダの関係は他のヨーロッパ諸国に比べて深く長い。1598年6月西回りでアジアに向けてオランダを出航した5隻のオランダ船隊のうちの1隻リーフデ号が1600年4月19日(慶長5年3月16日)豊後の海岸に漂着した。110人の乗組員のうち生き残った者わずかに24名で,その中には首席航海士ウィリアム・アダムズ(イギリス人),ヤン・ヨーステンらがいた。船長カーケルナックは徳川家康から通商許可状を受け,1605年タイのパタニにあるオランダ東インド会社の貿易基地に無事到着し,東インド会社は09年平戸にオランダ商館 を設立した。35年(寛永12)家光は鎖国政策を実施し,41年オランダ商館を平戸から長崎の出島 に移した。これ以後1860年(万延1)の商館閉鎖まで,出島は鎖国時代の日本がヨーロッパの文化・芸術・科学を学び,諸外国の動向を知る唯一の窓口であった。鎖国時代に長崎在住のオランダ人から学んだヨーロッパの文化と科学に関する知識(蘭学)によって,日本は幕末・維新期におけるヨーロッパ諸国の進出という未曾有の危機に対処することができ,また明治期に急速にヨーロッパ文化を吸収し受容するための実力を準備したのである。
オランダ人からヨーロッパ文化と科学を学ぶうえで,オランダ語の学習は必要不可欠のものであった。オランダ語研究は平戸や長崎の通詞たちによって行われていたが,1720年(享保5)吉宗により洋学の制限が緩和されると,オランダ語と蘭書の研究は盛んになった。青木昆陽,前野良沢,杉田玄白らの忍耐強い努力を引き継いで,大槻玄沢の《蘭学階梯》(1788),稲村三伯の《ハルマ和解》(1796),桂川甫周の《和蘭字彙》(1855)が完成された。志筑忠雄,宇田川玄随,玄真,箕作阮甫,緒方洪庵らの名前も蘭学史上よく知られ,緒方の適塾は大村益次郎,福沢諭吉らの逸材を生んだ。東インド会社の医師として来日したケンペル(日本滞在1690-92),フォン・シーボルト(同1823-28,1859-62),ポンペ(同1857-63)らは医療活動と教育を通じて西洋医学の普及に偉大な足跡を残したばかりでなく,日本文化の研究と著作を通じて日本をヨーロッパへ紹介した。こうして日本人は長崎商館に勤務する知的なオランダ人からあらゆる分野のヨーロッパの知識を吸収し,その総仕上げとして,西周,津田真道ら15名の幕末オランダ留学生が派遣されたのである。
オランダ東インド会社から日本への輸入品は中国産の生糸,絹織物が8割を占め,ほかに綿布,皮革,蘇木,砂糖,香料,薬種,中国産陶器などがあり,日本からの輸出品は大量の銀,金,銅,ショウノウ,陶器などであった。東インド会社にとって日本銀は法外の利潤の源泉であり,香料諸島(モルッカ諸島)におけるコショウの入手にも必要欠くべからざるもので,会社のアジア貿易において中枢的意義を担ったが,銀の大量流出に驚いた幕府によって1668年(寛文8)その輸出は禁止された。
鎖国時代の日蘭関係において,日本がオランダに与えたほとんど唯一の文化的インパクトは,オランダへ輸出された大量の日本磁器である。すでに16世紀から中国の景徳鎮窯などで生産された磁器類が大量にヨーロッパへ運ばれ,ヨーロッパ人の関心をひきつけていた。富裕なオランダ人は争って高価な中国磁器を購入し,食器としてまた暖炉や壁や食器棚の装飾品として珍重した。1650年代,明末・清初の争乱で中国産磁器の生産が停滞したとき,東インド会社は中国磁器の代替品を有田焼に求めた。1660-80年(万治3-延宝8)に,有田窯で生産された染付磁器の膨大な量がヨーロッパ市場へ送られ,しかもこれらの磁器は会社が本国から送った型見本に従って制作されたのである。18世紀初頭にヨーロッパでようやく磁器生産が開始されたが,もちろん東洋磁器の圧倒的影響のもとにおいてである。現在オランダで生産されるタイルやデルフト焼に有田焼の影響をみることができよう。
明治期になり,御雇外国人として何人かのオランダ人の来日,公使館,領事館の設置があったものの,もっぱら欧米の諸大国のみに目を向けた日本にとって小国オランダは注目を引かなかったといえる。第2次世界大戦中,日本はオランダの敵対国となり,1942年にはオランダ領東インドを占領し,在住オランダ人を強制収容所に収容した。戦後,航空協定,通商協定,租税条約が結ばれ,さらに80年にはファン・アフト首相が来日して文化協定を締結した。懸案は貿易不均衡是正問題で,日本からの自動車,テレビ,ラジオ,ビデオ・テープ,化学・金属製品などの輸入により,オランダ側は約10億ドルの輸入超過である。現在,在オランダの邦人数は数千人,日本企業は数百社で,在日本のオランダ人やオランダ企業も増えつつある。またオランダへの邦人観光客の数は非常に多く,学問・芸術の交流も盛んである。ライデン大学には日本学・韓国学センターが置かれ,日本語および日本研究の学生が増えつつあり,各大学にも日本研究者がいるのに対して,日本においてオランダ語およびオランダ研究に従事する研究者,学生は非常に少数であり,鎖国時代の日・オランダ関係と逆転している。
1990年代になって日本企業のオランダへの進出が活発になり,日本とオランダの経済関係は密接になりつつある。オランダ側は95年から,大学を卒業した20代の優秀な若者を日本で研修させるために国費で派遣する〈ジャパン・プログラム〉を開始した。洋学 栗原 福也