目次 形態学的分類 実の成熟 果皮 果皮による分類 実の役割 果実ともいう。花が受粉・受精したあと,主としてめしべの子房 が発達してできるもので,子房の内部では胚珠が生長して種子 をつくる。それゆえ実は成熟した花ともいえる。被子植物だけに発達した器官で,熟すとさまざまな方法で種子を散布させる。このため実の形,大きさ,色,裂開の仕方など形態学的にたいへん変化に富んでいて,実を正確に定義することはきわめて難しい。狭義には子房の発達したものであるが,萼,花托など子房以外の部分が残存し,発達したものも多く,これらのものも広義には実と呼ばれる。例えばイチゴの実には萼が残っていて,その上に花托が大きくふくらんで多汁質となった果托があり,狭義の実は果托の表面に点々とちらばっている堅い粒々(俗に種子と呼ばれるところ)である。バラの場合には,萼,花冠,おしべやめしべがつく花托がつぼ状となっていて,その中に数個の実が入っている。ナシやリンゴでは狭義の実は中央部のいわゆる芯と呼ばれる堅いところで,外側の食べる部分は萼,花冠,おしべの基部が合着し筒状となった花管floral tubeと呼ばれる部分の発達したものである。このような構造をもったものは,他にもザクロ,キュウリ ,バナナなど下位子房 をもつ花に広くみられる。クワでは四つの花被が子房とともに多汁質となり,実を包んでいる。カキやナスなどのように,萼が生長し,いわゆるへたとして残っていることも多い。花柱が残って子房とともに大きくなり散布に役立つものが,テッセン ,チングルマ などに知られている。
このように実の構成に子房以外の部分が関係しているものを偽果false fruitと呼び,子房からのみなる狭義の実を真果true fruitとして区別することがある。しかし両者の区別は必ずしも明瞭ではなく,例えばカキでは萼が著しく生長するので偽果となり,ミカンの萼はほとんど生長しないため真果とするのでは,あまりにも人為的過ぎる。イチゴやリンゴの偽果には明らかに真果があり,発達の程度に差があるが,子房以外の部分が付け加わっているのであって,決して偽の実ではない。偽果は用語として不適当で,これに代わる術語として装飾果accessory fruitが提案されている。実の定義については,めしべとその付属物の発達したもの(エームズEams,1961)と広い意味に解釈しておいたほうが,自然である。この定義によると,萼,花托,花管などの花の直接構成する部分のほかに,苞や花軸(パイナップル )など花に付随する器官も実の一部を構成することがある。
形態学的分類 形態学的に多様なため,実の分類の仕方はたいへん難しく,これまで数多くの試みがされている。そのうち最も伝統的で,一般的に使われているのは,花序,花,めしべの形態を重視して,次のように4型に大別する方法である。(1)単果simple fruit 一つのめしべをもつ花にみられ,実は主に子房が発達したもの,(2)複合果aggregate fruit 二つ以上の離生めしべをもつために,一つの花に複数の実ができるもの(個々の実を小果fruitletともいう),(3)集合果multiple fruit 見かけ上一つの実のように見えるが,多数の花に由来した実が密に集まったもの,さらに前述した(4)装飾果(偽果)である。
単果としてはモモ,マメ,ミカン,マンゴー ,カキ,トマト,ピーマン などがある(図1-a)。複合果はモクレン ,アケビ,ハス,ポポー,バラ,キイチゴ ,テイカカズラ ,トウワタ などにみられる(図1-b)。集合果の例としてはクワ,アナナス ,イチジク ,パイナップルなどがよく引用される(図1-c)。動物発生学の用語である桑実胚の語源ともなったクワの実は粒々が多数集まっていて,見かけ上キイチゴの複合果に似ているが,クワの粒々はそれぞれ一つの花の発達したものである。一つ一つの実は前述したように装飾果であるが,果序全体としては集合果となる。イチジクの花序はかなり変わっていて,花をつける軸(花軸)がつぼ状となり,その内側に多数の小さい花がついていて,熟すと花とともに花軸も多汁質となる。個々の実は単果であるが,果序全体が一つにまとまっていて集合果とされる。パイナップルの実は花軸と下位子房をもつ多数の花と,さらに個々の花につく苞とが互いに合着したものであり,一つ一つの実は装飾果である。集合果としてはこの他にヤシャブシ ,プラタナス ,トウモロコシ があげられるが,ブドウとなると集合果とすべきなのか単果とすべきか,はっきりしない。このように集合果と他の3型の区分は必ずしもはっきりしないため,ある種の実が集合果と他の3型の一つといったように,異なる型に分類されてしまうことになる。このような混乱は,この分類法が形態学的に異なる概念である花と花序とを基にしているために起こることである。集合果は形態学的な実の単位ではないが,散布体としては一つの単位となる。鳥はクワやイチジクの実を1粒ずつ食べるのではなく,果序全体あるいはつぼ状の花軸を含めてその一部を食べ,小さい種子をまとめて散布させることになる。
ウィンクラーH.Winkler(1939)はめしべの形態に基礎を置いた分類法を提案している(図2)。彼はまず離生めしべをもつ花から由来した複合果と1本の合生めしべをもつ花から生じた単果unit fruitに二大別し,さらに子房が上位か,中位または下位かで,前者を独立果free fruit,後者をカップ状の花托や花管が包んでいるので,カップ状果cup fruitとした。これらの組合せで実は次の四つに分類される。(1)複合独立果aggregate free fruit めしべが離生でしかも子房上位 の花から由来した実(モクレン,キンポウゲ ,イチゴ),(2)複合カップ状果aggregate cup fruit 離生めしべで子房中位 の花から由来したもの(ロウバイ,バラ),(3)単独立果unit free fruit 合生めしべで子房上位の花から由来したもの(ミカン,カキ,トマト),(4)単カップ状果unit cup fruit 合生めしべで子房中位または下位の花から由来したもの(ナシ,スイカ,バナナ)。この分類法は子房中位や下位に由来した実をカップ状果としたことに特徴があり,実の主体となるめしべの形態によっているため,実の型と被子植物の分類群が対応する。クワの実は単独立果となり,二つの異なる型に分類されることはなくなる。
実の成熟 実が熟し,子房壁が大きくなるとともに組織の分化が起こる。狭義には子房壁の発達したものが果皮pericarpである。下位子房に由来した実では,子房壁と花管の発達した部分が区別できる(ナシ,リンゴ)こともあるが,はっきりしないほうが多く,たとえ両者の区別ができたとしても,後で述べる果皮の組織分化は下位子房全体として起こる。下位子房のように,子房壁以外の組織(花管,花托,苞)が完全に子房と合着しているさいは,それらの組織を含めて果皮としておいたほうが実際的である。果皮が成熟するさい,モモやナシのように細胞分裂が起こり細胞の数が増すこともある。しかし多くの場合は,イチゴやガマズミ のように,果皮の細胞分裂の能力は開花後すぐになくなり,個々の細胞の大きさが増すことにより,子房の急速な生長が起こる。
実ができることと種子が形成されることとは密接な関係があり,種子ができないと子房が大きくならなかったり,落ちてしまう。しかし種子ができなくても実つまり種なし果実 ができることは,バナナ,ウンシュウミカン ,カキなどで知られ,この現象を単為結果 parthenocarpyという。種なし果実の成因はさまざまで,受粉しない場合,受粉はするが受精しない場合,受粉も受精もするが胚珠が発育不良となる場合がある。第1の例はキュウリ(単為結果性の品種)にみられ,受粉しなくても胚珠や胎座からホルモンが出され,子房を肥大させる。第2の例は花粉のホルモンが子房の肥大を刺激するが,なんらかの原因で受精しないもので,ウンシュウミカンではおしべの発育が悪く,また花粉も不完全なため受精しない。バナナでは染色体が三倍体であるため,花粉のできが悪い。パイナップルは正常な花粉はできるが,同じ系統の株の間の交配では種子ができない自家不和合性による。種なしスイカでは,正常な二倍体の花粉の交配が必要であるが,雌花をつける母植物は三倍体で卵は受精の機能がない。第3の例としては,シイやブナなどのある程度発達した胚珠をもつ〈しいな〉がある。このような単為結果については,種なし果実をつくったり,花を効率よく結実させるためや大きな実をつくるために,古くから多くの研究がある。トマトにナス,キュウリにヒマワリ などのように,全く異なる種の花粉によっても子房が肥大することがわかっている。また花粉には子房の生長を刺激するホルモンがあることも明らかとなり,花粉ホルモンは,トマト,ナス,スイカなどの栽培に実用化されている。
果皮 熟した果皮はふつう3層に区分され,外側から外果皮exocarp,中果皮mesocarp,内果皮endocarpと呼ぶ。カキを例にとると,外側の皮が外果皮で,表皮組織からなり,クチクラ層が発達し,その表面に白粉状の蠟があり,内部の保護に役立っている。種子のまわりのぬるぬるした半透明な部分が内果皮で,カキでは八つあるが,ふつう子房室の数と内果皮の数は一致する。外果皮と内果皮の間の果肉のよく発達した食用部が中果皮である(図3)。なお,モモ,ウメ,クルミ,マンゴーなどの実では内果皮は堅くなり,俗に核と呼ばれるが,動物に食べられたさい内部の種子を保護する。ミカンの内果皮は袋状となり,子房がふくらみかけてから,内側に多汁質の毛状突起がはえてくる。スイカ,ナス,ピーマンでは胚珠をつける胎座が大きくなっていて,子房室全体を満たし,実の大部分は果皮よりむしろ胎座によって占められる。このような胎座が肥大した実では,中果皮と内果皮が区別しにくいことがある。
果皮による分類 熟した果皮には,上に述べたように組織分化が起こったり,多汁質となったり,裂開したりなど花の時期にはみられなかった特徴が現れる。果皮の形態に基づいて実を分類すると次のようになる。まず果皮が乾いている乾果dry fruitと多汁質の液果fleshy fruitに二大別され,乾果はさらに果皮が裂開して種子が外へ出る裂果dehiscent fruitと裂開しない閉果indehiscent fruitに分けられる。裂果はふつう多数の種子をもつ実にみられ,裂開は離生めしべでは,心皮の辺縁の合着部(シャクヤク ),心皮の背側(モクレン),合着部と背側の両方(マメ類)にそって起こる(図4)。合生めしべでも裂開は同じように起こる。心皮が合着した隔壁にそって裂けることを胞間裂開septicidal dehiscence(カタバミ ,ハコネウツギ)といい,各心皮の背側にそって裂けるものを胞背裂開loculicidal dehiscence(スミレ)という。隔壁と背側両方で裂開するものがアカネ科に知られている。また横に裂けて上部が蓋のようになってあくものを蓋果(がいか)pyxis と呼び,ケイトウ,マツバボタン ,サクラソウ,オオバコにみられる。実が裂開するさい種子を飛散させるものがあるが,その機構は一様でない(図5)。フジではさやが乾燥すると二つに割れ,急激にねじれることにより機械的に種子を飛ばす。ホウセンカでは裂けた果皮が急に上へ巻き上がる力で種子を飛ばす。クワクサの実はU字型に肥厚した部分があり,側面は薄く膜状となっていて,肥厚部が図のように閉じることにより,種子はばね仕掛けで2~3mもはじき出される。カタバミでは外種皮が袋状となっていて,熟すとこの袋の一方が裂け,急に裏返しにそり返り,その反動で種子がはじき飛ばされる。このように自動的に種子を飛ばすものもあるが,裂果の多くは風などでゆれることにより小さい種子を飛ばす受動型である。裂果はさらに袋果follicle(離生めしべで,1ヵ所で縦に裂ける),豆果legume(マメ科のように1心皮性だが,心皮の腹側と背側で裂開する),蒴果(さくか)capsule(合生めしべ)などに分けられる。
閉果は一つの子房室にふつう一つの種子がある実にみられる。イチゴのように果皮が種皮状となっていて,そのために真の種皮が退化し薄く膜状となっていることが多く,まれに種皮と果皮が合着することもある。閉果はさらに次のように分けられる。瘦果(そうか)acheneは小型で1種子をもつ実で,狭義には1心皮性のもの(イチゴ,キンポウゲ)であるが,多心皮性の場合(オミナエシ,キク)も含めることが多い。カサスゲのように果皮が薄く種皮と離れているものを胞果utricule,イネのように果皮と種皮が合着しているものを穎果(えいか)caryopsisと呼ぶ。堅果(けんか)nutはクリ,ドングリ類,ハシバミのように比較的大型の堅い果皮をもつ実であるブナ科の堅果の基部にある椀状体(クリのいが,ドングリ類の皿)を殻斗(かくと)と呼ぶ。分離果schizocarpは一つの実に複数の種子が入っているが,それぞれは分離して,分果mericarpをなす。個々の種子は果皮で包まれているので閉果の1型とされる。ヌスビトハギでは,豆のさやが生長の過程でくびれができ,横に折れて数個の分果となる。シソの実では花の時期にすでに子房に四つのくびれがある。他にミツバ,コンフリー,ヤエムグラなども分離果である。
液果は果皮が厚く多汁質なため,動物に食べられることが多いが,糞とともに種子が出て種子の散布に役立つ。未熟な実では果皮が堅いが,熟すと柔らかくなる。色も初め緑色で後に美しく色づく。案外,赤い実が多いのは鳥が赤色に鋭敏であることと関係があると思われる。液果の中には野菜や果物として人に利用されるものも多い。系統発生的には液果は乾果から派生したものとみなされる。アケビのように裂開するものもあるが,ふつうは裂開しない。内果皮が堅くならないものと堅くなるものがあり,前者を漿果(しようか)berry,後者を核果(石果)drupeとして分ける。漿果にはブドウ,レモン,メロン,バナナが,核果にはクワ,モモ,オリーブ,ココヤシがある。
実の性質は分類群によってきまっていることが多い。とくに同じ属の中では一定しているし,科内でもブナ科の堅果,ナデシコ科の蒴果,シソ科の分果,キク科の瘦果というようにきまっている。しかしバラ科(袋果,蒴果,漿果,核果),スイカズラ科(蒴果,瘦果,漿果,核果)などのようにいろいろの形をとるものもある。
実の役割 実は種子をいろいろな所へ分散させる散布体として,種子とともに大切な働きをしている。実が裂開するさい自動的に種子を飛ばしたり,液果が動物に食べられ運ばれることはすでに述べた。イチゴの花托,イチジクの花軸など子房以外の部分が多汁質となることも動物をひきつけることと関係があろう。実が風によって散布されるものでは,イネ科のように果序全体が風にゆられて飛ばされるものが多いが,翼の発達したもの(イタドリ,ハルニレ),冠毛をもつもの(タンポポ),羽根をもつもの(ツクバネ)などもある。また,軽い海綿質の組織などがあり水に浮いて運ばれるもの(ココヤシ)もある。動物に付着して運ばれる実には鉤(かぎ)状(オナモミ)や針状(センダングサ)のとげがあったり,粘着物(メナモミ)を出すものなどがある。福岡 誠行
 〈ジツ〉
〈ジツ〉 〈み〉「
〈み〉「 [名]
[名] [副]まことに。本当に。
[副]まことに。本当に。 [形動ナリ]現実的なさま。また、真心のこもっているさま。
[形動ナリ]現実的なさま。また、真心のこもっているさま。 (2)中身・実質・実体・内実・内容/
(2)中身・実質・実体・内実・内容/ (3)真心・誠意・真情・誠・誠心・本当
(3)真心・誠意・真情・誠・誠心・本当


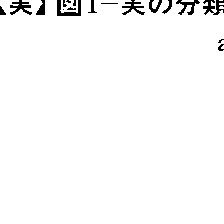


 物と爲す」(段注本)とするが、宀は宗
物と爲す」(段注本)とするが、宀は宗 、貫は貝貨を貫き連ねた形で、貝を宗
、貫は貝貨を貫き連ねた形で、貝を宗 (こくさたん)〕の字は、上部が冖(べき)の形に近い。鼎中にものを充たして供える意ともみられる。充実の意から誠実・実行の意となり、その副詞に用いる。
(こくさたん)〕の字は、上部が冖(べき)の形に近い。鼎中にものを充たして供える意ともみられる。充実の意から誠実・実行の意となり、その副詞に用いる。