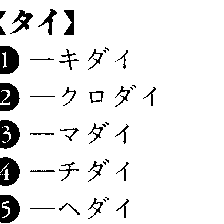目次 自然 住民,言語 社会,宗教 歴史 タイ族の興隆 アユタヤ朝 ラタナコーシン朝 立憲革命以後 政治 経済 日本との関係 文学 美術 音楽 基本情報 正式名称 =タイ王国Prathet Thai/Kingdom of Thailand 面積 =51万3120km2 人口 (2010)=6731万人 首都 =バンコクBangkok(日本との時差=-2時間) 主要言語 =タイ語 通貨 =バーツBaht
東南アジアの大陸部中央に位置する立憲君主制の独立国。1939年まではシャムSiamと呼ばれていた。国土はタイ(シャム)湾とアンダマン海に面し,東はメコン川を隔ててラオスと,南東はカンボジアと接している。西はミャンマーと接し,南のマレー半島部においてマレーシアと接している。
自然 タイの国土は,北から南へ走行する山地と河川,およびそれらに沿って開かれた平野によって構成され,西方のミャンマーとの国境を画するテナッセリム山脈と東方のメコン川との間に広がっている。地形的特徴からみて,北部,中部,東北部,南部に大きく分けられる。東西の大河,メコン川とサルウィン川に挟まれた北部の大部分は標高1000m前後の山地であり,最高峰インタノン(2595m)がチエンマイの西方にそびえる。メナム(チャオプラヤー)川の四大支流であるピン,ワン,ヨム,ナンの河川がその間を流れて多くの山間盆地を形成し,小規模で労働集約的な伝統的稲作が展開している。これらの河川は南下して合流し,タイ最大のメナム川となり,多くの分流を繰り返しながら中部に広がるチャオプラヤー・デルタを形成する。きわめて平たんで広大なこのデルタは,雨季には多くの部分がゆるやかな洪水によって冠水し,稲作に好条件を与える。タイの穀倉地帯は古くからこのデルタ地帯に形成され,近年,大チャオプラヤー・プロジェクトによって灌漑・排水事業が進展した。
東北部はコーラート高原 と呼ばれ,東のメコン川に向かってゆるやかに傾斜する隆起平原である。西はドンパヤージェン山脈によって中部と,南はドンラック山脈によってカンボジアと画される。標高は120~200mで,なだらかな起伏を繰り返す地形が続く。メコン川の支流,ムーン川とチー川に沿う低地では自給的稲作が行われるが,不安定である。南部はマレー半島部で,タイ湾に面する東海岸には小規模な沖積平野が広がり,アンダマン海に面する西海岸は花コウ岩を主とする山地が続いている。広大なスズ鉱床はこれらの花コウ岩を含む沖積層に広がっている。
南部のマレー半島を除く国土の大部分は,熱帯モンスーン気候 の影響下にある。雨季は5~10月で,南西モンスーンが雨をもたらす。北東モンスーンが卓越する11~4月が乾季で,2~5月ころはとくに暑季とも呼ばれ,極度の乾燥と高温にみまわれる。インド洋から吹く南西モンスーンは,テナッセリム山脈などによって遮断されるため,年降水量は1000~1500mm程度にすぎない。チュムポーン以南のマレー半島部は熱帯雨林気候に属し,年間を通じて降雨がある。とくに西海岸は多雨地帯で,年間4000mmを超える降雨がみられる。年平均気温は26~28℃で,北部の山地におけるまれな例を除いて降霜と降雪はない。一般に最低気温は12月か1月に,最高気温は5月初めにみられる。
住民,言語 主たる住民は,言語学的にタイ・カダイ語群と呼ばれるグループに属するタイ系民族で,最も人口が多いのは中部タイを中心とし,タイ語 (シャム語)を話すタイ族 である。東北タイにはラオ族,北タイにはタイ・ユアン族,南タイにはパク・タイ族がそれぞれ優勢である。そのほかに,北タイにはタイ・ルー族,タイ・ヤイ族(ギオ,シャンとも呼ばれる),東北タイにはプー・タイ族などの少数グループが分布する。これらのタイ系民族は全人口の80%以上を占め,ほとんどが上座部仏教徒である。彼らの間の言語の違いは,標準語化したタイ語からみて方言的な差であるといわれることが多いが,物質文化,口碑伝承,美術,芸能,儀礼,シンボリズムなど文化全体の固有性は依然として残存している。
タイ系民族以外では中国人(華僑)が多く,300万人以上に達する。彼らの間では古くから潮州語が優勢であり,客家(ハツカ),海南,広東,福建などの言語も話される。中国人とならんで約6万人のインド人がバンコクを中心にみられ,ベトナム人も東北タイの数都市に分布している。約100万人にのぼるマレー系民族は南部の国境地帯に住み,ほとんどがイスラム教徒である。これらのイスラム教徒の反政府運動はタイにおける民族問題の焦点になっている。カンボジアとの国境沿いにはクメール族が古くから居住し,1979年のカンボジア内戦 以来,避難民の流入が激しく続いた。
少数民族とは,タイ国内では主として北部の山地に居住する約30万人の少数部族民をさすのが一般的である。チベット・ビルマ語派に属するカレン族 が最大のグループで,13万人以上がミャンマー国境沿いの山地に居住している。そのほかに,ミヤオ族(モン族 ),ヤオ族,ラフ族,リス族,アカ族などが含まれる。これらの部族民は主として隔絶した山地において焼畑耕作に従事し,独自の社会と文化を形成している。それは平地におけるタイ系民族の文化と著しい対照を示し,タイ政府は行政,教育などを通じた国家的統合の問題に直面している。田辺 繁治
社会,宗教 広く知られているように,タイ族は13世紀に歴史の舞台に登場して以来現在にいたるまで,スリランカ系の上座部仏教を信奉している。タイに伝えられた上座部仏教は,一部の特権的支配階級のための宗教ではなく,上は国王から下は一般庶民にいたるまで,タイ社会の各層に幅広く受容され,タイ族の価値意識を根底から規定している点に一つの特徴がある。タイ族が仏教徒であることが,しばしば自明のこととして語られることがあるのは,こうした文化的状況を反映している。タイ的価値とは,すぐれて仏教的価値なのである。
上座部仏教とタイ社会とは,まず〈ブン(楽しみをもたらす原因となる行為)〉と〈バープ(苦しみをもたらす原因となる行為)〉という1対の観念をめぐって深いかかわりを示す。タイ族は,すべての社会的関係を上下の秩序においてとらえるが,この秩序内における個人の位置は,各自の〈ブン〉と〈バープ〉の相対的多寡によって決定されるのだと考える。〈ブン〉に恵まれた者は楽しみも大きく,〈バープ〉の多い者は苦しみが大きい。一般に社会的上位者は〈ブン〉に恵まれた人であり,下位にある者は〈ブン〉の乏しい人であると理解される。上下の秩序の最高位に位する人物は国王である。〈ブン〉の多寡は先天的に決まるのではない。〈ブン〉は各自の努力によって獲得されるものである。ただ〈ブン〉を獲得するための努力は,ただ1回の人生の間だけに行われるのではない。〈ブン〉は長大な時の流れのなかで無限に繰り返される,ひとつひとつの生において営まれる個人の行為(カムまたはカンマという)の累積の結果として獲得されるのである。民衆は,ブッダが前生に積んだ善行物語を集めたジャータカのなかに,この世における善行が,後の世の生存にとって好ましい結果をもたらすという仏教の教えの確かな証拠をみる。したがってタイの民衆は,国王に与えられた高い名誉と地位とを,その国王が前生において積んだ限りない善行の結果として了解するのである。
社会的上位者と下位者とは恩恵と奉仕の関係によって結ばれる。上位者は下位者に対し,それぞれの力量に応じた恩恵を与えることが文化的に期待されている。一方,恩恵を被った下位者は,上位者に対し力の許すかぎりの奉仕を行ってその恩恵にこたえなければならない。このように上位者と下位者の関係は双務的である。しかしその関係はあくまでも自発的に結ばれた関係であるため,いずれか一方の発意でその関係は消滅するのである。一般に上位者はこうした関係を,複数の下位者との間に取り結ぶ。タイ社会における個人の威信は,それに依存する下位者の数の大小によって決定される。地位が高ければ高いほど,その庇護下に入ることを望む下位者は増加する。このように下位者群が上位者を取り巻く構造を,ある人類学者は〈取巻き連entourage〉と名付けた。ある意味でタイの社会は,その全体が同じ原理によって結合された〈取巻き連〉の累積体とみることもできる。
上下の秩序における自己の位置は〈ブン〉によって決定されるという了解が,一般に共有されているタイ社会においては,仏教徒の宗教的関心がもっぱら〈ブン〉を増すことにあるのは当然といってよいであろう。〈ブン〉を増加させる行為は,タイ語で〈タンブン〉と呼ばれる。托鉢僧に対する日々の食事の供養,寺院の建設や修復のための寄進はいずれもすぐれた〈タンブン〉の手段とされている。みずから僧として出家すること,あるいは息子を僧として出家させることもまた大きな〈ブン〉を生む〈タンブン〉であるとされている。〈タンブン〉は出家者の教団でありタイ仏教の中核をなすサンガ の持続的発展に貢献する行為である。文字どおりの出家者であり,いっさいの生産活動にかかわりをもたないタイの僧とそのサンガが,今日もなお衰退から免れているのは,このように,在家者がみずからの〈ブン〉を増すために行う〈タンブン〉が,結果として出家者とそのサンガの物質的存在を支えているからである。
タイの仏教徒は,〈タンブン〉によって人生における心の平安を得ることができるが,それだけでは日常的に発生する人生のさまざまな危機を回避することはできない。このような日常的危機を解決するための手段の一つに〈パリット〉がある。〈パリット〉とは護呪経典を意味する。タイの民衆仏教徒は,〈パリット〉の読誦が,災厄を回避し,幸運を招き寄せるために効力をもつと信じている。
歴史 タイ族の興隆 現在タイの中心的民族をなすタイ族については,古くはその起源を《後漢書》にみえる哀牢 に求めたE.H.パーカー説(1890)や,ながらく定説とされていた南詔 =タイ族国家説,その批判として提出された白鳥芳郎の西爨白蛮(せいさんはくばん)=タイ族説(1957)などがある。いずれもその原居住地はおおむね中国南部の雲南から四川南部とされ,タイ族は北方からインドシナ半島 へと南下し定着した民族であると考えられている。これに対し一部のタイ人学者から,タイ族は現在の地にかなり古くから居住していたとする説,さらには南下ではなく,マレー半島およびインドネシアから逆に北上して現在の地に至ったとする仮説が提出されているが,研究の現段階では少数説にとどまる。稲作を主たる生業とするタイ族の移動は,人口の増加とともに次々と新村をつくりながら新しい土地へ浸透していくという,ゆるやかなそして持続的な過程であったものと思われる。しかし,おそらくは数百年にも及んだであろうこれらタイ族の空間的拡大運動を,文献的に後づけることはきわめて困難である。言語学者は,インドのアッサムのアホム語,ビルマ(現ミャンマー)のシャン語,ラオスのラオ語,タイ国語(シャム語),シプソン・パンナー のルー語,ベトナム北部の黒タイ語,白タイ語など,いずれも南西タイ語群に分類できる言語が,これほど広大な地域で話されているにもかかわらず比較的等質であるという事実を,タイ族の移動の時期がせいぜい過去1000年内外であったことを示す徴表と解釈している。
タイ族の国家形成が,文献的に立証可能となる時期は13世紀である。そのころから,アッサム,ビルマのシャン州,ラオス,中国南西部のシプソン・パンナー,北タイ,中部タイなどの各地に,タイ語で〈ムアン〉と呼ばれる小規模な政治単位の発生をみるにいたる。〈ムアン〉とは,1人の首長によって統轄され,中央に首長の居所(王宮)と比較的人口密度の高い行政,宗教,文化の中心をもち,周囲には水稲耕作民の居住と生産の空間が展開して,その余剰生産物をもって中心の存在を支えるという構造をもった自律的な政治的・地理的単位をさす。タイ族の〈ムアン〉の成立は13世紀よりかなり以前であったと考えられるが,初期の〈ムアン〉は多く山間小盆地などに立地し,互いに孤立して上位の政治的統合が形成されにくい状況にあったため,文献には現れなかったものと思われる。
現在のタイの核心域をなすメナム川流域は,11世紀以来アンコール朝の支配下にあったが,13世紀の前半にいたり,二つのタイ族〈ムアン〉連合軍が,クメール族太守支配下のスコータイを攻略し,ここにタイ族最初の国家スコータイ朝 を建設した。スコータイの版図は,第3代の王ラーマカムヘン (在位1275ころ-99ころか1317ころ)のとき最大規模に達した。同王の碑文によると,その勢力は,北はルアンプラバン ,東はビエンチャン,西はペグー,南はナコーンシータマラート にまで及んだが,王の死後,急速に衰微した。第5代の王マハータンマラーチャー(在位1347-70?)は失われた版図の回復に努めた。スコータイは,南方のマレー半島と西方の下ビルマを経てスリランカから上座部仏教を受容したが,これは王制とともに現在まで続く政治・文化の基盤となった。
アユタヤ朝 1351年,チャオプラヤー・デルタ下流部の河港アユタヤを中心に,新たなタイ族の国家アユタヤ朝 が成立し,北方に向かってその勢力を拡張すると,スコータイはやがてこれに併合され,政治的独立を失った。アユタヤとその周辺は,かつてモン族の国ドバーラバティ の支配下にあった地域である。アユタヤ朝の正式名称のなかにドバーラバティの名がとどめられているのは,こうした歴史の反映とみられる。しかしモン族は,西方に向かって膨張するクメール族によって圧迫されて衰微し,その中心の一つであるロッブリーも11世紀にはアンコール帝国 の一部となった。建国後,繰り返されたアユタヤによるアンコール攻撃は,この地域に対する伝統的なクメール族支配の排除を目ざすものであった。クメール文化のアユタヤへの影響の大きさは,タイ語に採用されたクメール語系語彙などによって知られる。しかし同時に新来のタイ族が先住民族モン族から受けた文化的影響も見のがすことはできない。アユタヤの基本法となったインド法典=ダンマサッタン は,モン族から受容されたものである。
アユタヤ朝は,スパンブリー川に沿うスパンブリーとアユタヤ北方の古邑ロッブリーという二つの〈ムアン〉の統合によって成立した国家である。王都アユタヤは,パサック,メナム両河の舟運を利用して,後背地の物産獲得が容易な地点に立地していると同時に,南に向かってはタイ湾を経て海上交易路と直結していたため,やがて東南アジア大陸部最大の商業・政治都市へと発展した。創始者ラーマティボディ1世 (在位1351-69)の死後,ウートーン(ロッブリー),スパンナプーム (スパンブリー)両王家の確執が続いたが,15世紀以降スパンナプーム王家の支配権が確立し,1432年にはアンコール朝をも滅ぼし,その威勢は遠くマラッカにまで及ぶ大国に発展した。16世紀中葉,ビルマの侵攻を受け国内の統一は一時失われたが,ナレースエン 大王(在位1590-1605)がでて独立を回復し,従前に勝る強力な支配体制を確立した。
アユタヤ朝の繁栄は,その貿易活動に負うところが大きい。建国以来の対中国朝貢貿易のほか,15世紀には琉球貿易も開始されている。17世紀に入るとオランダ人,日本人など外国人商人の渡来によって対外貿易はさらに活発化した。〈官買〉制度,〈唐船〉委託貿易,ベンガル湾貿易のためのインド人・ペルシア人官吏の登用など積極的な貿易振興策によってもたらされた利潤は王庫の繁栄に貢献した。ナライ 王(在位1656-88)はベルサイユ宮廷へ使節を派遣した王として知られている。アユタヤ朝は,バーンプルールアン王家 のボロマコート王 (在位1733-58)の治世下に学芸がおおいに栄え,仏教使節をセイロンへ派遣して衰微した首都キャンディに戒壇を復興させるなど,仏教国アユタヤの名声は海外にも響いたが,王の死後,後継者を得ず,1767年ビルマの侵攻を受けて滅亡し,アユタヤは416年の歴史の幕を閉じた。
ラタナコーシン朝 アユタヤ朝滅亡後ただちにビルマ軍を撃退して1767年みずから王位についたタークシン は,徹底的に破壊された王都アユタヤの再建をあきらめ,より河口に近いトンブリーに新たな都を開いた。タークシンはその後も執拗に繰り返されたビルマの侵入を撃退しつつ,まず旧畿内の諸〈ムアン〉の秩序を確立すると,みずから兵を率いてピッサヌローク ,ピーマイ,ナコーンシータマラートを制圧,さらに進んで,カンボジア,ラオス,ラーンナータイを攻撃し,アユタヤ以来の宗主権を回復した。アユタヤ朝のいずれの王家とも血縁関係のないタークシンは,仏教の篤信によって〈正法王〉の威光を示そうとしたが,晩年にいたって狂信に陥り,82年に〈非法王〉として部下の手で殺された。
タークシンに代わって82年王位についたラーマ1世 (チャクリ。在位1782-1809)は,都を対岸のバンコクに移して現在のラタナコーシン朝 (1782-)を開いた。ラーマ1世はボロマコート王の制にならって宮中の諸制度を改めるなど,すべてにアユタヤ朝の再興を目ざした。経律の結集 (けつじゆう)(1788)を後援しておおいに仏教を振興させ,また王朝年代記の勅撰(1795),《三印法典》の編纂(1805)を行い,国家統治の基礎を固めた。また対中国貿易を推進して新王朝の経済的基礎の確立に努めた。ラーマ2世(在位1809-24)は最大の門閥ブンナーク家と協調して権力の安定を図った。王が死ぬと,財務・外務長官であった長子がラーマ3世(在位1824-51)として即位した。1826年イギリスとの間に締結されたバーネイ条約 によって,伝統的な王室独占貿易に制限が加えられるようになると,その損失を補うため徴税請負制度が導入された。徴税請負人の多くが華僑であったことは華僑のタイ化の促進に貢献した。
4世王モンクット (在位1851-68)は,先進資本主義諸国の自由貿易要求を受け入れ,開国政策によって,近代化の契機を開いた啓蒙君主として知られる。55年に締結されたボウリング条約 は,支配層の伝統的経済基盤をゆるがせ,タイに社会秩序の再編成を迫った。また米輸出の解禁は商品米の生産を刺激し,やがて無人のチャオプラヤー・デルタをタイ最大の穀倉地帯へと変貌させた。5世王チュラロンコン (在位1868-1910)は,イギリス,フランス両植民地主義勢力の圧力を受けながらも,巧みな外交政策によって植民地化の危機を回避し,国内にあっては門閥の勢力を排除しつつ,タイを近代国家へと脱皮させることに成功した。有能な王弟ダムロン を内相に起用して地方行政制度を整備せしめ,タイ国史上初めて,絶対君主による領域支配の貫徹する集権的統治体制を確立した。行政組織の近代化にあたっては,各国へ留学生を派遣して人材の養成を図る一方,多数の〈御雇外国人〉を招聘(しようへい)している。日本からも政尾藤吉 ,安井てつ など,刑法,女子教育,養蚕などの専門家が渡タイした。
チュラロンコンのつくった近代的国民教育の基礎は,6世王ワチラウット (在位1910-25)の時代に〈初等教育法〉(1921)が成立し,義務教育制度が導入されることによって確立した。外国留学を経験した最初のタイ国王であるワチラウットは,文人としての評価はあるものの,すぐれた統治者とはいいがたかった。とくに〈スアパー〉と称する国王直属の疑似軍隊をつくって軍人の反感を買い,放漫な財政によって国家財政の危機を招くなどの失政は,のちに大きな禍根を残した。1925年王位を継いだ7世王プラチャーティポック (在位1925-35)は,財政再建に苦慮したが,世界大恐慌の発生という不幸が重なり,行政整理,官吏の減俸措置は伝統的な王族支配に対する批判を生み,ついに32年文武の若手官僚を中核とする人民党のクーデタ(立憲革命)が発生してタイの絶対王政は終りを告げた。
立憲革命以後 1932年以降のタイ現代史は,伝統的政治・文化と断絶のないままに,社会・経済的変化に適合する民主政治のあり方を模索した試行錯誤の軌跡である。その営みの困難さは立憲革命後の30年間に繰り返された憲法の改廃が,実に20回を超えるという事実のなかに明らかに示されている。38年までの6年間は,人民党内部における武官派勢力がしだいに増大し,その領袖に推されたピブン が権力を掌握していく過程である。首相の地位についたピブンは,伝統的な国名〈シャム〉を廃し,これを〈自由〉を意味する〈タイ〉に改めるとともに,近代国家の建設を目標に次々と国家主義的政策を打ち出した。太平洋戦争が勃発すると,ピブンは日本の軍事行動に追随したが,日本の軍事的劣勢とともにその勢力は衰え,44年ついに下野し,戦後は戦犯容疑に問われた。しかし,後継の文民内閣が戦後の混乱の収拾に失敗すると,47年のクーデタを契機として再びピブン復帰の動きが現れ,51年には,ピブン独裁体制が再現されるにいたった。ピブンは陸軍,警察両勢力の均衡の上に権力の確立を図ったが,57年,陸軍の指導者サリット のクーデタにより失脚,日本に亡命した。
首相となったサリットは,憲法を廃止し,行政組織を高度に集権化するとともに,数々の要職を兼任して権力を一身に集中化すると,国家開発を最優先の政治目標に掲げて,意欲的な開発政策を推進していった。100%の外資を認める〈産業投資奨励法〉の改正によって,外国企業が大量に進出したが,工業化の進行とともに首都バンコクの人口は急激に増加し,工場建設によって市域は急速に拡大した。また地方における高等教育機関,テレビ局などの建設は,地方都市の前例をみない発展を促した。63年,サリットが死ぬと,政権はタノム ,プラパートPraphat Charusathien(1912-97)という軍の2巨頭によって継承された。タノム=プラパート内閣は,世論の圧力に抗しきれず68年にいたってようやく憲法を施行し,翌年選挙を実施したが,内外の政治・経済情勢の変化に伴い緊張が高まると,71年再びクーデタに訴えて全権を掌握し,事態の収拾を図った。しかし73年の憲法制定要求を契機として,タイ国史上初の学生蜂起が発生し,腐敗したタノム=プラパート政権はついに瓦解し,同年10月14日,タノム,プラパートはともに国外へ亡命を余儀なくされた。
〈民主化の時代〉と呼ばれる73年10月14日以降の3年間は,学生運動の活性化,農民運動の組織化,労働争議の頻発によって特徴づけられるが,それはまた,石油価格の暴騰によるインフレーション の激化,ベトナム,ラオス,カンボジアにおける社会主義政権の成立と王制廃止という激動の時代でもあった。こうした内外の情勢の展開に対応する国内秩序の混乱に危機感を覚えた軍人官僚は,開発優先政策の生んだ保守的な都市新興ブルジョア階級の支持を背景に,〈ナワポン〉などの疑似大衆右翼組織を動員してしきりにタイ社会主義化の危険性を宣伝するとともに,76年10月6日には,学生のデモ隊に大弾圧を加え,クーデタに訴えて〈民主化の時代〉に終止符を打った。
〈民主化の時代〉は短命に終わったが,この間に代表民主制への道が開かれたことは,その後の政治の動きを規定する重要な点として見のがすことはできない。とくに経済人の政治への直接参加要求は,それまでのタイにまったくみられない現象として注目される。きわめて反動的なターニン極右内閣(1976年10月~77年10月)が,わずか1年で退陣を迫られたのも,経済規模の拡大を背景としてしだいに社会的発言権を増した経済人の官僚批判を,従来のように強権をもってかわすことがもはや不可能となった状況を示している。78年以後,軍部内に〈民主軍人グループ〉が形成され,軍部主導による民主革命の宣伝を開始したことは,こうした状況に対する軍部の新しい対応の一つとみられる。政治意識に目覚めた経済人は,批判勢力に甘んぜず,みずから政党を結成して政界に進出した。1974年に結成された社会行動党やタイ民族党のような軍部に拮抗しうる実力を備えた新政治勢力の台頭は,軍部と資本家政党の政治権力をめぐる対立というタイ政治史上初の図式を現出させている。石井 米雄
政治 1980年3月,プレーム(1920- )国防相兼陸軍司令官が首相に就任した。プレームは軍をバックに,自らは国会議員ではないものの,国会の多数派の支持を獲得し,国王の信任も厚く,長期安定政権を築いた。88年7月の総選挙後,連立与党はプレームの続投を支持したが,選挙の洗礼を受けていないプレームに対して,民選議員を首相に,との声が盛り上がり,プレームは続投を辞退,8月にタイ民族党のチャートチャーイ(1922- )が首相に就任した。12年ぶりの民選首相であった。チャートチャーイ政権は,軍部の政治介入を薄める憲法改正を実現させ,インドシナ各国との関係改善をはかったが,軍部との対立が激化した。91年2月,軍がクーデタを起こし,同年12月,軍主導で新憲法が制定された。92年3月の総選挙後,スチンダ国軍最高司令官が退役して首相に就任したが,民主化運動に対する軍の発砲が流血事件を招き,スチンダは2ヵ月で辞任を余儀なくされた。同年9月,改めて総選挙が行われ,民主党のチュアンを首相とする5党連立政権が発足,政治の民主化と経済の自由化に取り組んだ。95年7月の総選挙の結果,バーンハーン連立政権が誕生したが,スキャンダルで解散に追い込まれ,96年11月の総選挙をへてチャワリット連立政権が成立した。しかし,チャワリット首相は経済運営の失敗から97年11月に辞任し,チュアン元首相が首相に就任した。
現在の憲法は97年9月に国会で採択され,10月に国王が署名して発効した。間接選挙で選ばれた市民代表や学者で構成される新憲法起草委員会が草案をまとめたもので,旧憲法に比べて民主的な条項が数多く盛りこまれている。国会は上院,下院の二院制で,上院は任命制から直接選挙制となり,下院には小選挙区比例代表制が導入された。閣僚の資産公開の義務化,国家腐敗防止委員会,憲法裁判所,行政オンブズマンの設置などが特徴となっている。編集部
経済 1855年にタイのラーマ4世王とイギリスとの間で締結されたボウリング条約を皮切りに,タイは次々と欧米諸国と通商条約を結び,世界貿易ネットワークへ統合されると同時に,急速に商品生産社会へと変容していった。すなわち米,スズ,チーク材などをヨーロッパや香港,シンガポール経由でアジア域内に輸出する一方,綿糸布や雑貨,機械類をヨーロッパやインドから輸入する貿易構造が定着した。この過程で当初は,ヨーロッパ系商会が貿易,精米,製材,海運,保険を独占したが,20世紀初頭からは,精米と米輸出を基盤に華僑・華人が台頭し,彼らはのち銀行,保険,海運業にも進出して多角的なライス・ビジネスを展開した。
1932年の立憲革命ののち,新しい政府は王室や華僑,外国人の経済活動を制限する方針をとり,とりわけピブンが首相になった38年末以降からは,政府が経済活動に直接介入するに至った。国営・公企業を設置して精米,貿易,金融業の管理運営を図ると同時に,既存のヨーロッパ人,華僑が所有する製造企業を買収,統合して政府直轄の工場に変えたり(タバコ,マッチ,なめし革),あるいは新規の製造工場を設立した(織布,製糖,製紙)。政府による経済運営は第2次大戦の混乱で一時中断するが,47年のクーデタで政権に返り咲いたピブン政権がこの方針を再度推進していった。すなわち製造業を中心に国営・公企業を新設し,既存の華人事業を業種毎にシンジケート(サハ)に再編して統轄した。一方,中国革命以後のタイ政府による中国人抑制政策に危機意識をもっていた華人たちは,自分たちが所有・経営する銀行,保険,商事会社の会長や役員に軍閥の指導者を招聘し,事業の保全と利権の獲得を図ろうとした。こうして政府や軍指導者と有力華人グループの間に利権追求の協力体制が生まれ,そのことが国民経済の非効率性と停滞を引き起こす結果となった。
58年に登場したサリット政権は,政府による経済運営や経済ナショナリズム の方針を放棄し,外国人を含む民間企業の投資を奨励することで,本格的な工業化と経済開発政策に着手した。〈国の開発〉をスローガンに掲げたサリット首相は,投資委員会の設置,経済開発五ヵ年計画の導入,国家教育会議の設置と義務教育の拡充,道路・電力などを中心とする産業インフラストラクチャーの整備,地方開発など,一連の政策を実施に移していった。首相,開発大臣,陸軍司令官,警察長官を兼任するサリットは絶大な権力をもち,〈独裁者〉の代名詞となったが,他方では現在につながる〈開発体制〉の枠組みと成長志向の社会をタイにもたらしたと言える。
73年10月の〈学生革命〉でサリット政権以来続いた軍事政権は倒壊し,学生や労働運動の昂揚,石油ショックなどで,タイの政治と経済は深刻な混乱に陥る。しかし原油価格の引上げとともに生じた国際的な一次産品ブームに乗って,米,天然ゴム,タピオカ,砂糖の輸出金額が増大し,さらに80年代に入るとブロイラー,養殖エビ,ツナ缶詰などのアグロインダストリーの輸出が伸びた。農水産物やその加工品の輸出を伸ばしつつ,他方では繊維,自動車組立,鉄鋼二次製品などの輸入代替化を進めるというユニークな工業化,すなわち〈農産物関連新興国(Newly Agro-Industrializing Country)〉としての発展を遂げていった。ただし,80年代初めの一次産品ブームの終焉により輸出は次第に停滞し,タイ湾の天然ガスを利用した石油化学プロジェクトなどの公的借款の増加が引金となって負債比率が上昇し,80年代半ばにタイ経済は工業化を開始して以来最初の不況を経験した。
これに対して88年に登場したチャートチャーイ政権は,85年のプラザ合意以降の円高による未曾有の外国人投資ラッシュに助けられて,一連の経済拡大政策をとった。輸出企業に対する投資優遇,棚上げにしていた重化学工業プロジェクトの推進(石油化学,鉄鋼一貫,自動車エンジン),地方経済の振興,産業と金融両分野の規制の緩和などがそれである。その結果,88年を契機にタイは不況から一転して〈経済ブーム〉を経験し,2桁の成長率,繊維・衣類,電子部品など工業製品輸出の急増,民間製造企業の労働力雇用の急増を実現した。半面,このブームは無秩序な不動産投資,株式投機,ローンに頼った個人消費を併発させ,経済にバブル的性格を付与すると同時に,バンコクや地方の都市部と農村の間の所得格差を拡大した。
一方,92年から始まった金融の自由化政策は,国内外の金融機関の貸付競争と海外からの短期的投機的資金の大量流入を誘発し,金融面では過剰流動性が,生産面では過剰投資が生じた。その結果,金融統制を転機に金融機関の不良債権問題が顕在化し,国内投資と消費が減退する一方,ブームの中で生じた労賃の上昇によって労働集約的なアグロ製品や衣類・雑貨の輸出が低下した。そして97年7月のバーツの大幅切下げと管理フロート制への移行が引金となって,タイ経済は通貨不安,金融不安,深刻な国内不況に直面するに至った。60年代以降続いてきた成長パターンは,ここにきて全面的な見直しと〈構造調整〉を迫られているのである。末広 昭
日本との関係 日・タイ間の交渉は朱印船貿易で活発となる。17世紀のアユタヤには日本人町(南洋日本人町 )ができ,山田長政 が活躍した。しかし江戸幕府の鎖国政策で往来は途絶え,日・タイ友好通商条約が締結されたのは1898年(明治31)であった。政尾藤吉らの渡タイなどの文化交流期を経て,太平洋戦争が勃発(ぼつぱつ)すると日本軍が進駐し,それに反対する人々は国外で自由タイ の運動を展開した。戦後1947年に再開された日・タイ間の貿易は急速な伸びを示したが,タイ側の大幅な入超がつづいており,日本資本の進出も外国資本の40%弱を占めるにいたった。このような状況のなかで,72年以降,全国タイ学生センターを中心とする日本商品不買運動も,しばしば展開されている。山本 徹
文学 タイ族が文字をもったのは13世紀末であるが,タイ語が単音節的で5声調と百数十の韻をもつことが種々の詩型を生み,韻文が古典文学の主流を占めた。インド文化,とくに仏教とバラモン教の影が濃く,主人公の多くは王族である。
スコータイ朝の作品には特筆すべきものがない。17世紀初めまでのアユタヤ朝初期には,タイ古来の詩型であるラーイ詩とクローンkhlong詩を混ぜたリリット形式の国王賛歌《チエンマイ敗る》,悲恋詩《プラロー 》が生まれ,パーリ語から《布施太子本生経》が《マハーチャート 》として訳された。ナライ王時代(1656-88)は前期黄金時代で,詩型もカープ,クローンklon,クローンkhlong,チャン,ラーイと華やかになり,王自身の四つの小品をはじめ,《海鳴王子》《牛虎》,詩作宝典《宝珠篇》などが出た。このころの代表詩人は,王宮の美人に懸想して南タイに流謫(るたく)される道中をつづった《悲歌》のシープラートであろう。アユタヤ朝後期(1732-67)にはカープやクローンklon形式の詩劇が盛んになり,20編以上創作された。ジャワ伝来の《イナオ 》の原形もモンクット姫の手でなっていた。当時の最高の詩人は,多くの美しい恋歌,旅行詩,舟歌を残しながらむち打たれて死んだ悲恋のエビ王子(1715-55)であろう。アユタヤ朝は1767年ビルマ軍によって滅ぼされたが,そのとき多くの貴重な作品が灰に帰した。残巻中の詩劇には《マノーラー》《法螺貝王子》《カーウィー》など14編があるが,《クライトーン》など6作もすでにあったと思われる。
ラタナコーシン朝のラーマ1世時代(1782-1809)には古代インドの叙事詩《ラーマーヤナ》のタイ版《ラーマキエン 》が王宮で合作され,チャオプラヤー・プラクラン はモン語から《王中の王》を,また王命により《三国志演義》を《サームコック 》と題して訳した。後者は散文の規範とされ,インド風の物語に食傷気味だった文学界に清新な風を呼び込み,以後三十数編の中国歴史小説が訳された。現行《布施太子本生経》のクライマックス の二つの章もこの人の筆による。ラーマ2世時代(1809-24)はタイ文学の精華の時代で,宮廷には王やのちのラーマ3世をはじめ,市井の語彙を駆使して文学を大衆化したタイ最高の詩人スントーンプー ら一流の詩人が集い,けんらんたる舞踊歌劇の傑作《イナオ》や純タイ的でタイ文学史上最,傑作《クンチャーン・クンペーン 》が競作され,《法螺貝王子》《クライトーン》など多くの詩劇が完成された。個人の作としては最大のロマン《プラアパイマニー 》(スントーンプー作)が完成したのはラーマ3世時代(1824-51)であろう。このころ,10年をかけて英雄ナレースエン王(在位1590-1605)賛歌の名作《タレーンパーイ》を書いた僧籍のパラマーヌチットチノーロット親王 (1790-1853)は,《布施太子本生経》の約4割を名調子で書いている。
19世紀半ばから印刷が始まり新聞が発刊され,ヨーロッパに赴くタイ人が増え,1868年チュラロンコンが即位して文明開化期に入ると,散文全盛時代となったが,作家の生活は苦しく,現代文学にはまだ不朽の大傑作はなく,映画とテレビの普及は舞台演劇をも弱体化してしまった。冨田 竹二郎
美術 歴史を通じてこの国の美術はおもに仏教に奉仕した美術であるが,そのほかにヒンドゥー教の美術も含む。タイ国美術史は一般に大きく二つに分けて論じられる。一つは〈先タイ期〉と称し,タイ族が今日のタイに南下して移住してくる以前の先住民族たちの美術をさす。もう一つは〈純タイ期〉と呼び,タイ族が南下・移住し,タイに定住して以降の美術をさす。タイ美術の一般的特徴は,歴史を通じて,古い時代にさかのぼればさかのぼるほど,その性格がインド的であるという点にある。インドからの影響を濃厚に受けながら育ち,それがしだいにタイ独自の美術に発展していったのである。
先タイ期美術はドバーラバティ期,スリウィジャヤ期,ロッブリー期に分けられる。先のドバーラバティ期とスリウィジャヤ期はほぼ同時代の美術であるが,栄えた地域が違う。前者はタイ中部を中心に,後者はタイ南部に開花した美術である。いずれにせよ,この両者はともにインド美術からの影響を濃く受けている点で一致している。ドバーラバティ美術 の特徴は,ドバーラバティ王国がおもに上座部仏教を信奉したため,釈尊の像だけがつくられたことである。それらはおもに石灰岩でつくられ,全体的な作風はインドのグプタ朝時代のサールナート 美術の流れをくむものであった。このほか南インドのアマラーバティー 美術の流れをくむ像もある。これらの仏像はおもにナコーンパトム から発見されたが,ここからは法輪(石灰岩製)も多く出土している。仏像も法輪も,おもに7~8世紀のものと思われる。スリウィジャヤ期美術は大乗仏教美術で,チャイヤー を中心に栄えた。この期の代表的な作品として,チャイヤーより出た青銅製の観音像(トルソー)があげられる(バンコク国立博物館蔵)。これもインドの後グプタないしパーラ朝美術からの影響を感じさせる尊像である。ロッブリー期(11~13世紀)美術は,先の二つの美術の後の時代にくるクメール族の美術である。大乗仏教(密教)とヒンドゥー教美術 が共存し,カンボジアに栄えたアンコール朝(9~15世紀)の美術がタイに浸透し,その政治的な支配の下で生まれた。とくに蛇の上に座った宝冠仏が多くつくられ,青銅製の諸仏(小型の作品)も多産された。このころの重要な遺跡として,タイ北部のピマーイ寺院 があげられる。クメール族のタイにおける中心地がロッブリーにあった関係から,ロッブリーも当時の遺構や出土品が多い。
純タイ期美術はスコータイ期,アユタヤ期,バンコク期に分けられる。これらはすべてスリランカより伝えられた上座部仏教美術である。したがって仏像は,釈尊にのみ帰依するために釈尊の像しかつくらないのを特徴とする。スコータイ期(13~15世紀)は,この期に初めてタイ美術の基礎が確立されたため,一般に〈古典期〉と称している。この美術はスリランカの美術からの影響を受け,スリランカ風の仏像がつくられた。とくにこの期で注目される作品は,歩く姿を丸彫によって表現した遊行仏である。これはタイ美術が世界に誇りうる独創といえる。またこのころ,のちに日本にも輸出されて宋胡録(すんころく)焼 の名で親しまれた陶器がつくられた。アユタヤ期(14~18世紀)の美術は,一般にタイの国民美術の時代といわれる。仏像はスコータイ期の継承で,とくに体中に装飾をほどこした宝冠仏が多くつくられた。工芸美術の面にもみるべきものが多く,たとえば漆細工や象嵌細工にタイ美術独自の世界を現出した。バンコク期(18世紀末~)は,ラタナコーシン(バンコク)朝の美術で,やはり前代の美術を継承しているが,新たに西洋からの写実的な表現法の影響がみられる。仏教寺院の壁画にすばらしい作品が多く,たとえば,バンコク国立博物館のプッタイサーワーン礼拝堂の仏伝図(18世紀末作)があげられる。伊東 照司
音楽 タイはカンボジア,ラオスとならび,インドシナ半島を代表する音楽文化をもっている。理論的にはインドの音楽から多くの影響を受け,また中国の音楽ともかかわりが深いが,直接的にはクメール文化の影響を色濃く受けている。
(1)古典音楽 アユタヤ朝時代に宮廷の保護を受けて発展したもので,多くはコーン (仮面劇)やラコーン (舞踊劇)のような古典芸能と結びついている。伴奏には〈ピー・パート合奏〉(主旋律を奏するゴング系の打楽器コン・ウォン・ヤイに,ピーというダブル・リードの縦笛と太鼓などのリズム打楽器を加えたもので,楽器の種類,数により大小の編成になる)が用いられる。(2)宗教儀式音楽 仏教徒の多い民衆の日常生活に密着したもので,儀式にはピー・パート合奏が普通である。(3)民俗音楽 民謡など,地方の音楽については,ようやく研究の緒についたばかりで,実態はまだ明らかではない。各地で民謡の掘起しが行われており,その一部は舞踊公演などでも取り上げられている。こうした歌や踊りには,伝統的で素朴な器楽合奏や民俗楽器(ケーン など)が用いられる。そのほか,山間部にはミヤオ族,カレン族,ヤオ族など多くの少数民族が住み,それぞれ素朴な民俗楽器を用いて音楽の伝統を保持している。北部タイの民俗楽器によるウォン・プーン・ムアンと呼ばれる器楽合奏がこの十数年来新しく見直されている。また親から子へ伝えられた100種以上の子守歌が今日でも歌われている。(4)その他 ポピュラー音楽では,西洋音楽,日本の音楽など,外来の音楽を積極的に取り入れ,タイ風に消化している。また,冠婚葬祭などの機会にも音楽は生活と切り離すことができない。こうした結婚式や宴会などには,クルアン・サーイ合奏 (弦楽器を中心に笛とリズム楽器を加えたもの)やマホーリー合奏 (ピー・パートとクルアン・サーイにルバーブ系統の3弦の楽器を加えた規模の最も大きい器楽合奏)が用いられる。このほかに,簡単なラム・ウォン(輪踊)も盛んで,祭りのときには必ず踊られるといってもよい。
音楽形式の中で大きなものはタオと呼ばれるもので,基本の旋律型を段によって発展させていき,ここでは各楽器の個性が生かされ編成も多様である。もう一つはタプと呼ばれ,西洋音楽での組曲のように,いろいろな性格をもつ旋律や小曲を組み合わせていく。また音楽理論上の特徴としては,リズムは主として2拍子で,5音音階によるものが多い。本来,タイの音階は7等分平均律であるといわれてきたが,実際には,5音が主であり,第4音,第7音についても,絶対的な高さではなく,曲によって自由に高低がつけられる。桜井 笙子