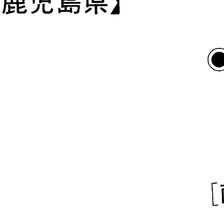精選版 日本国語大辞典 「鹿児島」の意味・読み・例文・類語
かごしま【鹿児島】
- [ 1 ]
- [ 一 ] 鹿児島県中南部、鹿児島湾に臨む地名。県庁所在地。江戸時代は島津氏七七万石の城下町として栄えた。特産は大島紬(つむぎ)、薩摩焼、焼酎(しょうちゅう)など。明治二二年(一八八九)市制。
- [初出の実例]「康国什麽 カゴシマ 鹿児島」(出典:日本図纂(1561))
- [ 二 ] 「かごしまけん(鹿児島県)」の略。
- [ 三 ] 鹿児島県、薩摩半島の北東部の郡。現在の鹿児島市域もかつては含まれていた。
- [初出の実例]「薩摩国 〈略〉鹿児島〈加古志万〉」(出典:二十巻本和名抄(934頃)五)
- [ 一 ] 鹿児島県中南部、鹿児島湾に臨む地名。県庁所在地。江戸時代は島津氏七七万石の城下町として栄えた。特産は大島紬(つむぎ)、薩摩焼、焼酎(しょうちゅう)など。明治二二年(一八八九)市制。
- [ 2 ] 〘 名詞 〙
- ① 薩摩国(鹿児島県)で産出される紬(つむぎ)。
- [初出の実例]「さやうかえ・かご島隅へちょっと脱」(出典:雑俳・あふむ石(1839))
- ② 「かごしまげた(鹿児島下駄)」の略。
- [初出の実例]「かごしまの音からからと」(出典:洒落本・窃潜妻(1807)下)
- ① 薩摩国(鹿児島県)で産出される紬(つむぎ)。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「鹿児島」の意味・わかりやすい解説
鹿児島(県)
かごしま
九州の南端に位置する県。北は熊本県、北東から東部にかけて宮崎県に接し、南は海を隔てて沖縄県と相対する。古くは薩摩(さつま)、大隅(おおすみ)の2国からなり、県名は中世以来島津氏統治の中心であった鹿児島郡にちなむ。東側には南に向かって突き出た大隅半島と、西側には薩摩半島があり、この2半島で鹿児島湾(錦江湾(きんこうわん))を擁し、湾奥近くに桜島が浮かぶ。また、大隅半島の先端、佐多(さた)岬から約40キロメートルの海上にある種子島(たねがしま)から南西方向に約500キロメートルの地点の与論(よろん)島(北緯27度付近)にまで及び、広い海域を有し、大隅半島―薩南諸島を境に東は太平洋、西は東シナ海に分けられる。これらの島嶼(とうしょ)列は大隅諸島、吐噶喇(とから)列島、奄美諸島(あまみしょとう)からなり、薩南諸島と総称される。主要な島には、種子島、屋久島(やくしま)、奄美大島、徳之島などがある。県庁所在地は鹿児島市。県土の占める位置の関係から、その自然環境は多様であり、生活様式もまた変化に富む。薩摩国、大隅国の創置以来、つねに中央からは僻遠(へきえん)の地でしかなかったが、それゆえにまた、大陸から、南の島々から、さらには遠くヨーロッパなどからの文化の伝来地ともなり、日本の玄関の役目を果たした。また、社会的には鎌倉時代以来近代に至るまで連綿と続いた島津氏の支配も特筆に値するだろう。これら自然的、社会的諸条件の反映の結果として、歴史上の随所にみられるような、本県人の保守性と革新性、あるいは後進性と進取性という相反する特性をみいだすことができる。
人口はその動態をさかのぼってみると、1920年(大正9)に142万であったが、1925年に147万となり、1927年(昭和2)に150万を超えた。その後、1935年まで漸増し159万となる。1945年(昭和20)までは第二次世界大戦の影響で150万人台の増減を繰り返し、その後の10年で204万(1955)に達する。昭和30年代の人口流出は以後1972年まで続き、170万まで減少した。その減少率は全国の1、2位を争うほどで、とくに若年層の減少が目だち、人口構造の老齢化をもたらした。2020年(令和2)の国勢調査では158万8256人となっている。
面積9187.06平方キロメートル。2020年10月現在、19市8郡20町4村からなる。
[塚田公彦]
自然
地形
地形の特色をひとことで表現すれば、それはシラス台地の分布ということに尽きよう。指宿(いぶすき)(阿多(あた))、姶良(あいら)両カルデラの生成に起因する「シラス」堆積(たいせき)物によって形成された台地や丘陵地が県土の50%以上の地域を占めている。台地面は平坦(へいたん)でかつ緩斜面をなすが、その縁辺部は比高数十メートル~200メートルの急崖(きゅうがい)で境される。大隅半島の中央部にある笠野原(かさのはら)、鹿児島空港のある十三塚原(じゅうさんつかばる)、霧島山麓(きりしまさんろく)付近の春山原(はるやまばる)、須川原(すかわばる)などはその代表例。これらの台地が古い山間低地を埋め、標高数十メートルから300メートルくらいの広い平坦面を随所に形成しているさまは、本県ならではの特殊な景観といえよう。一方、骨格をなす山地は、熊本県との境をなす約1000メートルの国見山地(くにみさんち)、やや南部の紫尾(しび)山を主峰とする出水山地(いずみさんち)、宮崎県との境をなす1500メートル内外の霧島山地、同じく約500メートルの日南山地が県域を取り囲み、わずかに県下最長の川内川(せんだいがわ)の河谷(川内平野)と、大淀(おおよど)川の支流横市(よこいち)川の谷が宮崎県の小林盆地や都城(みやこのじょう)盆地へと開いている。これら周囲の山地のほか、大隅半島の基部にある高隈山地(たかくまさんち)、同じく先端部の肝属山地(きもつきさんち)、鹿児島湾と川内川を分ける八重山山地(やえやまさんち)、薩摩半島の南薩山地(なんさつさんち)などが主要な骨格をなし、その間に桜島、開聞(かいもん)岳など1000メートル級の孤峰が点在する。本県の最高点は屋久島の宮之浦岳(みやのうらだけ)で1936メートルである。海域では弧状をなす島嶼(とうしょ)群が南西に向かって延び、離島面積では全国一、その数では全国第4位となっている。それら多くが火山島で、現在でも活発に活動しているものもある(諏訪瀬(すわのせ)島、硫黄(いおう)島、口永良部(くちのえらぶ)島など)。
自然公園には、霧島火山群と鹿児島湾岸一帯を範囲とする霧島錦江湾国立公園、屋久島、口永良部島からなる屋久島国立公園、奄美群島国立公園、雲仙天草(うんぜんあまくさ)国立公園(一部)、甑(こしき)島国定公園、日南海岸国定公園のほか、県立自然公園に阿久根(あくね)、吹上浜(ふきあげはま)、藺牟田(いむた)池、坊野間(ぼうのま)、川内川流域、高隈山、大隅南部、トカラ列島の8か所がある。
[塚田公彦]
気候
鹿児島県の気候を区分すると、南海型、西海型、亜熱帯型になる。南海型は九州の東半部から四国、紀伊半島南部に連なる地域に分布し、本県では大隅半島が属する。西海型は熊本県の一部、長崎県が含まれ、本県では鹿児島湾岸から西側の地域がこれに属す。亜熱帯型は種子島以南の島嶼部に分布する。南海型では、年平均気温17℃前後、1月の平均気温7~8℃で、雪をみることは年に一度あるかないかという程度で、降水量が年平均2000~3000ミリメートルに達する。植生は志布志(しぶし)湾の枇榔島(びろうじま)にみられるごとく亜熱帯樹が自生する。西海型は、前者より1~2℃低い気温で、降水量は2000ミリメートルを超える所が多い。温暖多雨ではあるが、冬の天気は南海型ほどよくはない。亜熱帯型では、年平均気温19~22℃、1月の平均気温も10℃を割ることはほとんどない。降水量のばらつきは島により大きいが、2000ミリメートル以上であり、南海型よりいっそう温暖な気候である。多くの亜熱帯樹や、サトウキビ、バナナ、パイナップル、パパイヤ、ポンカンなどの産物に示される気候である。
[塚田公彦]
歴史
先史・古代
1965年(昭和40)に出水(いずみ)市上場(うわば)高原に旧石器文化が発見されてから、約30か所の旧石器遺跡が発見されている。そのおもな地点は鹿児島市、阿久根市、薩摩川内(さつませんだい)市、指宿(いぶすき)市、湧水(ゆうすい)町、霧島市溝辺(みぞべ)町などである。縄文文化は「東高西低」といわれてきたが、1990年代に入り鹿児島県では考古学の定説を覆す縄文遺跡の発見が相次ぎ、なかでも草創期や早期遺跡の密集度は日本有数となった。鹿児島市の掃除山遺跡では縄文時代草創期(約1万2000年前)の最古の住居跡、南さつま市の栫ノ原(かこいのはら)遺跡からも草創期の大規模集落跡で定住生活を裏付ける出土品が発掘された。霧島市の上野原遺跡からは縄文早期(約7500年前)の壺(つぼ)形土器が出土、姶良(あいら)市加治木町日木山(かじきちょうひきやま)の干迫(ほしざこ)遺跡からは縄文後期の九州各地、瀬戸内海沿岸の土器が多数発見された。この時期の縄目の文様をもつ土器は少なく、貝殻を使用した押圧(おうあつ)文、条痕(じょうこん)文が多い。各時期を通じて遺跡は発見されるが、前期・中期には火山活動の激しい時期があり、一時的に文化が停滞した形跡がある。また、後期から晩期にかけて大いに海洋性を発揮した時期があったことが注目される。
弥生(やよい)文化は水稲耕作と金属器の使用に特色がみられるが、本県でもこの特色をもつ文化が弥生前期には確認でき、以後中期への発展をみせるが、後期には停滞する様相を呈する。おもな遺跡は、薩摩半島西岸沿いの南さつま市金峰(きんぽう)町、日置市吹上町、鹿児島湾岸の鹿児島市、垂水(たるみず)市、志布志(しぶし)湾周辺部の肝付(きもつき)町野崎(のさき)、川内川流域の伊佐(いさ)市、湧水町北方(きたかた)などがあげられる。南さつま市金峰町の高橋貝塚は前期の代表的な遺跡で、出土した土器には籾(もみ)の圧痕がみいだされ、また鉄器様遺物も発見されている。また、種子島南部の広田遺跡出土の貝符の1枚には「山」の文字が刻まれている。錦江(きんこう)町の山ノ口遺跡は中期の祭祀(さいし)遺跡である。
古墳文化は多様である。高塚墳は畿内(きない)、瀬戸内から九州東岸部を経由して伝わり、主として志布志湾周辺部に分布し、総数は400基を超えるが、大部分は円墳である。現存の代表的な古墳は横瀬古墳(大崎町)、県下最大の唐仁大塚古墳(とうじんおおつかこふん)(東串良(ひがしくしら)町)で、いずれも前方後円墳である。
これらの古墳文化は熊襲(くまそ)の文化であり、隼人(はやと)の文化でもあった。『古事記』や『日本書紀』に熊襲がまず登場し、のち隼人が現れる。熊襲は日本武尊(やまとたけるのみこと)の熊襲征伐物語にあるように大和(やまと)政権に頑強に抵抗しているが、隼人は抵抗した時期もあるが、のちには大和政権に服属している。
奈良時代、遣唐使が南西諸島経由の南島路を利用するようになると、多禰嶋(たねのしま)(種子島)、掖玖(やく)(屋久島)、阿麻彌(あまみ)(奄美(あまみ)大島)などの人々の来朝や、これらの島への遣使などがみられる。また薩南地方の重要性は増し、坊津(ぼうのつ)は日本三津の一つといわれるように繁栄した。
薩摩、多禰両国の成立は702年(大宝2)と推定され、713年(和銅6)には日向国(ひゅうがのくに)の一部を割(さ)いて大隅国が成立している。大隅国府は霧島市国分府中(こくぶふちゅう)、薩摩国府は薩摩川内市に置かれた。このように国府が置かれ律令(りつりょう)制度が強行されると、隼人たちとの間に摩擦が生じ、隼人の反乱がみられる。とくに720年(養老4)の反乱は大規模で、大隅国守を殺害するに至ったので、大和朝廷は大伴旅人(おおとものたびと)を隼人征討に向かわせた。薩摩、大隅両国の班田(はんでん)制の採用は800年(延暦19)で、他国よりはるかに遅れて実施された。このように大隅、薩摩両国の律令体制は8世紀から9世紀初めにかけてしだいに整えられた。
平安時代になると班田制度が崩壊し荘園(しょうえん)が成立する。薩摩、大隅両国の代表的な荘園は島津荘で、宮崎県都城(みやこのじょう)市付近の島津駅のあたりを大宰大監(だざいのだいげん)平季基(たいらのすえもと)が万寿(まんじゅ)年間(1024~1028)に開発したのが始まりである。この墾田は関白藤原頼通(よりみち)に寄進され、やがて薩摩、大隅の豪族たちは自分たちの荘園の権利を確保しようとして藤原氏に寄進した。島津荘の特色は「半(なか)ばを輸(ゆ)さ」ざるという寄郡(よせごおり)、すなわち租の半分を上納しない荘園が多いことにあった。
[村野守治・田島康弘]
中世
源頼朝(よりとも)が鎌倉幕府を創設すると、近衛(このえ)家に関係のある惟宗忠久(これむねただひさ)が島津荘下司職(げししき)に補任(ぶにん)された。やがて忠久は薩・隅・日3州にまたがる広大な島津荘の惣地頭職(そうじとうしき)となり、1197年(建久8)には薩摩、大隅の守護に、のちさらに日向の守護にも補任された。忠久、忠時、久経(ひさつね)の3代は多く鎌倉在番であったが、3代久経は蒙古(もうこ)襲来の弘安(こうあん)の役(1281)に薩摩の御家人(ごけにん)を統率して任国の経営にあたることになった。5代貞久(さだひさ)は鹿児島を根拠地として東福寺城(鹿児島市)に拠(よ)った。7代元久は東福寺城から清水城(しみずじょう)(鹿児島市)に移り、島津家の菩提(ぼだい)寺福昌(ふくしょう)寺を創建した。南北朝の対立から室町・戦国時代を通じ、島津氏以外の有力な豪族が島津氏と対立抗争した。大隅半島の豪族肝付(きもつき)氏、禰寝(ねじめ)氏、北薩の渋谷一族などがその代表的なものである。14代勝久は伊作家(いざくけ)の島津忠良(ただよし)の援助を得ようとして忠良の長子貴久(たかひさ)を養子とした。しかし、薩州家の島津実久(さねひさ)が両者間の離反を図ったので、勝久と忠良・貴久との間に争いが起こったが、勝久は豊後(ぶんご)(大分県)に亡命し、貴久は父忠良の後見のもとに守護職を継いだ。貴久は父忠良の援助、また義久(よしひさ)、義弘(よしひろ)、歳久(としひさ)、家久の4人の優れた男子の協力により、薩・隅・日の3国統一を実現し、義久の時代には九州制覇の偉業を成し遂げた。
このころ1543年(天文12)ポルトガル船が種子島に漂着して鉄砲を伝え、6年後の1549年にはザビエルが鹿児島出身のアンジロウ(ヤジロウ)に導かれて鹿児島に到着、貴久の許しを得てキリスト教を伝えた。
1578年(天正6)大友氏を討って全九州制覇の望みをもつ島津軍は豊臣秀吉(とよとみひでよし)の調停案を一蹴(いっしゅう)したが、秀吉の全国の精鋭をすぐった大軍に日向の根白坂(ねじろざか)の決戦(1587)で敗北した。川内泰平(たいへい)寺(薩摩川内市)に入った秀吉に島津義久は剃髪(ていはつ)して抗戦の罪を謝し、薩摩、大隅と日向の一部を安堵(あんど)された。文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役では島津義弘が1万余の軍勢を率いて出軍し、泗川の戦いに勇名をあげたばかりでなく、帰国後高野(こうや)山に「敵味方供養の碑」を建てたことは特筆されよう。1600年(慶長5)関ヶ原の戦いが起こった。上方(かみがた)滞在中の義弘は西軍に属したが、西軍総敗北のなかで義弘は徳川家康の本陣に向かって進む壮烈な敵前退却を敢行した。戦後島津氏は謝罪外交に徹するとともに、国境の警備を厳重にして、2年余の執拗(しつよう)な外交交渉によって徳川と島津の和解がなり、薩摩、大隅両国と日向国諸県(もろかた)郡の旧領を安堵することができた。
[村野守治・田島康弘]
近世
島津義弘の後を継いだ家久は1602年(慶長7)鶴丸城を構築した。天守閣をもたない屋形造(やかたづくり)の居館で、城中を本丸と二の丸に分けた。また、甲突(こうつき)川の川筋を現在のように付け替え、広く城下町を建設した。また、1609年琉球(りゅうきゅう)に武力侵入しこれを征服、支配下に置いた。
関ヶ原の戦い後、国替もなく、20万余の士卒を城下に集中することができないため、兵農一致の政策をとり、城下ばかりでなく郷村(ごうそん)の外城(とじょう)にも、武士である郷士を居住させた。郷は、鶴丸城の内城に対する外部的防衛の城という意味である。薩摩51郷、大隅42郷、日向諸県郡20郷の計113郷あった。郷の中心は麓(府本)(ふもと)で、郷士の大部分が居住し、郷の行政は地頭仮屋(じとうかりや)で執行された。地頭(寛永(かんえい)ごろから遙任(ようにん)となり城下居住)のもとに郷士年寄(としより)、組頭(くみがしら)、横目(よこめ)の3役が郷の実権を握っていた。この麓の周辺に村(在)、町、浦浜が連なり、百姓、町人、浦浜人(漁業、運送業に従事)が住んでいた。
郷士制度と並んで農民に強制していたのは、門割制度(かどわりせいど)である。村をいくつかの門に分け、各門に対する土地の割当て面積を決定して交付した。この耕地は一定の年限をもって割り換えられたが、享保(きょうほう)(1716~1736)以後1870年(明治3)まで約140年間は、小規模の割換えが行われただけであった。
25代島津重豪(しげひで)は積極的な開化政策を行い、また藩校造士館(ぞうしかん)、明時館(めいじかん)などを創設し、『成形図説』などの多くの書物を編集させた。このような政策と木曽(きそ)川の治水工事などにより出費がかさみ、文政(ぶんせい)の末年(1820年代)になると藩債は500万両にも達した。そのため、側用人(そばようにん)調所広郷(ずしょひろさと)に財政改革を命じた。藩債500万両の整理、奄美大島、喜界(きかい)島、徳之島3島砂糖の総買入れ、琉球貿易の拡大などにより改革は成功し、これにより薩摩藩は明治維新変革の経済的な基礎を得た。
28代斉彬(なりあきら)は高崎崩れ(お由良(ゆら)騒動)を経てようやく1851年(嘉永4)襲封したが、積極的な藩政改革を行い、藩の富国強兵策を強力に実行した。科学的事業として5年の歳月をかけて反射炉を造成するなどの集成館事業を行い、盛時には従業者毎日1200人を超えたというから、当時日本で最大かつ最新の軍事科学工場であったといえよう。
1858年(安政5)斉彬の没後、異母弟久光(ひさみつ)の子茂久(もちひさ)(のち忠義(ただよし))が継ぎ、久光が後見して、幕末・維新の変革期に藩政の赴くべき方向を誤らなかった。すなわち久光は公武合体策をとり、大久保利通(としみち)らを用いた。のち公武合体策が行き詰まると、沖永良部(おきのえらぶ)島に流されていた西郷隆盛(たかもり)を赦免して軍賦役(ぐんふやく)(薩摩軍司令官)とした。西郷は大久保らと協力して薩長連合に踏み切り、討幕の密勅、王政復古の大号令から鳥羽(とば)・伏見(ふしみ)の戦いに幕軍を追い込んだ。鳥羽伏見の戦いから箱館(はこだて)戦争までの戊辰(ぼしん)戦争に官軍の主力をなした薩摩藩は、出軍者8000余人、戦没者570余人を出し、全力をあげて戦った。
[村野守治・田島康弘]
近・現代
戊辰戦争に戦功をあげて帰国した凱旋(がいせん)兵士団が門閥を排して藩政を掌握した。藩治職制を設け家老座を廃し知政所を置き藩政の中心とした。知政所の参政には伊地知正治(いじちまさはる)、桂久武(かつらひさたけ)らが任命されたが、旧藩主島津忠義のじきじきの要請で西郷隆盛が参政に任命され、やがて西郷の力が大きくなった。1871年(明治4)の廃藩置県により、旧鹿児島藩の薩摩、大隅、日向は鹿児島県、都城県、美々津県(みみつけん)となったが、1873年美々津、都城県を廃して宮崎県が新設され、1876年宮崎県を廃して鹿児島県の所管とした。1883年宮崎県が独立し日向国を所管とした。琉球は1872年鹿児島県から分離して琉球藩となり、1879年沖縄県が置かれた。鹿児島県では廃藩置県後、従前の鹿児島藩権大参事(ごんだいさんじ)大山綱良(つなよし)が新制による県参事に任ぜられ、権令、県令に進み、1877年官位を奪われるまで県治の責任者として在任したが、このように県政担当者が郷士(ごうし)出身者であることは特異な例である。
西郷隆盛は征韓(せいかん)論に敗れて1873年(明治6)鹿児島に帰郷したが、1874年私学校を設けて、西郷に従って辞職帰郷した青年たちの教育にあたった。大山県令は私学校に協力し、県内各地の区長・副区長や警察の幹部などに私学校の人材を採用したので、私学校勢力は増大した。明治維新の実現に協力した鹿児島士族は、政府の打ち出す反封建的な諸政策、とくに封建的土地所有を否定する家禄(かろく)奉還や地租改正に大きな不満をもった。1877年西南戦争が勃発(ぼっぱつ)したが、西南戦争による鹿児島県の被害は大きく、その立ち直りも遅かった。
1880年県令、1886年県知事になった渡辺千秋(ちあき)は、稲の浸種法その他の栽培技術の向上を図り、また農業技術者を郡役所、町村などに配置して技術指導を図った。ついで1894年に赴任した加納久宜(かのうひさよし)知事も農業振興のため農村に指導の手を伸ばし、その結果、繭(まゆ)の6倍増産をはじめ主要農産物はすべて増産となった。
大正時代に入ると、1914年(大正3)の桜島爆発で被害を受けた農業生産も、第一次世界大戦の影響で1916年から1919年は好景気に沸いたが、1920年以降の恐慌到来で農村経済は不況となり、昭和金融恐慌に続く経済恐慌によりいっそう拍車をかけ、農村経済は窮乏を極めた。1936年(昭和11)になると準戦時体制へ移行し、食糧自給、増産が強調され、県内農業生産も回復して、農村経済も自立好転した。
日本本土の最南端に位置する本県は、日中戦争以来、航空機兵力の重要な先進基地となり、県下各地に海陸軍の航空基地が開設された。とくに1945年(昭和20)3月の沖縄戦では、特別攻撃隊(特攻隊)の出動で、隊員には若い少年兵や学徒兵が多く、鹿屋(かのや)(海軍)、知覧(ちらん)(陸軍)などの各基地から出動した。また、本県は本土決戦の最前線とされ、空襲は激甚で、その被害も大きかった。
第二次世界大戦の終戦により、国内各地の基地や戦地からの兵隊の引揚げ、中国東北(旧、満州)、朝鮮、台湾などからの引揚者で、本県の人口は半年間に9万人も増加した。1946年(昭和21)の連合国最高司令部の覚書によって奄美諸島は本土から切り離されたが、1951年ごろから復帰運動が盛り上がり、1953年「奄美群島返還日米協定」が調印され、同時に大島支庁が発足した。連合国軍は日本の非軍事化と民主化を促進するため種々の改革を実施したが、六三三制など教育制度の改革と、第二次農地改革などは、本県のような社会体質の古い県にとってはたいへんな改革であった。
戦後の経済は、朝鮮動乱の特需、高度成長、低成長とめまぐるしいが、畜産部門(養豚・ブロイラーは全国第1位、肉用牛は全国第2位)の成長、「国分隼人(こくぶはやと)テクノポリス」地区への京セラや電子機器工業などの進出にみられるように、緩慢ではあるが県勢の前進がみられる。
[村野守治・田島康弘]
産業
本土の最南端に位置し、幕末には外来文化の窓口の一つでもあったことから、工業の発達は早かったが、その後、産業、文化の急速な発達が太平洋ベルト地帯でおこるにつれて、農業県、日本の食糧基地としての性格を強めてきた。第一次産業の相対的比重は高く、農業とりわけ畜産の果たしている役割は大きい。工業もこれらを原料とする農産物加工業が中心である。しかし1993年(平成5)以降、鹿児島空港周辺を中心としてIC関連産業などの先端技術産業の生産が伸び、食品製造業に次ぐ地位を占めるようになってきた。
[田島康弘]
農業
農業の基盤としての自然条件は、とくに薩南諸島で代表される温暖性、梅雨や台風期に多い豊富な降水量、広大な畑地の存在など有利な面をもつ反面、シラスとよばれる火山灰性のやせた土壌の広範な分布や、台風の被害などがあり、また位置的にも大消費地から遠距離にあることなど不利な面もある。1995年(平成7)段階では、農家数は11万1000戸と多いが、1戸当り耕地面積は1.22ヘクタールと小さく、農業所得も全体としては低位にある。しかし、畜産部門の伸びは著しく、肉用牛(32万9000頭)こそ北海道に次いで第2位であるが、ブタ(135万9000頭)、ブロイラー(1883万羽)の飼養頭羽数は全国一であり、鶏卵(1180万羽、14万7000トン)でも愛知県を抜いて全国一となって畜産王国の地位を確立してきている。このような畜産部門の発展は、大手総合商社を中心とする外部資本の進出によるところが大きい。企業のなかには直営農場をもち、生産から処理、加工さらには流通まで一貫経営を行うものもあるが、多くは、生産において数戸ないし数十戸の農家に委託し、農家側は土地と労働力を提供して飼養するという契約生産体制をとっている。こうしてインテグレート(統合、系列化)された農家と企業の直営農場とをあわせた出荷の県全体に占める割合は、ウシでは約10%、ブタでは25%、ブロイラーでは50%にも達し、ブロイラーの場合は残りの大部分も農協系の団体にインテグレートされている。このように、畜産の発展は商社系外部資本にリードされて生じたものであるが、この傾向はブロイラーとブタの部門でとくに顕著である。産地は、いずれも県全体に広く展開されているが、ウシでは大隅半島、ブタでは大隅半島と川辺(かわなべ)、伊佐の各地域でとくに頭数が多い。なお、鹿児島の黒豚はその銘柄が全国的に知られている。
耕種部門では、稲作のほかに、工芸作物と野菜の生産額が多く、とくに野菜の生産が伸びている。稲は以前は暖地気候を生かした二期作もかなり行われていたが、1991年(平成3)以降は、奄美大島で行われているのみである。しかし依然として基幹作目の一つであり、川内(せんだい)川などの沖積平野を中心に、各地で栽培されている。工芸作物には、タバコ、茶、サトウキビがあり、茶は1万5400トン(1995)で、静岡に次いで全国第2位の生産量をもつ。サトウキビは薩南諸島の基幹作目で、種子島に1、奄美大島に7の製糖工場がある。このほか、サツマイモは、その半分以上がデンプン原料として使われ、デンプン生産量は全国一である。野菜では暖地性を生かした早期出荷が特色で、とくにサヤエンドウは全国一の生産をあげている。県内でも、南の薩南諸島から北の出水(いずみ)市まで時期をずらして出荷するリレー出荷体制がとられている。このほか、花卉(かき)の伸びも顕著で、キク、グラジオラス、ユリなどの切花、およびツツジ、サツキなどの花木類の伸びが目だっている。
[田島康弘]
林業
県の森林面積58万8000ヘクタール(1995)は県総面積の64%を占め、全国第11位で広い。そのうち国有林面積は27%であるが、霧島(きりしま)山、肝属(きもつき)山地、屋久島などの重要山地を占めている。国有林、民有林とも人工林率は50%を超えており、杉、ヒノキなどの針葉樹林化が進んでいる。林産物は素材が主だが、そのなかでも広葉樹を主とするチップやパルプ用材が半分以上と多く、一般用材を超えていることが特色である。素材以外の特用林産物には、竹材、タケノコ、干しシイタケ、苗木などがあり、とくに竹材とタケノコは全国でそれぞれ第1位と第2位である。また、屋久島の屋久杉加工品も特産品である。
[田島康弘]
水産業
長い海岸線と南方の広い海域をもつ鹿児島県は、古くから水産業が盛んであったが、その経営規模は零細で、5トン未満の漁船が90%を超える。大型漁船のほとんどはカツオやマグロ漁船であり、マグロは串木野港(くしきのこう)、カツオは枕崎港(まくらざきこう)や山川港を基地とし、南太平洋、インド洋などで操業している。総漁獲量は15万2000トン(1993)で、水揚げは、カツオは地元でなされるが、マグロは消費地に近い静岡県の清水(しみず)港や神奈川県の三崎港などで行われる。水産加工も活発で、かつお節が枕崎、山川で、塩干品(塩干サバ、干しイワシなど)が阿久根(あくね)、いちき串木野、鹿児島の各市でおもに行われているが、加工場の多くは家族労働を中心とする零細経営である。このほか、薩摩揚げ、かまぼこなどもある。1959年(昭和34)に実験的に始まった水産養殖は、1977年に設定された200海里漁業水域に直面して、年々伸びてきており、ハマチ、タイ、クルマエビ、ノリ、真珠などが行われているが、生産額ではハマチが断然多い。鹿児島湾、長島周辺、内之浦湾で行われているが、なかでも鹿児島湾の牛根(うしね)、海潟(かいがた)地区(垂水(たるみず)市)が中心である。内水面養殖のウナギも全国第1位(2006)の生産量がある。
[田島康弘]
工業
本県の工業は、食品、繊維、木材などの軽工業、とりわけ食品製造業の比率が高いことを特徴としているが、1993年(平成5)以降、半導体やICを中心とする電気機械工業の進出や生産の上昇が目だっており、24時間操業を行う企業もあって、その生産が急速に伸びてきている。業種別にみると、食料品が従業者で3万0331人(30.9%)、出荷額で8212億円(45.5%)ともっとも高いが、電気も2万2545人(22.9%)、3873億円(21.4%)と第2位を占めていて、年々その比率を高めている。主要製造品をみても、第1位は部分肉・冷凍肉(1221億円)であり、また、配合飼料(990億円)、ブロイラー加工品(728億円)、焼酎(しょうちゅう)(469億円)なども高いが、電子機器用部分品(1182億円)と半導体集積回路(1025億円)が第2位と第3位を占めてきており、また電気用陶磁器(651億円)も高い。これらの電気を中心とする先端技術産業は鹿児島空港周辺の県央地区や北薩地区を中心に進出、立地している。他方、食品関係の工場についてみると配合飼料工場のほとんどは鹿児島市臨海部、部分肉・冷凍肉工場は鹿児島市臨海部と旧曽於(そお)郡地方に集積がみられるが、ブロイラー加工品工場は各地に分散している。このほか、食料品工業のなかには、かつお節、干物などの水産食品、砂糖、焼酎、製茶、漬物などがあり、いずれも重要な地場産業である。かつお節はカツオ水揚げ港の枕崎と山川に工場が集中し、本県で全国の約50%を生産する。焼酎の生産は九州に多いが、なかでも鹿児島県にもっとも多い。工場は県下各地に分散しているが、大部分はサツマイモを原料とするいも焼酎で、一部黒糖焼酎が奄美(あまみ)諸島でつくられている。製茶業も、茶の生産全国第2位の実績を基にして、県内のおもな茶産地(南九州市知覧(ちらん)町、霧島市溝辺(みぞべ)町など)に分布しているが、工場規模は小さい。漬物は、桜島ダイコンの粕(かす)漬けである「さつま漬」と、ダイコンの産地として知られる指宿市山川の「山川漬」が代表的なものである。繊維のほとんどは大島紬(つむぎ)で、その産地は、奄美市名瀬を中心とする奄美地区と、鹿児島市を中心とする鹿児島地区に二分される。このほかの地場産業には、白物と黒物とをもつ薩摩焼、樹齢1000年以上の杉からつくられる屋久杉工芸品、川辺(かわなべ)仏壇、旧薩摩郡・姶良(あいら)郡に多い竹製品、種子鋏(たねばさみ)、大隅そろばんなどがある。
1990年代以降、本県企業の海外進出傾向が顕著になっている。進出企業38社の約8割はアジアへの進出であり、この約6割を香港(ホンコン)を中心とした中国が占めている。
[田島康弘]
開発
遠隔地に位置する本県では、中央と連絡する交通基盤の整備・充実はきわめて重要である。1995年(平成7)、人吉(ひとよし)―えびの間の開通により、九州縦貫自動車道の全線が開通して、北部九州への時間がさらに短縮した。現在、八代(やつしろ)―薩摩川内(さつませんだい)―鹿児島を結ぶ南九州西回り自動車道、および姶良(あいら)―志布志(しぶし)―宮崎を結ぶ大隅半島経由の東九州自動車道が建設中である。一方、九州新幹線鹿児島ルートは、2004年(平成16)に新八代―鹿児島中央間が開通、2011年には全線が開通し、博多(はかた)、新大阪への直通運転もそれぞれ行われるようになった。
また、本県はエネルギー基地としての性格をさらに強めてきており、鹿児島湾内の喜入(きいり)基地に加えて、志布志湾柏原地区の海面埋立てによる石油備蓄基地、東シナ海に面する串木野地区の地下石油備蓄基地がある。
一方、環境保全、自然回帰の風潮のなかで、本県でもいくつかの公園や環境整備の計画が着手され、実現してきている。吹上浜海浜公園が整備され、1996年には南薩の山川町(現、指宿市)に花卉(かき)生産の増進をもねらいとするフラワーパークが建設された。世界遺産に登録された屋久(やく)島でも、環境文化村の整備が進められ、「環境文化村センター」や「環境文化研修センター」が開館した。1997年には、鹿児島ウォーターフロント整備計画の一環であるかごしま水族館(愛称「いおワールド」)がオープンしている。以上のほか、霧島国際音楽ホール(愛称「みやまコンセール」)が、1994年、霧島山麓の牧園町(現、霧島市)に完成し、また同年、アジア・太平洋農村研修センターも鹿屋市にオープンして、国際的な文化・交流施設の整備も進んできている。
[田島康弘]
交通
九州ならびに日本の南の玄関という位置のため、各種交通が発達している。鉄道は、JRでは鹿児島中央(旧、西鹿児島)駅を起点として、西部に鹿児島本線、東部に日豊本線(にっぽうほんせん)が走っている。また九州新幹線も開通している。ローカル線では、南薩を走る指宿枕崎線(いぶすきまくらざきせん)のほか、北薩の肥薩線(ひさつせん)と、吉都線(きっとせん)、大隅半島の日南線があり、鉄道期成会が組織されて、運行の改善、駐輪場の整備など利用促進、利便性向上のための努力がなされている。ほかに第三セクターの肥薩おれんじ鉄道が通じる。
離島を多く抱えるため、海上交通も重要である。まず、鹿児島湾内のフェリーでは桜島フェリー(鹿児島―桜島)、垂水(たるみず)フェリー(鹿児島―垂水)がある。離島航路では、鹿児島と種子島、屋久島を結ぶ種子・屋久航路(口永良部(くちのえらぶ)島との連絡を含む)、鹿児島と奄美の各島を結び沖縄に達する奄美航路(加計呂麻(かけろま)島、請(うけ)島、与路(よろ)島との連絡を含む)、鹿児島と三島村および十島村とを結ぶ三島・十島航路、串木野(くしきの)と甑(こしき)島の各地とを結ぶ甑島航路の四つがある。以上のほか、大阪―志布志、東京―志布志―沖縄など鹿児島港を経由しない外洋航路がある。
航空路線には、国内線と国際線がある。国内線には、鹿児島空港を基点とする路線が国内主要都市とを結ぶ10路線と県内の各離島とを結ぶ7路線があり、合計17路線である。また、奄美空港と国内主要都市間が4路線(東京、大阪、福岡、沖縄)、奄美空港と離島間が4路線(喜界(きかい)島、徳之島、沖永良部(おきのえらぶ)島、与論島)あり、このほかに屋久島―大阪、福岡、沖永良部島―徳之島、沖縄などの路線がある。本県において航空交通は、国内遠距離移動の際になくてはならないものになってきている。国際線では、定期便としてソウル線と上海(シャンハイ)線、台北(タイペイ)線、香港(ホンコン)線がある(2018年)。
[田島康弘]
社会・文化
教育文化
室町時代、学僧桂庵(けいあん)(1427―1508)は、鹿児島市伊敷(いしき)町で朱子学を広め、多くの弟子を育てたが、これは薩南学派とよばれ、当時鹿児島は学問の中心の一つとなった。戦国時代には、種子島への鉄砲の伝来や、ザビエルのキリスト教布教などにより、鹿児島はヨーロッパ文化の門戸となった。薩摩藩では、儒学とりわけ朱子学の精神を取り入れた武士教育が重視され、これは1773年(安永2)島津重豪(しげひで)により創設された藩校造士館(ぞうしかん)で行われた造士館教育と、郷中(ごじゅう)教育という二重の形で実施された。郷中教育は、同じ区域の藩内武家子弟を対象とし、日常の会話、詮議(せんぎ)や、「曽我(そが)どんの傘焼(かさやき)」「妙円寺詣(みょうえんじまい)り」「義臣伝輪読会」の三大行事への参加などを行うもので、実践的な性格を特徴とした。西郷隆盛(たかもり)、大久保利通(としみち)らをはじめとした明治維新における多くの有用な人材は、郷中教育を受けた者のなかから輩出した。郷校も武士の子弟だけを対象とした。このように藩は藩士教育にはきわめて熱心であったが、一般庶民の教育にはほとんど関心を示さず、寺子屋の発達も他藩より遅れていた。
1875年(明治8)には鹿児島師範学校の前身、小学校授業講習所が設立され、1901年(明治34)には、藩校造士館を受け継いで、全国7番目の旧制高校として第七高等学校造士館が設立された。さらに1908年鹿児島高等農林学校、1944年(昭和19)鹿児島青年師範学校、1946年(昭和21)には鹿児島水産専門学校が創立され、これらの国・公立諸学校が合体統合して、1949年鹿児島大学(2018年現在、法文、教育、理、医、歯、工、農、水産学部、共同獣医学部)が誕生した。このほか県内には、鹿児島市に私立の2大学、1公立短大、2私立短大、霧島市に私立の1大学、1短大、1国立高専、薩摩川内市に私立の1大学、鹿屋(かのや)市に国立の1大学(鹿屋体育大学)が創設されている。マスコミでは、地方紙に、南九州最大の発行部数をもつ『南日本新聞』があり、民間放送には、テレビとラジオの両方をもつ南日本放送、テレビのみの鹿児島テレビ放送、鹿児島放送、鹿児島読売テレビ、FM鹿児島がある。鹿児島市内には博物館、美術館、明治100年記念の鹿児島県歴史資料センター黎明(れいめい)館のほか、各地の郷土資料館なども整備されている。
[田島康弘]
生活文化
台風の通り道であるうえに肥沃(ひよく)な平野の少ない鹿児島県は、経済的には恵まれなかった。これは現在でも変わらない。しかし、温暖な気候のもとで、自然の与えるものは種類が多い。この地の人々は、それらを有効に利用し生活に役だててきた。
衣の材料としては、他県と同様、木綿と麻が一般的であったが、南の奄美(あまみ)地方ではリュウキュウバショウを栽培し、その幹から繊維をとり、バシャギンとよばれる芭蕉布(ばしょうふ)を織った。芭蕉布は通気性に優れ、上質のものは絹に似た光沢があり礼服にもなった。また、甑島(こしきじま)列島ではクズの繊維を利用した仕事着「クズタナシ」が愛用されていた。夏から秋に白や紅の大形の花をつけるフヨウからも繊維が採取され、甑島列島ではこれで織った衣類を「ビーダナシ」と称している。藩政時代、紙の産地に近い加治木(かじき)地方では、紙衣(かみこ)もつくられていた。被(かぶ)り物、履き物の材料にも藁(わら)、シュロの皮、クバ(ビロウ)の葉、イグサ、竹の皮、カヤなどが利用されてきた。
日常の食事は第二次世界大戦後大きく変わったが、それまでは、多くが米に麦、アワ、ソバ、カライモ(サツマイモ)などを混ぜたものを主食としていた。たまにはカライモのみ食べる家庭もあった。カライモは煮て食べるほか、生のまま薄く輪切りにしてよく乾燥しておくと保存ができるので、団子の粉にもなった。ユリの根やクズの根からデンプンをとったり、シイの実を炊いて食べることもあったし、奄美地方ではソテツのナリ(実)や幹からデンプンをとり、命をつないだ時代もあった。ソテツには強い毒性があるのでよく水さらしをしないと危険だが、その実はいまでもみその材料に使われる。奄美ではタイモ(田芋)と称する水田に植える芋も栽培されている。副食は朝、昼、晩とも野菜の多く入ったみそ汁と漬物が主で、出し汁の材料にはかつお節のほか、海や川の魚類をいろりの火で乾かしたヒボカシ魚が使われた。モウソウチクやダイミョウチクをはじめとするタケノコ、ツワブキなどをコンブや揚げ豆腐、魚と煮込んだ煮しめも好まれる。沖縄に近い奄美では豚骨(とんこつ)料理を年越に食べ、豚(ぶた)みそをつくる習慣があるが、本土では鶏を祭りか来客のおりに食べるぐらいで、牛肉などを食べるようになったのは新しい。もっぱら、野山の鳥やけもの類、川や海の魚貝類がタンパク源であった。なお、熱帯原産のニガゴイ(ツルレイシ)やイトウリ(ヘチマ)もよく食べられる。いも焼酎や黒糖酒はお湯で割ってダイヤメ(晩酌)に飲まれている。
住居は、土壁でなく、ほとんど板壁で囲んでいる。屋根も以前は草葺(ぶ)きが多かった。それを本土では瓦(かわら)屋根にかえ、奄美地方では風が強いこともあってトタン屋根にしている。屋敷の周りに防風林や防風垣が多いのは、台風の被害を少なくするためのくふうである。また、かつては床も板でなく、篠(しの)竹の簀子(すのこ)床にし、天井も張ってないことが多かった。これは暑い夏をすこしでもしのぎやすくするためでもあった。住居部がイエ(オモテ)とナカエ(台所)とに分かれた「二つ家」(二棟造)はこの地方でも特色ある民家で、離島型とか知覧(ちらん)型など地域による違いもみられたが、急速に消滅しつつある。穀物を納めた奄美の高倉も同様に減少している。
[増田勝機]
民俗芸能
いわゆる大和(やまと)文化圏と琉球(りゅうきゅう)文化圏との接点であったために、民俗の宝庫といわれるほど多彩な行事や芸能が残されている。
大晦日(おおみそか)の晩、甑島(こしきじま)列島の下甑島では、高い鼻のついた紙面をつけ、蓑(みの)を着た異様なかっこうのトシドンが鉦(かね)をたたきながら幼児のいる家を訪れる(「甑島のトシドン」として国指定重要無形民俗文化財)。この行事は屋久島にもあり、東北地方のなまはげに似たものといわれる。小正月にもカセダウチなど来訪神行事があるが、種子島平山の蚕舞(かいこまい)(県指定無形民俗文化財)は、白面女装の若い男性がヤナギの枝に餅(もち)を刺した餅花を担ぎ、扇を持って舞うもので、養蚕ひいては稲作の豊饒(ほうじょう)を願ったものである。霧島市隼人(はやと)町にある鹿児島神宮(国分八幡(こくぶはちまん))の初午祭(はつうまさい)は春祭の一つで、鈴懸馬(すずかけうま)の踊りでにぎわう。薩摩川内(さつませんだい)市高江の南方(みなかた)神社やいちき串木野(くしきの)市の羽島崎(はしまざき)神社の太郎太郎祭(ともに県指定無形民俗文化財)などには、神社の境内を水田に見立てて、田打ちから田植までのまねをする田遊(たあそび)系の芸能がみられる。志布志(しぶし)市志布志町や鹿屋(かのや)市串良(くしら)町の山宮神社などでは、叉木(またぎ)を両方からかけて引き合うカギヒキ行事もある。お田植祭としては、薩摩川内市新田神社の奴踊(やっこおどり)(県指定無形民俗文化財)、鹿児島神宮の田の神舞、日置(ひおき)市日吉(ひよし)町の八幡神社のセッペトベ(精一杯飛べ)が名高い。
梅雨明け後に各地で行われる六月燈(どう)もにぎやかであるが、いちき串木野市大里の七夕踊(たなばたおどり)(国指定重要無形民俗文化財)はとくに盛大で、大きな作り物のシカ、ウシ、トラ、ツルの動物や、琉球王行列、奴行列、薙刀(なぎなた)行列などが登場し、太鼓踊を大きく取り巻いて回る。太鼓踊は盛夏に踊られる勇壮なもので、各地で踊られ、見る者の目を楽しませてくれる。旧暦8月になると三島村で八朔踊(はっさくおどり)があるほか、奄美各地で八月踊がみられ、夜通しチジン(太鼓)の音が鳴り響く。大隅の肝属(きもつき)川流域でも水神祭と関係した八月踊が行われる。十五夜行事としては薩摩川内市の十五夜大綱引きが盛大だが、国の重要無形民俗文化財に指定されている南さつま市坊津(ぼうのつ)町や枕崎(まくらざき)市の十五夜行事、南九州市知覧町の十五夜ソラヨイ行事も地域的特色の濃厚な行事で貴重なものである。ホゼ(放生会(ほうじょうえ))は収穫感謝の祭りであり、指宿(いぶすき)市開聞(かいもん)の枚聞(ひらきき)神社や志布志市有明町の熊野神社では神舞がみられる。曽於(そお)市大隅町岩川の弥五郎(やごろう)どん祭もホゼの一つである。このほか、日置市伊集院町の妙円寺詣(まい)り、姶良(あいら)市加治木町(かじきちょう)地区のくも合戦、鹿児島市の曽我(そが)どんの傘焼も名高い行事である。なお、瀬戸内町の諸鈍芝居(しょどんしばい)、龍郷(たつごう)町の秋名のアラセツ行事も国の重要無形民俗文化財に指定されている。
[増田勝機]
なお「甑島のトシドン」は、2009年(平成21)に単独でユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録されたが、2018年、三島村の八朔の行事に登場する「薩摩硫黄島のメンドン」や十島(としま)村に伝承される「悪石(あくせき)島のボゼ」などとともに、全国の来訪神行事10件で構成される「来訪神:仮面・仮装の神々」に含まれる形で改めて登録された。
[編集部 2019年3月20日]
文化財
鹿児島県は高温多湿な気候と台風の通路にあたるために有形文化財は残りにくい。そのうえ、明治初年の徹底した廃仏棄釈(はいぶつきしゃく)、西南戦争、太平洋戦争末期の空襲などは、天災を免れた文化財の多くを消滅させた。そのため、由緒ある文化遺産は少ない。建造物のうち伊佐市大口大田にある八幡神社本殿(国指定重要文化財)は室町および桃山形式の手法による建物といわれ、琉球建築の情調も強い。また、同市の白木神社本殿は室町時代の建物に鎌倉時代の手法を加えた貴重なもの、伊佐(いさ)市菱刈市山(ひしかりいちやま)の箱崎神社本殿も室町初期のものとみられている。鹿児島市の西田橋は肥後(ひご)の石工(いしく)岩永三五郎が架設した4連のアーチ式石橋で、甲突(こうつき)川に架かる5橋のうちでもっとも優れているといわれ、県の重要文化財に指定されていた。ところが、1993年(平成5)の災害で5橋のうち2橋が流出した。その後、河川改修のため西田橋を含む3橋も撤去されたが、それらの3橋については、同市の稲荷川に移設保存された。
鹿児島市磯(いそ)の旧鹿児島紡績所技師館(異人館)や尚古集成館(しょうこしゅうせいかん)(ともに国指定重要文化財)は日本における初期の洋風建築の代表的なもので、尚古集成館には薩摩切子(きりこ)(ガラス)など旧藩主の所蔵したみごとなものが多く収められている。
絵画では、南さつま市坊津歴史資料センター輝津館に保管の絹本著色八相涅槃図(はっそうねはんず)(国指定重要文化財)が鎌倉時代の作品と伝えられ、志布志市志布志町大慈寺の十六羅漢(らかん)徳庵(とくあん)筆の16幅なども貴重なものである。
工芸品のうち、照国神社(てるくにじんじゃ)(鹿児島市)所蔵の太刀(たち)は本県唯一の国宝で「国宗(くにむね)」の銘をもつ。枚聞神社(ひらききじんじゃ)所有の松梅蒔絵櫛笥(まきえくしげ)(国指定重要文化財)は化粧道具を入れる箱だが、俗に竜宮の玉手箱とよばれており、高貴な人物の献納品とみられる。鹿児島神宮所蔵の色々威胴丸兜大袖付(いろいろおどしどうまるかぶとおおそでつき)ほかの鎧(よろい)類にもみるべきものがある。彫刻には国指定重要文化財はないが、伊佐市白木神社の白木観音像は白木の寄木造の像で、裏面に「行基菩薩(ぎょうきぼさつ)御作也」と墨書されている。鹿児島市南州寺の不動明王像や出水市野田町感応(かんのう)寺の十一面千手観音(せんじゅかんのん)像などと同様、廃仏棄釈の難を運よくくぐり抜けたものである。
なお、民俗資料の田の神石像は本県と宮崎県の一部にしかない野の芸術品である。また、伊佐市の祁答院家住宅(けどういんけじゅうたく)と、肝付(きもつき)町の二階堂家住宅(にかいどうけじゅうたく)は二棟造の代表的例として国の重要文化財に指定されている。
[増田勝機]
伝説
太陽と緑に恵まれたこの風土は、「弥五郎どん(やごろうどん)」のようなユーモラスな巨人伝説を生んでいる。また離島の多くに落人(おちゅうど)伝説が定着しているのは興味深い。薩摩富士の称のある開聞岳(かいもんだけ)には源頼朝(よりとも)の名馬生食(いけずき)を産んだという牧場があり、その母馬の祠(ほこら)は縁結びの神になっている。近くの池田湖も数々の伝説に富む。竜が住むという湖は、風のない日に波立つという。霧島山の大浪池(おおなみのいけ)にも大蛇伝説がある。また、南鹿児島に、大坂の陣で自刃した豊臣秀頼(とよとみひでより)の屋敷と墓が残っている。南九州市知覧(ちらん)町には神話の豊玉姫と玉依姫(たまよりひめ)に関する地名伝説が、また南さつま市大浦町の干拓地には治水に付き物の人柱伝説がある。野間岳(のまだけ)の野間権現(ごんげん)は舟人の信仰を集めているが、本尊は中国娘の娘媽(ニャンマー)神女で霊能力をもち、海難を助けることを誓って投身したという伝説をもつ。巨人伝説は離島にも多い。島々の間を自由に飛び回る巨人は、南国人のおおどかな夢の結晶であろう。種子島(たねがしま)は古い島だけに妖怪(ようかい)伝説が豊富である。中種子町のヌレヨメジョウは非業(ひごう)の死を遂げた流人(るにん)の亡霊。島にはなお、メン、幽霊、目一つ五郎、チョカメン、火グワンス、ガラッパ(河童(かっぱ))、入道、白馬の若侍、天狗(てんぐ)、サイロク、犬神など妖怪の跳梁(ちょうりょう)の信仰が最近まであった。幽霊船に会うと海難に遭遇するという。平家落人伝説は大隅半島をはじめ、甑島(こしきじま)列島、硫黄(いおう)島、屋久(やく)島、吐噶喇(とから)列島の平島、諏訪瀬(すわのせ)島、悪石(あくせき)島、宝島と奄美大島などに及び、いずれも平家部落が存在し、落人の遺跡や墓所があって、その末裔(まつえい)が住んでいる。ことに硫黄島には安徳(あんとく)天皇の子孫と伝える家がある。この島と切り離せない伝説に「僧俊寛(しゅんかん)」があり、出水市野田町には俊寛の庵(いおり)跡というのが残っている。俊寛は鬼界(きかい)ヶ島を脱出しこの地に住んだという伝承がある。なお、奄美大島の平家落人は、平重盛(しげもり)の子資盛(もともり)・有盛、行盛らで、資盛は加計呂麻(かけろま)島の諸鈍(しょどん)に、有盛は浦上に、行盛は戸口にそれぞれ城を築いたという。龍郷(たつごう)町の行盛社は行盛の怨霊(おんりょう)を鎮めるために建てたと伝えている。
[武田静澄]
『川越政則著『鹿児島県史概説』(1963・至文堂)』▽『吉田正広編『鹿児島明治百年史年表』(1968・鹿児島県立図書館)』▽『『鹿児島県の文化財』(1973・鹿児島県)』▽『原口虎雄著『鹿児島県の歴史』(1973・山川出版社)』▽『『日本地誌21 大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県』(1975・二宮書店)』▽『村田煕著『日本の民俗 鹿児島』(1975・第一法規出版)』▽『『鹿児島県地誌』上下(1976・鹿児島県)』▽『椋鳩十・有馬英子著『鹿児島の伝説』(1976・角川書店)』▽『『鹿児島県の歴史散歩』(1977・山川出版社)』▽『山口恵一郎編『日本図誌大系 九州2』(1977・朝倉書店)』▽『小野重朗著『鹿児島歳時十二月』(1978・西日本新聞社)』▽『『鹿児島県史』5巻・別巻・年表(1980・鹿児島県)』▽『『鹿児島大百科事典』(1981・南日本新聞社)』▽『『鹿児島県風土記』(1982・鹿児島書籍株式会社)』▽『『角川日本地名大辞典46 鹿児島県』(1983・角川書店)』▽『『鹿児島県風土記』(1995・旺文社)』

桜島

佐多岬

開聞岳

宮之浦岳

硫黄島〈鹿児島県〉

与論島

栗生海域公園

鹿児島城(鶴丸城)跡

二階堂家住宅

高倉

甑島のトシドン

ソラヨイ

弥五郎どん祭り

妙円寺詣り

加治木くも合戦

ひらせまんかい

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)

尚古集成館

新田神社

大慈寺

大島紬

薩摩焼

薩摩切子

豚骨

鹿児島県位置図
鹿児島(市)
かごしま
鹿児島県のほぼ中央部に位置し、鹿児島湾(錦江湾(きんこうわん))に臨む県庁所在地。南九州第一の都市で、風光がよく東洋のナポリと愛称され、1960年(昭和35)ナポリと姉妹都市を結んでいる。1889年(明治22)市制施行。1934年(昭和9)中郡宇(なかごおりう)村、西武田村、吉野村、1950年伊敷(いしき)村、東桜島村を編入。1967年南に接する谷山市(たにやまし)(1958年市制)と合併。2004年(平成16)吉田町(よしだちょう)、桜島町(さくらじまちょう)、喜入町(きいれちょう)、松元町(まつもとちょう)、郡山町(こおりやまちょう)を編入。市域は、対岸に位置する桜島地区を含む。面積547.58平方キロメートル、人口59万3128(2020)。1980~1985年の5年間で2.5万人増と人口が急増したため、住宅、学校の建設、水の供給など生活環境整備の問題や交通問題が生じた。
[田島康弘]
自然
桜島地区を除く市域の多くは100~300メートルの丘陵・台地で、この台地は火山灰、火山砂、軽石質火山礫(れき)を主とするシラスからなっている。ここから稲荷(いなり)川、甲突(こうつき)川、神之(かみの)川、田上(たがみ)川、脇田(わきた)川、永田川などの中小河川が鹿児島湾に注ぎ、流域に侵食谷や扇状の小平野を形成している。海岸は、北部は姶良カルデラ(あいらかるでら)の陥没のため急壁をなしているが、中部は遠浅で埋立てが行われ、大規模な工業団地が造成されており、南部は薩摩(さつま)半島の分水界をなす南薩山地の東側斜面となっている。桜島は姶良カルデラの中央火口丘で裾野(すその)に集落が展開している。年平均気温は18.6℃、年降水量は2265.7ミリメートル(1981~2010年の平均)で温暖多雨である。風向きは北西の風がかなり多いが、夏季には逆方向の風が卓越し、ときおり大量の火山灰を市街地にもたらす。
[田島康弘]
歴史
薩摩国に属したが、北端は中世まで大隅(おおすみ)国吉田院であった。島津氏が鹿児島に入ったのは、1343年(興国4・康永2)5代貞久(さだひさ)が東福寺城(多賀山)に居城したときからである。1602年(慶長7)18代家久(いえひさ)が鶴丸城を築き、翌1603年、徳川家康が藩制を確立するに伴い薩摩藩が成立した。その後29代忠義(ただよし)(1840―1897)まで267年間にわたり、島津77万石の城下町として、また琉球(りゅうきゅう)など南方との交易も行い独自の発展をみた。1871年(明治4)の廃藩置県により、県庁が設置されるとともに県都となり、南九州の一大中心地として発展した。海上交通の発達により、早くから海岸区が商業区として栄えていたが、第一次世界大戦時の好況による商工業の発達から市街化が進展し、また士族屋敷であった天文館(てんもんかん)地区にも映画館や市場ができ、しだいに中心商業地区が形成されていった。第二次世界大戦下の大空襲(1945)で市街地の90%を焼失したが、戦後いち早く西鹿児島(現在の鹿児島中央)駅を表玄関とした戦災都市計画事業が実施され、戦前は田んぼであった甲突川南西部が急速に市街化されてきた。また、1952年(昭和27)から海岸部の埋立てが開始され、港湾の整備とともに、広大な臨海商工業地区が形成されてきた。1967年、喜入地区に日本石油(現、ENEOS喜入基地株式会社)の原油備蓄基地が建設(1969年操業)され有名になった。その貯蔵能力は735万キロリットル(日本国内の石油使用量の約2週間分)である。
[田島康弘]
産業
産業別就業人口をみると、第三次産業、とくに卸売・小売業とサービス業の比重がきわめて高く、商業卓越都市ということができる。小売業のうち飲食料品小売業、とくにバー、酒場、喫茶店などの遊興・娯楽的業種が多い。従業者規模では中小企業、とくに1~4人の零細企業が圧倒的に多い。工業は、業種別出荷額では食料品製造業が多く、ほかに木材、木製品、出版・印刷、繊維などがある。食料品では、配合飼料、生鮮・冷凍肉、ブロイラー加工品、水産干物、かつお節などで、その工場が臨海部を中心に立地している。郷土産業としては大島紬(つむぎ)のほか薩摩焼、竹細工、ツゲ細工、錫(すず)器などの民芸品、焼酎(しょうちゅう)、漬物、かるかんなどの飲食料品がある。農業では、農業就業人口は減少しているが、消費市場に近いなどの有利な条件を生かして、野菜、花卉(かき)、果樹を中心とした近郊農業とブロイラーの畜産が盛んである。西部の松元地区では茶栽培が盛んで、良質の手もみ茶を産する。桜島地区では、降灰対策としての土壌改良やビニルハウス、散水施設などを設置し、火山の緩斜面を利用して暖地性のミカン、降灰に比較的強いビワ、サクラジマダイコンなどが栽培されてきたが、降灰や火山ガスによる被害のため離農する者も増えている。近年は、住宅地開発によって近郊のベッドタウン化が進展している。
[田島康弘]
交通
鉄道はJR鹿児島本線、日豊本線(にっぽうほんせん)、九州新幹線が通じ指宿枕崎線(いぶすきまくらざきせん)を分岐する。道路は、国道3号、10号、224号、225号、226号、328号が通じ、九州自動車道、南九州西回り自動車道、指宿スカイラインの基点となっている。福岡、熊本などの各市へ定期高速バスが運行されている。鹿児島空港(霧島市)へは九州自動車道を利用して市内から1時間足らずの距離にあり、そこから国内主要都市や離島への国内線、上海(シャンハイ)、ソウル、香港などへの国際線もある。海上交通はよく発達しており、桜島と大隅(おおすみ)半島の垂水(たるみず)へはフェリーボートや定期船が、離島航路には種子島(たねがしま)、屋久(やく)島、奄美(あまみ)大島、沖縄などへの定期航路がある。
[田島康弘]
観光・文化
南九州の宮崎、霧島(きりしま)、指宿、奄美諸島など各観光地への交通上の結節点であり、また、市域内には世界有数の活火山の桜島や古里(ふるさと)温泉、市街地内の鹿児島温泉、明治維新前後の多くの優れた観光資源をもつ。おもな国指定文化財には以下のものがある。照国神社(てるくにじんじゃ)の太刀(たち)銘「国宗(くにむね)」は国宝。城山(しろやま)は天然記念物で史跡。朱子学者桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)の墓「桂菴墓」は史跡。尚古集成館(しょうこしゅうせいかん)は史跡で重要文化財。ほかに、重要文化財には異人館(旧鹿児島紡績所技師館)などがある。「キイレツチトリモチ産地」(吉野町)は国の天然記念物、「喜入のリュウキュウコウガイ産地」は国の特別天然記念物。名勝として仙巌園(せんがんえん)(磯庭園(いそていえん))がある。鹿児島(鶴丸)城跡、照国神社、ザビエル滞鹿(たいか)記念碑、私学校跡、南洲(なんしゅう)墓地、薩摩義士碑、西田橋なども名高い。桜島は霧島錦江湾国立公園域。その他の観光地としては、展望のすばらしい千貫平(せんがんびら)自然公園、生見(ぬくみ)海岸の海水浴場、島津初代藩主忠久(ただひさ)の母丹後局(たんごのつぼね)を祀(まつ)る花尾神社、川田堂園(どうぞの)供養石塔群などがある。施設には、市立美術館、県立博物館、県歴史資料センター黎明(れいめい)館、西郷南洲顕彰館、奄美の里、かごしま熱帯植物園、かごしま水族館(いおワールド)、県立鴨池(かもいけ)公園、平川動物公園、市立科学館、県文化センター、市民文化ホールなどが知られ、国立大学法人鹿児島大学のほか鹿児島国際大学、志学館大学、鹿児島県立短大、鹿児島純心女子短大、鹿児島女子短大などがある。年中行事には、7月の曽我(そが)どんの傘焼、六月燈(どう)、11月のおはら祭が有名。
[田島康弘]
世界遺産の登録
2015年(平成27)、ユネスコ(国連教育科学文化機関)により「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産として、旧集成館(反射炉跡、旧集成館機械工場、旧鹿児島紡績所技師館)、寺山炭窯跡(てらやますみがまあと)、関吉の疎水溝(せきよしのそすいこう)が世界遺産の文化遺産に登録された。
[編集部]
『『鹿児島のおいたち』(1955・鹿児島市)』▽『塚田彰夫編『かごしま史――郷土の歴史と物語』(1964・鹿児島書院)』▽『『鹿児島市史』3巻(1969~1971・鹿児島市)』
改訂新版 世界大百科事典 「鹿児島」の意味・わかりやすい解説
鹿児島[県] (かごしま)
基本情報
面積=9188.78km2(全国10位)
人口(2010)=170万6242人(全国24位)
人口密度(2010)=185.7人/km2(全国36位)
市町村(2011.10)=19市20町4村
県庁所在地=鹿児島市(人口=60万5846人)
県花=ミヤマキリシマ
県木=カイコウズ,クスノキ
県鳥=ルリカケス
九州地方南部の県。本州弧の最南西端と,その西方の甑島(こしきじま)列島およびその南方の沖縄諸島までの間に連なる薩南諸島を含む。北は宮崎・熊本両県に隣接する。
沿革
明治初年までの大隅国,薩摩国にあたり,江戸時代は鹿児島藩(薩摩藩)に属した。1871年(明治4)廃藩置県をへて,大隅国の一部と薩摩国,琉球国は鹿児島県に,他は都城県に属したが,翌年琉球国は鹿児島県を離れ,73年都城県が廃されて現在の県域となった。76年宮崎県を合併したが,83年再び分離した。第2次大戦後は薩南諸島の大部分が沖縄のアメリカ軍軍政下に置かれたが,1951年返還された。
鹿児島県の遺跡
先縄文文化期の本県の様子はまだよく解明されていないが,上場(うわば)遺跡(出水(いずみ)市)の第6層でナイフ形石器やチョッピングトゥールなどが出土し,第4層でナイフ形石器,台形石器などが,そして第2・3層では細石刃などの石器が爪形文土器を伴って出土している。縄文時代の遺跡としては貝塚が多い。県北八代(不知火)海岸には縄文早期から後期の土器を層位的に出土した出水貝塚(出水市),薩摩半島西海岸では縄文後期の人骨3体を出土した市来貝塚(いちき串木野市),薩南諸島では奄美大島の宇宿(うすく)貝塚(奄美市)や徳之島の面縄(おもなわ)貝塚(大島郡伊仙町)などがある。これら奄美諸島の貝塚では縄文・弥生式とは異なる琉球・奄美系の土器文化が中心をなすが,ことに宇宿貝塚では宇宿下層式と市来式が伴出したことから宇宿下層式が縄文後期並行であることが判明した。このほか塞ノ神(せのかん)遺跡(伊佐市),黒川洞穴(日置市)は,それぞれ前期塞ノ神式,晩期黒川式の標式遺跡として重要である。また指宿(いぶすき)遺跡(指宿市)は火山堆積層をはさんで上下に弥生式と縄文式を出土し,両土器文化の時間的前後関係が証明されたことで学史上著名である。
弥生文化では,種子島南東部海岸の中~後期の埋葬遺跡で饕餮文(とうてつもん)のある貝符や竜佩などの貝製品を出土したことで知られる広田遺跡(熊毛郡南種子町)のほか,前期の高橋貝塚(南さつま市)や中期の祭祀遺跡で立石と円形組石を伴う山ノ口遺跡(肝属郡錦江町),それに中~後期の集落址一の宮遺跡(鹿児島市)などがある。成川遺跡(指宿市)は弥生中期から古墳時代中期ごろの立石墓群で,200体にも上る埋葬人骨があったが,墓の形態や,土器と鉄器を中心とする副葬品などのうえで男女の差はあっても,どの時期にも特別の扱いのものはみられず,この地方では古墳時代に至ってもなお階級的社会が未成熟であったことを示していて興味深い。そればかりか弥生時代の北九州などに一般的な甕棺,箱式石棺,支石墓などもなく,畿内型高塚古墳の分布も,志布志湾沿岸と県北出水地方にほぼ限られる。これに対し南九州独特の墓制として,宮崎県南部から大隅半島とりわけ肝属(きもつき)平野や旧伊佐郡地方に多く分布する地下式横穴と,大隅地方にはまったくみられず熊本県南部から川内川流域,出水地方に集中的に分布する地下式板石積石室(地下式土壙)とがある。これらは弥生後期の伝統のもとに,3世紀ころから形成された隼人文化独特の地方的墓制なのであろう。歴史時代では,大隅国府並びに国分寺址(霧島市),薩摩国府並びに国分寺址(薩摩川内市)がある。
→大隅国 →薩摩国
シラス台地と亜熱帯の島々
県本土の形態の特色は薩摩半島と大隅半島が,中央の鹿児島(錦江)湾を両側からかかえるように並んで,南に突出しているという点にある。本土の西方および南方洋上には島嶼(とうしよ)が多く,西方には甑島列島の上甑島,下甑島など,南方には薩南諸島に含まれる大隅諸島,吐噶喇(とから)列島,奄美諸島などが点在し,亜熱帯的気候(名瀬市での1月平均気温14.2℃,年降水量3051mm)の特色を示している。県には大山地はないが,北から国見山地,出水(いずみ)山地,薩摩半島の南薩山地,大隅半島の高隈山地,肝属(きもつき)山地など標高数百mから1000m級の小山地が各地にある。また火山の多いことも特色で,その中核部は鹿児島湾を南北軸として北から霧島山,湾の中央に桜島,南の湾口に開聞(かいもん)岳があり,火山列はなお南の吐噶喇列島の諏訪之瀬島にまで延びている。古い姶良(あいら)火山から噴出したシラスと呼ばれる火山噴出物が県の半分以上の面積を占めて分布しており,水利の悪い比高20~600mの台地をつくっている。北部を流れる川内(せんだい)川以外にはあまり大きな河川は存在せず,大きな平野も発達していない。本土も南国的な気候で,1月の平均気温は鹿児島市で7.0℃,年降水量は2375mmである。台風の襲来も多く,とくに離島は毎年大きな被害を受ける。
先進,後進の交錯
記紀によれば鹿児島の古い住民は熊襲(くまそ),隼人(はやと)であって中央の住民と風俗,習慣が違い,しばしば中央権力に反抗して反乱を起こし,討伐された。鹿児島は中央から遠く,その権力や文化の及ばぬ後進地域とされる面があった。しかし,一方でこの地域は中国大陸や南方諸島に近いために外来文化の最先端受入地としての機能ももっていた。県南西部の坊津(南さつま[市])は7~9世紀のころ遣隋使船,遣唐使船の発着地であった。下って16世紀には鉄砲が種子島に伝来し,キリスト教もザビエルが鹿児島に上陸して布教を進めたことで日本に広まった。とくに江戸時代末期には藩主島津斉彬などの主導のもとに製錬所,溶鉱炉,造船所,洋式紡績工場をつくるなど多くの先進的事業が行われた。また薩摩藩では藩主居館の鶴丸城のほかに,100余の外城(郷)を置き,その周囲に郷士の居住する麓集落をつくって地域の軍事,行政を管轄していた。明治以降も麓の地名,集落景観などに独特のものを数多く残している。
乏しい資源と遅れた工業
明治になってからの鹿児島は再び中央から取り残された後進地域になった。その一つの現れは県民1人当り所得の低さで,全国都道府県中の最低クラスを続けてきた。その原因の一つは県の産業が農林(畜産を含む),水産などの第1次産業にかたより,第2次,第3次などの近代産業の発達が微弱だったためである。これは資源が乏しい上に地理的条件が悪く,商工業の発展に不利であったことによる。県のおもな地下資源は一鉱山で全国金産額の約90%を占める菱刈金山,歴史の古い串木野金山(1864年鉱床発見)や,枕崎市の岩戸・春日両金山などがある。その他の資源には17世紀半ばに発見された谷山(現,鹿児島市)の錫山があり,特産のスズ製品(酒瓶,茶筒など)の原料になっていたが,現在は採掘されていない。また工業についても大島紬などの絹織物,サツマイモ(カライモ)からの焼酎などの食料加工品,ほかに木材,木製品など,一次産品の加工工業が主である。しかし日本経済の高度成長に伴って,1960年代から鹿児島市の臨海部を埋め立て,大工業用地を造成する計画が進行し,通称木材団地,金属団地,卸商業団地などの諸団地が形成され,そのほかにも造船,機械,住宅関連,石油などの工場の立地が進んでいる。またテクノポリス地域に指定された国分市(現,霧島市)をはじめ,出水(いずみ)市および伊集院町(現,日置市),入来町(現,薩摩川内市),栗野町(現,湧水町)にエレクトロニクスなどの精密工業が進出し,県工業の将来が期待されている。
改良された畑作と盛んな林業,水産業
鹿児島県は全国有数の農業県であり,農家戸数では全国都道府県中6位(1995),耕地面積第11位である。とくに専業農家数では全国1位を占める。しかし農業の水準は必ずしも高くはなく,1戸当り農業所得は全国平均の6割程度にすぎない。その理由として考えられるのはシラス台地が広い面積を占めるため水田の少ない畑作県であること(畑作地率65%,1995),台風の被害の大きいこと,中央市場から遠いために商品性の高い作物の栽培に不利なことなどである。しかし輸送手段の発達や灌漑用の高隈ダムの完成(1968)などによって悪条件もしだいに克服されるようになった。従来シラス台地での畑作物として普通だった陸稲,麦,サツマイモ,ナタネなどが急激に減り,新しくさやエンドウ,ピーマン,サトイモなどが導入され全国での高いシェアを得るようになった。畜産の発展も著しく,農産物中産額の最も多いのは豚,ブロイラー,肉用牛,鶏卵などの畜産品である。また,樹木の生育がよく林業も盛んで,森林面積は全国第11位,屋久杉で有名な屋久島を主とし,そのほか出水山地,霧島山,高隈山地,肝属山地など各地に豊富な森林が見られる。水産業も盛んで,おもな港には串木野,枕崎,山川などがあり,カツオ,マグロなどの水揚げが多いが,とくに鰹節では全国一の産額をもっている。鹿児島湾内ではタイ,イワシ,サバの漁獲が多く,最近はハマチの養殖に力を入れている。
豊かな自然と観光・交通
明治以後の経済的発展が遅く,県民所得が低いが,このことは半面からいえば自然がよく残されているということでもある。南北に並ぶ霧島山,桜島,開聞岳の火山地域に離島の屋久島を含めて,霧島屋久国立公園に指定されている。この国立公園内には霧島温泉,指宿(いぶすき)温泉などがあり,そのほかにも県下には数多くの温泉が分布している。志布志湾内にある枇榔(びろう)島はビロウなどの亜熱帯性植物群落(特天)で知られ,日南海岸国定公園に含まれている。
鹿児島県は北を九州山地に隔てられて交通不便な地域であり,鉄道開通までは陸路では西部の三太郎越,東部の宗太郎峠によってかろうじて北九州と結ばれていたにすぎない。県西部に鉄道が開設されたのは1901年であるが,はじめは現在の肥薩線のコースを通っていて,海岸回りの鹿児島本線(2004年より八代~川内間は肥薩おれんじ鉄道)が全通したのは1927年であり,さらに東部の日豊本線が開通したのは32年である。そのほかにもいくつかのローカル線があったが,廃止されているものもあり,これに代わるバス網も縮小されつつある。なお,九州新幹線鹿児島ルートは2004年鹿児島中央駅と熊本県新八代駅の間が開業,11年に新八代駅と福岡県の博多駅の間が開業して全線開業となった。県は三方を海で囲まれているほか,島嶼部が多いため航路の発達が著しい。中心は鹿児島湾を横切って薩摩半島と大隅半島を結ぶ航路で,鹿児島港と桜島を結ぶ湾中央の航路は観光連絡船を兼ねている。離島航路はおもに鹿児島港を起点とするが,長距離航路として志布志を経て大阪に至るものもある。航空路としては1972年溝辺町(現,霧島市)に移転した鹿児島空港を拠点として東京,大阪と結ばれるが,離島航空路も多いため地方空港としては発着便数が多い。
県の南北軸,薩摩,大隅,島嶼部の4地域
自然条件,人文条件,歴史的条件などの違いから県を四つの地域に区分する。
(1)県の南北軸地域 中央の鹿児島湾に沿い,鹿児島市を中核として霧島市,垂水市,指宿市の3都市を含み,北の霧島火山地区と,南の南九州市の一部を合わせた地域である。鹿児島市は14世紀の半ばに島津氏が拠って以来,守護町,城下町として発展し,明治以後は県庁所在地となった。史跡に富み,風光にすぐれた観光都市でもある鹿児島市に加えて,火山,温泉が多く霧島屋久国立公園に含まれる面積が広いこの地域は,県の政治,経済,文化,観光,交通の中心をなしている。
(2)薩摩地域と大隅地域 薩摩・大隅両半島は地形上分かれた二つの地区というだけではなく,対照的な特色をもち,両者をそれぞれ西目,東目ということがある。西目は出水山地など山地も多いが,県内では比較的大きな川内川流域に大口盆地や川内平野が主要米作地帯をなし,また小河川によってシラス台地が樹枝状に細かく浸食されているため,東目のように広大な台地は発達せず,小さい谷も水田化されて,開発は早く進んだ。これに対し大隅の東目は,古墳時代は開けていたが笠野原,鹿屋原など広大なシラス台地が半島の大部分を占めるため,水田化が困難で,開発が遅れた。土地利用の上でも西目の水田卓越地域と東目の畑作卓越地域が対照的である。1970年代以降は東目でも畑地灌漑が進み,交通も発達して農作物の多様化などによって経済力が向上し始めている。肝付町の旧内之浦町には東京大学の宇宙空間観測所(ロケットセンター。現在は独立行政法人の宇宙航空研究開発機構の施設)が1963年開設された。都市の数からも対照的で,薩摩には出水,大口,阿久根,串木野,加世田,枕崎などがあるが,大隅側では鹿屋(かのや)のみである。
(3)島嶼部 この地域の共通の特色は交通を海にたよらなければならない点である。最近は航空路の発達が著しいが海の重要さには及ばず,そしてこの両者とも台風の場合など利用が不可能になり,住民の生活を脅かす。しかし一方では亜熱帯気候に恵まれて国内では沖縄とともに独自の性格をもつ。ソテツ,ビロウ,ガジュマル,アダンなどが茂り,天然記念物のルリカケス,アマミノクロウサギや猛毒のハブが生息する島もあり,作物で重要なのはサトウキビである。青い空,サンゴ礁の海は観光的に極めて高い価値をもっている。
執筆者:服部 信彦
鹿児島[市] (かごしま)
鹿児島県中央部の鹿児島(錦江)湾に面する県庁所在都市。2004年11月旧鹿児島市が喜入(きいれ),郡山(こおりやま),桜島(さくらじま),松元(まつもと),吉田(よしだ)の5町を編入して成立した。人口60万5846(2010)。
鹿児島
鹿児島市中部の旧市で,県庁所在都市。1889年市制。人口55万2098(2000)。市域には1950年に編入した桜島東部の旧東桜島村域,67年合体した旧谷山市域を含む。市域の大部分はシラス台地で占められるが,中心市街地は南東流する甲突(こうつき)川やその他2~3の河川によって湾岸に形成された複合三角州上にある。シラス台地の末端にあたる城山の山頂には,南北朝期に上山氏が上之山城を,山麓には江戸初期に島津氏が鶴丸城を築き,以来鹿児島は薩摩藩77万石の城下町として発展した。明治以後は県庁所在地として県の政治,経済,文化,交通の中心であるだけでなく,南九州の中心としての役割を果たすようになった。人口は1970年からの10年間に10万2051人と著しい増加をみせ,シラス台地上も宅地化が進んでいる。第3次産業人口率が約78%(1990)と高く,第2次産業人口率は約20%で,工業はあまり発展せず,食料品,木材木製品,繊維(大島紬)などの軽工業にすぎないが,海岸の埋立地に工場の進出が著しい。九州自動車道の鹿児島インターチェンジから南九州自動車道と指宿スカイラインが分岐する。九州の二大幹線であるJR鹿児島本線,JR日豊本線が鹿児島で結ばれ,JR指宿枕崎線を分岐している。2004年九州新幹線鹿児島ルートの鹿児島中央~新八代間が開業,11年には博多まで全線開業した。また薩摩・大隅両半島をはじめ,南西諸島の島々への航路の起点ともなっているが,空港は1972年溝辺町(現,霧島市)に移転した。史跡が多く,西南戦争の戦場となった城山周辺には石垣と堀だけ残る鶴丸城跡,1874年開校された私学校跡,西郷隆盛のこもった洞窟,その終焉(しゆうえん)の地などがある。市内北部には,島津家の別邸である仙巌園(磯公園),異人館(旧鹿児島紡績所技師館)などがある。市街地には昭和初めに発見された温泉がその後のボーリングによって数多く湧出し,旅館の内湯,共同浴場,ジャングル浴場などに利用されている。
執筆者:服部 信彦
鹿児島城下
島津家19代家久は1602年(慶長7)鶴丸城を築いて,内城(現在は大竜小学校)から移った。城は天守のない屋形造の居館であった。当時甲突川は柿本寺通辺を流れていたといい,また新上橋辺より東流し平ノ町,千石馬場,加治屋町を屈曲し俊寛堀より海へ注いでいた。西千石町辺はアシが茂り,後の南林寺辺は海中であった。甲突川の大改修を行って現位置に移し,それよりしだいに埋立てを行って士屋敷,町屋敷を建設したが,町屋敷は海岸の埋立地で,御船手は初め稲荷川口にあり,琉球諸島行の係船場もここにあった。天保末年(1840)ころまでの甲突川は川筋が屈曲し川底も上がり,洪水のために城下民は苦しんだが,天保の改革で川筋を整え川底を浚渫(しゆんせつ)し,玉江橋,新上橋,西田橋,高麗橋,武之橋など堅牢な石造眼鏡橋を架設した。天保山はこの時の揚砂でできたもので,御船手も甲突川口に移された。また祇園洲の埋立ても稲荷川の浚渫によりなされた。鹿児島は山川港を外港としていたが,南島運輸の重要性が増したので,同じころから港の改修に力を注ぎ,三五郎波戸,屋久島岸岐,鍋屋岸岐,石灯炉岸岐,弁天波戸などの防波堤を築いて海上交通の便を一新した。城下は〈町方三分,武家方七分〉と諸書に書かれているごとく,士屋敷の地域は広く,人口においても1826年(文政9)士は町方の3倍以上,家来,与力,足軽を加えれば7倍以上もあったが,当時の総人口は5万8065人であった。城下町は町奉行の支配で,町人役として惣年寄,年寄,年寄格,年行司,年行司格,十人格,乙名頭,横目役があり,町会所は下町にあった。町人(名頭)は屋敷持のことで畦掛銀(戸数割税)と水夫奉公という海上賦役の義務を負っていた。領内は大方自給自足経済で,かつほとんど物品は専売制度の網の目にかけられていたから,少数の巨大な御用商人のほかは大方が小前の町人であった。町の周囲には荒田浜と,いわゆる近在二十四ヵ村(郡元,中,荒田,武,西田,田上,西別府,原良,永吉,小野,犬迫,小山田,比志島,皆房,上伊敷,下伊敷,草牟田,花野,岡之原,川上,下田,坂元,吉野,花棚)の農村が付属していた。なお士屋敷では,千石馬場,平ノ馬場などは大身の士の居住地区で,古く守護町として発展してきた上町方面には中級士が住居し,加治屋町,新屋敷町,上之園町,高麗町や荒田村,吉野村,草牟田村など場末には下級士が住居し,鳥籠,傘,はし,櫛,金助まりの内職や農耕でくらしをたてていた。城下には,諏訪(薩摩,大隅,日向3州の惣社),祇園,稲荷,春日,若宮のいわゆる五社と,島津氏祈願所の真言宗大乗院,同菩提所曹洞宗福昌寺をはじめ多くの諸宗大小寺社があり,また江戸末期には島津家29代斉彬の開化政策により集成館事業と総称する紡績,ガラス,造船,兵器などの洋式工業の花がひらき,多くの維新英才が輩出した。
執筆者:原口 虎雄
喜入
鹿児島市南部の旧町。旧揖宿(いぶすき)郡所属。人口1万2802(2000)。薩摩半島の東側にあって,鹿児島湾に臨み,北は旧鹿児島市に接する。南薩山地とそれに続くシラス台地が海岸にせまり,海岸線に沿って並ぶ集落を結んでJR指宿枕崎線,国道226号線が走る。平安後期から島津荘の寄郡(よせごおり)給黎院(きいれいん)に属し,以後島津氏が支配した。1960年代以降,ミカン作主体に転換された農業は,近年畜産やエンドウの促成栽培も導入され経営の多角化が図られている。水深の深い海岸を利用して世界屈指の石油備蓄基地が建設され,69年から操業を開始した。町南端の生見(ぬくみ)に自生するメヒルギ(別名リュウキュウコウガイ)は世界最北端の紅樹林(マングローブ)として特別天然記念物に指定。
郡山
鹿児島市北西端の旧町。旧日置郡所属。人口8314(2000)。薩摩半島北部にあり,南東は旧鹿児島市に接する。集落は南流する諸河川の段丘上に発達するものが多く,中心市街は町役場のある郡山付近にある。米作を主体にキュウリ,ナス,イチゴなどの園芸作物の栽培が盛んで,アスパラガス,たけのこなどの缶詰工場も進出している。1960年ころから過疎化が進んだが,町南部が鹿児島市の通勤住宅地化した70年代から人口増に転じた。町南西の川田川沿いに郡山温泉がある。
鹿児島市東部の旧町。旧鹿児島郡所属。人口4678(2000)。鹿児島湾北部にある桜島の西半分を占める。桜島は現在も激しい火山活動を続けており,降灰などにより農業や生活に多大な影響を与えている。大隅半島と陸続きとなった1914年の大正噴火後,カンショ,サトウキビ,タバコ作から果樹作に転換し,ミカンを中心に桜島ダイコン,ビワが栽培される。集落はすべて鹿児島湾沿いにあり,桜島港のある袴腰は島内一周,中腹展望観光の基地で,対岸の鹿児島港とはフェリーで結ばれる。
松元
鹿児島市西部の旧町。旧日置郡所属。人口1万2065(2000)。薩摩半島中央部に位置し,東は旧鹿児島市に接する。無数のシラス台地と多くの渓谷からなり,谷底平野は水田,台地上は畑地,林野が占める。平安時代末期から伊集院氏の支配下に置かれたが,1536年(天文5)には島津氏の所領となった。霧が深いこともあって,近世以来シラス台地上で良質の茶を産し,明治期以降は主産業となっている。肉牛の肥育,野菜栽培も行われる。旧鹿児島市に隣接しているため,年々衛星都市的性格を強めており,1970年代以降人口の増加が著しい。JR鹿児島本線が通じる。
吉田
鹿児島市北東端の旧町。旧鹿児島郡所属。1972年町制。人口1万1736(2000)。薩摩半島基部に位置し,北部は姶良(あいら)平野南西端にあたる。南の旧鹿児島市との境には標高500mほどの丘陵性山地が連なるため,以前は北の蒲生町や姶良町重富との結びつきが強かった。1926年に鹿児島市から吉田町を通り蒲生町に至る県道が開通,さらに73年には九州自動車道の薩摩吉田インターチェンジが設置されたため鹿児島市の勢力圏に入るようになり,現在はそのベッドタウンとして発展している。水田率が50%を超え県下ではきわめて高いが,近年はハウス野菜や早熟メロンの栽培など都市近郊型農業の展開も見られる。町名は,古代に大隅国吉田院と称したことに由来する。吉田城跡や本城花尾神社の庚申二王石像などの史跡,文化財がある。
執筆者:吉成 直樹
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「鹿児島」の意味・わかりやすい解説
鹿児島[県]【かごしま】
→関連項目九州地方|鶏飯
鹿児島[市]【かごしま】
→関連項目鹿児島[県]|鹿児島中央[駅]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本歴史地名大系 「鹿児島」の解説
鹿児島
かごしま
- 鹿児島県:鹿児島市
- 鹿児島
当初は古代以来の鹿児島郡をさしたが(一一月二四日「源頼朝御教書」旧記雑録など)、応長元年(一三一一)閏六月二四日の沙弥道本義絶状(同書)に「国分寺御領麑島尼寺田御年貢」とみえるように、一四世紀初頭頃から郡名とは異なる使用法も確認できる。守護島津氏久が
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「鹿児島」の解説
鹿児島
かごしま
中世を通じて島津庄の地頭,薩摩守護であった島津氏が,1343年以降根拠地とした。戦国時代に島津氏が薩摩・大隅 (おおすみ) を統一し,1602年鶴丸城を居城とした。近世城下町としては,島津氏の外城政策のため77万石の大藩があったわりには小規模であった。1863年薩英戦争で戦火をうけた。'89年市制施行。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
動植物名よみかた辞典 普及版 「鹿児島」の解説
鹿児島 (カゴシマ)
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


 鹿児島県、
鹿児島県、